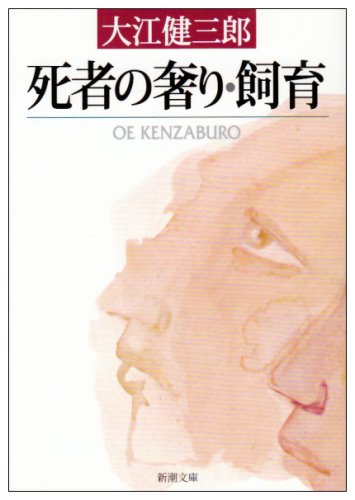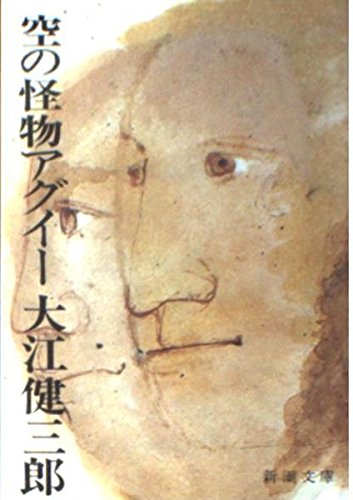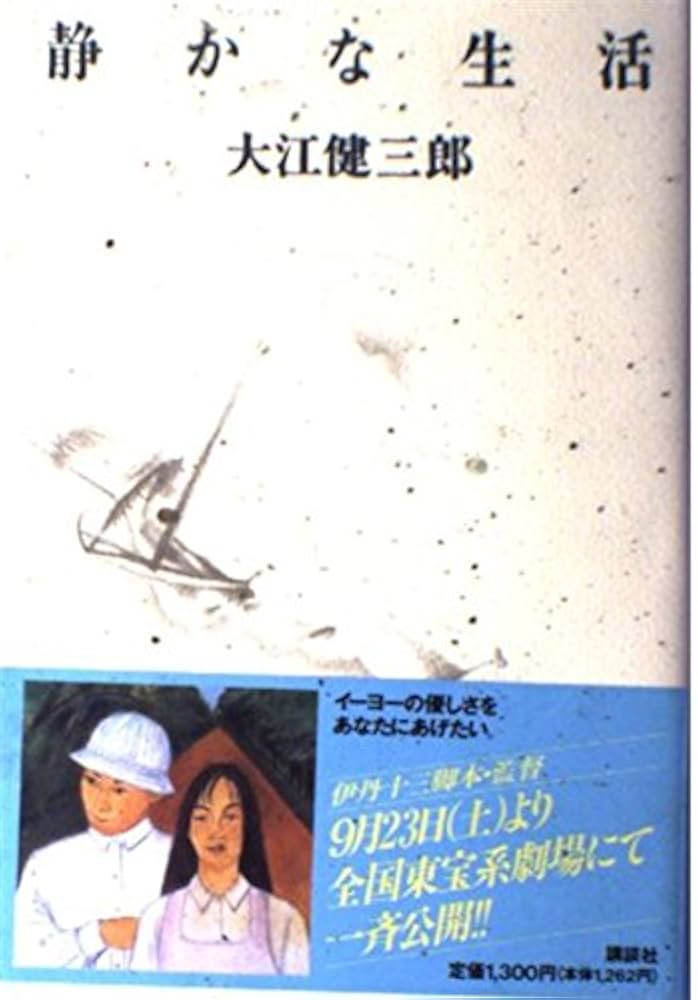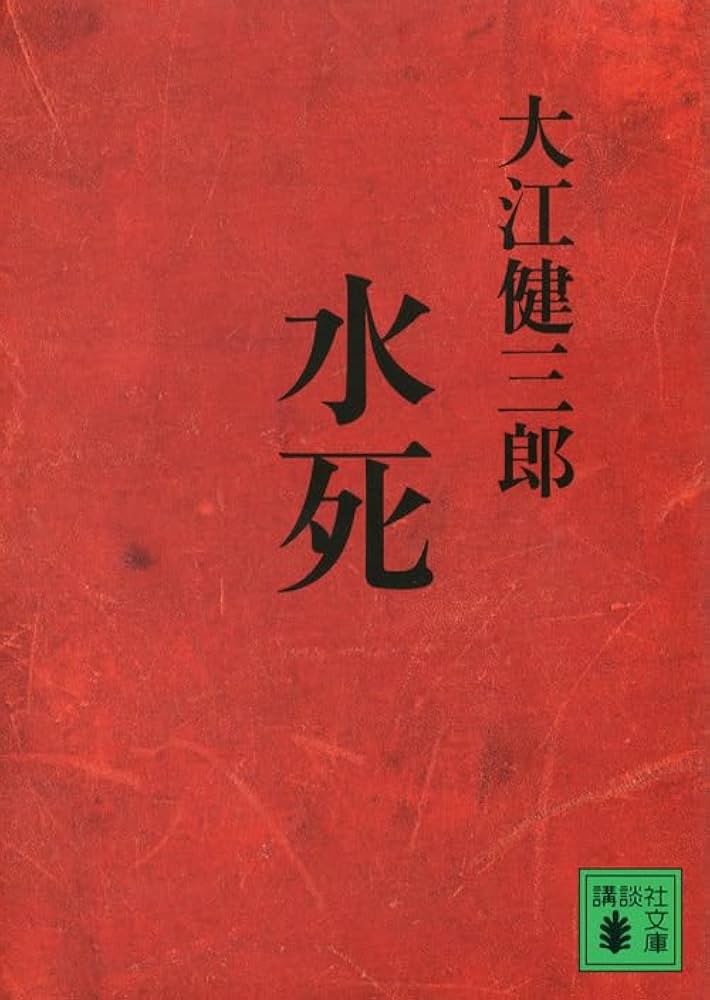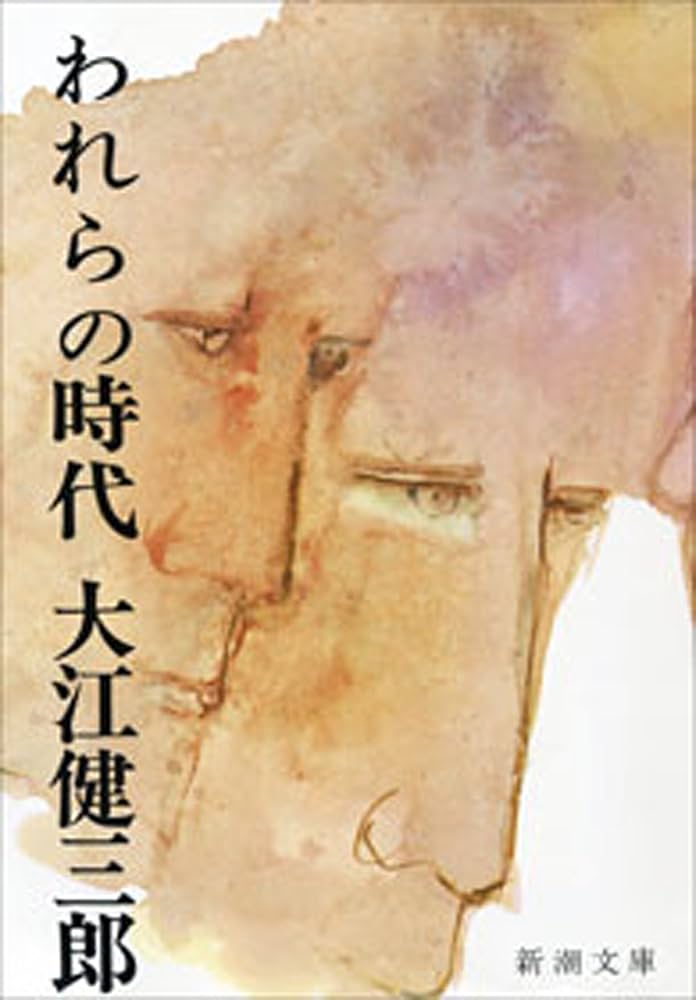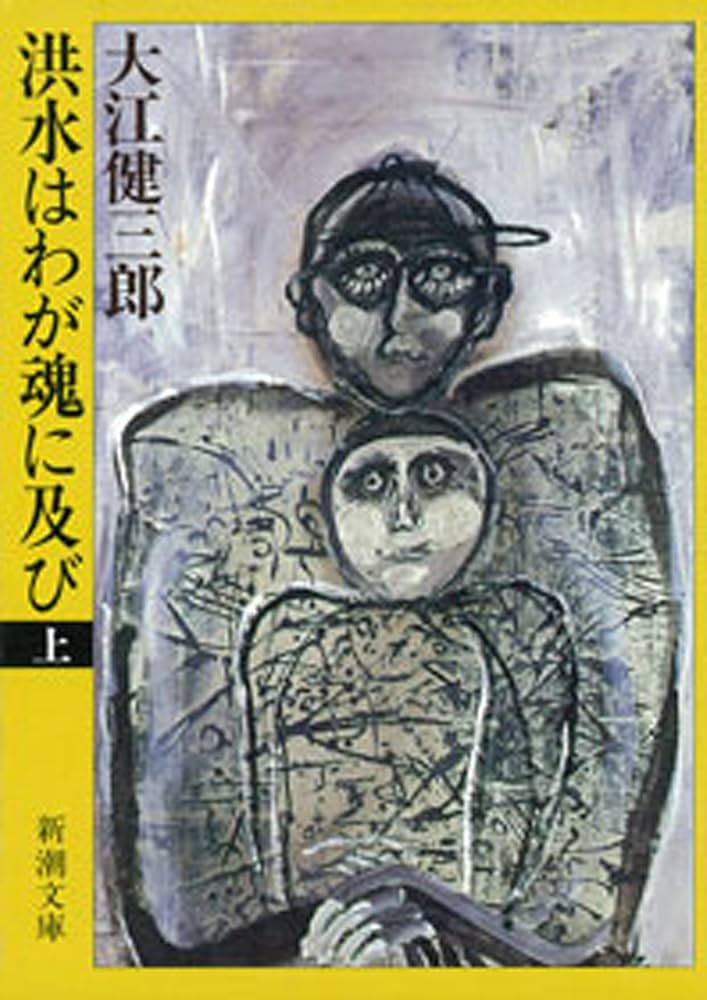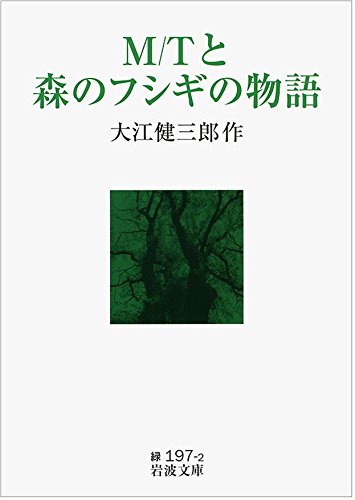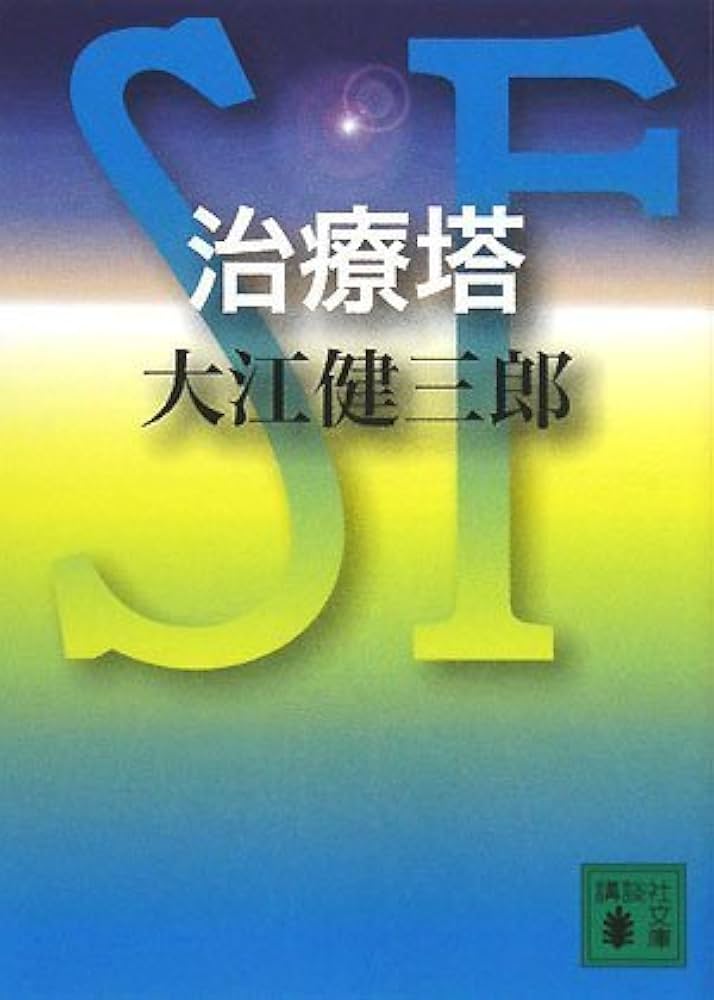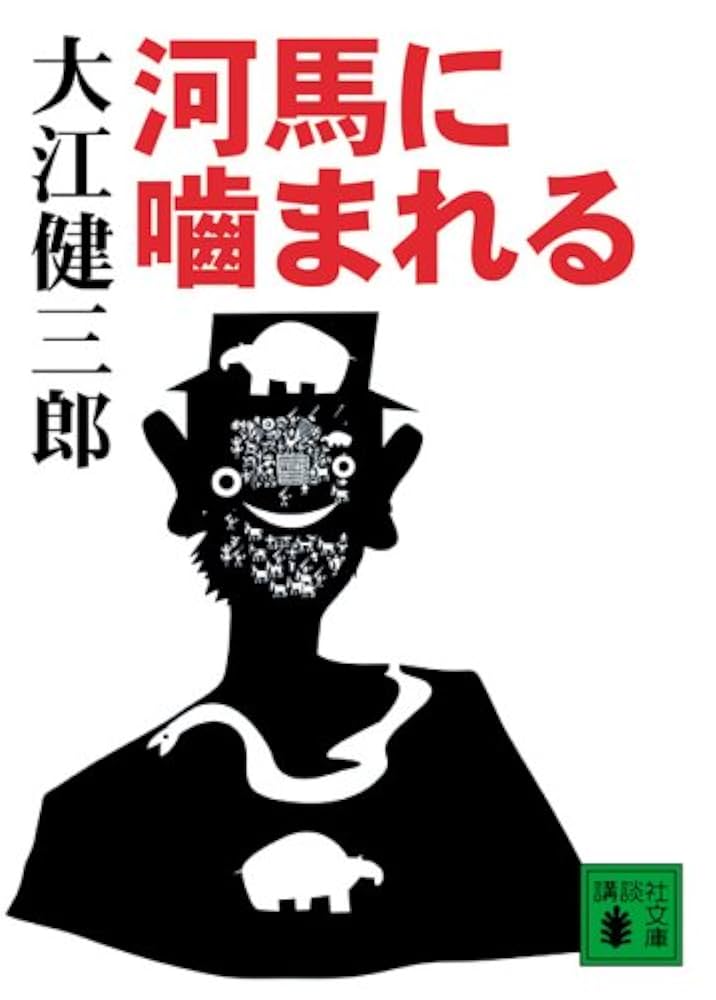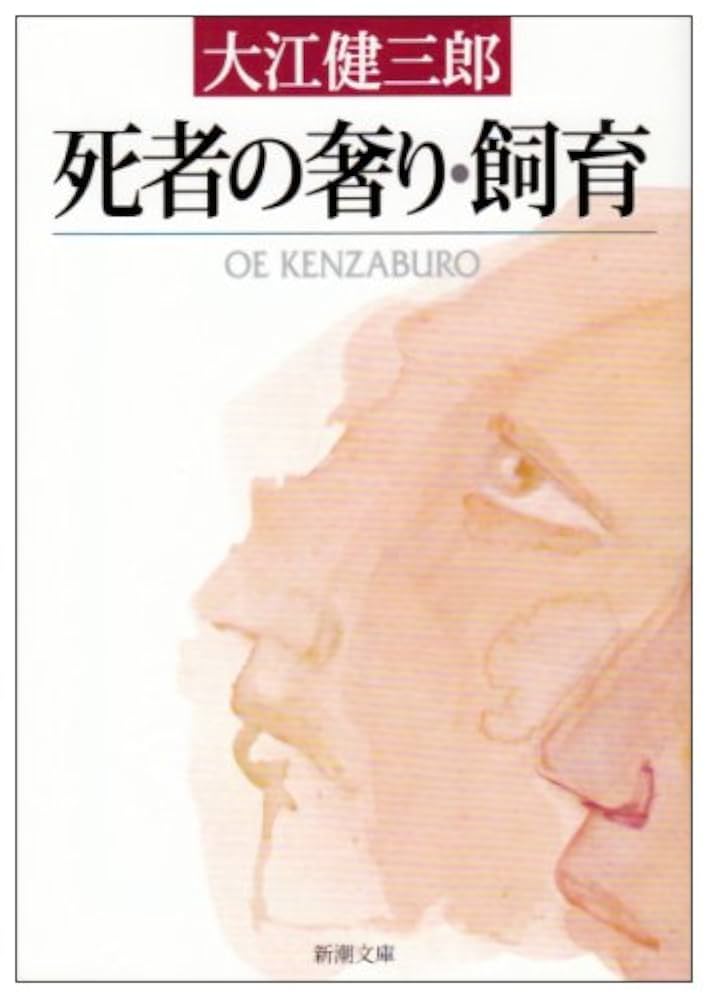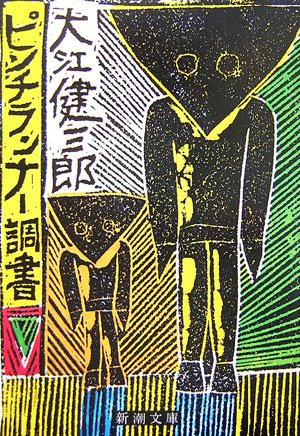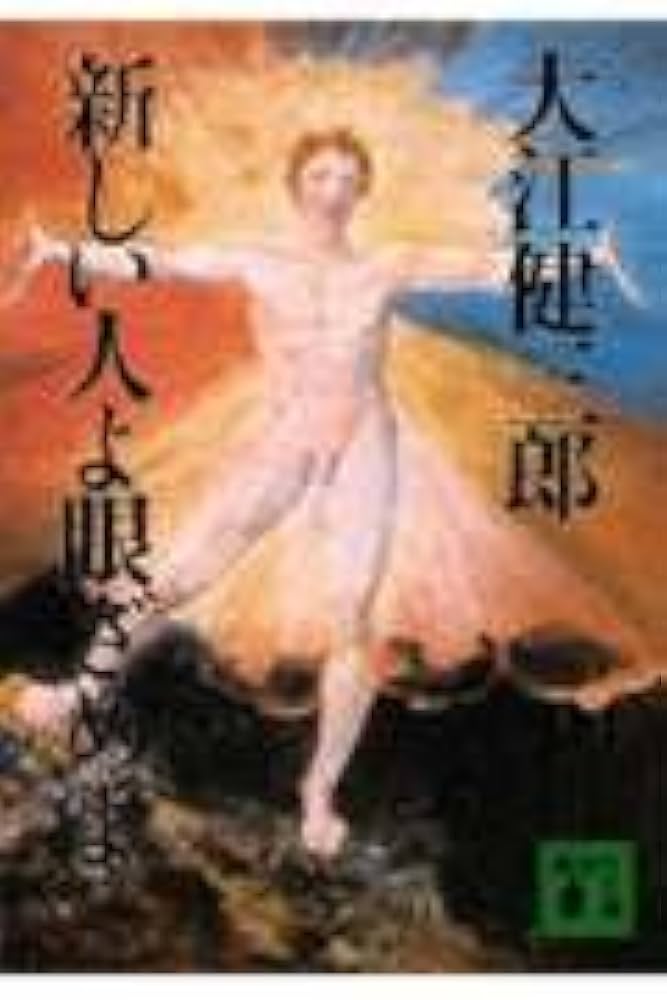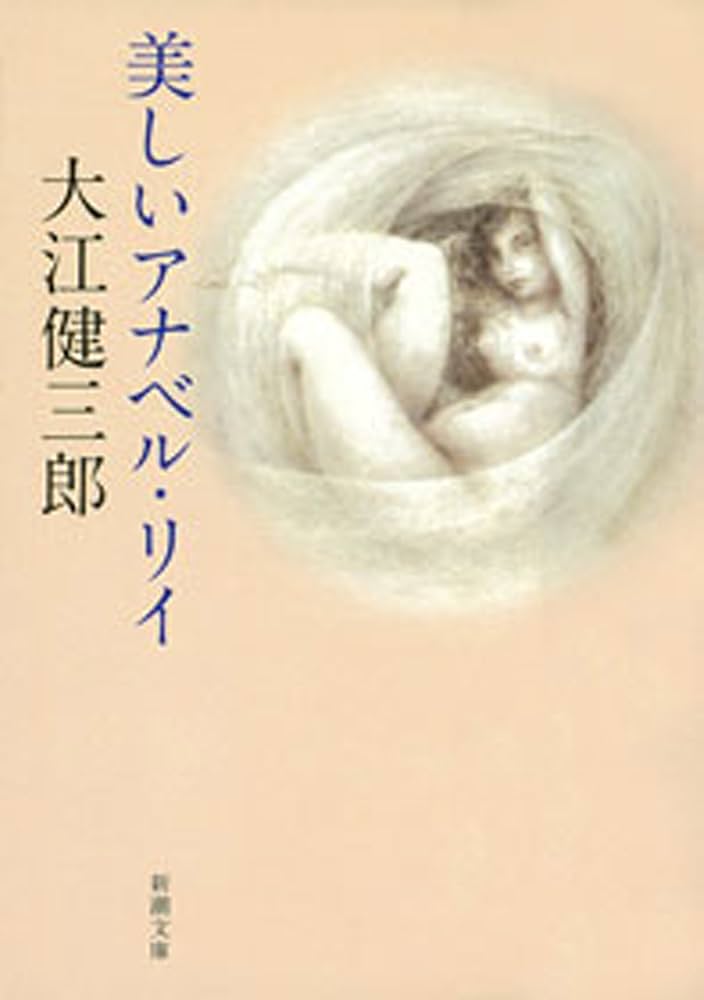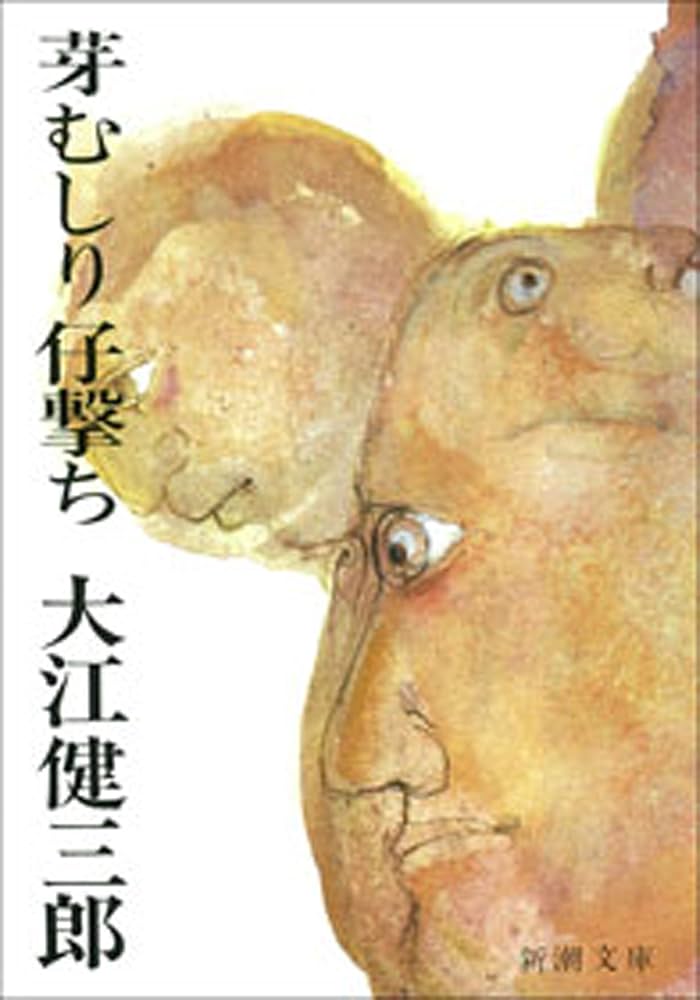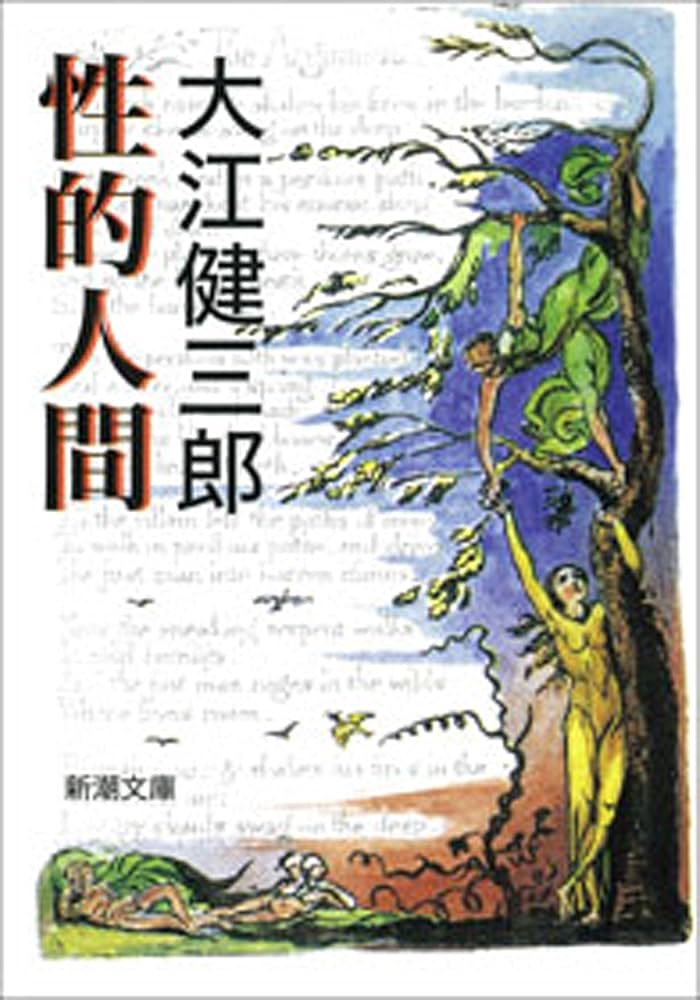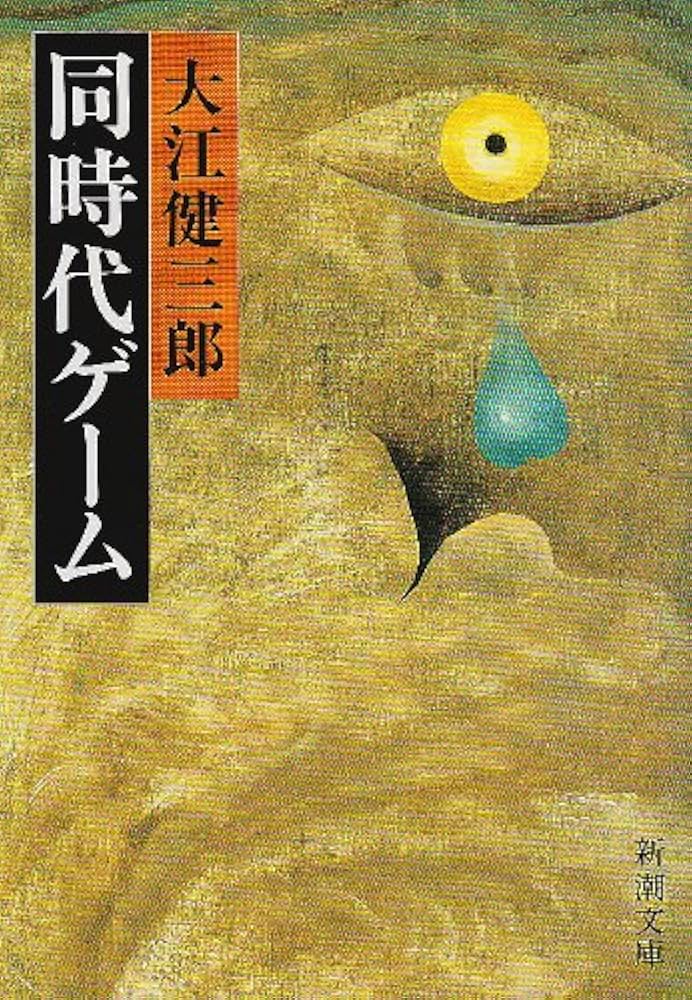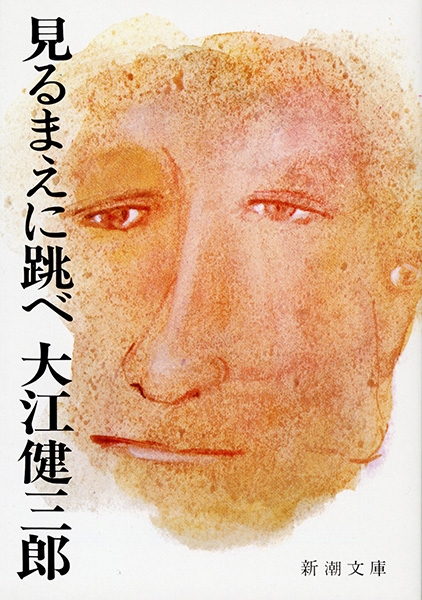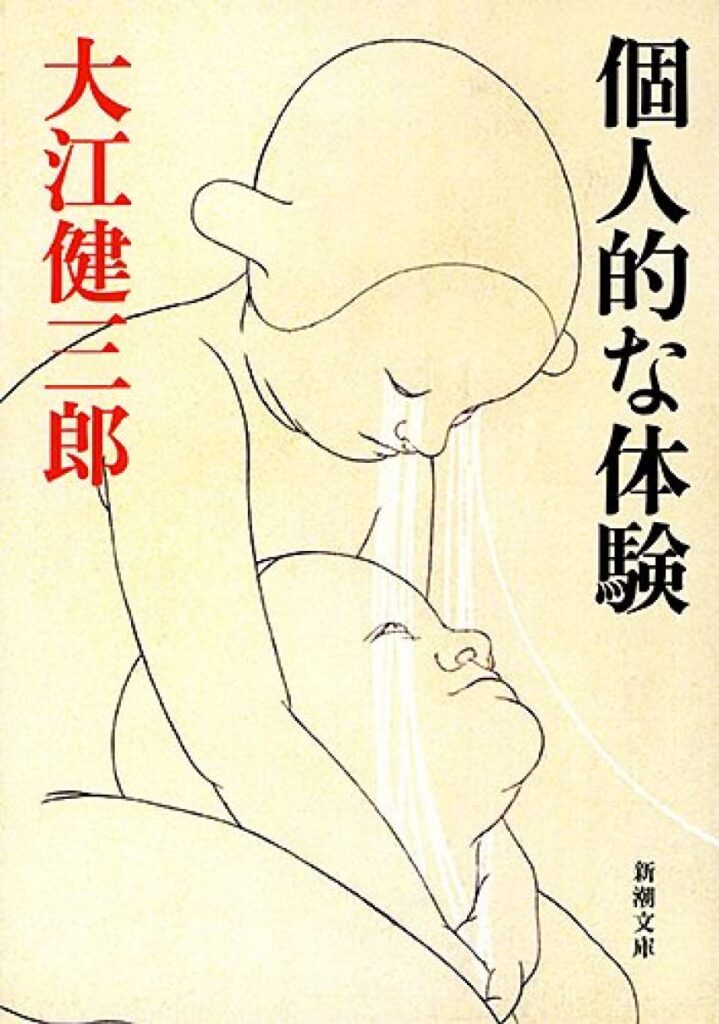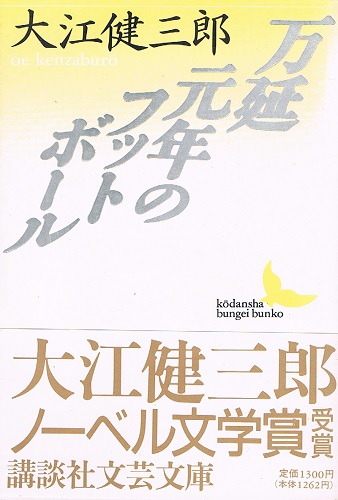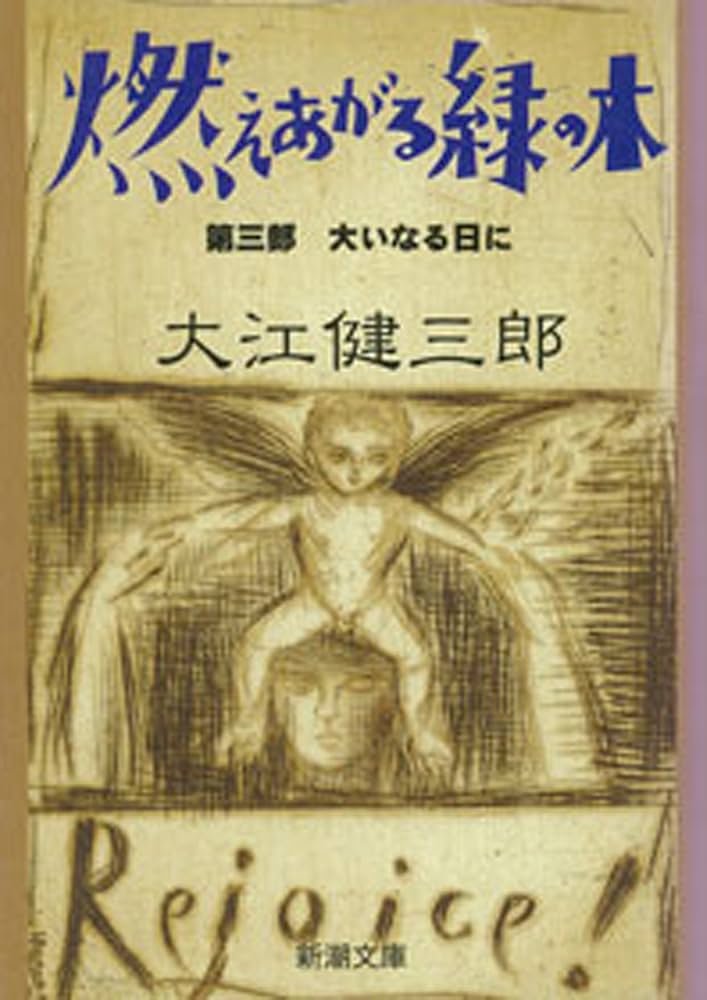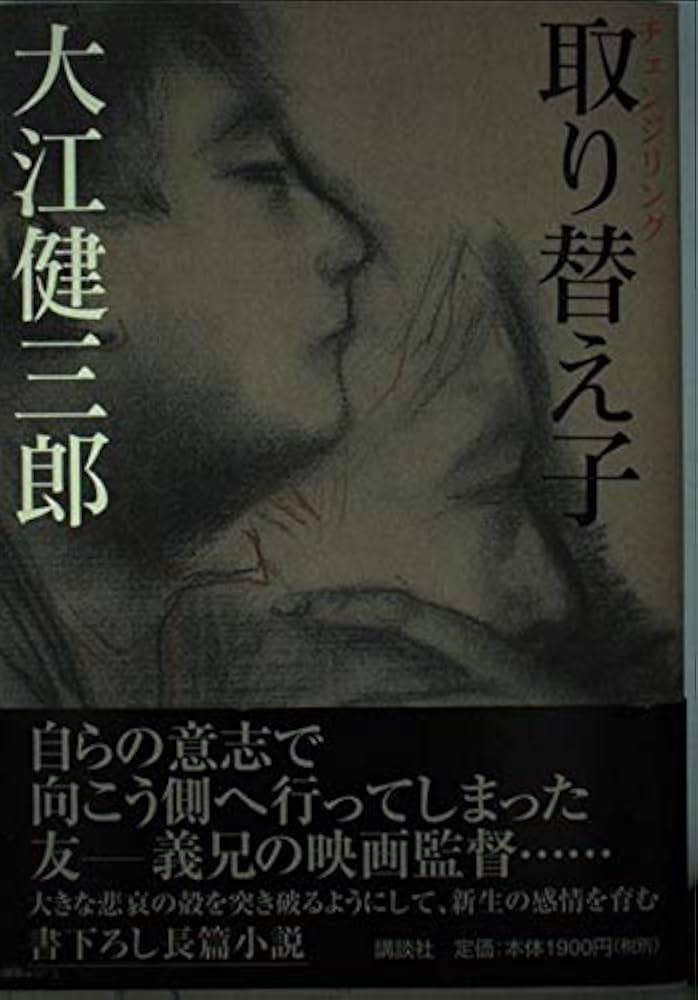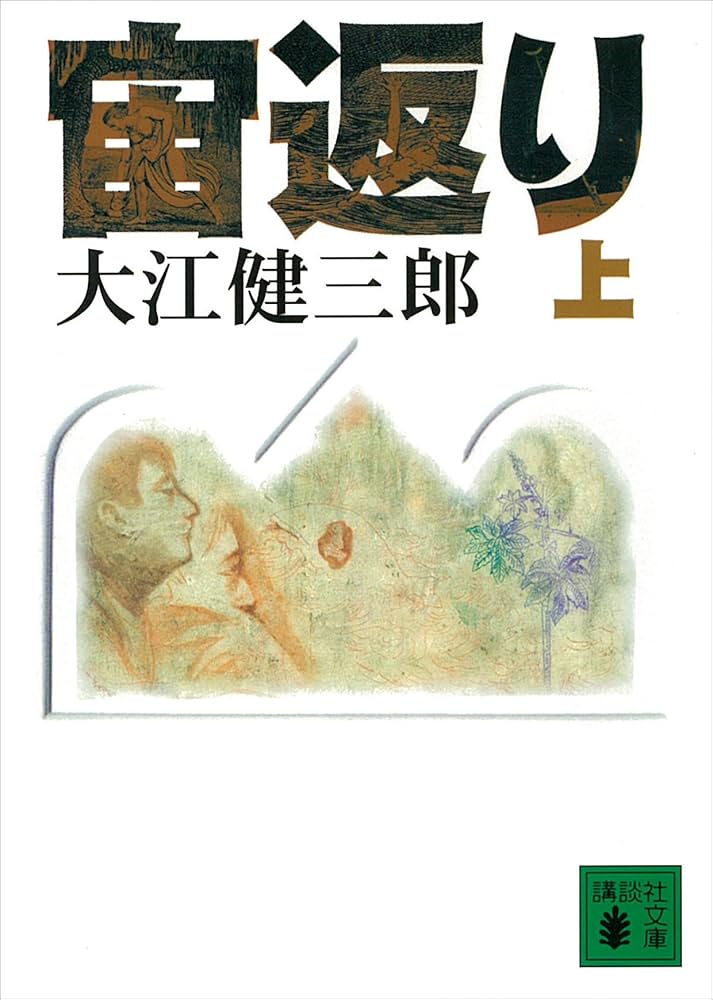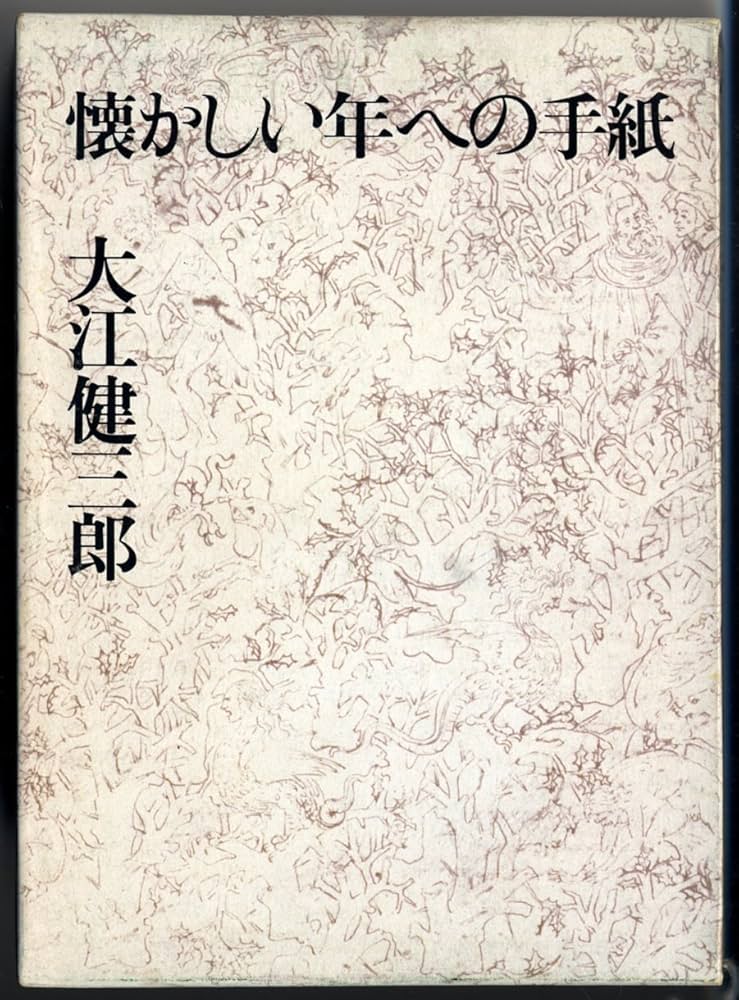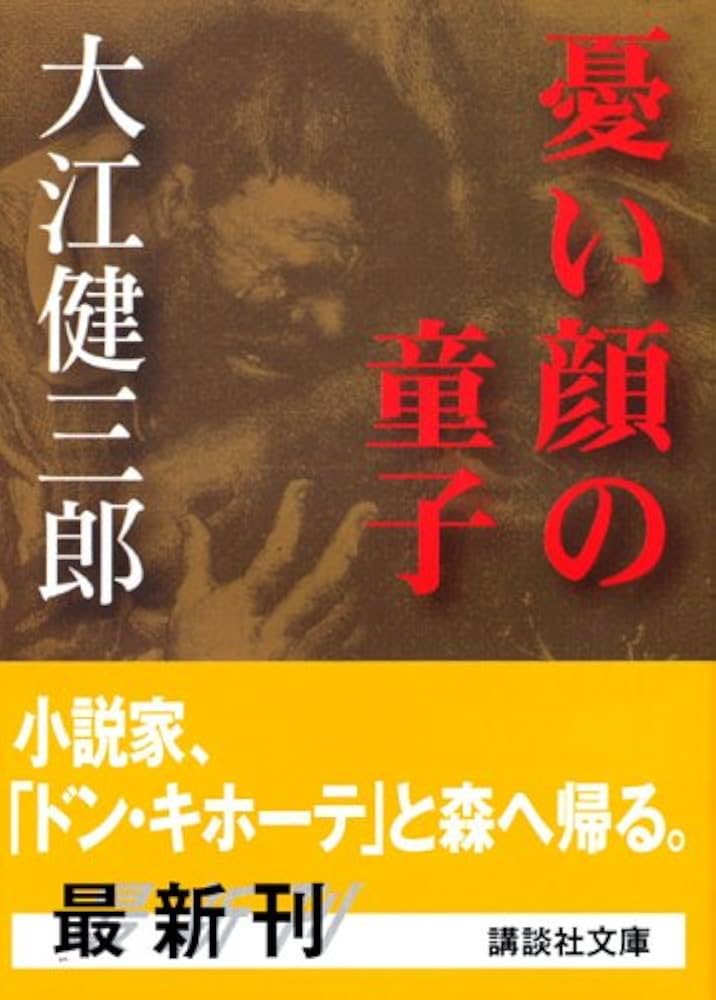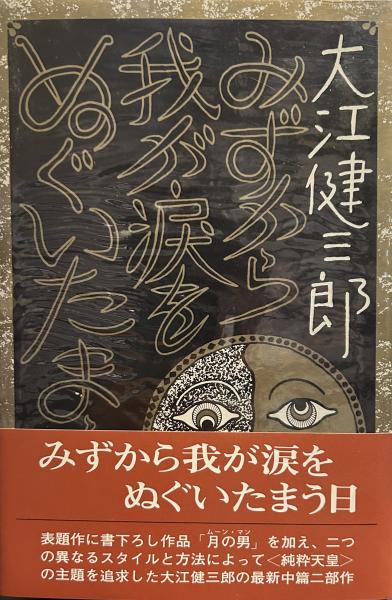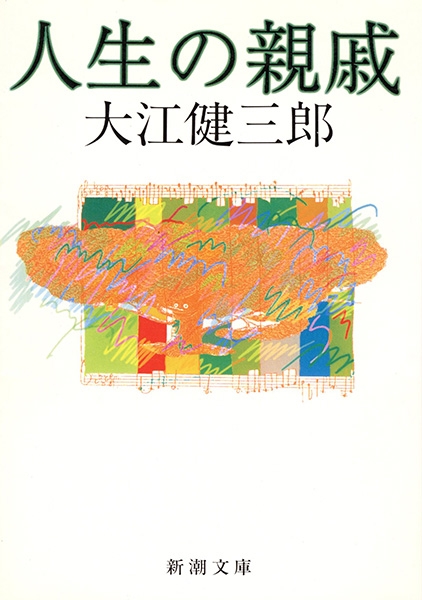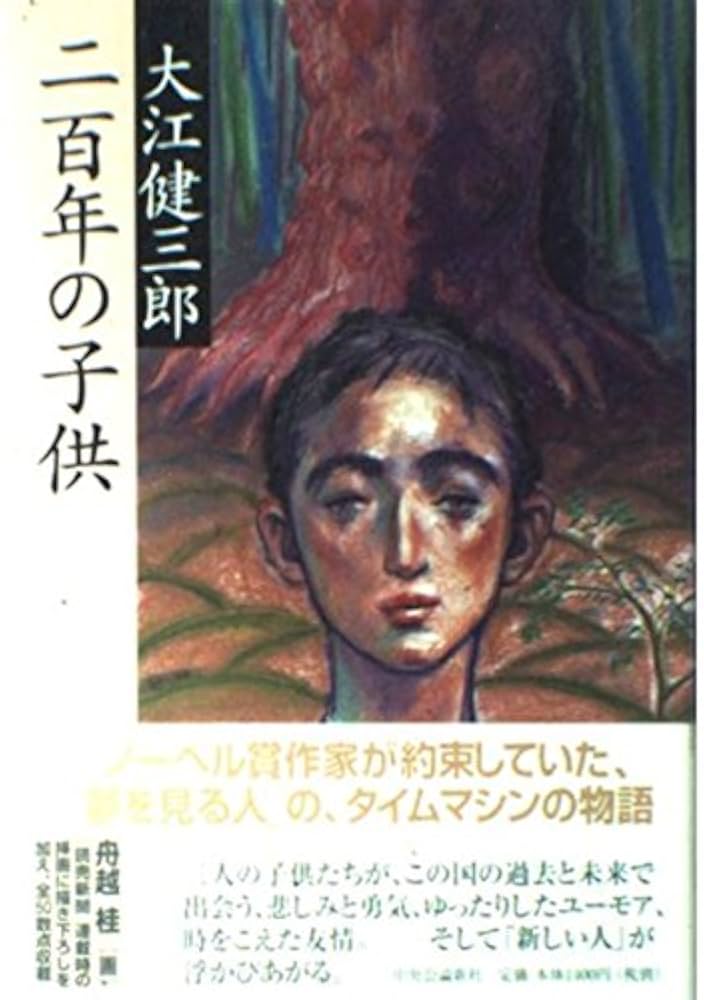小説「「雨の木」を聴く女たち」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この作品は、大江健三郎氏の中期を代表する連作短編集であり、読売文学賞を受賞したことでも知られています。物語の中心にあるのは、亡くなった友人Kが残した一本のカセットテープ。それを聴く二人の女性と、語り手である「僕」の思索を通して、魂の救済という深遠なテーマが描かれていきます。
小説「「雨の木」を聴く女たち」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この作品は、大江健三郎氏の中期を代表する連作短編集であり、読売文学賞を受賞したことでも知られています。物語の中心にあるのは、亡くなった友人Kが残した一本のカセットテープ。それを聴く二人の女性と、語り手である「僕」の思索を通して、魂の救済という深遠なテーマが描かれていきます。
物語は静かに、しかし抗いがたい力で読者を引き込みます。幻想的な「雨の木」というイメージは、一度読むと忘れられない印象を残すでしょう。この記事では、そんな『「雨の木」を聴く女たち』の物語の骨子に触れつつ、その魅力に迫っていきたいと考えています。
本記事の後半では、物語の結末にも触れる詳しいネタバレを含む感想を述べていきます。まだ『「雨の木」を聴く女たち』を読んでいないけれど、どんな話か知りたいという方、あるいは既読で他の人の解釈に触れたいという方にも、楽しんでいただける内容を目指しました。
それでは、大江健三郎氏が紡ぎ出した、死と再生をめぐる思索の森へ分け入っていきましょう。これから『「雨の木」を聴く女たち』の世界を、ご案内します。
「雨の木」を聴く女たちのあらすじ
作家である「僕」のもとに、ある日、大学時代の旧友Kの元妻が訪ねてきます。Kはアルコール依存症の末に事故で亡くなったと聞いていました。彼女が持参したのは、Kが死の直前に録音したカセットテープ。そこには、K自身の声で、ある樹木に関するテキストの朗読と、断片的な彼の体験が吹き込まれていました。
「僕」がテープを再生すると、Kの静かな声が「雨の木(レイン・ツリー)」という不思議な木について語り始めます。それは、夜降った雨をその無数の小さな葉に蓄え、翌日の昼過ぎまで滴らせ続ける、宇宙のモデルのような木だといいます。Kはこの「雨の木」のイメージに深く傾倒していたようです。
テープには、彼が客員教授として滞在したメキシコでの陰惨な体験も記録されていました。暴力と死のイメージに囚われた彼の精神状態がそこからはうかがえます。その後「僕」は、Kが亡くなるまで共に暮らしていた若い女優と出会います。彼女もまた、同じテープのコピーを持っており、夜ごとそれを聴き、Kの魂の救済を願っていました。
二人の女性は、Kという一人の男性の死を共有しながらも、対照的な態度を見せます。元妻は理知的に彼の遺した言葉を分析しようとし、現在のパートナーは情緒的に彼の魂に寄り添おうとします。Kの死の真相、そして彼がテープに込めた本当の思いとは何だったのでしょうか。「僕」は、二人の女性と共に、Kの魂の行方を追想していくことになります。
「雨の木」を聴く女たちの長文感想(ネタバレあり)
この物語に触れるということは、死者の声に耳を澄ます行為に他なりません。物語の中心には、すでにこの世にいないKという男がいます。彼の肉体は滅びていますが、その声、思索、そして魂の遍歴は、一本のカセットテープに封じ込められ、残された者たちの元へと届けられます。
『「雨の木」を聴く女たち』というタイトルが示す通り、この物語の主役はKの声を「聴く」人々です。語り手の「僕」、Kの元妻、そして彼の最期を看取った若いパートナー。彼女たちはそれぞれ異なる形でKの記憶と向き合い、彼が遺した「雨の木」という謎めいたメタファーを解き明かそうとします。
「雨の木」とは、宇宙のモデルであるとKは語ります。無数の葉の一枚一枚が宇宙の構成単位であり、そこに蓄えられた水滴が滴り落ちることで、個々の魂は癒され、再生される。この壮大で美しいイメージは、アルコールに溺れ、破滅的な人生を送ったKがたどり着いた、魂の救済のための装置であったのかもしれません。
物語を読み進める中で、読者もまた、この「聴く女たち」そして「僕」と同じ立場に置かれます。Kの断片的な語り、二人の女性の証言、そして「僕」の思索を組み合わせながら、Kという人物の輪郭を、そして彼の魂のありかを探っていくことになるのです。ここからは、物語の核心に触れるネタバレを含みながら、さらに深く作品を味わっていきたいと思います。
重要なのは、Kの死が単なる事故ではなかったという事実です。若いパートナーの口から、それが自死であったことが明かされます。このネタバレは、物語の様相を大きく変えます。彼はなぜ死を選んだのか。それは絶望からなのか、それとも、彼が語る「雨の木」の思想と結びついた、ある種の積極的な行為だったのでしょうか。
Kがメキシコで体験したという、人間の根源的な暴力と性の記憶。それは彼の精神を深く蝕みました。彼は自らの内にも潜む暴力性や、どうしようもない絶望から逃れるために、死を選んだのかもしれません。そして、その魂の救済を「雨の木」というイメージに託したのではないでしょうか。
対照的な二人の女性の存在が、『「雨の木」を聴く女たち』に奥行きを与えています。知性によってKのテクストを解体し、理解しようとする元妻。彼女の態度は、Kの破滅的な生き方から距離を置こうとする防衛本能の表れにも見えます。彼女はKを過去として、テクストとして処理しようとしているようです。
一方、若いパートナーは、Kのすべてを情緒的に受け入れ、彼の魂が「雨の木」によって救われることを純粋に信じています。彼女はKのテクストを分析するのではなく、ただひたすらに「聴く」ことで、彼の魂と一体化しようと試みます。この二人の女性の間に立ち、語り手である「僕」はKの魂の継承者としての役割を担うことになります。
この小説の構造自体が、死者の魂をいかに受け継ぐかというテーマを体現しています。カセットテープというメディアは、まさに死者の声を再生するための装置です。何度も繰り返し聴くことができるその声は、時間や空間を超えて、Kの存在を残された者たちの内に呼び覚まし続けます。
音楽家Tさんが登場し、「僕」が書いた「雨の木」に関する文章から曲を作るというエピソードも象徴的です。Kの思想は、テープの声として、そして「僕」によって書き起こされたテクストとして、さらには音楽として、形を変えながら再生され、継承されていくのです。これは、一つの魂が多くの他者を通して生き続ける可能性を示唆しています。
物語の結末で、「僕」が下す決断は、この物語の核心を突くものです。これから述べることは、この作品の最も重要なネタバレになります。「僕」は、Kがテープに残した「雨の木」のテクストを、自らの手で一語一語、書き写すことを決意します。
これは単なる模倣ではありません。他者のテクストを書き写すという身体的な行為を通して、Kの思索と魂を自らの内に取り込み、再生させようとする試みなのです。ペンを取り、紙に向かう「僕」の姿は、Kの魂の正式な継承者となったことを示す、静かで厳かな儀式のように見えます。
Kの肉体は消えましたが、彼の魂は「雨の木」から滴る水滴のように、彼を愛した女性たち、そして友人であった「僕」の中に染み込んでいきます。そして「僕」が書き写したテクストは、また新たな読者(あるいは聴き手)のもとへと届けられていくのかもしれません。『「雨の木」を聴く女たち』は、そうした魂の永遠の継承を描いた物語であると言えるでしょう。
この作品を読むという体験は、非常に静かで、内省的なものです。派手な事件が起こるわけではありませんが、言葉の一つ一つが持つ重みが、読者の心に深く沈み込んできます。大江健三郎氏の知性が凝縮されたような、濃密な読書体験がここにあります。
『「雨の木」を聴く女たち』は、喪失を抱えて生きるすべての人々にとって、一つの救いの形を示してくれる物語ではないでしょうか。死は決して終わりではなく、残された者たちがその記憶を語り継ぎ、受け継いでいく限り、魂は生き続けるのだと。
この物語は、明確な答えを与えてはくれません。Kの魂が本当に救済されたのかどうかは、最後まで読者の解釈に委ねられています。しかし、残された人々が彼のことを思い、彼の言葉に耳を澄まそうとする、その行為そのものの中に、救いの光が宿っているように感じられてなりません。
『「雨の木」を聴く女たち』は、一度読んだだけではその深淵のすべてを汲み尽くすことは難しいかもしれません。何度も読み返し、Kの声に耳を澄ますことで、そのたびに新たな発見がある。そんな、いつまでも心に残り続ける一冊です。
死と再生、記憶の継承、そして魂の救済という普遍的なテーマを、極めて知的かつ幻想的に描き出した『「雨の木」を聴く女たち』。未読の方はもちろん、かつて読んだという方も、この機会に再びページをめくってみてはいかがでしょうか。そこには、静かな雨音のように心に染み入る、深い感動が待っているはずです。
まとめ:「雨の木」を聴く女たちのあらすじ・ネタバレ・長文感想
この記事では、大江健三郎氏の名作『「雨の木」を聴く女たち』について、物語の導入となるあらすじから、結末に触れるネタバレを含む深い感想までを述べてきました。本作は、亡き友人が遺したカセットテープをめぐり、残された人々がその魂の行方を探る、思索的な物語です。
物語の核となる「雨の木」というメタファーは、死と再生、そして魂の救済を象徴しており、読者に強烈な印象を残します。破滅的な人生の果てに自ら死を選んだKの魂が、いかにして救われうるのか。その問いが、静かに、しかし切実に胸に迫ってきます。
感想の部分では、Kの死の真相に関するネタバレにも触れながら、語り手である「僕」がKのテクストを書き写すという結末の意味を考察しました。それは、死者の魂を受け継ぎ、自らの中に再生させようとする、希望の行為として描かれています。
『「雨の木」を聴く女たち』は、喪失の悲しみと、それでも続いていく生の中で、人が何を求め、何に救いを見出すのかを問いかける作品です。この静かで美しい物語が、あなたの心にも深く染み入ることを願っています。