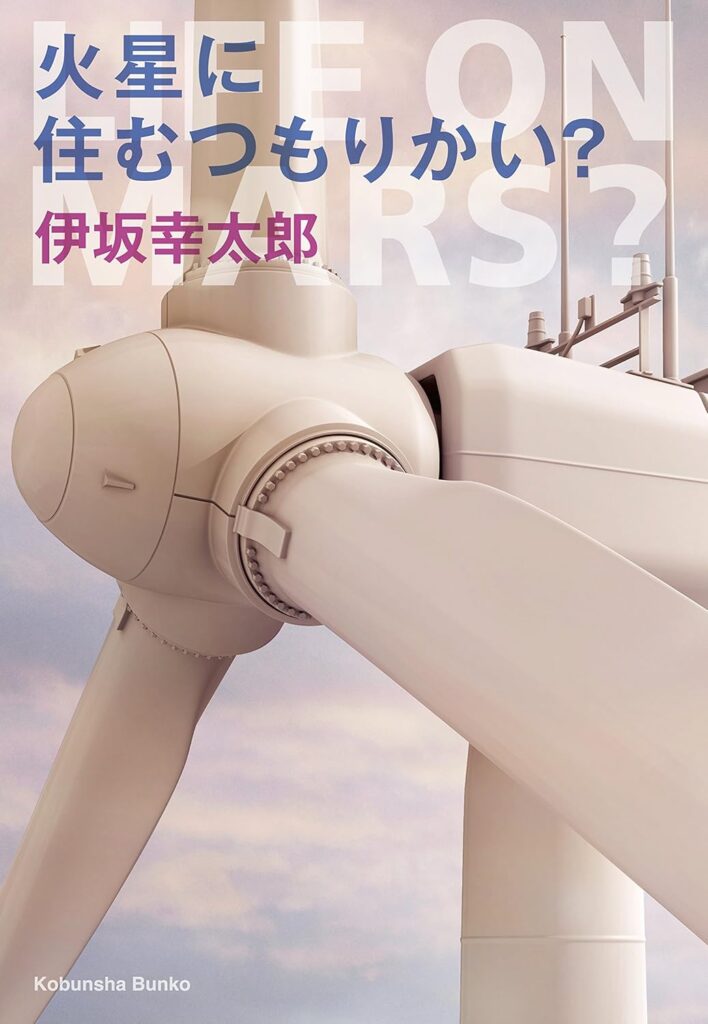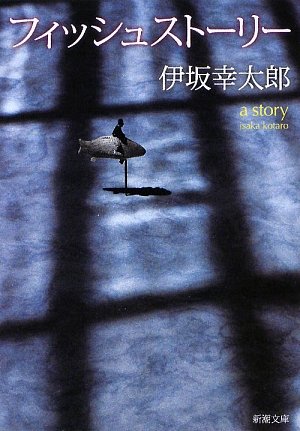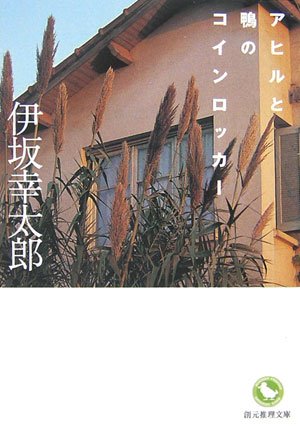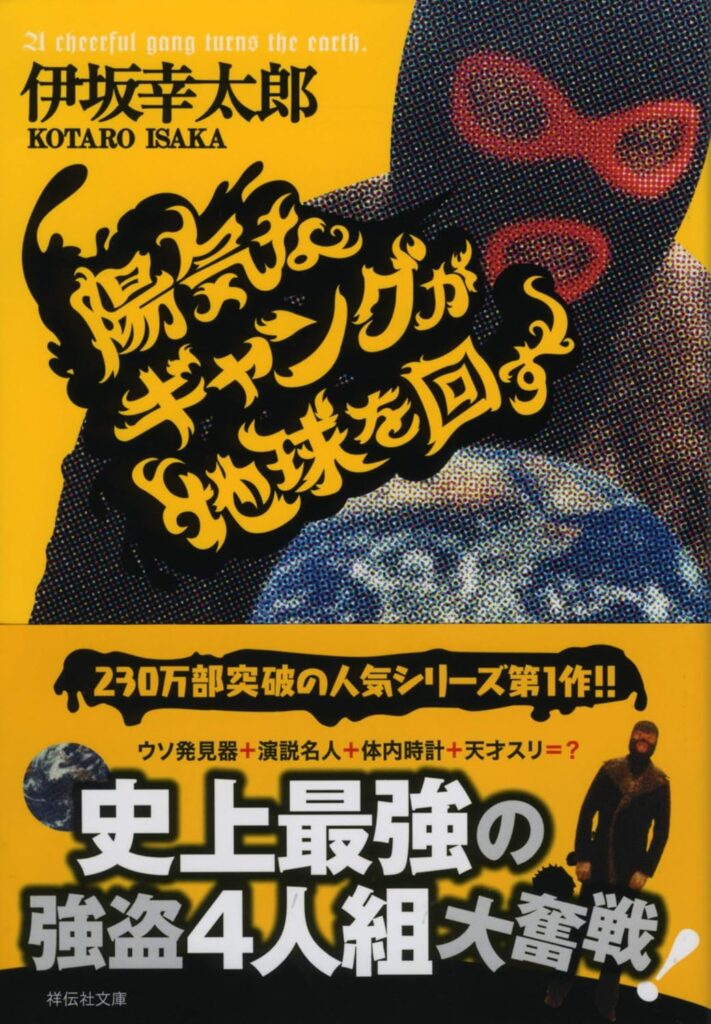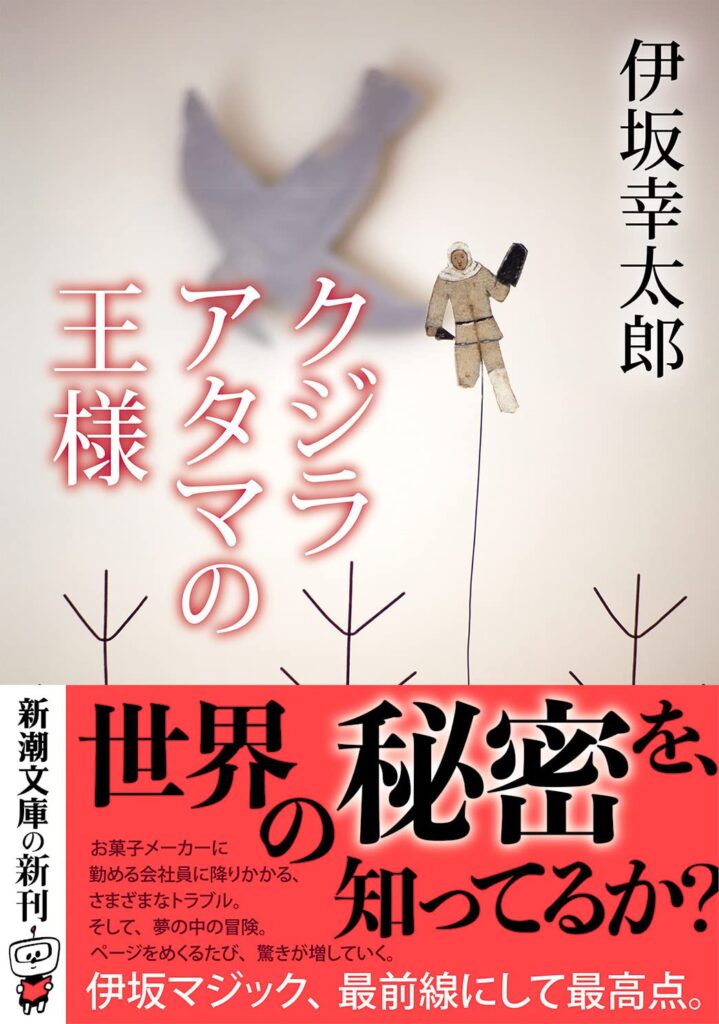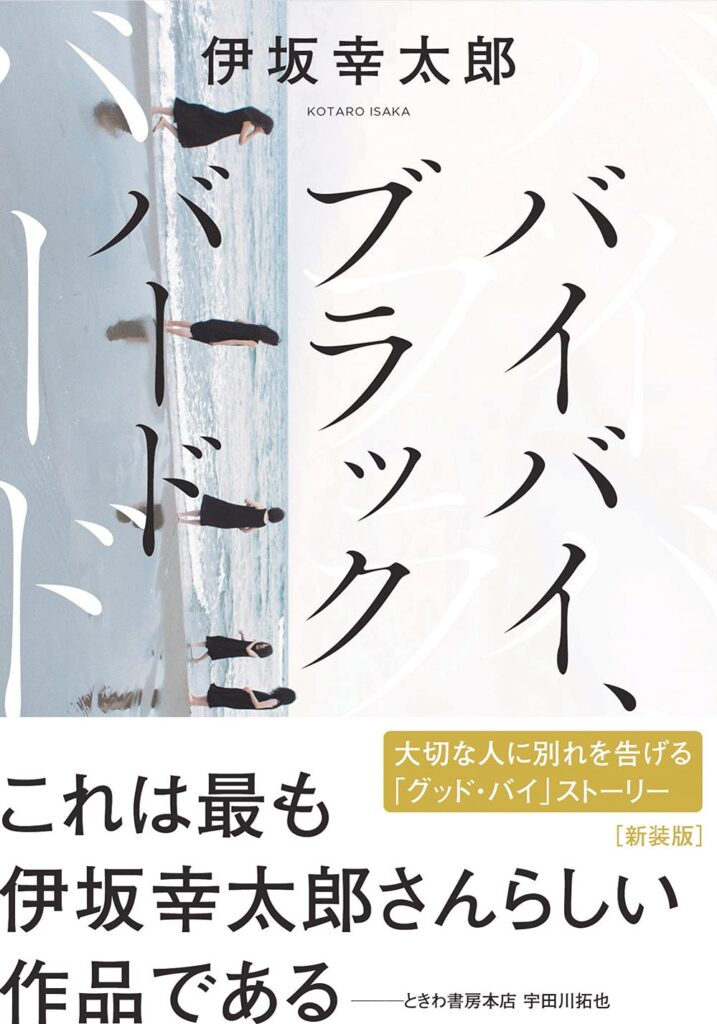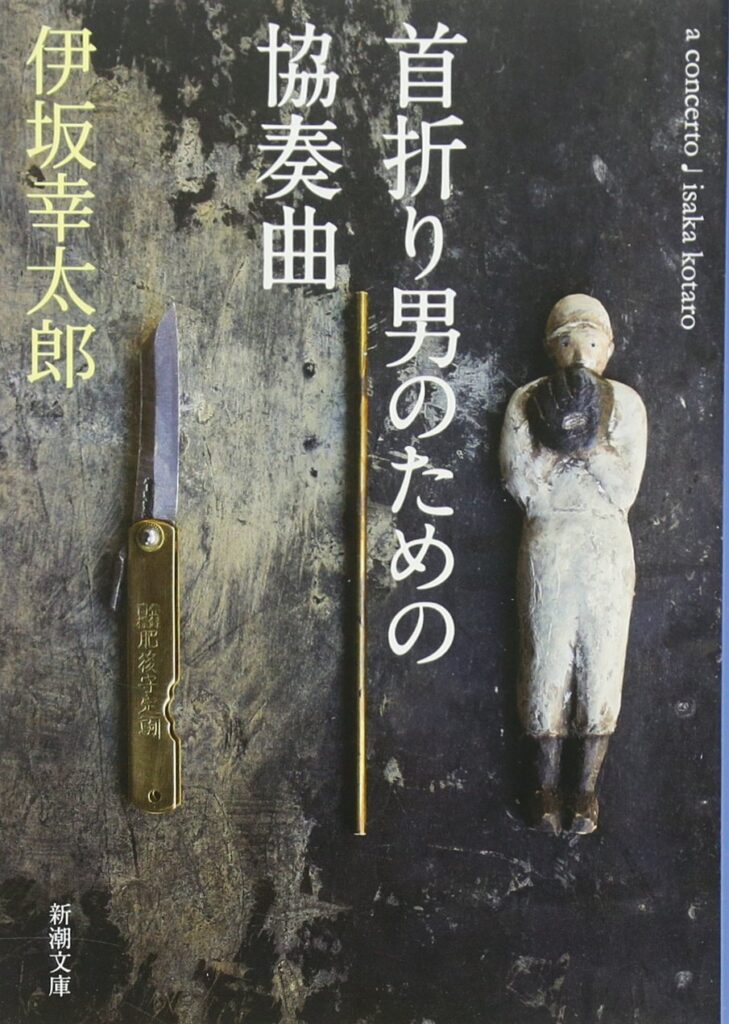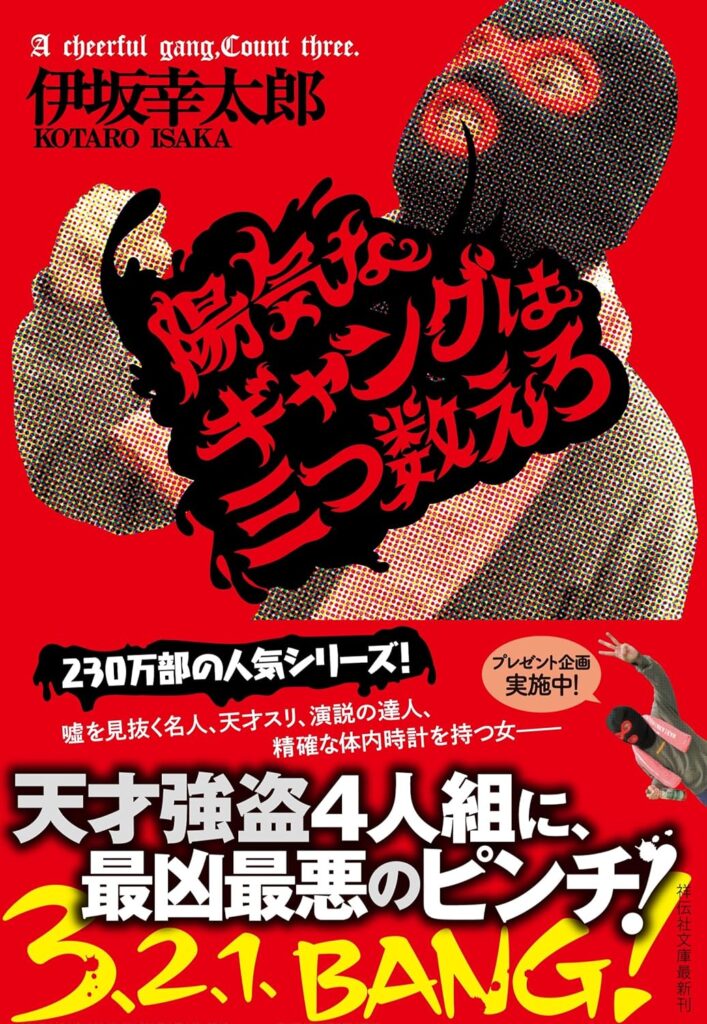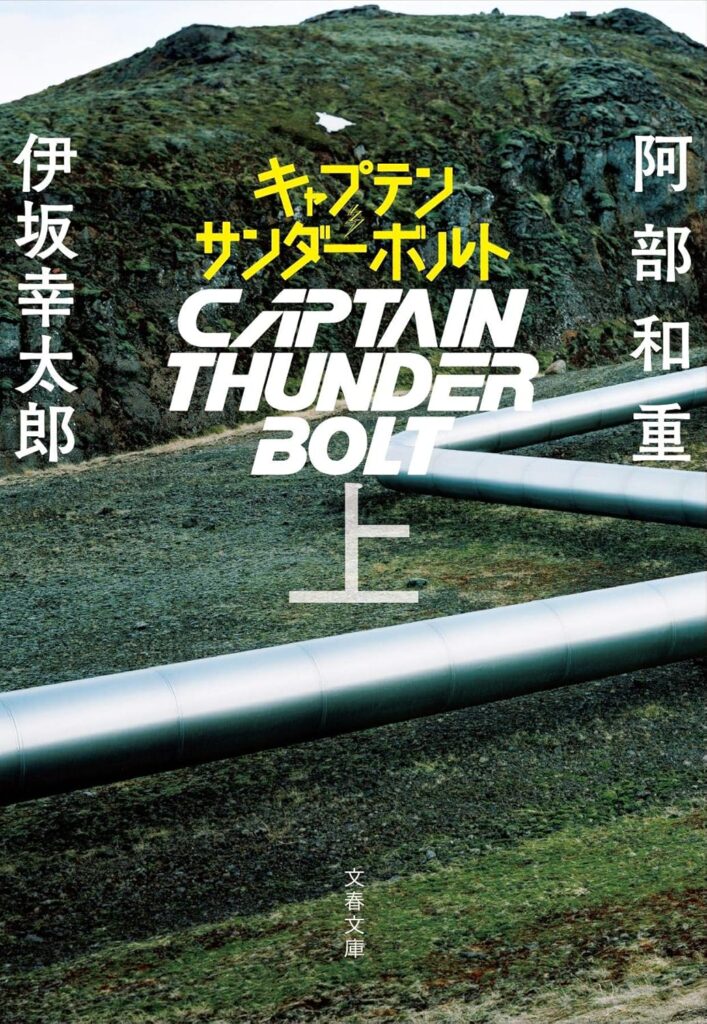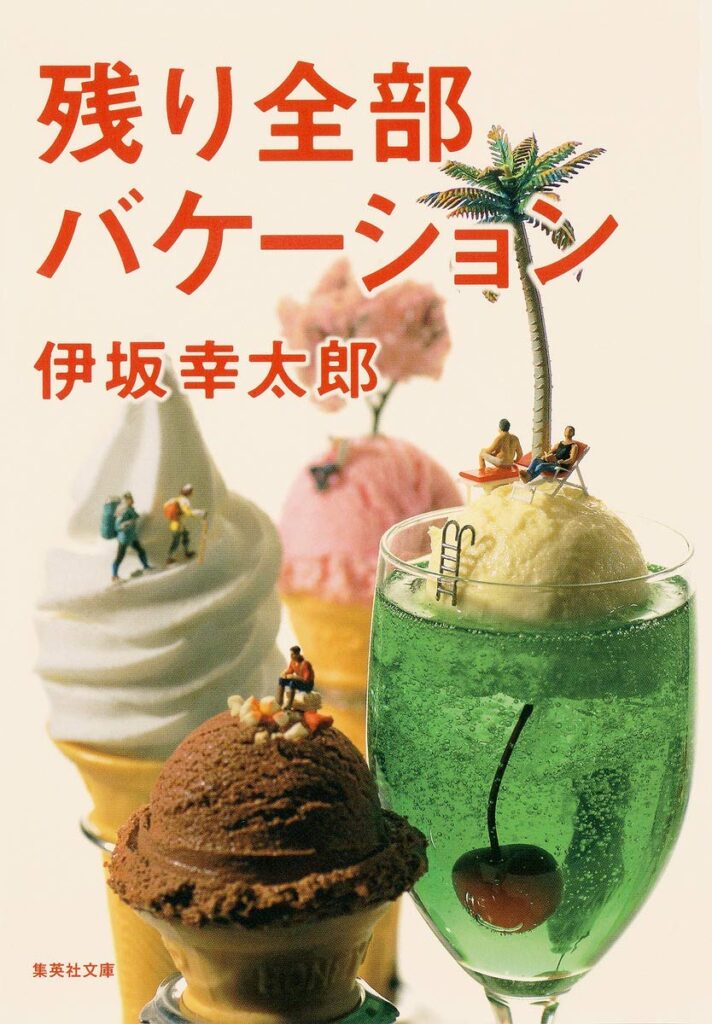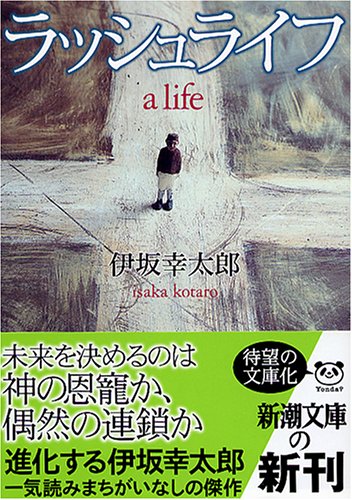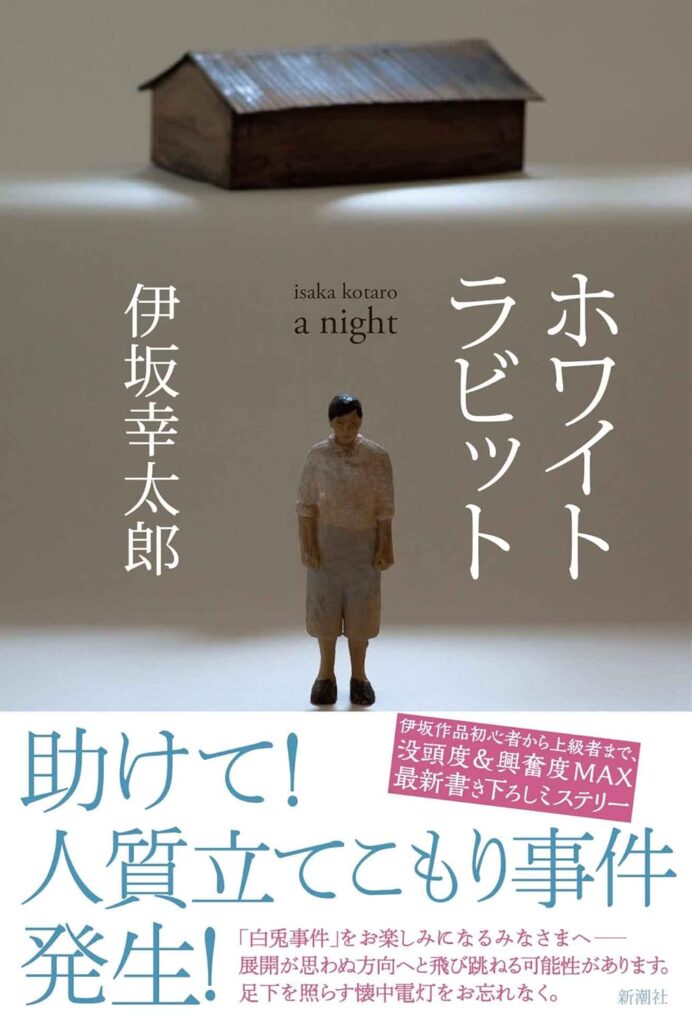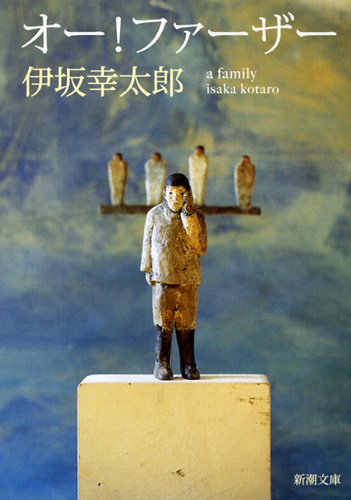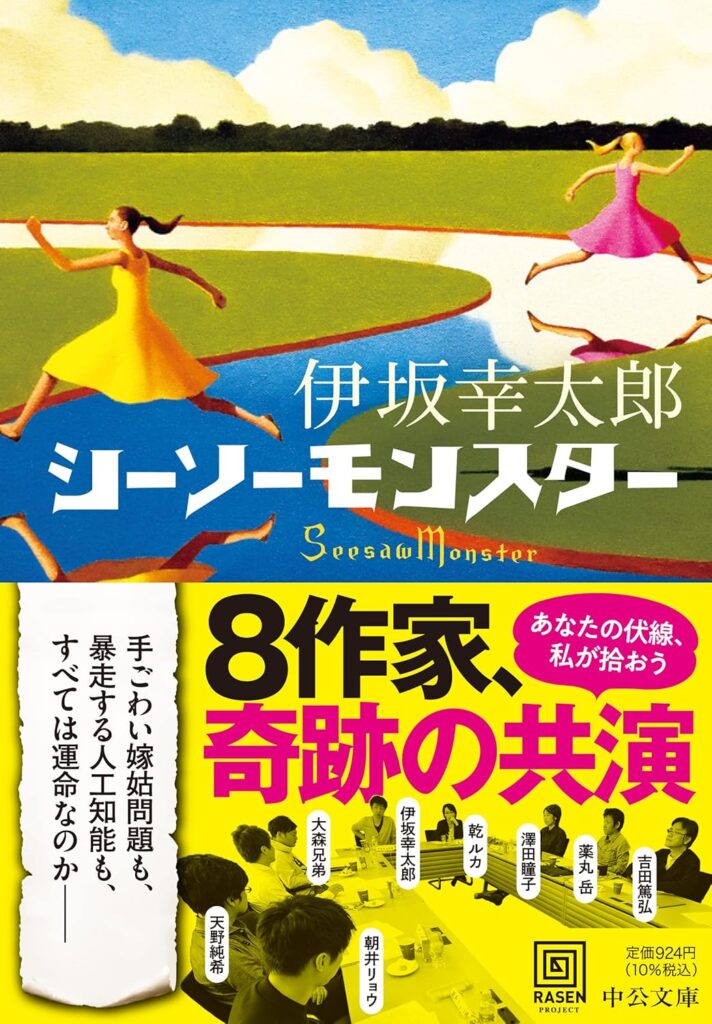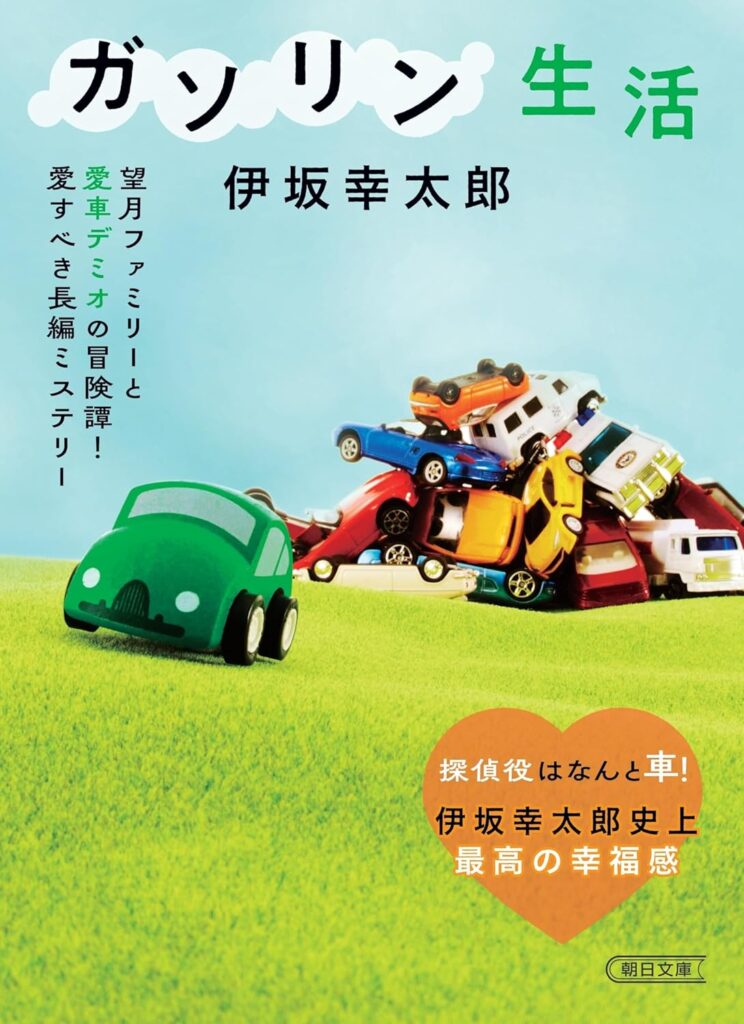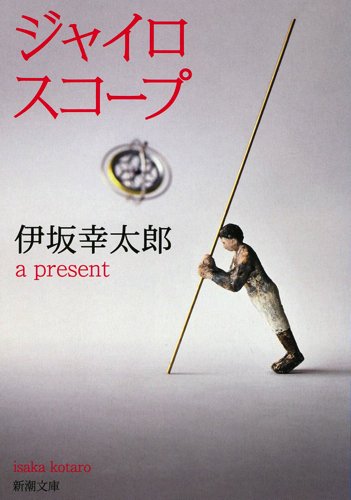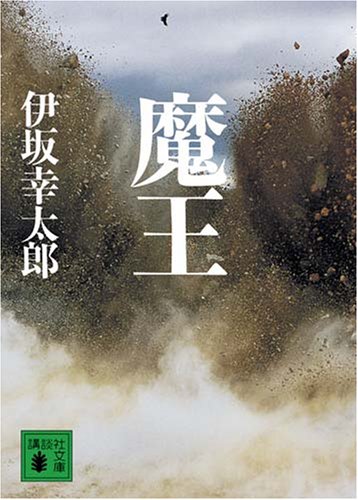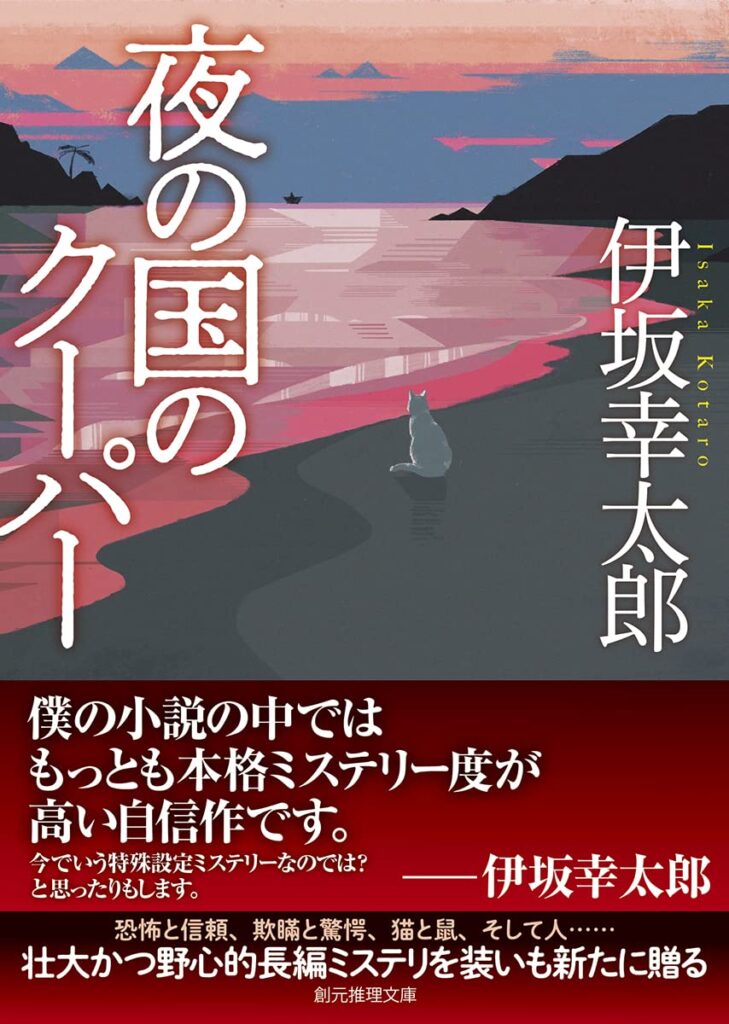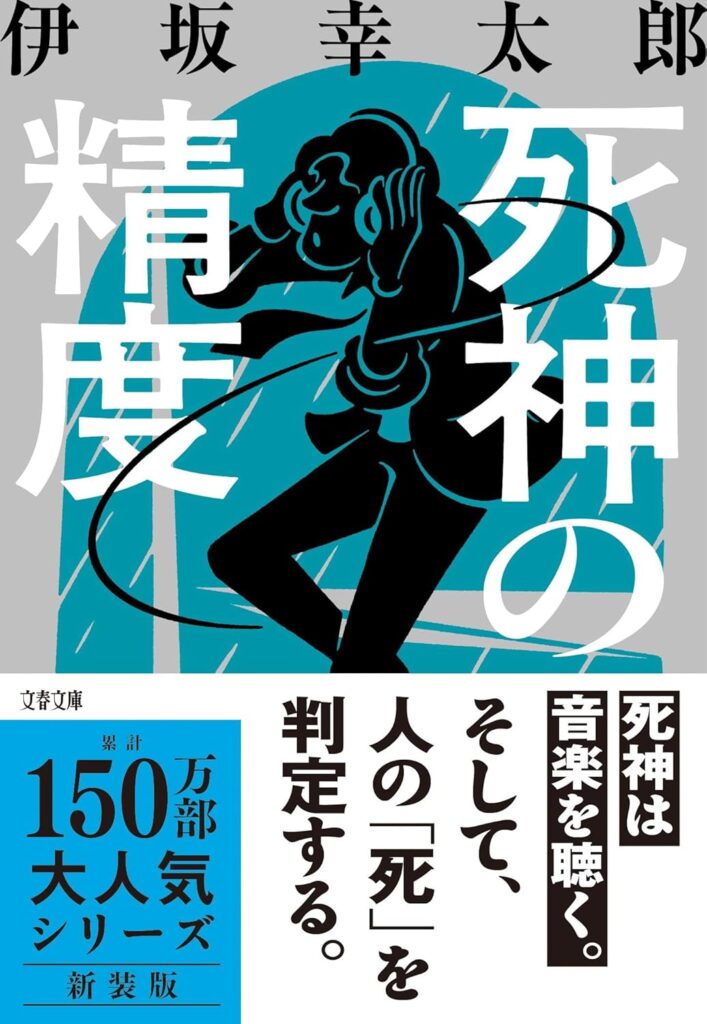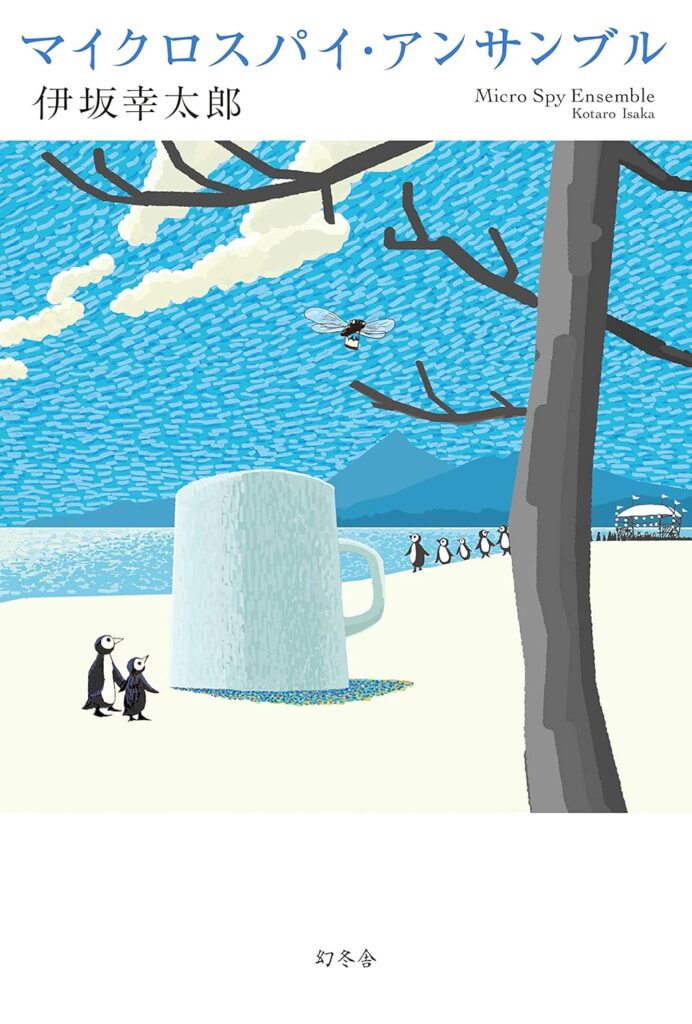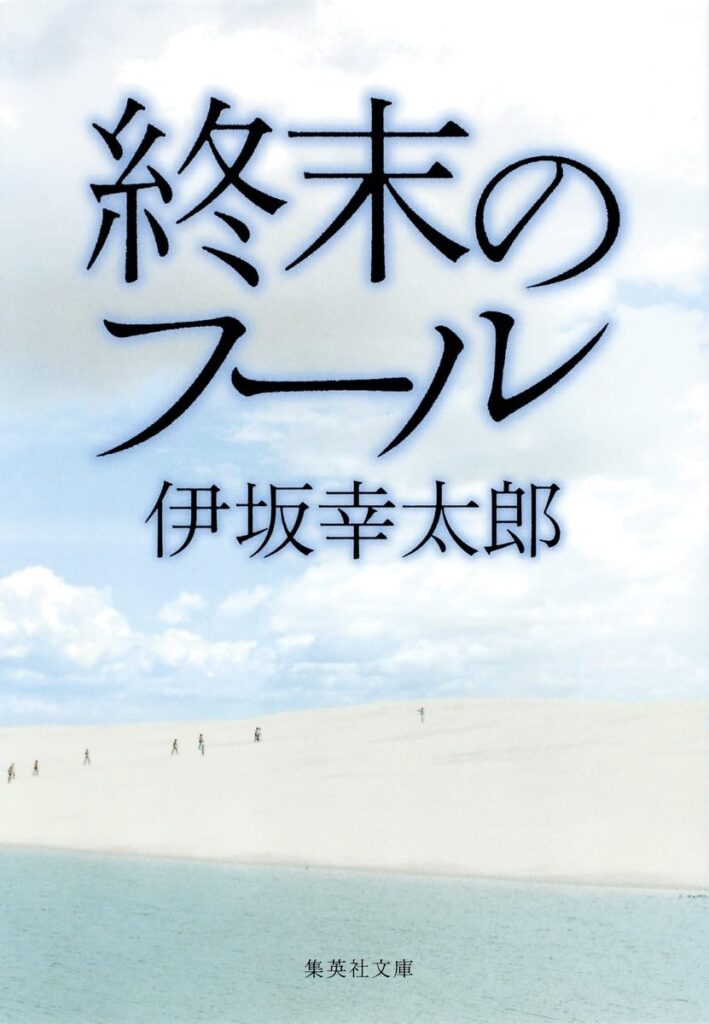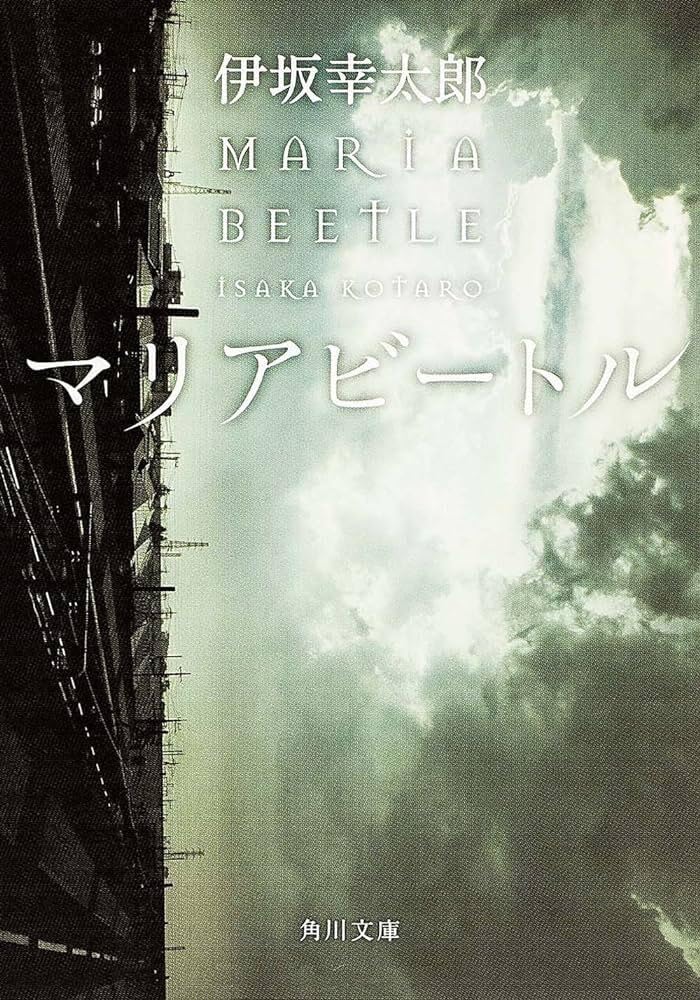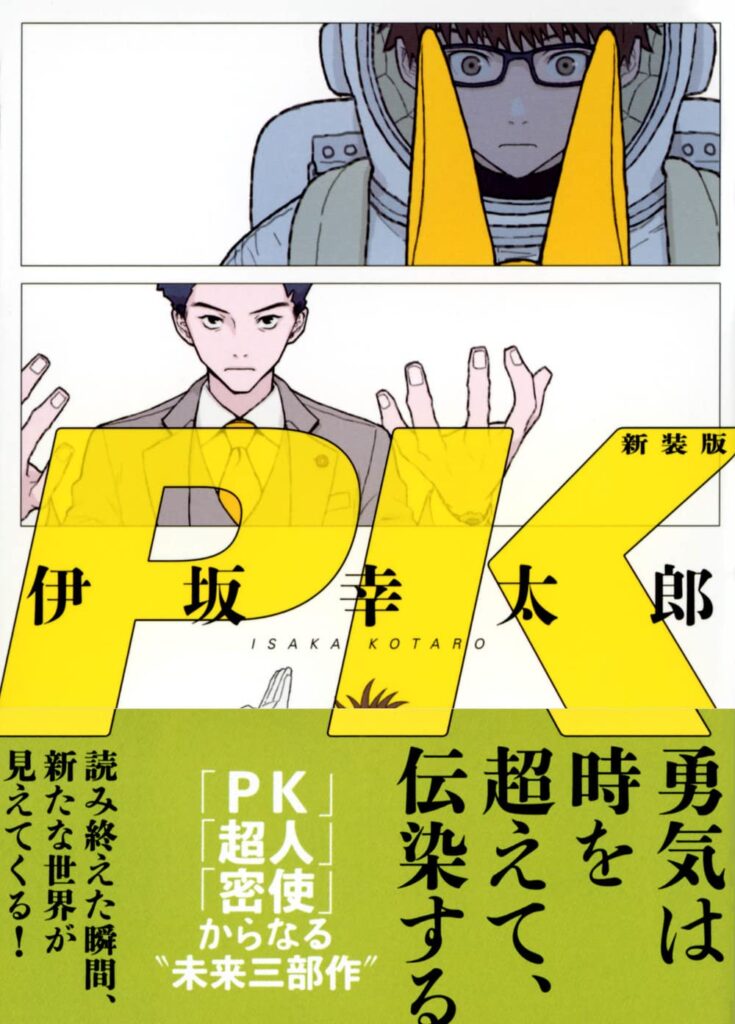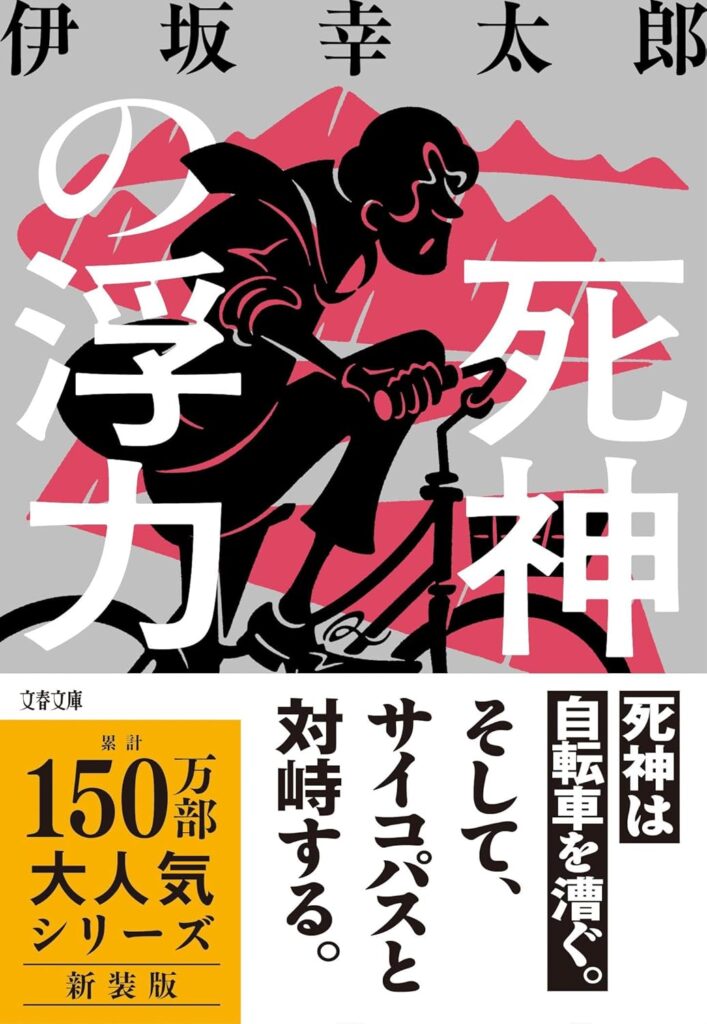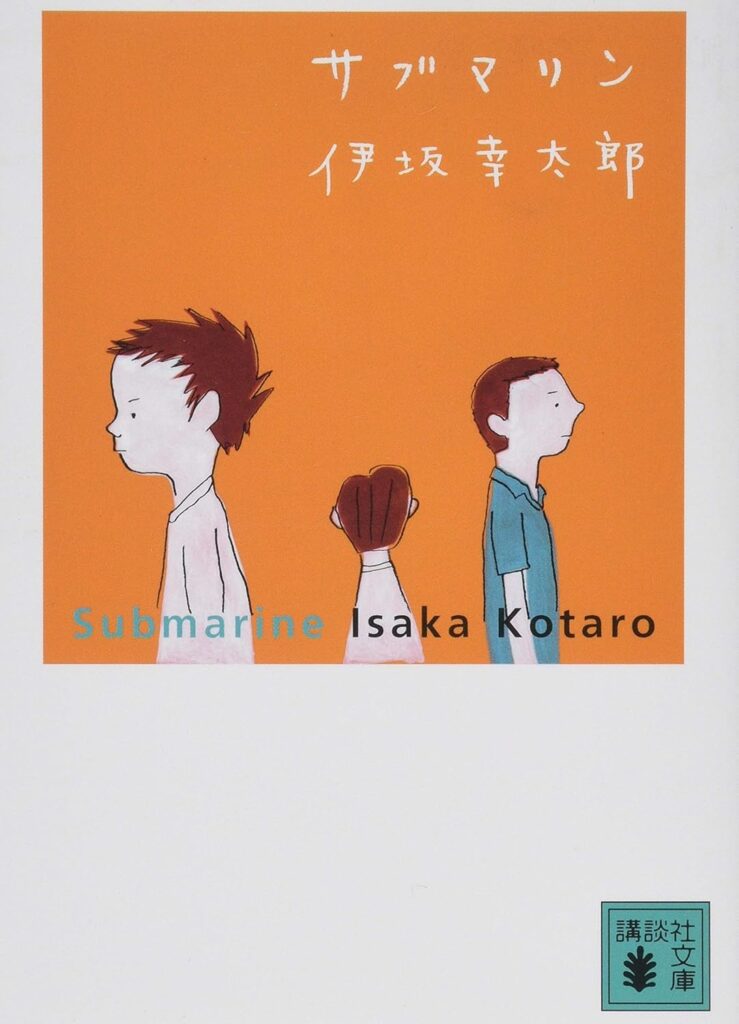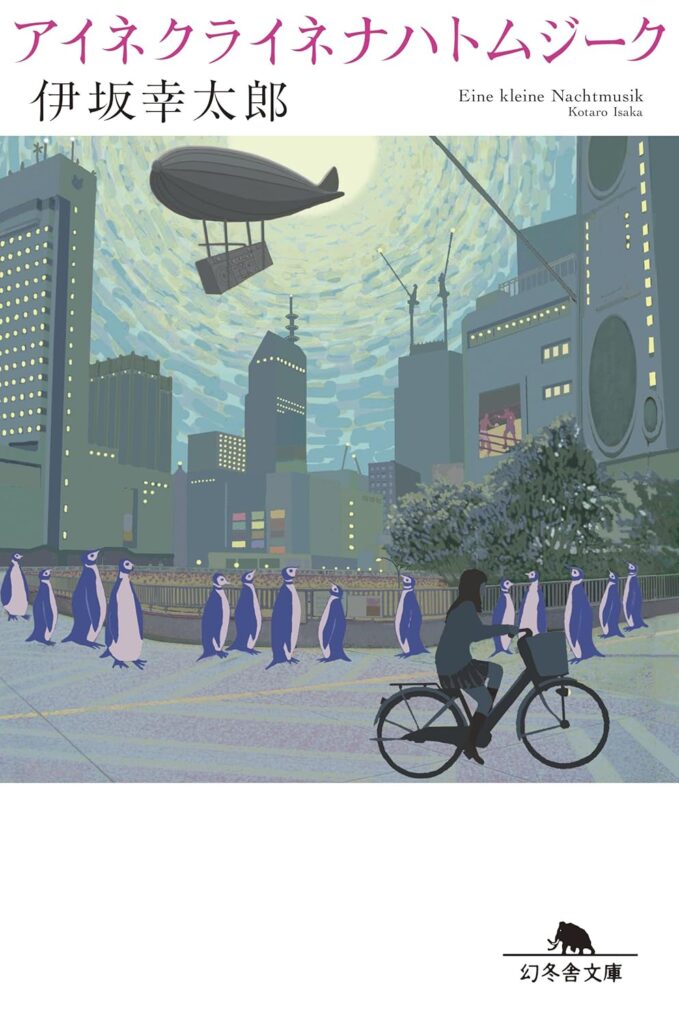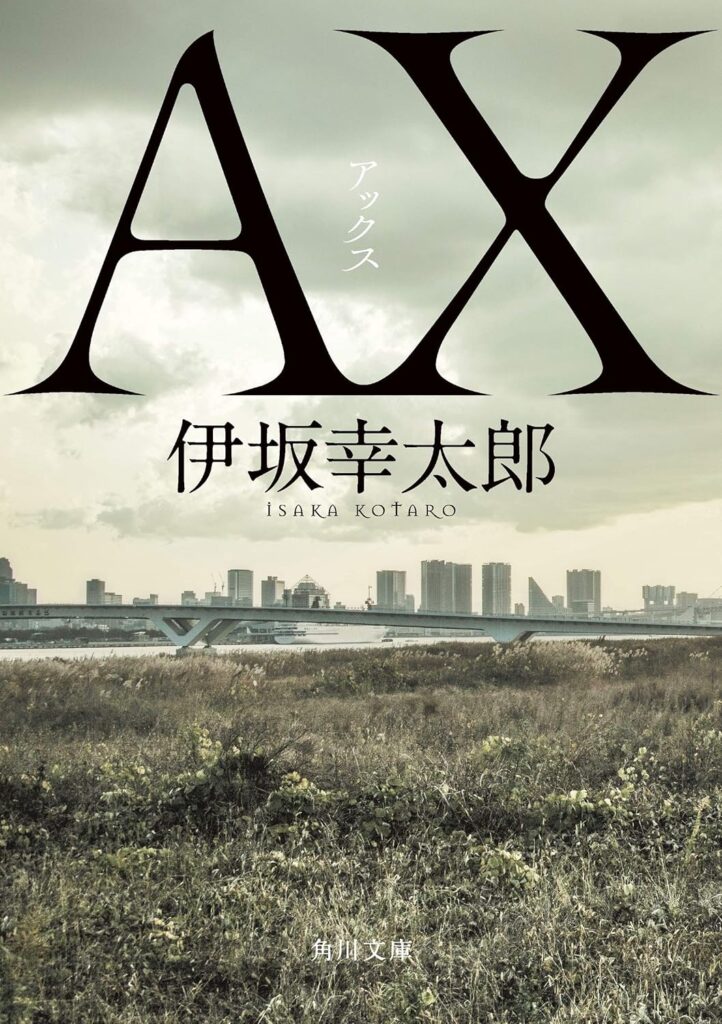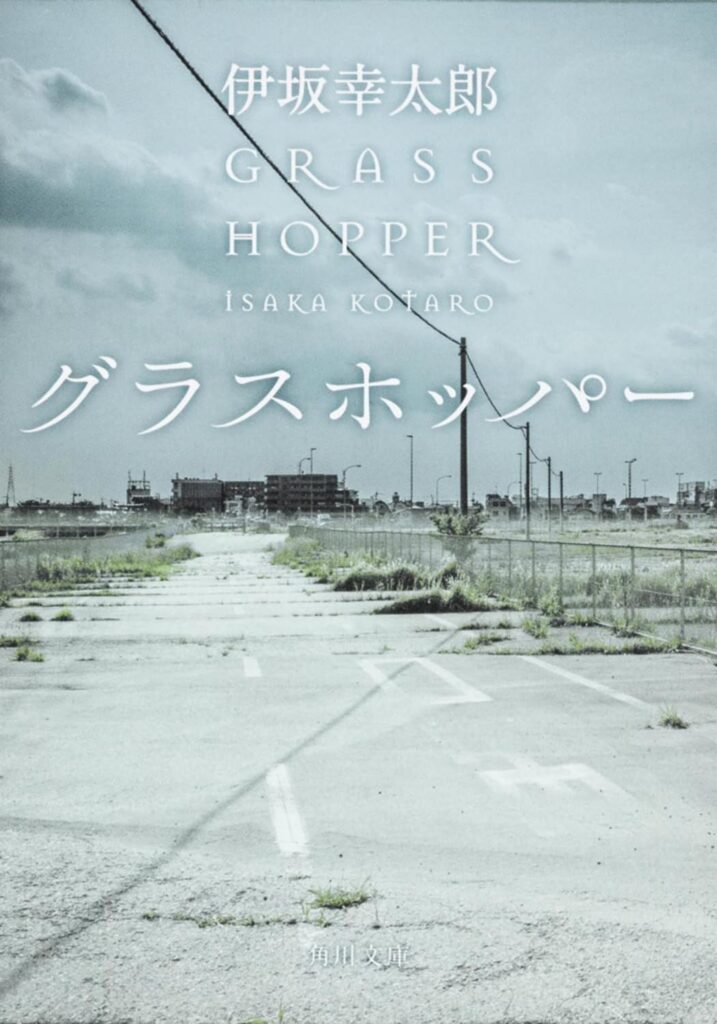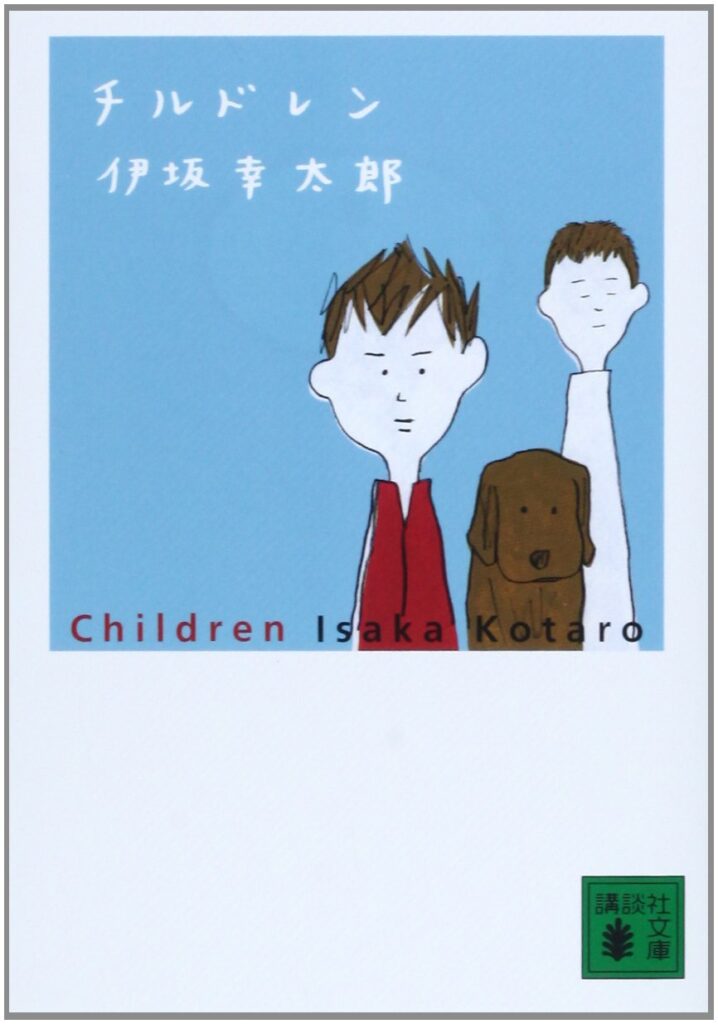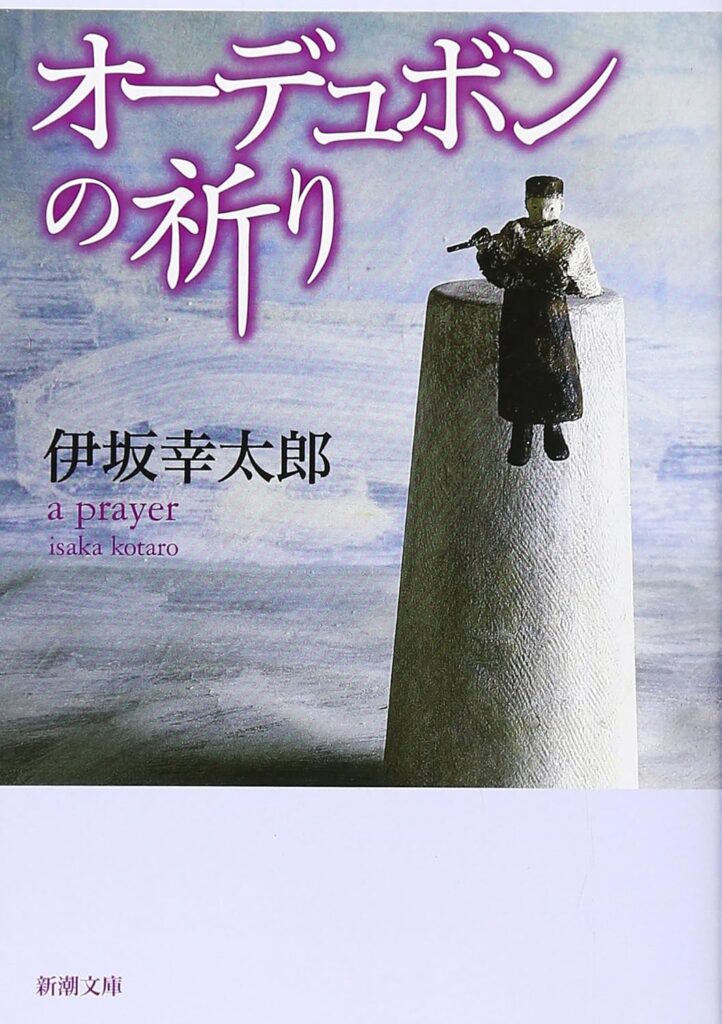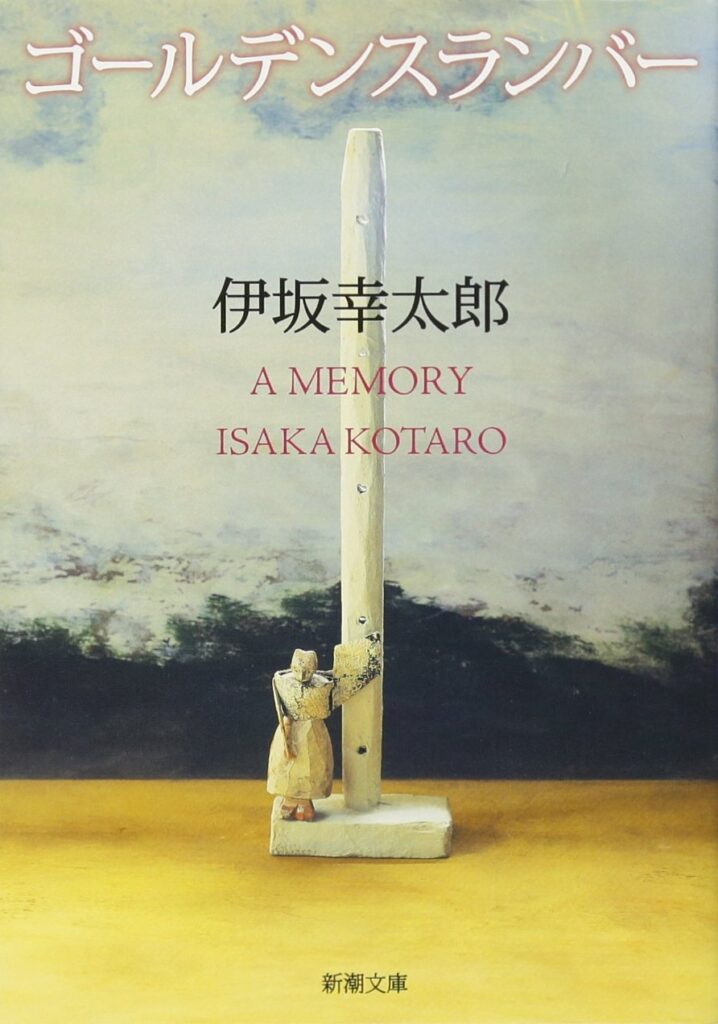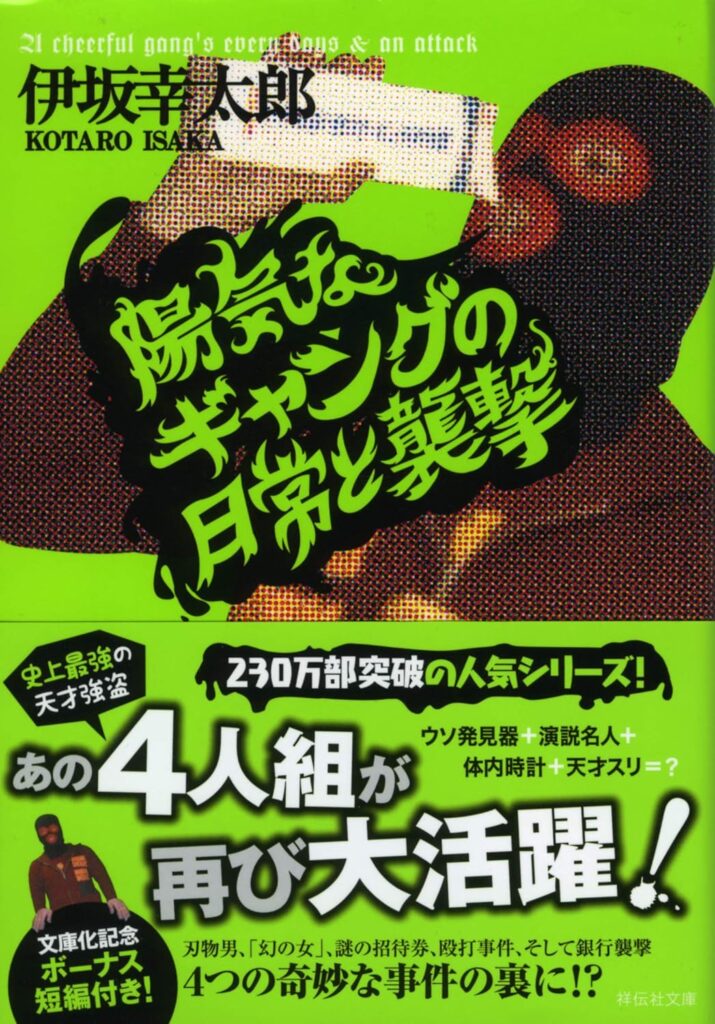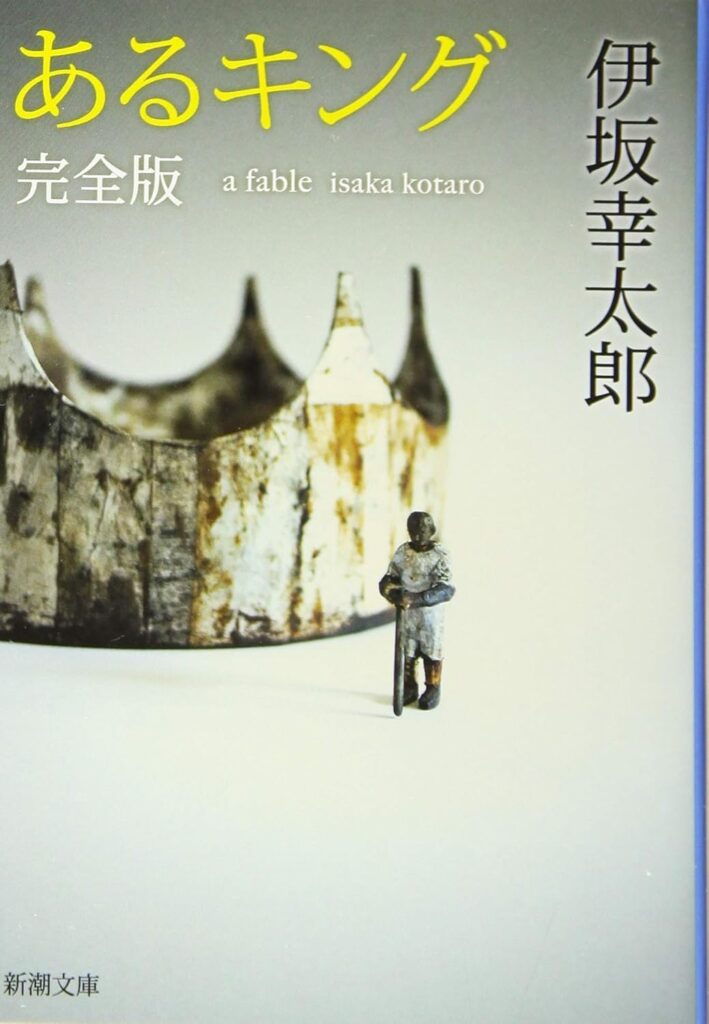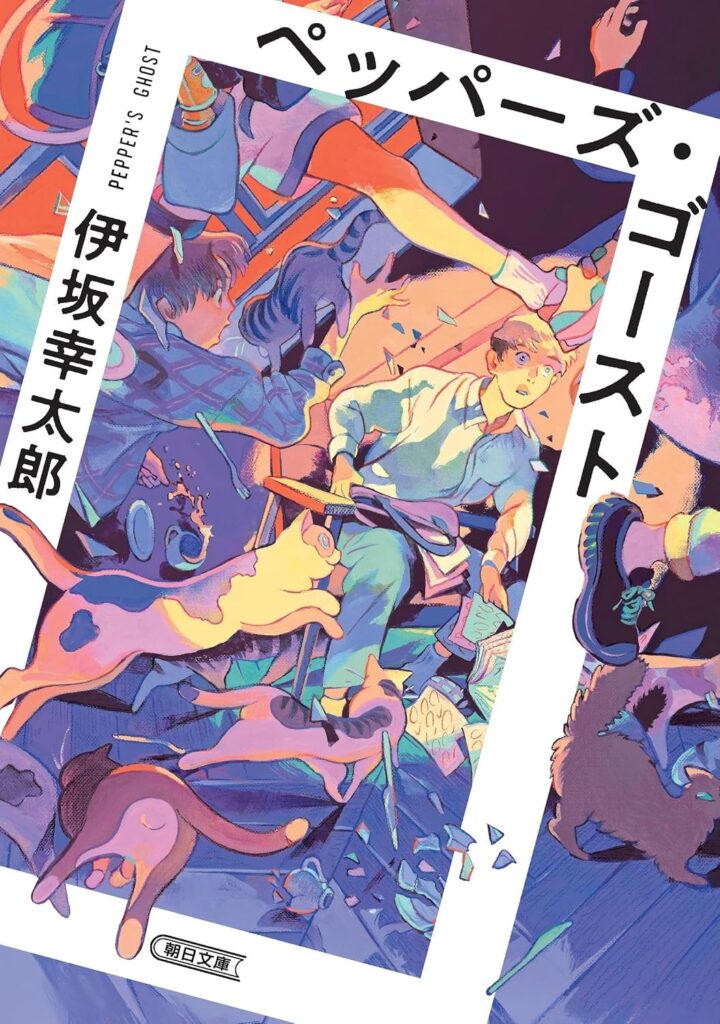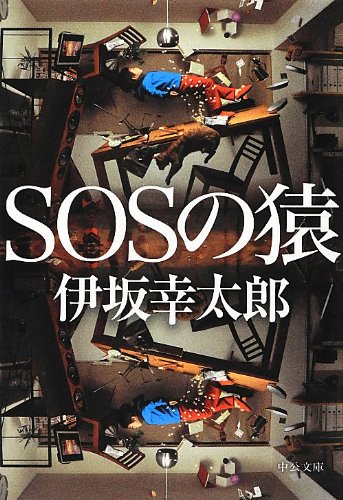小説「逆ソクラテス」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。伊坂幸太郎さんの作品の中でも、特に子どもたちが主人公ということで、いつもとは少し違う雰囲気を感じさせる短編集ですよね。でも、読めばやっぱり伊坂さんの世界。巧みな構成と、心に残るメッセージが詰まっていました。
収録されているのは「逆ソクラテス」「スロウではない」「非オプティマス」「アンスポーツマンライク」「逆ワシントン」の五編。どの話も小学生たちが、大人や社会が持つ「決めつけ」や「思い込み」に立ち向かっていく姿が描かれています。読んでいると、自分自身の中にある先入観にもハッとさせられる瞬間がたくさんありました。子どもたちの真っ直ぐな視点や、時に大人顔負けの知恵と行動力に、胸がすくような思いがします。
この記事では、各短編の物語の筋を追いながら、物語の核心にも触れていきます。そして、それぞれの物語を読んで私が何を感じ、考えたのか、詳しい気持ちをたっぷりとお伝えできればと思っています。読んだことがある方はもちろん、これから読もうか迷っている方にも、この作品の魅力が伝われば嬉しいです。
小説「逆ソクラテス」のあらすじ
『逆ソクラテス』は、子どもたちの視点から、大人たちの持つ「先入観」や「決めつけ」に疑問を投げかける五つの物語で構成されています。表題作「逆ソクラテス」では、小学六年生の加賀と転校生の安斎が中心となります。担任の久留米先生は、生徒たちの家庭環境や見た目で判断し、決めつけるような態度をとる人物。特に、勉強も運動も苦手な草壁くんを露骨に見下しています。安斎はそんな先生の「先入観」を覆すため、ある作戦を計画。草壁くんや優等生の佐久間さんを巻き込み、先生に一泡吹かせようと試みます。
「スロウではない」は、運動が苦手な少年・司が主人公。運動会のリレー選手に選ばれてしまい、憂鬱な日々を送ります。足が遅いことで劣等感を抱く司ですが、友人の悠太や、同じく選手に選ばれた村田花、そして転校生の高城かれんとの放課後の練習を通して、少しずつ変化していきます。子どもたちの純粋な友情や、コンプレックスとの向き合い方が描かれます。
「非オプティマス」では、小学五年生の将太のクラスが舞台。問題児の騎士人が授業を妨害し、新米の久保先生は困り果てています。クラスの多くがその状況を面白がっている中、転校生の保井福生だけが毅然と騎士人に立ち向かいます。将太は塾帰りに福生と話すようになり、彼の持つ独特な正義感や行動力に影響を受けていきます。福生は騎士人を懲らしめる計画を立てますが、その行方は…。
「アンスポーツマンライク」は、ミニバスケットボールに打ち込む少年たちの物語。小学校最後の大会、残り一分で一点差に迫る大事な場面で、エースの駿介が相手選手を躓かせてしまい、「アンスポーツマンライクファウル」を取られ、チームは敗北。その出来事は、彼らの心に影を落とします。高校生になった彼らが、当時のコーチである磯憲先生のお見舞いに集まる場面から物語は始まり、過去の試合の記憶と現在の彼らの関係性が描かれます。
最後の「逆ワシントン」では、謙介と倫彦、そして物知りの京樹(通称〈教授〉)の三人が、クラスメイトの靖が義父から虐待されているのではないかと疑い、彼を助けようと奔走します。ドローンを使って証拠を掴もうと考えますが、計画はなかなか上手くいきません。そんな中、彼らは大人たちの世界の複雑さや、真実を見抜くことの難しさに直面します。そして、この物語の中で、以前の短編に登場した人物たちのその後が垣間見え、物語全体が繋がっていきます。
小説「逆ソクラテス」の長文感想(ネタバレあり)
伊坂幸太郎さんの『逆ソクラテス』、読み終えた後の清々しさというか、心に残る温かい感覚がとても印象的な作品でした。子どもたちが主人公ということで、これまでの作品とは少し毛色が違うのかな、なんて思いながら読み始めたのですが、読み進めるうちに、やっぱりこれは伊坂さんの物語だな、と感じ入りました。散りばめられた伏線、個性的な登場人物たち、そして社会や人間の本質を突くような鋭い視点。それらが、子どもたちの純粋で真っ直ぐな目を通して描かれることで、また新たな魅力が生まれているように思います。
この作品集全体を貫いているのは、「先入観」というテーマですよね。大人は、というか人間は、どうしても物事を単純化したり、レッテルを貼ったりして分かった気になってしまう。でも、子どもたちは、そんな大人の「決めつけ」に対して、「本当にそうなの?」と素朴な疑問をぶつけます。その姿が、読んでいてとても小気味よく、そして考えさせられました。
では、各短編について、感じたことを詳しく書いていきたいと思います。もちろん、物語の核心に触れる部分もありますので、未読の方はご注意くださいね。
「逆ソクラテス」
まず表題作「逆ソクラテス」。この話が一番、作品集全体のテーマを象徴しているように感じました。久留米先生、いかにも「いるいる、こういう大人」って感じですよね。生徒の能力や将来を、家庭環境や成績だけで判断してしまう。しかも、それを隠そうともせず、むしろ自分の判断が正しいと信じ込んでいる。安斎くんが登場する前の教室の空気って、きっと重苦しかっただろうなと想像します。
そこに現れた転校生の安斎くん。彼が久留米先生の先入観、つまり「勉強ができない子は悪い子、できる子は良い子」という単純な図式をひっくり返そうとする「逆ソクラテス作戦」が痛快でした。カンニングという、普通なら非難される行為を逆手に取って、先生の思い込みを崩していく。その発想がまず面白い。そして、この作戦に、先生に見下されている草壁くんだけでなく、優等生の佐久間さんまで巻き込んでいくところがミソですよね。最初は戸惑いながらも、次第に安斎くんの考えに共感し、協力していくクラスメイトたちの姿に、小さな革命が起きているようでワクワクしました。
特に印象的だったのは、安斎くんの「僕はそうは思わない」という言葉です。周りが「そうだよね」と流されそうな時、あるいは強い立場の人間が「こうだ」と決めつけた時に、彼は臆せずに自分の意見を表明する。簡単なようで、大人でもなかなかできないことです。この言葉は、この短編集全体に通底するメッセージでもあるように感じました。自分の頭で考え、自分の言葉で語ることの大切さ。それを、小学生の安斎くんが体現している。
ただ、ラストは少しほろ苦さも残りますよね。大人になった加賀が再会した安斎くんは、かつての聡明さとは少し違う、荒んだ雰囲気になっていた。そして、草壁くんが立派なプロ野球選手になっている。人生って、子どもの頃の評価だけでは決まらない。まさに久留米先生の先入観が間違っていたことを証明するような結末ですが、同時に、安斎くんのような存在が、社会の中で生きにくさを感じてしまう現実もあるのかもしれない、と考えさせられました。それでも、あの小学生時代に彼らが起こした小さな抵抗は、きっと加賀や草壁くん、佐久間さんの心に残り続け、彼らの人生の糧になったのだろうと思います。
「スロウではない」
この話は、読んでいて自分の小学生時代を思い出して、少し胸がキュッとなるような感覚がありました。運動が苦手な子にとって、運動会、特にリレーなんて本当に憂鬱なイベントですよね。主人公の司くんの気持ち、痛いほどよく分かります。足が遅いというだけで、なんだかクラスの中でも肩身が狭いような、劣等感を抱いてしまう。
そんな司くんと、同じくリレー選手に選ばれてしまった村田花さん。そして、彼らをサポートする友達の悠太くんと、転校生の高城かれんさん。この四人の関係性が微笑ましかったです。特に司くんと悠太くんがやる『ゴッドファーザー』ごっこ。映画の内容もよく知らないのに、お決まりのセリフを言い合う感じ、すごく「男子小学生あるある」な気がして、クスッと笑ってしまいました。
高城かれんさんは、ちょっと不思議な魅力のある女の子でしたね。最初は、彼女も足が遅いことで悩んでいるのかと思いきや、実は…。彼女がリレーの練習中に見せる様々な行動、例えばピッコロのマントのエピソードなどは、後で「ああ、そういうことだったのか!」と膝を打つ伏線になっていました。渋谷さんのようなクラスの中心人物たちの目を欺き、チームを勝利(?)に導くための、彼女なりの作戦だったわけです。これもまた、ある種の「逆ソクラテス」的な展開と言えるかもしれません。
ただ、この話のラストは、少し切なさが残りました。運動会が終わり、高城かれんさんが再び転校していく。司くんが感じる寂しさ。小学生時代の友人関係って、永遠に続くように思えても、ちょっとしたきっかけで変化したり、離ればなれになったりするものですよね。あの短い期間に共有した秘密や達成感は、きっと司くんにとって忘れられない思い出になったでしょうけれど、同時に、過ぎ去った時間へのほのかな哀愁も感じさせる、そんな読後感でした。
「非オプティマス」
この短編は、登場人物のキャラクターが際立っていましたね。特に、保井福生くん。彼の存在感がすごい。いつも同じ服を着ていて、大人びたような、それでいてどこかズレているような言動。でも、彼の行動原理は一貫していて、「間違っていること」を許せない、強い正義感に基づいている。騎士人くんの授業妨害に、クラスの多くが面白がったり、見て見ぬふりをしたりする中で、彼だけが真っ向から立ち向かう。その姿は、読んでいて頼もしかったです。
主人公の将太くんは、どちらかというと内向的で、クラスの状況に疑問を感じつつも、なかなか行動に移せないタイプ。そんな彼が、福生くんと関わることで、少しずつ変わっていく様子が丁寧に描かれていました。塾帰りの二人だけの会話、福生くんが語る独自の理論、そして騎士人くんを懲らしめるための(ちょっと危なっかしい)計画。子どもならではの正義感と、危うさが同居している感じが、妙にリアルでした。
久保先生の変化も印象的でした。最初は生徒たちに振り回され、自信なさげだった新米先生が、福生くんの行動や、将太くんたちの変化に触発されて、少しずつ教師としての自覚や強さを見せていく。福生くんが起こした行動は、結果的にクラスに良い影響を与えたのかもしれません。
ラストシーン、福生くんが将太くんに何かを言いかけてやめる場面は、色々な想像を掻き立てられますね。彼は何を伝えたかったのでしょうか。自分の家庭の事情? それとも、また別の計画? 彼のミステリアスな魅力が最後まで残る、印象的な終わり方でした。福生くんのような、ちょっと変わっているけれど、自分の信念を貫くキャラクターは、伊坂作品の大きな魅力の一つだと改めて感じます。
「アンスポーツマンライク」
この物語は、他の短編とは少し趣が異なり、過去の出来事が現在の彼らにどう影響しているのか、という視点で描かれています。ミニバス時代の最後の試合での「アンスポーツマンライクファウル」。たった一つのプレイが、勝敗を分け、少年たちの心に長くしこりを残す。スポーツをやっていた経験がある人なら、こういう苦い記憶の一つや二つ、あるのではないでしょうか。
高校生になった歩、三津桜、駿介、剛央、匠。それぞれの道を歩んでいる彼らが、恩師である磯憲コーチのお見舞いをきっかけに再会し、過去の出来事と向き合うことになります。あの時の駿介のファウルは、本当に故意だったのか? それともアクシデントだったのか? そして、その出来事を、他のメンバーはどう受け止めていたのか。
大人になってから過去を振り返ると、当時は見えなかったことや、気づかなかった相手の気持ちが見えてくることがありますよね。この物語では、彼らの会話を通して、当時の状況やそれぞれの思いが少しずつ明らかになっていきます。ただ、この短編だけを読むと、少し物足りなさを感じるかもしれません。物語の核心部分は、次の「逆ワシントン」に持ち越される形になっているからです。
それでも、ミニバス時代の熱い思いや、仲間との絆、そして一つの出来事がもたらしたほろ苦い記憶といった要素は、青春小説としても十分に読み応えがありました。磯憲コーチという、厳しさの中にも生徒への愛情が感じられる大人の存在も、物語に深みを与えています。この物語が、最後の「逆ワシントン」でどう繋がっていくのか、期待感を持たせる構成になっていました。
「逆ワシントン」
そして、最後の「逆ワシントン」。この短編で、これまで散りばめられてきた伏線が見事に回収され、物語全体が一つに繋がっていきます。読んでいて、「なるほど!」と何度も唸らされました。
主人公は謙介くん。友達の倫彦くん、そして博識なあだ名を持つ〈教授〉こと京樹くんと一緒に、クラスメイトの靖くんを救おうと奮闘します。靖くんが義理の父親から虐待されているのではないか? 子どもたちなりに知恵を絞り、証拠を掴むためにクレーンゲームでドローンを手に入れようとするのですが、その発想がまた子どもらしくて微笑ましいやら、切実さが伝わってくるやら。
彼らの小さな行動が、まるで水面に投げた小石のように、静かに波紋を広げていく様子が印象的でした。謙介くんのお母さんの言葉、「最終的には、真面目で約束を守る人間が勝つんだよ」というセリフが、この物語の、そして作品集全体のテーマを補強しています。正直者は馬鹿を見る、なんて言われる世の中だけれど、それでも誠実であること、約束を守ることの大切さを、お母さんは身をもって示そうとしている。そして、その思いは、謙介くんたち子どもにも確かに伝わっている。
中山先生や、電気屋の店員さん(彼が誰なのかは、読めばすぐに分かりますよね)など、脇を固める大人たちのキャラクターも魅力的でした。特に、ラストシーン。電気屋の店員さんが涙を流す場面は、胸に迫るものがありました。「アンスポーツマンライク」で語られた過去の過ち。その彼が、新しい人生を歩み始め、謙介くんたちの純粋な行動に心を動かされる。人は過ちを犯すけれど、やり直すこともできる。そして、その姿を誰かが見ていてくれる。そんな静かな希望を感じさせる結末でした。
伊坂さんの物語は、時に社会の暗い部分や人間のどうしようもなさを描きながらも、決して読者を突き放さない優しさがあるように思います。この『逆ソクラテス』という作品集も、子どもたちの視点を通して、先入観や偏見といった重いテーマを扱いながら、読後には温かい気持ちと、前を向く力を与えてくれる、そんな作品でした。
全体を通して、「先入観を捨てること」「自分の頭で考えること」「諦めずに声を上げること」の大切さが、様々な形で描かれていたように思います。それは、子どもたちだけでなく、私たち大人にとっても、常に心に留めておくべきことなのかもしれません。そして、物語の繋がり方が本当に見事でした。それぞれの短編が独立した物語として面白いのはもちろん、読み終えた時に、一つの大きな物語として完成する。この構成力は、さすが伊坂幸太郎さんだな、と改めて感嘆しました。子どもが主人公だからこその真っ直ぐさ、純粋さが、伊坂さんの持ち味である巧妙なストーリーテリングと組み合わさることで、他にはない読書体験を与えてくれる一冊だと思います。
まとめ
伊坂幸太郎さんの短編集『逆ソクラテス』は、五つの物語を通して、子どもたちの視点から「先入観」という大きなテーマに挑んだ作品でした。どの物語も、小学生たちが主人公でありながら、彼らが直面する問題や葛藤は、私たち大人の世界にも通じる普遍性を持っています。
表題作「逆ソクラテス」をはじめ、「スロウではない」「非オプティマス」「アンスポーツマンライク」「逆ワシントン」と、それぞれの物語が個性を放ちつつ、登場人物やテーマが緩やかに繋がり合い、読み進めるほどに深みを増していきます。子どもたちの純粋な正義感や友情、そして大人たちの決めつけや偏見に立ち向かう姿には、胸がすくような思いがしました。
巧みに張り巡らされた伏線が、最後の物語「逆ワシントン」で繋がっていく構成は見事と言うほかありません。読み終えた時には、爽快感と共に、心にじんわりと温かいものが残ります。社会の理不尽さや人間の弱さも描きながら、それでも希望を感じさせてくれる読後感は、伊坂作品ならではの魅力でしょう。子どもたちの真っ直ぐな言葉や行動に、ハッとさせられ、自分自身の思い込みについて考えさせられる、そんなきっかけを与えてくれる一冊です。