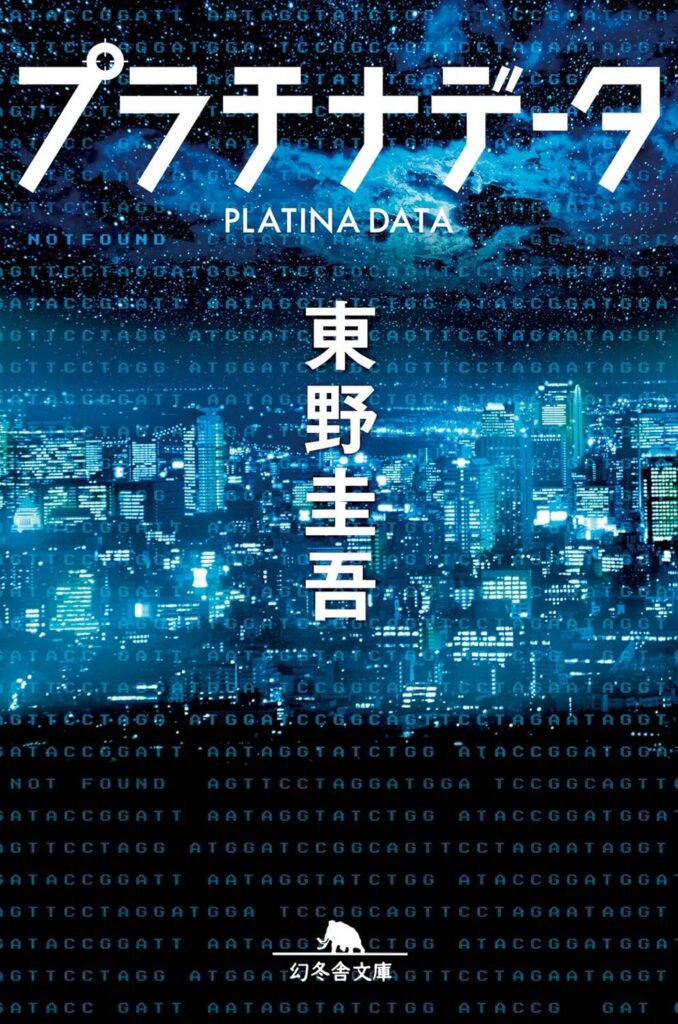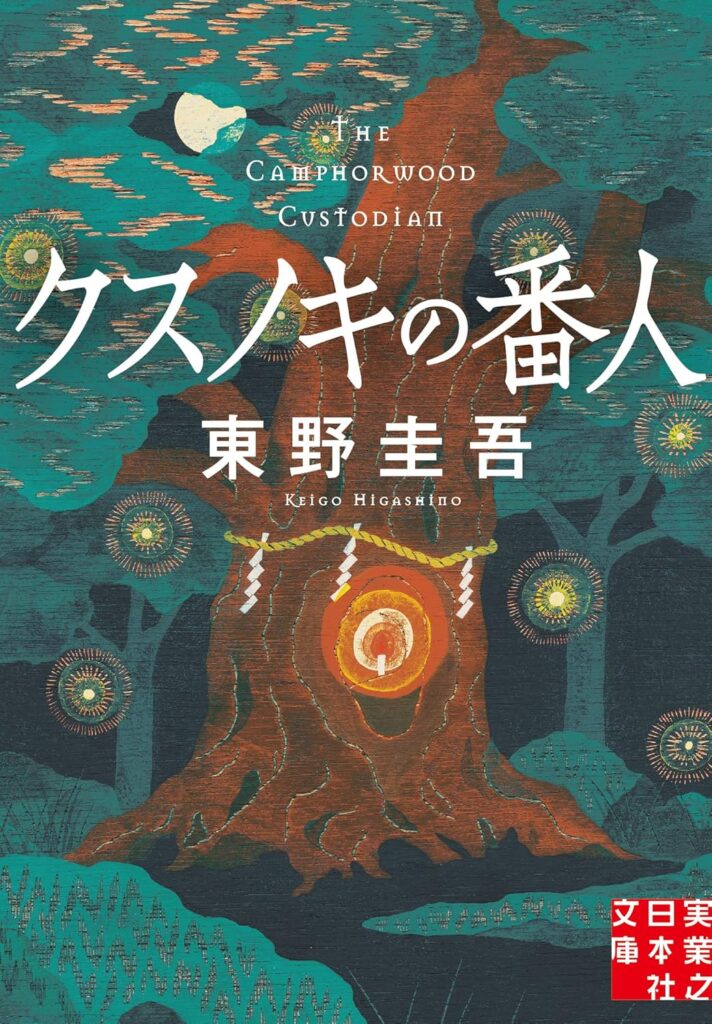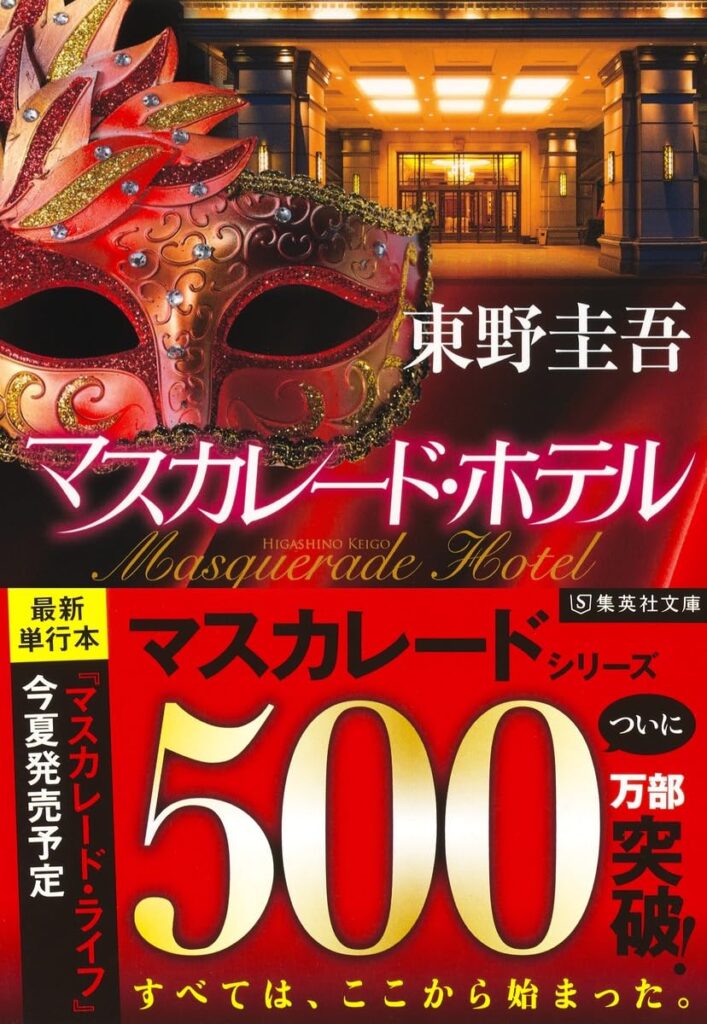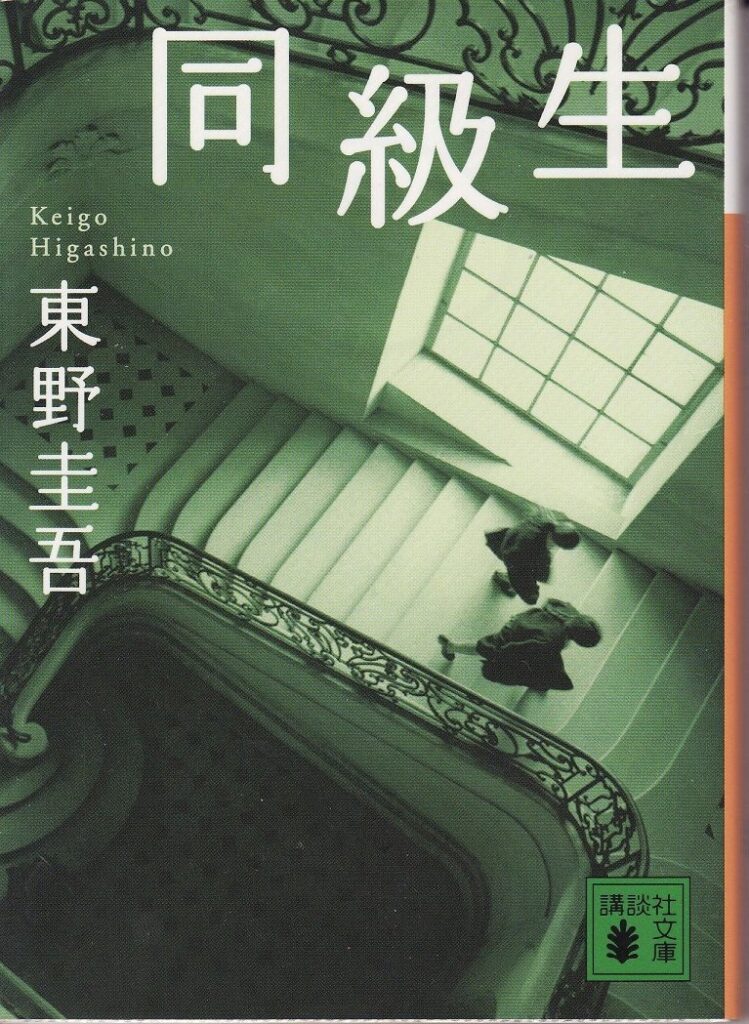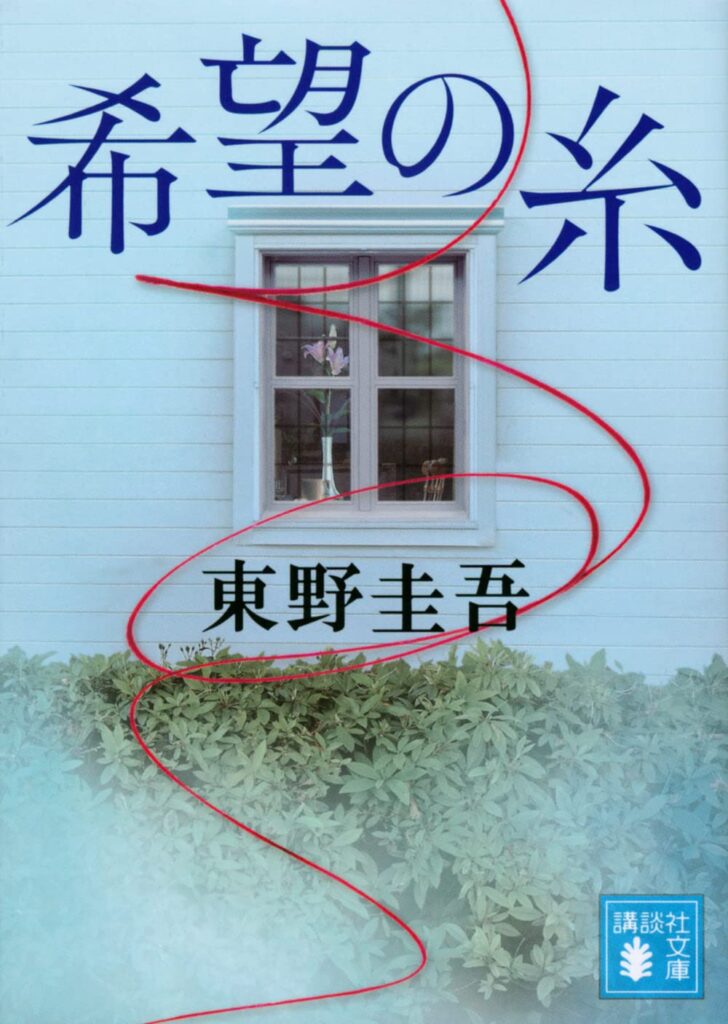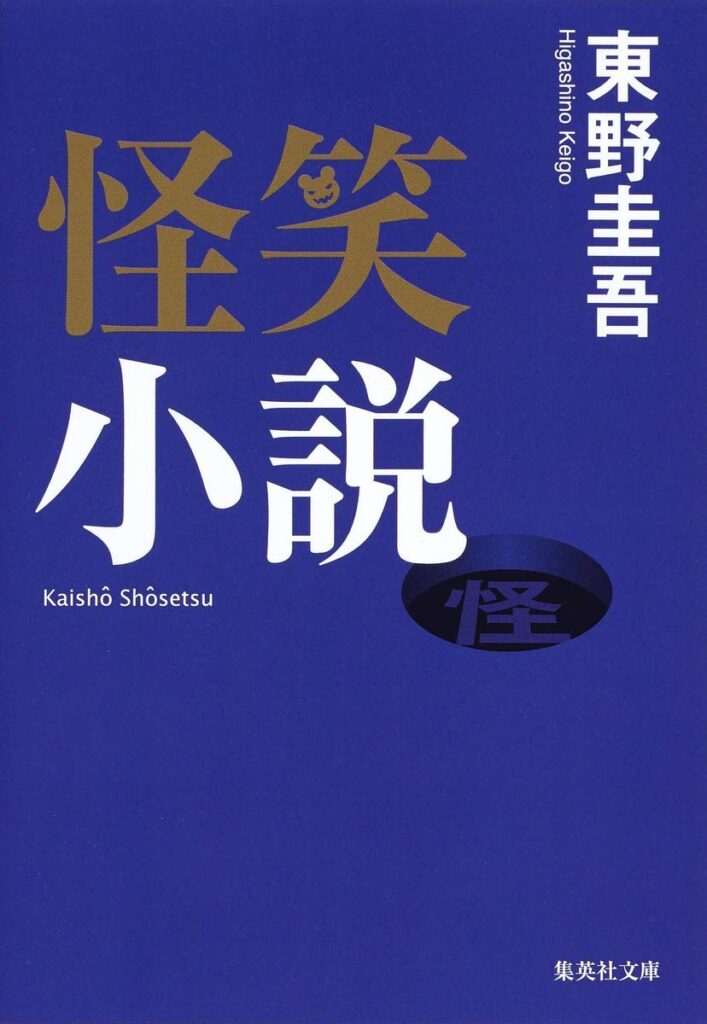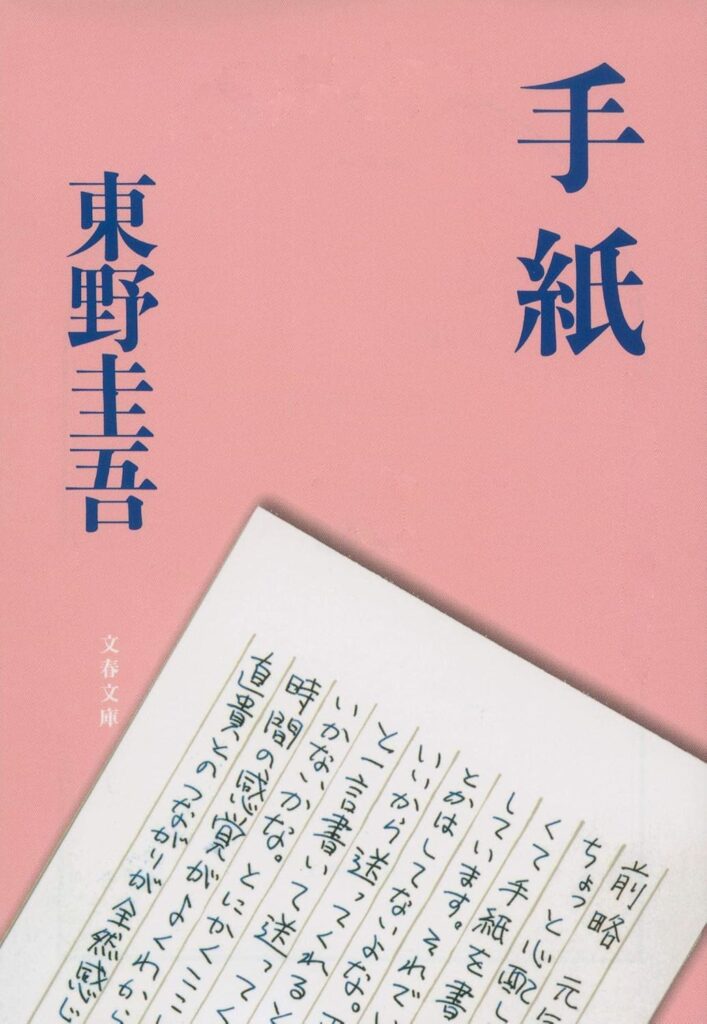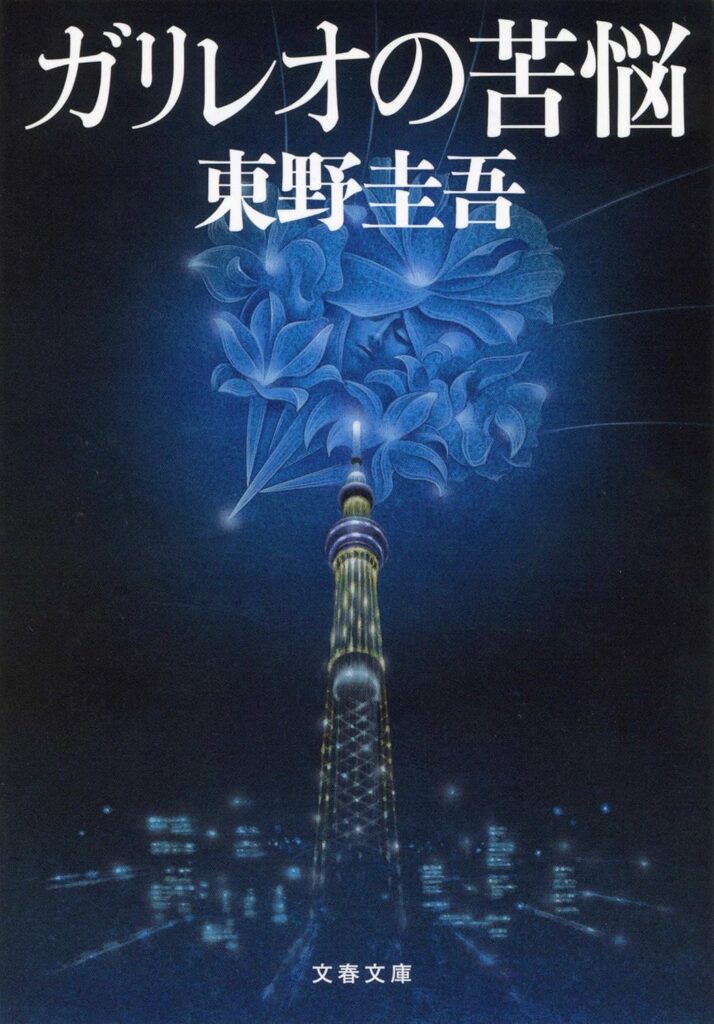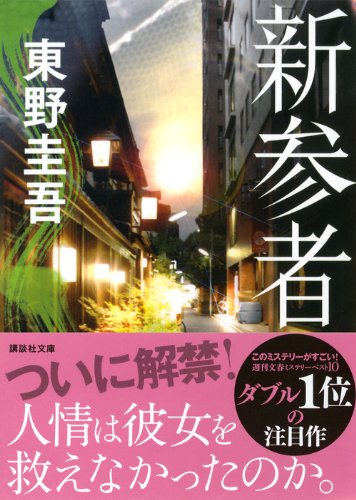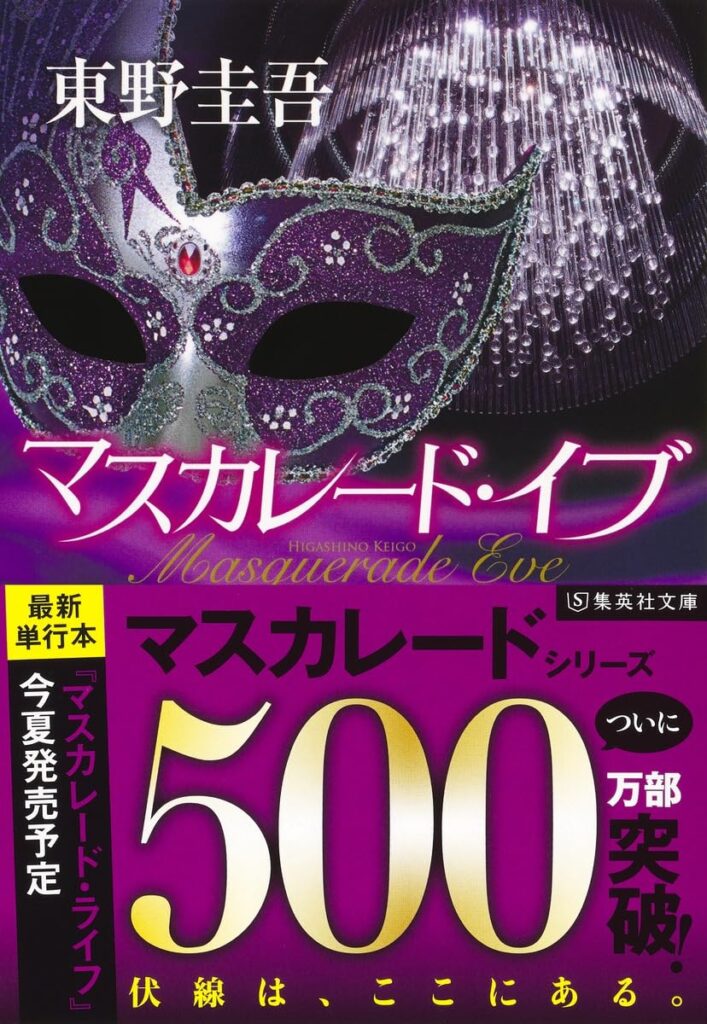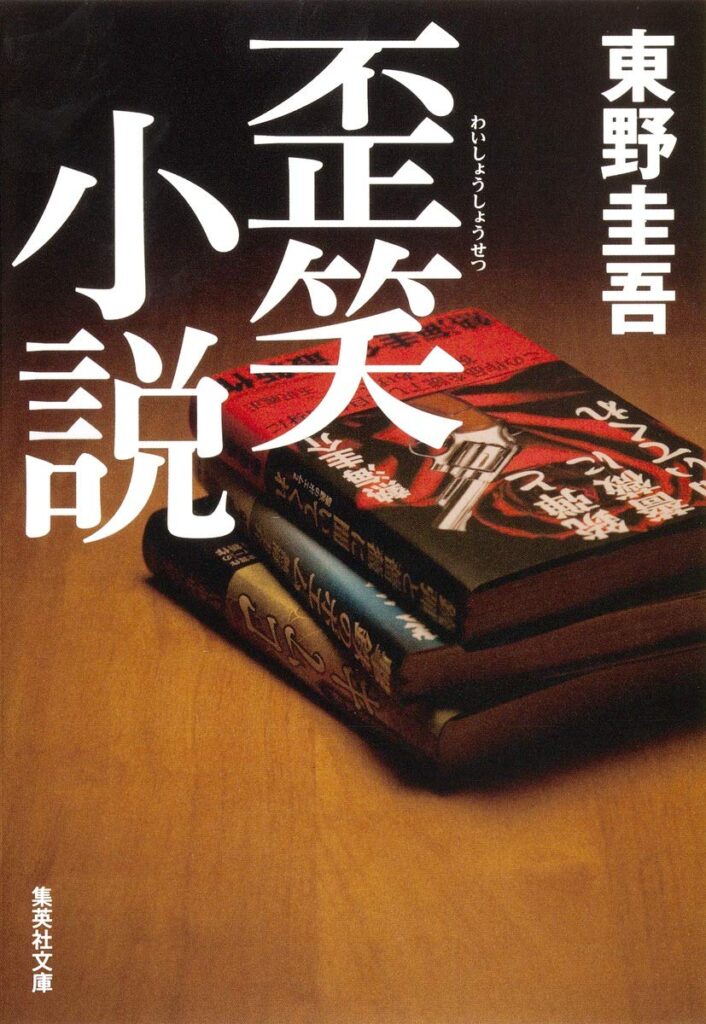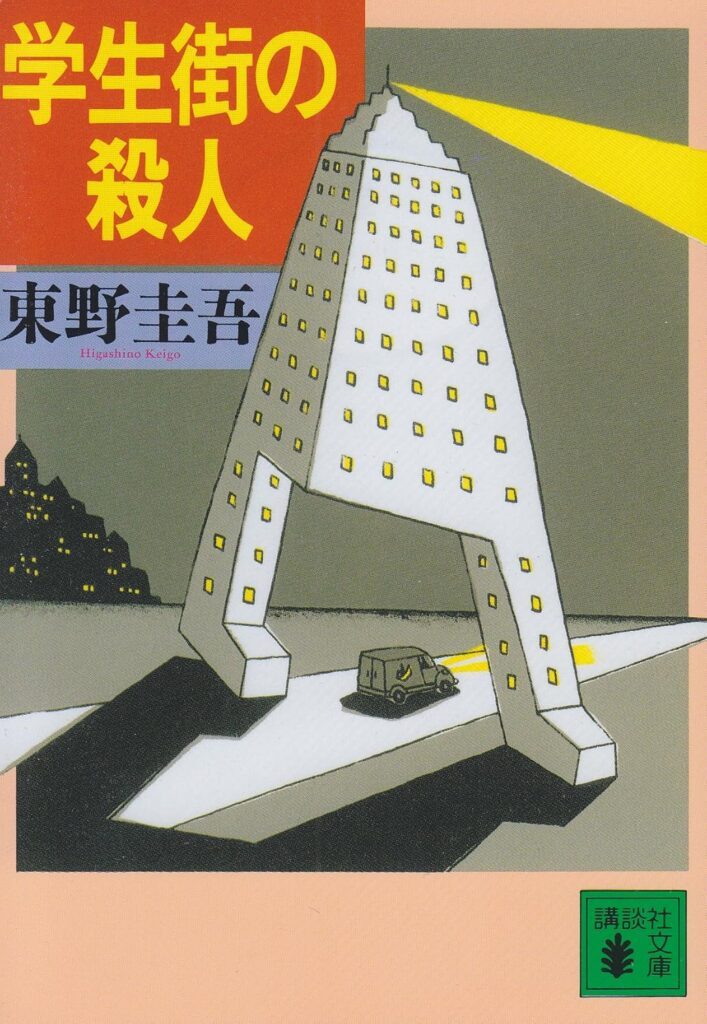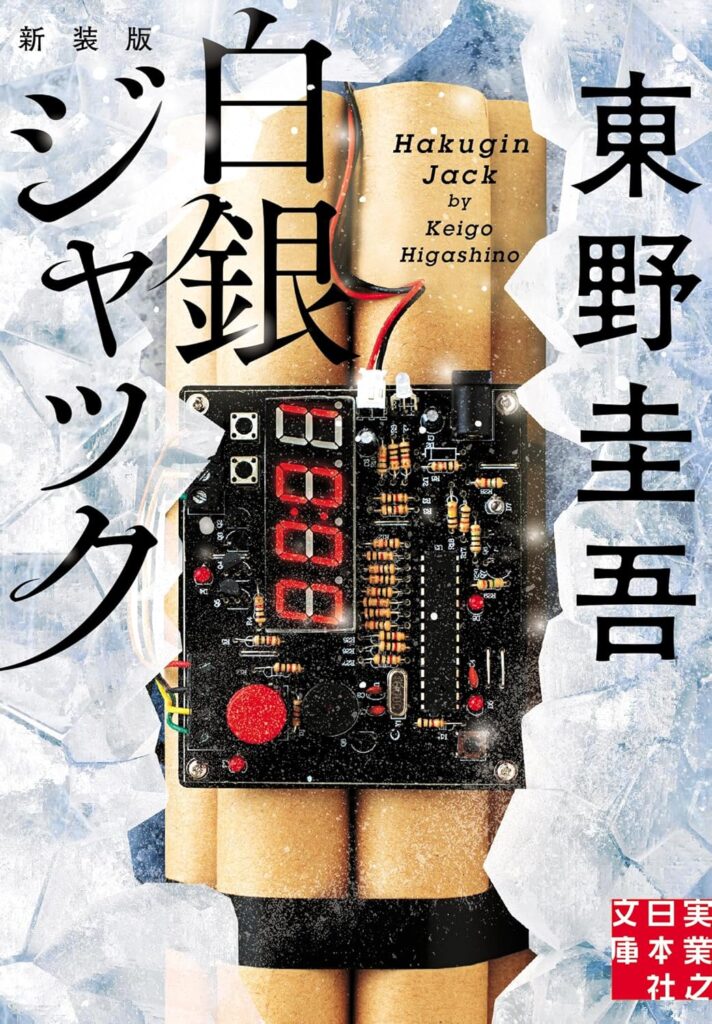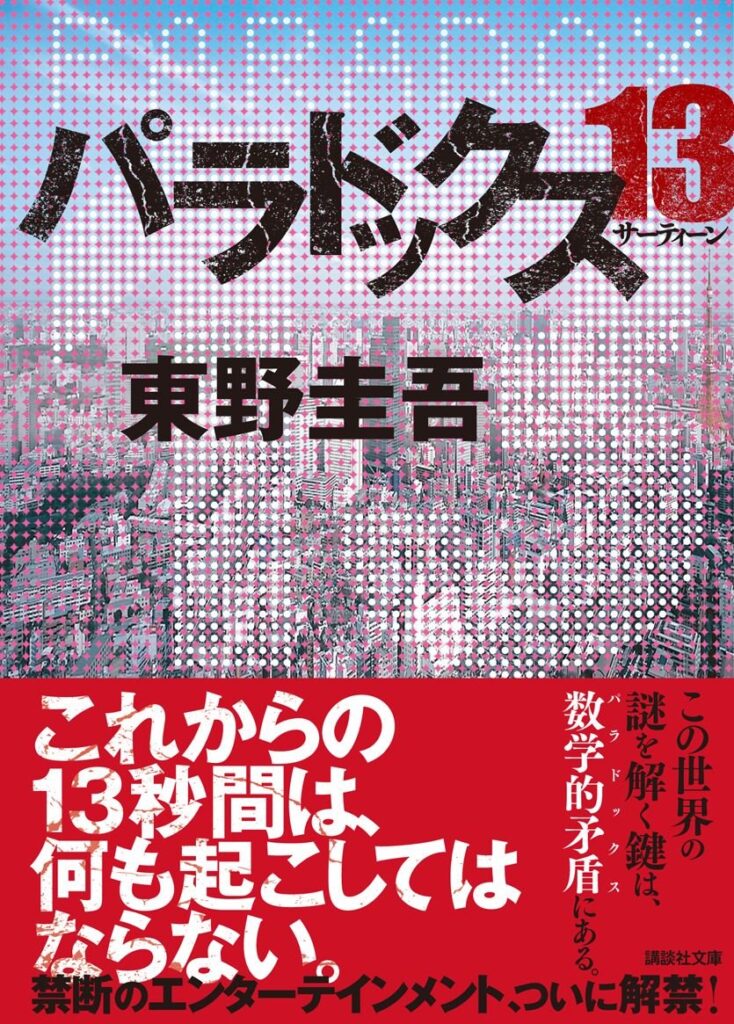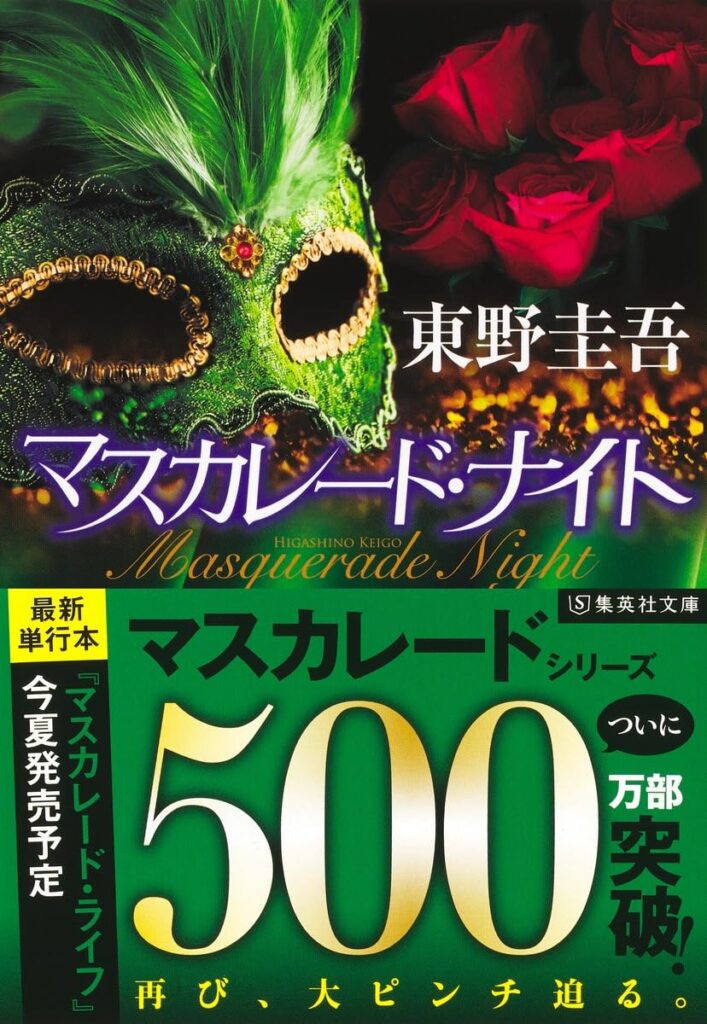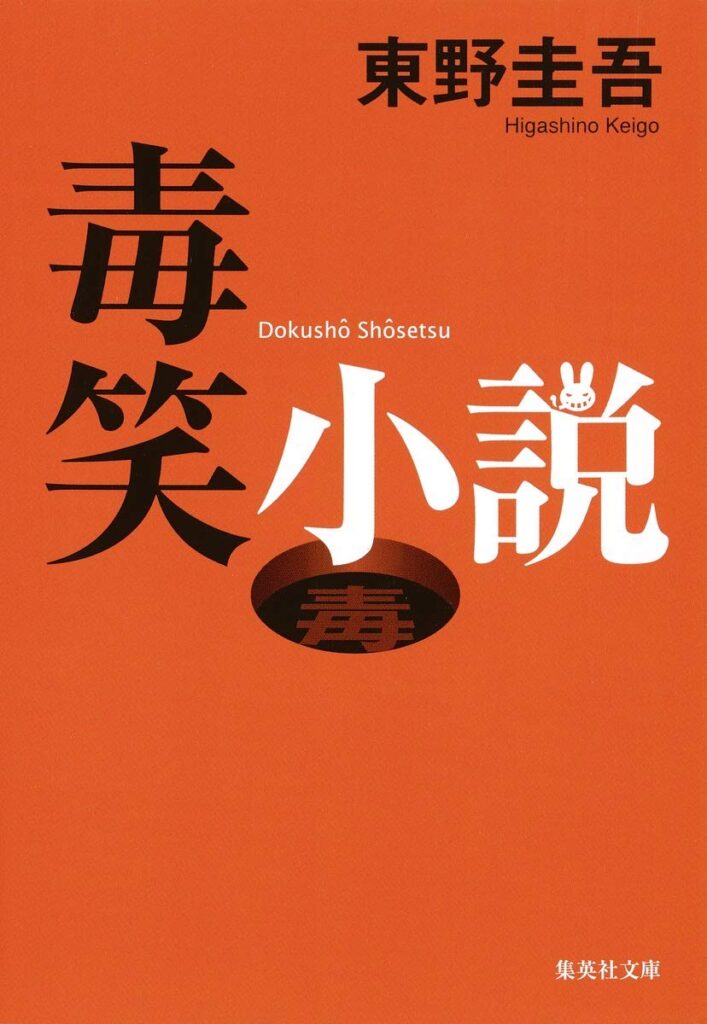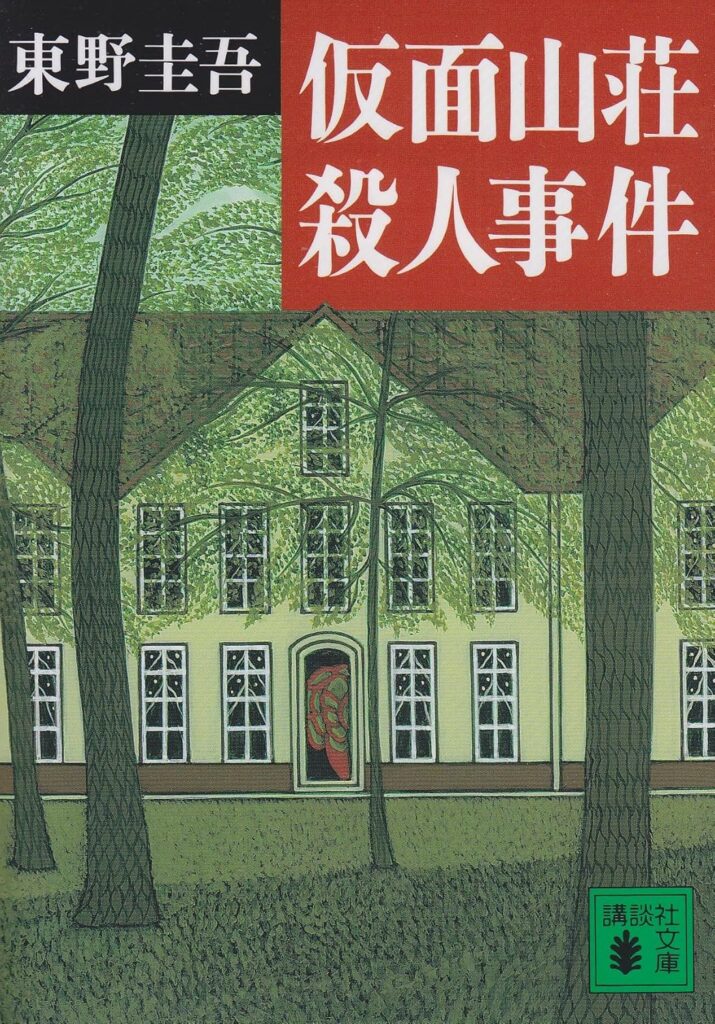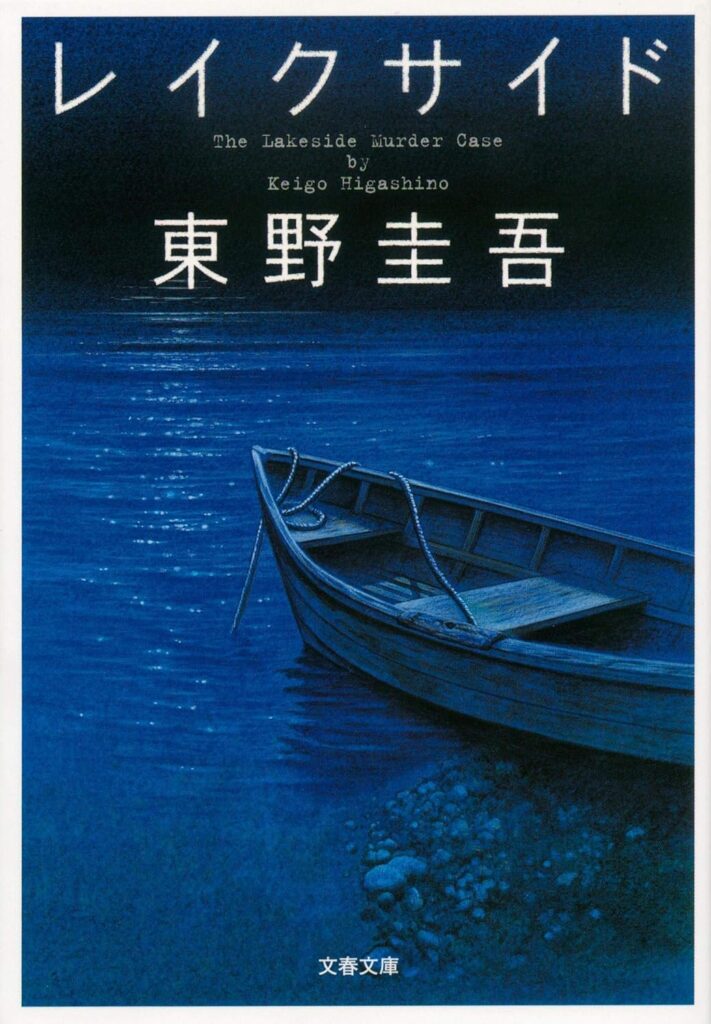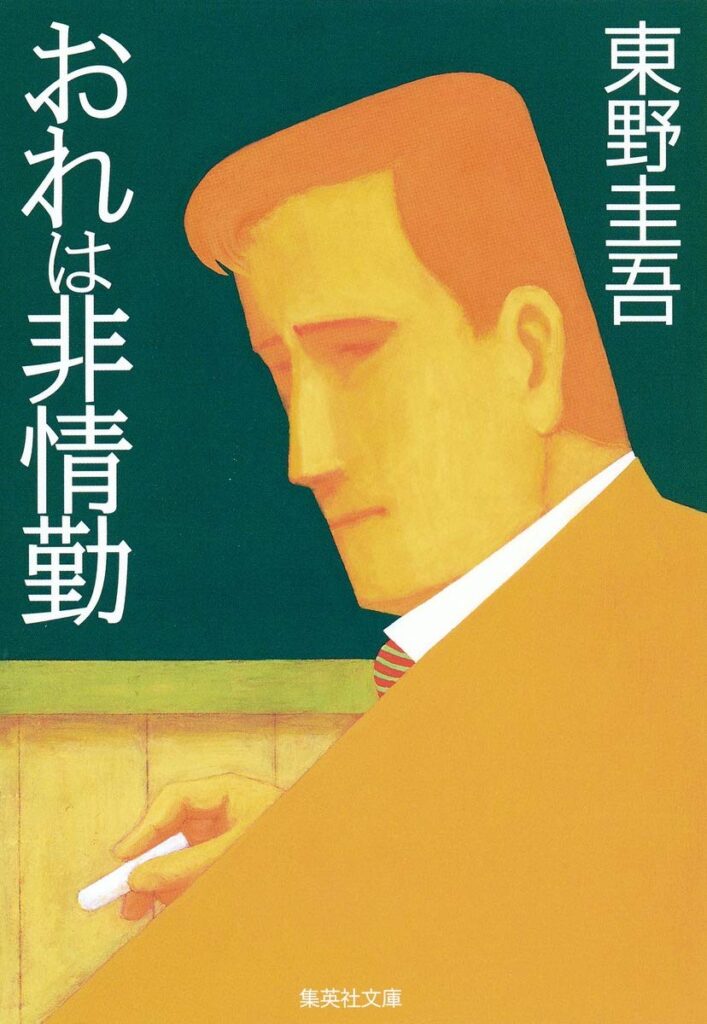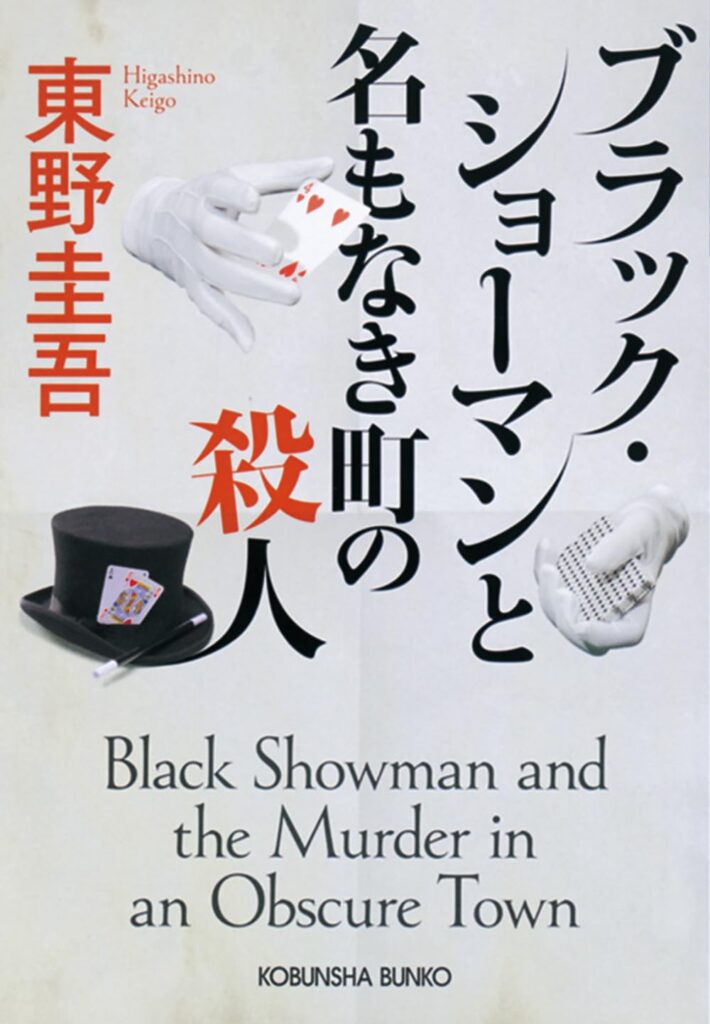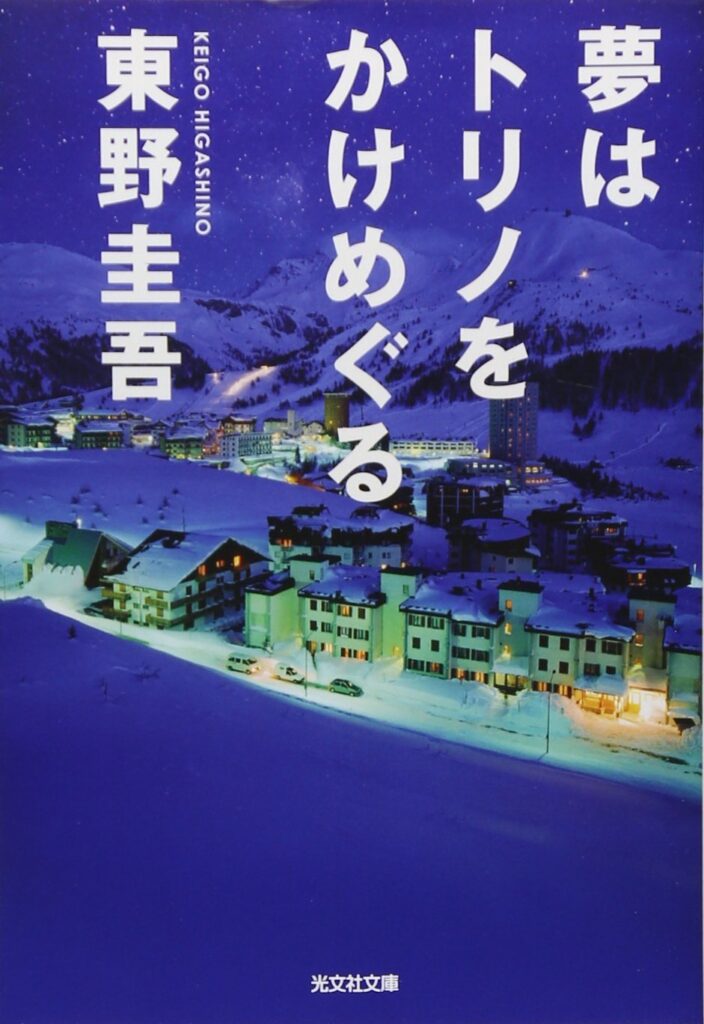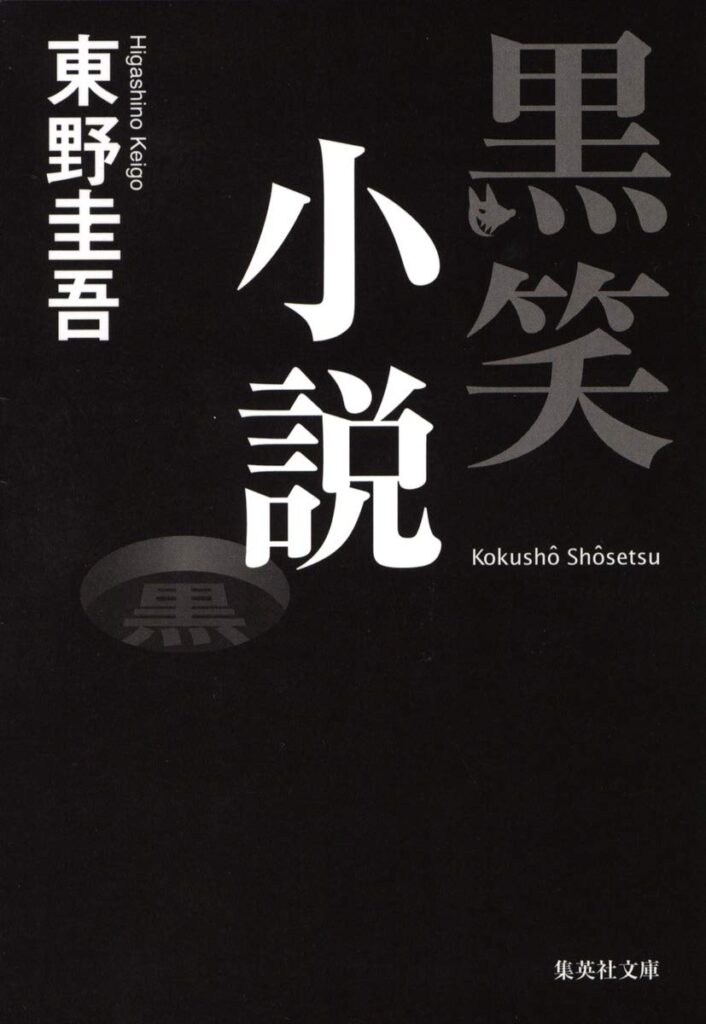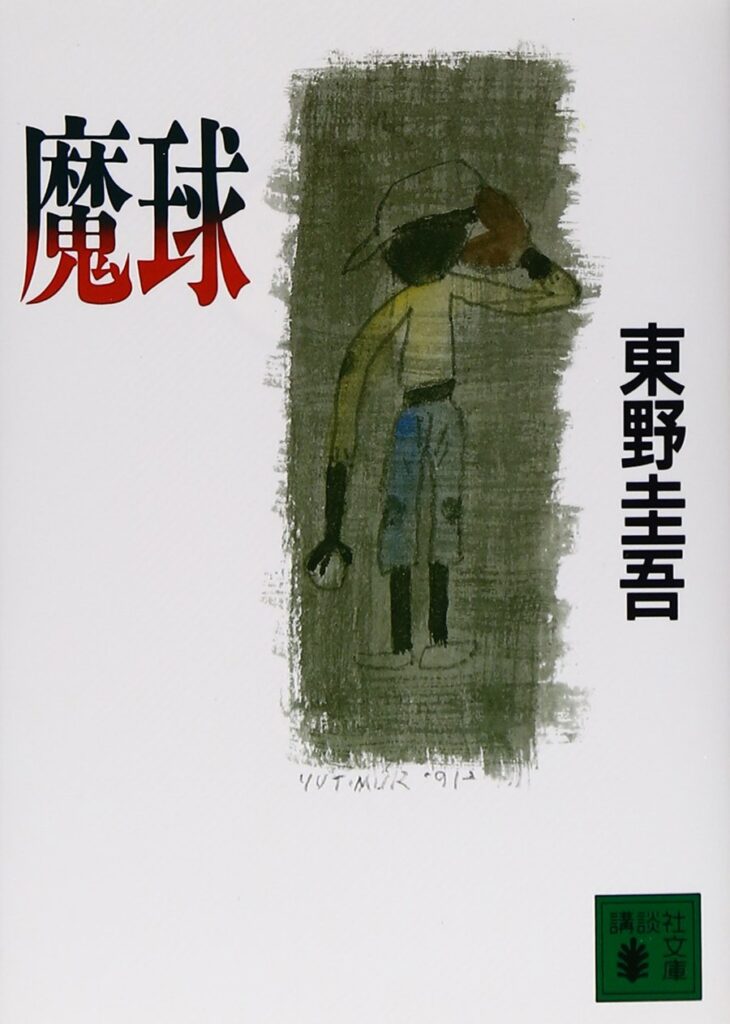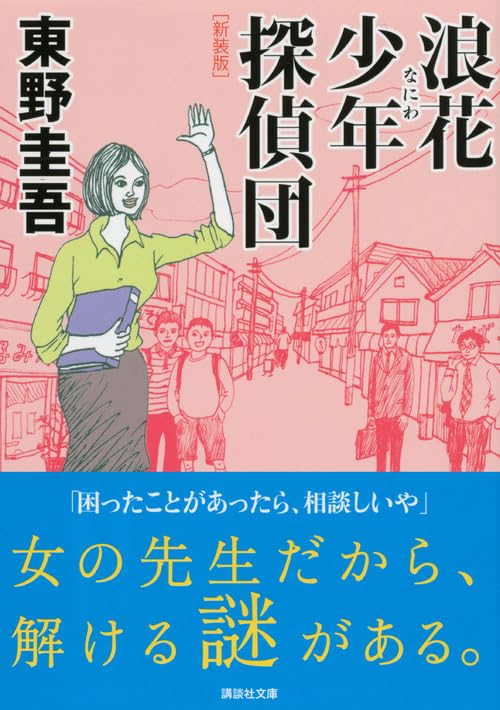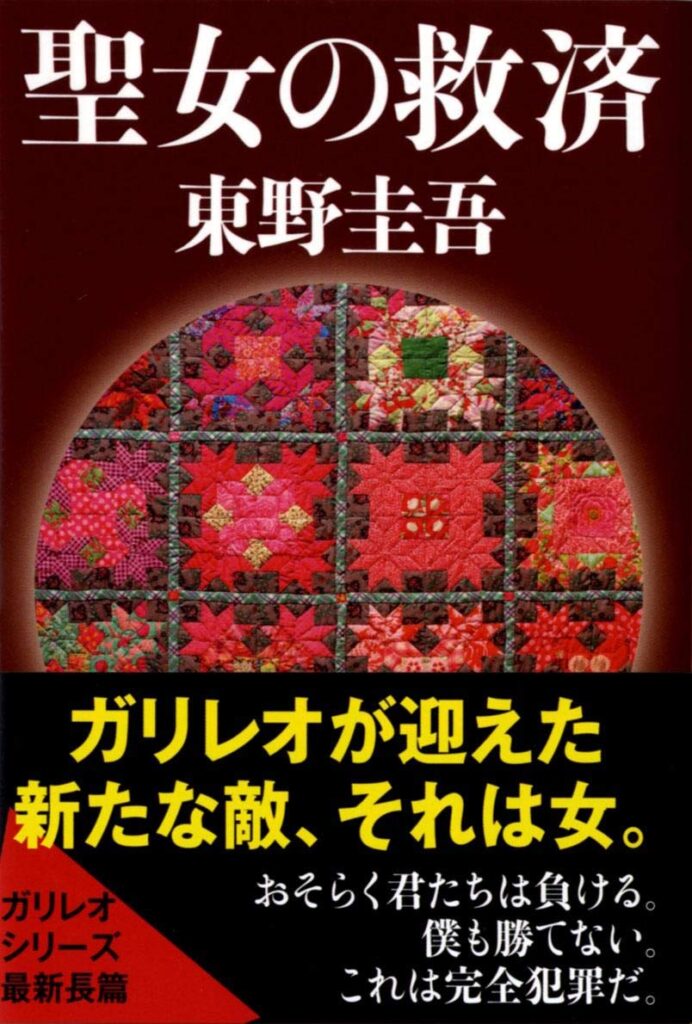小説「赤い指」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。東野圭吾氏が紡ぎ出す、加賀恭一郎シリーズの中でも特に異彩を放つこの一作。家族という、ありふれた、しかし逃れようのない枠組みの中で起こる悲劇と、そこに隠された人間の業を描き出しています。凡庸な日常が、一つの罪によっていかに脆く崩れ去るのか、その様は読む者の心に冷たい何かを残すでしょう。
小説「赤い指」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。東野圭吾氏が紡ぎ出す、加賀恭一郎シリーズの中でも特に異彩を放つこの一作。家族という、ありふれた、しかし逃れようのない枠組みの中で起こる悲劇と、そこに隠された人間の業を描き出しています。凡庸な日常が、一つの罪によっていかに脆く崩れ去るのか、その様は読む者の心に冷たい何かを残すでしょう。
物語は、どこにでもあるような平凡な家庭に投げ込まれた一つの石…いや、もっとおぞましい何かによって、波紋が広がっていく様子を克明に追っていきます。息子が犯したとされる罪を隠蔽しようとする夫婦。その背後には、介護、嫁姑問題、そして親子の断絶といった、現代社会が抱える根深い問題が横たわっています。練馬署の刑事、加賀恭一郎が、その複雑に絡み合った糸を、彼ならではの鋭い観察眼で解きほぐしていくのです。
この記事では、そんな「赤い指」の物語の筋を追いながら、その核心に迫る情報…そう、いわゆるネタバレも含めて詳しく解説していきます。さらに、私がこの作品を読んで抱いた個人的な所感も、たっぷりと語らせていただきましょう。これから読もうとされている方、あるいは既に読了された方も、しばし私の語りにお付き合いいただければ幸いです。心の準備はよろしいでしょうか?では、始めましょう。
小説「赤い指」のあらすじ
前原昭夫、47歳。照明器具メーカーに勤める彼は、妻・八重子、中学3年生の一人息子・直巳、そして認知症を患う母・政恵と共に暮らしています。しかし、その家庭は平穏とは程遠いものでした。八重子は義母である政恵の介護に疲れ果て、敵意をむき出しにし、息子・直巳は甘やかされた末に癇癪持ちとなり、父親である昭夫も家庭から逃避するように残業を繰り返す日々。家族の関係は、見えない壁で隔てられているかのようでした。
そんなある晩、昭夫のもとに妻からの切羽詰まった電話が入ります。「早く帰って来て欲しい」。嫌な予感を胸に帰宅した彼が目の当たりにしたのは、自宅の庭に横たわる見知らぬ少女の亡骸でした。八重子の説明によれば、直巳が少女を家に連れ込み、殺害したというのです。一瞬、警察への通報を考える昭夫でしたが、「息子の将来が」と泣きつく八重子の言葉に、彼は禁断の選択をしてしまいます。それは、息子の罪を隠蔽することでした。
深夜、夫婦は少女の亡骸を自転車に乗せ、家から離れた公園のトイレに遺棄します。証拠隠滅のため、昭夫は軍手をはめ、自転車の轍を靴で踏み消すといった細工も施しました。翌朝、遺体は発見され、警視庁練馬署に捜査本部が設置されます。担当となったのは、日本橋署から異動してきたばかりの刑事、加賀恭一郎。彼は現場に残された僅かな手掛かり、特に遺体に付着していた芝生の種類と、不自然に消されたタイヤ痕に注目し、地道な捜査を開始します。
加賀の捜査線上に、前原家が浮かび上がります。聞き込みに訪れた加賀に対し、昭夫は平静を装いますが、その心は動揺を隠せません。そんな中、認知症のはずの母・政恵が、昭夫が遺体運搬時に使った軍手をはめて加賀の前に現れるという奇妙な出来事が起こります。政恵の不可解な行動、庭の芝生と遺留品との一致、そして家族に漂う不自然な空気。加賀は、前原家に対する疑念を深めていくのです。追い詰められた昭夫と八重子は、さらなる隠蔽工作として、認知症の政恵に罪を着せるという、非情な計画を実行に移そうとします。
小説「赤い指」の長文感想(ネタバレあり)
さて、東野圭吾氏の「赤い指」について、私の考えを述べさせていただきましょう。この物語は、単なるミステリの枠を超え、現代社会に巣食う家族という名の病巣を、冷徹なメスで切り開いて見せた作品と言えるのではないでしょうか。読み進めるほどに、登場人物たちの身勝手さや弱さが露呈し、読者は遣る瀬無い気持ちにさせられます。しかし、それこそが東野氏の狙いであり、この作品の持つ深みなのかもしれません。
物語の中心にいるのは、前原昭夫という男。彼は、どこにでもいるような、しかし決定的な場面で主体性を欠く、弱い人間として描かれています。家庭内の不和から目を背け、仕事に逃避する。息子の非行の兆候に気づきながらも、正面から向き合おうとしない。そして、息子が犯した殺人という取り返しのつかない罪に対しても、妻の言いなりになって隠蔽に加担してしまう。彼の行動原理は、常に「面倒事を避けたい」「波風を立てたくない」という自己保身に基づいているように見えます。しかし、その弱さが、結果的に家族全員を更なる破滅へと導いていくのです。彼の姿は、現代社会に生きる多くの父親、いや、多くの人間の持つ脆さを象徴しているようで、読んでいて実に歯がゆい気持ちにさせられますね。
そして、昭夫の妻である八重子。彼女の行動は、一見すると息子を守ろうとする母性から来ているように思えます。しかし、その実態は、自己中心的なエゴイズムに他なりません。義母である政恵への憎悪、息子への過剰なまでの甘やかし、そして罪を隠蔽するためなら、認知症の義母に罪をなすりつけることさえ厭わない冷酷さ。彼女の言動は、終始、読者の神経を逆撫でします。特に、政恵に犯行の筋書きを言い聞かせ、練習させようとする場面などは、人間の醜悪さを見せつけられるようで、背筋が寒くなる思いがしました。彼女は「息子のため」と言いますが、それは結局、世間体や自分自身の安寧を守りたいという歪んだ願望の裏返しではないでしょうか。
息子の直巳に至っては、言葉もありません。甘やかされ、自己中心的に育った彼は、些細なきっかけで人命を奪い、反省の色すら見せない。彼の存在は、家庭内における教育やコミュニケーションの欠如が、いかに恐ろしい結果を招くかを示唆しています。彼がなぜそのような人格になってしまったのか、その背景には両親の無関心や歪んだ愛情があったことは想像に難くありませんが、それにしても、彼の犯した罪の重さと、その後の態度の乖離には、強い嫌悪感を抱かざるを得ません。
そんな救いのない前原家の中で、唯一、異質な光を放っているのが、昭夫の母、政恵です。当初、彼女は認知症を患い、事件の真相を知らない、あるいは理解できない存在として描かれます。しかし、物語が進むにつれて、彼女の行動が、実はすべて計算されたものであったことが明らかになる。軍手を持ち出す行為、加賀の前で見せる不可解な言動、そして指に塗られた赤い口紅。これらはすべて、息子夫婦の罪を告発し、彼らに正しい道を歩んでほしいという、悲痛なメッセージだったのです。認知症のふりをすることでしか、家族の歪みを正す術を見つけられなかった老婆の孤独と絶望。そして、それでもなお息子を想う深い愛情。政恵の存在は、この陰惨な物語の中で、一条の光…いや、それはあまりに陳腐でしょうか。言うなれば、泥沼の中に咲いた、一輪の痛々しい花のようです。彼女の真意が明かされる場面は、本作の白眉と言えるでしょう。
そして、我らが加賀恭一郎。彼は、単に事件の謎を解くだけの刑事ではありません。彼の視線は常に、事件の背後にある人間の心の機微に向けられています。前原家の不自然な空気を敏感に察知し、物的証拠だけでなく、家族それぞれの表情や言動から真相を手繰り寄せていく。特に、政恵の行動に隠された意味を見抜き、昭夫の良心に訴えかける手法は見事です。彼が昭夫に、政恵が大切にしていた鈴のついた杖を手渡す場面。その鈴の音が、昭夫の心の奥底に眠っていた母親への純粋な愛情と罪悪感を呼び覚まし、ついに彼を自白へと導く。このクライマックスは、単なる推理の決着ではなく、失われた人間性の回復への一歩を示す、感動的な瞬間と言えるでしょう。
加賀は言います。「事件は犯人を捕まえれば終わりではありません。関係者の人間性を取り戻し、彼らが本当の意味で罪を理解し、償うことが必要です」。この言葉は、加賀恭一郎シリーズ全体を貫くテーマであり、「赤い指」においても強く響きます。彼は、法で裁くだけでは解決しない、人間の心の闇と再生という、より根源的な問題に挑んでいるのです。
また、本作では、加賀自身の親子関係も重要な要素として描かれています。癌に冒され入院中の父・隆正。かつて警察官だった父との間には確執があり、加賀は見舞いにも行こうとしません。しかし、事件を通して前原家の親子の歪みと愛情を目の当たりにし、そして従弟である松宮脩平とのやり取りの中で、加賀自身の心にも変化が訪れます。終盤、彼が父の病室を訪れ、静かに将棋を指す場面は、言葉少ないながらも、親子の和解と、加賀自身の成長を感じさせます。前原家の悲劇と、加賀自身の物語が、親子という共通のテーマで響き合っている点も、この作品の構成の巧みさと言えるでしょう。
「赤い指」は、読んでいて決して楽しい気分になる物語ではありません。むしろ、重苦しく、後味の悪さを感じる方も多いでしょう。しかし、そこに描かれている家族の問題、介護の現実、親子の断絶といったテーマは、決して他人事ではない、現代社会の縮図でもあります。私たちは、この物語を通じて、家族とは何か、親子の情愛とは何か、そして罪と向き合うとはどういうことなのか、改めて考えさせられるのではないでしょうか。東野圭吾氏の鋭い人間観察と、巧みなストーリーテリングが融合した、忘れがたい一作であることは間違いありません。
まとめ
東野圭吾氏の小説「赤い指」は、加賀恭一郎シリーズの一作として、多くの読者の心を掴んで離さない力を持っています。それは、巧妙なプロットや意外な真相といったミステリとしての面白さだけではなく、現代社会が抱える普遍的なテーマ、すなわち「家族」というものの光と影を容赦なく描き出しているからに他なりません。
物語は、平凡な家庭で起きた少年による幼女殺害事件と、その隠蔽工作から始まります。しかし、その背景には、介護疲れ、嫁姑の確執、親子のコミュニケーション不全といった、根深い問題が横たわっています。加賀恭一郎刑事は、鋭い観察眼と人間への深い洞察力をもって、この複雑に絡み合った事件の真相と、前原家が抱える闇に迫っていきます。特に、認知症を装う老婆・政恵の真意が明らかになる展開は、読者に大きな衝撃と感動を与えるでしょう。
この物語は、決して読後感が爽快なものではありません。むしろ、人間の弱さや醜さ、そして家族という関係性の持つ重さに、打ちのめされるかもしれません。しかし、同時に、僅かな希望や、人間性の回復への道筋も示唆されています。加賀恭一郎という刑事の存在を通して、罪と罰、そして赦しとは何かを問いかけられる、深く考えさせられる作品です。もしあなたが、単なる謎解きに留まらない、人間の心の深淵に触れるような物語を求めているのなら、この「赤い指」は、避けて通れない一冊と言えるでしょう。