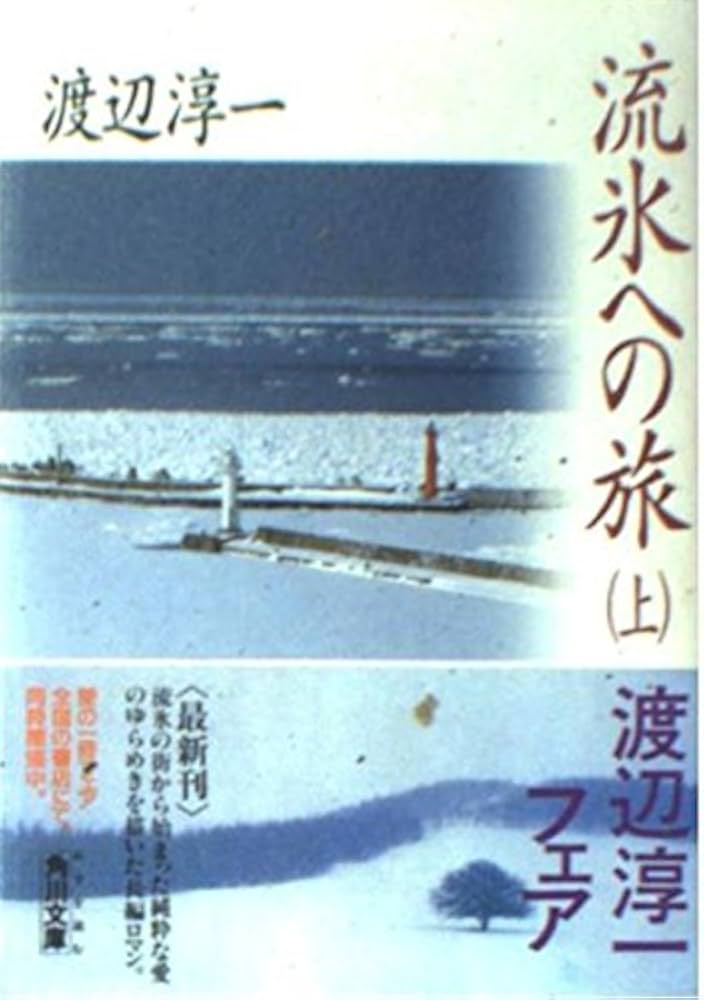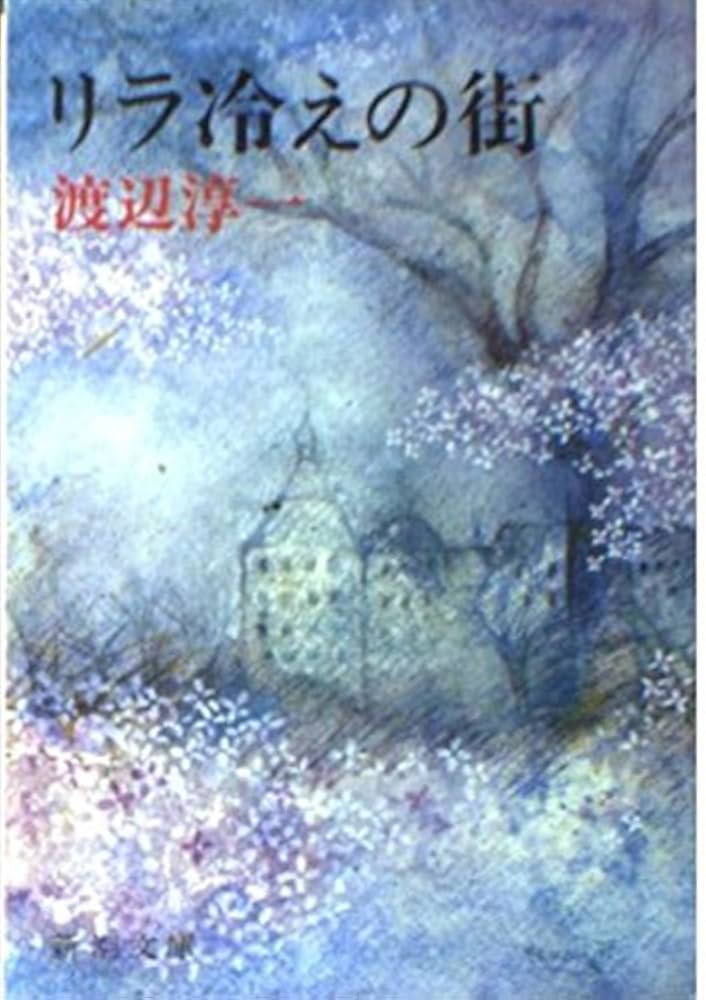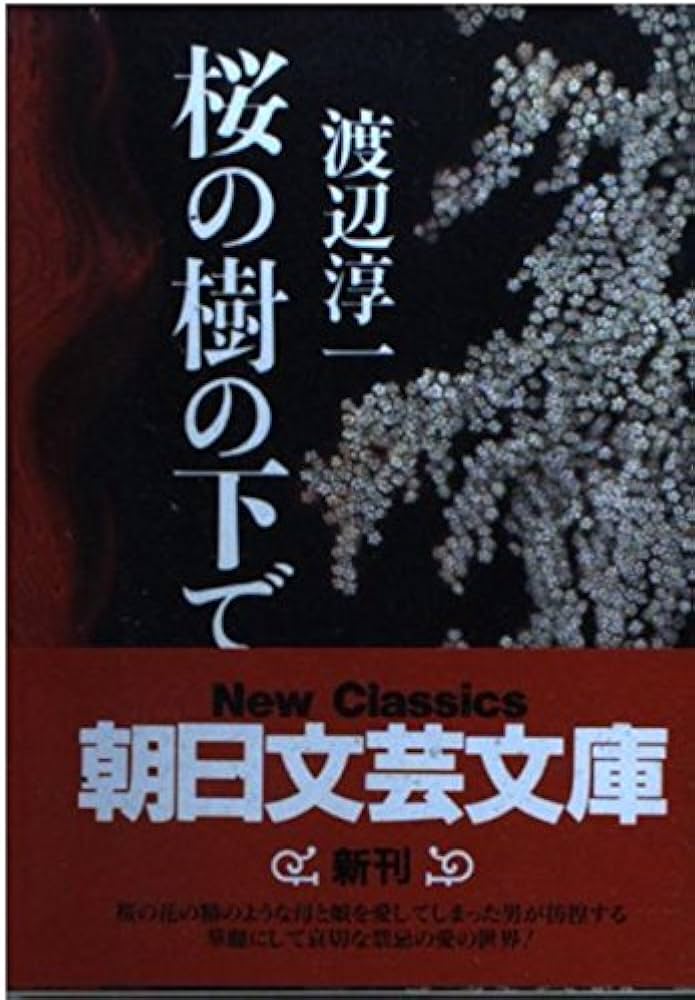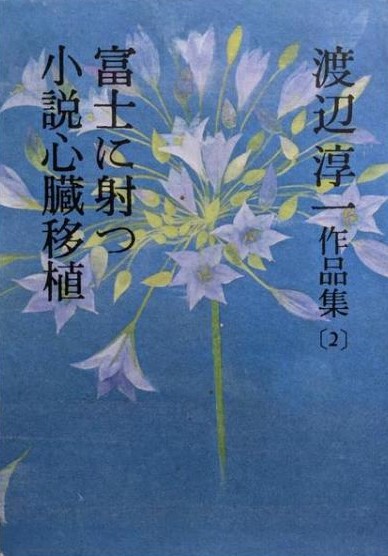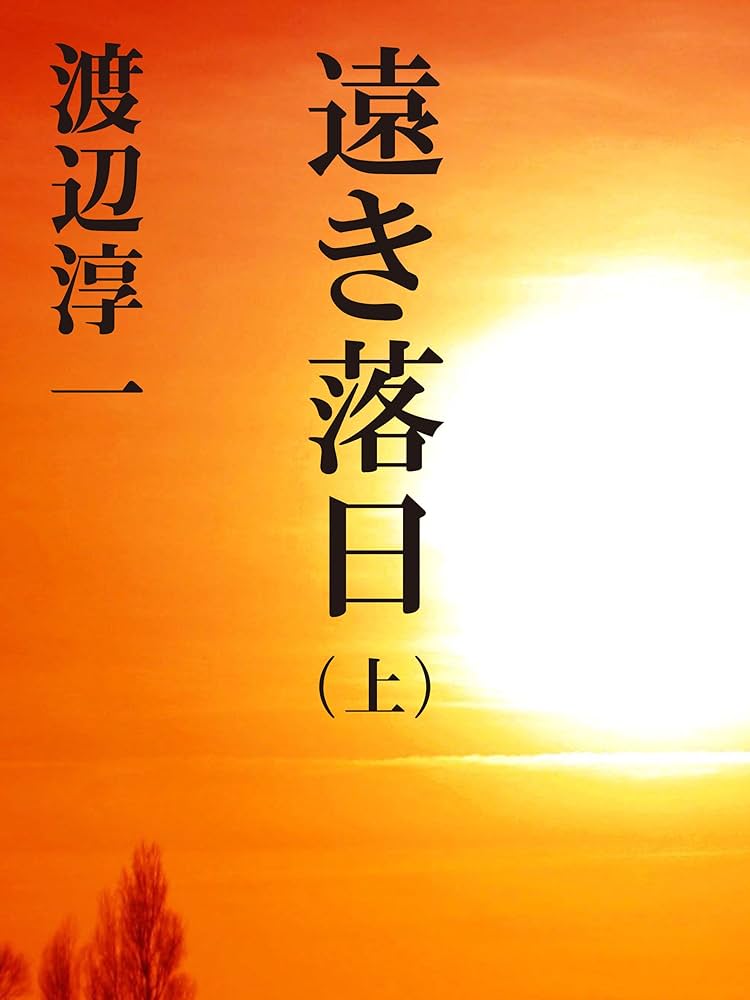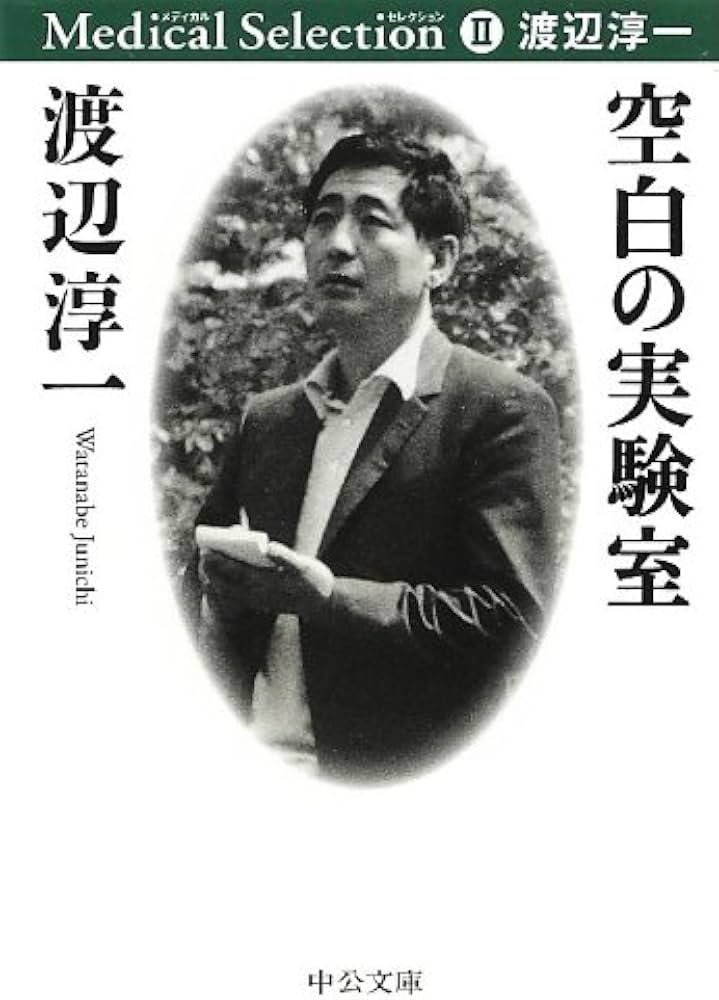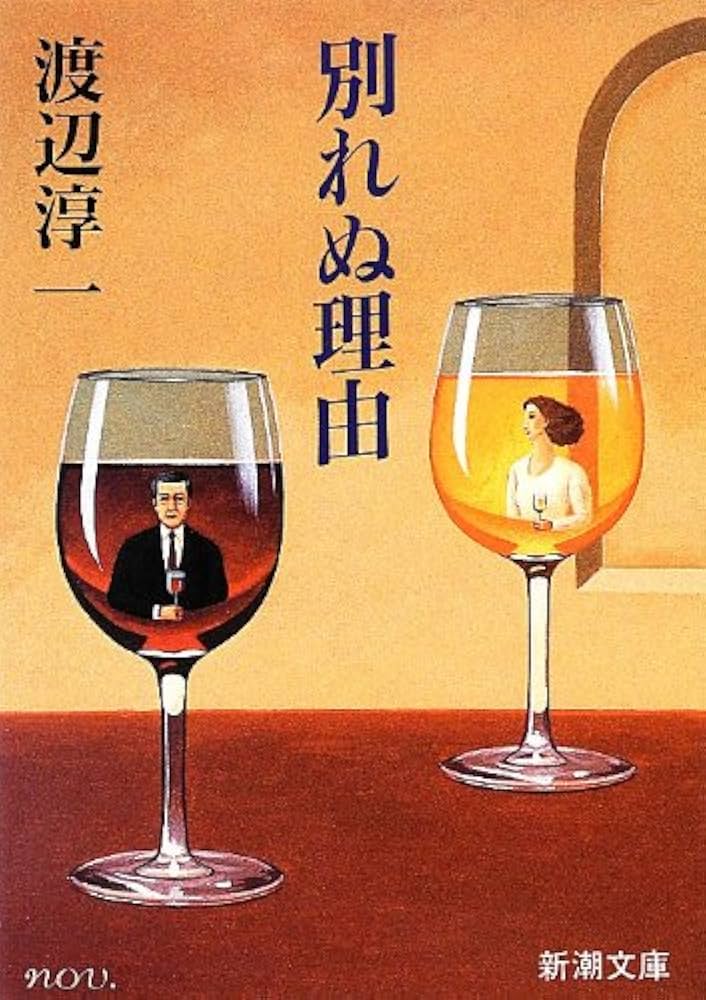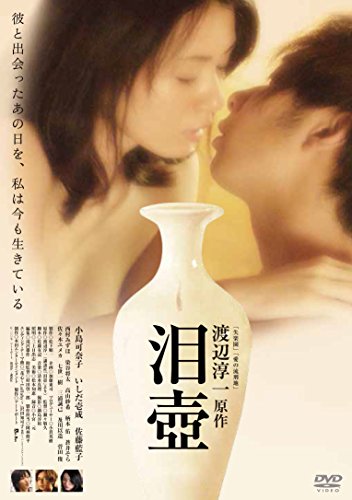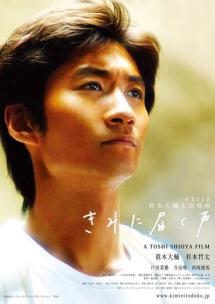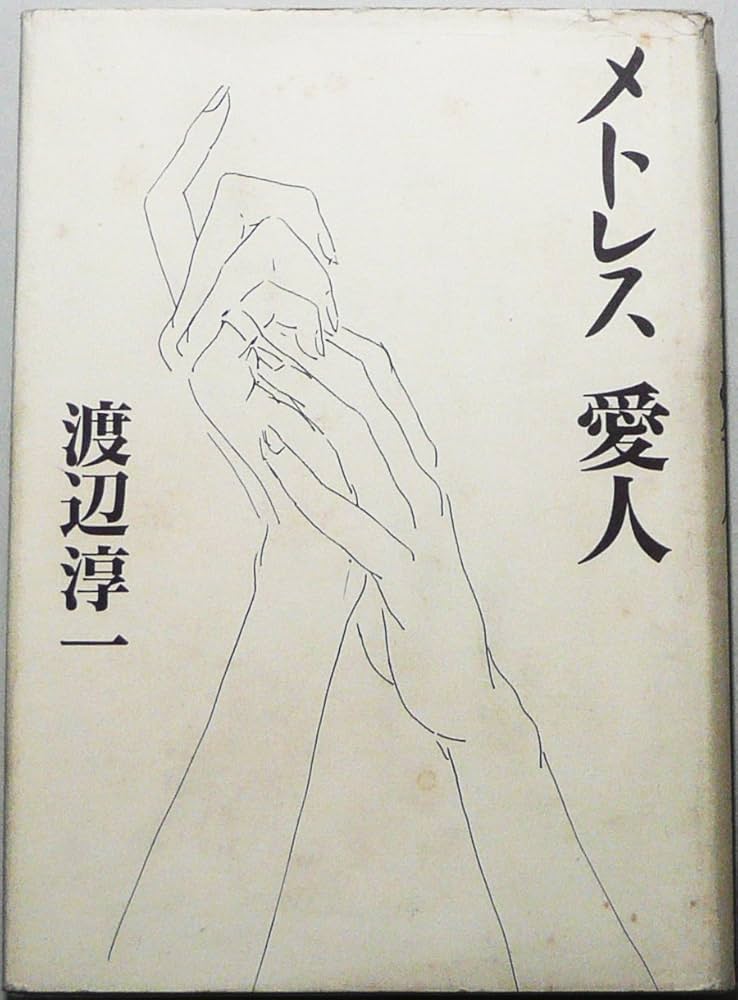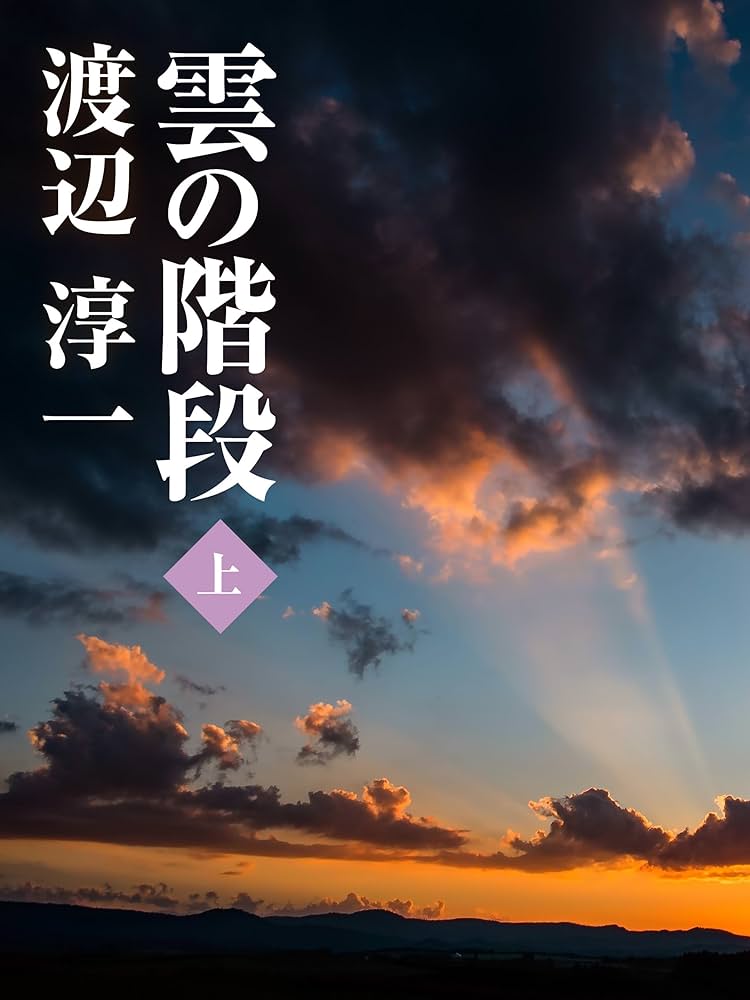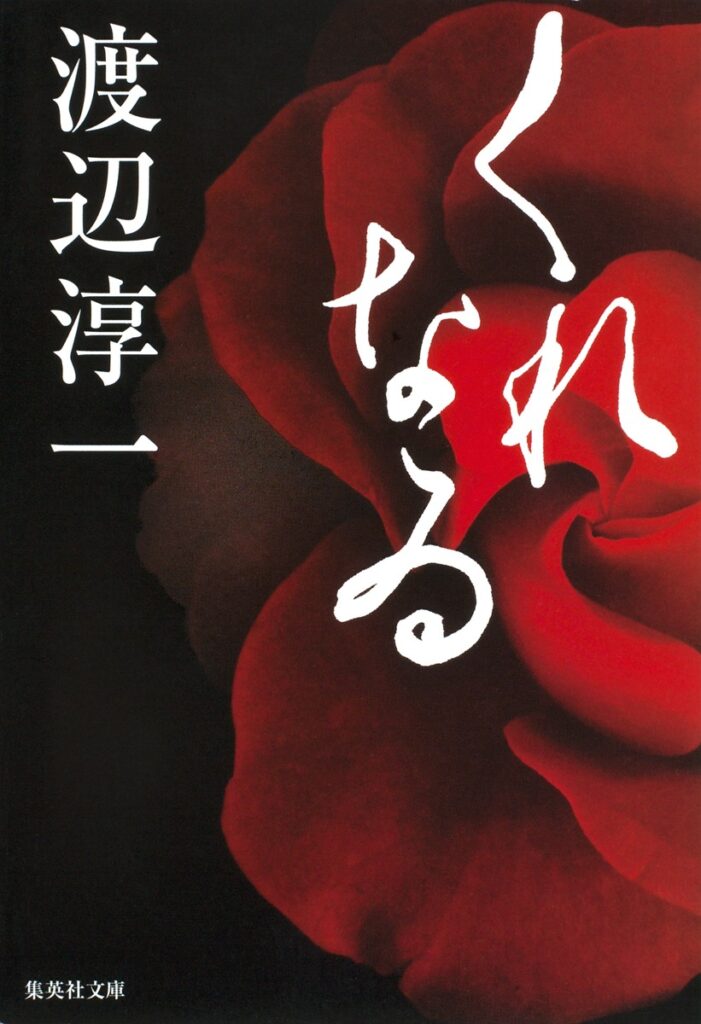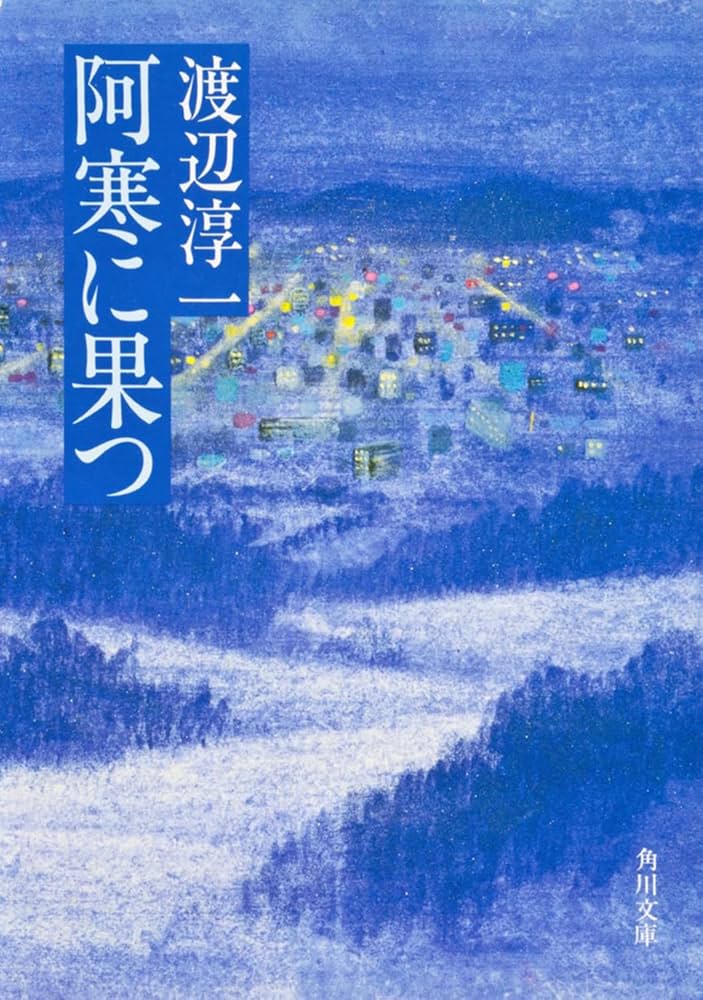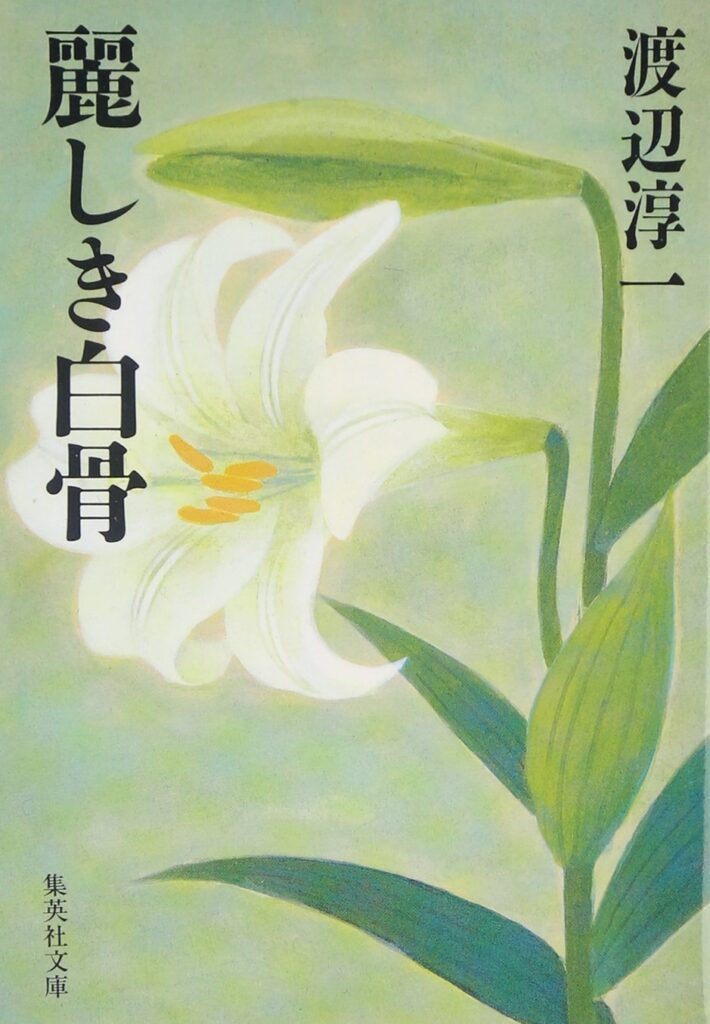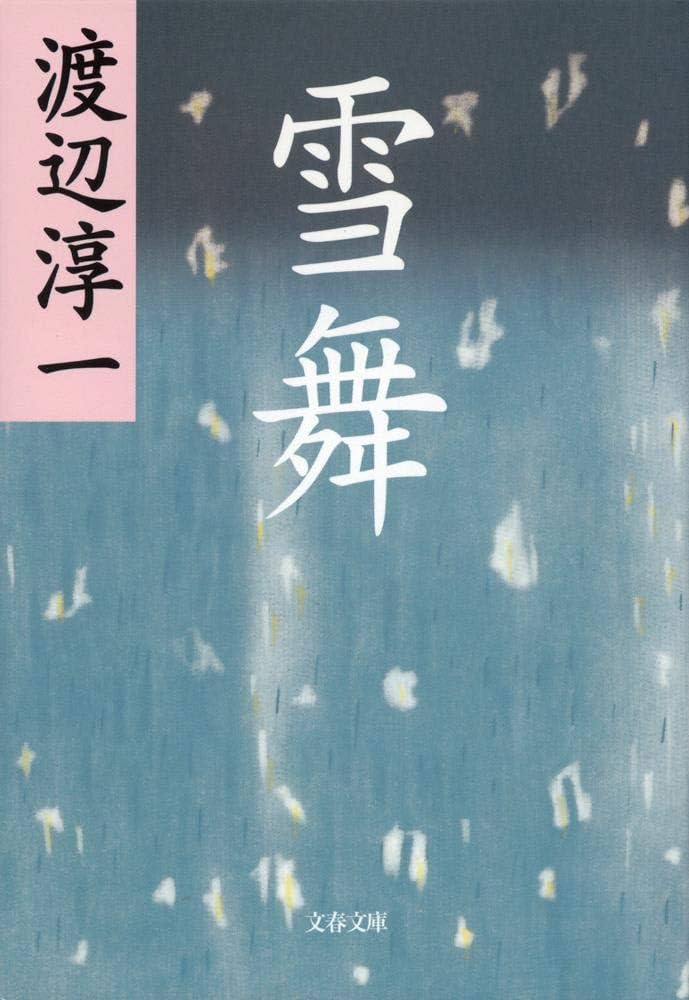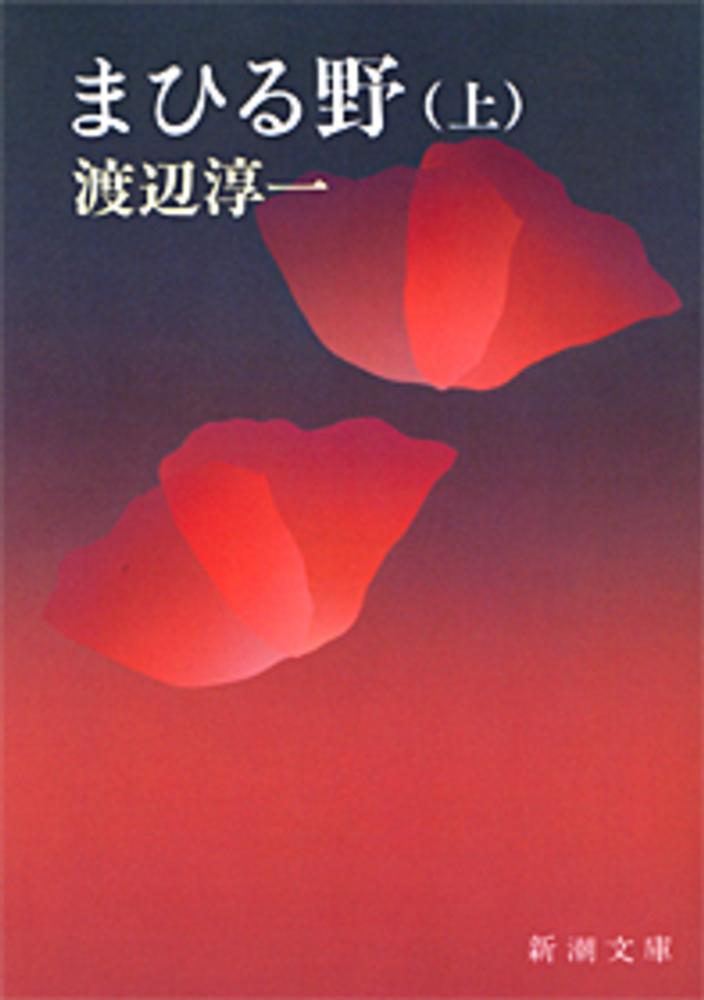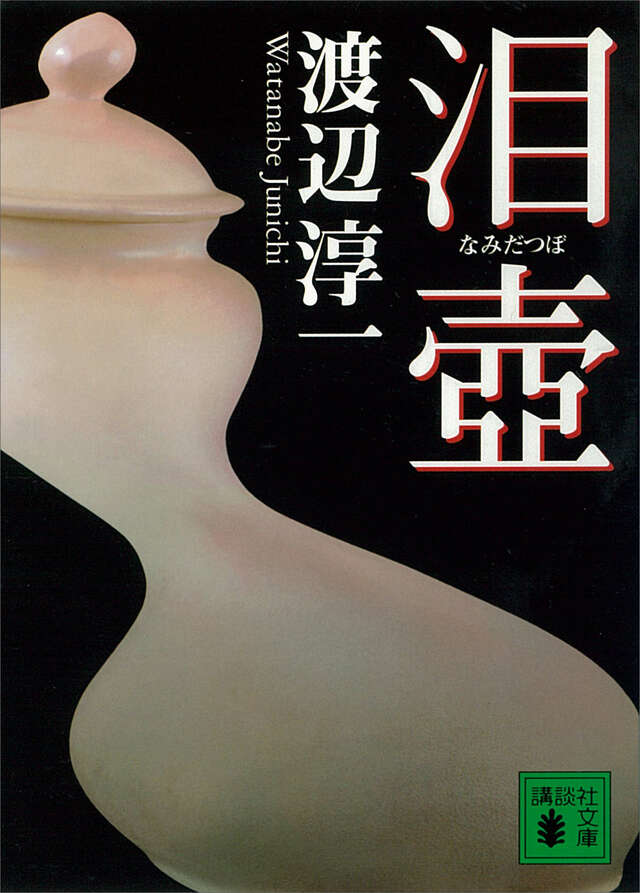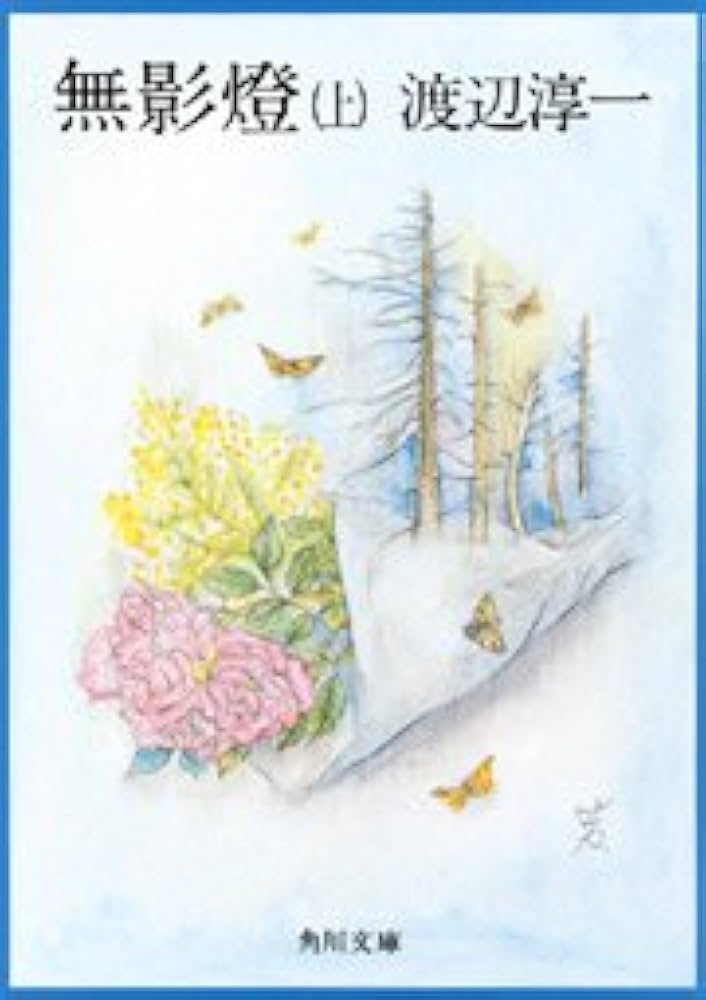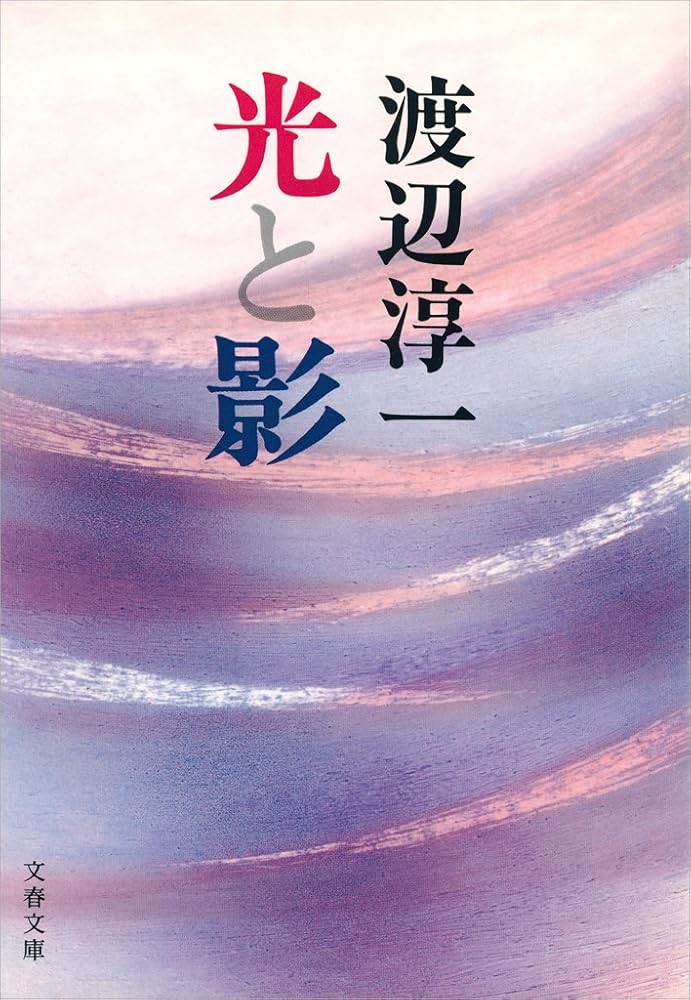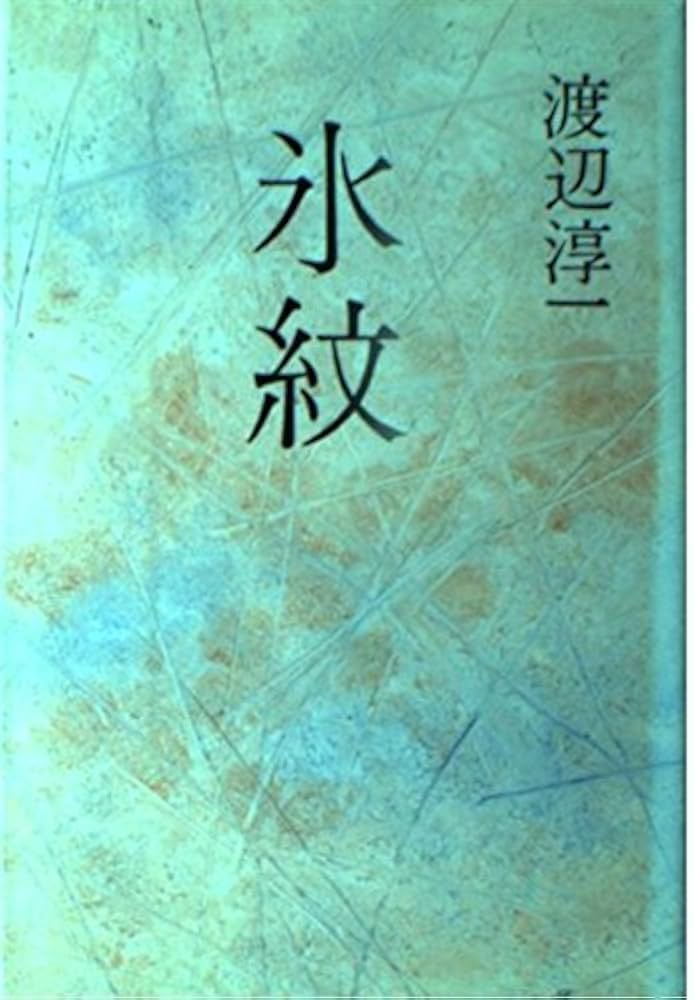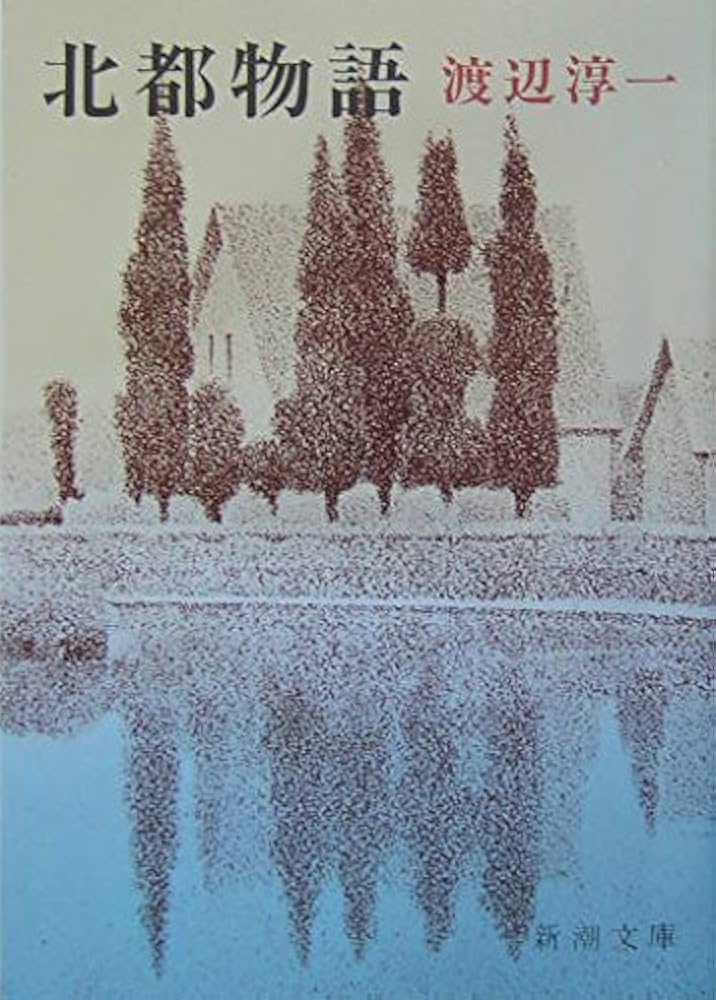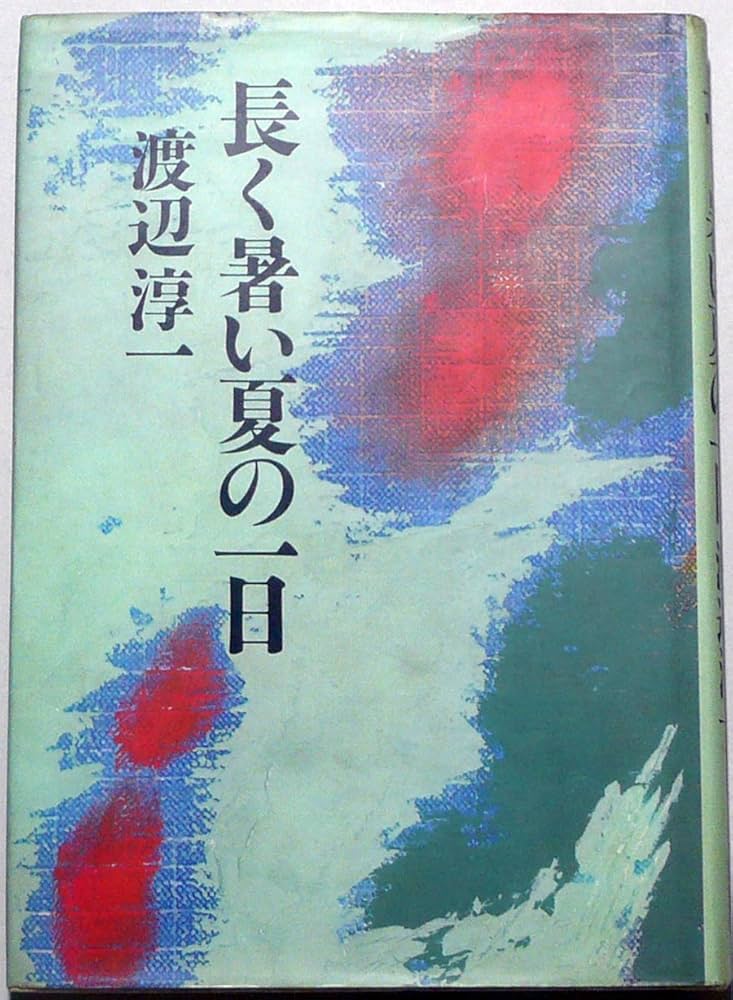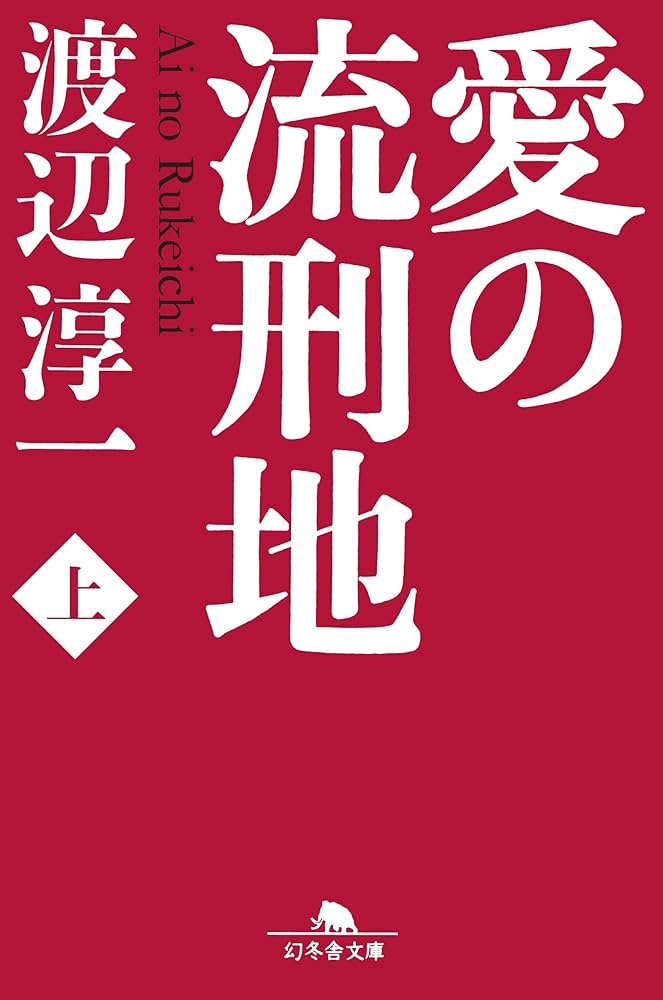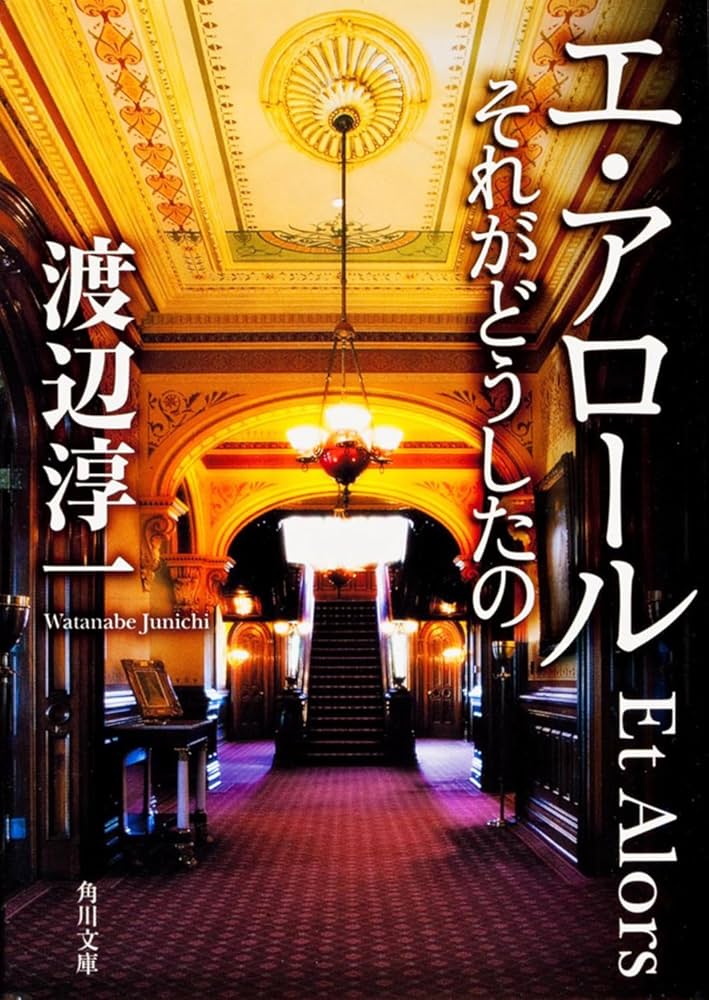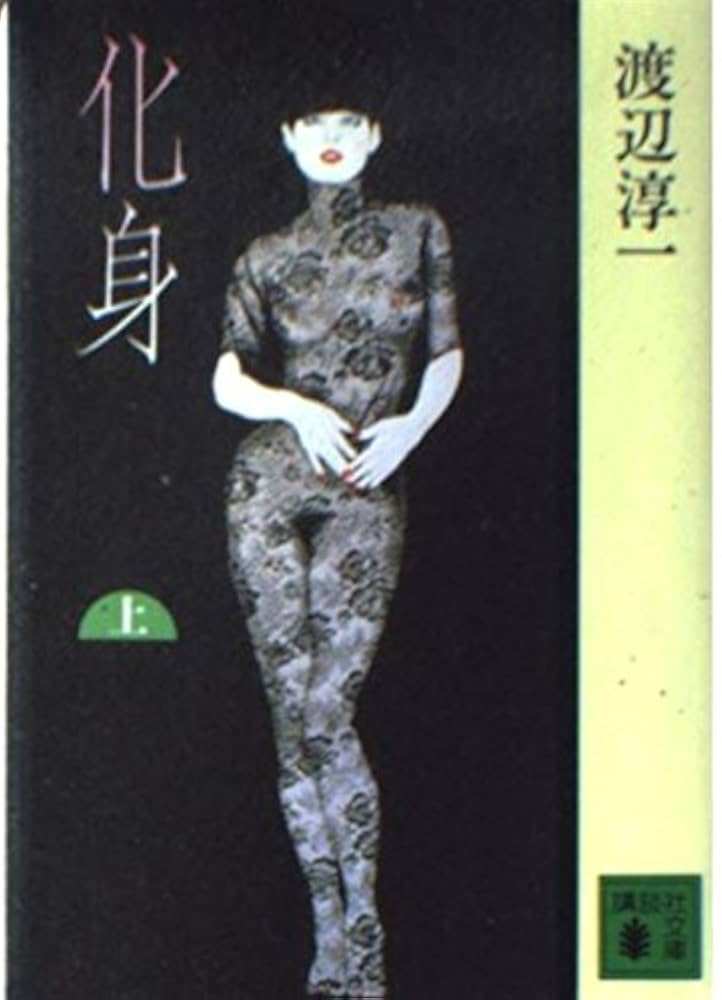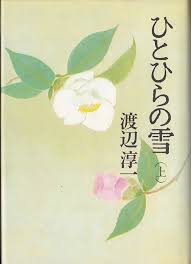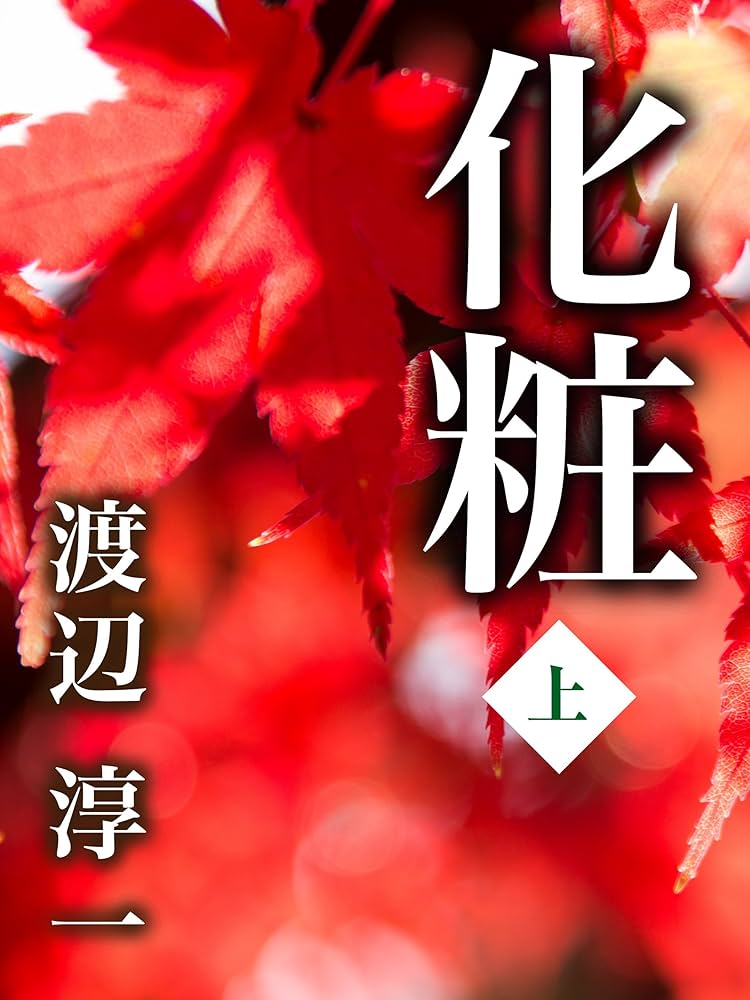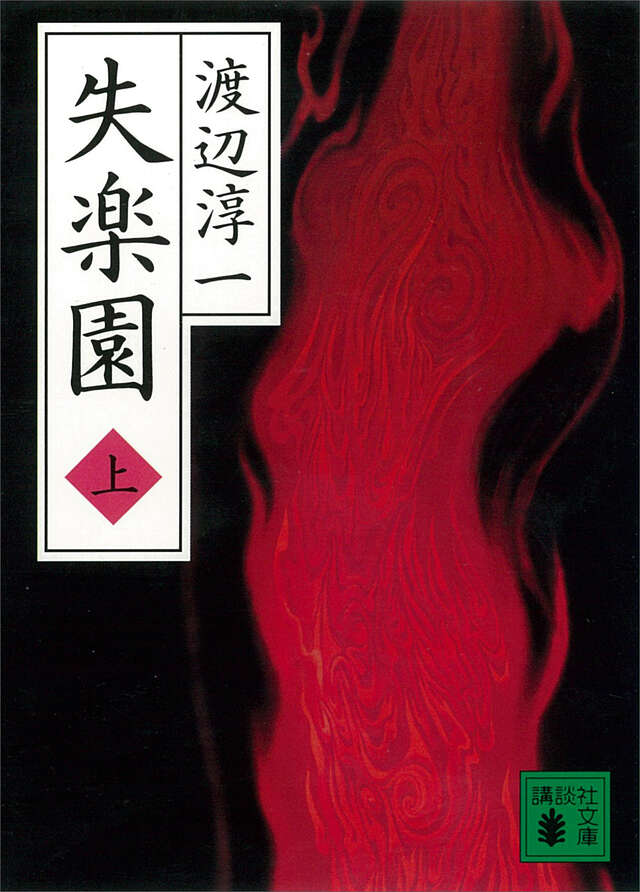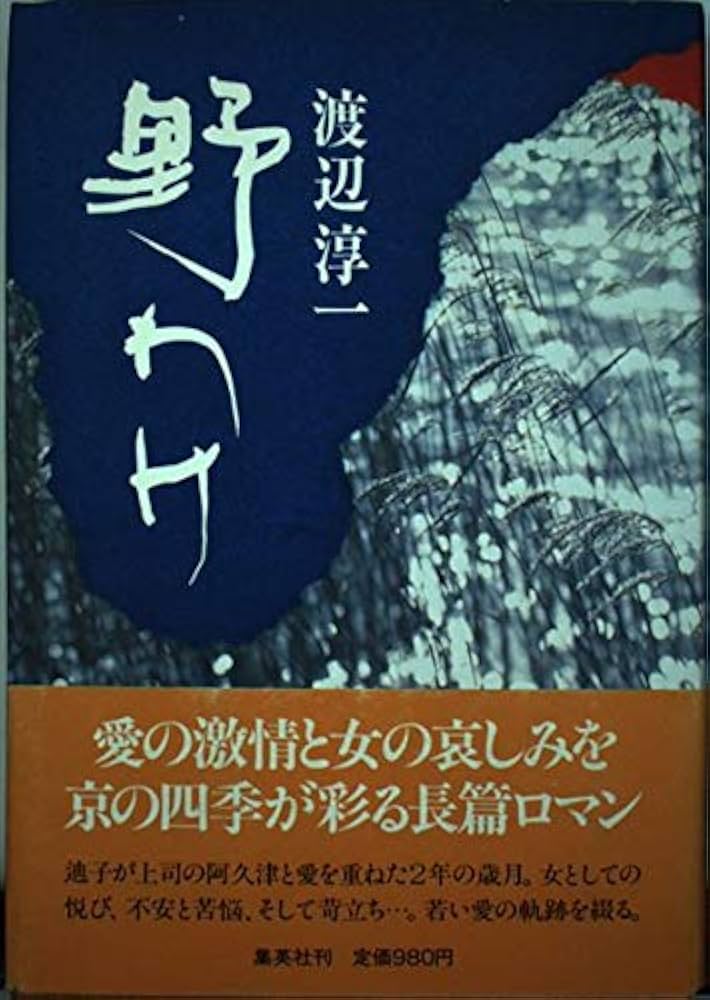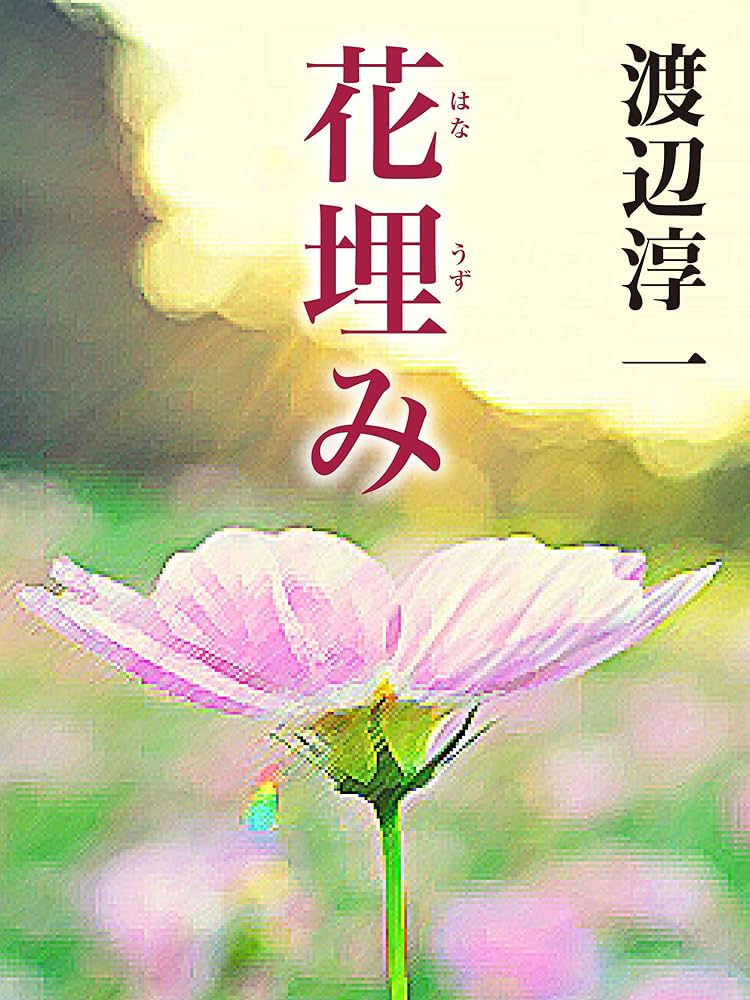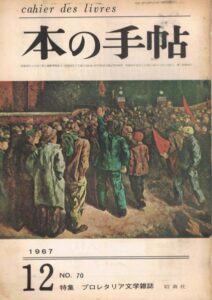 小説「訪れ」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「訪れ」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
この物語は、作家・渡辺淳一さんの原点とも言える作品で、元医師である彼にしか描けない、生と死の壮絶な現実が描かれています。一度読み始めると、その世界に引き込まれてしまうことでしょう。
物語の中心となるのは、末期の癌に冒された患者と、その事実を伝えられない医師の間の、静かで、しかし息が詰まるような心理戦です。患者の生きようとするすさまじい執念と、医師の抱えるどうしようもない無力感。この二つの感情が交錯する様は、読む者の心を強く揺さぶります。
この記事では、まず物語の概要をお伝えし、その後、結末にも触れながら、この作品がなぜこれほどまでに人の心を捉えるのか、その魅力の核心に迫っていきたいと思います。単なる医療小説という枠には収まらない、人間の根源的なテーマを扱った「訪れ」の世界へ、ご案内いたします。
「訪れ」のあらすじ
物語の語り手は、医師である「私」です。ある日、「私」のもとを、K先生という名の患者が訪れます。K先生は他の病院で胃潰瘍だと診断されていましたが、「私」は診察を通して、彼が手術不可能な末期の胃癌であり、もはや助かる見込みがないことを即座に確信します。しかし、当時の医療現場では、患者本人に癌であることを告知しないのが一般的でした。
「私」は、K先生に真実を告げることなく、「胃潰瘍」という偽りの病名のもと、治療を開始します。しかし、K先生はただおとなしく病を受け入れるような人物ではありませんでした。彼は著名な知識人であり、自らの病状について執拗に質問を繰り返し、様々な民間療法に手を出し、回復への凄まじい執着を見せつけます。
その姿を前に、「私」は良心の呵責に苛まれます。医学的には全く無意味だと知りながら、患者に希望を与え続けるためだけの投薬や処置を施し、嘘に嘘を重ねる日々。それは、医師としての倫理と、一人の人間としての罪悪感との間で引き裂かれる、苦痛に満ちたものでした。
K先生の病状は、当然のことながら快方に向かうことはありません。日に日に衰弱し、かつての知性や理性を失い、ただ死の恐怖に怯える存在へと変わっていくK先生。その痛ましい変化を目の当たりにしながら、「私」は無力感に打ちひしがれます。そして、運命の「訪れ」が、刻一刻と近づいてくるのでした。
「訪れ」の長文感想(ネタバレあり)
この小説「訪れ」を読んだ後、心に残るのは、単純な感動や悲しみだけではありません。むしろ、人間の生命が持つどうしようもない現実を突きつけられたような、一種の畏怖の念に近い感情が渦巻くのです。これは、感傷的なお涙頂戴の物語では断じてありません。元医師である渡辺淳一さんが、その冷静な観察眼で、死にゆく人間と、それを見つめるしかない人間の姿を、容赦なく描ききった作品だと言えるでしょう。
物語の語り手である医師「私」は、決して英雄などではありません。彼は、患者の運命を100%正確に知っているという、いわば神のような視点を持っています。しかし、その絶対的な「知」は、彼を救うどころか、深い孤独と欺瞞の淵へと突き落とす呪いとなります。真実を告げられないという当時の医療倫理の中で、彼はK先生に対して、悲劇的な芝居を演じ続けるしかないのです。
一方の患者、K先生の人物像も非常に印象的です。彼は単なる哀れな患者として描かれているわけではありません。むしろ、その生への執着は、時に醜いとさえ思えるほどの凄まじさをもって描かれます。様々な病院を渡り歩き、根拠のない治療法に大金を投じる。その姿は、死の恐怖から逃れたいという、人間の根源的な衝動の現れであり、物語に強烈なリアリティを与えています。
このリアリティこそ、渡辺淳一さんならではのものでしょう。彼自身が医師として数多くの死に直面してきたからこそ、医療現場の空気、医師の内心、そして患者の心理と肉体の変化を、これほどまでに克明に描き出せるのです。ページをめくるたびに、消毒液の匂いや、重苦しい診察室の空気が伝わってくるかのようです。
物語の大きな軸となっているのが、「癌を告知しない」という、今では考えられないような当時の倫理観です。この設定が、医師「私」の苦悩を何倍にも増幅させます。患者のためを思った優しい嘘は、結果的に患者が自らの運命と尊厳をもって向き合う機会を奪い、医師自身をも蝕んでいく。このジレンマは、私たち読者に「真実を知ること、知らせることの本当の意味とは何か」という重い問いを投げかけます。
批評などを読むと、このK先生のモデルは、実在した文芸評論家の亀井勝一郎氏であると言われています。この事実を知ると、物語はさらに深い意味を帯びてきます。K先生は、単なる一人の患者ではなく、知性や教養を象徴する存在として立ち現れてくるのです。
その知性の塊のような人物が、自らの肉体の死という、抗いようのない生物学的な現実の前に、いとも簡単に打ち負かされていく。この皮肉こそ、本作の核心にあるテーマの一つではないでしょうか。文学も哲学も、死の恐怖の前では慰めになりえない。人間の理性が、いかに脆い基盤の上に成り立っているかを、この物語は冷徹に暴き出します。
さらに踏み込んで考えると、これは医師から作家へと転身した渡辺淳一さんによる、文学界そのものへの一種の「解剖」であったのかもしれません。彼は、自らがこれから身を投じる文学という世界を、まず冷静に分析すべき「患者」として捉えた。そして、医学というメスを用いて、その深層心理を切り開いて見せようとしたのではないでしょうか。
そう考えると、この「訪れ」というタイトルも、二重の意味を帯びて聞こえてきます。一つは、医師が患者のもとへ往診にやってくる「訪れ」。そしてもう一つは、作家・渡辺淳一が、文学の世界の精神へと「訪問」し、その本質を観察するという「訪れ」です。彼は、医師の眼差しでしか見ることのできない真実を描くことで、自らの文学的な立ち位置を確立しようとしたのかもしれません。
物語の中で最も心を抉られるのは、K先生が肉体的にも精神的にも崩壊していく過程の描写です。かつて尊厳と知性に満ちていた人物が、その理性を剥ぎ取られ、ただ原始的な恐怖に支配された存在へと変貌していく。社会的な立場や虚飾がすべて剥がれ落ちたとき、そこに現れるむき出しの人間心理の様は、読んでいて恐怖すら覚えます。
そして、物語は衝撃的な結末を迎えます。K先生の最期は、決して穏やかなものではありません。そこには、美しい受容や魂の救済といったものは存在しないのです。ただ、本人の意志とは無関係に、生命が強制的に消滅させられるという、残酷で冷徹な事実があるだけです。この救いのない結末は、読者の心に深い衝撃と、医師「私」が感じたであろう途方もない無力感を残します。
この冷徹とも思える「医師の眼差し」は、本作の欠点ではなく、むしろ最大の強みです。渡辺さんは、安易な感傷主義を徹底的に排除することで、死という現象の生物学的な真実と、それに直面した人間の本性を、ごまかしなく描き切りました。だからこそ、この物語はこれほどまでに力強いのです。
しかし、この物語はただ死の残酷さを描くだけではありません。理屈では説明のつかないK先生の生への執着は、見方を変えれば、消えゆく直前に放たれる、生命そのものの力強い輝きとも捉えられます。醜くとも、滑稽であっても、最後まで生きようともがく姿に、私たちは根源的な生命の尊さを見出すのかもしれません。
興味深いことに、この初期の医療小説「訪れ」には、後の恋愛小説の金字塔『失楽園』へと繋がる、渡辺文学の核心的なテーマがすでに確立されています。それは、「極限状態に置かれた人間の探求」というテーマです。「訪れ」では、患者が「病による死」という抗えない極限状態に置かれます。
一方で、『失楽園』では、恋人たちが「愛の情熱」という自ら選んだ極限状態に身を置き、社会的な死、そして文字通りの死へと突き進んでいきます。「訪れ」の極限が非自発的なものであるのに対し、『失楽園』のそれは意識的な選択であるという違いはありますが、その根底にある関心は同じです。人間が追い詰められたとき、その精神はどうなるのか。それを解剖することこそが、渡辺文学の一貫した目的だったのです。
この視点を持つと、渡辺淳一という作家は、単に「医療作家」から「恋愛作家」へと転身したのではないことがわかります。彼は生涯をかけて、様々な状況下における人間の心理を解剖し続けた作家だったのです。「訪れ」は、その記念すべき最初の成功例であり、彼が自らの文学的手法を初めて完成させた、基礎となる作品なのです。
インフォームド・コンセントが当たり前となり、患者が自らの病について知る権利を持つようになった現代において、この「訪れ」を読むことには、また新たな意味があるように感じます。真実を知らされることの重さ、そして知らされないことの残酷さ。この物語は、医療倫理が大きく変わった今だからこそ、より深く私たちの心に響くのかもしれません。
結論として、「訪れ」は、単なる医療小説というジャンルを遥かに超えた、不朽の傑作です。それは、死とは何か、生きるとは何かという、人間にとって最も普遍的で根源的な問いを、医学的なリアリズムと文学的な深みをもって描ききっています。時代を超えて読者の心を打ち、私たち一人ひとりに自らの生と死について考えさせる、力強い物語だと言えるでしょう。
まとめ
この記事では、渡辺淳一さんの小説「訪れ」について、物語の筋立てから、結末のネタバレを含む深い部分まで踏み込んで考察してきました。本作が、単なる悲しい物語ではなく、人間の生と死の現実を冷徹なまでに描き出した、重厚な作品であることがお分かりいただけたかと思います。
物語の中心にあるのは、末期の癌であることを告知されない患者・K先生と、真実を隠して治療を続ける医師「私」との間の、息詰まるような心理的な葛藤でした。この設定を通して、当時の医療が抱えていた倫理的な問題や、死を前にした人間のむき出しの心理が、克明に描き出されています。
また、本作が渡辺文学全体の原点であることにも触れました。医師としての冷静な観察眼で「極限状態の人間」を描くという手法は、後の『失楽園』などの恋愛小説にも通底する、作家の一貫したテーマなのです。この視点から読むことで、「訪れ」の持つ文学的な重要性もより深く理解できます。
「訪れ」は、読む者に生きることの意味を鋭く問いかける力を持った小説です。少し重いテーマかもしれませんが、だからこそ心に残り、人生の折に触れて読み返したくなる、そんな深みを持った一冊です。ぜひ一度、手に取ってみてはいかがでしょうか。