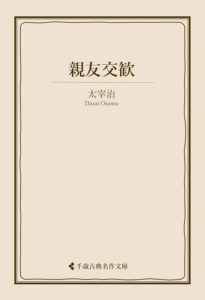 小説『親友交歓』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。太宰治の作品の中でも、読後に何とも言えない気持ちになる、ある意味で強烈な印象を残す短編ではないでしょうか。
小説『親友交歓』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。太宰治の作品の中でも、読後に何とも言えない気持ちになる、ある意味で強烈な印象を残す短編ではないでしょうか。
この物語は、戦後間もない時期、故郷の津軽に疎開している「私」のもとに、小学校時代の親友だと名乗る男「平田」が突然訪ねてくるところから始まります。しかし、「私」にはその男の記憶がほとんどありません。それなのに、平田は馴れ馴れしく家に上がり込み、傍若無人な振る舞いを繰り広げるのです。
この記事では、そんな『親友交歓』の物語の詳しい流れ、つまりあらすじを、結末まで含めてお伝えします。核心部分に触れていますので、まだ読みたくない方はご注意くださいね。
そして、物語の詳細なあらすじに続いて、私がこの作品を読んで感じたこと、考えたことを、かなり長文になりますが、正直に綴ってみました。この奇妙な「親友」との一夜が、私たちに何を問いかけているのか、一緒に考えていけたら嬉しいです。
小説『親友交歓』のあらすじ
物語は、昭和二十一年の九月はじめ、「私」が津軽の実家で過ごしている場面から始まります。戦争で被災し、東京から家族と共に疎開していたのです。そこへ、小学校時代の同級生で「親友」だと名乗る平田という男が、何の予告もなく訪れます。「私」はその顔にかすかな見覚えを感じ、とりあえず家へ招き入れます。
平田は、「私」と昔よく喧嘩をした、その時の傷がまだ残っている、などと一方的に親しげな思い出話を始めますが、「私」には全く身に覚えのないことばかり。曖昧な笑みを浮かべて聞き役に徹するしかありません。平田の訪問の目的は、クラス会を開くための相談でした。その費用として、酒を二斗(約36リットル)ほど集めたいが、どうすれば良いか、というのです。
「私」がお金を出そうとすると、平田は「金は後でもらうかもしれんが、今は相談と、親友の顔を見に来ただけだ」とかわします。しかし、その直後、「酒はないのか。かか(『私』の妻)のお酌で一杯飲ませろ」と要求するのです。「私」は、愛想の良くない妻に見せるのをためらい、「女房はいない」と嘘をつき、仕方なくとっておきのウイスキーを出すことにしました。
そのウイスキーは、「私」がなけなしの金で手に入れ、作家の井伏鱒二が訪ねてきた時にでも一緒に飲もうと、大切に保管していたものでした。しかし平田は、そんな「私」の思いなどお構いなしに、「まむし焼酎に似ている」「たいして強くない」などと無粋なことを言いながら、ガブガブと飲み干していきます。「私」が全く興味を持てない自慢話や、東京での「私」の失敗談を持ち出しては、弱みに付け込もうとするような態度に、「私」は嫌悪感を募らせていきます。
酔いが回るにつれて、平田の言動はさらにエスカレートします。「私」の先祖はただの油売りだったと貶める一方で、自分の一族の自慢話を延々とし、ついには「お前のお酌では飲まん、かかを呼んでこい!」と騒ぎ立てます。仕方なく妻を呼び出すと、平田は妻に対しても失礼な話を続け、妻が部屋を出ようとすると「お前のかかはいかん!」などと怒鳴り散らす始末。
さんざん騒ぎ、大切にしていたウイスキーをほとんど飲み干し、挙句の果てには無惨な歌を歌った後、平田はようやく「帰る」と言い出します。「私」は引き止めもせず、平田が要求するままに残っていた最後のウイスキーまで手渡します。玄関まで送り届けた「私」に、平田は別れ際、耳元で強くこう囁くのでした。「威張るな!」と。結局、「私」の記憶には全くない男との、奇妙で不快な「親友交歓」は、こうして幕を閉じるのです。
小説『親友交歓』の長文感想(ネタバレあり)
いやはや、この『親友交歓』という作品、読んでいる間、ずっと眉間にしわが寄っていたような気がします。読後感は、爽快さとは程遠い、むしろ何とも言えない居心地の悪さ、不快感、そして一種の当惑でしょうか。嵐が過ぎ去った後のような、静かな、しかし気まずい沈黙が心に残る、そんな物語でした。
まず、この平田という男。一体何なのでしょうか。突然現れて「親友」を名乗り、人の家にずかずかと上がり込み、貴重な酒を飲み散らかし、自慢話と失礼な言動を繰り返し、最後には「威張るな!」という謎の捨て台詞。彼の行動原理は、一読しただけでは全く理解できません。ただただ、その傍若無人さ、厚かましさに圧倒され、不快感を覚えるばかりです。
しかし、何度か読み返してみると、この平田という人物像が、単なる「嫌な奴」というだけではない、もっと複雑な人間の弱さや歪みを体現しているようにも思えてくるのです。彼は、おそらく「私」(太宰治自身をモデルにしているとされる)が作家としてある程度の成功を収めていることに対して、強い劣等感や嫉妬心を抱いていたのではないでしょうか。
だからこそ、昔の(彼だけが覚えている)対等だった(と彼が信じている)関係性を持ち出し、「親友」という言葉で距離を縮めようとした。そして、酒の力を借りて虚勢を張り、自慢話をすることで、自分の方が上なのだと誇示しようとしたのかもしれません。さらに、「私」の過去の失敗(女関係のしくじり)を持ち出すあたりは、相手を引きずり下ろして安心したい、という心理の表れとも取れます。
一方の「私」の態度はどうでしょう。彼は終始、平田に対して曖昧な微笑みを浮かべ、内心の不快感を押し殺し、波風立てずにやり過ごそうとします。これは、いわゆる「大人の対応」と言えるのかもしれません。しかし、その態度は、平田の増長を許し、結果的に彼に言いたい放題やらせてしまうことにも繋がっています。
「私」の中には、平田に対する嫌悪感だけでなく、もしかしたら憐れみや、知識人としての優越感のようなものもあったのかもしれません。平田の言動を内心で見下しながらも、それを表に出さず、冷静に対応する。その余裕のある(ように見える)態度が、平田の劣等感をさらに刺激した可能性も考えられます。
そして、物語の核心とも言える最後の「威張るな!」。この一言に、様々な解釈が可能です。単純に考えれば、さんざん迷惑をかけておきながら、逆ギレしているようにも聞こえます。しかし、もっと深く考えると、これは平田の魂の叫びのようにも感じられるのです。
「お前は作家として成功し、良い暮らしをしているかもしれない。俺はこんな風にみっともなく振る舞うしかない。だが、そんな俺を見下して、余裕ぶって対応するな。心の中で俺を憐れんで、自分の方が上だなんて思うな!」…そんな、平田の屈折したプライド、惨めさ、そして「私」への強い反発が込められた言葉なのかもしれません。平田は、「私」の内心の優越感や憐れみを敏感に感じ取っていたのではないでしょうか。
この作品は、「私」=太宰治自身という私小説的な要素が色濃いと言われています。津軽という故郷、井伏鱒二の名前、「修治」という呼び名(太宰の本名)など、符合する点は多いです。もし、これが太宰自身の実際の体験に基づいているとしたら、なんとも生々しい話です。自分が体験した不快な出来事を、ほぼそのまま(あるいは脚色して)作品として昇華させる。その行為自体に、太宰の作家としての業のようなものを感じずにはいられません。
体験した嫌なことを、愚痴るように小説にして発表する。それはある種の暴露であり、同時に自己分析でもあるのかもしれません。平田という存在を通して、太宰自身の中にあるかもしれない、見栄や俗物的な部分、あるいは他者に対する優越感のようなものを、客観視しようとしていた可能性はないでしょうか。
また、この物語は「親友」とは何か、という根源的な問いも投げかけてきます。平田は一方的に「親友」を名乗りますが、「私」にはその記憶がありません。そもそも、親友とは、互いに記憶し、尊重し合える関係のはずです。平田のような一方的で、相手を利用しようとするような関係は、果たして「交歓」と呼べるのでしょうか。
しかし、人間関係というのは、常に清らかで美しいものばかりではありません。多かれ少なかれ、人は誰かを利用したり、見栄を張ったり、嫉妬したりするものです。平田の行動は極端ですが、その根底にある感情は、程度の差こそあれ、誰の心の中にも潜んでいるのではないでしょうか。「私」が平田の要求を無下に断れなかったのも、どこかでそうした人間の弱さに対する共感、あるいは同族嫌悪のようなものがあったのかもしれません。
戦後間もない混乱した時代背景も、この物語の不穏な空気に影響を与えているでしょう。価値観が大きく揺らぎ、誰もが必死で生きている中で、人と人との関係性もまた、奇妙に歪んでしまうことがあったのかもしれません。平田のなりふり構わない生き方は、そうした時代の産物とも言えるかもしれません。
読み進めるほどに、平田への不快感は、「私」へのもどかしさや、さらには人間関係そのものの厄介さ、一筋縄ではいかない複雑さへと、思考が広がっていきます。明確な答えや救いは提示されません。ただ、人間のどうしようもなさ、愚かさ、そして、それでも続いていく日常が、淡々と、しかし強烈に描かれているのです。
この作品のすごさは、読者に強烈な印象と問いを残す点にあると思います。単純な勧善懲悪ではない、割り切れない人間の感情や関係性の機微を描き出すことで、読者は自らの心の内や、周囲との関係性について、深く考えさせられることになるのです。気持ちの良い読後感ではありませんが、一度読んだら忘れられない、太宰治の底知れない深淵を覗かせる一作だと言えるでしょう。
太宰の他の作品、例えば『人間失格』のような自己破滅的な苦悩とはまた違う、もっと日常に潜む、じっとりとした人間の嫌な部分、関係性の軋轢を描いている点で、非常に興味深い作品です。もしかしたら、『人間失格』よりも、こちらの『親友交歓』の方が、より多くの人が共感、あるいは「こういうこと、あるかも」と感じる部分が多いのではないでしょうか。
平田のような人物に出会った経験、あるいは「私」のように、内心の不快感を隠して曖昧に対応してしまった経験。そうした記憶が、読者の心のどこかを刺激するのかもしれません。だからこそ、不快でありながらも、妙に心に引っかかるのでしょう。
結局のところ、平田の「威張るな!」は、もしかしたら「私」だけでなく、私たち読者一人ひとりにも向けられた言葉なのかもしれない、とさえ思えてきます。他者をどこかで見下したり、自分の物差しで勝手に判断したりしていないか。表面的な対応の裏で、優越感に浸ってはいないか。そんな風に、自らを省みるきっかけを与えてくれる、恐ろしくも示唆に富んだ一言なのです。
まとめ
太宰治の『親友交歓』は、戦後の津軽を舞台に、突然訪ねてきた自称「親友」平田と、「私」との奇妙で不快な一夜を描いた短編小説です。平田の傍若無人な振る舞いと、それに翻弄されながらも曖昧な態度を取り続ける「私」の姿が、読者に強烈な印象を与えます。
物語の結末、平田が最後に放つ「威張るな!」という一言は、様々な解釈を呼び、作品の読後感を一層複雑なものにしています。それは単なる平田の捨て台詞ではなく、彼の劣等感や嫉妬、「私」の内心を見抜いた上での反発、あるいは人間関係に潜む普遍的な感情の表れとも考えられます。
この作品は、単に不快な出来事を描いているだけでなく、「親友」とは何か、人間関係の複雑さ、見栄や嫉妬といった人間の持つ普遍的な感情について、深く考えさせられます。太宰治自身の体験が色濃く反映された私小説的な側面も持ち合わせており、太宰文学の奥深さを知る上で欠かせない一作と言えるでしょう。
読後感は決して良いものではありませんが、人間の本質や関係性の難しさを鋭く描き出した、一度読んだら忘れられない力を持った物語です。ぜひ、ご自身の解釈を探しながら読んでみてはいかがでしょうか。




























































