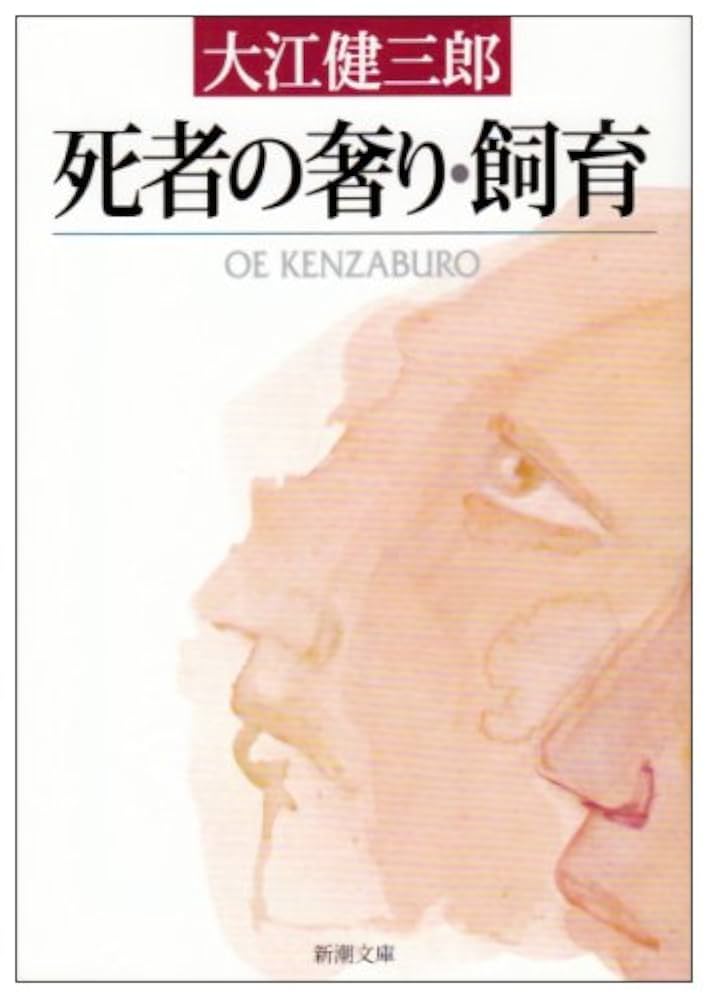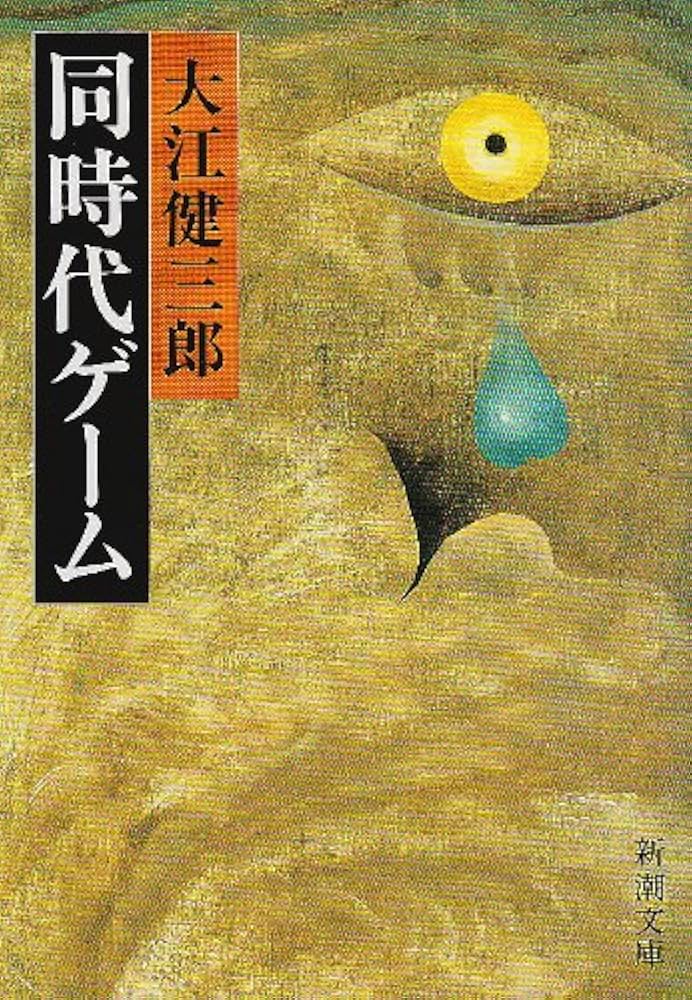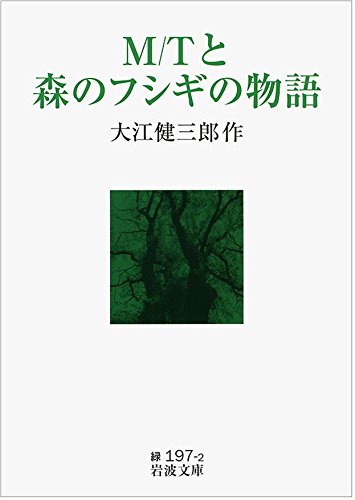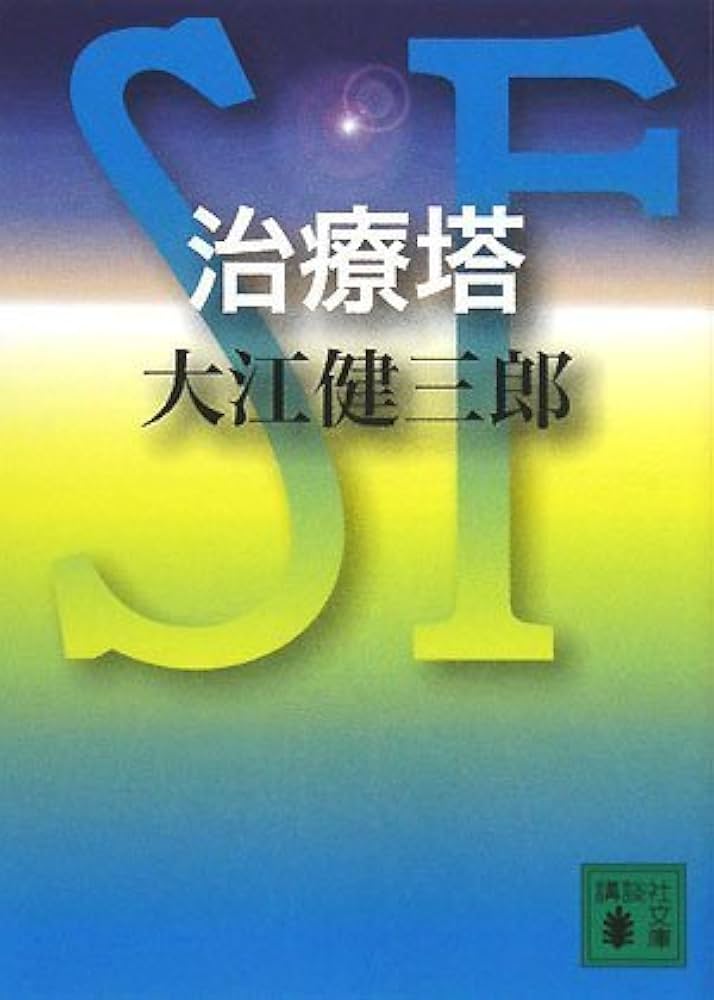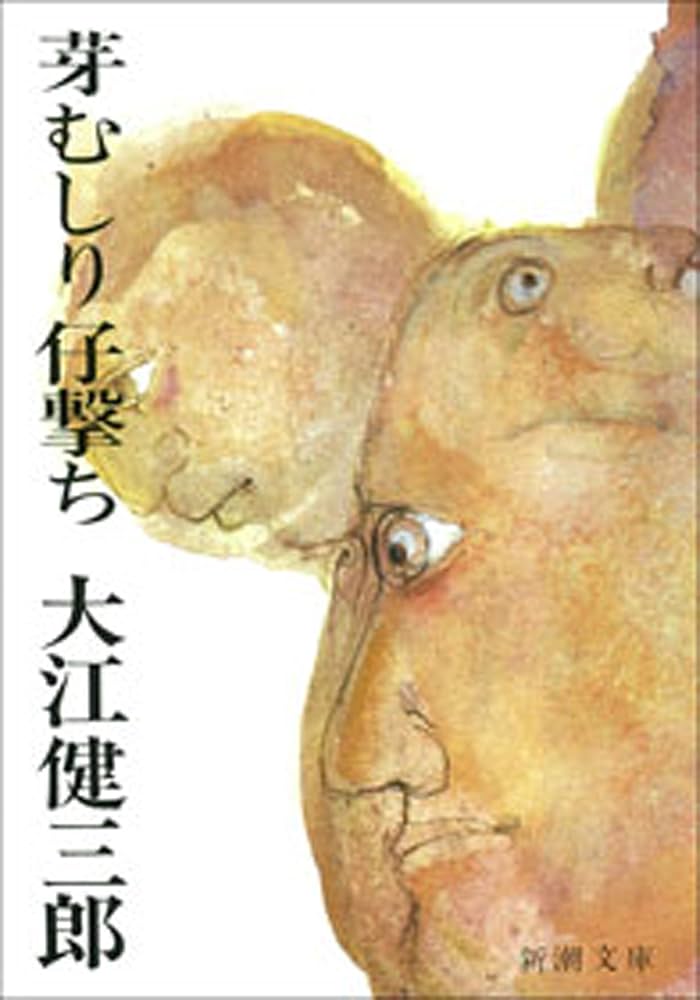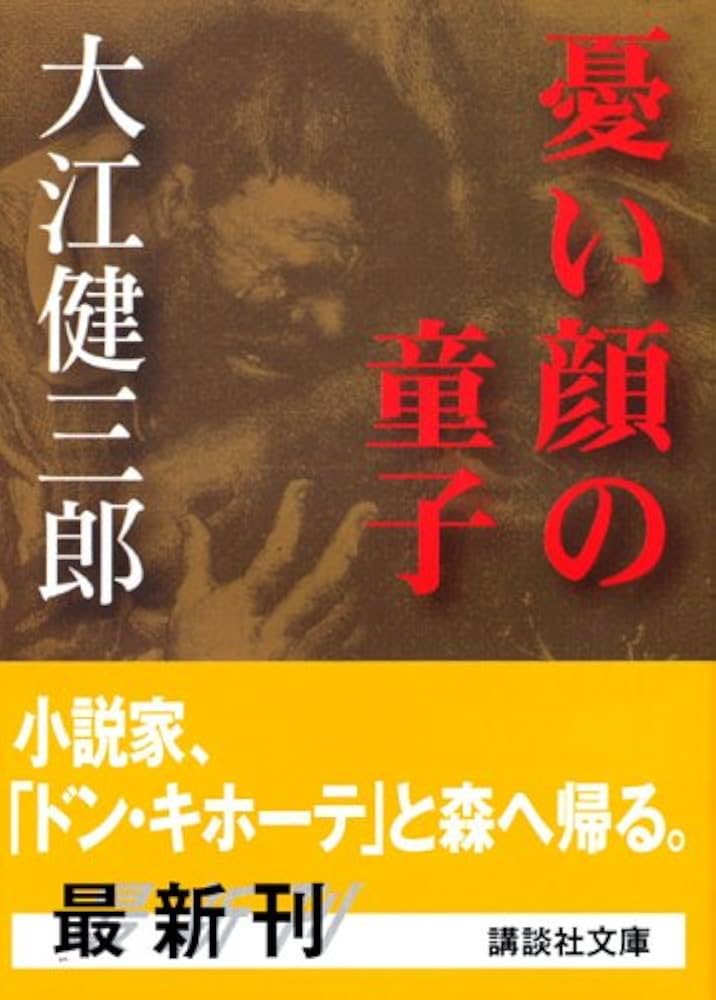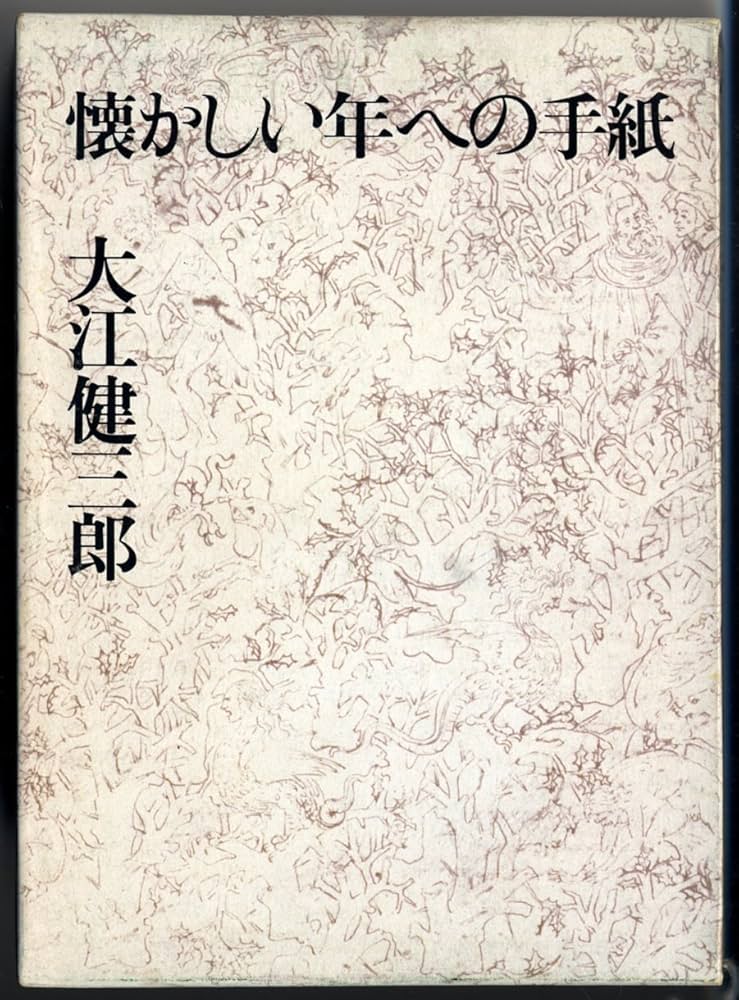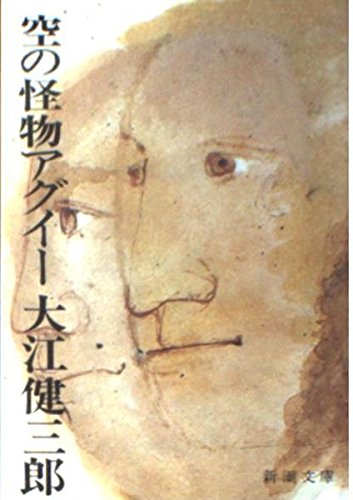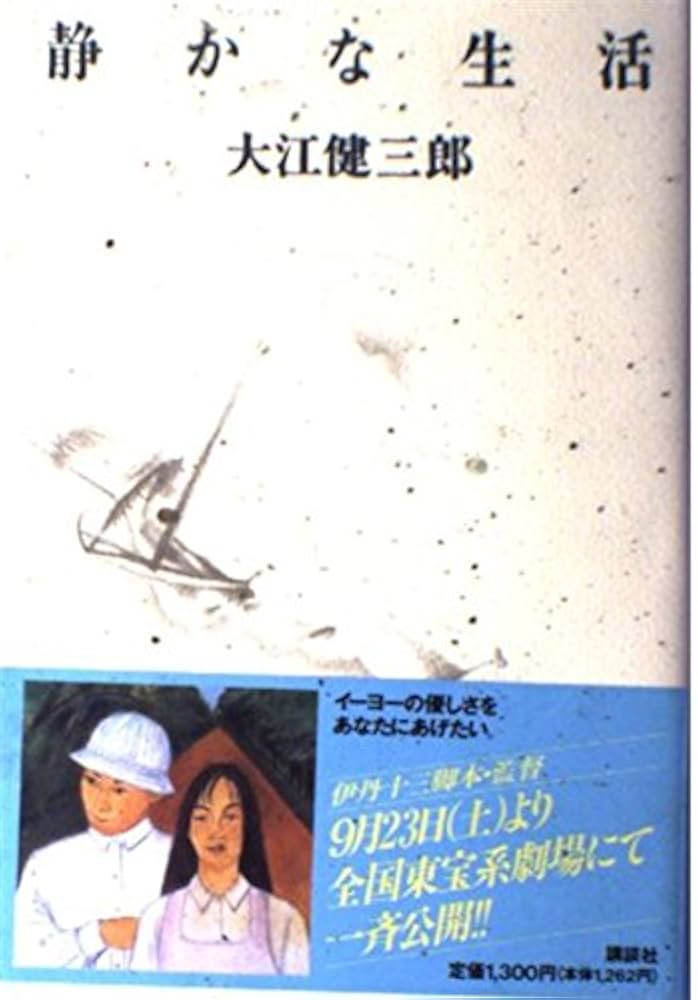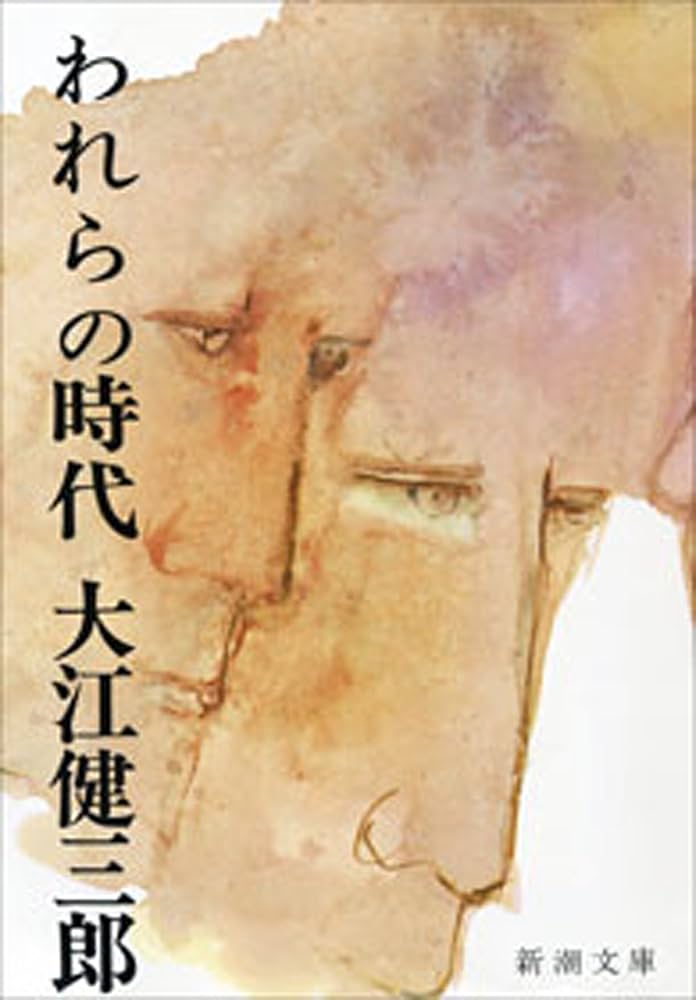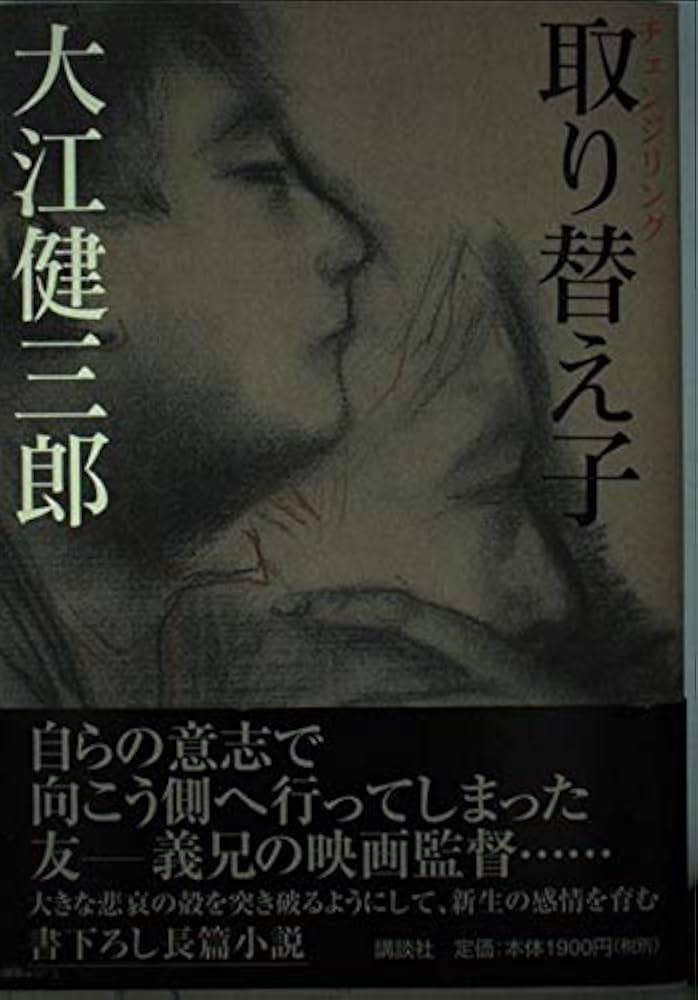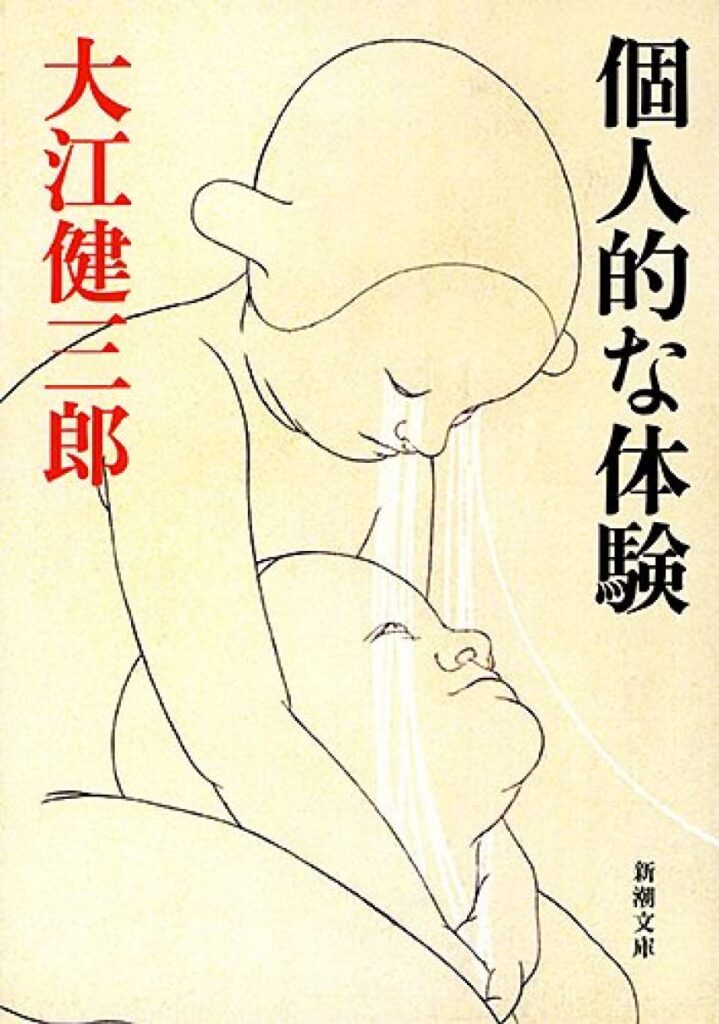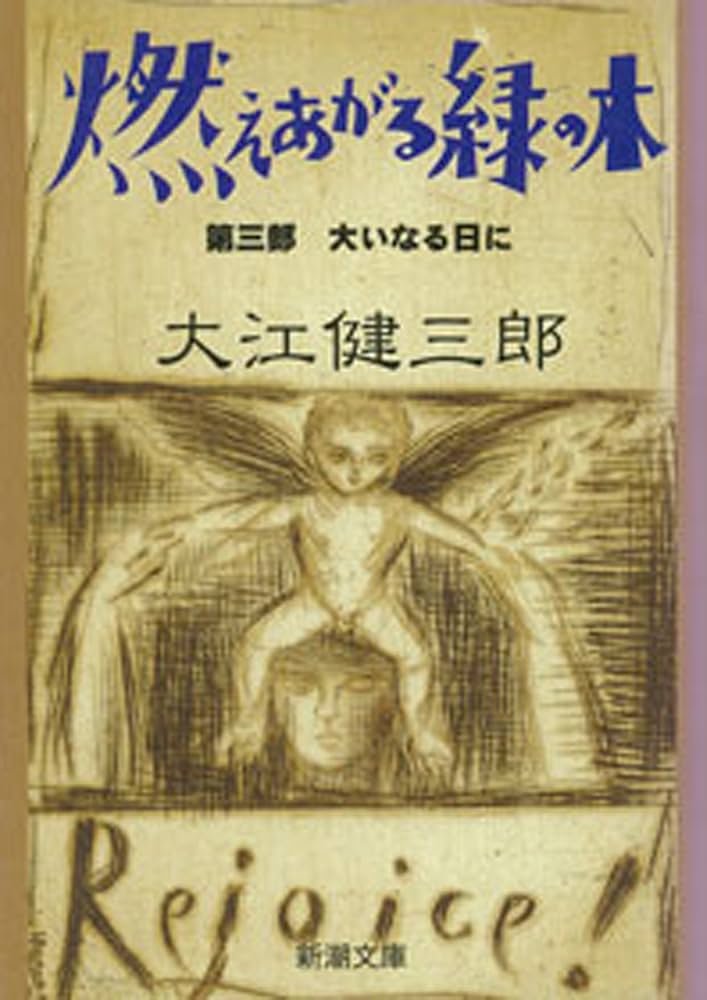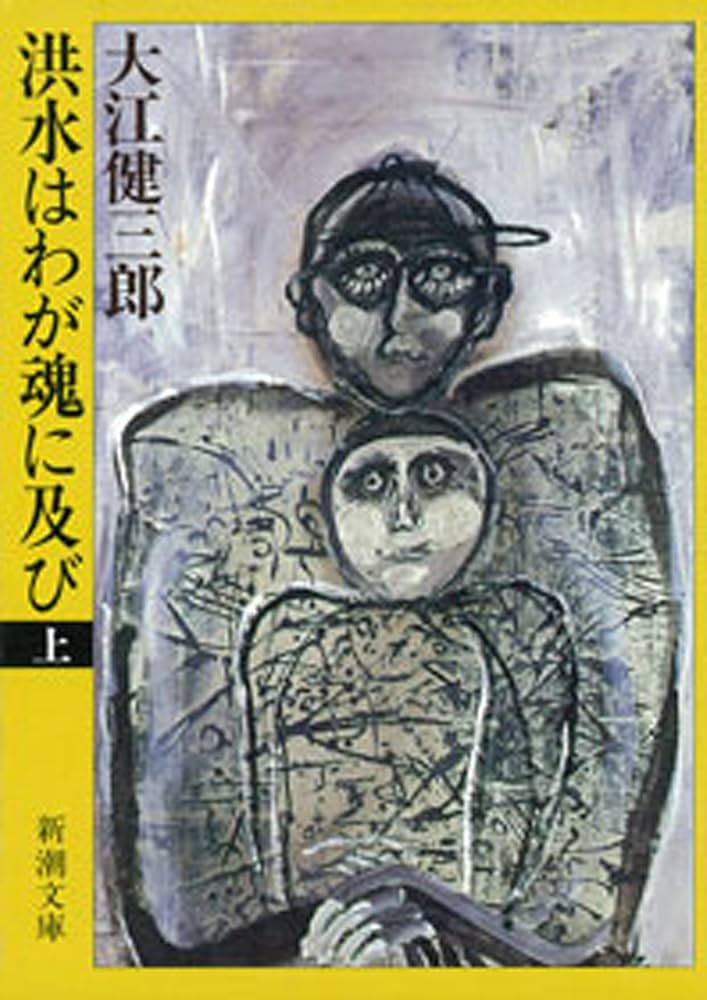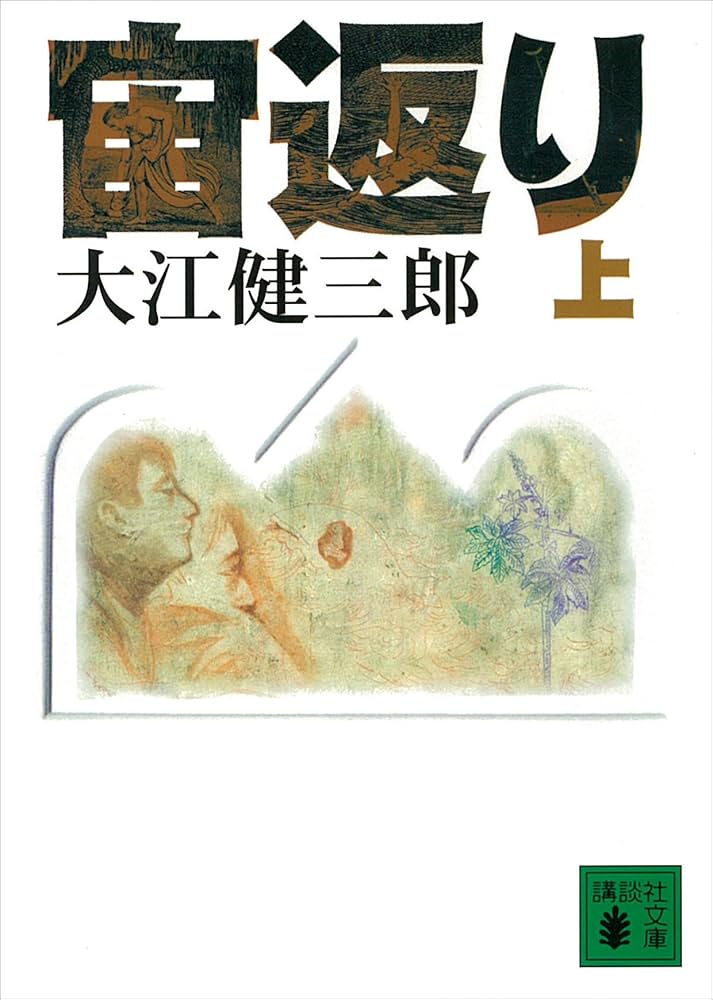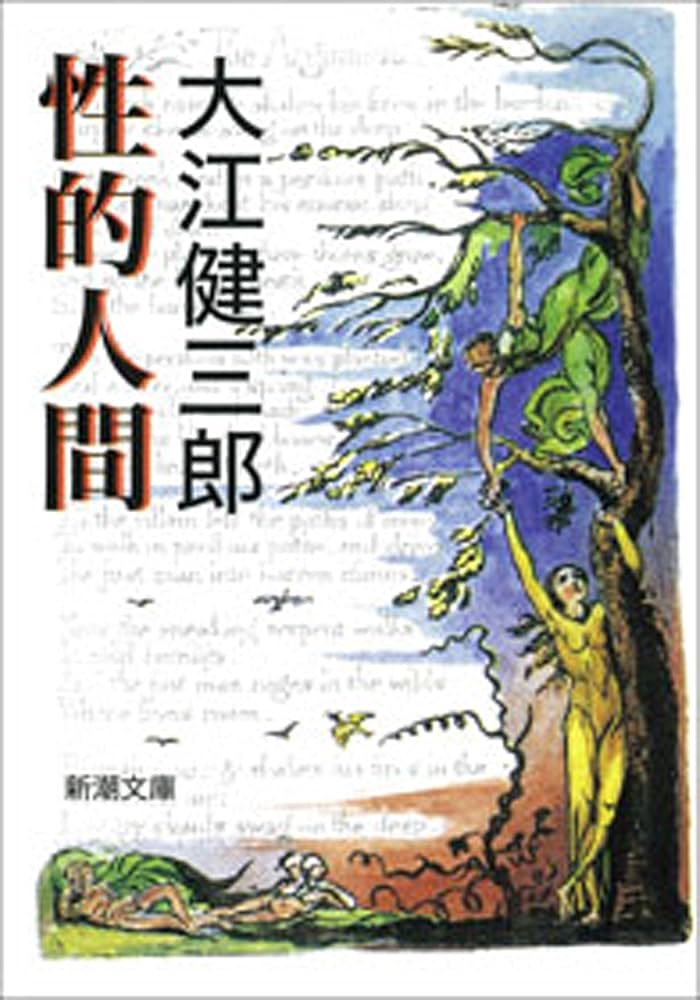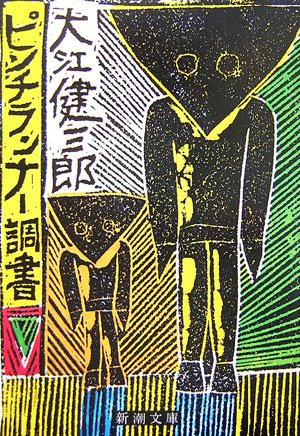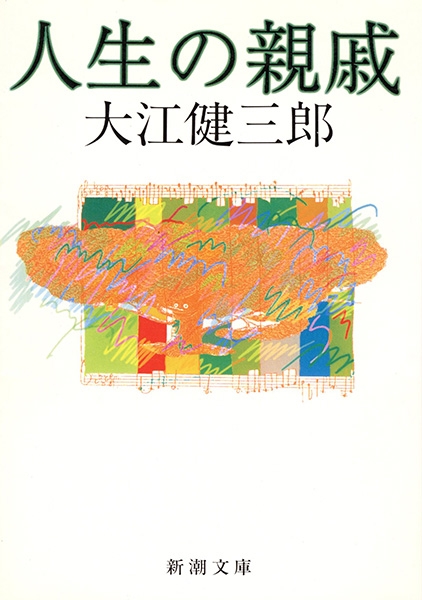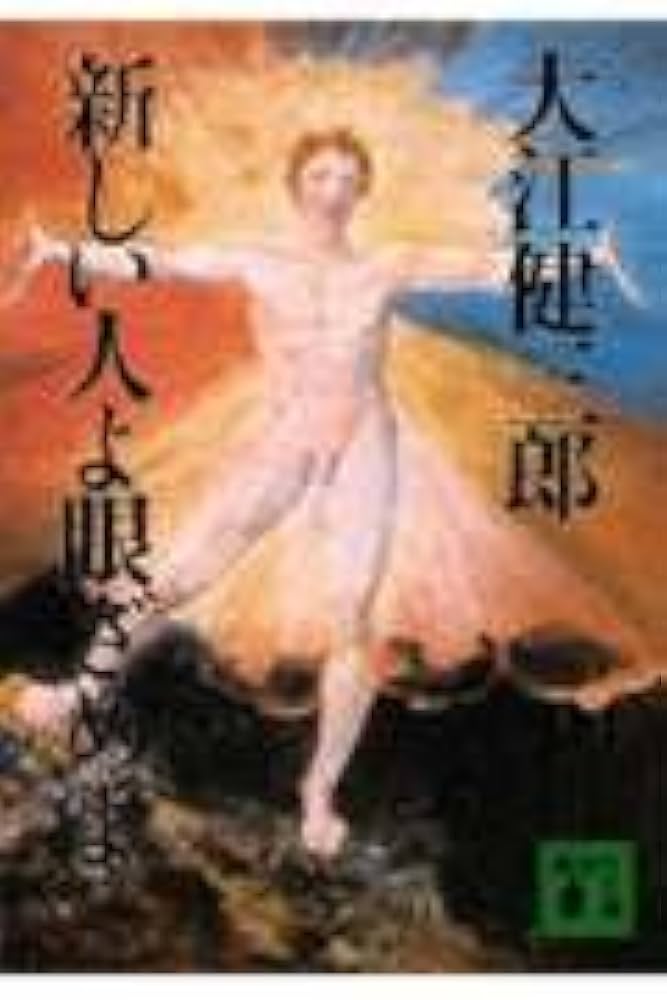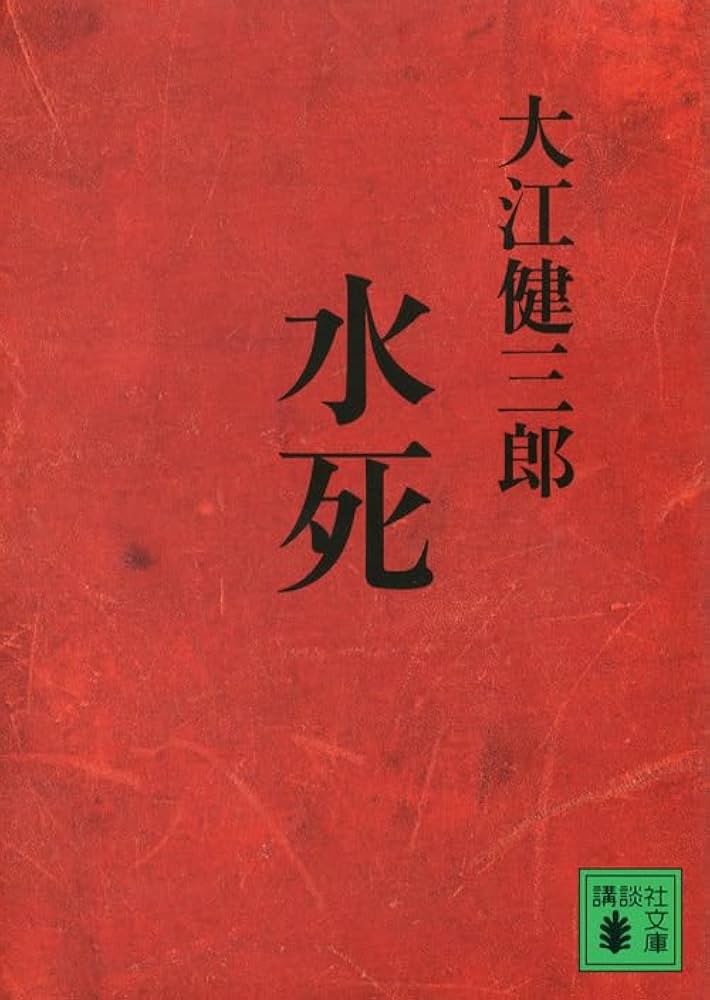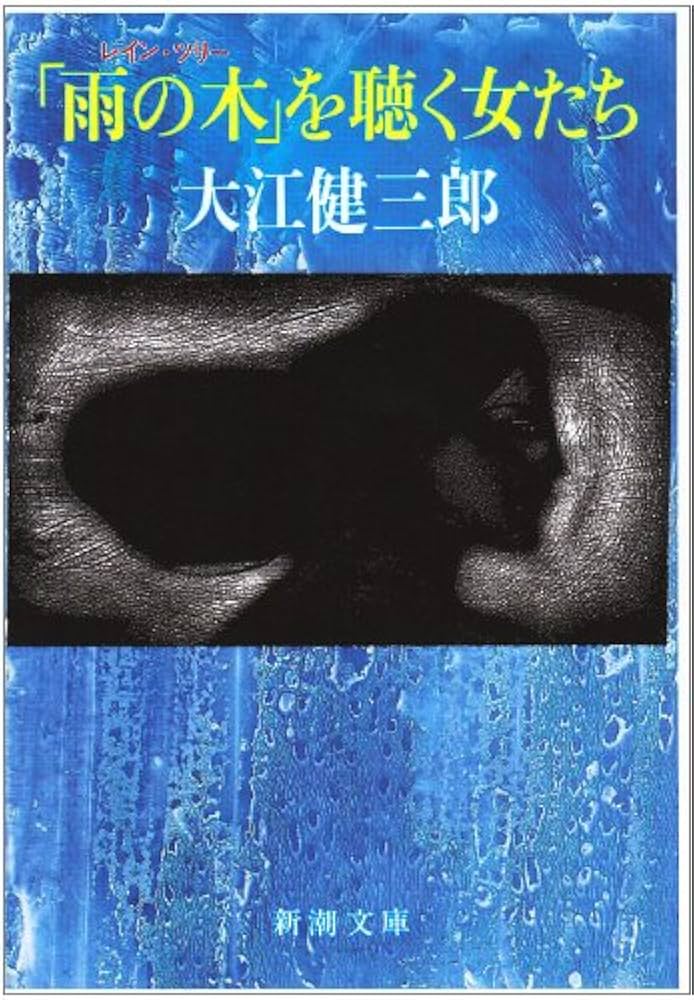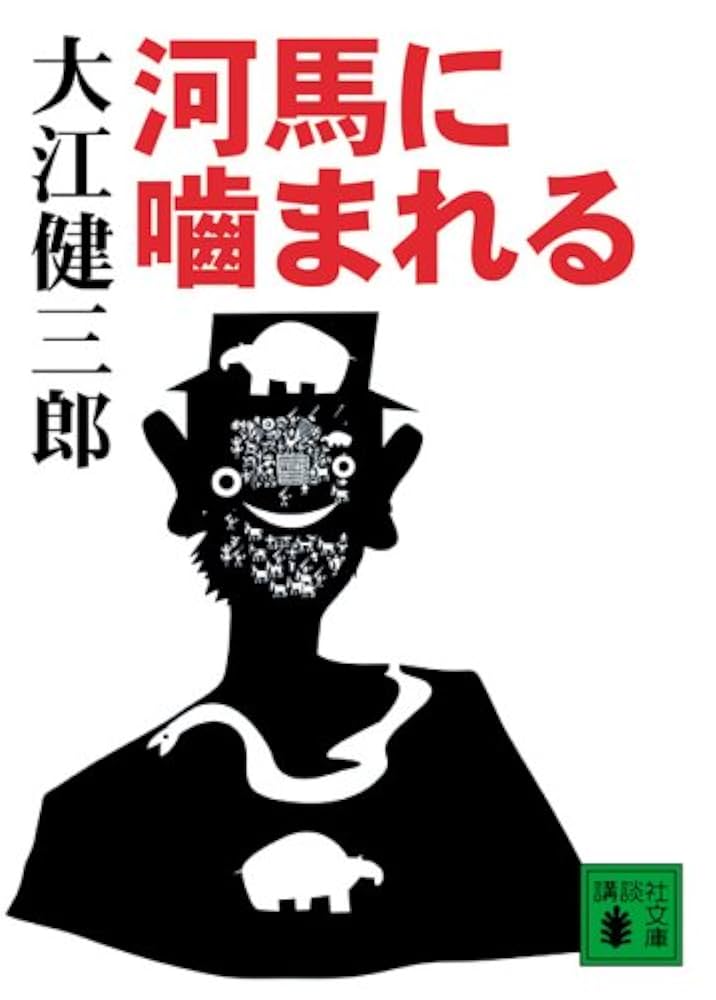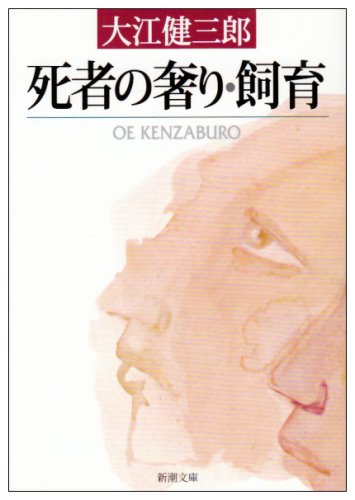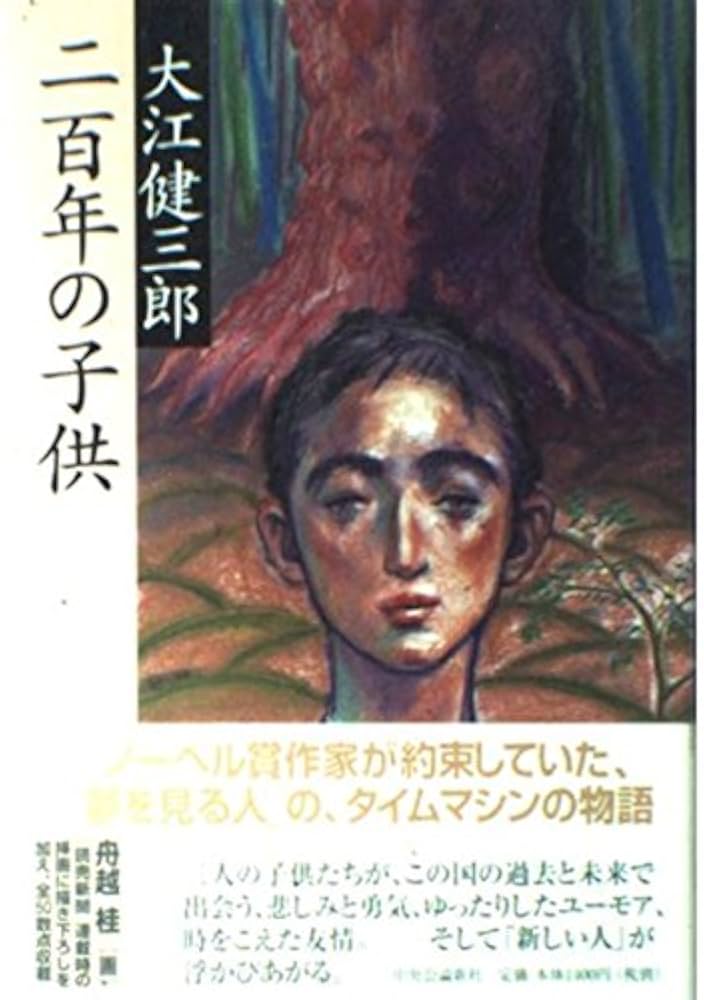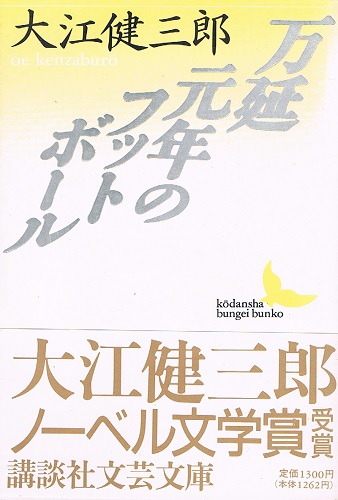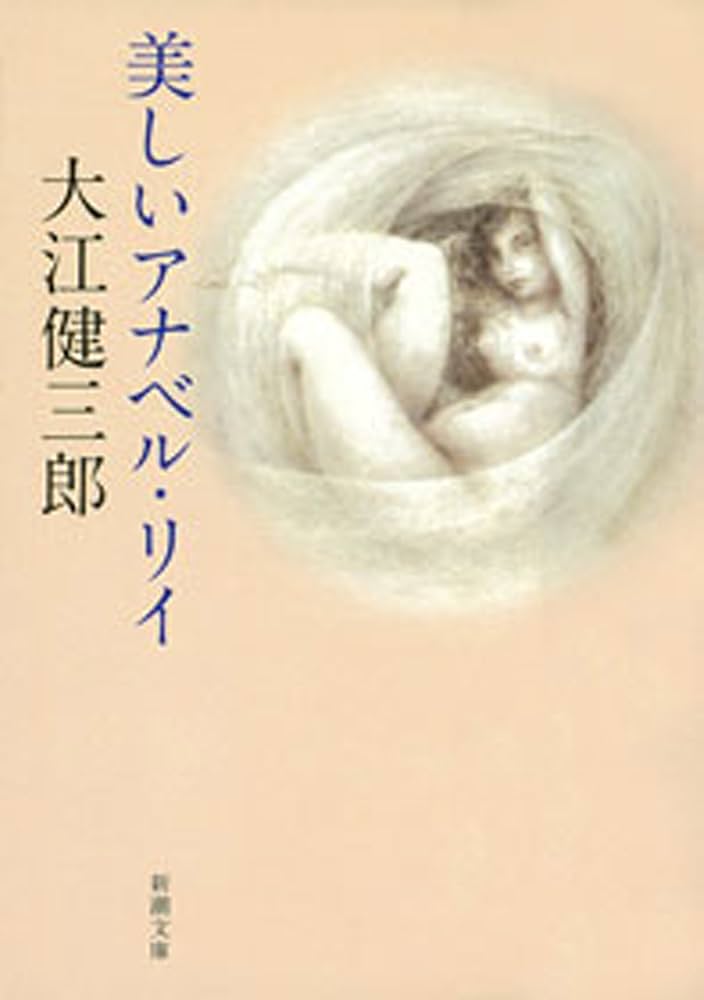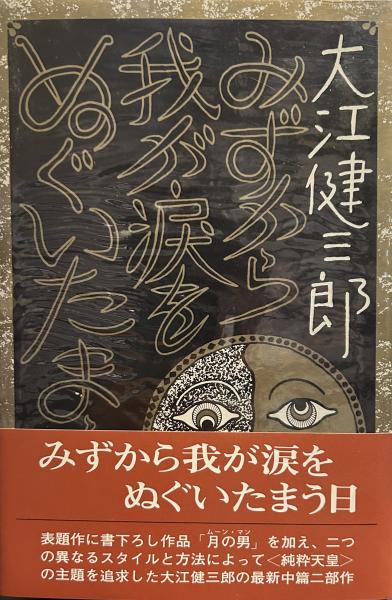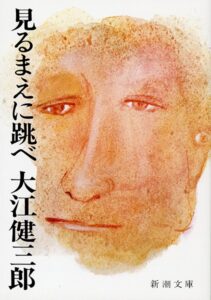 小説「見るまえに跳べ」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この作品は、大江健三郎さんの初期を代表する一作であり、1950年代の若者が抱える言いようのない閉塞感や、行動を起こすことへの渇望とためらいを見事に描き出しています。物語全体に漂うこの息苦しさは、現代を生きる私たちにも通じるものがあるのではないでしょうか。
小説「見るまえに跳べ」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この作品は、大江健三郎さんの初期を代表する一作であり、1950年代の若者が抱える言いようのない閉塞感や、行動を起こすことへの渇望とためらいを見事に描き出しています。物語全体に漂うこの息苦しさは、現代を生きる私たちにも通じるものがあるのではないでしょうか。
主人公である大学生の「ぼく」は、あらゆることから距離を置き、ただ「見る」だけの傍観者として日々を過ごしています。そんな彼が、ある外国人との出会いをきっかけに、自身の生き方を根底から問われることになるのです。タイトルでもある「見るまえに跳べ」という言葉は、彼の心に鋭く突き刺さります。この記事では、この『見るまえに跳べ』が持つ深い意味について、詳しく掘り下げていきたいと思います。
物語の結末に関わる重大なネタバレも含まれていますので、未読の方はご注意ください。しかし、結末を知った上で読むことで、より深く物語の構造やテーマ性を理解できる側面もあります。特に、主人公の青年がなぜ「跳ぶ」ことができなかったのか、その理由を知ることは、「見るまえに跳べ」という作品の本質に触れる上で欠かせない体験となるでしょう。
それでは、まずは物語の骨子から見ていきましょう。主人公の無気力な日常が、どのように揺さぶられ、そしてどのような結末を迎えるのか。大江健三郎さんが描き出した、一人の青年の魂の軌跡をたどります。
「見るまえに跳べ」のあらすじ
フランス文学を学ぶ大学生の「ぼく」は、かつて学生運動に参加したものの挫折した過去を持ち、政治的な活動から距離を置いていました。彼はあらゆる物事に対して傍観者でいることを選び、年上の娼婦である良重の部屋に住み、無気力で屈折した毎日を送っています。彼の生活は、現実から目をそらし、ただ「見る」ことに徹しているかのようでした。
そんな彼の前に、良重の客であるフランス人ジャーナリストのガブリエルが現れます。ガブリエルは「ぼく」にとって圧倒的な強者であり、彼の存在は戦後の日本人としての屈辱的な立場を意識させます。「ぼく」は対抗心から「平和にはあきあきしている」「ベトナムで戦いたい」と虚勢を張りますが、ガブリエルはそれを見抜いていました。
ある日、ガブリエルは「ぼく」をベトナムへ特派員として連れて行ってやると提案します。突然の申し出にうろたえ、尻込みする「ぼく」に対し、ガブリエルはオーデンの詩の一節を引用し、「見たけりゃ見なさい、けれどもあんたは跳ばなきゃいけない」と言い放ちます。 この言葉は、行動を起こさず傍観するだけの「ぼく」の生き方を痛烈に批判するものでした。
その後、「ぼく」は芸術大学を目指す受験生の田川裕子と出会い、無料でフランス語を教えるようになります。裕子との純粋な関係は彼の生活に光をもたらし、やがて二人は恋に落ち、彼女は「ぼく」の子どもを妊娠します。 「父」になるという実感は、彼に生きる希望を与え、世界との新しい関わり方を予感させました。 しかし、その希望は残酷な運命によって打ち砕かれることになります。
「見るまえに跳べ」の長文感想(ネタバレあり)
この物語の核心は、題名にもなっている「見る」ことと「跳ぶ」ことの対立にあります。主人公の「ぼく」は、まさに行動を起こす前に延々と「見て」しまう青年として描かれています。彼は学生運動に挫折して以来、現実の出来事に関わることを避け、安全な場所から世界を眺める傍観者となりました。彼の態度は、単なる無気力という言葉だけでは片付けられない、根深い屈辱感と自己欺瞞に根差しています。
その彼の前に現れるのが、フランス人のガブリエルです。彼は「ぼく」とは対照的に、世界を股にかけ、行動し、そして「跳ぶ」側の人間として描かれます。ガブリエルが「ぼく」に投げかける「見たけりゃ見なさい、けれどもあんたは跳ばなきゃいけない」という言葉は、この小説のテーマを凝縮した一撃です。 見てばかりで決して行動しない生き方を、容赦なく断罪するのです。
ガブリエルはさらに、朝鮮戦争の際に日本人が米兵に侮辱されても、ただ黙って見ていただけだったと語り、「ぼく」を含む日本人全体の臆病さを侮辱します。 この侮辱に激昂した「ぼく」は、初めて衝動的な行動に出ます。ガブリエルを背後から殴りつけるのです。これは小さく、そして卑劣な一撃かもしれませんが、彼が初めて「見た」後に「跳んだ」瞬間であったと言えるかもしれません。
しかし、この物語の本当の転換点は、田川裕子との出会いです。彼女との関係は、「ぼく」にとって初めての、現実への積極的な関わりでした。裕子を愛し、彼女が自分の子どもを身ごもったと知った時、「ぼく」は人生で初めて、傍観者ではない「当事者」としての未来を夢見ます。父親になるということ、新しい生活を築くということ。それは、彼にとって最大の「跳躍」となるはずでした。
ここから物語は、最も重要なネタバレの領域へと入っていきます。この希望に満ちた跳躍の予感こそが、この小説における最大の皮肉であり、悲劇の始まりなのです。満員電車の中で、汗臭い人々に「力づよい連帯」すら感じた「ぼく」の希望は、しかし、あまりにも残酷な現実の前に脆くも崩れ去ります。
裕子が結核菌を持っており、出産すれば彼女自身の命が危ういという事実が判明するのです。 この宣告は、「ぼく」から跳躍するための足場そのものを奪い去りました。彼らが選んだのは、子どもを諦める、つまり堕胎するという決断でした。未来への希望そのものであった子どもを失ったことで、二人の関係もまた、「感動もなく別れ」を迎えます。
この結末は、非常に重い意味を持っています。なぜなら、「ぼく」は自らの意志で跳ぶことをやめたのではなく、「跳ぶ」こと自体が不可能であるという現実を突きつけられたからです。彼は行動しようとしました。父親になり、責任を負い、人生の当事者として生きようと決意したのです。しかし、運命はそれを許しませんでした。この痛烈な挫折は、彼の心を完全に折ってしまいます。
全てを失った「ぼく」が最終的に戻る場所は、娼婦である良重の部屋です。物語の中で、彼女の部屋は暗い坂の奥にある、生垣に囲まれた場所として描かれています。 それはまるで、安全で閉鎖的な子宮への回帰を象徴しているかのようです。裕子との関係で一度は「父」になろうとした彼は、結局その役割を果たせず、再び良重という「母」の保護下にある「子ども」へと逆戻りするのです。
物語の最後で、彼は「これからも決して跳ぶことはないだろう」と悟ります。 一度の跳躍の試みがもたらしたあまりにも大きな痛みは、彼から再び跳ぼうとする意志を永遠に奪い去りました。これは、単なる個人の挫折物語ではありません。戦後の日本が抱えていた、どうにもならない閉塞感や無力感そのものを体現しているかのようです。
『見るまえに跳べ』が投げかける問いは、現代においても有効です。私たちは情報を「見る」ことは得意になりました。しかし、リスクを恐れ、失敗を怖がり、なかなか「跳ぶ」ことができません。この小説は、そんな私たちの姿を映し出す鏡のような作品なのかもしれません。
主人公の選択、あるいは選択の余地のなかった結末は、重苦しい読後感を残します。彼はなぜ跳べなかったのか。それは彼の臆病さだけのせいだったのでしょうか。それとも、彼を取り巻く「状況」が、そもそも跳躍を許さないほど過酷だったのでしょうか。この問いへの答えは、簡単には出せません。
この物語における重要なネタバレは、主人公が「跳ぼうとした」という事実、そしてその試みが外的な要因によって無残に打ち砕かれたという点にあります。彼はただの傍観者でいることに安住していたわけではなく、一度は本気で人生の当事者になろうとしたのです。その希望が大きかった分、挫折の絶望もまた深くなります。
『見るまえに跳べ』は、若者の挫折と停滞を描いていますが、そこには常に「政治と性」という大江文学の初期から見られるテーマが色濃く反映されています。 ガブリエルとの対立は政治的・国際的な屈辱を、裕子との関係は個人的な生の希望と挫折を象徴しており、この二つが複雑に絡み合いながら物語を動かしていきます。
良重と裕子という二人の女性の対比も鮮やかです。良重が過去や停滞、母性的な保護を象徴する一方で、裕子は未来や希望、そして新しい家族の創造を象徴しています。主人公が最終的に良重の元へ帰るという結末は、彼が未来へ向かうことを断念し、過去へと退行していく姿を明確に示しています。
この小説の文体も、主人公の内面の屈折を表現する上で重要な役割を果たしています。観念的で、ややもすれば粘着質ともいえる文体が、行動に移れない青年の鬱屈した思考を的確に描き出しています。読み手は彼の思考の迷路に引き込まれ、同じような閉塞感を追体験することになるでしょう。
『見るまえに跳べ』は、読者に安易な希望を与えてはくれません。むしろ、行動しようとすることの困難さと、それに伴う痛みを突きつけてきます。しかし、それでもなお、この物語が多くの読者を惹きつけるのは、そこに描かれている葛藤が、時代を超えて普遍的なものだからではないでしょうか。
最後に、この物語の結末、つまり堕胎という悲劇的なネタバレについてもう一度触れたいと思います。この出来事は、単に「子どもを失った」という事実以上の意味を持っています。それは「未来を築く」という行為そのものの挫折であり、「跳ぶ」というメタファーの完全な崩壊を意味します。だからこそ、「ぼく」は二度と跳ぶ気力を取り戻せなかったのです。
『見るまえに跳べ』は、まさに青春の痛みを凝縮したような一作です。希望と絶望、行動と停滞、そして生と死の狭間で揺れ動く青年の姿は、読む者の心に深く刻み込まれます。一度は跳ぼうとして、地面に叩きつけられた彼の痛みを通して、私たちは自らの人生における「跳躍」の意味を、改めて考えさせられるのです。
まとめ:「見るまえに跳べ」のあらすじ・ネタバレ・長文感想
この記事では、大江健三郎さんの小説『見るまえに跳べ』について、あらすじから結末のネタバレを含む詳細な感想までを綴ってきました。本作は、行動を起こせずに傍観者として生きる青年の内面を深くえぐり出し、「見る」ことと「跳ぶ」ことの相克という普遍的なテーマを描き出した物語です。
主人公「ぼく」は、無気力な日常を送る中で、外国人ガブリエルから行動しない生き方を痛烈に批判されます。その後、恋人・裕子の妊娠を機に、父親として人生を「跳躍」する希望を見出しますが、残酷な運命によってその希望は打ち砕かれます。この挫折が、彼の心を決定的に折ってしまうのです。
物語の結末で、全てを失った主人公は再び無気力な日常へと回帰します。一度は跳ぼうとしたからこそ味わった絶望の深さが、彼から未来への意志を奪い去りました。この悲劇的な結末は、単なる個人の物語にとどまらず、時代の抱える閉塞感をも象徴しているように感じられます。
『見るまえに跳べ』は、読む者に重い問いを投げかける作品です。しかし、そこに描かれた葛藤と痛みは、時代を超えて私たちの心に響きます。行動することの困難さと、それでもなお捨てきれない希望について、深く考えさせられる一冊と言えるでしょう。