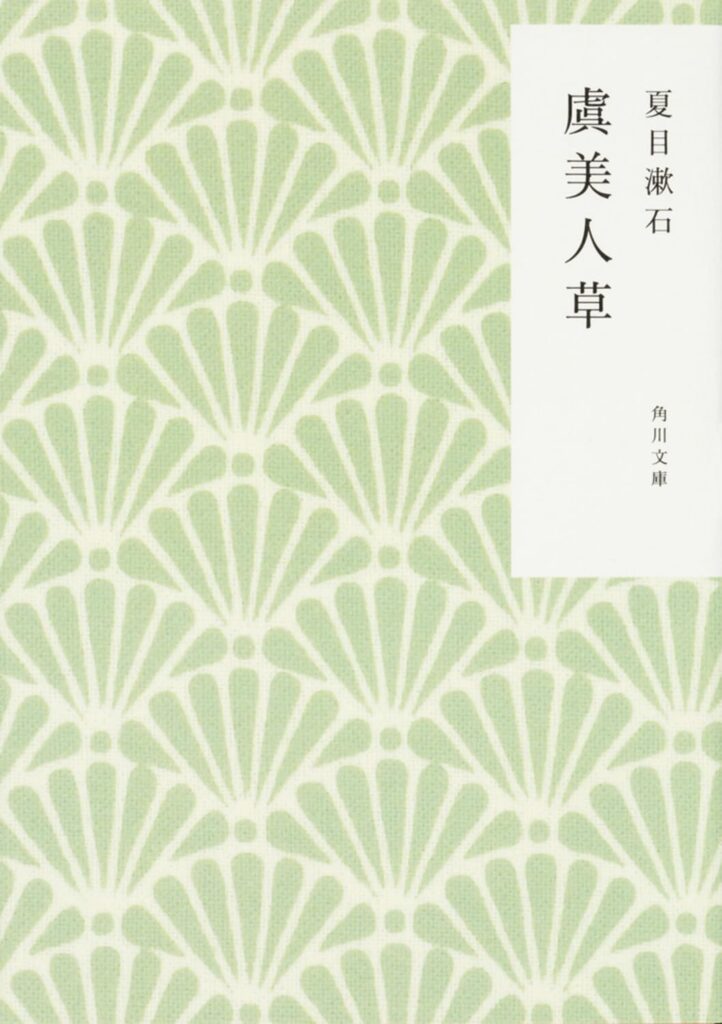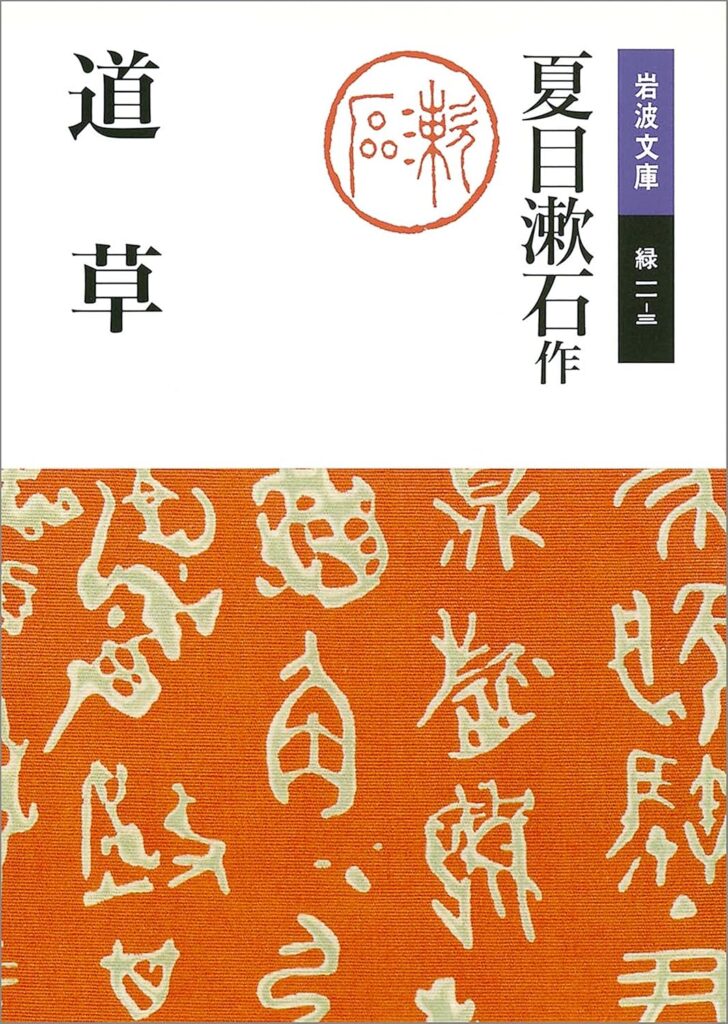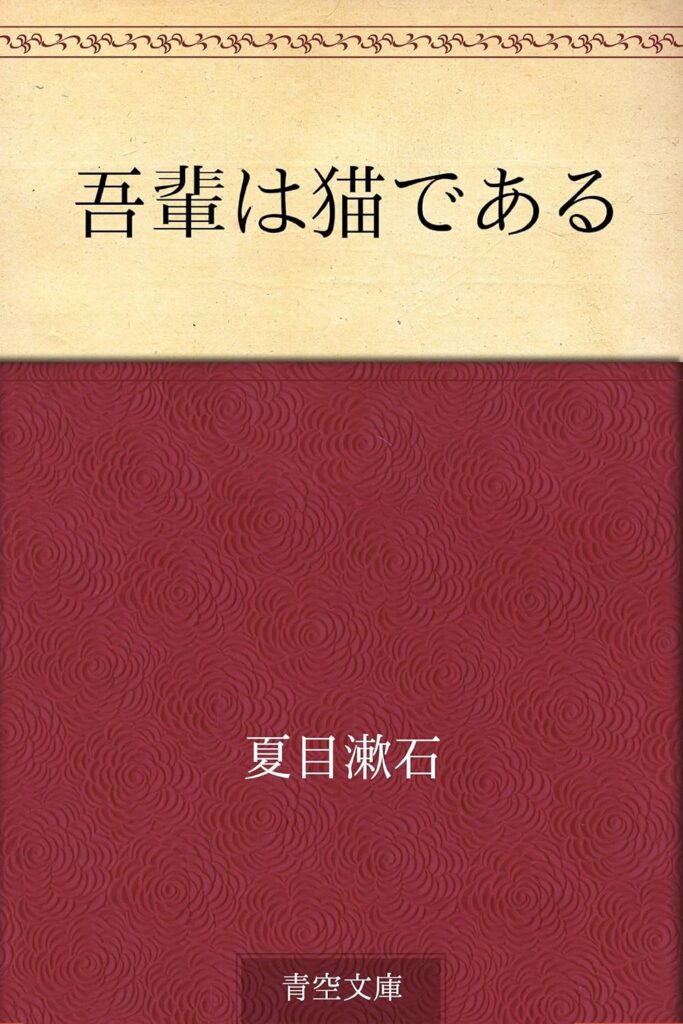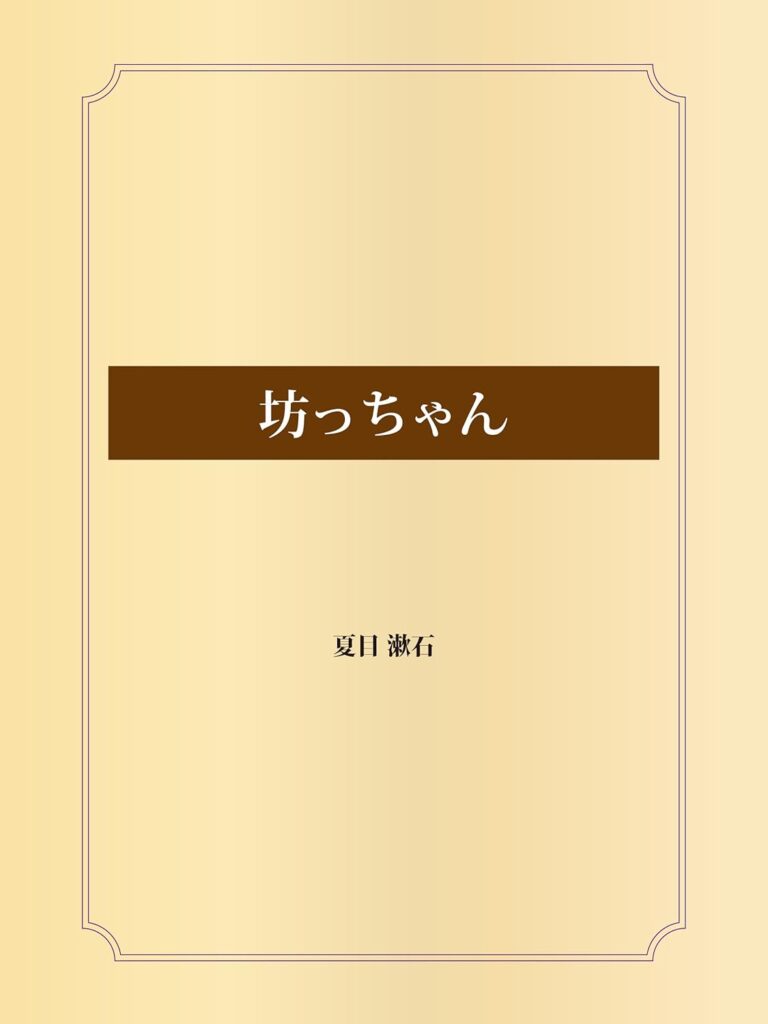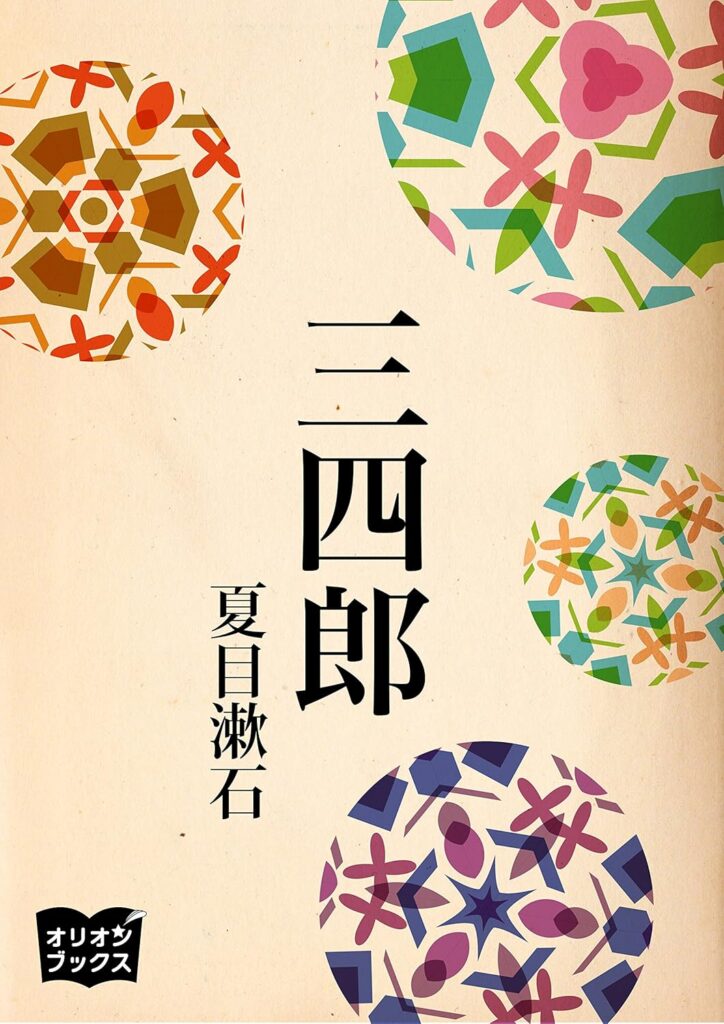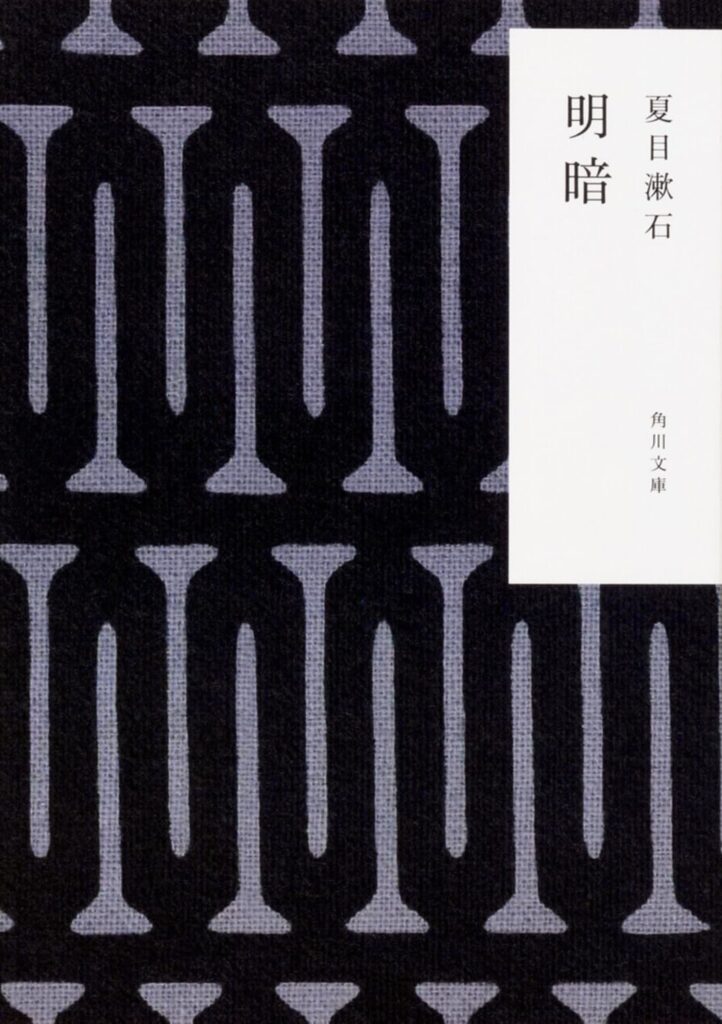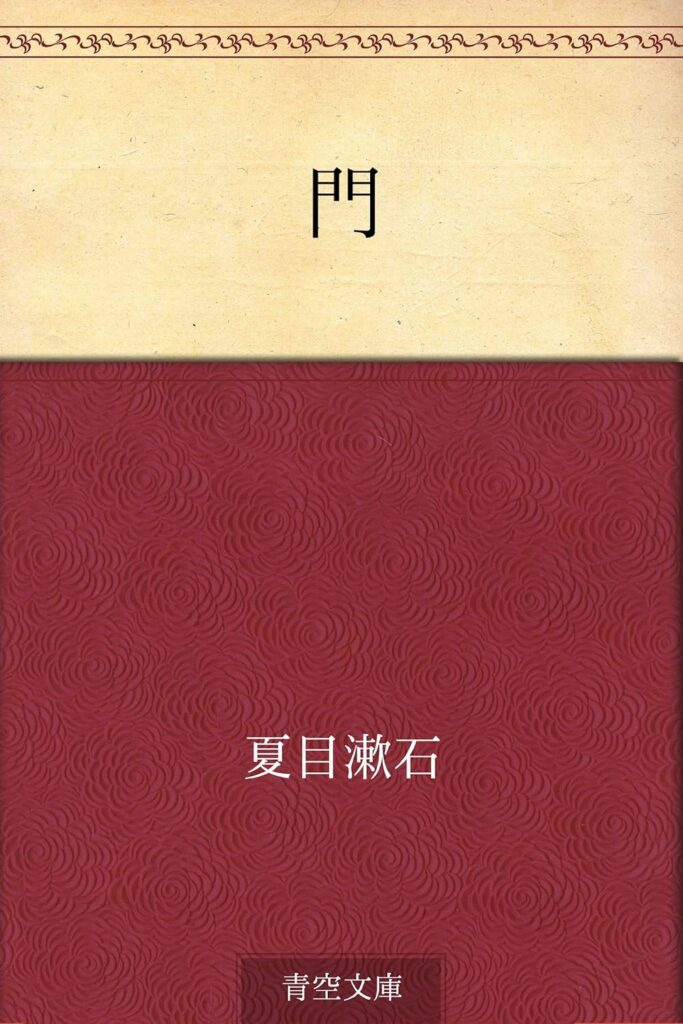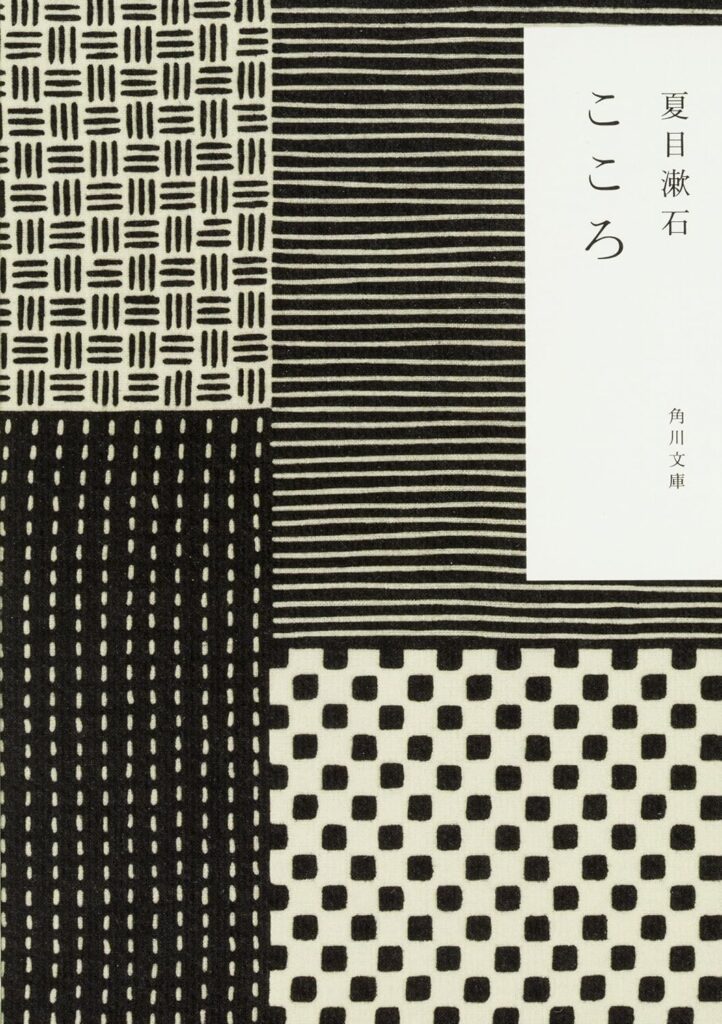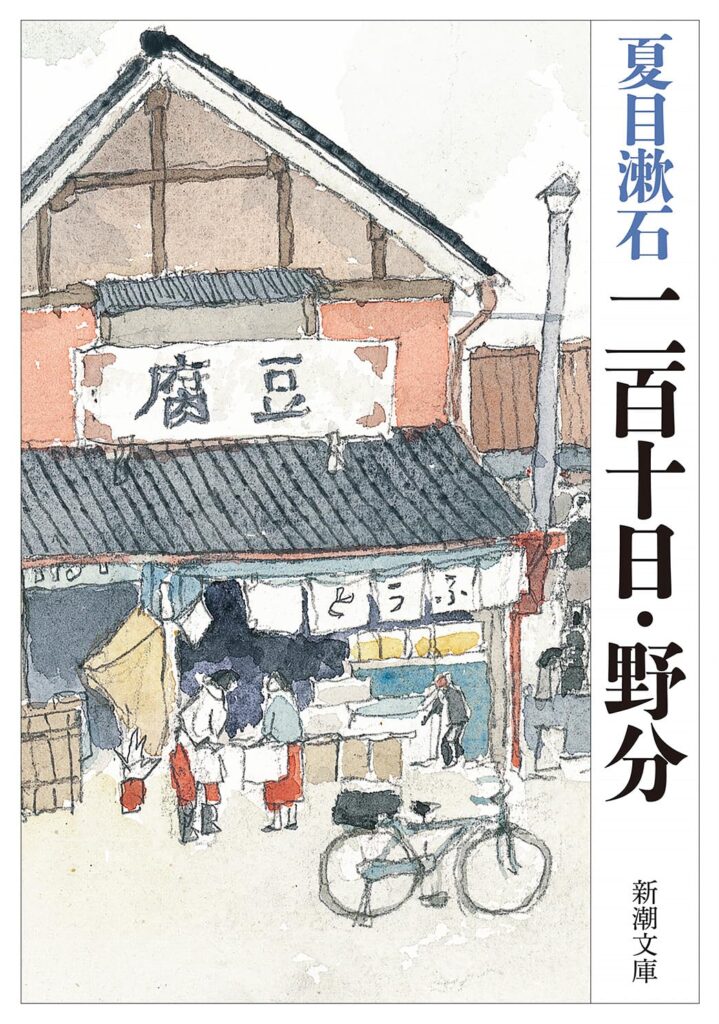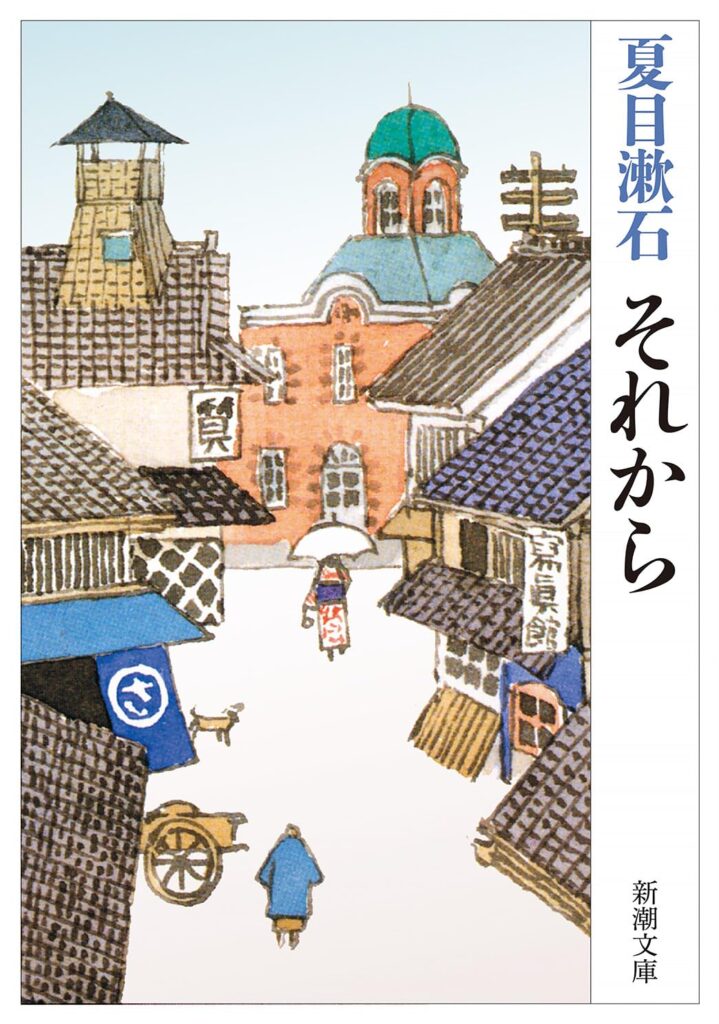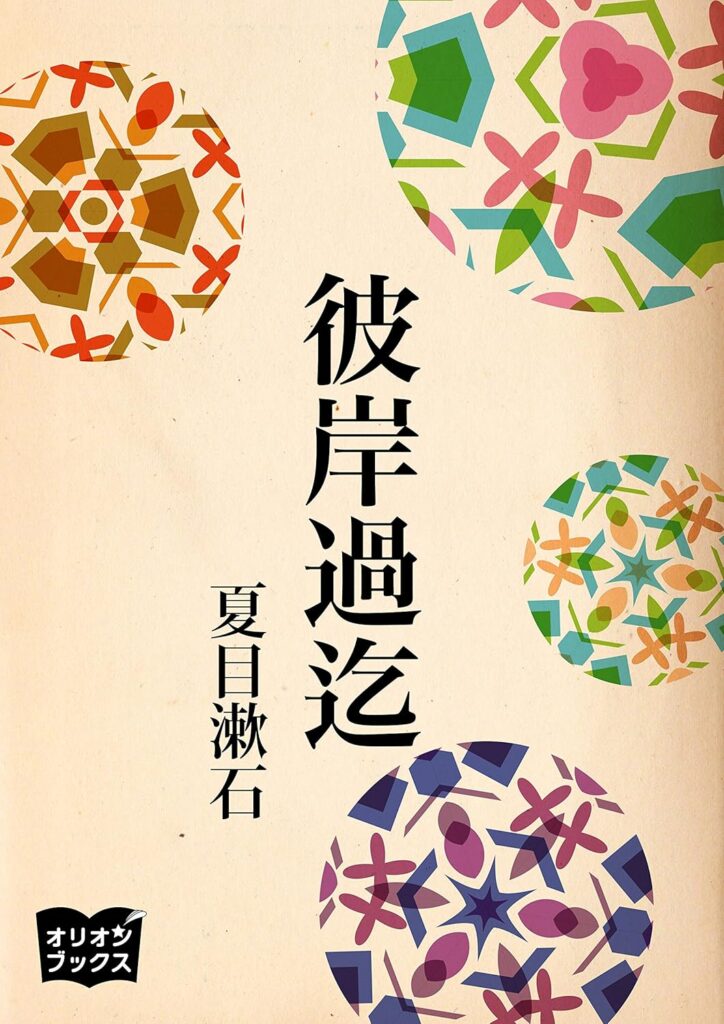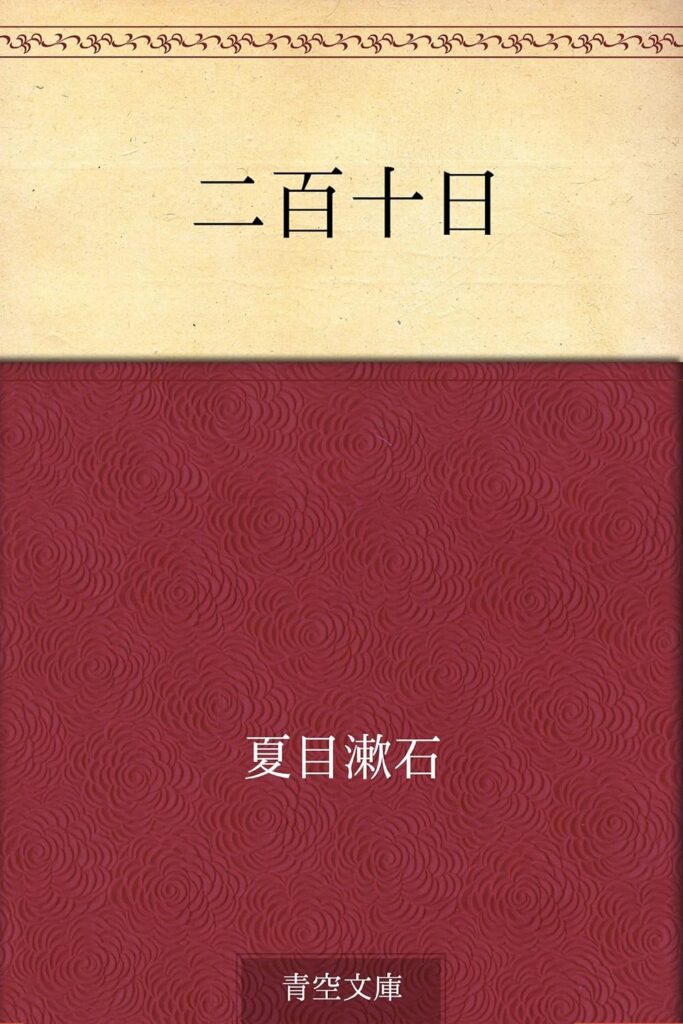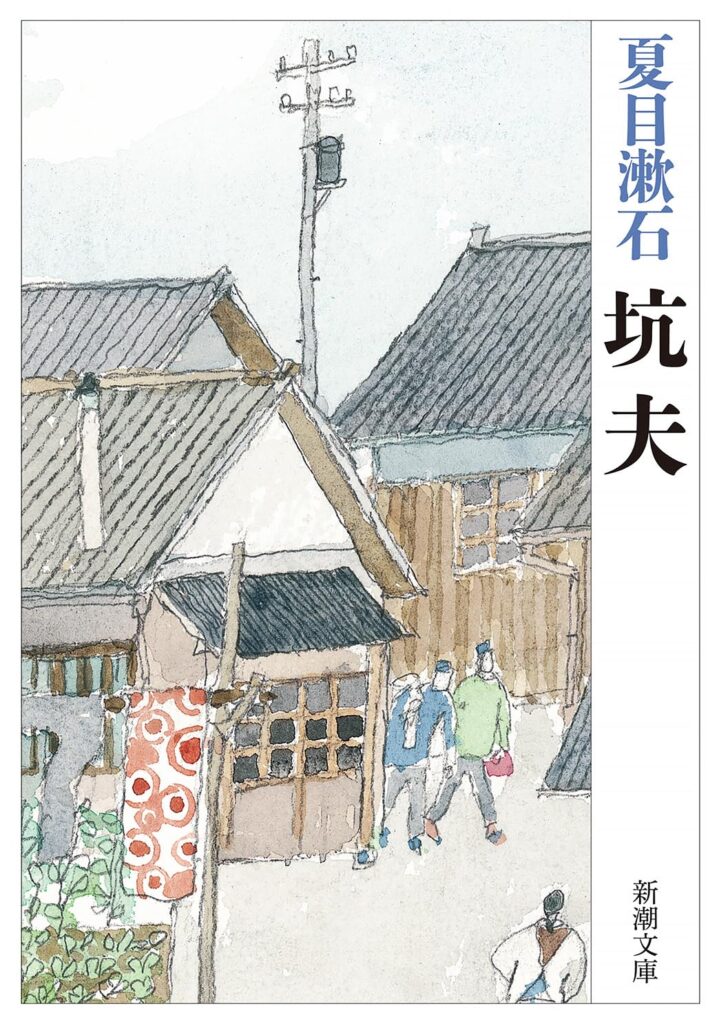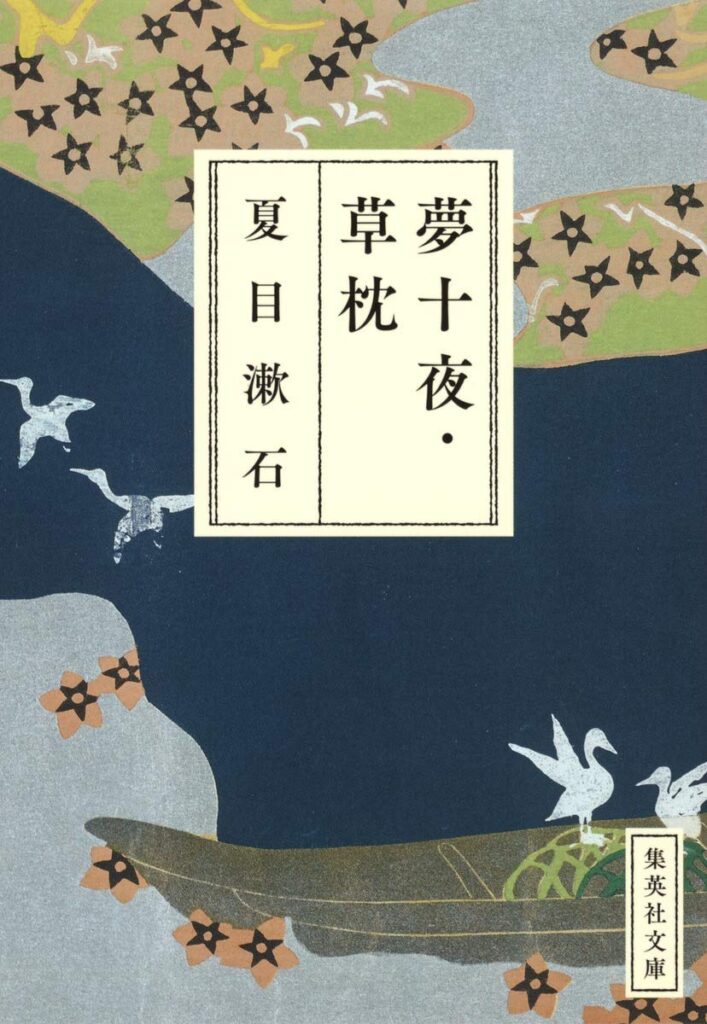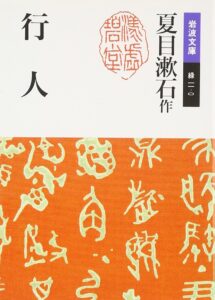 小説「行人」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。夏目漱石の後期三部作の一つに数えられるこの作品は、人間の内面に深く分け入り、近代知識人の抱える苦悩や孤独、そして複雑な人間関係を描き出しています。
小説「行人」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。夏目漱石の後期三部作の一つに数えられるこの作品は、人間の内面に深く分け入り、近代知識人の抱える苦悩や孤独、そして複雑な人間関係を描き出しています。
物語の中心にいるのは、主人公・二郎の兄である一郎です。彼は大学で教鞭をとる知識人でありながら、妻の直を信じることができず、絶えず疑念と不安に苛まれています。その苦しみは、彼自身だけでなく、妻、弟、そして周囲の人々をも巻き込んでいきます。
本作は「友達」「兄」「帰ってから」「塵労」という四つの編から構成されており、それぞれの編で視点や舞台を変えながら、一郎の苦悩の深層と、それを取り巻く人々の姿が少しずつ明らかになっていきます。大阪、和歌山、東京、箱根と、旅の要素が多いのも特徴で、移動していく中で登場人物たちの心理も揺れ動いていく様子が描かれています。
この記事では、まず物語全体の流れを追い、その後、登場人物たちの心情や関係性、作品が問いかけるテーマについて、私なりの読み解きを詳しく述べていきたいと思います。結末に至るまでの重要な展開にも触れていきますので、まだ作品を読んでいない方はご注意くださいね。
小説「行人」のあらすじ
物語は、主人公である長野二郎が、友人・三沢との約束や家の用事で大阪へ向かうところから始まります。「友達」編では、大阪で二郎が出会う人々との交流が描かれます。家の元食客である岡田夫妻の世話になりながら、下女・貞の縁談相手である佐野と面会したり、体調を崩して入院した友人・三沢を見舞ったりします。三沢が入院する病院で出会った、同じく胃腸を病む「あの女」とのエピソードは、後の展開にも影を落とします。三沢は、かつて自分が精神を病ませてしまった娘と「あの女」を重ね、見舞金を渡して退院していきます。
続く「兄」編では、二郎の母、兄の一郎、兄嫁の直が大阪へやってきます。一家は岡田夫妻のもてなしを受け、その後和歌山へと旅行に出かけます。しかし、旅先で一郎は弟の二郎に対し、妻・直が二郎に好意を寄せているのではないかという疑念を口にし、さらに直の貞節を試すために二人きりで一晩過ごすよう頼むという、異常な行動に出ます。二郎は困惑しつつも兄の頼みを断り切れず、直と二人で出かけますが、嵐に見舞われ、結果的に一晩を共に過ごすことになってしまいます。この出来事は、兄弟、そして夫婦の関係に深い亀裂を生じさせます。
「帰ってから」編では、東京に戻った長野家の日常が描かれます。和歌山での出来事について話そうとしない二郎に対し、一郎は激昂。二郎は家に居づらくなり、下宿生活を始めます。一方で、家の奉公人であった貞と佐野の結婚式が執り行われますが、一郎と直の関係はますます悪化していく様子がうかがえます。一郎は精神的に不安定な状態に陥り、家族は彼の身を案じ始めます。
最後の「塵労」編では、一郎の苦悩がいよいよ深刻化します。見かねた家族は、一郎の親友であるHに頼み、一郎を旅行に連れ出してもらうことにします。旅行先からHが二郎に宛てて送った長い手紙には、一郎が抱える深い孤独、人間存在への懐疑、そして宗教的な救済への渇望などが赤裸々に綴られていました。一郎はHに対し、「死か、気が違うか、宗教に入るか、この三つしか道はない」とまで語ります。Hは、一郎を単なる気難しい人物として片付けるのではなく、彼の苦悩を理解し、寄り添うことの重要性を二郎に説くのでした。物語は、このHの手紙によって締めくくられます。
小説「行人」の長文感想(ネタバレあり)
夏目漱石の後期三部作、その真ん中に位置する「行人」を読み終えて、ずしりと重いものが心に残りました。知識人の苦悩、夫婦関係の破綻、家族という共同体の揺らぎ、そして近代における個人の孤独。これらのテーマが、一郎という一人の男の姿を通して、実に克明に、そして容赦なく描かれているように感じます。
まず、何と言っても中心人物である一郎の存在感が際立っています。彼は大学で教鞭をとるインテリでありながら、妻の直に対する不信感に絶えず苛まれています。彼の苦悩は、単なる嫉妬というレベルを超え、人間存在そのものへの根源的な疑いへと繋がっているように見えました。彼は直に、そして弟の二郎に、ほとんど病的な疑いの目を向けます。特に和歌山で二郎に「直がお前に惚れているのではないか」「一晩泊まって試してくれ」と頼む場面は、常軌を逸しているとしか言いようがありません。
彼の苦悩の根源はどこにあるのでしょうか。作中で彼が語るように、結婚によって女性の「天真が損なわれる」「夫のために邪になる」という考えを持っていること、そしてその原因が夫の側にあると自覚していること。これは、彼自身の内面にある矛盾や葛藤の表れなのかもしれません。理想と現実のギャップ、人を完全に理解することの不可能性、そしてそれ故の孤独。彼は、近代知識人が陥りがちな、観念の世界と現実世界との乖離に苦しんでいるように見えます。
しかし、彼の苦悩に同情できる部分があったとしても、彼が妻の直に対して行ったとされる行為は、決して許されるものではありません。Hへの手紙の中で、一郎は直を何度も打ったことを告白しています。現代の視点から見れば、これは紛れもない家庭内暴力です。理由はどうあれ、暴力を正当化することはできません。直が抵抗しなかったから、彼女はもっと残酷だ、という彼の言い分は、自己正当化に過ぎないように感じます。一郎の苦悩の深さと、彼の行動の非道さ。この二面性が、一郎という人物を非常に複雑で、そして問題含みな存在にしています。
物語の語り手である二郎は、兄・一郎と兄嫁・直の間で揺れ動きます。彼は兄の異常な言動に困惑し、反発しながらも、どこか兄を突き放せないでいます。和歌山での兄からの頼みを、最終的に引き受けてしまう(結果的に嵐でそうなったとはいえ、当初は昼間に帰る約束で出かける)あたりに、彼の人の良さ、あるいは状況に流されやすい性格が見て取れます。彼が兄に対して、あるいは直に対して、もっと強い態度で接していれば、事態は変わったのかもしれない、とも考えてしまいます。
二郎は、兄夫婦の問題に深く関わりながらも、どこか傍観者的というか、事態の核心に踏み込もうとしない印象も受けます。一郎から和歌山での一夜について問われても、はぐらかしてしまう。家を出て下宿を始めても、兄の問題から完全に距離を置けるわけではない。彼は、いわば「巻き込まれ型」の主人公であり、彼の視点を通して一郎の苦悩や家族の歪みが浮き彫りにされていきますが、彼自身が主体的に状況を変えようとする力強さは、あまり感じられませんでした。
一郎の妻である直もまた、複雑な内面を持つ女性として描かれています。夫の異常なまでの疑念と、おそらくは暴力に耐えながら、彼女は何を思っていたのでしょうか。二郎と二人きりで過ごした嵐の夜、彼女が「どうせなら暴風雨の中で猛烈で一息な最期を迎えたい」と口にする場面は、彼女のうちに秘められた激しい感情、あるいは絶望を垣間見せるようで印象的でした。夫を愛しているのか、それとも憎んでいるのか。二郎に対して特別な感情を抱いているのか。彼女の本心は、作中ではっきりと語られることはありません。
「男は嫌になればどこへでも行けるけど、女はそうはいかない。立ち枯れになるまでじっとしているしかない」という彼女の言葉は、当時の女性が置かれていた社会的な制約と、彼女自身の諦念を表しているようで、胸が痛みました。一郎の苦悩が声高に語られる一方で、直の苦しみは内へと沈潜していく。その対比が、物語にさらなる深みを与えているように思います。彼女がもっと自己主張できていれば、あるいは周囲が彼女の苦しみに気づき、手を差し伸べることができていれば、とも思わずにはいられません。
物語の終盤、「塵労」編で登場する一郎の親友Hの存在は、この重苦しい物語に一条の光を投げかけるかのようです。Hは、二郎からの依頼を受け、一郎と共に旅に出ます。そして、旅先から二郎に送った手紙の中で、一郎の苦悩の核心に触れ、彼への深い理解と共感を示します。Hは一郎を「凡庸な私に頭を下げ涙を流すほどの正しい人」と評し、「彼をただの気難しい人と解釈してはいけない」「私のように彼の不安を取り除く努力をすべき」と二郎に語りかけます。
このHの手紙は、一郎という人物に対する新たな視点を提供します。単なる異常者、DV夫として断罪するのではなく、彼の苦悩の根源にある純粋さや正しさに目を向け、寄り添うことの重要性を説いているのです。一郎が語る「行動と目的が一致しないほど苦しい事はない」「人間全体の不安を自分一人に集めている」「生死を超越しなければダメだと思う」といった言葉は、Hのフィルターを通して読むと、単なる自己憐憫や誇大妄想ではなく、近代人の抱える普遍的な苦悩の叫びとして響いてくるようにも感じられます。
しかし、Hの手紙によって物語が締めくくられることには、やや疑問も感じます。Hの解釈は、あくまでH個人のものであり、それが絶対的な真実とは限りません。また、一郎の行った行為(特に暴力)を、彼の内面の「正しさ」によって相対化してしまう危険性も孕んでいるように思えます。Hの言うように、一郎の不安を取り除く努力をすることは大切かもしれませんが、それによって直が受けた傷や苦しみが癒えるわけではありません。
そして何より、この物語はHの手紙で終わってしまい、その後、長野家の人々がどうなったのか、一郎と直の関係はどう変化したのか、二郎は自身の問題(例えば三沢から勧められた女性との結婚話など)にどう向き合ったのか、といった点が全く描かれていません。いわゆる「起承転結」の「結」がないのです。これは漱石作品にしばしば見られる特徴ではありますが、読者としては、やはりその先を知りたいという気持ちが強く残ります。Hの提言を受け、家族は一郎を受け入れる努力をしたのでしょうか。それとも、やはり関係は修復できなかったのでしょうか。
作中で描かれる旅の場面も印象的でした。大阪の街の雰囲気、和歌山の紀三井寺や今はなき屋外エレベーター、箱根の自然。これらの場所が、登場人物たちの心理状態と響き合うように描かれています。特に和歌山での嵐の場面は、一郎の心の荒れ具合や、二郎と直の間に漂う不穏な空気を象徴しているかのようです。旅という非日常的な空間が、登場人物たちの隠された感情や関係性の歪みを露わにする装置として機能しているように感じました。
また、序盤の「友達」編で描かれる、三沢と「あの女」のエピソードも、物語全体を考える上で重要だと感じます。三沢が、かつて自分が関わったことで精神を病んでしまった娘と、「あの女」を重ね合わせる姿。そして、胃腸の弱い「あの女」に無理に酒を勧めた過去。これは、後の章で描かれる一郎の姿とどこか重なります。他者との関わりの中で、意図せず相手を傷つけてしまうこと、あるいは自身の内面の問題から他者を支配しようとしてしまうこと。そうした人間の業のようなものが、三沢と一郎という二人の人物を通して描かれているのかもしれません。
漱石自身の体験も、この作品には色濃く反映されていると言われています。特に胃の病気に苦しんだ漱石自身の姿は、三沢や「あの女」、そして最終的に心身を病んでいく一郎の姿に投影されているのかもしれません。また、修善寺の大患という生死の境をさまよった体験が、一郎の口を通して語られる「死か、気が違うか、宗教か」という切迫した問いや、「生死を超越したい」という願望に繋がっている可能性も考えられます。
「行人」は非常に重く、読後も考えさせられる作品でした。人間のエゴイズム、理解しあえない孤独、コミュニケーションの不全といったテーマは、百年以上経った現代においても、決して古びていないと感じます。一郎のような極端な人物はそういないかもしれませんが、彼が抱える苦悩の断片は、程度の差こそあれ、多くの人が内に抱えているものなのかもしれません。ただ、その苦悩が他者への加害に繋がってしまうことの危うさも、同時に強く感じました。Hの言うように、理解し寄り添う努力は必要だとしても、健全な境界線を引くこともまた、重要なのではないでしょうか。
まとめ
夏目漱石の「行人」は、近代知識人の深い苦悩と、それに伴う家族関係の崩壊を描いた、重厚な物語でしたね。主人公・二郎の視点を通して、兄・一郎の常軌を逸した疑念や行動、そしてその根底にある人間不信や孤独が、痛々しいほどに伝わってきました。
物語は、大阪、和歌山、東京、箱根と舞台を変えながら進みます。特に和歌山での、一郎が二郎に妻・直との一夜を強いる場面は、物語の大きな転換点であり、登場人物たちの関係に決定的な亀裂を生じさせます。一郎の苦悩は深まる一方で、妻の直もまた、声にならない苦しみを抱えている様子がうかがえます。
終盤、一郎の親友Hから二郎へ送られた手紙は、一郎の内面を深く掘り下げ、彼の苦悩を理解しようと試みる視点を提供します。Hは、一郎を単なる異常者として片付けるのではなく、彼の「正しさ」や「苦しみ」に寄り添うことの重要性を説きます。しかし、この手紙で物語が終わるため、その後の長野家がどうなったのかは描かれず、読者の想像に委ねられています。
「行人」は、人間の内面の複雑さ、他者を完全に理解することの難しさ、そして近代という時代がもたらした個人の孤独といった普遍的なテーマを扱っています。読後、登場人物たちの誰に感情移入するか、一郎の行動をどう捉えるか、Hの言葉をどう受け止めるか、様々なことを考えさせられる、深く心に残る作品だと言えるでしょう。