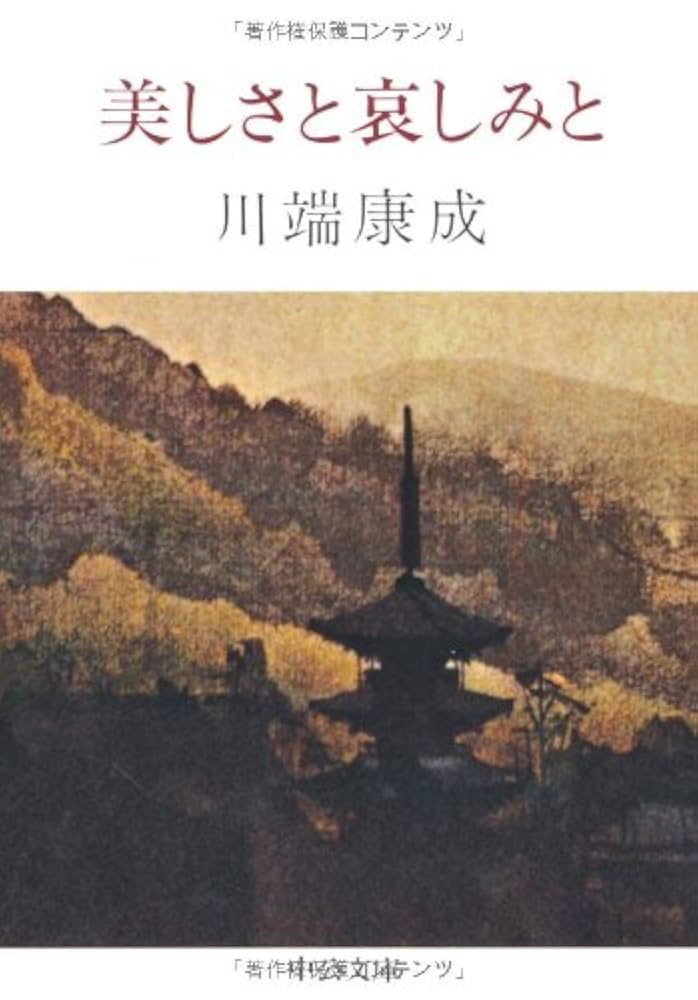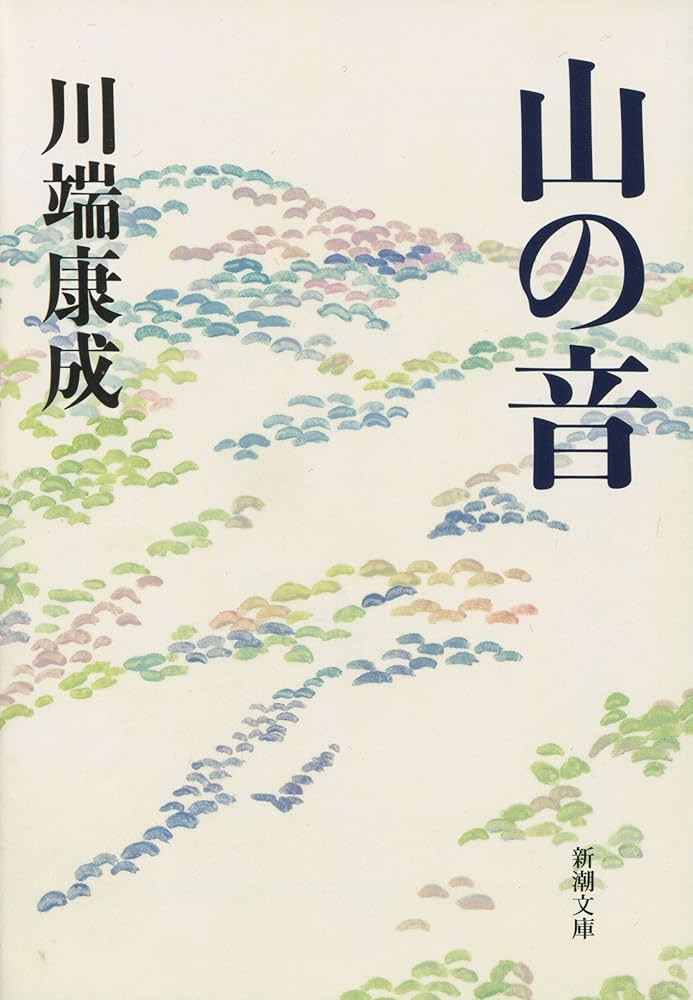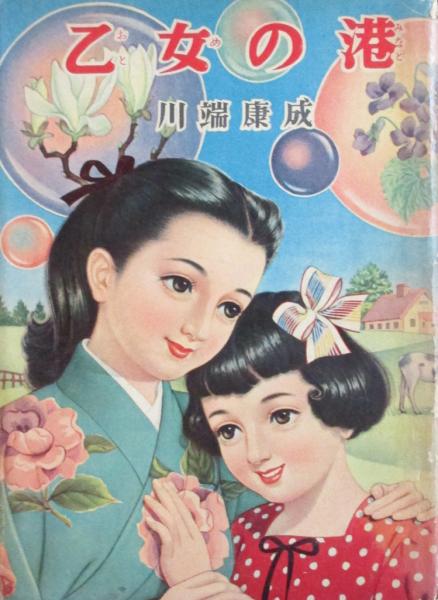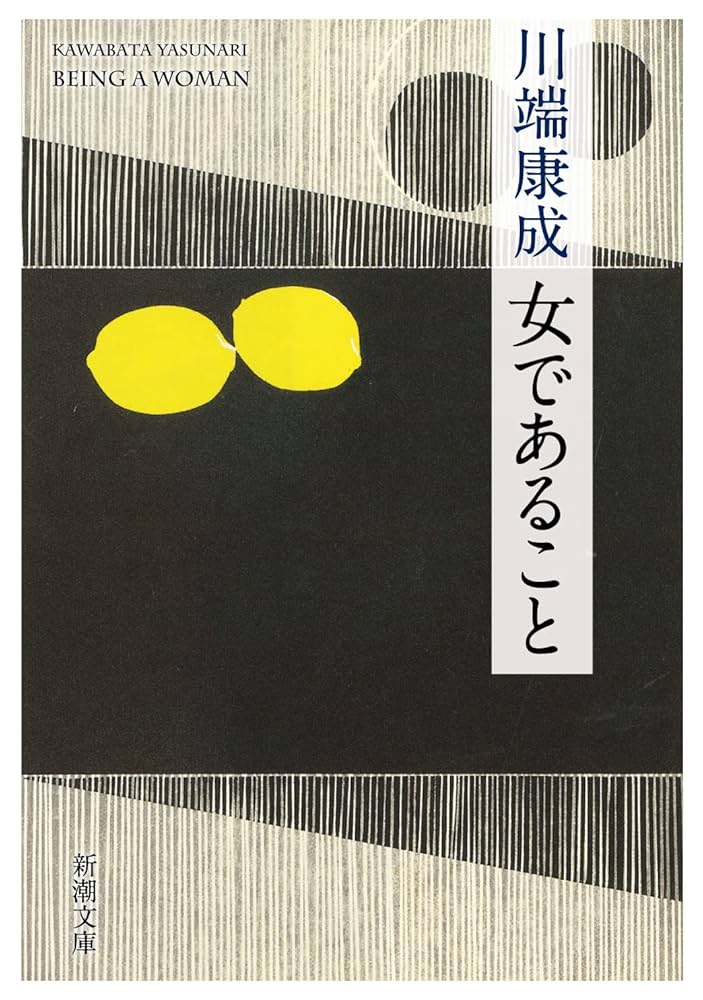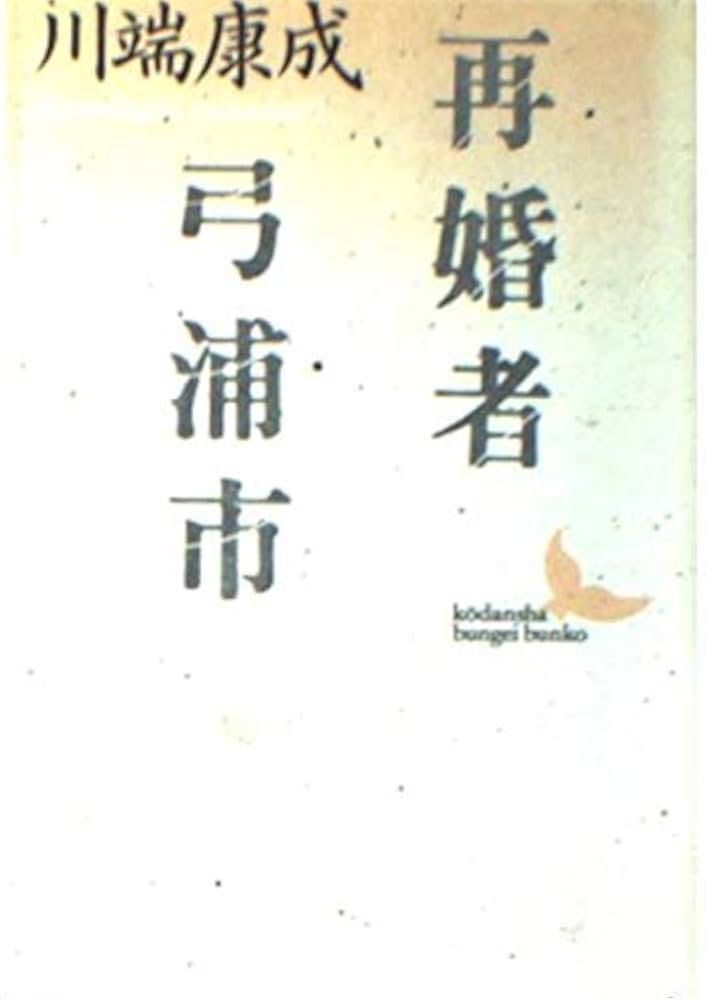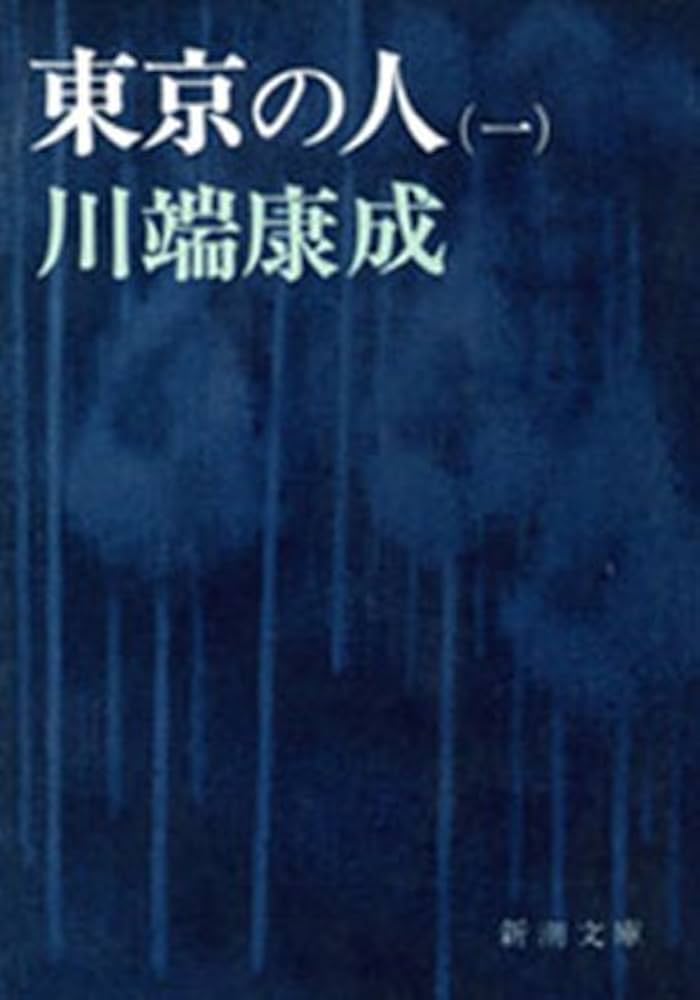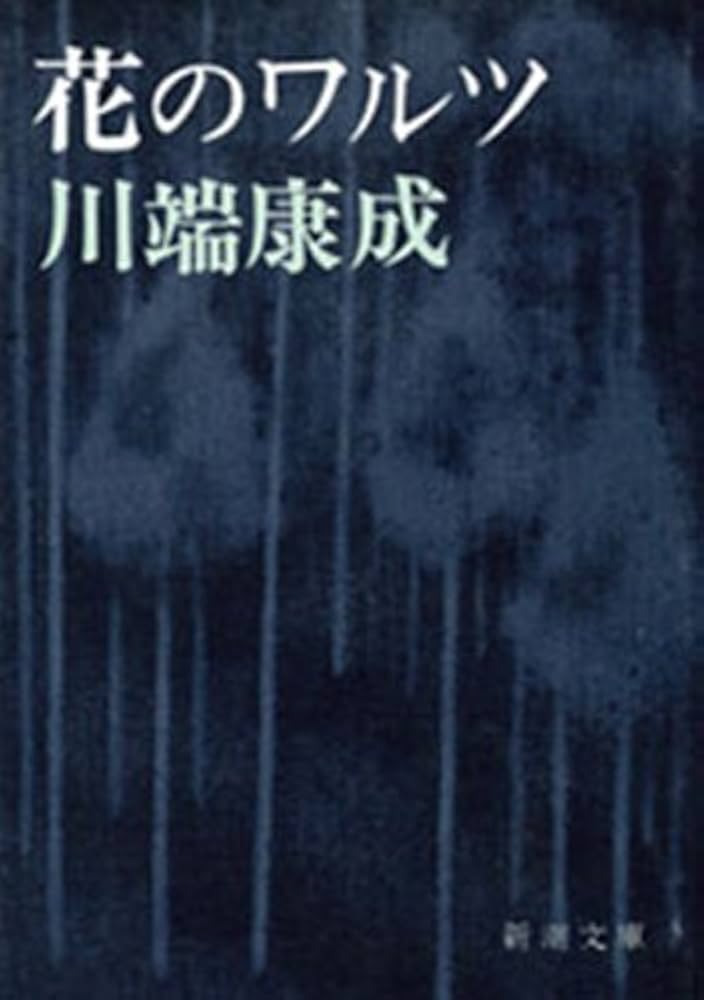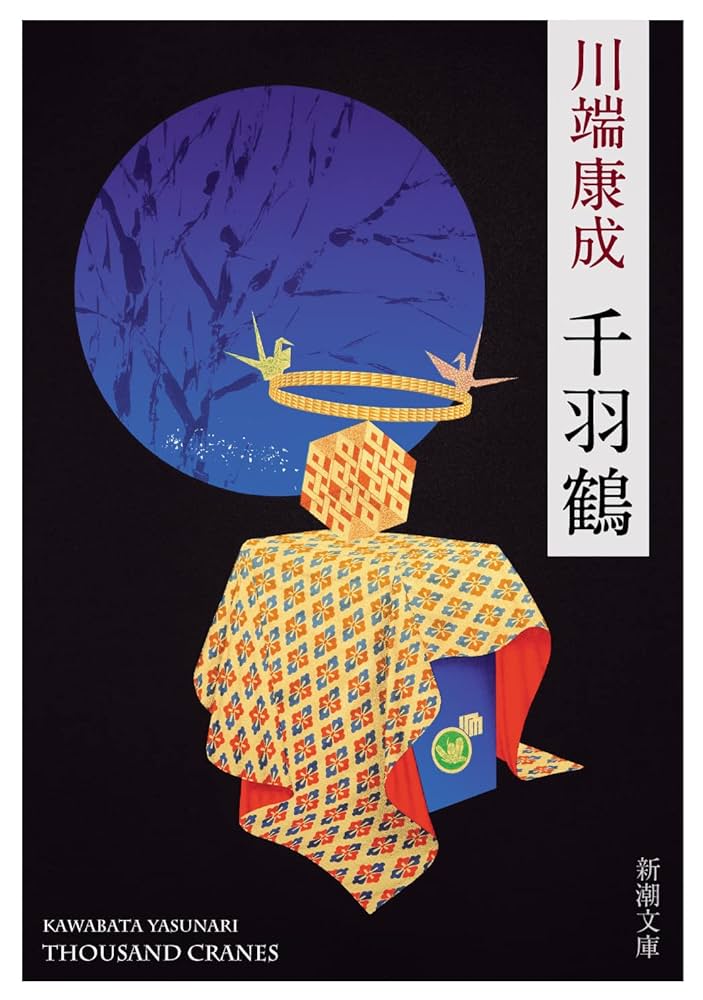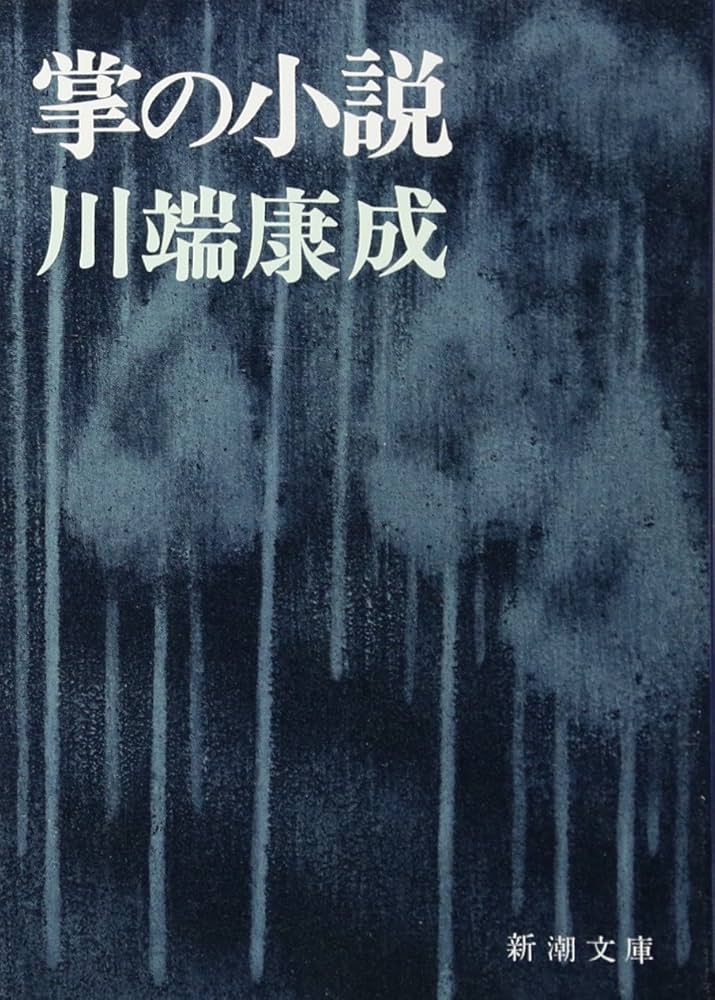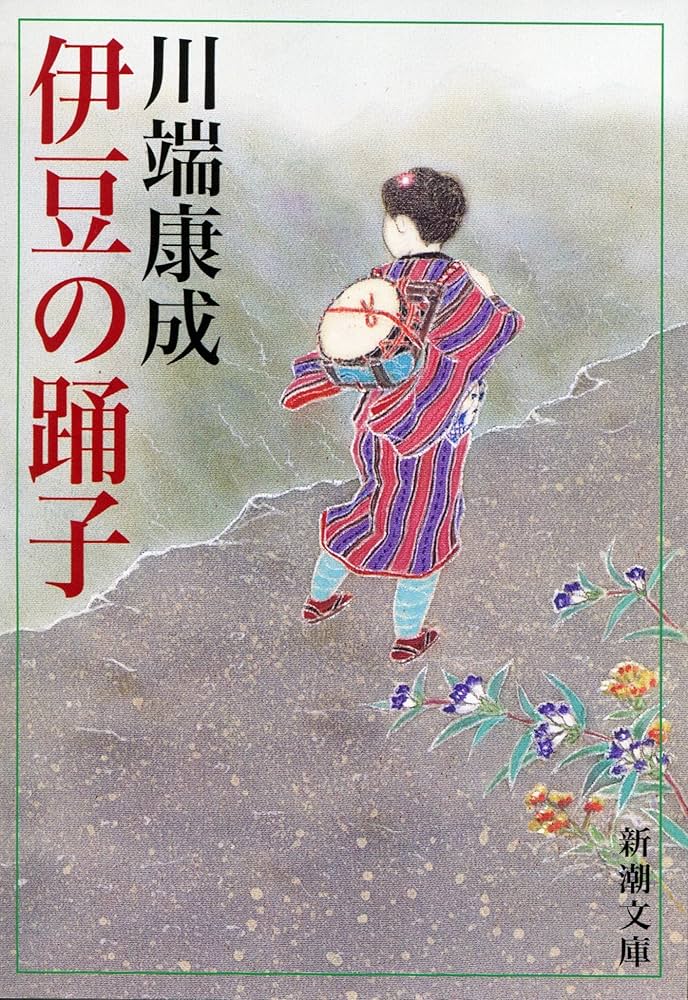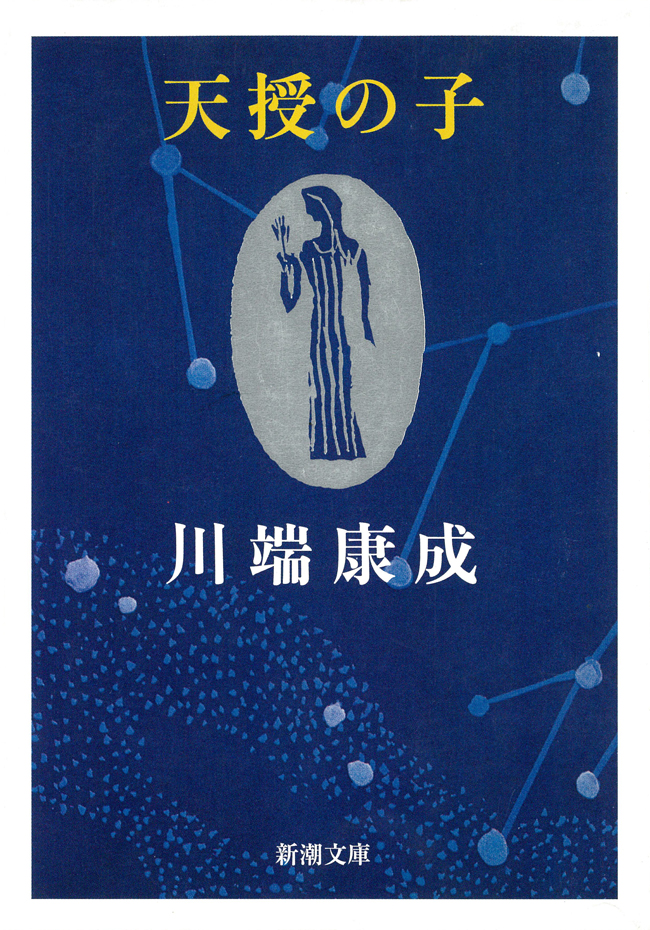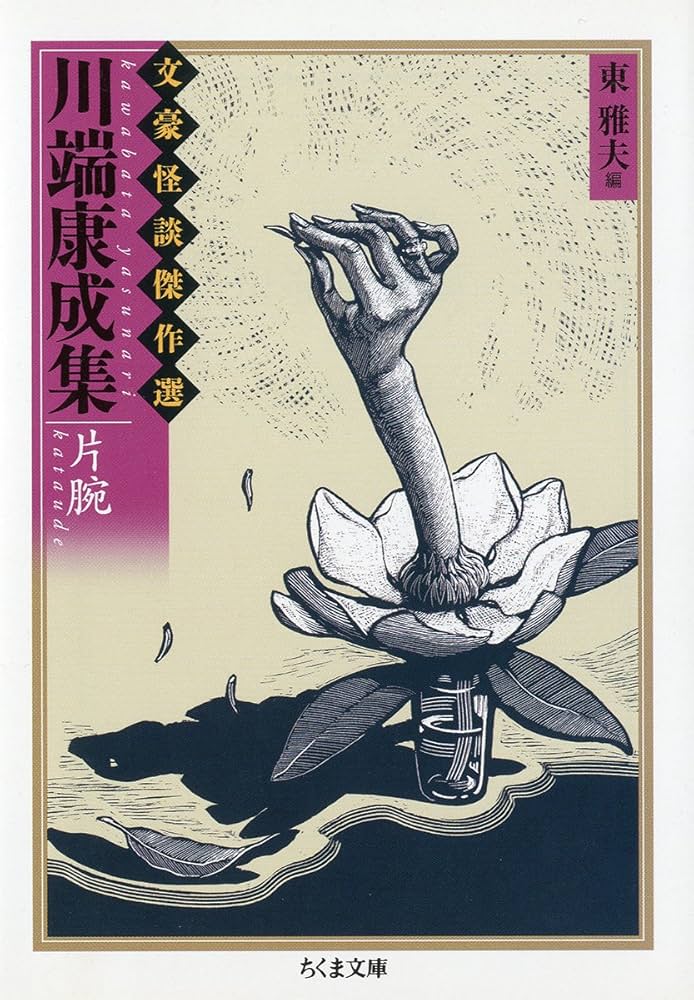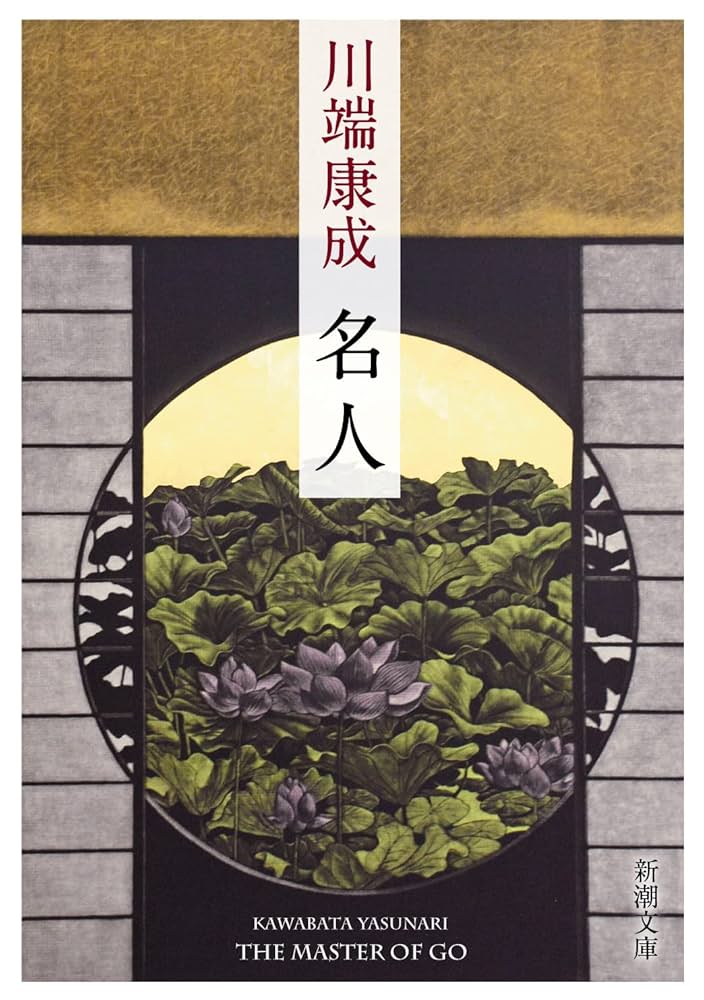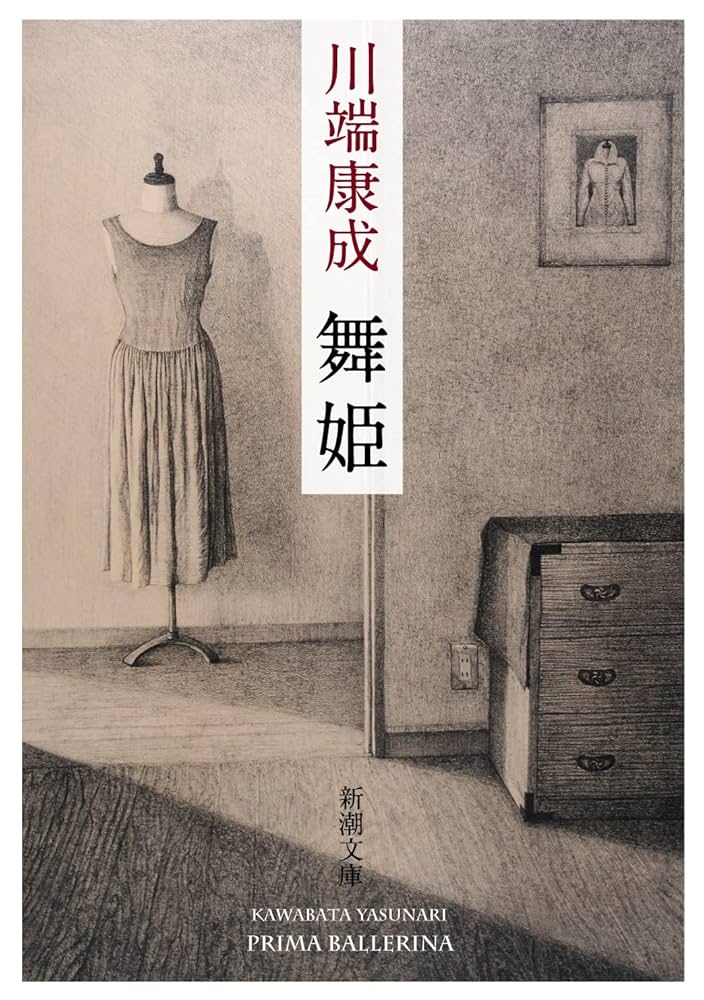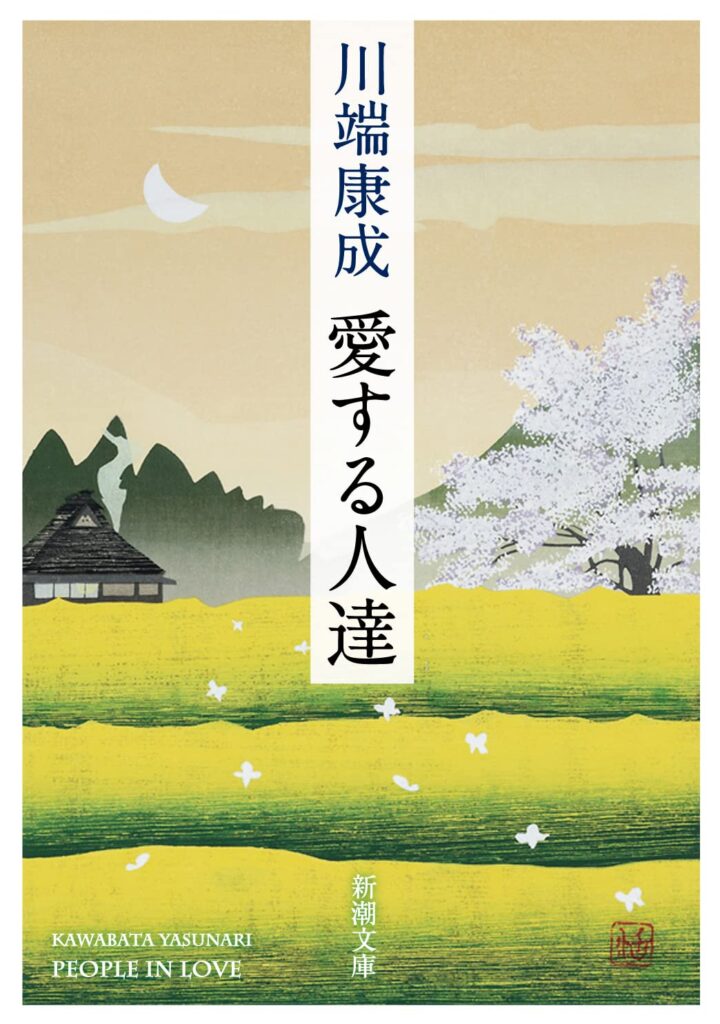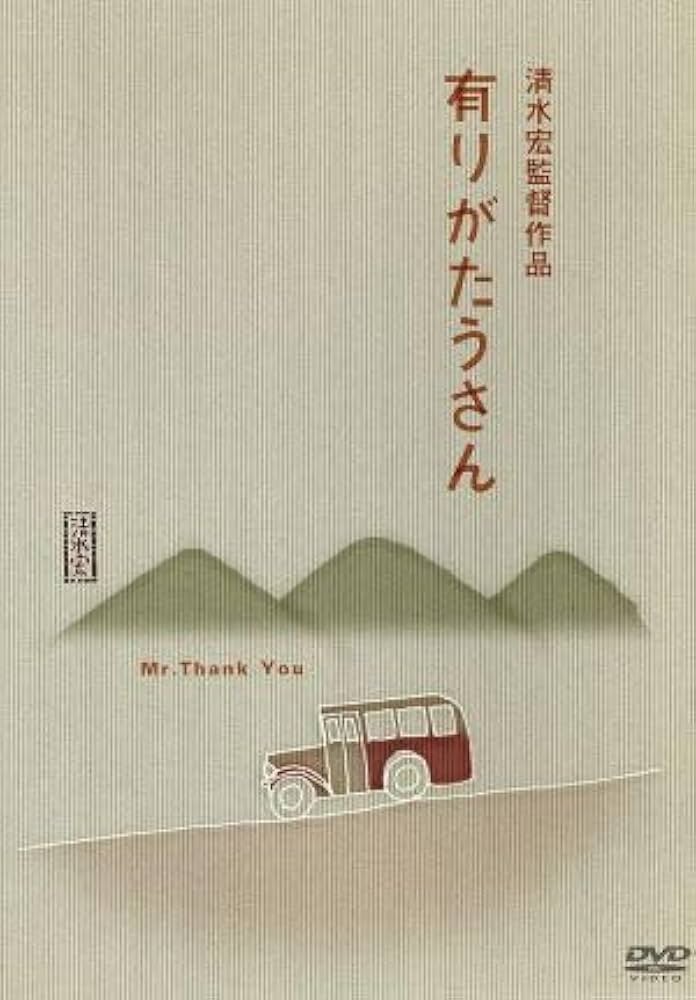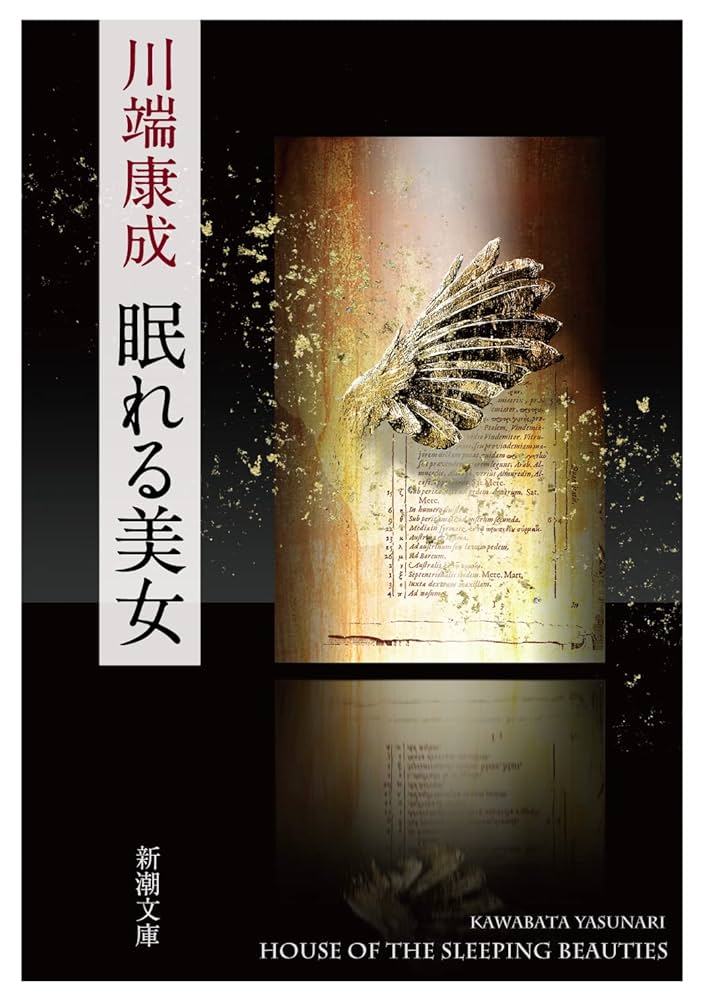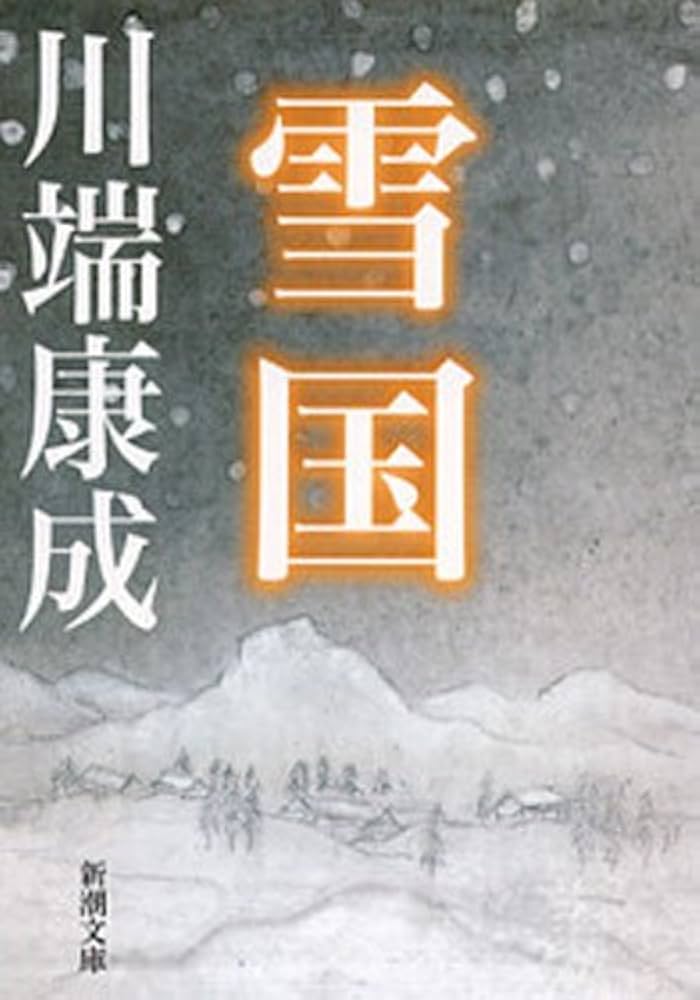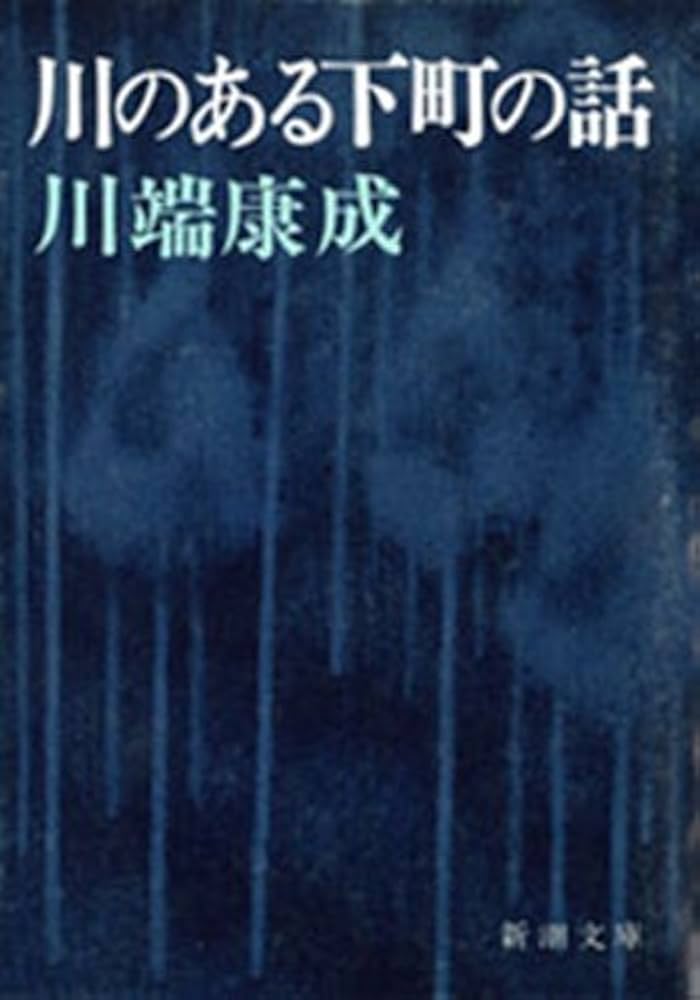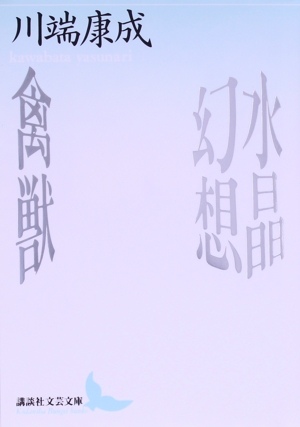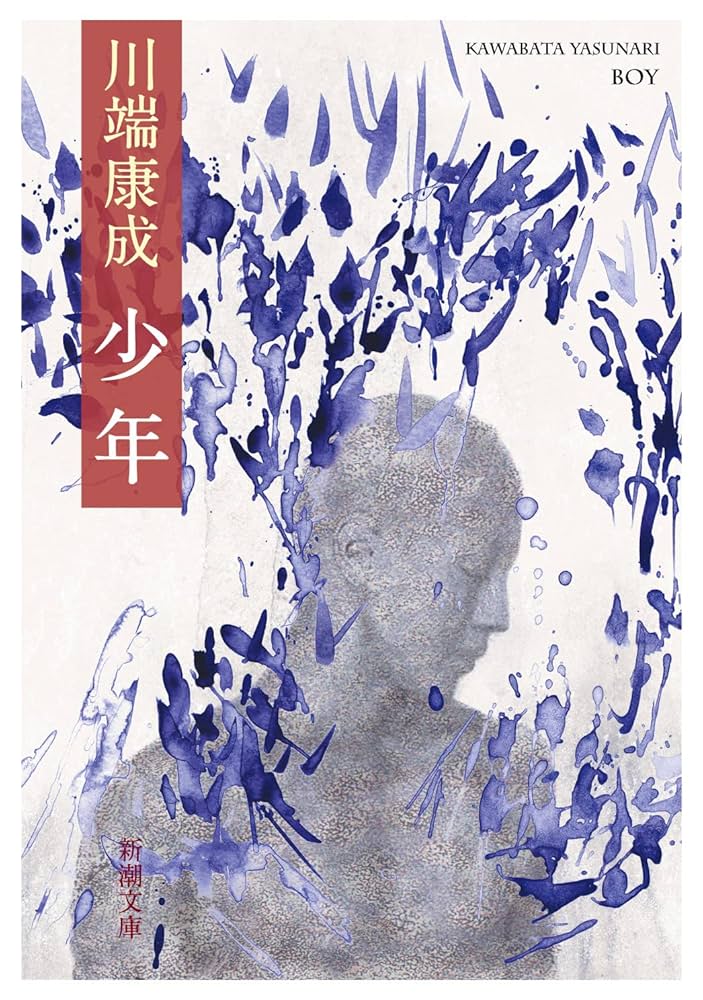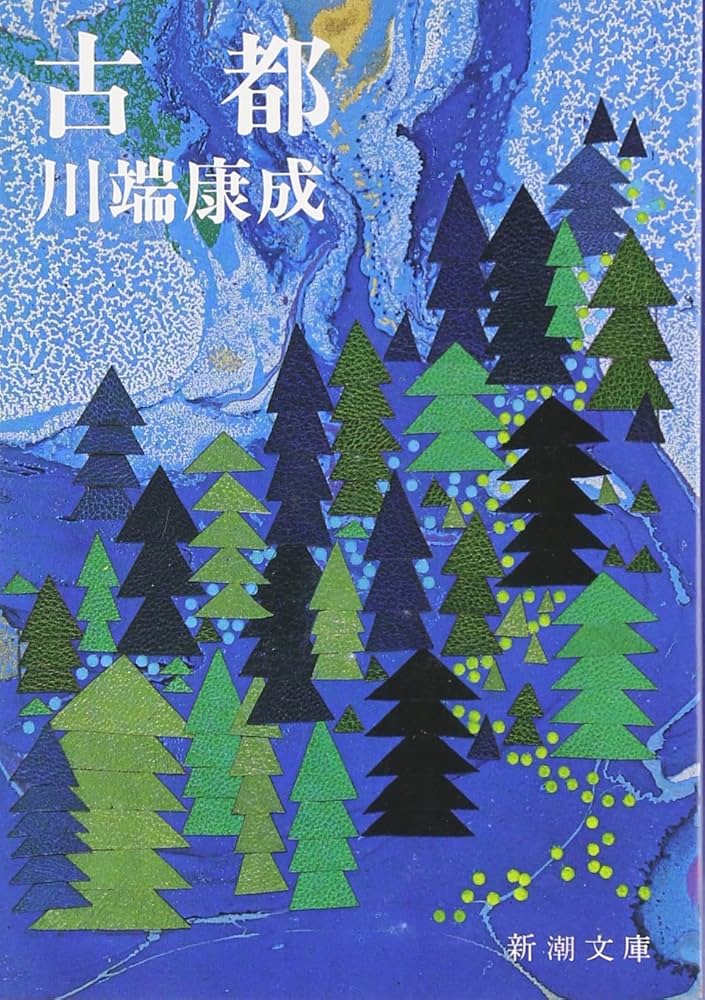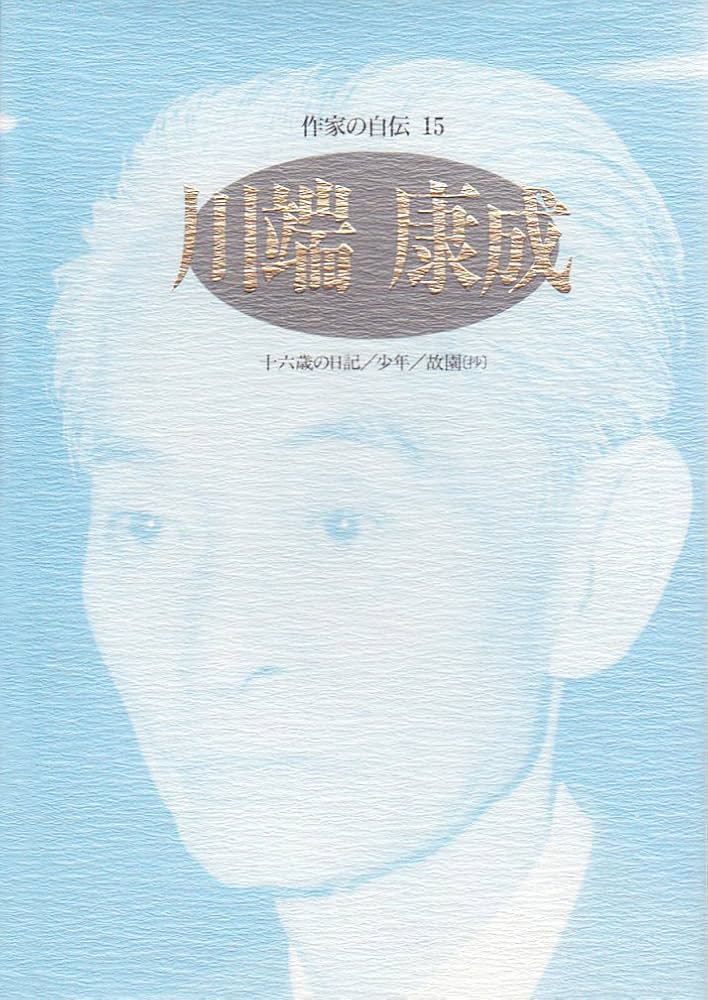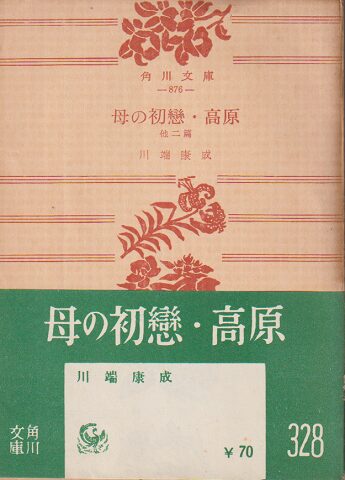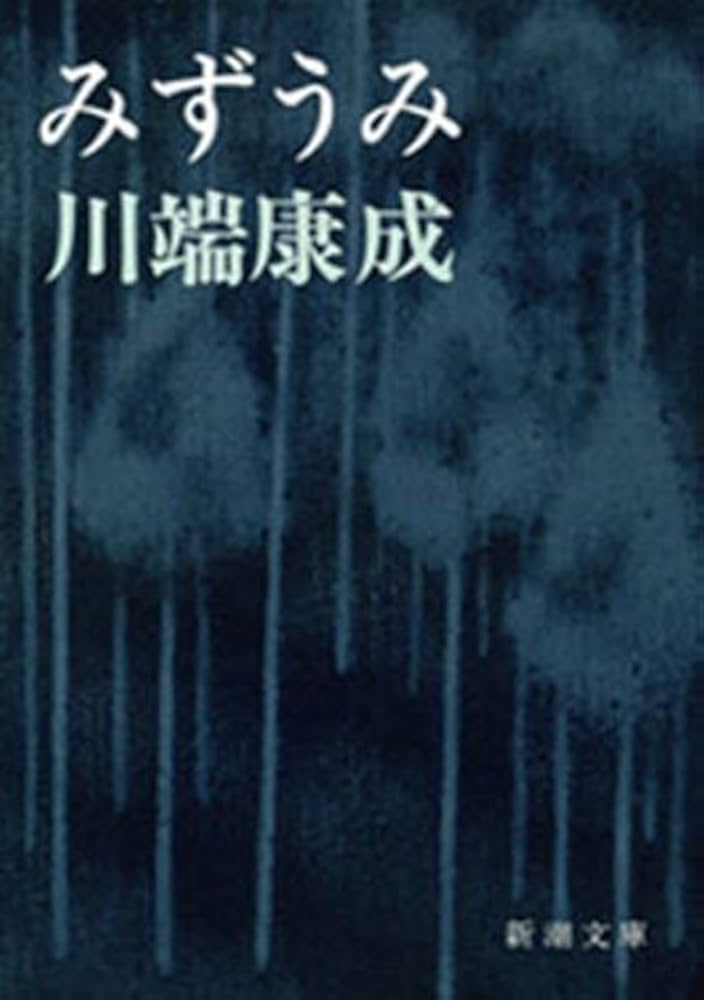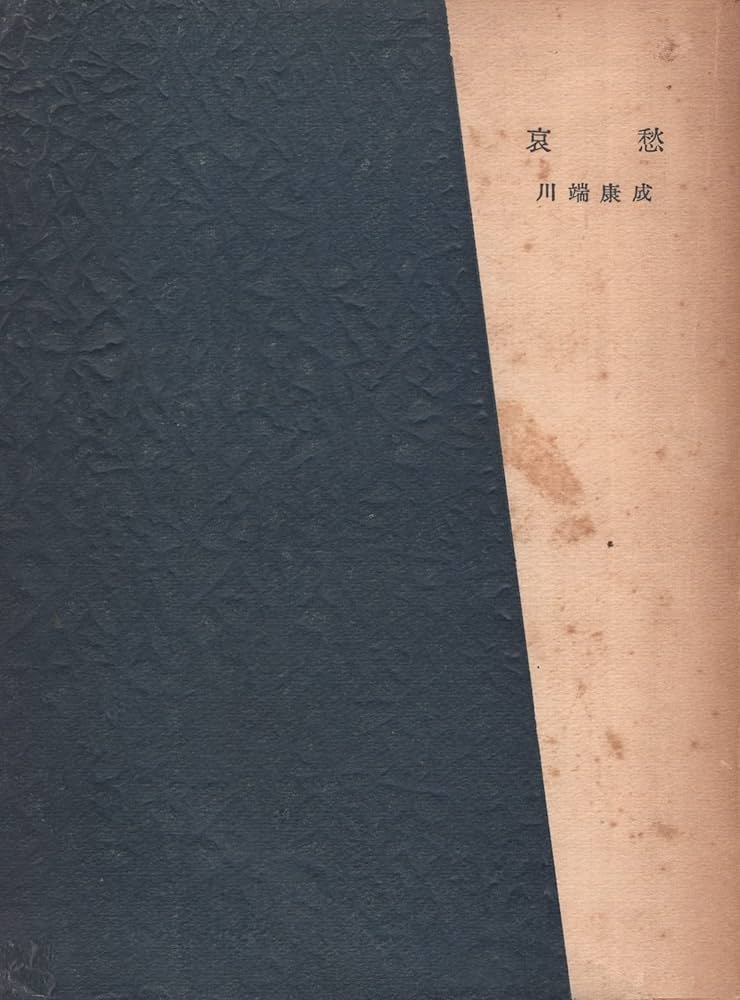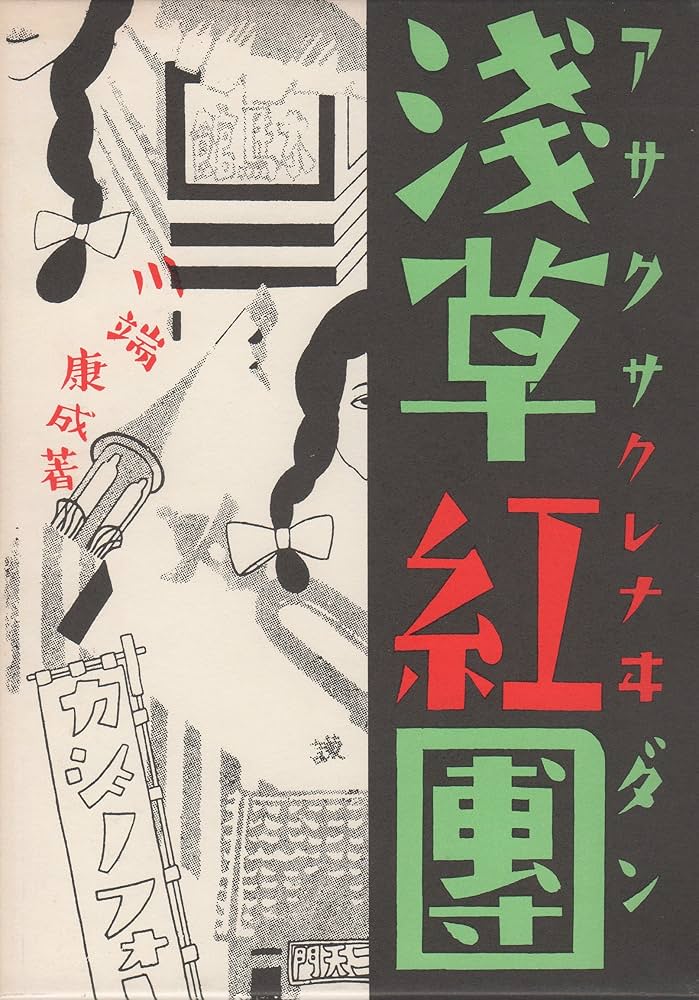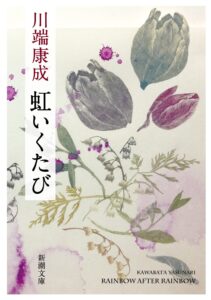 小説「虹いくたび」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「虹いくたび」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
川端康成が描く世界は、息をのむほどの美しさと、背筋が凍るような悲しみが常に隣り合っています。この『虹いくたび』という物語も、まさにその真骨頂。戦後の混乱期を背景に、ある家族の崩壊と再生の兆しを、儚くも鮮烈な筆致で描き出しています。一見すると、美しい三姉妹の物語のように思えるかもしれません。
しかし、その水面下では、父親の奔放な愛が生んだ歪みが渦巻き、娘たちの運命を静かに、しかし確実に蝕んでいきます。特に、物語の中心に存在するある「遺物」は、愛と死、聖と俗が入り混じった、強烈な象徴として読者に迫ります。それは、この物語が単なる家庭劇ではないことを示唆しているのです。
この記事では、まず物語の骨子となる部分をご紹介し、その後、物語の核心に触れるネタバレを含んだ深い読み解きへと進んでいきます。川端文学の持つ、美しくも残酷な世界の深淵を、一緒に覗いてみませんか。この物語が投げかける「救いとは何か」という問いに、きっと心を揺さぶられるはずです。
「虹いくたび」のあらすじ
著名な建築家である水原常男には、それぞれ母親の違う三人の娘がいました。長女の百子は、父が次女・麻子の母と結婚したことで愛に破れ、自ら命を絶った女性の娘。次女の麻子は、水原の唯一の正妻であった亡き妻との間に生まれた娘。そして三女の若子は、京都の芸者との間に生まれた娘で、父とは長年顔を合わせていませんでした。
この複雑な家庭環境は、姉妹の心に微妙な影を落としていました。特に百子は、母の死と、戦争で初恋の人を失ったという二重の喪失感を抱え、その心の傷を埋めるかのように、破滅的な生き方を選んでいました。一方、心優しい麻子は、そんな姉の危うい姿を案じながら、父と暮らす日々を送っていました。
ある春、水原は娘たちを連れて京都へ旅に出ます。この旅は、家族にとって一つの転機となるはずでした。しかし、古都の美しい風景とは裏腹に、彼らを待ち受けていたのは、封印していた過去との予期せぬ再会でした。京都で偶然出会う人々、そして明らかになる秘密。
この旅をきっかけに、水原家の止まっていた時間が、大きく、そして悲劇的に動き始めます。三姉妹の運命は、そして彼女たちの心を縛り付ける過去は、どのような結末を迎えるのでしょうか。物語は、静かに、しかし抗いがたい力で、クライマックスへと向かっていきます。
「虹いくたび」の長文感想(ネタバレあり)
『虹いくたび』という作品は、読む者の心を深くえぐる、痛切な物語です。ここからは物語の核心、つまりネタバレに触れながら、その魅力と恐ろしさについて、私の考えを述べていきたいと思います。
物語の根幹にあるのは、水原家という家族そのものが抱える構造的な欠陥です。建築家である父・水原常男は、美しい建物を設計する一方で、自らの家庭は愛と喪失、秘密の上に築かれた、きわめて脆いものでした。彼の「僕は二度恋愛して、一度結婚した」という言葉は、彼のロマンティックな、しかし無責任な性質を象徴しています。
この父親のあり方が、三人の娘たちの人生に決定的な影響を与えます。長女の百子は、母の悲劇的な死という「原罪」を背負い、その心には深い傷が刻まれています。次女の麻子は、「正妻」の子として純粋に育ちますが、その無垢さゆえに家族の歪みから目をそむけることができません。そして、婚外子である三女の若子は、その存在自体が家族の秘密であり、不在でありながらも物語に緊張感を与え続けます。
この三姉妹は、それぞれが父の愛を求めながらも、決して満たされることのない渇望を抱えています。彼女たちの間の静かな嫉妬や葛藤は、この家庭が精神的な支柱を欠いていることの証左にほかなりません。水原家は、愛によって結ばれていると同時に、愛によって引き裂かれているのです。
この物語で最も強烈な印象を残すのが、「乳碗」という名の遺物です。これは、百子の戦時中の恋人、特攻隊員であった青木啓太が、彼女の乳房の型を取って作らせた盃です。死を目前にした彼は、「それを盃にして、僕の命の最後を飲みほしたい」という常軌を逸した願いを口にします。
このエピソードは、読む者に強烈な不快感と衝撃を与えます。生命の象徴である乳房が、死を飲み干すための器へと変えられる。この愛(エロス)と死(タナトス)の倒錯した融合は、百子の心を永遠に縛り付ける呪いとなります。彼女の愛が歪められ、一人の人間としてではなく、一個の「モノ」として扱われた瞬間でした。
百子はその後の人生で、このトラウマから逃れることができません。彼女が年下の美しい青年たちを次々と弄び、捨てていく破滅的な行動は、かつて自分が受けた仕打ちを反転させ、他者を支配することで失われた尊厳を取り戻そうとする、悲しい試みだったのです。「乳碗」は単なる思い出の品ではなく、彼女の魂を蝕む、物質化されたトラウマそのものでした。
物語の転換点となるのが、一家の京都への旅です。川端康成は、都をどりや桂離宮といった雅やかな古都の風景を、登場人物たちの混沌とした内面と対比させる装置として巧みに用いています。美しい伝統文化の表層が、人間の心の醜さや葛藤をかえって際立たせるのです。
この京都で、家族は封印してきた過去と直面します。麻子と父は、まだ見ぬ妹・若子と偶然にも遭遇し、その存在の重さを知ります。一方、百子は、かつて弄んで捨てた、戦死した恋人の弟・夏二と再会し、自らの罪と向き合うことを余儀なくされます。
京都は、彼らに過去からの逃避を許しません。むしろ、鏡のように彼らの内なる混乱を映し出し、葬り去りたいと願う真実を突きつけます。優雅な美の空間が、登場人物たちの隠された感情が噴出する、悲劇の舞台へと変貌していく様は、実に見事です。
百子の心の傷が最も破壊的な形で現れるのが、学生である竹宮との関係です。彼女にとって、年下の青年を誘惑し、支配し、そして捨てるという行為は、もはや自己を保つための防衛機制となっていました。竹宮との関係は、この悲劇的なサイクルの頂点でした。
嵐の夜、百子は竹宮に妊娠を告げます。それは愛の告白ではなく、相手を追い詰めるための冷酷な最後通告でした。責任という現実に耐えきれなくなった竹宮は、闇の中へ逃げ出し、やがて自ら命を絶ってしまいます。この出来事によって、百子は単なる被害者ではなく、他者の死に責任を負う加害者へと変貌してしまうのです。
この物語が示すのは、トラウマがいかに伝染し、他者を破壊する力を持つかという冷徹な事実です。百子の心の傷は彼女の内にとどまらず、新たな悲劇を生み出してしまいました。死者に憑かれた生者は、新たな死者を生み出し、悲しみの連鎖は続いていくのです。
事態を収拾するため、百子の父・水原と、死んだ恋人の父・青木が介入します。彼らは「娘のため」という大義名分のもと、医師と共謀し、百子の同意なしに妊娠を中絶させることを決定します。これは配慮や救済という名で行われる、百子の身体と自己決定権に対する重大な侵害でした。
彼らの行動の根底には、娘を思う気持ちだけでなく、厄介な問題を抹消したいという自己中心的な論理が見え隠れします。この家父長的な支配は、かつて「乳碗」を作らせた行為と構造的に同じです。どちらも、男性が女性を客体化し、その主体性を奪うという点において、本質的な違いはありません。守るべきはずの父親が、ここでは別の形の暴力の担い手となってしまうのです。
物語は京都・嵐山でクライマックスを迎えます。ここで初めて三姉妹は公式に対面し、そして過去の呪縛を象徴する「乳碗」が砕け散ります。この物理的な破壊は、百子が過去の重圧から解放される可能性を示す、極めて重要な象徴的行為です。
この場で、三女・若子が見せる態度は印象的です。彼女は、父たちが押し付けようとする感傷的な和解を、清く激しい態度で拒絶します。それは、家族の病的な力学に巻き込まれることを拒み、自らの意志を貫く強さの表明でした。彼女は、この家族の悲劇に新たな視点をもたらします。
一方で、百子の悲劇とは対照的に、妹の麻子と、恋人の弟であった夏二との間には、穏やかで健全な愛が育まれていきます。彼らの関係は、未来へ向かう希望の道筋を象徴しているかのようです。このクライマックスは、一つのトラウマから抜け出すための、異なる複数の道筋を提示しているのです。
物語は、はっきりとした解決を迎えないまま、静かに幕を閉じます。最後の場面、百子は窓の外に、一瞬、虹を見たような気がします。この「見た気がする」という曖昧な表現こそ、この物語の結末の核心です。
虹は、この小説全体を貫く象徴であり、三姉妹の儚い美しさや、生と死、悲しみと幸福の間に架かる束の間の橋を意味します。しかし、百子に与えられたのは、確かな希望の光景ではありません。それは、確信ではなく、あくまで可能性の示唆に過ぎないのです。
『虹いくたび』という題名は、幸福の虹を求めて、いくたびも彷徨い続ける百子の姿そのものを表しているのかもしれません。彼女は幸福を見つけたわけではない。しかし、おそらく生まれて初めて、それを探し求めることができる出発点に立ったのです。この結末は、安易なカタルシスを読者に与えるのではなく、深い傷を負った人間が、未来への何の保証もないまま、最初の一歩を踏み出す痛切な姿を提示します。それこそが、川端文学の真髄といえるでしょう。
まとめ
川端康成の『虹いくたび』は、一つの家族を通して、愛と喪失、そして人間の心の深淵を描ききった作品です。父親の奔放な愛がもたらした家族の歪みは、娘たちの運命を大きく狂わせ、悲劇の連鎖を生み出していきます。
物語の中心にある「乳碗」のエピソードは、愛と死が倒錯した形で結びついた、強烈なトラウマの象徴です。この呪縛から、主人公の百子がいかにして解放の兆しを見出すのかが、物語の大きな見どころとなっています。ネタバレになりますが、その結末は単純なハッピーエンドではありません。
しかし、すべての悲劇と絶望の先に、主人公が見る「虹」の幻影は、かすかでありながらも、確かな希望を感じさせます。それは、深い傷を負った魂が、それでも未来へ向かおうとする瞬間の、痛々しくも美しいきらめきです。
この物語は、読む者の心に静かな、しかし忘れがたい余韻を残します。美しくも残酷な川端文学の世界に、ぜひ触れてみてください。家族とは何か、救いとは何かを、深く考えさせられる一冊です。