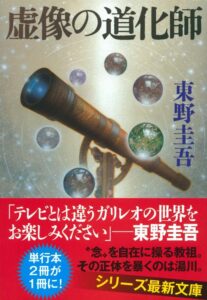 小説「虚像の道化師」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。東野圭吾氏が紡ぎ出す、ガリレオシリーズ第七弾。この短編集は、単行本『虚像の道化師 ガリレオ7』に、かつて『禁断の魔術 ガリレオ8』に収められていた三つの物語、「透視す」「曲球る」「念波る」を加え、文庫として新たな装いを見せたものです。つまり、実質二冊分の愉しみがここに凝縮されているというわけです。
小説「虚像の道化師」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。東野圭吾氏が紡ぎ出す、ガリレオシリーズ第七弾。この短編集は、単行本『虚像の道化師 ガリレオ7』に、かつて『禁断の魔術 ガリレオ8』に収められていた三つの物語、「透視す」「曲球る」「念波る」を加え、文庫として新たな装いを見せたものです。つまり、実質二冊分の愉しみがここに凝縮されているというわけです。
一見すると超常現象、オカルトとしか思えぬ事件の数々。しかし、その裏には必ず、冷徹な科学の法則が隠されている。帝都大学物理学准教授、湯川学が、その明晰な頭脳で虚像を剥ぎ取り、真実を暴き出す。彼の相棒役を務めることが多い草薙刑事との、どこか噛み合わないようでいて、核心を突くやり取りもまた、このシリーズの醍醐味と言えるでしょう。
この記事では、各編の物語の筋書きを追いながら、その仕掛けや人物像について、少々踏み込んだ解釈を披露するつもりです。もちろん、結末に至るまでの重要な情報にも触れていきます。読み進めるかどうかは、貴方自身の判断にお任せしますが、知的好奇心を刺激されたいのであれば、この先へ進むことをお勧めしますよ。
小説「虚像の道化師」の物語の筋書き
この『虚像の道化師』は、七つの不可思議な事件を綴った短編集です。物理学者・湯川学と、警視庁の刑事・草薙俊平(そして時には内海薫)が、科学的な視点から事件の真相に迫っていきます。
第一章「幻惑す」では、新興宗教の教祖が「念力で信者をビルから転落させた」と自首するところから物語が始まります。果たして本当に超能力なのか、それとも巧妙なトリックなのか。湯川がその謎に挑みます。第二章「透視す」は、客の情報を言い当てる不思議な能力を持つホステスが登場。湯川自身もその能力に一度は惑わされますが、彼女が殺害されたことで、その能力の秘密と事件の真相を探ることになります。
第三章「心聴る」では、ある企業の社員が相次いで謎の「幻聴」に悩まされる事件が発生。自殺と見られた上司の死と、部下の暴走。その背後には、耳に聞こえぬはずの声を届ける技術が関わっていました。第四章「曲球る」は、引退を考えるプロ野球選手が中心。殺害された妻が遺した謎の置時計と、選手生命を揺るがす問題に、湯川が意外な形で関わっていきます。
第五章「念波る」は、双子の姉妹のテレパシーが事件解決の鍵となるかのように見えます。妹が感じ取った「姉の危機」。それは本当に超感覚的なものなのか、それとも…。第六章「偽装う」では、湯川と草薙が偶然立ち寄った別荘地で殺人事件に遭遇。閉ざされた環境の中で、偽装工作を見破ろうとします。第七章「演技る」は、劇団内で起きた殺人事件。残された凶器と、役者たちの証言。草薙が推理を進める中、意外な真実が明らかになります。これら七つの物語が、貴方を不可思議な世界へと誘うのです。
小説「虚像の道化師」の長文感想(ネタバレあり)
さて、ここからは遠慮なく、物語の核心に触れながら、私の所感を述べさせていただきましょう。『虚像の道化師』、実に興味深い短編集でした。ガリレオシリーズといえば、超常現象めいた事件を物理学で解き明かすのが定石ですが、本作はその定石を踏まえつつも、少々変化球を織り交ぜてきた印象を受けますね。
まず特筆すべきは、文庫化にあたり三編が追加され、七編構成となったボリュームでしょう。おかげで、様々なタイプの「謎」と「解決」を堪能することができました。まるで、様々な味わいの料理が並ぶフルコースのようでありながら、一貫して『科学的真実の追求』というメインディッシュが存在感を放っていますね。 個人的には、初期のガリレオシリーズを彷彿とさせるオカルト風味の強い物語が好みなので、「幻惑す」「透視す」「心聴る」「念波る」あたりは特に楽しめました。
「幻惑す」は、いかにもガリレオシリーズらしい幕開けです。新興宗教の教祖が「念力」で人を殺めたと主張する。フッ、そんな非科学的なことがあるはずもない。湯川先生が登場するまでもなく、トリックの存在は明白です。マイクロ波による加熱、あるいは指向性の音響か。まあ、大方そんなところだろうと予想はつきます。しかし、この物語の面白さは、トリックそのものよりも、登場人物たちの人間模様にあります。教祖・連崎至光は、自身の力を本物だと信じ込んでいる。一方、妻の佐代子や幹部の真島たちは、それを知りながら宗教ビジネスとして利用している。この構造が、単なる謎解きに留まらない深みを与えています。特に、純粋(あるいは愚鈍)な教祖と、彼を利用する者たちの対比は、皮肉が効いていてなかなか。ラスト、草薙の姉が湯川に占いのチケットを渡す場面は、科学万能主義者へのささやかな当てこすりでしょうか。実に結構。
「透視す」もまた、興味深い一編でした。銀座のホステスが見せる「透視」の芸。名刺を見ずに名前を言い当てる。最初は単なる観察眼かと思いきや、下の名前や職業まで当てられては、さすがの湯川も動揺します。この掴みは上手いですね。真相は、超小型赤外線カメラとランプを用いた、言ってしまえば古典的な技術の応用。しかし、なぜ彼女がそんな手の込んだことをしていたのか。その動機を探る過程で、亡き母親(実は継母)への思慕や、彼女を手本として生きてきた健気な姿が浮かび上がってきます。トリックの解明と、被害者の背景にあるドラマが綺麗に結びついており、読後感は悪くありません。ただ、もう少しトリックに独創性が欲しかった、というのは贅沢な望みでしょうか。
「心聴る」は、少々評価が分かれるかもしれませんね。「幻聴」を引き起こすトリックとして、指向性の音響装置が登場します。しかし、作中でも触れられている通り、物語の舞台となったであろう時期には、まだ実用化には程遠い技術。フィクションである以上、ある程度の飛躍は許容されるべきですが、ガリレオシリーズの根幹である「現実に根差した科学的解明」という点からは、やや逸脱している感も否めません。電磁波で音声を…という説明も、正直、ピンとこない読者も多いのでは?とはいえ、草薙が刺されるという衝撃的な展開や、警察学校同期の北原との関係性が描かれることで、物語としては成立しています。シリーズの縦軸を意識した配置なのかもしれません。
「曲球る」は、本作の中でも異色の存在でしょう。プロ野球選手の妻が殺害される事件が発端ですが、物語の主眼は、むしろ選手自身の再起に向けられています。妻が遺した置時計の謎は、あくまでも副次的な要素。湯川が物理学者の立場から、選手のフォーム改善に協力し、最終的には精神面の影響が大きいと示唆する。これは、従来のガリレオ像からすると、かなり踏み込んだ描写と言えます。科学一辺倒ではない、湯川の人間的な側面を垣間見ることができる。ミステリとしての鋭さは薄れるかもしれませんが、一篇の物語としての味わいは深いものがあります。たまにはこういう変化球も悪くない、そう思わせるだけの筆力は流石です。
「念波る」は、再びオカルト色の濃いテーマ、双子のテレパシーです。姉の危機を察知した妹。果たして本当に超能力なのか?…と期待させつつ、真相は「妹が、ある理由から夫を疑っており、警察を動かすためにテレパシーを装った」というもの。ううむ、動機としては少々弱い気がしないでもありません。警察に直接相談できない理由も、やや説得力に欠けるような。湯川が介入しなければ、事態はもっと複雑化していた可能性が高いでしょう。しかし、ラストで再び双子の不思議な繋がりを示唆する終わり方は、含みがあって良いですね。非科学的なものを否定しつつも、完全には切り捨てない。そのバランス感覚が、このシリーズの魅力の一つなのかもしれません。
「偽装う」は、正統派のミステリという趣です。湯川と草薙が、友人の結婚式に向かう途中で殺人事件に遭遇。大雨による土砂崩れで現場は孤立し、さながらクローズドサークルの様相を呈します。湯川の活躍は限定的で、むしろ草薙が刑事として捜査を進める場面が多いのが特徴。トリック自体も、物理学的な知識を必要とするものではなく、観察と推理によって解き明かせる範疇です。ガリレオシリーズである必要性は薄いかもしれませんが、湯川と草薙の旧友との関係性や、湯川の人間性を掘り下げるという意味では、意義のある一編と言えるでしょう。読後感は非常にすっきりとしており、良質なミステリを読んだという満足感があります。
最後の「演技る」も、ミステリとしては面白い構成です。劇団内で起きた殺人事件。当初は、草薙が女優のアリバイ工作を見抜き、犯人を特定したかのように思われます。しかし、真犯人は別にいた、というどんでん返し。倒叙ミステリかと思わせておいて、もう一捻り加えてくるあたり、読者を飽きさせません。ただ、前の「偽装う」で湯川が「警察は偽装工作を見抜ける」と語っていただけに、今回の犯人の偽装が(結果的に草薙を誤導したとはいえ)成功したかに見えるのは、少々皮肉な気もします。トリックの根幹である「劇団の小道具」という設定も、やや都合が良すぎる感は否めません。ラストの花火のシーンは、映像化を意識した演出でしょうか。
全体として、『虚像の道化師』は、ガリレオシリーズのファンであれば間違いなく楽しめる一冊です。科学トリックのアイデアが枯渇してきたのでは、という懸念も囁かれますが、本作ではトリックの多様性や、人間ドラマへの注力によって、その壁を乗り越えようとしているように感じられます。湯川学というキャラクターも、単なる変人天才科学者から、少しずつ人間味を増しているように見えます。特に草薙との関係性は、初期の頃のぶっきらぼうなやり取りとはまた違った、信頼に基づいた(それでもどこか噛み合わない)面白さがありますね。いくつかの物語では、科学的考証に疑問符が付く部分や、トリックの強引さを感じなくもありませんでしたが、それを補って余りある物語の構成力、人物描写の巧みさは健在です。個人的には、「幻惑す」の宗教と科学の対比、「透視す」の哀しい人間ドラマが印象に残りました。貴方のお気に入りは、どの物語でしたか?
まとめ
東野圭吾氏による『虚像の道化師』は、ガリレオシリーズの魅力を再認識させてくれる短編集と言えるでしょう。七つの物語は、それぞれが異なる趣向を持ちながらも、「科学の目を通して虚像を見破る」というシリーズの根幹は揺らいでいません。超常現象と見紛う事件の裏に潜む論理的な解答、それを解き明かす湯川学の鮮やかな推理は、知的興奮を与えてくれます。
本作では、初期のオカルト色の強い事件から、人間ドラマに重きを置いた物語、正統派ミステリに近いものまで、バラエティに富んだ内容が楽しめます。文庫化に際して三編が追加収録されたことで、その多様性はさらに増しました。湯川と草薙の関係性にも微妙な変化が見られ、シリーズを追い続けている読者にとっては、その点も興味深いのではないでしょうか。
いくつかのトリックについては、科学考証の厳密さや、やや強引とも思える設定に物足りなさを感じる向きもあるかもしれません。しかし、それを補うだけの物語の推進力、巧みな伏線、そして魅力的なキャラクター造形は、さすが東野圭吾作品と言うべきでしょう。貴方の知的好奇心を刺激するには十分すぎる一冊であると、私は断言しますよ。
































































































