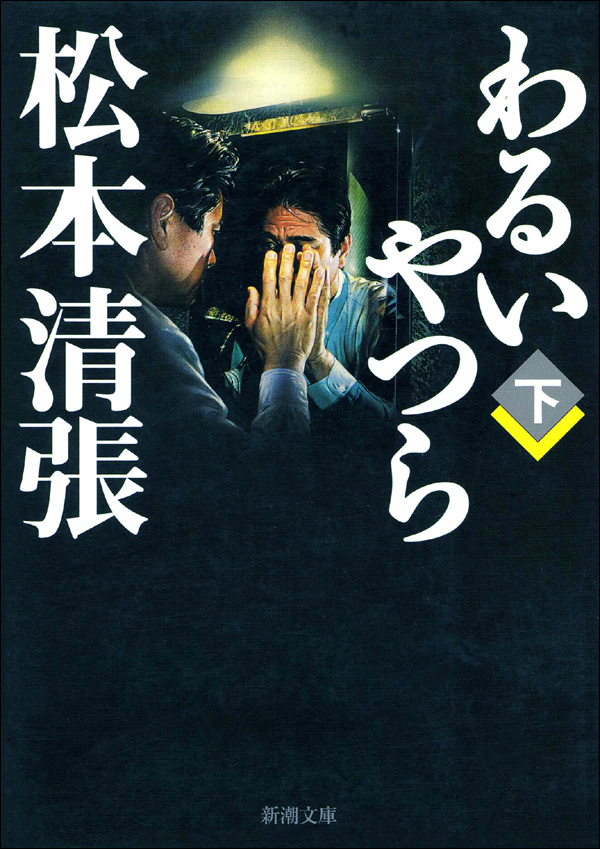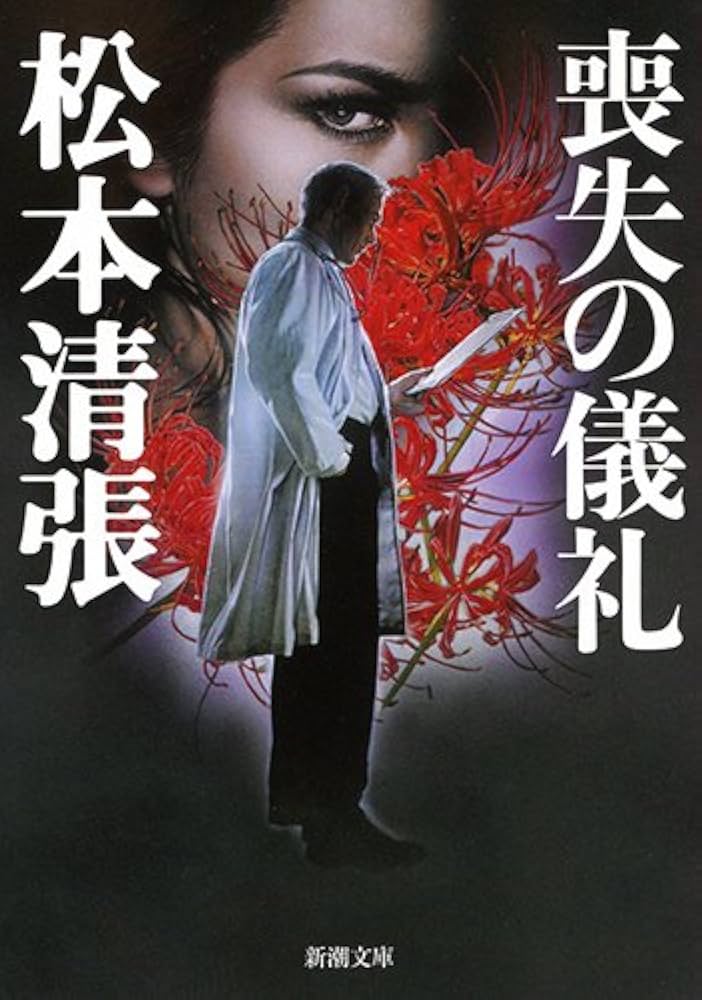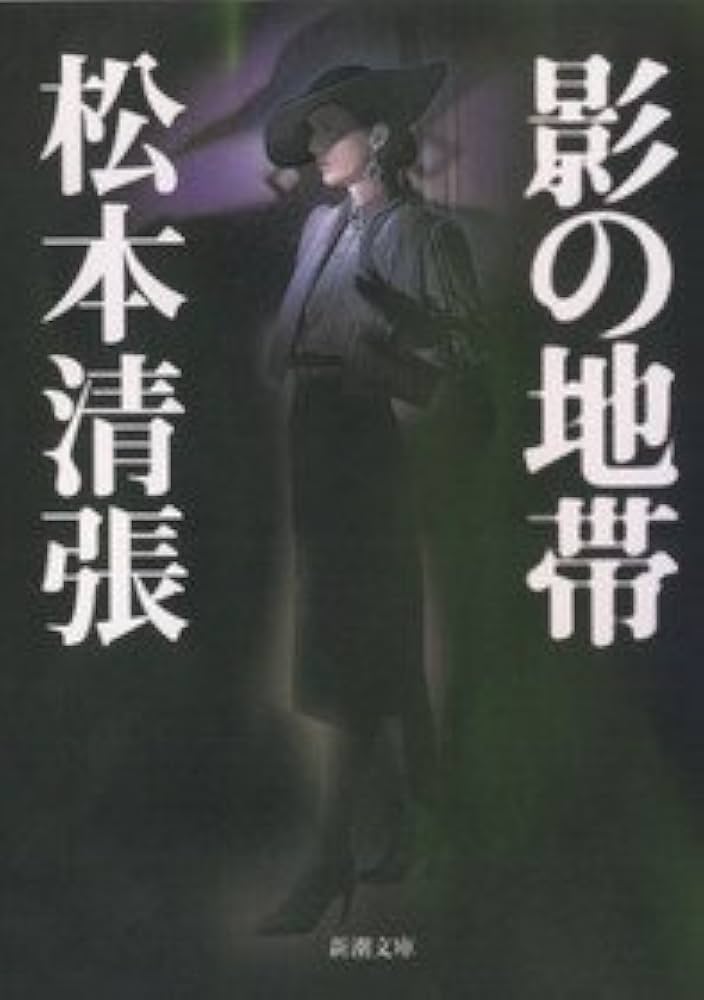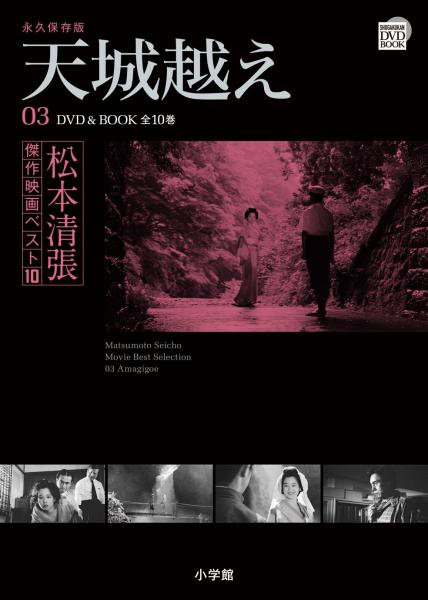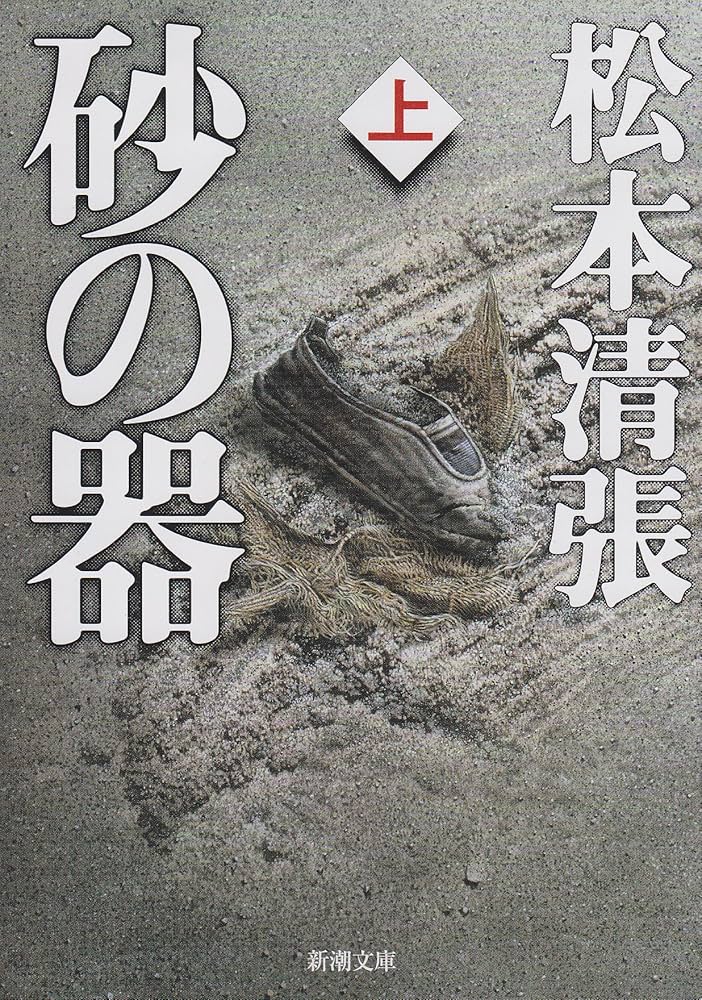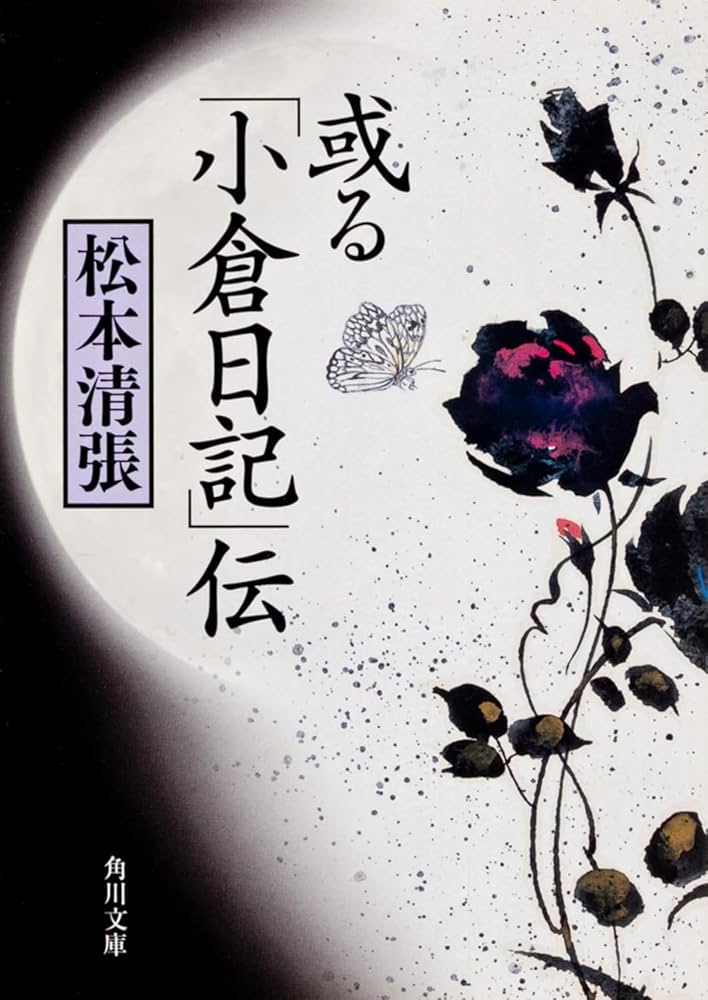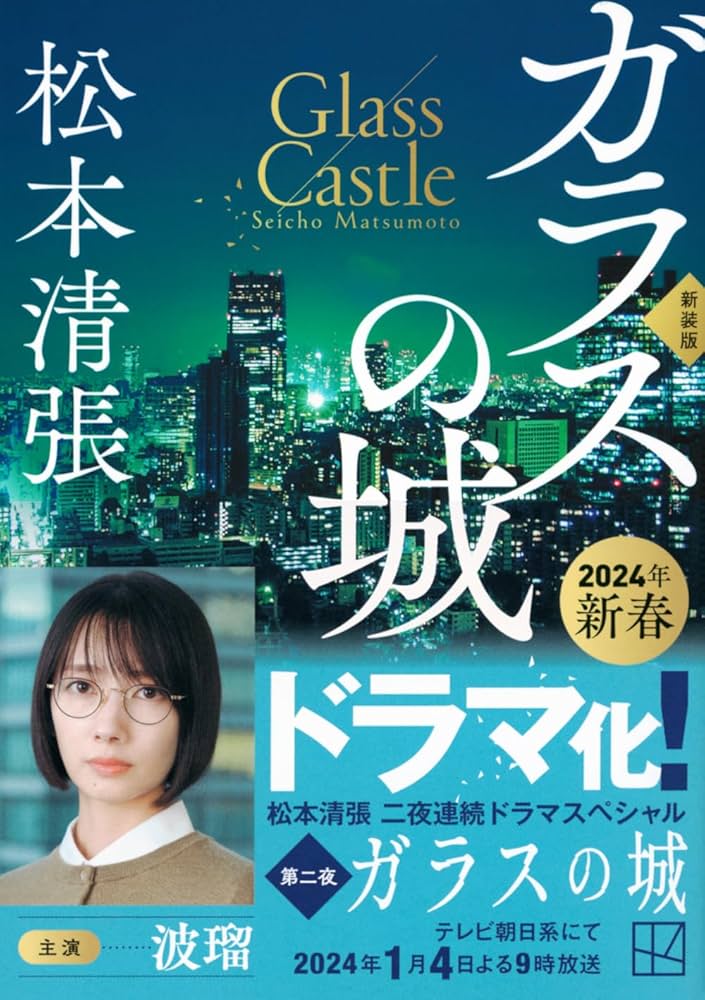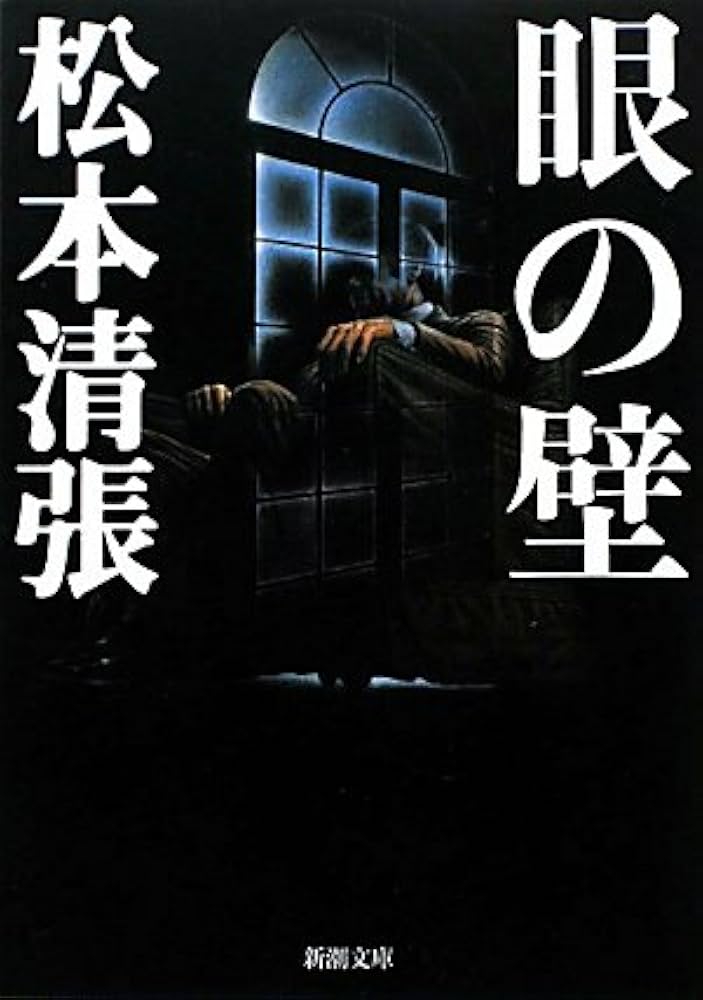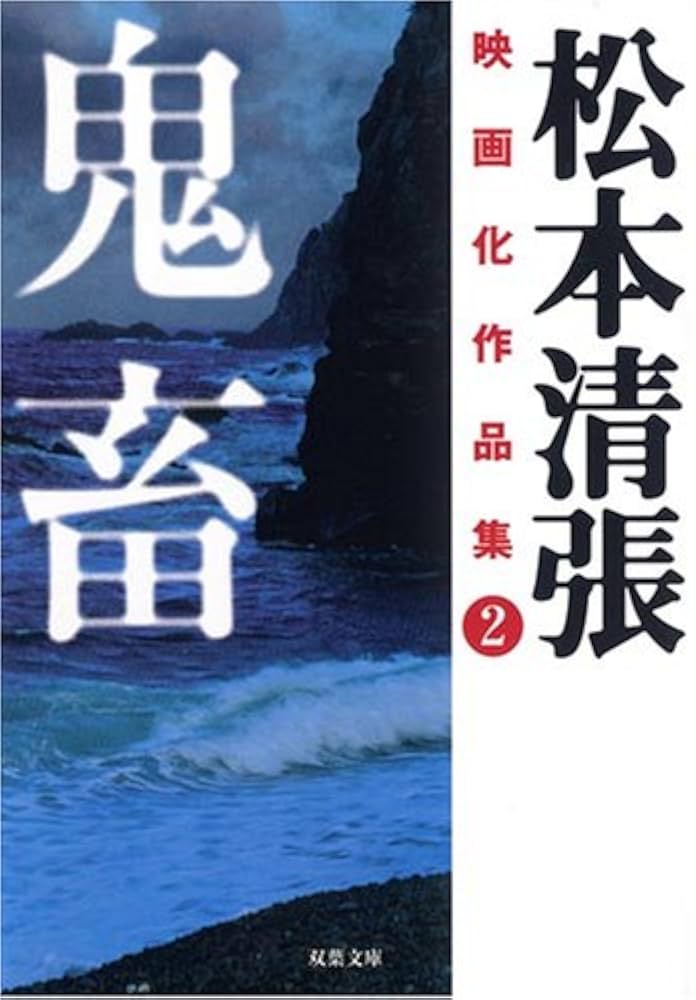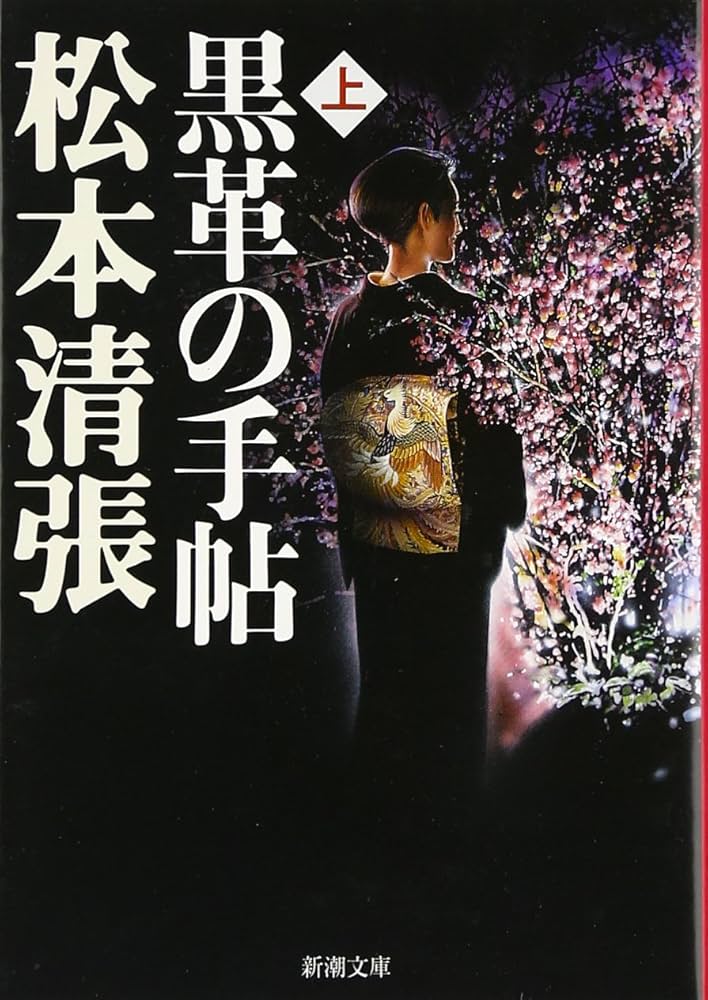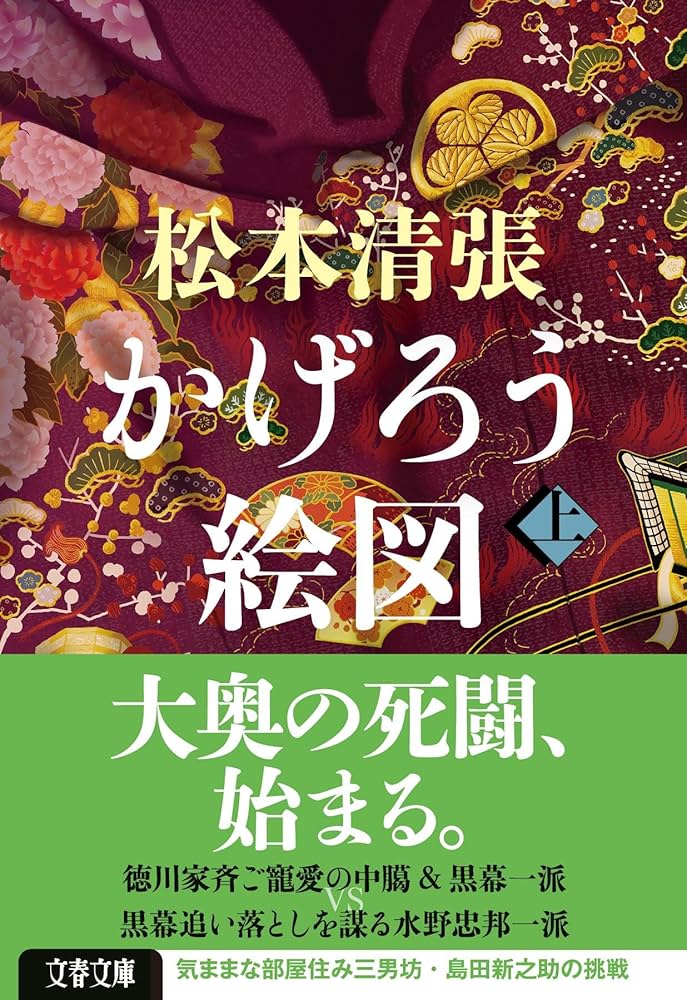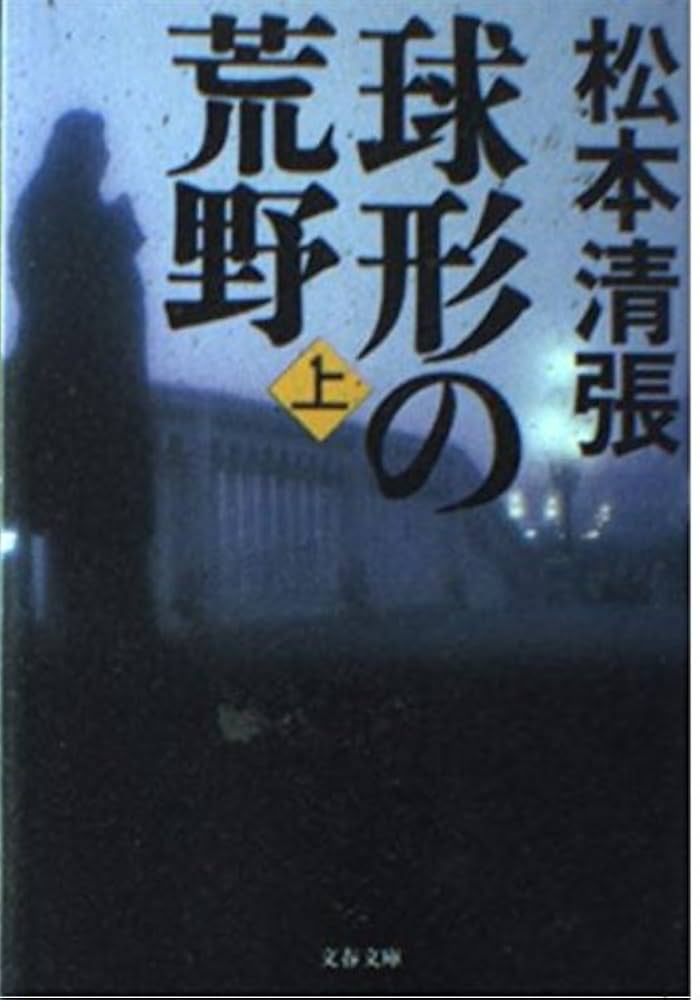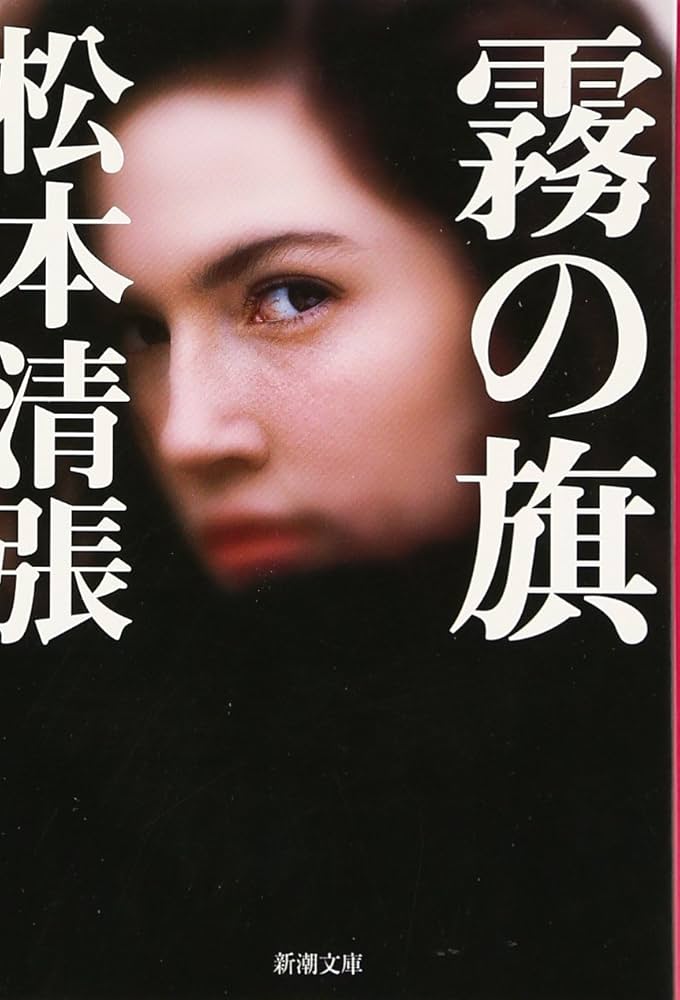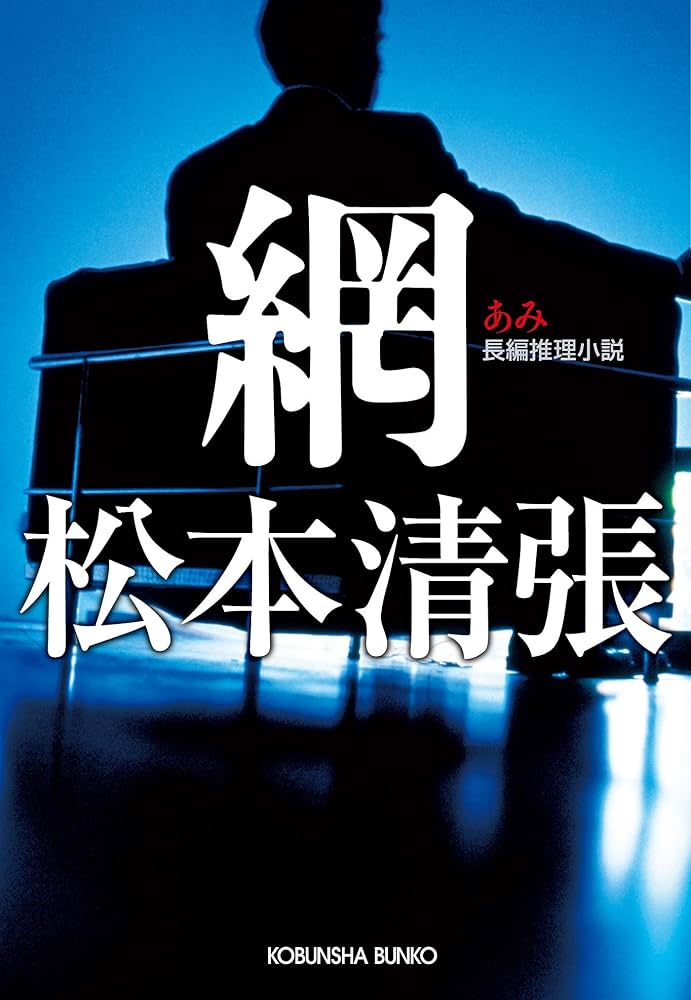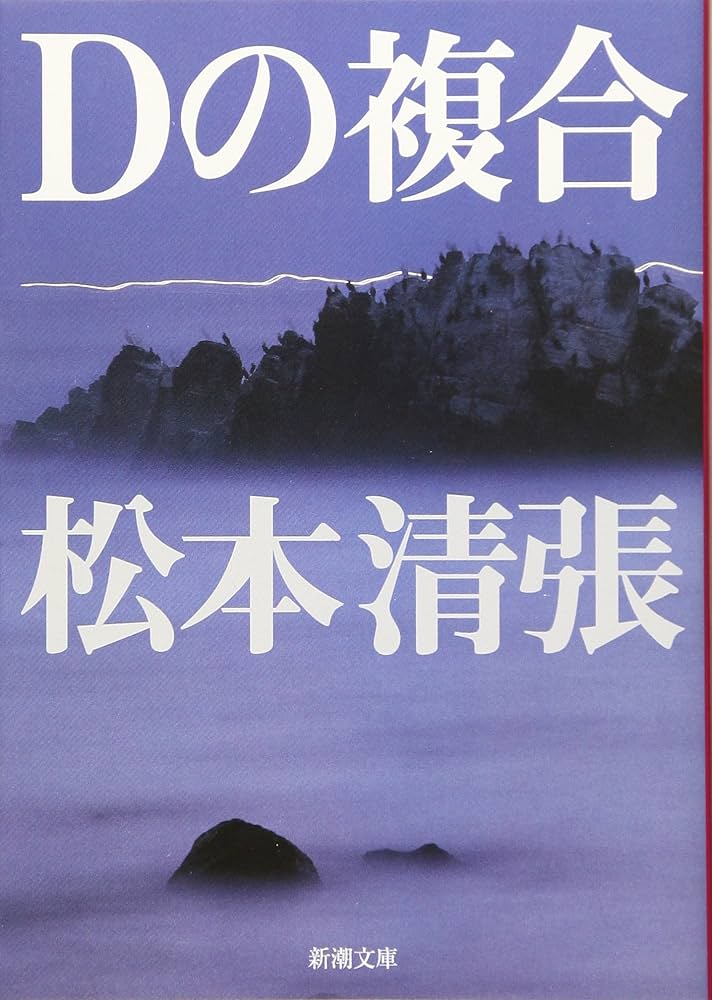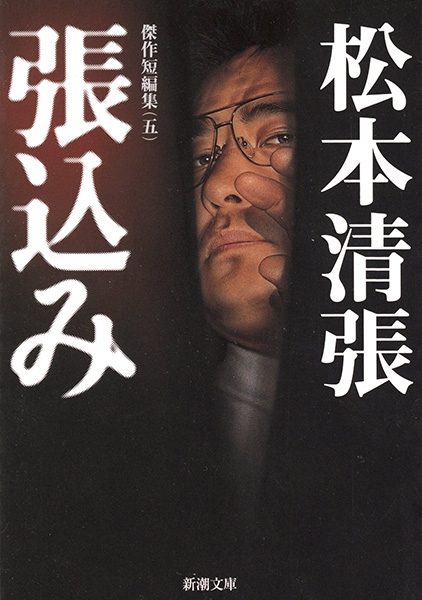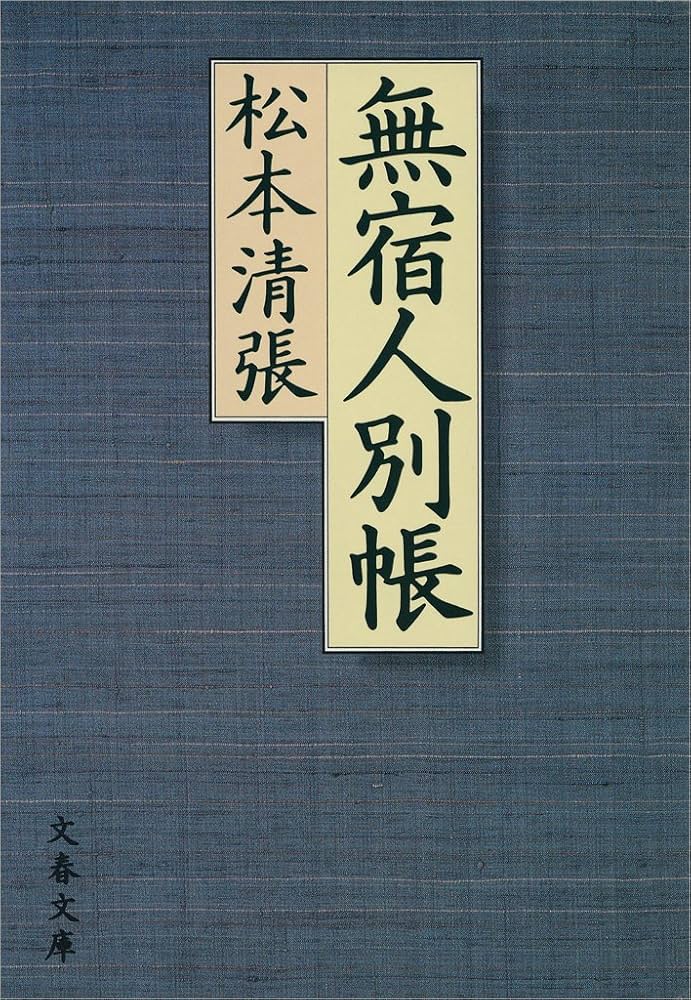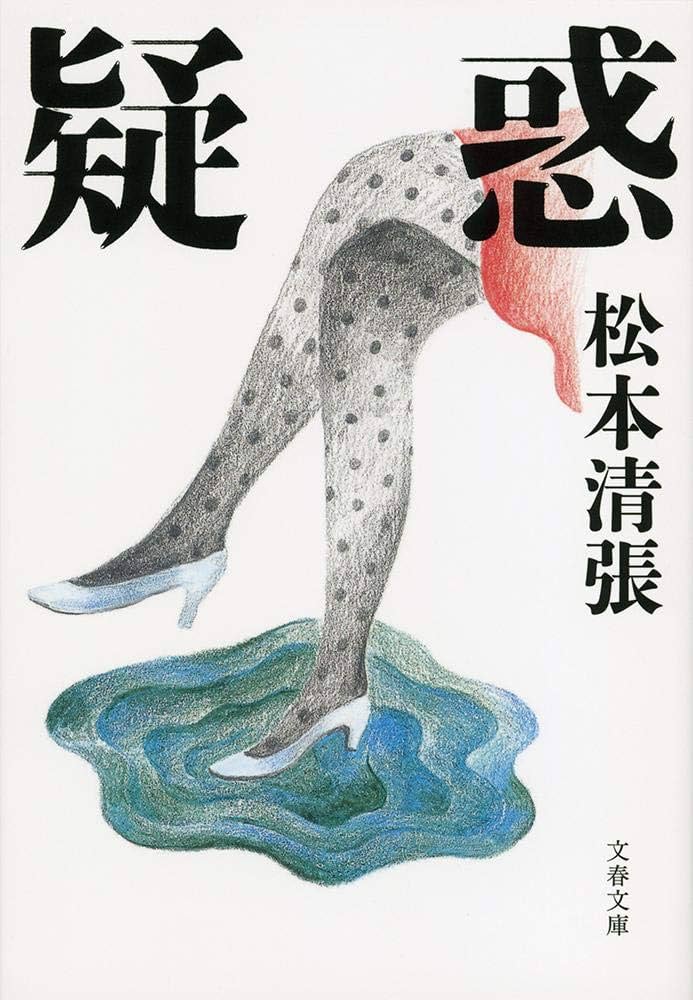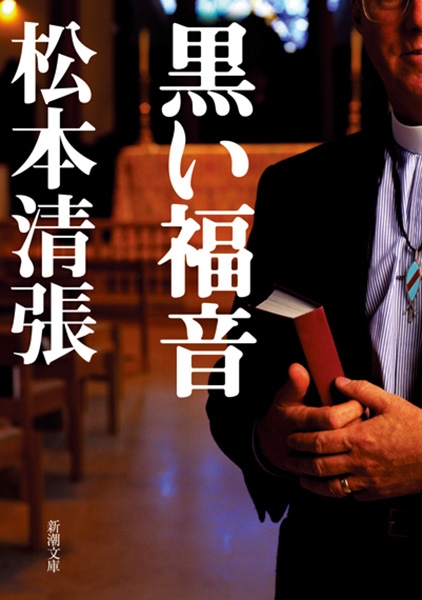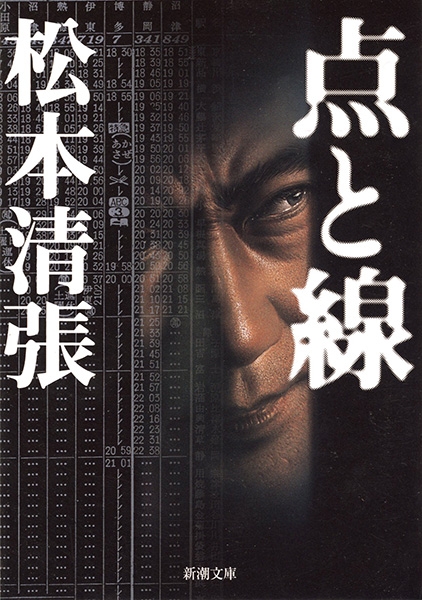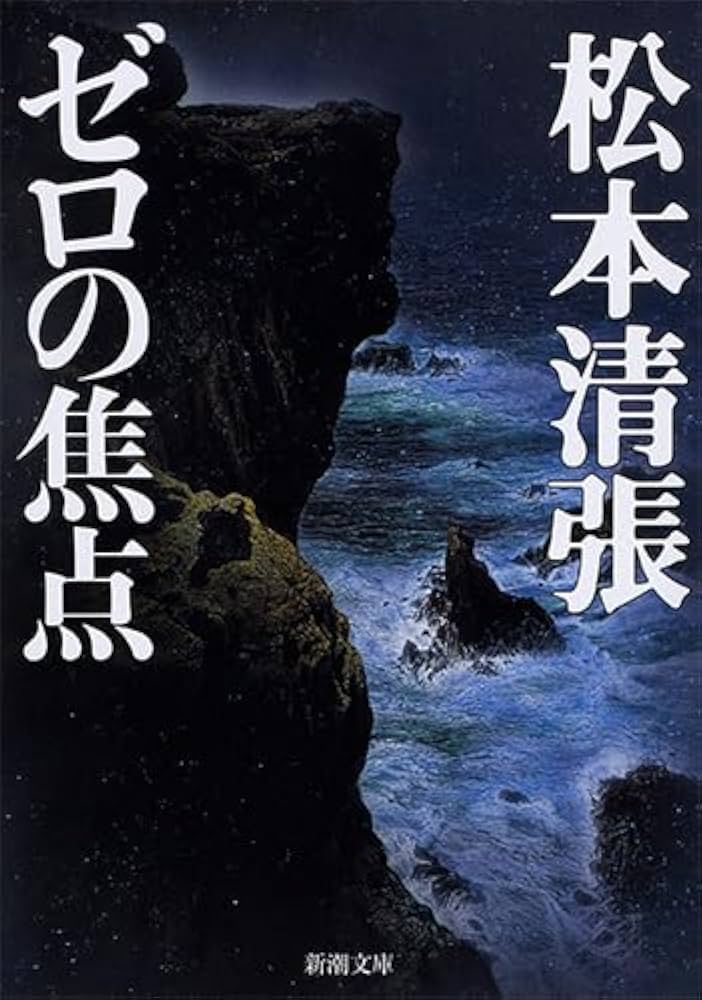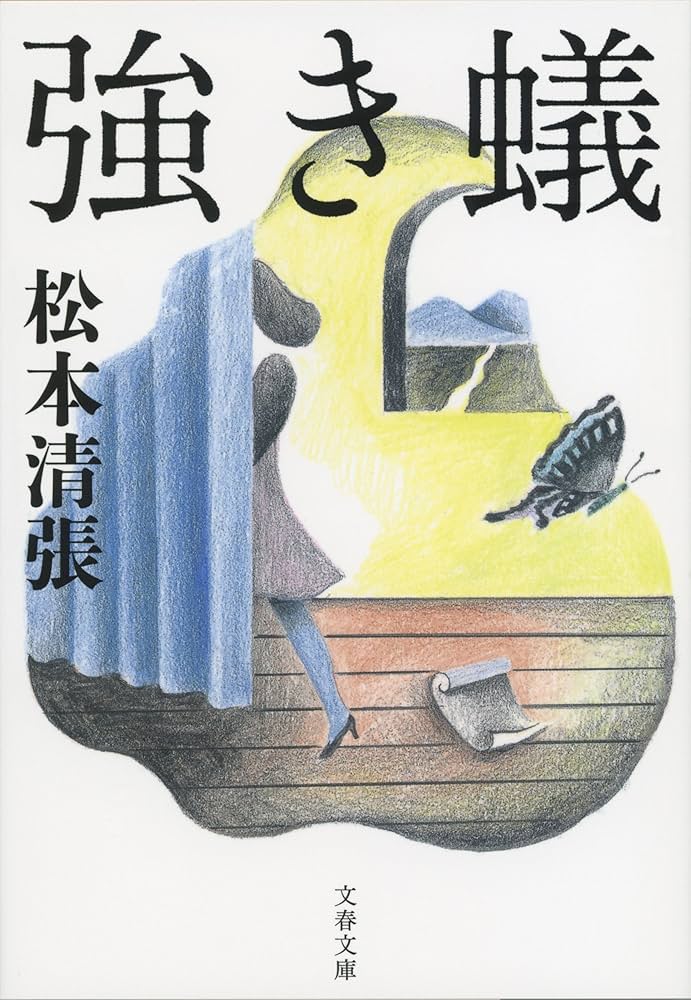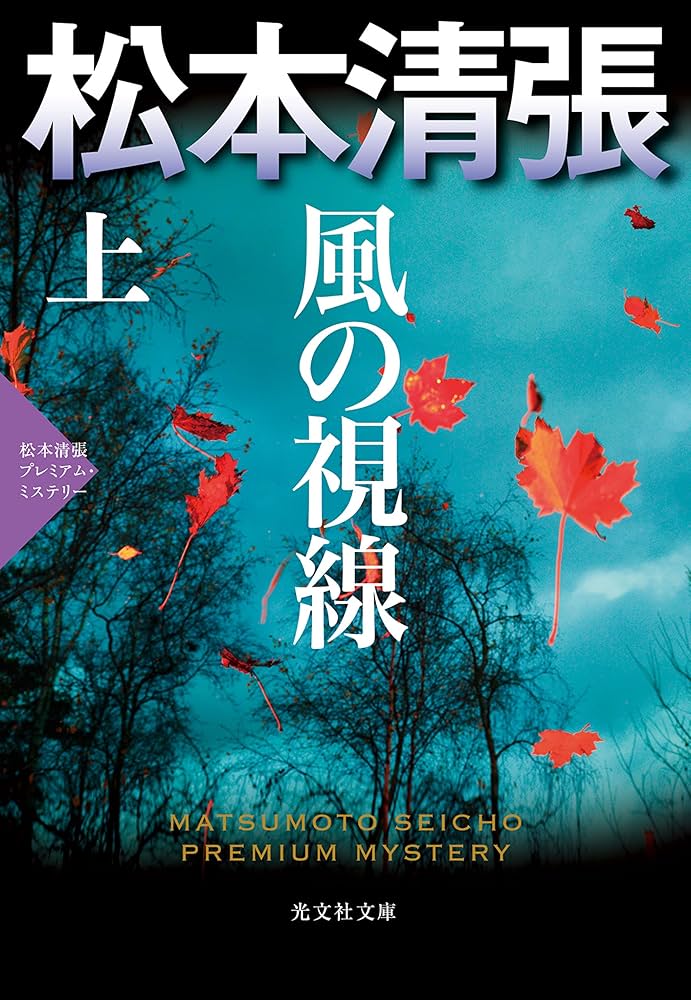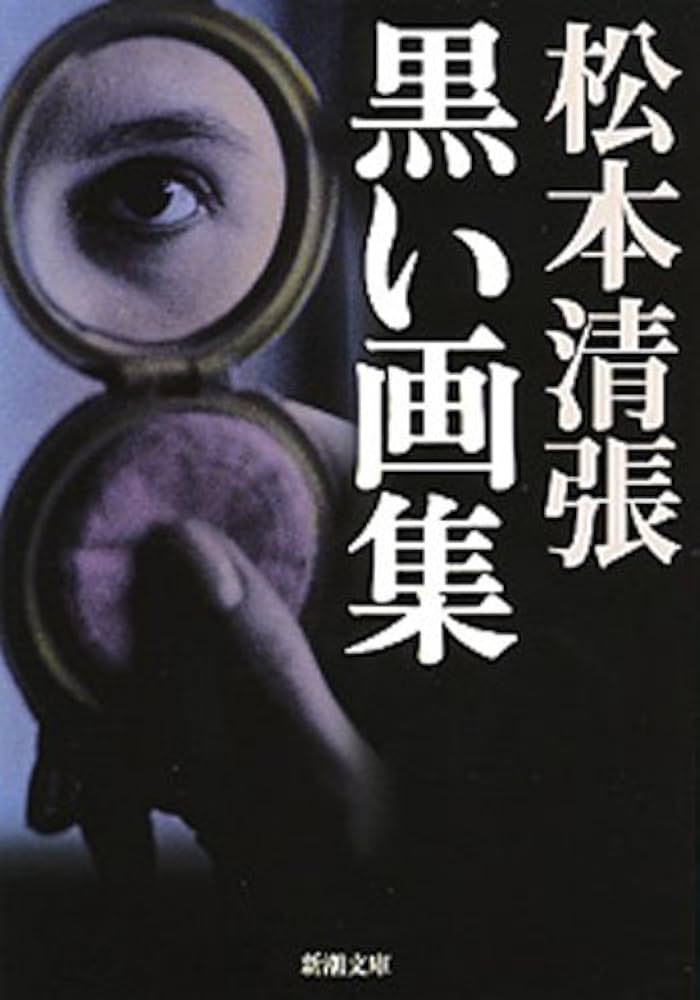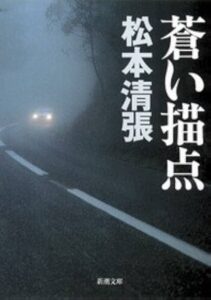 小説「蒼い描点」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「蒼い描点」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
松本清張作品の中でも、特にミステリーとしての完成度と、人間の業を描く深みにおいて、高く評価されている一作ではないでしょうか。華やかな文壇の裏に隠された欺瞞と、それに翻弄される人々の姿が鮮烈に描かれています。
物語は、単純な殺人事件の犯人捜しに留まりません。なぜ事件は起きたのか、その根源にあるのは何なのか。過去へと遡る調査の過程で、登場人物たちの複雑な人間関係と、悲しい真実が少しずつ明らかになっていく構成は見事です。特に「代作者」という存在が、物語の核心に据えられているのが大きな特徴といえるでしょう。
この記事では、まず物語の序盤から中盤にかけての展開を、結論には触れずに紹介します。その後、事件の真相や犯人、そして全ての謎が解き明かされる部分まで、詳しいネタバレを含んだ感想をたっぷりと語っていきます。
これから「蒼い描点」を読もうと思っている方も、すでに読了して物語の深い部分を考察したい方も、ぜひお付き合いいただければと思います。この傑作が持つ、抗いがたい魅力の一端に触れていただけたら幸いです。
「蒼い描点」のあらすじ
出版社の若き女性編集者・椎原典子は、人気女流作家・村谷阿沙子の遅れている原稿を受け取るため、箱根の旅館へ向かいます。阿沙子は才能ある作家として世間の注目を集めていましたが、その一方で、執筆中の姿を誰にも見せないなど、謎の多い人物でもありました。
箱根に着いた典子は、そこでうさんくさいフリーライターの田倉義三と出会います。田倉は阿沙子について「最近苦しそうだ」と意味深な言葉を残し、典子の心に小さな疑念の種を蒔きます。その後、典子は阿沙子と田倉が密会しているような場面や、阿沙子の夫が見知らぬ女性といるところを目撃し、不安を募らせていきました。
そんな矢先、事件が起こります。あの田倉が、渓谷の底で死体となって発見されたのです。警察は早々に事故として処理しますが、田倉の謎めいた言葉が忘れられない典子は、その結論を素直に受け入れることができませんでした。この出来事をきっかけに、典子の平凡な出張は、危険な謎解きの旅へと姿を変えていきます。
東京に戻った典子は、先輩編集者の崎野竜夫に事の次第を打ち明けます。すると、まるで田倉の死に呼応するかのように、阿沙子の夫、そして家の女中までもが次々と失踪。ついには、当の村谷阿沙子本人も姿を消してしまいます。あまりに不可解な連続失踪に、典子と崎野は「村谷阿沙子の作品は、すべて代作者が書いたものではないか」という大胆な仮説に行き着くのでした。
「蒼い描点」の長文感想(ネタバレあり)
「蒼い描点」を読み終えた今、心に残るのは、巧妙に張り巡らされた謎解きの面白さはもちろんのこと、その奥底に流れる人間のどうしようもない悲しさ、そして切なさです。これは単なるミステリーではなく、人間の魂の物語なのだと感じています。
この物語の魅力は、何よりもその構成の巧みさにあります。序盤、箱根という閉鎖的でありながら開かれた観光地を舞台に、怪しげな人物たちが交錯し、不穏な空気が醸成されていく様は見事でした。読者は主人公の典子と共に、何が起きているのか分からないまま、ただただ渦中に引きずり込まれていきます。
そして起きる田倉の死。警察が「事故」と結論づけるのは、ミステリーの定石ではありますが、これにより「警察が見過ごした真実を、素人である典子が探求する」という構図が生まれます。ここから、物語は一気に加速していくのです。
私が特に引き込まれたのは、「代作者」という仮説が浮上する展開です。村谷阿沙子という華やかな存在そのものが、実は空っぽの虚像だったのではないか。この疑念が、単なる殺人事件の捜査を、文壇という世界の根幹を揺るがす巨大な不正の告発へと昇華させています。
さらに物語を複雑にしているのが、典子たちの上司である編集長・白井の存在です。彼は二人の調査を後押しするように見せかけながら、実は巧みに情報をコントロールし、二人を操っている節があります。彼こそが黒幕なのではないか、という疑念が常に付きまとい、物語に一層の緊張感を与えていました。彼の存在は、読者を惑わすための見事な仕掛けだったと思います。
物語の中盤からは、トラベルミステリーの様相を呈してきます。典子と崎野が、秋田や犬山といった日本各地を巡り、過去の断片を拾い集めていく過程は、本当に骨の折れる地道な調査です。現代のようにインターネットで簡単に情報が手に入る時代ではないからこそ、一つ一つの発見に重みがあり、読者も彼らと共に旅をしているような感覚に陥ります。
そして、この過去への旅こそが、「蒼い描点」の核心に迫る道でした。事件の根源は、現代に起きた殺人事件ではなく、阿沙子の亡き父である学者・宍戸寛爾を中心とした、過去の人間関係の中にあったのです。この時間軸を遡る構成が、物語に圧倒的な奥行きを与えています。
ここで浮上する「よし子」という謎の人物。彼女こそが事件の鍵を握る人物だと分かるのですが、その正体はなかなか掴めません。情報が錯綜し、読者も典子たちも混乱させられます。しかし、この「よし子という人物を、誰もが勘違いしていた」という事実こそが、この物語最大のどんでん返しであり、全ての謎を解く鍵でした。この仕掛けには、本当に驚かされました。
さて、ここからが核心的なネタバレになります。村谷阿沙子として世に出ていた女性は、実は本物の才能を持つ「よし子」が作り上げた偶像でした。彼女はいわば女優であり、天才的な代作者である「よし子」の影武者に過ぎなかったのです。
そして、田倉を殺害した犯人は、この代作者である「よし子」を深く愛し、彼女の世界を守ろうとした人物でした。田倉は、代筆の事実だけでなく、代作者の悲劇的な過去と正体までをも突き止め、二人を脅迫しようとしたのです。だからこそ、犯人は口封じのために彼を殺害する必要がありました。
その殺害方法もまた、巧妙でした。箱根の複雑な道路網や、旅館のケーブルカーといった地理的特徴を最大限に利用したアリバイトリック。これはまさに、松本清張作品の真骨頂といえるでしょう。犯行の動機が金銭や名声ではなく、「男女の愛憎」と、愛する者を守りたいという絶望的な「庇護」の感情にあったという点も、物語に悲劇的な深みを与えています。
犯人の行動は許されるものではありません。しかし、その背景にある、あまりにも痛切な愛情を知ると、単純に断罪できない気持ちにさせられます。これこそが、松本清張作品が持つ人間描写のリアリズムなのだと思います。
では、読者を悩ませた数々の失踪事件は何だったのか。これも見事なミスディレクションでした。夫の失踪は不倫と金銭問題からの逃避、女中の失踪は全くの私的な理由。そして阿沙子本人の失踪は、嘘で固めた世界が崩壊し始めたことへのパニック反応。殺人とは全く無関係だったのです。複数の事件を同時に起こすことで、あたかも巨大な陰謀が進行しているかのように見せかける手腕には、舌を巻くほかありません。
そして最後に明かされる、編集長・白井の真意。彼もまた、過去の因縁に縛られた一人でした。彼は、亡き宍戸寛爾に恩義があり、その周囲で起きた悲劇の真実が、歪んだ形で葬り去られるのを良しとしなかったのです。自らの手は汚さず、部下である典子たちを駒として使い、事件を操ることで、長年埋もれていた真実を白日の下に晒そうとした。彼の「複雑な事情」とは、この古く、根深い個人的な因縁だったのです。
この物語は、「村谷阿沙子」という一つの虚構を守るために、多くの人々が動き、そして悲劇が生まれる話です。しかし、その虚構は、本物の代作者「よし子」にとっては、自らの才能を発揮し、生きていくための唯一の術でもありました。創造(代筆)を守るための破壊(殺人)。この二元性が、物語をより一層複雑で味わい深いものにしています。
小説のタイトルである「蒼い描点」。この意味が最後に明かされた時、私は深く納得しました。「描点」とは、代筆によって描かれた偽りの作品であり、事件の真相を示すたった一つの点。そして「蒼い」という言葉は、その点に残された悲しみや未熟さ、そして悲劇の痕跡を象徴しているのでしょう。嘘というキャンバスに滲み出てしまった、あまりにも悲しい真実の一滴。それこそが「蒼い描点」だったのです。
事件の終結は、決して明るいものではありませんでした。しかし、この過酷な謎解きの旅を通して、典子と崎野の間に確かな絆と愛情が芽生えたことは、唯一の救いでした。嘘の上に築かれた破壊的な関係とは対照的に、真実の探求の上に築かれた彼らの純粋な繋がりが、暗い物語の最後に一条の光を灯してくれているように感じました。
まとめ
松本清張の「蒼い描点」は、単なるミステリー小説の枠を超えた、人間の業と悲劇を描く傑作です。華やかな文壇の裏に隠された「代作者」という秘密を軸に、物語は二転三転し、読者を最後まで惹きつけます。
この記事では、序盤のあらすじから、事件の核心に触れるネタバレまでを詳しく解説しました。箱根を舞台にした巧みなトリック、過去の因縁が現在に影を落とす壮大な構成、そして登場人物たちの心理描写の深さは、さすが松本清張作品と言わざるを得ません。
特に、「よし子」という人物の誤認が全ての鍵を握るというどんでん返しと、犯行動機の根底にある悲しい「愛憎」は、読後に深い余韻を残します。この物語は、犯人を当てること以上に、なぜ悲劇が起きてしまったのかを考えさせられる作品です。
「蒼い描点」は、巧妙なプロットと深い人間ドラマが融合した、読み応えのある一冊です。この記事が、作品の魅力を再発見したり、新たな視点を得たりする一助となれば幸いです。ミステリー好きならば、必読の作品だと断言できます。