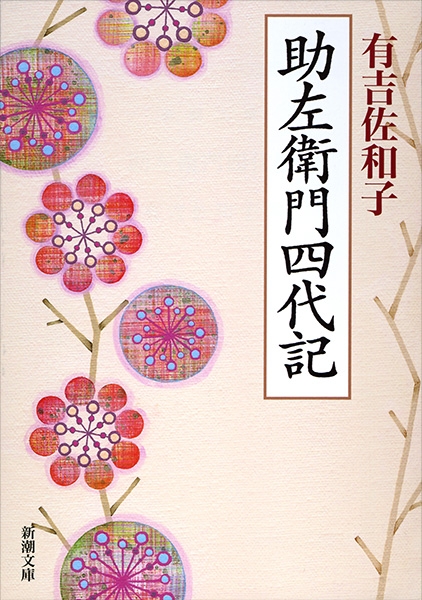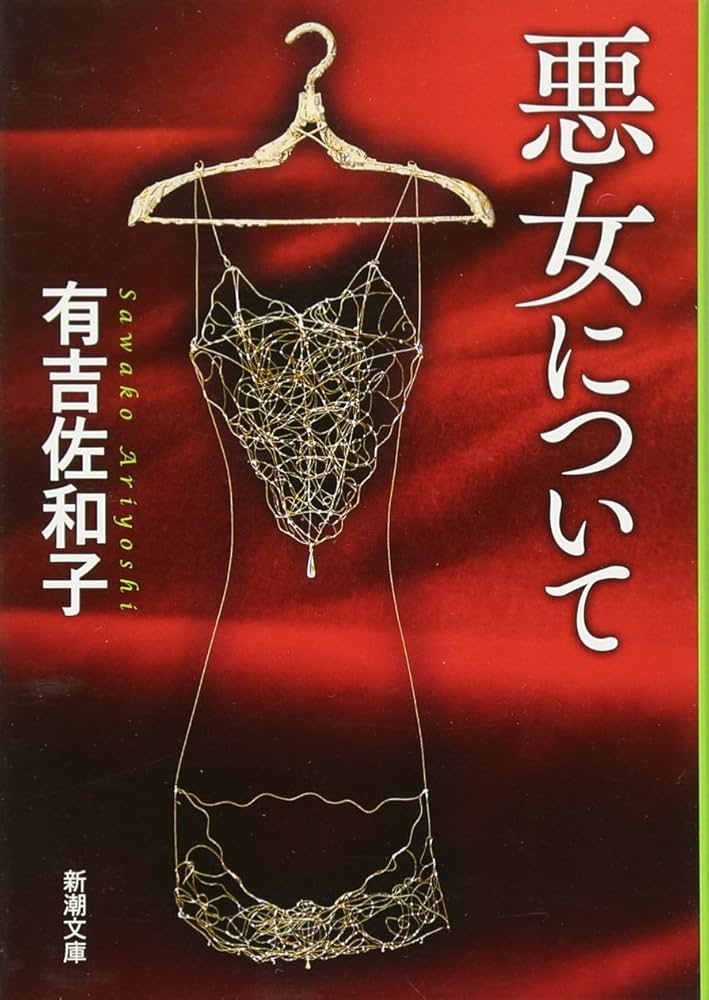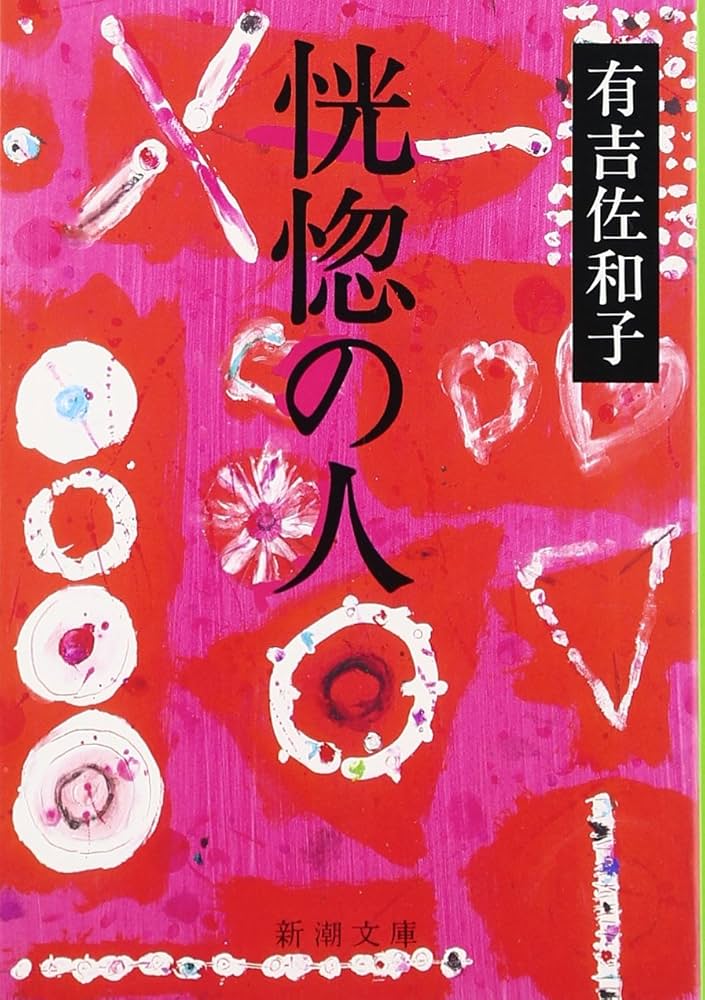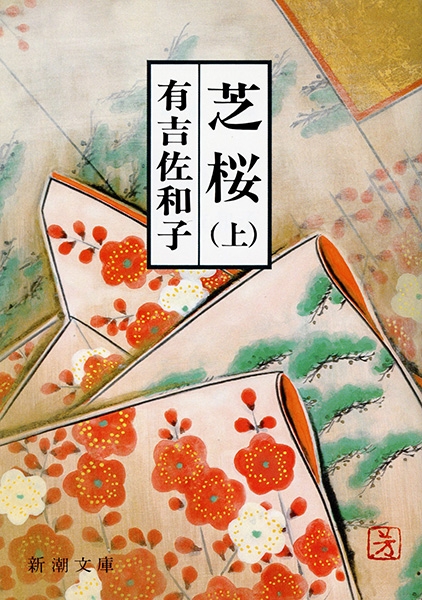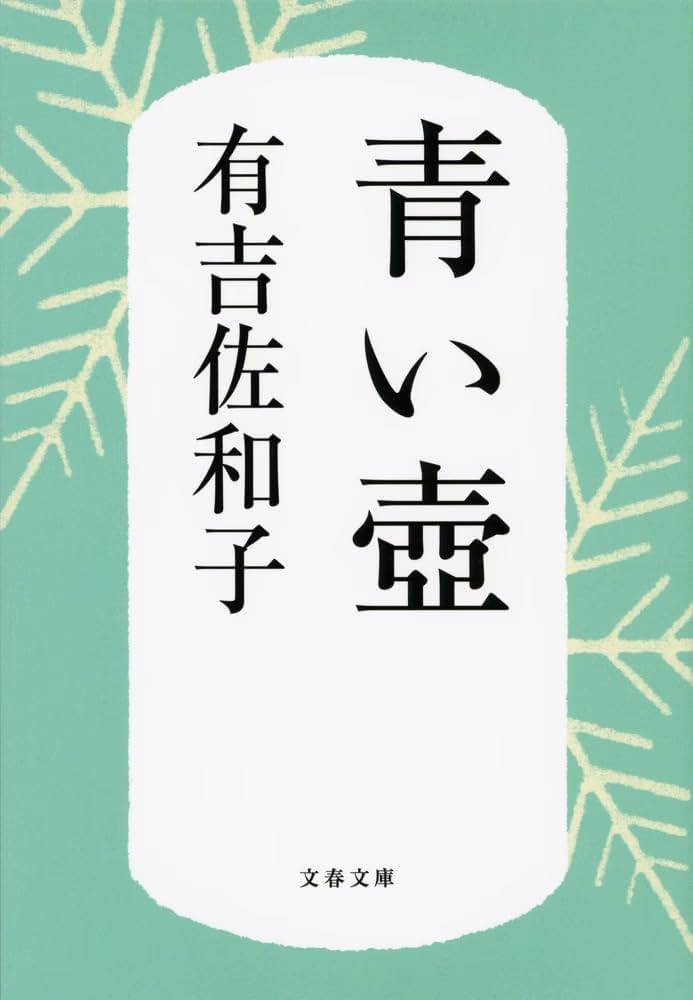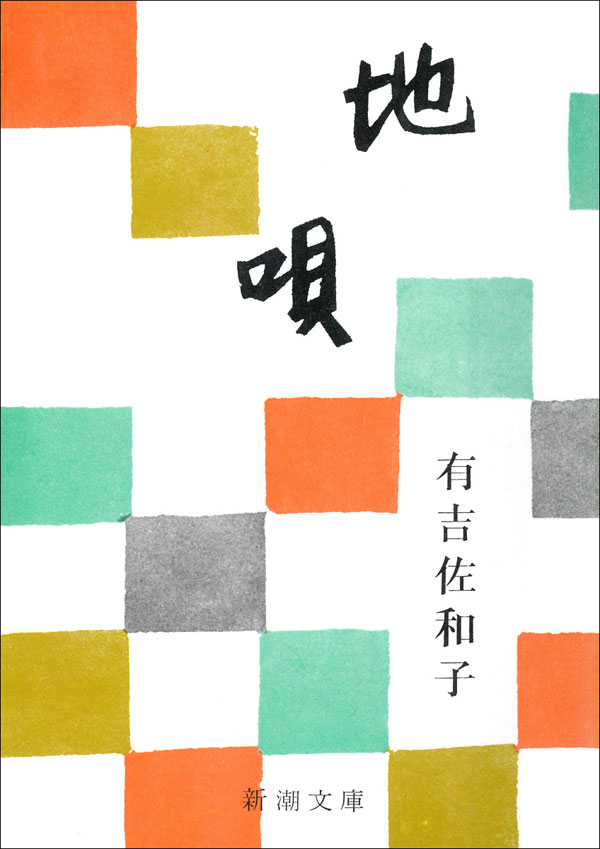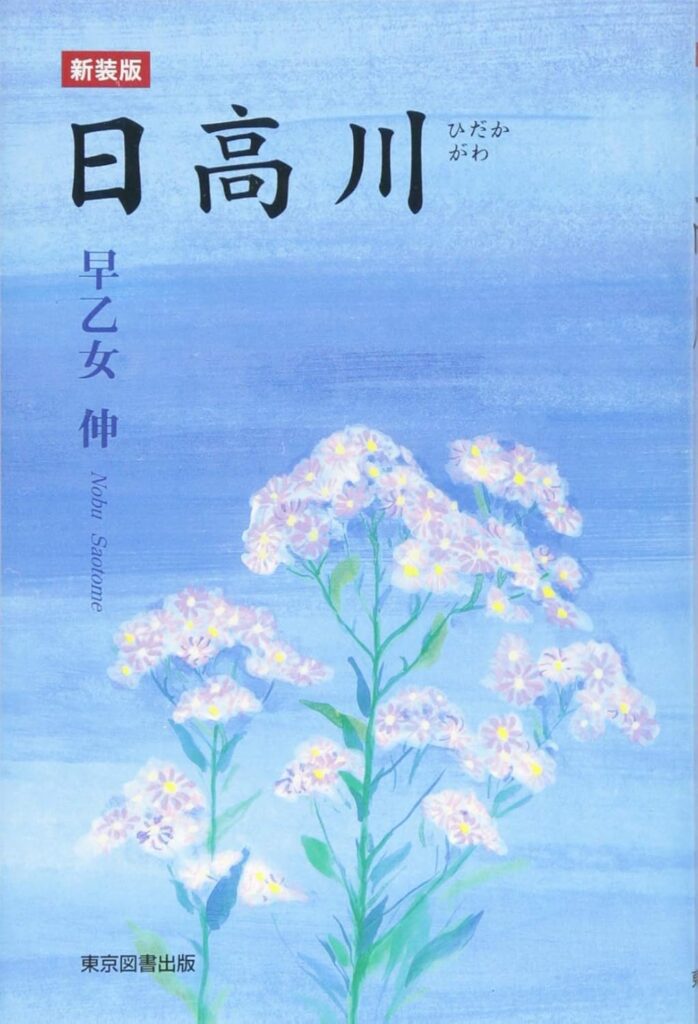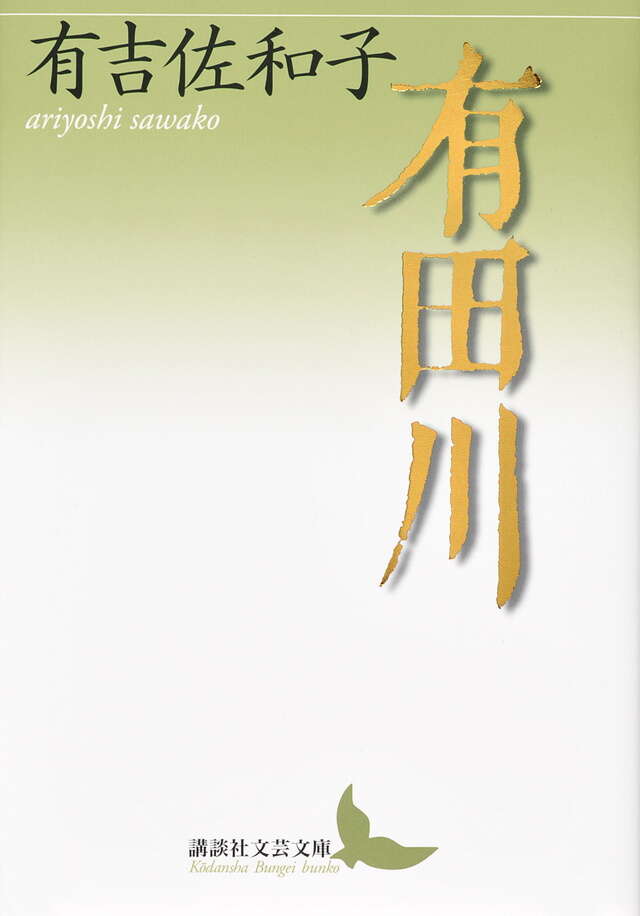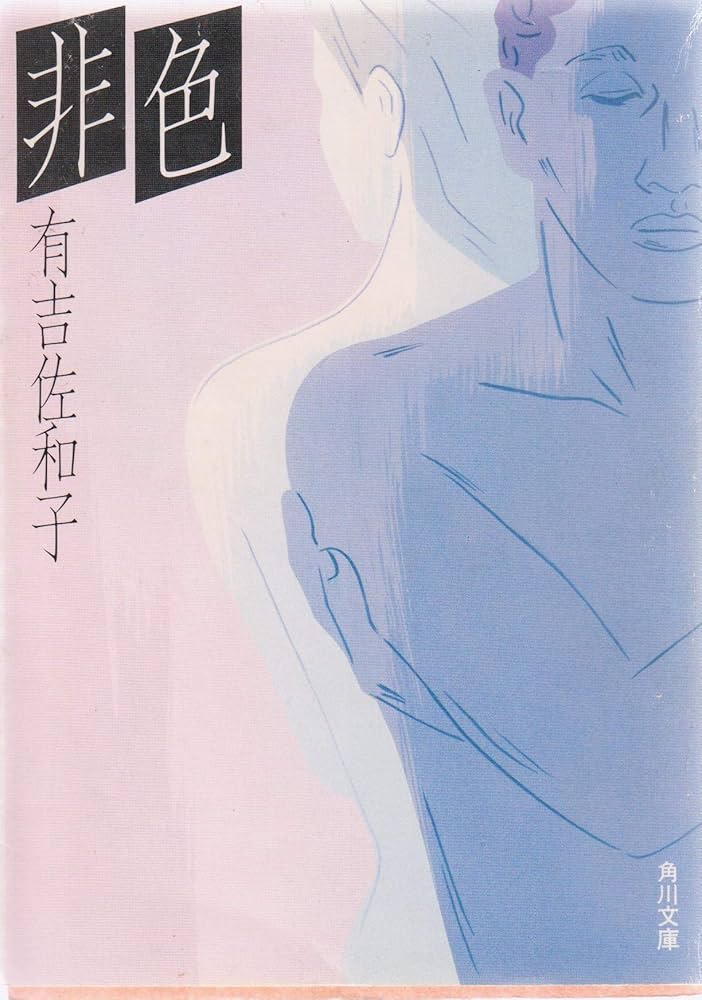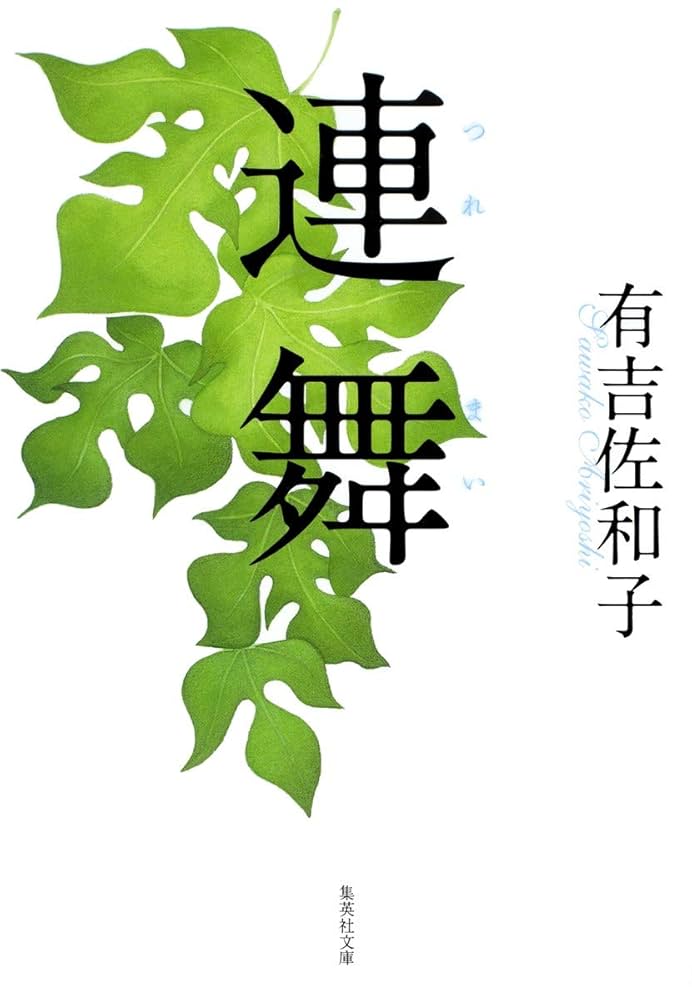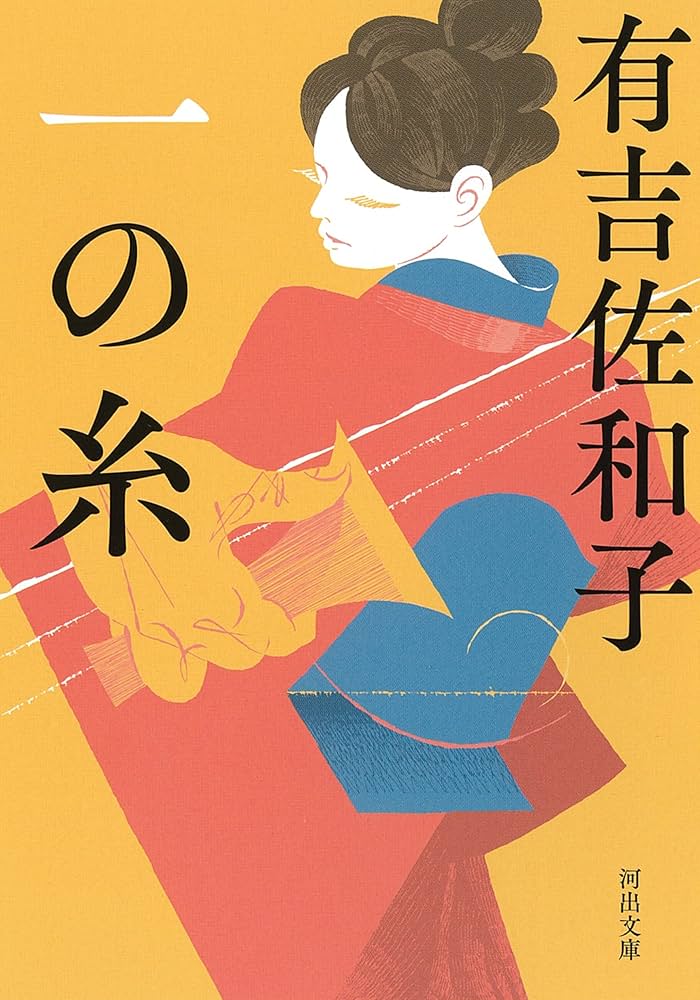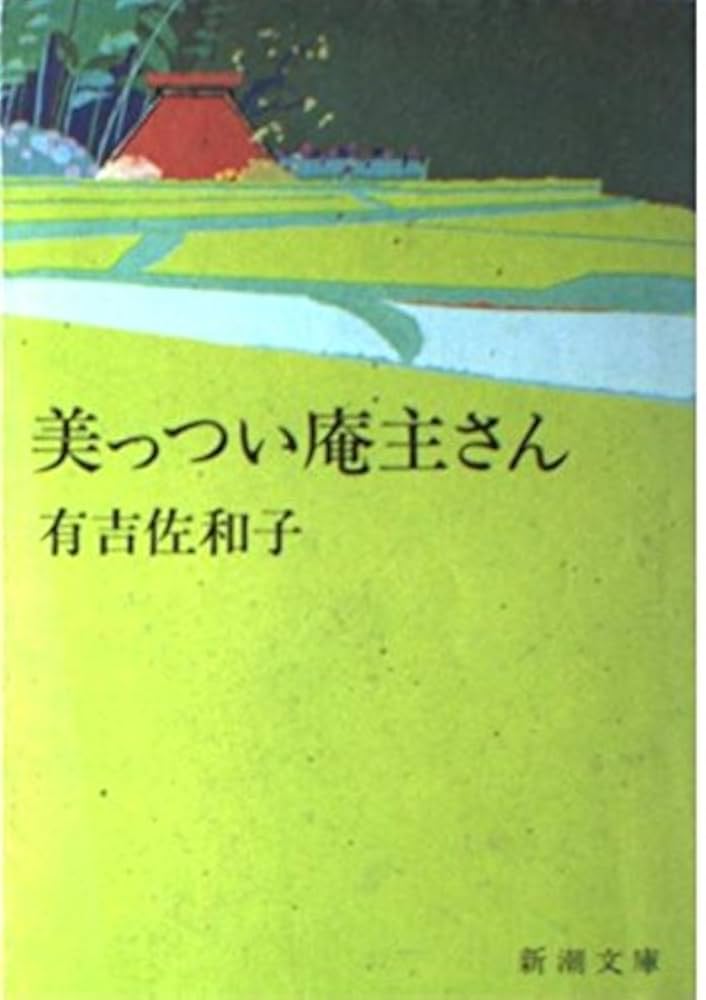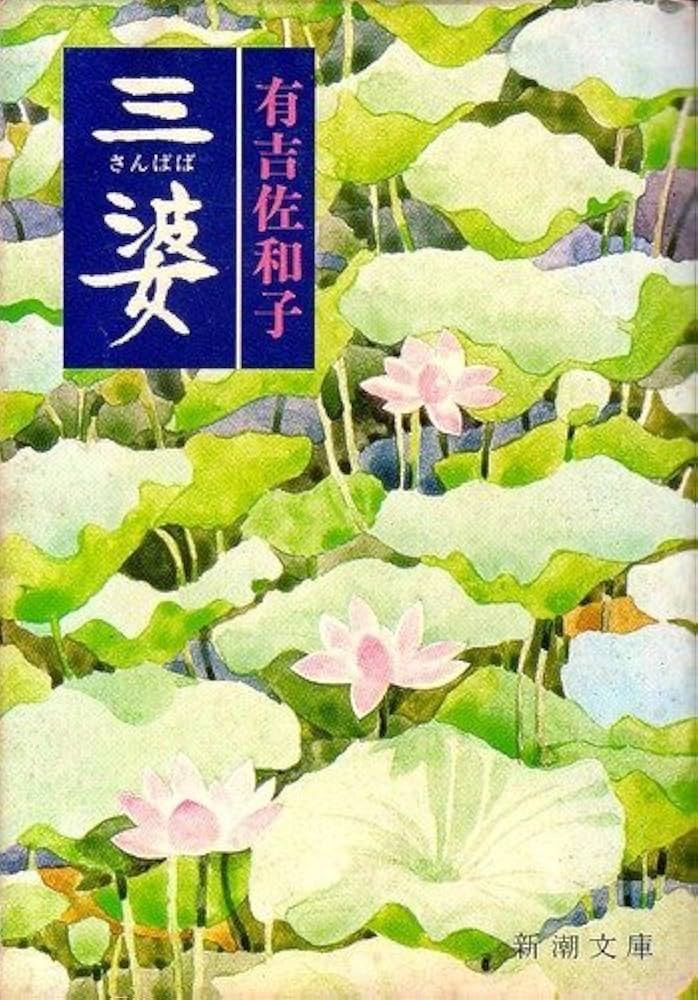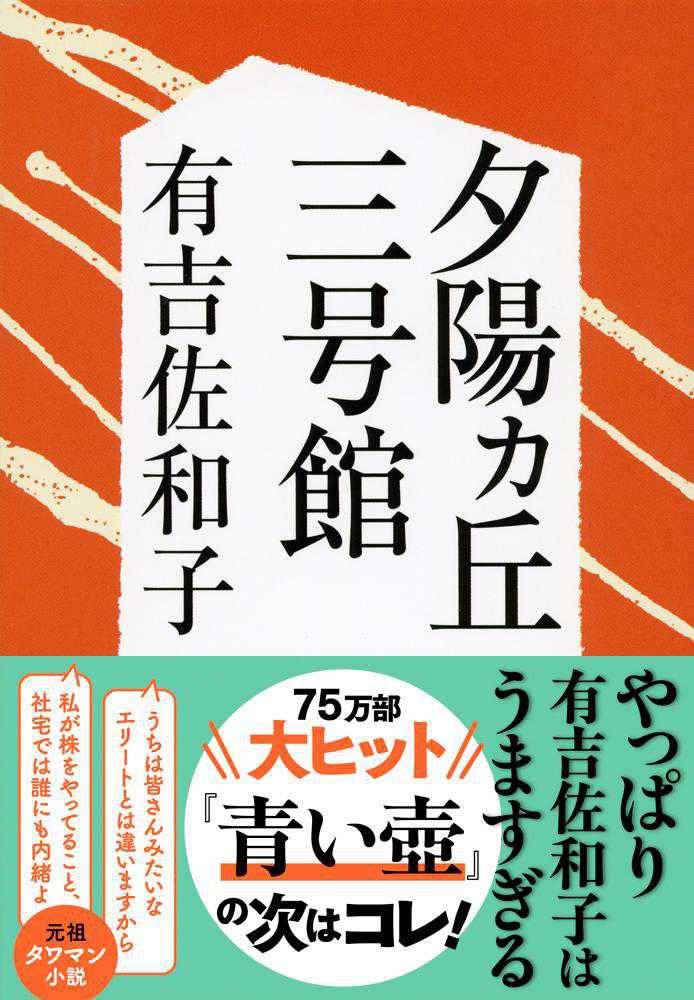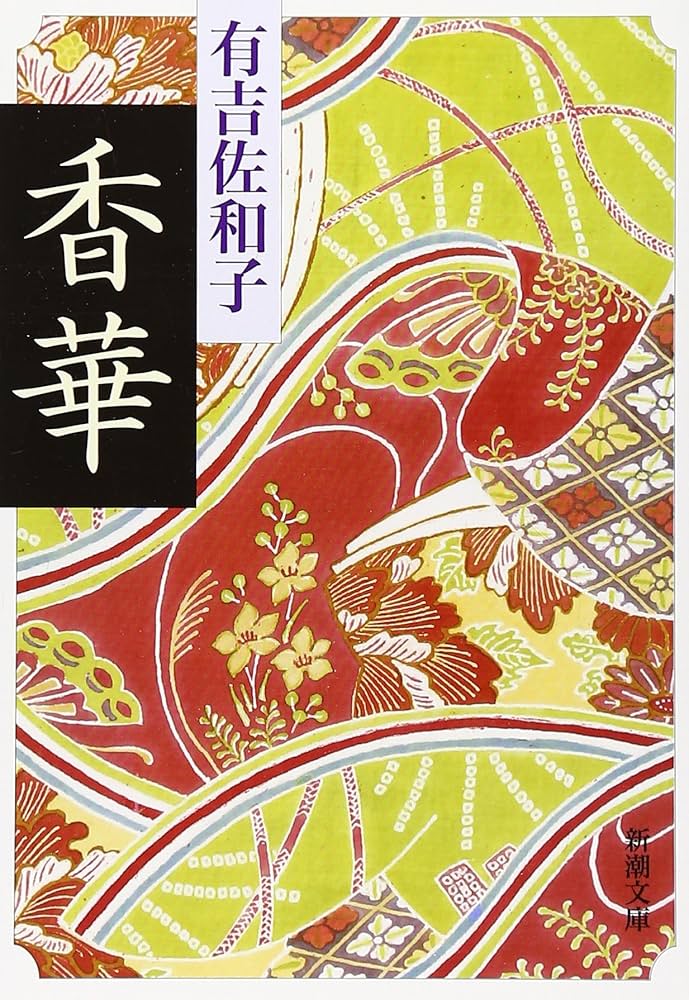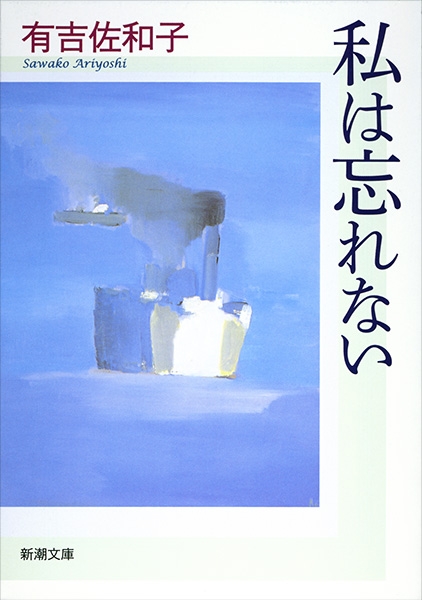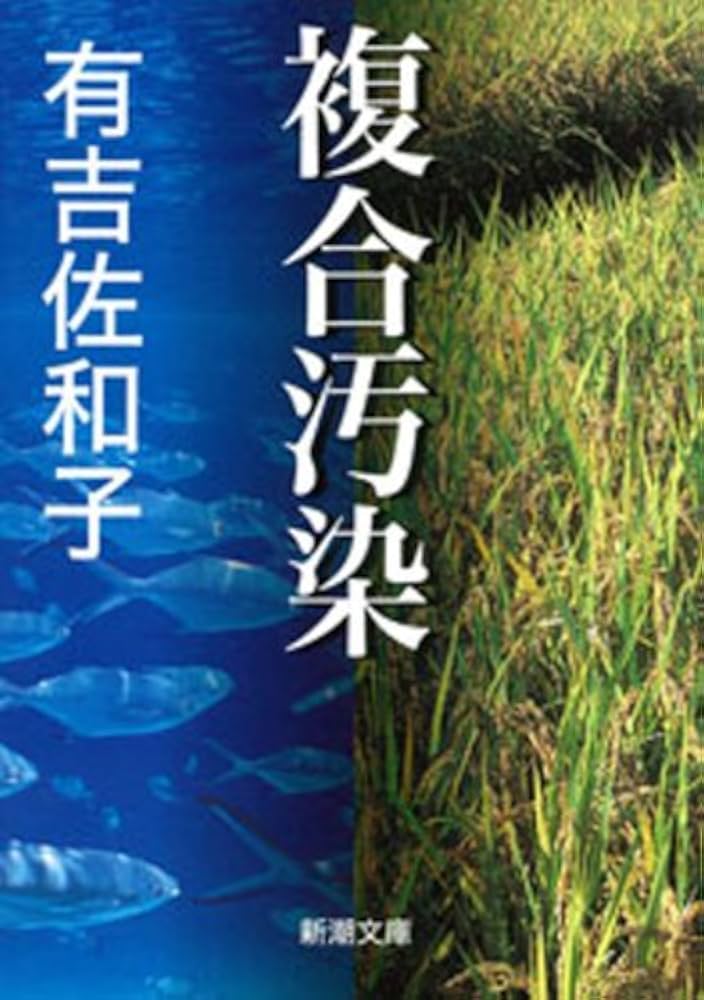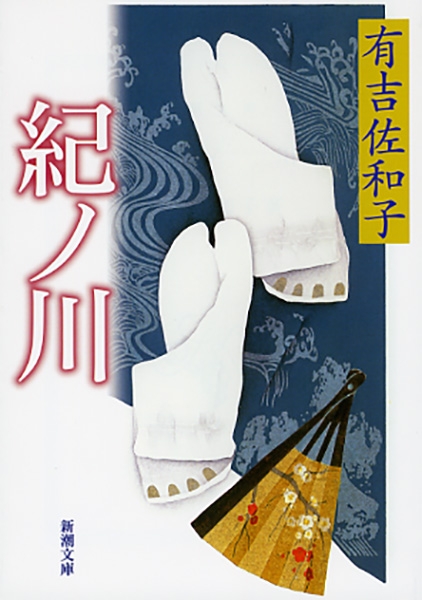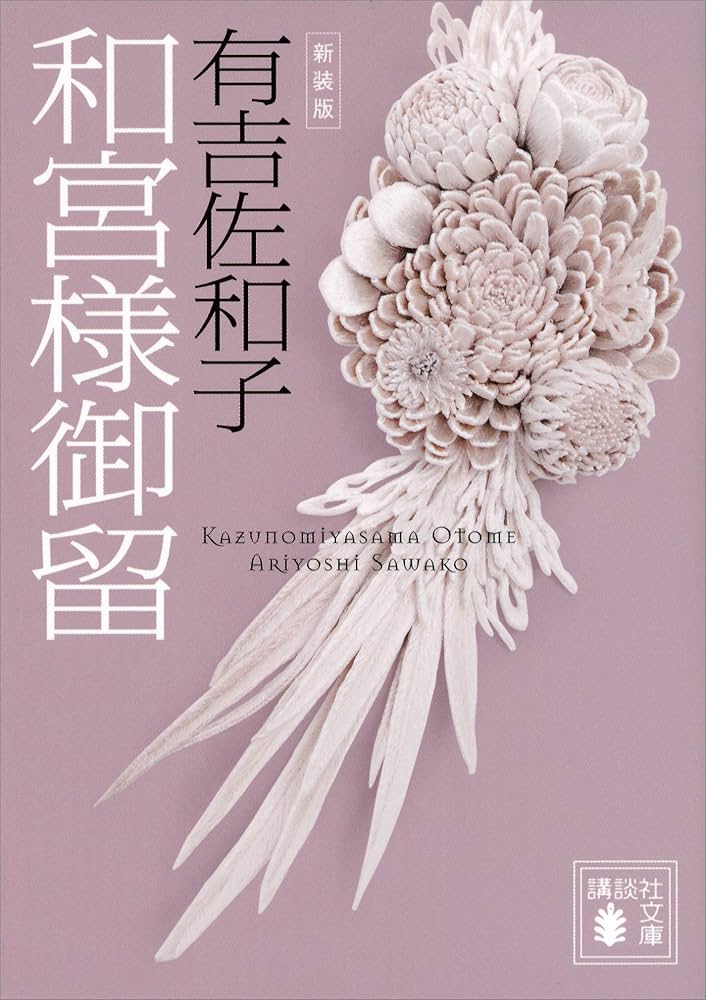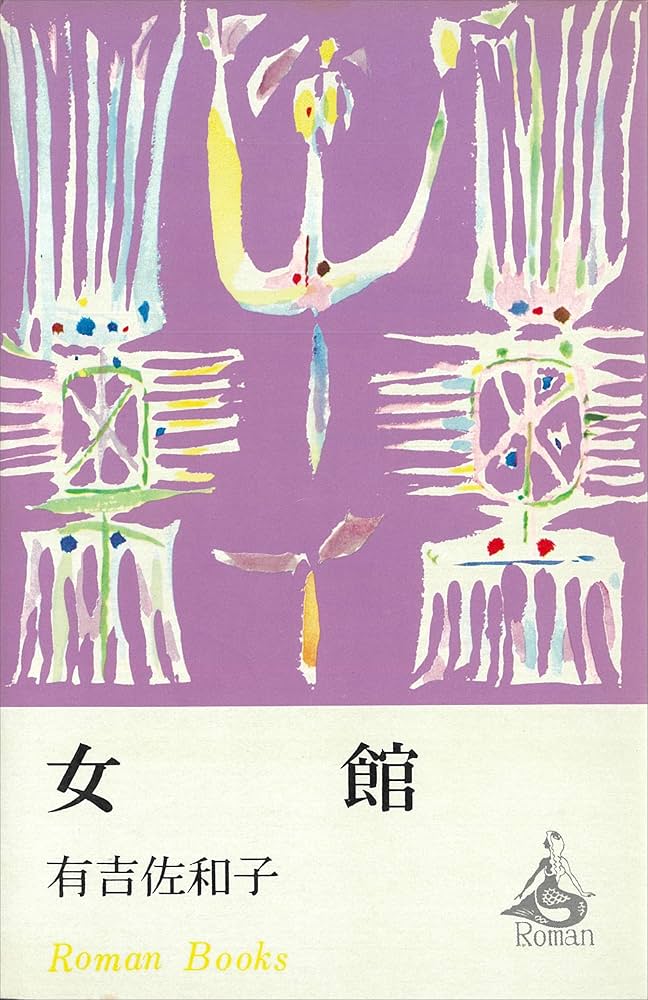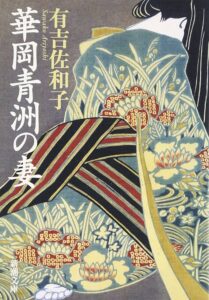 小説『華岡青洲の妻』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説『華岡青洲の妻』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
有吉佐和子先生の不朽の名作『華岡青洲の妻』は、読み終えた後も長く心に残る一冊です。この作品は、世界で初めて全身麻酔による乳がん手術を成功させた外科医・華岡青洲の偉業を支えた二人の女性、すなわち彼の母・於継と妻・加恵の壮絶な生き様を描いています。単なる歴史物語にとどまらず、封建社会における女性の立場、そして人間が持つ普遍的な愛憎が織りなすドラマは、読む者の胸を強く打ちます。
幕末の激動期、医学界に新たな光をもたらそうと奮闘する青洲。その陰には、彼を支えようとする二人の女性の、あまりにも激しい献身と対立がありました。母としての深い愛情、妻としての純粋な慕情、それらが入り混じり、時には憎しみにも似た感情へと変貌していく様は、まさに人間心理の深淵を覗き見ているようです。
読者は、彼女たちの葛藤を通して、「愛とは何か」「自己犠牲とは何か」という根源的な問いと向き合うことになります。表面的な美談の裏に隠された生々しい感情のぶつかり合いは、時代を超えて現代にも通じる普遍的なテーマを私たちに提示してくれるでしょう。
本作が描くのは、単なる歴史上の出来事ではありません。それは、一人の天才を巡る女性たちのドラマであり、同時に、個人の尊厳が「家」という大きな枠組みの中でどのように揺れ動くかを示唆する物語でもあります。
『華岡青洲の妻』のあらすじ
物語は、紀州の片田舎に暮らす少女、加恵の幼少期から幕を開けます。彼女は、医者の家系である華岡家の長男・雲平(後の青洲)の妻として見初められ、わずか八歳で華岡家へと嫁ぎます。しかし、当時の雲平は京都で医学の修行中であり、加恵は夫不在のまま、義母である於継と二人で三年間を過ごすことになります。
於継は、気品に満ちた美しい女性で、加恵は彼女に深く憧れていました。於継もまた、加恵を温かく迎え入れ、加恵は機織り仕事で学費を稼ぎながら、於継に懸命に尽くします。二人の間には穏やかで平穏な日々が流れていました。加恵は、夫となる雲平の帰りを心待ちにしながら、華岡家での生活に慣れていきます。
やがて、三年間の修行を終えた雲平が帰郷します。初めて見る夫の顔に、加恵は胸をときめかせ、これから始まる新婚生活への期待に胸を膨らませます。しかし、雲平の帰郷を境に、於継の態度が一変します。於継は、まるで加恵を邪魔者であるかのように扱い、雲平の世話を独り占めするようになります。冷遇される加恵は、かつて憧れと尊敬の念を抱いていた於継に対し、次第に憎しみに似た感情を抱くようになるのです。
青洲は医学研究に没頭し、特に麻酔薬の開発に心血を注ぎます。そして、その研究の過程で、華岡家にはさらなる試練が訪れることになります。やがて、人体への臨床試験という究極の選択を迫られることになるのですが、その時、於継と加恵は、それぞれの「愛」の形を示すべく、ある決断を下すことになります。
『華岡青洲の妻』の長文感想(ネタバレあり)
有吉佐和子先生の『華岡青洲の妻』は、ただ「全身麻酔を成功させた偉人の物語」として語られるにはあまりにも奥行きが深く、そして何よりも、そこに描かれる人間ドラマが私たちの心を激しく揺さぶります。読み進めるほどに、この作品が単なる歴史小説ではなく、普遍的な人間心理を抉り出す傑作であると確信しました。
まず、主人公である加恵の心理描写には、並々ならぬ筆力が感じられます。幼い頃から於継に憧れ、華岡家へと嫁いだ加恵は、夫である青洲が不在の間、於継の愛情を一身に受けて育ちます。この期間の描写は、加恵が於継を心から敬愛し、信頼していたことを明確に示しています。しかし、夫の帰郷によって、その幸福な関係性は脆くも崩れ去ります。於継の掌を返したような冷酷な態度に直面し、加恵の心に芽生えるのは、愛情が裏返ったかのような深い憎しみと嫉妬です。この変化はあまりにも鮮烈で、読者は加恵の苦悩を肌で感じることができます。彼女が表面上は冷静を装いながらも、内面では激しい葛藤に苛まれている様子は、まさに人間の複雑さを物語っています。
於継の人物像もまた、単なる「意地悪な姑」という枠には収まりません。彼女は、息子である青洲の成功こそが、華岡家の繁栄、ひいては自分の人生の全てであると信じて疑わない女性です。その信念は、時に他者への支配欲や独占欲へと姿を変え、特に息子に近づく加恵を排除しようとする原動力となります。於継の行動の根底には、息子への偏執的なまでの愛情と、華岡家という「家」を守ろうとする強い責任感が同居しているのです。彼女が麻酔実験の被験者に名乗り出る場面は、その母性愛と執着が最高潮に達した瞬間であり、読む者に息をのませるほどの迫力がありました。
そして、この物語の中心にいる華岡青洲という人物。彼は医学への情熱に突き動かされ、麻酔薬の開発という偉業に邁進します。しかし、彼の家庭で繰り広げられる二人の女性の壮絶な愛憎劇には、どこか鈍感な部分があるように感じられます。彼が於継と加恵に異なる麻酔薬を投与したという事実は、彼が母と妻のどちらをより「特別」な存在と認識していたのか、あるいは、医学者としての冷静な判断が、人間的な感情を凌駕したのか、という問いを私たちに投げかけます。彼の偉業の陰で、二人の女性が払った犠牲の重さを思うと、読者は複雑な感情を抱かずにはいられません。
特に印象的なのは、於勝の存在です。青洲の妹である於勝が乳がんで命を落とす場面は、この物語に悲劇的な転機をもたらします。彼女が麻酔薬未完成のために手術を受けることができず、苦しみながら亡くなっていく様は、青洲が麻酔薬の開発に全てを賭ける理由をより強く印象づけます。また、於勝が残したとされる「結婚しないでよかった」という言葉は、加恵や於継が「家」や「夫/息子」に縛られて生きていくことの重さ、そしてそれとは対照的な於勝の自由な生き方を暗示しており、物語に深みを与えています。
この作品の核心は、やはり「愛」という感情の多面性にあると感じます。於継と加恵は、それぞれ異なる形で青洲を愛し、その愛ゆえに激しく対立します。彼女たちが麻酔実験の被験者に名乗り出る場面は、まさにその愛憎と自己犠牲が交錯する頂点です。「夫の役に立ちたい」「息子を助けたい」という献身的な思いの裏には、相手に対する嫉妬や、自分が相手より優位に立ちたいという自己顕示欲が潜んでいる。この人間の本質的な部分を、有吉佐和子先生は容赦なく描き出しています。純粋な愛と、歪んだ執着の境界線が曖昧になる瞬間は、読む者に深い問いを投げかけます。
封建社会における「家」の重みも、本作の重要なテーマです。女性が「家」に嫁ぎ、その繁栄のために尽くすことが美徳とされた時代、個人の幸福や願望は往々にして抑圧されました。加恵も於継も、華岡家という大きな枠組みの中で、それぞれの役割を果たそうとします。しかし、その過程で彼女たちの個性がぶつかり合い、抑えきれない感情が噴出するのです。「個と家」の相克は、現代社会においても形を変えて存在する普遍的な問題であり、だからこそ私たちは彼女たちの葛藤に共感し、心を揺さぶられるのでしょう。
また、本作は史実に基づきながらも、有吉佐和子先生の想像力によって、登場人物たちの内面がこれほどまでに豊かに描かれていることに感嘆します。当時の医療事情や生活様式が詳細に描写されているだけでなく、女性たちが抱える心の闇や光が、まるで手に取るように伝わってきます。それは、単なる記録文学ではなく、紛れもない文学作品としての輝きを放っています。
加恵が失明し、やがて於継が亡くなった後の描写も、非常に示唆に富んでいます。盲目となった加恵が、於継のように美しい笑みを浮かべながら成長した医院を眺める姿は、彼女が於継という存在を超越し、新たな境地へと辿り着いたことを暗示しているかのようです。それは、憎しみや嫉妬を超えた、ある種の赦しや理解に到達した姿なのでしょう。この結末は、単なるハッピーエンドとは異なり、深い余韻を残します。
『華岡青洲の妻』は、医学の偉業を成し遂げた男性の物語であると同時に、その偉業の陰で、愛と憎しみ、献身と犠牲、そして「家」のしがらみの中で葛藤し続けた女性たちの物語です。読み終えた後、私たちは、人間の感情の複雑さ、そして時代を超えて変わることのない「人間の強さ」と「弱さ」について、深く考えさせられることになります。この作品は、私たちの心に長く残り、折に触れてその問いかけを思い出す、そんな一冊となるでしょう。
まとめ
有吉佐和子先生の『華岡青洲の妻』は、日本の医学史に名を刻む華岡青洲の偉業を題材としながらも、その裏で繰り広げられる人間ドラマに焦点を当てた傑作です。物語の中心となるのは、青洲を支えた二人の女性、彼の母・於継と妻・加恵の壮絶な愛憎劇であり、彼女たちの激しい葛藤が読む者の心を強く捉えて離しません。
封建的な「家」のしがらみの中で、自己犠牲と献身を競い合うかのように見えながら、その内面では嫉妬や支配欲が渦巻く彼女たちの心理は、深く複雑に描かれています。純粋な愛情と歪んだ執着が混じり合う様は、人間の感情の奥深さと、その普遍的な性質を浮き彫りにします。
この作品は、単なる歴史物語にとどまらず、愛、憎しみ、自己犠牲、そして「個と家」の相克といった普遍的なテーマを私たちに問いかけます。青洲の医学的偉業の影に隠された、二人の女性の壮絶なドラマは、時代を超えて現代にも通じる強いメッセージを放っています。
『華岡青洲の妻』は、読み終えた後も長く心に残り、人間とは何か、愛とは何かという根源的な問いについて深く考えさせてくれる、示唆に富んだ一冊と言えるでしょう。未読の方はもちろん、既読の方も、改めてその奥深さに触れてみてはいかがでしょうか。