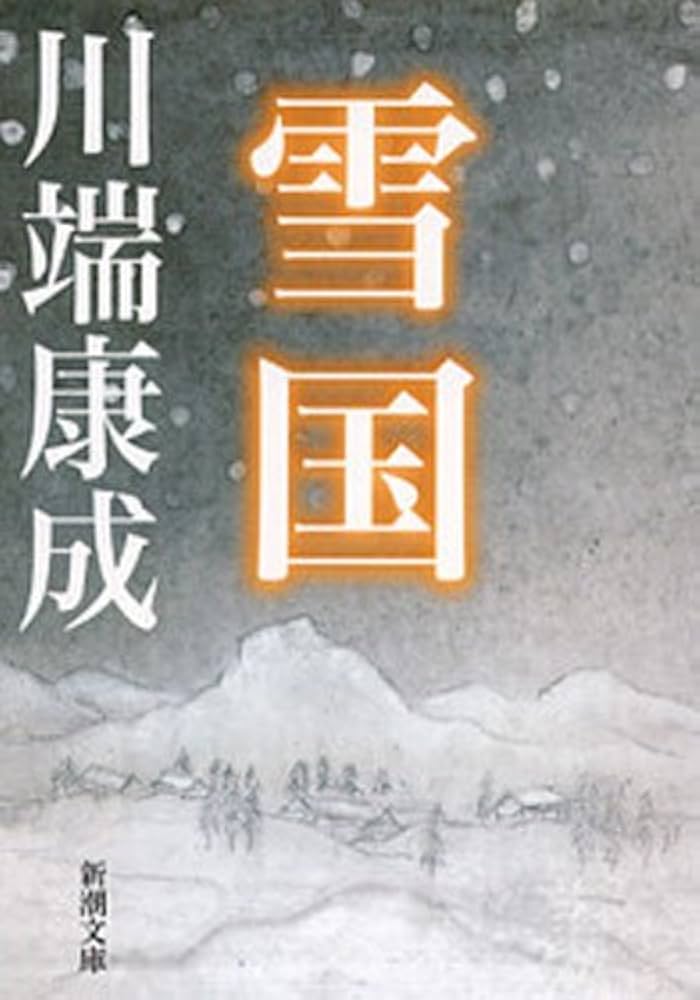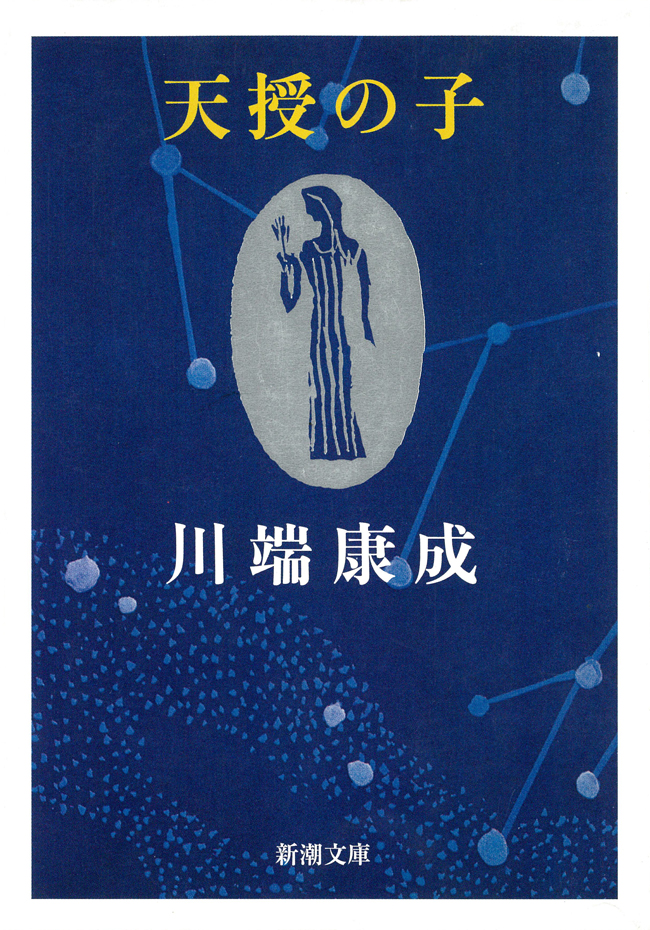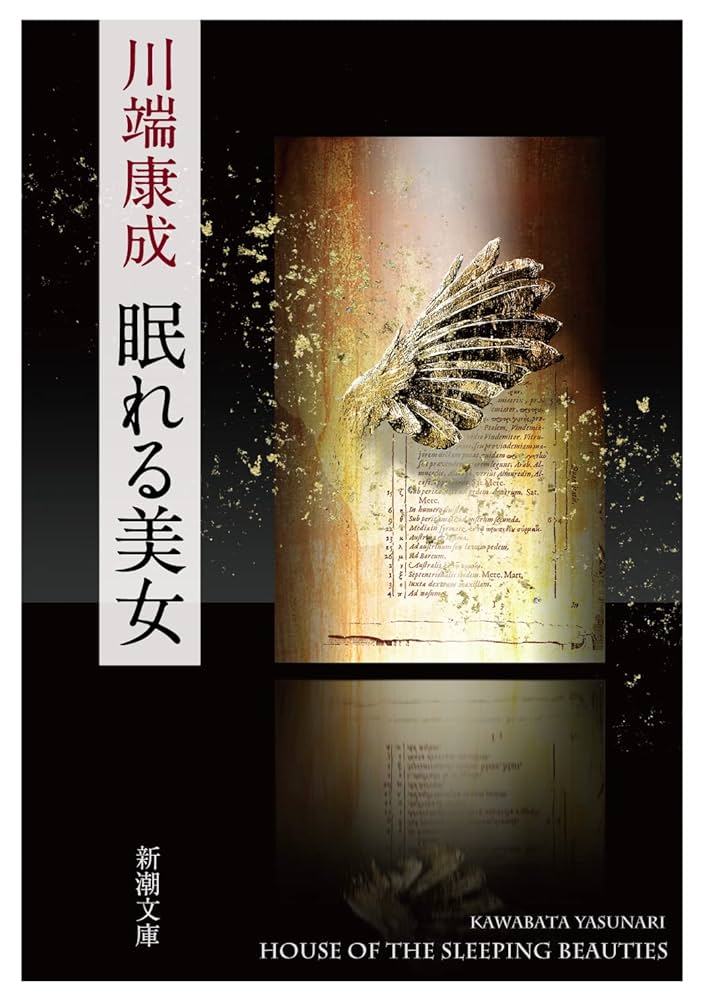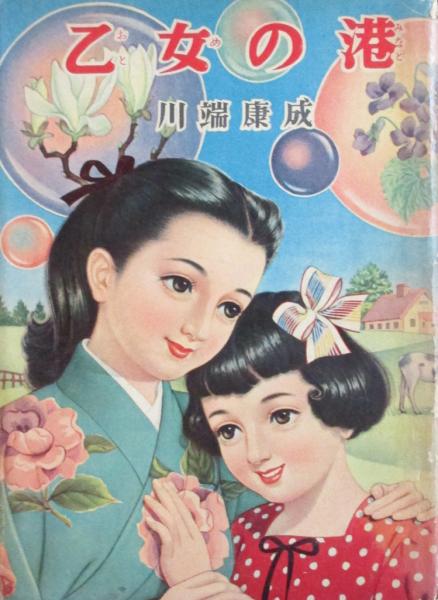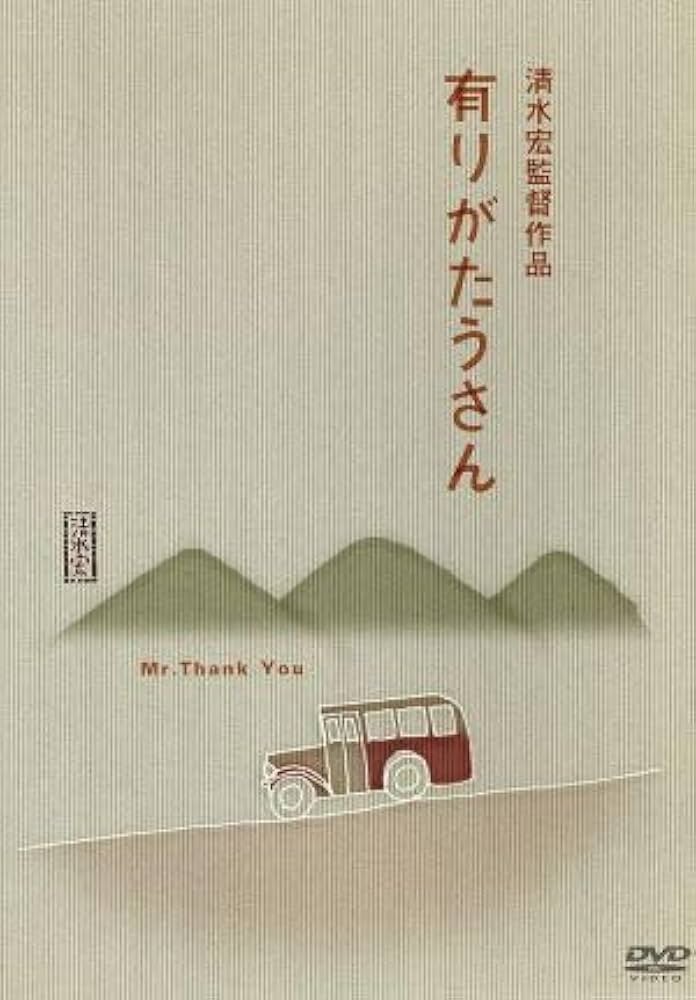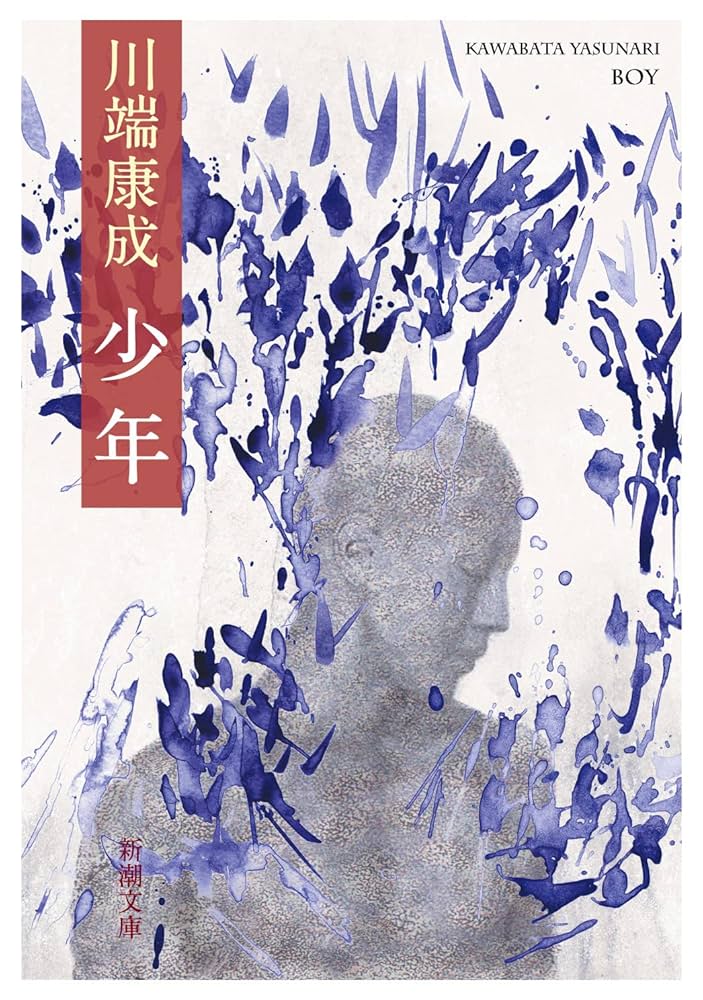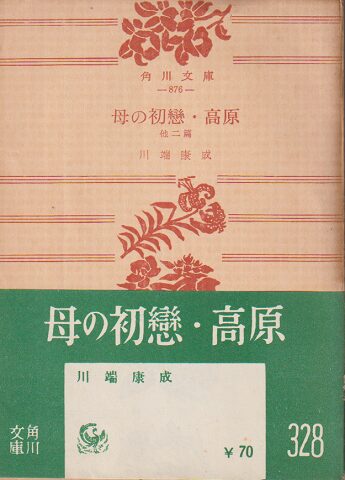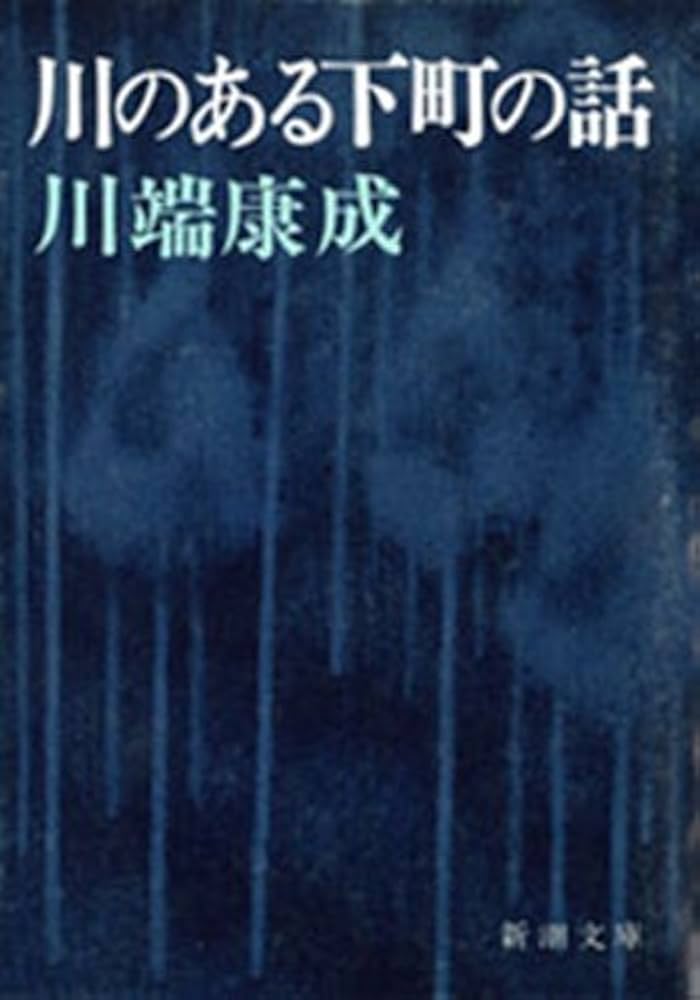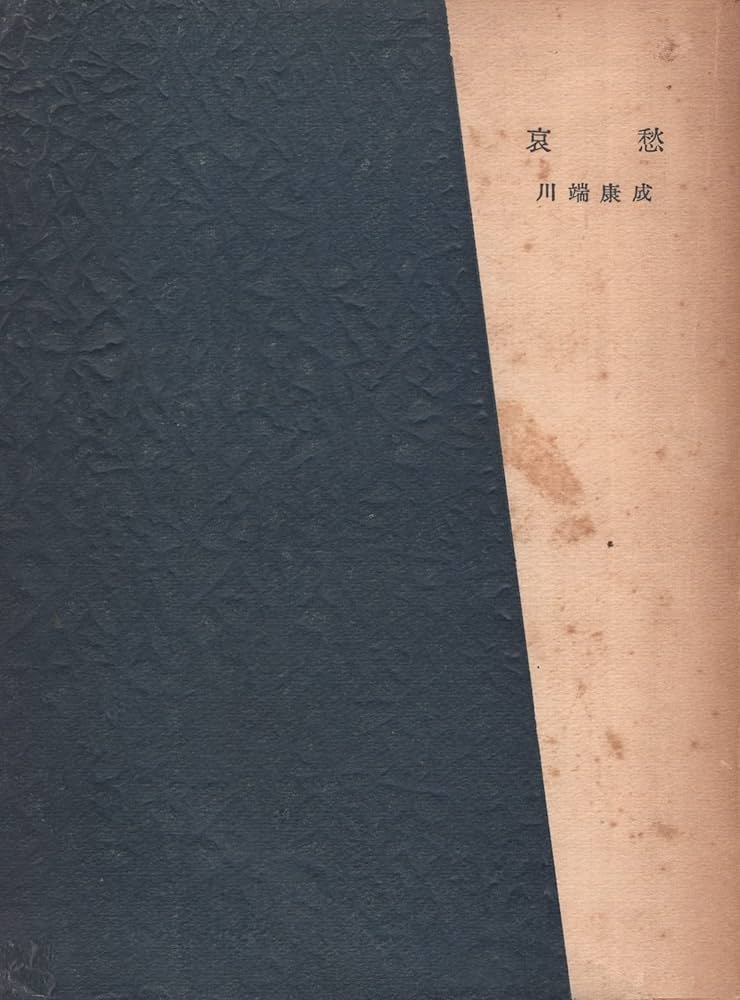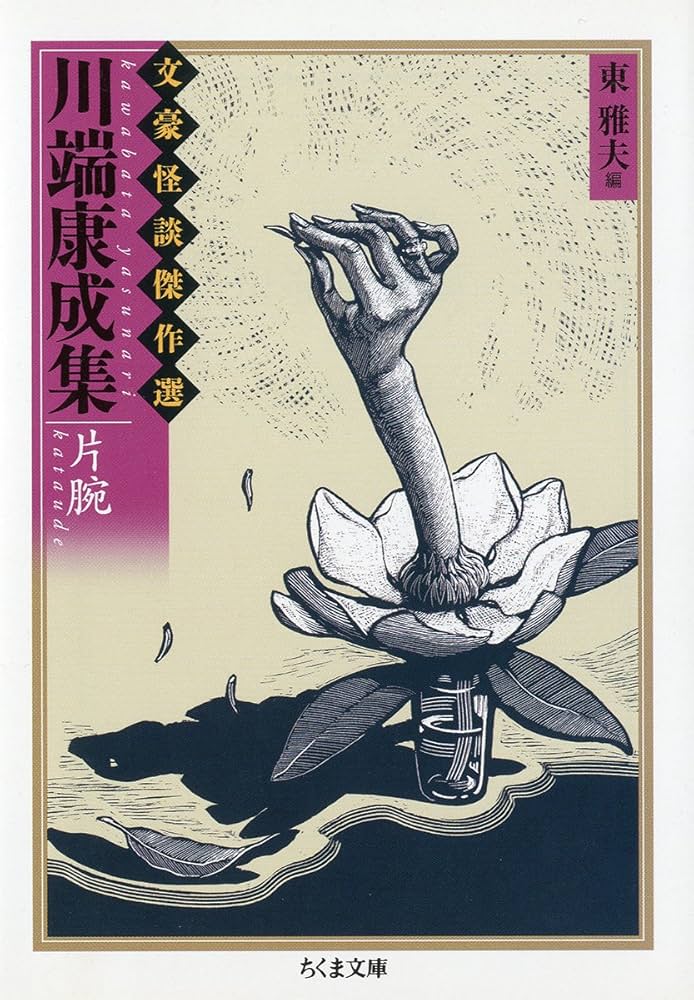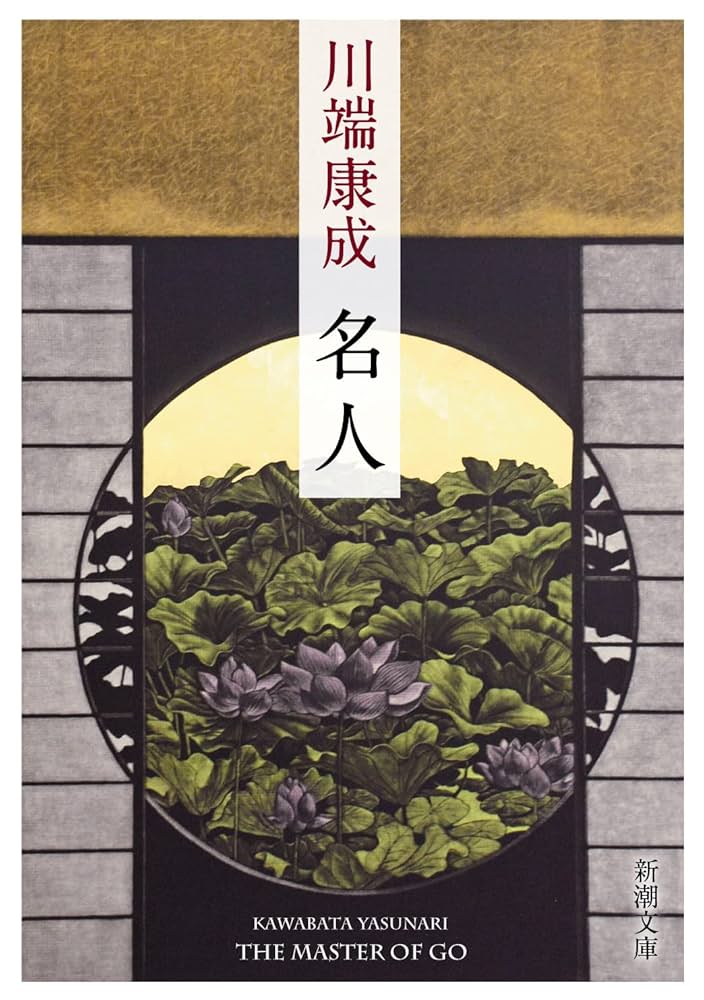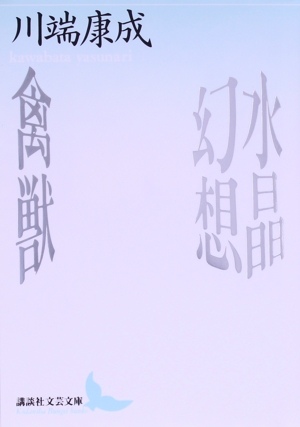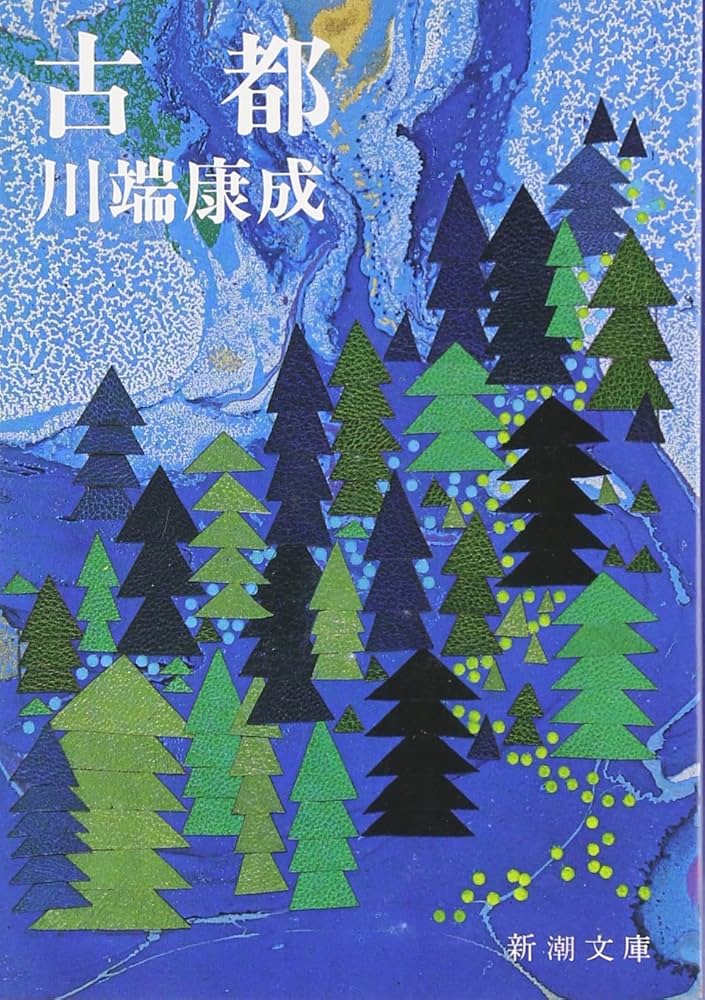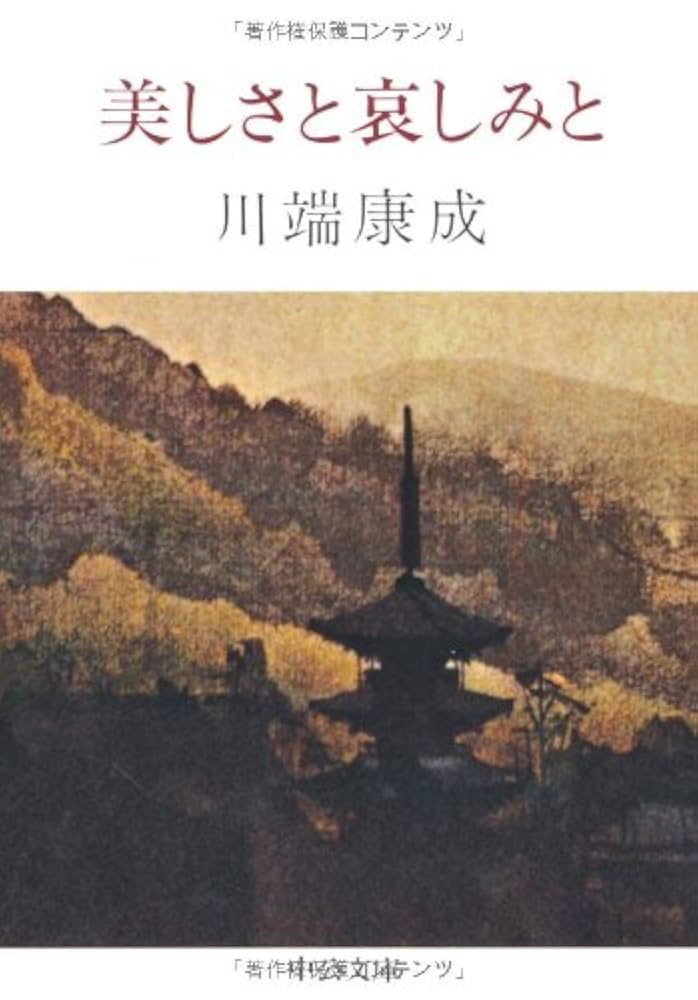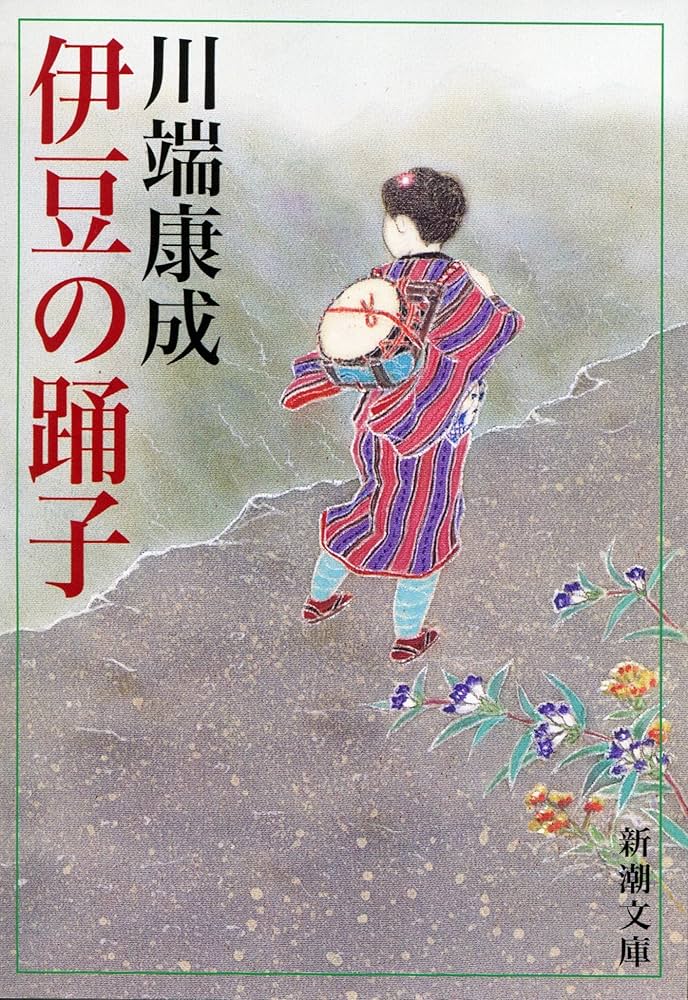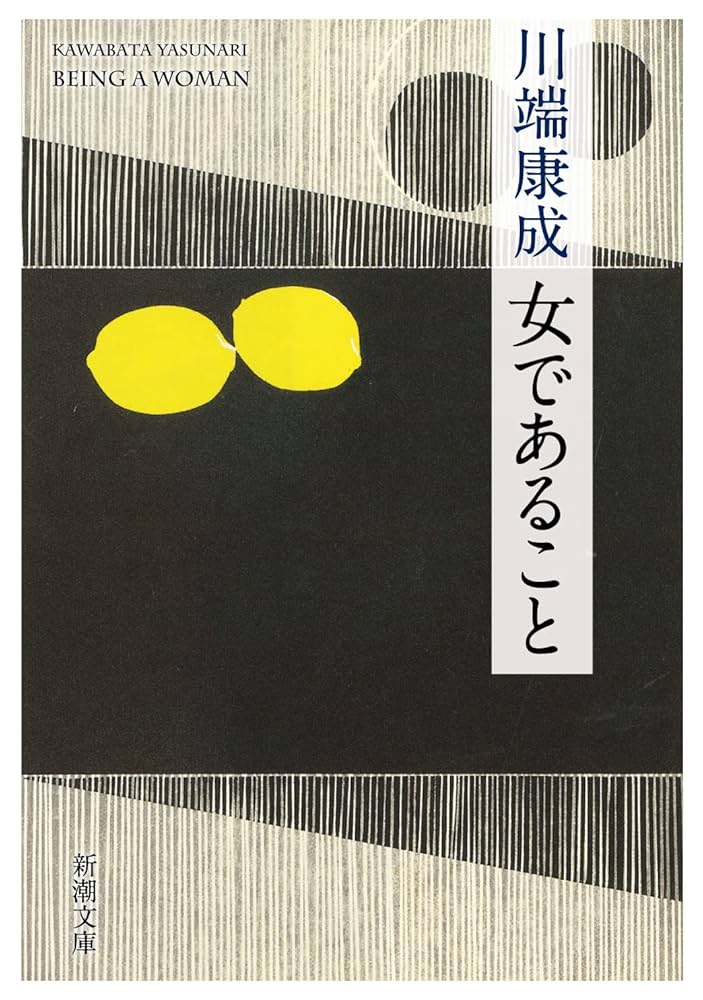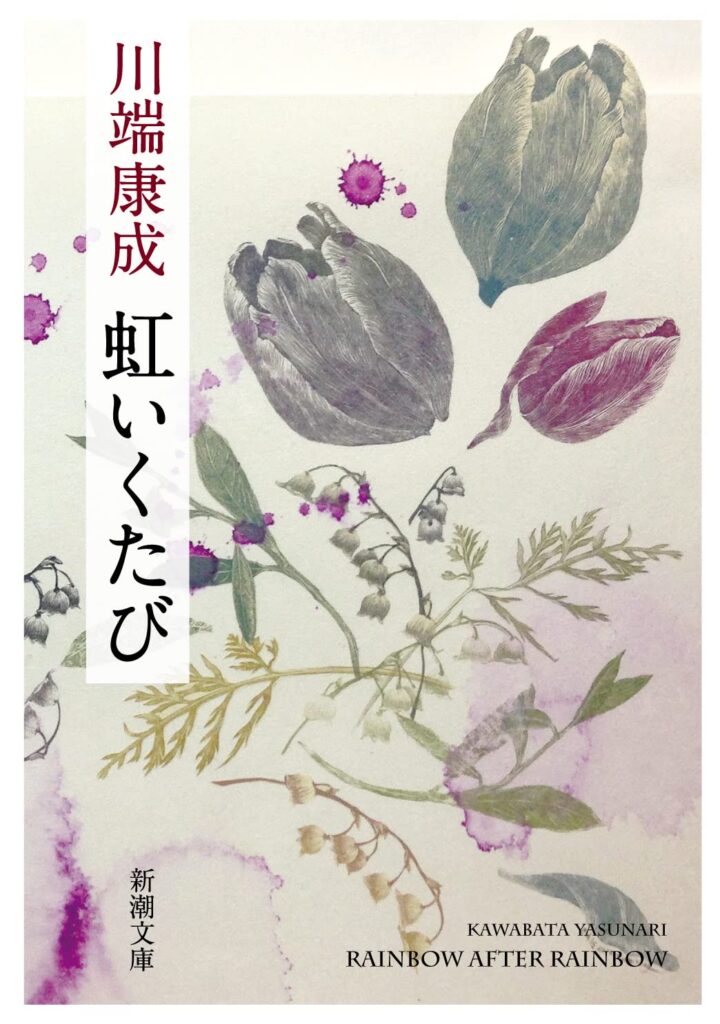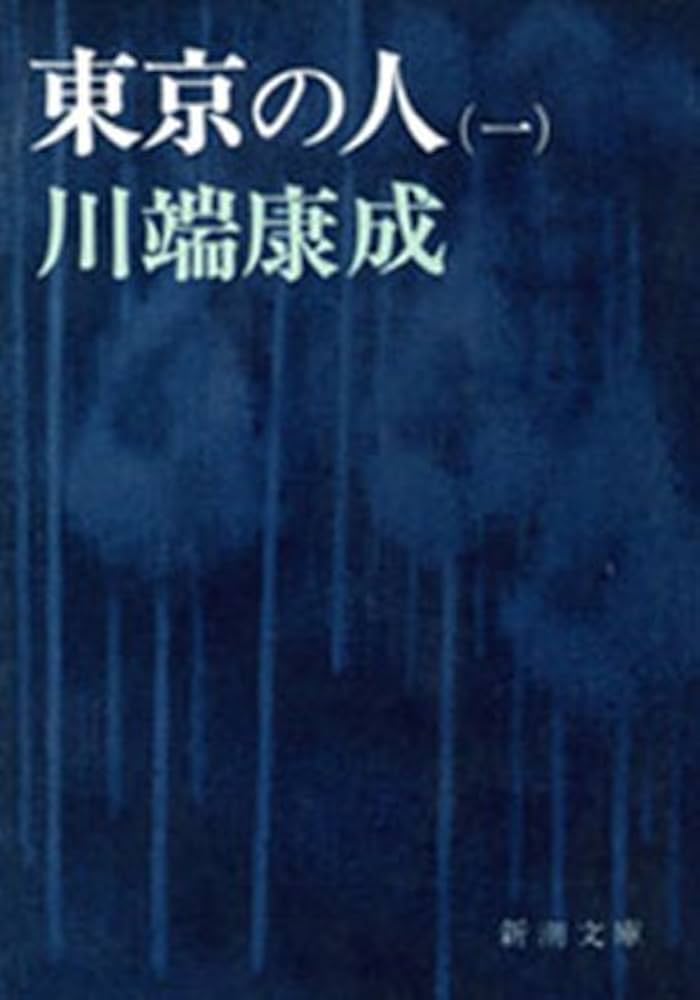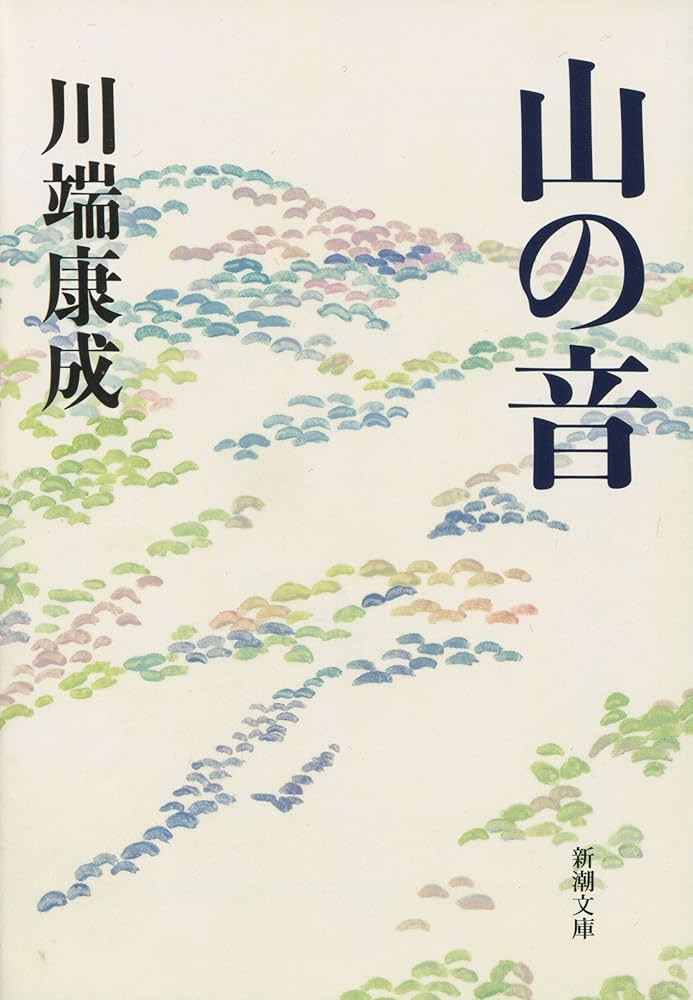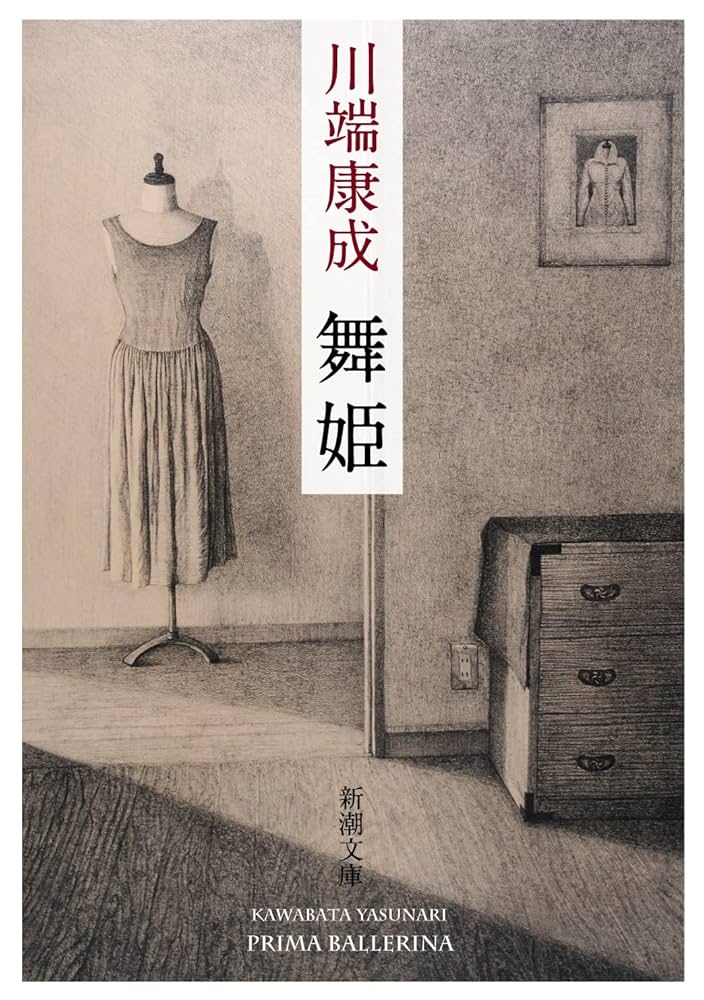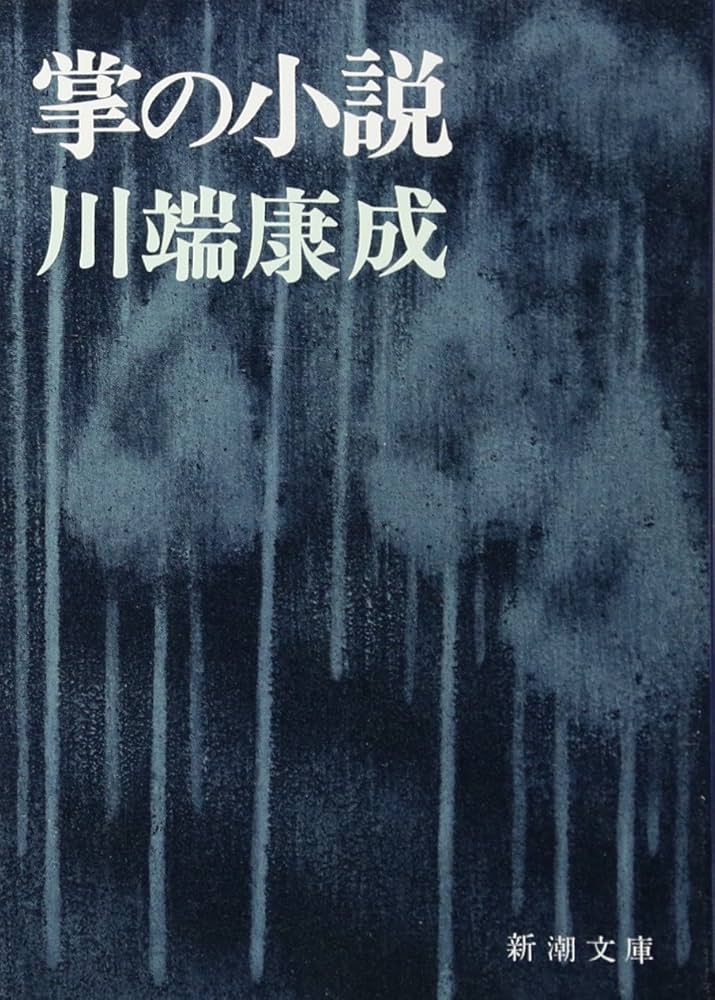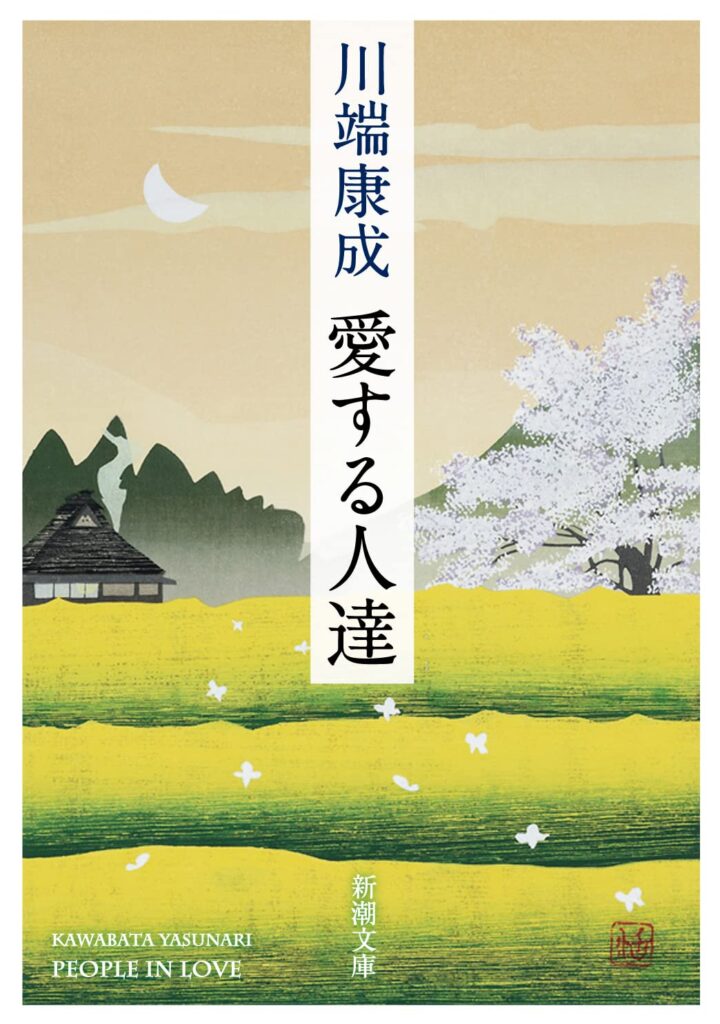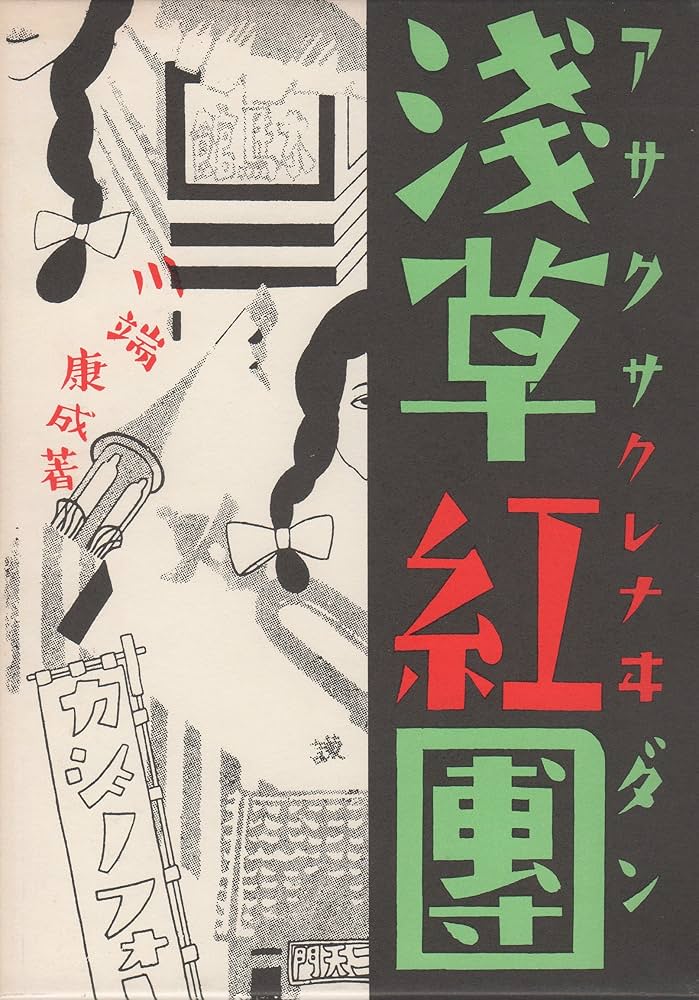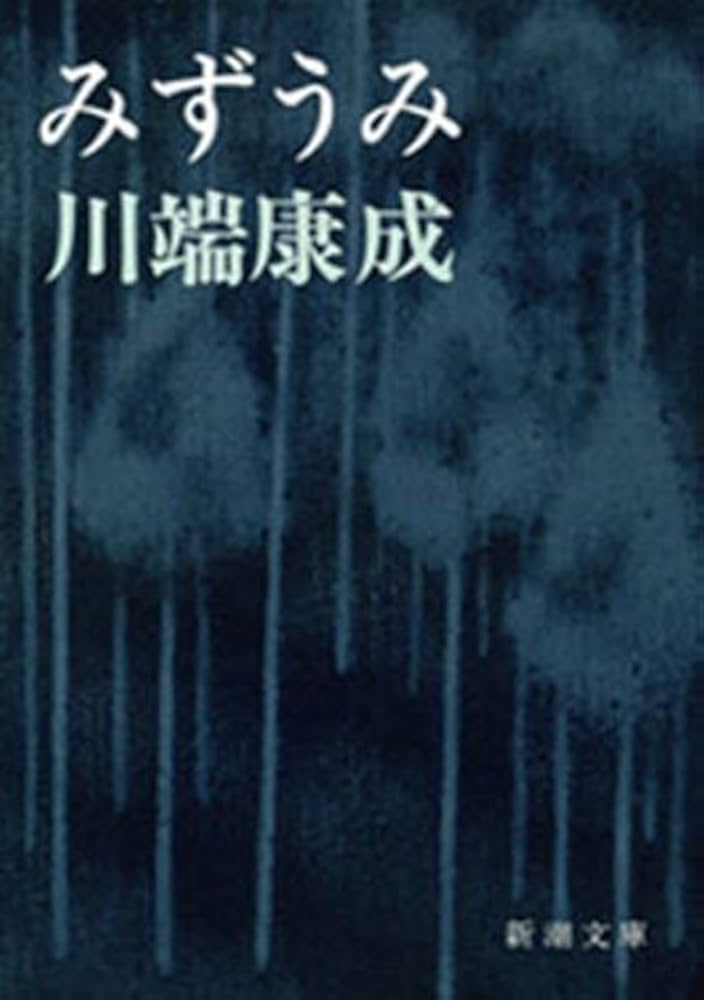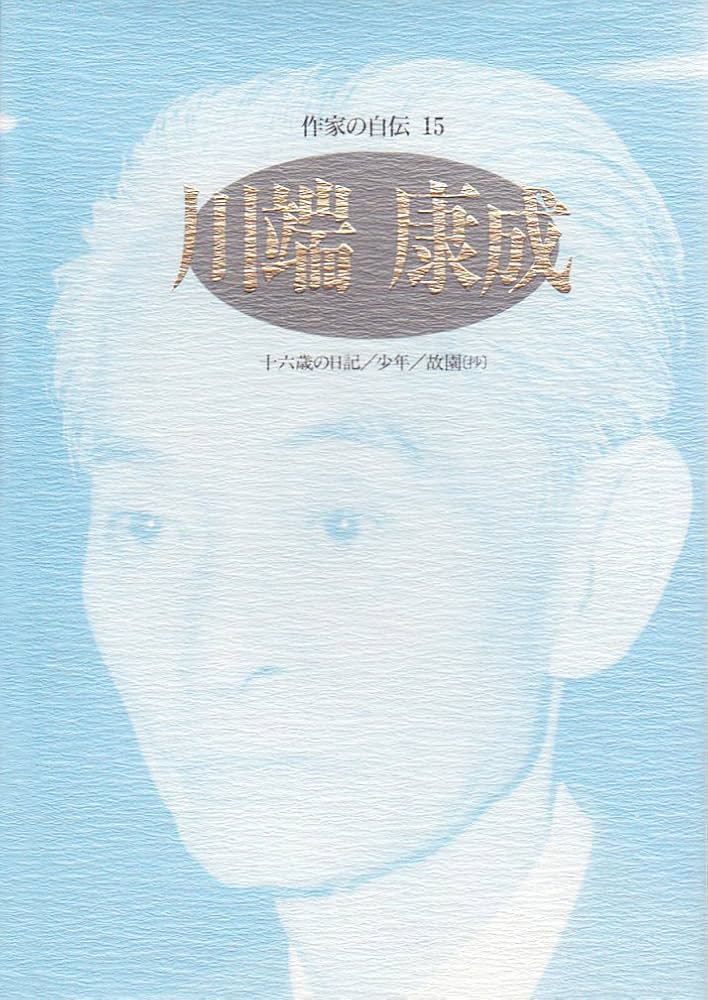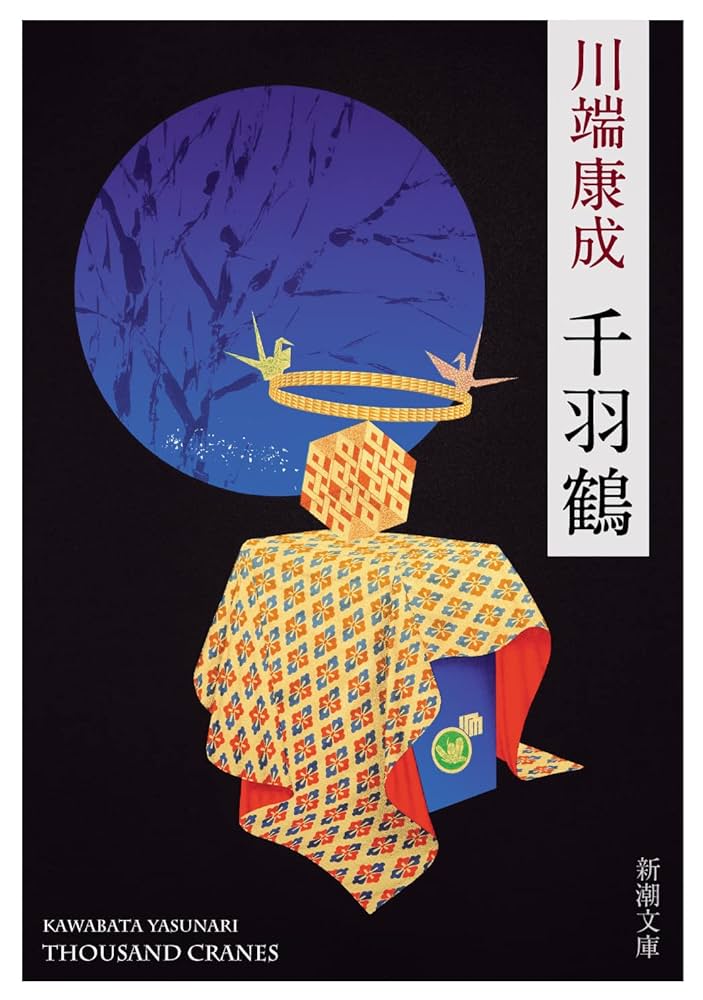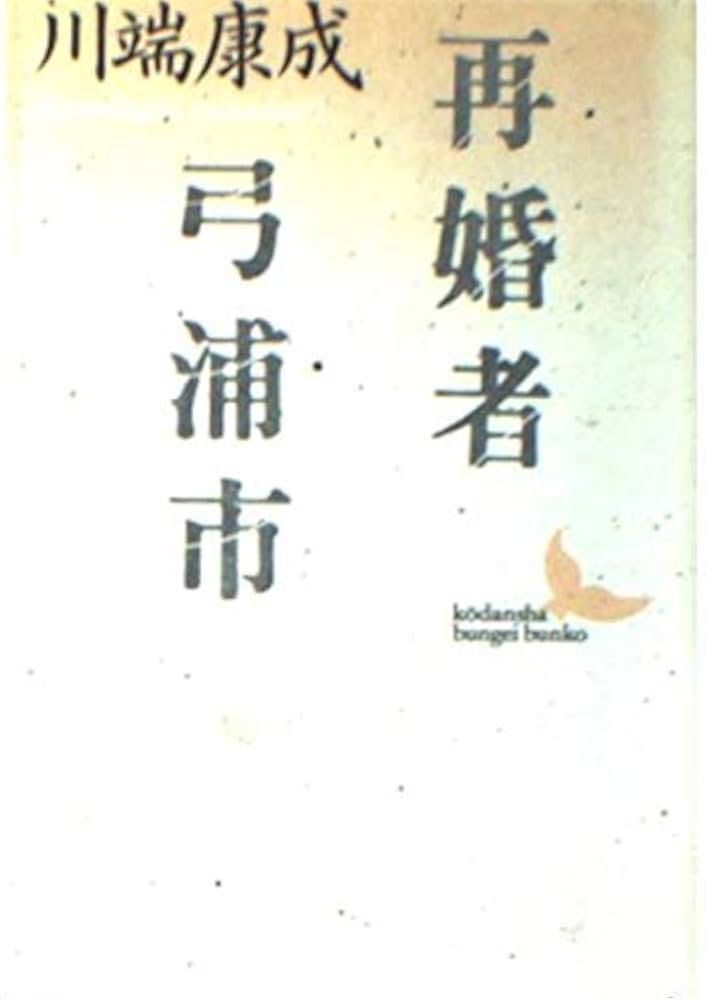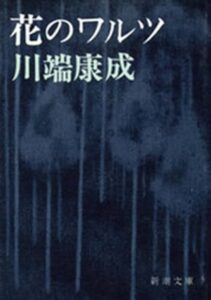 小説「花のワルツ」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「花のワルツ」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
川端康成と聞くと、『雪国』や『伊豆の踊子』のような、叙情性あふれる美しい作品を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。しかし、彼の作品群の中には、読む者の心を激しく揺さぶり、突き放すような鋭さを持った物語も存在します。その一つが、今回取り上げる「花のワルツ」です。
この物語は、一見するとバレエの世界を舞台にした華やかな人間模様を描いているように思えます。しかし、その内側で渦巻いているのは、芸術への純粋すぎる情熱、才能をめぐる嫉妬、そして救済という名の下に行われる残酷な魂のぶつかり合いなのです。物語は衝撃的な場面で幕を閉じ、多くの謎を残します。
この記事では、まず「花のワルツ」がどのような物語なのか、その魅力的な導入部分のあらすじをお伝えします。そして後半では、物語の核心に触れるネタバレを含んだ、より深い読み解きと私なりの感想を詳しく語っていきたいと思います。この未完の名作が、なぜこれほどまでに心を捉えて離さないのか、その秘密に一緒に迫っていきましょう。
「花のワルツ」のあらすじ
舞踊研究所の看板である友田星枝と早川鈴子は、チャイコフスキーの「花のワルツ」を舞台で踊り、喝采を浴びます。二人は親友でありながら、ライバルでもありました。奔放で天才肌の星枝と、真面目で努力家の鈴子。その性格の違いは、芸術に対する考え方の違いにも繋がっており、二人の間には常に緊張が走っていました。
公演の直後、楽屋で二人は些細なことから口論になります。芸術とは何か、踊りとは何か。その議論は白熱し、互いの根底にある価値観の違いを浮き彫りにします。そこに現れた師匠の竹内が、衝撃的な知らせをもたらします。かつて二人が憧れ、5年前に洋行して以来、音信不通だった天才舞踊家、南条が帰国するというのです。
しかし、再会を喜ぶ二人の前に現れた南条は、かつての輝きを失っていました。足を痛め、松葉杖なしでは歩くことすらできない姿になっていたのです。彼の帰国は、星枝と鈴子の関係、そしてそれぞれの芸術との向き合い方に、決定的な変化をもたらすことになります。
絶望の中にいる南条を前にして、二人の女性の思いが交錯します。一人は彼を支えようとし、もう一人は彼を挑発する。物語は、この三人の魂が激しく火花を散らす、予測不能な展開へと進んでいきます。この先に待ち受ける出来事の詳しい内容は、ぜひ本編で確かめてみてください。
「花のワルツ」の長文感想(ネタバレあり)
ここからは、「花のワルツ」の物語の核心に触れる部分、つまり結末までのネタバレを含んだ詳細な感想をお話しさせていただきます。この物語がなぜ「未完の傑作」と評されるのか、その理由を私なりに紐解いていきたいと思います。まだ結末を知りたくない方はご注意ください。
この作品が発表されたのは昭和11年(1936年)のことです。川端康成が文壇で独自の地位を確立し、様々な実験的手法に挑んでいた時期にあたります。有名な『雪国』の連載と並行して、実際の事件記録を基にした小説なども手掛けていた頃で、彼の創作エネルギーが多方面に爆発していたことがうかがえます。
本作は、同じくバレエを題材にした戦後の長編『舞姫』と比較されることがあります。『舞姫』が戦後の社会の変化を背景に、ある家族の崩壊をゆっくりと描いた作品であるのに対し、「花のワルツ」はもっと凝縮されています。限定された登場人物、閉鎖的な空間で交わされる鋭い対話。その様子は、まるで舞台上の心理劇を見ているかのようです。
この物語の構造は、まさに「室内劇」と呼ぶのがふさわしいでしょう。物語を動かすのは外部の大きな事件ではなく、友田星枝、早川鈴子、そして南条という三人の心の内側にある葛藤と、彼らが交わす芸術をめぐる言葉の応酬です。舞台裏や森の中といった限られた場面設定が、かえって息詰まるほどの緊張感を生み出し、魂のドラマを鮮明に浮かび上がらせているのです。
物語を理解する上で欠かせないのが、三人の主要登場人物の個性です。まず、友田星枝。彼女は誰もが認める天賦の才を持ちながら、気分屋で内向的、衝動的な踊り子です。彼女の才能は、飼いならすことのできない野生の獣のようです。
星枝の芸術に対する考え方は、彼女の「芸術なんか、ありがたいと思ってませんわ。いつも自分でいたいの」というセリフにすべてが集約されています。彼女にとって踊りとは、誰かから教わる技術や形式ではなく、どこまでも純粋な自分自身の内なる衝動の発露に他なりません。この純粋さが、後に大きな波紋を広げることになります。
星枝と完璧な対をなすのが、早川鈴子です。一途で責任感が強く、世話焼き。彼女は勤勉で、努力を重ねることで芸術の高みに至ろうとします。規律や形式を重んじ、芸術を献身を捧げるべき崇高な対象と見なしています。星枝の予測不能な天才性に、彼女が苛立ちを覚えるのは当然のことでした。
鈴子の芸術観は、自己犠牲的な愛に基づいています。彼女は、師である南条が西洋で得たものを、たとえそれがどのような形であれ、すべて学び、受け継ぎたいと願います。彼女にとって芸術とは、守り、継承していくべき知の体系なのです。この二人の対照的なあり方が、物語の大きな軸となっていきます。
そして、この二人の対立の中心に置かれるのが、悲劇の人物、南条です。かつて将来を嘱望されながら、5年の洋行の末に足を痛め、松葉杖を手放せなくなった元舞踊家。彼の絶望は、「星枝さんの踊を見るまでの僕は、生きながら死んでいた」という痛切な告白に表れています。
南条は単なる一人の登場人物ではなく、星枝と鈴子、二つの異なる哲学がぶつかり合うための、いわば「るつぼ」のような存在です。彼は失われた才能、妥協(松葉杖という偽り)への誘惑、そして本物の芸術への渇望を一身に体現しており、物語のすべての葛藤は彼をめぐって展開します。
物語の核心的なドラマは、この堕ちた天才・南条をいかにして「救済」するか、という二つの競合するプランをめぐって進みます。鈴子が提示するのは、支持と献身による救済です。彼を支え、彼から学び、共に踊ることで、彼が再び立ち上がるための新たな「松葉杖」になろうとします。これは、育む愛による救済の形です。
一方、星枝が示す道は全くの正反対です。彼女は南条が松葉杖に頼ることを「偽り」だと激しく攻撃し、彼から「持っているものを、みんな取ってやる」と宣言します。真の芸術、真の生は、どんなに苦痛でも、すべての幻想や依存を打ち砕いた先に見出されると彼女は信じているのです。これは、浄化の炎による、破壊的な救済の形と言えるでしょう。この二人の対立は、単なる恋のさや当てではなく、魂の再生をめぐる深刻な哲学的衝突なのです。
ここから、物語の具体的な展開のネタバレに入ります。物語は、星枝と鈴子の舞台裏での口論、そして南条の帰国という知らせで大きく動き出します。そして、物語の頂点であり、最も重要な場面が、保養地の森の中で訪れます。星枝が、偶然にも南条と遭遇するのです。
この森の場面で、突如としてピストルの音が鳴り響きます。間を置いて四発、そして最後の一発。それは近くで狩りをしていた星枝の家族のものでした。この銃声は、単なる効果音ではありません。バレエという美の世界に、暴力や死を連想させる「リアル」な世界の音が侵入してくる瞬間です。純粋な美の追求の中にも、常に暴力や過酷な現実が隣り合わせにあることを、この音は突きつけてくるのです。
この異様な緊張感の中で、星枝と南条は踊り始めます。星枝に促され、南条は松葉杖を投げ捨てる。その踊りは、公演のそれとは全く違う、魂の叫びそのものです。鬱積した情熱、苦痛、そして芸術的なエネルギーが爆発する、生の表現。それは、かつて南条自身が理想とした「心のままに踊るのが、ほんとうの踊というもの」が、肉体を持って現れた瞬間でした。この場面の描写は、本作のあらすじの中でも最も重要な部分と言えます。
しかし、この奇跡的な解放の瞬間の直後、物語は残酷な展開を迎えます。ここが最大のネタバレ箇所です。疲れ果てた南条が星枝に支えを求めたとき、彼女は彼を突き放し、松葉杖に頼る彼の姿を「偽り」だと激しく非難します。真の自分と向き合うことを妨げている、と。この行為は、どんなに残酷でも真実こそが至上であるという、彼女の哲学を鮮烈に示しています。それは南条にとって救いだったのか、それともただの破壊だったのか。読者は答えの出ない問いを突きつけられます。
そして物語は、この森での出来事の直後、あまりにも唐突に幕を閉じます。三人の関係がどうなったのか、南条は再び踊れたのか、星枝と鈴子の対決の行方はどうなったのか、何一つ解決されないまま、読者は物語の外に放り出されます。この結末は、初めて読んだ時、正直「これで終わり?」と戸惑う方がほとんどでしょう。この唐突な結末のネタバレこそ、「花のワルツ」を語る上で避けては通れない点です。
しかし、この「未完成」に見える結末こそが、作者・川端康成の意図したものではないかと私は思います。この物語の主題的なクライマックスは、森の中で繰り広げられた、あの束の間の、しかし永遠のような激しい踊りの瞬間にあります。プロットを整然と完結させてしまうことは、かえってあの瞬間の輝きを色褪せさせてしまう。川端は、あえて物語を唐突に断ち切ることで、あの爆発的な一場面の重要性を、読者の心に永遠に刻みつけようとしたのではないでしょうか。
芸術の純粋な輝き。それは、日常の時間の流れや、物語の起承転結といった枠組みの外に存在するものです。その一瞬の真実を描くために、物語そのものが犠牲にされた。そう考えると、この未解決の結末は、失敗ではなく、むしろこの作品のテーマを最も純粋な形で表現するための、必然的な選択だったように思えるのです。芸術の一瞬のために、物語の完成を放棄する。これほど芸術家のエゴイズムと誠実さを感じさせる結末もありません。この作品に対する私の感想は、この一点に尽きると言っても過言ではないのです。
まとめ
川端康成の「花のワルツ」は、バレエという華やかな世界を舞台に、芸術家の魂の衝突を描いた、鋭利で美しい物語です。天才肌の星枝、努力家の鈴子、そして挫折した舞踊家・南条。三人の関係性は、読む者の心を強く揺さぶります。
この記事では、まず物語の導入部分のあらすじを紹介し、三人の複雑な関係性が始まるまでを解説しました。そして後半では、物語の核心である森での出来事や、あまりにも有名な唐突な結末のネタバレにまで踏み込み、その深い意味について考察を試みました。
この物語が未完のまま終わることは、欠点ではなく、むしろ芸術の一瞬の輝きを永遠に焼き付けるための、作者の意図的な選択だったのかもしれません。解決されないからこそ、私たちはこの物語を何度も読み返し、その余韻に浸り続けることができます。
もしあなたが、ただ美しいだけではない、魂を抉るような文学体験を求めているのなら、「花のワルツ」は必読の一作です。その不協和音のような読後感が、きっとあなたの心に長く残り続けることでしょう。