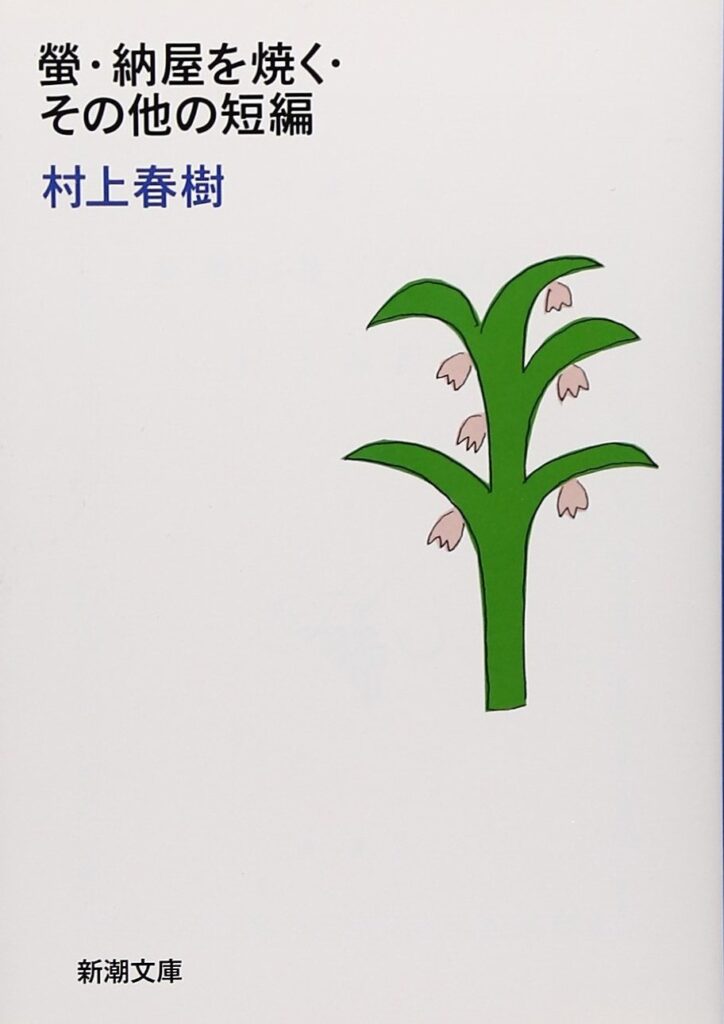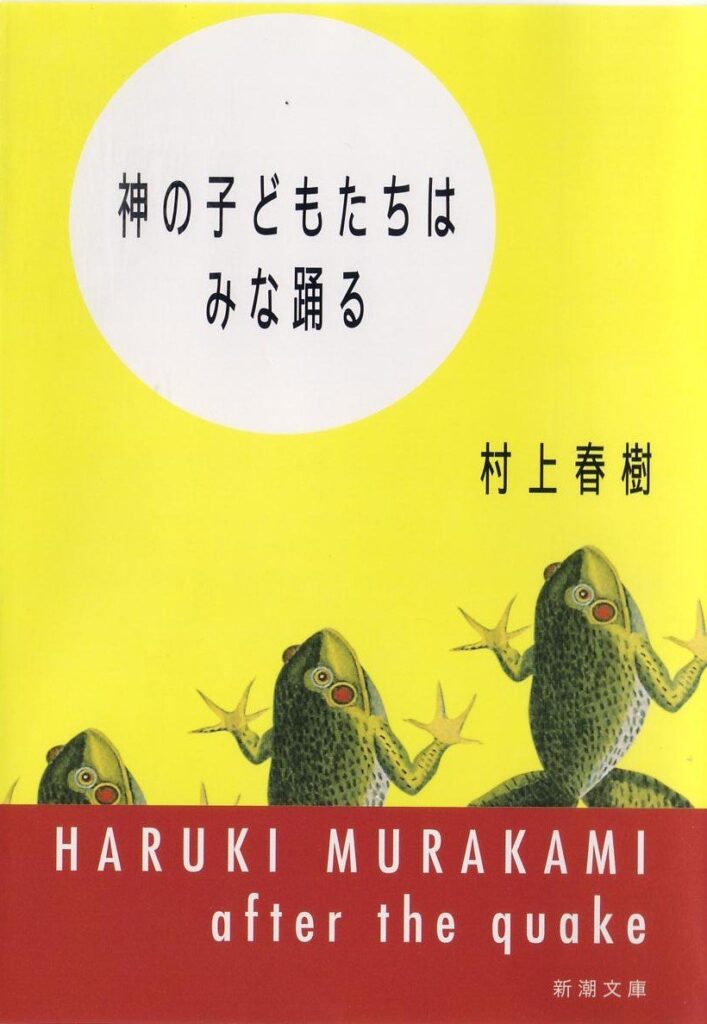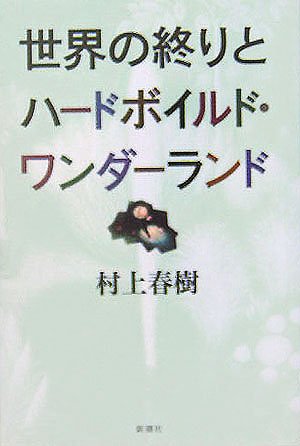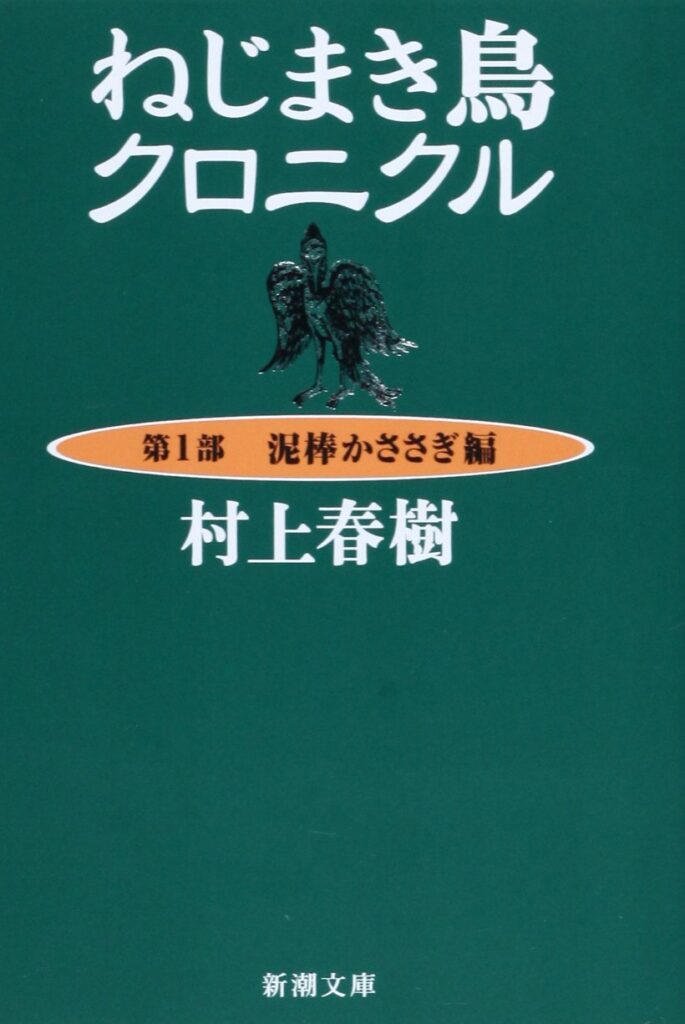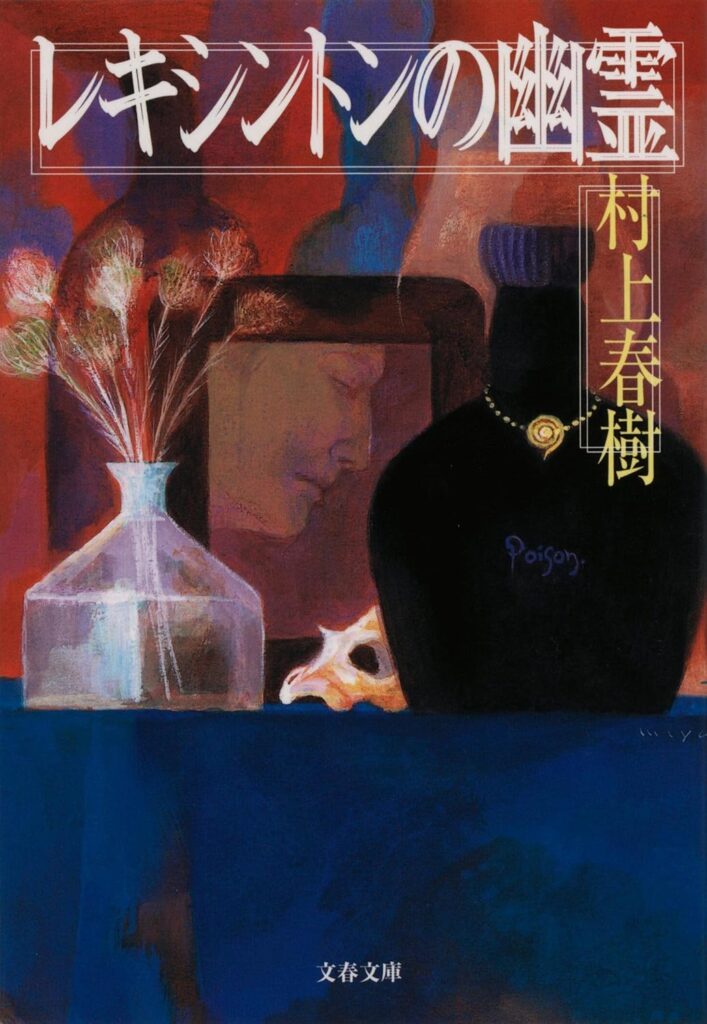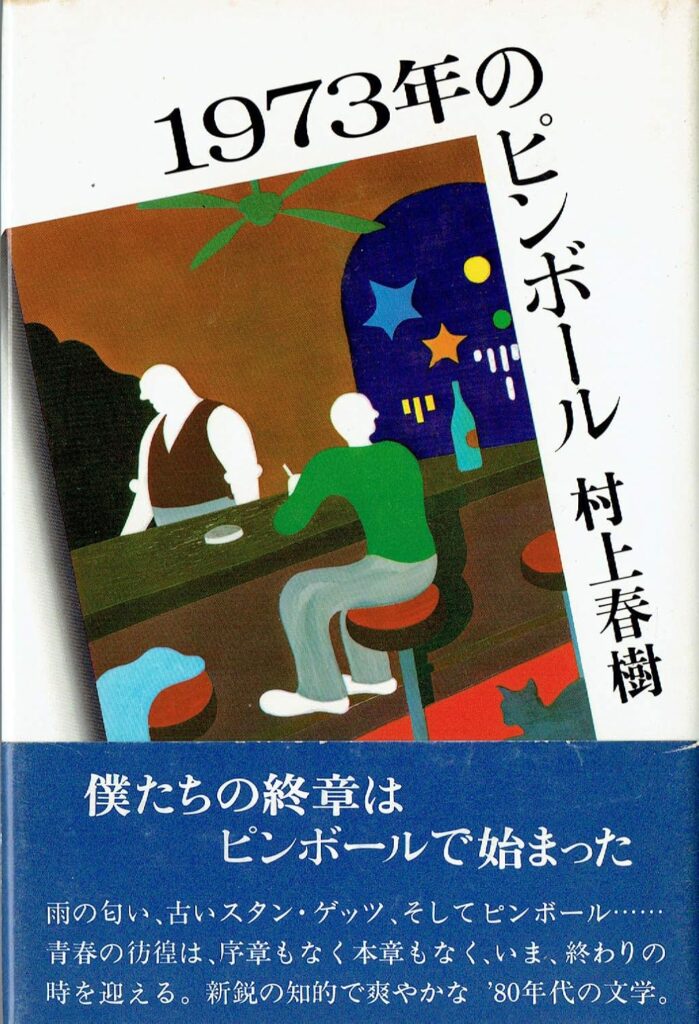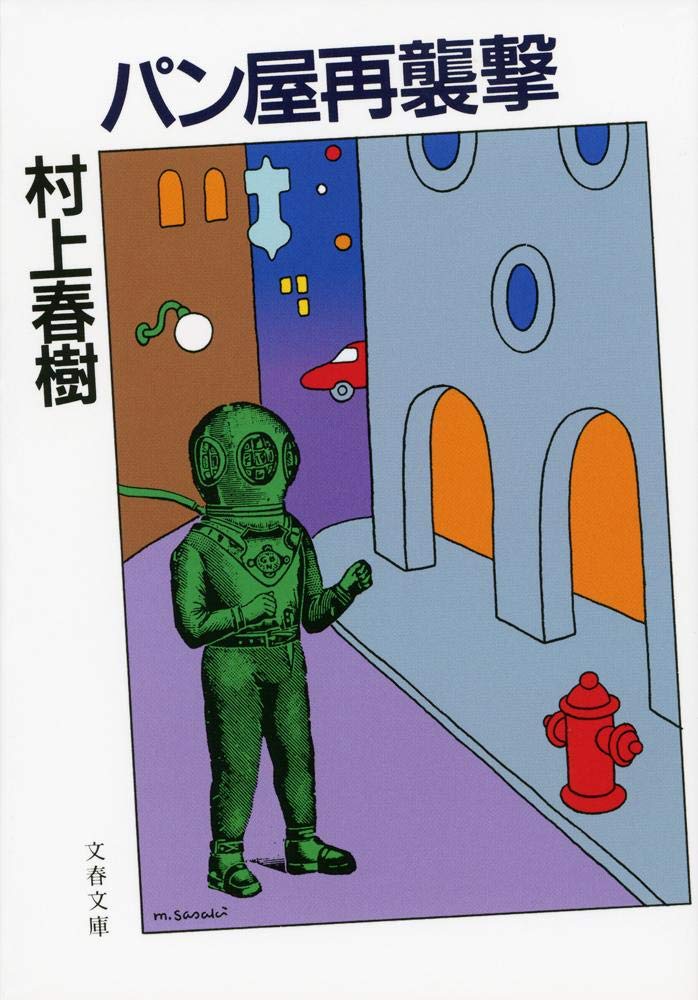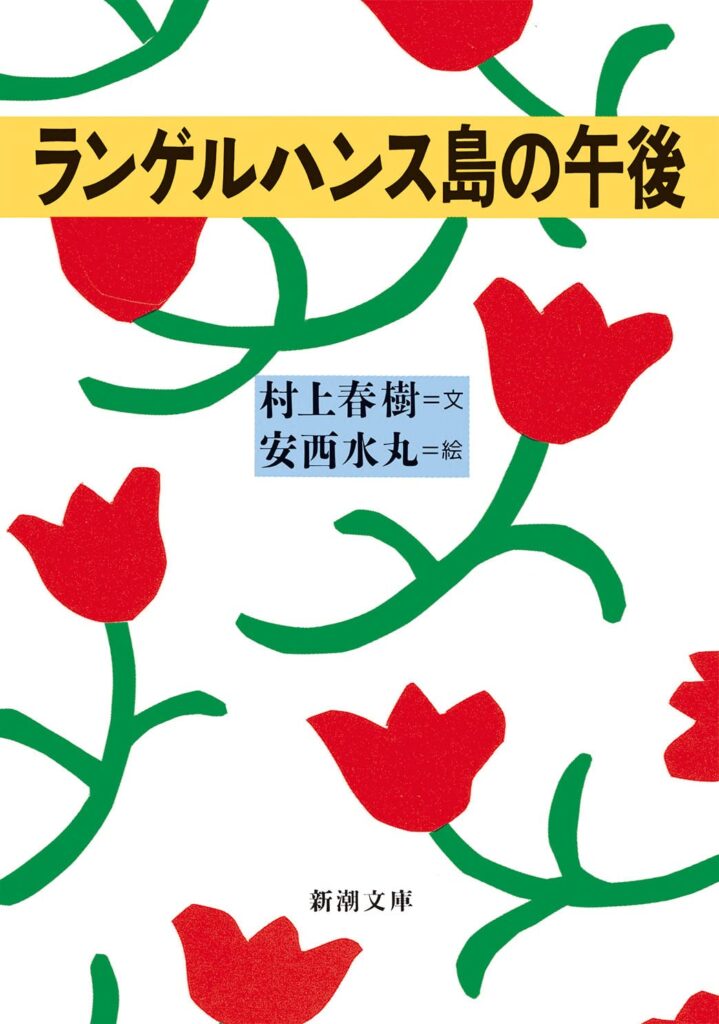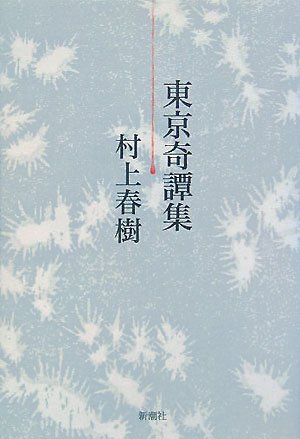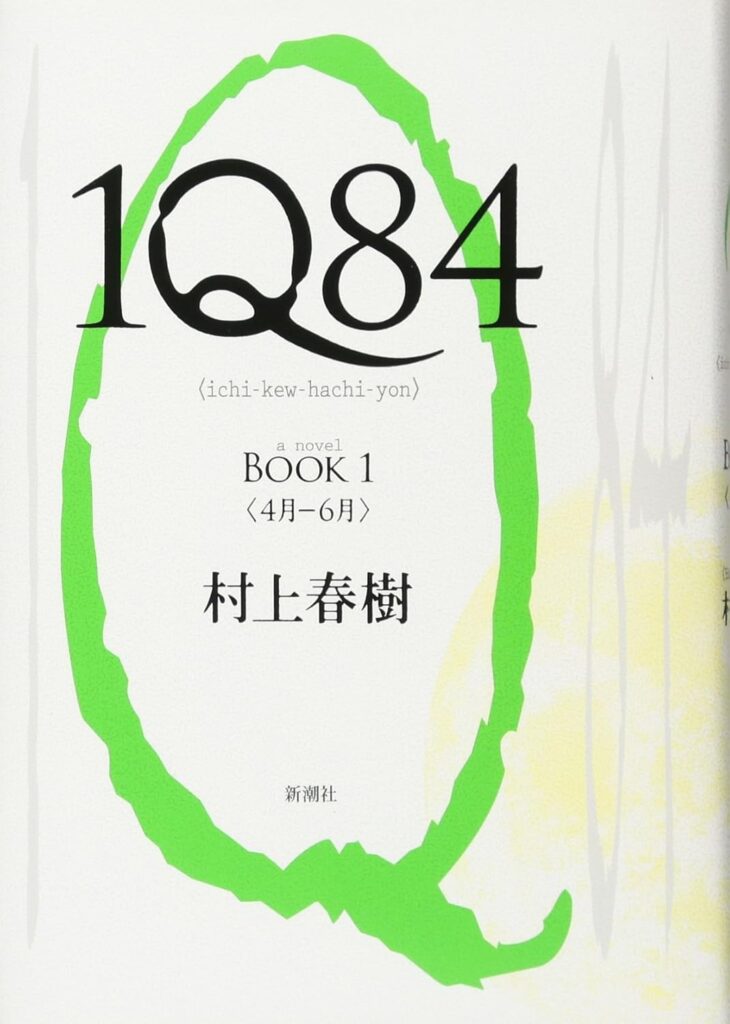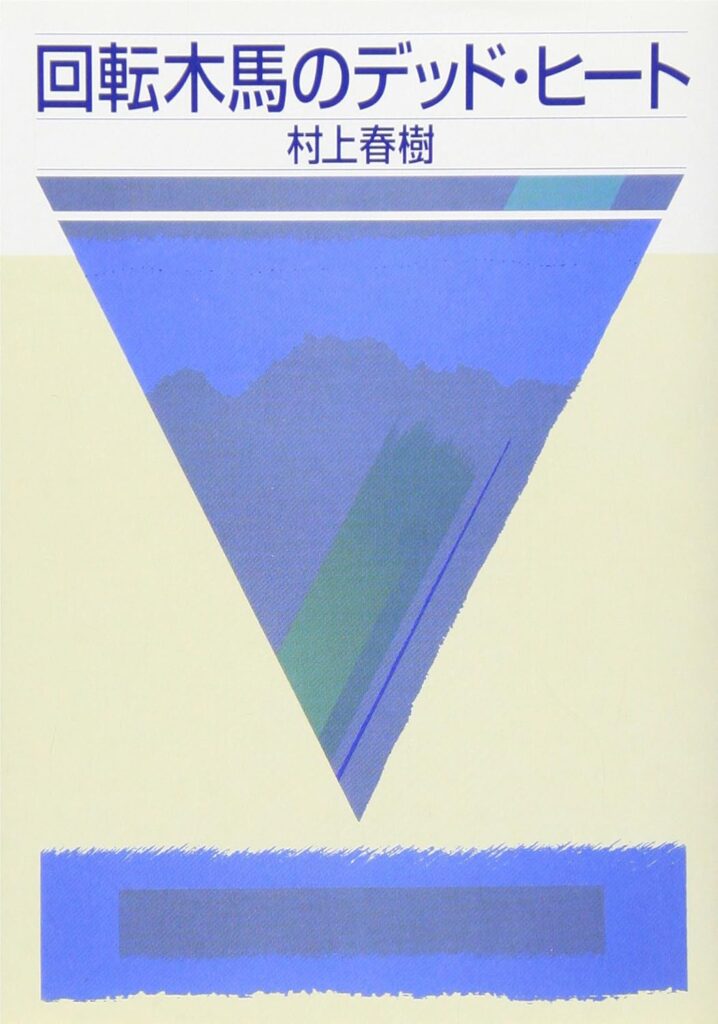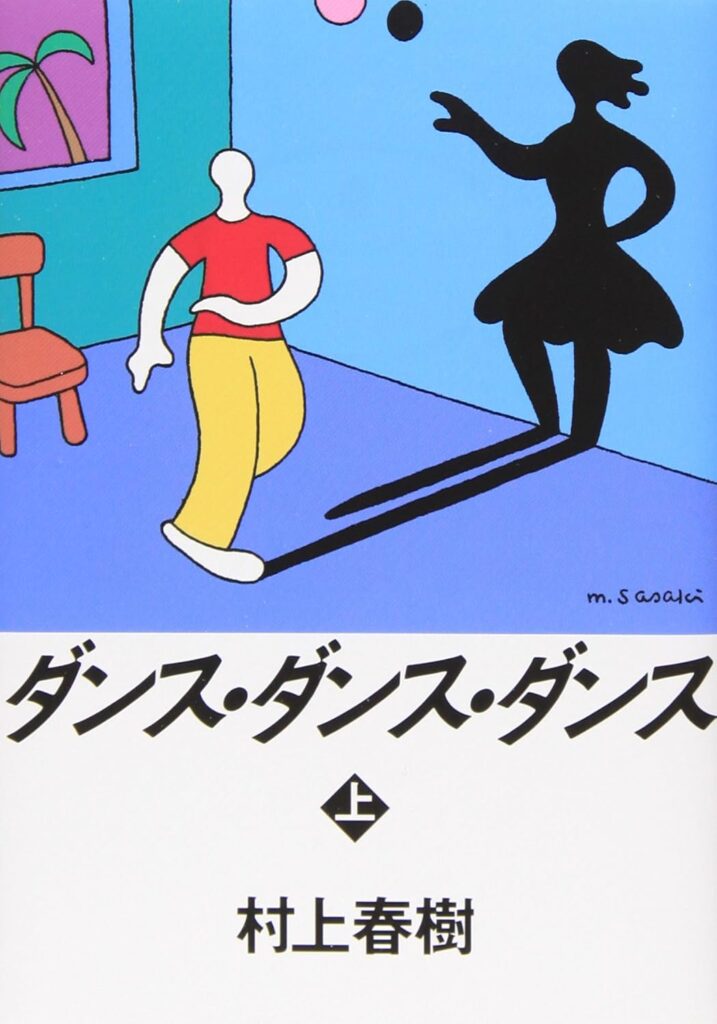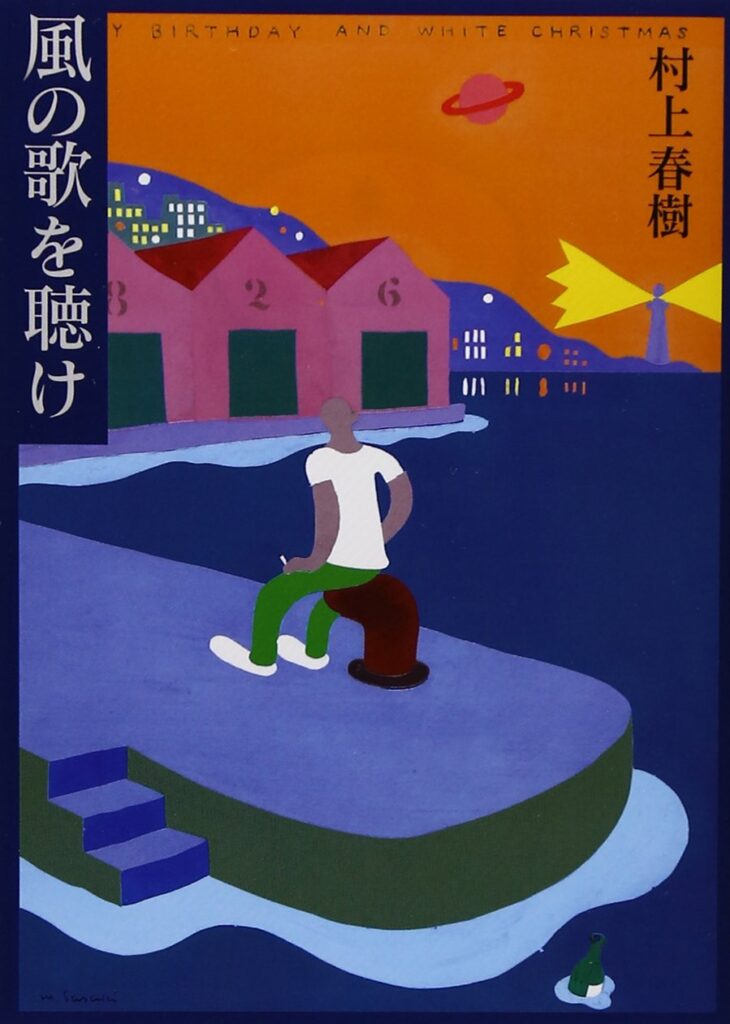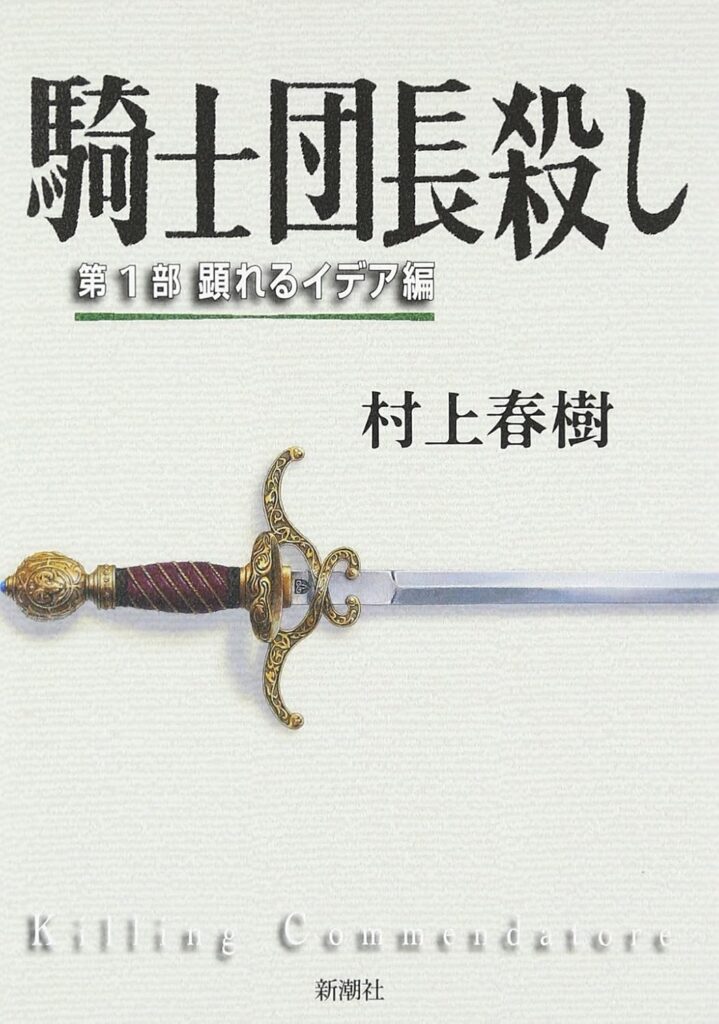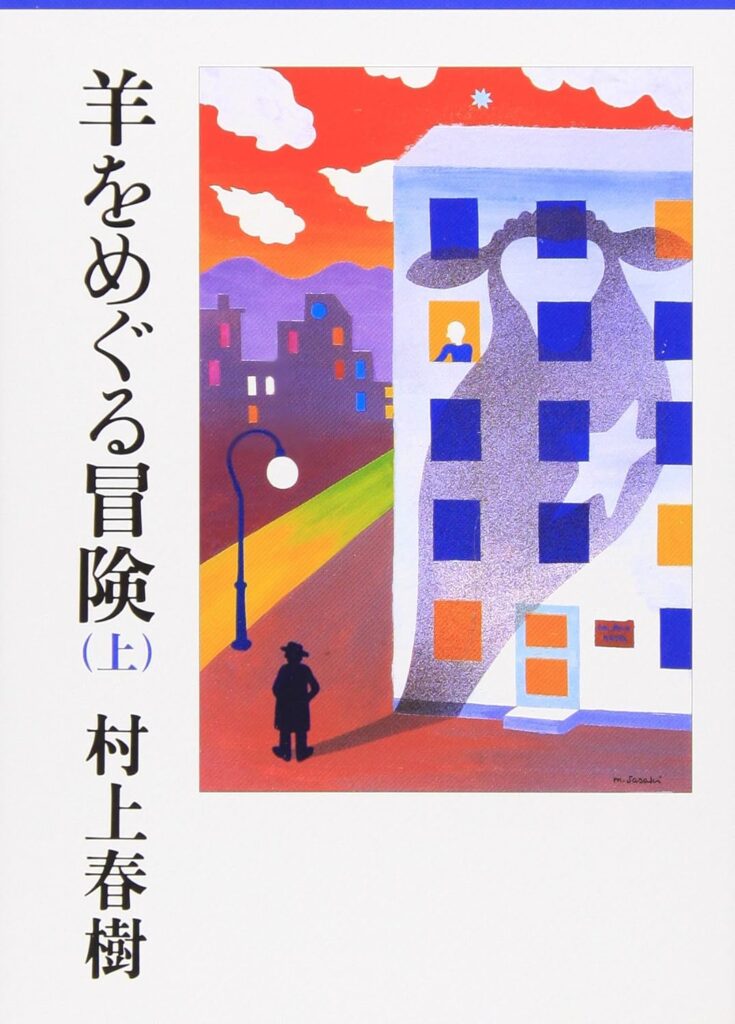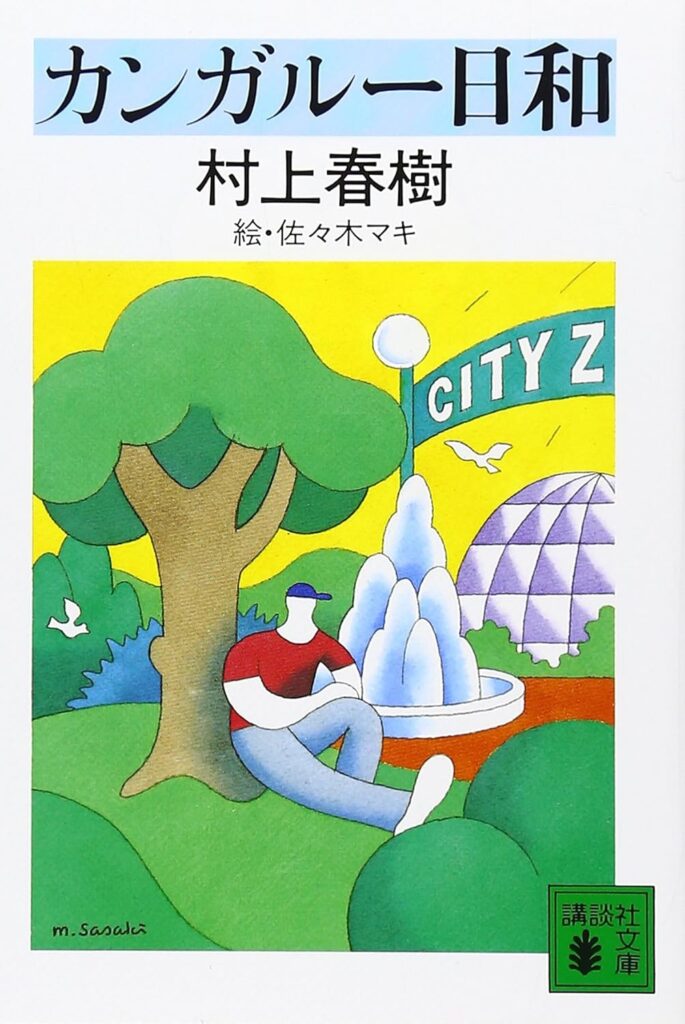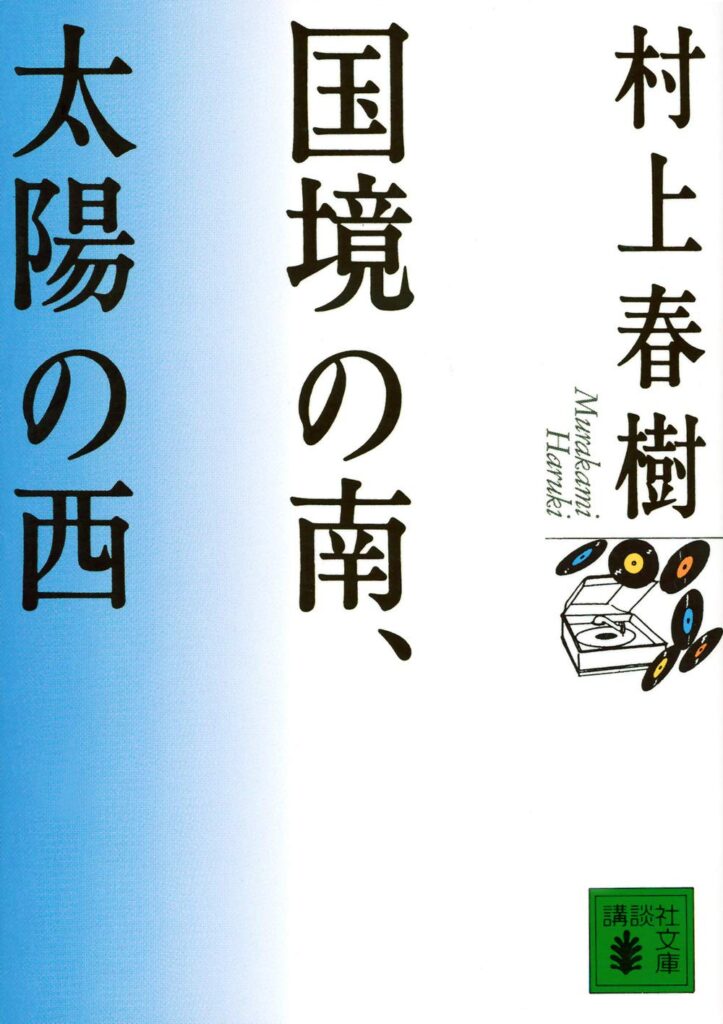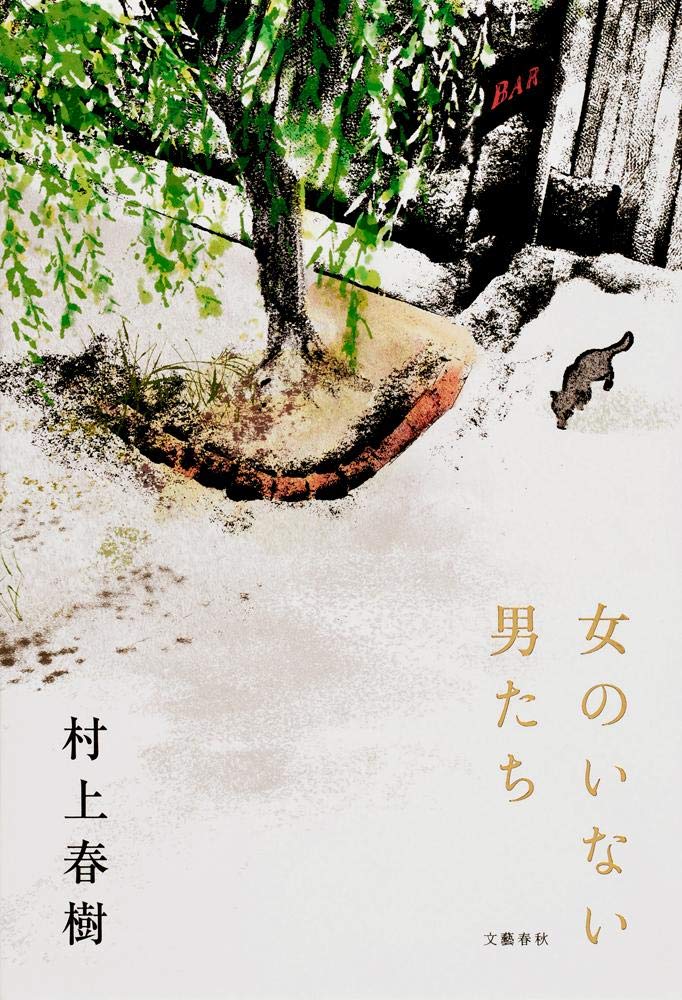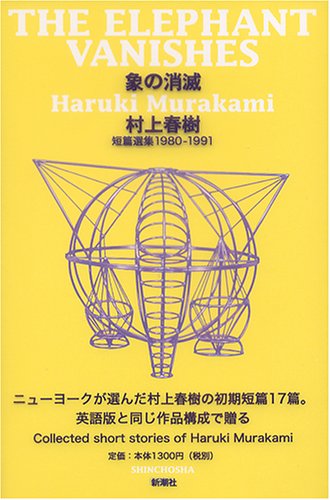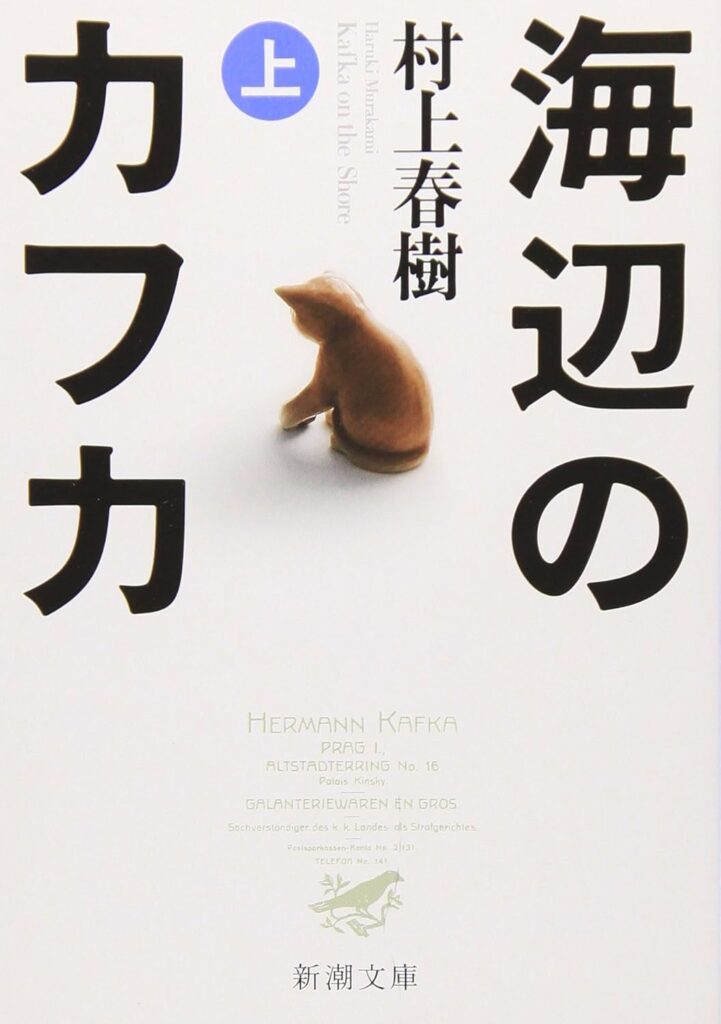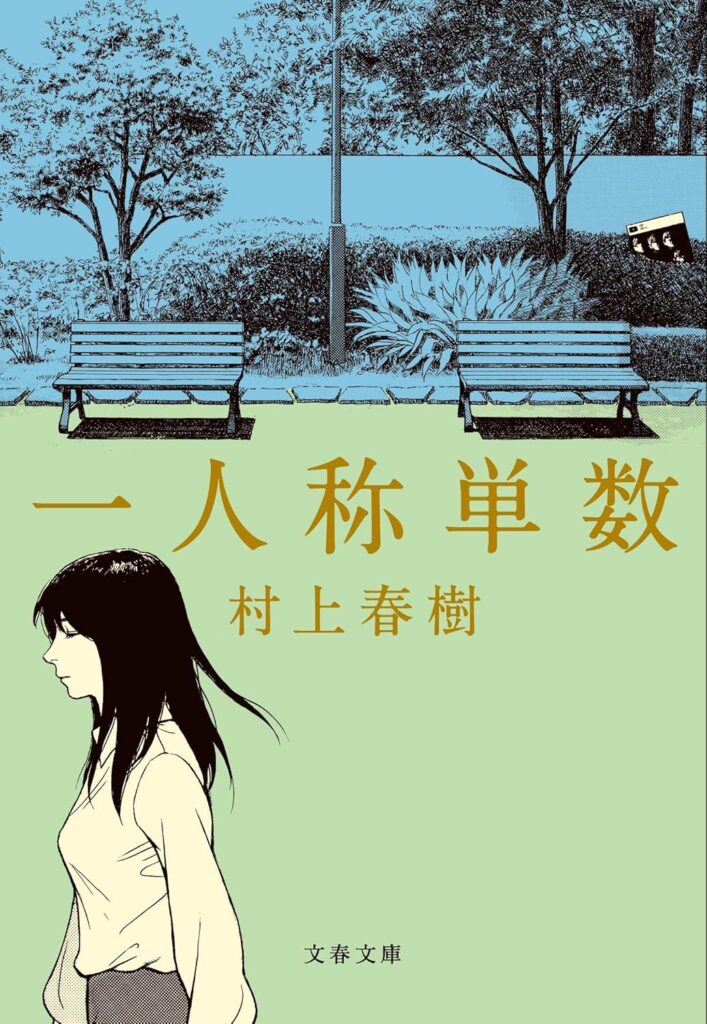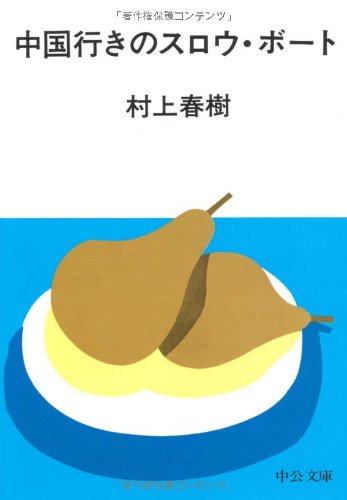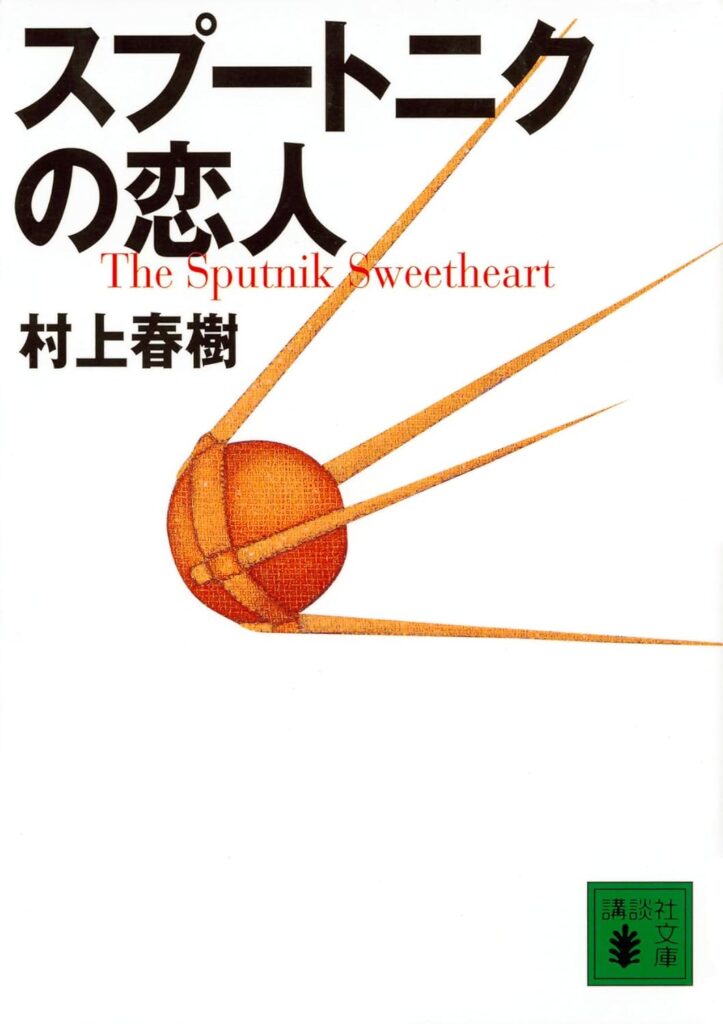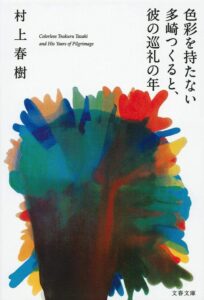 小説「色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。村上春樹さんの作品は、いつも私たちの心の奥底にある何かを静かに揺さぶる力を持っていますが、この物語も例外ではありません。主人公、多崎つくるが経験する喪失と再生の旅は、多くの読者の共感を呼ぶのではないでしょうか。
小説「色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。村上春樹さんの作品は、いつも私たちの心の奥底にある何かを静かに揺さぶる力を持っていますが、この物語も例外ではありません。主人公、多崎つくるが経験する喪失と再生の旅は、多くの読者の共感を呼ぶのではないでしょうか。
この物語は、過去に深く傷ついた一人の男性が、その原因を探るためにかつての友人たちを訪ね歩く、いわば「巡礼」の物語です。高校時代に固い友情で結ばれていたはずの仲間から、ある日突然、理由も告げられずに絶交されてしまったつくる。その出来事が彼の心に残した深い影と、長い年月を経て再び過去と向き合おうとする彼の姿が描かれます。なぜ彼は仲間たちから拒絶されたのか、そしてその経験が彼の人生にどのような影響を与えたのか。
この記事では、まず物語の筋道を追いながら、重要な出来事や転換点について触れていきます。その後、ネタバレを含む形で、物語の核心や登場人物たちの心理、そして私自身が感じたこと、考えたことを詳しくお話ししたいと思います。この物語が持つ独特の雰囲気や、読み解く上で鍵となる要素についても触れていきますので、すでに読まれた方も、これから読もうと考えている方も、ぜひお付き合いください。
小説「色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年」のあらすじ
物語の中心人物は、鉄道会社で駅の設計をしている三十六歳の多崎つくるです。彼は名古屋での高校時代、四人の親しい友人たちと常に一緒に過ごしていました。赤松慶(アカ)、青海裕司(アオ)、白根柚木(シロ)、黒埜恵理(クロ)。彼らの苗字にはそれぞれ「色」が含まれていましたが、多崎つくるだけが名前に色を持っていませんでした。そのことに、つくるはわずかな疎外感を抱きつつも、五人は完璧な調和を保ち、強い絆で結ばれた共同体として青春時代を過ごします。
しかし、つくるが東京の大学に進学して間もなく、その完璧な関係は突然終わりを迎えます。大学二年生の夏休み、名古屋にいる四人の友人から、理由も告げられずに「もう二度と連絡してこないでほしい」と一方的に関係を断絶されてしまうのです。この出来事はつくるの心に深い傷を残し、彼は半年もの間、ほとんど死の淵をさまようような精神状態で過ごしました。なぜ自分が拒絶されたのか、その理由は全く分かりませんでした。
それから十六年が経ち、つくるは駅舎の設計という仕事に打ち込みながらも、どこか心を閉ざしたまま生きていました。人間関係においても、深く踏み込むことを避けているようなところがありました。そんな彼に、二歳年上の恋人、木元沙羅(サラ)は、過去と向き合うことを勧めます。彼女の言葉に背中を押され、つくるはかつての友人たちを訪ね、十六年前に何があったのかを確かめるための「巡礼」に出ることを決意します。
まず名古屋でアオと再会したつくるは、衝撃的な事実を知らされます。絶交の原因は、シロが「つくるにレイプされた」と他の三人に告白したことだったのです。つくるには全く身に覚えのないことでした。次にフィンランドで陶芸家として暮らすクロを訪ねます。クロは、シロの告発はもしかしたら真実ではなかったかもしれないこと、そしてシロが数年前に浜松で何者かに殺害されていたことを告げます。つくるは、自分が知らない間に起きていた悲劇と、解き明かされない謎に打ちのめされながらも、過去の断片をつなぎ合わせようとします。
小説「色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年」の長文感想(ネタバレあり)
この『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』という作品は、読後、心の中に静かでありながらも、深く長く響き続ける問いを残していく物語だと感じます。それは、私たちが生きていく上で避けては通れない、喪失の痛みと、それでも他者と繋がりを求めずにはいられない人間の性(さが)についての問いかけのようです。主人公、多崎つくるの「巡礼」は、単なる過去の謎解きではなく、彼自身の魂の遍歴であり、自己を発見し、受け入れていくための旅路でした。
物語の核となるのは、つくるが高校時代に経験した、理由なき追放です。アカ、アオ、シロ、クロという「色彩」を持つ四人の友人たちと、唯一「色彩を持たない」つくる。この五人の完璧な調和と共同体は、つくるにとって世界の全てでした。しかし、彼はその一員でありながらも、どこかで自分だけが違うという感覚、言い換えれば「欠落感」のようなものを抱えていたのかもしれません。名前の色が象徴するように、彼は自分を、他者とは異なる、何か本質的なものが欠けた存在だと感じていた節があります。だからこそ、突然の絶交は、彼の存在そのものを否定されるような、耐え難い衝撃だったのでしょう。
絶交の理由が十六年後に明かされる場面は、物語の大きな転換点です。アオから告げられた「シロのレイプ告発」という事実は、つくるにとって青天の霹靂でした。身に覚えのない罪を着せられ、最も信頼していた友人たちから拒絶されたという事実は、彼の受けた傷の深さを改めて浮き彫りにします。しかし、物語は単純な冤罪事件の真相究明には向かいません。フィンランドで再会したクロの口から語られるのは、シロの精神的な不安定さ、告発の信憑性への疑念、そしてシロ自身の悲劇的な死です。
ここで、物語はミステリーの様相を帯びてきます。シロはなぜつくるを名指ししたのか? 本当は何があったのか? そして、シロを殺害したのは誰なのか? これらの問いは、読者の心にも強く響きます。特にシロの死に関しては、様々な憶測を呼ぶ要素が散りばめられています。参考にした文章でも触れられているように、ネット上では「父親犯人説」や、さらに踏み込んで「つくる犯人説(多重人格などを含む)」まで考察されています。つくるが見る、妙に生々しいシロとの性交の夢、シロが殺された時期とつくるの父親が亡くなった時期の近さ、シロが住んでいた浜松という場所(名古屋と東京の中間)など、確かにつくる自身への疑念を抱かせるような描写は存在します。あるいは、シロが父親から性的虐待を受けていた可能性を考えると、彼女の精神的な不安定さや謎の妊娠(クロが付き添って堕胎したという事実)にも説明がつくかもしれません。
しかし、村上春樹さんの作品において、こうした謎は必ずしも明確な解答が用意されているわけではありません。むしろ、解き明かされないこと自体に意味があるのかもしれません。シロの死の真相は、つくるにとっても、読者にとっても、永遠に霧の中です。つくるはクロに「彼女を殺したのは僕かもしれない」と語り、クロは「ある意味では私かもしれない」と返す。このやり取りは、直接的な犯人探しではなく、もっと深いレベルでの関与、つまり、自分たちの過去の選択や無関心が、巡り巡って悲劇を招いたのではないかという、重い責任感や罪悪感の共有を示唆しているように思えます。未解決の謎は、まるで深海に沈んだままの古い宝箱のように、読者の心に重く、しかし魅力的な問いを投げかけ続けます。
そして、もう一つの大きな謎が、大学時代につくると親しくなった後輩、灰田文紹の存在です。彼は頭脳明晰で哲学的、つくるにリストの「巡礼の年」を教え、緑川という奇妙なピアニストの話をする、どこか浮世離れした青年です。彼がつくるの前に現れ、そしてある日忽然と姿を消す。参考文章にもあったように、「灰田はつくるが生み出した幻想ではないか」と感じた読者も少なくないでしょう。彼の存在の曖昧さ、彼が語る象徴的な物語(特に緑川の持つ「六本目の指」の話は、五人の友人グループとの関連を想起させます)、そして彼がつくるの性的な夢の中に現れる場面などは、彼の存在を現実と幻想の狭間に置いているかのようです。
灰田は、つくるが深い喪失感を抱えていた時期に現れ、彼が再び他者との関係性を模索し始める段階で消えていきます。彼は、つくるが自己を取り戻す過程で必要とした、一時的な「伴走者」あるいは「触媒」のような役割を果たしたのかもしれません。彼の実在を証明する「退寮届」という客観的な事実はありますが、彼の物語における役割は、現実的な友人という以上に、つくるの内面世界を映し出す鏡のような、象徴的な意味合いを強く持っているように感じられます。灰田が残したリストの「巡礼の年」の音楽は、まさにつくる自身の人生の旅路と重なり合い、物語全体を静かに彩っています。
これらの解き明かされない謎や象徴的な要素は、物語を多層的にし、様々な解釈を可能にしています。しかし、物語の中心にあるのは、やはり多崎つくるという一人の人間の、傷からの回復と再生のプロセスです。彼は「巡礼」を通して、過去の出来事の断片を集め、友人たちの現在の姿を知り、そして何よりも自分自身と向き合います。彼は、自分が「色彩を持たない」ことに劣等感を抱いていましたが、旅を通して、それが欠点ではなく、彼自身の個性の一部であると受け入れ始めるのです。
その過程で重要な役割を果たすのが、恋人である沙羅の存在です。彼女はつくるに過去と向き合う勇気を与え、彼の話に耳を傾け、彼を支えます。彼女自身もまた、他の男性との関係を持つなど、単純ではない側面を持っていますが、つくるにとっては、十六年間の孤独の後で初めて、心から繋がりを求めたいと思える相手となります。参考文章で触れられていた「沙羅=シロの姉」説は、確かに「沙羅双樹」という名前や、彼女がつくるに近づいた理由に別の意味合いを持たせる興味深い推測ですが、作中で明確な根拠は示されていません。むしろ、沙羅との関係における不確かさや葛藤こそが、つくるが乗り越えなければならない壁なのかもしれません。
物語の終盤、つくるは沙羅に自分の気持ちを伝え、彼女の答えを待つことを決意します。結果がどうなるかは描かれていません。しかし、重要なのは、彼が再び他者に対して心を開き、関係性を築こうと一歩踏み出したことです。それは、参考文章にあった緑川の言葉を借りれば、「跳躍」です。過去の傷や未来への不安、相手への疑念(沙羅が別の男性と関係を持っていることへの)といった、足元の見えない深い淵を前にして、それでも手を伸ばすことを選んだのです。
村上春樹さんは、別の作品のあとがきで「人の心と人の心は調和だけで結びついているのではない。それはむしろ傷と傷によって深く結びついているのだ」というようなことを書いていますが、この言葉は『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』のテーマをよく表していると思います。つくるは、友人たちとの完璧な調和が崩れたことによって深く傷つきましたが、その傷と向き合い、他者の傷や痛みを知ることを通して、新たな繋がりを見出そうとします。完璧ではない、不確かで、時に痛みを伴うかもしれないけれど、それでもなお求めずにはいられない人間関係のあり方を、この物語は静かに描き出しているのではないでしょうか。
読み終えた後、私たちは多崎つくるがこれからどのような人生を歩むのか、沙羅との関係はどうなるのか、そしてシロの死の真相は、などと考えを巡らせるでしょう。しかし、それらの答えが見つからないことこそが、この物語が持つリアリティなのかもしれません。私たちの人生もまた、解き明かせない謎や、完全には癒えない傷を抱えながら続いていくものです。それでも、過去を受け入れ、未来に向かって歩き出すこと。その静かな決意の中に、確かな希望の光を見出すことができる、そんな作品だと感じました。
まとめ
この記事では、村上春樹さんの小説『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』について、物語の筋道と、ネタバレを含む感想や考察をお話しさせていただきました。主人公の多崎つくるが、高校時代に理由なく友人たちから絶交された過去の傷と向き合い、真相を探る「巡礼」の旅に出る物語です。
旅を通して、つくるは友人たちとの再会を果たし、絶縁の理由が友人シロの偽りの告発にあったこと、そしてそのシロが後に殺害されていたという衝撃的な事実を知ります。物語には、シロの死の真相や、大学時代の謎めいた友人・灰田の存在など、解き明かされないままの要素が多く残されています。しかし、それらの謎も含めて、つくるが過去を受け入れ、自己を再発見していく過程が丁寧に描かれています。
最終的に、つくるは恋人である沙羅との関係において、不確かさを受け入れながらも未来へ踏み出すことを決意します。この物語は、喪失と再生、人間関係における傷と絆、そして解き明かせない謎を抱えながらも生きていくことの意味を問いかけてくる、深く静かな余韻を残す作品です。読まれた方が、それぞれに何かを感じ、考えるきっかけとなれば幸いです。