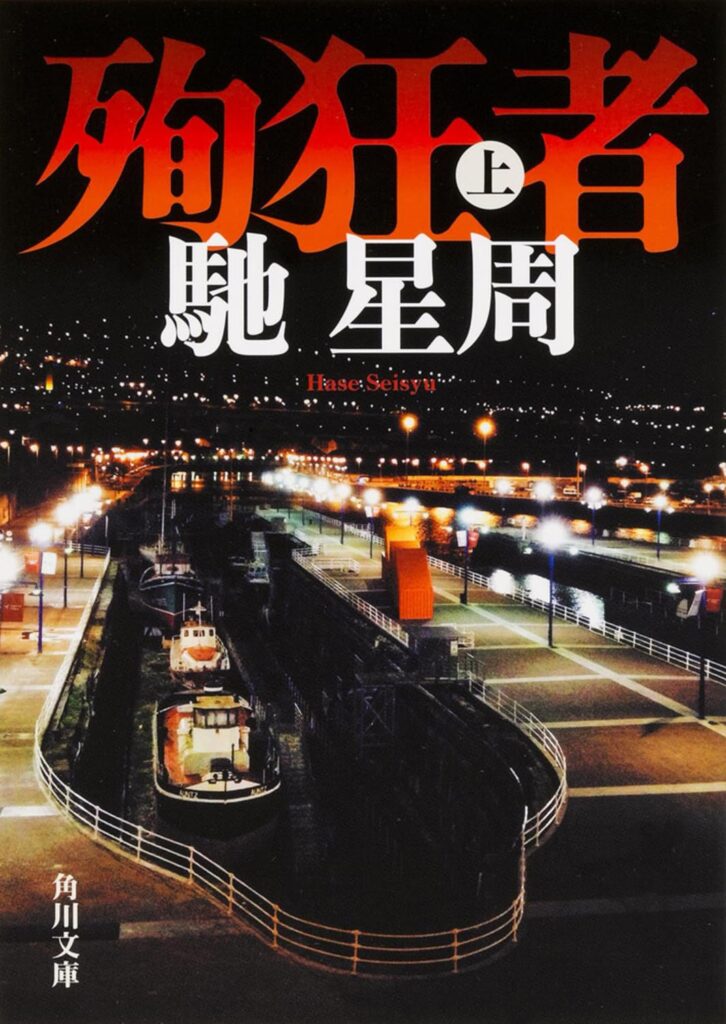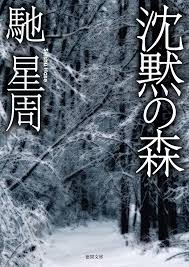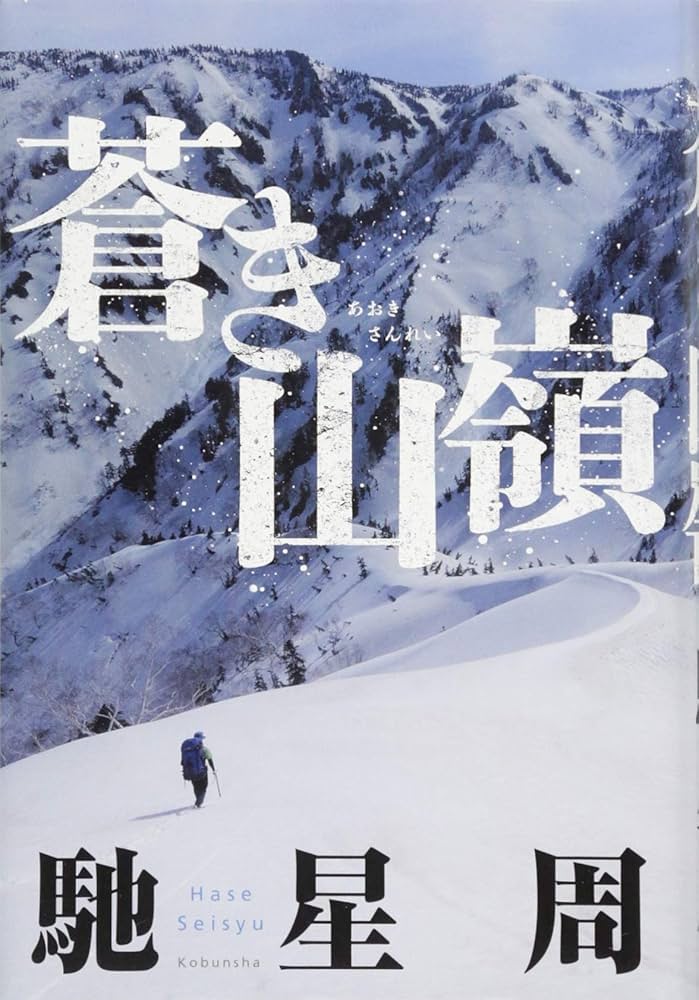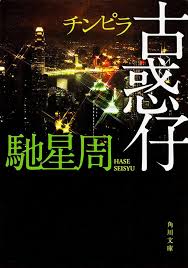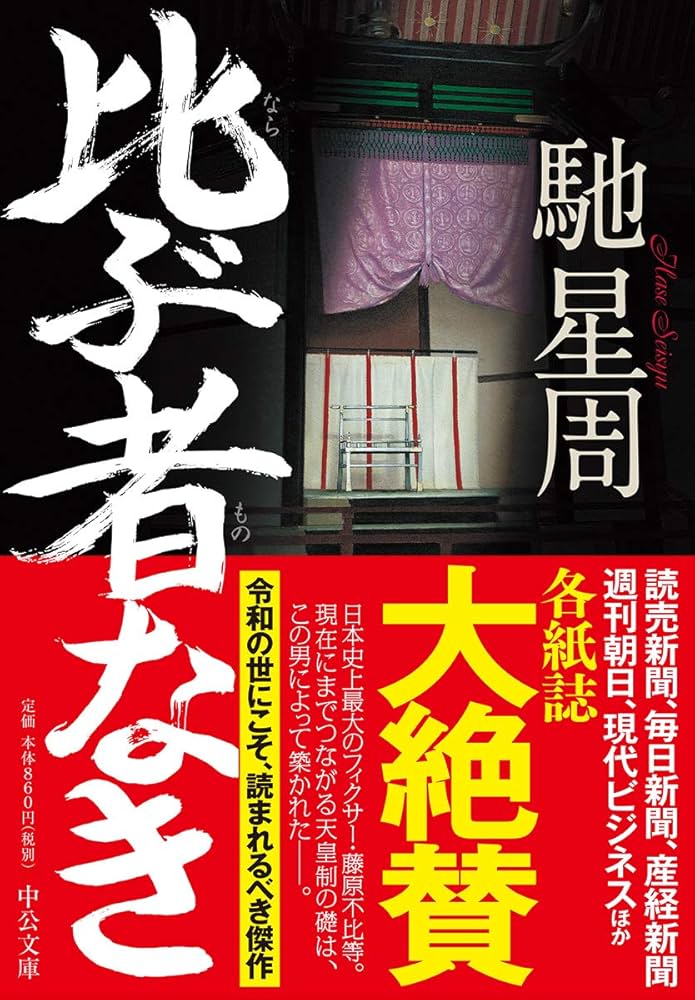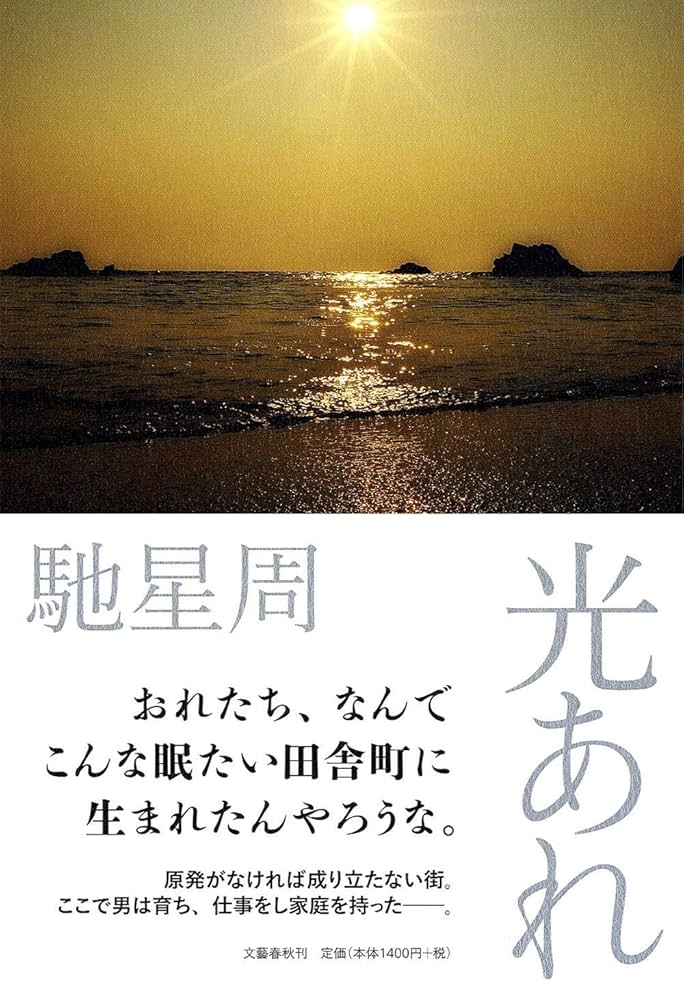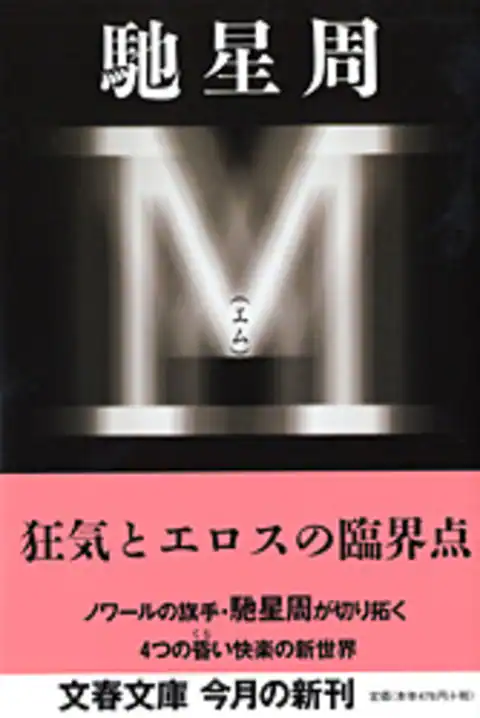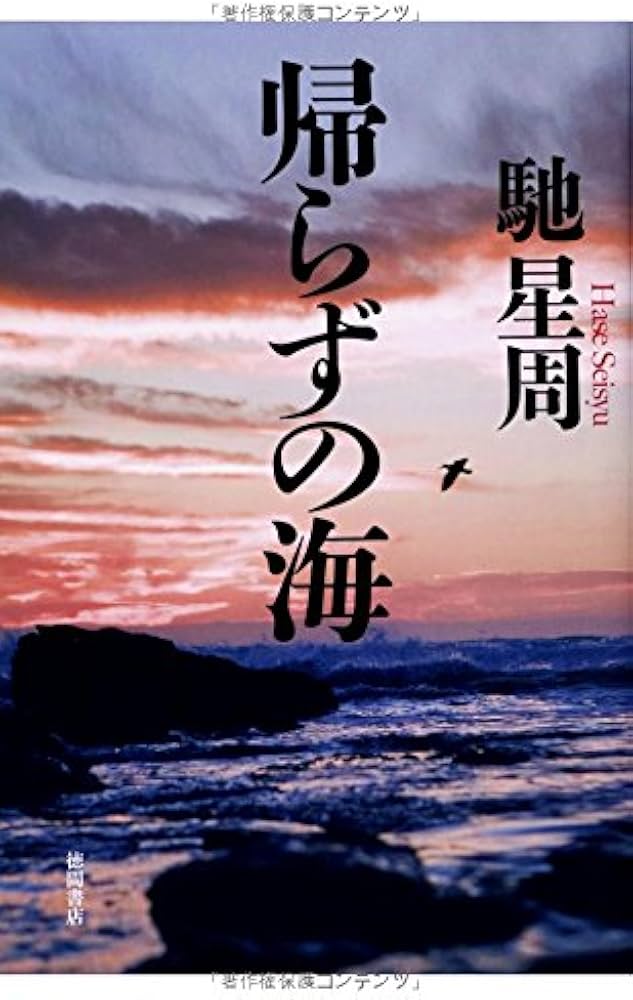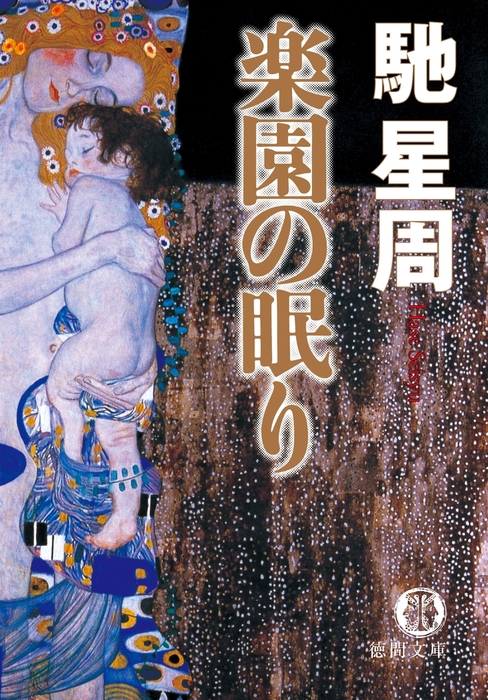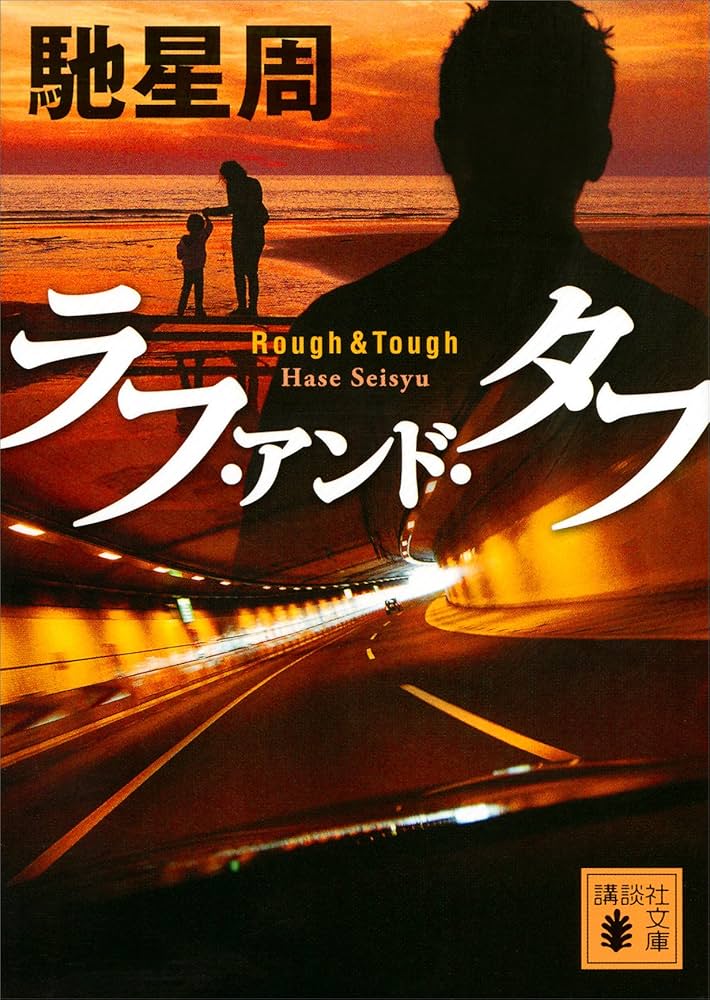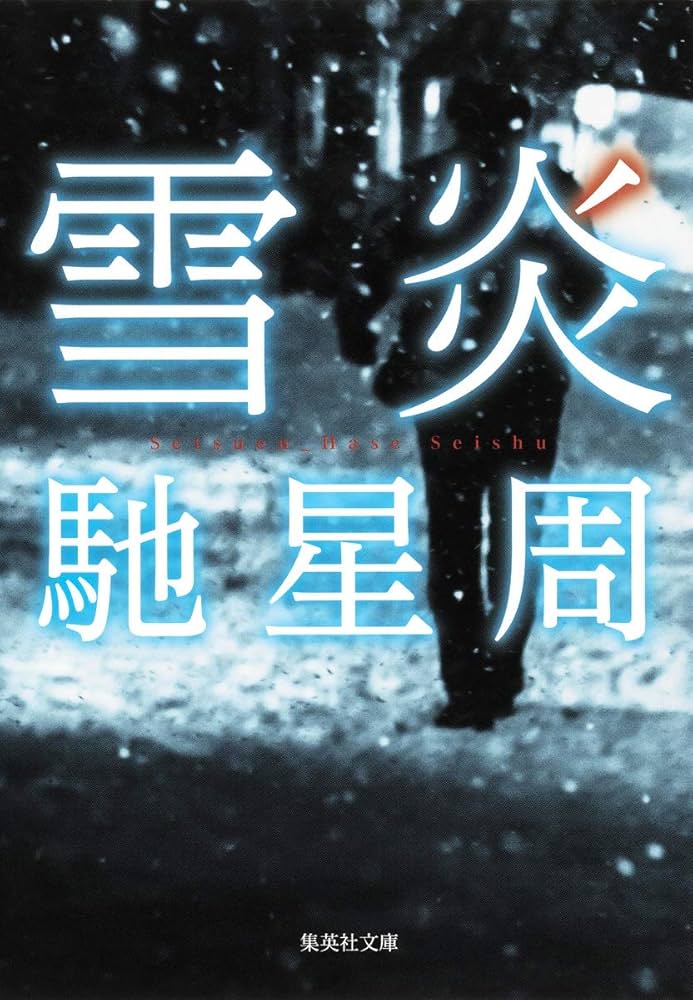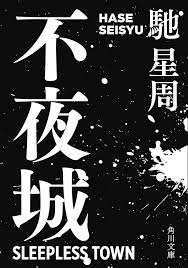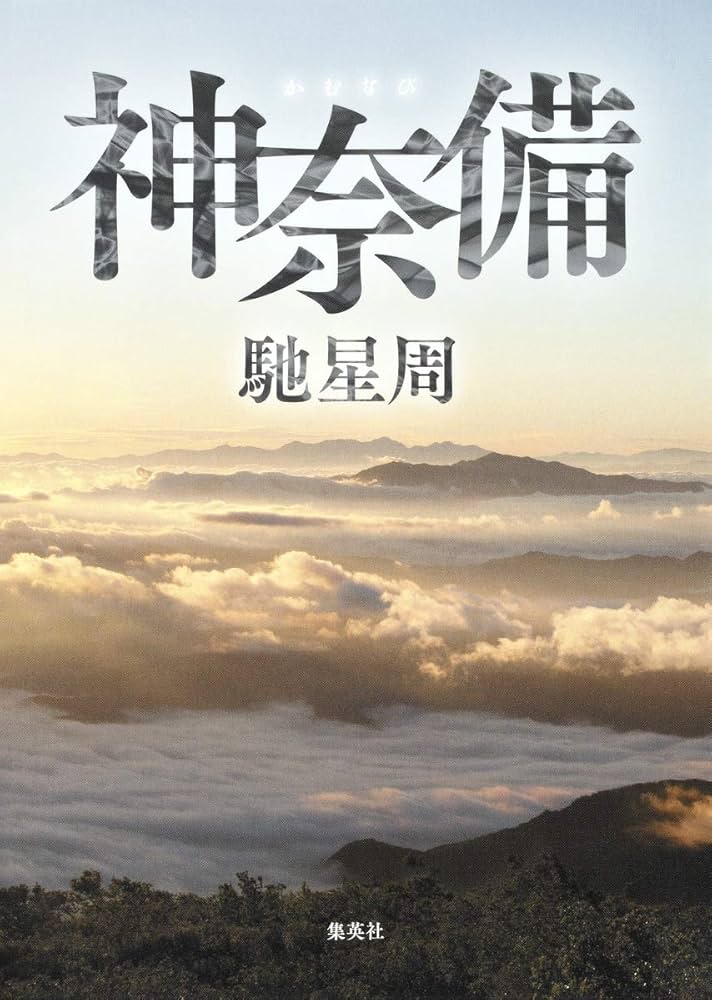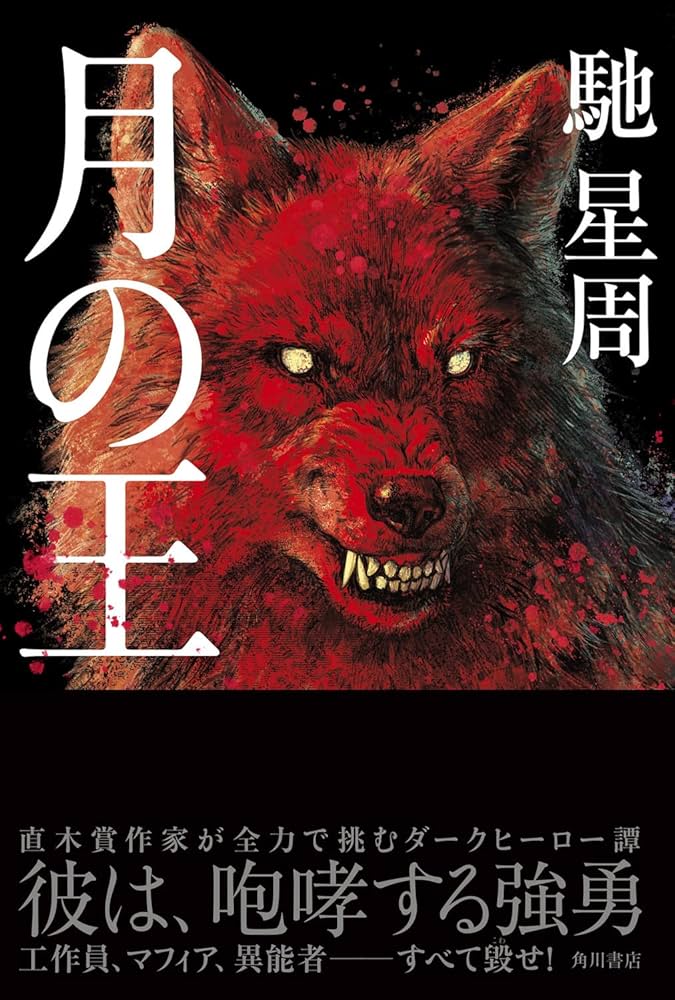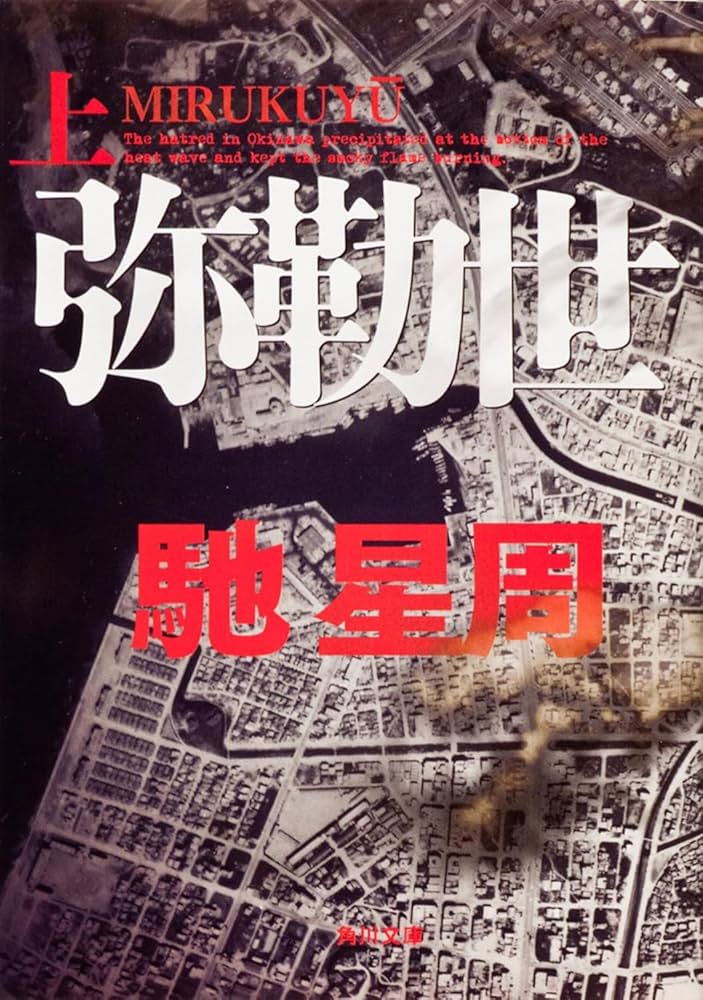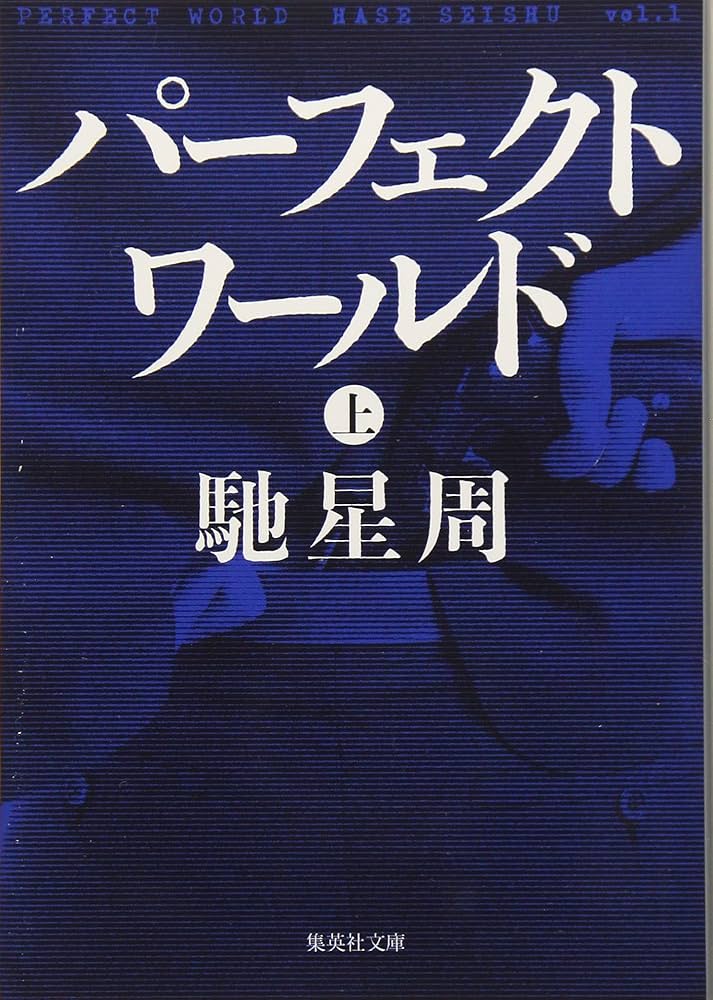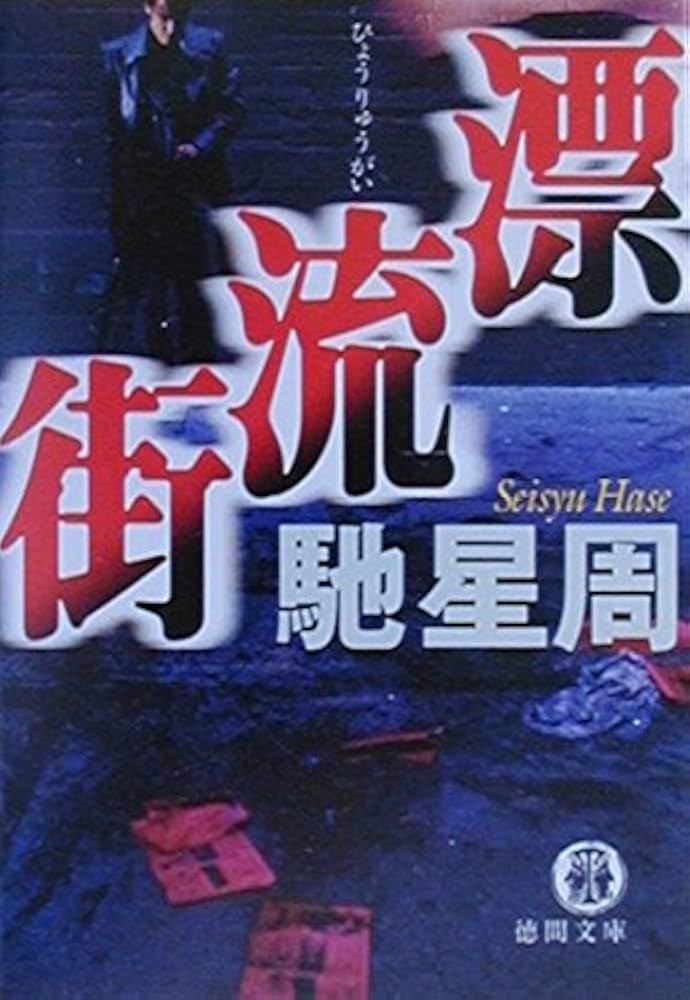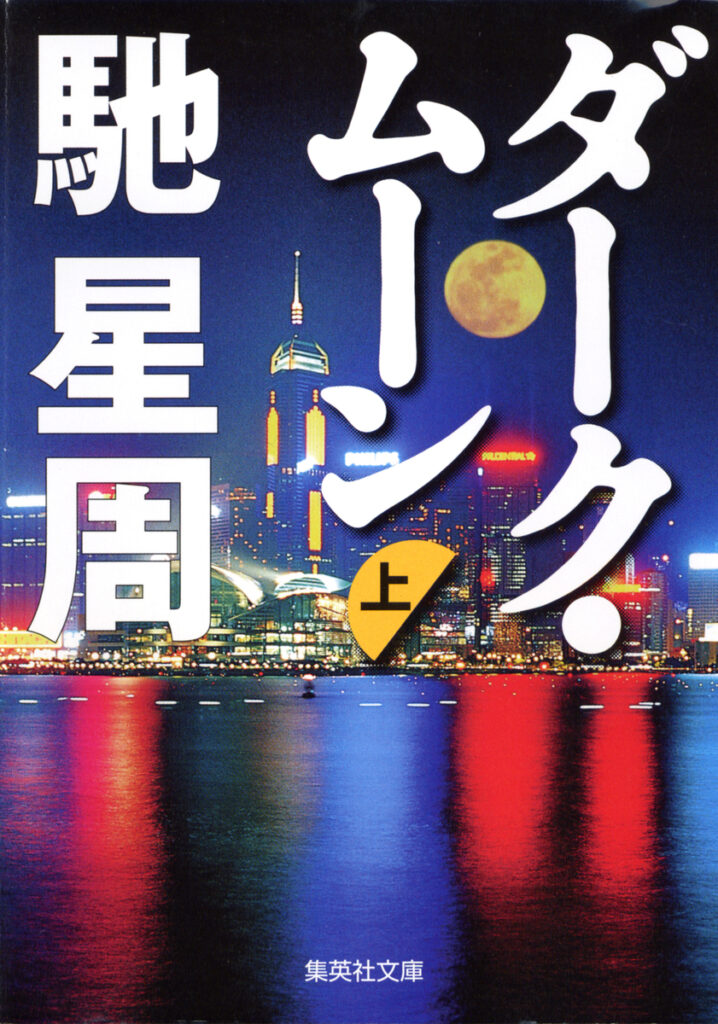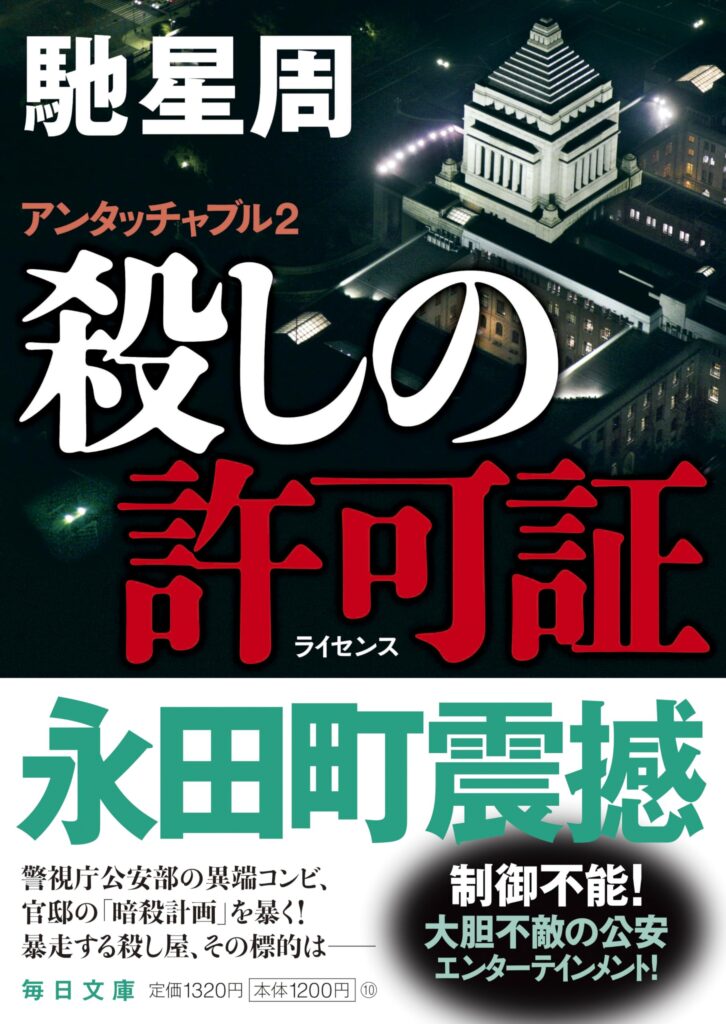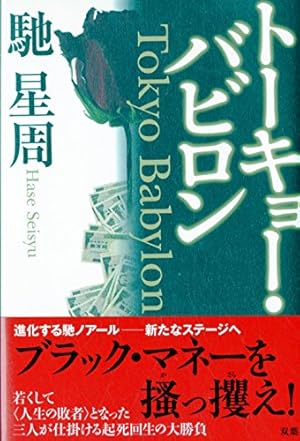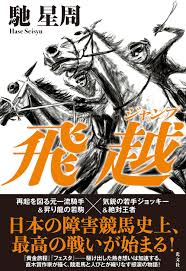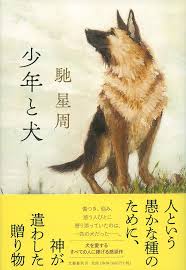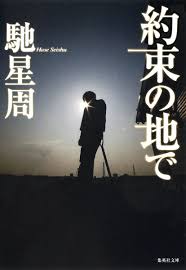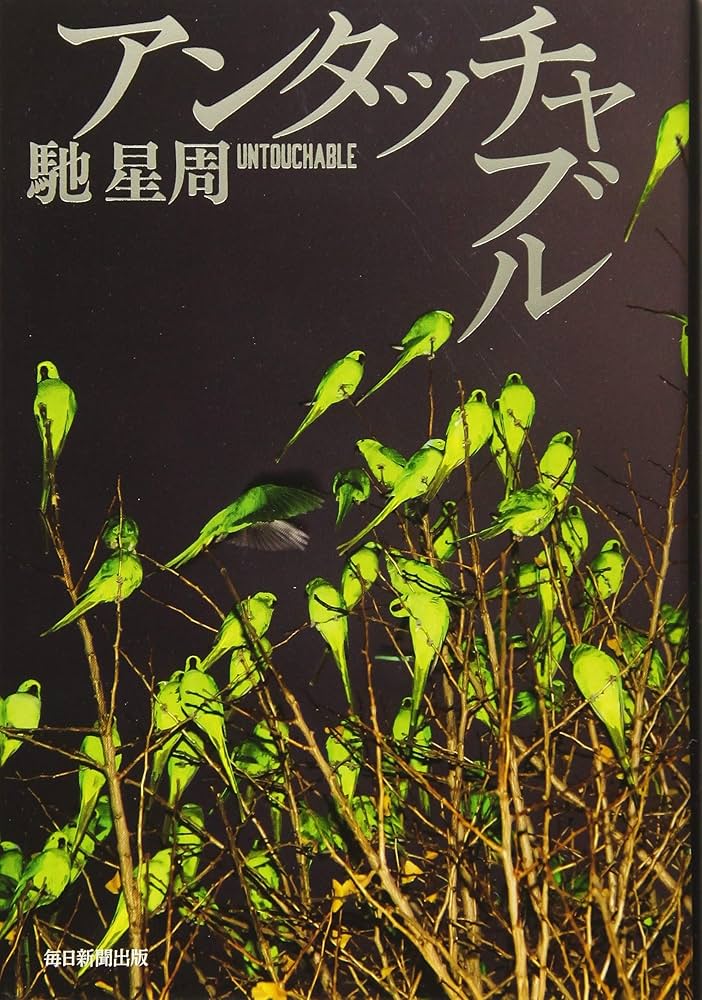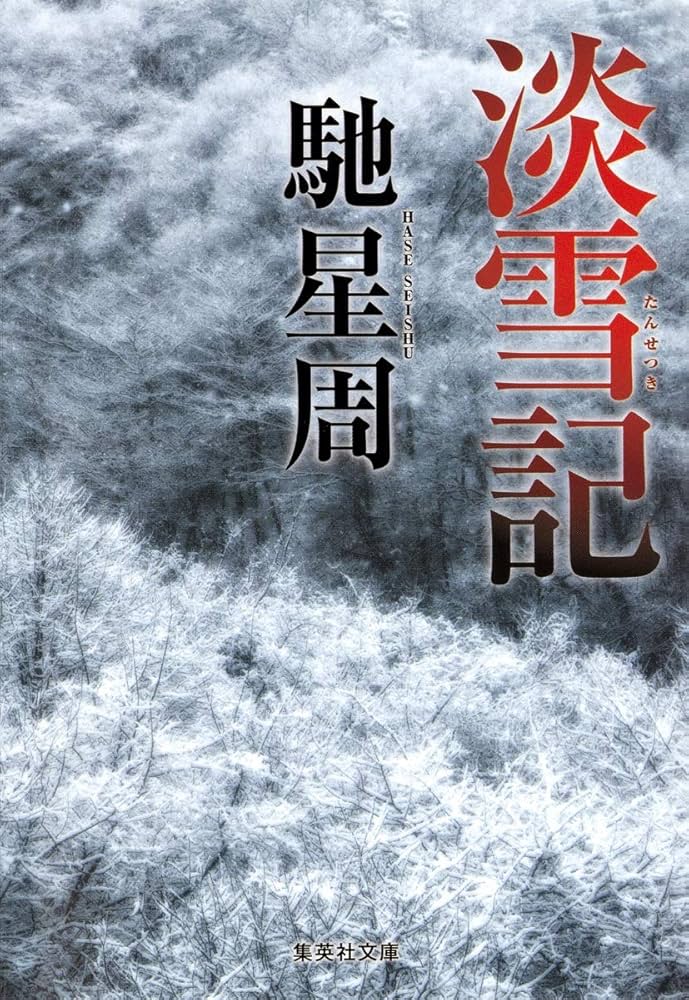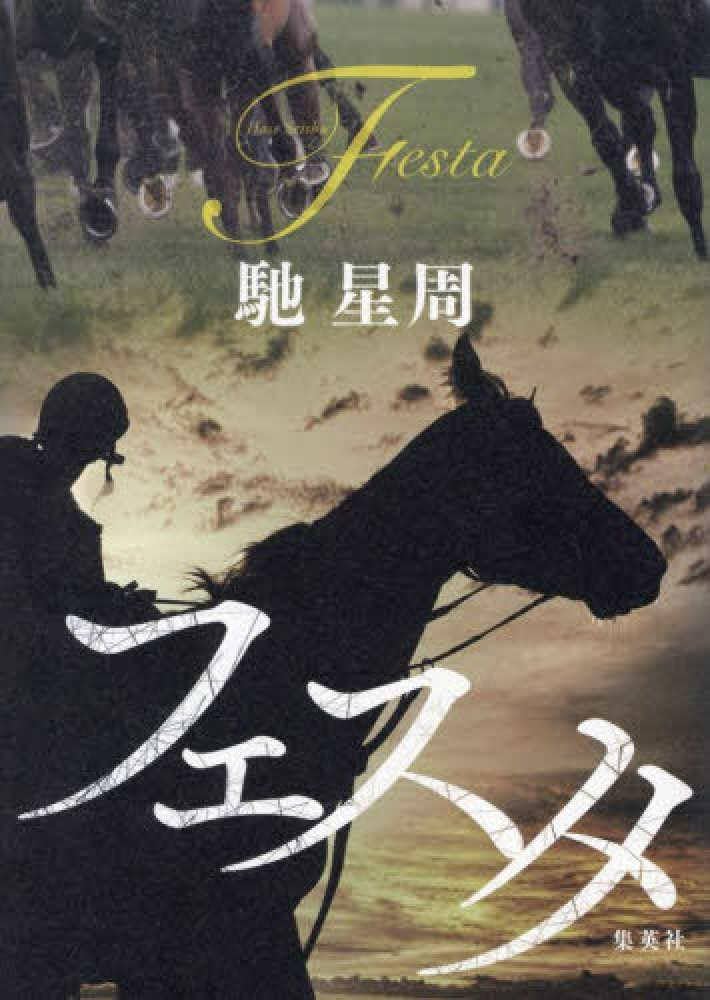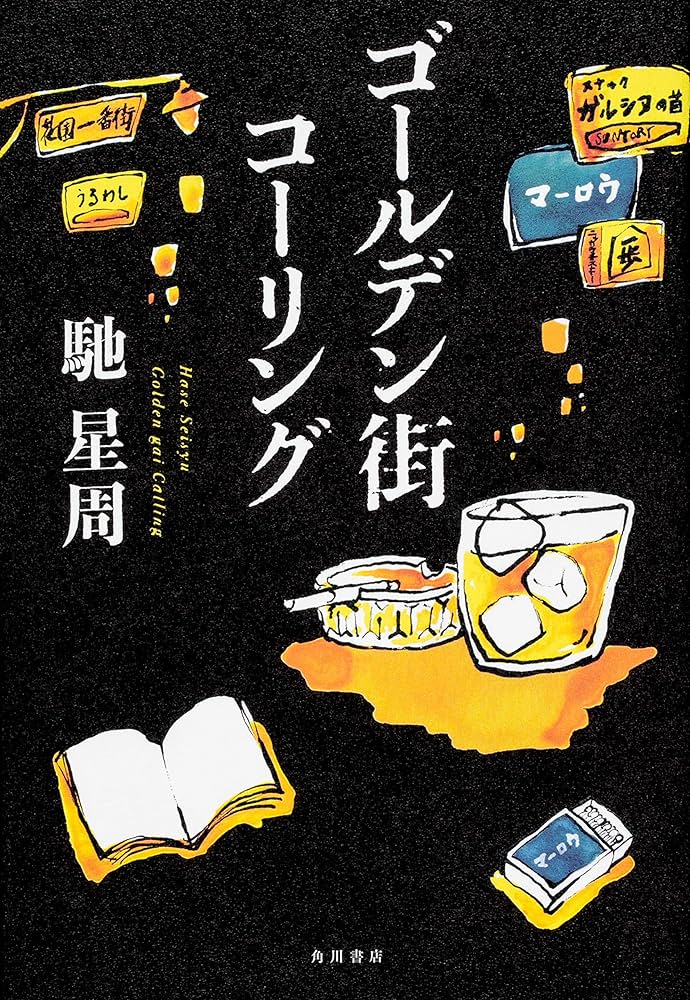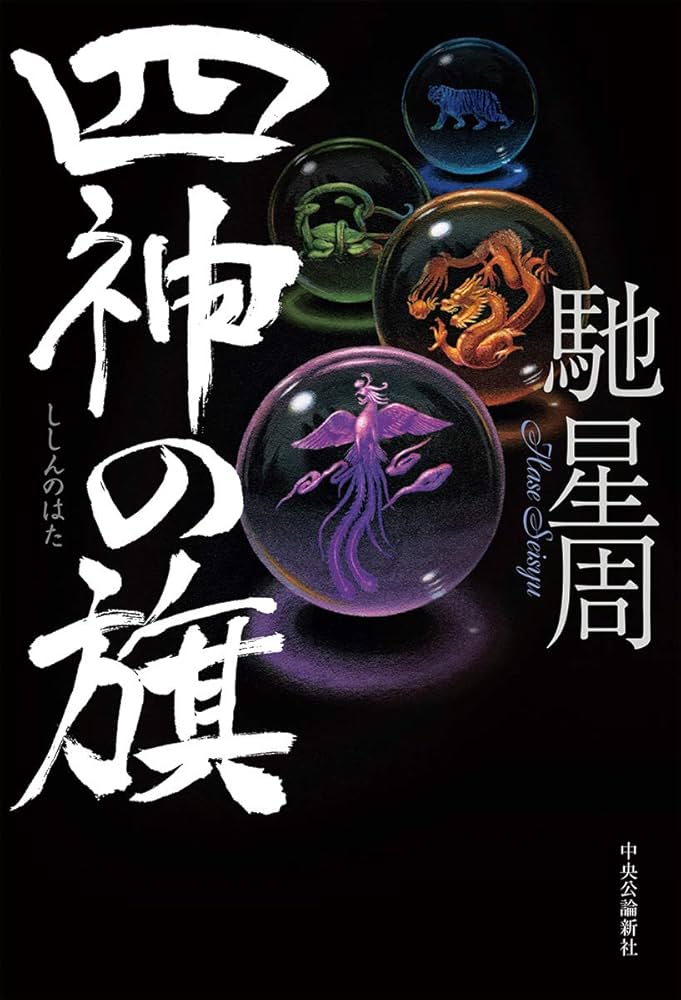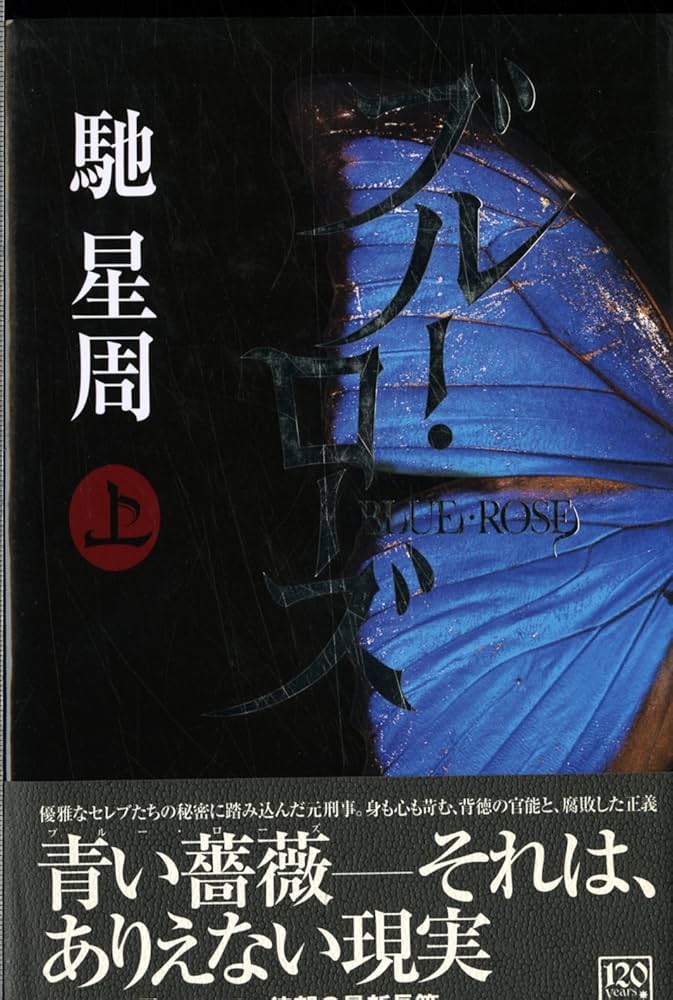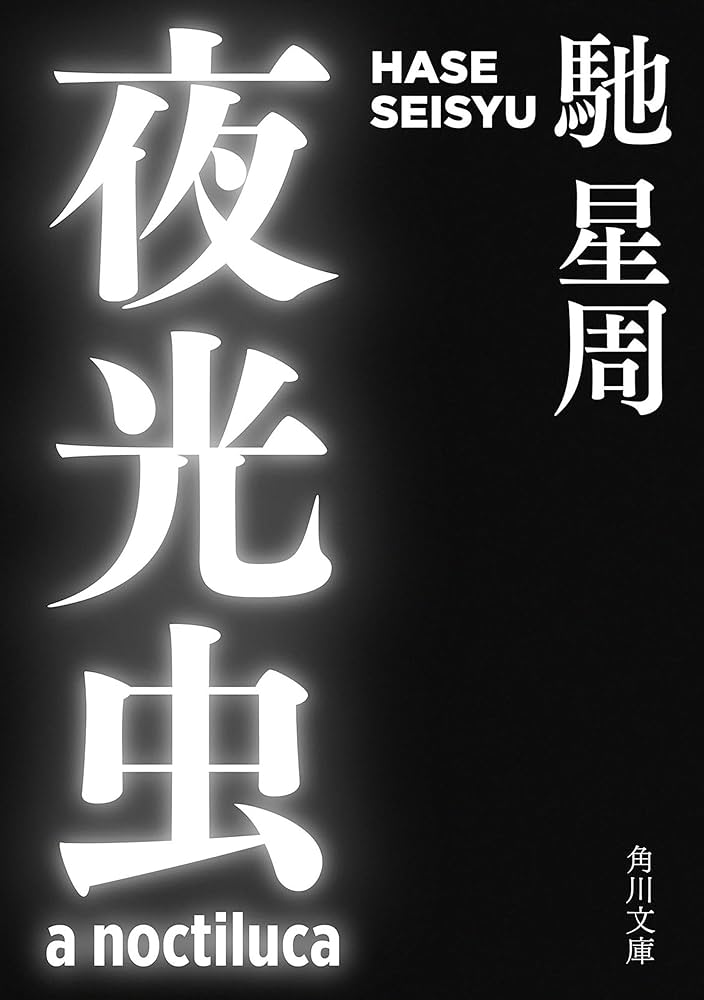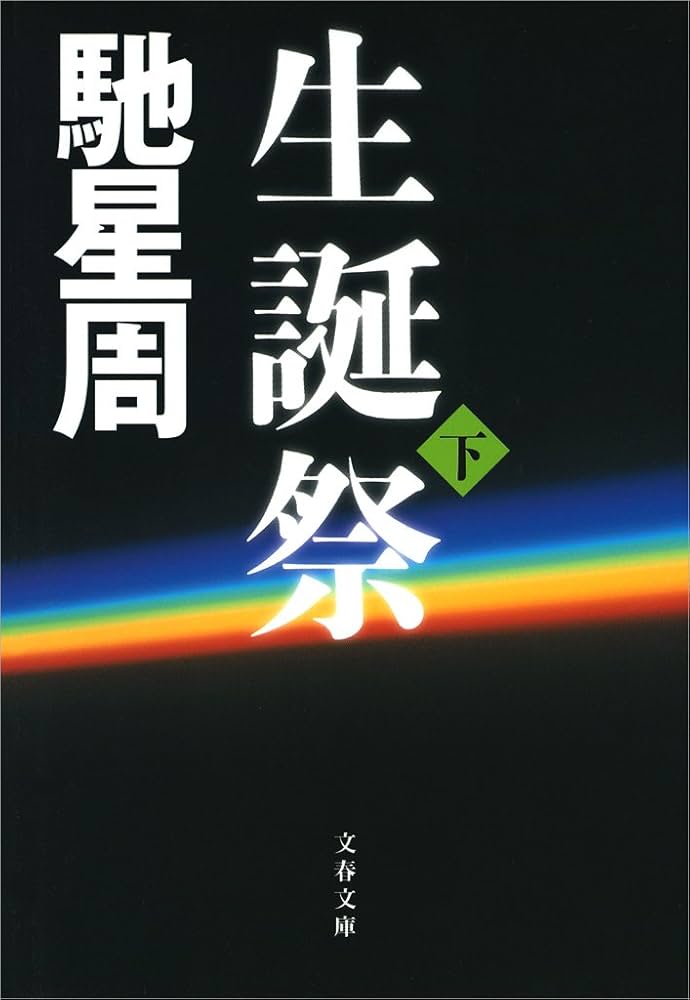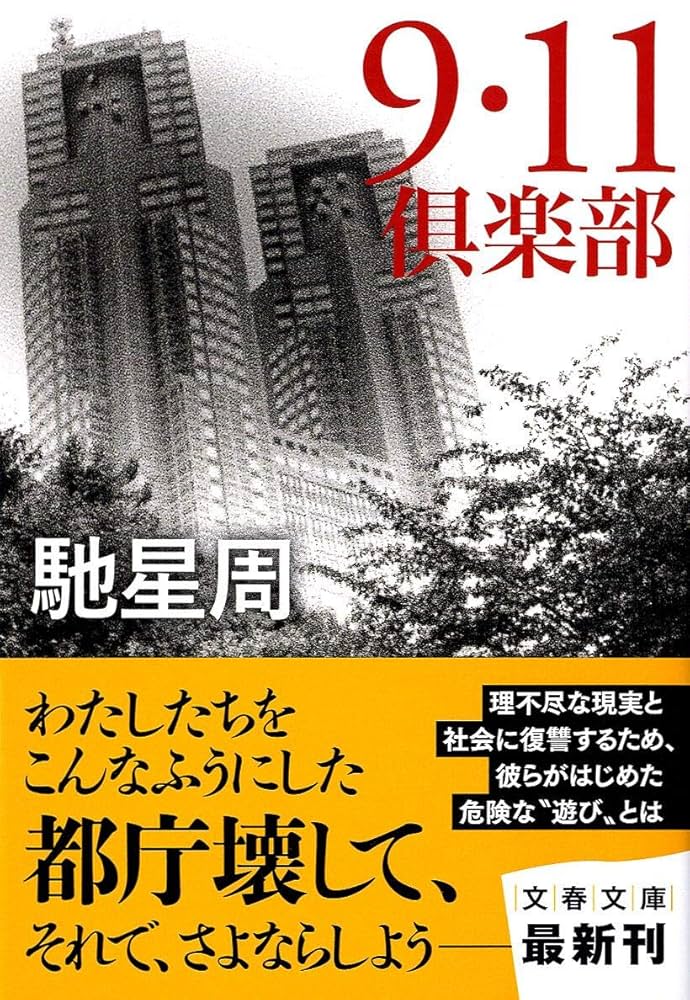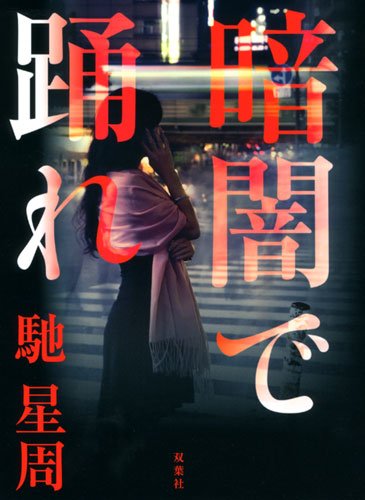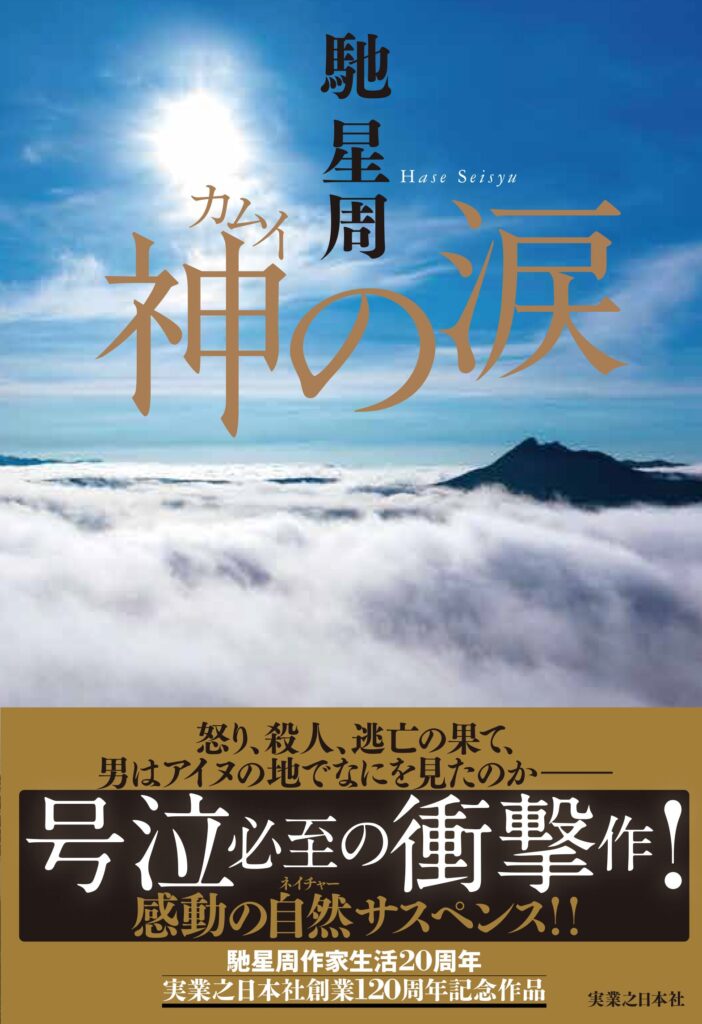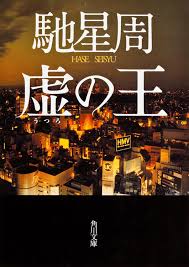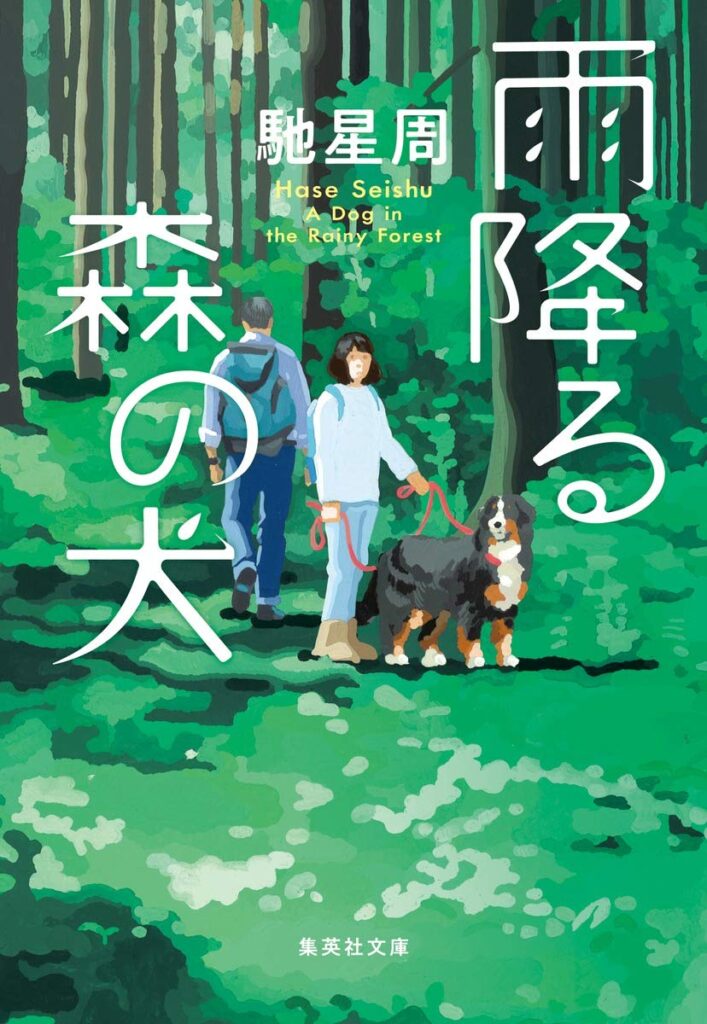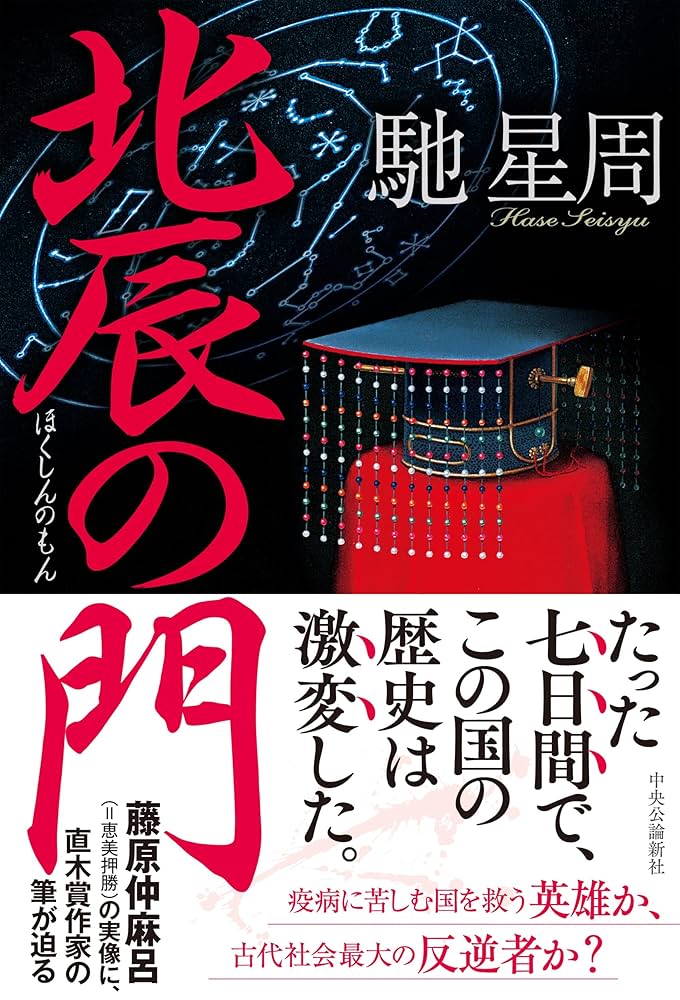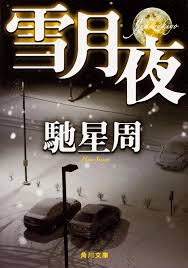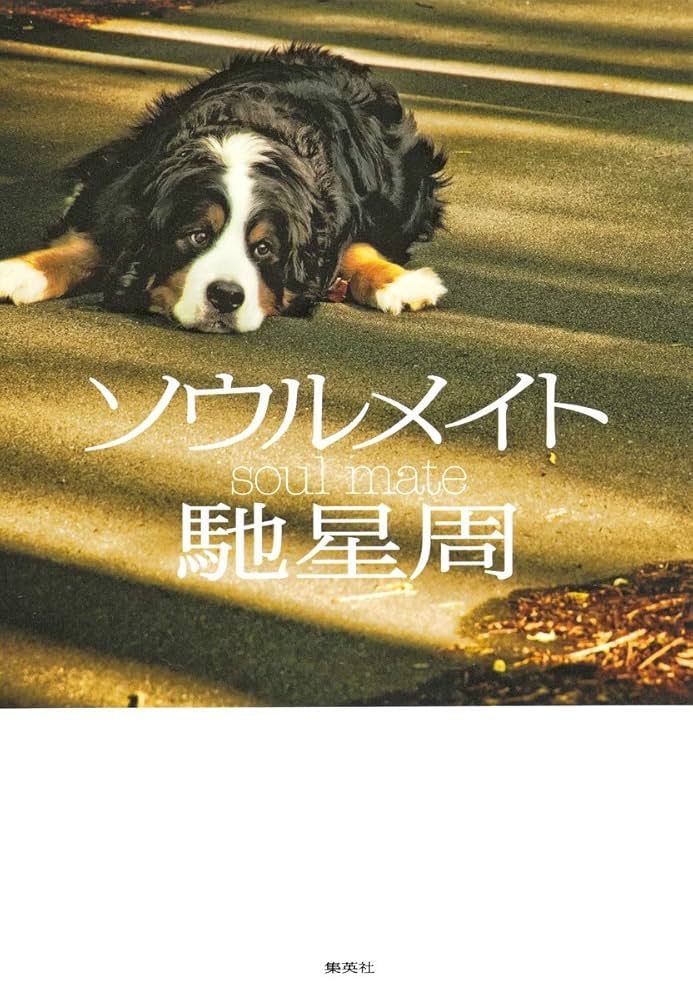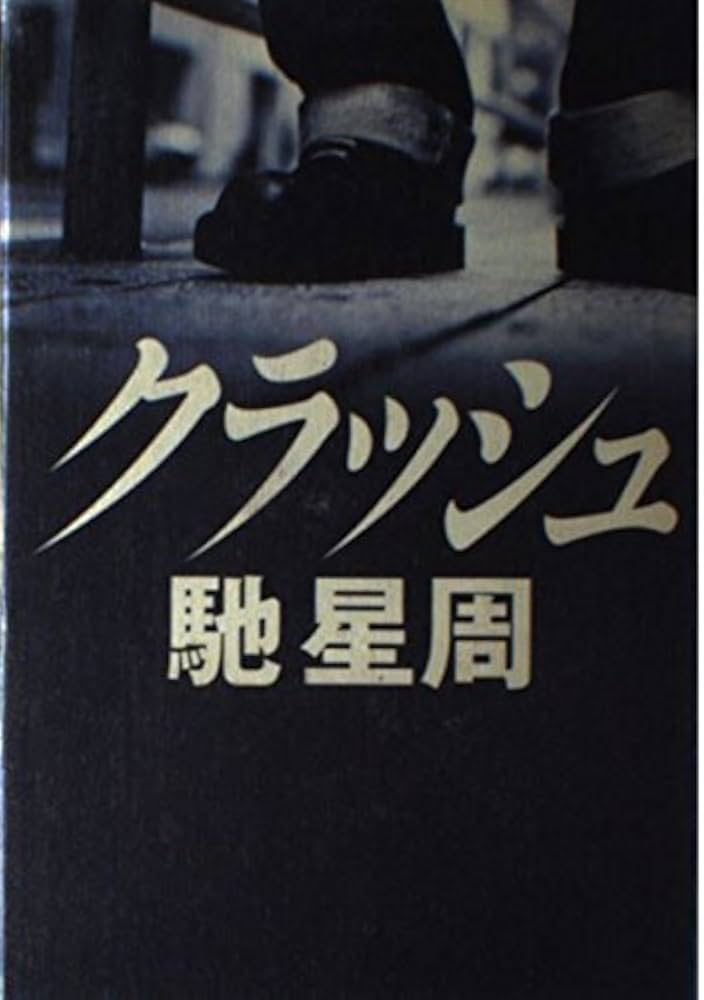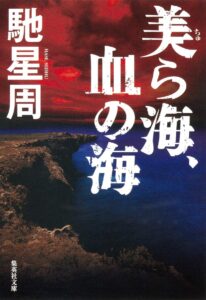 小説「美ら海、血の海」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「美ら海、血の海」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
「ノワール小説の旗手」として知られる馳星周さんが、沖縄戦という重いテーマに正面から挑んだ一作です。そのタイトルから、壮絶な物語であることは想像に難くありません。ですが、この物語の始まりが1945年の沖縄ではなく、2011年の東日本大震災の被災地であると知ったとき、私はまず軽い混乱と強い興味を覚えました。
なぜ、沖縄戦の物語が東北から始まるのか。この構成こそが、作者が私たち読者に突きつける最初の、そして最も重要な問いかけなのかもしれません。馳星周さんといえば、裏社会に生きる人間たちの乾いた関係性を描き出す作風で知られていますが、本作ではその筆致が、歴史の渦に飲み込まれた一人の少年の内面を、痛々しいほど鮮やかに描き出しています。
この記事では、まず物語の骨子を追い、その後で私が何を感じ、何を考えさせられたのかを、物語の核心に触れながら詳しく語っていきたいと思います。これは単なる戦争の記録ではなく、巨大な悲劇を生き延びてしまった人間の、魂の彷徨の物語です。
「美ら海、血の海」のあらすじ
物語の幕は、2011年3月、東日本大震災から間もない宮城県石巻市で上がります。老いた男性、真栄原幸甚(まえはら こうじん)は、津波にのまれた妹の行方を捜し、凄惨な光景が広がる被災地をさまよっていました。目の前に広がる瓦礫と泥、そして死の匂いは、幸甚が66年もの間、心の奥底に封印してきた記憶の扉をこじ開けるには十分すぎる引き金でした。
彼の意識は、瞬く間に1945年の沖縄へと引き戻されます。当時14歳だった幸甚は、大日本帝国の勝利を信じて疑わない純粋な「軍国少年」でした。天皇は神であり、日本は神の国である。そう教え込まれた彼は、仲間たちと共に「鉄血勤皇隊」に志願し、お国のために命を捧げることに何の疑問も抱いていませんでした。彼の心は、輝かしい未来と英雄的な自己犠牲の幻想に満ちていたのです。
しかし、1945年4月、米軍が沖縄本島に上陸を開始すると、彼の信じていた世界は粉々に砕け散ります。「鉄の嵐」と呼ばれる圧倒的な物量の前に、日本軍はなすすべもなく後退。幸甚が目の当たりにしたのは、英雄的な兵士の姿ではなく、飢えと恐怖から民間人から食料を奪い、同胞であるはずの沖縄県民を盾にする兵士たちの醜い姿でした。
信じていたものすべてに裏切られ、美しかった故郷が血と肉片にまみれた地獄へと変わっていく中で、幸甚はたった一人、逃げ惑う少女と出会います。彼は、この少女を守ることだけを唯一の希望として、終わりなき戦場を彷徨うことになります。この地獄の底で、彼は人間性を保ち続けることができるのでしょうか。そして、二人の運命はどこへたどり着くのでしょうか。
「美ら海、血の海」の長文感想(ネタバレあり)
この物語は、単に「沖縄戦は悲惨だった」という一言で終わらせることを、断固として拒絶してきます。私が最初に心を揺さぶられたのは、やはり物語の始まり方でした。2011年の石巻、つまり東日本大震災という「天災」の現場から、1945年の沖縄戦という「人災」の記憶へと繋ぐ。この導入部が、物語全体のテーマを鮮烈に浮かび上がらせているように感じます。
自然の猛威という抗いがたい力と、人間の悪意や狂気が引き起こした地獄。この二つの巨大な悲劇を対峙させることで、作者は私たちに静かに問いかけます。どちらも等しく悲劇であることに違いはありません。しかし、人間の手によって、明確な意図をもって作り出された地獄の特異性、そのおぞましさが、この対比によってより一層際立って見えてくるのです。これは、物語の構造そのものが持つ、痛切な告発だと言えるでしょう。
物語の主軸は、過去の沖縄へと移ります。そこで描かれる14歳の幸甚は、純粋な、そして熱烈な「信者」でした。彼は、日本という国家の正義を、そして天皇の神性を心から信じていました。「生きて虜囚の辱めを受けず」という教えを胸に刻み、米兵は鬼であり、捕まれば男は無残に殺され、女は辱められると固く信じていました。
この物語の悲劇性を深くしているのは、幸甚が単なる戦争の「被害者」として描かれていない点にあります。彼は、自らが信じていたものに裏切られ、その信仰が根底から崩壊していく過程を、身をもって体験するのです。これは、物理的な苦痛よりもはるかに深刻な、精神的な凌辱と言えるかもしれません。彼の旅は、無垢な少年が大人になる物語などではなく、確固たる信念を抱いた人間が、恐ろしい虚無へと突き落とされるまでの記録なのです。
鉄血勤皇隊として戦場に動員された少年たち。それは彼らの選択ではなく、抗うことのできない命令でした。国のために死ぬことを栄誉だと信じていた幸甚の子供時代は、そこで終わりを告げます。彼は、戦争という巨大な機械に組み込まれた、名もなき歯車の一つとなりました。
作者は、主人公をあえて狂信的なまでに純粋な「信者」として設定することで、国家という大きな存在が個人に与える影響の恐ろしさを、より鮮明に描き出しているように思います。彼が信じていた神聖な帝国陸軍が、実は自分たち沖縄県民を見捨てるための嘘で塗り固められていた。この真実を突きつけられた時の絶望は、どれほど深かったでしょうか。彼の内面で起こる葛藤と崩壊こそが、この物語の核心的な痛みを生み出しているのです。
そして、1945年4月1日、米軍の上陸と共に、本当の地獄の蓋が開きます。馳星周さんの筆が最も冴えわたるのは、この戦場の描写かもしれません。海からの絶え間ない砲撃、空から降り注ぐ機銃掃射、そして洞窟(ガマ)に隠れた人々を焼き尽くす火炎放射器。そこには、人間同士の戦いという情緒的なものは一切ありません。あるのは、工業製品のように人間が処理されていく、圧倒的な殺戮の光景だけです。
読者は、幸甚の視点を通して、この恐怖を追体験することになります。薬莢の匂い、硝煙の味、血のぬかるみ、そしてすぐ隣で肉体が爆散する音。五感に直接訴えかけてくるような描写は、読んでいるこちらの呼吸さえ浅くさせます。英雄的な行為や戦略的な駆け引きなど入り込む余地のない、ただただ純粋な恐怖と混乱が、ページを支配していました。
しかし、物語が真の道徳的危機を迎えるのは、敵である米軍からではなく、味方であるはずの日本軍によってもたらされます。撤退する日本軍の道案内を命じられた幸甚は、そこで信じがたい光景を目撃するのです。彼が神の軍隊と信じていた兵士たちは、敗色が濃くなるにつれて理性を失い、守るべきはずの沖縄県民に牙をむきます。
民間人の食料を奪い、女子供が隠れるガマを乗っ取り、自分たちが助かるために彼らを無防備な砲火の下へと追い立てる。そして、この物語における最大の裏切りが行われます。日本軍は、米軍の進軍を少しでも遅らせるために、沖縄の民間人を意図的に「人間の盾」として利用したのです。この事実を知った瞬間、幸甚の中で何かが音を立てて崩れ落ちました。彼の信仰は、ここで完全に死んだのです。
戦場の地獄は、幸甚自身の内面をも容赦なく蝕んでいきます。絶え間ない飢えと渇き、そして死の恐怖は、人間の理性をいとも簡単に麻痺させます。最初は日本兵の残虐行為におののいていた幸甚もまた、生き延びるための一線を越えざるを得ない状況に追い込まれていくのです。
その姿は、まるで極限状態に置かれた人間の倫理観を問う実験のようでした。彼は、死体の懐を探り、食料や金品を奪います。そして、ついに彼自身が銃を手に取り、同じ日本人である民間人、それも老人や子供を脅して、わずかな食料を強奪するに至ります。かつて彼が憎み、恐れていた怪物に、彼自身が成り果ててしまった瞬間でした。
ここに、馳星周さんという作家の本質が凝縮されているように感じます。彼は戦争を、国と国とのぶつかり合いとしてではなく、道徳や倫理が贅沢品と化し、ただ「生き延びる」ことだけが至上の価値となる究極の無法地帯として描いています。幸甚の変貌は、過酷な環境下で、善良な人間がいかにして堕ちていくかという、普遍的なテーマを突きつけてきます。戦争の感傷的な側面は完全に剥ぎ取られ、極限状況でむき出しになる人間の本性と、そのおぞましさが容赦なく描かれていました。
この終わりの見えない暗闇の中、物語に唯一の光が差し込みます。南部へと逃げる混乱のさなか、あるガマで、幸甚は一人の少女と出会います。彼女もまた、家族を失い、たった一人で生き延びていました。この少女を守ること。それが、すべてを失った幸甚にとって、生きるための唯一の目的であり、理由となります。
それは、もはや動物的な生存本能を超えた、失われた自分自身のかけらを取り戻すための闘いだったのかもしれません。彼らの逃避行は、愛や恋といった言葉で飾れるような生易しいものではありません。ただ、互いの存在だけを頼りに、明日生きているかもわからない絶望的な日々を共に過ごすのです。
この少女の存在は、幸甚の中に辛うじて残っていた人間性の象F徴だったのだと思います。彼女を生かそうと必死にもがく幸甚の姿は、自らの魂が完全に地獄に堕ちてしまうことへの、最後の抵抗のようにも見えました。だからこそ、彼女の運命は、この物語の結末にとって決定的な意味を持つことになります。彼女が生き残ることは、幸甚の人間性の一部が救われることを意味し、彼女の死は、戦争という巨大な暴力が彼に対して完全な勝利を収めたことを意味するのです。
そして、物語は最も苛烈な戦闘が繰り広げられた本島最南部で、クライマックスを迎えます。しかし、読者がどこかで期待してしまうような、奇跡や救いは訪れません。この地獄においては、ほんのわずかな希望さえも許されないのです。幸甚と少女は、「切ない別れ」という言葉では到底表現しきれない形で、引き裂かれます。
彼は、彼女を守れませんでした。彼は生き残り、彼女は失われる。このどうしようもない失敗の事実こそが、その後の幸甚の人生を縛り続ける、根源的なトラウマとなります。物語は、英雄的な自己犠牲といった感傷的な慰めを読者に与えません。この結末は、ただただ無慈悲で、無意味な喪失として描かれます。これこそが、戦争というものの本質に対する、作者の誠実な態度なのだと感じました。
物語は再び2011年の石巻に戻ります。沖縄でのすべての記憶を追体験した幸甚は、静かに瓦礫の中に佇んでいます。彼の生存は、勝利ではありませんでした。それは、死んでいった者たちの記憶を背負い、彼らの無念を語り継ぐという、重い責務として描かれます。「死者たちの呪詛が刻まれた血まみれの大地の上で」生き続けること。それが、生き残ってしまった彼の宿命なのです。
この物語が最終的に私たちに突きつけるのは、「沖縄の戦後はまだ終わっていない」という、重い現実です。幸甚個人の癒えることのないトラウマは、今なお米軍基地問題を抱え、国家の犠牲にされたという記憶を抱き続ける沖縄全体の、終わらない苦難の象徴として描かれています。物語の始まりと終わりが繋がったとき、私たちは、幸甚の体験が過去の歴史ではなく、現代にまで続く地続きの問題であることを痛感させられるのです。
まとめ
この「美ら海、血の海」という小説は、読むのに覚悟がいる一冊であることは間違いありません。しかし、これは単に沖縄戦の悲劇を描いた物語にとどまらない、人間の尊厳とは何か、記憶とは何か、そして生き残った者にはどのような責任があるのかを、深く問いかけてくる作品です。
馳星周さんの容赦のない筆致は、戦争というものの感傷的なベールを剥ぎ取り、その醜く、残酷な素顔を私たちの目の前に突きつけます。主人公・幸甚が体験する地獄は、彼の信仰を打ち砕き、人間性を蝕み、そして彼の生涯を決定づける癒えない傷を残しました。
そのあまりにも救いのない展開に、ページをめくる手が何度も止まりそうになりました。しかし、その先に描かれる、生き残った者の終わらない苦しみと、それでも記憶を語り継ごうとする姿に、私たちは目を背けてはならないのだと感じます。
これは過去の物語ではなく、現代を生きる私たち一人ひとりに関わる物語です。幸甚という一人の少年がくぐり抜けた地獄を通して、歴史の事実と、それが個人の魂に刻み込んだ傷の深さを知る。その重い読書体験は、きっと忘れられないものになるはずです。