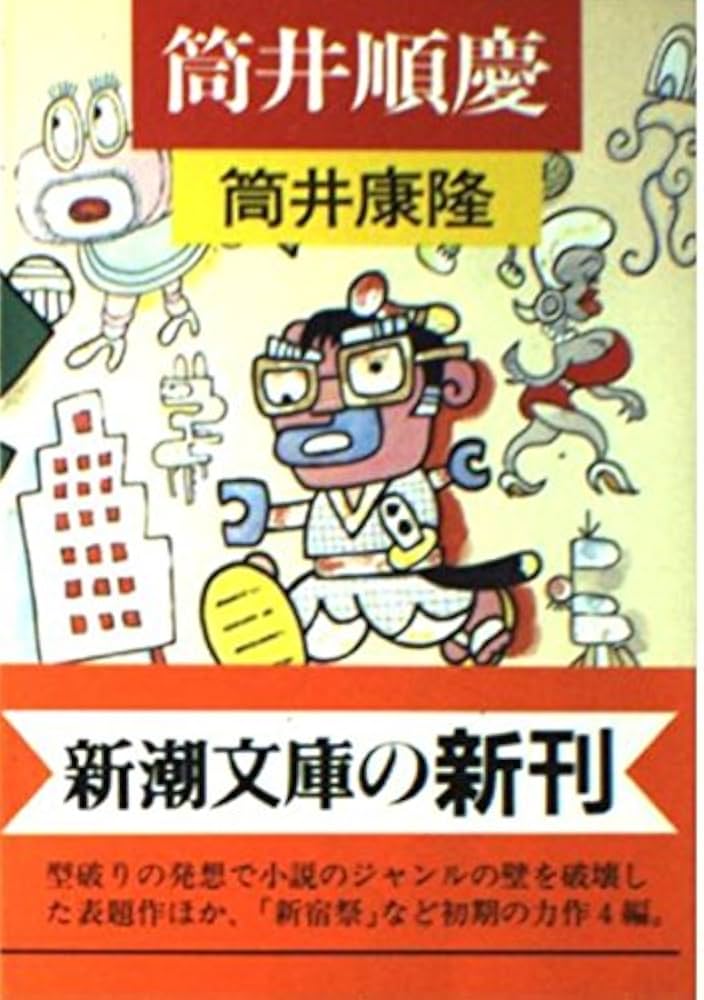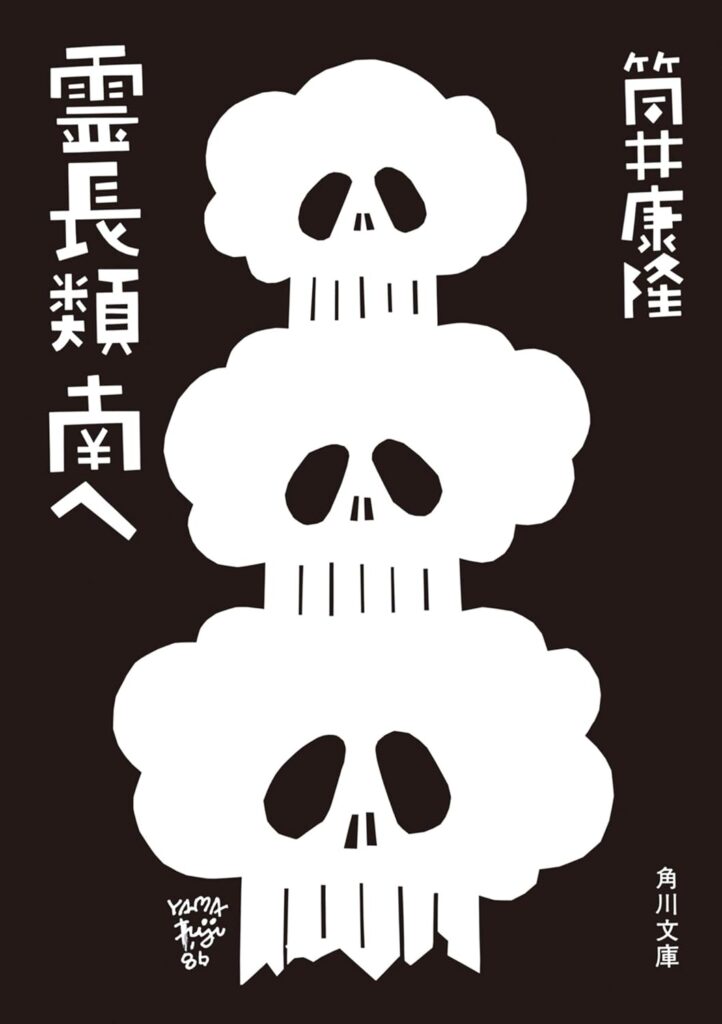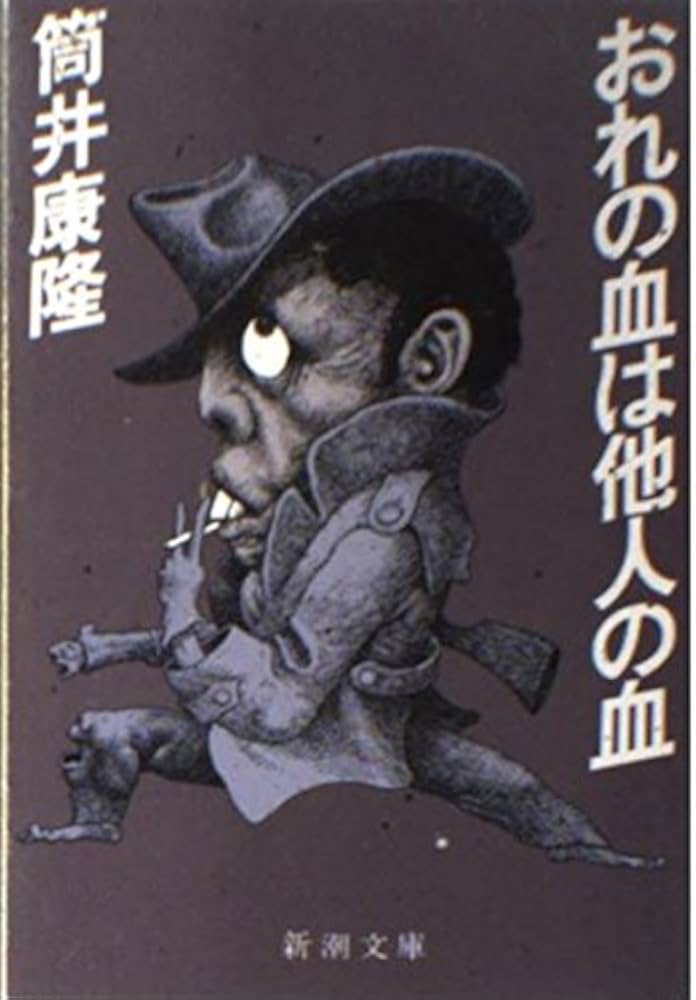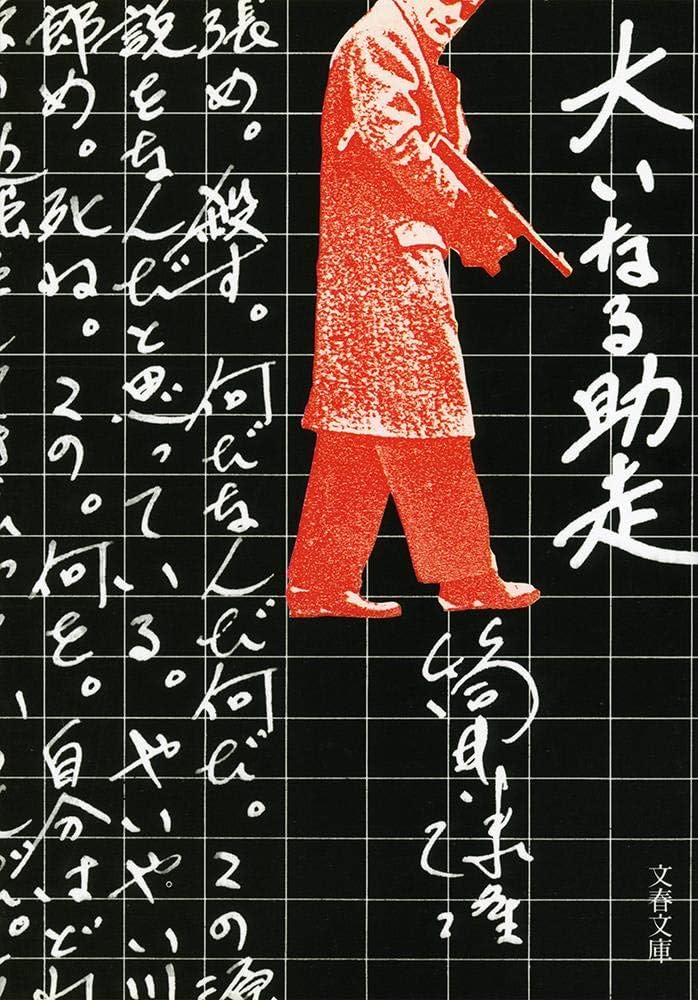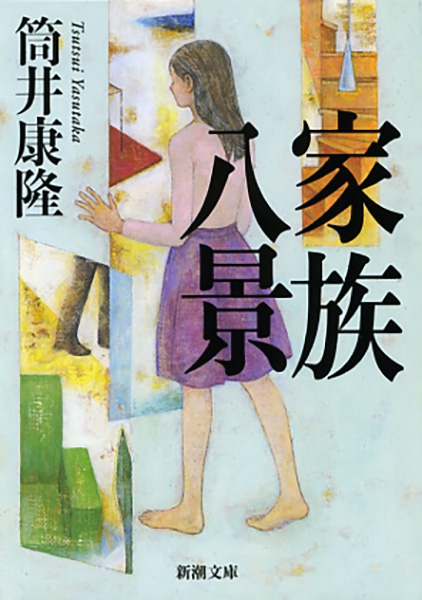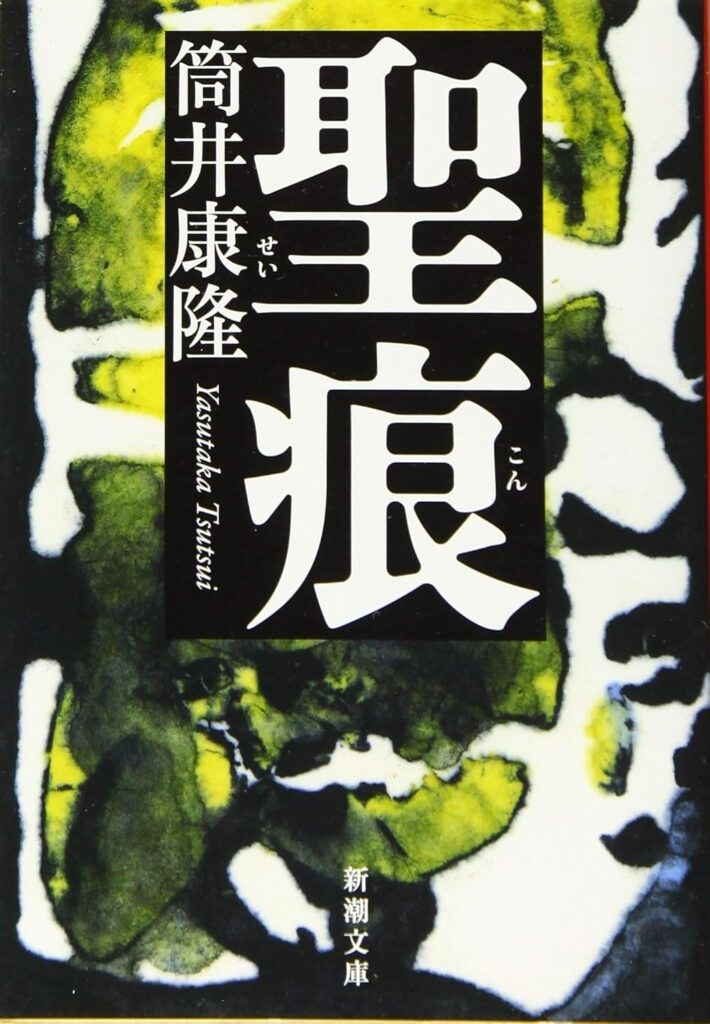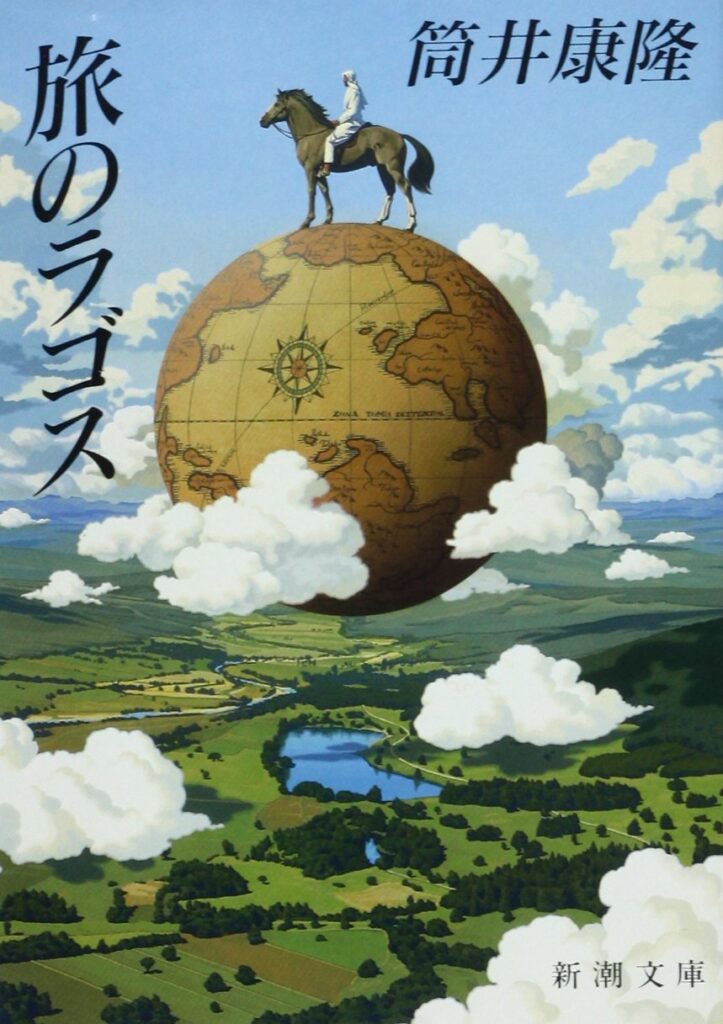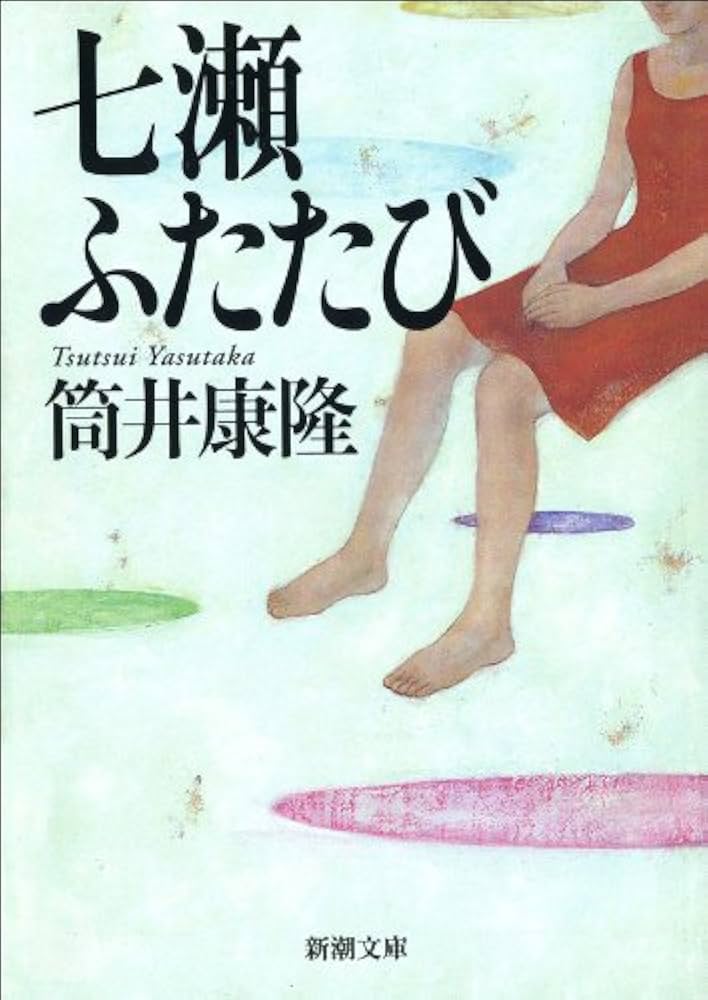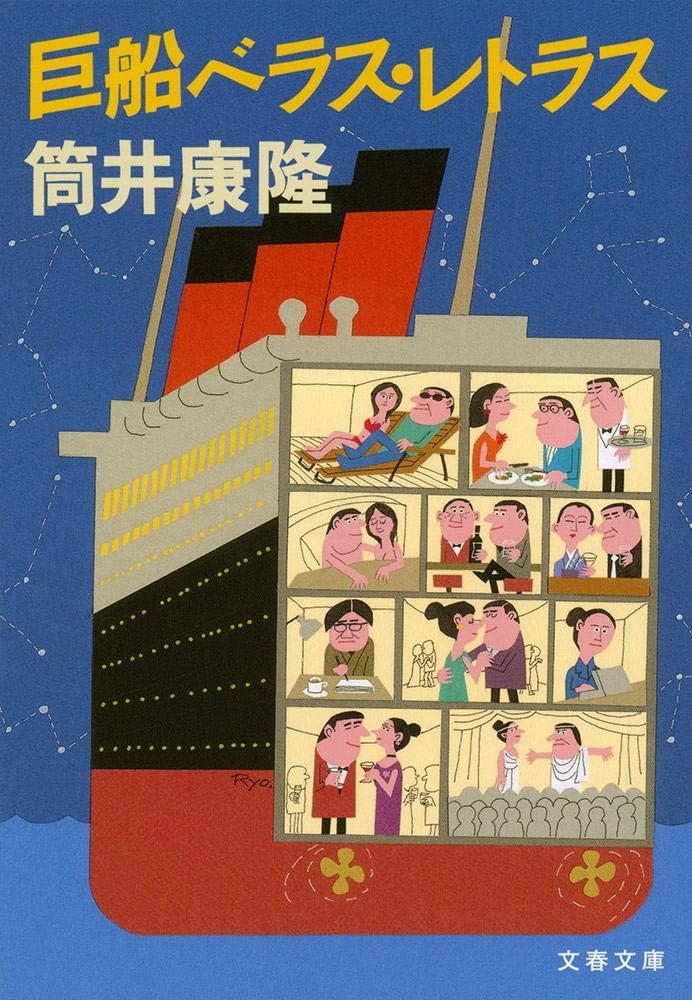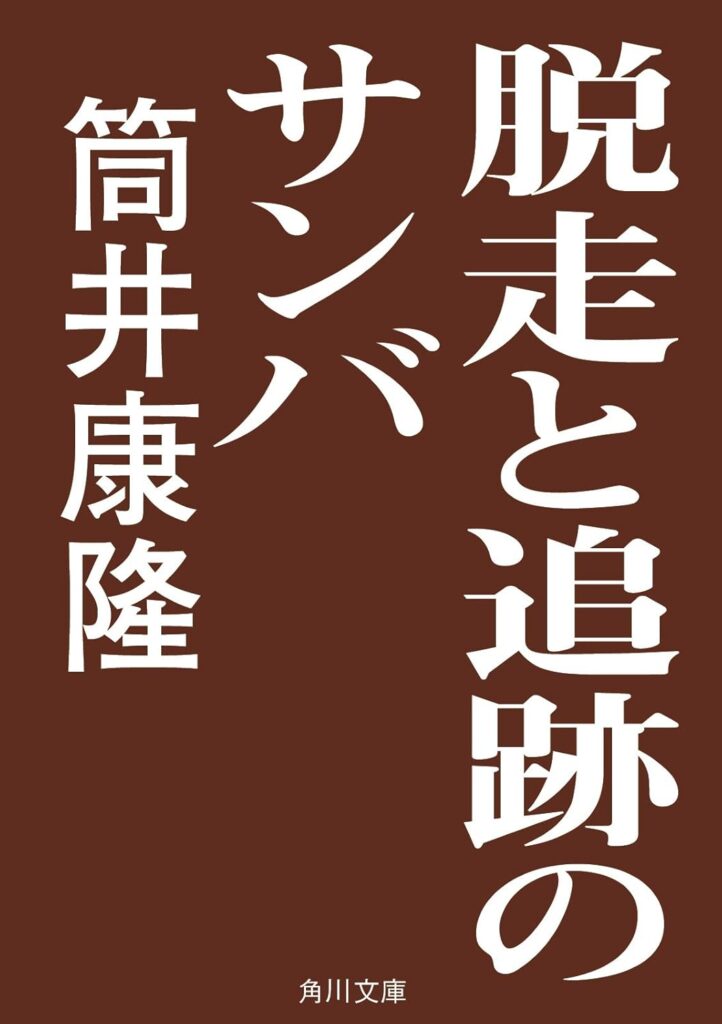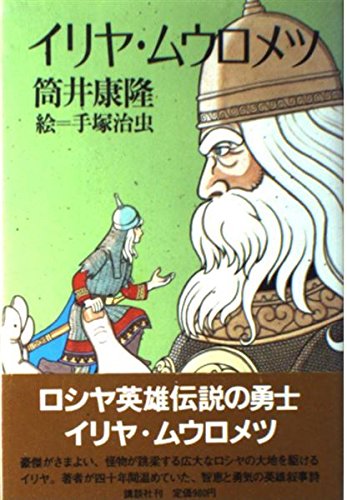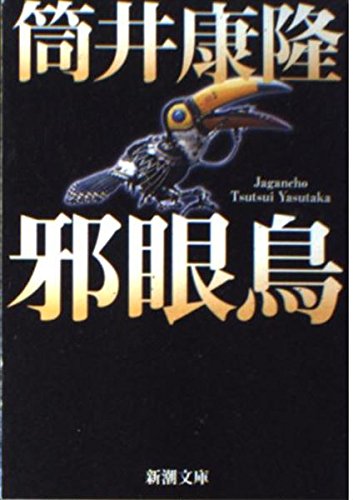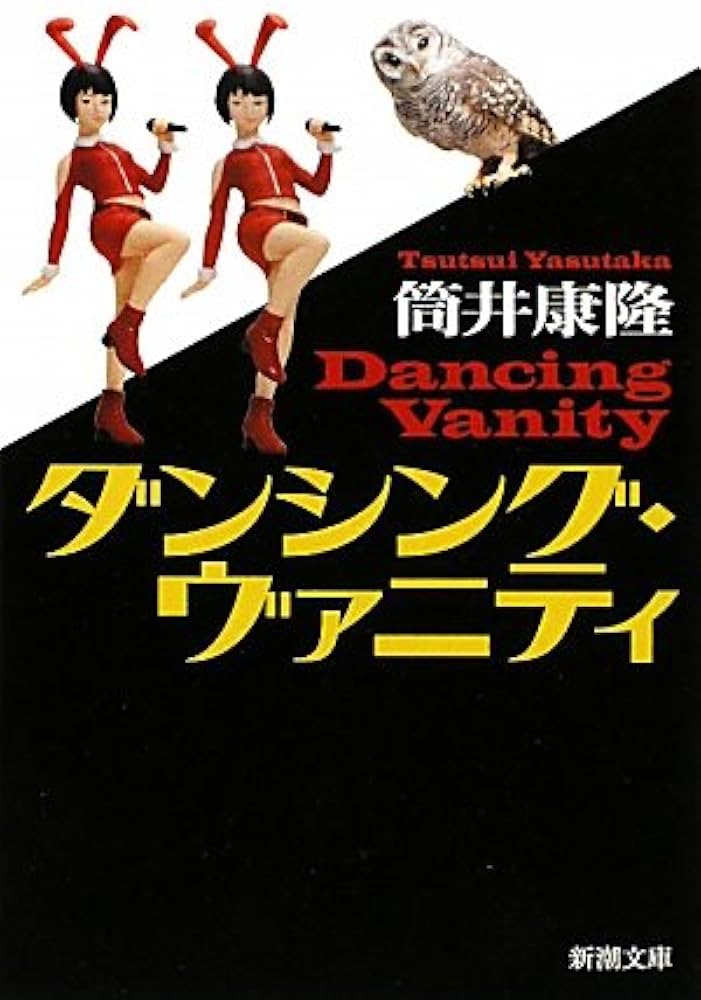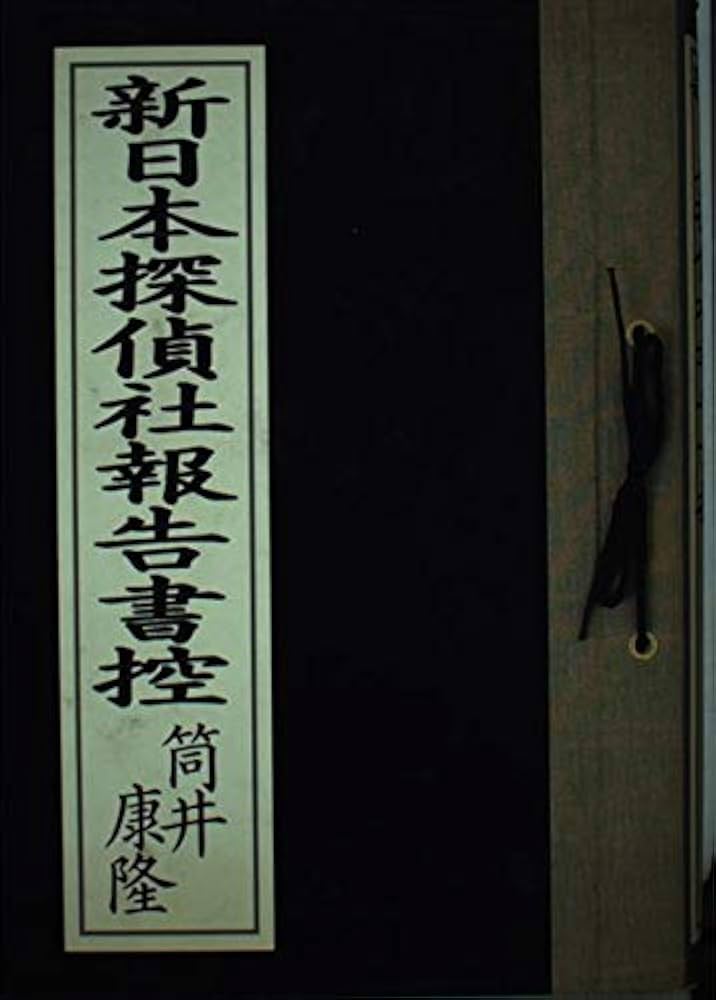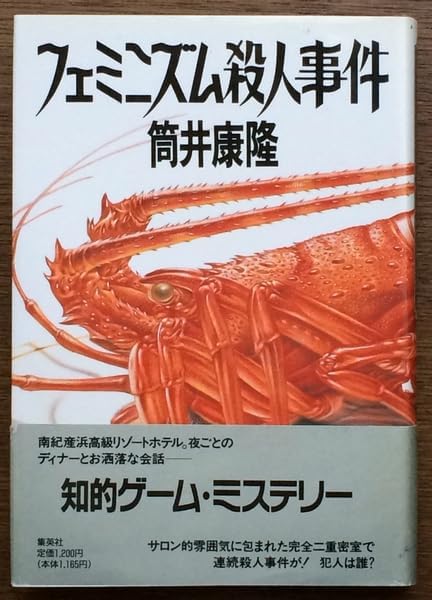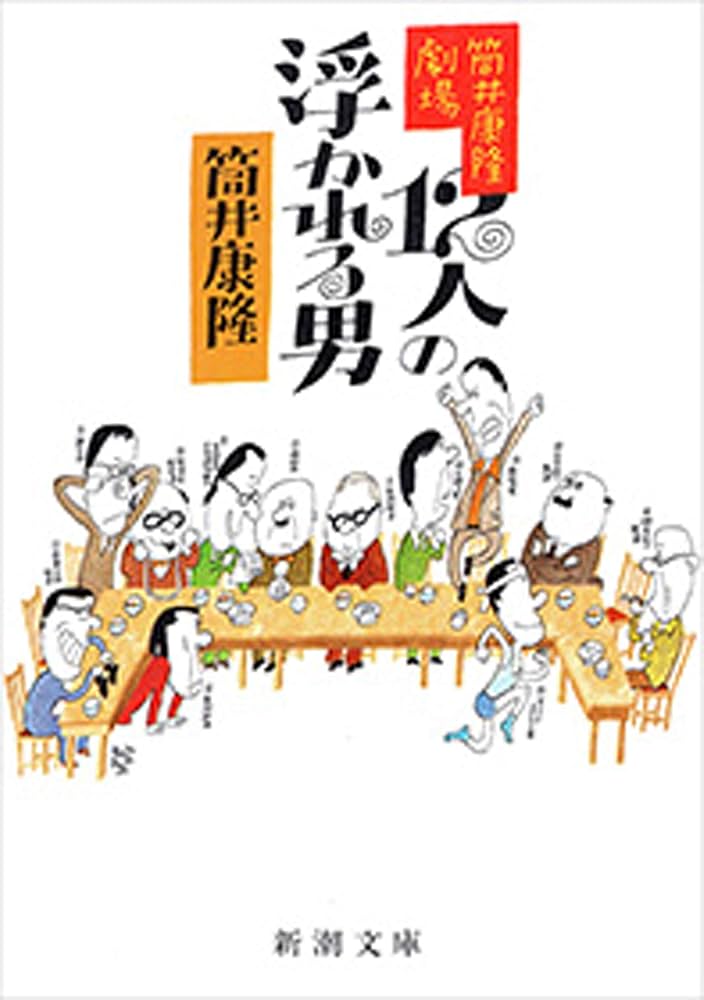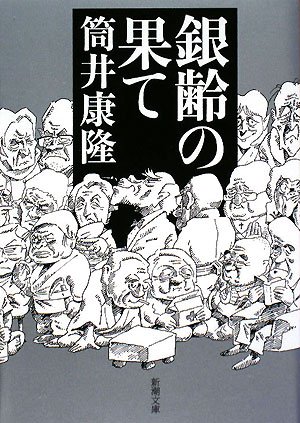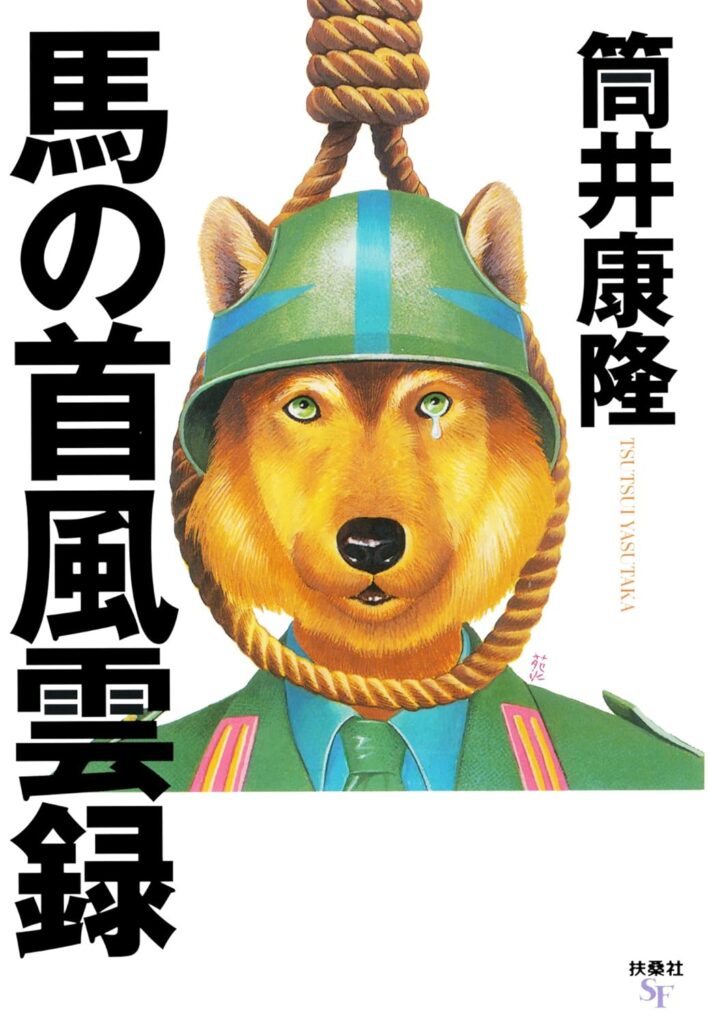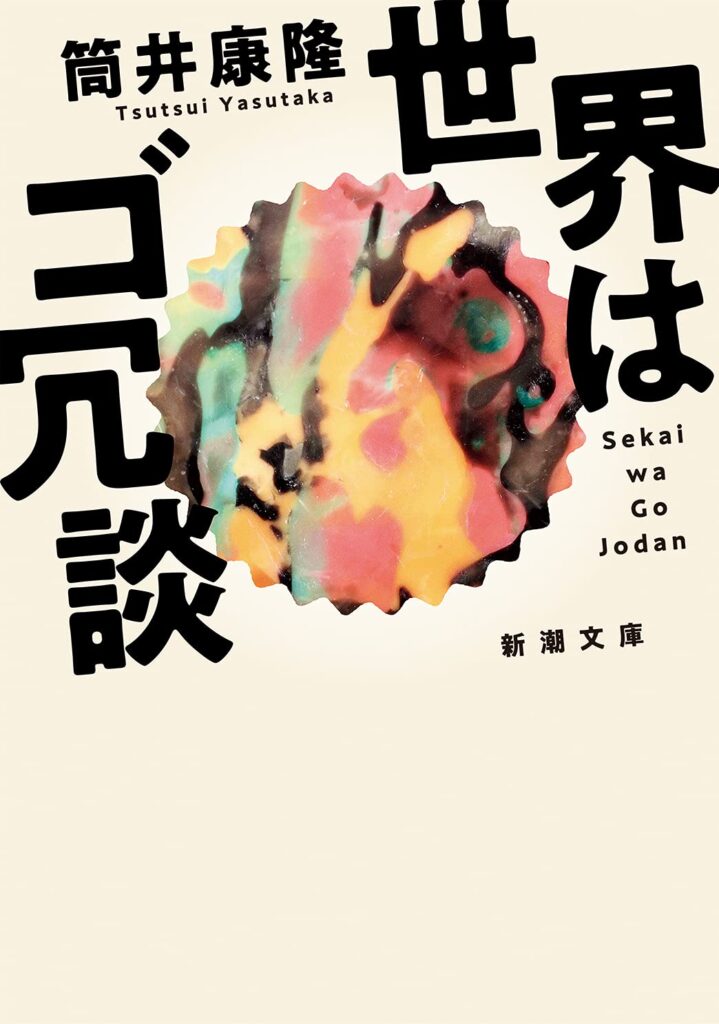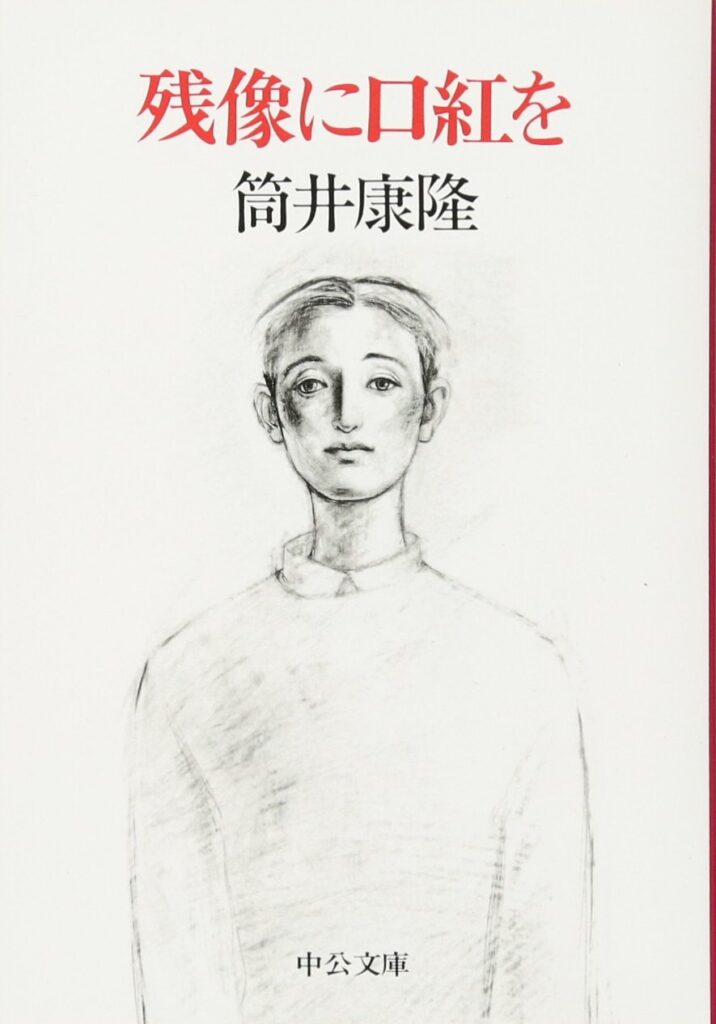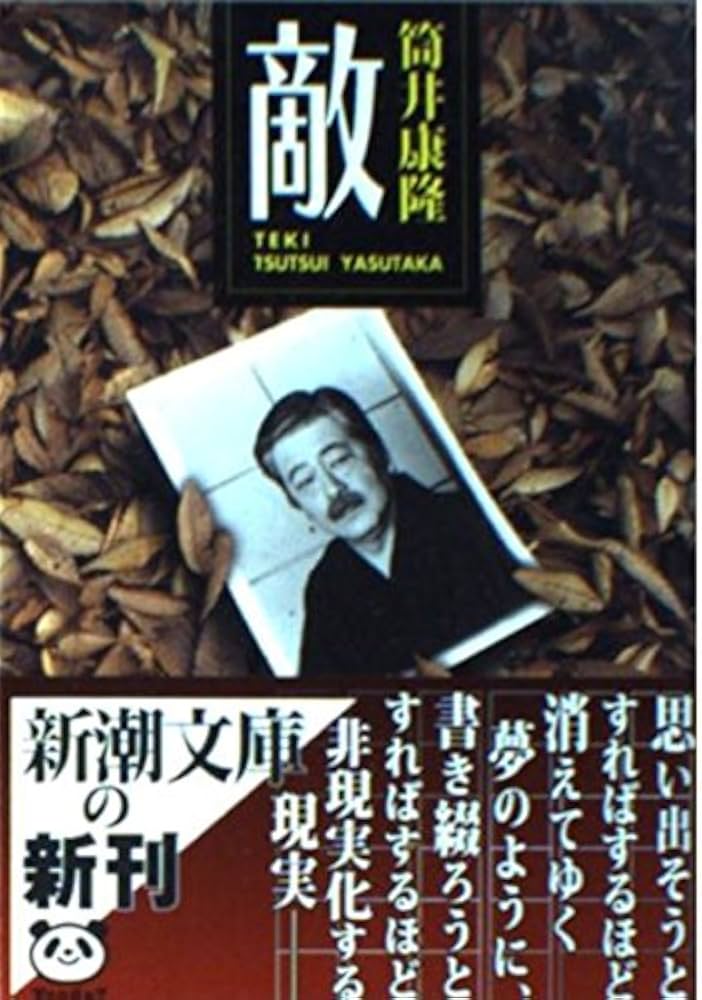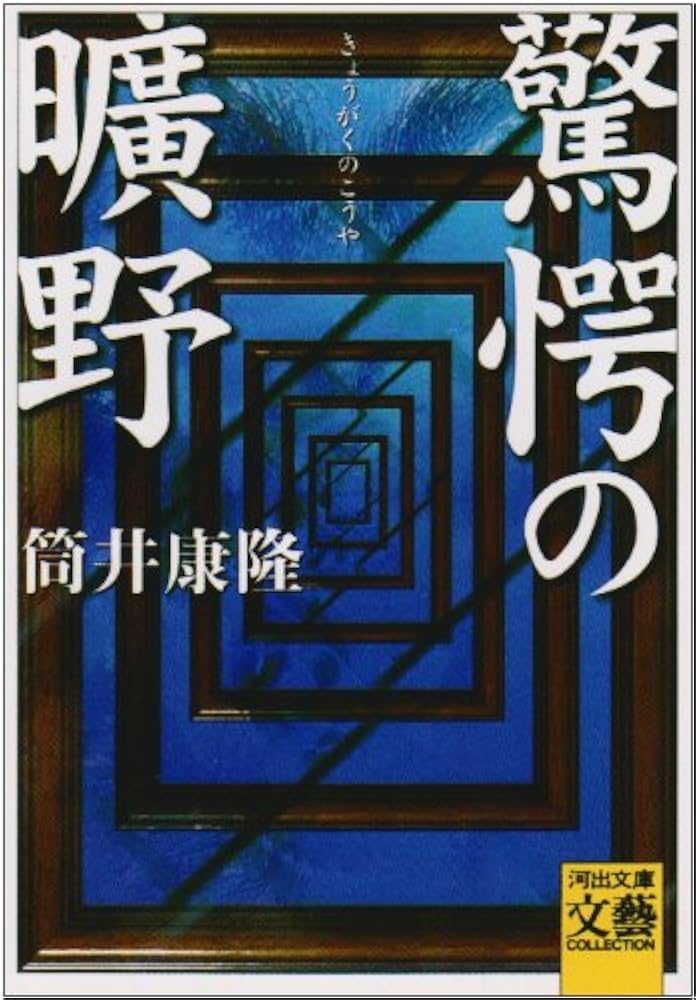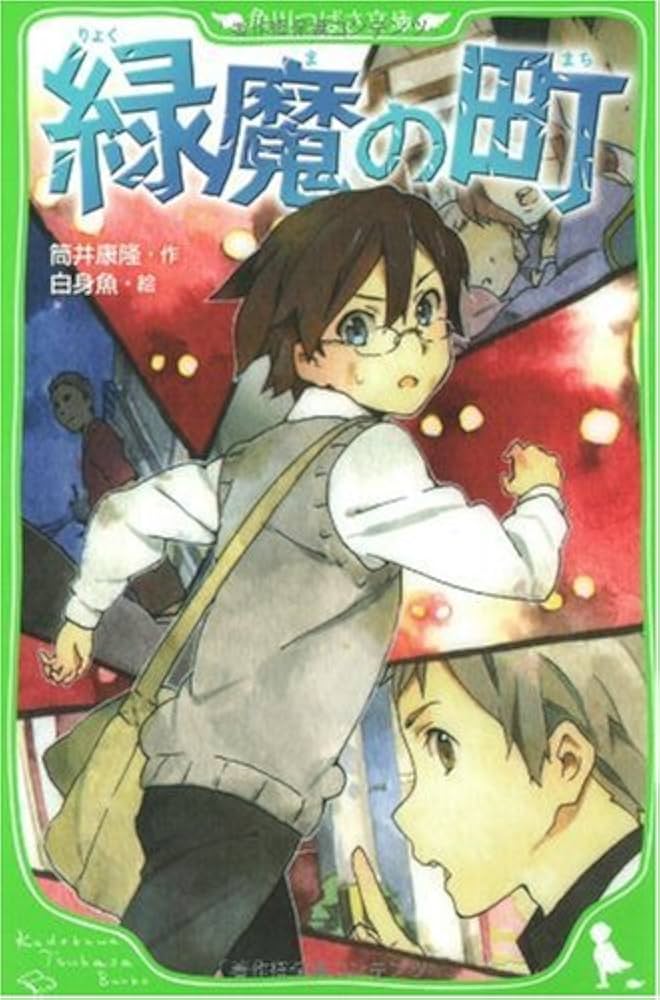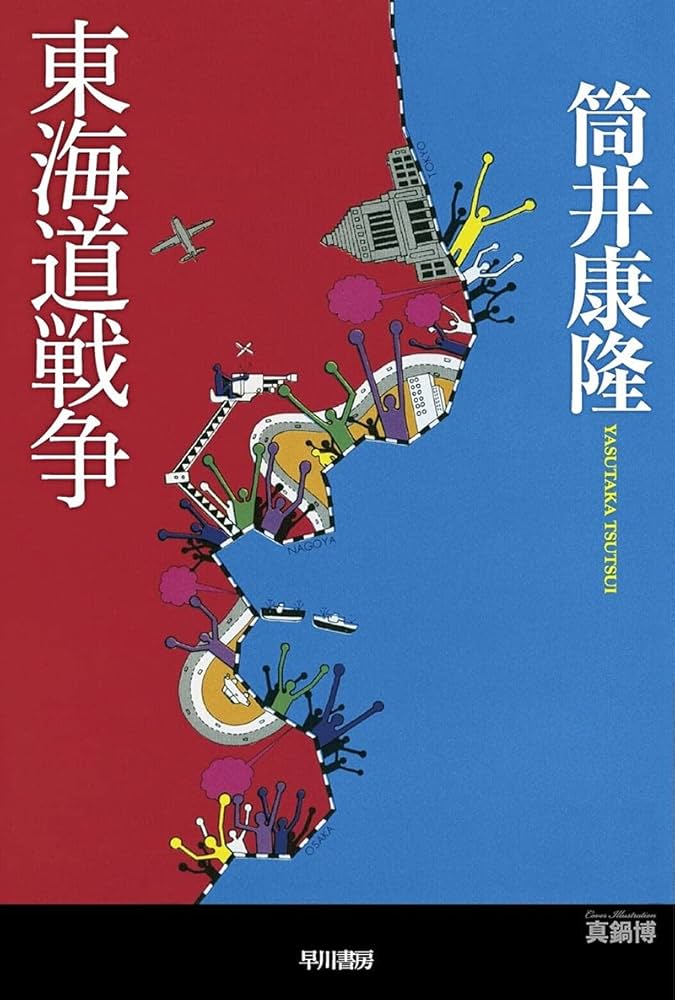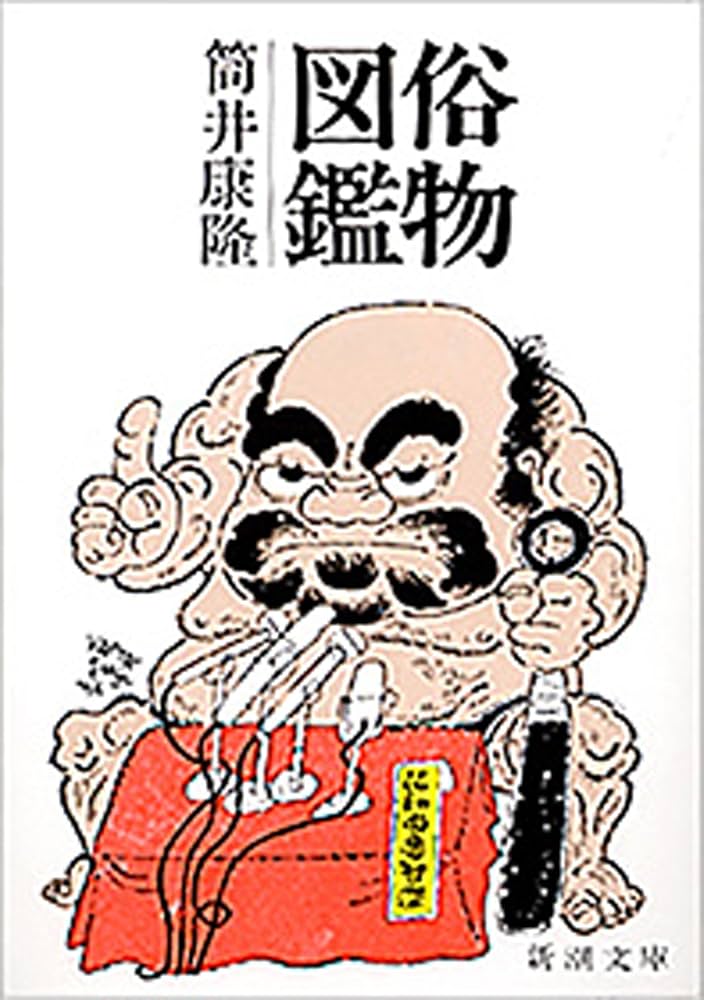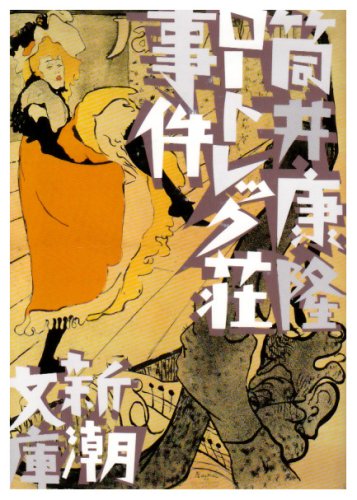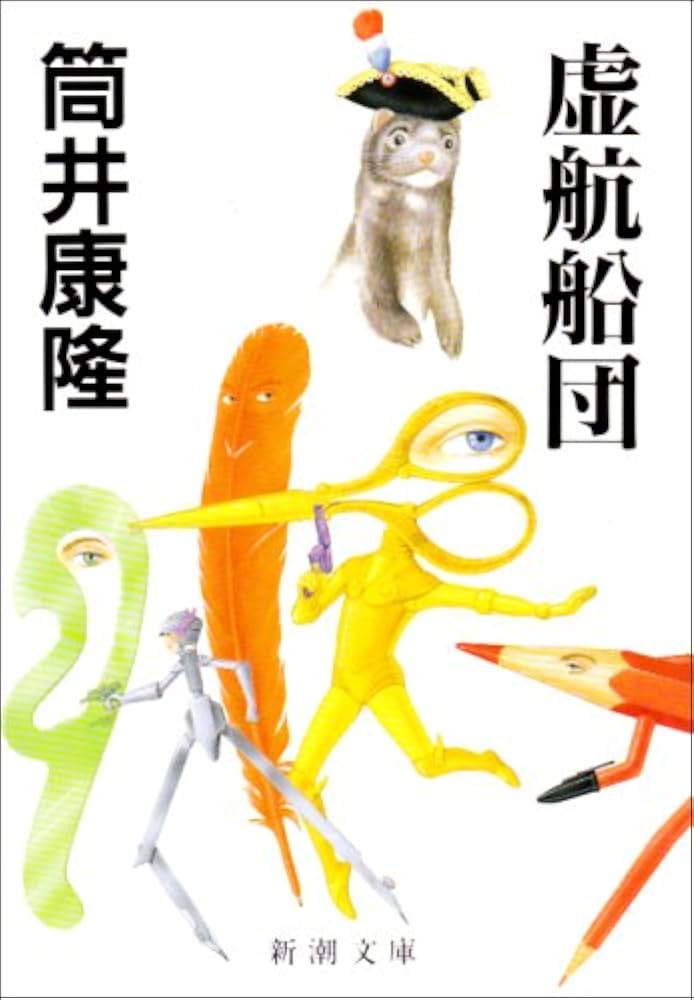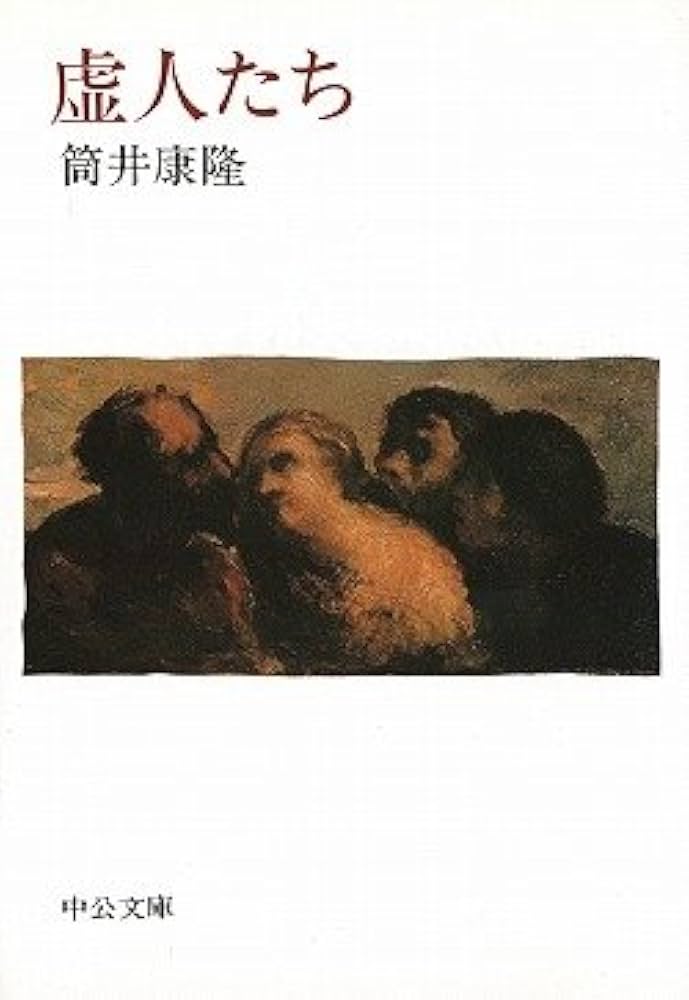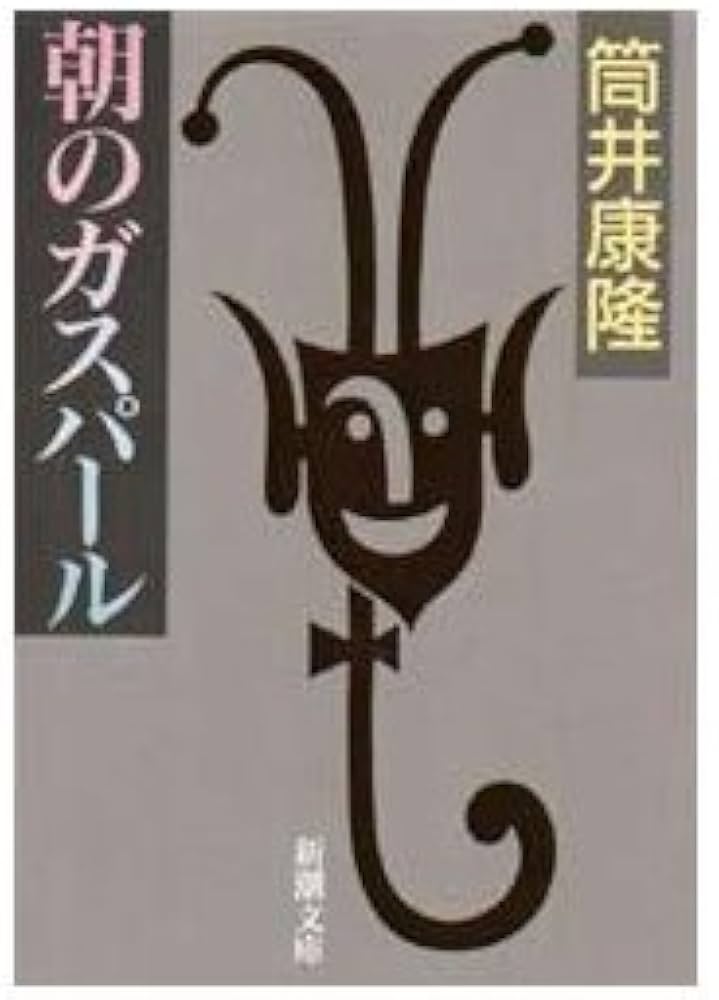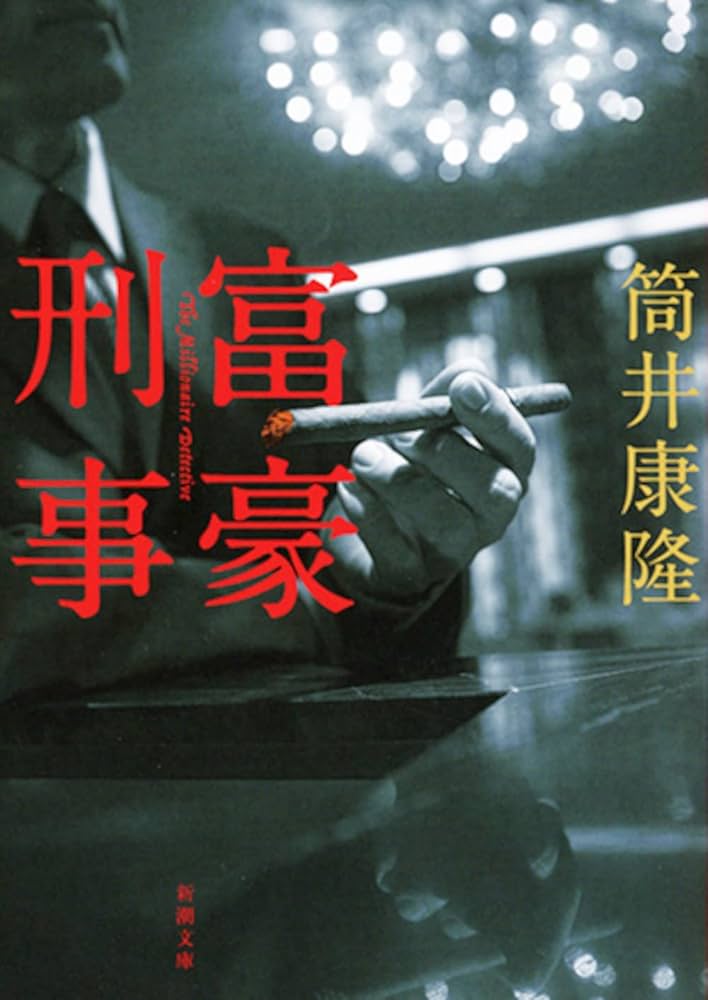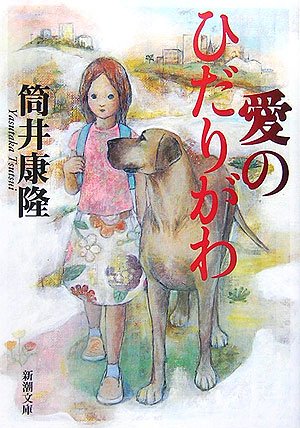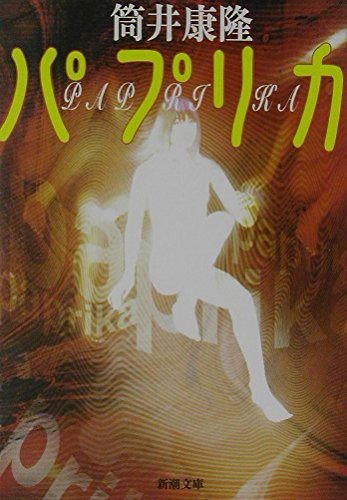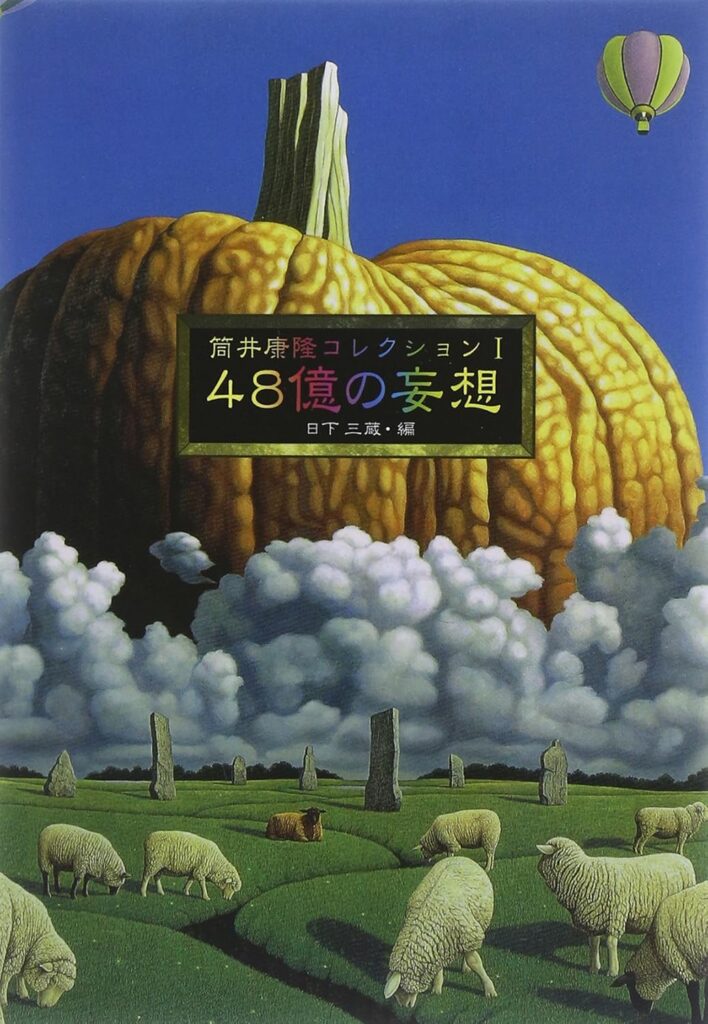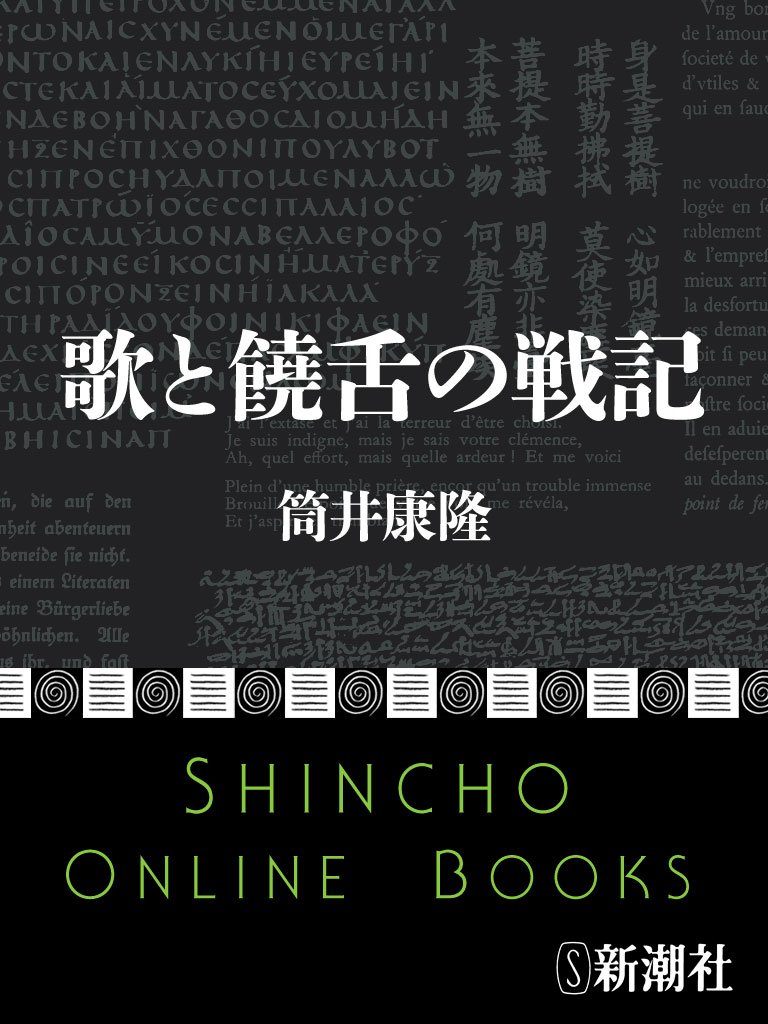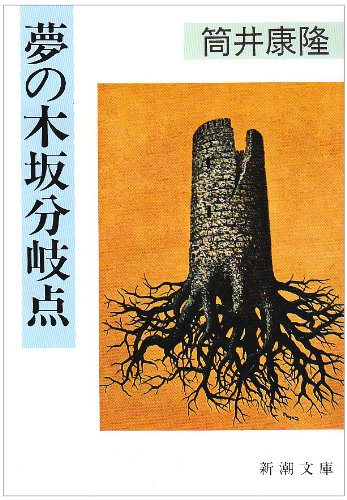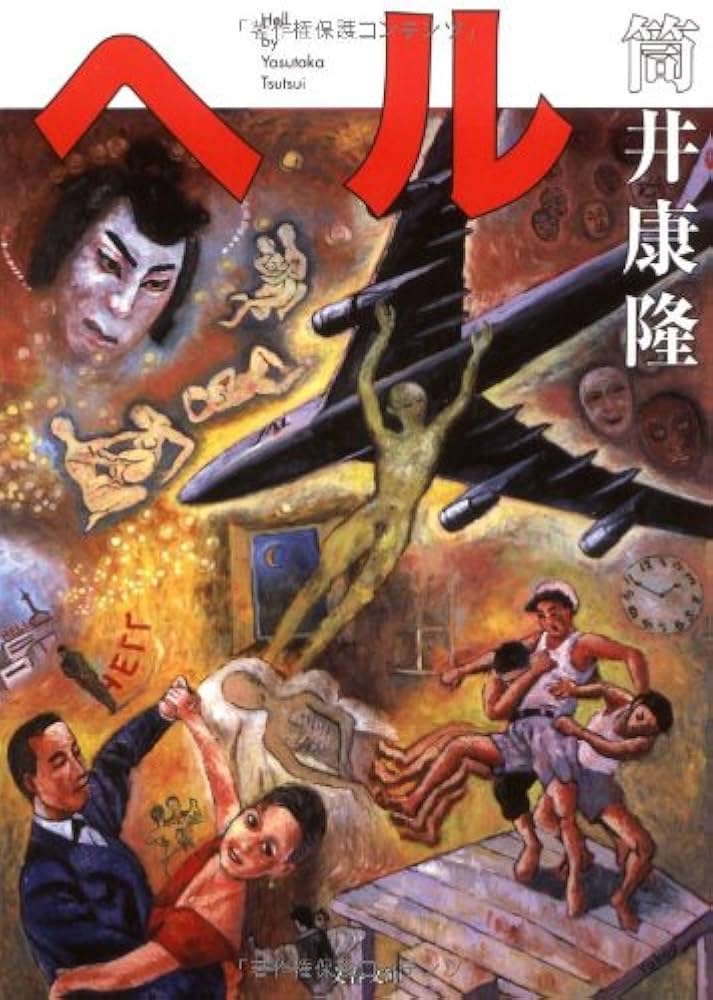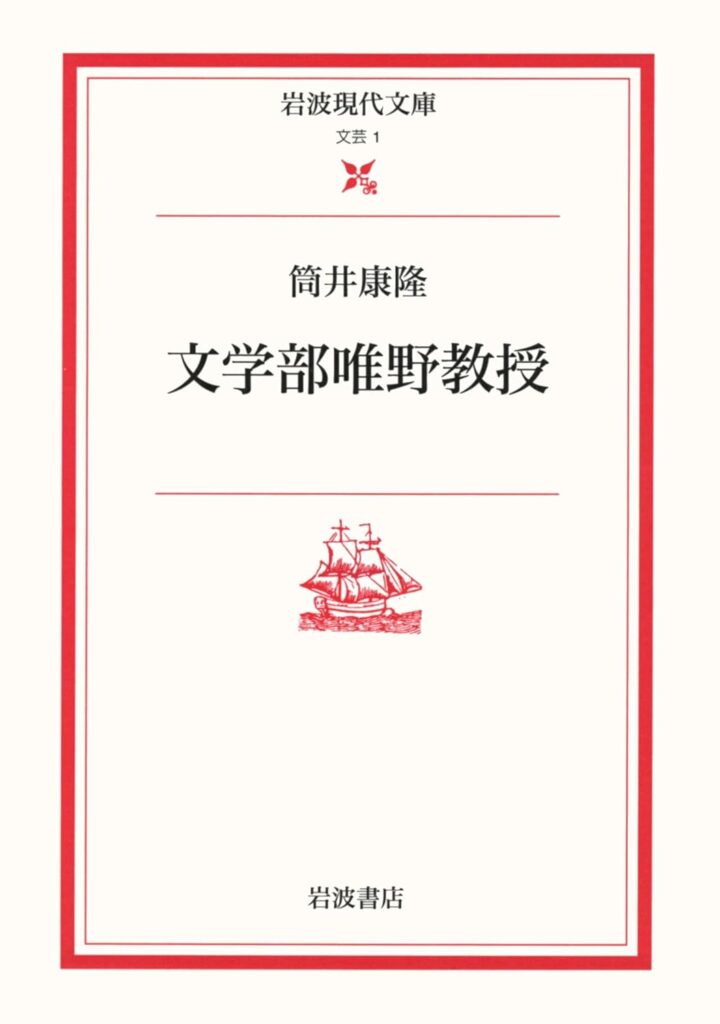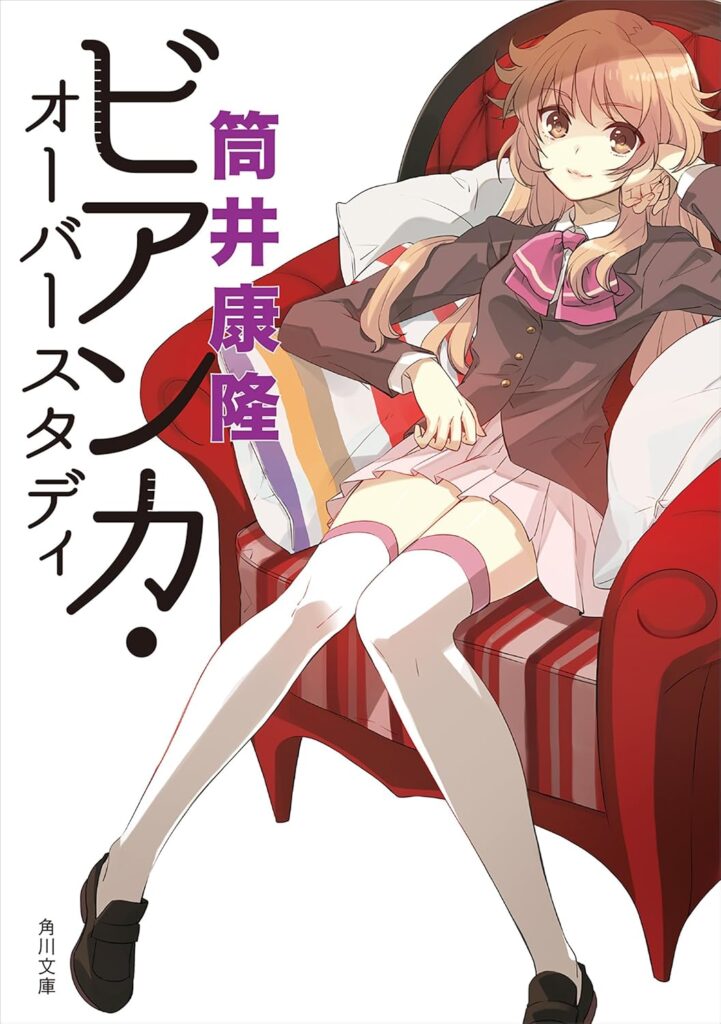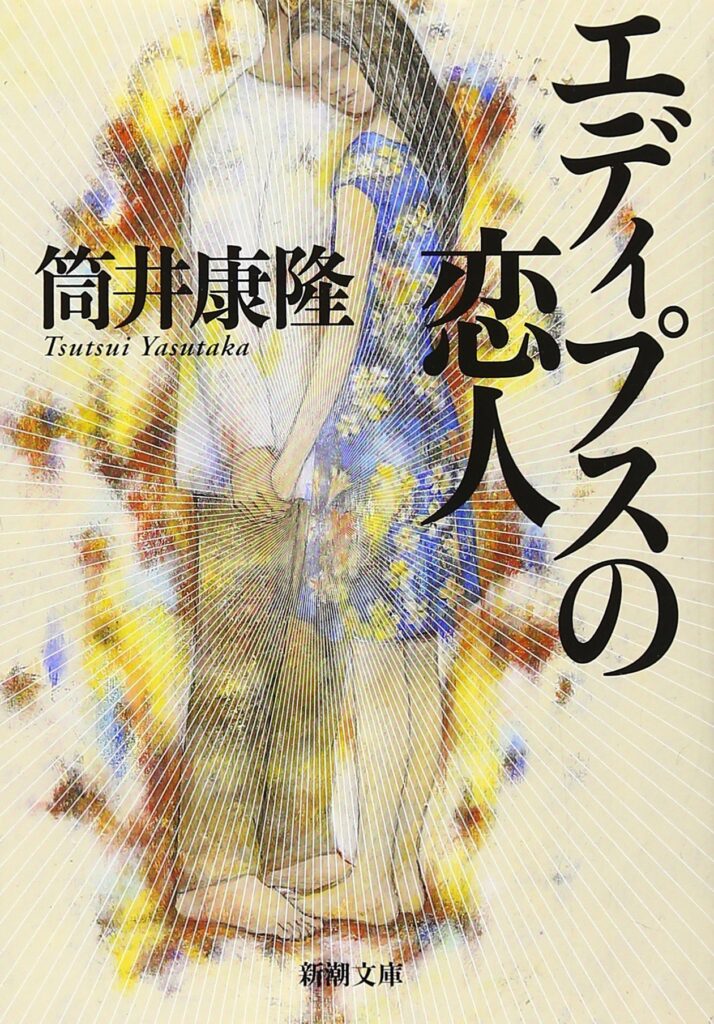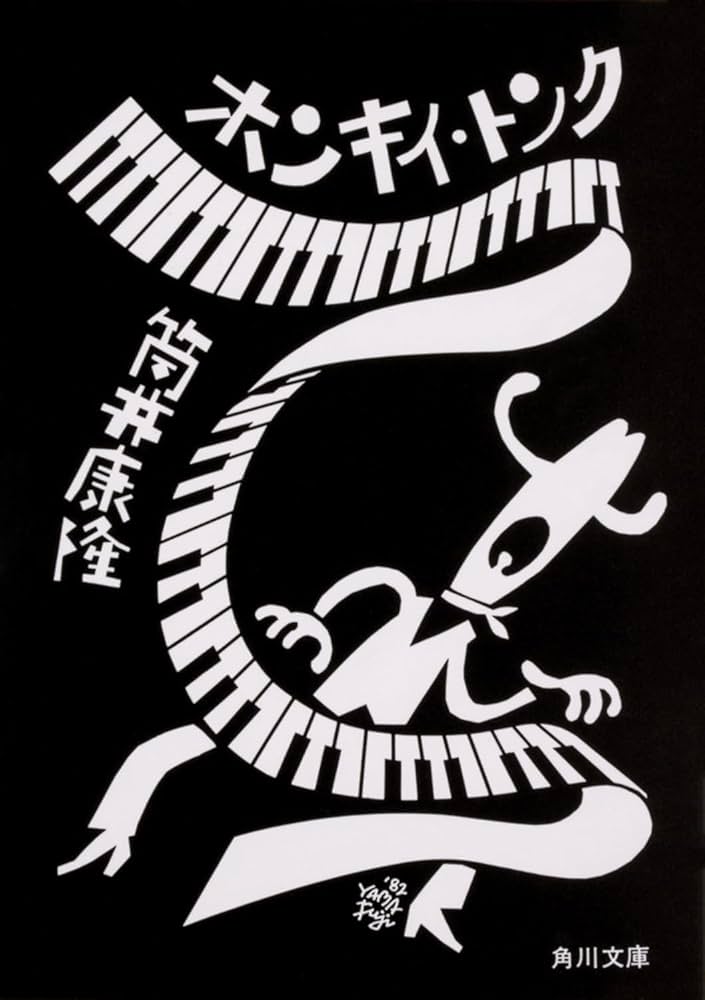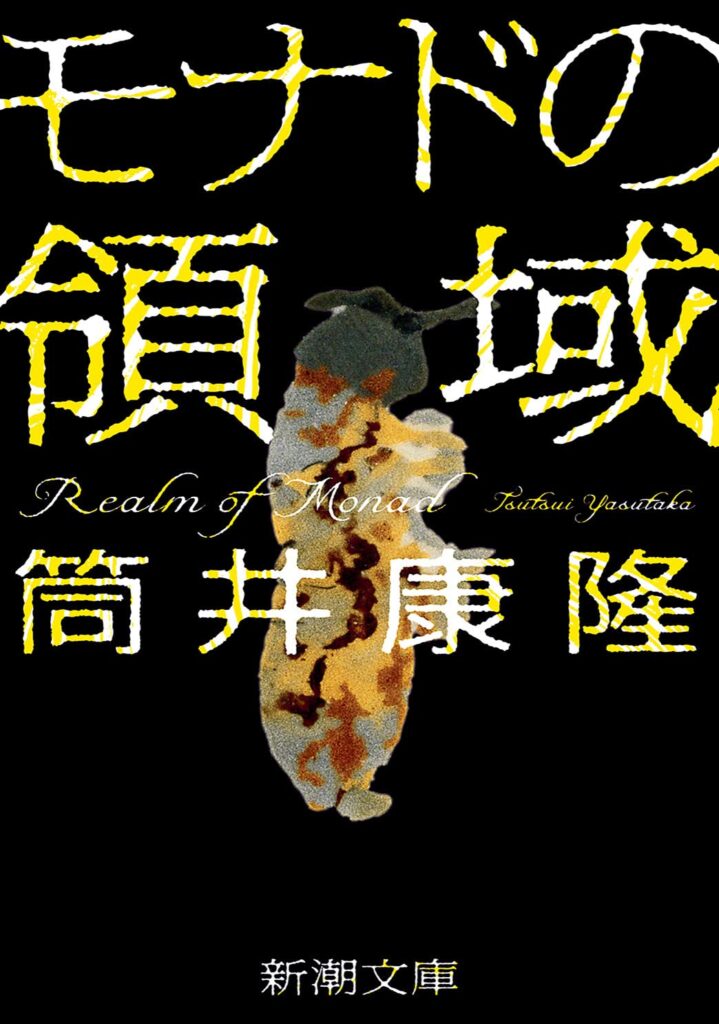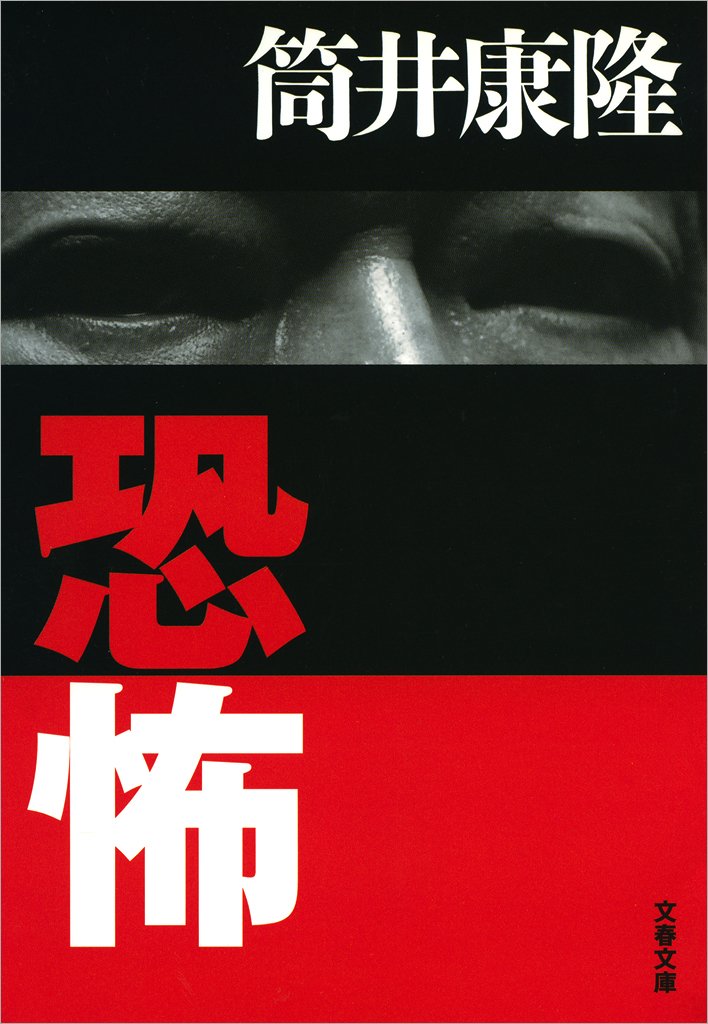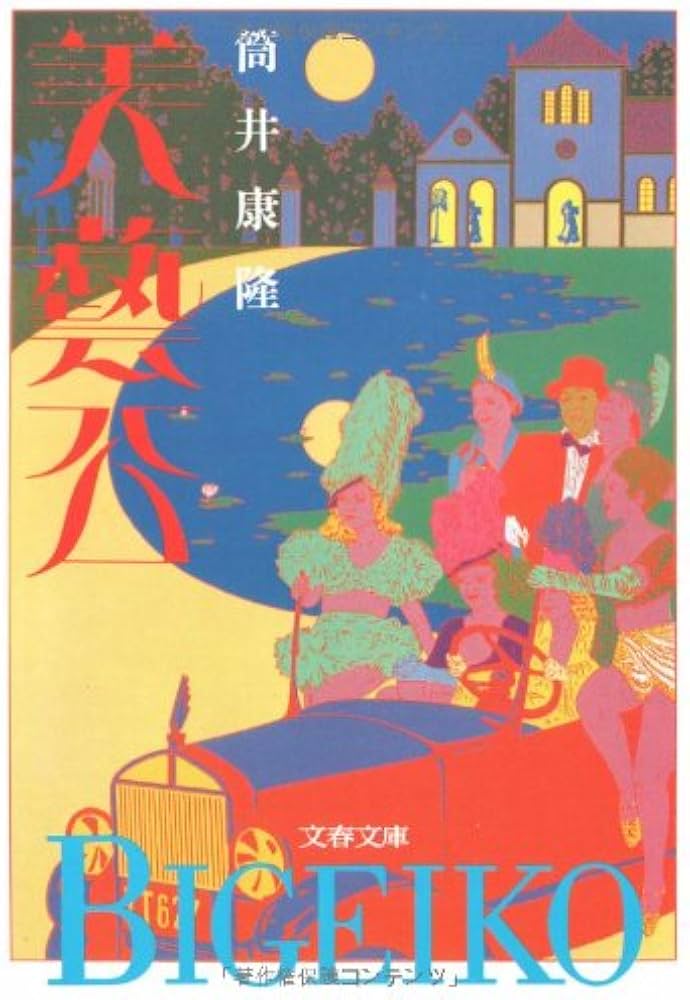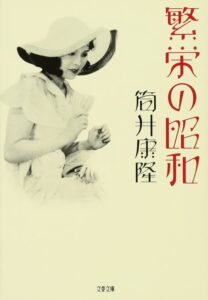 小説「繁栄の昭和」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文の感想も書いていますのでどうぞ。
小説「繁栄の昭和」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文の感想も書いていますのでどうぞ。
筒井康隆氏の「繁栄の昭和」は、単なるミステリー小説の枠に収まらない、多層的な魅力に満ちた作品です。ノスタルジックな昭和の風景を舞台にしながら、読者は時間や現実の曖昧さに引き込まれていきます。一見すると古典的な探偵小説の体裁を取りながら、その根底には筒井氏ならではの仕掛けが隠されているのです。
物語の語り手である「私」は、岸本法律事務所の経理担当。彼が目撃する殺人事件をきっかけに、読者は深遠な謎の世界へと誘われます。しかし、この作品の真髄は、事件の真相そのものよりも、その「世界」がどのように構築されているか、そしてその世界が何を意味するのかという点にあります。
この作品は、昭和という時代への郷愁と、それが失われていくことへの静かな抵抗がテーマとして深く根差しています。高度経済成長期という変革の時代の中で、変わらないもの、変わってはいけないものへの著者の強い思いが、物語全体に染み渡っています。
小説「繁栄の昭和」のあらすじ
岸本法律事務所は、第二次世界大戦前から建つ岸本ビルの1階にあり、明治通りに面しています。私はそこで経理を担当する事務員として働いており、商学部の出身であるため、法律に関する知識は持ち合わせていません。ビルの2階には芸能事務所と探偵社があり、1階の法律事務所と廊下の間はガラス張りになっているため、来客の姿がよく見えます。
ある冬の日、私は表通りで微かな銃声を聞き、帳簿から視線を上げると、ビルの入口から入ってきた大柄な男性が血を流しながら倒れ込んでいるのを目撃します。電話を受けて警察官が駆けつけた時には、被害者の東亜工業取締役社長・檜垣六太郎はすでに亡くなっていました。
事件発生当時、明治通りを歩いていた主婦の証言によれば、銃声は聞こえたものの、銃弾が飛んできた方角も分からず、怪しい人影も見ていません。1階の岸本法律事務所、2階の探偵社と芸能事務所、いずれの事業所の責任者も、檜垣氏とは面識がないと供述します。捜査関係者の調べによると、檜垣氏が経営する会社は業績も順調で、取引相手から恨みを買うようなこともないようです。
何の進展もないまま事件が迷宮入りとなっていく中で、熱心な推理小説の愛読者である私は、真犯人の正体について自由気ままに想像を巡らせます。次第に、今回の事件の概要と、私が特に敬愛する一人のミステリー作家との間に不思議な共通点が浮かび上がってきました。
その作家とは、緑川英龍。彼は昭和初期から太平洋戦争勃発の直前にかけて、数多くの探偵小説を世に送り出してきた人気作家です。過激な描写と進歩的な思想から、戦時中は思想警察や軍部から目をつけられ、何冊かの代表作は厳しい検閲を受けて発禁処分にまで追い込まれてしまいます。戦後を迎えても根強いファンからの支持を集めていましたが、本人はなかなか次回作を発表しませんでした。
私が購読している文芸雑誌のゴシップ欄に、緑川英龍が新たな作品を構想中だという小さな記事が掲載されました。彼が長編小説を書いたとすれば実に十数年ぶりになり、私は新作が書店の店頭に並ぶ日が待ちきれません。しかし、いつまで経っても檜垣六太郎殺害事件は解決せず、緑川英龍も執筆活動を再開しません。そして、私も30代半ばのままで年を取ることもなく、岸本法律事務所で働いているメンバーの顔ぶれも依然として同じままなのです。
小説「繁栄の昭和」の長文感想(ネタバレあり)
「繁栄の昭和」を読み終えて、まず感じたのは、筒井康隆氏の底知れぬ創造力と、既存の枠にとらわれない自由な発想への畏敬の念です。この作品は、単なるミステリーとして消費されることを拒否し、読者に深く、そして何度も問いかけます。一体、私たちは何を読んでいるのか。そして、この「私」とは、この世界とは、一体何なのか、と。
物語の冒頭で語られる殺人事件は、古典的な探偵小説の導入部を思わせます。謎の銃声、血を流して倒れる被害者、そして迷宮入りする事件。読者は自然と、「私」と共に犯人探しに没頭しようとします。しかし、読み進めるうちに、この物語が一般的なミステリーの範疇をはるかに超えていることに気づかされます。時間の流れが曖昧になり、登場人物たちの変化が止まり、そして岸本ビルまでもが朽ちることなく佇み続ける。この異様な状況が、作品全体に奇妙な引力をもたらしているのです。
特に印象的なのは、「私」が推理小説の愛好家であるという設定です。彼が敬愛する緑川英龍という架空の作家の存在が、物語の構造に大きな意味を持たせます。緑川氏の作品、その表現、そして彼が置かれていた時代背景が、「私」が身を置く現実と奇妙に符合していく。この時点で、読者の頭の中にはある仮説が生まれることでしょう。それは、この物語自体が、緑川氏の、あるいは別の誰かの「作品」なのではないか、という疑念です。
そして、その疑念は終盤で明確な形を取ります。「私」が小説の中の登場キャラクターでしかない、という衝撃的な事実が明かされるのです。この瞬間に、読者は自身のこれまでの読書体験、そして現実というものの認識そのものを揺さぶられることになります。物語の中で読者が共感し、感情移入してきた「私」が、実は創造された存在であったというカミングアウトは、まさに筒井文学の真骨頂と言えるでしょう。
この作品は、現実と虚構の境界線が曖昧になることで、読者に多大な刺激を与えます。私たちが普段「現実」として認識しているものも、もしかしたら誰かの想像の産物、誰かの「作品」なのではないか。そんな哲学的問いを投げかけてくるかのようです。筒井氏は、読者に安易な答えを与えることをせず、ただひたすらに、その不可思議な世界観を提示し続けることで、私たちを深く思考の淵へと引きずり込みます。
また、「繁栄の昭和」というタイトルが示唆するように、この作品は昭和という時代への深い郷愁と、変化への抵抗を内包しています。高度経済成長期という、あらゆるものが目まぐるしく変化していく時代の中で、変わらないもの、変わってはいけないものへの著者の強い思いが、物語全体に染み渡っています。岸本ビルが古くなることもなく、人々が年を取ることもないという描写は、まさに「永遠の昭和」を願う心の表れと言えるでしょう。
「もう二度と取り返すことのできない昭和の繁栄」という作中のセリフは、この作品の根底に流れるテーマを端的に表しています。それは、失われたものへの哀愁であり、しかし単なる感傷にとどまらず、それを書物の中に、物語の中に永遠に焼き付けておこうとする著者の強い決意を感じさせます。経済的、文化的な発展を享受しつつも、古き良きものを忘れてはいけないというメッセージが、静かに、しかし力強く伝わってきます。
筒井康隆氏は、過去の膨大な知識を受け継ぎつつ、新たな物語を生み出していく旺盛な創作意欲の持ち主です。この作品もまた、既存のミステリーの枠を超え、SF的要素、そしてメタフィクションの要素を巧みに取り入れながら、読者に新たな読書体験を提供しています。彼の作品が常に刺激的であり続けるのは、こうした既存概念への挑戦と、物語の可能性を追求し続ける姿勢にあると言えるでしょう。
「私」が推理小説を愛読する中で、緑川英龍の作品と自身の「現実」との間に共通点を見出す過程は、まるで読者自身がこの物語の謎を解き明かしていくかのようです。しかし、最終的に提示されるのは、謎の解決ではなく、謎そのものが新たな次元へと昇華していくという、ある種の諦めにも似た、しかし深い示唆に富んだ結末です。それは、現実の不可思議さ、人生の不条理さをそのまま受け入れることへの、ある種の肯定とも言えるかもしれません。
この作品は、一度読んだだけではその全貌を理解し尽くすことは難しいかもしれません。再読するたびに新たな発見があり、異なる解釈が生まれるような、深みのある作品です。文学における現実と虚構の関係性、作者と登場人物の関係性、そして読者と物語の関係性について、深く考えさせられるでしょう。
特に、作中で緑川英龍が思想警察や軍部から目をつけられ、作品が発禁処分になるという描写は、表現の自由という普遍的なテーマをも示唆しています。物語の中でさえ、作者がその世界を自由に創造することが許されないという状況は、現実世界における表現の抑圧に対する、筒井氏からの静かなメッセージとも受け取れます。
「繁栄の昭和」は、単なる懐古趣味に終わらない、多義的で示唆に富んだ作品です。昭和という時代背景を巧みに利用しながらも、その主題は普遍的なものであり、時代を超えて多くの読者に響くはずです。現代社会において、情報が溢れ、現実と虚構の境界が曖昧になりつつある今だからこそ、この作品が持つ意味はより一層深まっているように感じます。
ミステリーとしての面白さ、SF的な世界観、そして哲学的問いかけ。これらが渾然一体となった「繁栄の昭和」は、まさしく筒井康隆氏の才能が凝縮された珠玉の一冊と言えるでしょう。この作品は、私たちに読書の喜びを再認識させるとともに、思考の扉を大きく開いてくれるはずです。
まとめ
筒井康隆氏の「繁栄の昭和」は、単なるミステリーに留まらない、深く多層的な魅力を秘めた作品です。昭和という時代を舞台にしながら、現実と虚構の境界を曖昧にし、読者に認識の揺らぎを与えます。物語の語り手である「私」が目撃する殺人事件をきっかけに、読者は緑川英龍という架空の作家の存在を通して、作品の構造そのものに疑問を抱くことになります。
最終的に「私」が小説の登場人物であったことが示唆される衝撃的な展開は、読者に現実とは何か、物語とは何かという根源的な問いを投げかけます。失われた昭和への郷愁と、変わらないものへの願いが込められたこの作品は、単なる懐古趣味ではなく、普遍的なテーマを内包しています。
筒井氏ならではのメタフィクション的手法と、既存のジャンルにとらわれない自由な発想が融合し、読者にこれまでにない読書体験を提供します。情報化社会において、現実と虚構の区別がつきにくくなっている現代において、この作品はさらにその意義を増していると言えるでしょう。
「繁栄の昭和」は、読者に思考の余地を与え、再読を促す奥深い作品です。ミステリー、SF、そして哲学的な要素が巧みに織り交ぜられ、筒井康隆氏の独創的な世界観を存分に堪能できる一冊です。