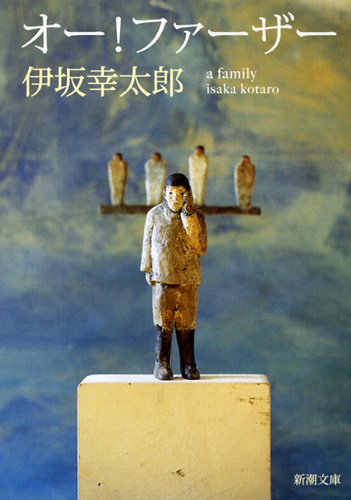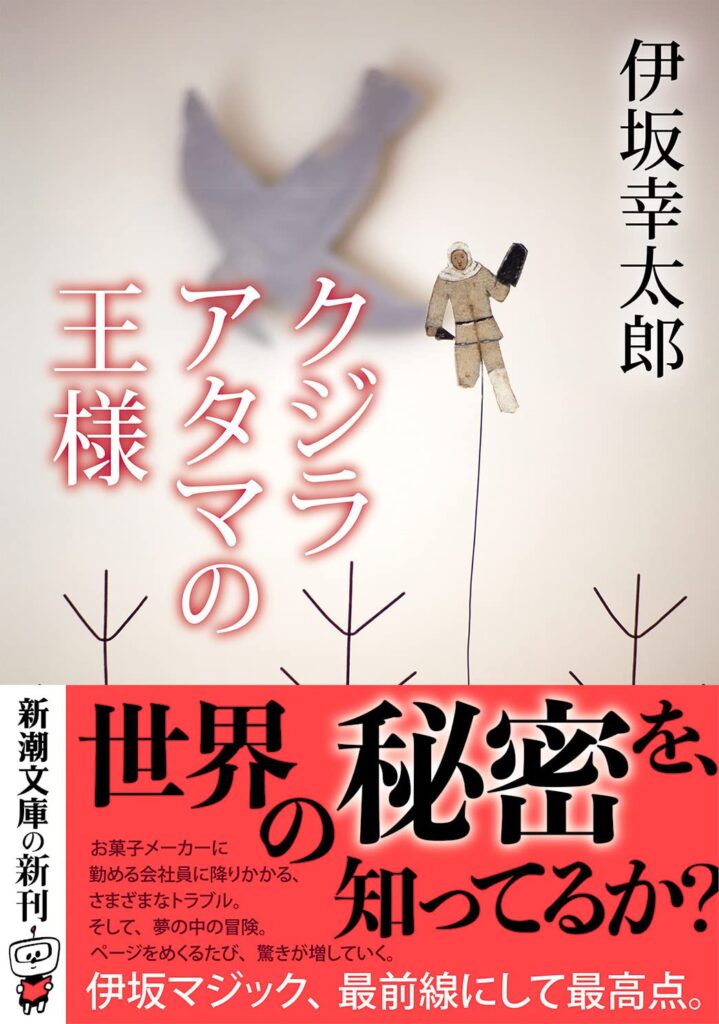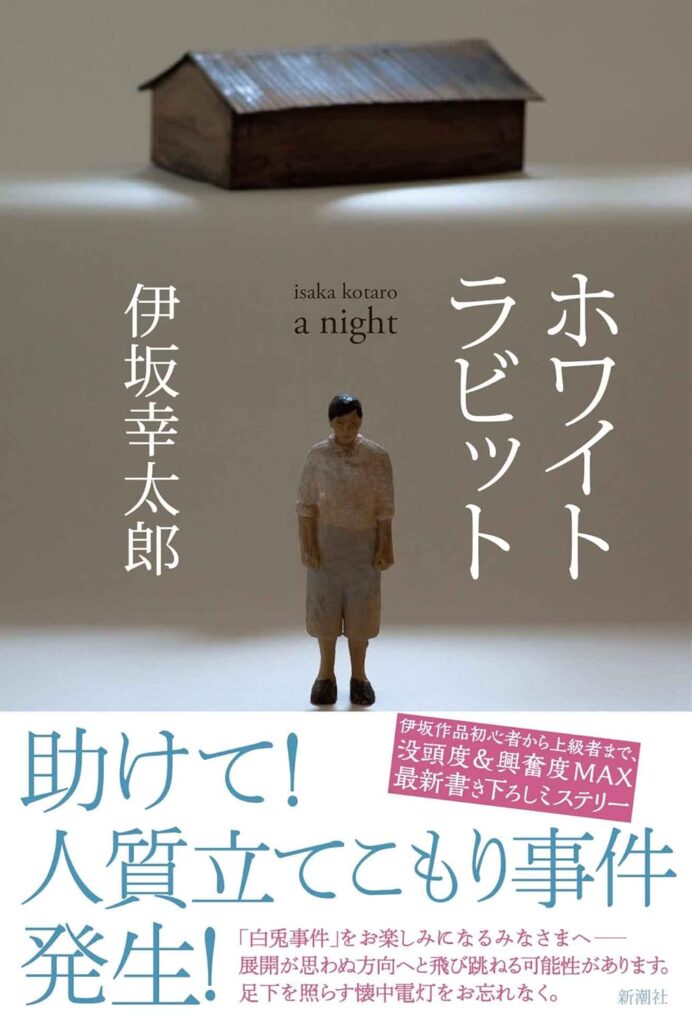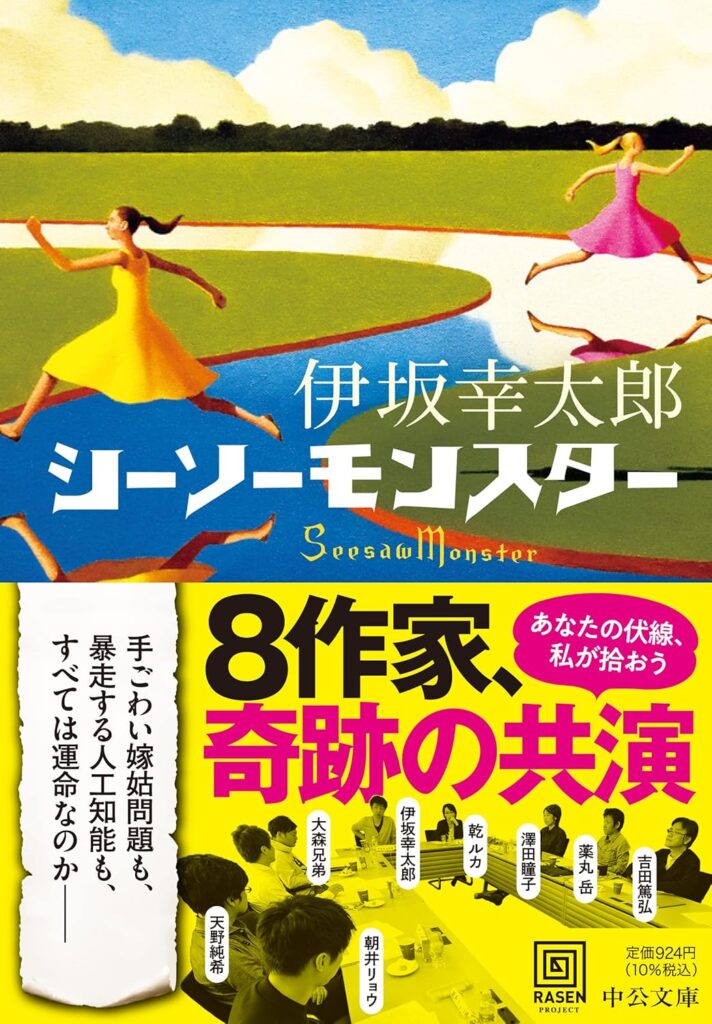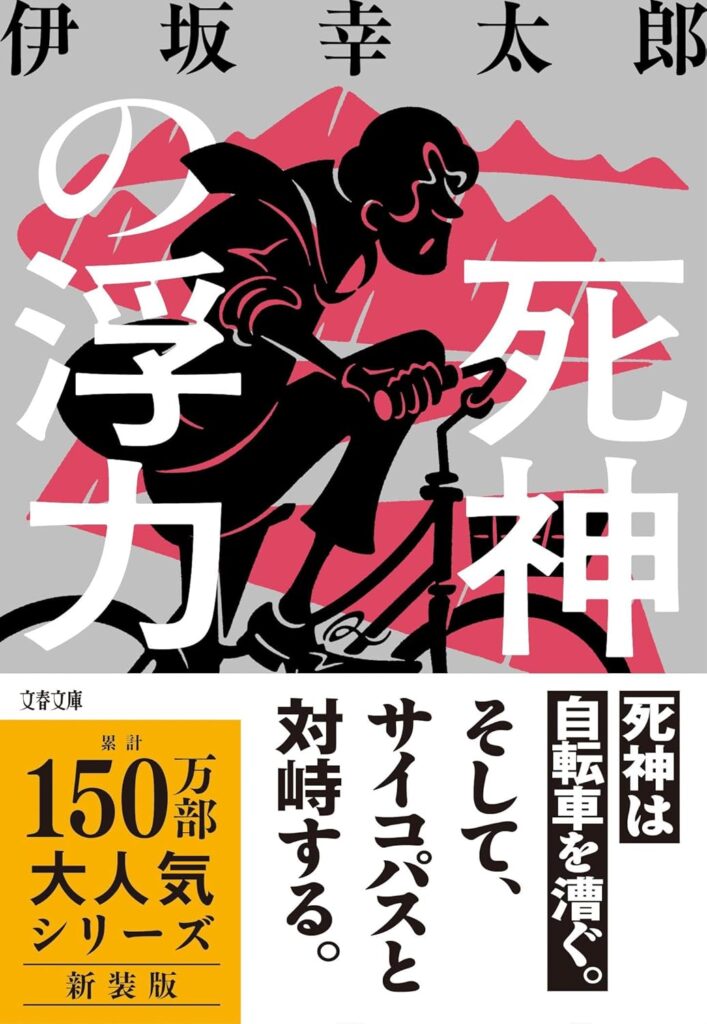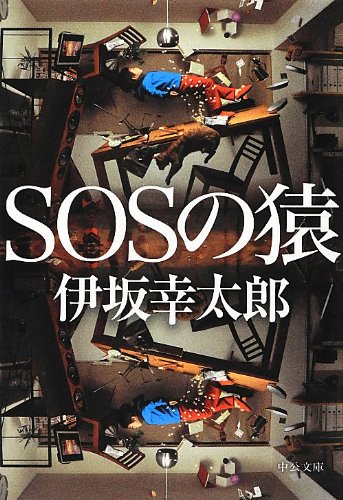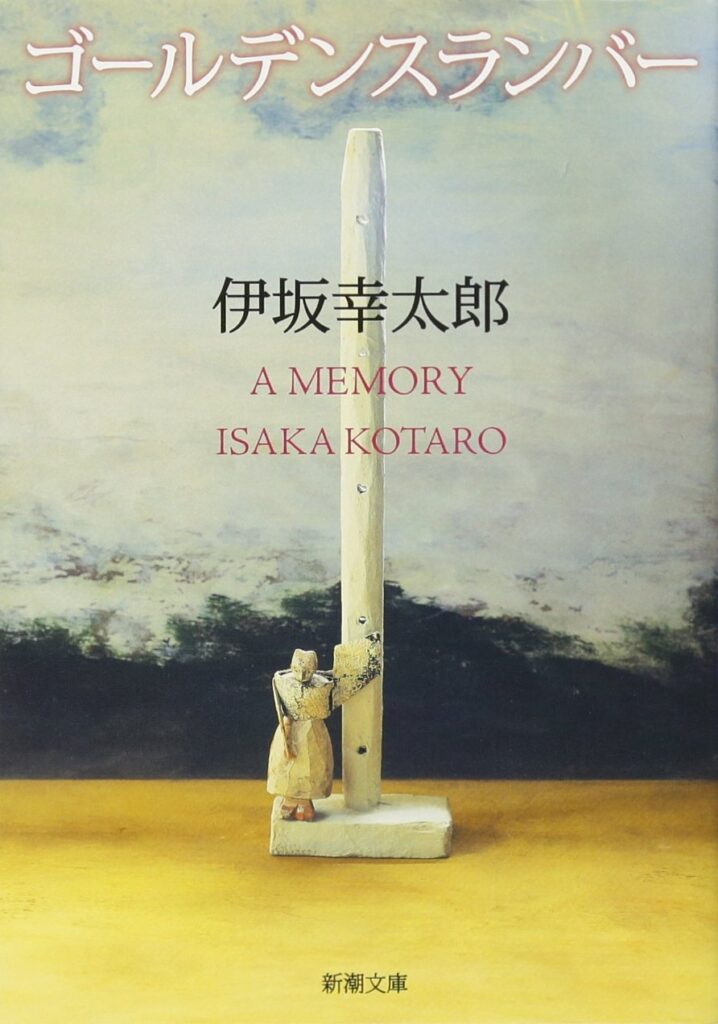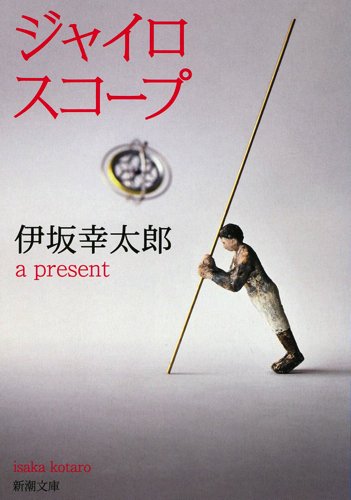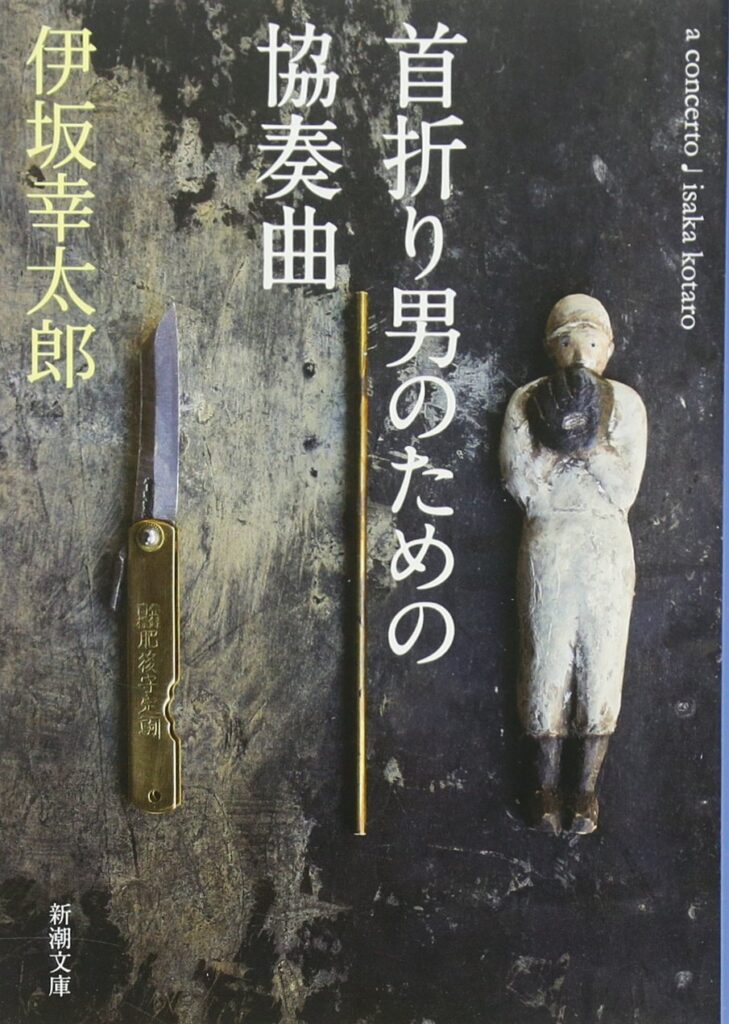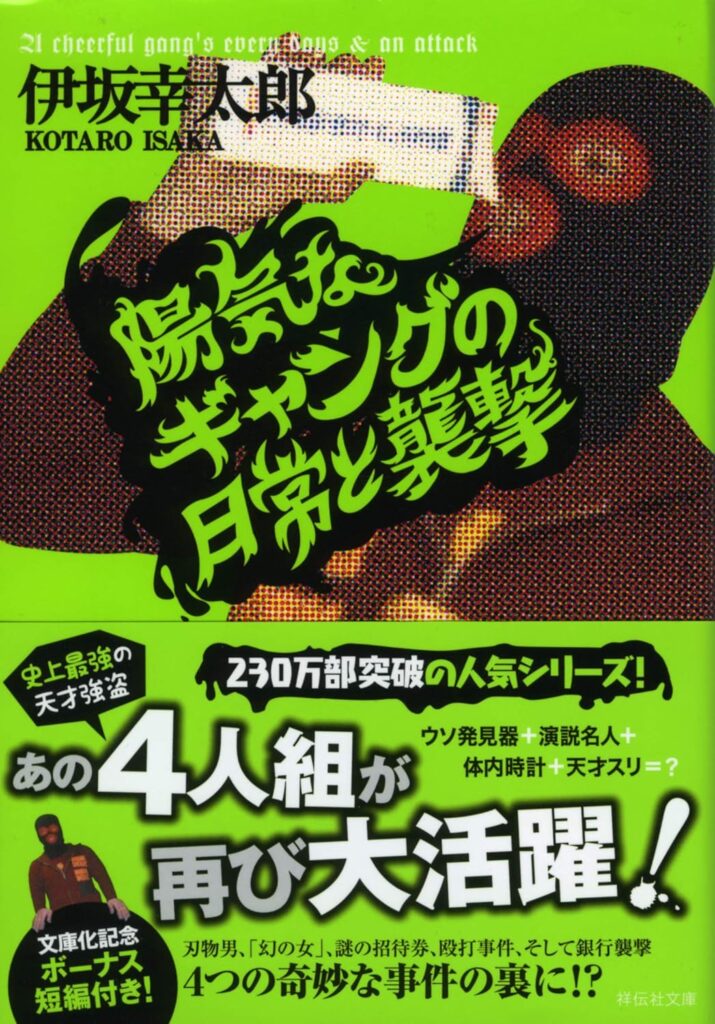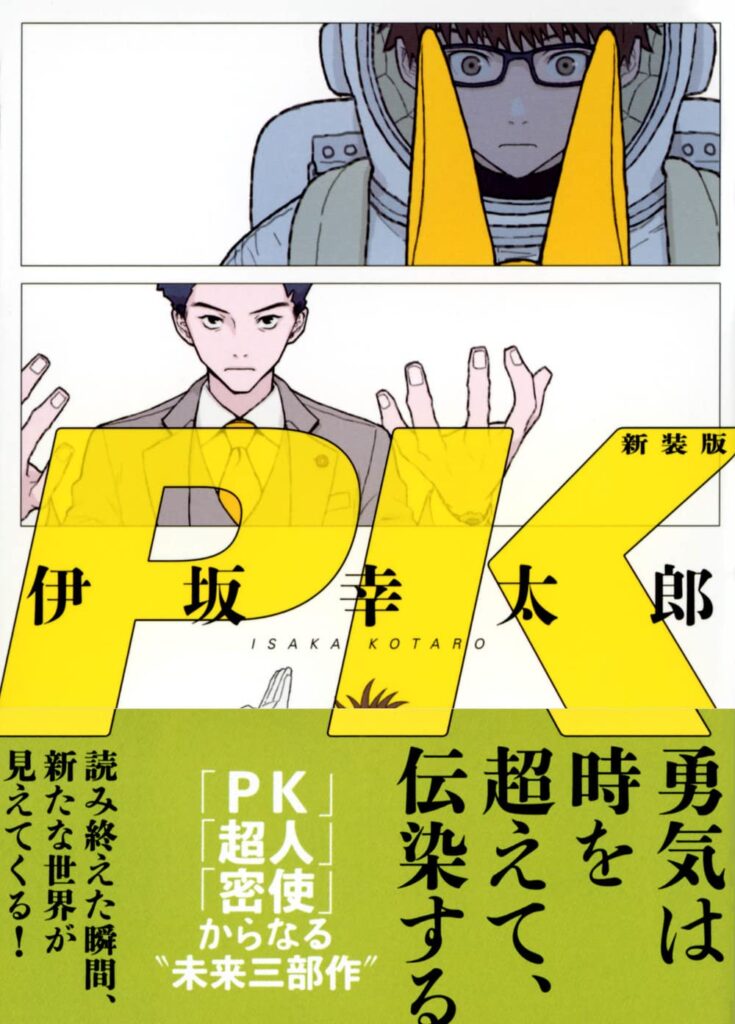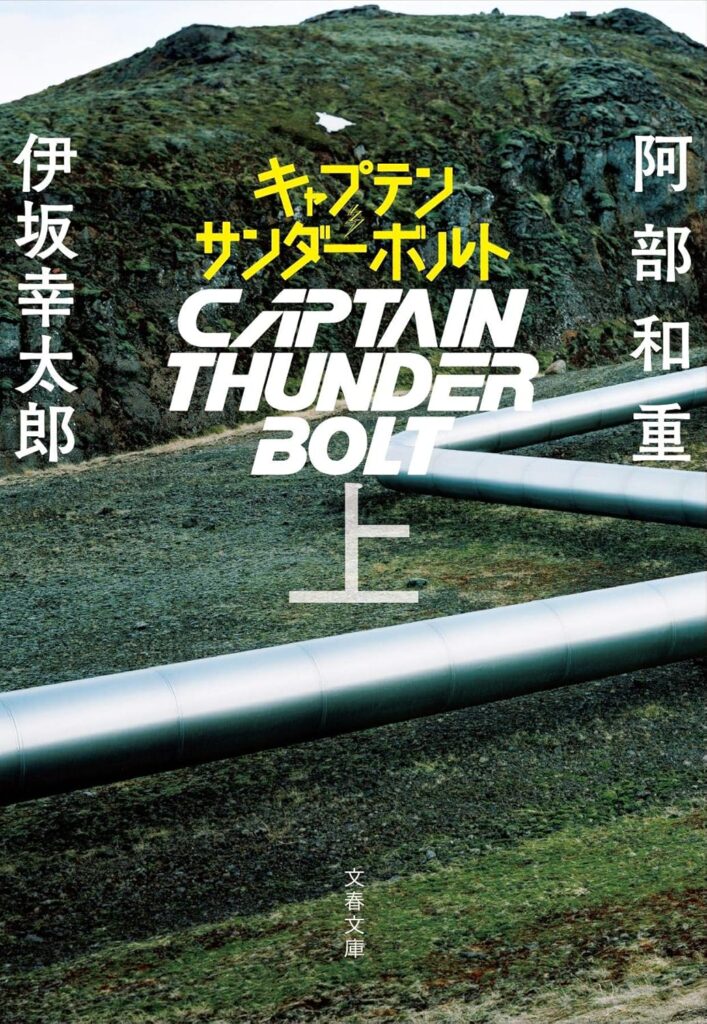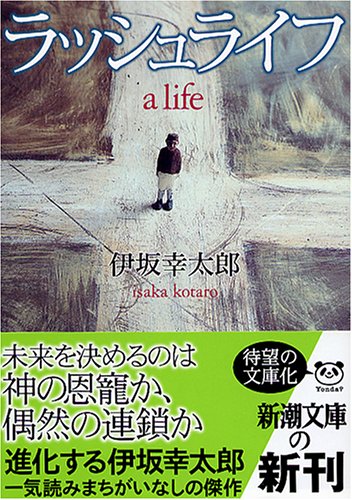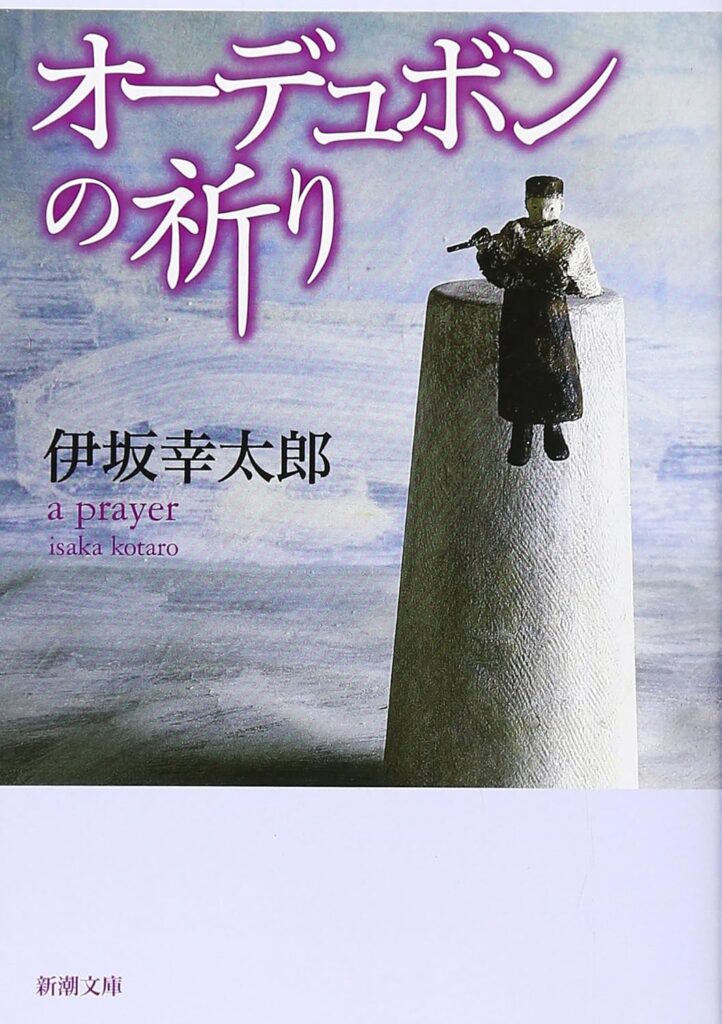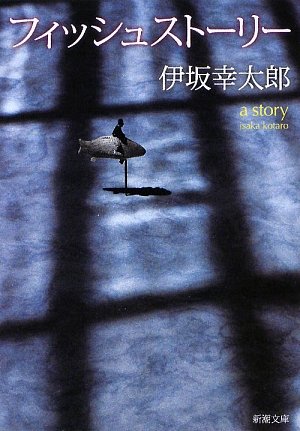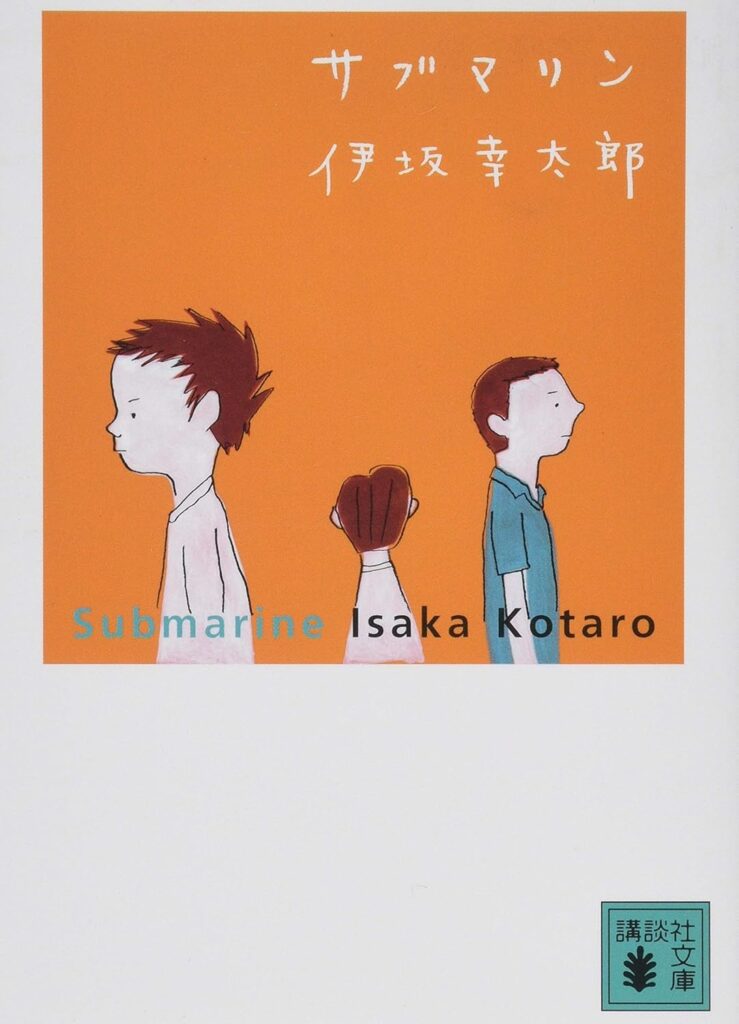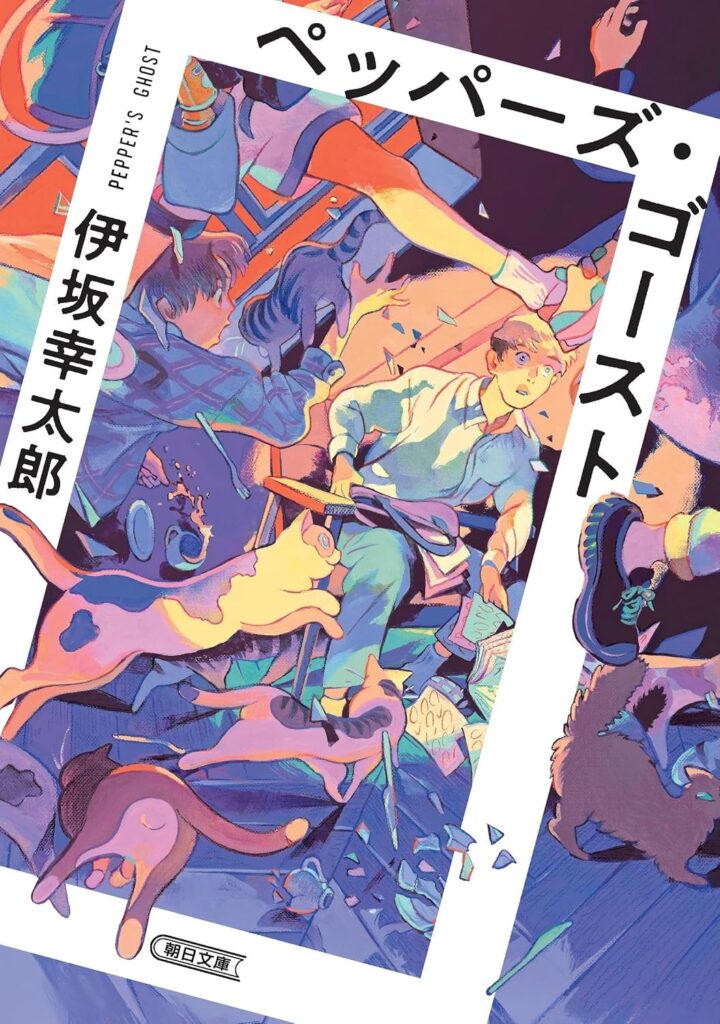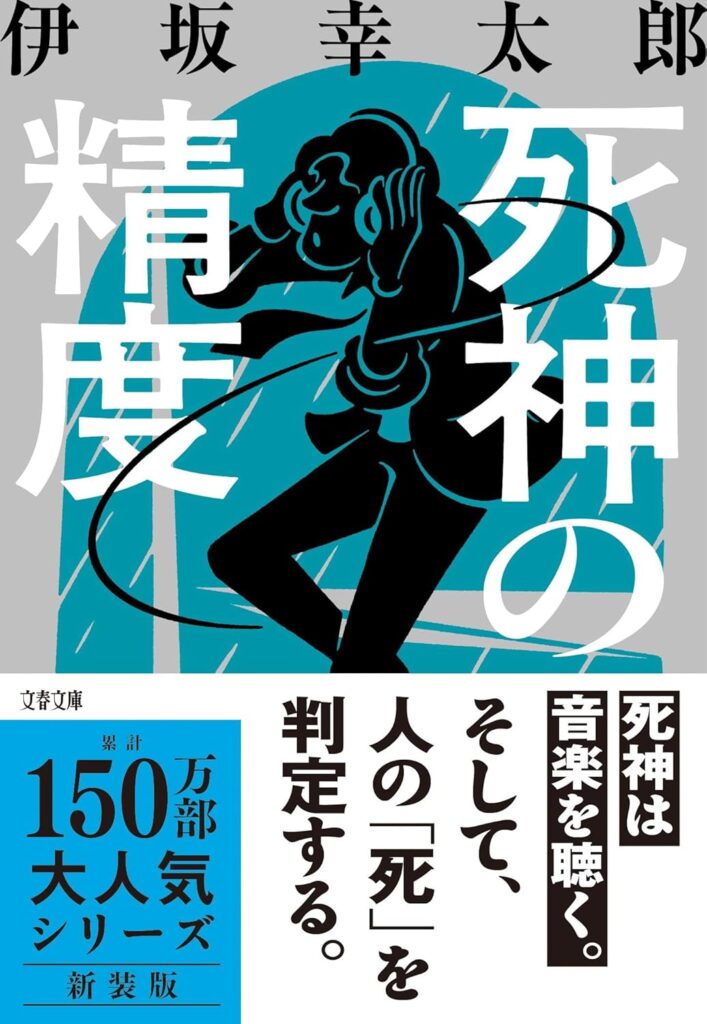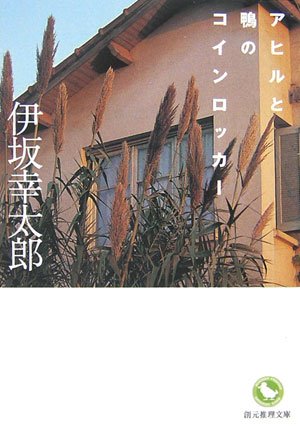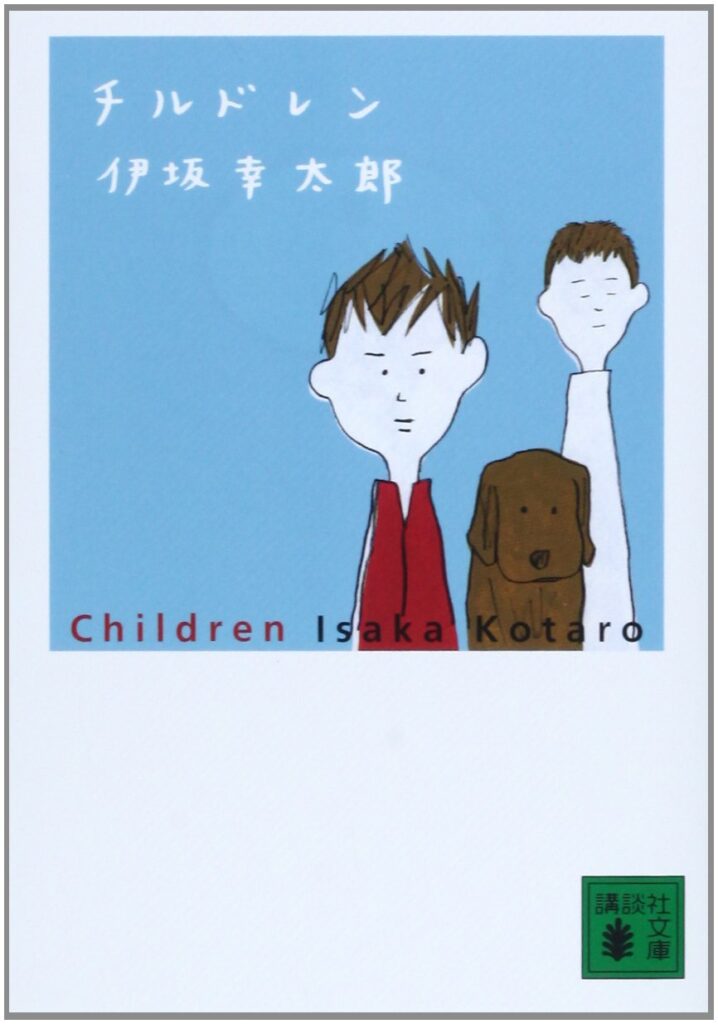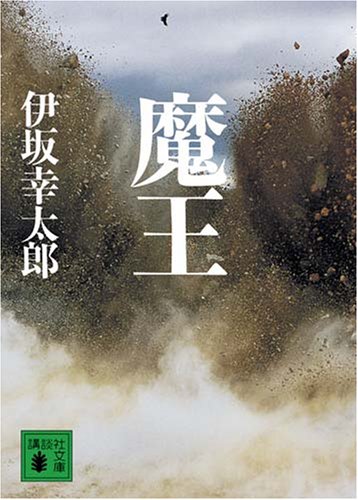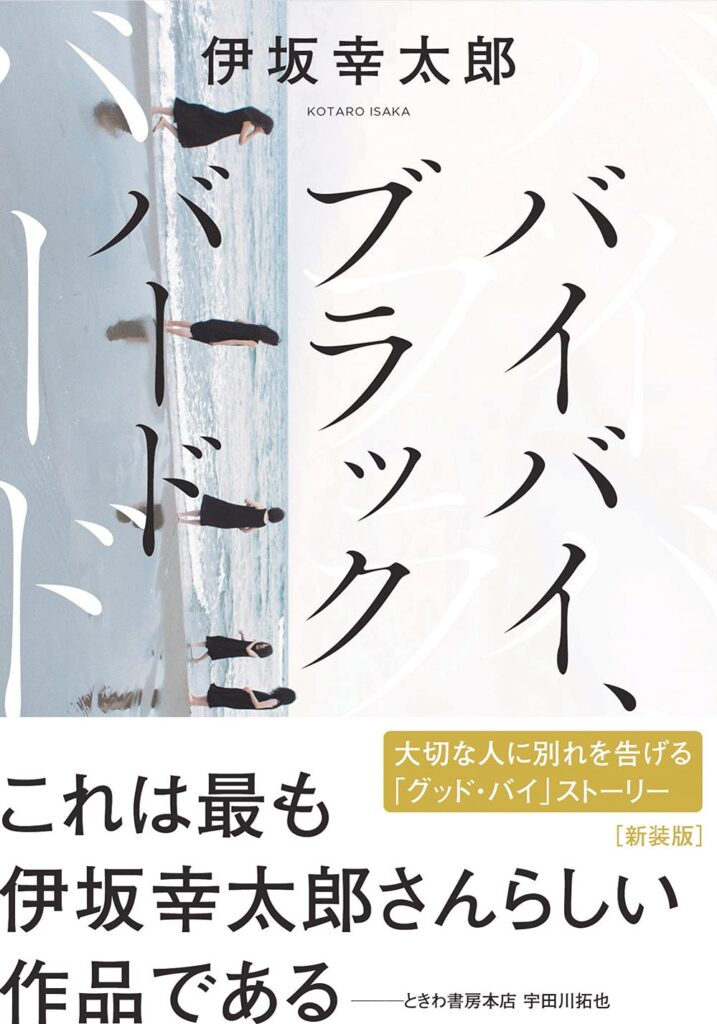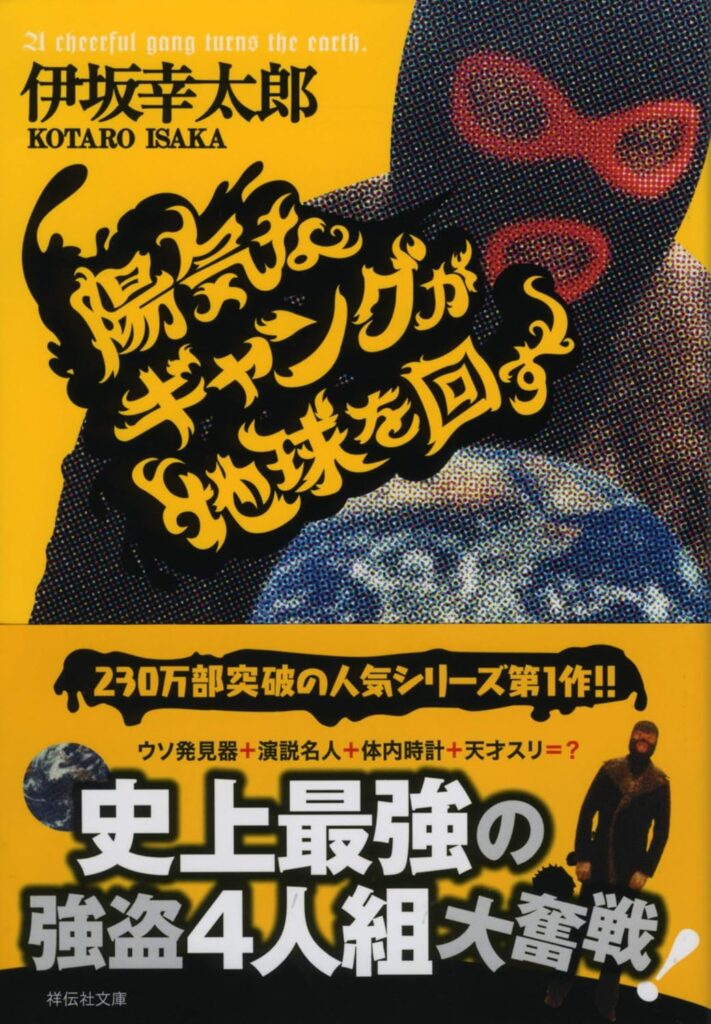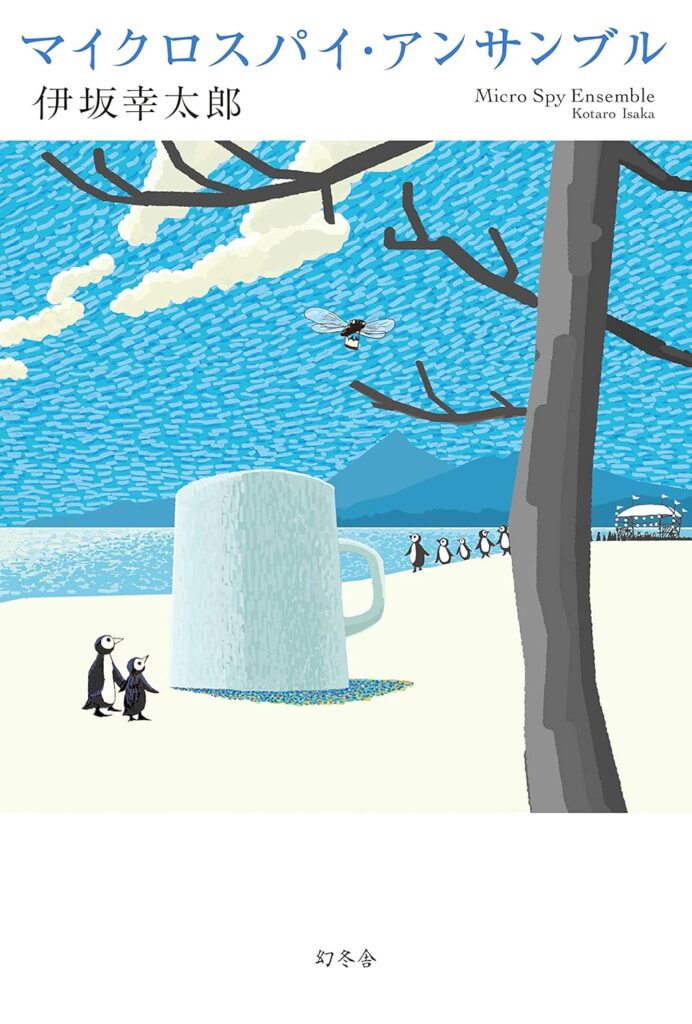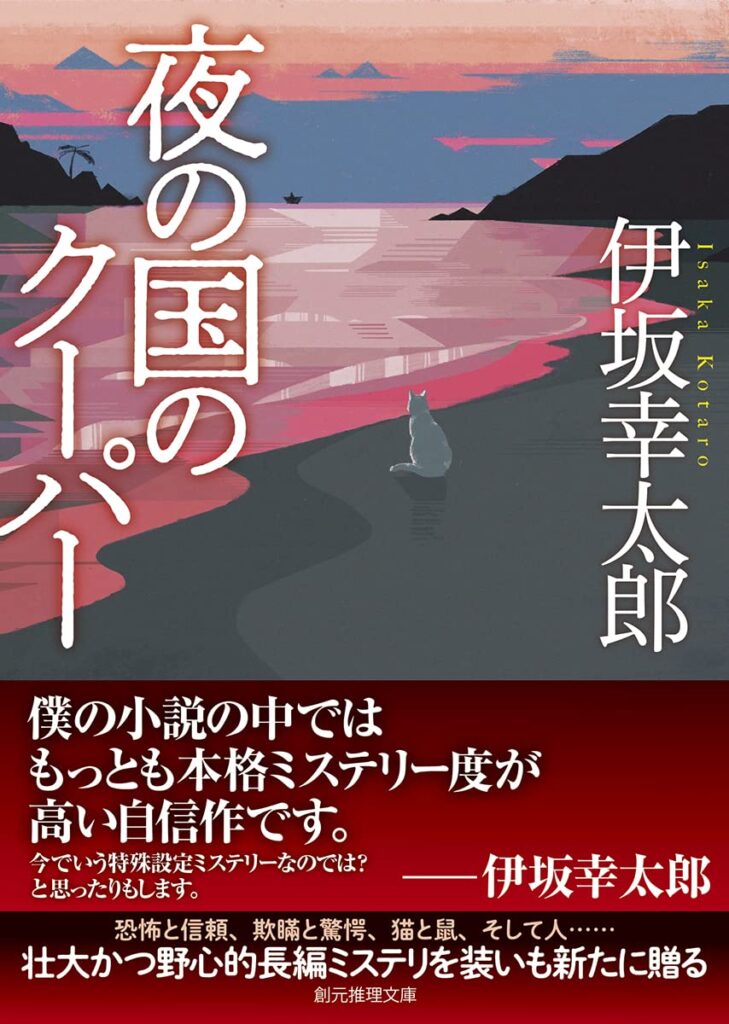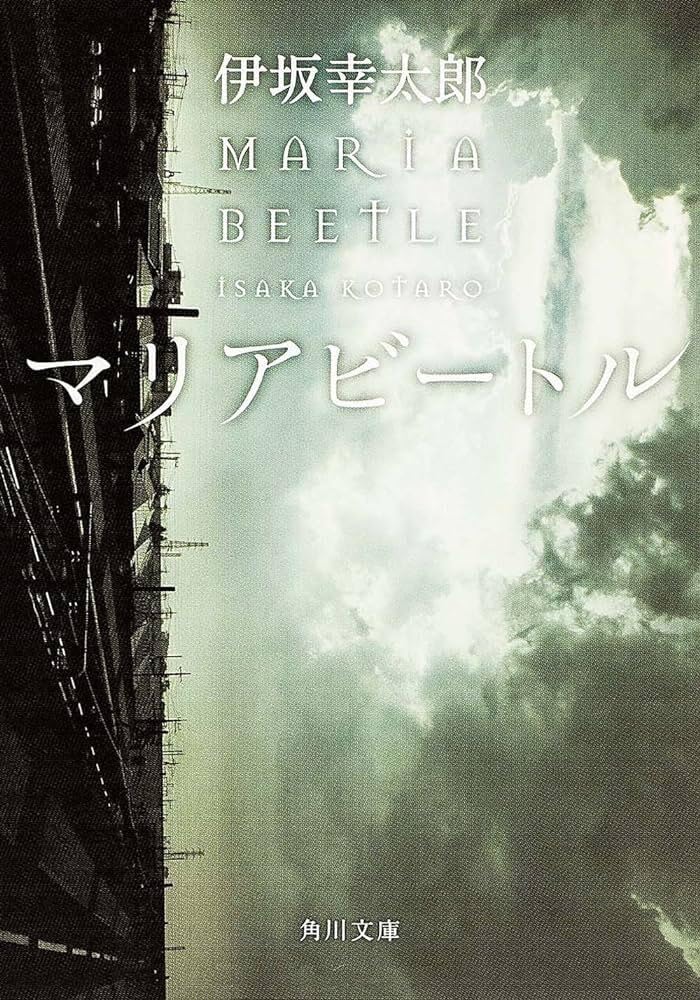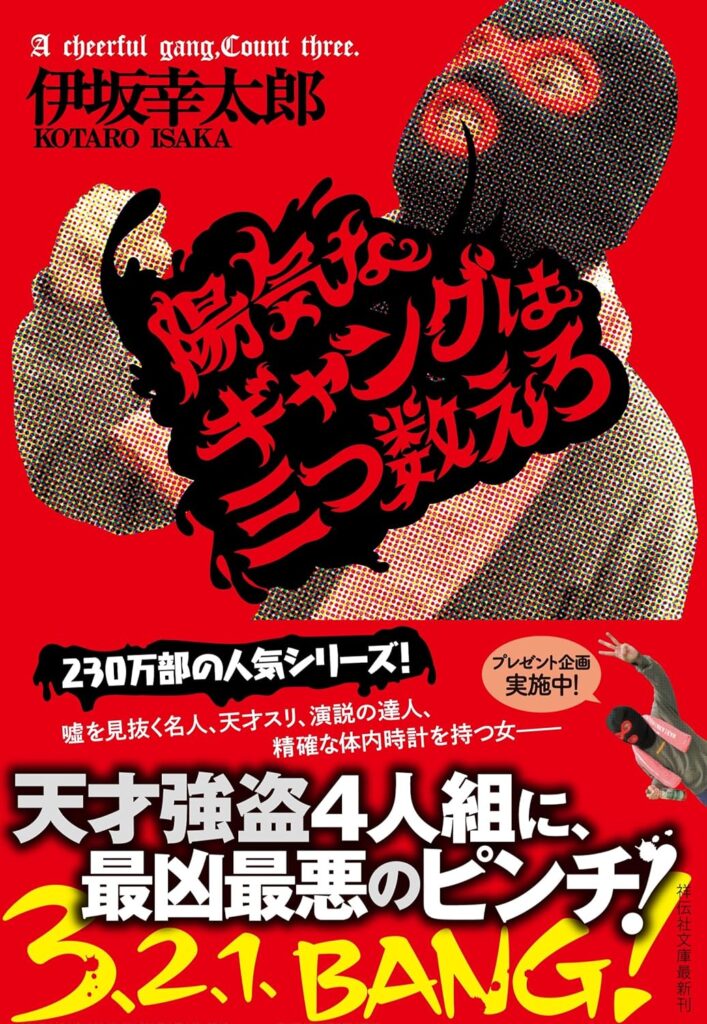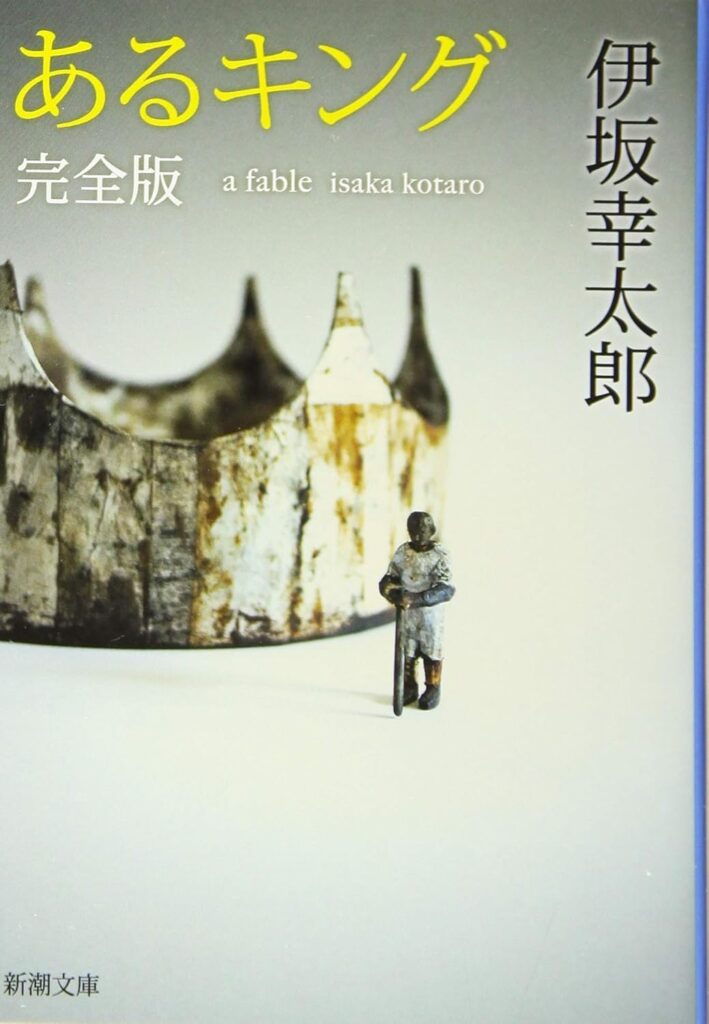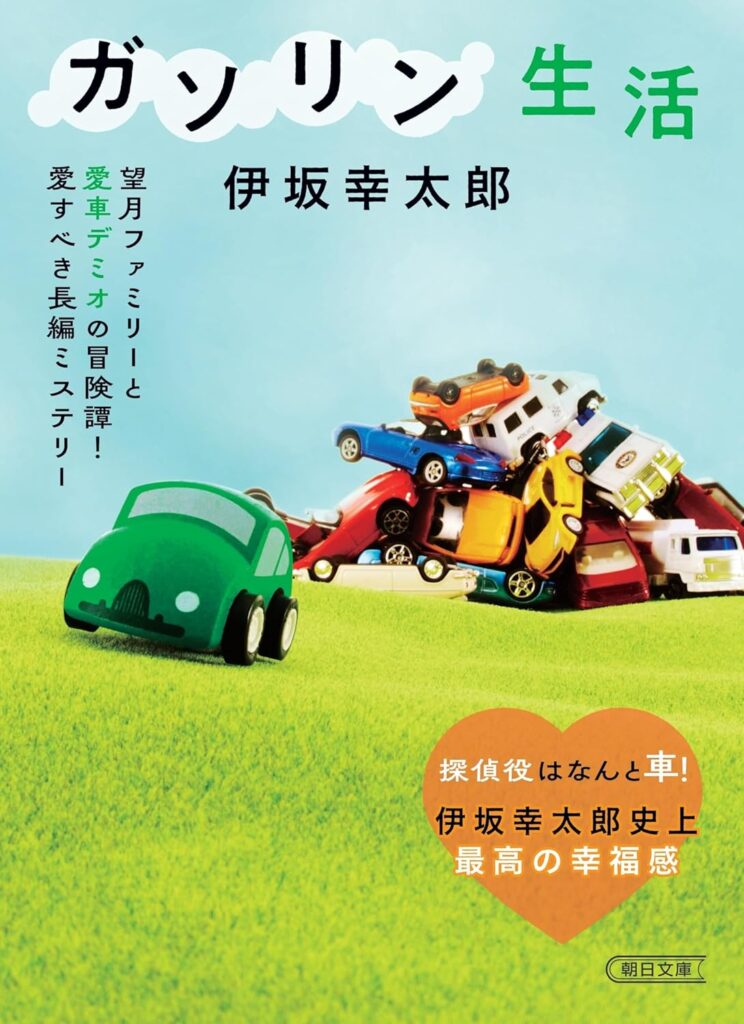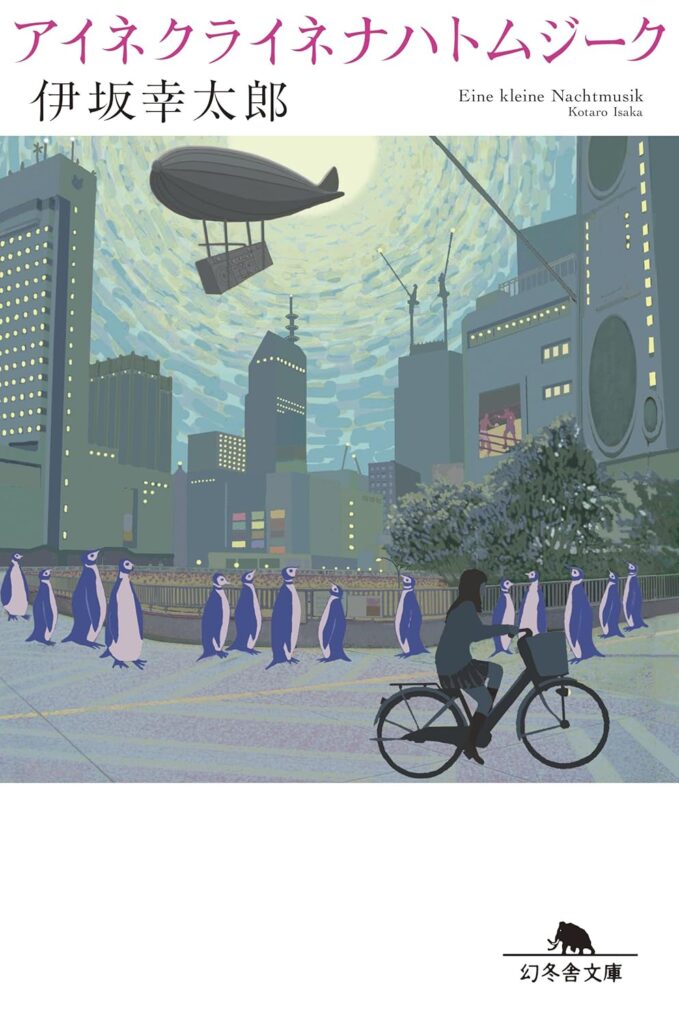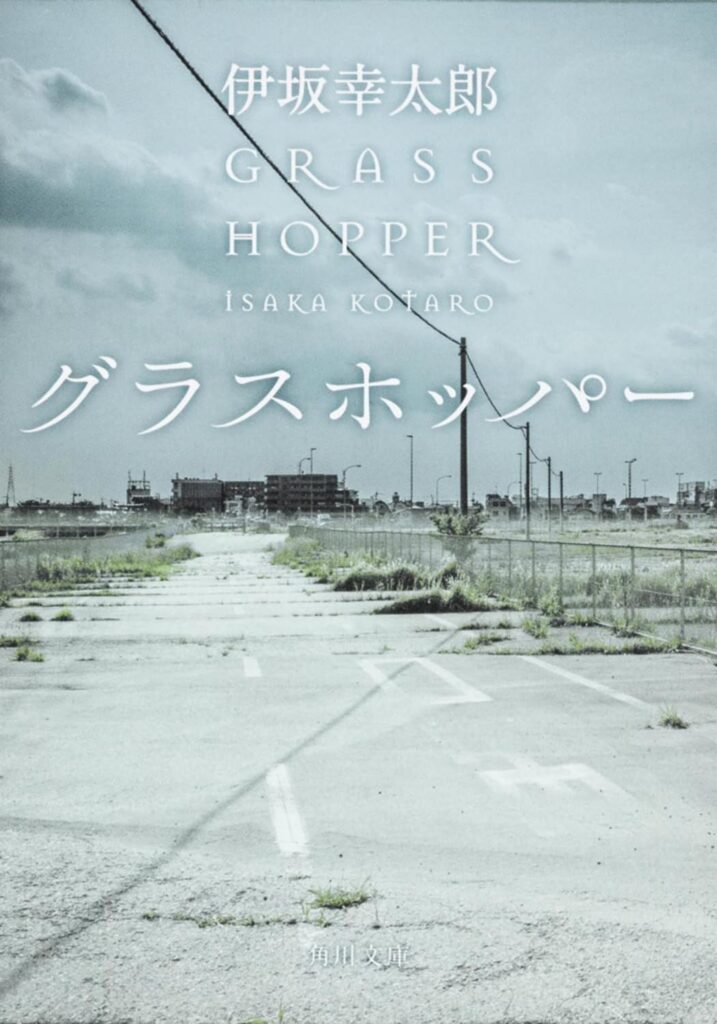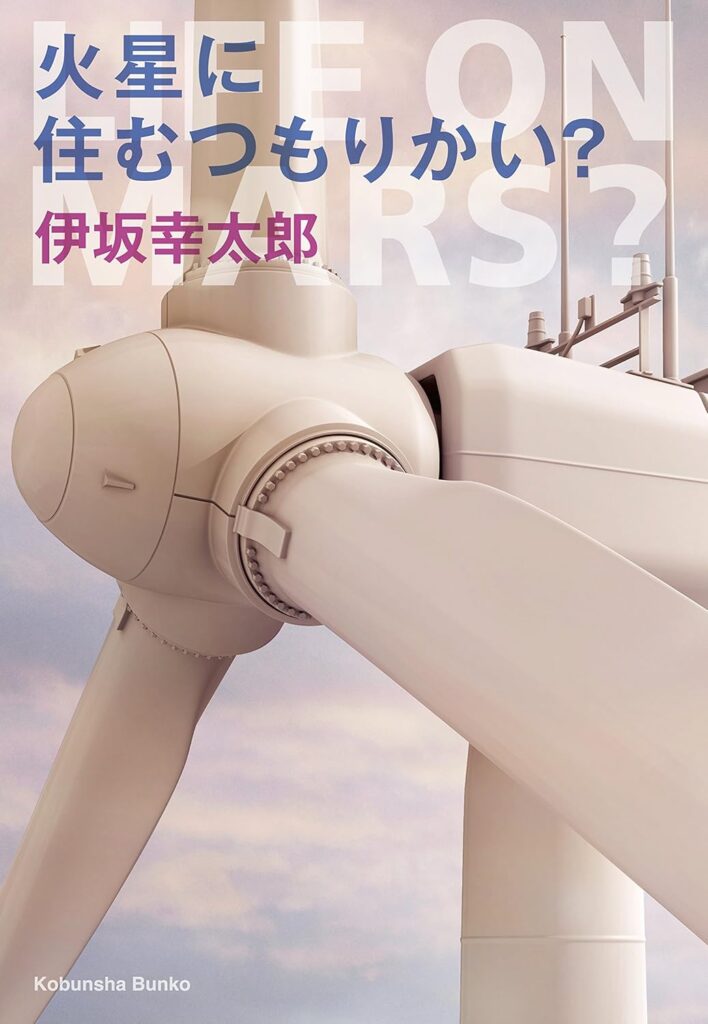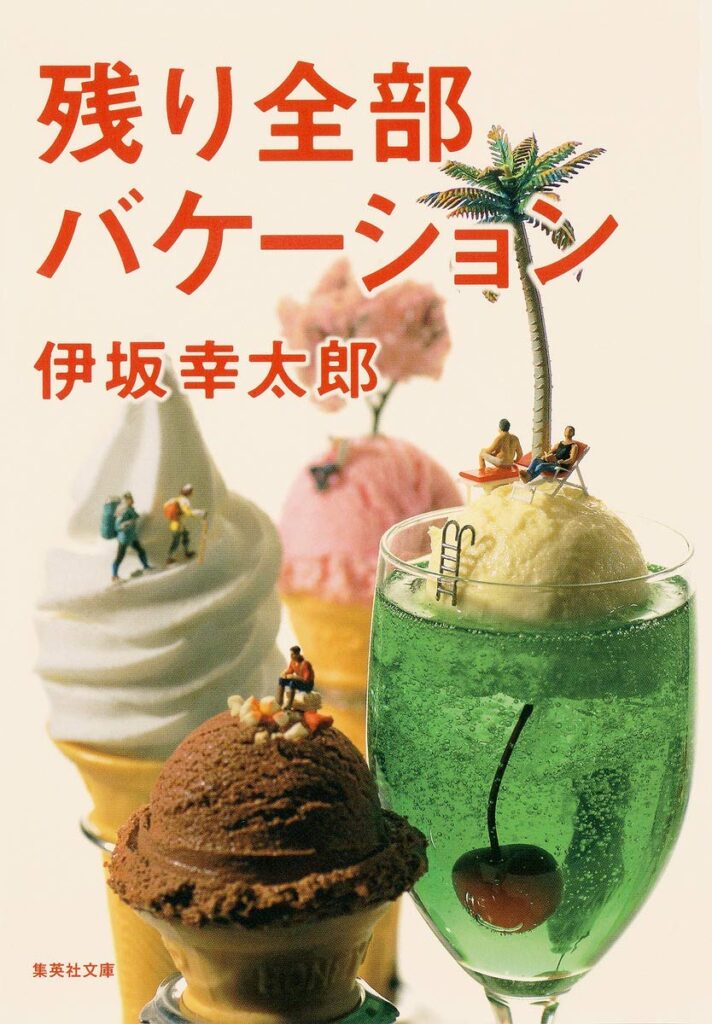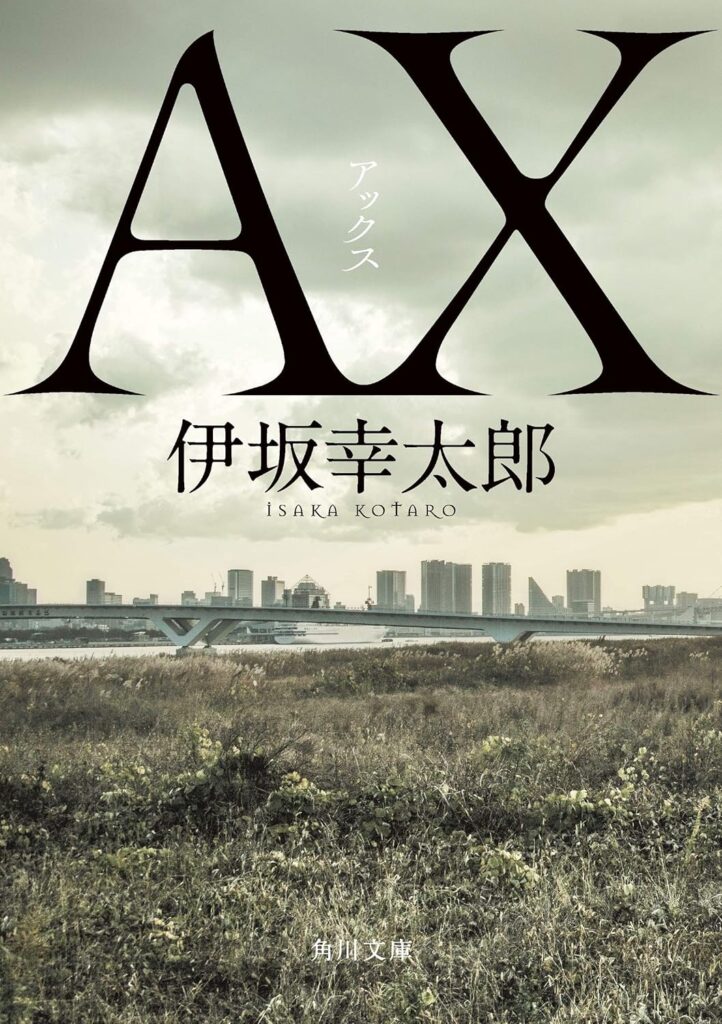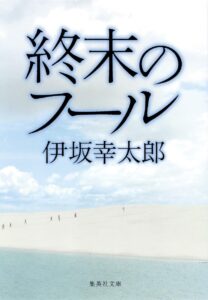 小説「終末のフール」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「終末のフール」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
本作は、8年後に小惑星が衝突し地球が滅亡すると予告された世界で、残された日々を生きる人々の姿を描いた連作短編集です。舞台は仙台の北部に位置する「ヒルズタウン」という名の団地。絶望的な状況下でありながらも、どこか淡々と、そして懸命に日常を送ろうとする住民たちの物語が、8つの短編を通して語られていきます。
それぞれの物語は独立しているようでいて、登場人物や出来事が緩やかに繋がり、ヒルズタウンというコミュニティの輪郭を浮かび上がらせます。家族の再生、新たな命の選択、過去への復讐と赦し、ささやかな目標、変わらない信念、人生の終わり方、疑似家族の絆、そして未来への希望。多様なテーマが、終末を控えた人々のドラマを通して描かれています。
この記事では、そんな「終末のフール」の物語の核心に触れながら、各短編の概要と、私が感じたことを詳しくお伝えしていきたいと思います。読み進めることで、作品の世界観や登場人物たちの魅力、そして物語に込められたメッセージを深く味わっていただけるはずです。
小説「終末のフール」のあらすじ
物語の舞台は、小惑星衝突による地球滅亡まであと3年となった世界。かつてパニックと暴動に揺れた社会も、今は一種の諦観と共に奇妙な落ち着きを取り戻しています。人々は残された時間をどう過ごすか、それぞれの答えを見つけようとしていました。物語の中心となるのは、仙台北部の丘陵地に立つ団地、ヒルズタウンの住民たちです。
第一話「終末のフール」では、10年前に家を出た娘・康子が実家に戻ってくることから、ぎくしゃくしていた家族の関係が変化していく様子が描かれます。父親のかつての発言が原因で長男が亡くなったという重い過去を抱えながらも、終末を前にして家族が再び向き合おうとします。続く「太陽のシール」では、妊娠が判明した夫婦、富士夫と美咲が、残り少ない世界で子供を産むべきか葛藤します。優柔不断な夫としっかり者の妻、そして周囲の人々の言葉が、彼らの決断に影響を与えていきます。
「籠城のビール」は、他の短編とは少し毛色が異なり、緊迫した状況下での物語です。妹をメディアの過熱報道によって失った兄弟が、その元凶と信じる元アナウンサー・杉田玄白の家に復讐のために押し入ります。しかし、そこには予想外の事実が待っていました。一方、「冬眠のガール」では、両親を亡くした若い女性・美智が、「恋人を見つける」という新たな目標に向かって一歩を踏み出す、ささやかながらも心温まる物語が展開されます。
このように、「終末のフール」は、ヒルズタウンに住む様々な人々の視点から、終末を控えた世界の日常と非日常を描き出します。キックボクサーの再起、妻を亡くした男の選択、元役者の女性が演じる様々な役割、そして全てを見守るレンタルビデオ店店長の物語へと繋がっていき、それぞれの人生が交錯しながら、絶望の中にも確かに存在する希望や人間の繋がりを浮かび上がらせていくのです。
小説「終末のフール」の長文感想(ネタバレあり)
伊坂幸太郎さんの「終末のフール」を読み終えたとき、なんとも言えない静かな感動と、胸にじんわりと広がる温かさを感じました。地球滅亡まであと3年という、途方もなく重い設定。それなのに、描かれるのは劇的なスペクタクルではなく、仙台の団地「ヒルズタウン」に住む人々の、ある意味で「普通」の日常と、その中での心の動きなのです。
この作品は8つの短編からなる連作短編集ですが、それぞれの物語が独立しているようでいて、登場人物や場所が緩やかにリンクし、読み進めるほどにヒルズタウンというコミュニティの全体像が見えてくる構成になっています。この繋がりを発見するのも、伊坂作品を読む楽しみの一つですよね。
まず表題作でもある「終末のフール」。これは、家族の再生の物語です。主人公である父親は、かつて自分の心ない一言が原因で長男・和也を自殺に追い込んでしまったという過去を背負っています。10年ぶりに娘の康子が帰ってくるのですが、家族の間には気まずい空気が流れています。しかし、「あと3年で世界が終わる」という状況が、彼らが再び向き合うきっかけを与える。特に、和也が遺した言葉や、彼が好きだった映画の話題を通じて、少しずつわだかまりが解けていく様子は、切なくも優しい。世界が終わるからといって、過去の傷が完全に癒えるわけではないけれど、それでも残された時間で関係を修復しようとする姿に、人間のささやかな強さを感じました。レンタルビデオ店の渡部さんが、さりげなく彼らを見守っているのもいいですね。
「太陽のシール」は、終末を前にして「産む」という選択をする夫婦の話。富士夫の優柔不断さと、姉さん女房の美咲のしっかり者っぷりの対比が印象的です。妊娠がわかったとき、あと3年しかない世界に子供を産み落とすことへの迷いや不安は、想像に難くありません。でも、高校時代の友人・土屋とその息子リキとの交流を通じて、富士夫は覚悟を決める。土屋が語る「今を生きる子供」の話や、美咲の「私たちが太陽みたいになって、その子を照らしてあげればいい」という言葉には、未来への希望が託されているように感じました。絶望的な状況だからこそ、「生」や「未来」について深く考えさせられるエピソードです。「大逆転」という土屋の異名も、状況を考えると皮肉でありながら、どこか希望を感じさせる響きがあります。
「籠城のビール」は、この短編集の中では異質な、サスペンス色の濃い物語です。妹・暁子をメディアスクラムの末に亡くした虎一と辰二の兄弟が、元凶と信じる元アナウンサー・杉田玄白に復讐すべく家に押し入る。序盤は兄弟の怒りと悲しみがひしひしと伝わってきて、杉田一家に対する憎しみが募ります。特に、襲撃されているのに平然と食事を続けようとする妻と娘の姿には、読んでいるこちらも「なんて奴らだ!」と思ってしまう。しかし、物語は急展開を迎えます。実は杉田一家は、暁子の命日に合わせて無理心中を図ろうとしていたのです。食卓の料理には毒が盛られていた…。このどんでん返しには驚かされました。復讐するはずだった相手が、自分たちと同じように深い苦悩と後悔を抱えていたと知った時の兄弟の動揺。そして、これ以上迷惑はかけられないと、兄弟を逃がそうとする杉田一家。加害者と被害者の境界線が曖昧になり、憎しみや復讐心が溶けていく過程が巧みに描かれています。「生き延びて苦しむことが復讐になる」という考えに至る兄弟の心境の変化も、やるせないけれどリアルです。最後に「ランナウェイ・プリズナー(逃亡する囚人)」という映画のセリフが引用されるのも、伊坂さんらしい締め方だなと思いました。
「冬眠のガール」は、一転して穏やかで心温まる話です。両親を亡くし、一人で暮らす田口美智。父親の本を読み終えた彼女が次に立てた目標は「恋人を見つける」こと。なんとも可愛らしい目標ですが、終末を前にした世界では、それも切実な願いなのかもしれません。スーパーマーケットの店長(キャプテンと呼ばれたがる!)や、同級生の誓子との交流、そして高校時代の家庭教師だった小松崎との再会。物語は淡々と進みますが、美智の少し不器用ながらも前向きな姿に心が和みます。「冬眠」というキーワードは、単に寒い季節の話というだけでなく、世界の終わりを前に活動を停止していたような美智の心が、再び動き出すことを象徴しているように思えました。スーパーで美咲(「太陽のシール」の!)が言った言葉が伏線になっていて、ラストで美智が小松崎と良い雰囲気で出会うシーンは、ささやかな希望を感じさせてくれます。香取さん(「終末のフール」の夫婦)の名前がここでわかるのも、連作短編ならではの楽しみですね。
「鋼鉄のウール」は、個人的にとても好きなエピソードです。主人公は、引きこもりがちだった両親を持つ16歳の「ぼく」。彼は5年ぶりにキックボクシングのジムを訪れ、元チャンピオンの苗場や会長と再会し、再び練習に打ち込み始めます。苗場さんがとにかく格好いい。世界の終わりが近づいても、彼は以前と変わらずストイックに練習を続けている。「明日死ぬとしたら、生き方が変わるんですか?」「やるべきことをやるだけだ」という彼の言葉は、重く響きます。終末だからといって、自暴自棄になったり、全てを投げ出したりするのではなく、ただ淡々と、自分が信じる道を貫く。その姿は、迷いや不安を抱えながら生きる「ぼく」にとって、大きな支えとなります。亡くなった専属カメラマン・三島愛への想いを胸に秘めながら戦い続ける苗場の姿は、切なくも美しい。この話を読むと、どんな状況でも自分を見失わずに生きることの大切さを教えられます。そして、ここで桜庭夫妻(「太陽のシール」の!)の名前も判明します。
「天体のヨール」は、少し哀愁漂う物語。妻・千鶴を通り魔に殺され、その犯人に復讐を果たした元社長の矢部。彼は自らも命を絶とうとしますが、大学時代の友人である天体オタク・二ノ宮からの電話で思いとどまります。二ノ宮の家で、昔話に花を咲かせ、そして天体望遠鏡を覗く。妻を失い、復讐という目的も果たしてしまった矢部にとって、残された世界は空虚だったのかもしれません。しかし、二ノ宮との時間や、星空を見上げる中で、彼は何か別のものを見つけたのかもしれません。ラスト、彼がどのような選択をしたのかは明確には描かれていませんが、妻のいない世界との別れを選んだとしても、それは絶望だけではない、ある種の静かな諦念と安らぎがあったのではないかと感じました。
「演劇のオール」も、とても心に残る一編でした。元劇団員の倫理子は、様々な人の「役割」を演じています。孫娘、姉、母親、彼女…。それは、終末を前に孤独や喪失感を抱える人々の心を埋めるための「優しい嘘」のようなもの。早乙女おばあちゃん、亜美、勇也と優希、そして一郎。彼らは倫理子が演じていることを知りながら、その関係性を受け入れています。演じている倫理子自身も、その役割を通して誰かの役に立つことに喜びを見出している。タマという名前の犬(猫かと思いきや!)や、一郎と亜美の意外な職業(警察官!)など、小さな驚きもちりばめられています。ラストで語られる、かつて倫理子が憧れた俳優「ミスターカメレオン」のインタビューの答えが、この物語全体を象徴しているようで、見事な締めくくりでした。「誰かの人生の一部になれるなら、それは役者冥利に尽きる」…倫理子の生き方は、まさにそれを体現しているかのようです。登場人物がみんな温かくて、読後感がとても良いお話です。
そして、最後を飾る「深海のポール」。この物語の語り手は、これまでの短編にも度々登場してきたレンタルビデオ店の店長・渡部修一です。彼の視点を通して、ヒルズタウンの様々な人々が再び登場し、物語が一つに収束していくような感覚があります(矢部さん以外はほぼ出てきますね)。渡部の父親が、マンションの屋上に意味不明な「櫓(やぐら)」を作り始めるというエピソードが中心になりますが、これがまた良い味を出している。最初は奇行にしか見えないけれど、そこには父親なりの終末への向き合い方や、家族への想いが込められているのかもしれません。妻・華子の「じたばたして、足掻いて、もがいて。生き残るのってそういうのだよ、きっと」という言葉や、娘・未来の無邪気な「死んでも死なない、死んでも死なない」という繰り返し。これらの言葉が、絶望的な状況の中でも諦めずに生きようとする力を与えてくれます。10年間も延滞している蔦原耕一の父親のエピソードも、ささやかな抵抗や希望を感じさせます。そして、渡部が最後に櫓の上から見るヒルズタウンの風景。それは、終わりゆく世界の中にも確かに存在する人々の営みと、未来への微かな光を象徴しているかのようでした。まるで暗い海に差し込む一筋の光のように、未来への希望を示唆しているかのようです。
「終末のフール」全体を通して感じるのは、極限状態における「日常」の尊さです。世界が終わるとわかっていても、人々はご飯を食べ、仕事をし、恋をし、悩み、笑い、そして誰かを想う。その一つ一つの営みが、とても愛おしく感じられます。伊坂さん特有の軽妙な会話や、さりげない伏線、そして登場人物たちの魅力的なキャラクター造形も健在で、重いテーマを扱いながらも、読後感は決して暗くはありません。むしろ、静かな希望や、生きていくことへの肯定感を与えてくれる作品だと思いました。
特に印象的だったのは、登場人物たちがそれぞれに「やるべきこと」を見つけ、それを淡々とこなしていく姿です。復讐を計画する者、子供を産む決意をする者、過去と向き合う者、恋人を探す者、練習に打ち込む者、役割を演じる者、櫓を作る者…。その行動が世界を救うわけではないけれど、彼らにとってはそれが「今を生きる」ということなのでしょう。
「終末のフール」は、派手さはないかもしれませんが、読めば読むほど味わいが増す、深く心に染みる物語でした。絶望の淵に立たされたとき、人はどう生きるのか。その問いに対する一つの答えを、ヒルズタウンの住民たちの姿を通して見せてくれたように思います。もし、まだ読んだことがない方がいらっしゃれば、ぜひ手に取ってみてほしい一冊です。きっと、あなたの心にも温かい何かが残るはずですから。
まとめ
伊坂幸太郎さんの小説「終末のフール」は、小惑星衝突による地球滅亡を3年後に控えた世界を舞台に、仙台の団地「ヒルズタウン」に住む人々の日常と心の機微を描いた、8編からなる連作短編集です。この記事では、各短編の物語の核心に触れつつ、その魅力について詳しく語ってきました。
家族の再生、出産という選択、復讐と赦し、ささやかな目標、変わらない信念、人生の終わり方、疑似家族の絆、そして未来への希望といった多様なテーマが、ヒルズタウンの住民たちのドラマを通して、時に切なく、時に温かく描かれています。絶望的な状況下でありながらも、人々が日々の暮らしを大切にし、人と繋がり、それぞれの「やるべきこと」を見つけて生きていく姿は、私たちに静かな感動と勇気を与えてくれます。
物語はそれぞれ独立しているようでいて、登場人物や出来事が緩やかにリンクし、作品全体として一つの大きな世界観を構築しています。伊坂さんならではの軽妙な会話、巧みな伏線、そして魅力的な登場人物たちが、重いテーマを扱いながらも読後感を温かいものにしています。「終末のフール」は、人間の強さ、弱さ、そして日常の尊さを改めて感じさせてくれる、深く心に残る一冊と言えるでしょう。