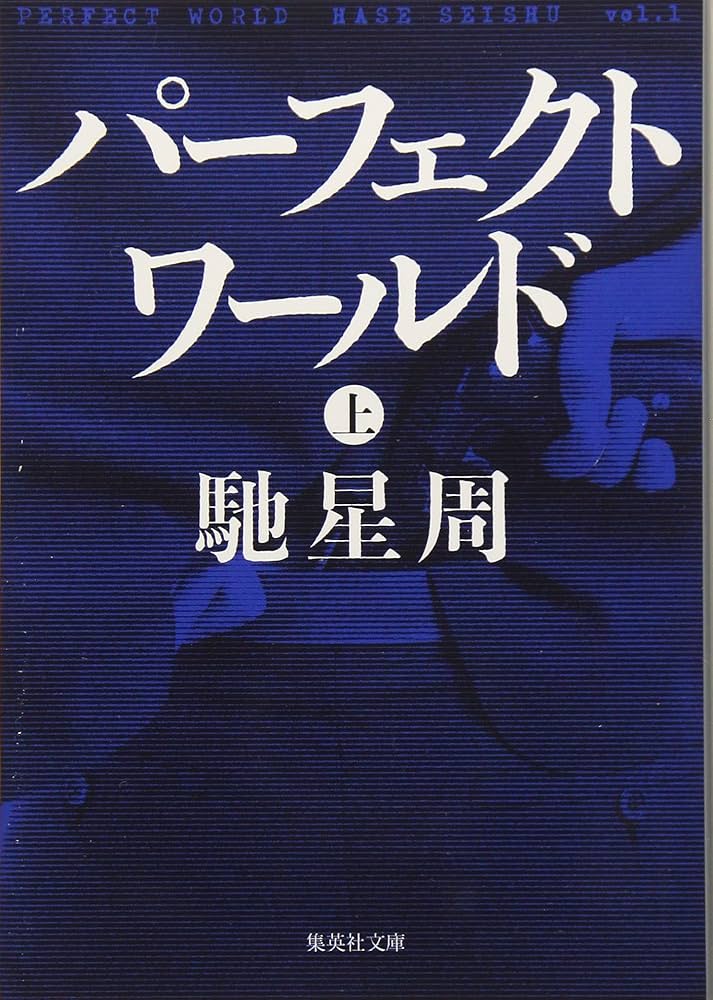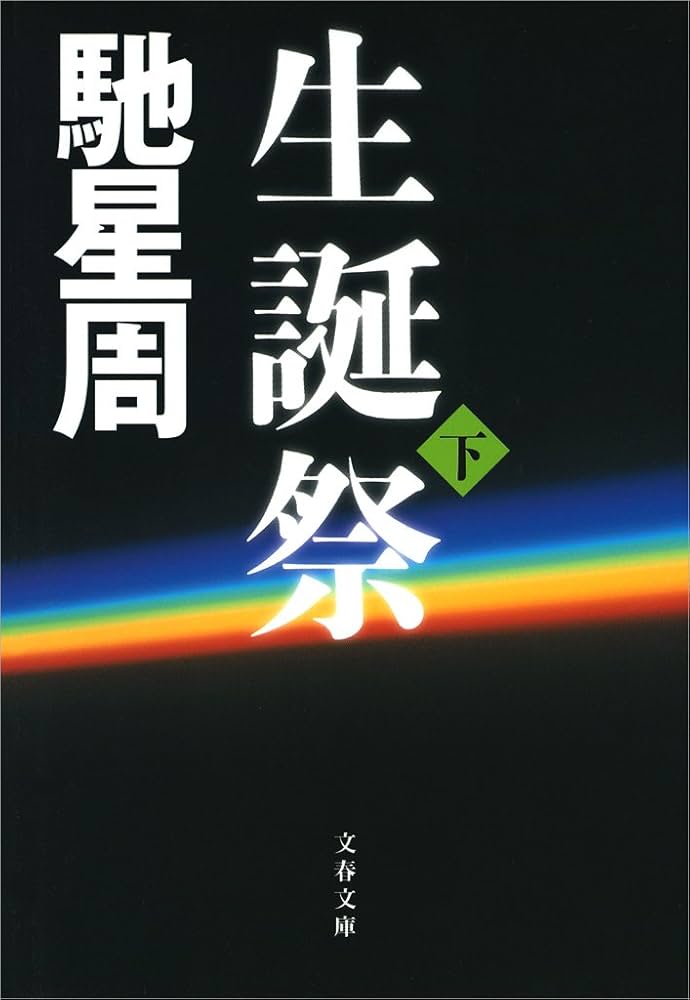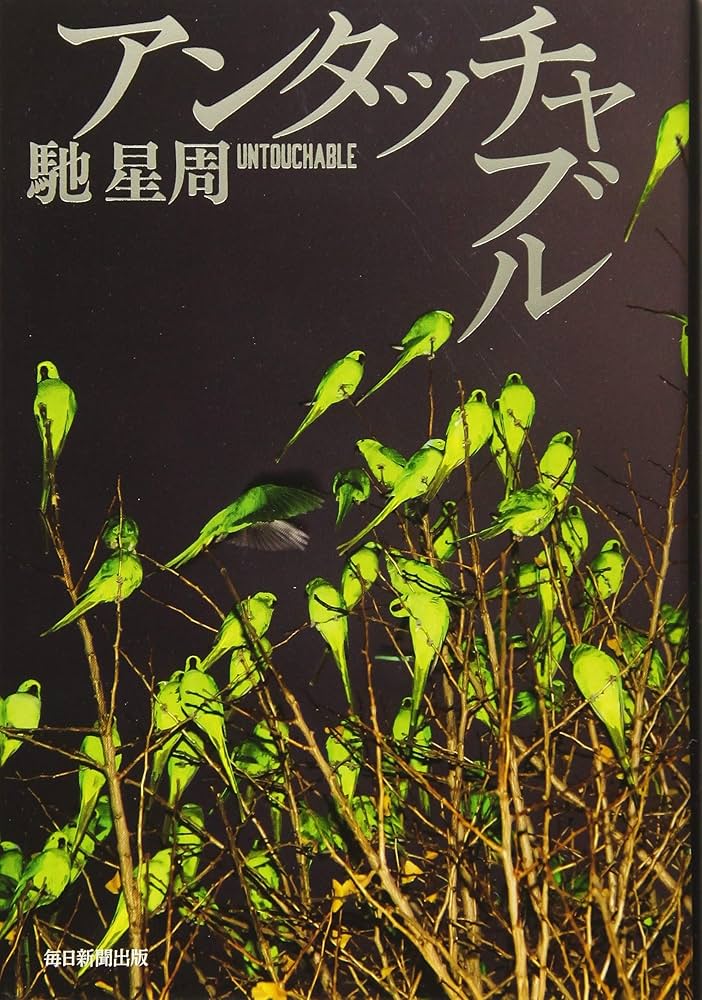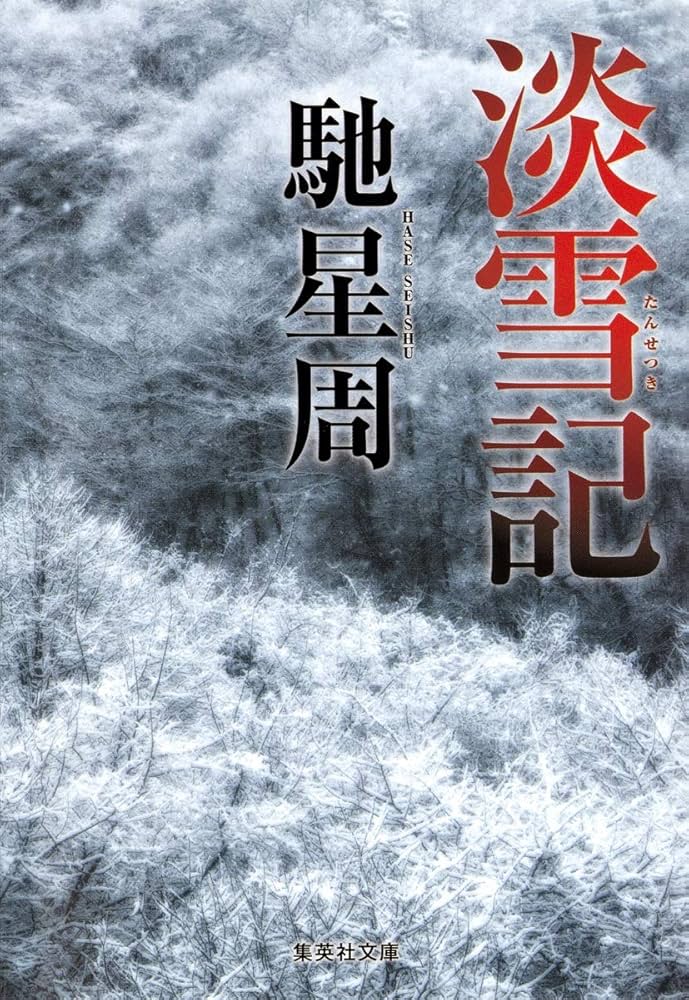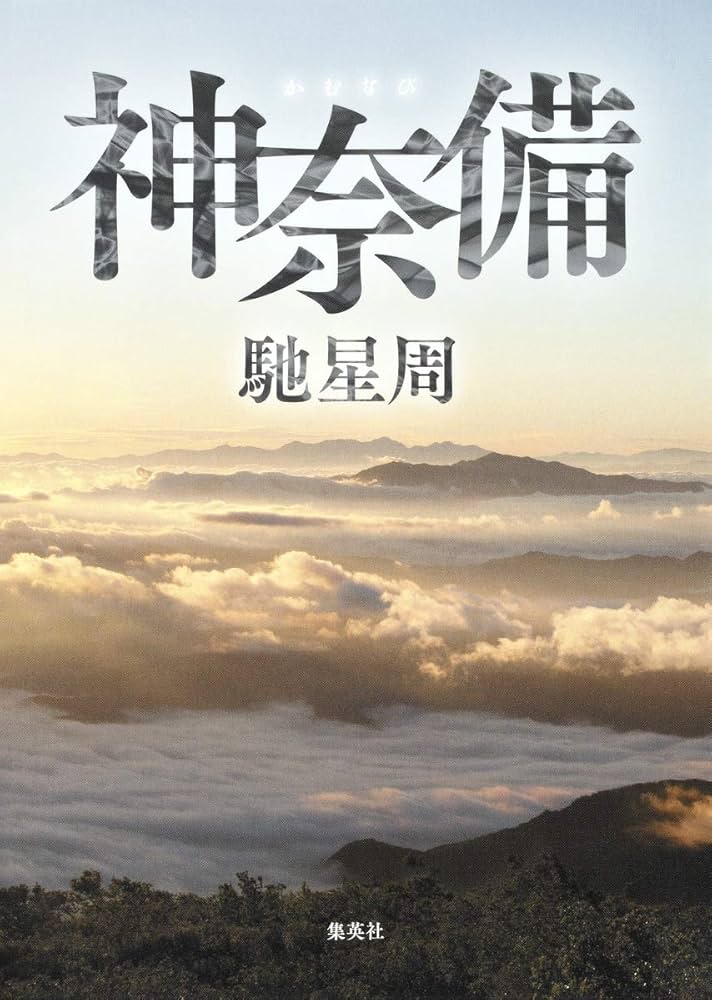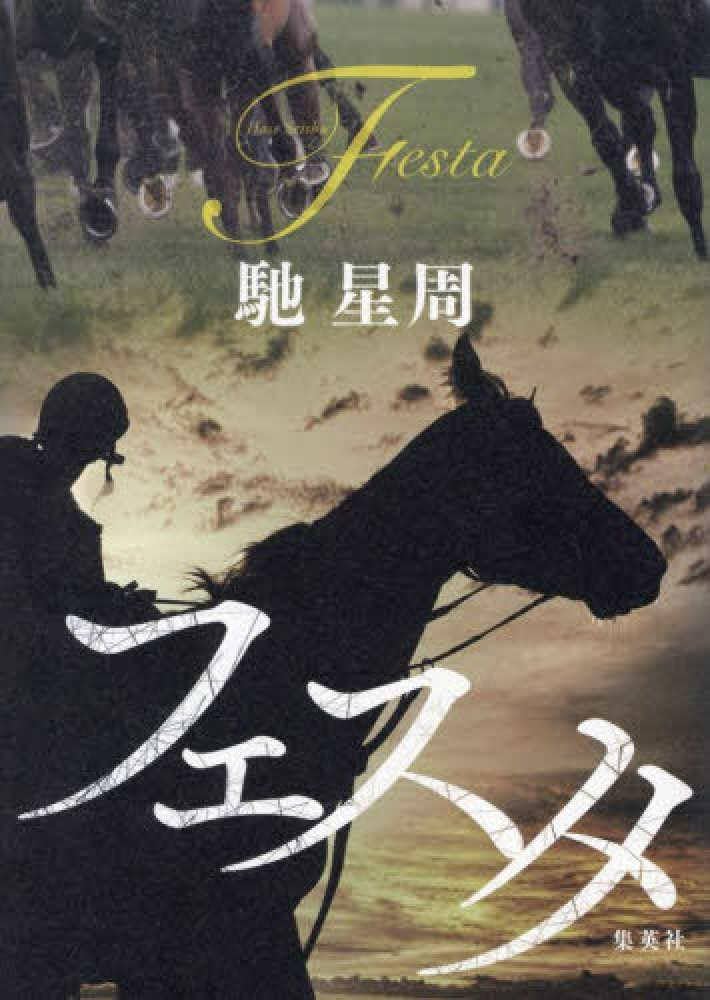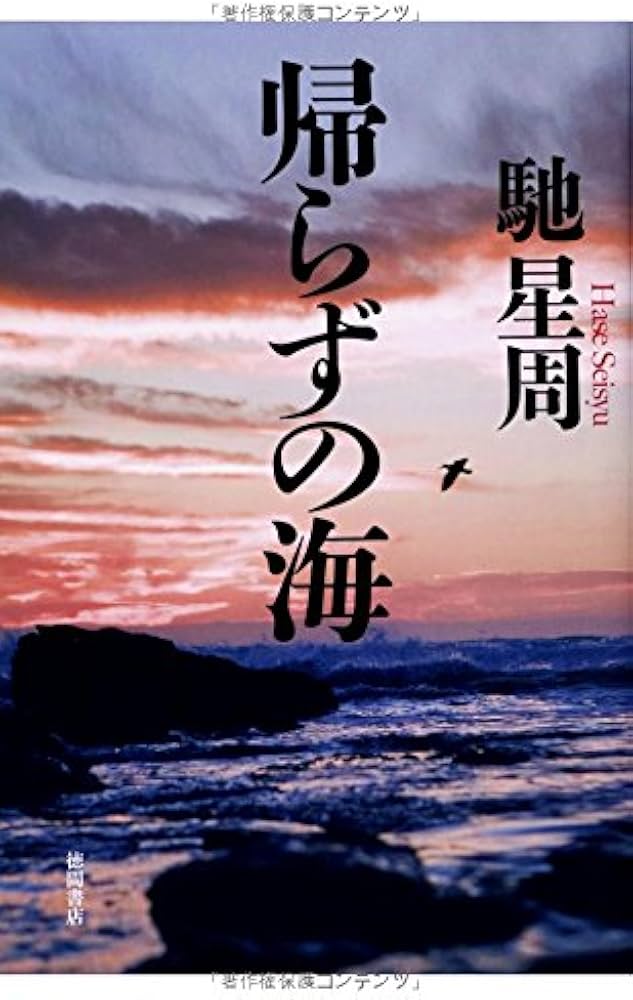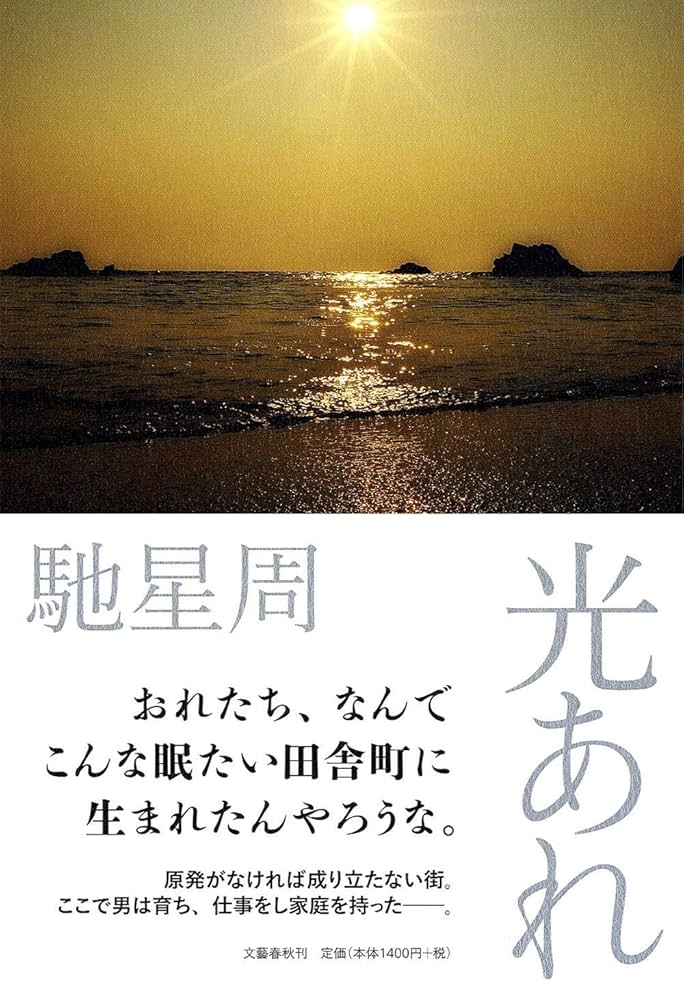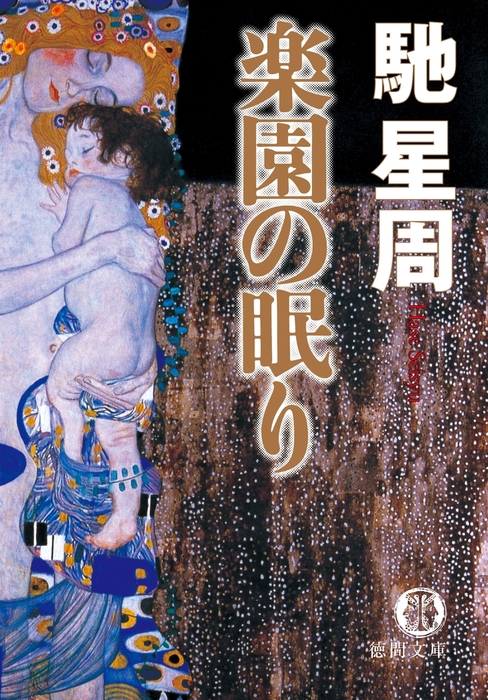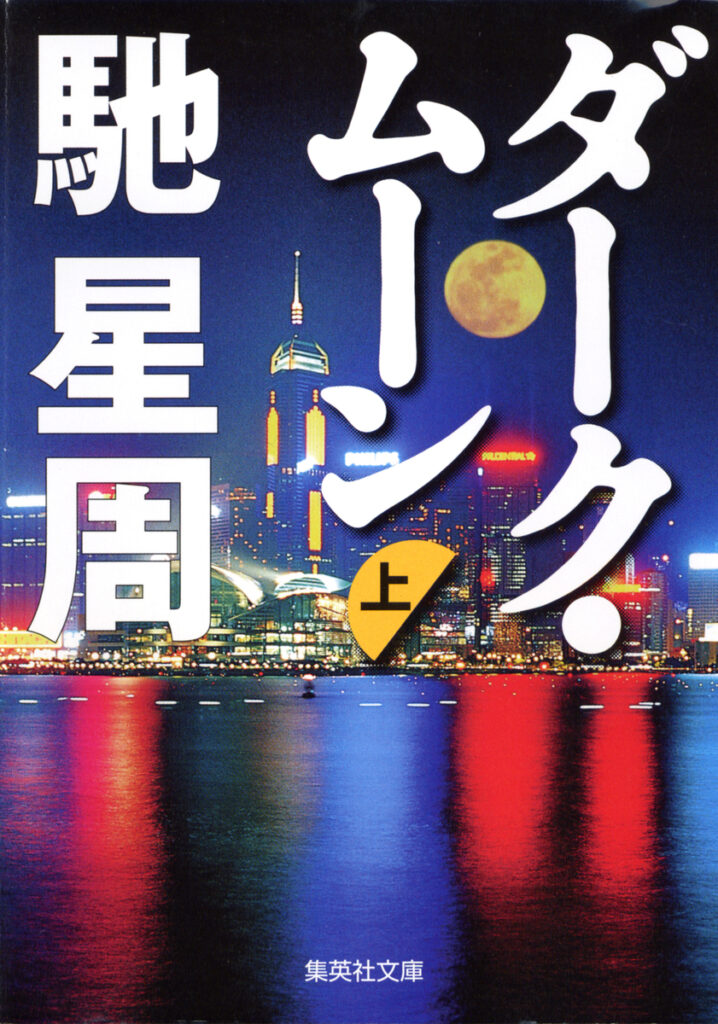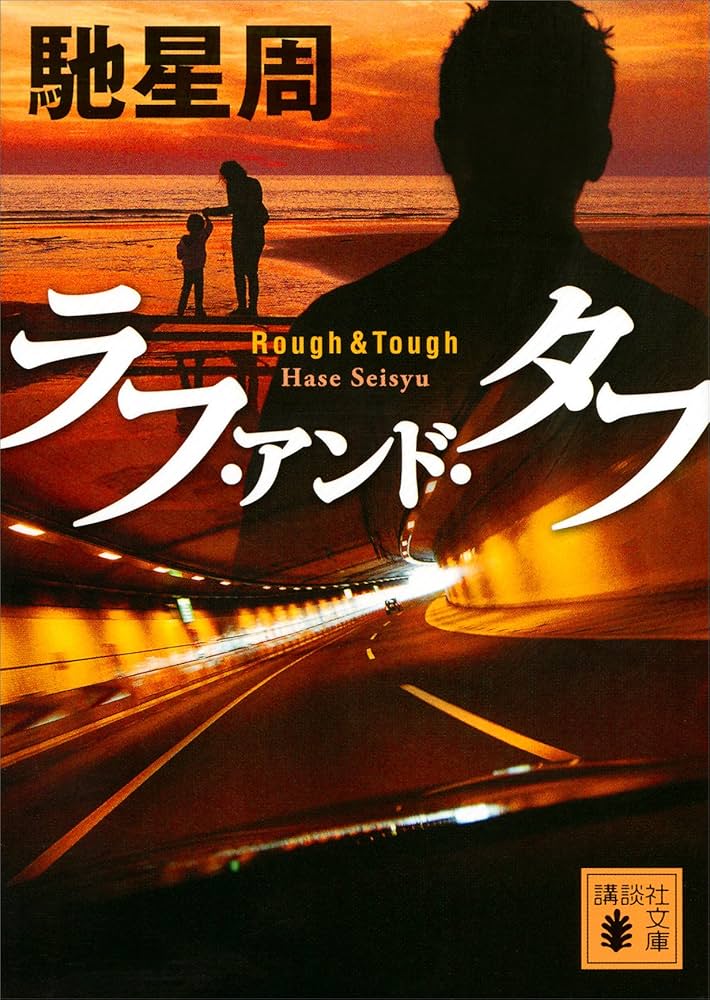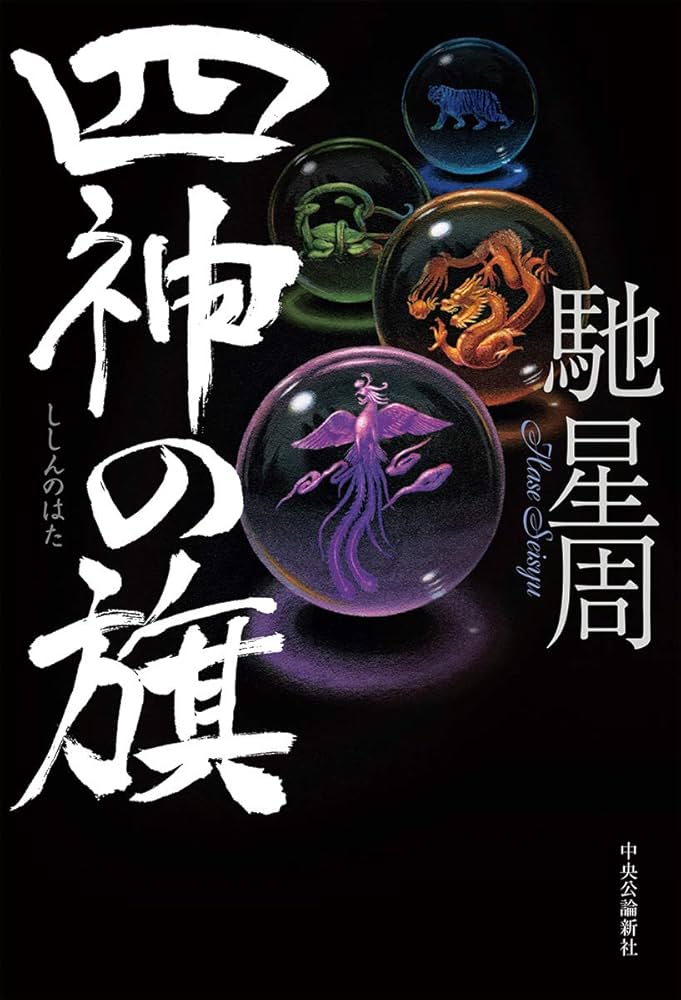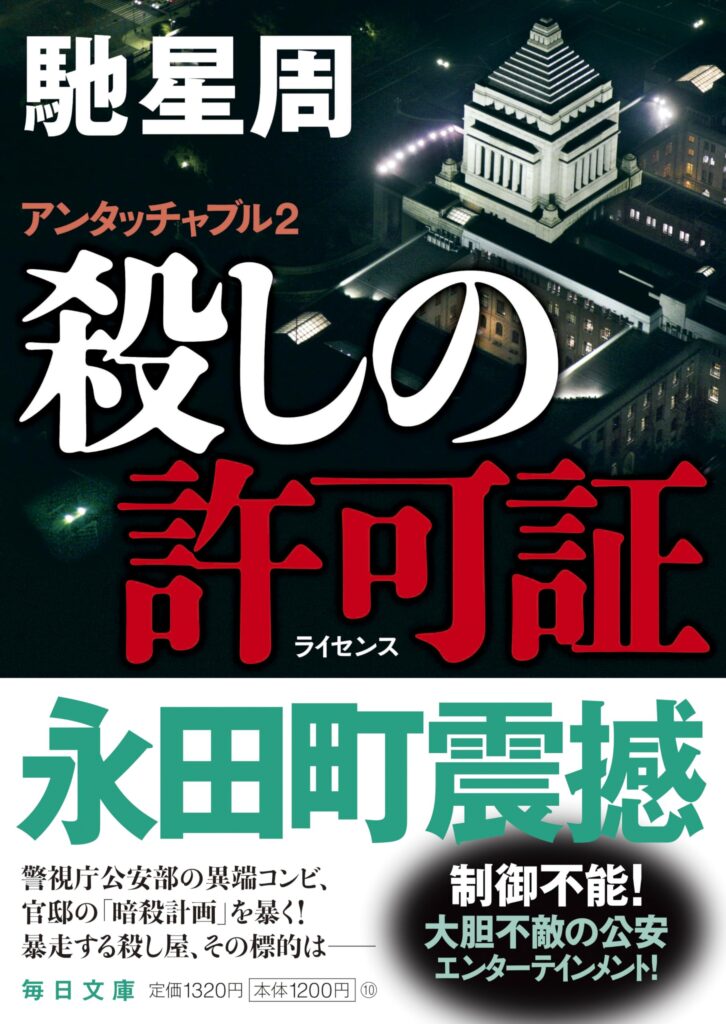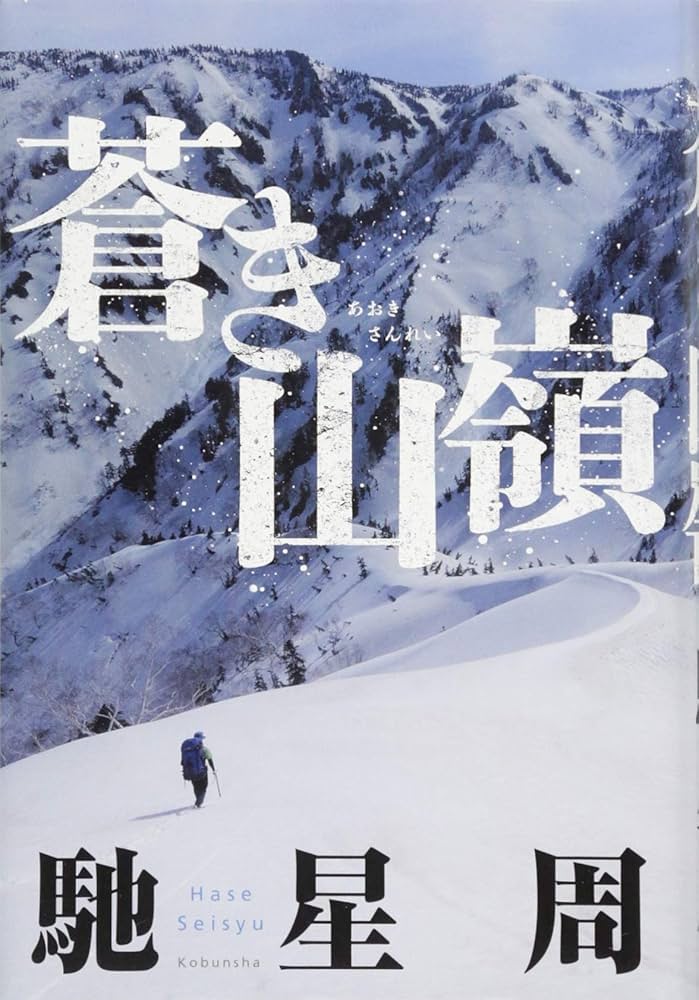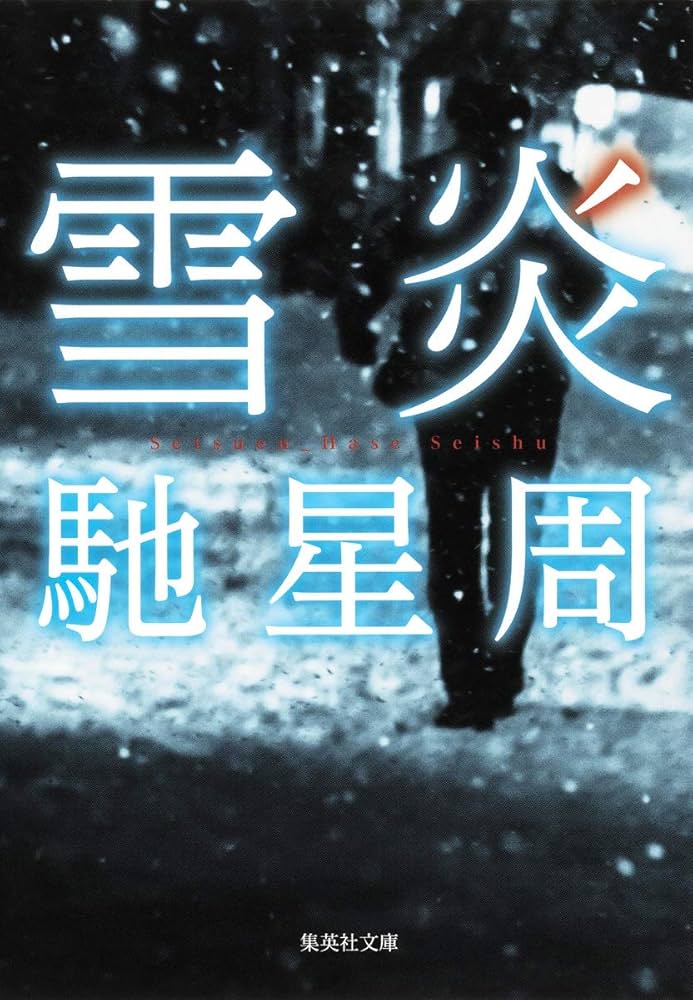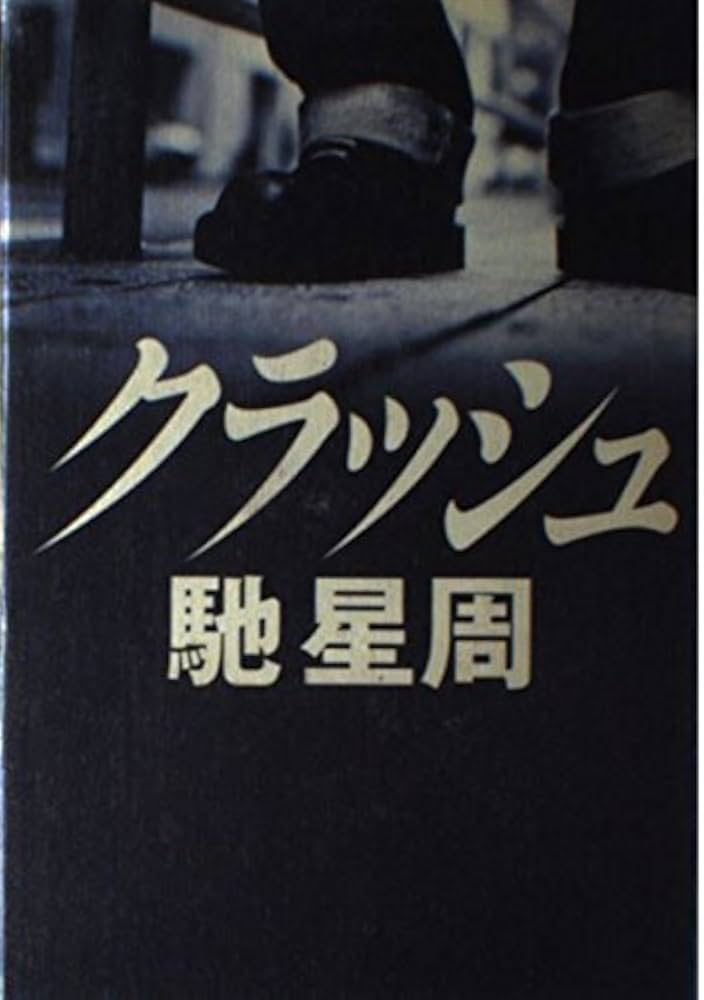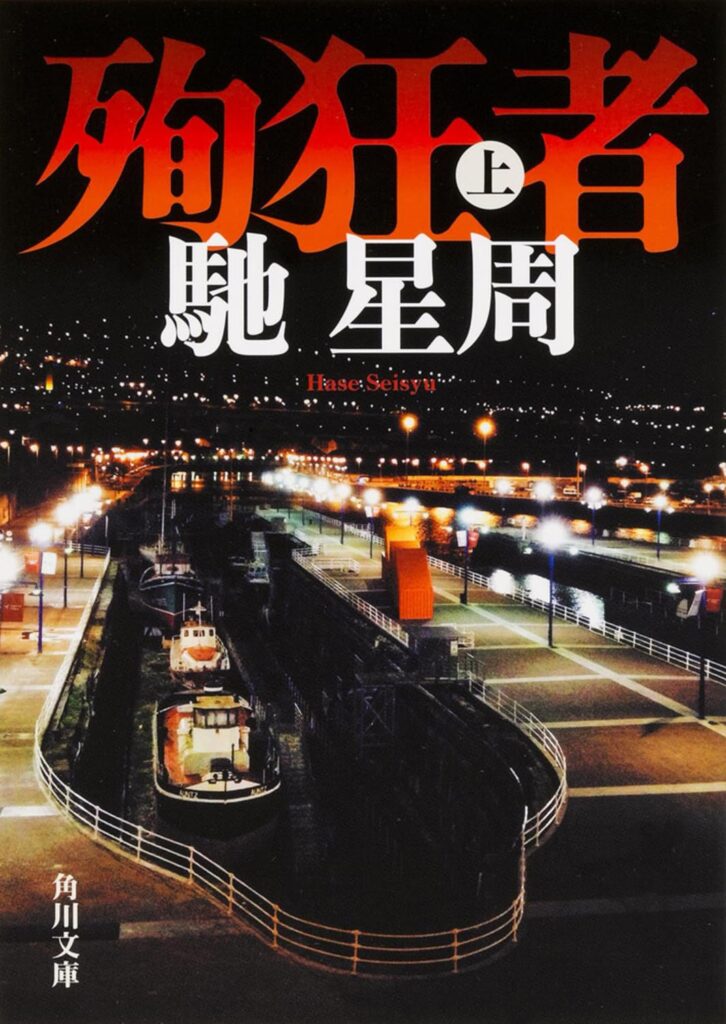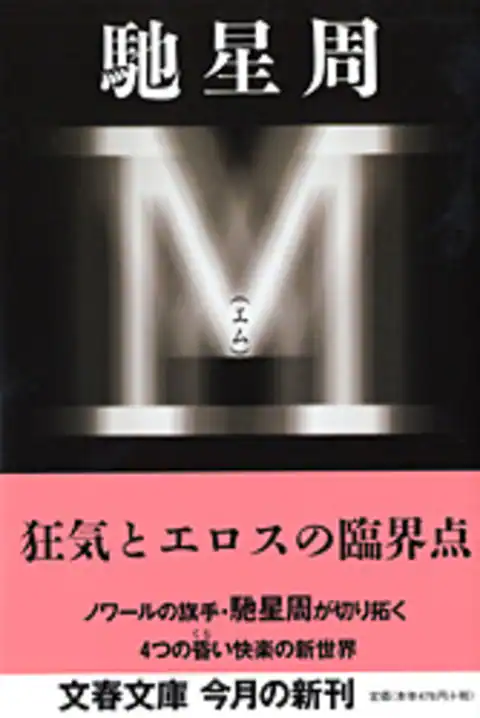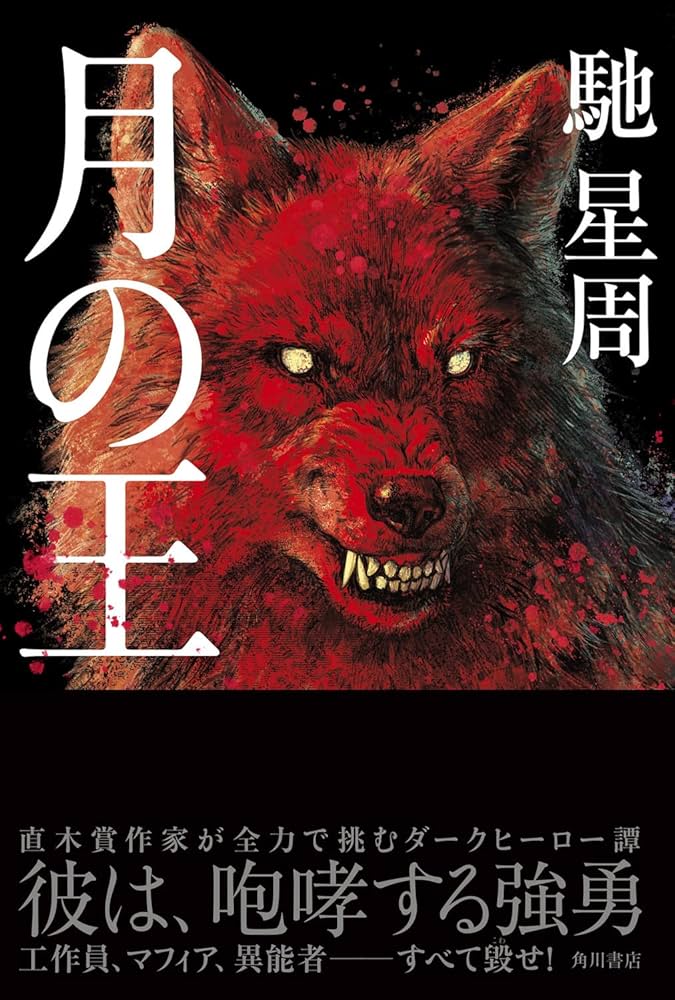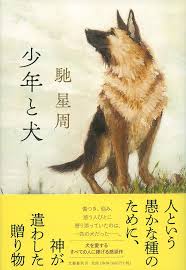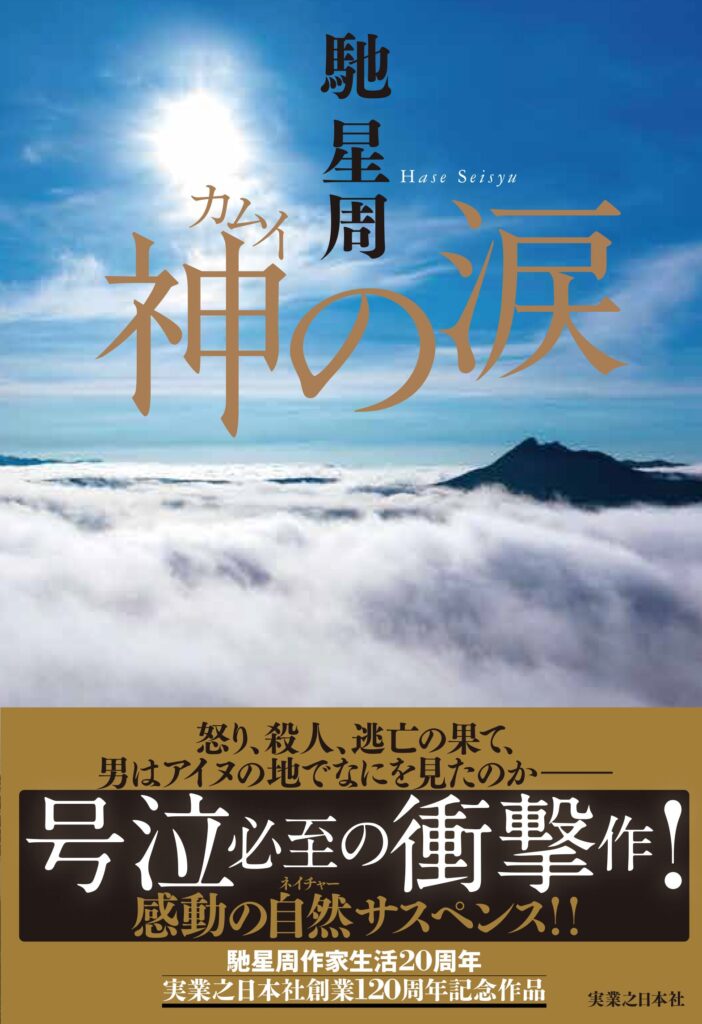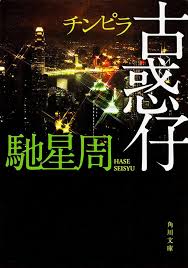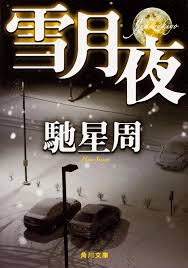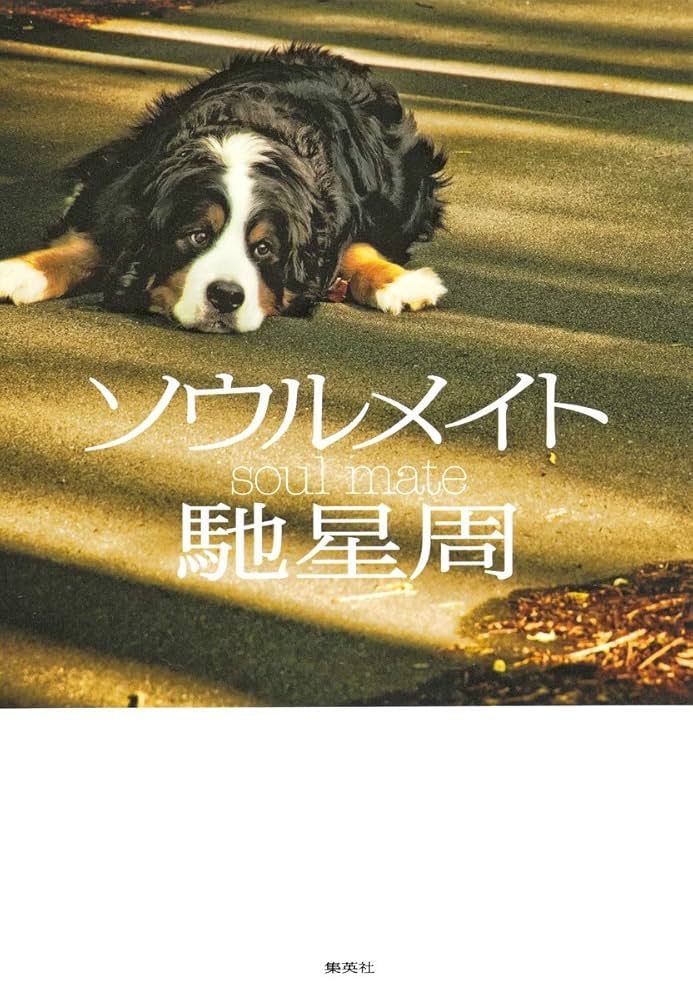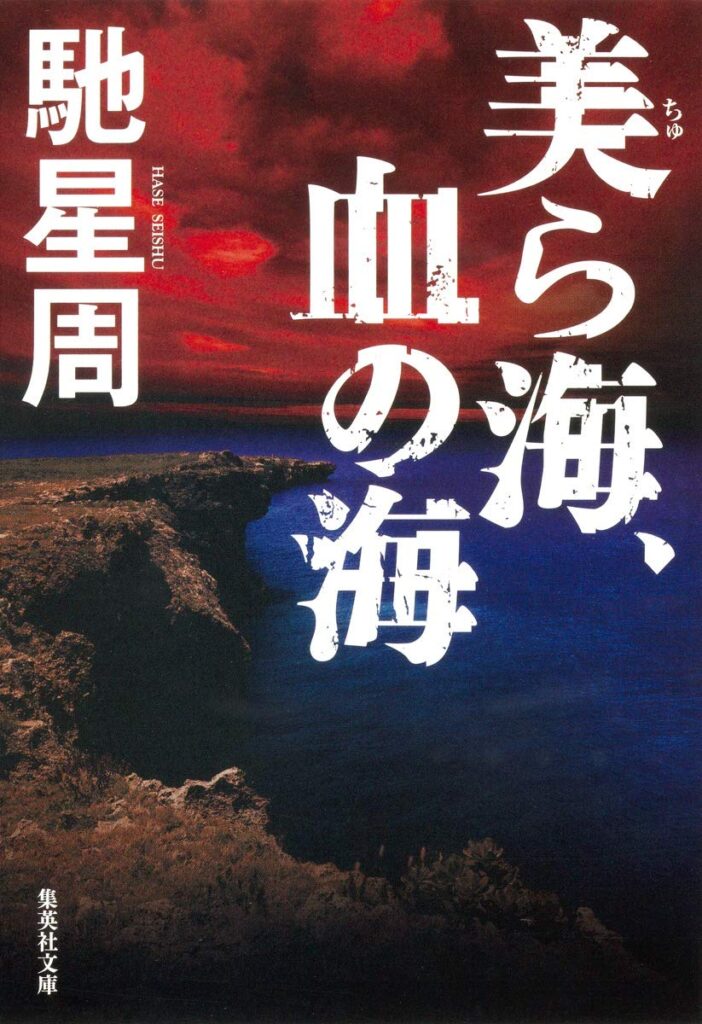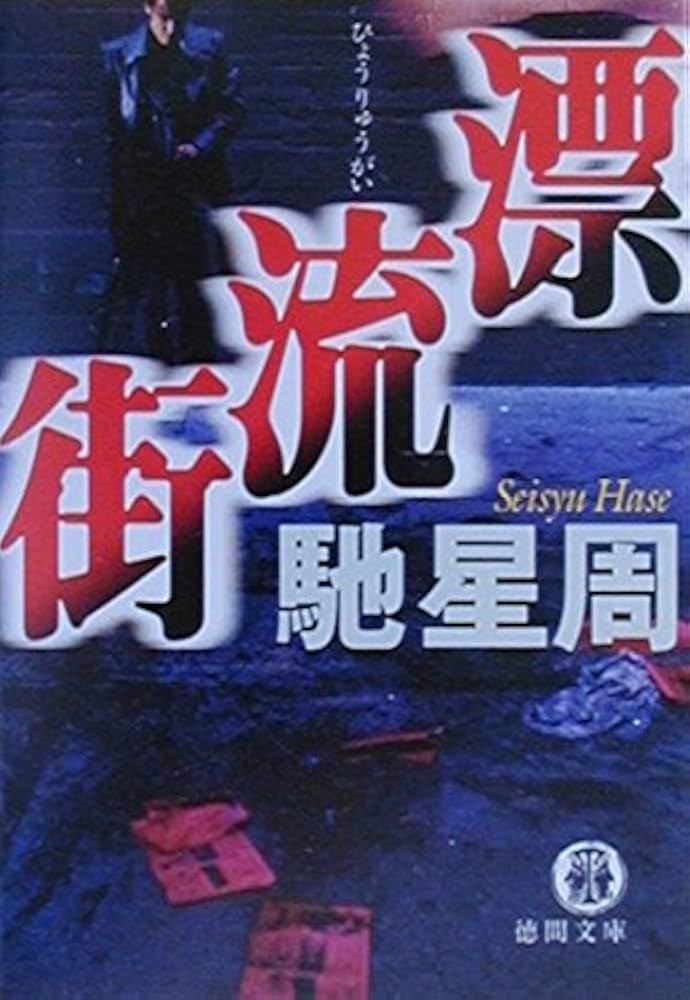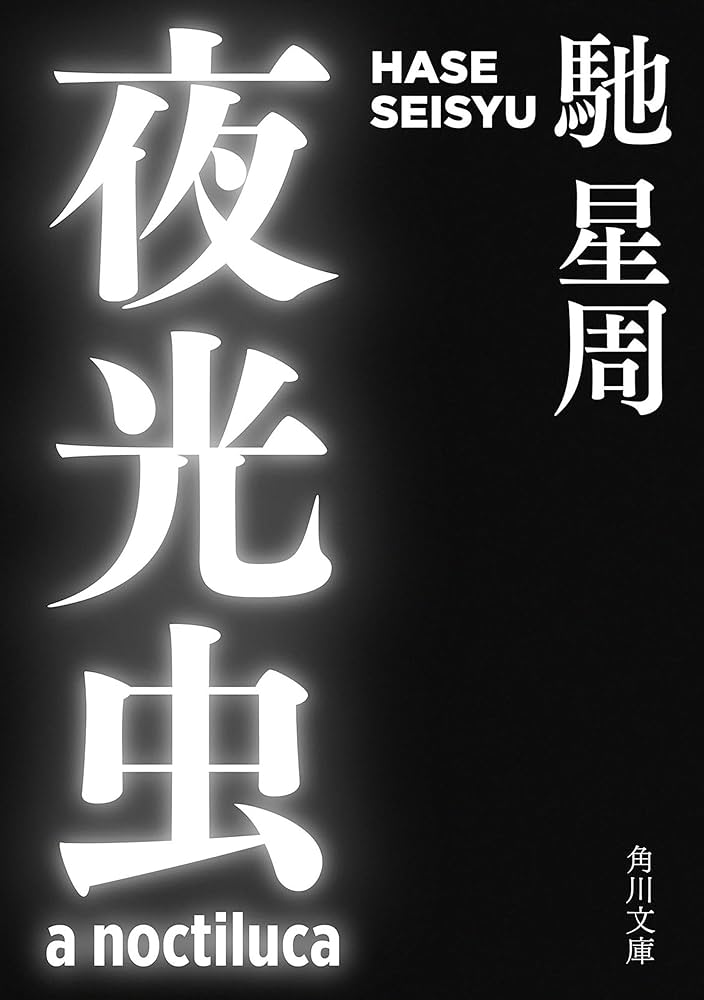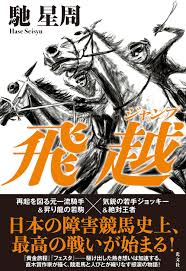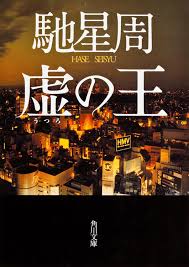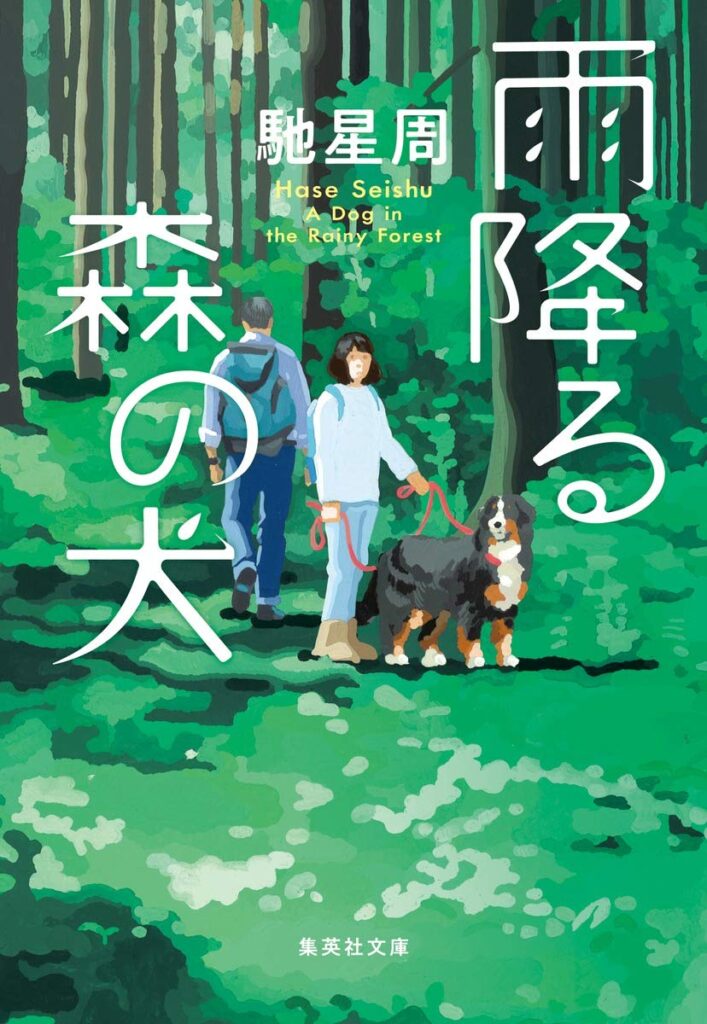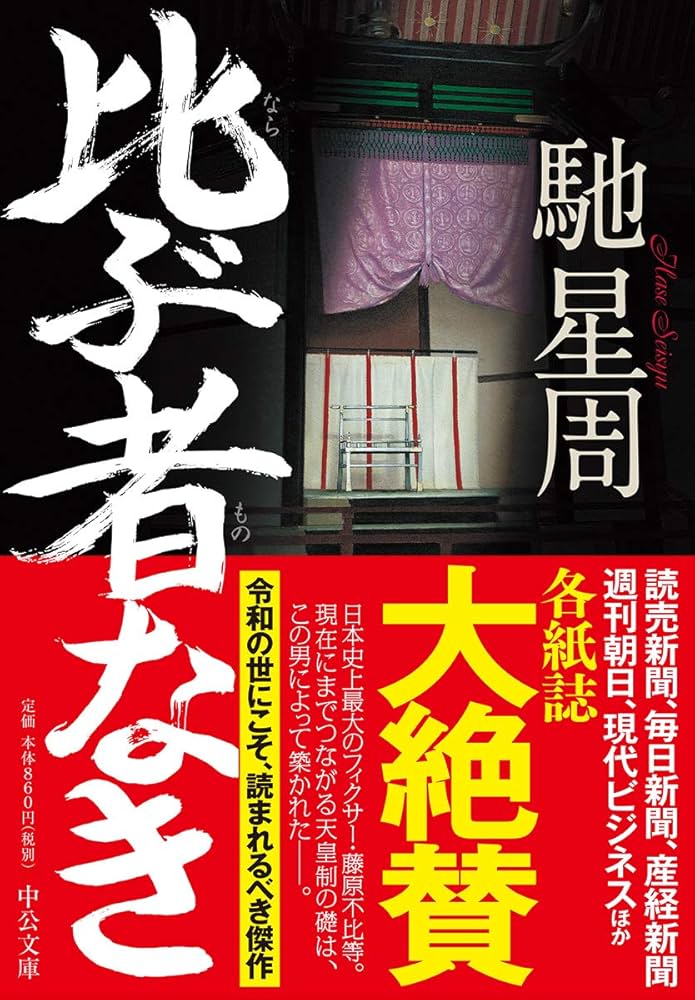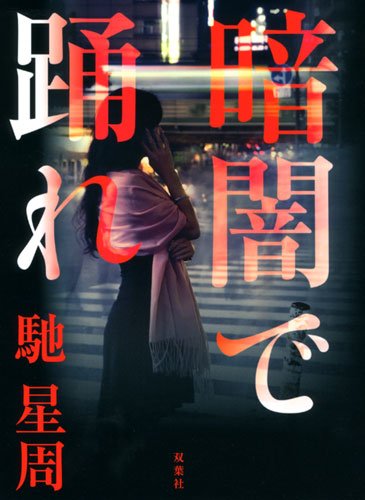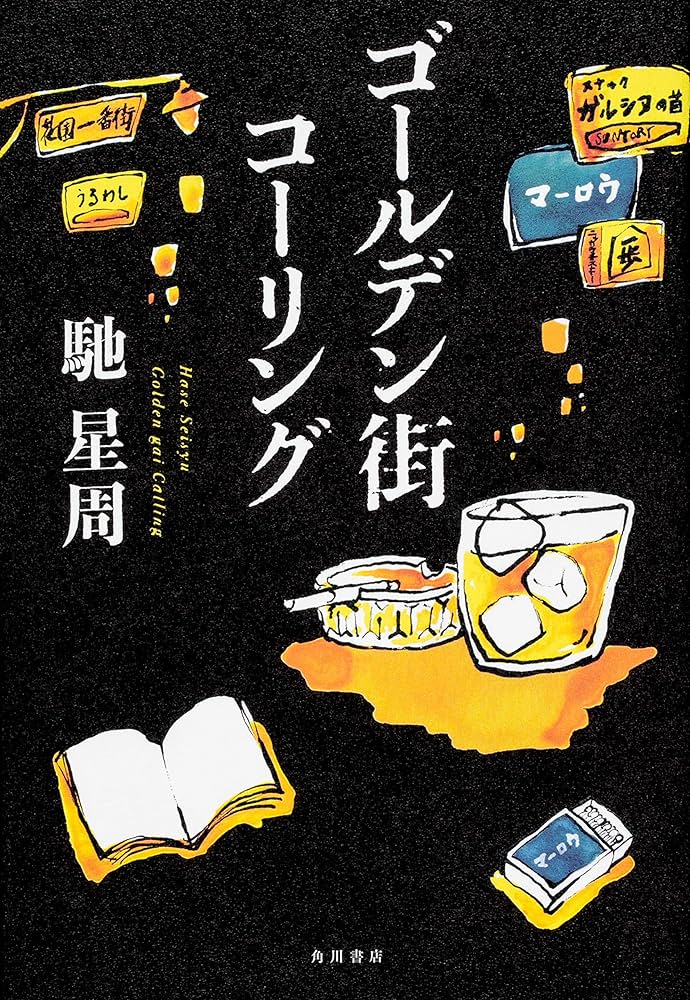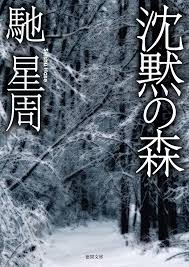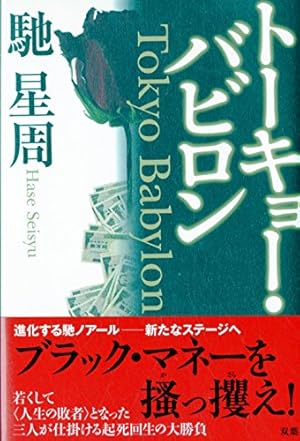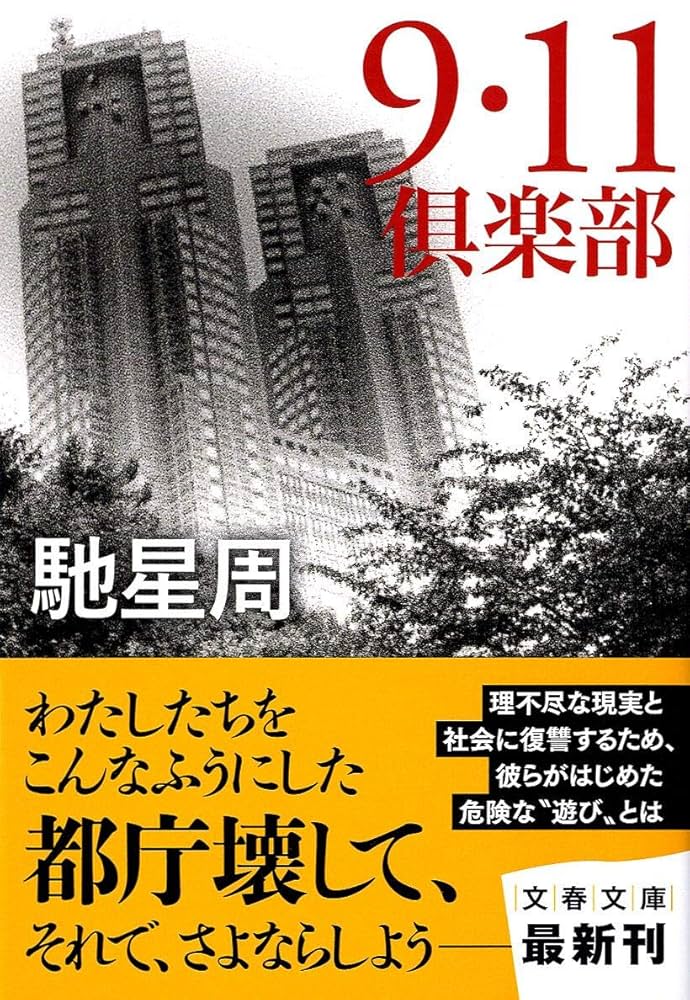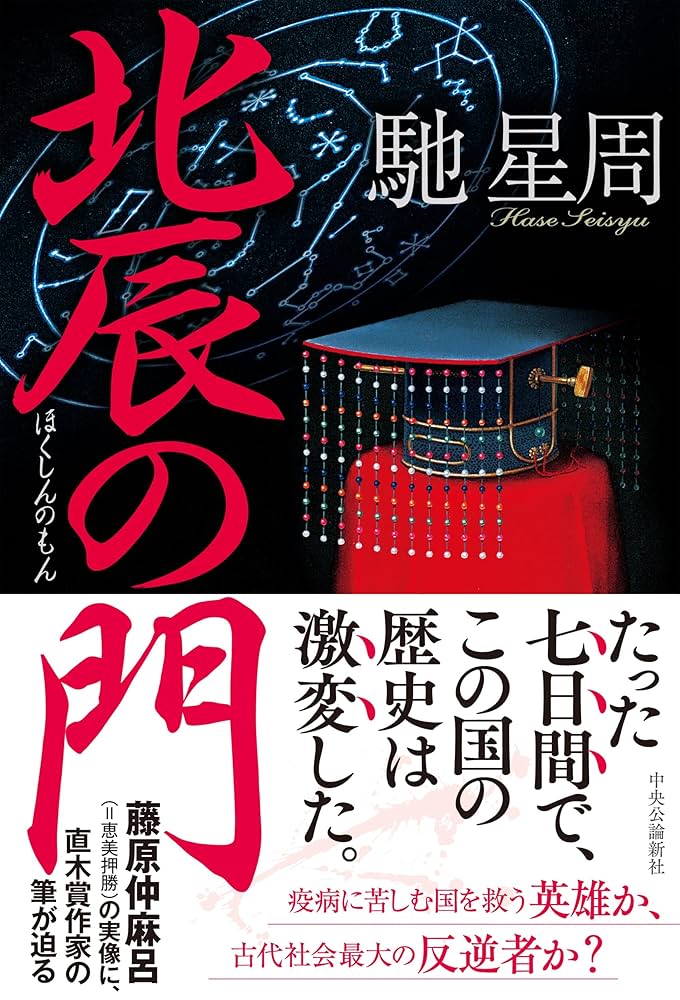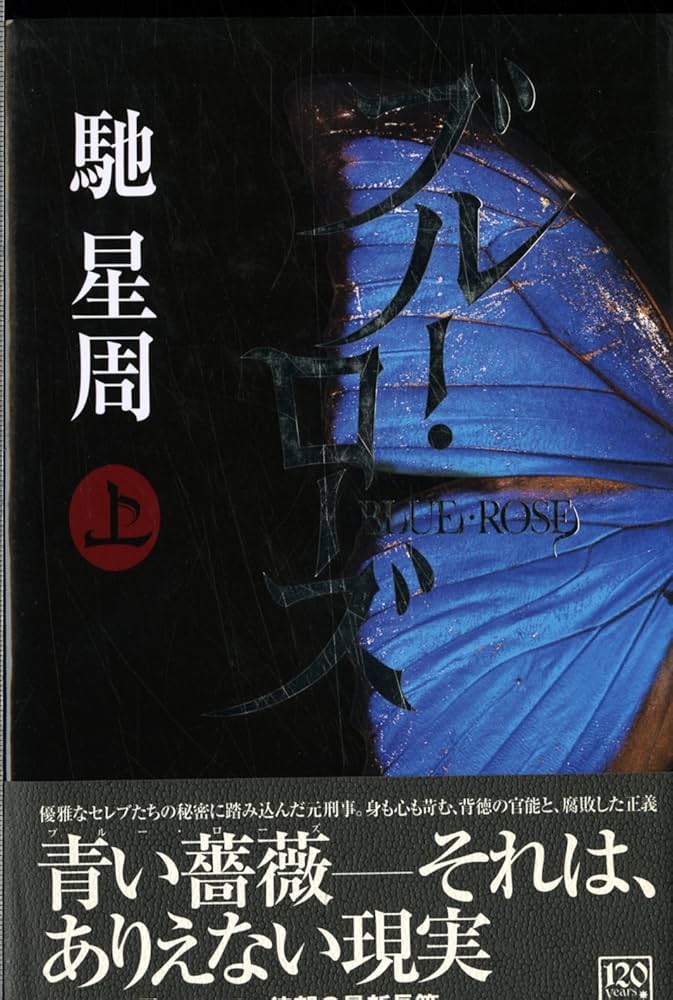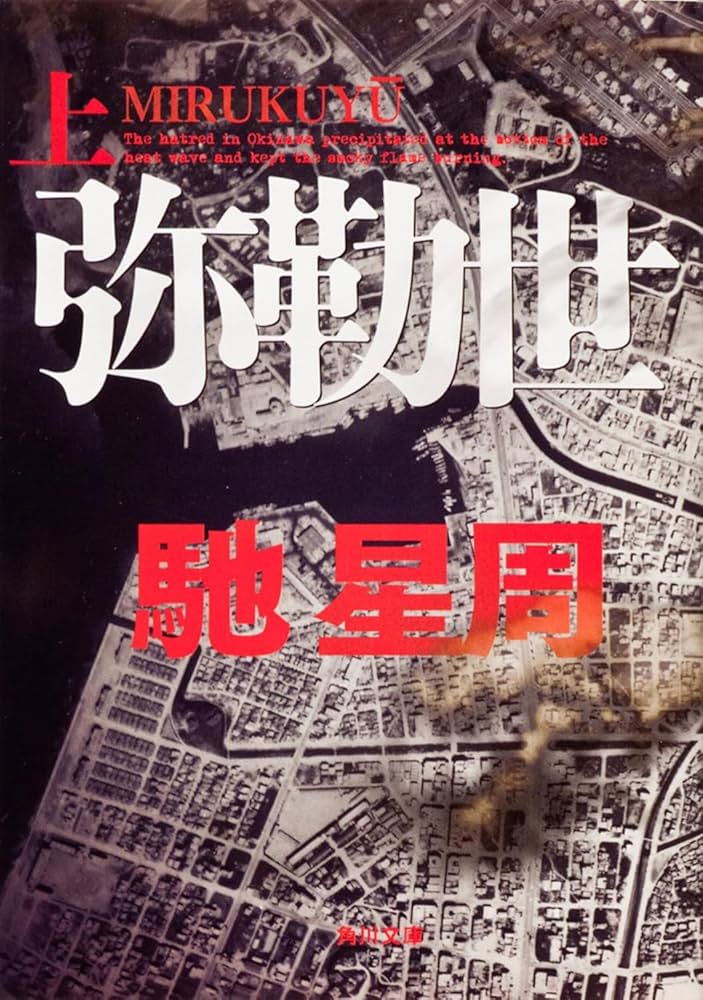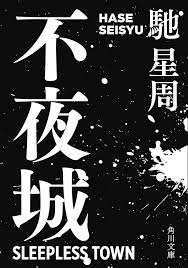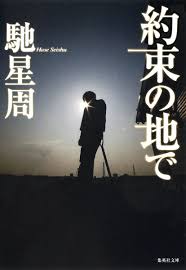 小説「約束の地で」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「約束の地で」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
この作品は、作家・馳星周さんが自身の故郷である北海道を舞台に描いた、心をえぐるような連作短編集です。2007年に発表され、直木賞の候補にもなった本作は、都会の喧騒を描いてきた馳さんの新たな境地を感じさせます。
この記事を手に取ってくださった方の中には、同じく馳さんの作品である『少年と犬』の物語を思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、ここでご紹介する『約束の地で』は、それとは全く異なる、5つの救いのない物語が連なる作品です。その点を最初にお伝えさせてください。
「約束の地」という題名には、実は強烈な皮肉が込められています。私たちはその言葉から希望や理想郷を思い浮かべますが、この物語で描かれるのは、むしろその対極にある世界。登場人物たちは、それぞれの「約束の地」を目指してもがきますが、その先には厳しい現実が待ち受けています。
この記事では、そんな『約束の地で』の物語の概要から、各話の結末にまで踏み込んだ詳しい物語の紹介、そして心揺さぶられた私の想いを綴っていきます。この物語が持つ、冷たくも切実な魅力に、少しでも触れていただければ幸いです。
「約束の地で」のあらすじ
物語は、北海道の日高地方、浦河町から始まります。6年ぶりに故郷へ戻った堀口誠。彼の目的は、山で炭焼きをして暮らす父が隠し持っていると噂される大金でした。人生をやり直すためのお金、それが彼の求める「約束の地」。しかし、父との間には長年の深い確執があり、その道のりは決して平坦ではありませんでした。
舞台は富川へ移り、次の主人公は田中美恵子という女性です。彼女は認知症の母親の介護に追われる日々を送っていました。恋人も去り、社会から孤立していく中で、彼女の精神は少しずつ追い詰められていきます。母親を施設に入れるというささやかな希望を胸に抱きますが、現実はあまりにも過酷です。
三番目の物語の舞台は苫小牧。いじめが原因で不登校になった15歳の少年が主人公です。彼の唯一の心の支えは愛犬のレオ。彼は自分とレオだけの聖域「世界の終わり」を創り出すことに没頭します。しかし、その聖域にも、やがて残酷な現実が忍び寄ります。
物語はさらに、定職に就かない若者・原田雅史の視点へと移ります。彼は心に傷を抱える同僚の由希を連れ、あてのない旅に出ます。降りしきる雪の中、函館を目指す二人。しかし、その逃避行は、決して希望に満ちたものではなく、過去から逃れるための必死の疾走に過ぎませんでした。彼らがたどり着く場所とは一体どこなのでしょうか。
「約束の地で」の長文感想(ネタバレあり)
この『約束の地で』という作品は、単に舞台が北海道というだけではありません。作者の故郷でもあるその土地は、物語の中で重要な役割を果たしています。私たちが抱く雄大で美しい北海道のイメージはここにはなく、むしろ経済的に衰退し、冬の厳しい寒さが人々の心象風景と重なるような、閉塞感に満ちた場所として描かれているのです。
この物語は、登場人物たちの絶望を映し出し、さらに増幅させる鏡として、北海道という土地を見事に描き出しています。それは日本の地方が抱える現実を背景にした、独特の暗い情感に満ちた文学の世界と言えるでしょう。
絶望が巡る、巧みな物語の仕組み
本作は、5つの短編が連なる形式ですが、その構成が非常に巧みです。物語はロンド形式、つまり輪舞のように、登場人物たちが別の物語に顔を出し、鎖のように繋がっていきます。しかし、その繋がりは希望や救いを生むものではなく、不幸が伝播し、共有されるための鎖として機能しているのが、この物語の最も恐ろしい点なのです。
例えば、最初の物語の主人公・堀口誠は、最後の物語に姿を現します。第三の物語で少年を追い詰める加害者は、第四の物語の主人公・原田雅史です。このように物語が巡り、円環構造を描くことで、読後、私たちは再び最初の物語の地点に引き戻されるような感覚に陥ります。
これは、物語にありがちなカタルシスや明確な結末を、作者が意図的に拒否していることの表れです。登場人物たちはどこかへ向かっているのではなく、ただ、その逃れられない絶望のサイクルの中に「いる」だけ。この構造自体が、どうすることもできない閉塞感というテーマを、見事に形にしているのです。
第一話『ちりちりと……』:金の幻影と親子の確執
最初の物語は、堀口誠が浦河町の実家へ戻る場面から始まります。彼の目的は、炭焼き職人の父が持つという大金。その金さえ手に入れば、失敗した人生をやり直せる。彼にとって、その金はまさに「約束の地」への切符でした。
しかし、物語が進むにつれて明らかになるのは、父子の間の憎しみにも似た深い溝です。金の探求は、単なる物欲だけでなく、彼の切羽詰まった心の叫びでもありました。題名の「ちりちりと」という音は、彼の心を焦がす焦燥感と、希望がゆっくりと焼き尽くされていく痛みそのもののように感じられます。
結末は、あまりにも破滅的です。結局、金などどこにも存在せず、父との対立は最悪の結末を迎えます。怒りに駆られた誠は、父に手をかけてしまうのです。噂に踊らされ、最後の希望を打ち砕かれた彼は、以前よりもさらに深い闇の中へと突き落とされます。この物語は、本作全体の救いのないトーンを決定づける、強烈な幕開けとなっています。
第二話『みゃあ、みゃあ、みゃあ』:介護の果てにある崩壊
舞台は富川へ。主人公の田中美恵子は、認知症の母親の介護に心身ともに疲れ果てています。終わりの見えない日々、母親からの暴言、社会からの孤立。彼女の精神は、静かに、しかし確実に蝕まれていきました。
母親が飼っている猫たちの鳴き声「みゃあ、みゃあ、みゃあ」が、彼女が狂気へと堕ちていく不気味な伴奏のように響き渡ります。母親を施設に入れるという「約束の地」は、あまりにも遠い夢。積み重なる疲労と憤りは、ついに彼女の心の限界を超えさせてしまいます。
この物語の恐ろしさは、劇的な事件ではなく、静かな絶望への降伏にあります。母親との壮絶な口論の末、生まれたばかりの子猫たちを、彼女は新たな重荷としか認識できなくなります。そして、橋の上から子猫たちを川へ投げ捨ててしまうのです。この行為は、彼女の中に残っていた最後の優しさや希望が、完全に死んでしまったことの象徴でした。
第三話『世界の終わり』:少年が築いた脆い聖域
苫小牧を舞台にした三番目の物語は、「ぼく」という15歳の少年の視点で語られます。知的な遅れがあり、学校ではいじめに遭う彼にとって、唯一の安らぎは愛犬のレオでした。彼の「約束」は、誰にも邪魔されない自分だけの世界を創ること。彼はスクーターに乗り、墓地などから骨を盗み出し、秘密の場所に撒くという儀式を始めます。そこは彼とレオだけの聖域、「世界の終わり」でした。
この物語の描写は、冒涜的な行為の中に、不思議なほどの美しさを見出しています。少年が骨の粉を撒く光景は、まるで雪が舞うかのように幻想的に描かれます。それは、彼が現実の世界からどれほど疎外され、死の気配の中にしか安らぎを見出せなかったかという、彼の深い孤独を物語っているかのようです。
しかし、その聖域は無残にも破壊されます。いじめの主犯格であり、次の物語の主人公でもある原田雅史が、その場所を見つけ、嘲笑うのです。唯一の安息の地を奪われ、さらに愛犬のレオまで失った少年の世界は完全に崩壊します。物語は、彼が自らの「世界のおわり」を完結させるべく、レオの後を追うことを示唆して終わります。その絶望の深さに、言葉を失います。
第四話『雪は降る』:行き止まりの逃避行
主人公は、前の話で少年の世界を破壊した原田雅史です。彼は、同じように希望のない日常を送る年上の女性・由希に惹かれ、彼女を連れて函館を目指すあてのない旅に出ます。
しかし、それは未来へ向かう旅ではありませんでした。語られることのない互いの過去から逃げるための、ただの逃避行です。降り続く雪は、彼らの前途を覆い隠す冷たい現実そのもののようで、何も清めてはくれません。由希が抱える心の傷、そして雅史の自分勝手で浅はかな動機が、二人の空虚な会話から透けて見えます。
当然ながら、この旅が新しい人生に繋がるはずもありません。お金が尽き、車が動かなくなった時、彼らの逃避行はあっけなく終わりを迎えます。隠されていた緊張と行き場のない絶望が爆発し、二人の関係も破綻します。彼らがたどり着いたのは、希望の地ではなく、物理的にも精神的にも完全な行き止まりでした。
第五話『青柳町こそかなしけれ』:巡り続ける暴力と絶望
最終話の舞台は函館。主人公の保は、夫からの壮絶な暴力に苦しむ日々を送っていました。彼女は、亡くなった愛犬の遺骨を肌身離さず持ち歩くことで、かろうじて心の均衡を保っています。
この函館で、保は前の物語に登場した由希と出会います。由希もまた、暴力的な関係から逃れられずにいました。同じ痛みを抱える二人の間には、暗い共感が生まれます。追い詰められた保は、ついに由希に夫の殺害を依頼するまでに至るのです。
そして、この物語は、この連作短編集全体の構造を決定づける、衝撃的な事実を読者に突きつけます。思い詰めた保が立ち寄った焼肉屋の店主、彼女が「マコっちゃん」と呼ぶその男こそ、第一話の主人公・堀口誠だったのです。彼は浦河での破滅の後、生き延びてはいましたが、決して救われたわけではありませんでした。ただ、他人の悲劇がすぐそばで起きていることも知らず、静かな絶望の中で息をしているだけ。この結末は、物語全体を終わりのない円環として繋ぎ合わせ、私たち読者を再び冒頭の絶望へと引き戻すのです。
救いのない世界に響く魂の叫び
『約束の地で』に登場する人々は、決して極悪人ではありません。介護に疲れた女性、いじめられる少年、先の見えない若者。どこにでもいるような普通の人々が、日常の重圧によって、いとも簡単に闇に転落していきます。その過程は、恐ろしいほどの現実味を帯びています。
家族や恋人といった人間関係は、彼らを救うどころか、より深く傷つける要因となります。ここには正義の味方も、問題を解決してくれる探偵も登場しません。ただ、被害者が加害者へと転じていく、救いのない連鎖があるだけです。
この物語が描き出す「約束の地」とは、結局のところ、彼らが生きるこの荒涼として逃れようのない現実そのものなのです。そこでは、苦しみが永遠に続くことだけが、唯一確かなことなのかもしれません。本作は、人間の心の暗部を、広大で冷たい故郷の大地を舞台に見事に描ききった、忘れがたい一冊です。その読後感は重く、決して楽しいものではありませんが、魂を揺さぶる力を持った傑作であることは間違いないでしょう。
まとめ
馳星周さんの小説『約束の地で』は、希望を求める人々が、いかにして絶望の淵に沈んでいくかを描いた、胸に突き刺さる連作短編集でした。5つの物語は独立しているようでいて、登場人物たちが交差し、まるで終わりのない円環のように繋がっています。
「約束の地」という題名が示す場所は、決して安らぎの地ではありません。それは、登場人物たちが逃れることのできない、閉塞感に満ちた現実そのものでした。物語を読み進めるうちに、その題名の持つ本当の意味が、ずしりと心に重くのしかかってきます。
各物語で描かれるのは、介護疲れ、いじめ、暴力、貧困といった、私たちのすぐそばにあるかもしれない問題です。だからこそ、登場人物たちの転落は他人事とは思えず、その絶望がリアルな痛みとして伝わってきました。読んでいる間、何度も心が苦しくなりました。
もしあなたがこの本を手に取るなら、相応の覚悟が必要かもしれません。しかし、人間の心の闇と、現代社会が抱える歪みをこれほどまでに深く、そして鮮烈に描いた作品は稀有です。読後、きっとあなたの心に長く残り続ける一冊となるはずです。