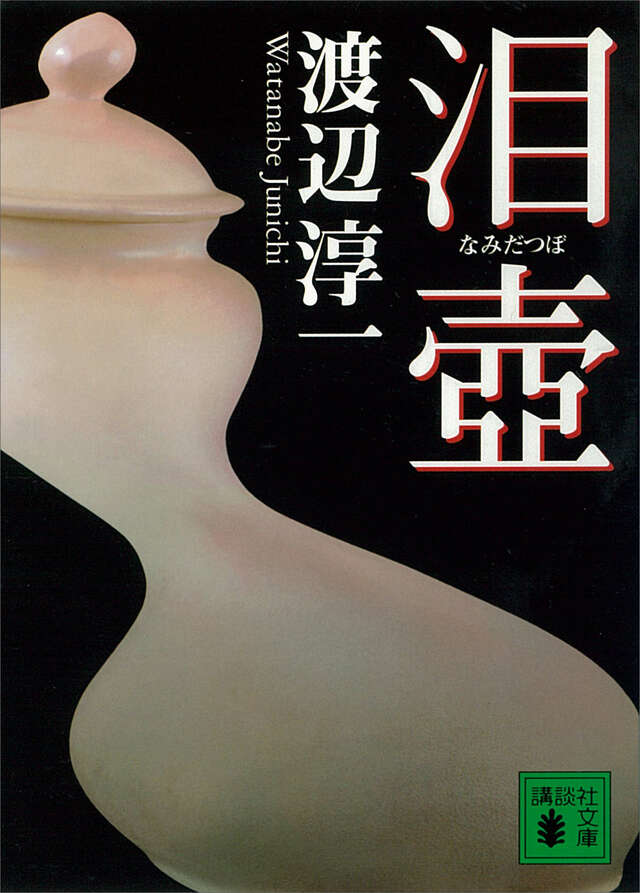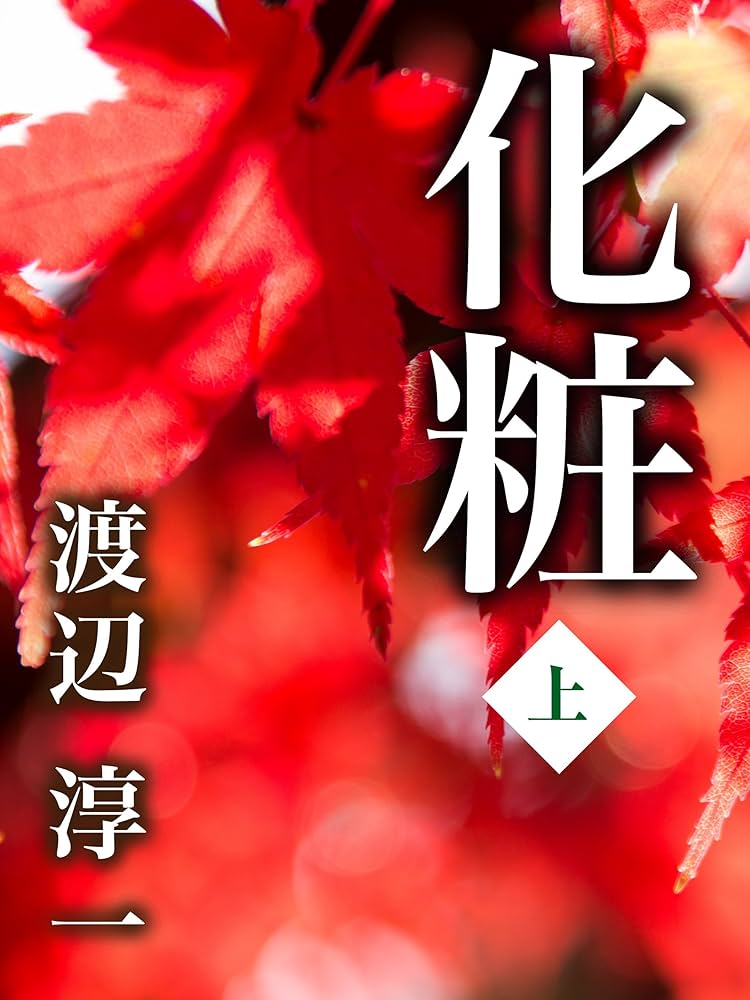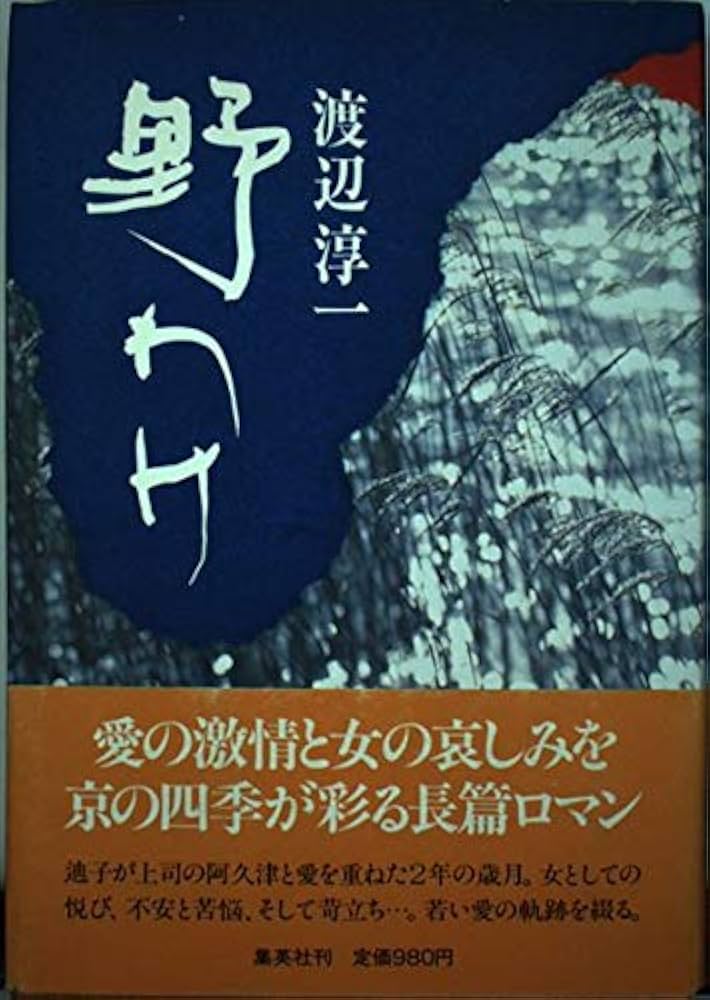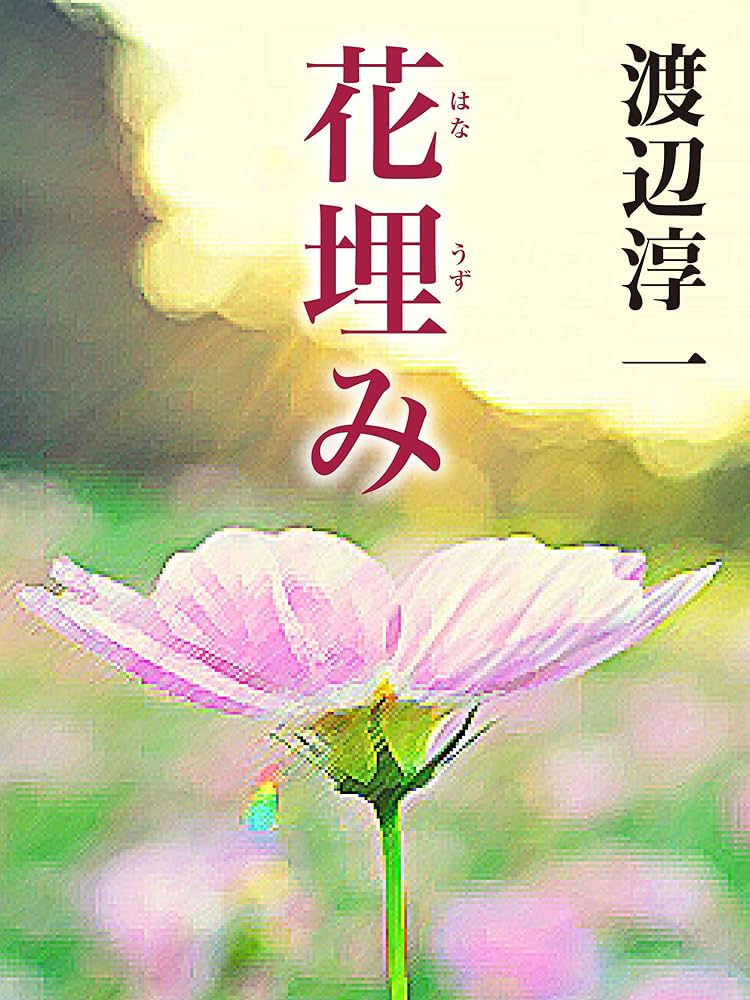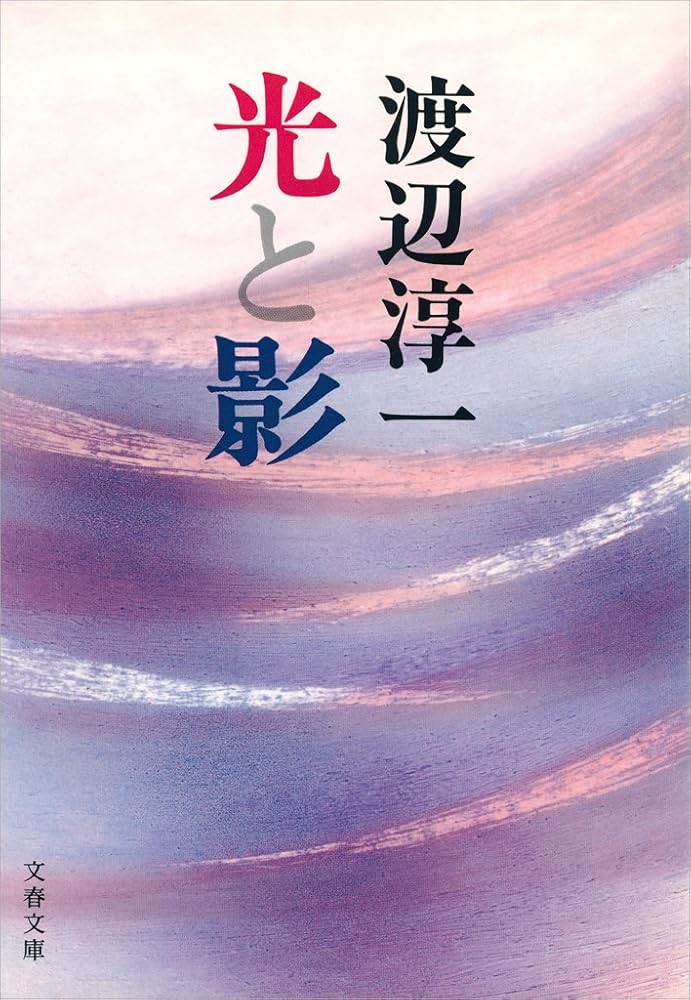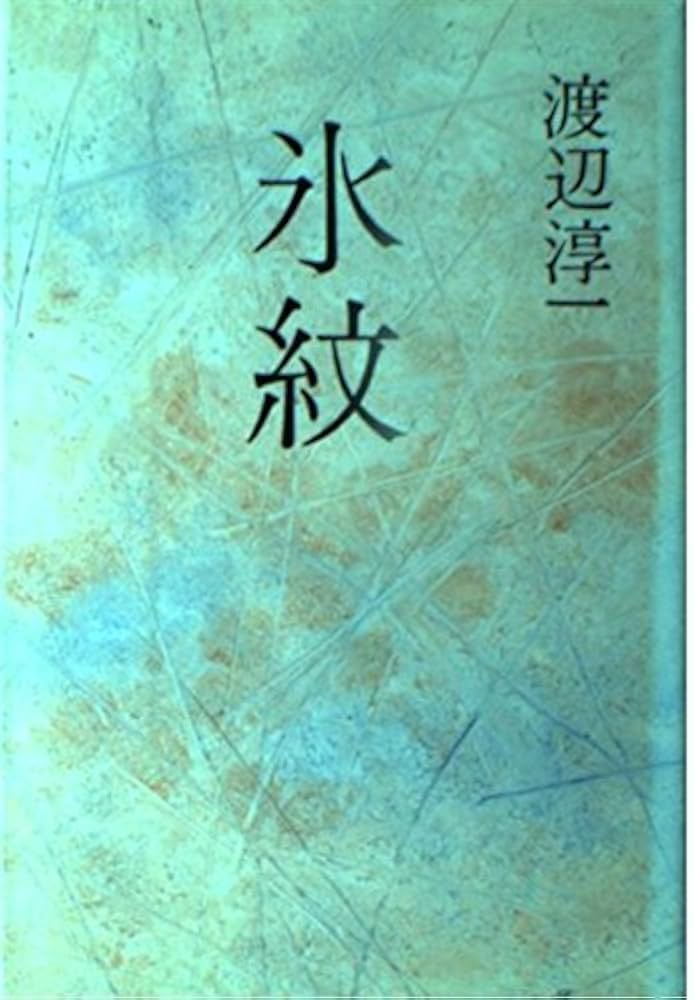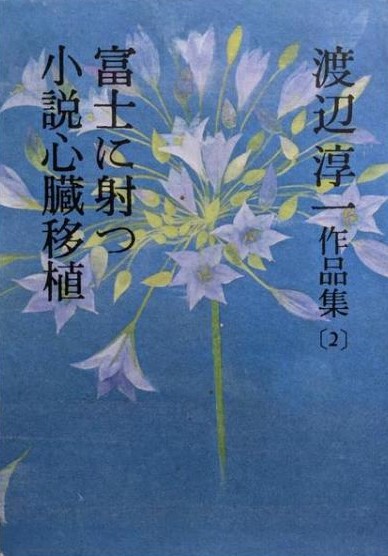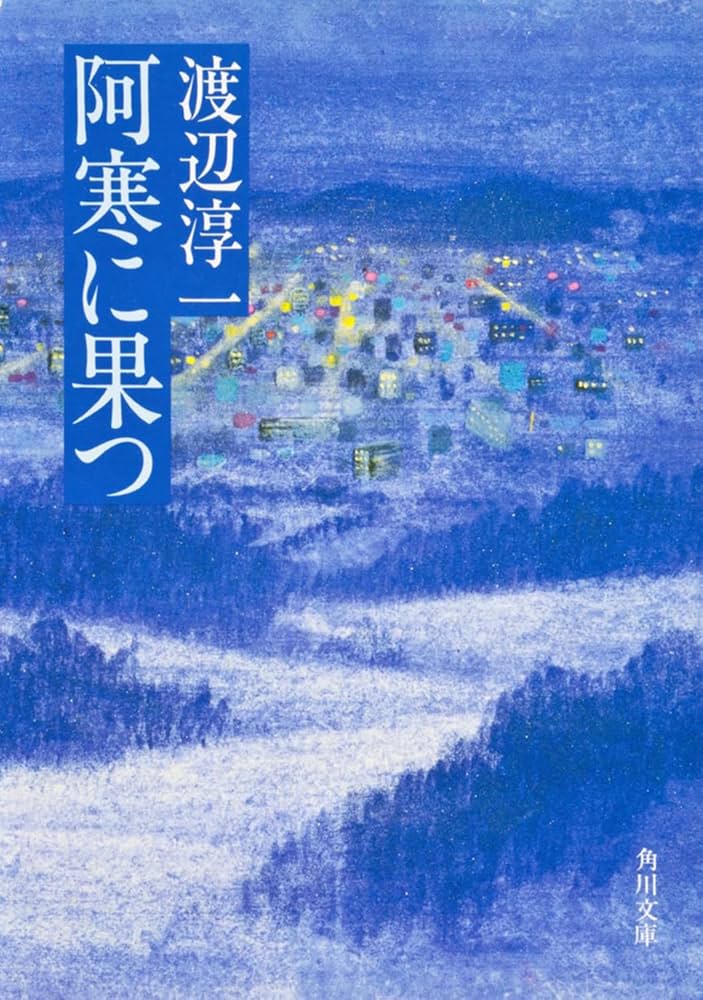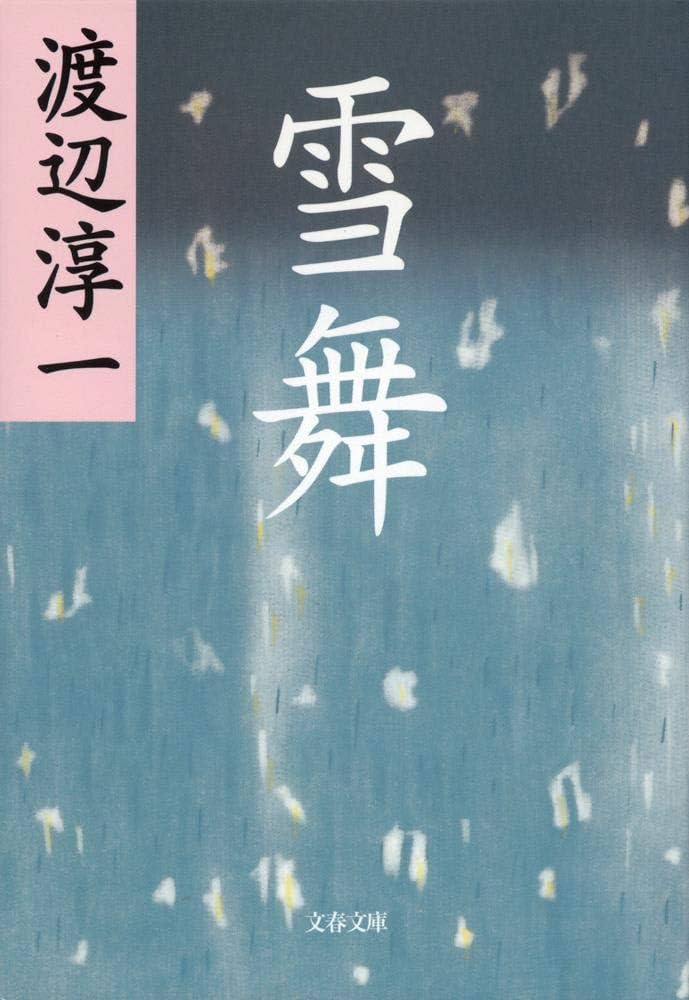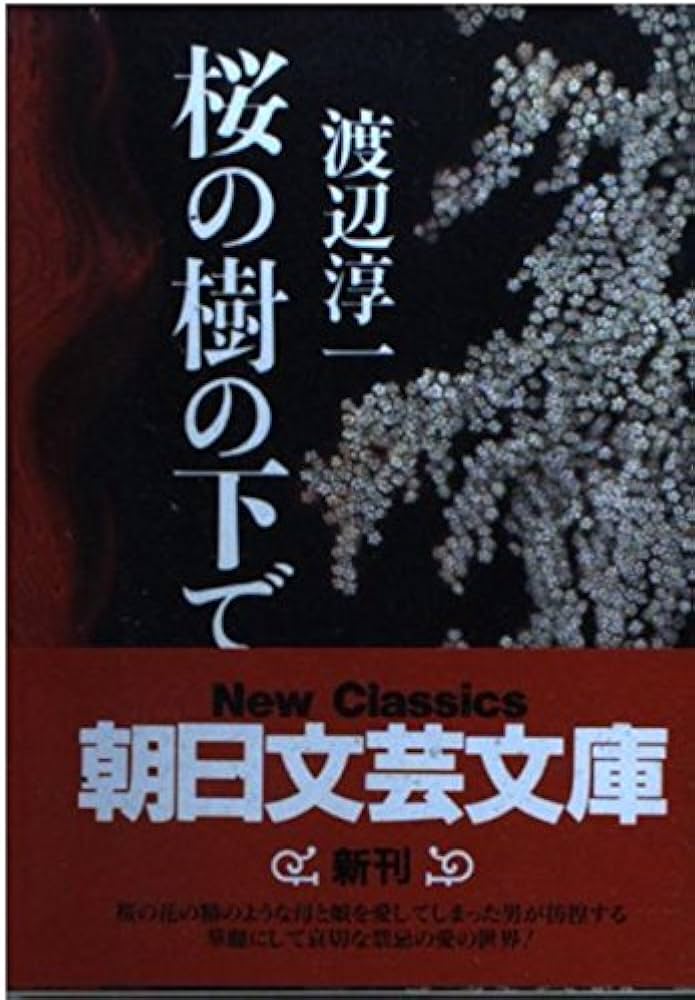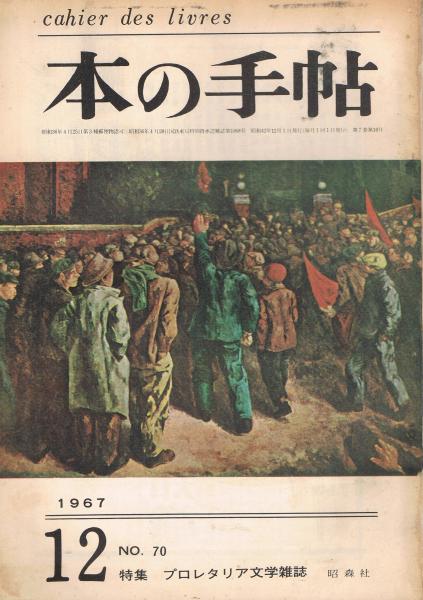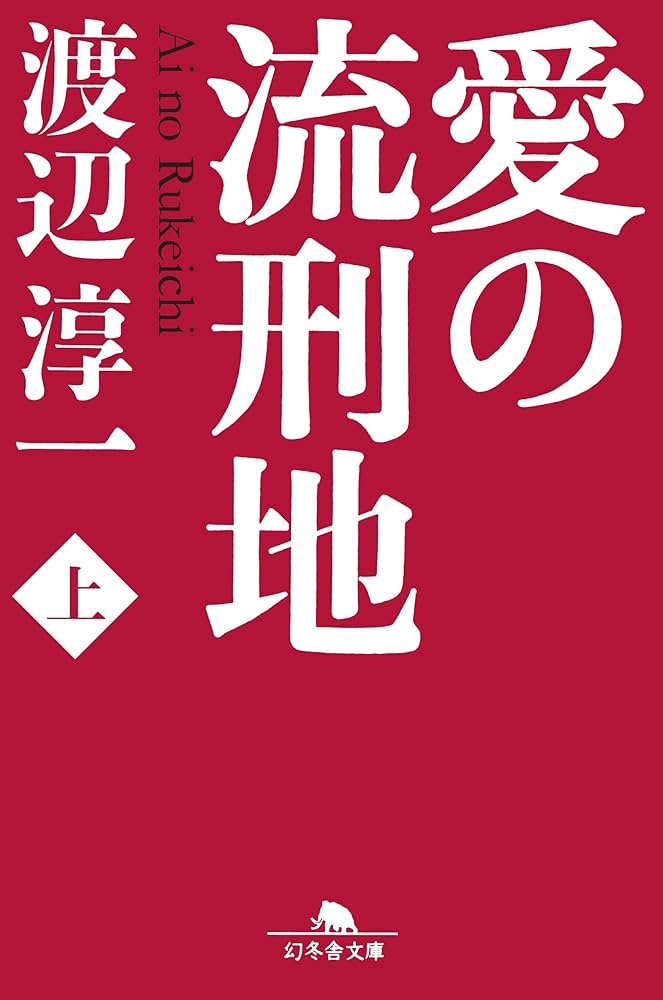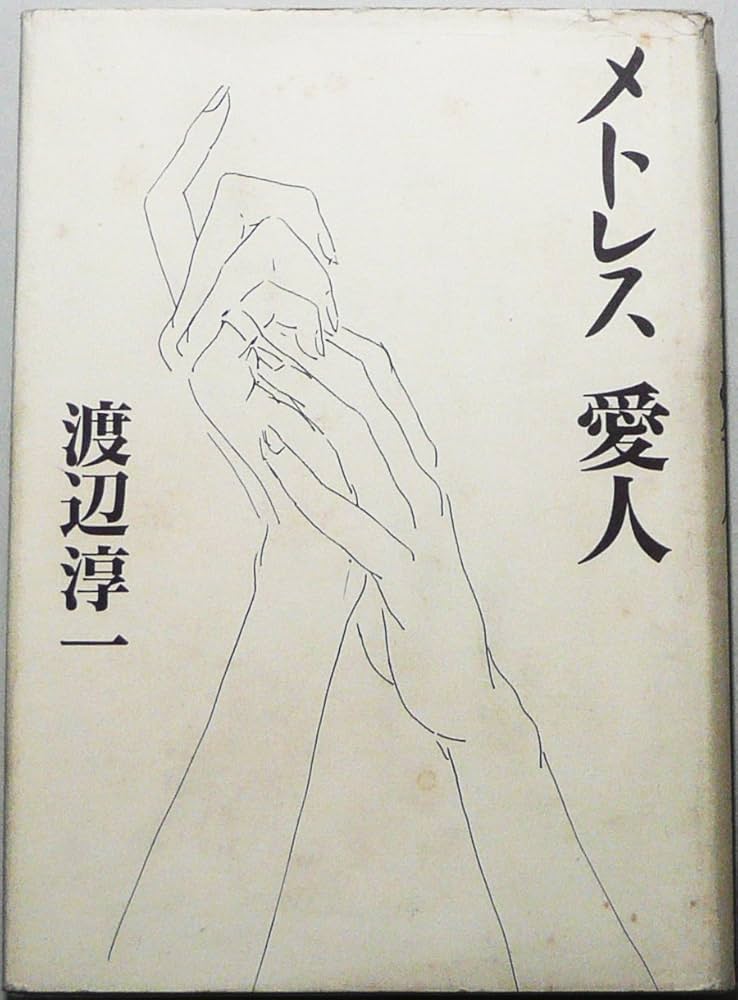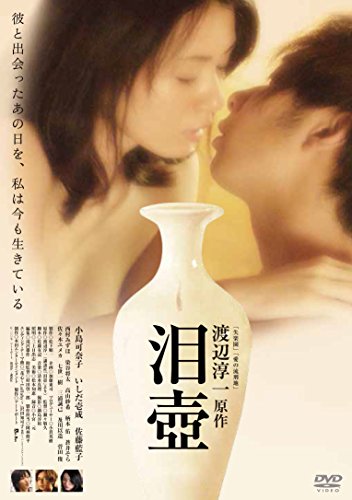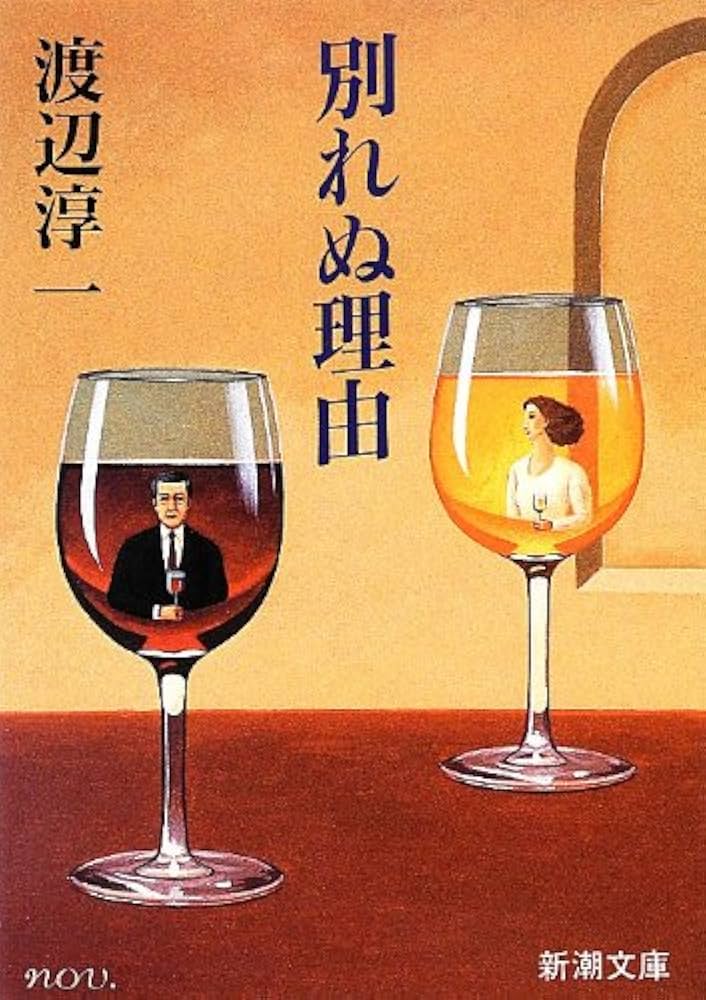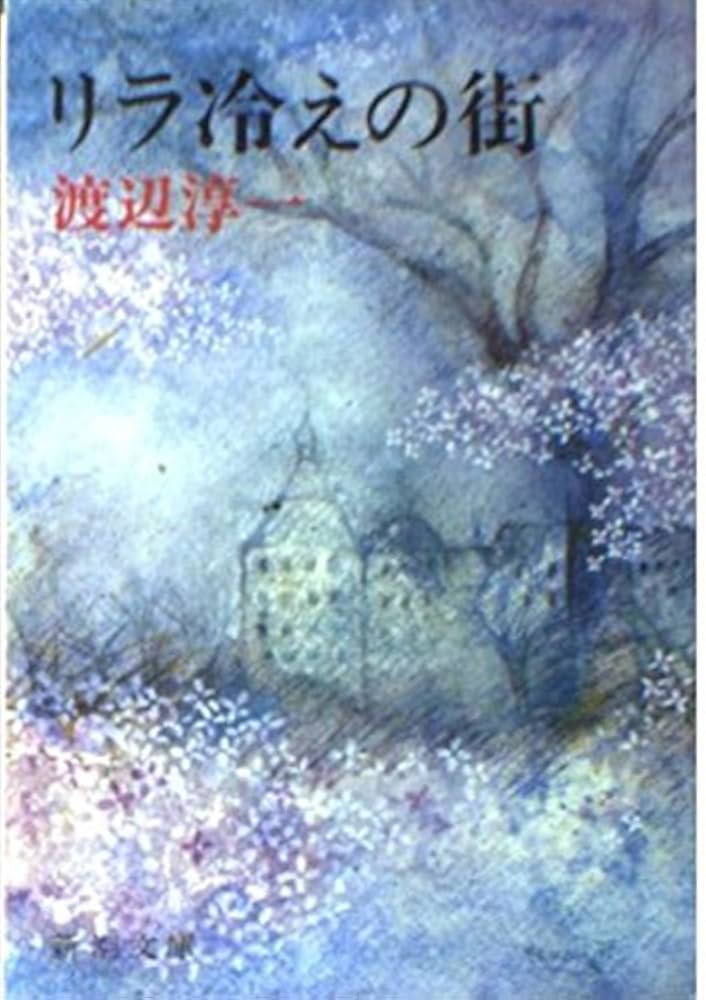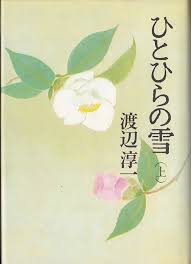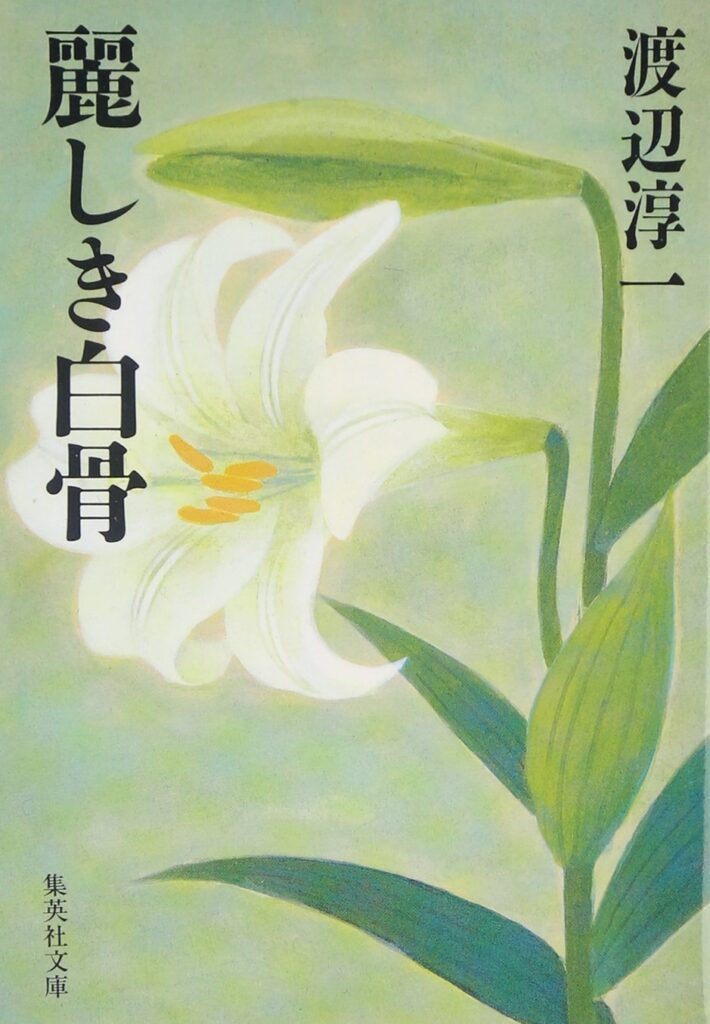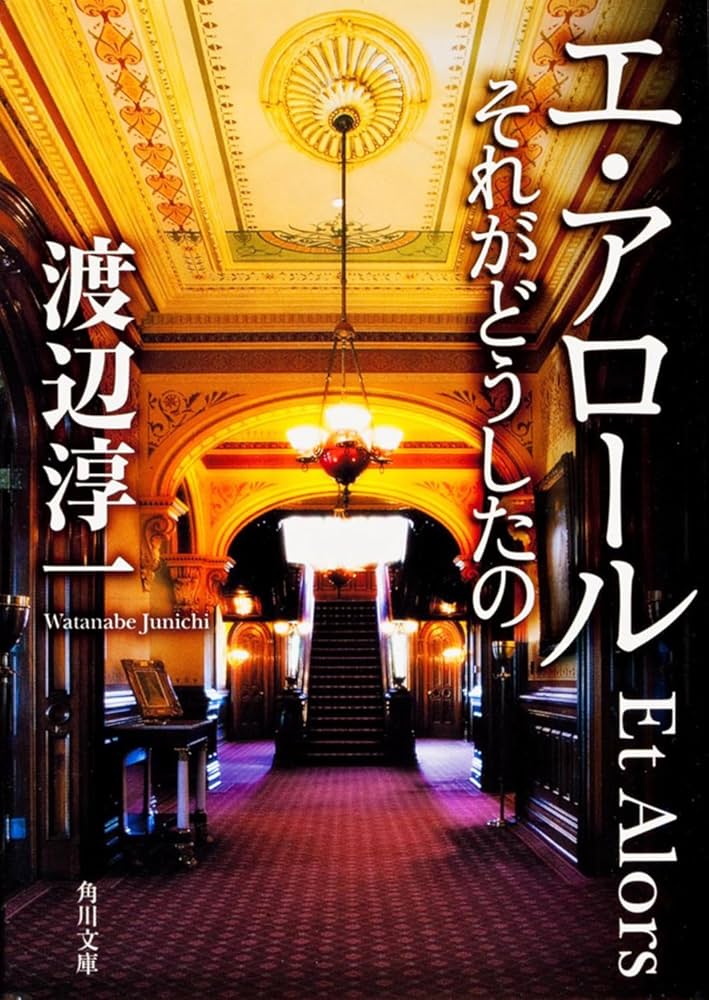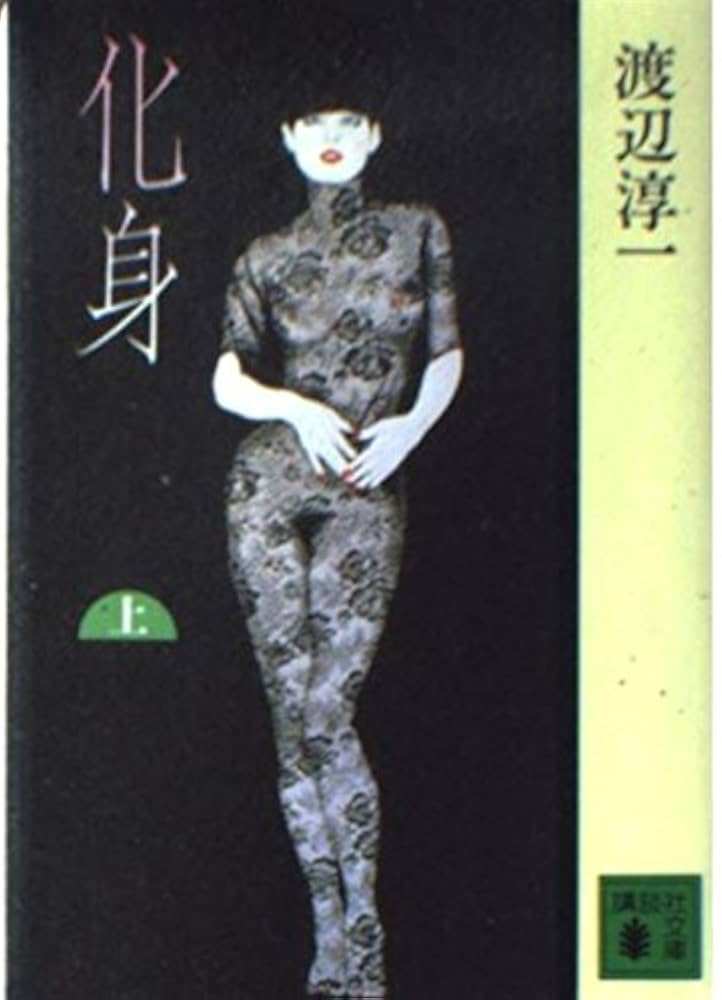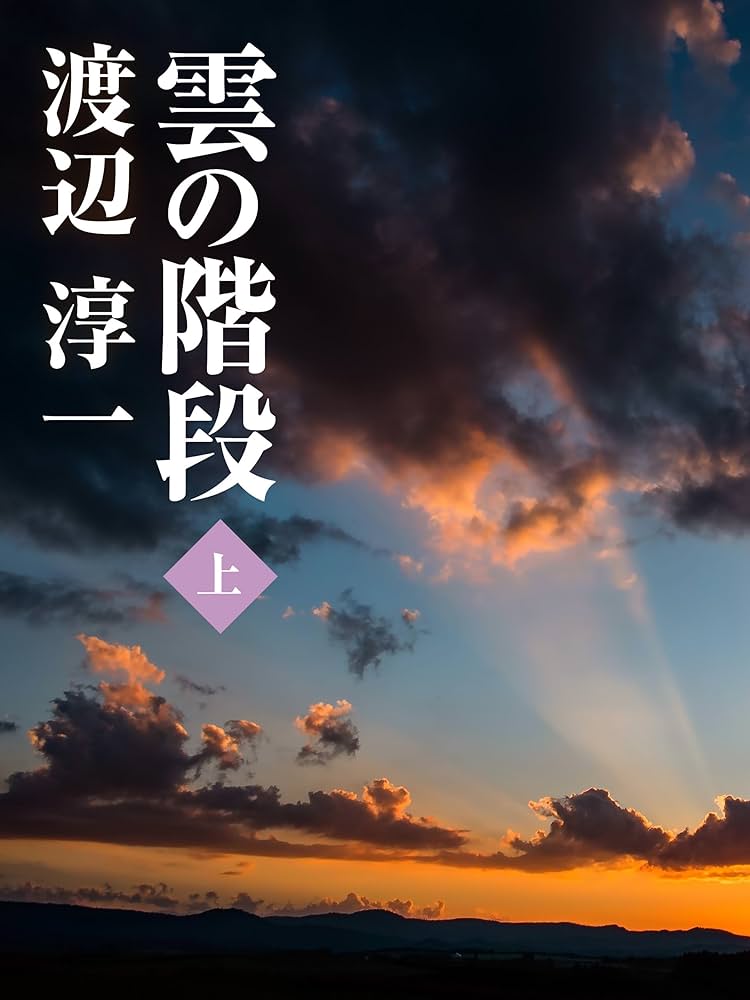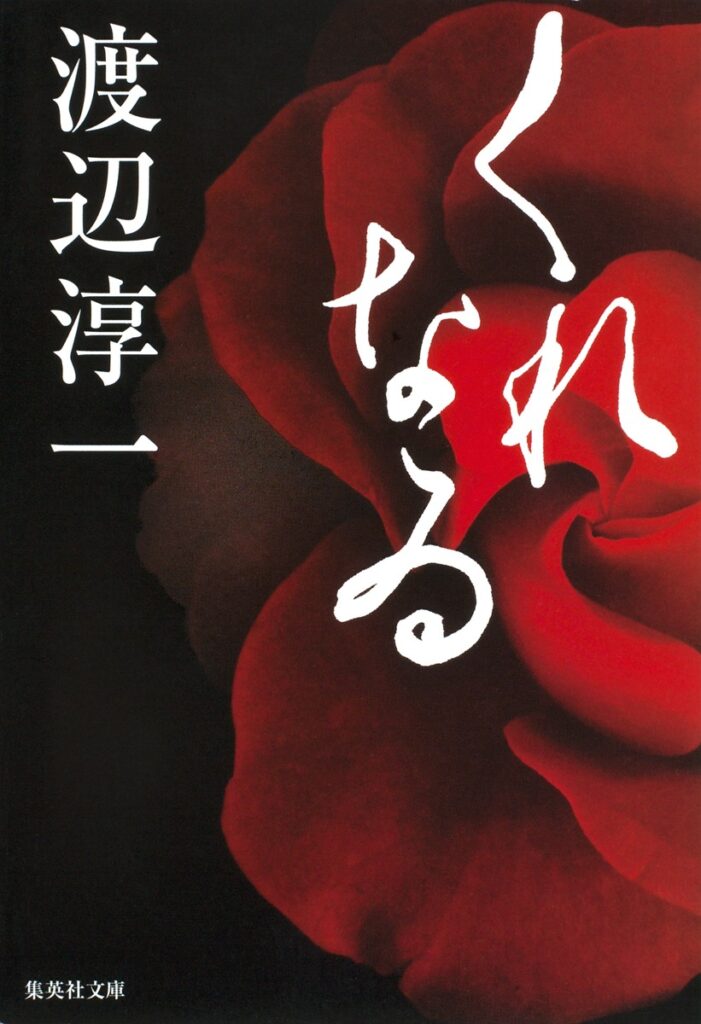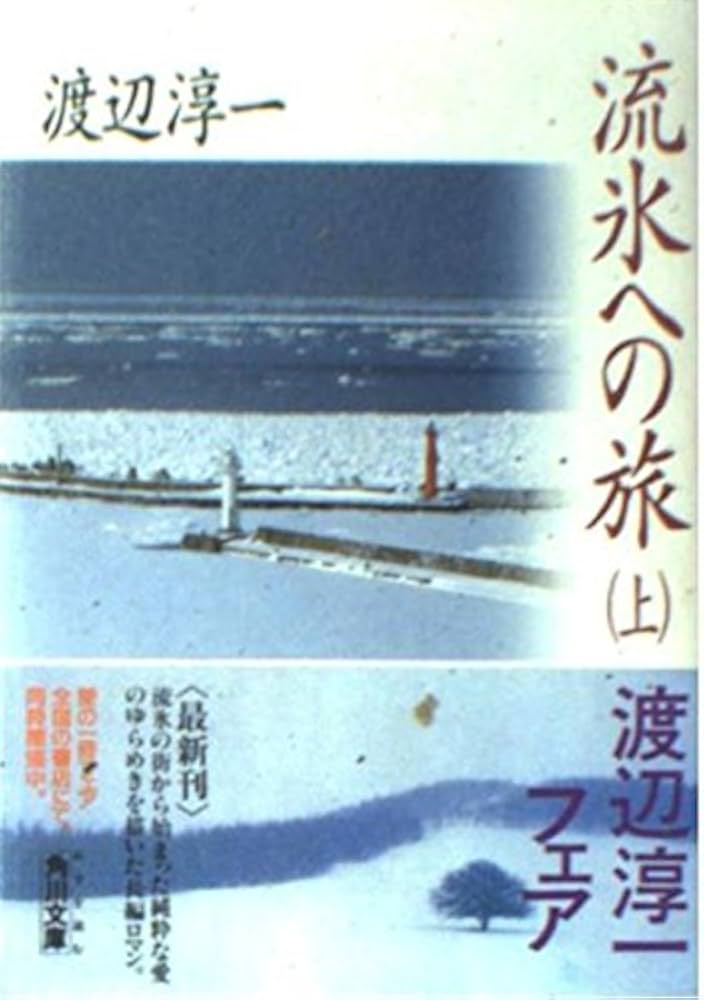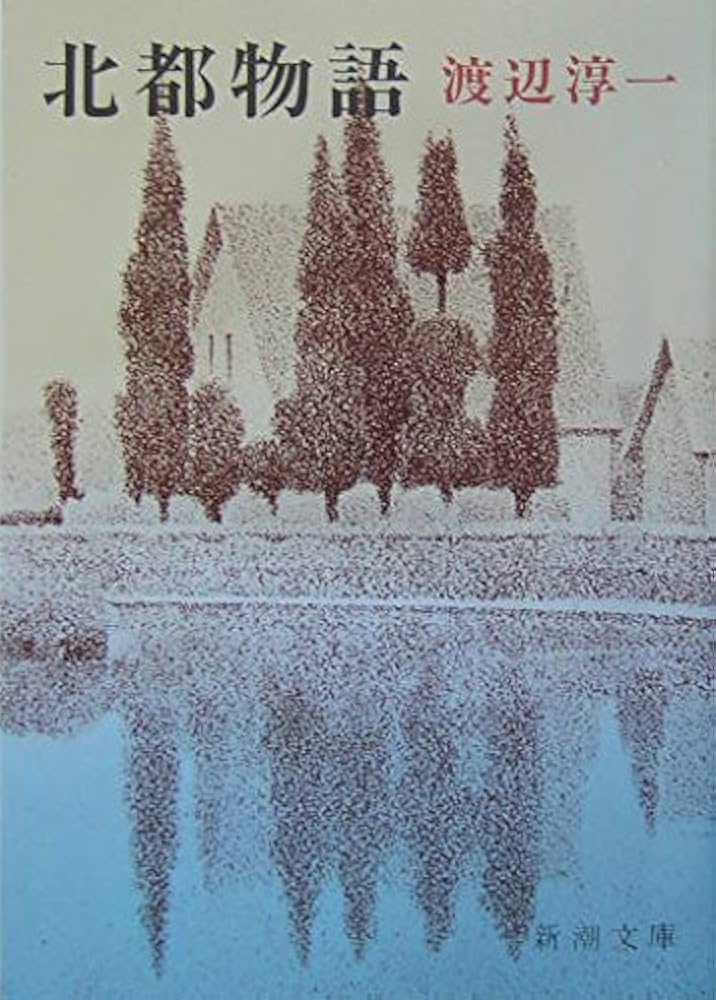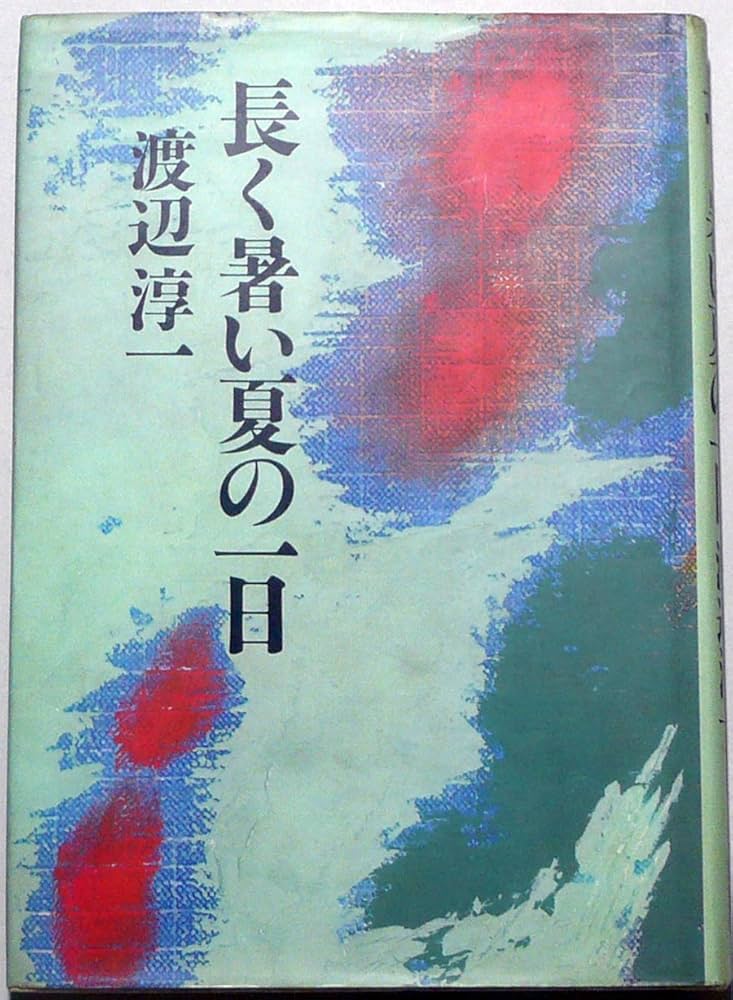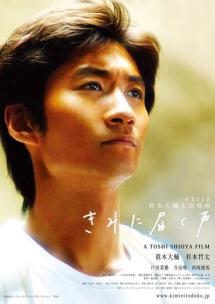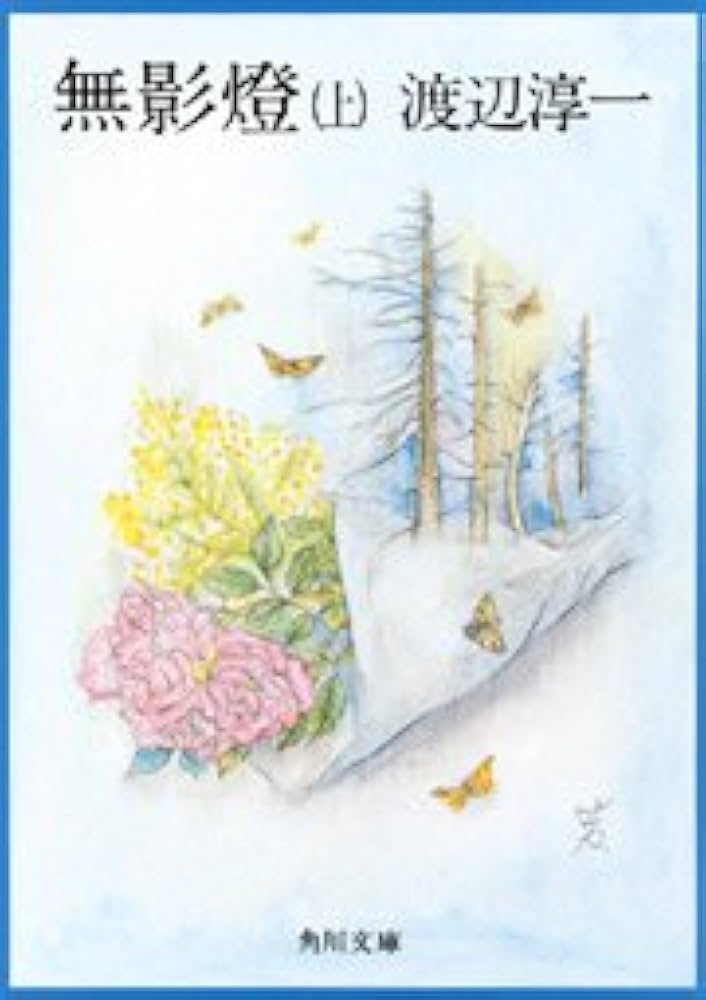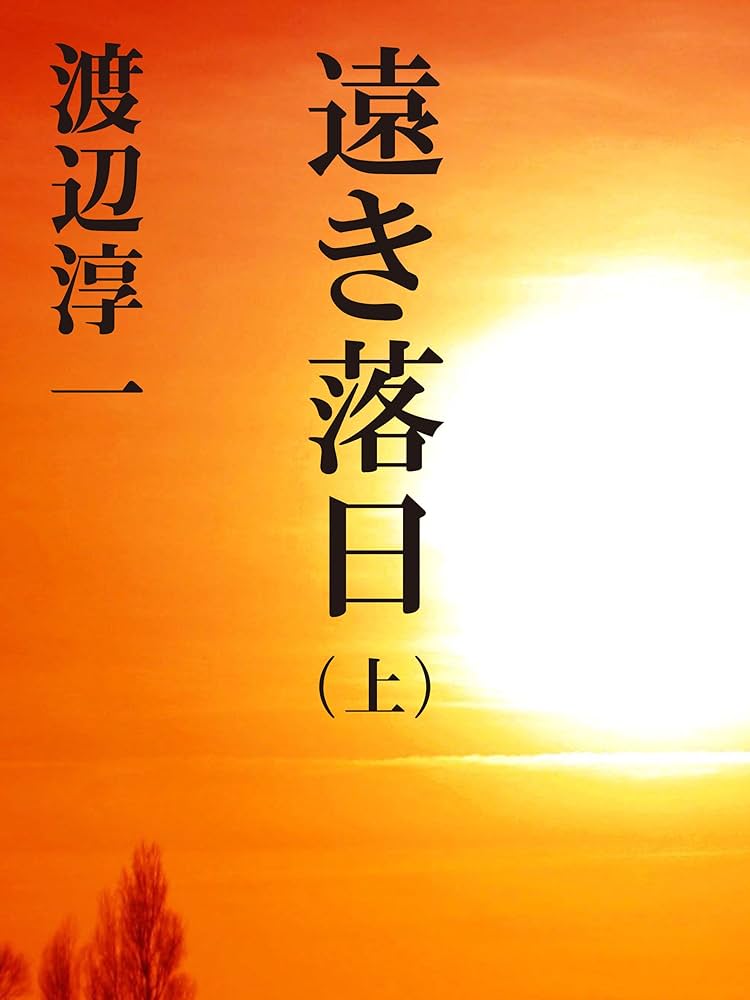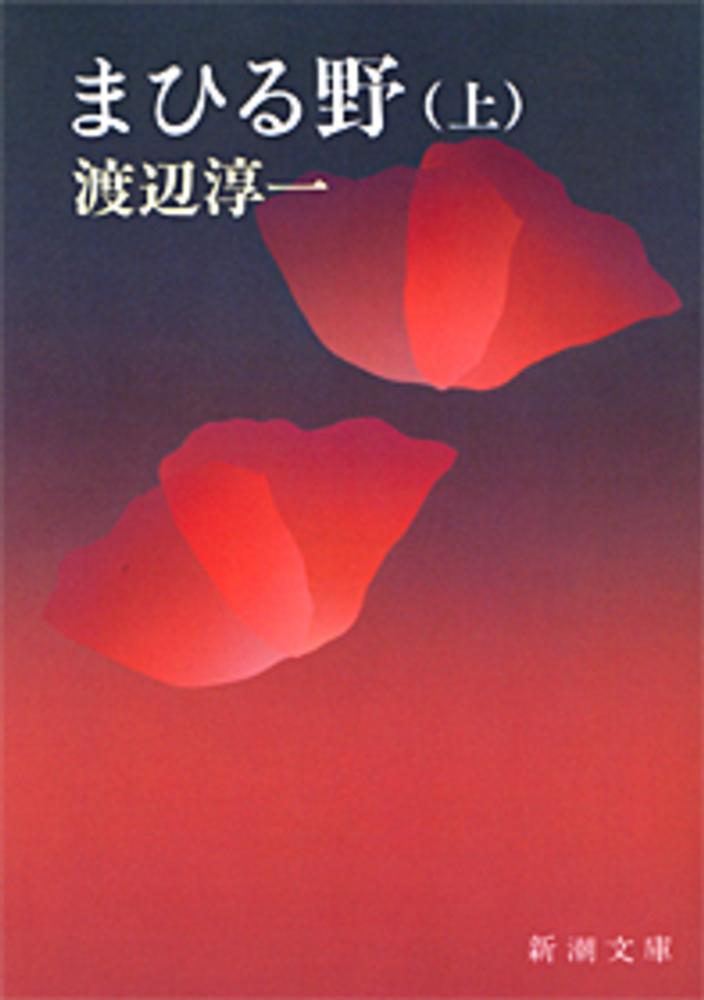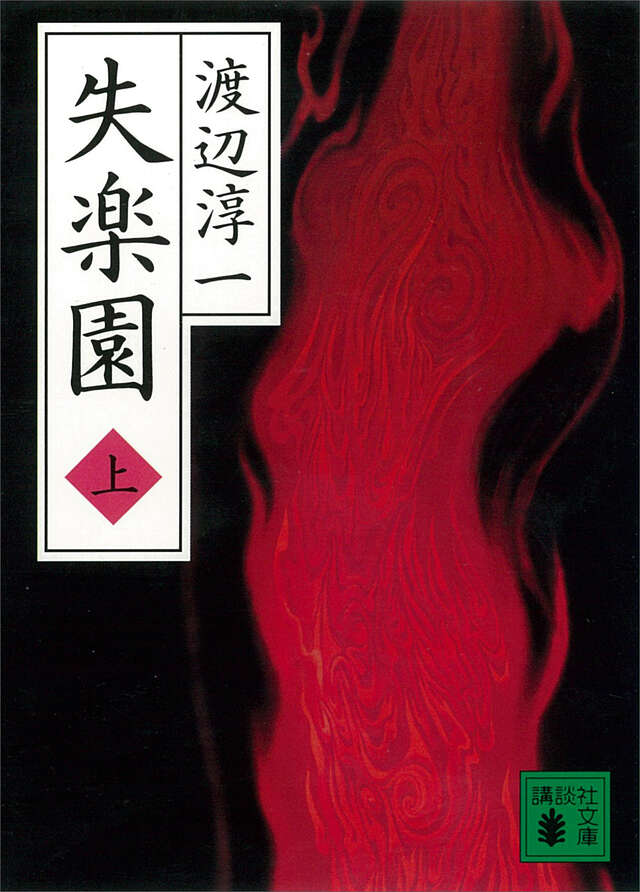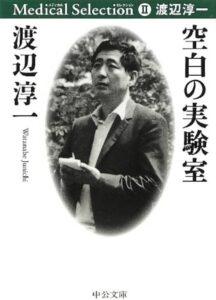 小説「空白の実験室」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「空白の実験室」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
本作は、元医師である渡辺淳一さんならではの、医学的知見に基づいたリアリティあふれる医療サスペンスの傑作です。物語の舞台は、権威と野心が渦巻く大学病院。そこで起こる二つの不可解な死をきっかけに、一人の医師が巨大な組織のタブーへと挑んでいきます。
この記事では、まず物語の導入部分と謎が深まっていく過程を紹介します。その後、核心に触れる部分、すなわち犯人の正体やその驚くべき犯行手口、そして人間の心の闇を描ききった動機まで、深く踏み込んで語っていきます。
手に汗握る展開だけでなく、人間の本質に迫る重厚なテーマも本作の大きな魅力です。なぜこの物語が多くの読者を引きつけてやまないのか、その秘密に迫りたいと思います。この記事が、あなたが「空白の実験室」の世界に浸るための一助となれば幸いです。
「空白の実験室」のあらすじ
名門として知られるS医科大学付属病院の第一外科は、絶対的な権力を持つ教授を頂点とした、厳格な階級社会が形成されている世界でした。医局員たちの人生は、教授の一存で決まると言っても過言ではなく、次期教授の座を巡る競争は、常に静かな熱を帯びていました。物語は、この閉鎖された世界で起きた、最初の悲劇から始まります。
半年前、医局を統べていた高村教授が、当時治療が困難だった白血病でこの世を去りました。医局は大きな悲しみに包まれましたが、難病による死であったため、誰もその最期に疑いを抱くことはありませんでした。それは、医学の世界では起こり得る、ごく自然な出来事として受け止められたのです。この「疑いようのない死」が、後に続く惨劇の序章とは、誰も知る由もありませんでした。
物語が本格的に動き出すのは、その半年後です。高村教授の後を継ぐと誰もが信じていた宮坂助教授が、あろうことか高村教授と全く同じ白血病で命を落としたのです。白血病は、罹患率が極めて低い稀な病気です。その病で、同じ医局のトップ2が、わずか半年の間に相次いで亡くなる。それは、単なる偶然で片付けるには、あまりにも異常な事態でした。
この天文学的な確率で起きた出来事に、合理的な思考を持つ医師たちの間に、口に出せない疑惑と恐怖が広がっていきます。「何かがおかしい」。その異様な雰囲気の中、第一外科の講師である倉本は、この偶然というには出来過ぎた現実に真っ向から向き合うことを決意します。彼は、二人の死が単なる病死ではないのではないか、という危険な仮説を胸に、孤独な真実の探求へと足を踏み出すのでした。
「空白の実験室」の長文感想(ネタバレあり)
S医科大学第一外科という、名声と権威が支配する閉鎖的な空間。物語は、この象牙の塔の頂点に君臨する人物たちの、にわかには信じがたい連続死から幕を開けます。教授の言葉が絶対であり、その地位の継承が医局員たちの最大の関心事である世界。この特殊な環境こそが、物語の根幹をなす人間関係と、底知れぬ動機を生み出す土壌となっているのですね。
物語の始まりは、医局の絶対的権力者であった高村教授の死です。死因は白血病。当時は治療法も確立されていなかった難病ですから、医局員たちはその死を悲劇として受け止めつつも、医学的な見地から疑うことはありませんでした。この「疑いのない最初の死」が、巧みな伏線として機能していることに、後になって気づかされるのです。
半年後、物語は大きく動きます。次期教授の最有力候補であった宮坂助教授が、高村教授と全く同じ白血病で亡くなる。ここで、読者である私も、そして作中の登場人物たちも、初めて「異様さ」に気づかされます。罹患率が10万人に3人程度という非常に稀な病気に、同じ組織のトップ2が立て続けに罹患する。この統計的な異常性を提示された瞬間、物語は単なる悲劇から、知的な謎解きを伴うサスペンスへと昇華します。
この「あり得ない偶然」こそが、科学者である医師たちの心を揺さぶり、疑惑を生む最初のきっかけとなるのです。悲しみや同情は、次第に不信と恐怖へと変質していきます。元医師である渡辺淳一さんならではの、医学的知識に裏打ちされた設定が、物語に圧倒的なリアリティを与えていると感じました。この統計的異常こそが、人為的な介入、つまり「殺人」の可能性を示唆する、何より雄弁な証拠となるわけです。
この不気味な沈黙を破ったのが、主人公である第一外科の講師、倉本でした。彼は、二人の上司の死を偶然として片付けることができませんでした。科学者としての良心が、彼に思考停止を許さなかったのでしょう。彼は、専門の違う内科の井石助教授に「二人はひょっとして他殺ではないか」という、とてつもない仮説を打ち明けます。この一言が、巨大な組織のタブーに挑む、長く困難な戦いの始まりを告げるのです。
倉本の熱意と論理的な疑念に、井石助教授も協力者となることを決意します。閉鎖的な外科の世界において、内科医である井石の存在は非常に重要です。異なる視点と人脈が、倉本の孤独な調査を、組織的なものへと変えていきます。真実を追求する者が孤立しがちな巨大組織の中で、信頼できる協力者の存在が、倉本にどれほどの勇気を与えたか、想像に難くありません。
二人の秘密調査が始まり、やがて最初の物証が浮かび上がります。それは、亡くなった宮坂助教授の遺骨が、火葬後に「ボロボロになっていた」という情報でした。白血病でも骨に影響は出ますが、経験豊富な医師たちが異常だと感じるほどの脆さ。これは、病気の進行だけでは説明がつかない何かがあったことを示唆します。この発見が、新たな疑惑の扉を開く鍵となりました。
そして、倉本と井石は、真実を明らかにするため、倫理的に危うい一線を越える決断をします。宮坂助教授の遺骨の一部を秘密裏に入手し、さらに高村教授の未亡人を説得して遺骨を提供してもらうのです。この執念とも言える行動の末に、彼らは衝撃的な科学的証拠を手にすることになります。
専門機関による分析の結果、両名の遺骨から高濃度の放射性同位元素、特に骨に蓄積しやすい性質を持つストロンチウム90が検出されたのです。これは、二人が何者かによって、長期間にわたり計画的に放射性物質を投与され続けたことを示す、動かぬ証拠でした。被害者の身体は、犯人によって巧みに設計された「実験室」と化していたのです。
この犯行手口の恐ろしさは、外部からは一切痕跡が見えず、通常の検死では決して見抜けない点にあります。ストロンチウムはカルシウムと誤認されて骨に取り込まれ、内部から静かに白血病を誘発します。これにより、表面上は「病死」という結果しか残らない完全犯罪が成立する。捜査の手が及ぶことのない「空白」の空間。これこそが、タイトル「空白の実験室」が示す、第一の意味なのだと理解した時、私は背筋が凍る思いがしました。
放射性物質による連続殺人という事実が判明し、調査は「誰が犯人か」という次の段階へ移ります。ここで、ごく自然に一人の容疑者が浮かび上がります。同じ第一外科の講師であり、二人の死によって次期教授の座に最も近づいた男、小貫です。教授の座という、医局員にとって最高の栄誉を手に入れるためなら殺人も厭わない。彼の動機は、誰の目にも明らかで、あまりにも説得力がありました。
さらに、倉本が真相を探っていると知った小貫は、大学の名誉を盾に、あからさまに調査を妨害しようとします。この行動は、大学を守ろうとする忠誠心とも取れますが、自らの罪を隠蔽するための工作だと解釈することもできます。動機、機会、そして怪しい行動。状況証拠は、すべてが小貫が犯人であることを示しているように見えます。物語は、読者を巧みに小貫犯人説へと誘導していくのです。
しかし、このミスディレクションこそが、本作のもう一つのテーマを浮き彫りにします。小貫という人物は、彼自身が犯人であるかどうかにかかわらず、この大学病院という権威主義的なシステムが生み出した「産物」なのです。彼の野心も、組織防衛を口実にした自己保身も、すべてはこの歪んだ競争社会の症状に他なりません。渡辺淳一さんは、最も論理的な容疑者を描くことで、医学界という組織そのものが内包する病理を鋭く批判しているのだと感じます。
物語は、倉本が全ての証拠を手に小貫と対峙する場面で、最大のクライマックスを迎えます。しかし、そこで語られたのは、予想された自白ではなく、物語の前提を全て覆す衝撃の真実でした。小貫は、犯人ではなかったのです。彼が調査を妨害したのは、彼自身もまた別の人物を疑っており、その人物が犯人だった場合のスキャンダルを恐れてのことでした。この大どんでん返しには、本当に驚かされました。
そして、ついに真犯人がその姿を現します。それは、権力闘争の中心から外れた場所にいた、誰もが予想し得なかった人物でした。教授の座を狙う野心とは無縁と思われていた、しかし被害者たちの日常に深く関わっていた人物。この意外な犯人の設定が、物語の焦点を権力闘争という分かりやすい動機から、人間の心の奥底に潜む、より深く暗い情念へと移行させるのです。
犯人の告白によって、悪魔的とも言える犯行手口の全貌が明らかになります。長期間にわたり、微量のストロンチウムを繰り返し投与する。その方法は、被害者たちが日常的に使うコーヒーポットや万年筆のインクに混入させるという、あまりにも巧妙で気づきようのないものでした。凶器はなく、犯行の瞬間もない。ただ静かに、被害者の身体という実験室の中で、死に至る病が培養されていく。その冷徹さに、人間性の欠如を感じ、深い恐怖を覚えました。
そして、物語の最も核心的な部分、犯人の動機が語られます。それは、出世欲や野心といったものではありませんでした。その根源にあったのは、過去に受けた個人的な屈辱や裏切りに対する、冷たく、執拗な復讐心でした。自らの研究成果を奪われた恨み。決して許すことのできない人間的な裏切り。渡辺淳一さんの作品に一貫して流れる「愛憎」というテーマが、最も純粋で、最もおぞましい形でここに現れたのです。
この物語の真の恐怖は、犯行の科学的な冷徹さと、その根底にある燃え盛るような個人的な情念との、すさまじいギャップにあります。犯人は自らの優れた知性を、倫理や道徳から完全に切り離し、純粋な悪意と復讐心のためだけの道具として使ったのです。この知性の倒錯こそが、「空白の実験室」というタイトルの持つ、もう一つの、そして最も恐ろしい意味なのではないでしょうか。共感や倫理を失った犯人の心の中こそが、真の「空白の実験室」だったのです。
まとめ
渡辺淳一さんの小説「空白の実験室」は、単なる医療サスペンスの枠を超えた、人間の心理と組織の病理を深くえぐる傑作でした。物語は、大学病院という閉鎖的な世界で起きた連続死の謎を追う形で進みますが、その根底には普遍的なテーマが流れています。
本作の魅力は、まずそのプロットの巧みさにあります。放射性物質という見えない凶器を使った完全犯罪のアイデアは、元医師である作者ならではのリアリティに満ちており、読者を知的な興奮へと誘います。そして、巧みなミスディレクションの末に明かされる真相と、予想を裏切る真犯人の動機には、誰もが衝撃を受けることでしょう。
しかし、この物語が深く心に残るのは、犯行の裏に隠された、人間のどうしようもない情念を描いているからだと思います。地位や名誉といった社会的な価値ではなく、個人的な愛憎が、人をどれほど恐ろしい行動に駆り立てるのか。その描写は、人間の本質的な弱さと恐ろしさを見せつけます。
科学の知識は、使い方一つで人を救うことも、完璧な凶器となることもできる。そして、人間の心の中には、時に倫理さえも失わせるほどの深い闇が広がっている。読み終えた後、そんなことを考えさせられる、重厚な余韻の残る物語でした。