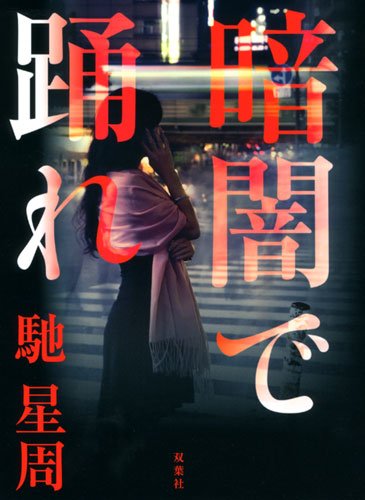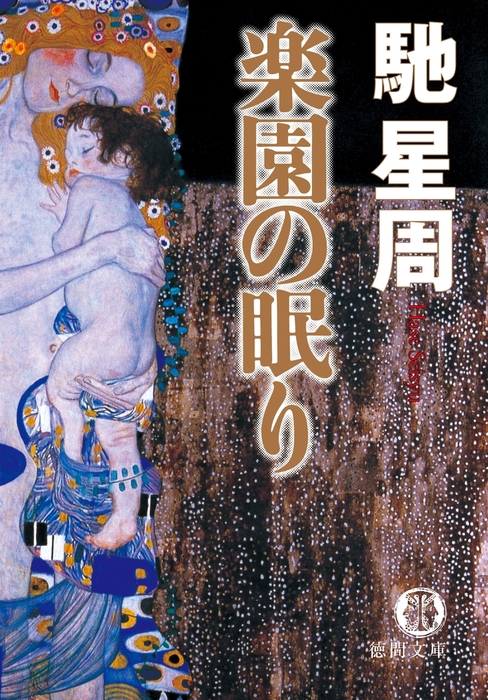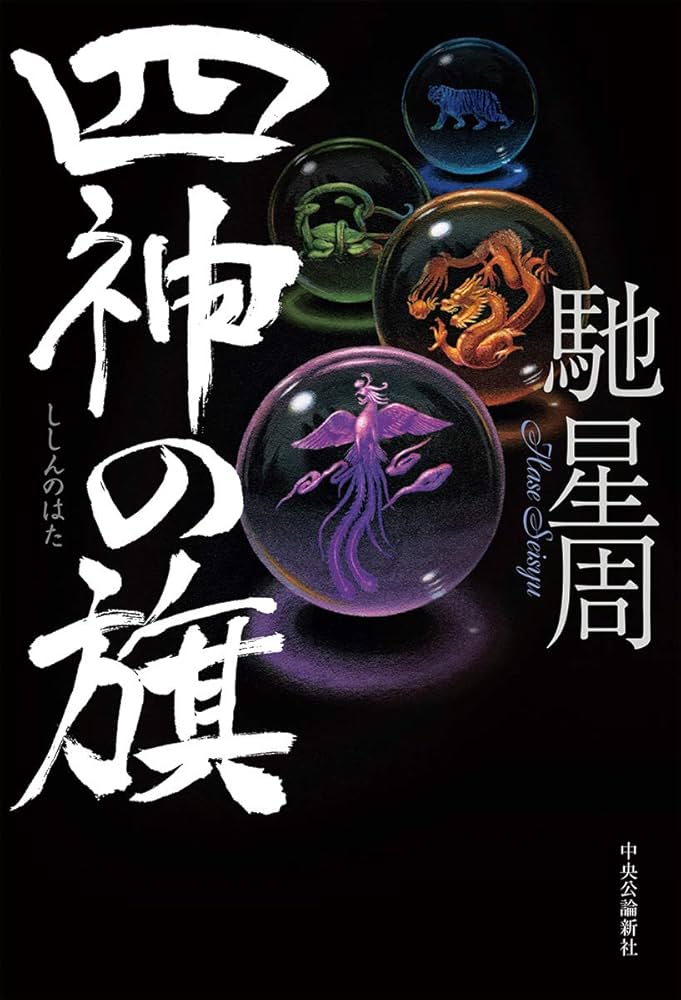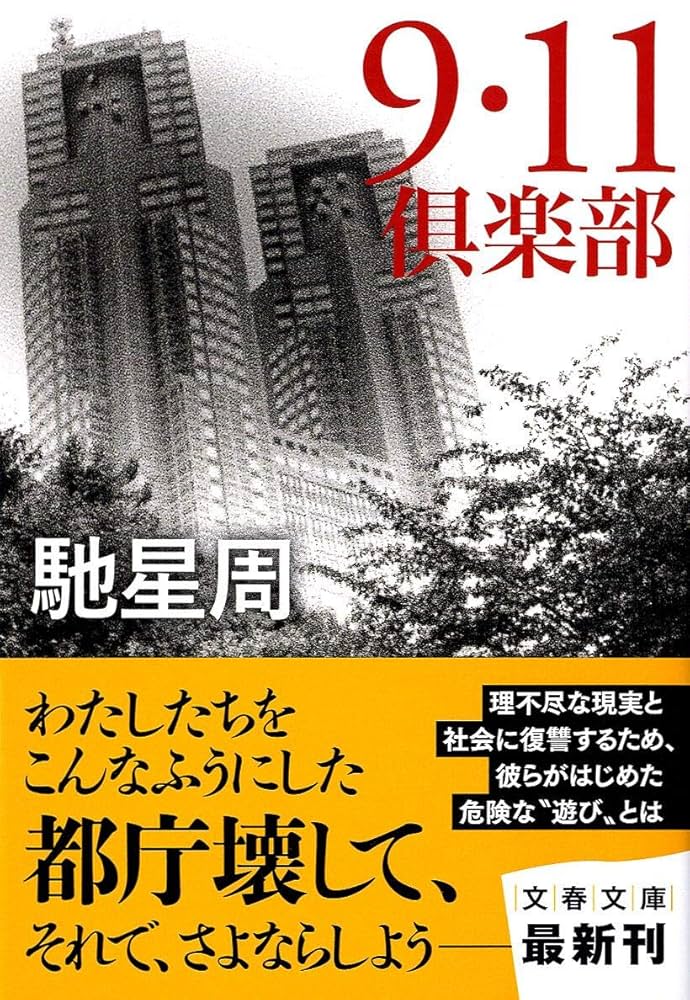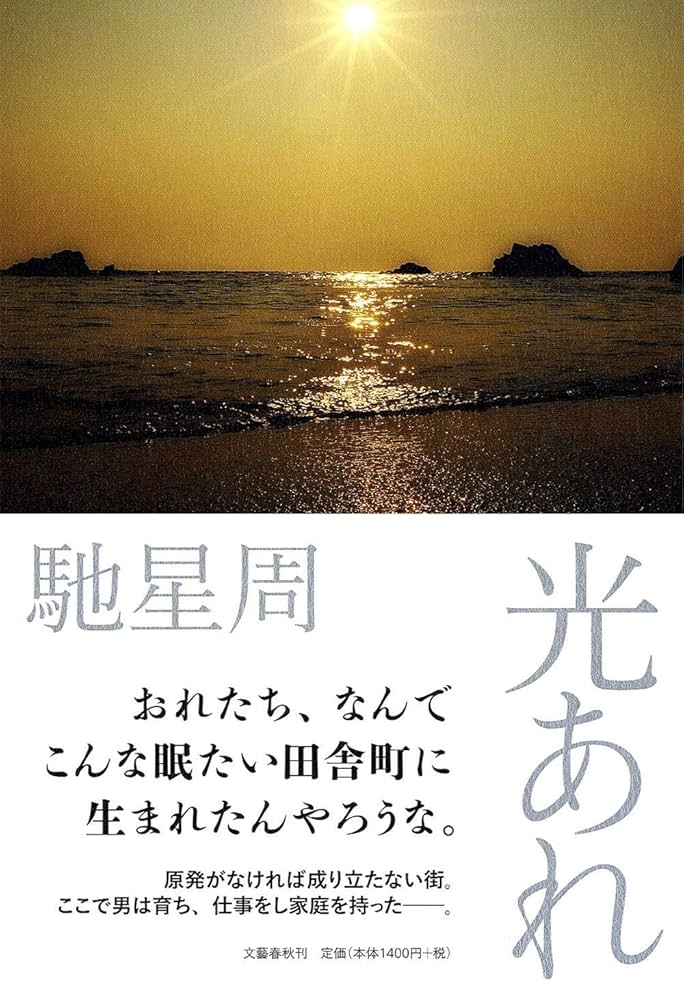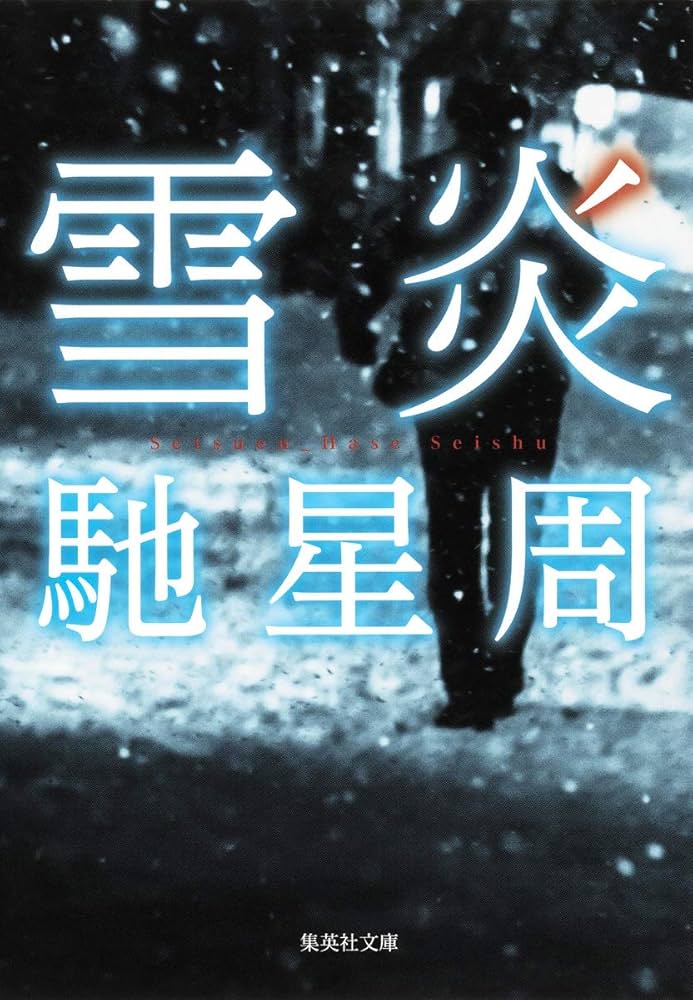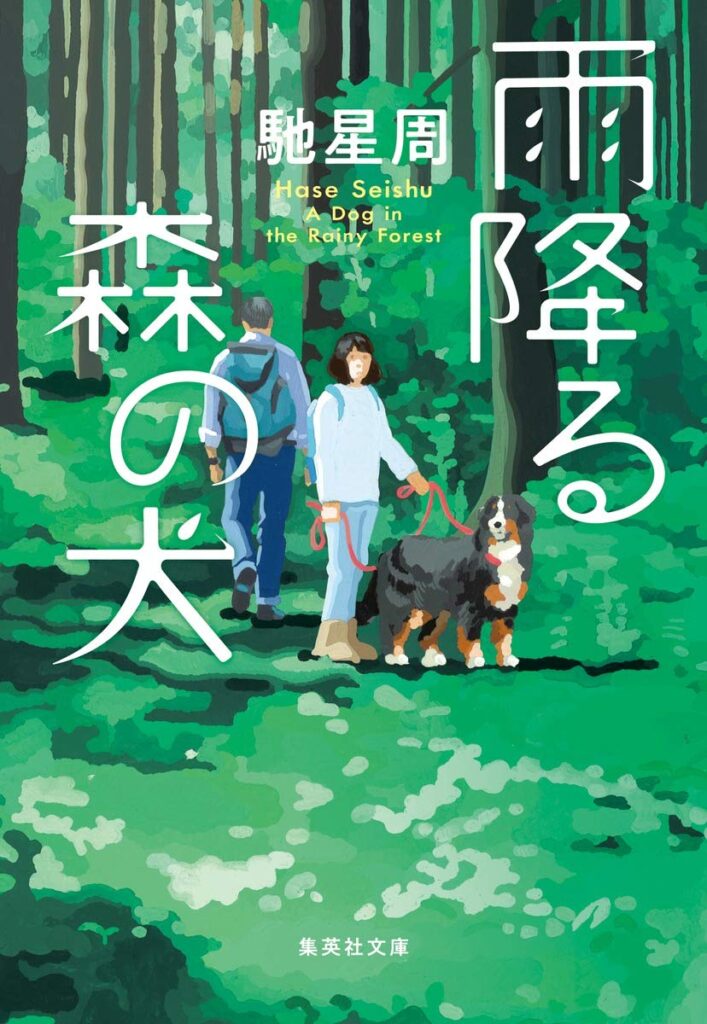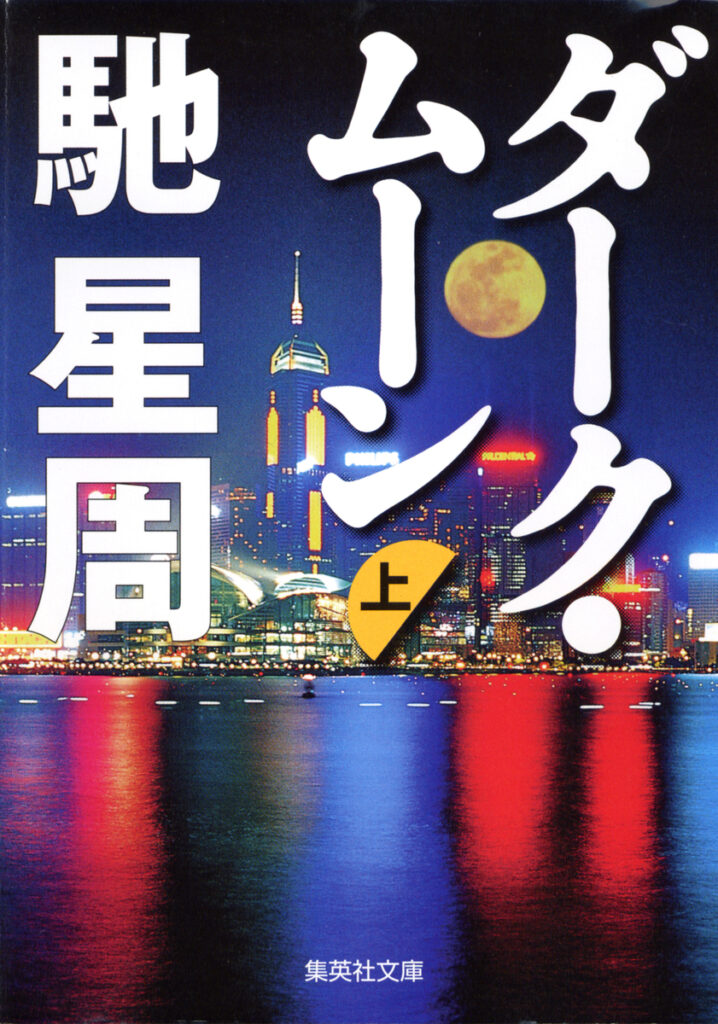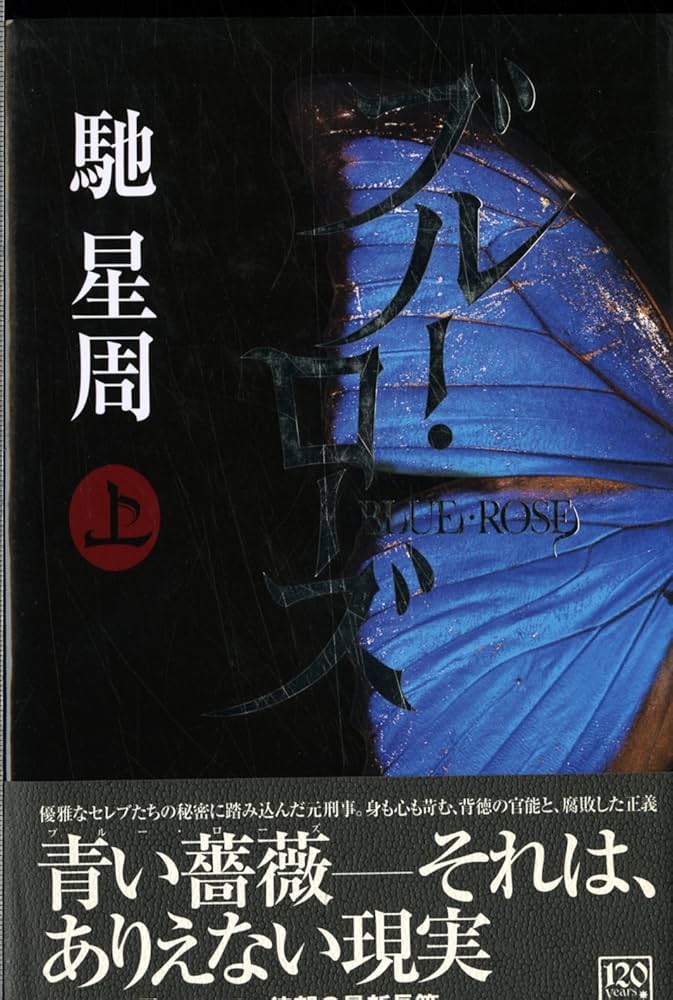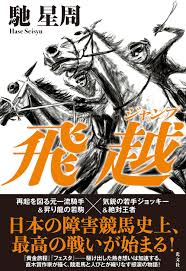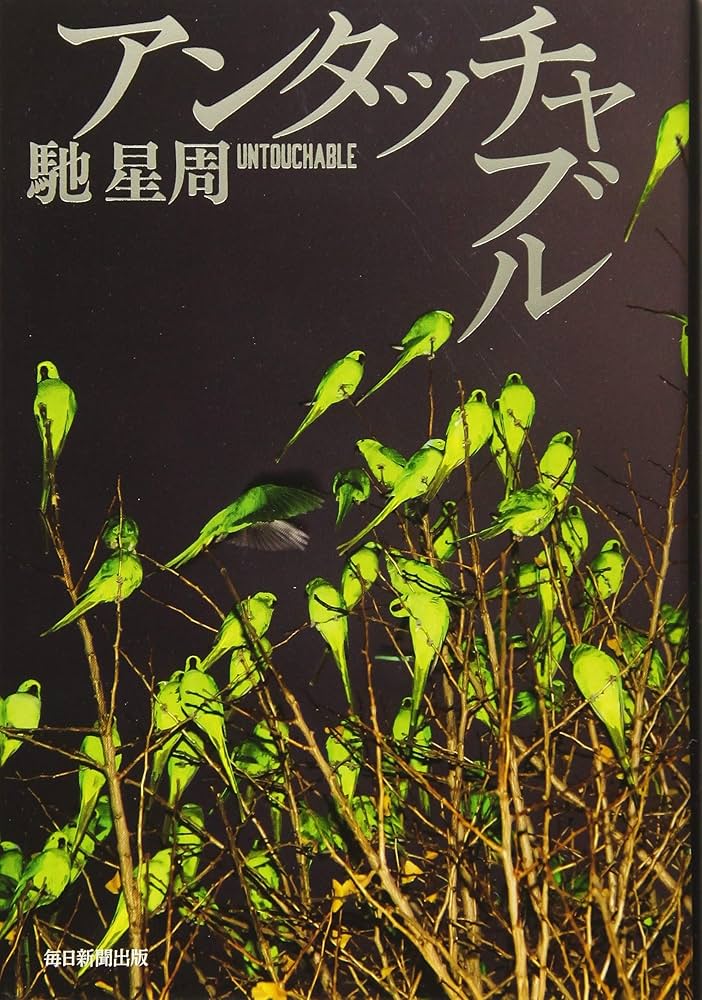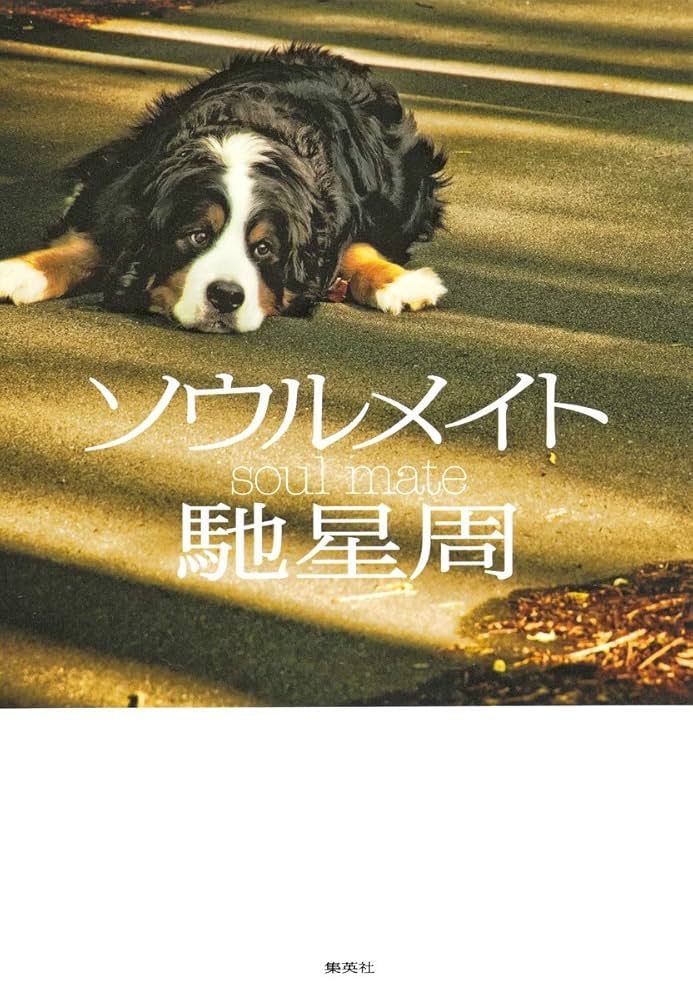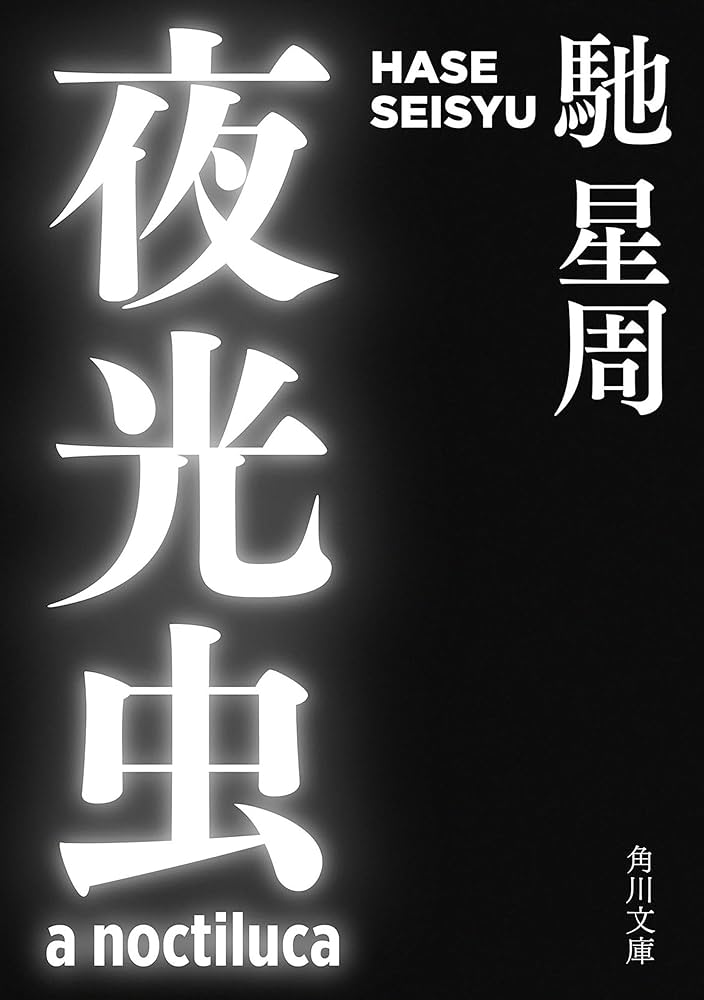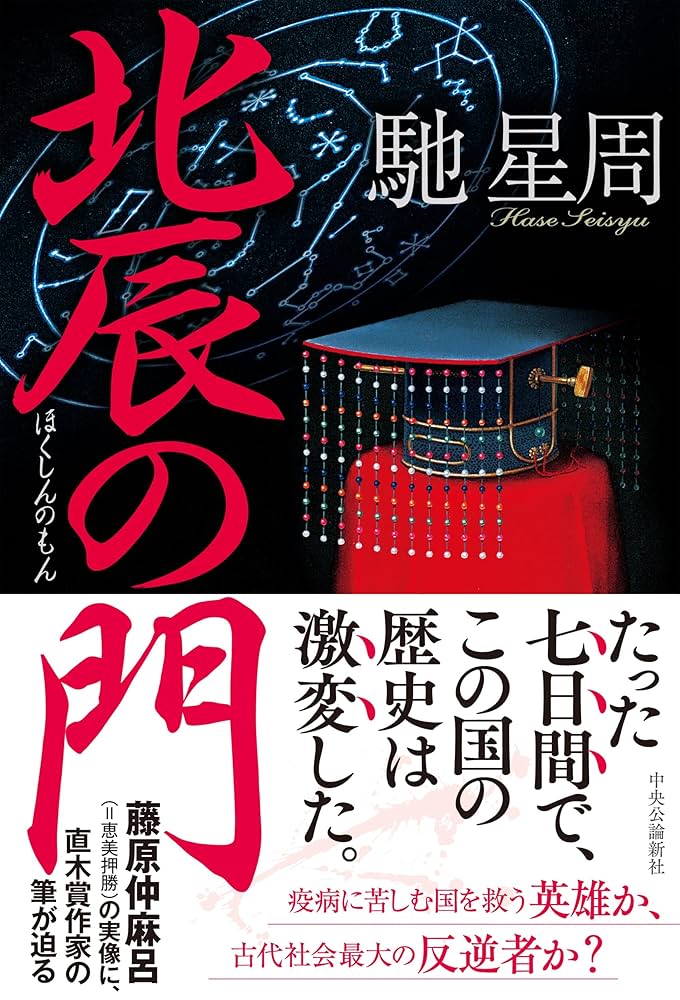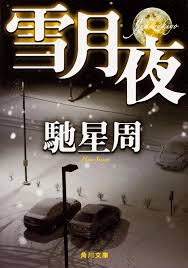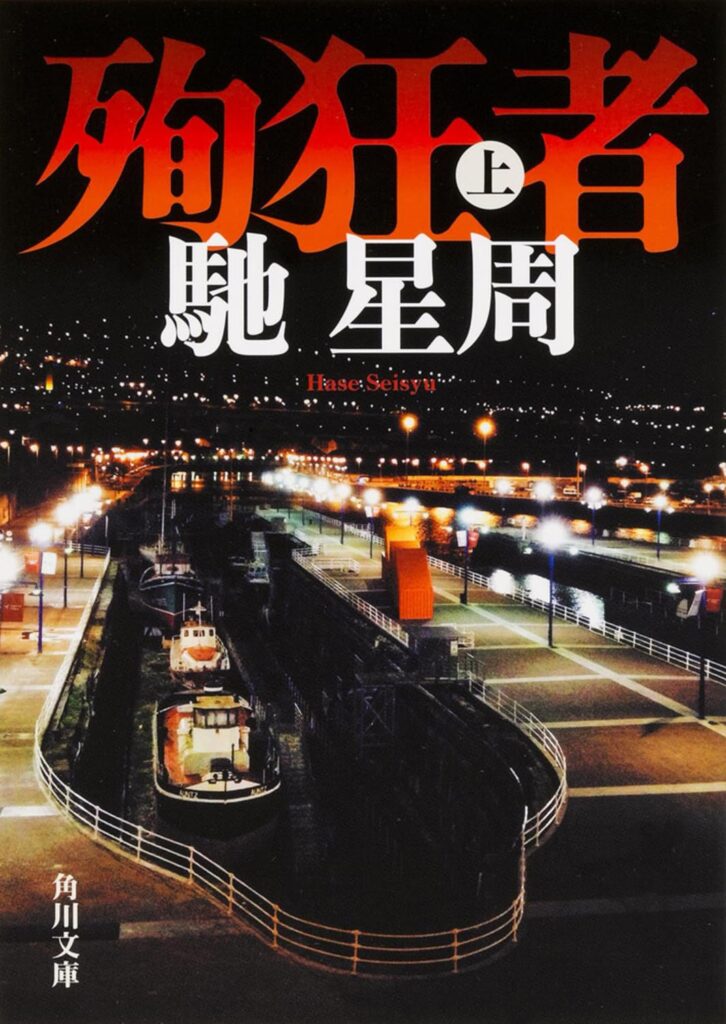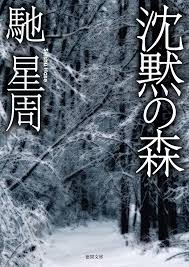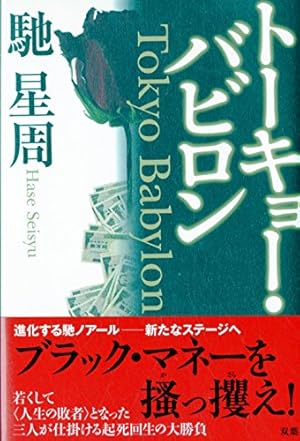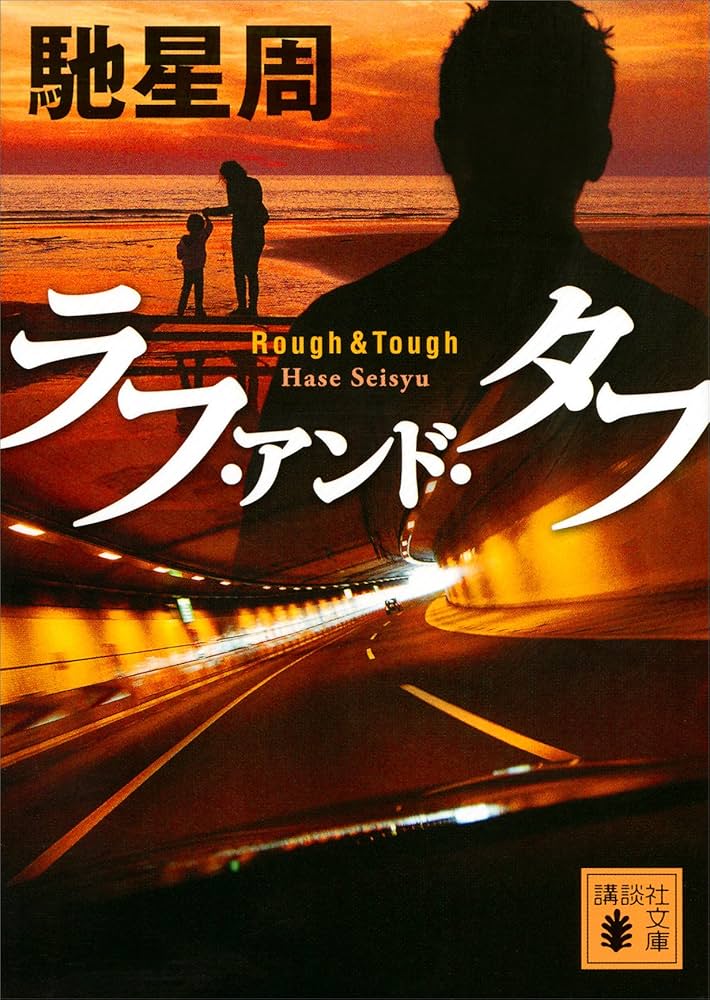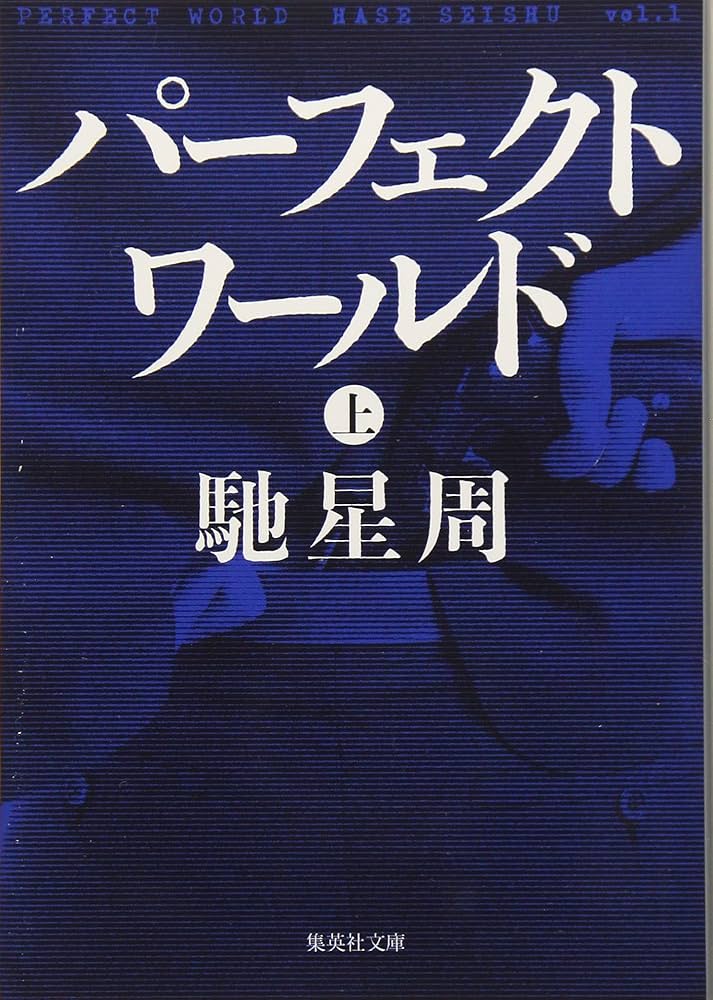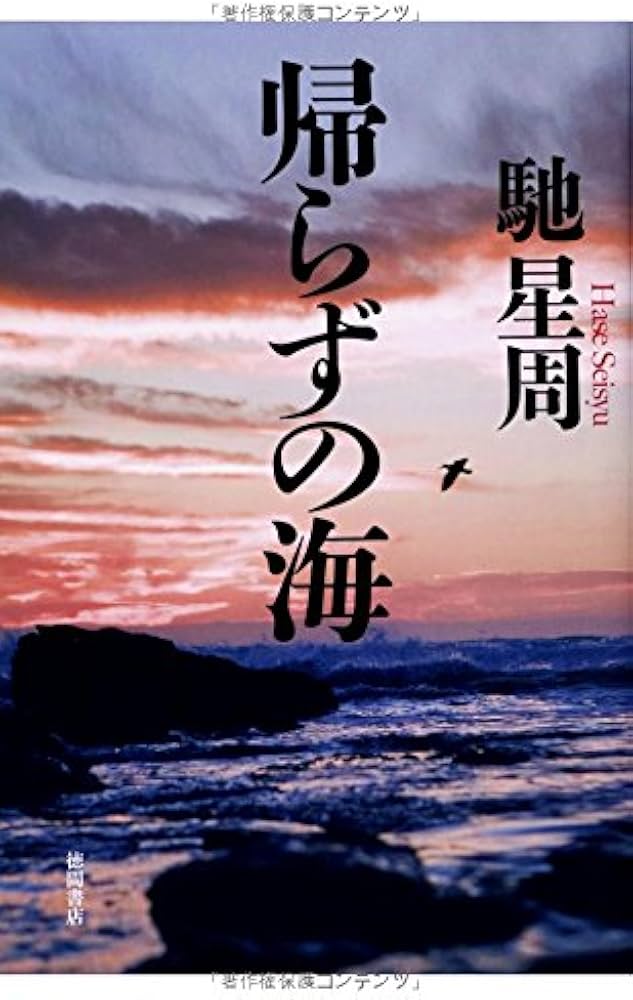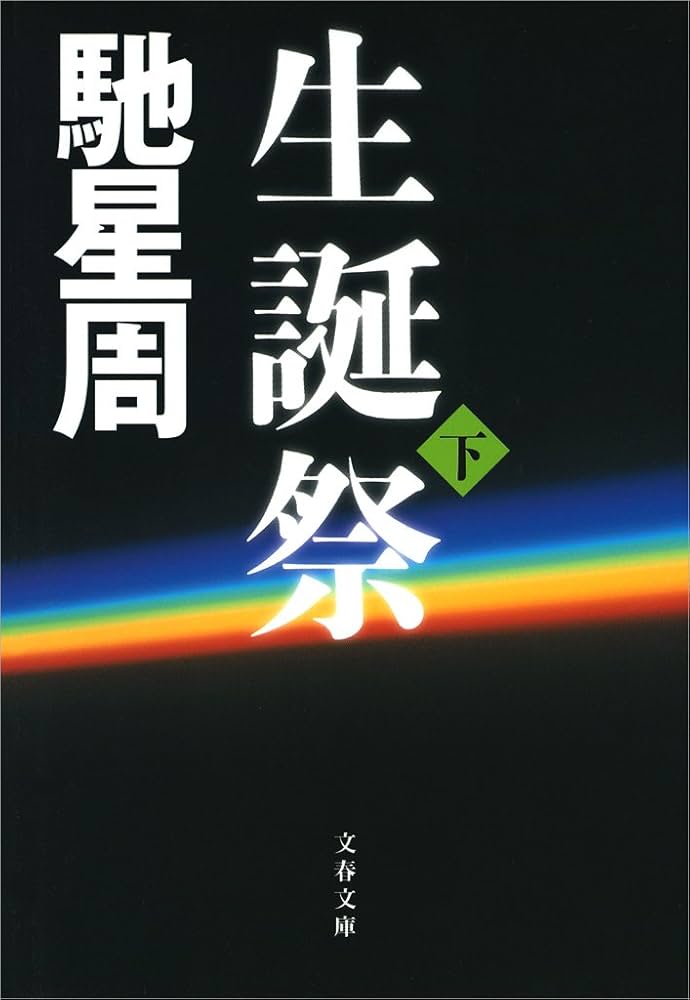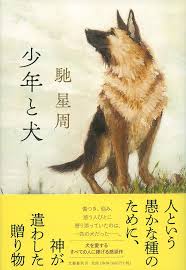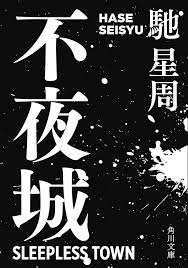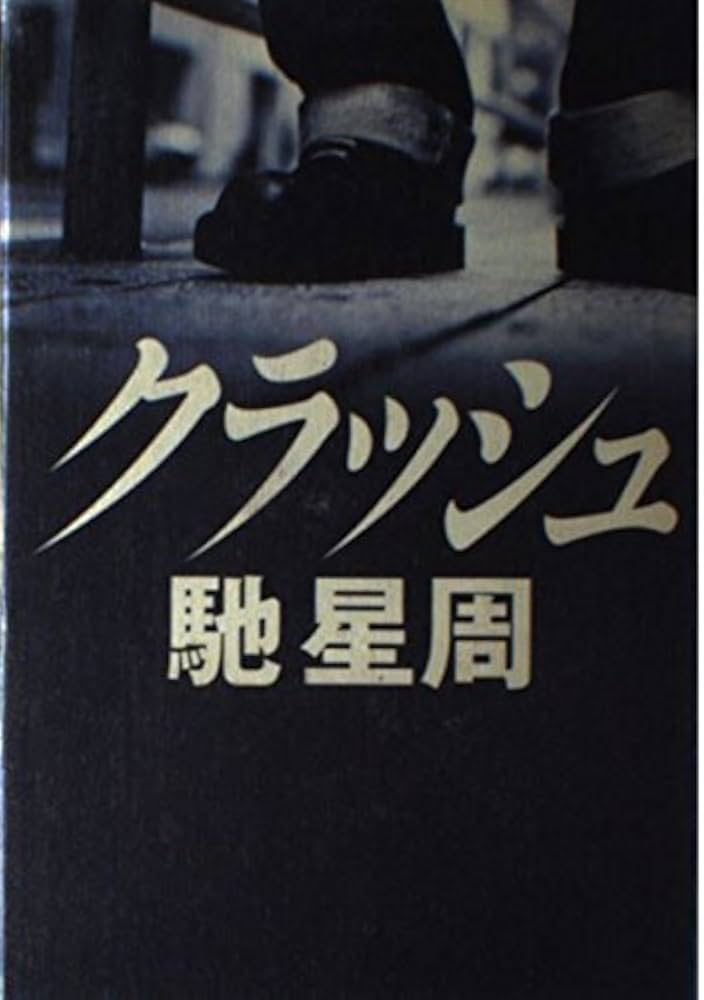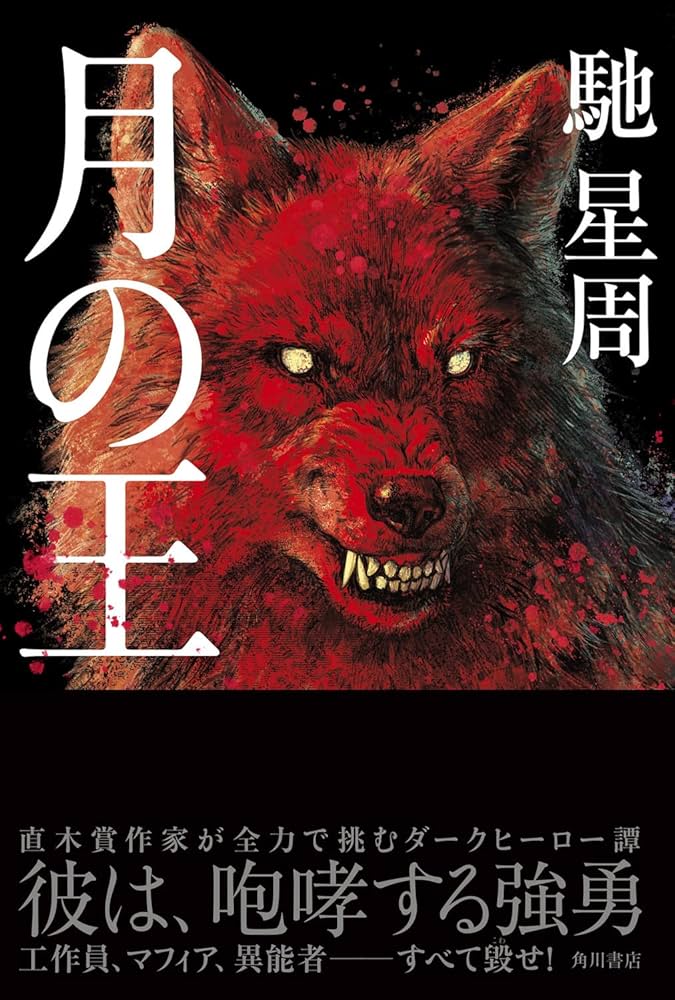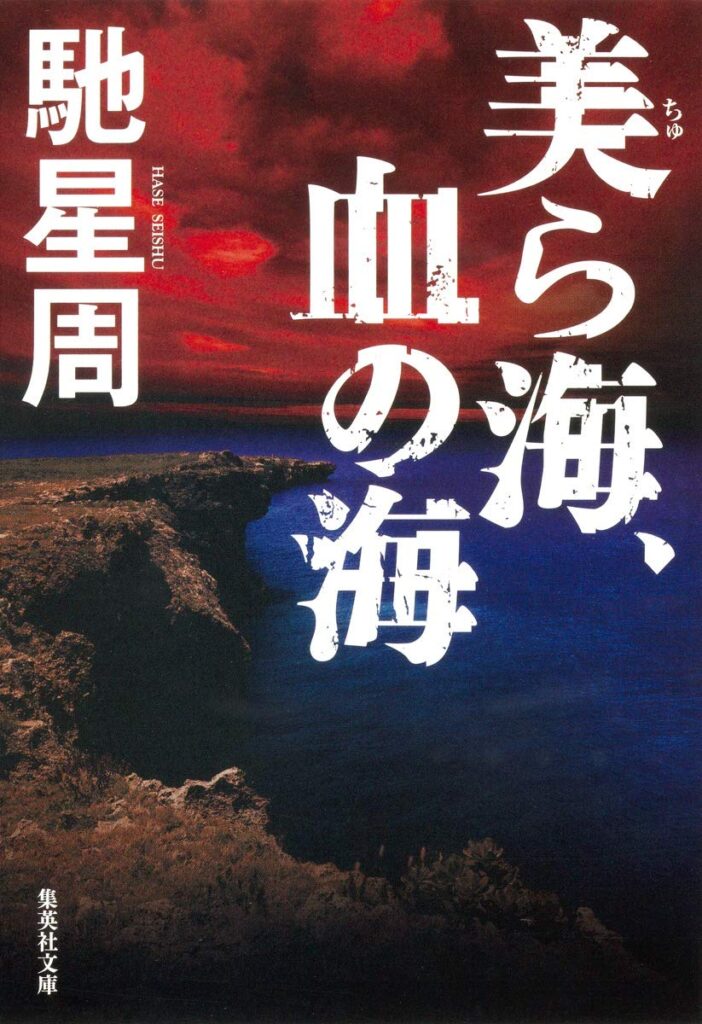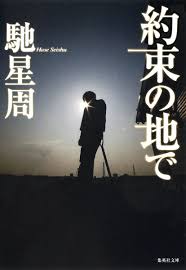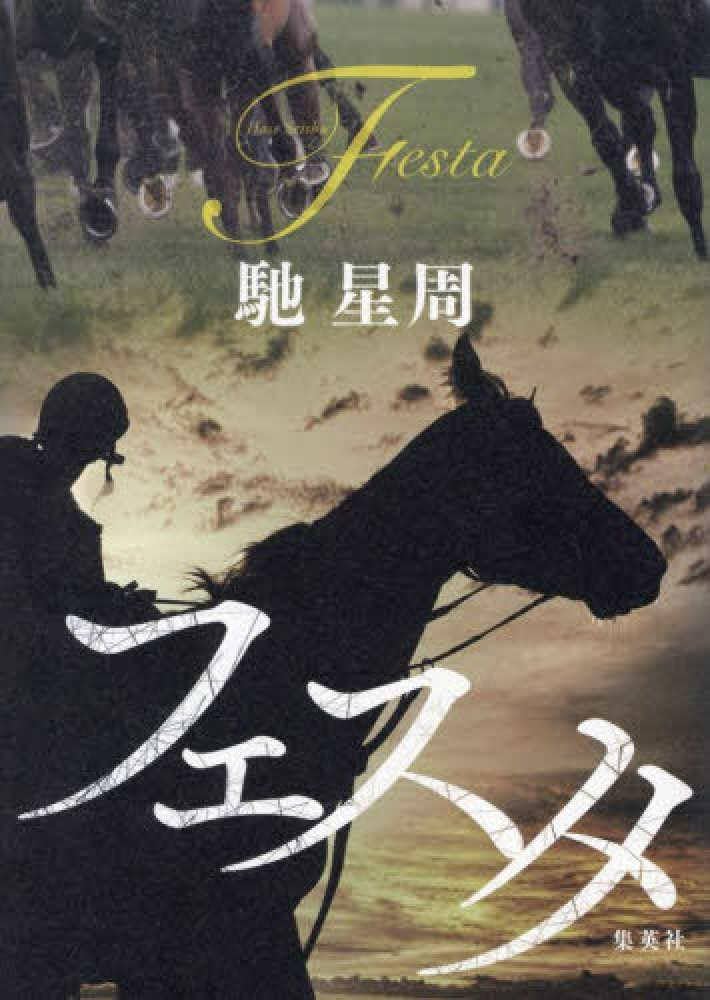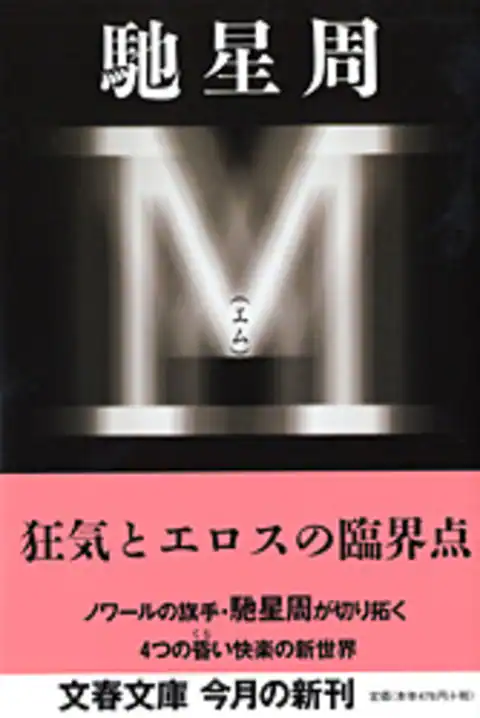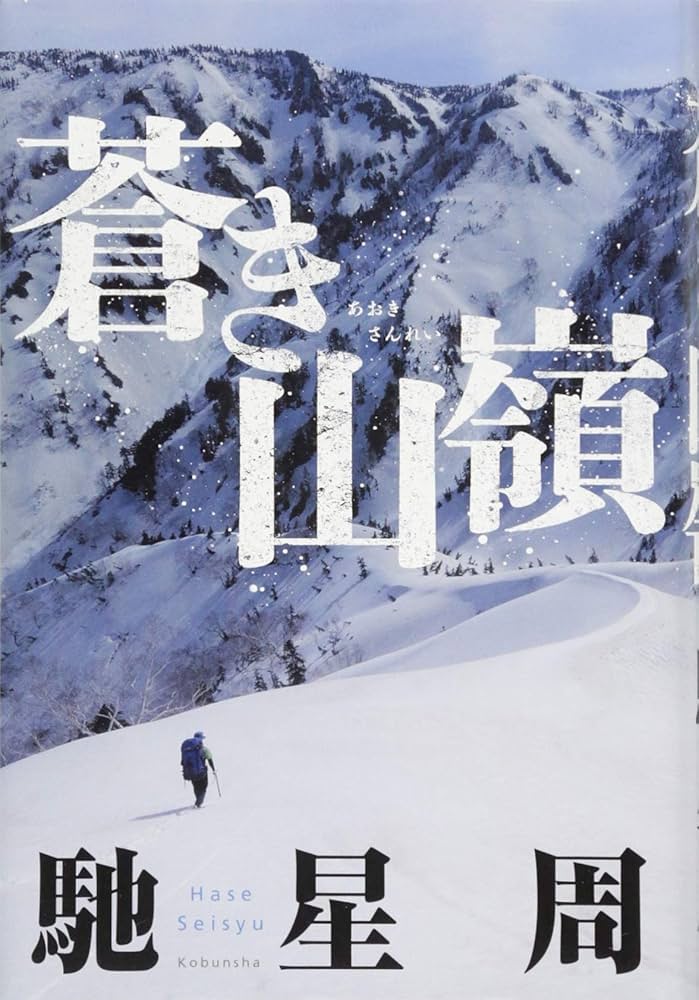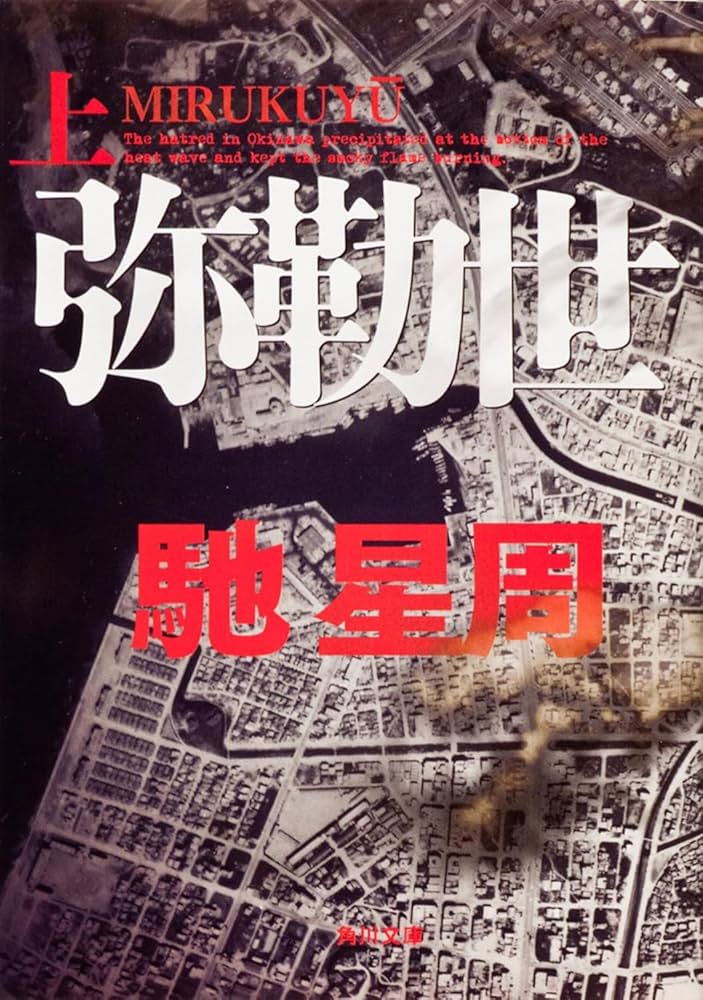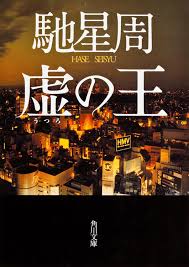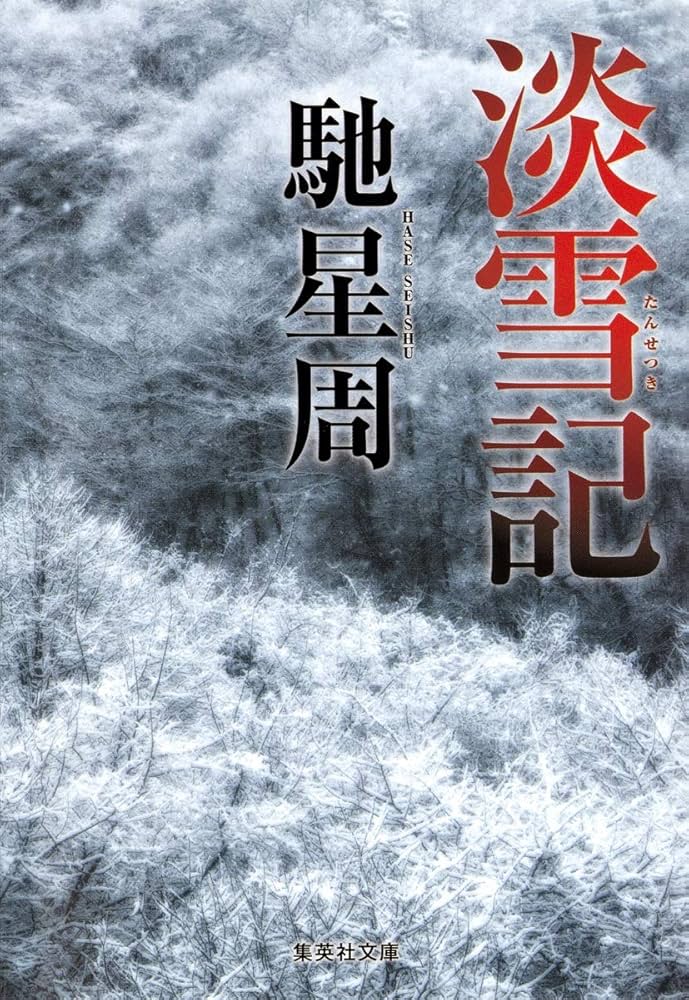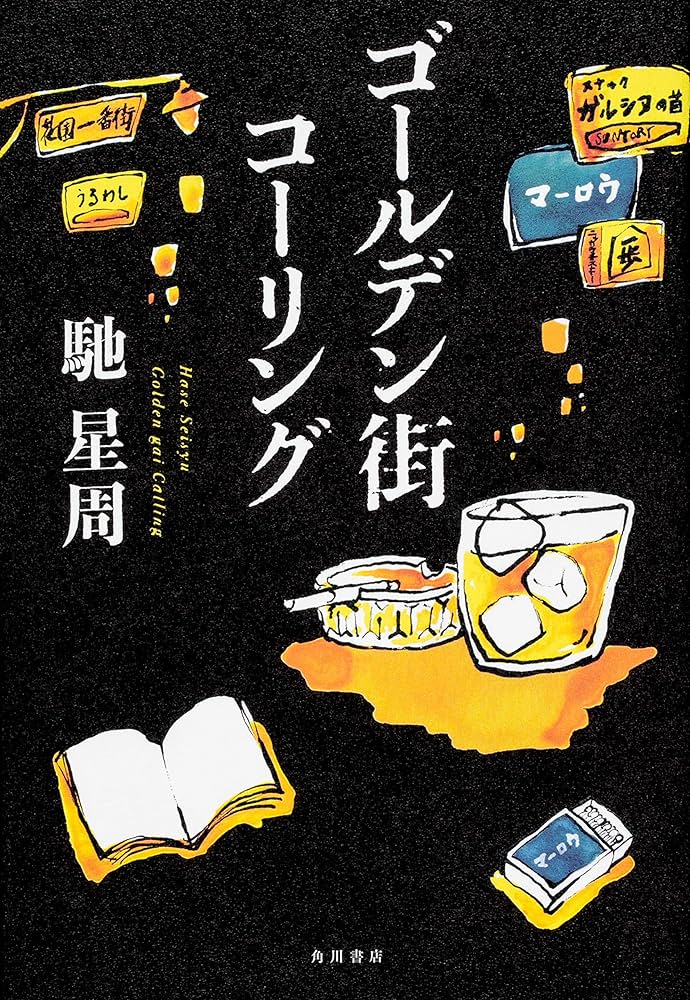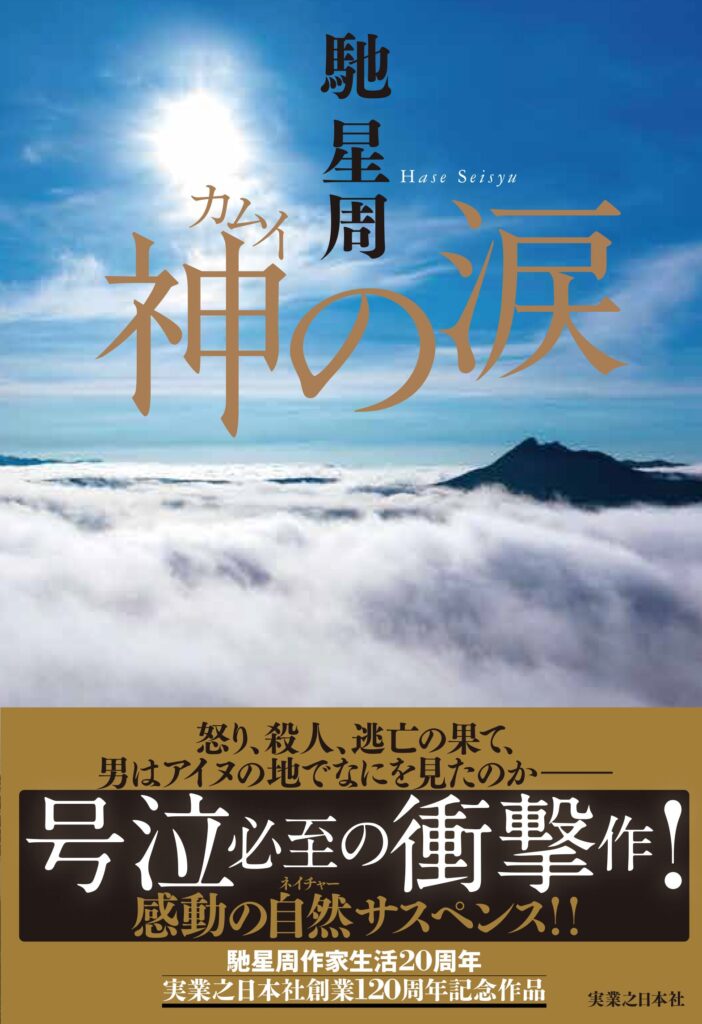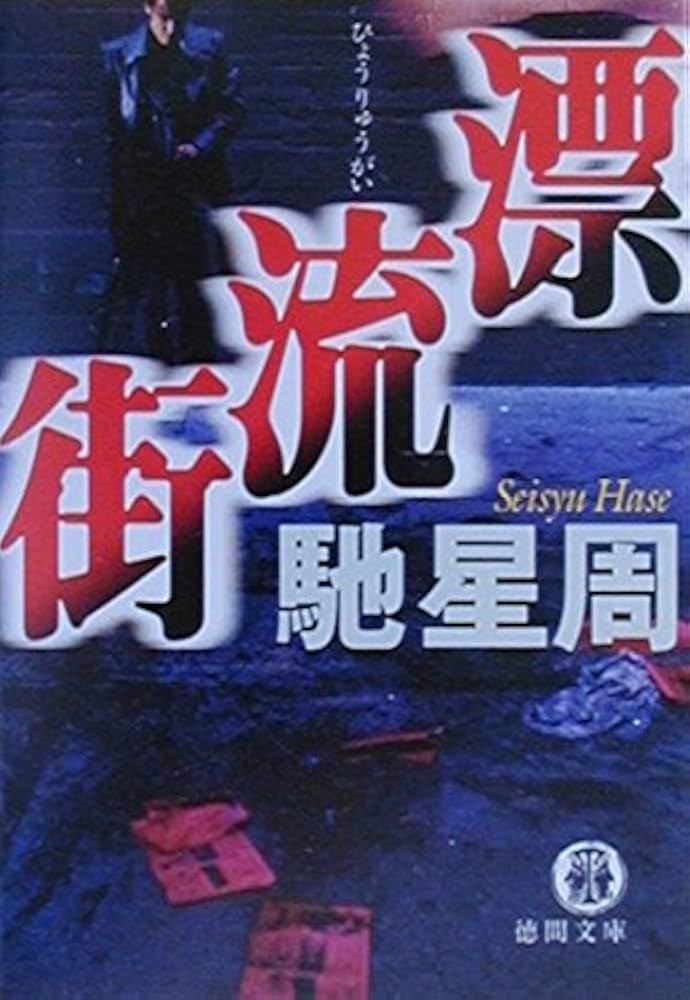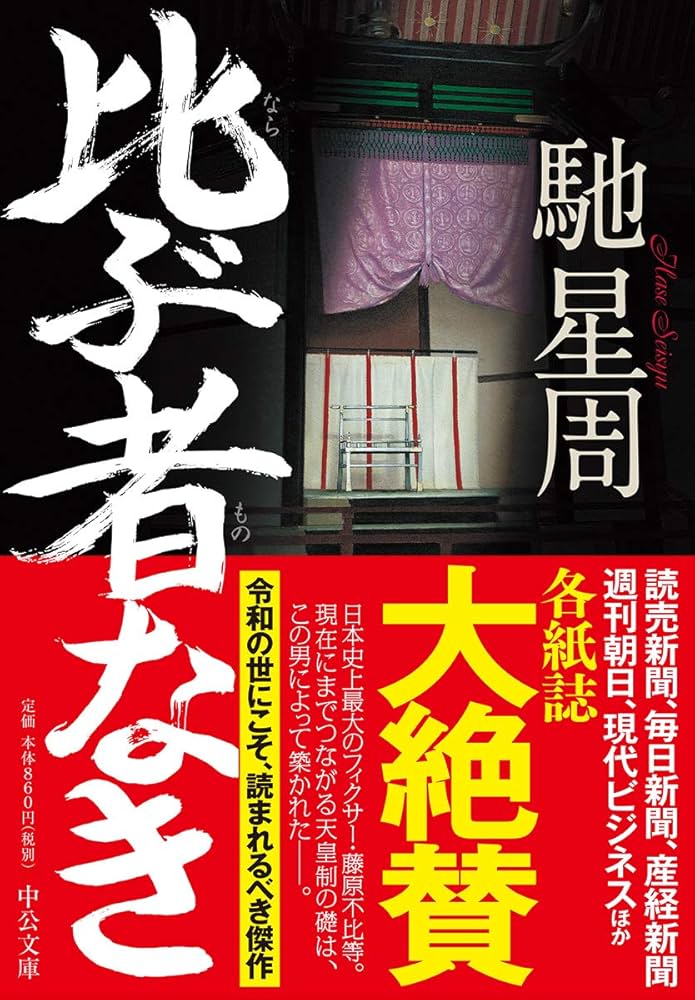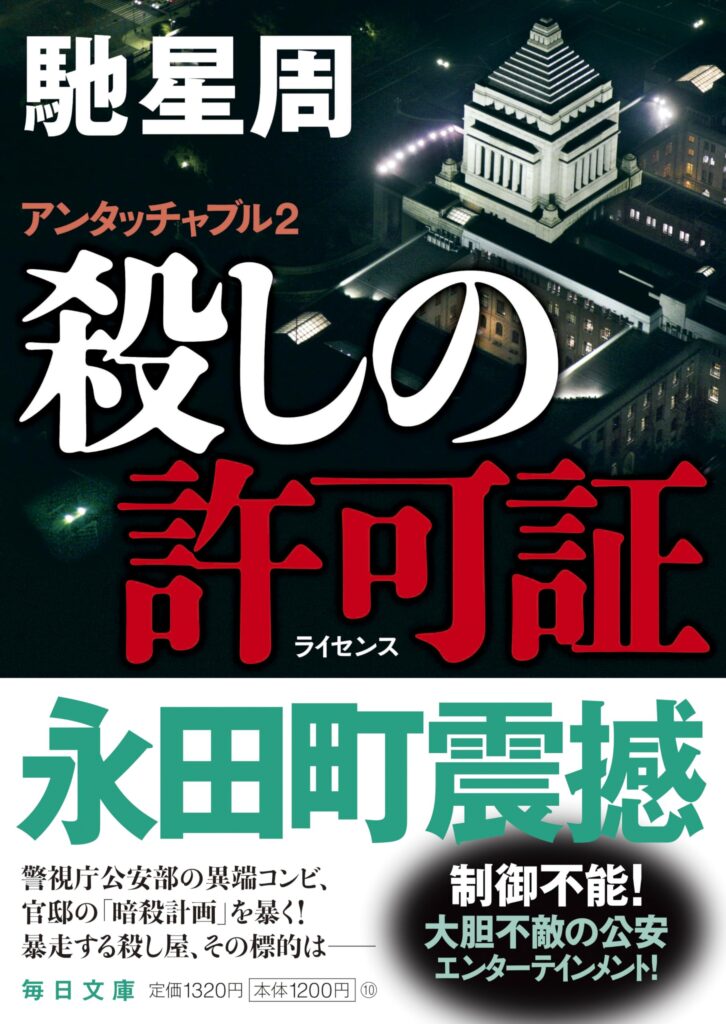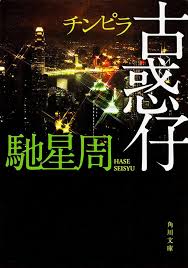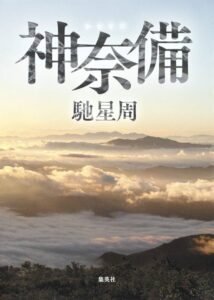 小説「神奈備」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「神奈備」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
馳星周さんの作品といえば、裏社会を舞台にしたノワール小説の旗手という印象が強いかもしれません。しかし、この「神奈備」という作品は、その舞台を雄大かつ過酷な自然、雪山に移し、人間の根源的な問いと魂の救済を描いた、まさに圧巻の一作と言えるでしょう。
物語は、あまりにも絶望的な状況に置かれた一人の少年が、神に会うために冬の御嶽山を目指すところから始まります。この記事では、彼の壮絶な旅路と、彼を追う男の物語を追いながら、物語の核心に迫っていきます。息を呑むような自然描写と、心を抉るような登場人物たちの感情が、読む者の魂を激しく揺さぶります。
後半では、物語の結末を含む詳細な考察を記しています。もし、まだこの物語を読んでおらず、結末を知りたくないという方がいらっしゃいましたら、ご注意いただければと思います。それでは、心をえぐる傑作、「神奈備」の世界へご案内しましょう。
「神奈備」のあらすじ
物語の始まりは、17歳の少年、芹澤潤が送る、あまりにも悲惨な毎日です。母親の恭子は彼を産んだ瞬間から育児を放棄し、酒と男に溺れる日々。潤はろくな食事も与えられず、母親からは罵声を浴びせられ、その存在自体を否定され続けてきました。彼の心身は、希望という光をすべて奪われた深い闇の中にありました。
そんな潤にとって、唯一の光はロードバイクでした。テレビで見たツール・ド・フランスに魅せられ、新聞配達のアルバイトで貯めたお金で手に入れた自転車だけが彼の世界のすべてでした。しかし、自転車部のある高校への進学というささやかな夢さえも、母親によって無情にも絶たれてしまいます。
すべての望みを失った潤は、自転車で地蔵峠へと向かいます。そこで目の当たりにしたのは、木曽の御嶽山の噴火という、人知を超えた光景でした。その圧倒的な力に、潤は「あれほどの力を持つ山には神がいるはずだ」と確信します。そして、自らの存在理由を問うため、たった一人で、神が坐す山「神奈備」へ向かうことを決意するのです。
一方、その頃、山麓ではベテランの強力(ごうりき)である松本孝が、悪天候のために下山の準備をしていました。彼は山で生きていながら、神の存在など信じない現実主義者でした。そんな彼の元に、潤の母親である恭子から一本の電話が入ります。そして、潤が山へ向かったこと、さらに、その潤が他ならぬ孝の息子であるという衝撃の事実を告げられるのです。
「神奈備」の長文感想(ネタバレあり)
この「神奈備」という物語が読後に残す感情は、安易な言葉で表現することがためらわれるほど、重く、そして深く、魂に刻み込まれるものです。これは単なる山岳小説ではありません。馳星周さんという作家が、極限状況における人間の「救い」とは何か、その本質をえぐり出した、哀切な祈りのような物語だと感じました。
まず語らなければならないのは、主人公である芹澤潤の置かれた、あまりにも過酷な状況でしょう。彼の母親である恭子が行う仕打ちは、「毒親」という言葉ですら生ぬるく感じるほど凄惨です。育児放棄は当たり前、食事は菓子パンとジュースのみ。絶え間ない罵声によって、潤の自尊心は根こそぎ奪われていきます。彼の人生は、生まれてきたこと自体が罰であるかのような、出口のない絶望に満ちています。
その暗闇の中に見出した、ロードバイクという一条の光。それは潤にとって、生きるための、本当にささやかな希望でした。しかし、母親はその光さえも許しません。高校進学を諦めさせ、工場で働くことを強制する。この瞬間、潤の世界と社会とをつなぐ最後の糸は、ぷっつりと断ち切られてしまったのです。
ここで潤が向かうのが、御嶽山です。彼の目の前で起きた噴火という天変地異は、常人にとっては恐怖の対象でしかありません。しかし、すべてを奪われた潤にとって、その人知を超えた破壊的な力は、むしろ「神」の存在を確信させる啓示となります。彼の信仰は、体系的な教義に基づくものではなく、自らを虐げる母親という理不尽な力を超える、さらに強大な存在への渇望から生まれた、あまりにも切実なものでした。
そして、物語はもう一人の主人公、松本孝を登場させます。彼は山を生業としながら、噴火で多くの命が奪われる現実を見てきたがゆえに、神の存在を信じないリアリストです。潤の物語が天上の神性を求める旅であるとするならば、孝の物語は、唾棄すべき過去という地上の現実に引きずり込まれる追跡劇と言えるでしょう。
恭子からの一本の電話は、孝の平穏を根底から覆します。潤が自分の息子かもしれない、という衝撃の事実。彼女は過去の過ちを盾に、孝に捜索を強要します。孝が嵐の御嶽山へと足を踏み入れる動機は、父性愛という美しい感情ではありません。それは、山に生きる者としての職業倫理、過去への責任、そして未知の息子への戸惑いが入り混じった、極めて人間的な葛藤の結果なのです。
ここに、この物語の構造の巧みさが光ります。神という名の「父」を求めて雪山を登る少年。その少年を、神の存在を否定する生物学上の「父」が追う。彼らは互いの本当の関係性を知らぬまま、嵐が吹き荒れる山という舞台で、一直線に破滅へと向かっていくのです。この設定自体が、一つの巨大な悲劇を内包しています。
物語の中盤からは、潤と孝、二人の視点が交互に描かれ、緊張感は極限まで高まっていきます。舞台となるのは、二つ玉低気圧が猛威を振るう、わずか一昼夜。ここで描かれる御嶽山は、美しい自然などではありません。猛吹雪とホワイトアウトで、登場人物たちの命を執拗に脅かす、敵意に満ちた存在として描かれています。山は、第三の主人公なのです。
潤の登山は、ほとんど殉教者のようです。貧弱な装備で、あえて最悪の天候に挑むのは、その真摯さこそが神に届く道だと信じているからです。低体温症と疲労で朽ちていく肉体と、それでもなお山頂を目指す彼の純粋で狂気的な精神力との対比が、読んでいて胸を締め付けます。
対照的に、孝の追跡行は、自然の猛威に立ち向かう人間の技術と経験の記録として描かれます。しかし彼の内面では、神への不信と、見ず知らずの少年への奇妙な共感、そして彼が本当に息子であったならという恐怖が、常に渦巻いているのです。彼の経験と知識が、皮肉にも潤の存在を少しずつ捉えていきます。
この物語の白眉は、なんと言っても、幾度となく繰り返される「すれ違い」の描写でしょう。猛烈な吹雪と視界を奪うガスの中、二人は時にほんの数メートルの距離まで近づきながら、互いの存在に気づくことができません。同じ嵐の中、同じ苦しみを味わいながら、二つの孤独な魂は、決して交わることがない。これは、追いつ追われつのサスペンスではなく、二つの魂が並行して苦悶する様を描いた、壮絶な叙事詩なのです。
そして、この「すれ違い」は、単なる偶然の産物ではありません。それを引き起こしているのは、吹雪であり、ホワイトアウトであり、つまりは山そのものです。父と子の出会いを阻む、巨大で冷徹な神の実体。人間の祈りや絶望などには一切関知せず、ただ物理法則に従ってそこに存在するだけ。二人の悲劇は、その無慈悲なまでの公平さがもたらした、必然の結果として描かれます。
物語は、誰もが予想し、そして心のどこかで願っていたであろう結末を、無残に裏切ります。潤は山頂を目前にして、ついに力尽きます。彼の肉体的な旅は、ここで終わりを迎えるのです。
しかし、その死の淵で、潤の意識は一つの奇跡を捉えます。それは、一羽の雷鳥の姿でした。山岳信仰において神の使いともされる鳥。それが本当に神の啓示だったのか、あるいは低酸素状態が見せたただの幻覚だったのか。物語は、その答えを明確には示しません。
ですが、この幻視は潤に、絶対的な安らぎと許しをもたらしました。彼は、自分を虐待し続けた母親を、その最期の瞬間に許すのです。これこそが、彼が命を懸けて探し求めていた問いへの答えであり、彼が自らの力でたどり着いた、真の山頂でした。潤は、幸福感に包まれながら、静かに息絶えます。
その直後、ついに孝が潤を発見します。潤の父となる決意を固め、嵐を乗り越えてきた彼が見たものは、救うべき息子の姿ではなく、すでに冷たくなった亡骸でした。読者が待ち望んだであろう父子の対面と和解というカタルシスは、永遠に訪れません。この「間に合わなかった」という結末は、一般的な物語の約束事を根底から覆す、あまりにも痛切なものでした。
物語は、潤の安らかな死で幕を閉じるのではなく、生き残った孝の、底なしの絶望と共に終わります。一度も言葉を交わせなかった息子の亡骸を抱きしめ、ただ立ち尽くす彼の胸に去来するのは、取り返しのつかない後悔、「無念」という感情でした。この、救いようのない感情こそが、物語が読者の心に残す、最も重い余韻なのです。
結局、潤は孝によってではなく、自分自身の力によって「救われた」のです。それは肉体的な死と引き換えに得られた、精神的な救済でした。死んだ少年は安らぎを得て、生き残った男は癒えることのない傷を負う。この「神奈備」は、救済というものが、必ずしも生者のためにあるのではないという、残酷で深遠な真理を突きつけます。
馳星周さんはこの作品で、「山岳ノワール」という新たな境地を切り開きました。悲劇的な結末が避けがたい運命として描かれる宿命論的な色合い、心に傷を負った登場人物たち、そして彼らを翻弄する敵対的な自然。そこには、冷酷な世界における存在意義を問う、実存的な絶望が満ちています。これは、神の沈黙する広大な世界で、それでも救いを求める人間の魂の叫びを描ききった、忘れがたい傑作です。
まとめ
馳星周さんの「神奈備」は、単に手に汗握る山岳冒険小説という枠には到底収まらない、深遠なテーマを内包した作品でした。絶望の淵にいた少年が求める「救い」と、彼を追う男が直面する「現実」が、過酷な冬山を舞台に交錯します。
物語を通して描かれるのは、神の存在をめぐる問いかけです。しかし、作者は安易な答えを与えてはくれません。神を信じる者も、信じない者も、等しく自然の猛威の前に無力です。その中で、人が最後に何を見出し、何を得るのか。その問いが、重く心に響きます。
結末は、多くの読者が想像するものとは異なり、決して甘いものではありません。むしろ、胸が張り裂けるような無念と哀しみが残ります。しかし、その痛みこそが、この物語が傑作であることの証左でもあるのです。人間の存在の脆さと、それでもなお求める魂の尊厳が、胸に迫ります。
もしあなたが、心を揺さぶられ、読んだ後しばらく立ち上がれないような、強烈な読書体験を求めているのであれば、この「神奈備」を手に取ってみることを強くお勧めします。きっと、忘れられない一冊になるはずです。