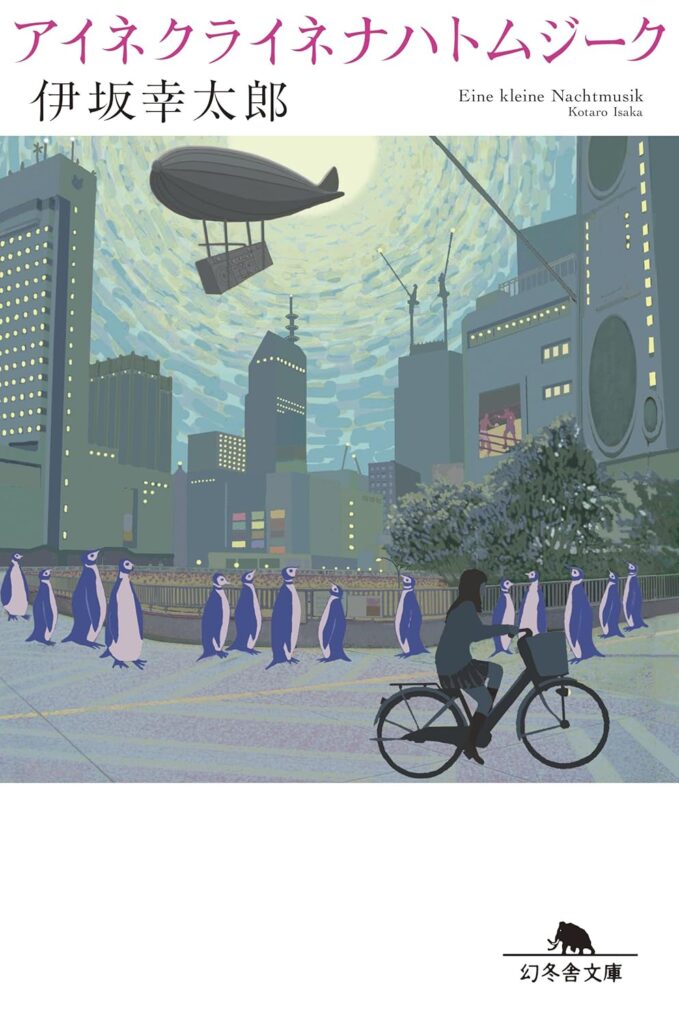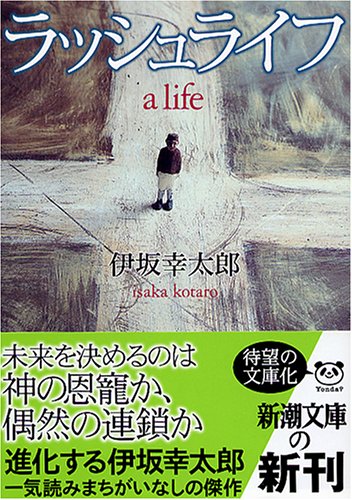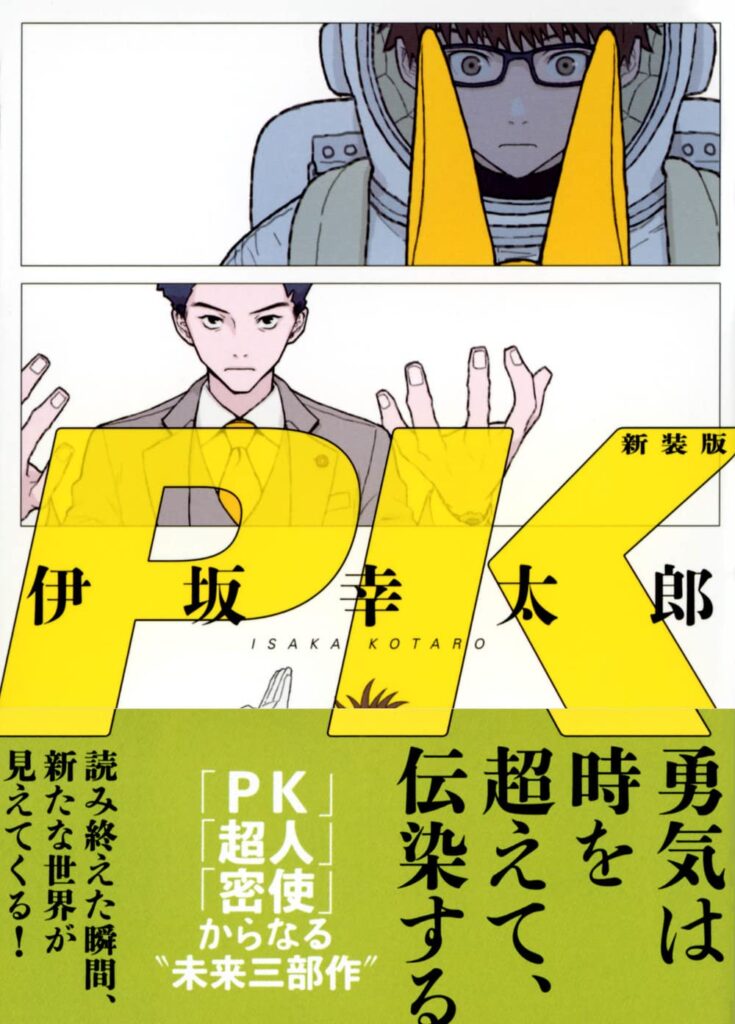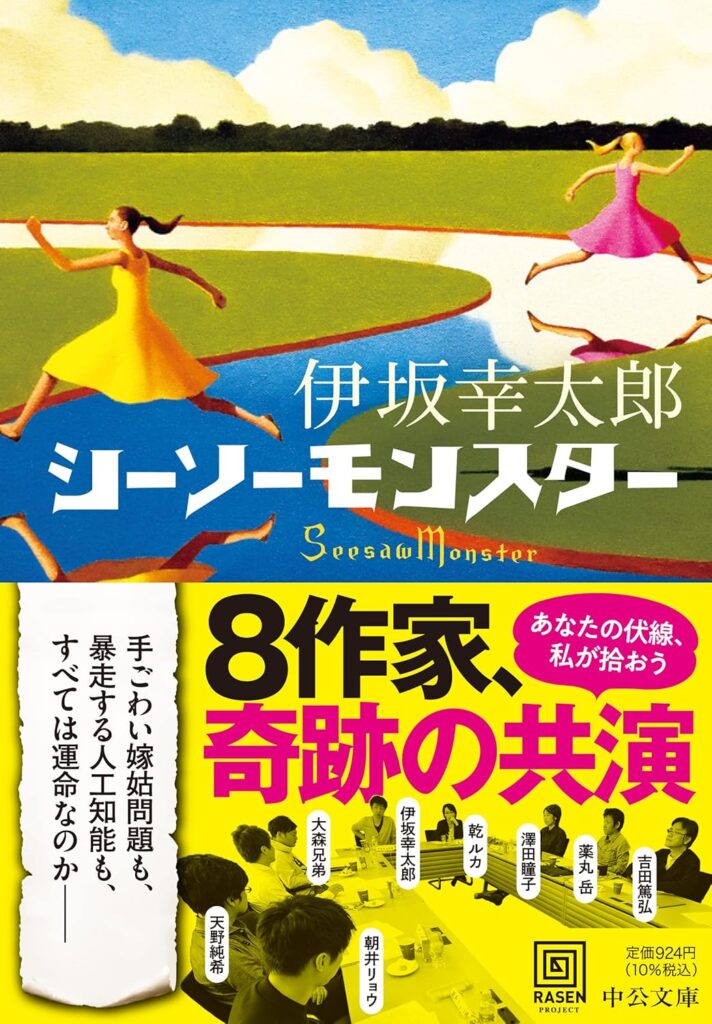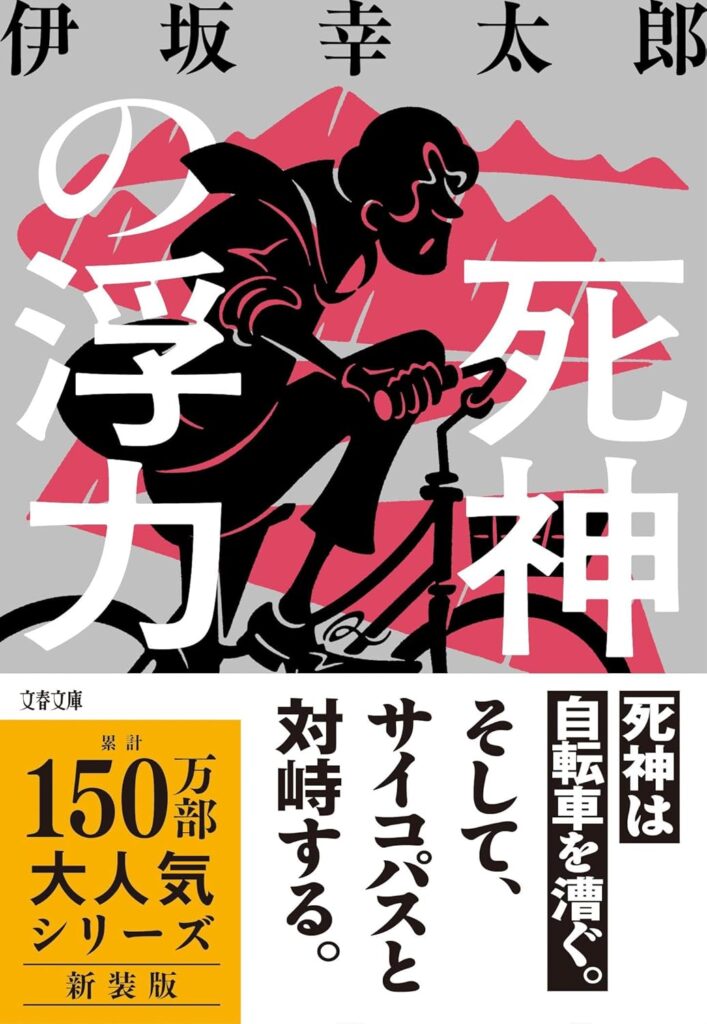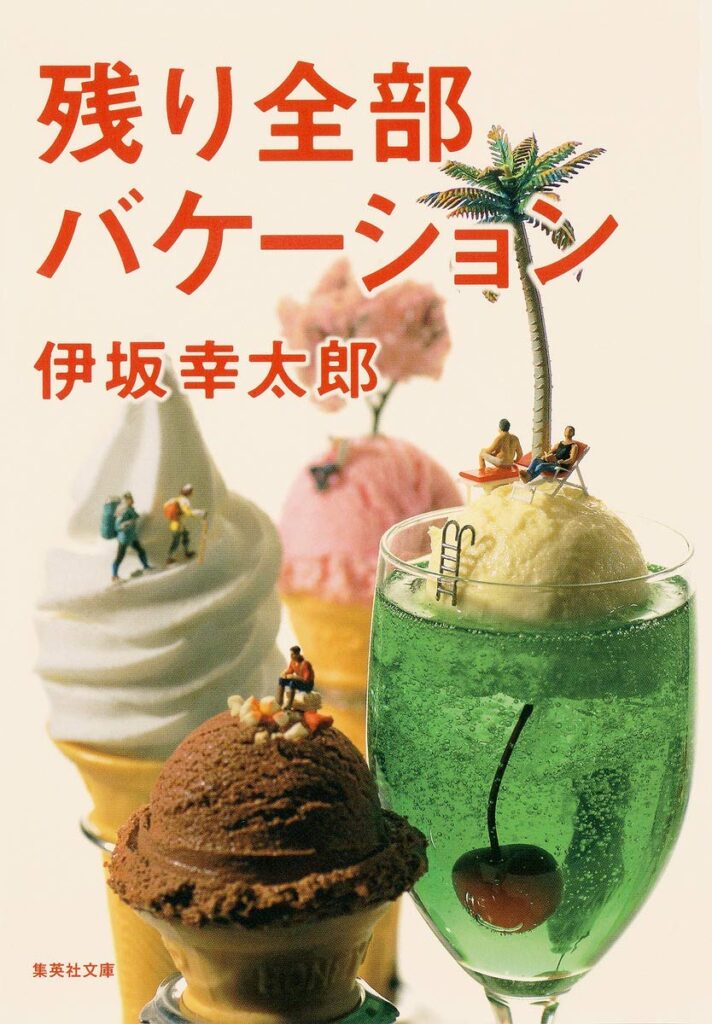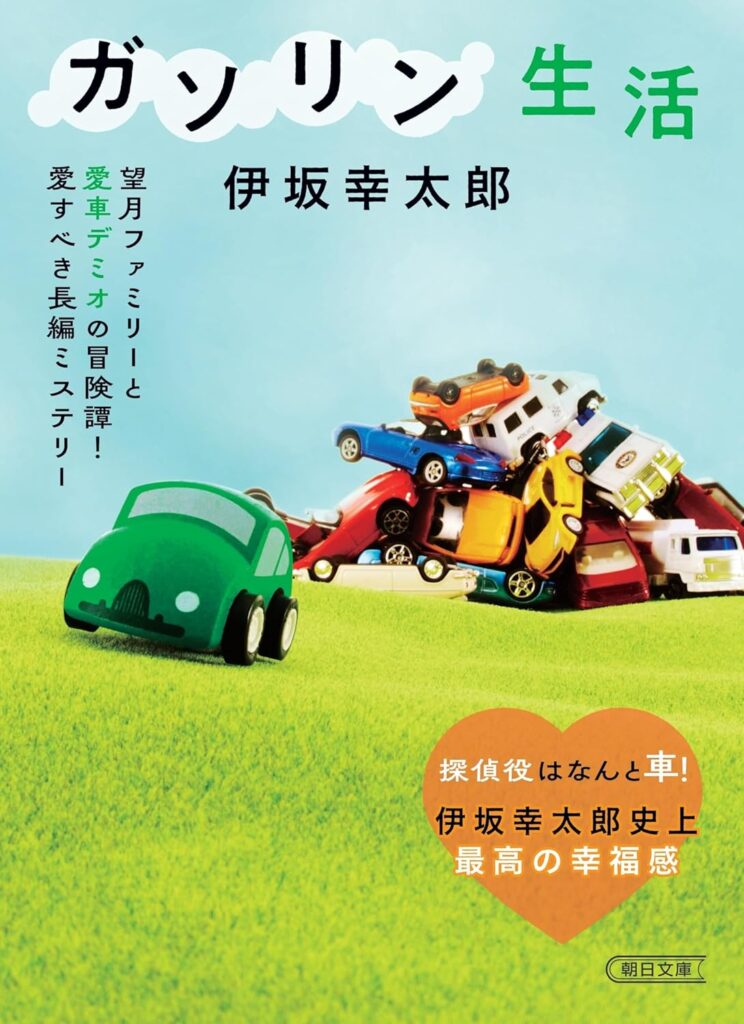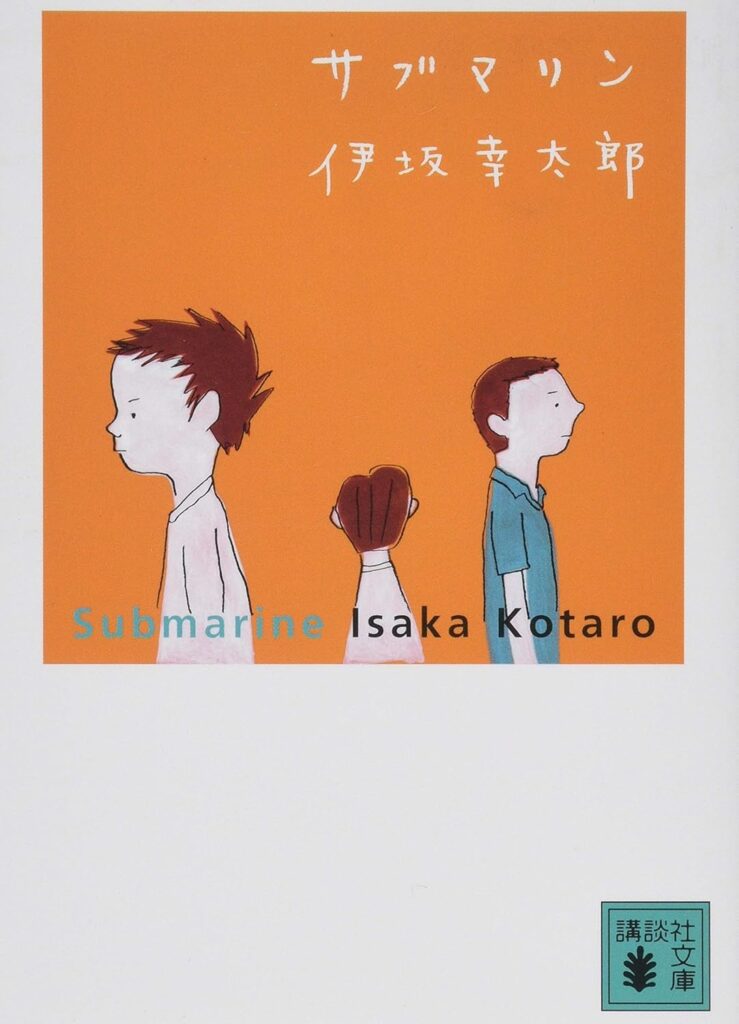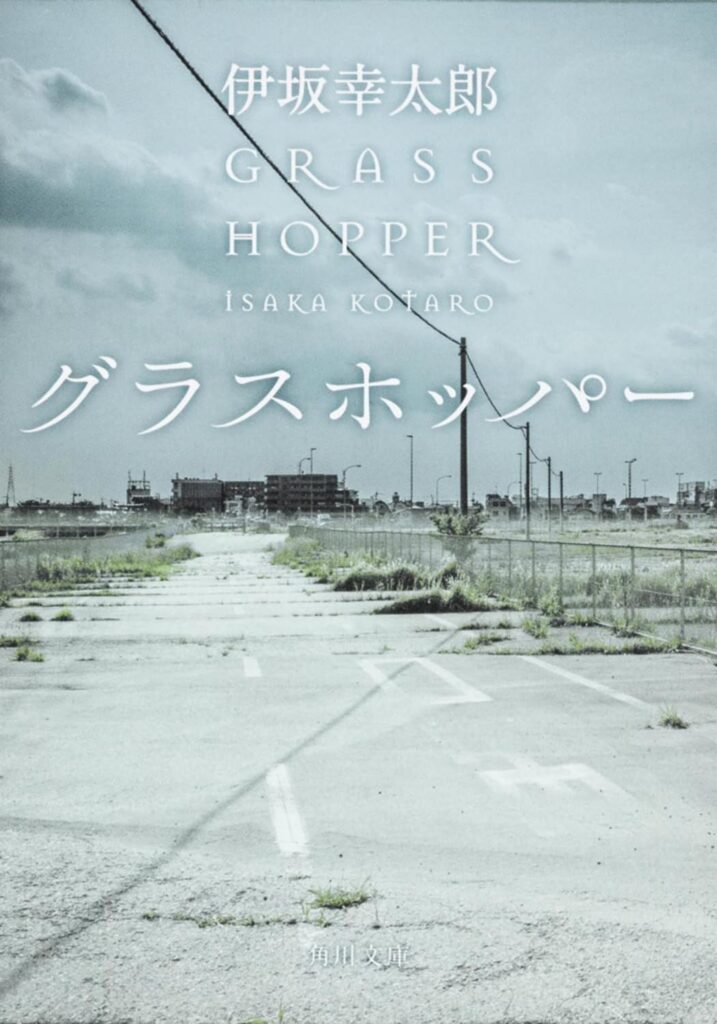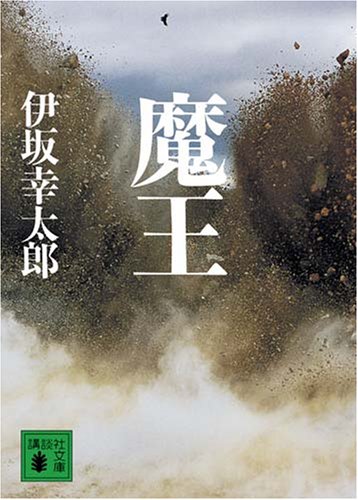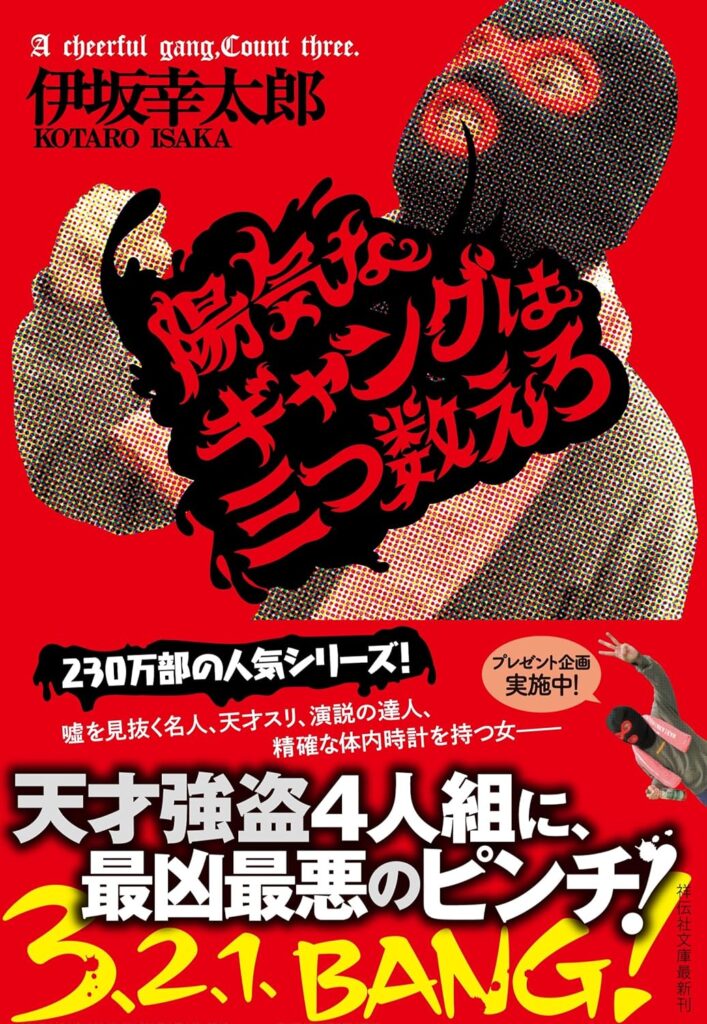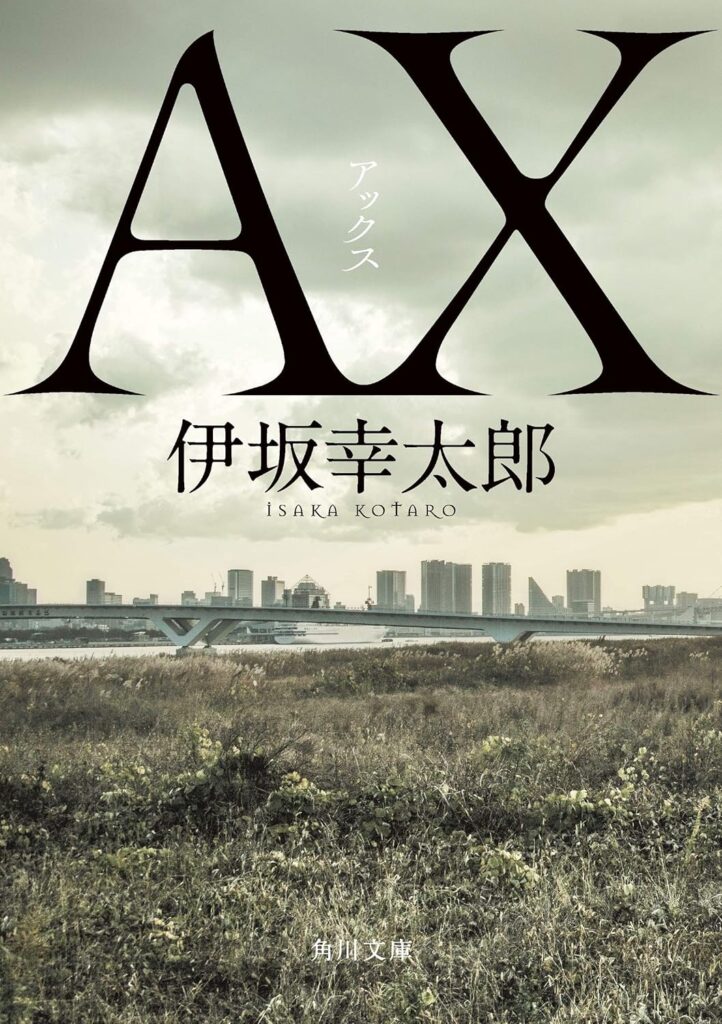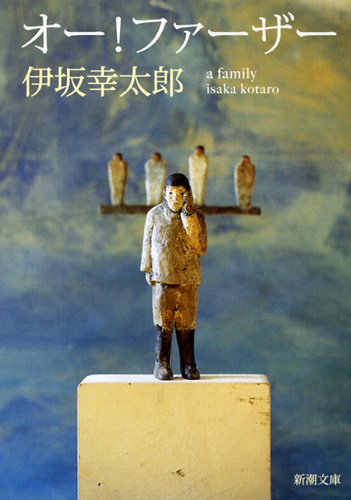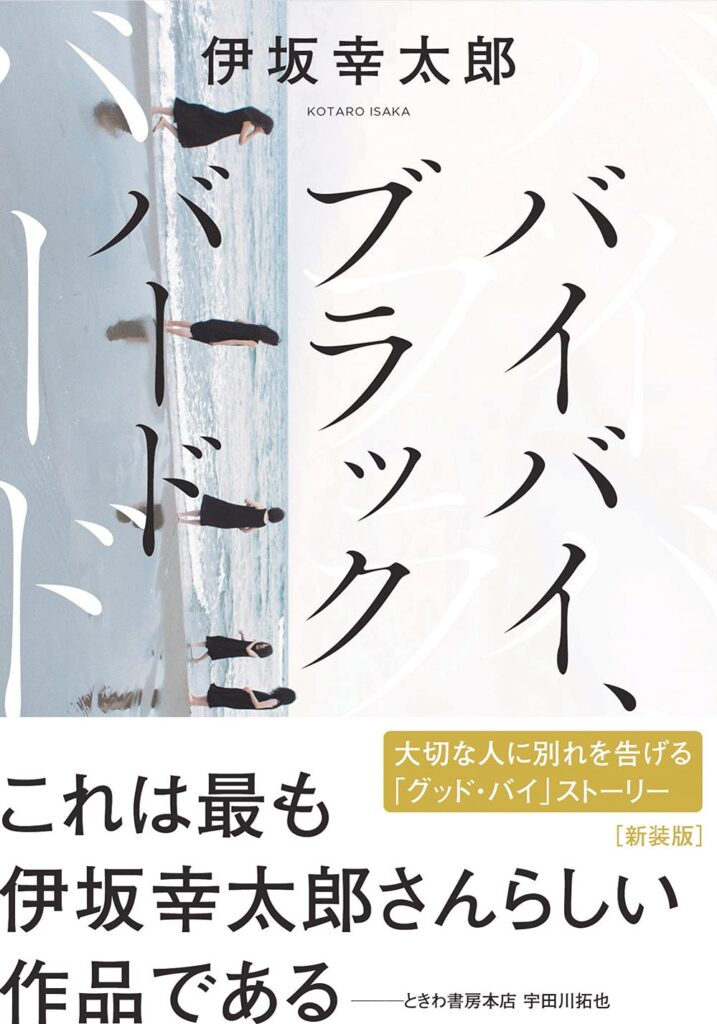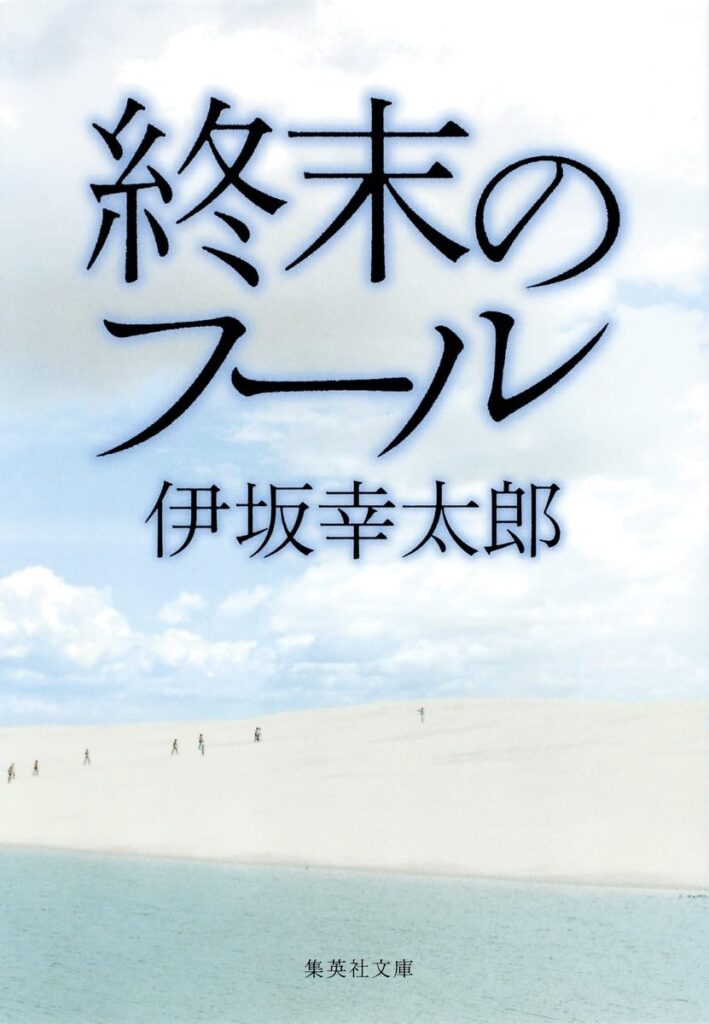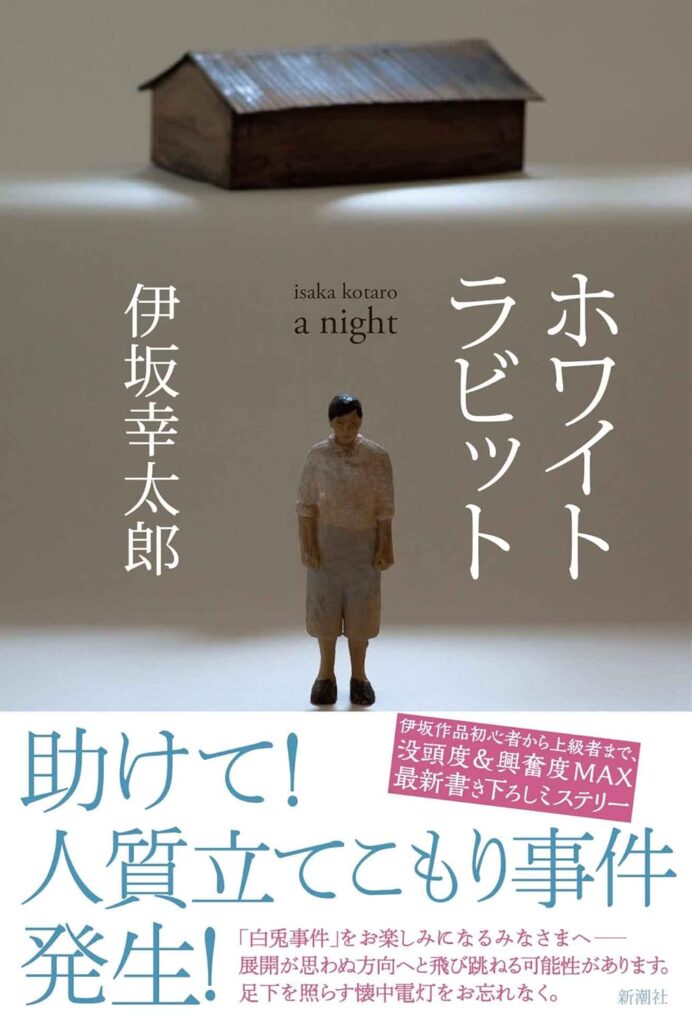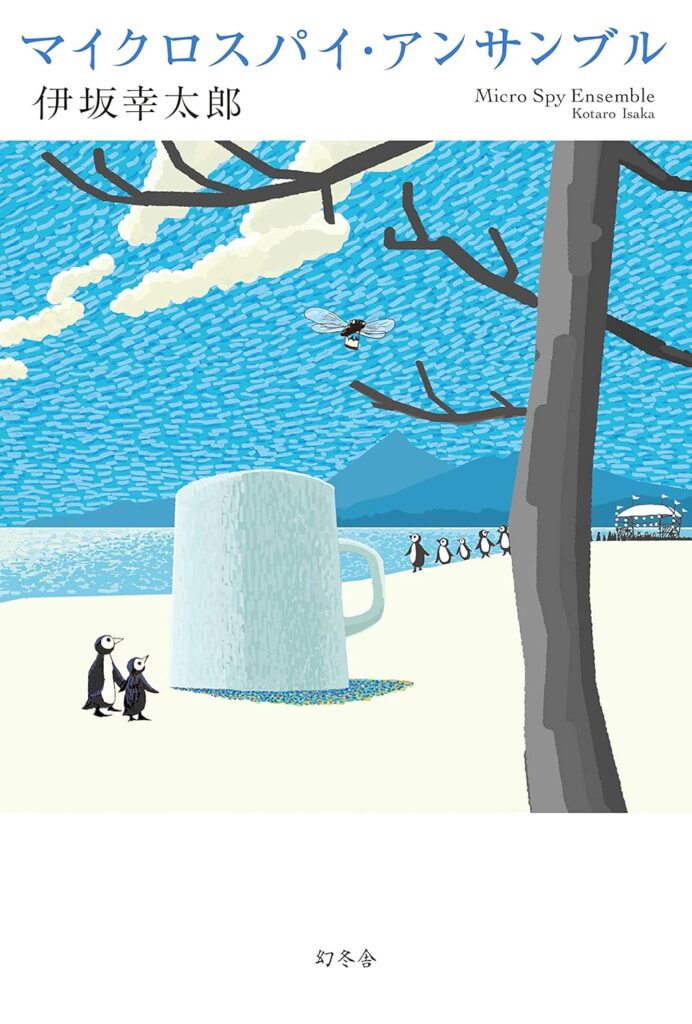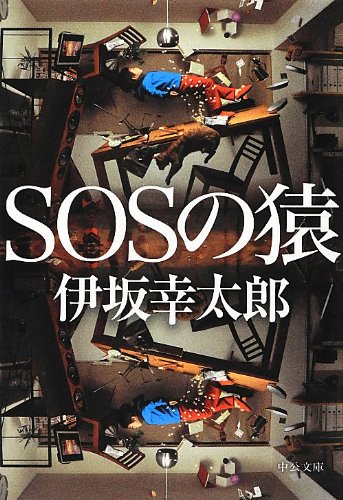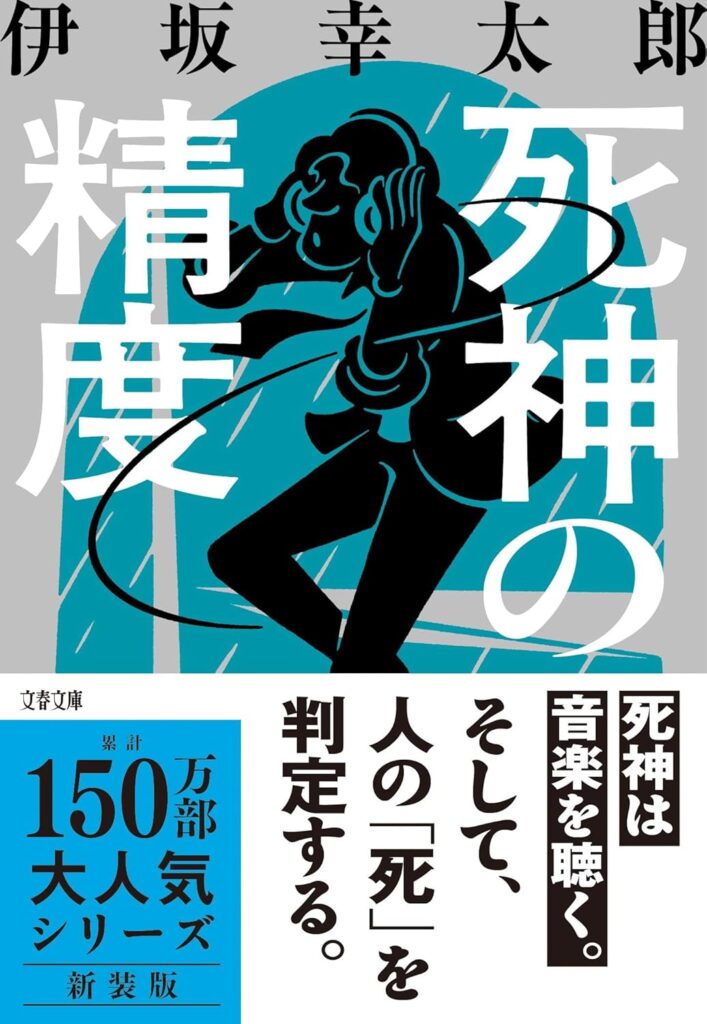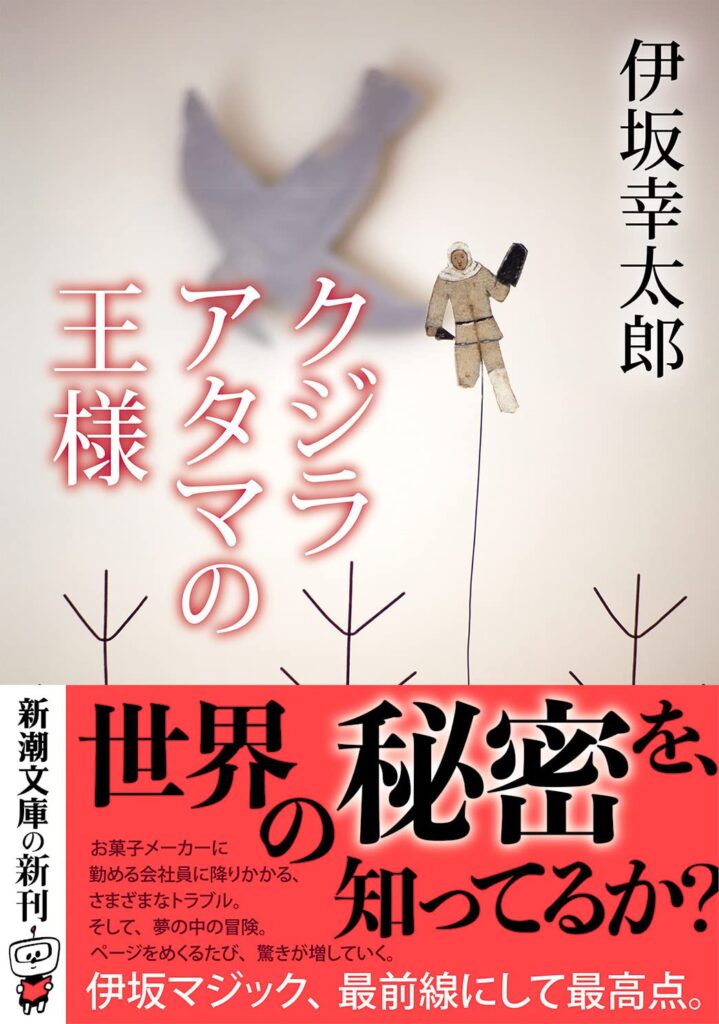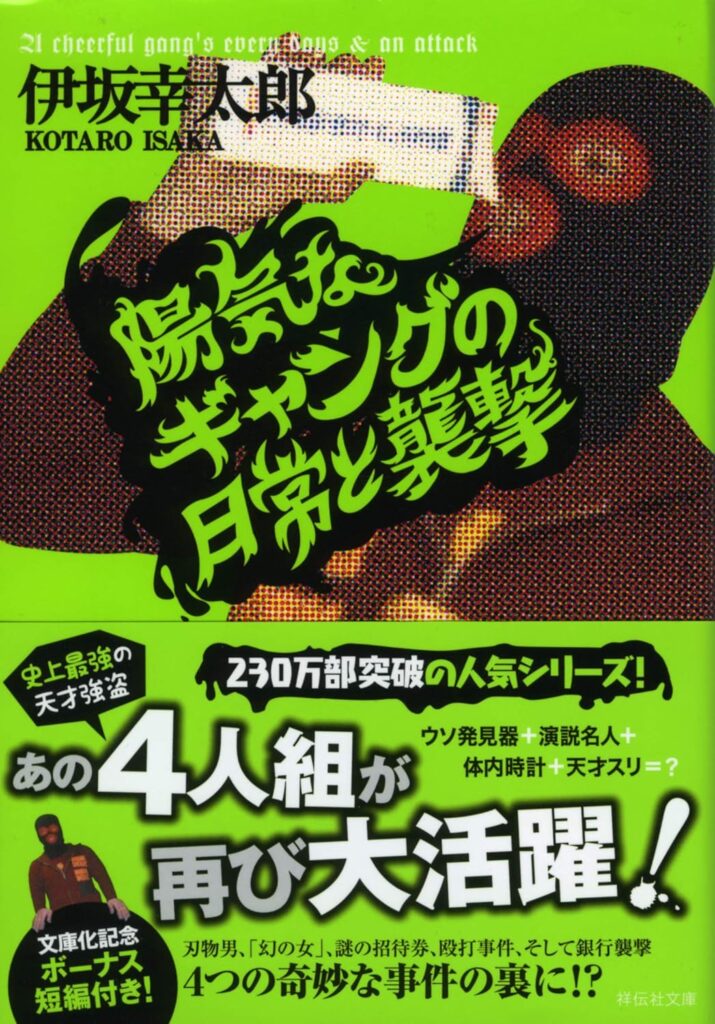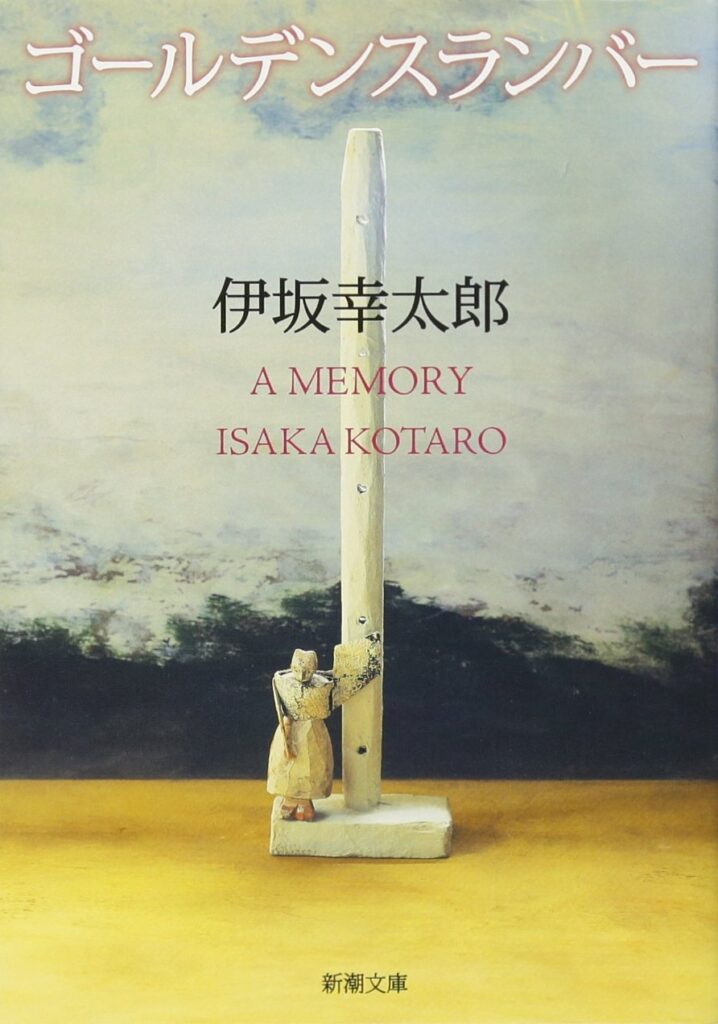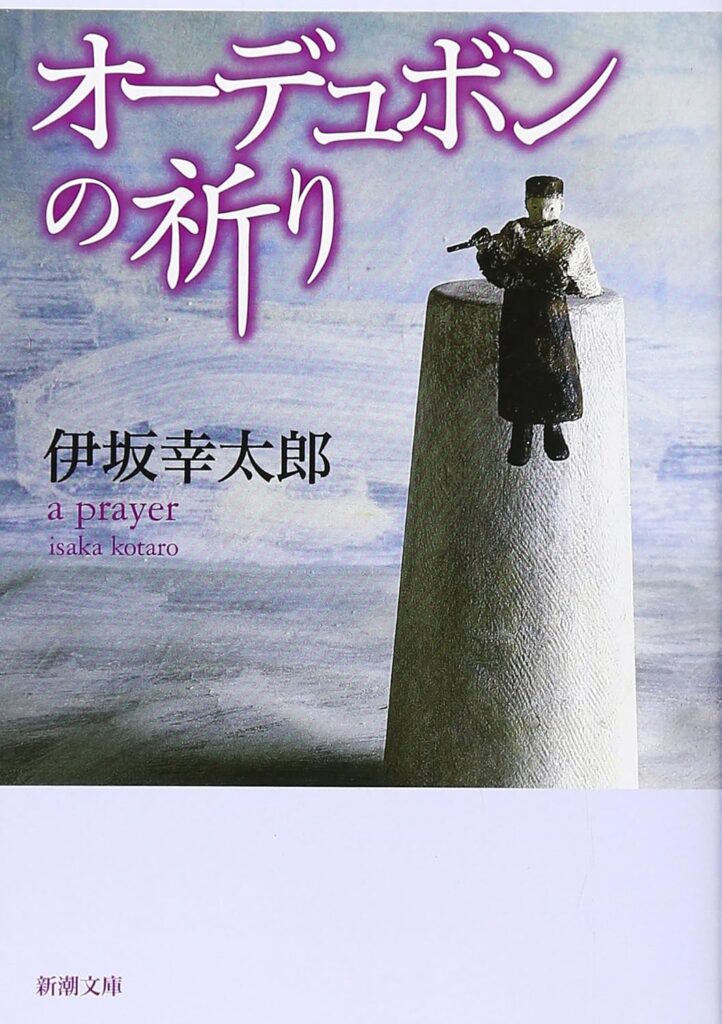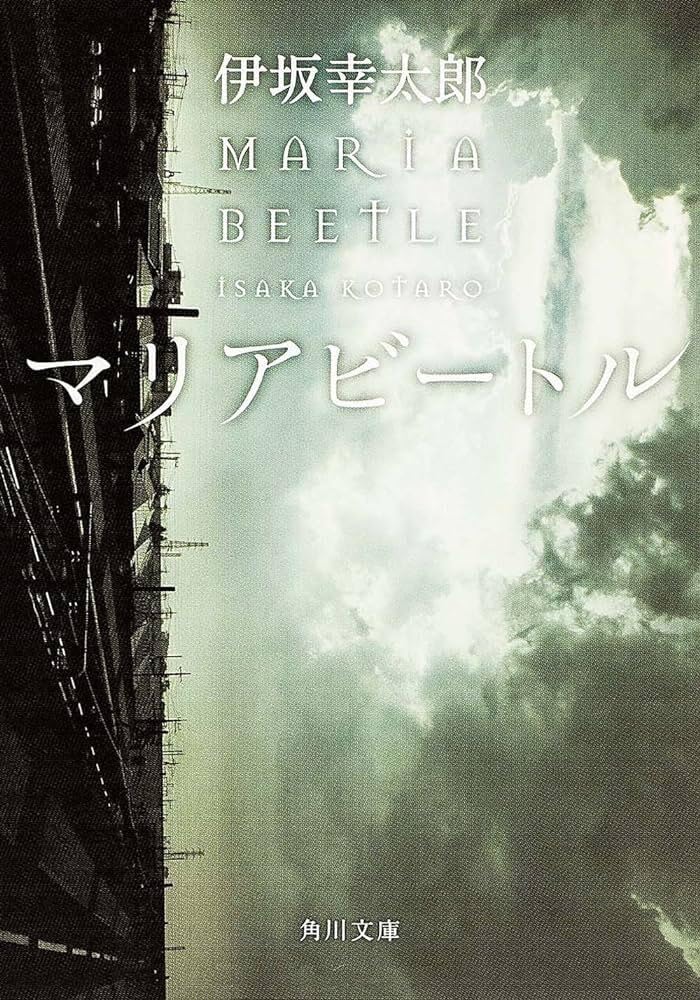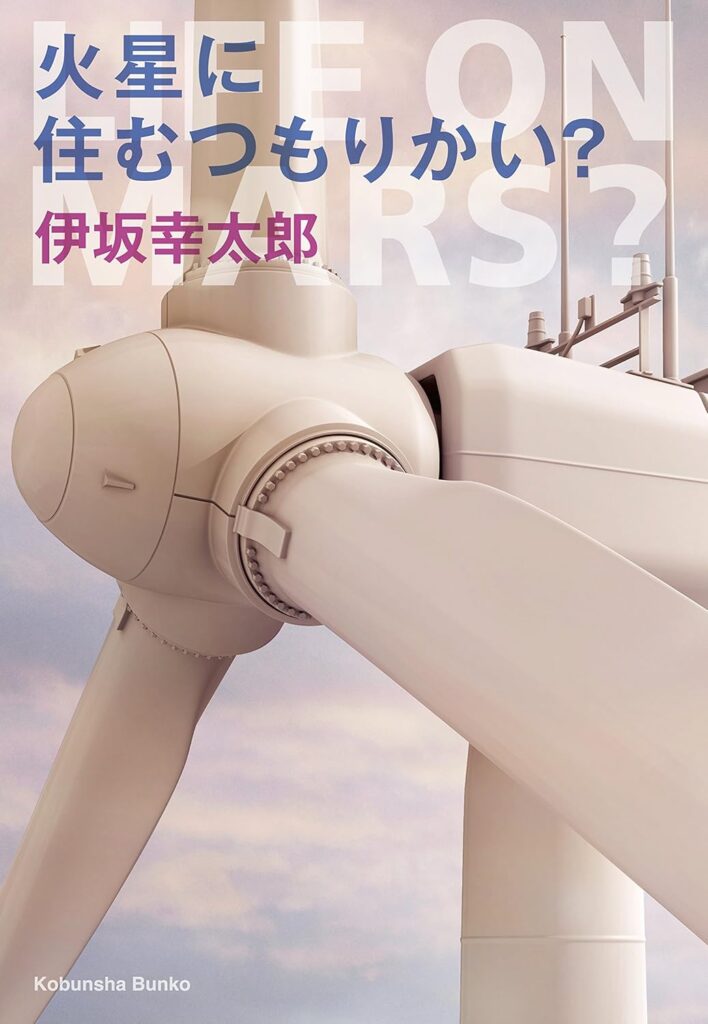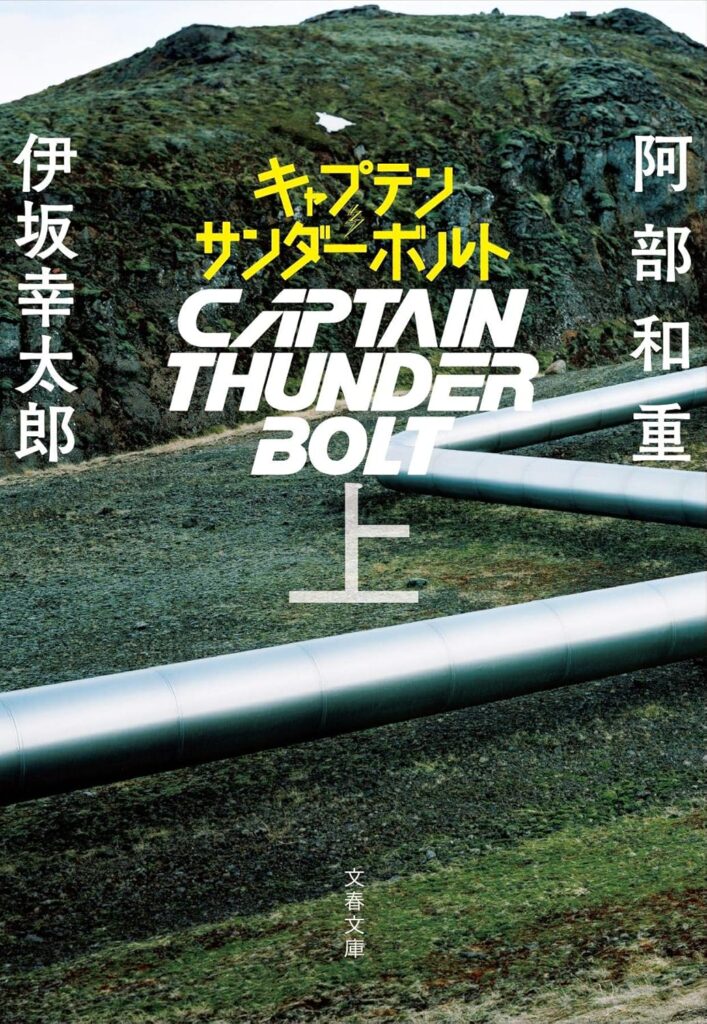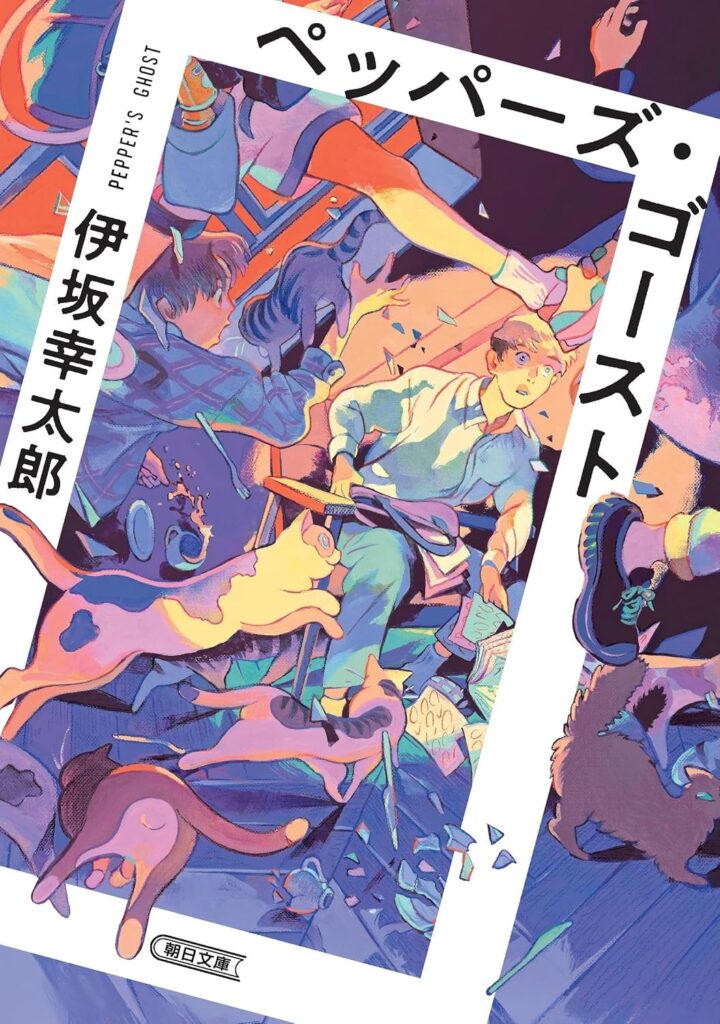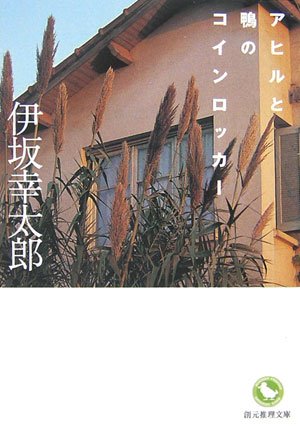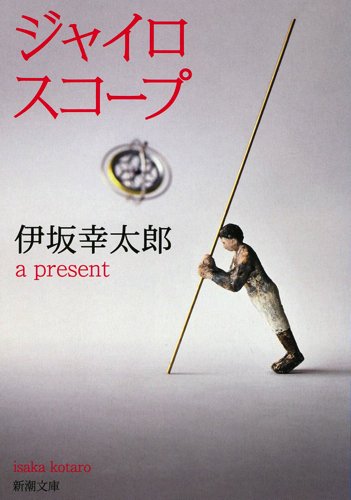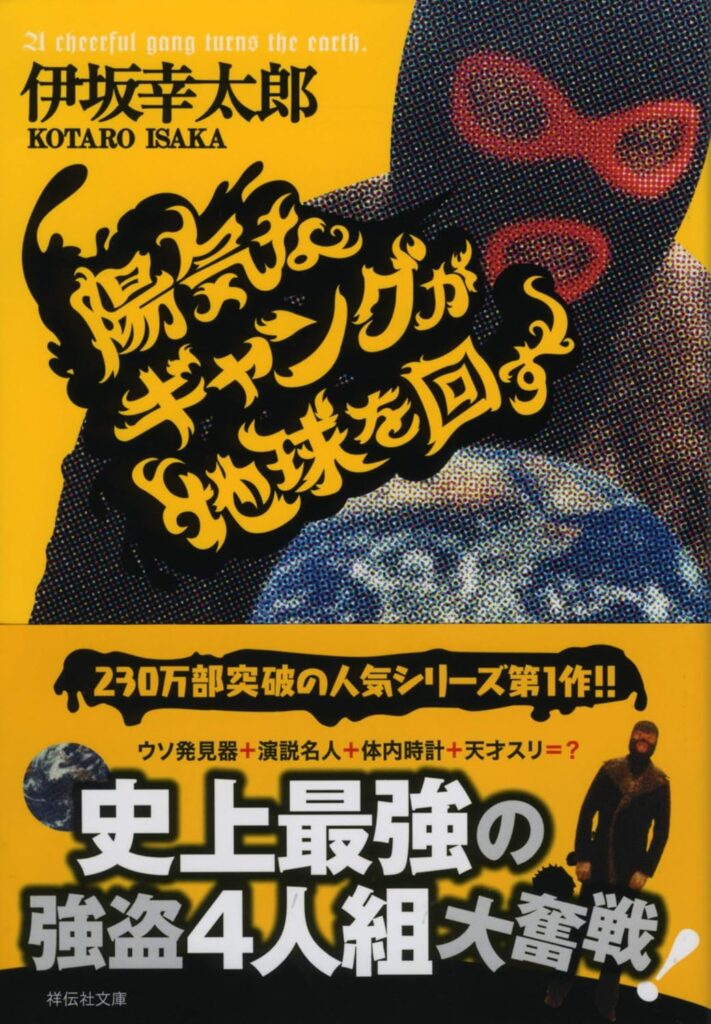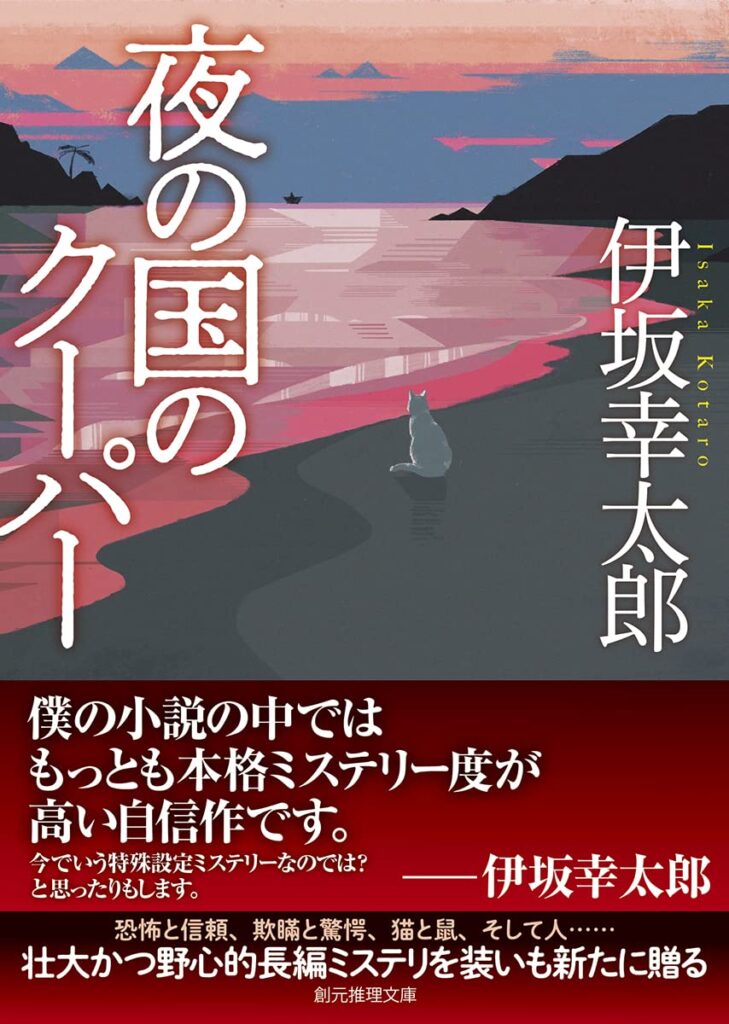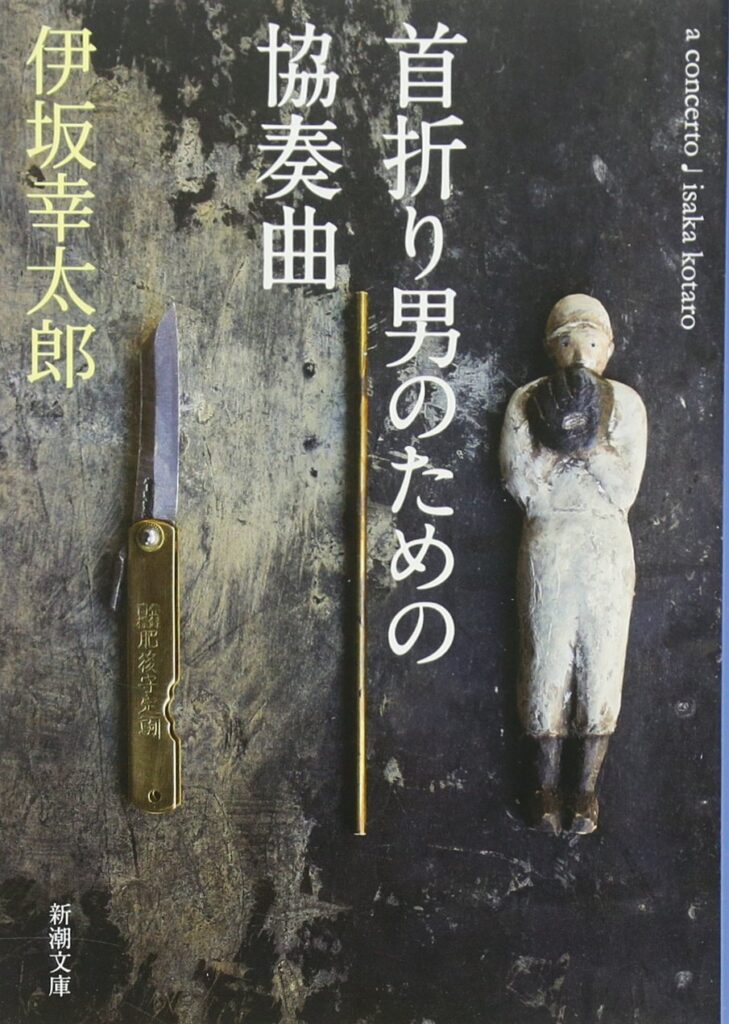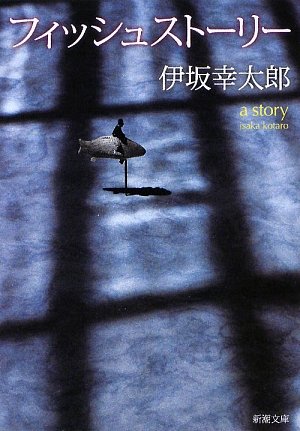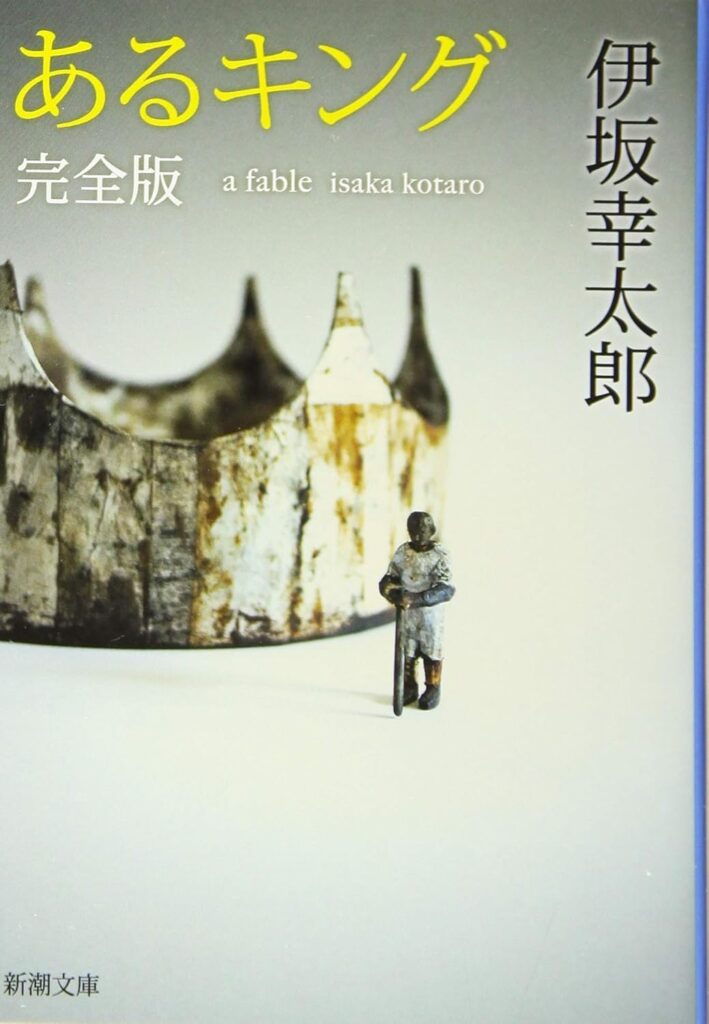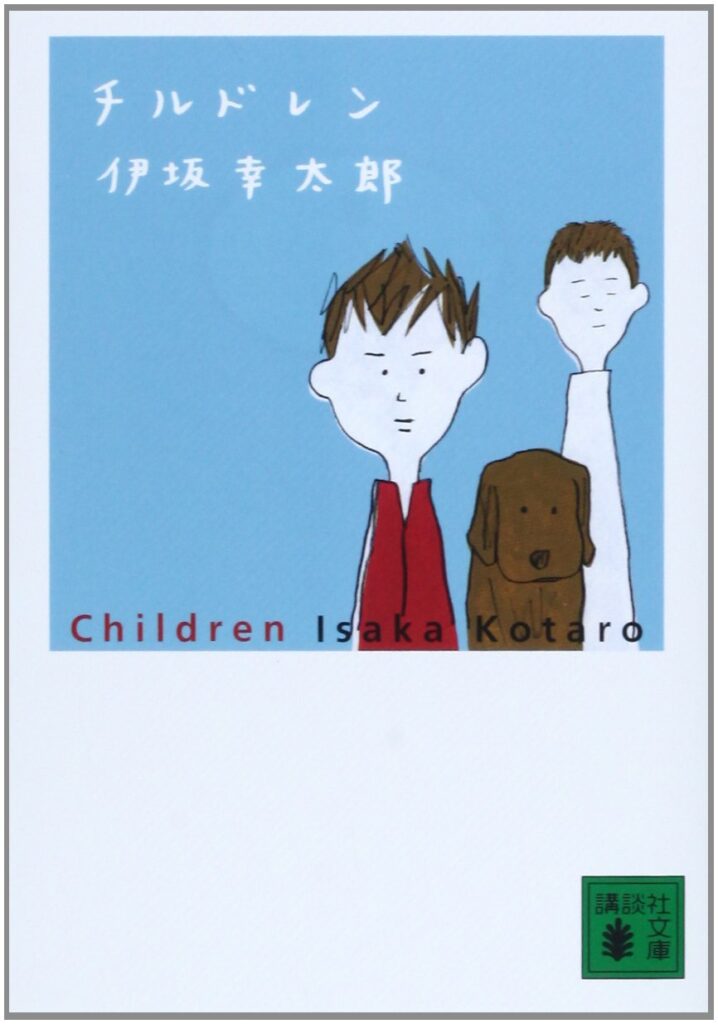小説「砂漠」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。伊坂幸太郎さんの作品の中でも、特に心に深く刻まれる物語の一つではないでしょうか。読んだ後には、爽やかさと共に、どこか切ない気持ちが残る、そんな不思議な魅力を持った作品です。この記事では、物語の筋道を追いながら、その核心部分に触れ、私が感じたこと、考えたことを詳しくお伝えしたいと思います。
小説「砂漠」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。伊坂幸太郎さんの作品の中でも、特に心に深く刻まれる物語の一つではないでしょうか。読んだ後には、爽やかさと共に、どこか切ない気持ちが残る、そんな不思議な魅力を持った作品です。この記事では、物語の筋道を追いながら、その核心部分に触れ、私が感じたこと、考えたことを詳しくお伝えしたいと思います。
物語の舞台は仙台。大学に入学したばかりの北村青年が出会うのは、それぞれに強い個性を持つ4人の学友たちです。彼らとの出会いから始まる大学生活は、麻雀や合コンといった日常的な出来事から、思いがけない事件との遭遇まで、様々な経験を通して、彼らの絆を深め、それぞれを成長させていきます。それは、誰もが経験するかもしれない、けれど彼らにしか経験できなかった、特別な時間の記録なのです。
この記事を通じて、まだ「砂漠」を読んでいない方にはその魅力の一端を、すでに読んだ方には新たな発見や共感をお届けできれば幸いです。物語の結末にも触れていますので、内容を知りたくない方はご注意くださいね。それでは、彼らが駆け抜けた、輝かしくもほろ苦い青春の日々を一緒に辿っていきましょう。
小説「砂漠」のあらすじ
物語は、岩手から仙台の大学に進学してきた北村が、新入生歓迎コンパで個性的な面々と出会うところから始まります。何事にも少し冷めた視線を持ち、「鳥瞰型」と評される北村。彼が出会ったのは、お調子者で女性好きな鳥井、不思議な力を持つと自称する南、誰もが振り返る美貌を持つ東堂、そして、パンクロックを愛し、独自の正義感を熱く語る西嶋でした。この5人が、意気投合したのか、腐れ縁なのか、行動を共にするようになります。
彼らの大学生活は、一見すると平凡なものです。講義そっちのけで麻雀に興じたり、合コンに繰り出したり、ボウリングで賭けをしたり。くだらないおしゃべりに花を咲かせ、時には恋愛模様も垣間見えます。しかし、その日常の中には、伊坂作品らしいスパイスが効いています。南が本当に不思議な力を持っていることが示唆されたり、街で噂される通り魔「プレジデントマン」に遭遇しかけたり、捨てられた犬を救うためにちょっとした騒動を起こしたりと、穏やかなだけではない出来事が彼らを待ち受けます。
特に物語に影を落とすのは、鳥井が空き巣グループとのいざこざに巻き込まれ、大きな怪我を負ってしまう事件です。仲間の一人が深く傷ついたことで、彼らの関係性や日常の空気は一変します。それでも彼らは、それぞれのやり方で困難に向き合い、支え合おうとします。また、南の力が本物なのかどうかを確かめるための対決や、西嶋の真っ直ぐすぎる言動が引き起こす波紋など、飽きさせない展開が続きます。
物語は、彼らが出会った春から始まり、夏、秋、冬、そしてまた春へと、季節の移ろいと共に進んでいきます。麻雀卓を囲み、くだらない話で笑い合った日々。時にはぶつかり、悩み、傷つきながらも、彼らは確かに成長していきます。しかし、大学生活という限られた時間には終わりが近づいてきます。それぞれの進路、そして訪れる別れの予感。彼らが過ごした、かけがえのない時間の結末は、読者の心に静かな余韻を残すのです。
小説「砂漠」の長文感想(ネタバレあり)
伊坂幸太郎さんの「砂漠」は、私にとって特別な一冊です。初めて読んだのはいつだったか、もう定かではありませんが、それ以来、何度読み返したか分かりません。読むたびに新しい発見があり、その度に登場人物たちへの愛着が深まっていく。まるで、古い友人に再会するような感覚です。なぜ、この物語はこれほどまでに私の心を捉えて離さないのでしょうか。それはきっと、この物語が描く青春の輝きと痛みが、あまりにも普遍的で、そして愛おしいからなのだと思います。ネタバレを含みますので、未読の方はご注意くださいね。
個性という名の輝き:登場人物たちの魅力
この物語の最大の魅力は、やはり登場人物たちでしょう。北村、鳥井、南、東堂、そして西嶋。この5人のバランスが絶妙なのです。
まず、西嶋。彼の存在なくして「砂漠」は語れません。パンクロックを愛し、クラッシュやラモーンズの言葉を引用しながら、独自の理論を展開する熱い男。周囲から見れば奇妙で、時には煙たがられる存在かもしれません。彼の「プレジデントマン」に対する評価や、「その気になればね、砂漠に雪を降らすことだって、余裕でできるんですよ」という、あまりにも有名なセリフ。最初は「なんだこの人は?」と思うかもしれません。しかし、読み進めるうちに、彼の持つ純粋さ、不器用な優しさ、そして確固たる信念に、読者は否応なく惹きつけられてしまいます。
彼が放つ言葉は、時に青臭く、理想論に聞こえるかもしれません。「今、目の前で泣いてる人を救えない人間がね、明日、世界を救えるわけがないんですよ」。でも、その言葉にはっとさせられる瞬間がある。社会の常識や多数派の意見に流されず、自分の信じる「正しさ」を貫こうとする姿は、忘れかけていた何かを思い出させてくれるようです。彼が古賀との関係で見せる不器用さや、万引きで捕まった過去のエピソードなども、彼の人間性を多層的に見せてくれます。東堂が彼に惹かれていくのも、彼の内面にある揺るぎない輝きに気づいたからでしょう。西嶋は、物語を力強く牽引するエンジンであり、読者の心に最も強く印象を残すキャラクターだと思います。
語り手である北村は、私たち読者の視点に最も近い存在かもしれません。最初はどこか冷めた目で周囲を観察し、「鳥瞰型」と自認しています。西嶋の熱さに呆れたり、鳥井の軽薄さにため息をついたり。しかし、この個性的な仲間たちとの日々の中で、彼の心は確実に変化していきます。当初は感情を表に出すことをためらっていた彼が、次第に怒りや喜びを露わにし、仲間たちのために行動するようになる。特に、鳩麦さんとの関係や、終盤で見せる仲間への強い思いには、彼の成長がはっきりと見て取れます。
彼の口癖である「なんてことはまるでない、はずだ」。これは、彼の斜に構えた態度を表すフレーズとして何度も登場しますが、物語の最後、仲間たちとの別れを予感する場面で使われる時、それは単なる照れ隠しではなく、永遠ではない青春への切なさ、失われていく時間への愛惜の念を凝縮した、深く響く言葉となります。彼の視点を通して語られるからこそ、私たちはこの物語に没入し、彼らと共に笑い、悩み、そして感傷に浸ることができるのです。
紅一点の東堂は、単なる「美人」という記号ではありません。自分の美貌を自覚し、それを武器として使う強かさを持っていますが、決してそれに溺れることはありません。他人に媚びず、自分の意志をしっかりと持っている。西嶋の真っ直ぐさに惹かれ、夜中にCDショップへ走る行動力も彼女らしい。彼女の存在は、男性ばかりのグループに華やかさだけでなく、異なる視点や緊張感をもたらします。鳩麦さんとの会話で垣間見える、記憶力に関するやり取り(元ネタを知っているとさらに面白いですね)など、知的な一面も魅力的です。
グループのムードメーカー、鳥井。彼の軽やかさと社交性は、ともすればバラバラになりそうなメンバーを繋ぎとめる潤滑油のような役割を果たしています。「そこからかよー」というツッコミは、物語の中で繰り返され、彼のキャラクターを象徴する言葉となっています。しかし、彼が空き巣グループとの争いで左腕を失うという出来事は、物語に大きな衝撃と影を落とします。いつもの明るさが消え、仲間たちが戸惑う場面は読んでいて胸が締め付けられます。それでも、南をはじめとする仲間たちの支えによって、彼は少しずつ前を向き、再びあのツッコミを口にする。彼の存在が、グループの明るさや日常の象徴であったことを、失いかけて初めて痛感させられます。彼の軽薄さの裏にある仲間への思いやりや、困難を乗り越えようとする姿は、物語に深みを与えています。
そして、南。彼は「超能力が使える」という、物語にファンタジー的な要素を持ち込む存在です。スプーンを曲げたり、物を動かしたり。その力の真偽は、物語の中で巧みにぼかされながら進みますが、終盤、驚くべき形でその力が証明されます(四年に一度の伏線回収は見事でした)。しかし、彼の魅力は超能力だけではありません。穏やかで心優しく、仲間たちの間の緩衝材のような存在です。鳥井とは中学の同級生であり、彼が傷ついた時には特に心を痛め、支えようとします。彼の不思議な存在感と優しさが、このグループの独特な空気感を作り出す一因となっているのは間違いありません。
巧みな構成と時間の流れ
物語は「春」「夏」「秋」「冬」そして再び「春」へと、季節の移ろいを追って進みます。しかし、単に1年間の話ではなく、実は1年生の春、2年生の夏、3年生の秋、4年生の冬、そして卒業後の春…というように、数年の歳月が流れていることが、鳥井の隣人の変化や、登場人物たちの会話の端々から示唆されています。この時間経過の描き方が非常に巧みで、読み返すたびに「ああ、ここはそういうことだったのか」と気づかされます。
大学生活という、人生の中でも特殊な「モラトリアム」の期間。そこには、将来への漠然とした不安と、今この瞬間を謳歌する自由さが同居しています。麻雀、合コン、ボウリング、くだらない会話、そして時折起こる非日常的な事件。それらが積み重なっていく日々は、リアルでありながらも、どこか夢のような輝きを放っています。伊坂さんは、その空気感を巧みに捉え、読者を懐かしいような、切ないような気持ちにさせるのです。
「砂漠」に込められた意味を探る
この物語のタイトルである「砂漠」。作中で西嶋が「社会は砂漠だ」というようなことを言います。水も緑もなく、どこまでも広がり、方向感覚を失わせる場所。それは、これから彼らが足を踏み入れていく社会の厳しさ、あるいは人生そのものの困難さを象徴しているのかもしれません。
しかし、西嶋はこうも言います。「その気になればね、砂漠に雪を降らすことだって、余裕でできるんですよ」。不可能なことを可能にする、という彼の強い意志表明です。これは、若さゆえの万能感の表れと見ることもできますが、それだけではない気がします。たとえ周りがどれだけ不毛に見えても、困難な状況であったとしても、自分の意志と行動次第で、何かを変えることができる、奇跡を起こすことだってできるのだ、という希望のメッセージではないでしょうか。
人生という広大な砂漠を、彼らは時にぶつかり、時に支え合いながら、蜃気楼のような儚い希望を追い求めて歩んでいく。一人では心細い道のりも、信頼できる仲間がいれば、笑い合い、励まし合いながら進んでいける。たとえその関係が永遠ではなかったとしても、共に過ごした時間は、その後の人生の糧となり、心の支えとなる。この物語は、そんな人間の繋がりのかけがえのなさを教えてくれます。
それは、物語の終盤、いつも飄々としていた莞爾が北村に漏らす「本当はおまえたちみたいなのと、仲間でいたかったんだよな」という言葉にも表れています。彼らの関係性を外から見ていた人物の言葉だからこそ、その友情の価値が際立って感じられるのです。
言葉の響きと伏線の妙
伊坂作品の魅力の一つは、その軽妙でありながら、時に深く突き刺さる会話と、散りばめられた伏線や小ネタです。
西嶋が引用するパンクロックの歌詞や文学作品の一節(坂口安吾、三島由紀夫、サン=テグジュペリなど)。東堂の記憶力に関する会話(大西巨人の『神聖喜劇』)。南が麻雀で呟く犬の名前(『南極物語』)。これらの引用は、単なる衒学的なものではなく、登場人物の性格を際立たせたり、物語のテーマを補強したりする役割を担っています。知っているとニヤリとでき、知らなくても物語の流れを妨げない絶妙なバランスで配置されています。
そして、南の超能力に関する伏線。「四年に一度」という言葉が、最後の最後に鮮やかに回収される展開には唸らされました。また、西嶋が高校時代に出会った家庭裁判所の調査官が、『チルドレン』などに登場する陣内ではないか、という示唆も、ファンにとっては嬉しい遊び心です。
これらの要素が、物語に奥行きと読み返す楽しみを与えています。
青春の終わりと、その先の人生
物語の最後、彼らは大学卒業を迎え、それぞれの道へと進んでいきます(西嶋は留年しますが)。北村は、仲間たちとの別れを予感し、「なんてことはまるでない、はずだ」と心の中で呟きます。輝かしい青春の日々は終わりを告げ、彼らは否応なく「砂漠」へと足を踏み出していく。
読後には、彼らと共に過ごした時間への愛惜と、これから彼らがどうなるのだろうかという一抹の寂しさが残ります。学生時代の友人とは、卒業と共に疎遠になってしまうことが多い、という現実を知っているからこそ、北村の言葉は切なく響きます。
しかし、物語の最後で学長が引用するサン=テグジュペリの言葉、「人間にとって最大の贅沢とは、人間関係における贅沢のことである」が示すように、彼らが過ごした時間は、何物にも代えがたい宝物です。そして、「学生時代を思い出して懐かしがるのはいいけれど、あの頃に戻りたいと思ってはいけない」という学長の言葉は、過去を美化しすぎず、未来に向かって歩んでいくことの大切さを教えてくれます。
彼らが「砂漠」で雪を降らせることができたのかどうか、それは描かれていません。しかし、彼らが共に過ごした時間が、それぞれの未来を照らす光となったであろうことは、想像に難くありません。この物語は、青春の終わりを描きながらも、決して後ろ向きなだけではない、未来への静かな希望を感じさせてくれるのです。
結論として
「砂漠」は、単なる大学生の日常を描いた物語ではありません。そこには、友情、成長、恋愛、喪失、そして人生という普遍的なテーマが、伊坂幸太郎さんならではの筆致で鮮やかに描かれています。個性的なキャラクターたちの魅力的な会話、巧みなストーリーテリング、心に響く言葉の数々。読み終えた後には、爽快感と共に、自分の学生時代を思い出したり、これからの人生について考えたりする、深い余韻が残ります。
何度読んでも色褪せない、まさに一生モノの物語。もしあなたがまだこの「砂漠」を訪れたことがないのなら、ぜひ一度、彼らと共に、あの輝かしくも切ない時間を体験してみてほしいと思います。きっと、あなたの心の中にも、忘れられない風景が広がることでしょう。
まとめ
この記事では、伊坂幸太郎さんの小説「砂漠」について、物語の詳しい筋道や結末に触れながら、その魅力や私自身の深い思い入れを込めた考察を述べてきました。仙台の大学で出会った5人の若者たちが繰り広げる、日常と非日常が交錯する青春の日々を追体験していただけたでしょうか。
西嶋の熱い言葉、北村のクールな視線の変化、東堂の強さ、鳥井の明るさと痛み、南の不思議な存在感。個性的な登場人物たちが織りなす関係性と、彼らが直面する出来事を通して描かれる成長の物語は、読む人の心を強く打ちます。「社会は砂漠だ」という言葉と、「砂漠に雪を降らす」という希望。その対比の中に、人生の厳しさと、それでも前を向くことの大切さが込められているように感じます。
巧みに配置された伏線や、文学・音楽からの引用なども、物語に深みを与え、読み返すたびに新たな発見をもたらしてくれます。読後には、爽やかさと共に、過ぎ去った時間への切ない感傷が残るかもしれませんが、それこそがこの作品の持つ大きな魅力なのでしょう。まだ読んでいない方には、ぜひ手に取っていただきたい一冊ですし、すでに読んだことがある方にも、この記事が再読のきっかけとなれば嬉しいです。