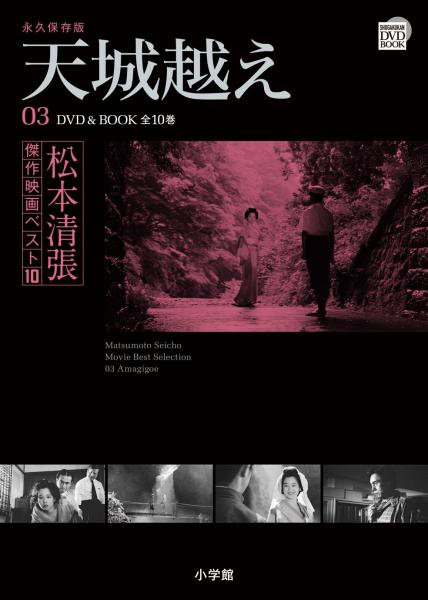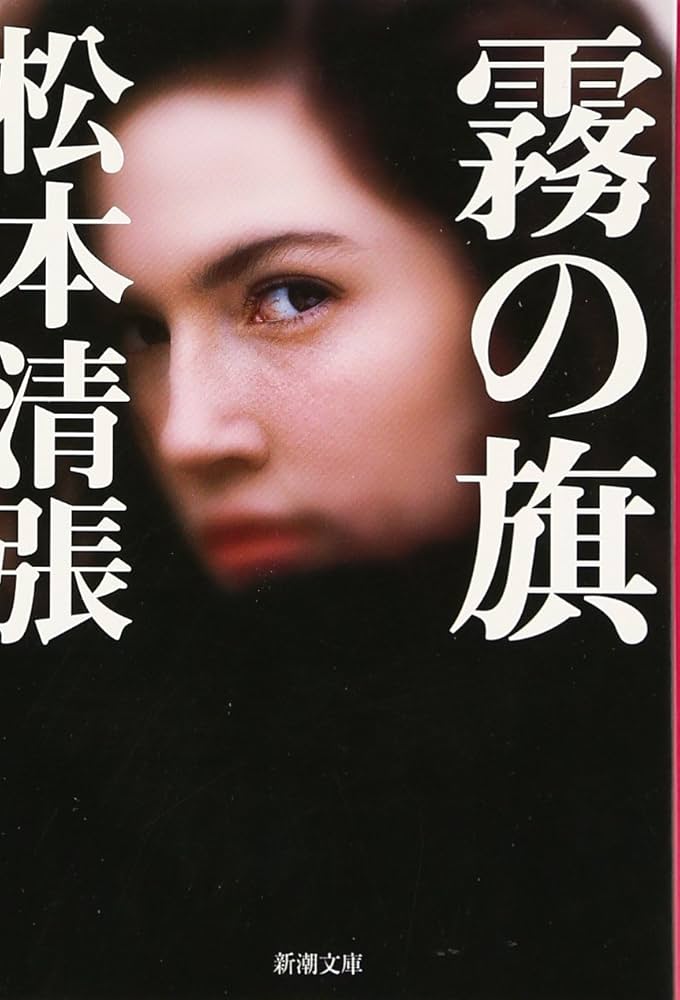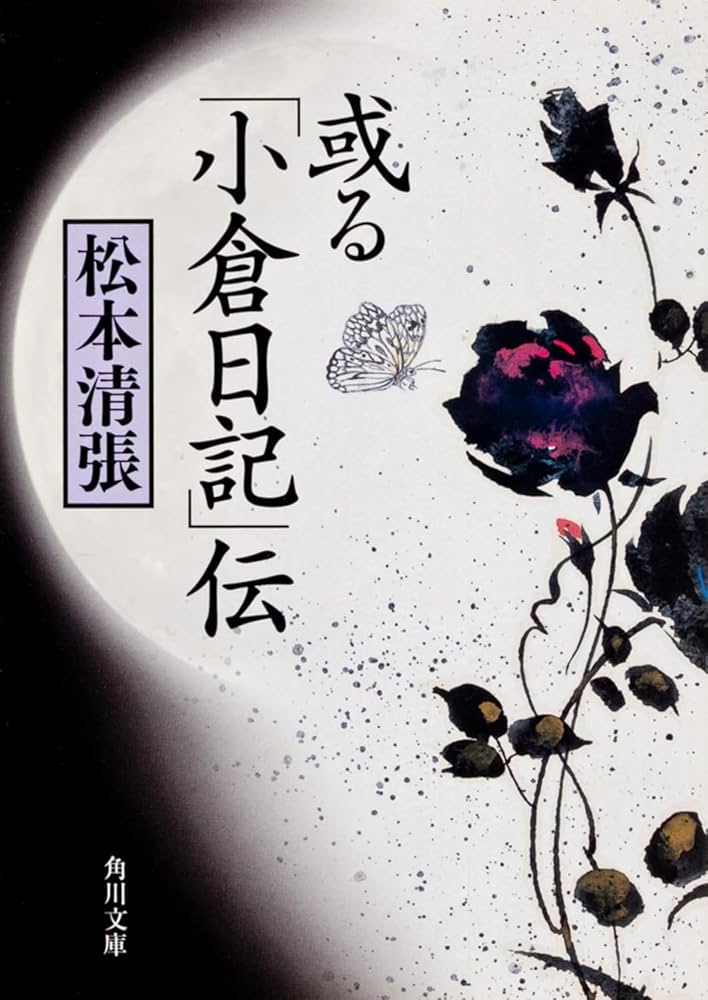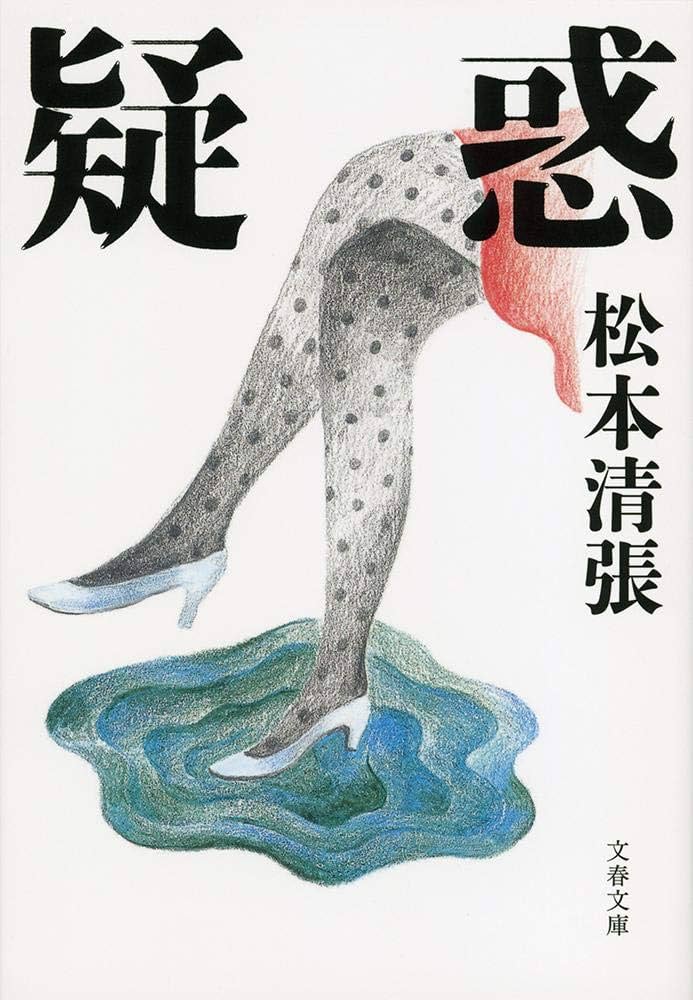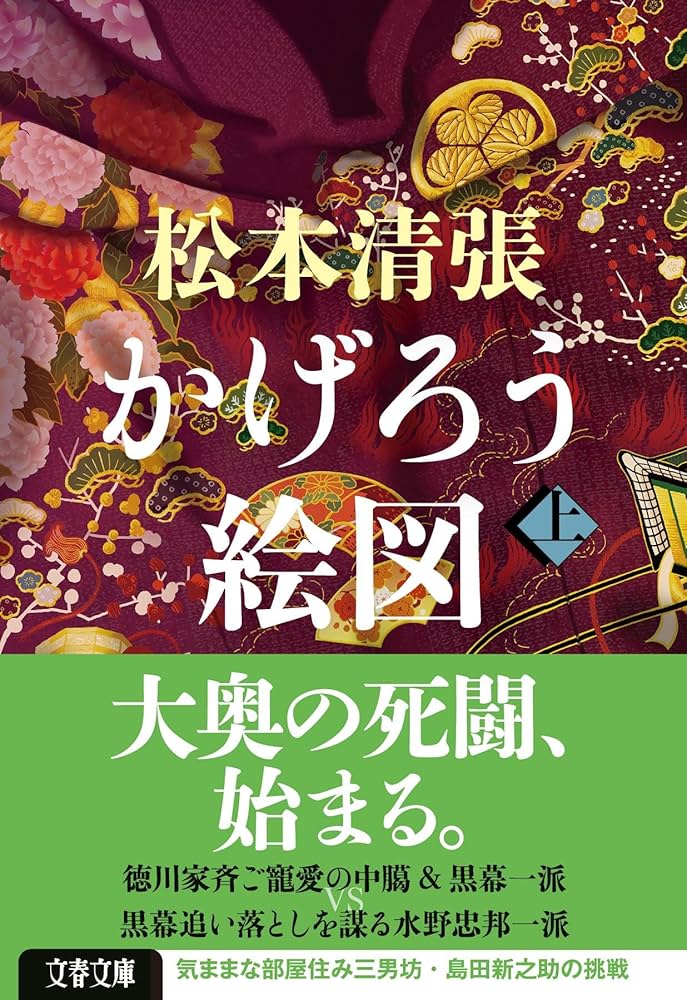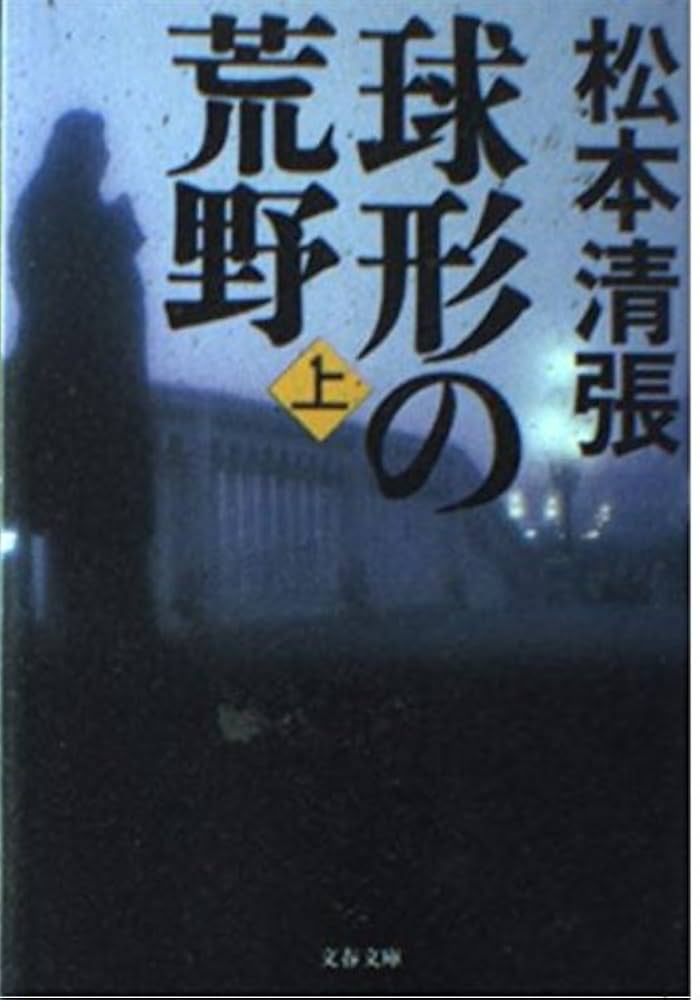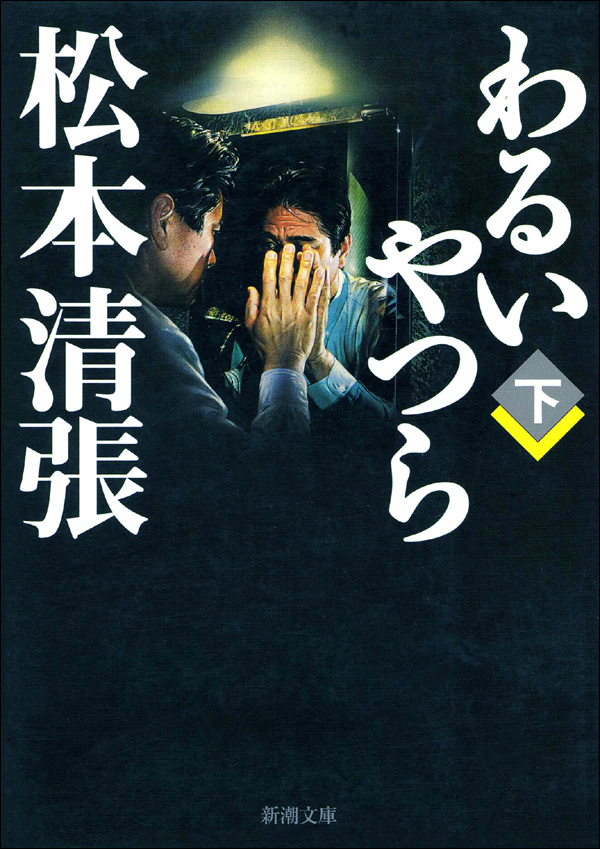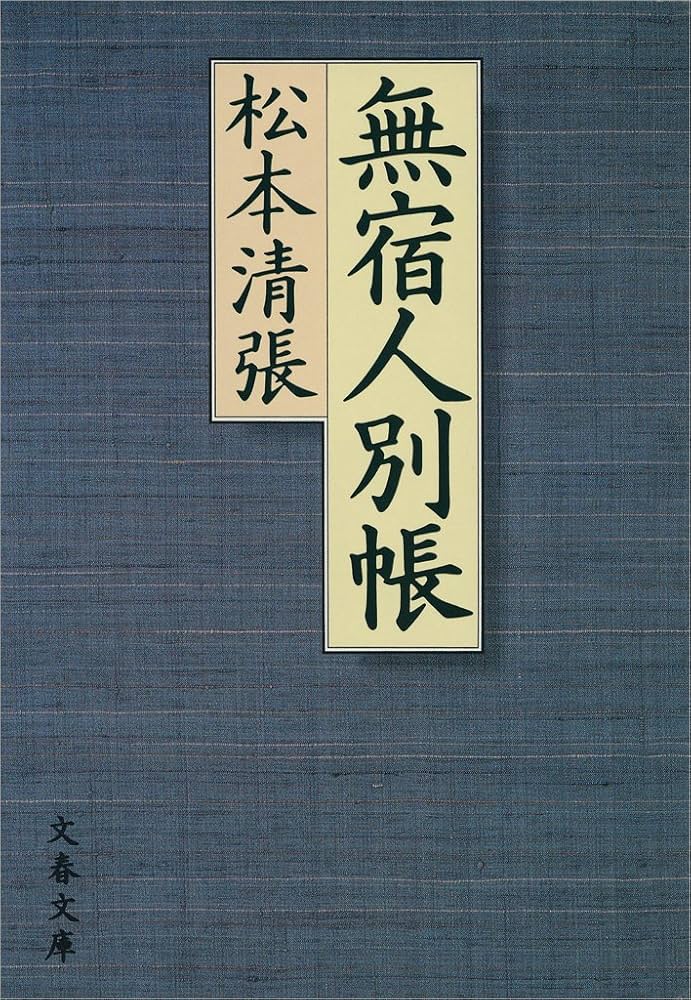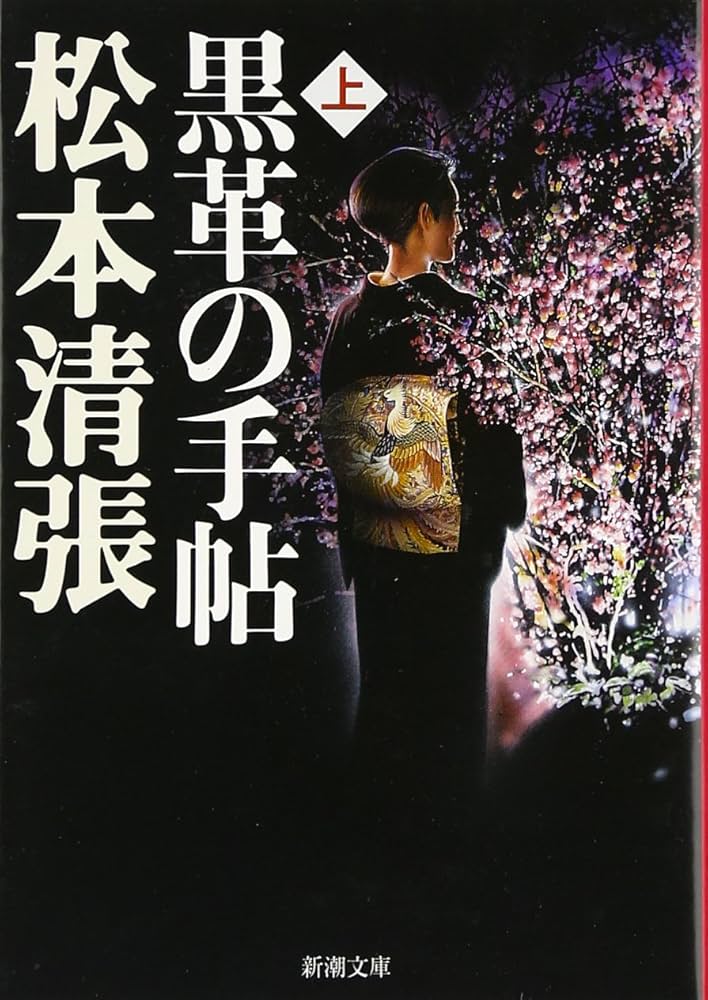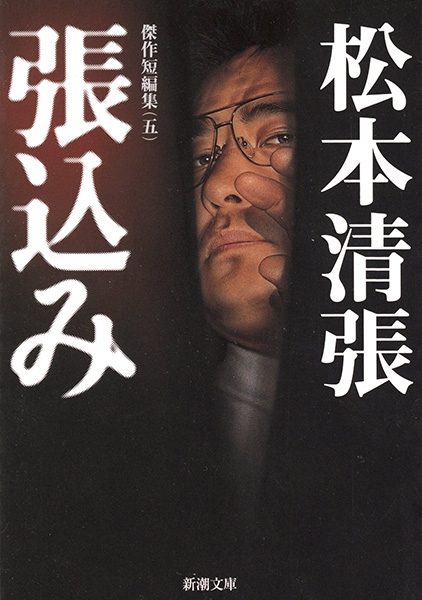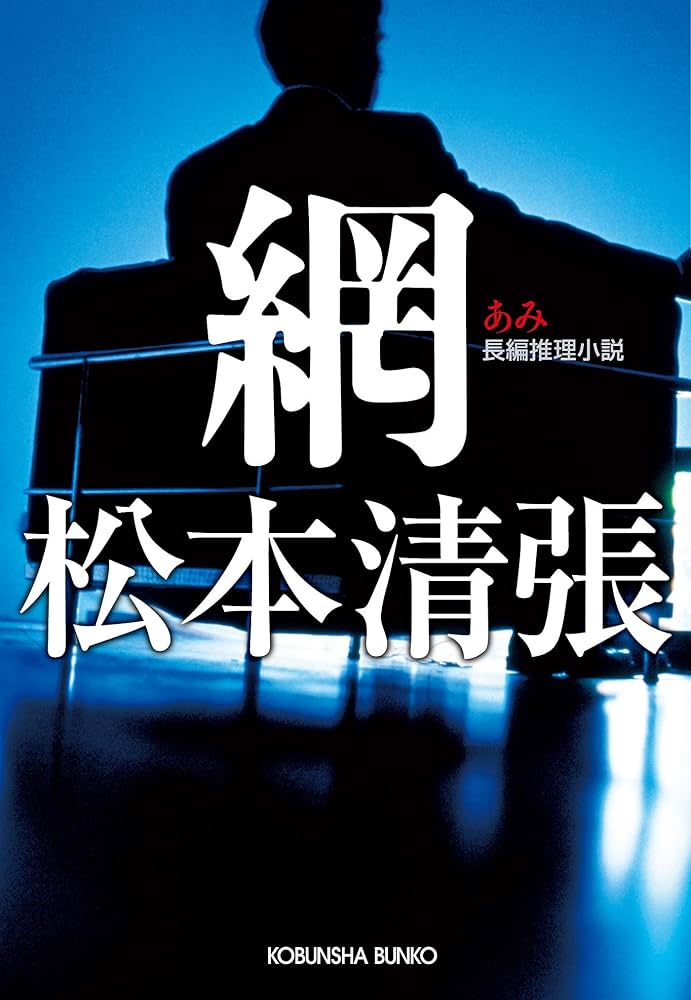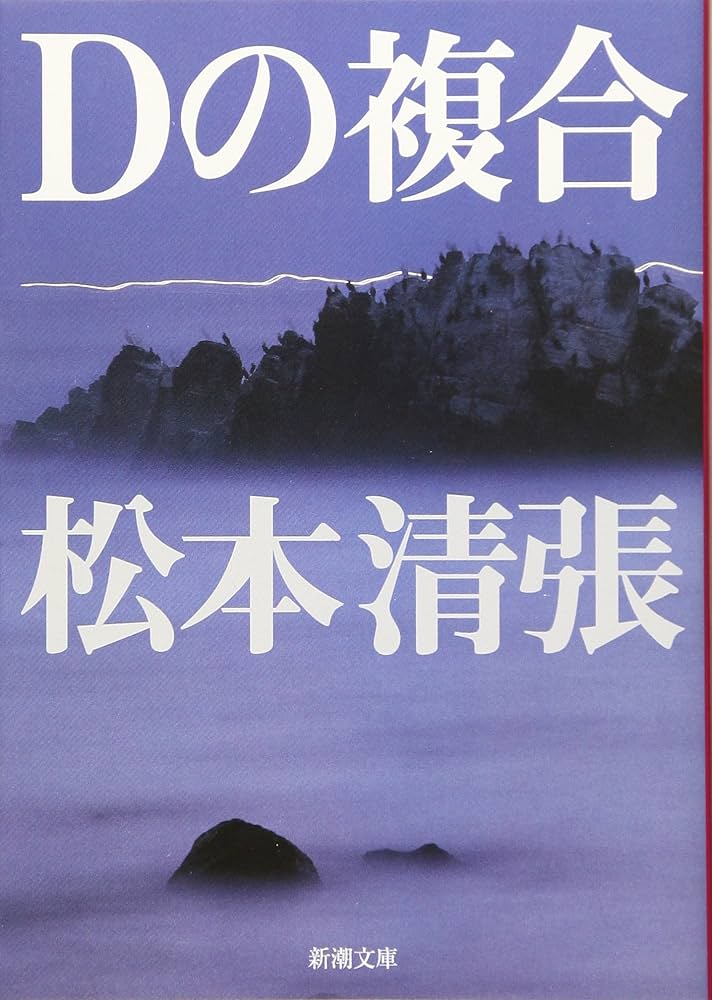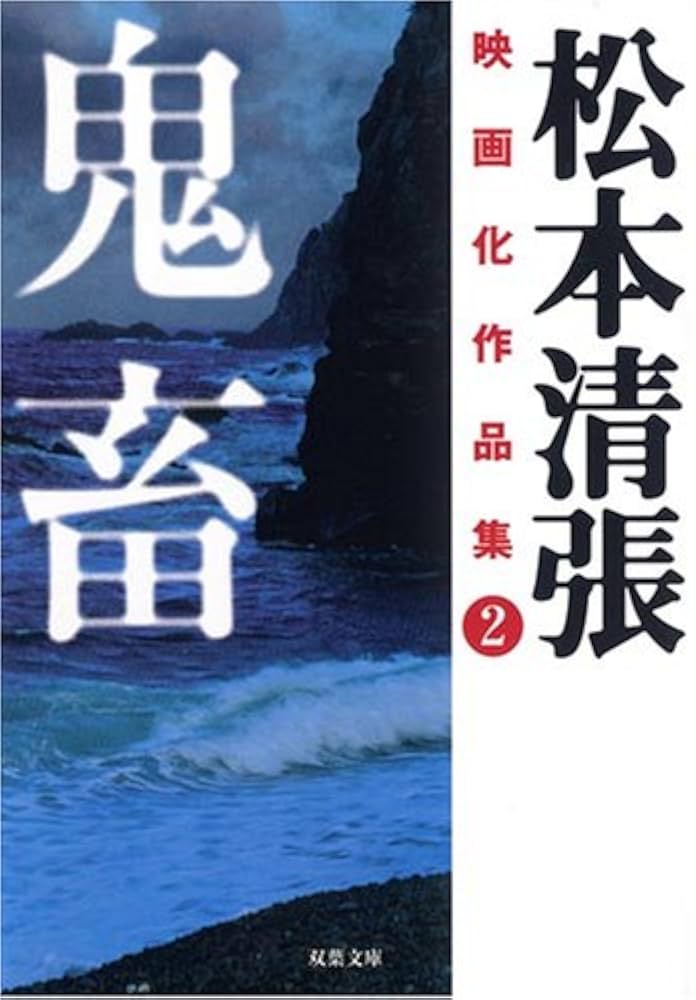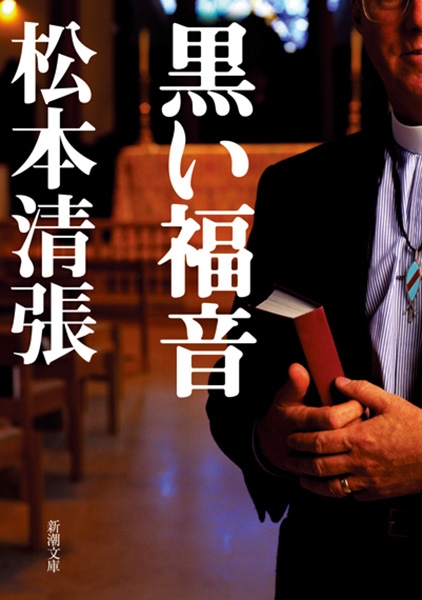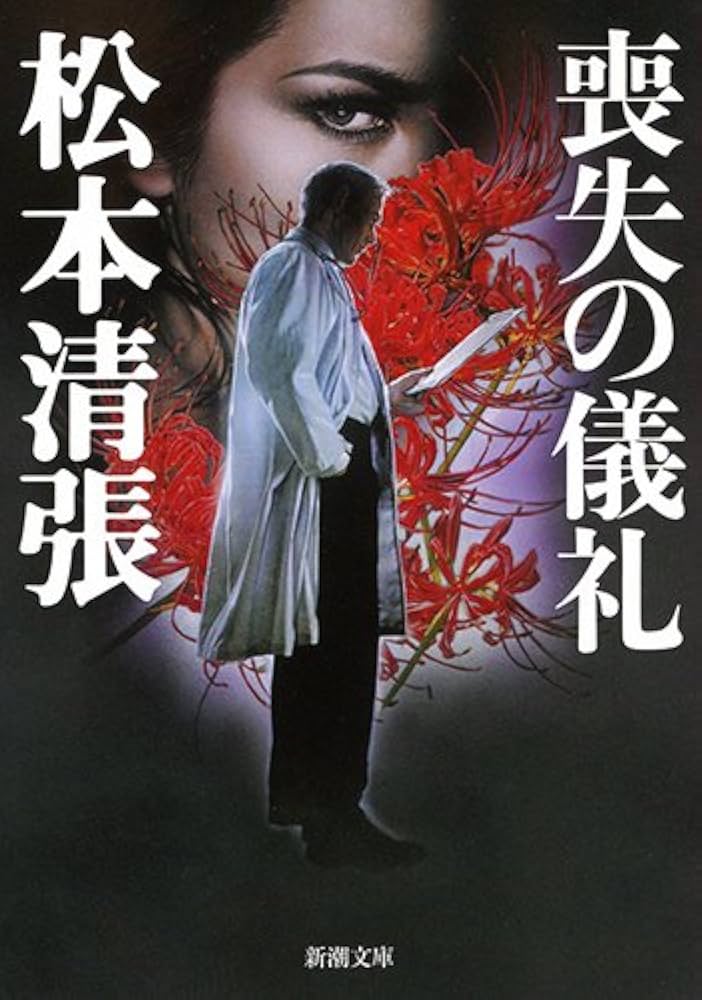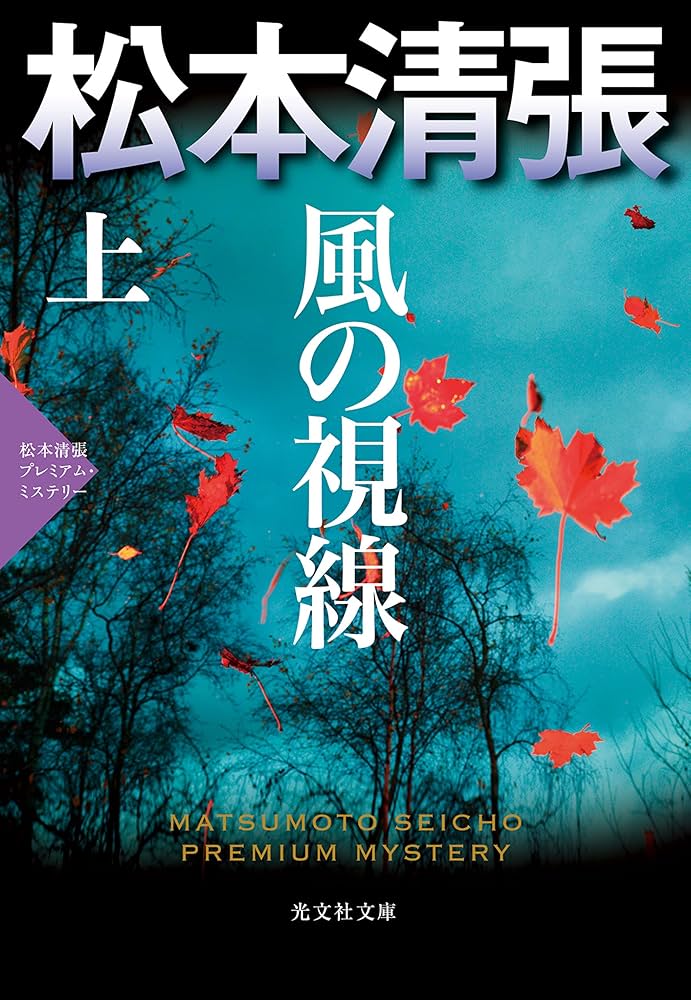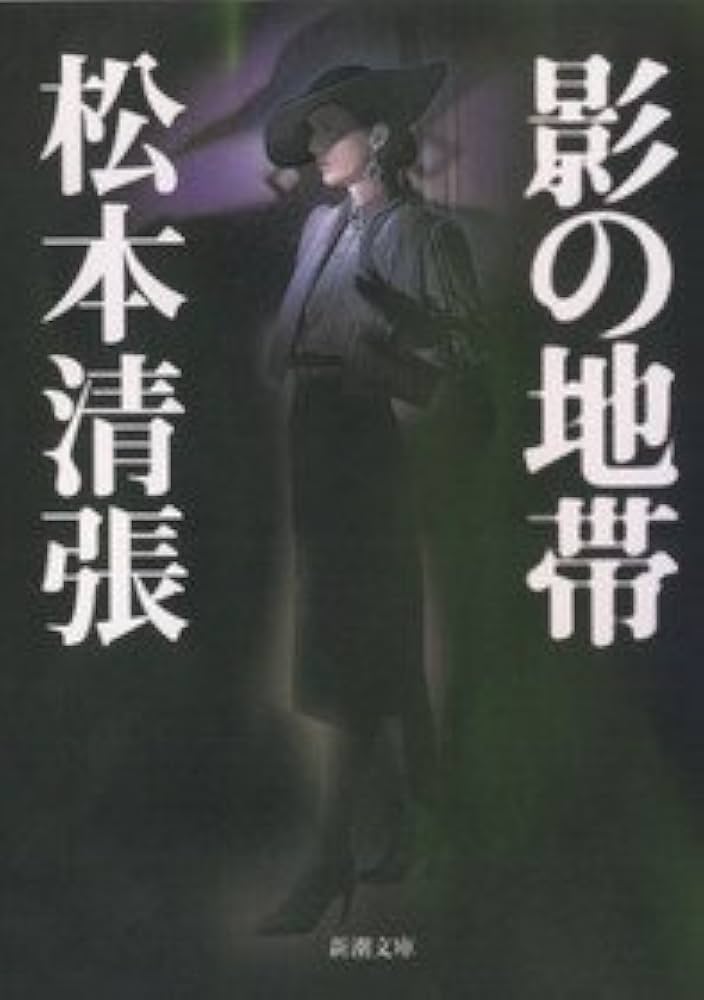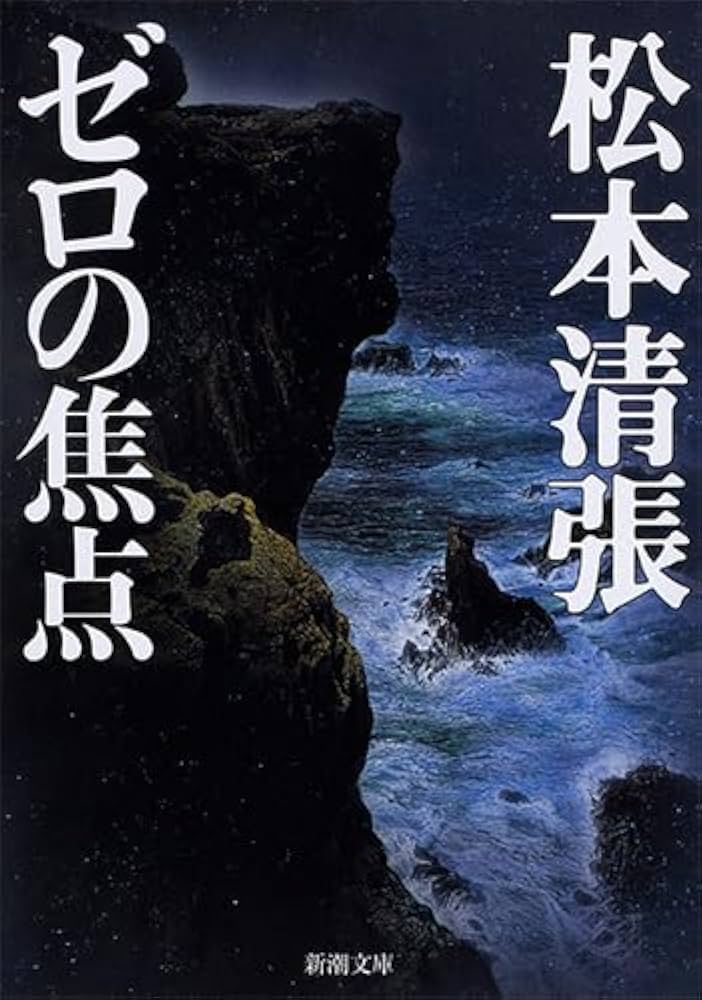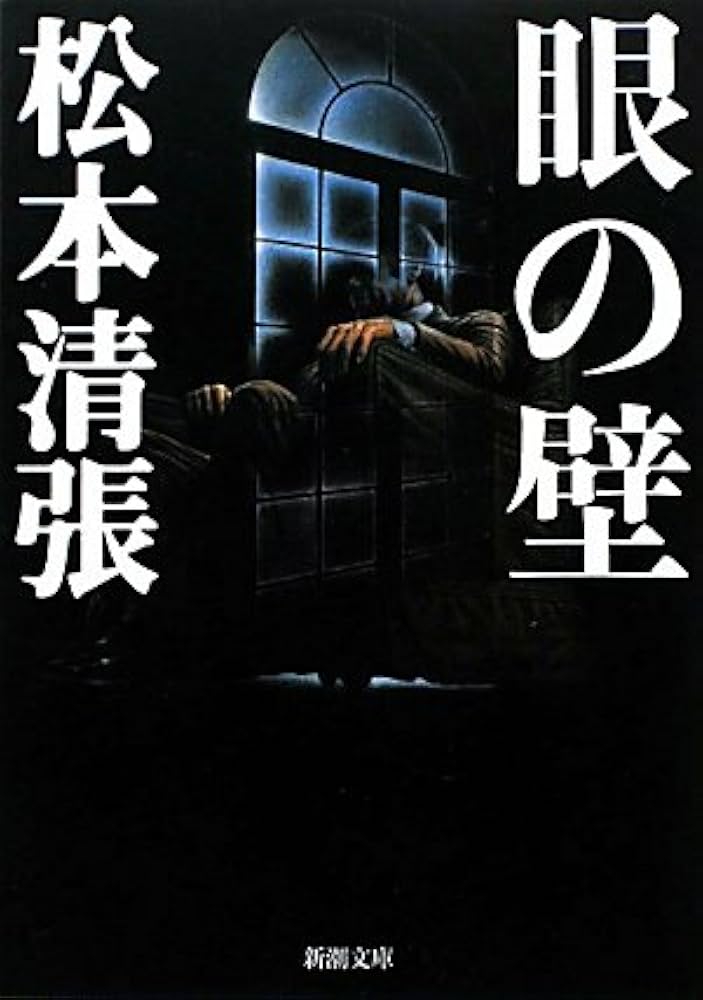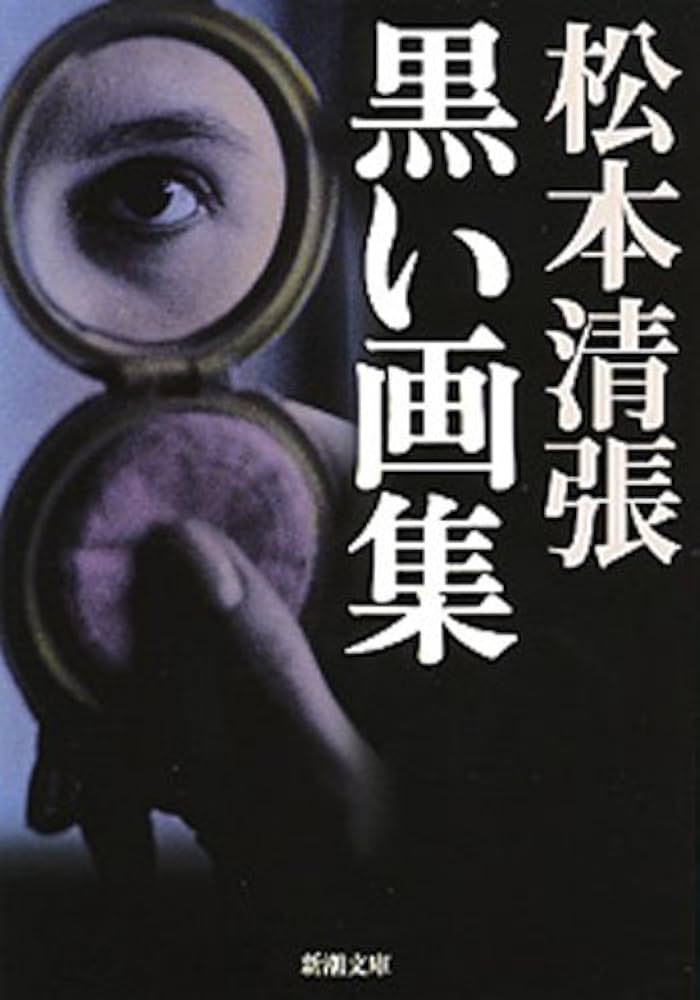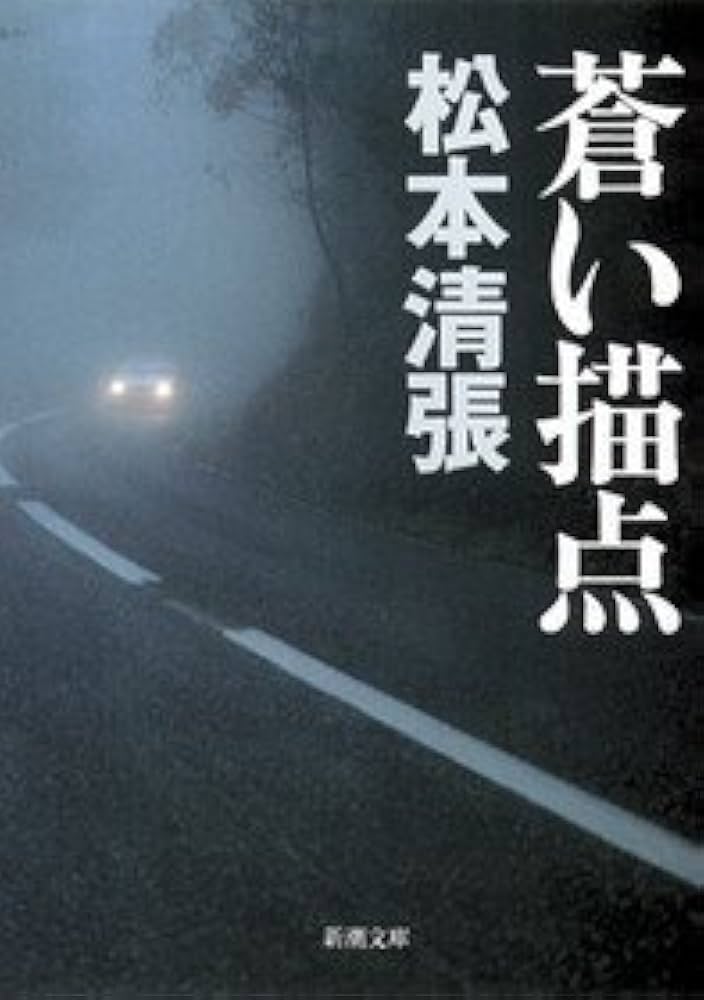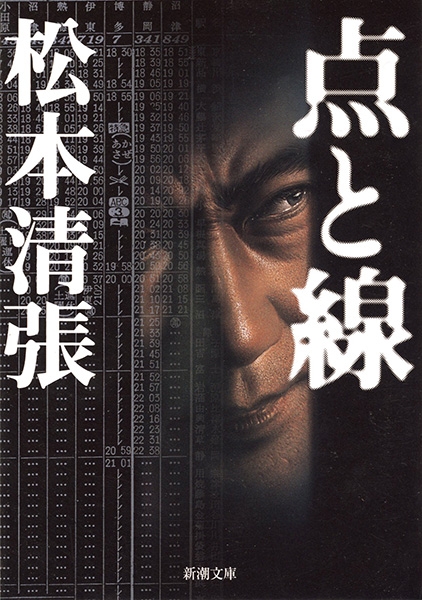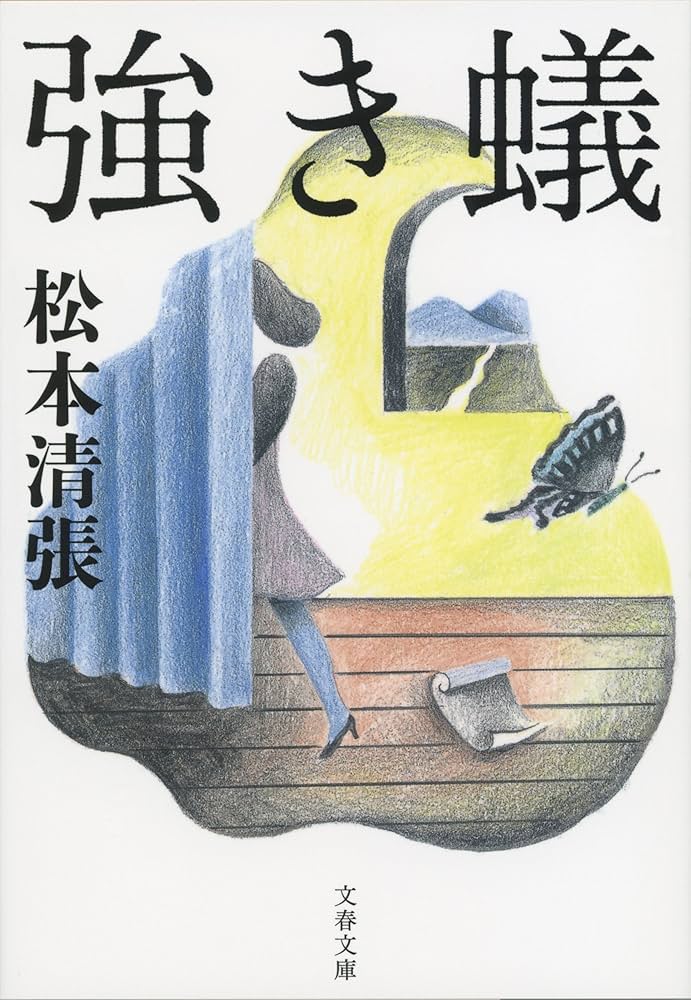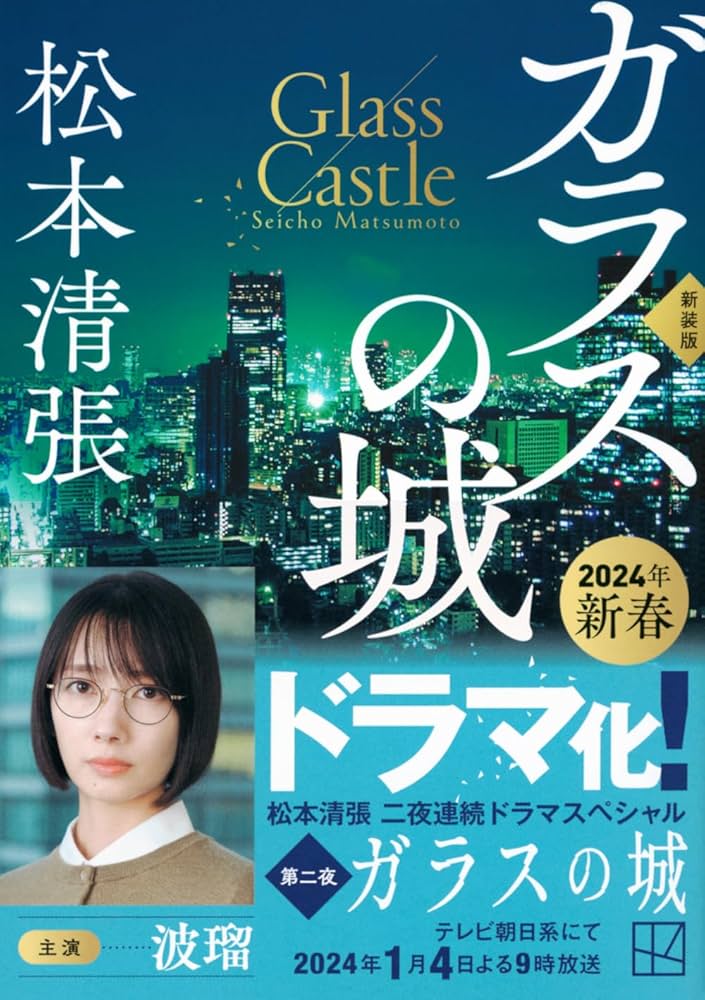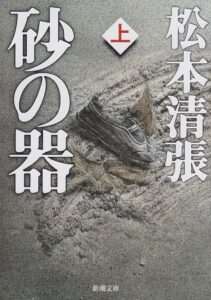 小説『砂の器』のあらすじをネタバレ込みで紹介いたします。長文の感想も書いていますので、どうぞ。
小説『砂の器』のあらすじをネタバレ込みで紹介いたします。長文の感想も書いていますので、どうぞ。
松本清張が紡ぎ出した本作は、単なる推理物語の枠を超え、人間の根源的な「業」や社会の深部に潜む差別といった重厚なテーマを描き切った傑作でございます。昭和という時代背景を色濃く反映しつつも、その本質は現代に生きる私たちにも深く問いかけます。ある殺人事件を起点に、刑事たちが執念深く真実を追い求める過程は、まさに人間の心理の奥底を覗き込むような緊張感に満ちています。
本作の魅力は、犯人が誰なのかという「How done it」よりも、なぜその行為に及んだのかという「Why done it」に重点が置かれている点にあります。犯人の動機が明らかになるにつれて、読者は単なる犯人への憎悪だけではない、複雑な感情を抱くことになるでしょう。社会の不条理が生み出した悲劇が、個人の人生をいかに狂わせるかという、松本清張作品ならではの骨太な視点が貫かれています。
そして、その悲劇の背景には、ある特定の病に対する根深い差別問題が横たわっています。この社会的なテーマが、物語に一層の深みと普遍性をもたらしているのです。私たちは、登場人物たちの人生を通して、差別がもたらす計り知れない影響と、それによって生まれた人間の苦悩を目の当たりにします。
読み終えた後も、心の奥底に重くのしかかるような余韻を残す『砂の器』。その物語が描き出すのは、私たち自身の心の中にも潜むかもしれない、無意識の差別意識や偏見です。本作は、読者一人ひとりに、人間とは何か、社会とは何かという問いを投げかける、まさしく文学の金字塔と呼べる作品と言えるでしょう。
『砂の器』のあらすじ
物語は、昭和の初夏、東京のとある操車場で発見された身元不明の男性の撲殺死体から始まります。事件は難航を極め、捜査陣は唯一の手がかりである、犯人らしき若い男が発した東北訛りの「カメダ」という言葉を頼りに、広大な日本中を駆け巡ることになります。
警視庁のベテラン刑事・今西栄太郎と、若手刑事の吉村弘は、この些細な情報を手がかりに、地道な聞き込み捜査を重ねていきます。行く先々で様々な人々に出会い、新たな情報がもたらされる中で、事件の輪郭が少しずつ見えてくるのです。しかし、「カメダ」が地名なのか人名なのかも定かではなく、捜査は何度も袋小路に入り込みそうになります。
そんな中、今西刑事は言語学的な視点から、東北弁と出雲弁に音韻の類似性があるという学説に注目し、捜査の範囲を島根県へと広げるという大胆な決断を下します。この意外な方向転換が、事件解決の大きな突破口となるのですが、そこには想像を絶するような人間の「宿命」が隠されていました。
捜査が進むにつれて、被害者の身元がかつてある土地の駐在所に勤務していた元巡査であることが判明し、さらに新進気鋭の天才作曲家・和賀英良が事件に深く関わっている可能性が浮上します。華やかな表舞台で活躍する和賀の完璧な人生の裏には、人知れず隠蔽されてきた、あまりにも悲しく、そして残酷な過去が潜んでいたのです。
『砂の器』の長文感想(ネタバレあり)
『砂の器』を読み終えた時、私の胸には、ただ「すごい」という一言だけでは語り尽くせない、複雑な感情が渦巻いていました。松本清張という作家が、いかに人間の心の深淵を覗き込み、社会の暗部をえぐり出すことに長けていたのかを、改めて痛感させられたのです。これは単なる殺人事件の謎解きではありません。そこには、ある一人の人間の想像を絶する「宿命」が、あまりにも鮮烈に、そして悲しく描かれていました。
物語の導入は、東京の蒲田操車場で発見された身元不明の男性の遺体から始まります。この最初の段階で、読者はこの事件がただならぬものであることを直感します。被害者の身元が全く不明であるという状況は、通常の推理小説であれば捜査が行き詰まる大きな壁となるはずです。しかし、今西刑事と吉村刑事という対照的な二人の刑事が、この困難な事件に真正面から立ち向かっていく姿が、まず心を掴みます。
特に印象深いのは、今西刑事の粘り強い、そして驚くほど地道な捜査です。彼が唯一の手がかりである「カメダ」という言葉と東北訛りを頼りに、全国津々浦々を巡る様子は、まさに執念と呼ぶにふさわしいものです。現代であれば、データベースやデジタル技術を駆使してあっという間に解決しそうな事柄も、昭和の時代では足で稼ぐしかありません。その泥臭いまでの捜査の過程が、読者に深い共感を呼びます。
そして、今西が東北弁と出雲弁の音韻的な類似性に着目し、捜査範囲を出雲へと広げる場面は、本作における最大の転換点であり、松本清張の卓越した構成力を示す部分だと感じました。一見、無関係に見える地域と言葉が、実は歴史的な繋がりを持っていたという事実に鳥肌が立ちました。この「点と点が線になる」瞬間は、ミステリー作品における最高の醍醐味の一つであり、そのカタルシスは計り知れません。
捜査が進むにつれて、被害者の身元が元巡査の三木謙一であることが判明し、さらに若き天才作曲家・和賀英良の名前が浮上します。ここで読者は、華やかな音楽界で脚光を浴びる和賀と、殺された三木という全く接点のないように見える二人が、どのようにして繋がっていくのかという新たな謎に引き込まれます。この段階で、読者は和賀が犯人である可能性に気づき始めますが、その動機はまだ不明であり、それが作品に深い奥行きを与えています。
和賀英良の存在は、本作における最も重要な要素の一つでしょう。彼は、誰もが羨むような成功を収め、華々しいキャリアを築いています。しかし、その完璧な表の顔の裏には、決して誰にも知られてはならない、あまりにも悲惨な過去が隠されていました。彼の隠された正体が、ハンセン病患者の息子である本浦秀夫であると判明する時、物語は一気にその本質を露わにします。
ハンセン病に対する社会の根深い差別と偏見が、和賀の人生をいかに決定づけたか。その描写は、読者に強烈な衝撃を与えます。幼い頃、父と共に社会から排斥され、石を投げられ、行く先々で冷遇される。その過酷な放浪の日々は、想像を絶する苦難に満ちていたに違いありません。この部分が、和賀の犯行の動機を単なる自己保身を超えた、より深い「宿命」へと昇華させています。
特に心に残るのは、和賀の父である本浦千代吉と幼い秀夫(和賀)が旅をするシーンです。セリフがなく、ただ彼らの姿が描かれるだけですが、その姿から伝わる悲しみ、絶望、そして互いを慈しむ親子の絆は、言葉以上に雄弁です。当時、ハンセン病患者とその家族が置かれていた悲惨な状況を、読者は肌で感じることができます。三木謙一が、そんな彼らに手を差し伸べた唯一の「善意の人物」であったという事実は、彼の死の悲劇性を一層際立たせます。善意が、まさか殺人を引き起こす原因となるという皮肉に、人間の運命の残酷さを感じずにはいられません。
和賀が三木謙一を殺害した動機は、まさに「過去の清算」でした。彼が築き上げてきた華やかな人生は、まさに「砂上の楼閣」であり、三木という過去の証人が現れたことで、その砂の器が崩れ去ることを恐れたのです。この殺人は、彼の成功への執着と、過去の差別から逃れようとする悲壮なまでの決意の現れであり、そこに彼の苦悩と業が凝縮されています。
高木理恵子の存在も、和賀の人間性を深く掘り下げる上で重要な役割を果たしています。彼女との関係性、そして彼女が身籠った子供を冷酷に堕胎させようとする和賀の姿は、彼が成功のためには手段を選ばない人物であることを示唆すると同時に、彼が過去の自分自身(父親のいない子供)を重ね合わせていることを暗示しています。理恵子の悲劇的な死は、和賀の罪の深さと、彼が背負う「宿命」が、彼自身だけでなく、彼に関わる人々にも悲劇をもたらすことを象徴しているように感じました。
物語のクライマックス、今西刑事による捜査会議での事件の全貌解明と、同時進行で演奏される和賀英良の組曲「宿命」は、圧巻の一言です。今西が淡々と事実を語る一方で、和賀の指揮とピアノ演奏、そして彼自身の悲惨な過去の回想が交錯する演出は、読者の感情を揺さぶります。この対比が、和賀の犯行が単なる悪意から生まれたものではなく、社会が生み出した差別という「宿命」から逃れようともがいた一人の人間の悲劇であったことを、より深く心に刻みつけます。
和賀が自身の人生を「宿命」と名付けた楽曲に込めた思いは、計り知れません。それは、彼がハンセン病の父の息子として生まれ、その出自ゆえに受けた差別が、彼の人生を決定づけたという絶望感であり、それでもなお、父への深い愛情と鎮魂の念が入り混じった複雑な感情なのでしょう。今西刑事が「和賀は音楽を通じて、今、父と会っているんだ」と語る言葉は、この「宿命」が単なる悲劇だけでなく、親子の絆という普遍的なテーマをも内包していることを示唆しており、深い感動を覚えました。
最終的に、和賀が拍手喝采を浴びるその瞬間、舞台袖には彼を逮捕しようとする刑事たちが待ち構えているという構図は、あまりにも悲劇的でありながら、同時に彼の「宿命」の終着点を示唆しているように感じられました。彼の成功が、結局は過去の砂の上に築かれた脆い器であったことを、この結末が雄弁に語っています。
『砂の器』は、単なるミステリーとしてだけでなく、社会が抱える根深い差別問題、人間の業、そして親子の絆という普遍的なテーマを深く掘り下げた作品として、今なお多くの人々に語り継がれる理由がよく分かりました。私たちが無意識に持っているかもしれない差別意識や偏見を突きつけ、善良な多数派が恐怖や保身のために差別を生み出してきた歴史を想起させる力を持っています。この物語が問いかける「宿命」とは、特定の病気や出自に限らず、誰もが背負う可能性のある過去や社会的な制約のことかもしれません。私たちはこの「宿命」にどう向き合い、どう生きていくべきなのか。深く考えさせられる一冊でした。松本清張の社会派としての真骨頂を味わえる、紛れもない傑作であると断言できます。
まとめ
松本清張の『砂の器』は、単なる殺人事件の解明に留まらず、人間の宿命、差別、そして親子の絆という重厚なテーマを深く掘り下げた傑作でございます。蒲田操車場での身元不明死体発見を起点に、今西刑事と吉村刑事の執念深い捜査が、事件の深層に隠された悲劇的な真実を炙り出していきます。
唯一の手がかりである「カメダ」という言葉から、今西刑事が言語学的な知見を頼りに捜査範囲を出雲へと広げる展開は、松本清張作品ならではの巧みな構成力を感じさせます。そして、華やかな音楽界のスターである和賀英良が、過去にハンセン病患者の息子として過酷な放浪生活を送った本浦秀夫であったという衝撃的な事実が明らかになります。
和賀が三木謙一を殺害した動機は、彼が築き上げた偽りの成功と名声を、過去の証人である三木に壊されることを恐れた自己防衛にありました。しかし、その根底には、ハンセン病に対する社会の根深い差別が生み出した、彼自身の「宿命」が横たわっています。成功という「砂の器」が、過去という名の「砂」によって崩れ去るという暗示は、深く心に響きます。
物語のクライマックスでは、今西刑事の冷静な捜査報告と、和賀が作曲した「宿命」の演奏が同時並行で描かれ、犯人の罪と悲しみが一体となって観る者に迫ります。この対比が、差別という社会の不条理と、それから逃れようともがいた一人の人間の悲哀を鮮やかに描き出し、深い感動と社会への問いかけを促すのです。