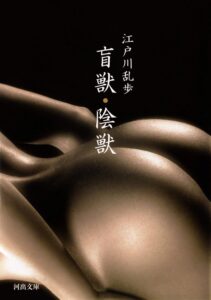 小説「盲獣」のあらすじを結末まで含めて紹介します。詳細な物語の解釈や感じたことも書いていますのでどうぞ。江戸川乱歩によるこの物語は、昭和初期、1931年から翌年にかけて雑誌「朝日」で連載された中編作品です。乱歩作品の中でも、その特異なテーマと猟奇的な展開で知られていますね。
小説「盲獣」のあらすじを結末まで含めて紹介します。詳細な物語の解釈や感じたことも書いていますのでどうぞ。江戸川乱歩によるこの物語は、昭和初期、1931年から翌年にかけて雑誌「朝日」で連載された中編作品です。乱歩作品の中でも、その特異なテーマと猟奇的な展開で知られていますね。
物語の中心となるのは、視覚を失った代わりに異常なまでに発達した触覚を持つ「盲獣」と呼ばれる男です。彼はその特殊な感覚で女性の肉体を「鑑賞」し、ついには恐ろしい事件を引き起こしていきます。本作には、読者の多くが期待するであろう名探偵・明智小五郎は登場しません。それどころか、事件を追う探偵や刑事といった存在すら描かれず、犯罪者の視点に近い形で物語が進むのが特徴と言えるでしょう。
この物語は、人間の感覚、特に触覚というものに焦点を当て、美と醜、芸術と狂気、愛と死といったテーマを深く掘り下げています。読み進めるうちに、不気味でありながらもどこか引き込まれるような、独特の世界観に浸ることになるでしょう。猟奇的な描写も含まれるため、読む人を選ぶかもしれませんが、乱歩文学の持つ暗い魅力が凝縮された一作であることは間違いありません。
この記事では、まず物語の詳しい筋道を追い、その後で、この作品から受けた印象や考えたことを詳しく述べていきます。結末に関する情報も含まれますので、まだ読んでいない方はご注意ください。それでは、江戸川乱歩が描いた触覚の迷宮、「盲獣」の世界へご案内しましょう。
小説「盲獣」のあらすじ
浅草オペラの花形女優、水木蘭子は、弟子と共に訪れた美術館で、自身の姿をモデルにした彫刻に異様なほど執着する盲目の紳士に出会います。その彫刻は彫刻家・里見雲山の手によるものでした。盲人は警備員が来る前に姿を消しますが、この出会いが蘭子の運命を大きく狂わせる序章となります。
数日後、蘭子の楽屋に見慣れない盲目の按摩師が現れます。彼は蘭子の体を執拗に撫で回し、不気味さを感じた蘭子は彼を追い返します。しかし、翌日馴染みの按摩師から、前日は蘭子側から断りの連絡があったと聞かされ、蘭子はあの盲人が計画的に近づいてきたことを悟るのでした。さらに、舞台公演中、客席にあの盲人の姿を見つけた蘭子は恐怖に駆られます。
公演後、恋人である小村昌一からの迎えの車だと信じて乗り込んだ車は、蘭子を麹町にある謎めいた洋館へと連れ去ります。女中に導かれるまま、鏡の裏の隠し通路を通り、真っ暗闇の地下室へ。そこで蘭子を待っていたのは、壁一面に人間の体の一部を模したオブジェが飾られた異様な空間と、あの盲目の男でした。
盲人は、視覚がない代わりに触覚に無上の喜びを見出し、特に女性の体に触れることを至上の快楽としていると語ります。蘭子の体が素晴らしいという評判を聞きつけ、手に入れたいと願っていたのでした。抵抗もむなしく、蘭子は地下室に監禁されてしまいます。しかし、不思議なことに、蘭子はこの暗闇と触覚だけの世界で、次第に盲人の男を愛するようになり、その異常な世界に没入していくのです。
数ヶ月後、盲人は蘭子に飽き、彼女を殺害してしまいます。その後、銀座に雪が降った日、盲人は雪で女の像を作り上げます。その雪像が溶けて崩れた時、中から女性の片脚が発見され、大騒動となります。バラバラにされた死体は、やがて水木蘭子のものであると判明しますが、警察の捜査は難航し、犯人は捕まりませんでした。
盲人は按摩師として銭湯に潜り込み、「真珠夫人」と呼ばれる美しい未亡人を次の標的にします。彼は言葉巧みに真珠夫人を誘い出し、例の屋敷へ連れ去ります。真珠夫人もまた蘭子と同じように盲人を愛するようになりますが、やがて飽きられ、殺害されてバラバラ死体となって発見されるのでした。その後も、盲人は寡婦クラブの女性たちに近づき、最も若く美しい大内麗子を狙います。麗子は盲人が犯人だと感づき、罠を仕掛けますが、逆に見抜かれて殺害されてしまいます。探偵役が存在しないため、盲獣の犯行は止まることなく続いていくのです。
小説「盲獣」の長文感想(ネタバレあり)
江戸川乱歩の「盲獣」を読み終えたとき、心に残るのは一種の戦慄と、奇妙な感覚の渦でした。おどろおどろしい、という言葉だけでは言い表せない、人間の感覚の根源に触れるような、それでいて深い闇を覗き込むような読書体験だったと感じています。乱歩作品には様々な怪奇譚や探偵譚がありますが、この「盲獣」は、その中でも特に異彩を放つ、忘れがたい物語の一つではないでしょうか。
物語の核心を成すのは、言うまでもなく「盲獣」と呼ばれる盲目の男の存在です。彼は単なる異常者、猟奇殺人鬼として片付けるにはあまりにも複雑な人物像を持っています。視力を失った代償として、あるいはそれゆえに、触覚という感覚を極限まで研ぎ澄ませ、そこに美と快楽を見出す。彼の行動は常軌を逸していますが、その根底には、彼なりの美学、彼なりの「芸術」への渇望があるように思えてなりません。作中、彼がなぜそうなったのか、その過去は一切語られませんが、だからこそ読者は彼の内面に広がる暗闇を想像し、ある種の畏怖を感じるのかもしれません。
最初の犠牲者となる水木蘭子の心理描写も、この物語の特筆すべき点でしょう。最初は恐怖と嫌悪感しか抱かなかったはずの蘭子が、暗闇の地下室で、視覚を奪われ触覚だけの世界に置かれるうちに、加害者である盲人を愛し、その世界に耽溺していく。この倒錯した関係性は、人間の心理の不可解さ、環境がいかに容易に人の価値観を変えてしまうかという恐ろしさを見事に描き出していると感じました。単なる被害者ではなく、ある意味で盲獣の世界の共犯者ともなっていく蘭子の姿は、読者に倫理的な問いを投げかけます。
物語の舞台となる昭和初期の東京の雰囲気も、作品の魅力を高めています。浅草オペラの華やかさ、モダンな洋館、銀座の街並みといった表の顔と、その裏に潜む人間の欲望や狂気が、コントラストとして効果的に描かれています。特に盲獣のアトリエとなる地下室の描写は強烈です。壁一面に飾られた、どぎつい色に塗られた人体のオブジェ。それは視覚的にはグロテスク極まりないものですが、盲獣にとっては最高の芸術作品であり、触覚で味わうための楽園なのでしょう。この視覚と触覚のギャップが、物語の根幹にあるテーマを象徴しているように感じます。
そして、本作で繰り返し描かれる猟奇的な殺人描写。死体をバラバラにし、それを雪像に隠したり、ハムと偽って売りさばいたりする場面は、直接的な描写は避けられているものの、読者の想像力を刺激し、強烈な不快感と恐怖を与えます。乱歩の持つ独特の嗜好性が色濃く反映されている部分であり、物語全体に暗く粘りつくような雰囲気をもたらしています。単なる残酷さだけでなく、そこには死体すらも「素材」として扱う盲獣の異常な価値観が表れているのでしょう。
この物語の最も大きな特徴の一つは、やはり「触覚」という感覚への異常なまでのこだわりです。私たちは普段、視覚情報に頼って世界を認識していますが、「盲獣」はその常識を覆し、触覚こそが世界の真実を捉える唯一の手段であるかのように描きます。盲獣にとって、女性の肌の滑らかさ、体の曲線、その温もりこそが至上の美であり、芸術なのです。彼の作る彫刻もまた、目で見るのではなく、手で触れて初めてその真価がわかるものとして描かれます。これは、視覚中心主義的な現代社会に対する、ある種の挑戦とも受け取れるかもしれません。
また、探偵役が一切登場しないという構成も非常にユニークです。通常、このような猟奇的な事件が起これば、名探偵が現れて謎を解き明かし、犯人を追い詰めるのが定石でしょう。しかし、「盲獣」では警察の捜査は後手に回り、盲獣は次々と犯行を重ね、自由に行動し続けます。読者は、事件を解決してくれる存在がいない状況で、ただただ盲獣の狂気に翻弄されることになります。この構造が、物語全体の不気味さや救いのなさを強調していると感じました。
蘭子の後に犠牲となる真珠夫人、そして大内麗子のエピソードは、盲獣の冷酷さと、彼の「愛」がいかに移ろいやすく、自己中心的なものであるかを際立たせます。特に麗子のエピソードは悲劇的です。彼女は盲獣の正体に気づき、自ら罠を仕掛けるという能動的な行動に出ますが、その計画は盲獣に完全に見透かされ、自身が惨殺される結果を招きます。知恵を絞っても、常人の理解を超えた盲獣の前では無力であるという絶望感が漂います。
寡婦クラブの描写も興味深い部分です。当時の社会における未亡人たちの立場や、閉鎖的なコミュニティの中での人間関係が生々しく描かれています。彼女たちが盲目の按摩師に興味を持ち、結果的に麗子の悲劇を招いてしまう流れは、人間の好奇心や噂話の恐ろしさをも示唆しているように思えます。
盲獣は東京での犯行が露見しそうになると、あっさりと逃亡します。その途中で海女たちを殺害するなど、彼の凶行は止まる気配がありません。社会の監視の目から逃れ、捕まることなく悪事を続ける盲獣の姿は、法や秩序といったものが、時にいかに無力であるかを感じさせます。彼の存在自体が、社会の常識や倫理観を嘲笑っているかのようです。
物語の終盤、盲獣は自らを「盲目の彫刻家」と名乗り、彫刻家の首藤春秋に接触します。そして、自身の最高傑作ともいえる、触覚によってのみ理解される彫刻を展覧会に出品させるのです。この彫刻は、最初は視覚的な不気味さから酷評されますが、やがて盲目の人々がその価値を認め、触れて感動するという異様な光景が繰り広げられます。これは、盲獣の歪んだ美学が、少なくとも一部の人々には理解され、受け入れられた瞬間と言えるのかもしれません。芸術とは何か、美とは何かという問いを、極端な形で突きつけてきます。
そして、物語は衝撃的な結末を迎えます。展覧会の最終日、その問題の彫刻の上で、作者である盲獣が自殺しているのが発見されるのです。これは、彼の「芸術」の完成を意味するのでしょうか?それとも、触覚の世界に生き続けた彼の、究極の自己表現だったのでしょうか?あるいは、もはや触れるべき新たな「素材」を見つけられなくなった末の破滅だったのか。彼の死は多くの謎を残し、読者に様々な解釈を委ねます。捕まることなく自ら命を絶つという結末は、ある意味で彼の「勝利」とも言えるのかもしれず、後味の悪さとともに強い印象を残しました。
「盲獣」は、江戸川乱歩の持つエロティシズムとグロテスク、そして人間の深層心理への探求心が見事に融合した作品だと感じます。明智小五郎が登場するような論理的な謎解きや勧善懲悪のカタルシスはありません。むしろ、不条理で、救いがなく、読後には言いようのない不安感や不快感が残るかもしれません。しかし、それこそがこの作品の持つ力であり、魅力なのではないでしょうか。
現代の視点から読んでも、「盲獣」のテーマは古びていないと感じます。感覚の持つ意味、異常心理、芸術と狂気の境界線、社会の闇といったテーマは、普遍的なものだからです。視覚情報が溢れる現代において、あえて「触覚」という感覚に焦点を当てたこの物語は、私たち自身の感覚や認識のあり方を問い直すきっかけを与えてくれるかもしれません。
「盲獣」は決して万人受けするタイプの物語ではないでしょう。しかし、一度その世界に足を踏み入れたら、忘れられない強烈な印象を刻みつけられることは間違いありません。江戸川乱歩という作家の、底知れない想像力と、人間の暗部を描き出す筆力に圧倒される、他に類を見ない読書体験でした。この不気味で美しい触覚の迷宮は、これからも多くの読者を惹きつけ、そして惑わせ続けるのだろうと思います。
まとめ
この記事では、江戸川乱歩の小説「盲獣」の物語の筋道を、結末の詳細を含めてご紹介し、併せて作品から受けた印象や考えたことを詳しく述べさせていただきました。視覚を失い、触覚に異常な執着を見せる「盲獣」が引き起こす一連の猟奇的な事件を描いた本作は、乱歩作品の中でも特に異質な光を放っています。
物語は、浅草の歌姫・水木蘭子が盲目の男に魅入られ、誘拐・監禁されるところから始まります。暗闇の中で触覚の世界に目覚め、加害者を愛してしまう蘭子の倒錯した心理、そして彼女が飽きられて殺害される衝撃的な展開。その後も盲獣は犯行を重ね、真珠夫人、大内麗子といった女性たちが次々と犠牲になります。
本作の大きな特徴は、探偵役が存在せず、犯人である盲獣が捕まることなく物語が進行する点です。読者は、盲獣の歪んだ美学と狂気に満ちた行動を、ただ見守るしかありません。触覚のみを至上とする彼の価値観、グロテスクでありながらもどこか芸術性を感じさせる彼の行動原理、そして衝撃的な結末は、読者に強烈な印象と多くの問いを残します。
「盲獣」は、猟奇的な描写や救いのない展開が含まれるため、読む人を選ぶ作品かもしれません。しかし、人間の感覚や心理の深淵、芸術と狂気の境界といった普遍的なテーマを、江戸川乱歩ならではの独創的な筆致で描いた傑作であることは確かです。もしあなたが、日常の感覚を揺さぶられるような、忘れがたい読書体験を求めているのであれば、ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。この記事が、その一助となれば幸いです。






































































