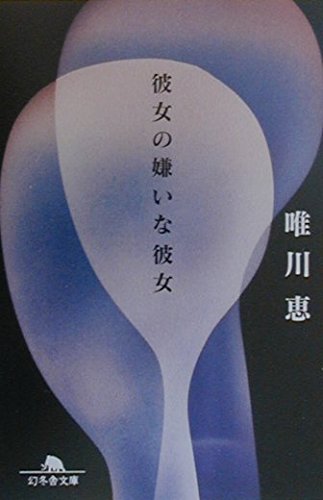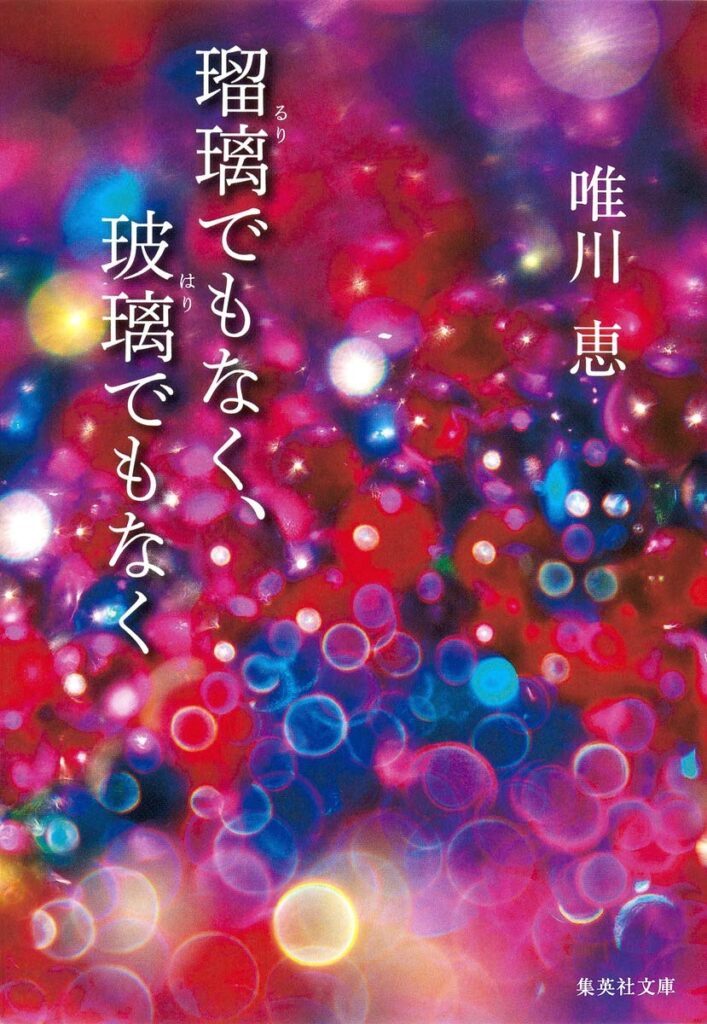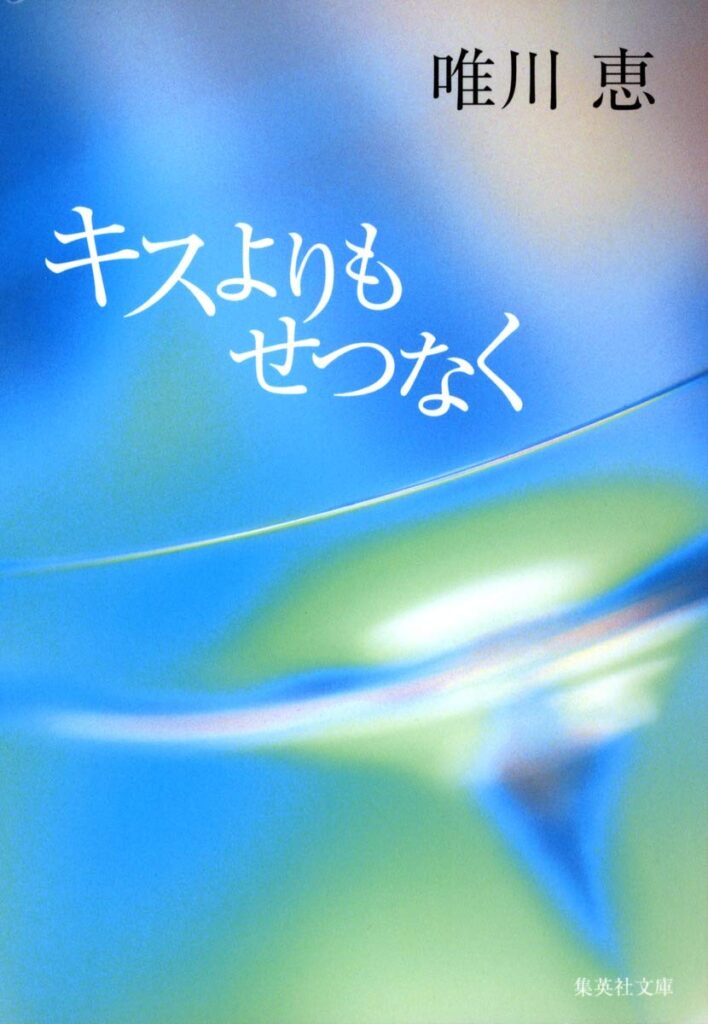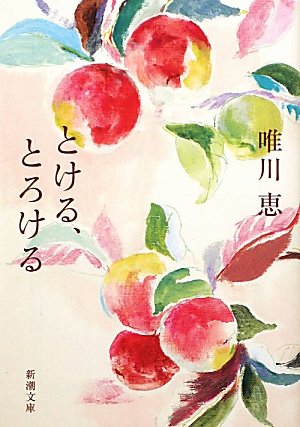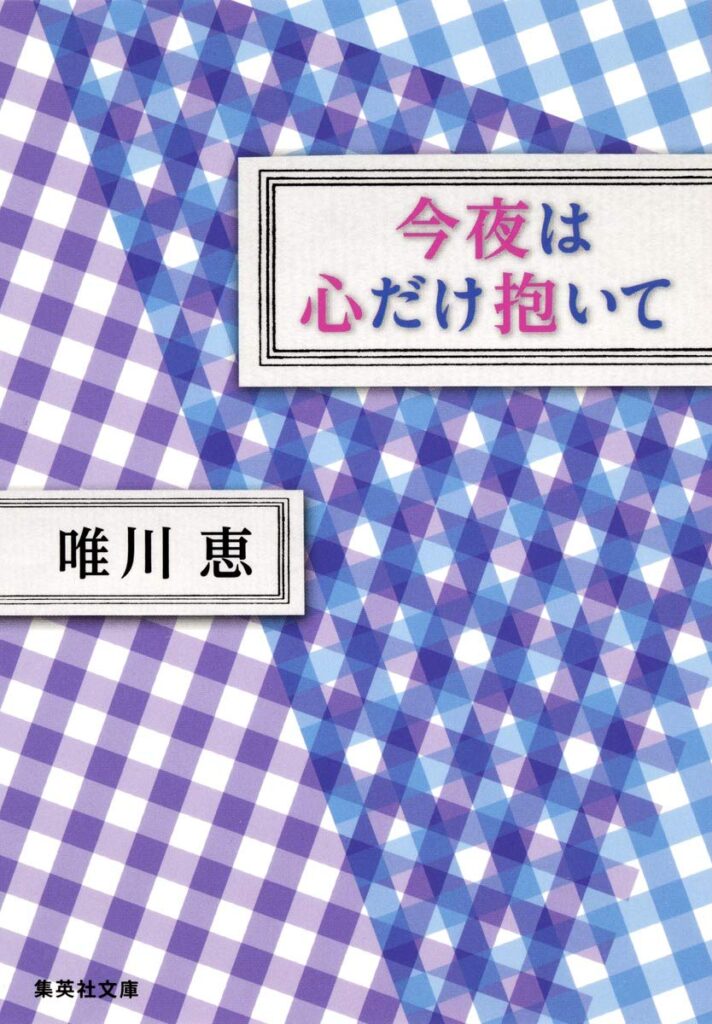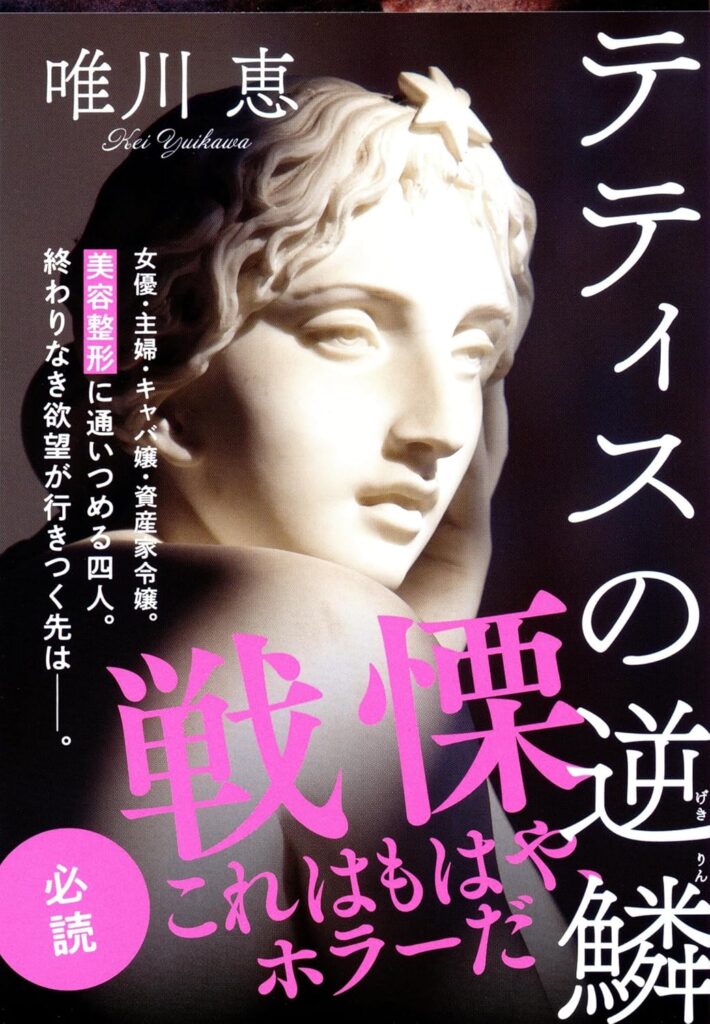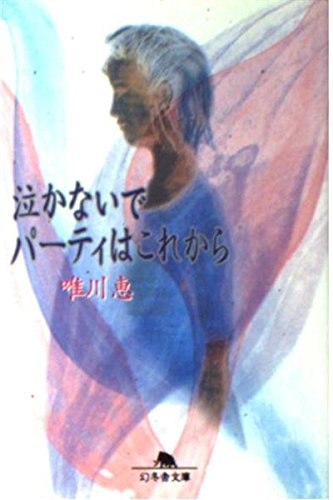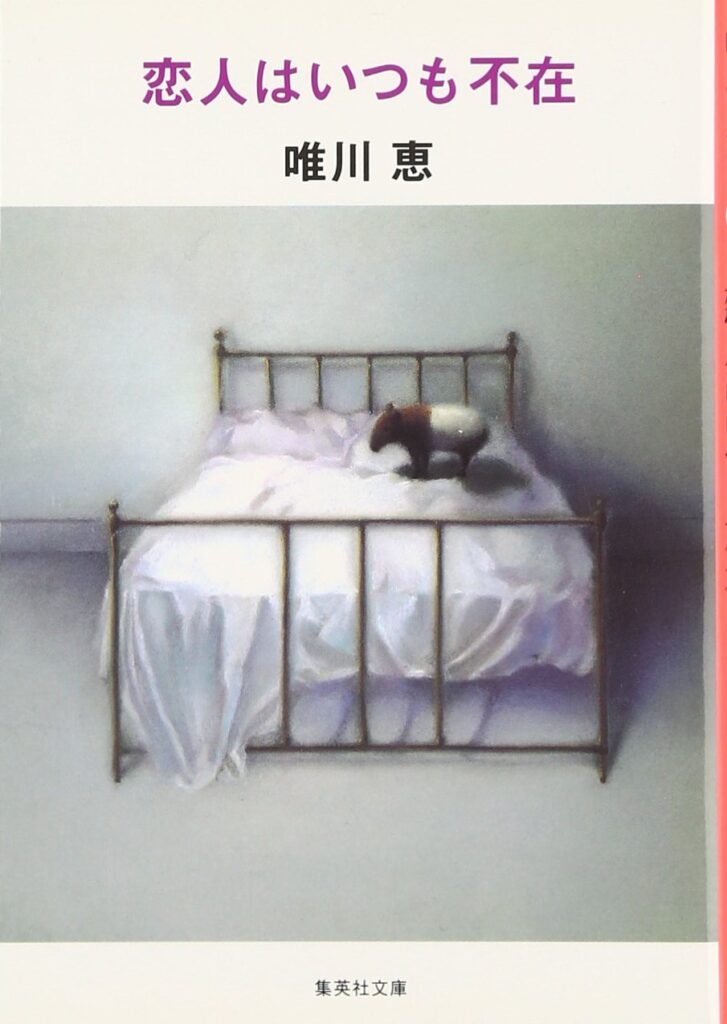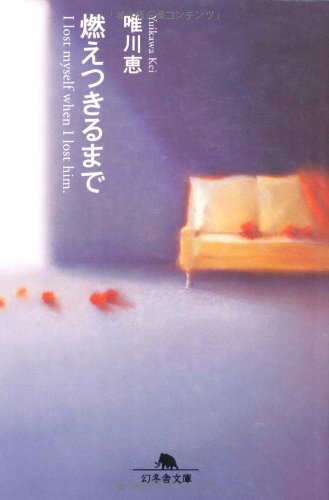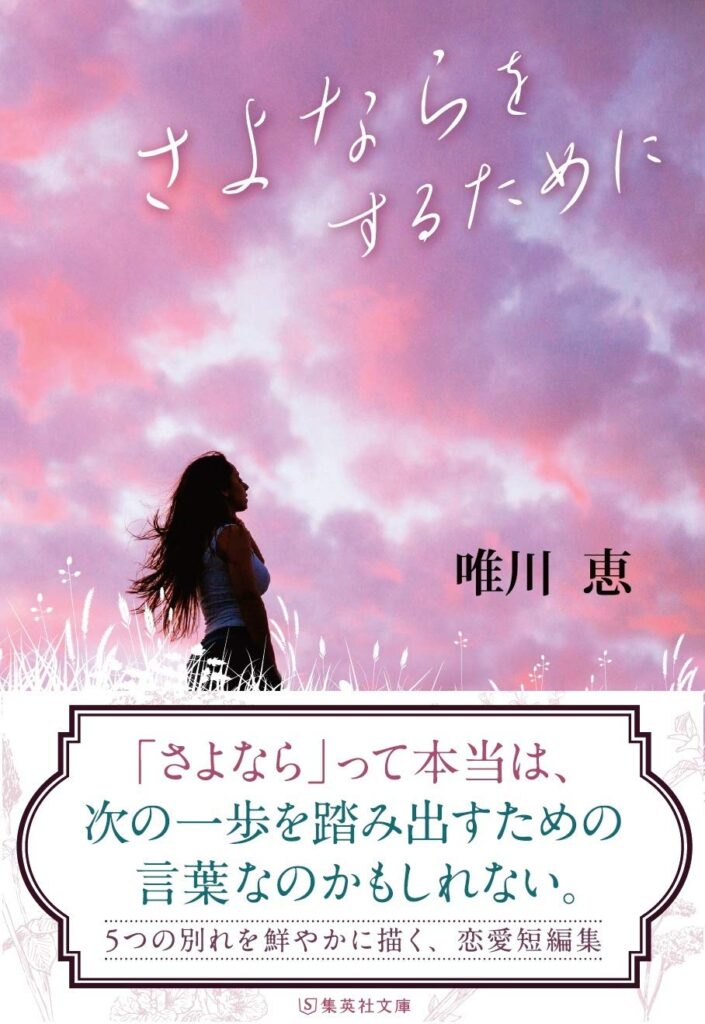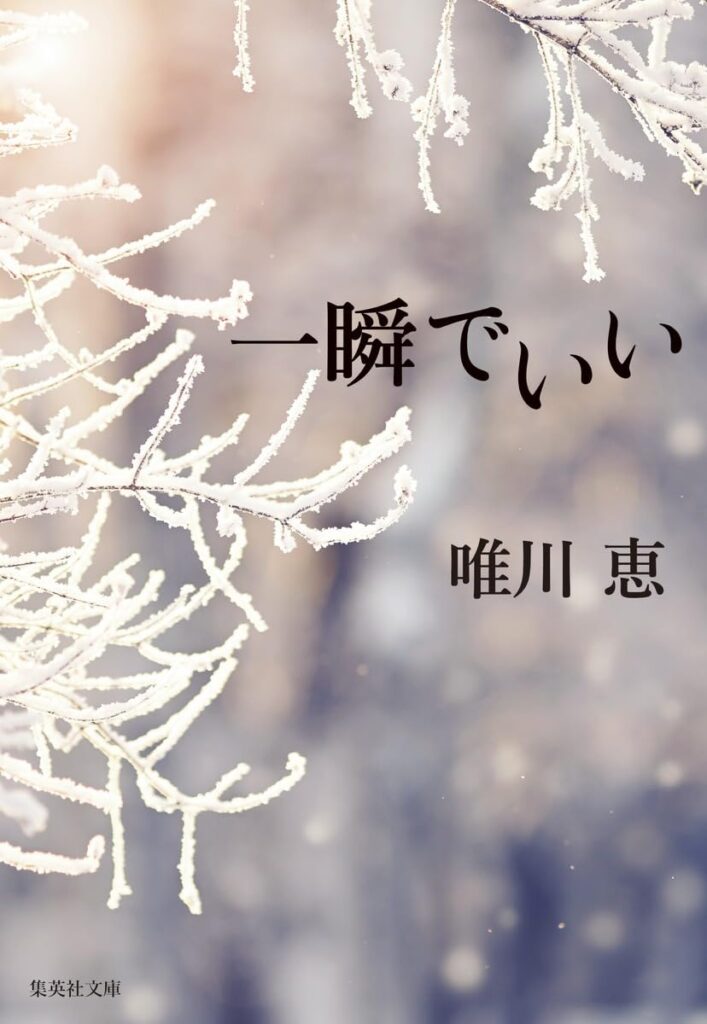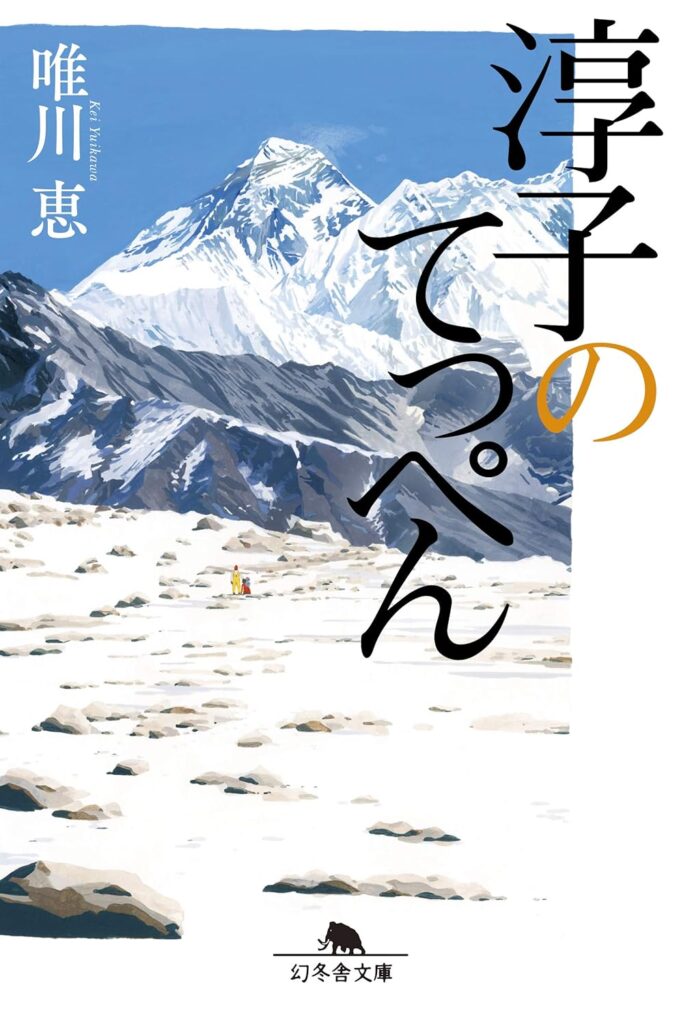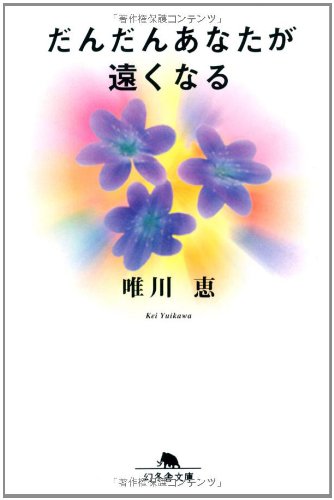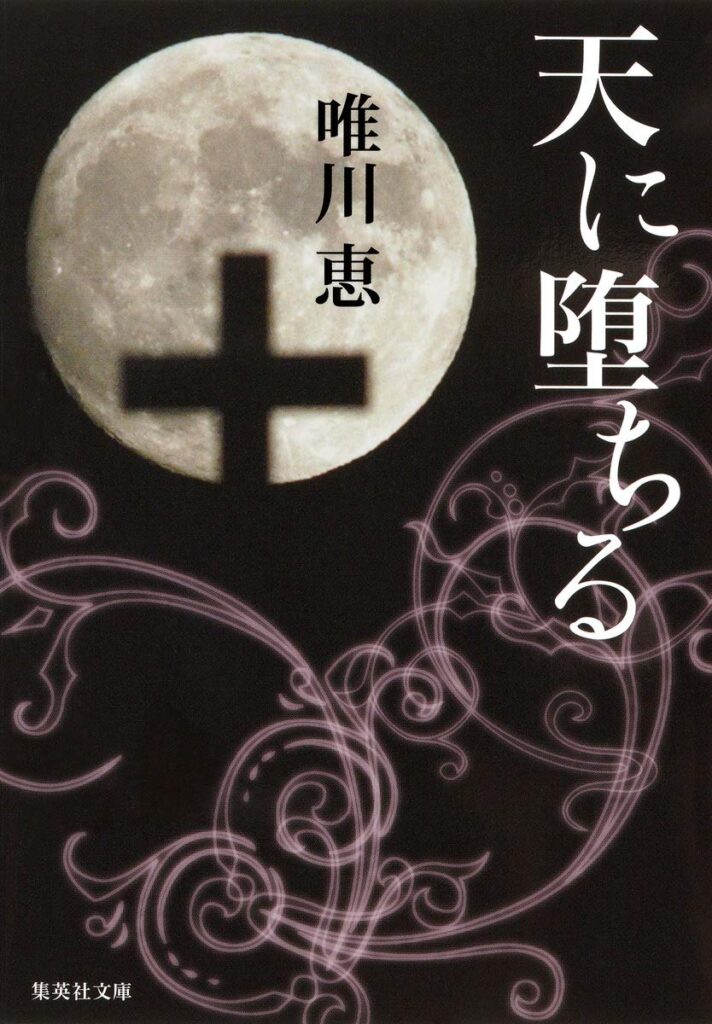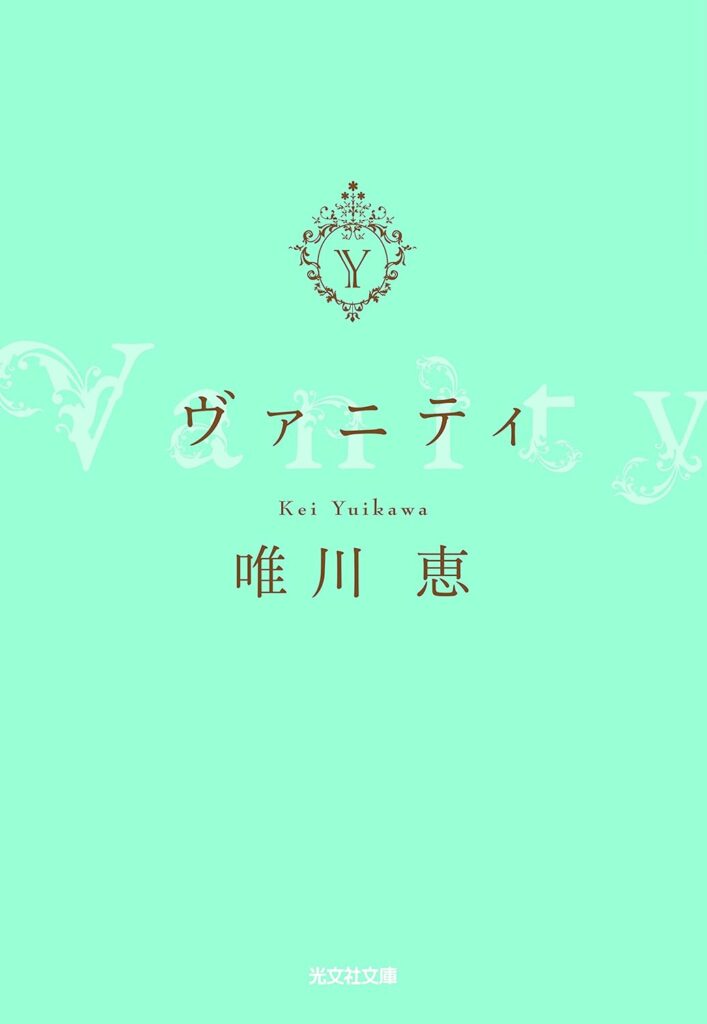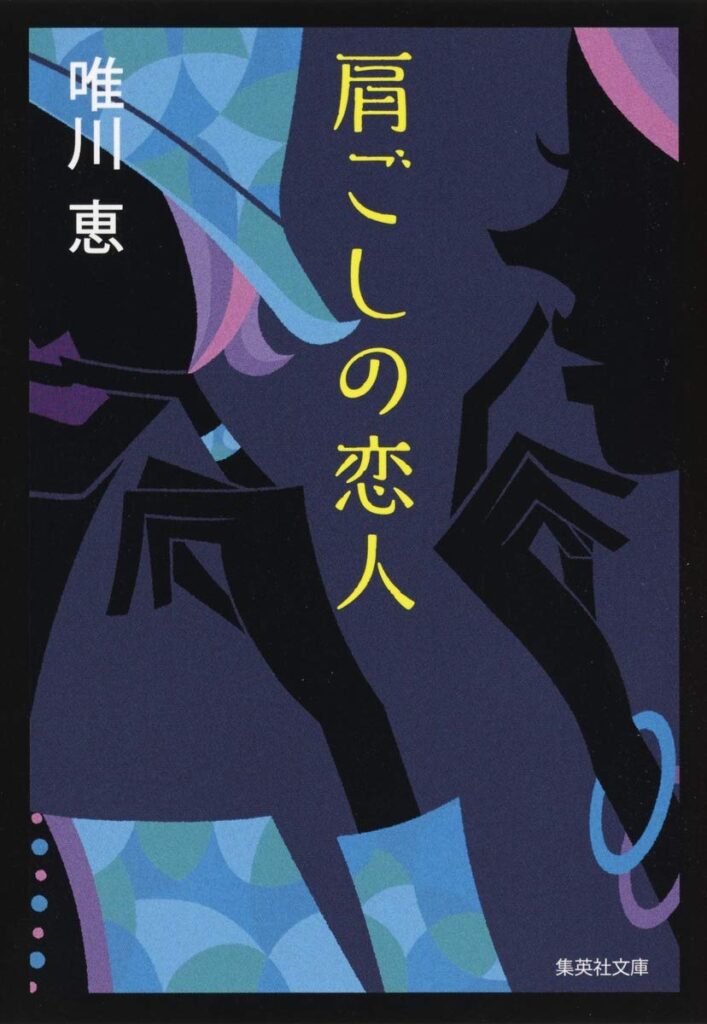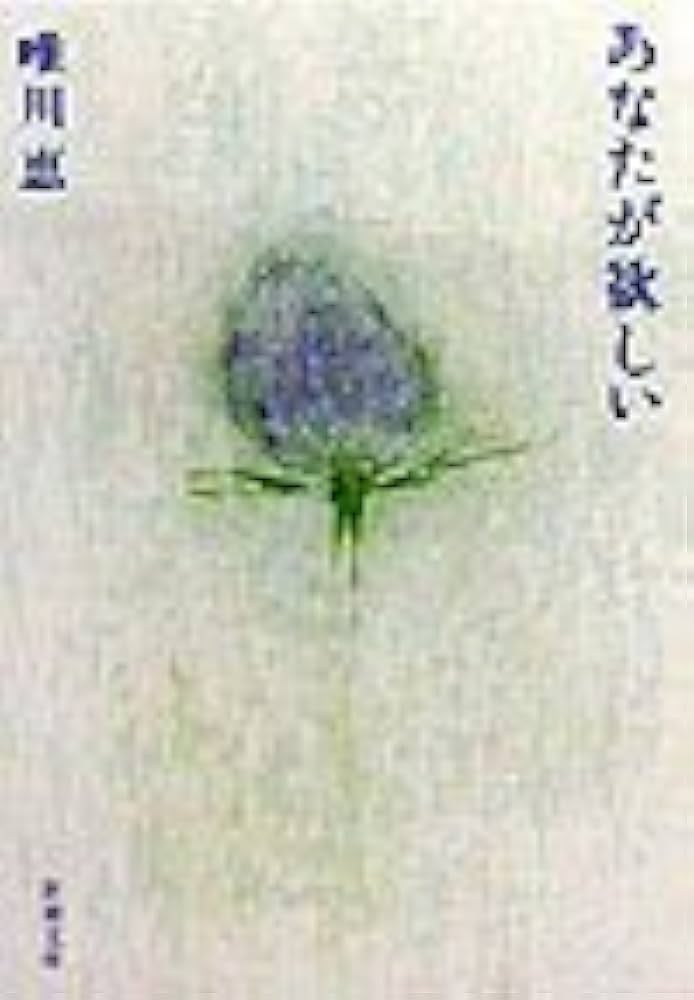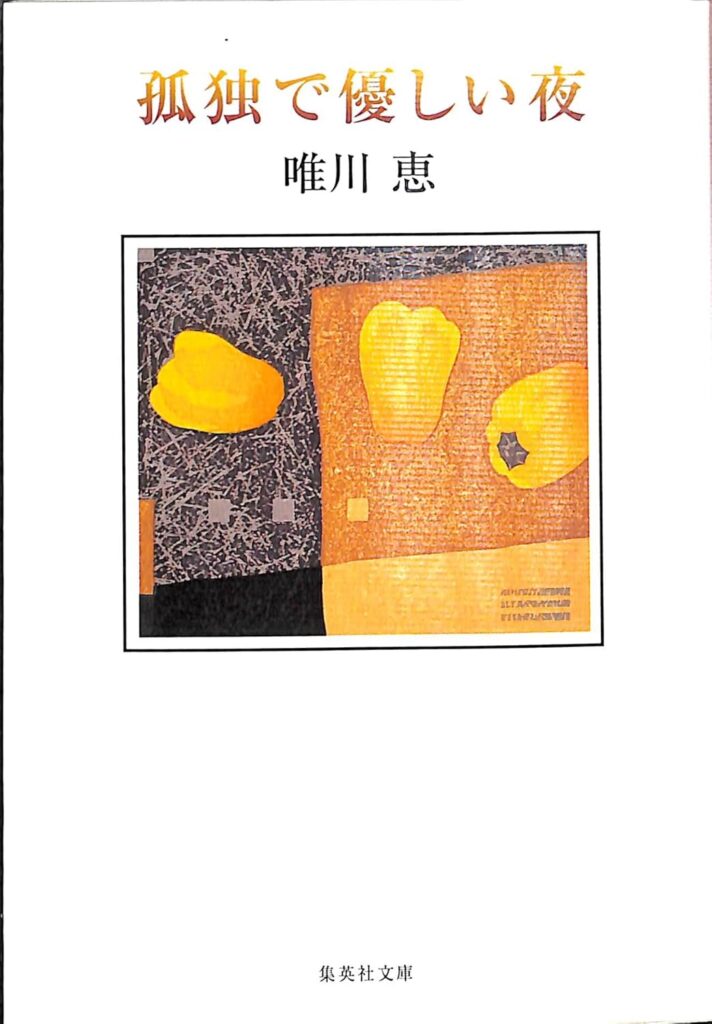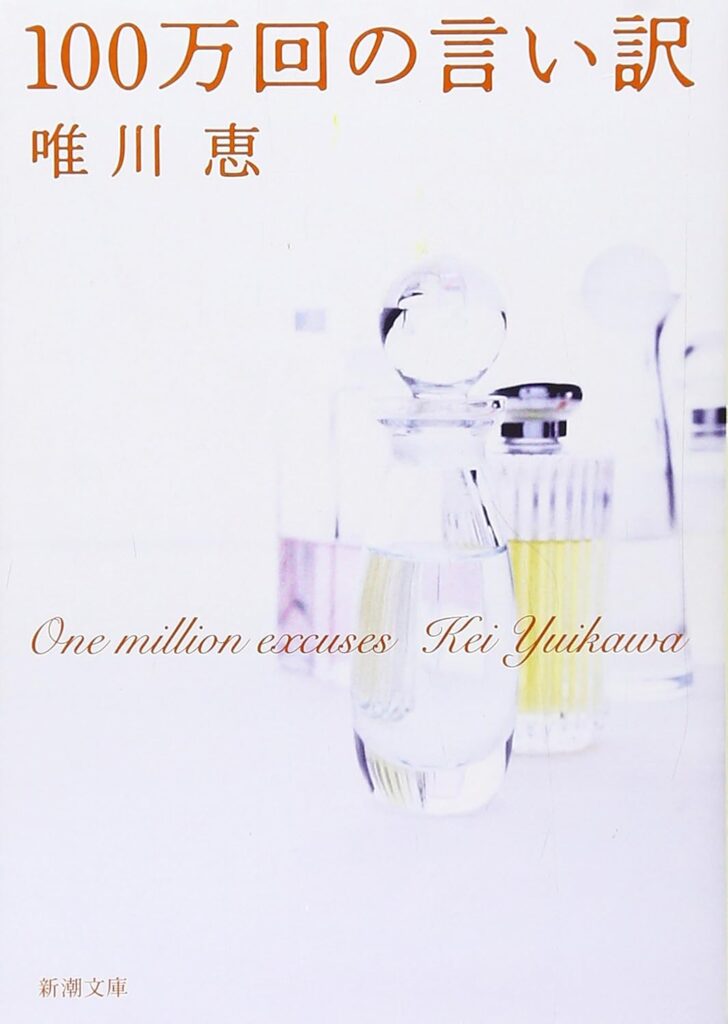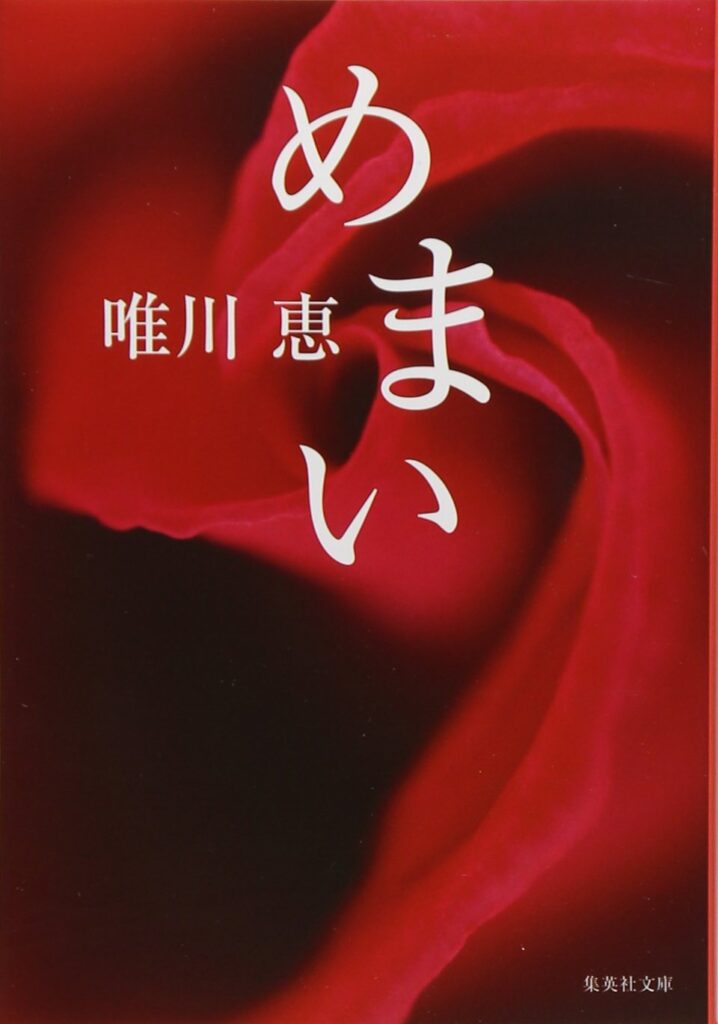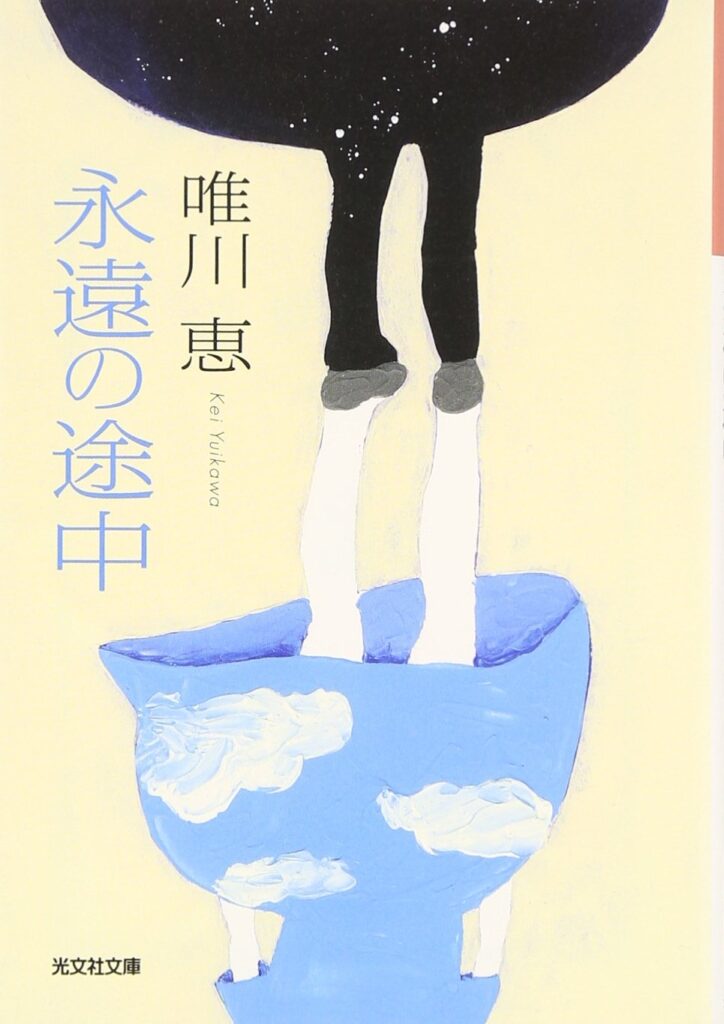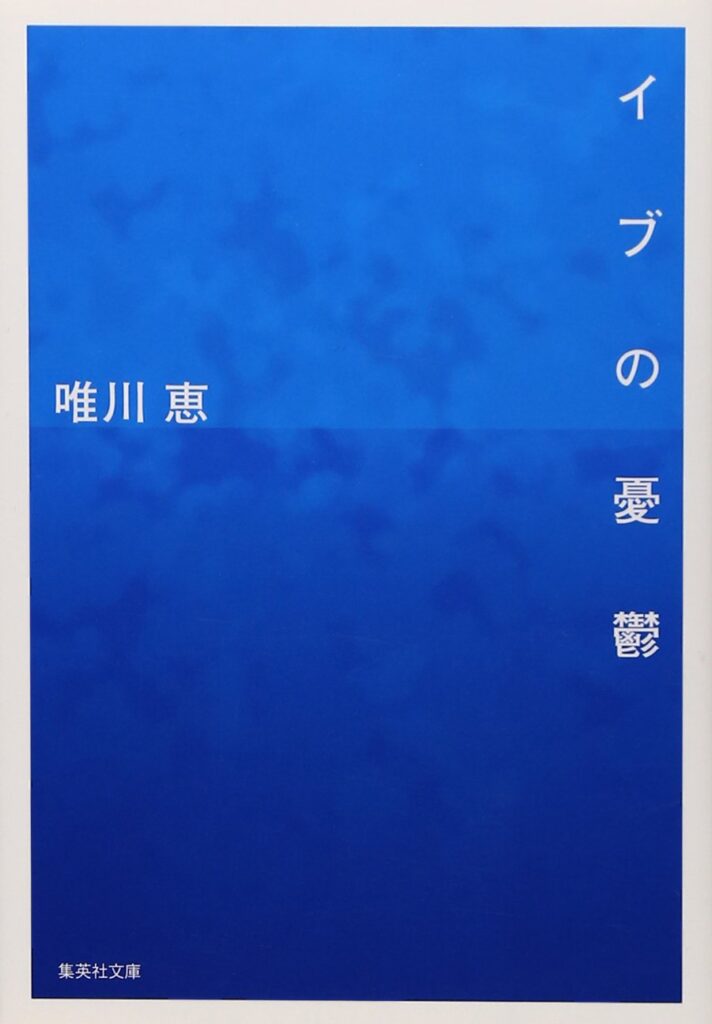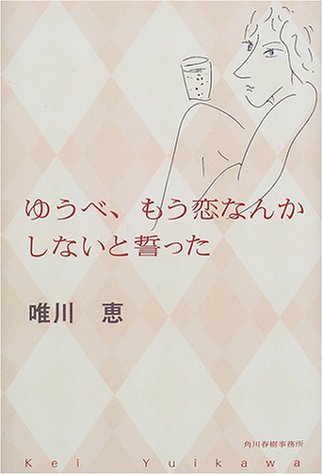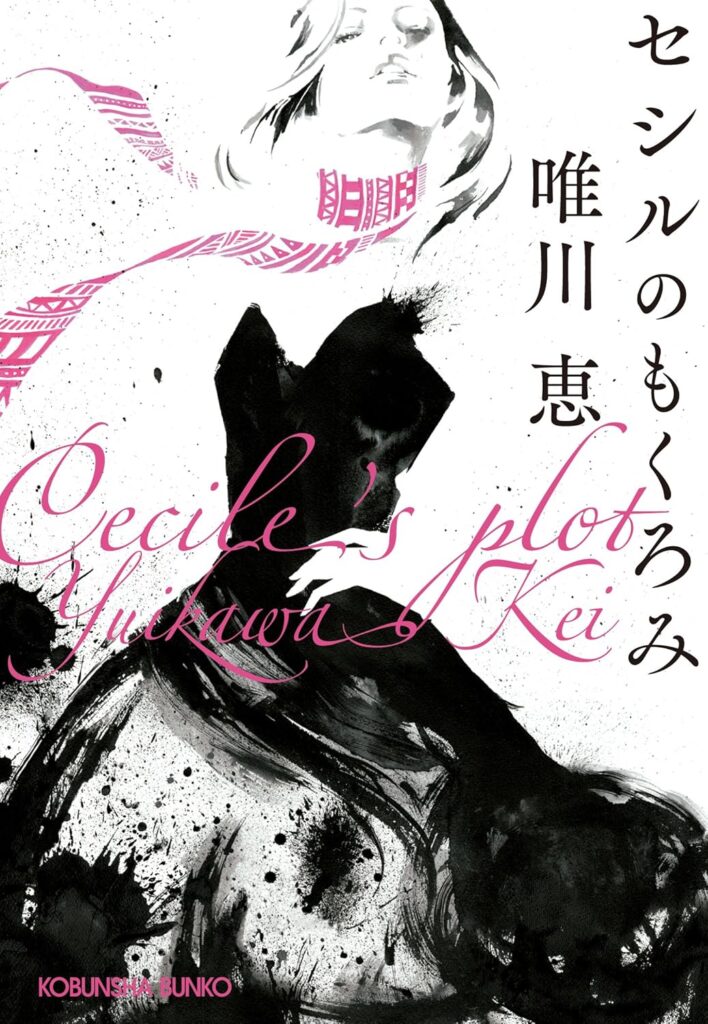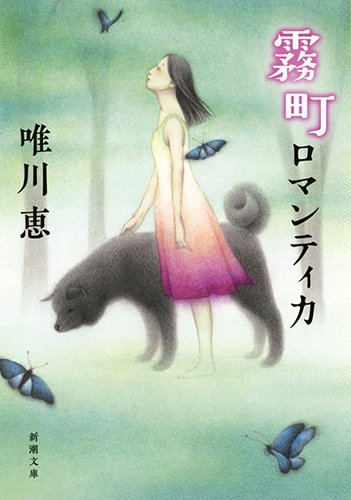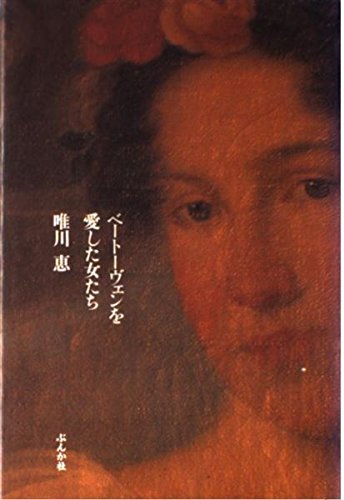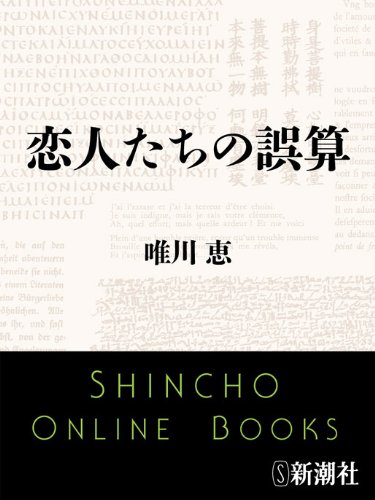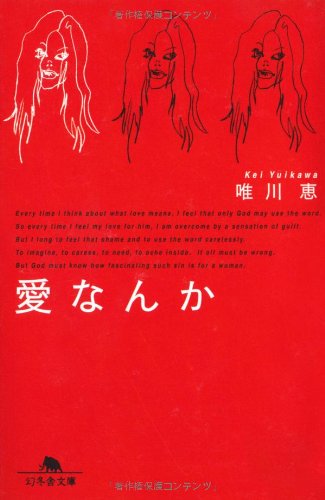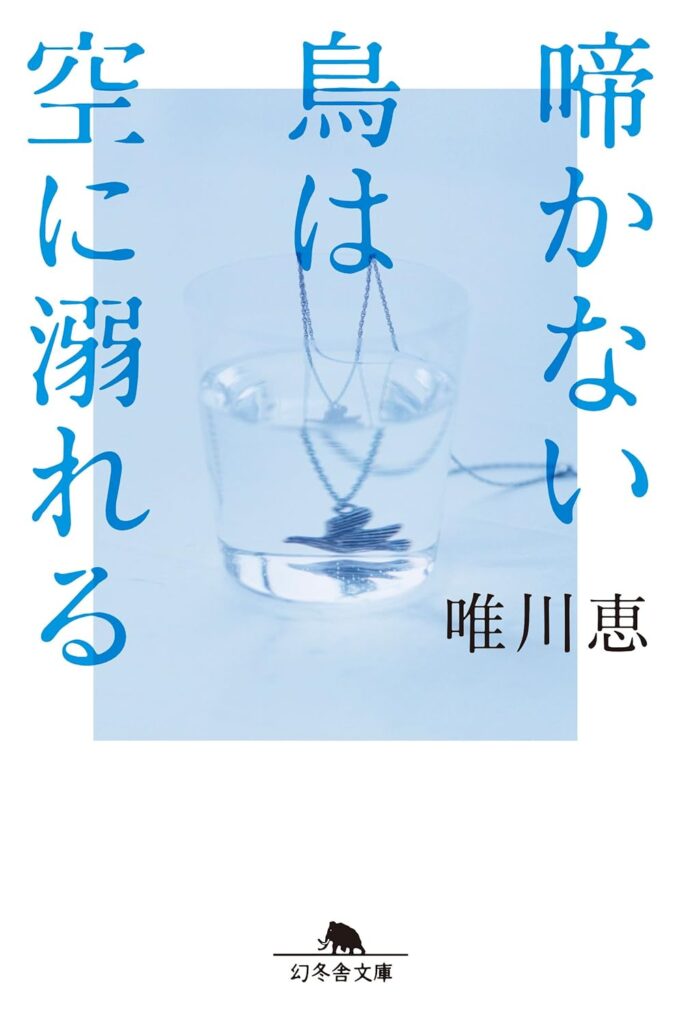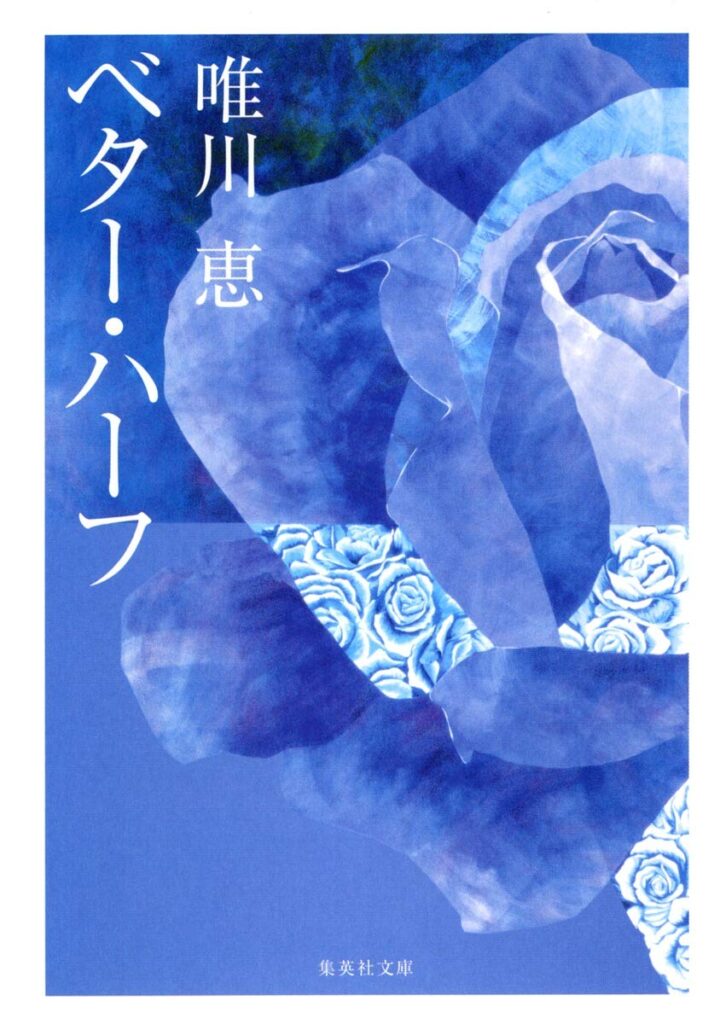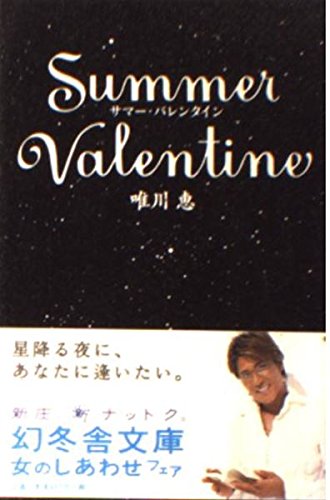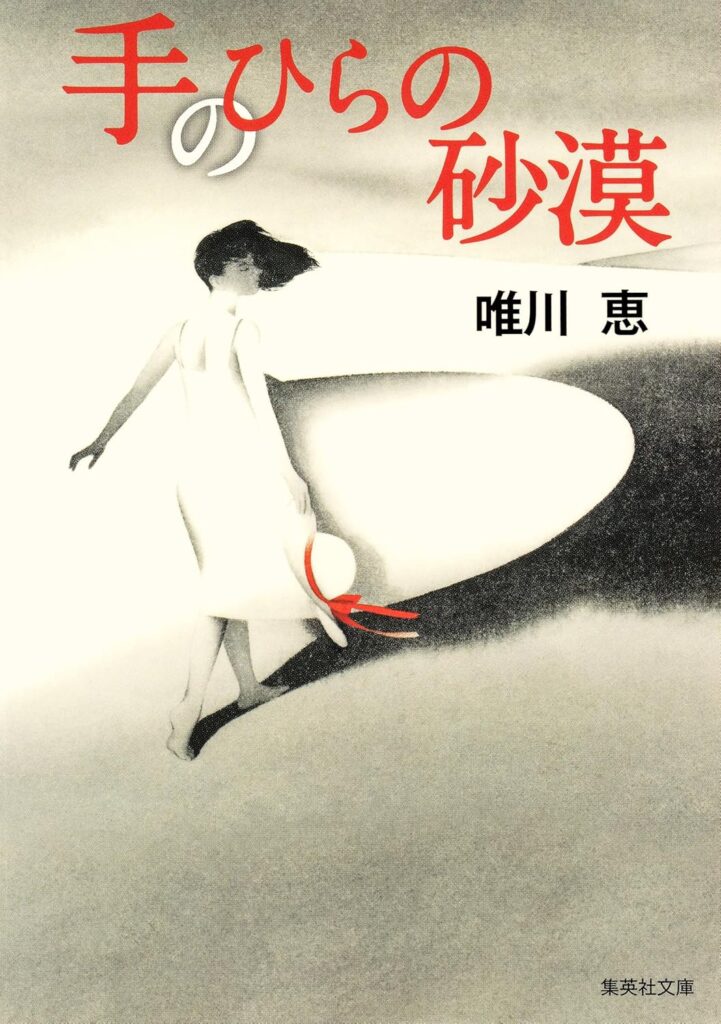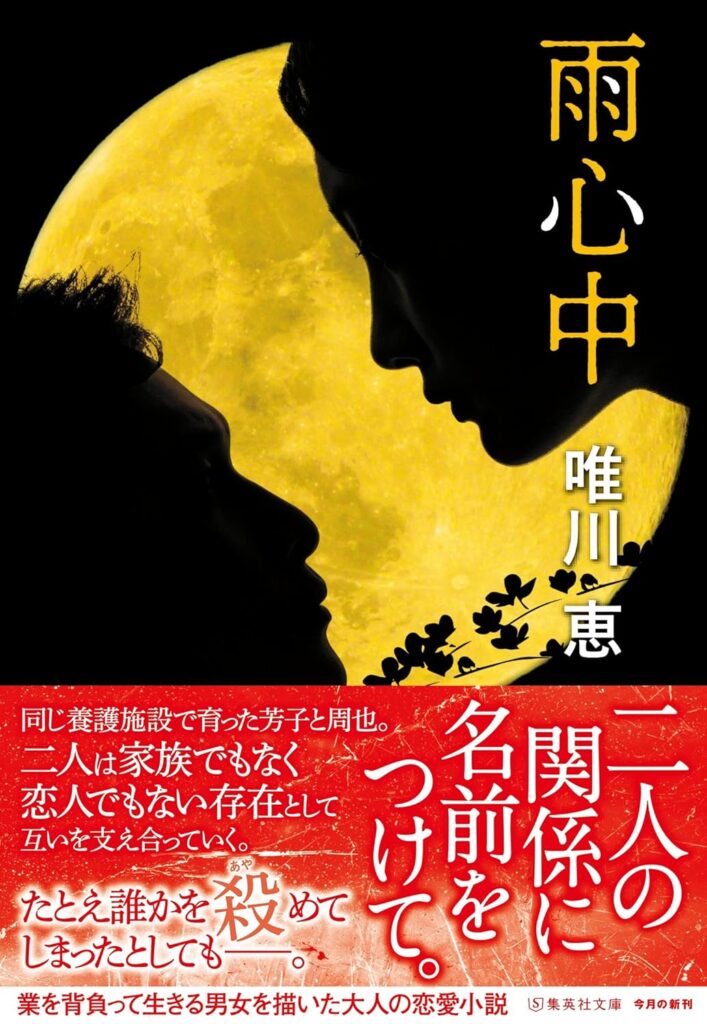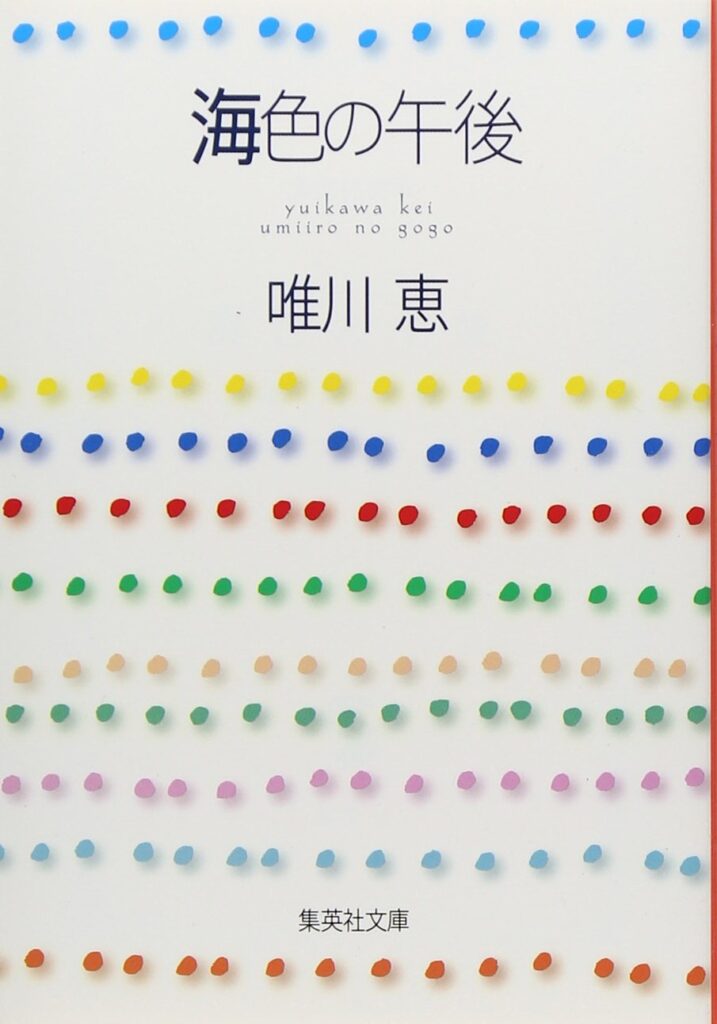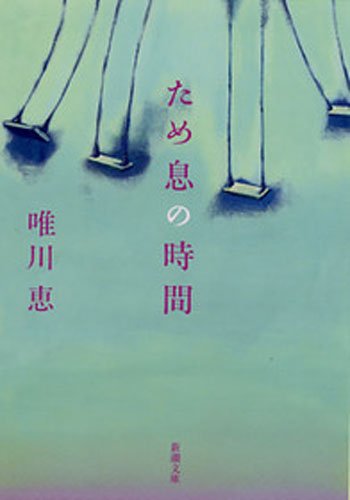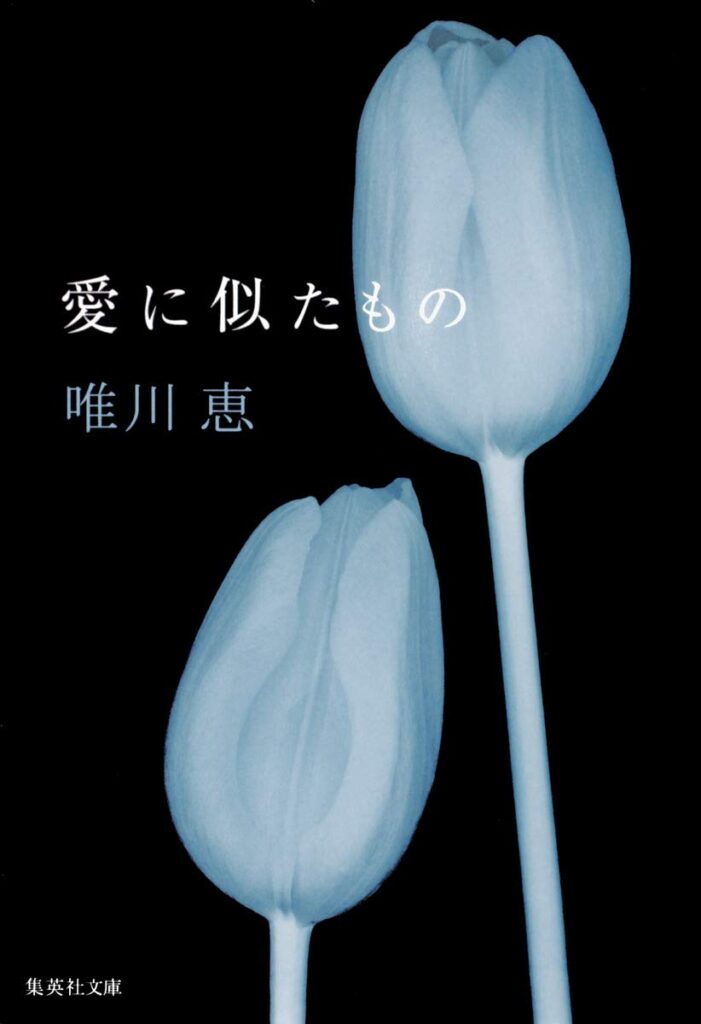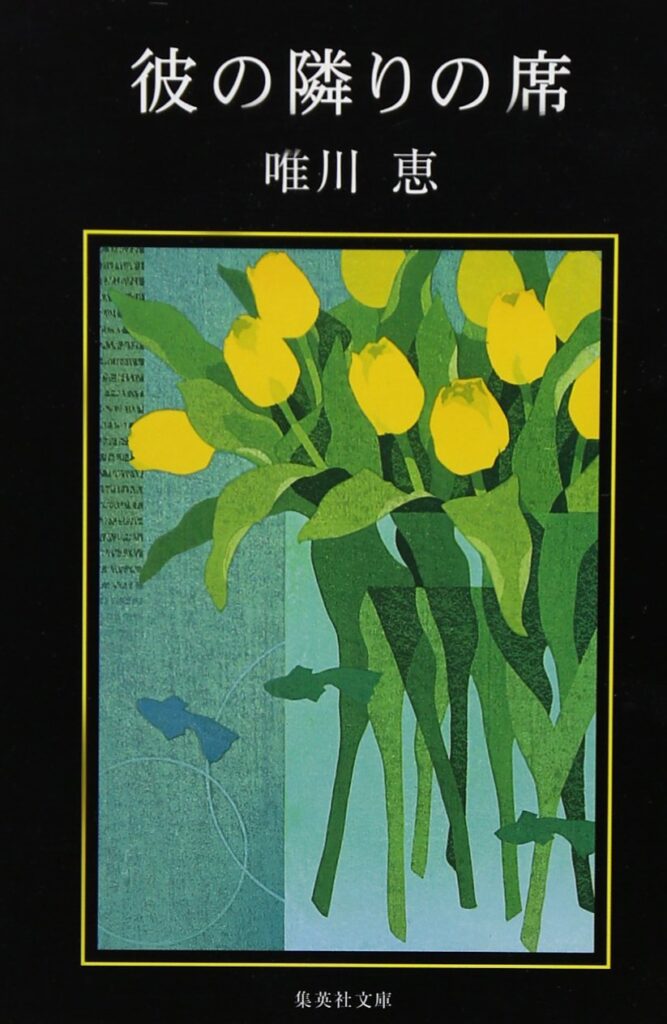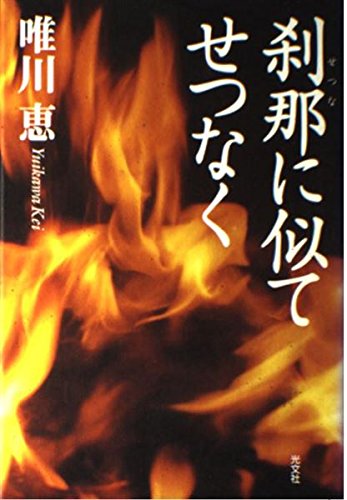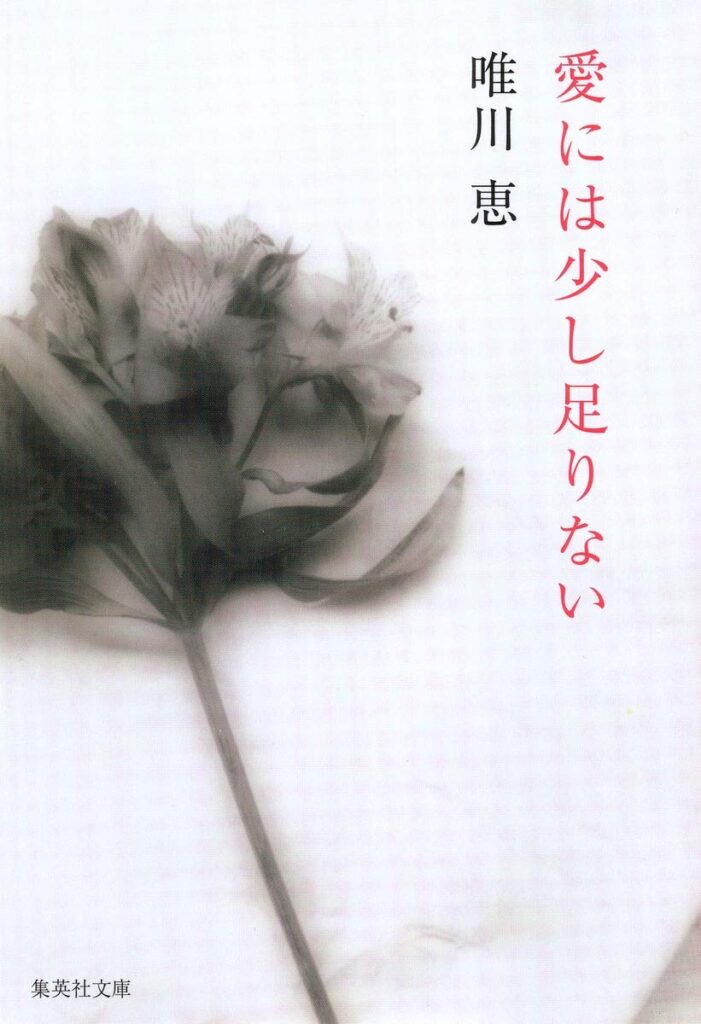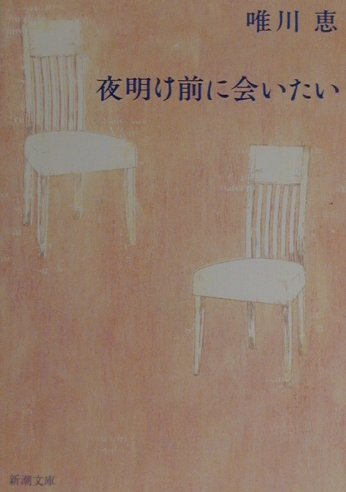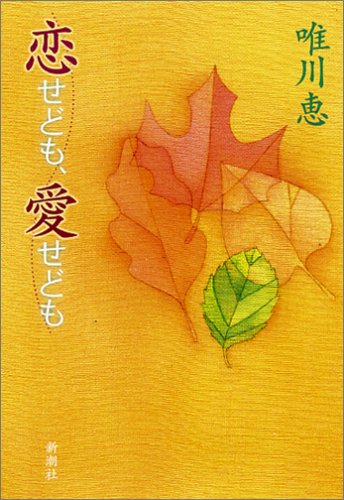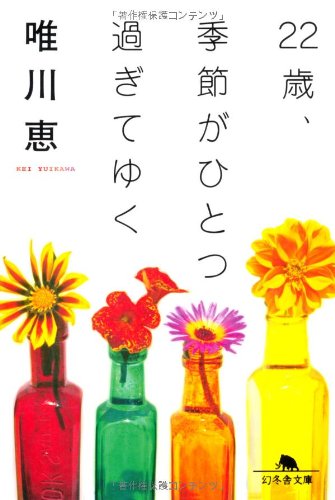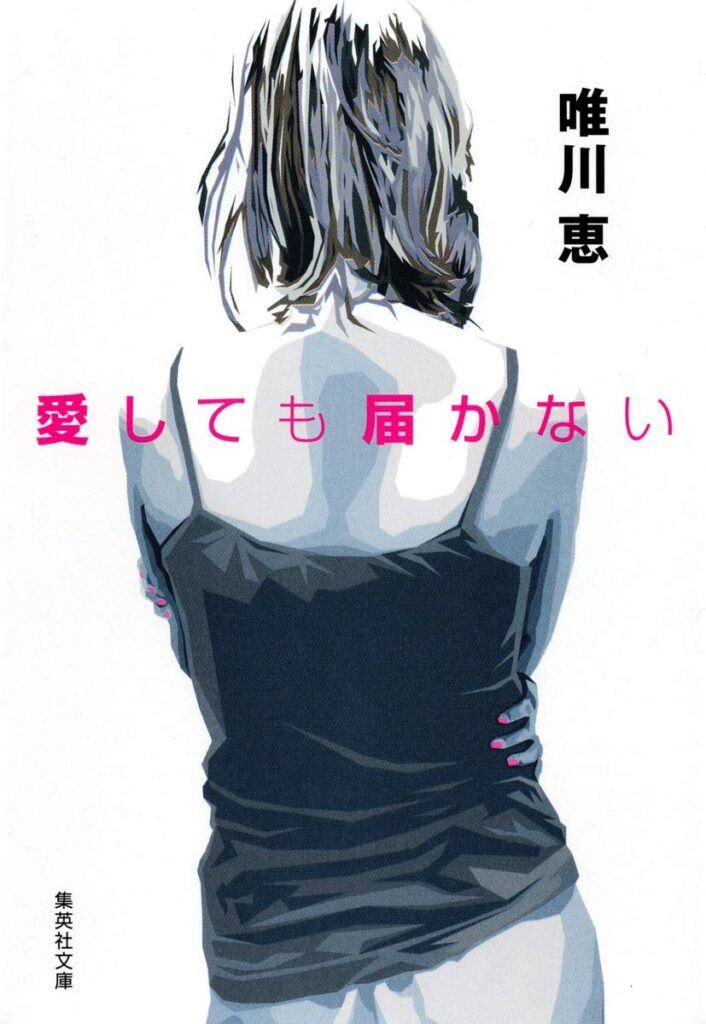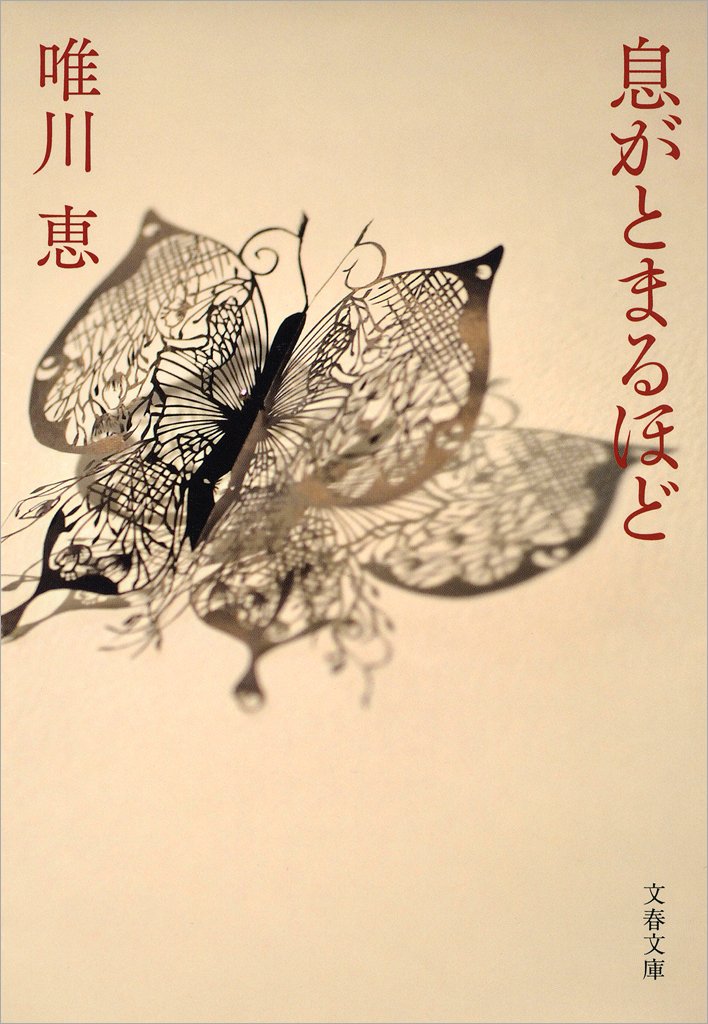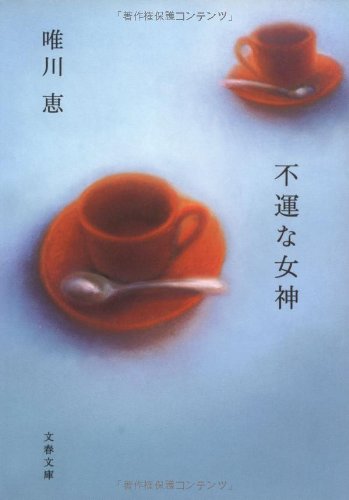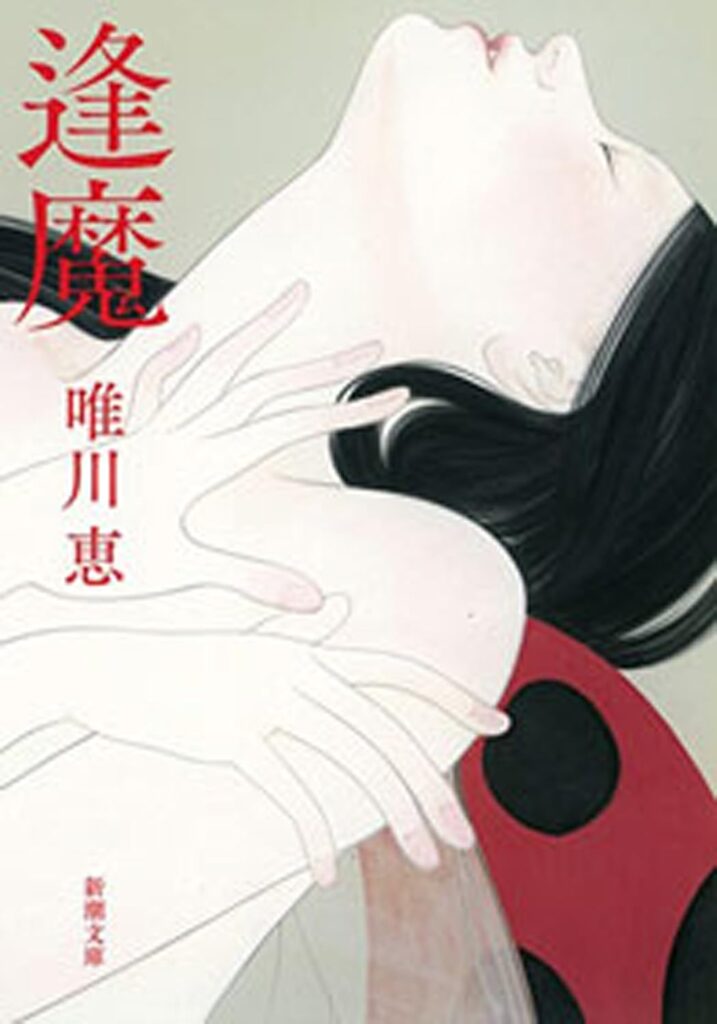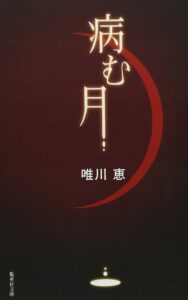 小説「病む月」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。唯川恵さんが紡ぎ出す物語は、いつも私たちの心の奥底にある、普段は蓋をしているような感情を巧みに映し出してくれます。特にこの「病む月」という作品集は、そのタイトルが示す通り、どこか翳りのある、それでいて目を逸らせない人間の深層心理に焦点を当てているように感じます。
小説「病む月」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。唯川恵さんが紡ぎ出す物語は、いつも私たちの心の奥底にある、普段は蓋をしているような感情を巧みに映し出してくれます。特にこの「病む月」という作品集は、そのタイトルが示す通り、どこか翳りのある、それでいて目を逸らせない人間の深層心理に焦点を当てているように感じます。
この物語の舞台は、古都・金沢。美しい街並みとは裏腹に、そこに生きる女性たちの心の中には、嫉妬、憎悪、渇望、そして誰にも言えない秘密が渦巻いています。一見、穏やかな日常を送っているかのように見える彼女たちが、ふとしたきっかけでその心の闇を露わにする瞬間は、息をのむほどのリアリティがあります。
「病む月」に収められた10の短編は、それぞれが独立した物語でありながら、金沢という共通の舞台と、女性たちの複雑な心理描写という点で響き合い、作品全体として独特の重厚な雰囲気を作り出しています。これから、各物語がどのように私たちの心を揺さぶり、どんな感情の深淵へと誘うのか、その魅力に迫っていきたいと思います。
この記事では、「病む月」がどのような物語なのか、そして私がこの作品から何を感じ取ったのかを、できる限り詳しくお伝えできればと思っています。もしかしたら、あなた自身の心のどこかに共鳴する部分が見つかるかもしれません。
小説「病む月」のあらすじ
唯川恵さんの短編集「病む月」は、古都・金沢を背景に、10人の女性たちが抱える心の闇や複雑な人間模様を描き出した作品群です。一見、静かで美しいこの街で、彼女たちの日常の裏側には、嫉妬、憎しみ、満たされない渇望、そして誰にも明かせない秘密が息づいています。時には、ほんのわずかな救いの光が差し込むこともありますが、多くは人間の感情の深淵を覗き込むような物語が展開されます。
例えば、「いやな女」という物語では、香の専門店を営む脇子が主人公です。彼女は年上のパトロンに支えられながらも、どこか満たされない日々を送っています。そんな時、高校時代から気に食わないと思っていた同級生・比佐子と再会します。美貌も富も、そして傲慢さも手に入れている比佐子に対し、脇子は複雑な感情を抱き、ある行動に出てしまいます。しかし、その先には衝撃的な気づきが待っているのでした。
また、「雪おんな」では、年に一度だけ、新調した着物をまとい、ある男性と密会を重ねる女性の物語が描かれます。その日だけは「虚構の女」として生きる彼女の現実と、その秘密の関係の儚さが、雪深い金沢の風景と重なり、切なくも美しい情景を織りなします。彼女がなぜそのような関係を続けるのか、その背景にある孤独や満たされなさが静かに伝わってきます。
他にも、かつての同僚からの執拗な嫌がらせがエスカレートしていく「過去が届く午後」、障害のある息子を亡くした女性が型破りな方法で心の空白を埋めようとする「聖女になる日」、穏やかに見える叔母の隠された悪意が徐々に明らかになるホラータッチの「魔女」など、各編がそれぞれ異なる角度から女性の心の深層に迫ります。
「川面を滑る風」では、故郷に戻ったシングルマザーが抱える秘密、「愛される女」では、毒親である母との歪んだ関係とその連鎖、「玻璃の雨降る」では、援助交際から始まる関係が意外な形で見せる真実の愛、「天女」では、過去を捨てて手に入れた平穏な生活を自ら手放してしまう女性の業、「夏の少女」では、亡くした子供への想いが幻想的な出会いへと繋がる、少し毛色の異なる感動的な物語も収められています。
これらの物語は、金沢という土地の持つ独特の湿り気や伝統の重みを感じさせながら、普遍的な人間の感情、特に女性が内に秘めがちな複雑な思いを鮮やかに描き出しています。読者は、彼女たちの行動に時に共感し、時に慄きながらも、その心の奥深くにある声に耳を傾けずにはいられないでしょう。
小説「病む月」の長文感想(ネタバレあり)
唯川恵さんの「病む月」という短編集は、読了後、ずっしりとした重みと、なんとも言えない余韻を心に残す作品でした。10編の物語は、それぞれが異なる女性の人生の一断面を切り取っていますが、共通して流れているのは、人間の心の奥底に潜む「闇」と、そこから逃れられない「業」のようなものでしょうか。金沢という美しい古都が舞台でありながら、そこで描かれるのは、決して美しいだけではない、生々しく、時には残酷なほどの人間ドラマです。
まず、「いやな女」ですが、主人公の脇子が抱く比佐子への嫉妬や劣等感は、読んでいて非常に胸が痛みました。自分が持っていないものをすべて持っているように見える他者への羨望は、誰しもが一度は感じたことがあるのではないでしょうか。しかし、物語が進むにつれて、脇子自身が、実は自分が最も「いやな女」であったことに気づかされる展開は、非常に皮肉であり、人間の自己欺瞞の深さを見せつけられた気がします。比佐子の夫を誘惑してしまう脇子の行動は短絡的ではありますが、そこに至るまでの彼女の心の葛藤を考えると、単純に非難できない複雑さがあります。結局のところ、他者を「いやな女」と断じることで、自分自身の欠点や満たされなさから目を背けていたのですね。
「雪おんな」は、年に一度だけの密会という設定が非常に印象的でした。「虚構の女」としてその日を生きる主人公の姿は、現実逃避でありながらも、彼女にとっては生きるための儀式のようなものなのかもしれません。新調した着物に袖を通す高揚感と、その関係の刹那的な美しさが、雪の冷たさと相まって、独特の詩情を醸し出していました。倉沢が彼女の現実を知らないという設定も、この関係の危うさと儚さを際立たせています。読み終えた後、彼女がまた一年、どのような思いで日常を過ごすのだろうかと、切ない気持ちになりました。
「過去が届く午後」は、この短編集の中でも特にホラー色の濃い一編でした。有子のもとに、かつての同僚・真粧美から次々と送られてくる「借りたもの」。最初は些細なものだったのが、次第にエスカレートしていく様子は、じわじわと恐怖心を煽ります。才能がありながらも結婚して家庭に入った真粧美の、有子に対する積年の怨恨が、このような形で噴出するとは…。最後に何が送られてきたのか、あるいは真粧美がどのような行動に出たのか、具体的な描写がないからこそ、余計に想像力を掻き立てられ、背筋が凍るような感覚を覚えました。「壊れてしまった女性」という表現が、すべてを物語っているようです。
「聖女になる日」は、個人的には少し受け止めるのが難しい物語でした。障害を持つ息子を亡くした主人公が、息子の介護をしていた日々を「お祭り」のようだったと語る感覚は、周囲には理解されにくいものでしょう。しかし、彼女にとってはそれが偽らざる真実だったのかもしれません。友人のミチが、孤独な女性たちから財産を奪い、心中を持ちかける男の犠牲になるという展開は、あまりにも救いがなく、人間の心の弱さや孤独につけこむ者の存在に暗澹たる気持ちになりました。主人公がその男のいるバーに足を運んでいるというラストは、彼女もまた、その暗い魅力に引き寄せられているのか、あるいは何か別の目的があるのか、様々な解釈ができて不穏な余韻を残します。
「魔女」もまた、人間の外面と内面のギャップに慄然とする物語でした。母の介護のために実家に戻った逸子。そこには、優しく献身的に見える叔母の咲江がいました。しかし、逸子の周りで次々と起こる不可解な不幸。咲江が実は悪意を秘めていたという真相には、信頼していた身内からの裏切りという、最も根源的な恐怖を感じました。介護という、本来ならば尊い行為が悪用される可能性を示唆している点も、現代社会の闇を映し出しているように思えます。逸子が最終的にどのような行動をとるのか、読者の想像に委ねられている部分も、この物語の深みを増しています。
「川面を滑る風」は、乃理子のついた「嘘」が鍵となる物語ですね。5年ぶりに故郷に戻り、息子を連れている乃理子。彼女が息子の年齢を偽る理由…。それは、息子の父親が誰であるかを隠すため。この事実に気づいた時の衝撃は大きかったです。「ボク、三歳じゃない、四歳だよ」という子供の無邪気な言葉が、逆に母親の計算された嘘を際立たせ、女性のしたたかさ、あるいは必死さのようなものを感じさせました。「やっぱ女はこわい」という感想を抱く読者がいるのも頷けますが、彼女がそうまでして守りたかったものは何だったのか、と考えさせられます。
「愛される女」は、母娘関係の負の連鎖という、非常に重いテーマを扱っています。常に男性からの注目を渇望し、娘である語り手のことなど顧みない母親。その母親に嫌悪感を抱きながらも、語り手自身もまた、夫から「女らしいこと」をしなくなったと離婚され、娘とも会えない状況に陥っています。母親の死後にかかってきた一本の電話が、この「ループ」がさらに続くことを暗示しているようで、読んでいるだけで息が詰まるような思いでした。自己肯定感の欠如や、歪んだ形でしか愛を表現できない不器用さが、世代を超えて受け継がれてしまう悲劇に、胸が締め付けられます。
「玻璃の雨降る」は、この短編集の中では比較的、救いのある物語と言えるかもしれません。ガラス工芸家を目指す聡子と、彼女を経済的に支援する初老の男性・芹沢。二人の関係は、肉体関係を伴う援助という、決して褒められたものではない形で始まります。しかし、芹沢が末期の病に冒されていることが明らかになり、彼の最後の行動が、当初の取引関係を超えた「真の愛情」を示すものだったという展開には、不覚にも心を打たれました。打算から始まった関係性が、死を意識することで純粋な思いへと昇華することがあるのだと、人間の心の複雑さと可能性を感じさせてくれました。
「天女」は、一度手に入れた平穏な日常を、自ら壊してしまう女性の物語です。元ソープランド従業員だった加寿子は、真面目な男性と結婚し、過去とは無縁の安定した生活を送っていました。しかし、かつてのヒモだった男との再会が、彼女の心の奥底に眠っていた破滅的な欲求を呼び覚ましてしまいます。騙されるとわかっていながらも、その刺激に抗えない加寿子の姿は、愚かしくも哀れです。「一人の男と百回寝るのは許せても、百人の男と1回ずつ寝るのは許せない」という彼女の言葉は、女性の性的経歴に対する社会の偽善を鋭く突いており、彼女が抱える息苦しさの一端を示しているように感じました。
そして最後の「夏の少女」。この物語は、それまでの暗く重い雰囲気から一転し、温かく、どこか幻想的な余韻を残してくれました。主人公の尚子が出会う「この世ならぬもの」である少女。それは、彼女が持つことのなかった子供への想いが具現化した存在なのでしょう。流産や中絶といった、言葉にしにくい喪失感を抱える女性にとって、この物語は一種の慰めや救いになるかもしれません。少女の正体を悟る瞬間や、亡くなった祖父母らしき存在の言葉は、悲しみとの和解、そして静かな受容を感じさせ、読後には不思議と穏やかな気持ちになりました。この短編集の最後にこの物語が置かれていることには、作者の明確な意図を感じます。
「病む月」全体を通して感じるのは、唯川恵さんの人間観察の鋭さ、特に女性心理の深層を抉り出す筆致の巧みさです。登場する女性たちは、決して聖人君子ではなく、むしろ欠点だらけで、時には周囲を傷つけ、自分自身をも破滅に追いやってしまうことさえあります。しかし、彼女たちの行動の背景には、誰にも理解されない孤独や、満たされない渇望、過去のトラウマといった、複雑な要因が絡み合っています。だからこそ、読者は彼女たちを単純に断罪するのではなく、その心の叫びに耳を澄ませようとするのかもしれません。
金沢という舞台設定も、物語の雰囲気を高めるのに大きく貢献しています。伝統が息づく美しい街並みと、そこに生きる人々の心の内に渦巻くどす黒い感情とのコントラストが、物語に一層の深みを与えています。湿度の高い空気感や、どこか閉鎖的な人間関係の濃密さが、登場人物たちの息苦しさや葛藤を際立たせているようにも感じられました。
この「病む月」は、決して読後感が爽快な作品ではありません。むしろ、人間の心の闇に触れることで、重苦しい気持ちになったり、考えさせられたりすることの方が多いでしょう。しかし、それこそがこの作品の持つ力であり、魅力なのだと思います。目を背けたくなるような感情や現実から目を逸らさず、人間の本質に迫ろうとする唯川恵さんの真摯な姿勢が、読者の心を強く掴んで離さないのではないでしょうか。読み終えてしばらく経っても、登場人物たちの顔や、金沢の風景がふと心に浮かび、物語の世界に引き戻されるような感覚があります。それは、彼女たちの「病み」が、私たち自身の心の中にも、形は違えど存在しているからなのかもしれません。
まとめ
唯川恵さんの「病む月」は、古都・金沢を舞台に、10人の女性たちの心の深淵に潜む感情や人間関係を、鮮烈な筆致で描き出した短編集です。嫉妬、憎悪、渇望、秘密、そして時には仄かな救いまでもが、それぞれの物語の中で巧みに織りなされています。読者は、彼女たちの抱える「闇」に触れ、その複雑な心理描写に引き込まれることでしょう。
各短編は独立していますが、金沢という共通の舞台と、女性心理の陰影に深く切り込む視点によって、作品集全体として独特の統一感と重厚な雰囲気を醸し出しています。一見穏やかな日常の裏に隠された、人間の生々しい感情のうねりは、読む者の心を強く揺さぶります。そして、時にそのリアリティに息をのみ、登場人物たちの選択に胸を痛めることもあるかもしれません。
この作品は、決して明るく楽しいだけの物語を求める方には向かないかもしれません。しかし、人間の心の奥深くにある、普段は見過ごされがちな感情の機微や、複雑な人間関係の綾に興味がある方にとっては、非常に読み応えのある一冊となるはずです。唯川恵さんならではの鋭い洞察力と表現力によって、登場人物たちの息遣いまでもが伝わってくるようです。
「病む月」を読み終えた後、あなたはきっと、登場人物たちの誰か、あるいはその感情の断片に、自分自身の心のどこかを重ね合わせていることに気づくかもしれません。そして、人間の心の複雑さや、ままならない人生のありようについて、深く考えさせられるのではないでしょうか。