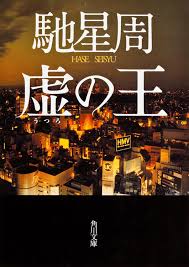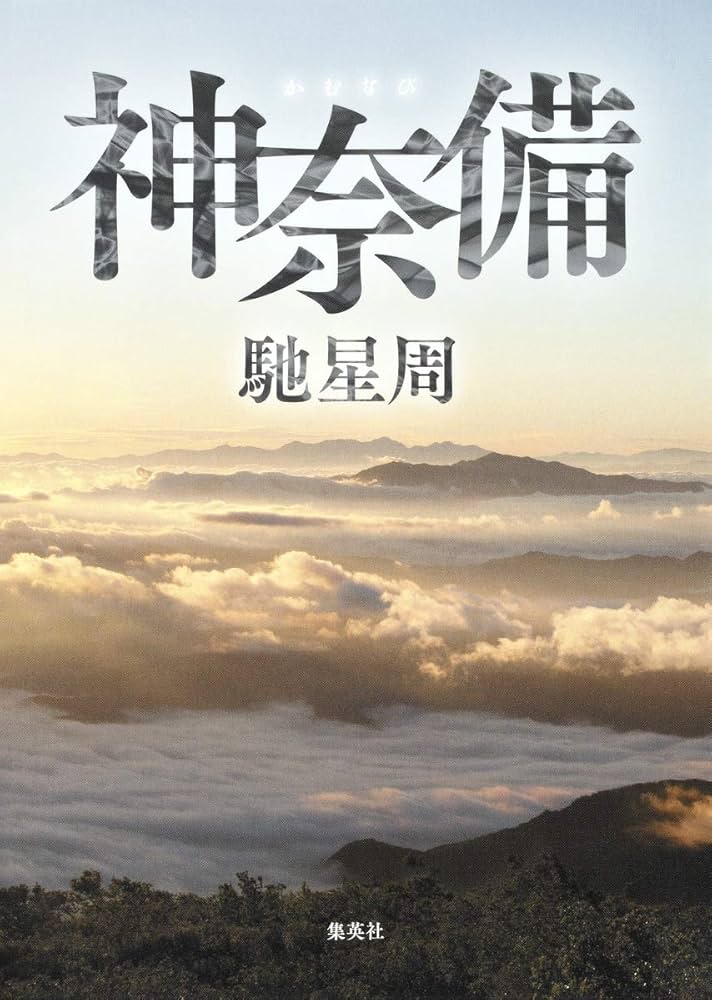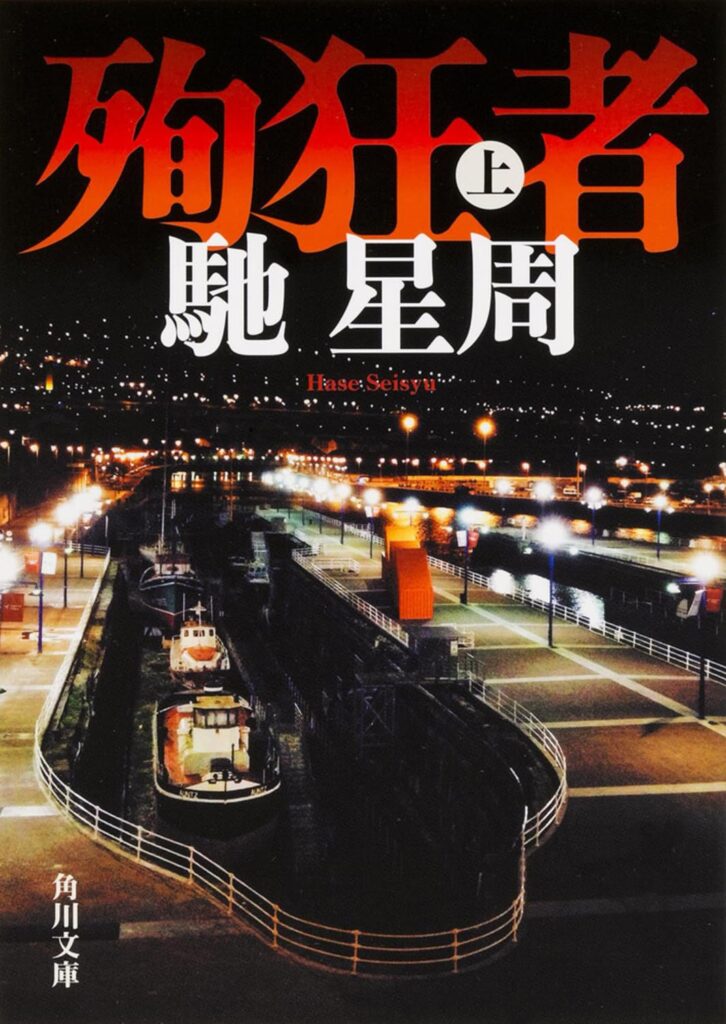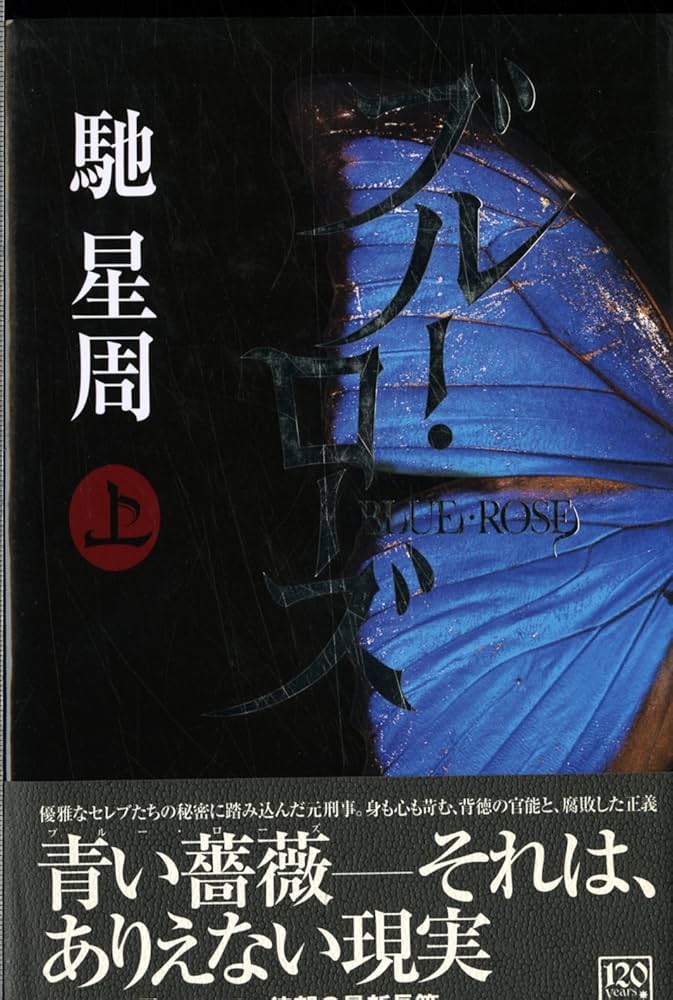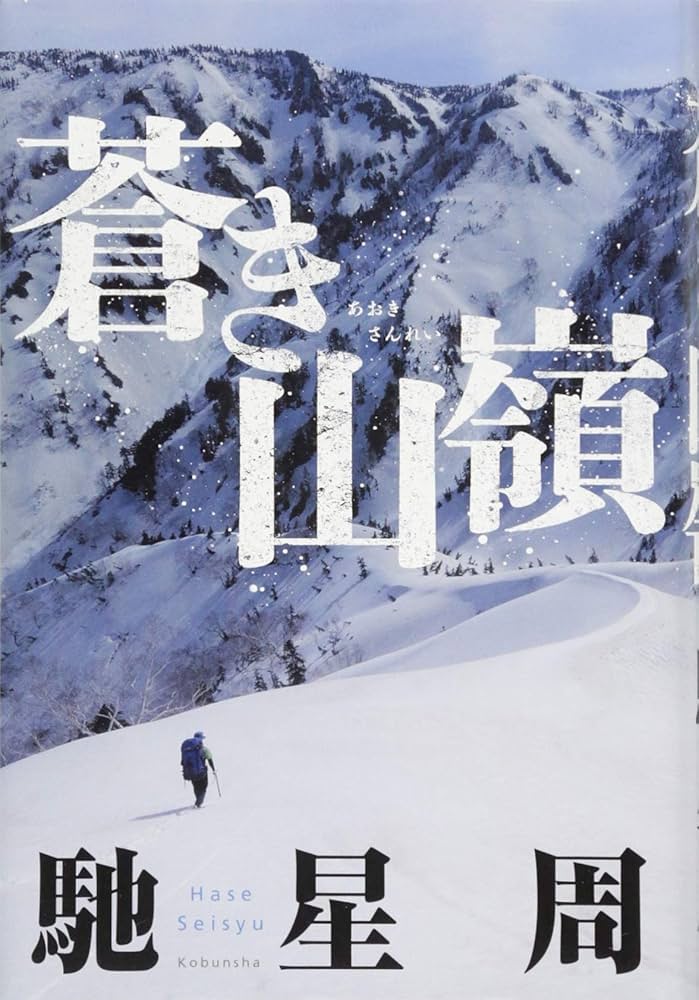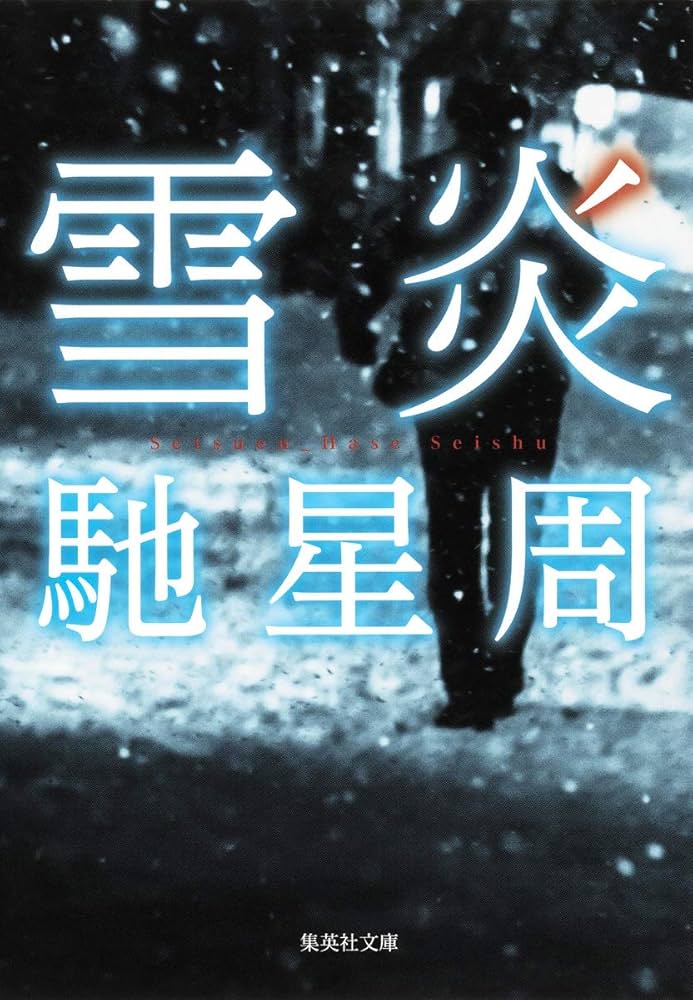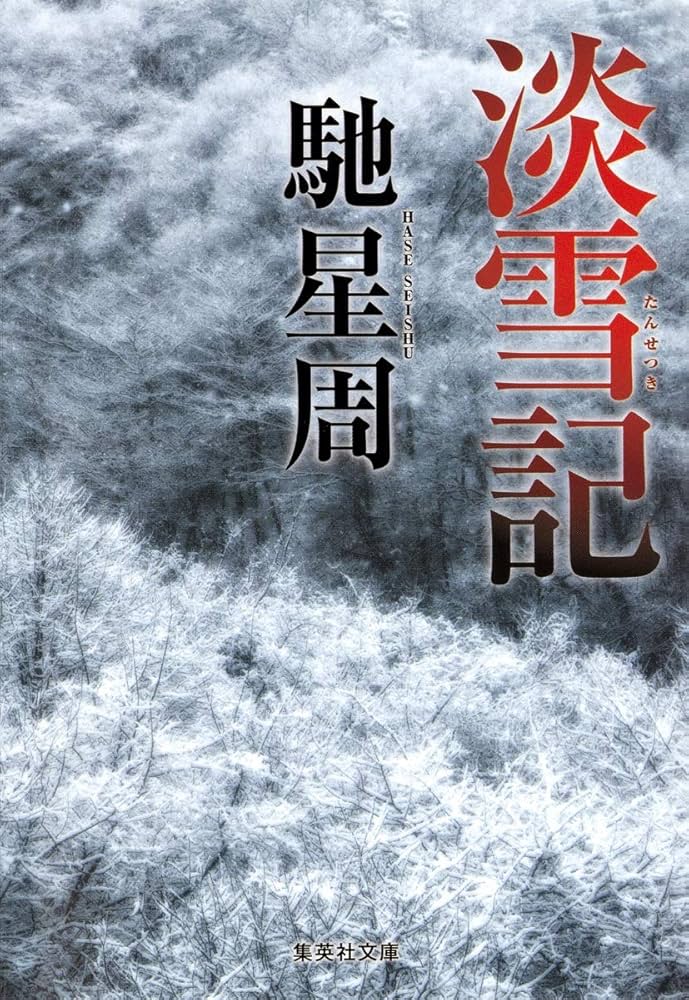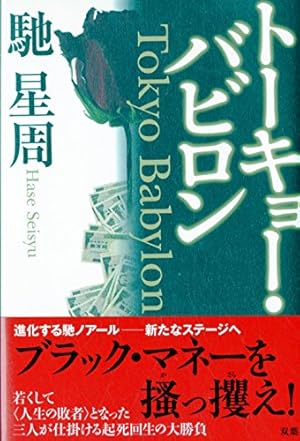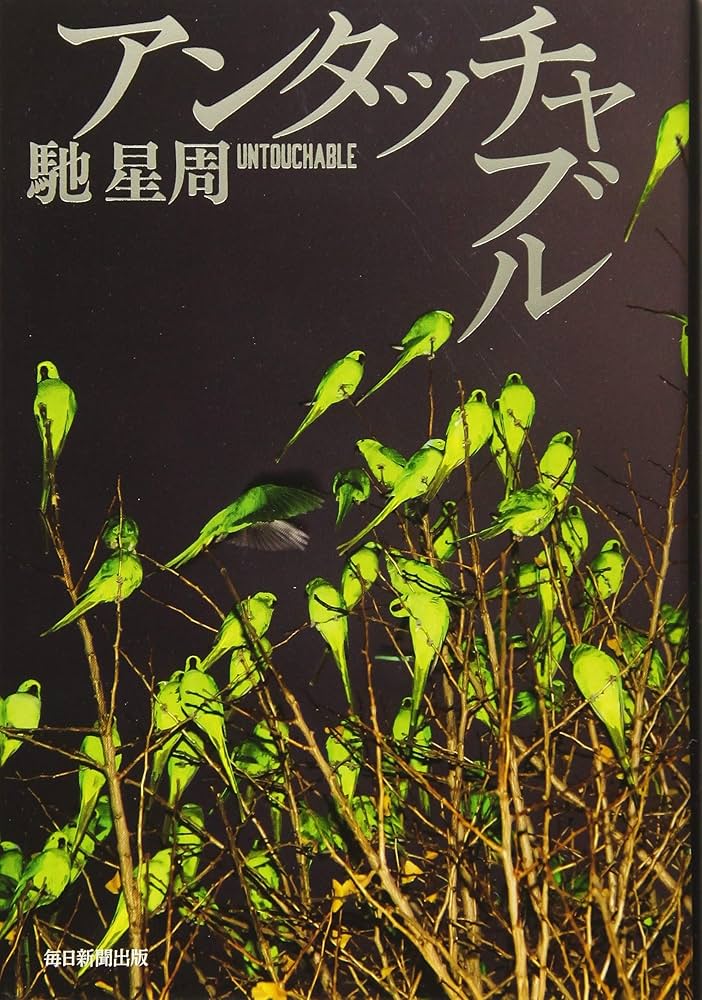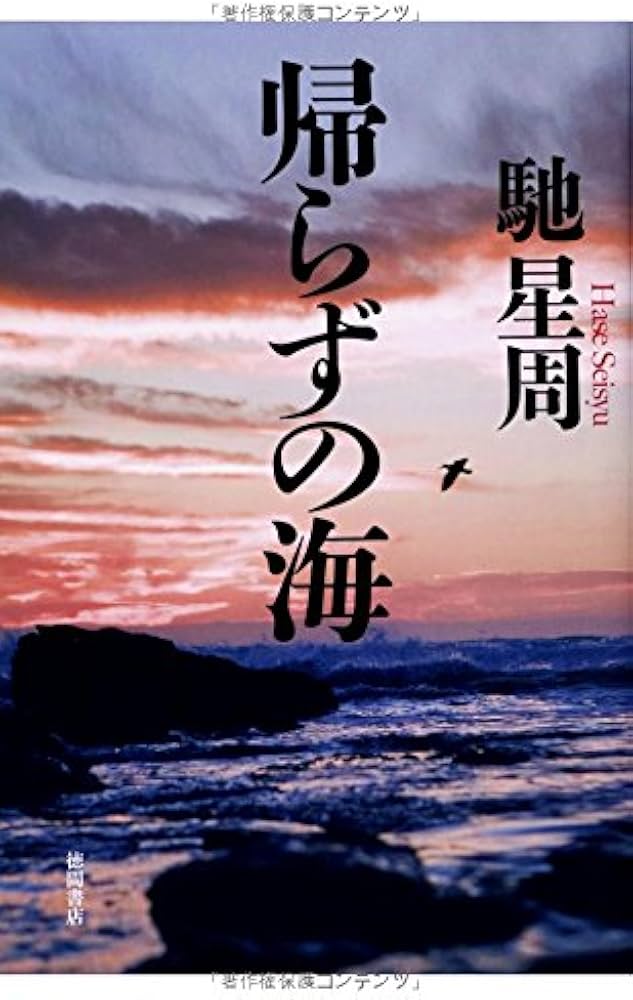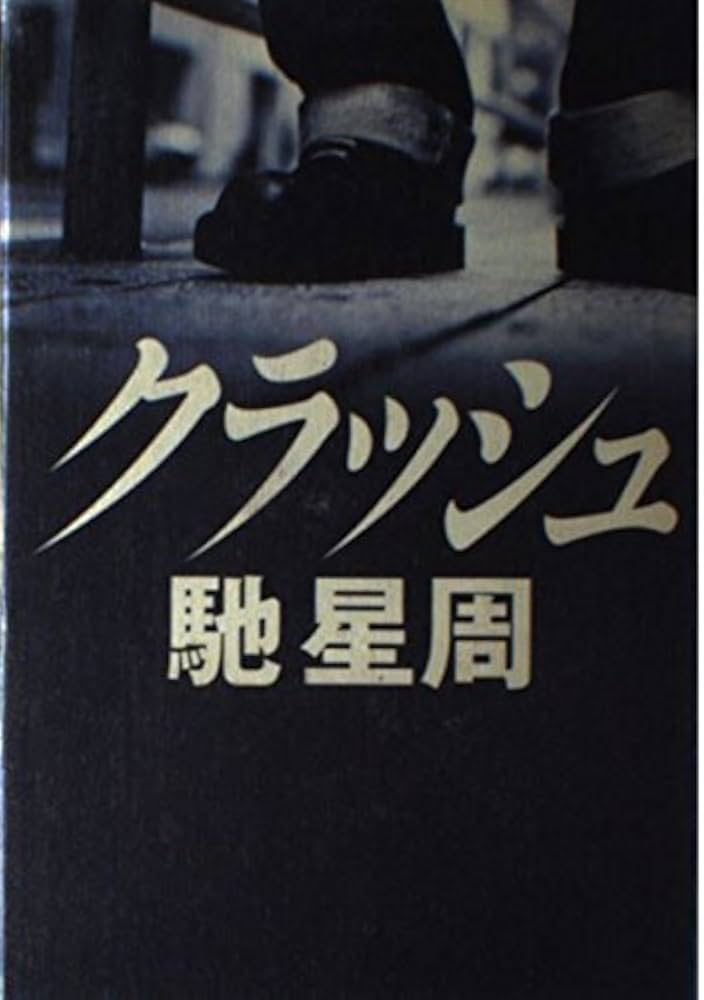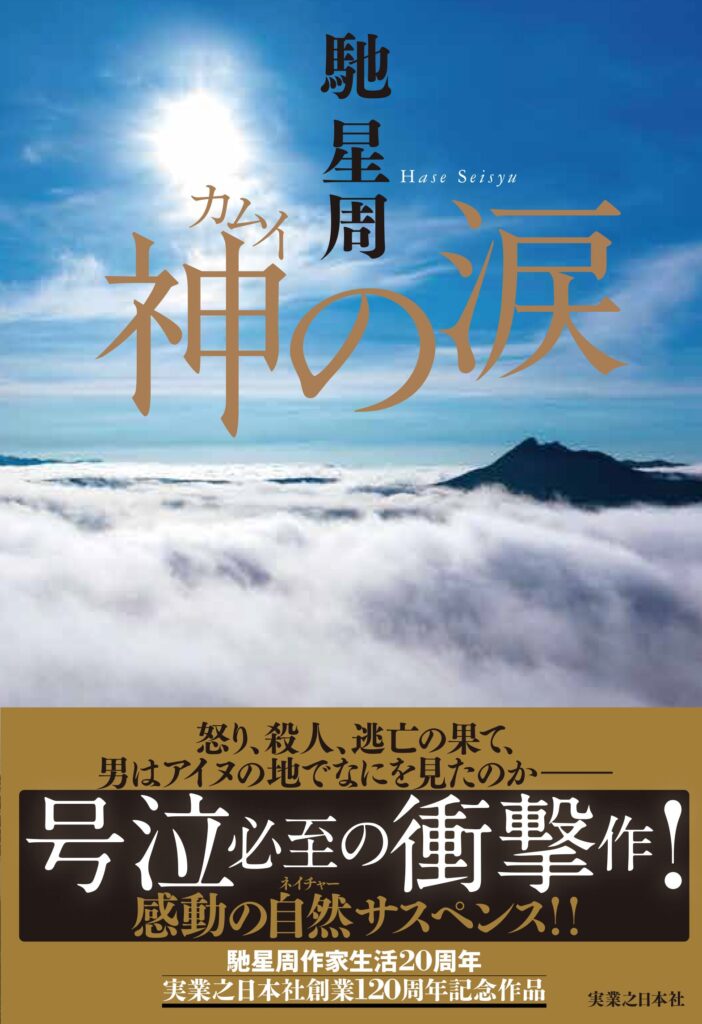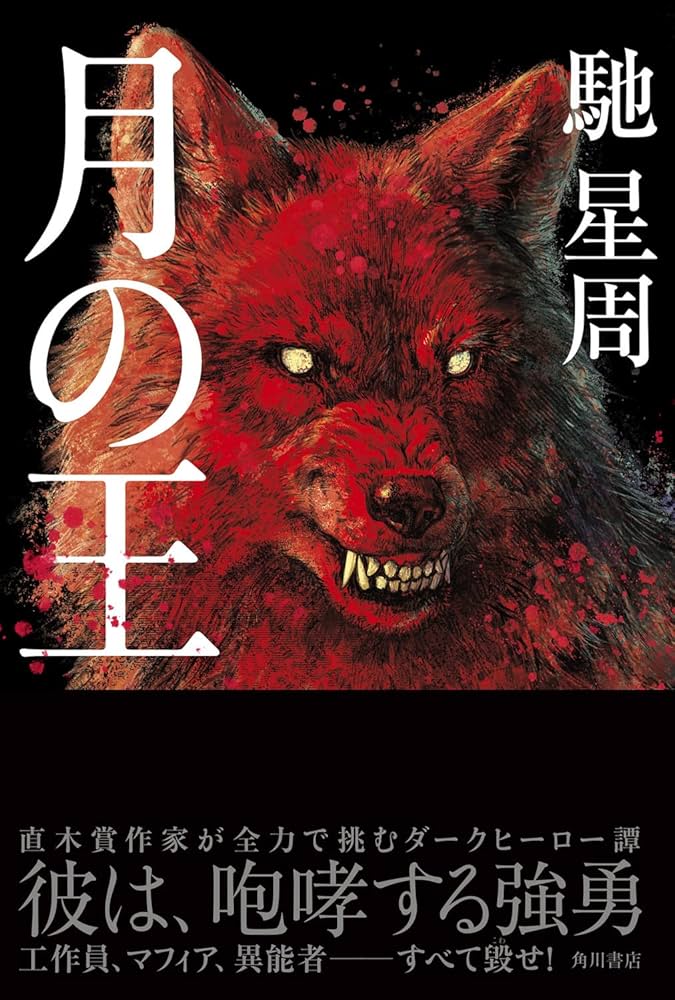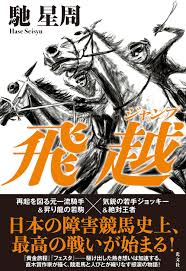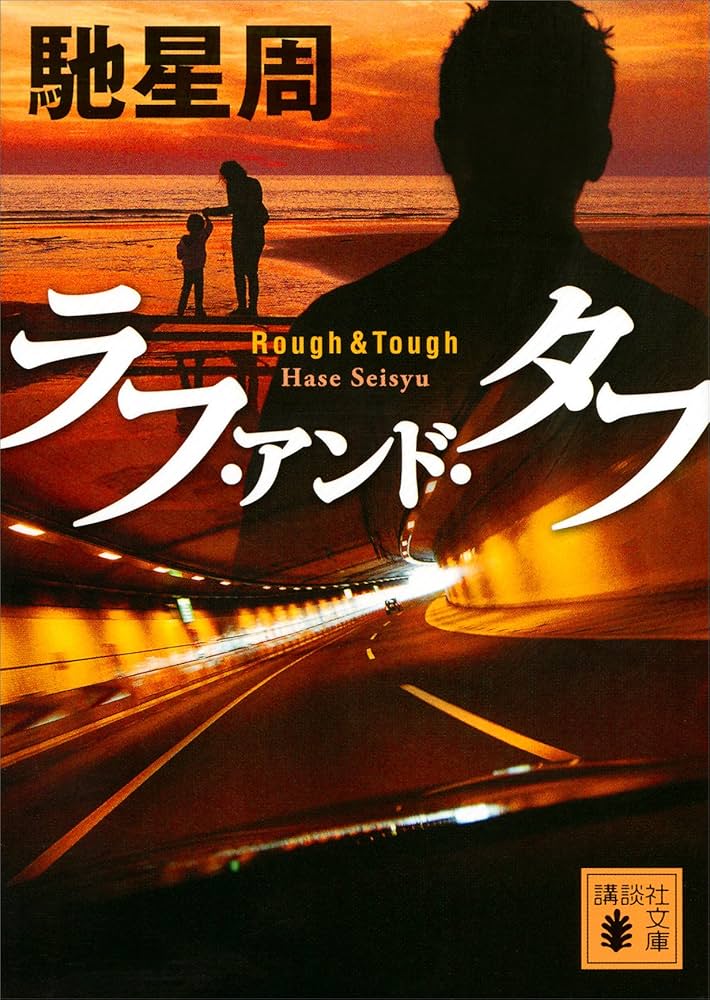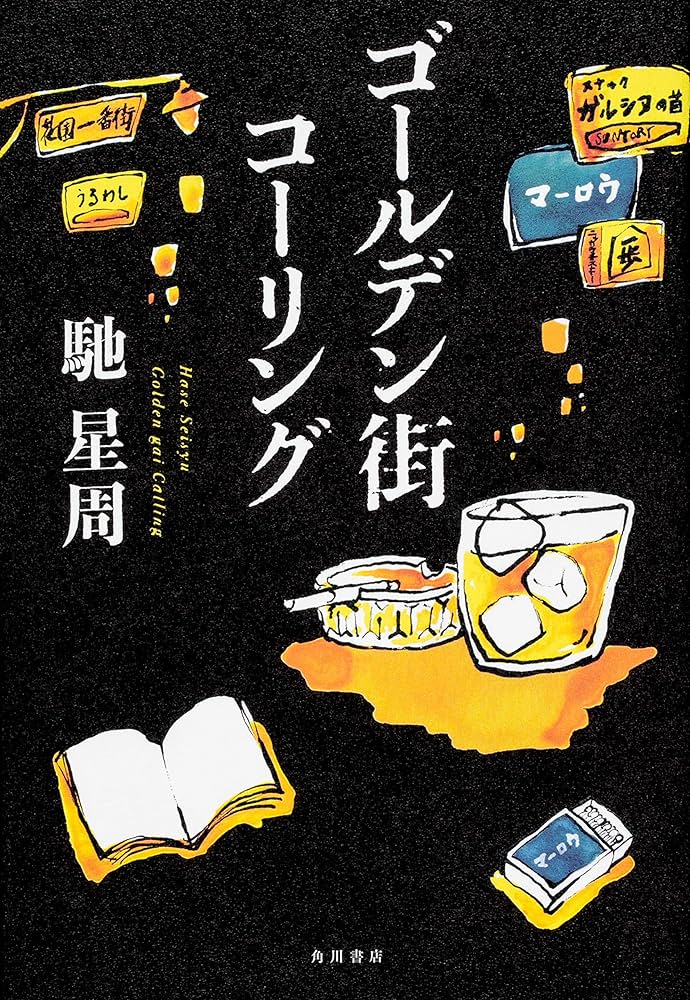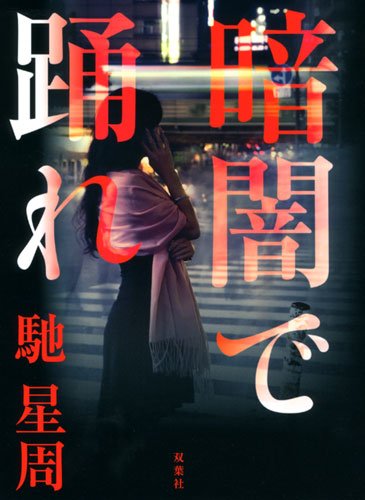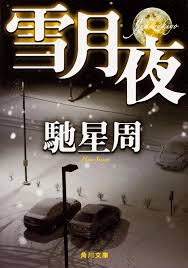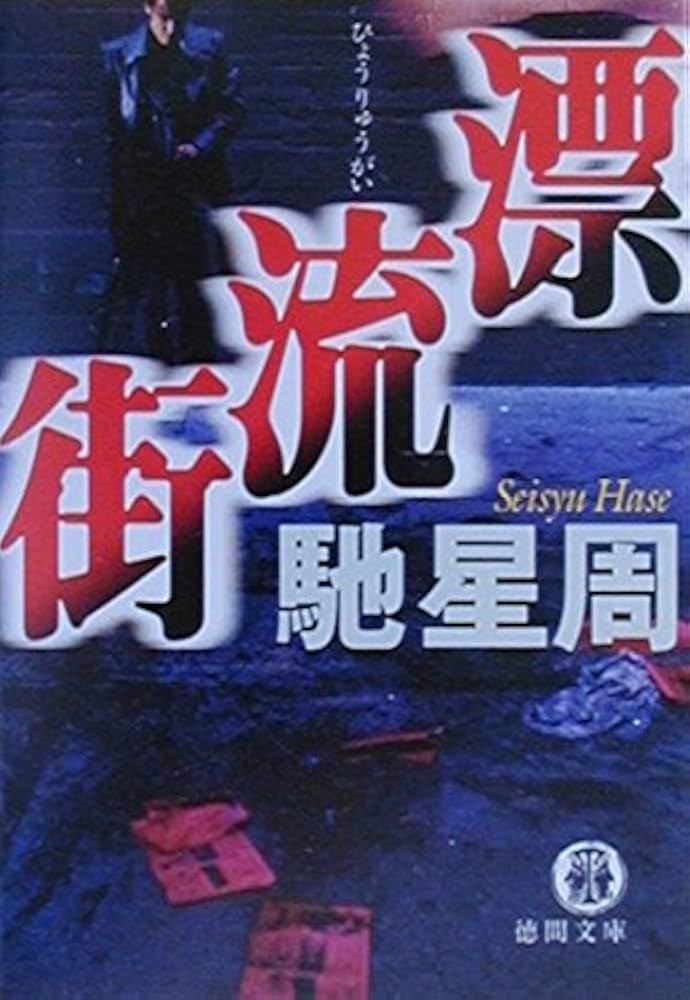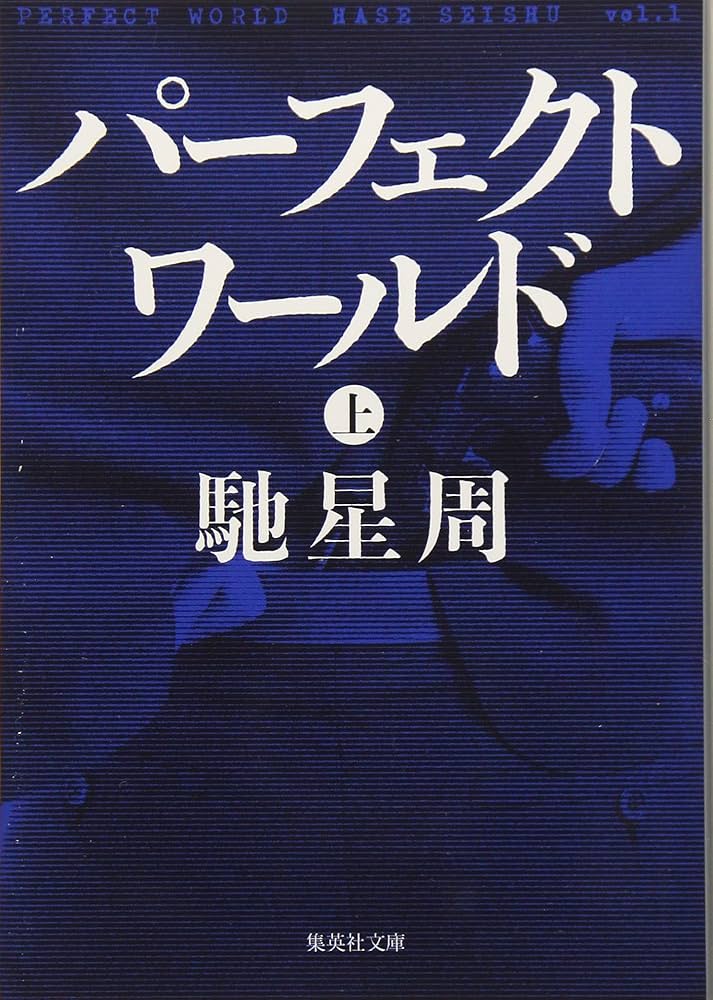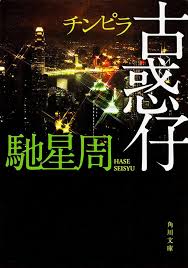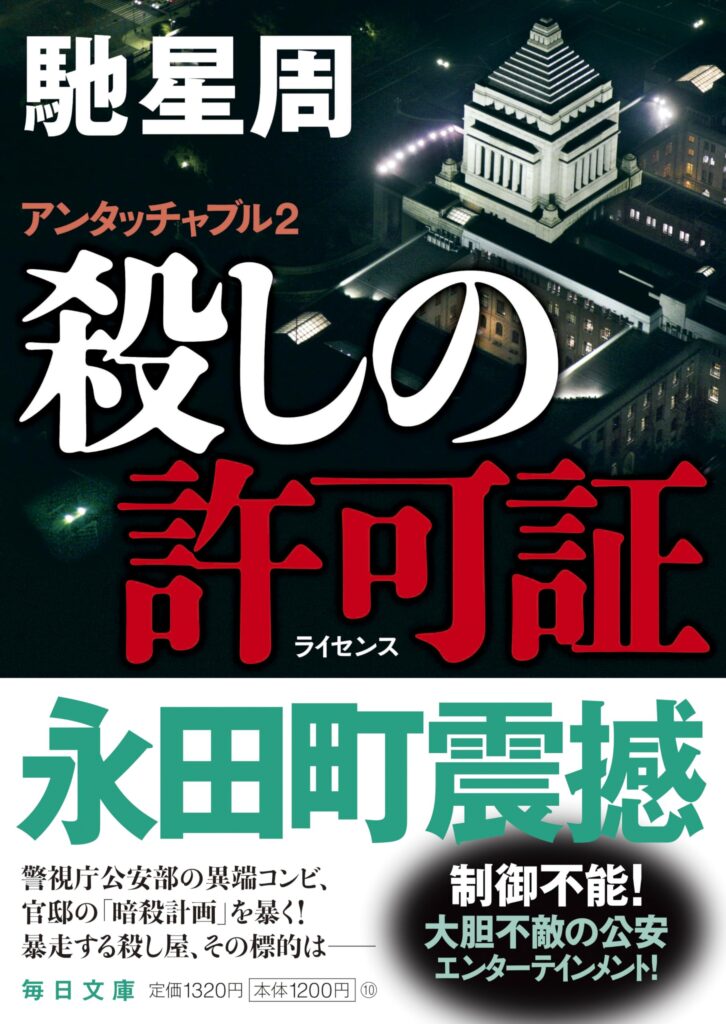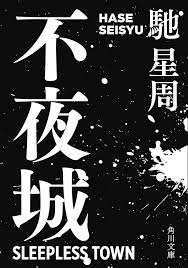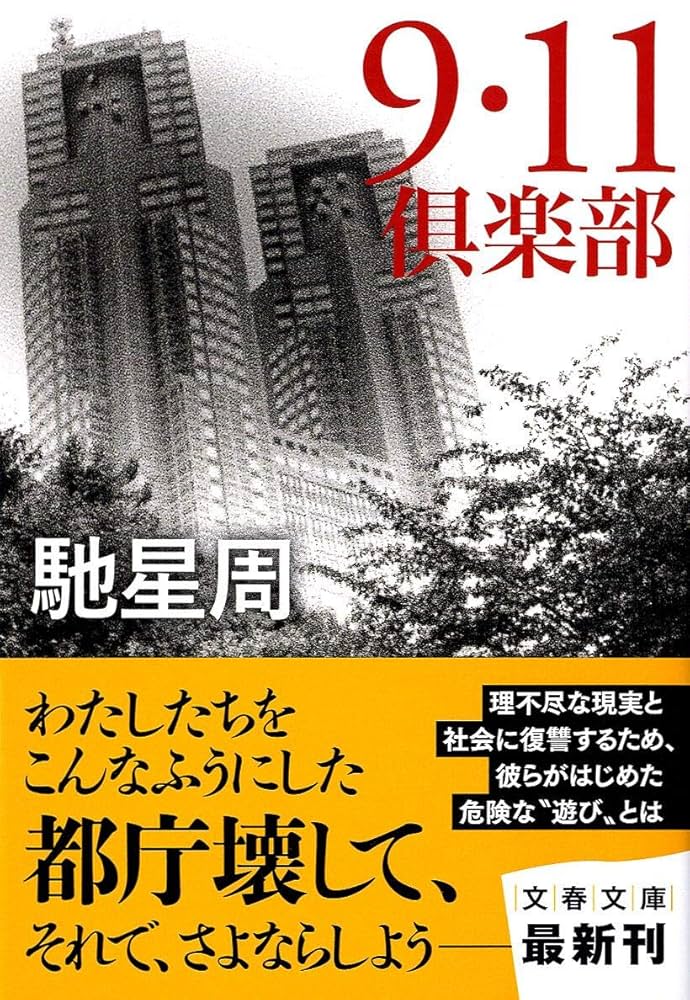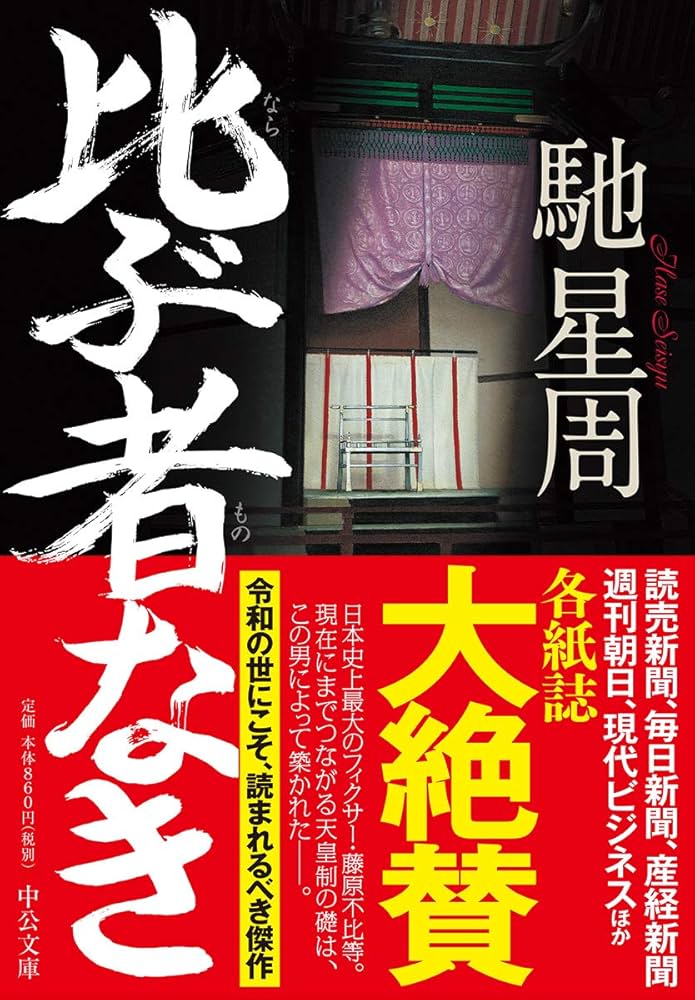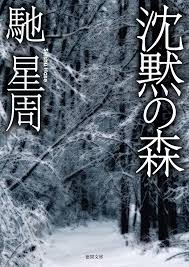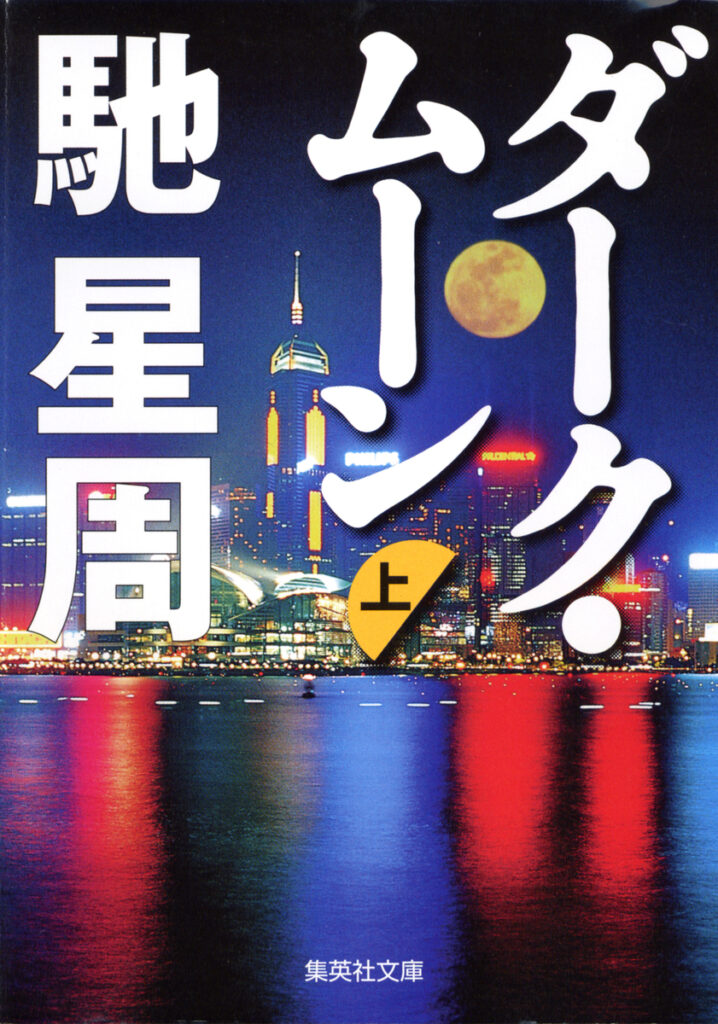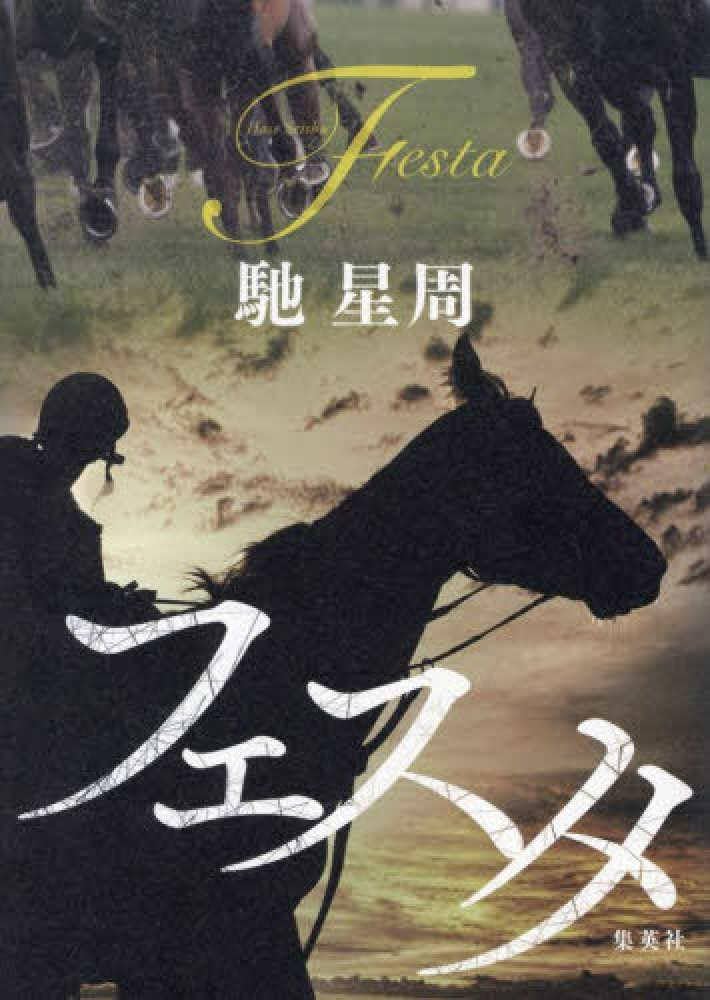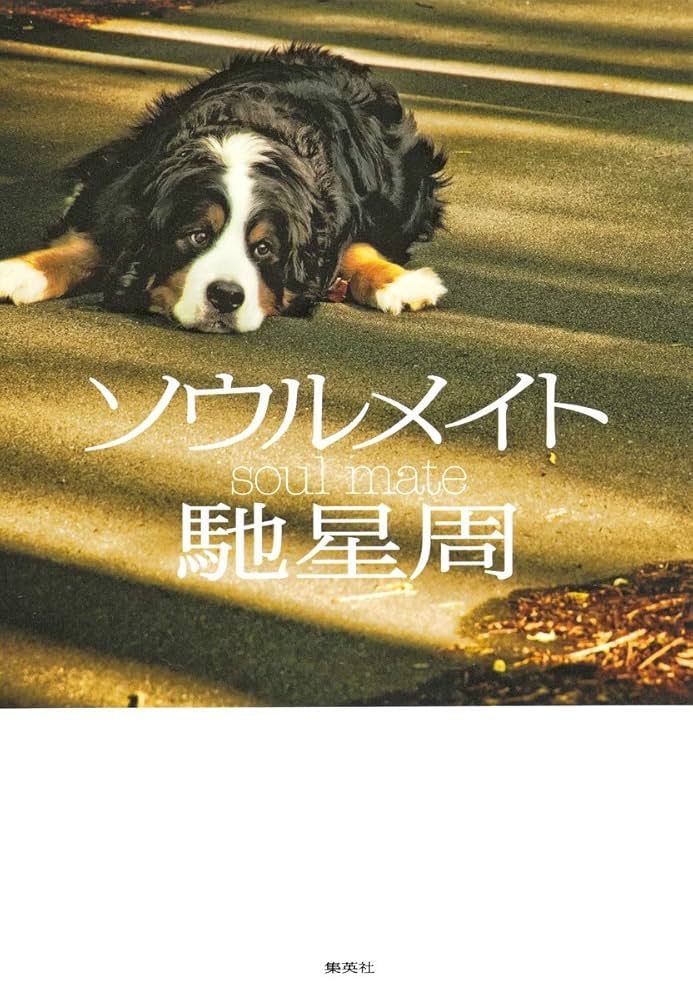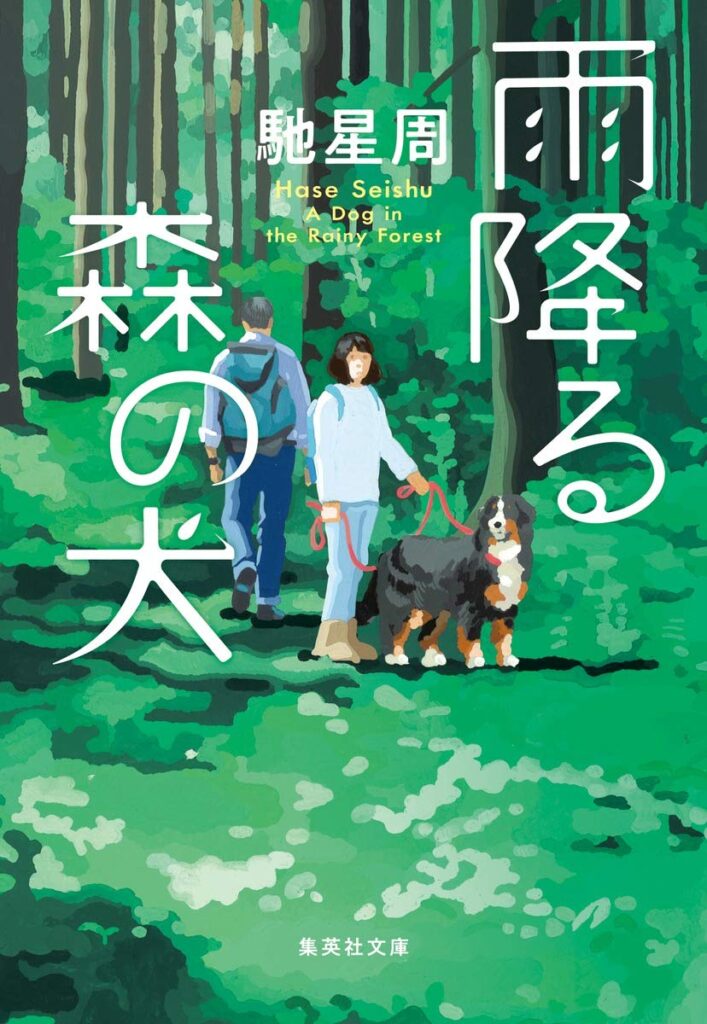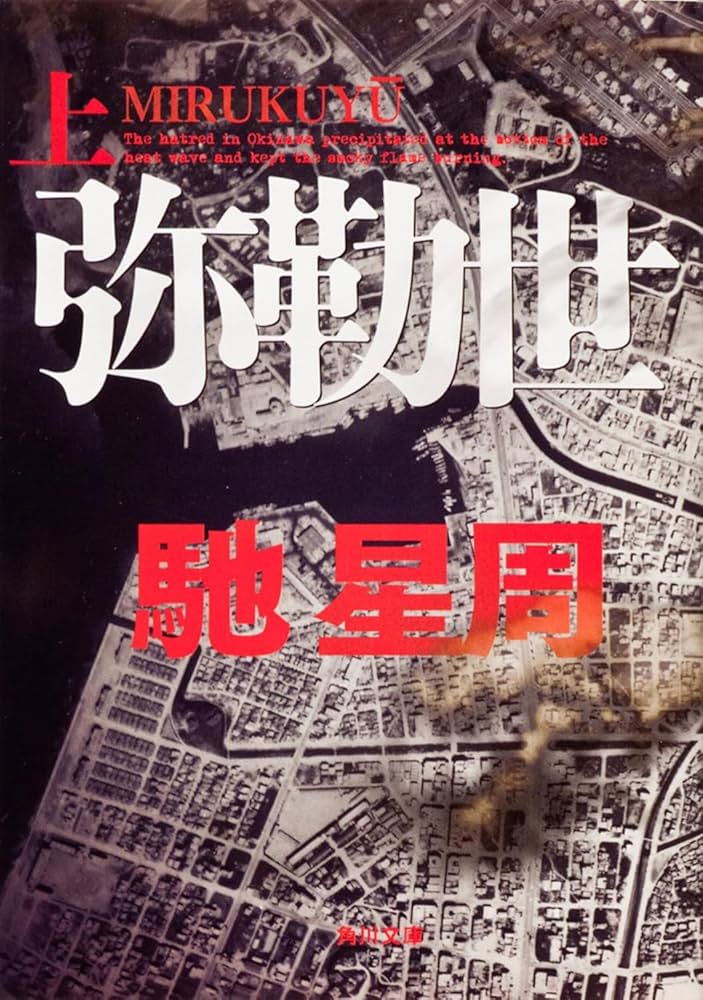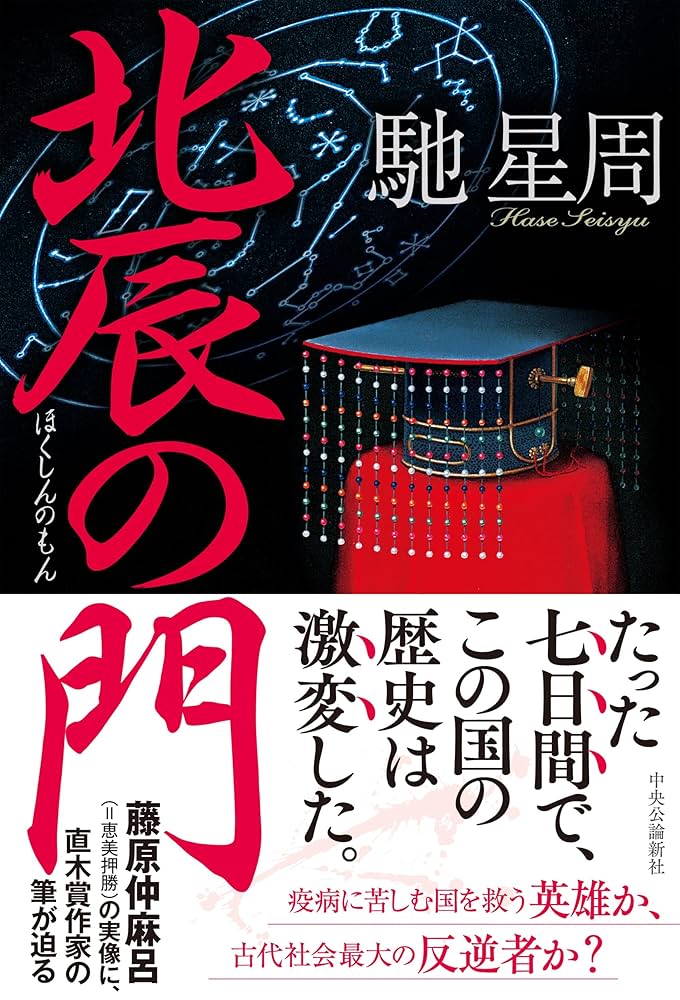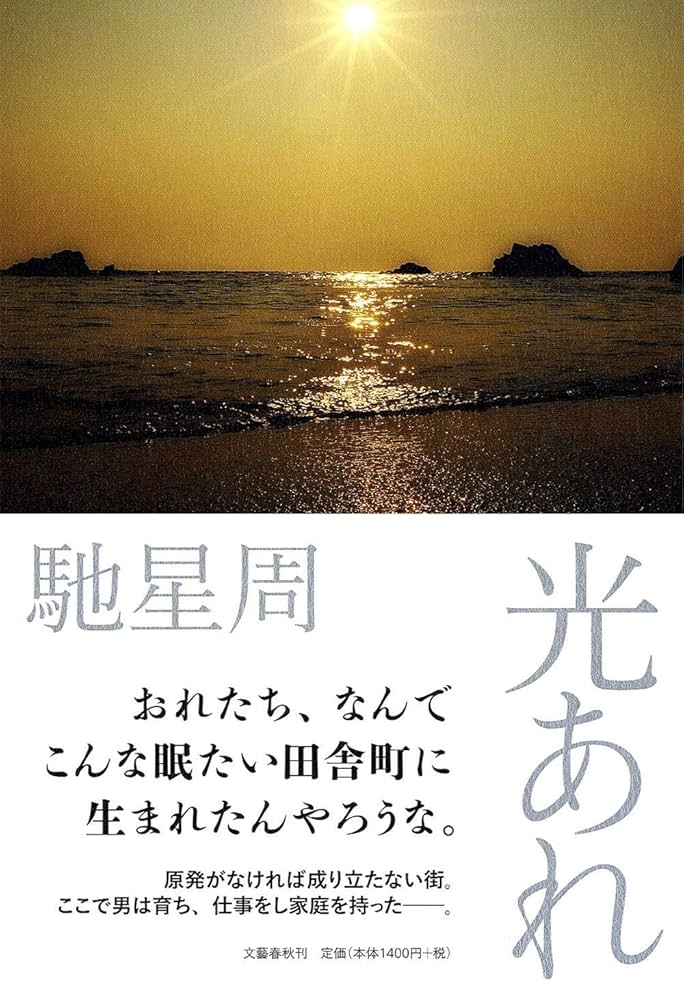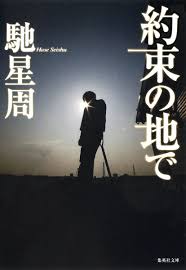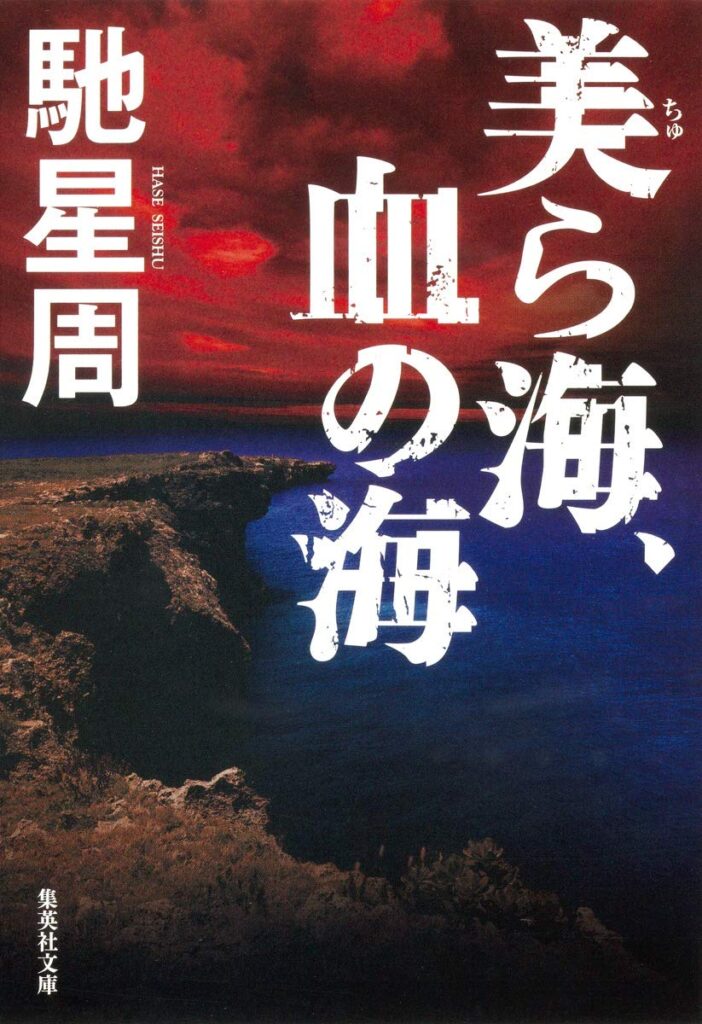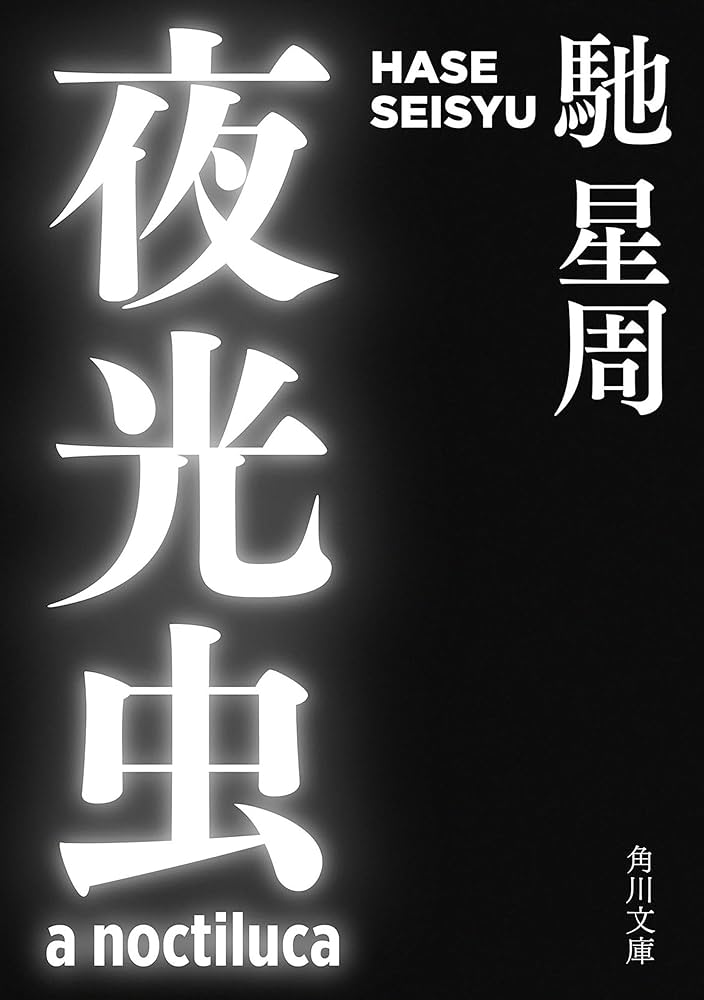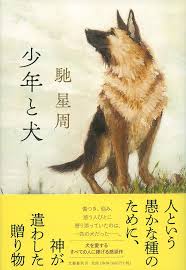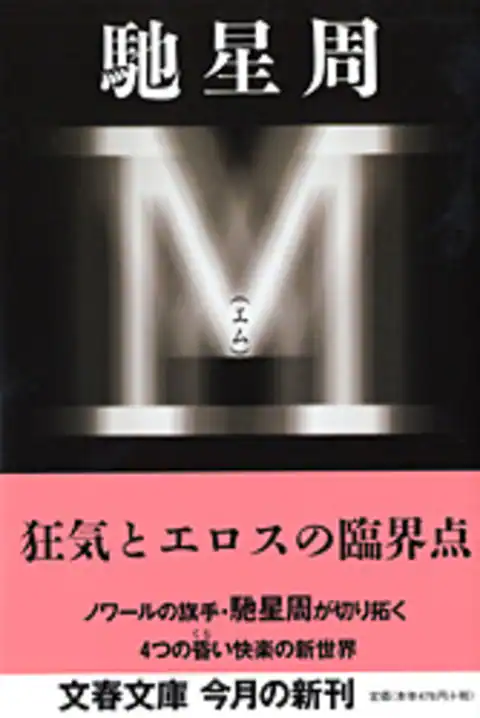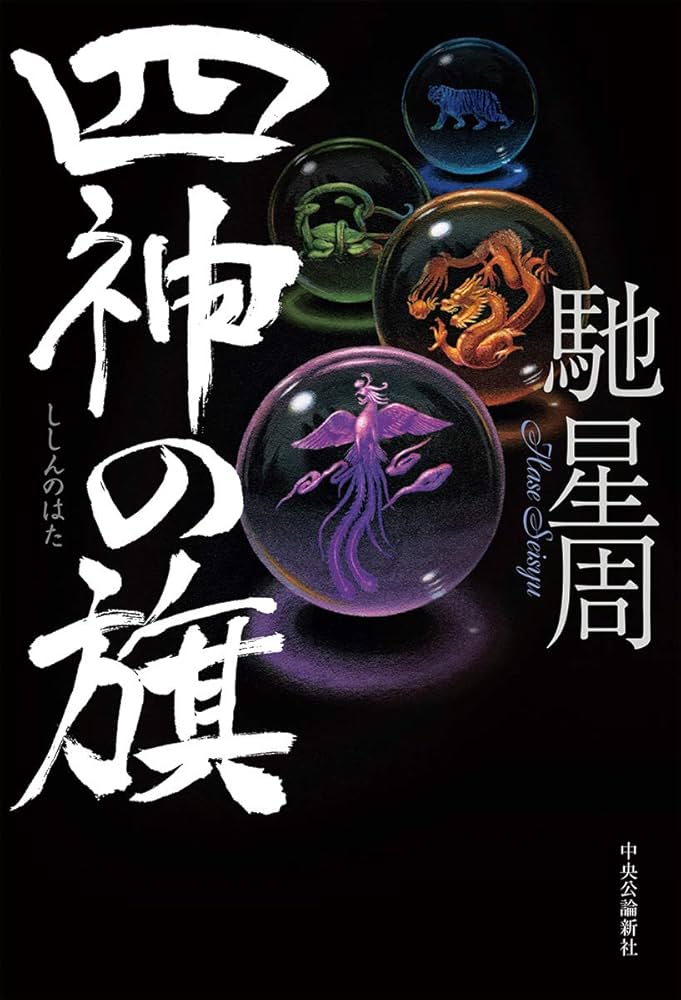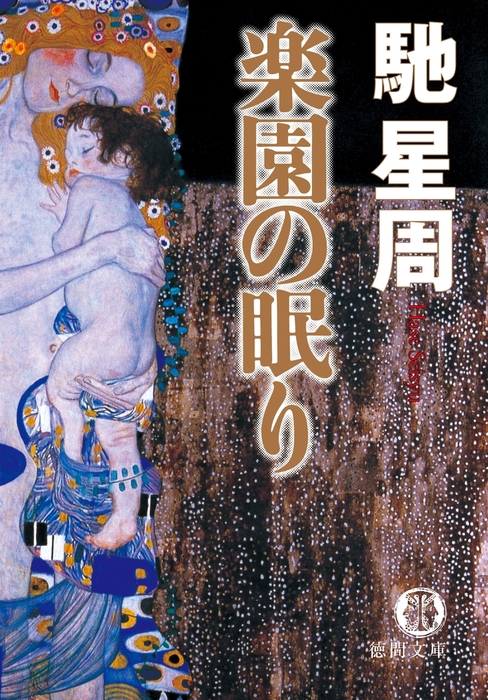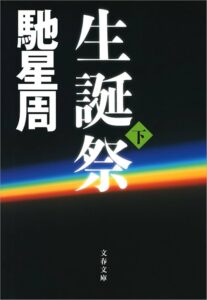 小説「生誕祭」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「生誕祭」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
バブル時代の熱狂と狂気に満ちた東京を舞台に、一人の青年が欲望の渦に飲み込まれていく様を描いたこの物語は、一度読み始めるとページをめくる手が止まらなくなる引力を持っています。馳星周さんが描く、人間の剥き出しの欲望や、時代の持つ異様なエネルギーは、読む者の心を強く揺さぶります。
この物語の魅力は、単なるノワール小説に留まらない、登場人物たちの深い心理描写にあります。なぜ彼らは破滅へと向かう道を突き進んでしまったのか。何が彼らをそこまで駆り立てたのか。その答えを探していくうちに、私たちはバブルという時代が持つ、抗いがたい魔力の一端に触れることになるでしょう。お金だけではない、もっと根源的な何かを求めた男の姿は、滑稽でありながら、どこか哀しく、私たちの心に突き刺さるのです。
この記事では、物語の導入部分から、核心に迫る部分まで、私の解釈を交えながらじっくりと語っていきたいと思います。まだお読みでない方はご注意いただきたいのですが、物語の結末に大きく関わる部分にも触れていきます。この物語が持つ「ひりひりする」ような感覚を、少しでもお伝えできれば幸いです。それでは、狂乱の時代の扉を開けていきましょう。
この物語を読み終えたとき、きっとあなたも「生誕祭」というタイトルの持つ、深く皮肉な意味を噛みしめることになるはずです。それは祝福されるべき誕生の物語なのか、それとも…。どうぞ最後までお付き合いください。
「生誕祭」のあらすじ
物語の舞台は、バブル経済が頂点に達しようとしていた1980年代後半の東京。主人公の堤彰洋は21歳、六本木のディスコで黒服として働きながら、退屈な日常に言いようのない渇望を抱えていました。「金が欲しいわけじゃない。ただひりひりしたいだけなんだ」。そんな彼の燻る心に火をつけたのは、偶然の再会でした。
相手は幼馴染の浅野麻美。かつての少女は見る影もなく洗練された大人の女性に変貌し、「地上げの神様」と恐れられる不動産王・波潟の愛人となっていました。彼女の紹介で、彰洋は若くカリスマ的な不動産デベロッパー、齋藤美千隆と出会います。「おれはおれの王国を作りたいんだ」。齋藤の野心に満ちた言葉に、彰洋は探し求めていた「何か」を見出し、彼の世界へと足を踏み入れることを決意します。
彰洋が身を投じたのは、非合法な手段も厭わない強引な土地買収、すなわち「地上げ」の世界でした。何億円という大金が目の前で動く興奮は、彼の心を瞬く間に麻痺させ、中毒的な快感を与えていきます。祖父から教えられた「嘘をついてはいかん。人を騙してはいかん」という道徳律に自ら唾を吐きかけ、彼は欲望渦巻くマネーゲームのプレイヤーとなっていくのです。
しかし、その先で彼を待ち受けていたのは、想像を絶する裏切りの連鎖でした。齋藤と波潟、そして二人を手玉に取る麻美。さらには関西から乗り込んできた新たな勢力も加わり、騙し騙されのゲームは激しさを増していきます。誰が味方で誰が敵なのか。彰洋は、嘘で塗り固められた迷宮の中で、次第に自分自身を見失っていくのでした。
「生誕祭」の長文感想(ネタバレあり)
この物語は、バブルという時代そのものが持つ、異常なまでの熱量を肌で感じさせてくれる作品でした。単なる背景としてではなく、登場人物たちを狂わせ、破滅へと導く巨大な怪物として、バブル経済が描かれています。土地の値段が天文学的に跳ね上がり、誰もがその祝祭が永遠に続くと信じて疑わなかった時代。その空気感が、ページの中からむせ返るように伝わってくるようでした。
物語の中心にいる主人公、堤彰洋の人物像がまた、実に印象的です。彼は六本木のディスコで働く、どこにでもいるような若者。しかし彼の内面には、日常を破壊してくれるような強烈な刺激、つまり「ひりひりする」ような感覚への渇望が渦巻いています。この満たされない思いこそが、彼を時代の狂気へと引き寄せる磁石となったのです。
彼の「金が欲しいわけじゃない」という独白は、この物語の核心を突いていると感じます。彼が求めたのは富や権力そのものではなく、退屈な生から逃れるためのアドレナリンでした。この純粋なまでの渇望が、彼の行動をより痛々しく、そして悲劇的なものに見せているように思います。目的を失った時代の空虚さと、彰洋の内面の空っぽさが、見事に重なり合っているのです。
私たちは、このバブルがいつか必ず弾けることを知っています。この歴史的な事実が、物語全体に不穏な緊張感を与えています。まるで時限爆弾のカウントダウンを聞きながら、登場人物たちの危険なゲームを見守っているかのよう。音楽が止まった時、一体誰がババを掴むことになるのか。その一点に、否が応でも引き込まれてしまいます。
物語が大きく動き出すきっかけは、彰洋と幼馴染の麻美との再会です。かつての面影を失い、不動産王・波潟の愛人として生きる彼女は、彰洋が焦がれる世界への案内人でした。そして彼女が引き合わせた若き不動産デベロッパー、齋藤美千隆の存在が、彰洋の運命を決定づけます。
「おれはおれの王国を作りたいんだ」。齋藤のこの言葉は、空っぽだった彰洋の心に強烈な光を差し込みます。それは一つのイデオロギーであり、生きる目的そのものでした。しかし、その「王国」の実態は、不動産を巡るゼロサムゲームで他者を打ち負かすという、剥き出しの征服欲に過ぎませんでした。破壊と強欲に、「王国建設」という大義名分を与えたに過ぎないのです。
齋藤の魅力に絡め取られた彰洋は、地上げの実行部隊として、その才能を開花させていきます。大金が動く快感は、もはや彼にとってなくてはならない麻薬となっていきます。このあたりの、悪の世界に染まっていく過程の描写は、読んでいて背筋がぞくぞくするほどのリアリティがありました。
同時に、彼の内面では激しい葛藤が描かれます。クリスチャンだった祖父の「人を騙してはいかん」という教えと、目の前にある興奮。彼は自らの良心を踏みにじり、新しい世界の住人となることを選択します。彼が生まれながらの悪人ではなく、自らの意思で堕ちていくことを選んだ人間であることが、この物語に深みを与えていると感じました。
物語は、齋藤、波潟、そして麻美という、三人のプレイヤーが繰り広げる権力闘争を軸に進んでいきます。齋藤は旧世代を打倒し、自らの時代を築こうとする冷徹な野心家です。彼は彰洋をはじめ、周りの人間を自分の野望のための駒として、実に巧みに操ります。対する波潟は、業界に君臨する「地上げの神様」。しかし、その力も時代の大きなうねりの前では、次第に色褪せていくのが哀しいところです。
そして、この二人の男の間で立ち回るのが、浅野麻美です。彼女こそ、この物語における究極の生存者であり、最も冷静な策略家と言えるかもしれません。波潟の愛人という立場を利用し、齋藤とも繋がることで、両者を天秤にかける。彼女の行動原理はただ一つ、自らの利益の最大化。その剥き出しの野心は、ある意味で誰よりも「正気」であったのかもしれません。
彰洋の心の揺れは、対照的な二人の女性との関係にも表れています。一人は、まっとうな生き方を象徴する恋人の早紀。しかし、この物語の世界では、彼女の善良さはどこか無力で、現実から目を背けた弱さのようにも映ります。もう一人が、麻美です。彼女は、バブルという時代が生み出した、蠱惑的で非道徳的な精神そのものを体現している存在でした。
この物語が突きつけるのは、伝統的な美徳や善良さがいかに無力であるか、という冷徹な現実です.麻美の冷酷なまでの自己利益の追求は、逆説的に一種の「強さ」として描かれます。腐敗しきったシステムの中では、他者よりもっと腐敗することだけが、唯一の生存戦略であるかのようです。この割り切りには、一種の爽快感すら覚えてしまいました。
ゲームのプレッシャーが頂点に達するにつれ、彰洋の精神はドラッグとセックスによって蝕まれていきます。これらは単なる快楽ではなく、増大する罪悪感や恐怖、そして自分を見失っていく感覚から逃れるための、自己破壊的な行為でした。彼の魂が、少しずつ削られていく様子が痛々しく伝わってきます。
物語の中盤からは、まさに裏切りのオンパレードです。信じていた人間に裏切られ、その裏切りすらもさらなる裏切りへの布石でしかない。誰が本当のことを言っているのか、誰を信じればいいのか、彰洋だけでなく読んでいるこちらも混乱の渦に叩き込まれます。彼は齋藤の駒となり、波潟を欺くスパイとなり、しかしその全てが麻美に筒抜けという、何重もの嘘の迷宮に迷い込んでしまうのです。
この絶え間ない緊張状態は、彰洋の精神を完全に破壊していきます。当初の「ひりひりしたい」という刺激への渇望は、いつしか絶え間ないパラノイアへと変質。ドラッグの影響も相まって、彼の行動は予測不能なものとなり、ゲームの均衡を崩しかねない危険な存在、ジョーカーとなっていきます。この危うさが、物語のサスペンスを極限まで高めていました。
男たちが権力とプライドを賭けた争いに夢中になる中、麻美だけは常に冷静でした。彼女は男たちを利用し尽くし、最終的に全ての利益を独り占めしようと画策します。彼女の冷徹な計算高さと行動力は、この物語の中で最も印象に残るものでした。彼女こそが、バブルという時代の真の勝者だったのかもしれません。
やがて、歴史の必然としてバブルは崩壊します。音楽は止み、熱狂は絶望へと変わるのです。価値のなくなった資産を押し付け合う、最後の醜い椅子取りゲーム。その結末は、あまりにも無慈悲でした。彰洋は、文字通り全てを失います。金も、恋人も、正気も、そして自分自身さえも。彼はゲームの完全な敗者として、ただ瓦礫の中に立ち尽くすのです。
興味深いのは、馳星周作品にありがちな、血で血を洗うような結末を避けている点です。主要な登場人物のほとんどが、肉体的には生き残ります。これは決して甘さではありません。死は、ある意味で救済です。しかし作者は彼らを生かし、バブル後の冷え切った現実の中で、自らの愚かさと人生の空虚さに直面させるという、もっと残酷な罰を与えたのだと感じました。彼らにとって、生き続けることこそが地獄なのです。
そして物語の最後に、彰洋は痛烈な自己認識に至ります。「だれにも心を開かなかったくせに、心を開いてくれない他人を憎んだ」。この一文に、彼の悲劇の全てが集約されているように思いました。彼の渇望の根底にあったのは、どうしようもない孤独と自己欺瞞だったのです。ここで初めて、「生誕祭」というタイトルの持つ、強烈な皮肉が胸に突き刺さります。これは祝福されるべき誕生ではなく、全てを失った場所からの「再出発」、バブルの幻想から覚めた過酷な現実への「誕生」を意味していたのです。それは、古い自己の死と、痛みを伴う新しい自己の誕生を祝う、暗い儀式だったのかもしれません。
まとめ
馳星周さんの「生誕祭」は、バブルという時代が持つ狂気と、そこで翻弄された人々の姿を生々しく描き切った傑作でした。物語を通して描かれるのは、人間の抑えきれない欲望と、その果てにある破滅の姿です。しかし、そこには単なる断罪ではない、登場人物たちへのある種の共感や哀れみも感じられました。
主人公・彰洋が求めた「ひりひりする」感覚は、彼一人のものではなく、あの時代を生きた多くの人々が共有していたものなのかもしれません。誰もが熱に浮かされ、永遠に続くかのような祭りに酔いしれた。その結末を知っている私たちは、彼の転落をどこか切ない気持ちで見守ることになります。
物語の終盤で明らかになる「生誕祭」というタイトルの本当の意味には、深く考えさせられました。それは、古い自分が死に、新しい自分が生まれる儀式。しかし、それは決して祝福に満ちたものではなく、全てを失った痛みの中から始まる、過酷な現実への誕生でした。この皮肉に満ちた結末こそが、この物語の読後感を忘れられないものにしています。
この物語は、バブルという一つの時代を描いた作品でありながら、現代を生きる私たちの心にも強く訴えかける普遍性を持っています。人間の欲望は、時代が変わっても形を変えて存在し続けるのかもしれません。続編である「復活祭」では、彼らがどのように「復活」していくのか、期待が膨らみます。