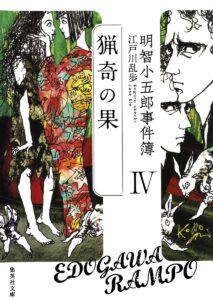 小説「猟奇の果」のあらすじを物語の核心に触れる部分を含めて紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この作品は、江戸川乱歩の長編の中でも、とりわけ異色な存在として知られていますね。読む人によって評価が大きく分かれる、実に不思議な魅力を持った物語です。
小説「猟奇の果」のあらすじを物語の核心に触れる部分を含めて紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この作品は、江戸川乱歩の長編の中でも、とりわけ異色な存在として知られていますね。読む人によって評価が大きく分かれる、実に不思議な魅力を持った物語です。
私自身、この「猟奇の果」という作品には、初めて読んだ時から強く惹かれるものがありました。前半のじわじわと迫りくるような不気味さと、後半の思いもよらない展開の連続。その奇妙なちぐはぐさが、かえって忘れられない読書体験を与えてくれるのです。
この記事では、そんな「猟奇の果」の物語の筋道を追いながら、その核心部分にも触れていきます。未読の方は、物語の結末に関する情報も含まれますので、その点をご留意の上、読み進めていただければと思います。
そして、物語の紹介だけでなく、私がこの作品に対して抱いた思いや考えを、たっぷりと語らせていただきます。なぜこの作品がこれほどまでに私の心をつかむのか、その理由をじっくりとお伝えできればと考えています。どうぞ最後までお付き合いください。
小説「猟奇の果」のあらすじ
物語は、主人公の青木愛之助が、友人の品川四郎とそっくりな人物を奇妙な状況で見かけるところから始まります。品川本人も、映画の中に自分と瓜二つの男が映っているのを発見し、不安を募らせます。どうやら、品川の「偽者」が、彼の周囲で不可解な行動を繰り返しているようなのです。
事態はさらに深刻化します。青木は、その偽品川が、あろうことか品川の妻である芳江と密会している場面を目撃してしまうのです。疑念を抱いた青木が偽品川の後を追うと、そこは怪しげな洋館でした。彼は屋敷に忍び込みますが、偽品川に見つかり、もみ合いの末、相手を射殺してしまいます。
混乱し、街をさまよう青木の前に、以前出会ったことのある、まるでお面をかぶったかのような、異様な風貌の青年が現れます。青木はその青年に導かれるまま、謎めいた地下室へと足を踏み入れます。そこで彼を待ち受けていたものとは…。このあたりで、物語の前半は幕を閉じ、不穏な空気を残します。
後半に入ると、物語の雰囲気は一変します。品川の妻、芳江が偽品川によって誘拐され、その後、彼女のものと思われる切断された腕が発見されるという、衝撃的な事件が発生します。前半の心理的な恐怖から、より直接的で残酷な展開へと移り変わるのです。この猟奇的な事件は世間の注目を集めます。
このニュースを聞きつけ、警視庁に現れたのは、なんと二人の品川四郎。本物と偽物、どちらがどちらなのか判別がつかない状況に、浪越警部も困惑します。そこに偶然(?)居合わせたのが、我らが名探偵、明智小五郎。彼はこの奇怪な事件の捜査に乗り出すことになります。
ここから物語は、世界征服を企む謎の犯罪組織「白蝙蝠団」と明智小五郎の対決を描く、冒険活劇の色合いを濃くしていきます。「人間改造術」なる、人を別人に作り変えてしまう恐るべき技術の存在が明らかになり、誰が本物で誰が偽者なのか、登場人物たちの正体さえも疑わしくなる、混沌とした状況へと突き進んでいくのです。
小説「猟奇の果」の長文感想(ネタバレあり)
さて、この「猟奇の果」ですが、一般的には乱歩作品の中でも「失敗作」や「珍作」と呼ばれることが多いようですね。作者である乱歩自身も、後年、この作品について「珍妙な作品」と述懐しているほどです。確かに、一つのまとまった物語として見たとき、前半と後半の接続のスムーズさや、伏線の回収という点では、疑問符が付く部分があるのは否めません。
物語の前半は、自分のそっくりさんが現れるという、ドッペルゲンガー的な怪異譚から始まります。日常に潜む不安や、正体不明の存在に対する恐怖が、じわりじわりと描かれていきます。これは、乱歩が得意とする心理描写、いわゆる「乱歩らしい」世界観が色濃く出ている部分と言えるでしょう。主人公の青木愛之助が、友人であるはずの品川四郎の不可解な行動や、その偽者の存在に翻弄され、次第に精神的に追い詰められていく様は、読んでいて息苦しさを感じるほどです。
特に、偽品川が本物の品川になりすまし、その妻である芳江と逢瀬を重ねているのではないか、という疑惑が持ち上がるあたりは、背筋が寒くなるような展開です。自分の知らないところで、自分そっくりの何者かが自分の大切なものを侵食していくかもしれない、という恐怖。これは非常に根源的な不安を掻き立てられます。青木が偽品川を追跡し、乱闘の末に殺害してしまう場面も、前半のクライマックスとして強烈な印象を残します。
しかし、物語が後半、いわゆる「白蝙蝠篇」に突入すると、その雰囲気は驚くほど変わります。芳江の誘拐と、切断された腕の発見というショッキングな事件を皮切りに、物語は個人の心理的な恐怖劇から、犯罪組織と名探偵の対決という、よりスケールの大きな冒険活劇へとシフトしていくのです。この転換は、あまりにも唐突で、まるで別の物語が始まったかのように感じる読者も多いのではないでしょうか。
この急激な路線変更には、実は執筆の裏話があります。連載当時、乱歩は前半部分を書いた後、物語の展開に行き詰まってしまったそうです。そこで相談を受けたのが、当時『文藝倶楽部』の編集長であり、自身も高名な探偵作家である横溝正史でした。横溝は「いっそ『蜘蛛男』のような派手なスリラーにしてはどうか」と提案したと言われています。この助言を受け、乱歩は「人間改造術」という奇抜なアイディアを思いつき、物語を大きく方向転換させたわけです。
この「人間改造術」という設定が、後半の物語をある意味で破綻させ、同時に、他に類を見ない奇妙な面白さを生み出す要因となっています。何しろ、整形手術のような技術で、人間をまったくの別人、それも特定の人物そっくりに作り変えることが可能だというのですから。この設定が登場したことで、もはや誰が本物で誰が偽者なのか、まったく信用できなくなります。
登場人物の多くが、実は偽者だった、あるいは偽者にすり替わっているのではないか、という疑念が常に付きまといます。主人公の友人である品川はもちろん、事件の被害者であるはずの芳江、さらには警視総監までもが偽者として登場する始末。ここまでくると、もはやミステリとしての整合性や論理性を問うこと自体が野暮に思えてくるほどです。
中でも笑いを誘うのが、名探偵・明智小五郎の立ち回りです。彼は颯爽と登場し、事件解決に乗り出すのですが、この「人間改造術」と偽者の氾濫によって、彼自身も大いに混乱させられます。ある場面では、二人の品川を前にして、どちらが本物かを見抜けず、偽者を取り逃がしてしまうという失態を演じます。普段の怜悧な名探偵ぶりからは想像もつかない、どこか間の抜けた姿を見せるのです。
さらに物語が進むと、明智小五郎自身にも偽者が登場し、どの明智が本物なのか、読者はおろか、作者自身も混乱しているのではないかと思わせるような描写も見られます。この、本来シリアスであるはずの探偵役までもが偽者の存在に脅かされるという展開は、一種のパロディのようでもあり、本作の「珍妙さ」を際立たせています。常識的な探偵小説の枠組みを、ある意味で破壊しているとも言えるでしょう。
このように、後半は荒唐無稽とも言える展開が続きます。前半で丁寧に描かれた心理的な恐怖や謎は、ある種、力技でねじ伏せられ、奇想天外なアクションとサスペンスが繰り広げられます。当初乱歩が構想していたであろう、品川の自作自演、一人芝居だったのではないかという解決案の痕跡が、作中で警視総監(これも偽者ですが)の口から語られる場面がありますが、それはあくまで「仮説」として処理され、物語は「人間改造術」を用いた壮大な陰謀へと突き進んでいきます。
この前半と後半の断絶、そして後半の破天荒な展開こそが、「猟奇の果」が「失敗作」と呼ばれる所以なのでしょう。しかし、私個人としては、このアンバランスさ、支離滅裂さこそが、本作の最大の魅力ではないかと感じています。整合性を欠いた物語、常識外れの設定、迷走する名探偵。これらが渾然一体となって、他に類を見ない、悪夢のような、それでいてどこか滑稽で、不思議な読後感をもたらしてくれるのです。
前半のじっとりとした恐怖と、後半のジェットコースターのような展開。一つの作品で二つの異なる味わいを楽しめる、と言えば聞こえは良いかもしれませんが、実際にはもっと混沌としていて、カテゴライズが難しい作品です。しかし、そのカテゴライズ不能な「怪作」ぶりに、私は強く惹かれます。読み返すたびに、その奇妙なエネルギーに圧倒され、やはり面白い、と感じてしまうのです。
特に、後半の「誰が本物で誰が偽者か分からない」という状況は、現代のアイデンティティの問題や、現実と虚構の境界線の曖昧さといったテーマにも通じるものがあるように思えます。もちろん、乱歩がそこまで意図していたかは分かりませんが、結果的に、この荒唐無稽な物語が、ある種の普遍的な不安や混乱を映し出しているようにも感じられるのです。
「猟奇の果」は、決して万人受けする作品ではないでしょう。探偵小説としての完成度を求める読者にとっては、物足りなさや不満を感じる点が多いかもしれません。しかし、江戸川乱歩という作家の持つ、グロテスクで、エロティックで、そしてどこかユーモラスでもある、その混沌とした魅力、奇想の奔流のようなものを体感したいのであれば、これほど適した作品もないのではないでしょうか。一度ハマると抜け出せない、まさに「猟奇の果て」へと誘う、恐ろしくも魅力的な一作だと、私は思います。
まとめ
江戸川乱歩の「猟奇の果」は、その評価が大きく分かれる、まさに「珍作」と呼ぶにふさわしい長編小説です。物語は、日常に潜む不気味な謎を描く前半と、名探偵・明智小五郎が登場し、荒唐無稽な犯罪組織と対決する後半とで、その様相をがらりと変えます。この急激な変化は、連載中の紆余曲折に起因するものですが、結果として他に類を見ない独特な作品世界を生み出しています。
特に後半で登場する「人間改造術」という設定は、物語を破綻寸前のカオスへと導きます。登場人物のほとんどが偽者かもしれないという状況は、ミステリとしての整合性を超え、シュールで滑稽な味わいすら醸し出します。名探偵であるはずの明智小五郎でさえ、この混乱に巻き込まれ、迷探偵のような一面を見せることもあります。
このような構成のアンバランスさや、展開の奇抜さから、「失敗作」と評されることも少なくありません。しかし、その一方で、この支離滅裂さ、常識外れのエネルギーこそが「猟奇の果」の抗いがたい魅力であるとも言えます。一つの作品で、心理的な恐怖と冒険活劇、そして悪夢的な混乱を同時に味わえる、他に類を見ない読書体験を提供してくれるのです。
完成度や整合性を求める方にはおすすめしにくいかもしれませんが、江戸川乱歩の持つ混沌とした想像力、奇想の世界に触れたい方にとっては、忘れられない一作となる可能性を秘めています。賛否両論あることを理解した上で、ぜひ一度、この奇妙で魅力的な「猟奇の果」の世界に足を踏み入れてみてはいかがでしょうか。






































































