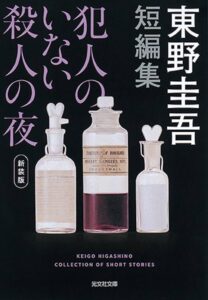 小説「犯人のいない殺人の夜」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。東野圭吾氏によるこの短編集、表題作をはじめとして、人間の心の内に潜む闇と、そこから生まれる悲劇、あるいは喜劇とも呼べるような事件の数々を描き出しております。一筋縄ではいかない物語が七編、読者を待ち構えているというわけです。
小説「犯人のいない殺人の夜」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。東野圭吾氏によるこの短編集、表題作をはじめとして、人間の心の内に潜む闇と、そこから生まれる悲劇、あるいは喜劇とも呼べるような事件の数々を描き出しております。一筋縄ではいかない物語が七編、読者を待ち構えているというわけです。
さて、本書に収められた物語は、いずれも日常に潜む悪意や、ふとした偶然が引き起こす予想外の結末を扱っています。巧妙に仕掛けられた罠、登場人物たちの心理描写、そして読者の予想を裏切る展開。これらが東野作品の持ち味であることは、衆目の一致するところでありましょう。特に表題作は、そのタイトル自体が既に一つの謎かけとなっているのですから、興味をそそられずにはいられません。
この記事では、まず各編の物語の筋立てを追い、特に表題作「犯人のいない殺人の夜」については、その仕掛けの核心に触れながら、詳細な物語の顛末と、それに対する私の所感を述べてまいります。もちろん、他の短編についても、それぞれが持つ独特の味わいを、可能な限りお伝えするつもりです。少々長くなりますが、しばしお付き合いいただければ幸いです。
小説「犯人のいない殺人の夜」のあらすじ
東野圭吾氏の短編集「犯人のいない殺人の夜」は、七つの独立した物語で構成されています。いずれもミステリの要素を含んでいますが、その趣は様々です。高校生の淡い恋と死の真相が絡み合う「小さな故意の物語」、弟の死の謎を追う姉の葛藤を描く「闇の中の二人」、純粋な憧れが思わぬ悲劇を招く「踊り子」、大阪を舞台に夫の死の真相を探る妻の物語「エンドレス・ナイト」、会社内で起こる連続死の裏にある悪意を暴く「白い凶器」、アーチェリー選手の死に隠された秘密を解き明かす「さよならコーチ」、そして、タイトルが示す通り、不可解な状況設定が際立つ表題作「犯人のいない殺人の夜」。
表題作「犯人のいない殺人の夜」は、ある雨の夜、建築家・岸田創介の邸宅で起こった出来事を描きます。創介の息子・拓也の家庭教師である安藤敦子は、岸田家からの緊急の呼び出しを受け、駆けつけます。そこで彼女が目にしたのは、殺害されたと思われる男の死体でした。しかし、岸田家の人々——創介、妻の靖子、そして拓也——は、警察への通報をためらい、事件そのものを隠蔽しようと画策します。さらに、拓也のもう一人の家庭教師であり、恋人でもある高野雅美もこの計画に加担することになります。
物語は、事件当日の夜の出来事を「夜」の視点(主に雅美の視点から語られるようにミスリードされる)と、事件後の捜査状況を描く「今」の視点(主に拓也の視点)を交互に織り交ぜながら進行します。岸田家の人々と家庭教師たちは、口裏を合わせ、死体を運び出し、完璧な隠蔽工作を図ろうとします。しかし、警察の捜査は徐々に彼らに迫り、綻びが生じ始めます。なぜ彼らは事件を隠蔽しようとしたのか。そして、タイトルにある「犯人のいない」とは何を意味するのか。
警察の執拗な捜査と、関係者たちの証言の食い違いから、徐々に事件の輪郭が明らかになっていきます。特に、二人の家庭教師、敦子と雅美の存在、そして拓也の不可解な言動が鍵となります。最終的に、読者は巧妙に仕掛けられた叙述トリックと、事件の驚くべき真相、そして人間のエゴイズムが引き起こした悲劇の全貌を知ることになるのです。この結末は、まさに東野ミステリの真骨頂と言えるでしょう。
小説「犯人のいない殺人の夜」の長文感想(ネタバレあり)
さて、東野圭吾氏の短編集「犯人のいない殺人の夜」について、もう少し踏み込んだ話をいたしましょう。この作品集、初期の作品群に属するということもあり、後の洗練された長編作品とはまた異なる、荒削りながらも瑞々しい、あるいは毒々しい魅力に満ちていると感じます。七つの物語は、それぞれが独立したミステリとして成立しており、読後感も様々です。甘酸っぱい青春の切なさから、人間の業の深さに打ちのめされるようなものまで、実に多彩な味わいを提供してくれます。
まずは収録作全体に目を向けてみましょう。「小さな故意の物語」は、高校生たちの揺れ動く心情と、友情、そして淡い恋心が絡み合い、一つの死の真相へと収斂していく様が見事です。親友の不可解な死。自殺か、事故か、それとも…。真相を知った時の、何とも言えない苦さが胸に残ります。「故意」という言葉の重みが、青春の脆さと相まって、深く突き刺さるのです。タイトルの意味するところが、実に秀逸と言えましょう。
「闇の中の二人」は、赤ん坊の弟の死という衝撃的な幕開けから、家族の中に潜む闇を炙り出していきます。警察の捜査が進むにつれて、容疑者は絞られていくものの、物語はそれだけでは終わりません。なぜ幼い命が奪われなければならなかったのか。その動機が明らかになった時、読者は人間の心の暗部に触れ、慄然とするのではないでしょうか。特に、犯人の心情を思うと、同情の余地はないにしても、やりきれない思いが残ります。
「踊り子」は、中学生の純粋な憧れが、予期せぬ悲劇へと繋がっていく物語です。塾帰りに見かけた新体操の練習に励む少女。彼女に近づきたい一心で行動する主人公・孝志の姿は、微笑ましくもあります。しかし、ある出来事を境に物語は暗転し、少女は姿を消します。その後の展開、そして明らかになる事実は、孝志にとってはもちろん、読者にとっても受け入れがたい、残酷なものです。善意が必ずしも良い結果を招くとは限らない。人生の皮肉を感じさせる一編です。読者の先入観、例えば「新体操をする美しい少女」というステレオタイプなイメージを巧みに利用している点も、この作品の妙味と言えるでしょう。
「エンドレス・ナイト」は、大阪という街の持つ独特の空気感と共に、夫の死の真相を探る妻・厚子の心情を描き出します。単身赴任中の夫が殺害された。夫が嫌っていたはずの大阪で。厚子は、刑事と共に夫が生きた街を歩き、その足跡を辿ります。夫が大阪で何を思い、どのように生きていたのか。次第に明らかになる事実と、厚子の心に芽生える感情。そして最後の台詞が、深い余韻を残します。大阪という街の描写が、物語に奥行きを与えています。ただ、刑事の「匂いでわかる」という勘には、少々肩透かしを食らった感も否めませんが。
「白い凶器」は、オフィス内で起こる連続不審死を扱った作品です。事故にも見える死。しかし、そこには微かな事件の匂いが漂います。合間に挿入される犯人の独白によって、容疑者はある程度推測できるものの、その動機と犯行の全貌はすぐには見えません。なぜ犯人は犯行を重ねるのか。その理由は、驚くほど自己中心的で、身勝手な思い込みに基づいています。人間のエゴイズムの恐ろしさを突きつけられるような作品です。犯人の独白の相手については、見事にミスリードされました。こういう仕掛けは、やはり東野氏らしいと言えるでしょう。
「さよならコーチ」は、元アーチェリー選手の自殺という形で幕を開けます。彼女が遺したビデオメッセージ。「さよなら、コーチ」。その言葉に込められた意味とは。栄光と挫折、選手生命の苦悩。コーチが抱える後悔と自責の念。しかし、彼女が自ら死を選んだ理由を深く探っていくと、思いもよらない事実が浮かび上がってきます。彼女が本当に伝えたかったメッセージは何だったのか。自殺の方法に、理系出身の作家らしい凝った仕掛けが見られるのも特徴的です。蜘蛛がトリック解明のきっかけとなるあたりは、上手いと感じました。
そして、いよいよ表題作「犯人のいない殺人の夜」です。この作品こそ、本書の白眉であり、東野ミステリの初期における一つの到達点と言っても過言ではないでしょう。タイトルからして、実に挑戦的です。「犯人がいない」のに「殺人の夜」とは、一体どういうことなのか。この矛盾を孕んだタイトルが、まず読者の好奇心を強く刺激します。
物語は、いわゆる倒叙ミステリに近い形式を取りながらも、単純な犯人当てやトリック解明に留まらない、複雑な構造を持っています。岸田家で起こった殺人事件。しかし、その場に居合わせた家族と家庭教師たちは、事件を隠蔽しようとします。死体を運び出し、アリバイを作り、口裏を合わせる。その必死の隠蔽工作の過程が、「夜」の視点と「今」の視点を交錯させながら描かれていきます。
この「夜」の視点の語り手が、実に巧妙な仕掛けとなっています。読者は当初、この「あたし」という一人称の語り手を、拓也の恋人でもある家庭教師・雅美だと自然に思い込んでしまうでしょう。文章のトーンや、状況描写が、そう思わせるように巧みに誘導されているからです。しかし、読み進めるうちに、特に「今」の視点における拓也や他の登場人物の証言と、「夜」の描写との間に、微妙な、しかし無視できない齟齬が生じていることに気づかされるはずです。例えば、拓也が警察に対して「由紀子(殺害された被害者)の死亡時、警察に届けるべきだと言った」と証言する場面。これは、「夜」の場面で描かれた、隠蔽を主導するような人物像とは明らかに食い違います。
この違和感こそが、作者が仕掛けた罠なのです。終盤に至り、全ての真相が明らかになった時、読者はこの「あたし」の正体を知り、愕然とすることでしょう。「あたし」は雅美ではなかった。では誰だったのか? その答えは、物語の根幹を揺るがす驚きと共に提示されます。犯人は、確かに存在した。しかし、ある意味で「犯人のいない」状況が作り出されていた。この叙述トリックの見事さには、思わず唸らされます。最初から読み返してみると、確かに「あたし」の語りには嘘はない。ただ、読者が勝手に主語を誤認していただけなのです。この構成力は、まさに圧巻です。まるで手品師が一瞬の隙に観客の視線を欺くかのように、鮮やかに読者を騙し通すのです。
さらに、登場人物たちの動機も見逃せません。なぜ岸田家の人々は、そこまでして事件を隠蔽しようとしたのか。そこには、世間体、家族の名誉、そして個人的な欲望といった、人間の持つ醜い側面が凝縮されています。特に、息子の拓也と、彼の恋人である雅美の関係性。雅美が拓也の犯罪隠蔽に協力する背景には、愛情だけではない、打算的な思惑も透けて見えます。彼女もまた、謎を秘めた存在として描かれているのです。金銭的な動機が絡むあたりは、実に人間臭いと言えましょう。
また、作中で描かれる「ルミノール反応」の説明に一家が青ざめる場面は、当時の科学捜査の進歩と、それが犯罪者に与えるプレッシャーを象徴的に示しています。時代設定を感じさせると同時に、普遍的な人間の心理を描写する巧みさも感じられます。
総じて、「犯人のいない殺人の夜」は、巧妙なプロット、読者の意表を突く叙述トリック、そして人間のエゴイズムや心の闇を深く抉り出す洞察力において、非常に優れた短編ミステリです。この一編だけでも、本書を読む価値は十分にあると言えるでしょう。他の六編も、それぞれに個性的な魅力があり、短編集としての完成度を高めています。初期作品ならではの粗削りな部分も散見されますが、それも含めて、後の巨匠・東野圭吾の原点を垣間見ることができる、興味深い一冊であることは間違いありません。読後、しばらくの間、物語の仕掛けや登場人物たちの行動について、あれこれと考えを巡らせてしまう。そんな作品です。
まとめ
東野圭吾氏の短編集「犯人のいない殺人の夜」は、七つの異なる顔を持つミステリが詰まった、いわば宝石箱のような一冊と言えましょうか。青春のほろ苦さから、人間の業の深淵を覗き込むような物語まで、その振り幅は実に大きい。どの短編も、それぞれに読ませる力を持っています。
特に表題作「犯人のいない殺人の夜」は、そのタイトルが示す通りの不可解な状況設定と、読者を巧みに欺く叙述トリックが見事です。事件の隠蔽を図る登場人物たちの心理描写も秀逸で、人間のエゴイズムや脆さがリアルに描かれています。真相が明らかになった時の衝撃は、まさに格別。この一編を読むだけでも、本書を手にする価値はあるでしょう。
初期の作品集ということで、後の作品と比較すれば、技巧的に未熟な部分がないわけではありません。しかし、そこには瑞々しい感性や、テーマに対する鋭い切り込み、そして何より、読者を楽しませよう、驚かせようという気概が満ち溢れています。東野圭吾という作家の原点を知る上でも、興味深い作品集であることは間違いありません。ミステリ好きならば、一度は手に取ってみることをお勧めします。きっと、あなたの知的好奇心を刺激してくれるはずです。
































































































