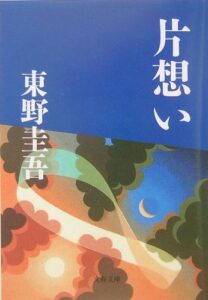 小説「片想い」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。東野圭吾氏が描く、性の境界線という実にデリケートな領域。ミステリーの皮を被ってはいますが、その核心は、人間の抱える根源的な孤独と、一方通行の想いの交錯にあるのかもしれません。まあ、少々説教臭さが鼻につくのは否めませんがね。
小説「片想い」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。東野圭吾氏が描く、性の境界線という実にデリケートな領域。ミステリーの皮を被ってはいますが、その核心は、人間の抱える根源的な孤独と、一方通行の想いの交錯にあるのかもしれません。まあ、少々説教臭さが鼻につくのは否めませんがね。
物語は、かつての仲間との再会から始まります。しかし、その再会が、平穏だったはずの日常を根底から揺るがすことになるのです。殺人という衝撃的な告白、そして隠された秘密。登場人物たちは、友情や愛情、あるいは自己満足のために、危うい道へと足を踏み入れていきます。果たして、彼らの選択は正しかったのか。実に興味深い問いではありませんか。
この記事では、物語の顛末と、それに対する私の個人的な見解を、少々辛辣かもしれませんが、率直に述べさせていただきます。これからこの作品を読む予定の方は、ご注意ください。もっとも、結末を知った上で読むことで、また違った味わい方ができるかもしれませんよ。フッ、それもまた一興でしょう。
小説「片想い」のあらすじ
西脇哲朗。かつて大学のアメフト部でクォーターバックを務め、現在はスポーツライターとして生計を立てる男。彼の日常は、年に一度の同窓会をきっかけに、予期せぬ方向へと転がり始めます。帰り道、彼はアメフト部の元マネージャー、日浦美月と再会します。しかし、彼女の様子は明らかにおかしい。投げやりな化粧、そして声を発しようとしない態度。哲朗は彼女を自宅へ招き入れますが、そこで待っていたのは、想像を絶する告白でした。
「オレは男だったんだ」。化粧を落とし、ウィッグを外した美月は、男性としての姿を現します。性同一性障害。女性の身体に男性の心を宿して生まれた苦悩を、彼女は初めて哲朗に打ち明けたのです。結婚し、子供まで儲けながらも、偽りの人生に耐えきれず家を出たこと。ホルモン注射を打ち、喉を潰して低い声を手に入れたこと。そして現在、新宿のバーで男性として働いていること…。しかし、彼女の告白は、それだけでは終わりませんでした。
「人を殺したんだ」。バーの同僚ホステスにつきまとっていたストーカーを、衝動的に殺害してしまったというのです。自首を決意していた美月でしたが、哲朗の妻であり、美月のかつての親友でもある理沙子は、それを強く引き止めます。「警察には行かせない」。男の心を持つ美月が、刑務所で女性として扱われることの残酷さを、理沙子は案じたのでした。哲朗と理沙子は、美月を匿うことを決意します。
しかし、事態は複雑化していきます。美月の元恋人である中尾功輔、そして事件を追う新聞記者の早田といった、かつての仲間たちが次々と関わってくるのです。警察の捜査、記者の追求、そして隠された過去の秘密。美月を匿う中で、哲朗は事件の裏に潜む、さらに根深い問題に直面することになります。戸倉の家から発見された美月の戸籍謄本。失踪した美月。そして、性別を超えた人々をつなぐ、秘密のネットワークの存在。すべてが明らかになった時、彼らを待つ結末とは…?
小説「片想い」の長文感想(ネタバレあり)
東野圭吾氏の『片想い』。ジェンダーという現代的なテーマを扱い、ミステリーの要素を織り交ぜた意欲作、とでも言えば聞こえはいいでしょうか。しかし、読み終えた後に残るのは、どうにもすっきりしない、むしろ苛立ちに近い感情でした。登場人物たちの行動原理が、どうにも理解し難い。いや、理解したくない、と言うべきかもしれません。
まず、主人公である西脇哲朗。この男、どうにも好感が持てませんね。スポーツライターという職業柄か、正義感ぶった言動が目立ちますが、その実、かなり独りよがりで鈍感な人物と言わざるを得ません。かつての仲間である美月が殺人を犯したと告白しても、自首を止め、匿うことを選択する。友情、と言えば聞こえはいいですが、それは果たして美月のためだったのでしょうか? 彼の行動は、自己満足的な感傷に基づいているようにしか見えません。
さらに呆れるのは、彼が妻である理沙子にすら、自身の片目が不自由であることを隠していたという事実です。他人の秘密には土足で踏み込むくせに、自身の抱える重要な事実はひた隠しにする。それでいて、美月の元恋人である中尾が、血の繋がらない母親に育てられていたという事実を卒業後十数年経って初めて知った際に、「自分たちの関係は一体何だったのだろう」などと感傷に浸るのですから、開いた口が塞がりません。他人に完璧な開示を求めながら、自分は秘密主義を貫く。フッ、滑稽なものです。おまけに、美月とは過去に肉体関係を持ち、妻が望まないにも関わらず避妊を怠る始末。彼の行動原理は、徹頭徹尾、自己中心的と言えるでしょう。こんな人物に感情移入など、到底できませんね。
そして、物語の中心人物である日浦美月。性同一性障害という、計り知れない苦悩を抱えていることは想像に難くありません。しかし、彼女の行動もまた、疑問符が付くものばかりです。殺人を犯したと告白しながら、結局は哲朗たちの説得(というより甘言でしょうか)に乗り、自首を思いとどまる。そして、匿われている間に精神的に不安定になり、あろうことか哲朗に迫ろうとする。挙げ句の果てには失踪。彼女が真に望んでいたものは何だったのか。男として生きること? それとも、ただ現状から逃避したかっただけなのでしょうか。
作中では、彼女はXジェンダー(自認する性が曖昧)に近い存在としても描かれています。「心は男」と言いながら、哲朗や中尾とは肉体関係を持つことができた。この矛盾。まあ、人間の心とは、それほど単純ではないということなのでしょう。相川が語る「メビウスの帯」や、中尾が語る「グラデーション」の話は、性の多様性を示すものとして、一応は理解できます。しかし、それを延々と説明されると、正直、「だから何だ?」と言いたくもなりますね。「完全な男も完全な女もいない」…結構なことですが、それを盾に自身の行動を正当化するのは、少々虫が良すぎるのではないでしょうか。私から言わせれば、あなたが男であろうが女であろうが、あるいはその中間であろうが、どうでもいいことです。人としての魅力があるか、ないか。ただそれだけのこと。美月の行動は、自身の性の問題以前に、人としてあまりにも未熟で、身勝手に見えてしまいます。
哲朗の妻、理沙子も大概です。「賢い」という設定らしいですが、その行動は感情的で、短絡的に見えます。「美月の人生を中途半端なままで終わらせたくない」という想いは分からなくもありませんが、そのために殺人犯を匿い、時効まで女性の姿でいることを強いるというのは、本末転倒も甚だしい。ホルモン注射を止めさせれば女性の体に戻るから容疑者とは見られないだろう、という発想も、あまりに楽観的、いや、愚かと言ってもいいかもしれません。彼女の行動は、友情というよりは、支配欲に近いものすら感じさせます。
そして、物語の鍵を握る中尾功輔。彼こそが真犯人であり、戸籍交換システムの中心人物だった。彼の行動原理は、美月への「片想い」と、システムに関わる人々への「責任」でしょうか。癌に侵され、余命いくばくもない身でありながら、すべての秘密を抱えて自ら命を絶つことを選ぶ。自己犠牲と言えば聞こえはいいですが、これもまた、独りよがりな感傷に過ぎないように思えます。彼が本当に守りたかったものは何だったのか。美月か、システムか、それとも彼自身の美学か。彼の死によって、確かに秘密は守られたのかもしれません。しかし、残された者たちの心に、深い傷跡を残したこともまた事実です。
この物語に登場する主要な人物たちは、皆、それぞれの「片想い」を抱えています。美月から理沙子へ。中尾から美月へ。あるいは哲朗の、歪んだ友情という名の片想い。そして、社会に対する、理解を求める声という名の片想い。しかし、その想いは一方通行で、交わることはありません。まるで終わりのないメリーゴーラウンドのように、彼らは同じ場所をぐるぐると回り続け、決して目的地にたどり着くことはないのです。
ミステリーとしての側面、特に戸籍交換のトリックなどは、それなりに練られているとは思います。しかし、それ以上に、登場人物たちの身勝手さや、説教臭いジェンダー論が鼻についてしまい、素直に物語を楽しむことができませんでした。性の多様性を描こうとした意欲は認めますが、その描き方があまりにも感傷的で、登場人物たちの行動にリアリティが感じられない。結局、彼らは皆、自分の抱える問題や感情に酔っていただけなのではないか。そんな疑念が、読後も晴れることはありませんでした。まあ、これも一つの「片想い」なのかもしれませんね。作品に対する、私の。
まとめ
東野圭吾氏の小説『片想い』は、性同一性障害という重いテーマを扱いながら、殺人事件の謎を追うミステリーの形式をとっています。大学時代のアメフト部の仲間たちが、ある告白をきっかけに、複雑な人間関係と隠された秘密の渦へと巻き込まれていく様が描かれています。友情、愛情、そしてそれぞれの「片想い」が交錯する中で、登場人物たちは危うい選択を重ねていきます。
物語の核心には、男と女という二元論では捉えきれない、性の多様性と、それに伴う葛藤があります。「メビウスの帯」や「グラデーション」といった概念を用いて、その複雑さが語られますが、その一方で、登場人物たちの行動原理には、共感し難い身勝手さや独りよがりな感傷が目立ちます。主人公をはじめ、主要な登場人物たちの行動は、時に理解を超え、読者を苛立たせるかもしれません。
ミステリーとしての仕掛けや、戸籍交換といったトリックは興味深いものの、作品全体としては、ジェンダーというテーマに対する作者のメッセージ性が強く押し出されている印象を受けます。それが説教臭いと感じるか、深く考えさせられると感じるかは、読者によって意見が分かれるところでしょう。読後、爽快感よりも、むしろ重苦しい問いが残る。そんな作品と言えるかもしれませんね。
































































































