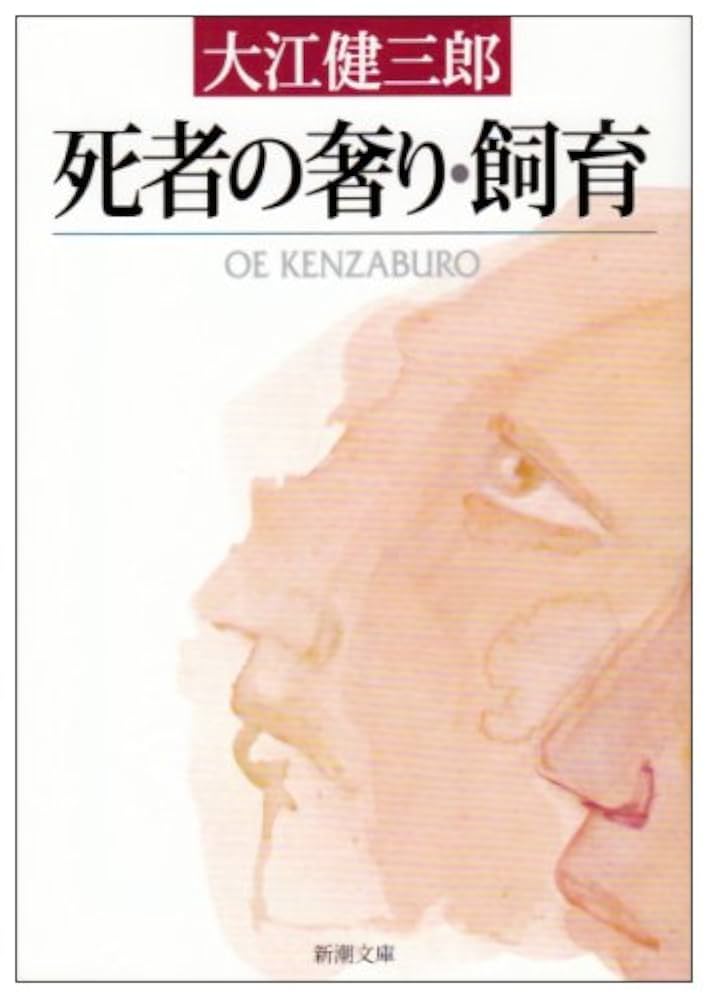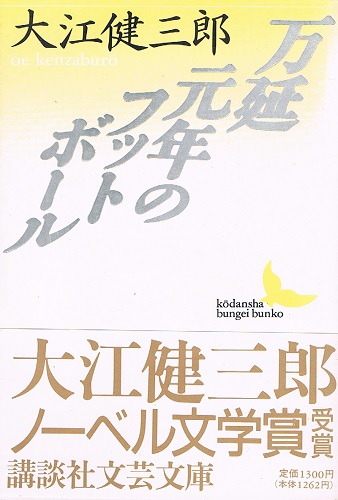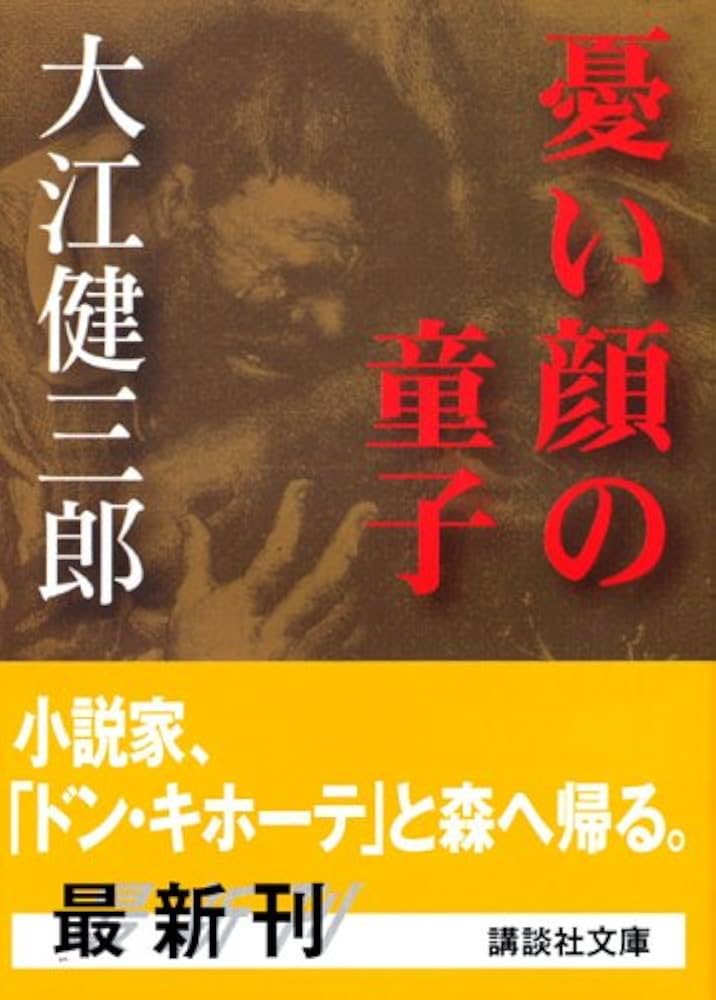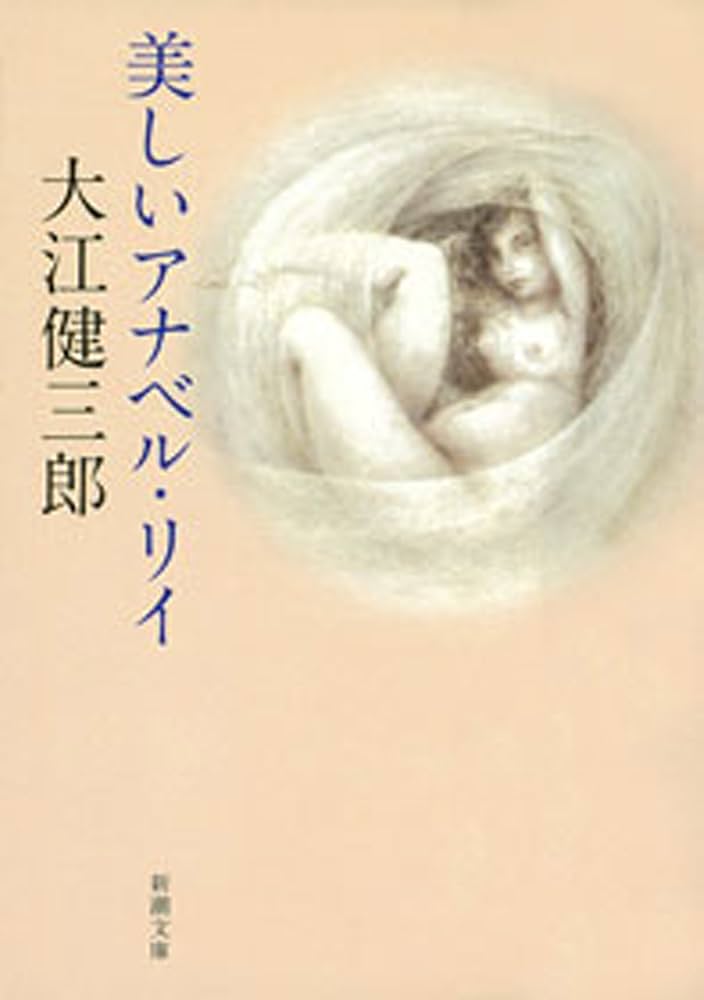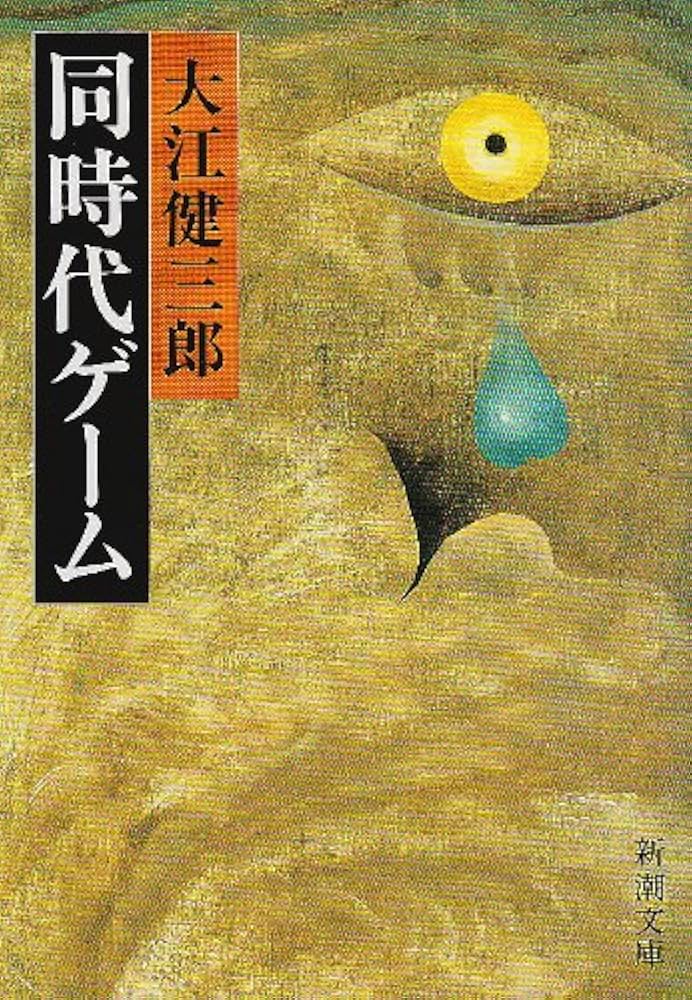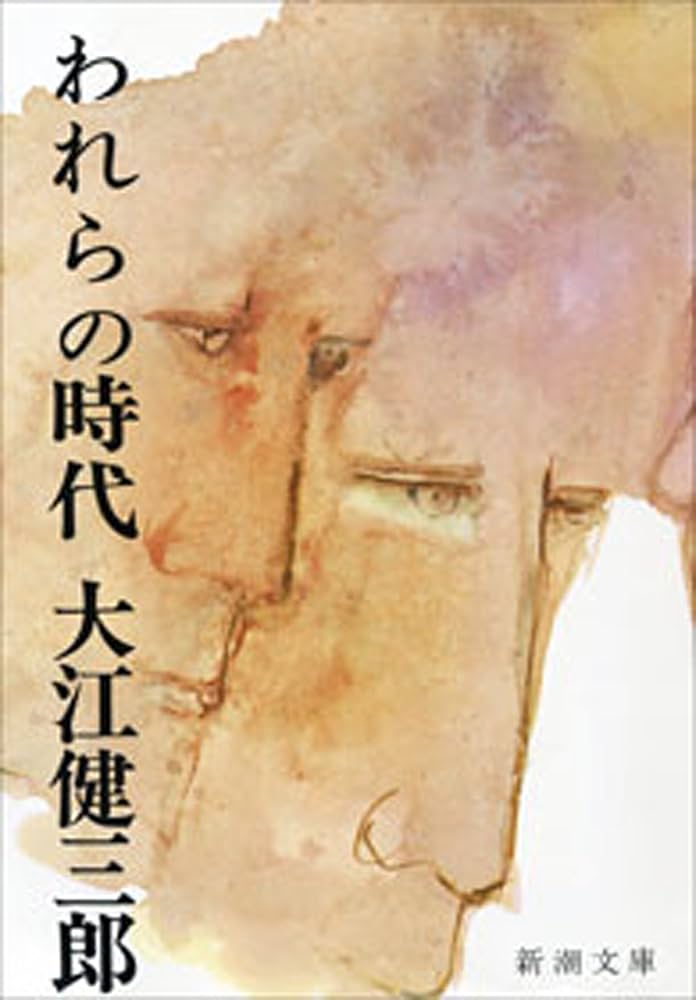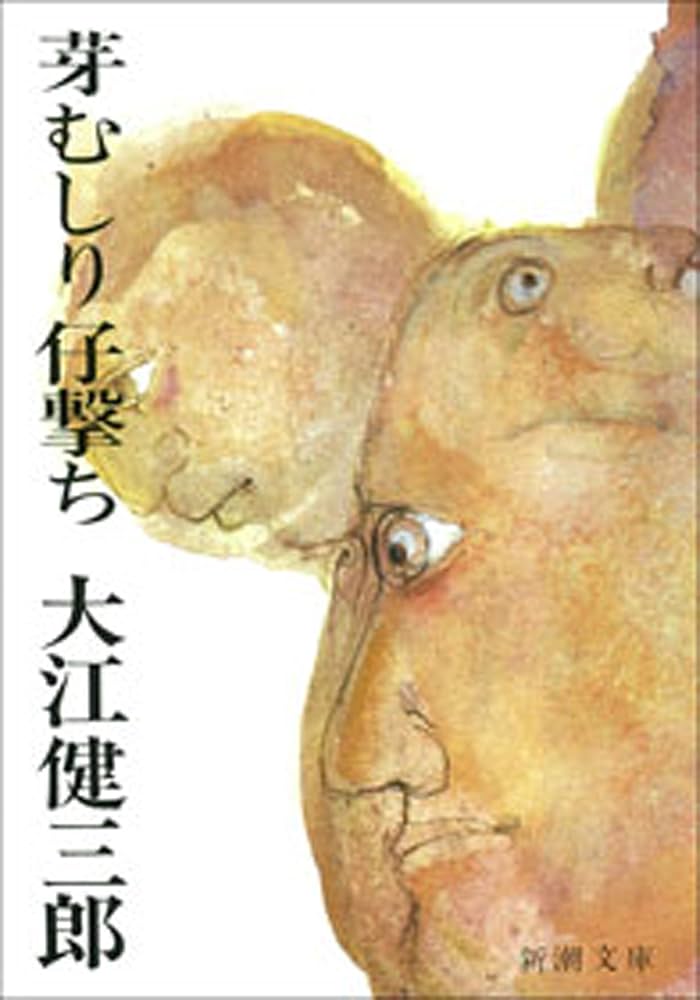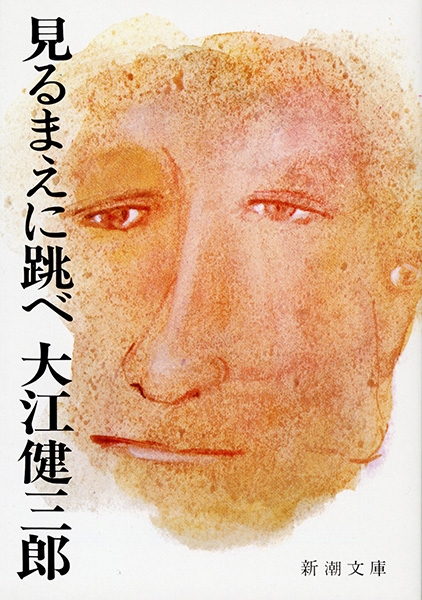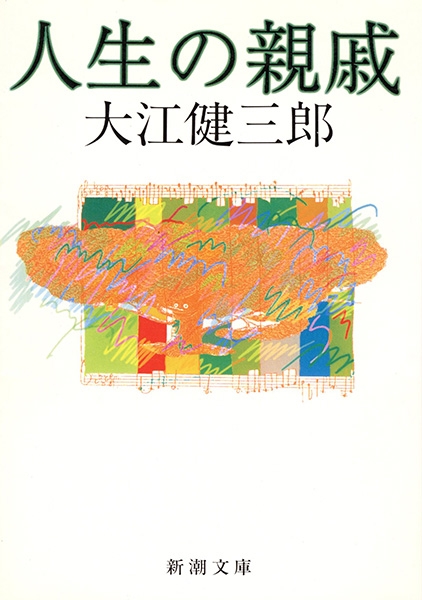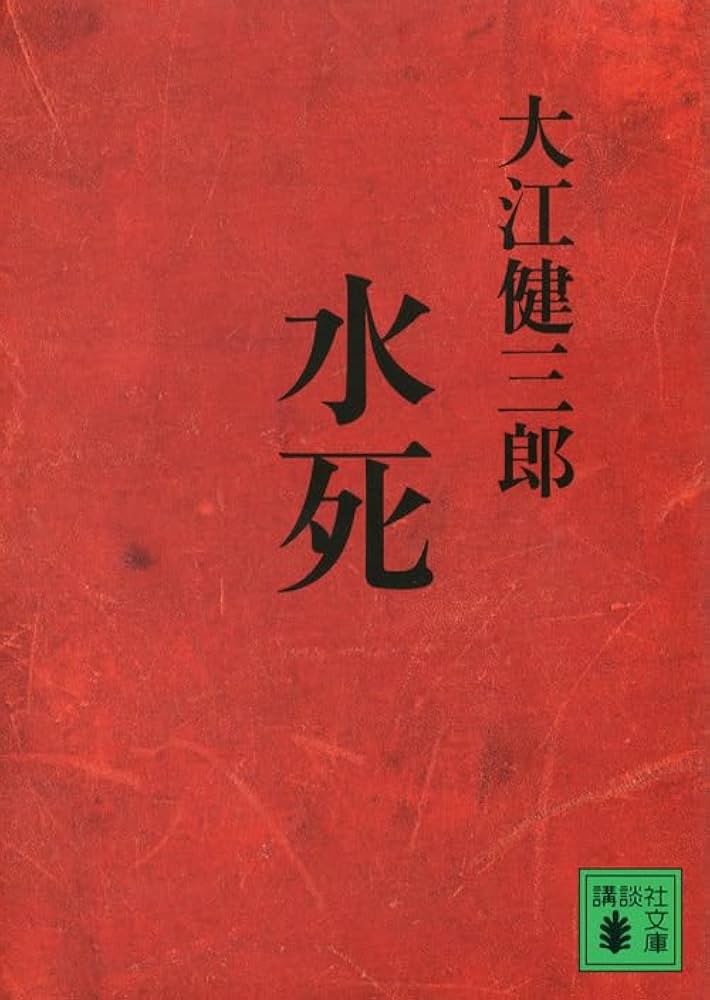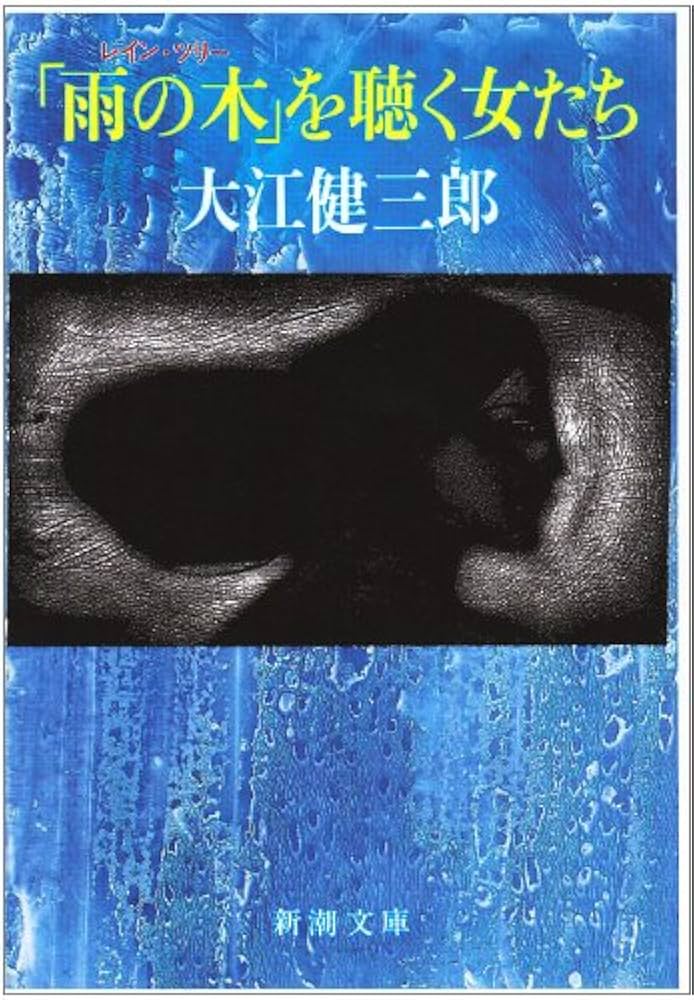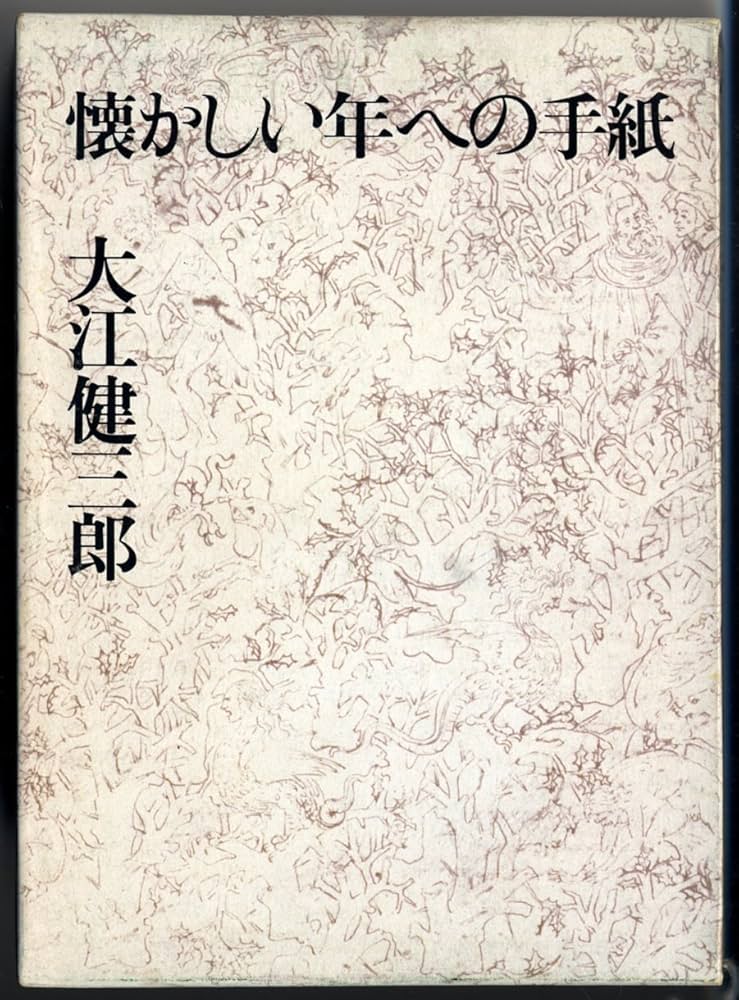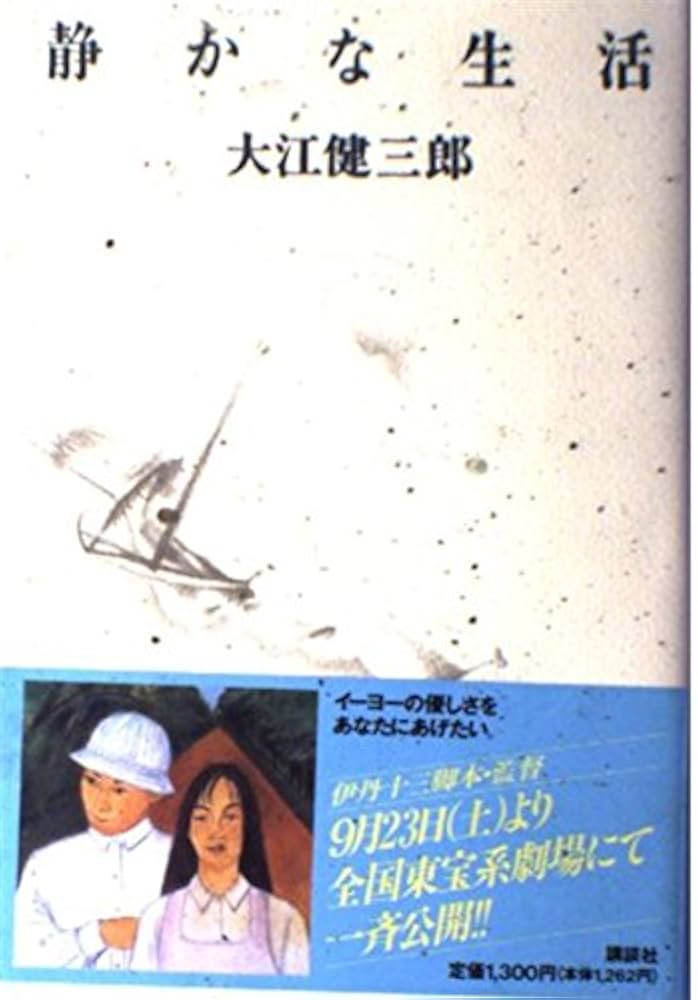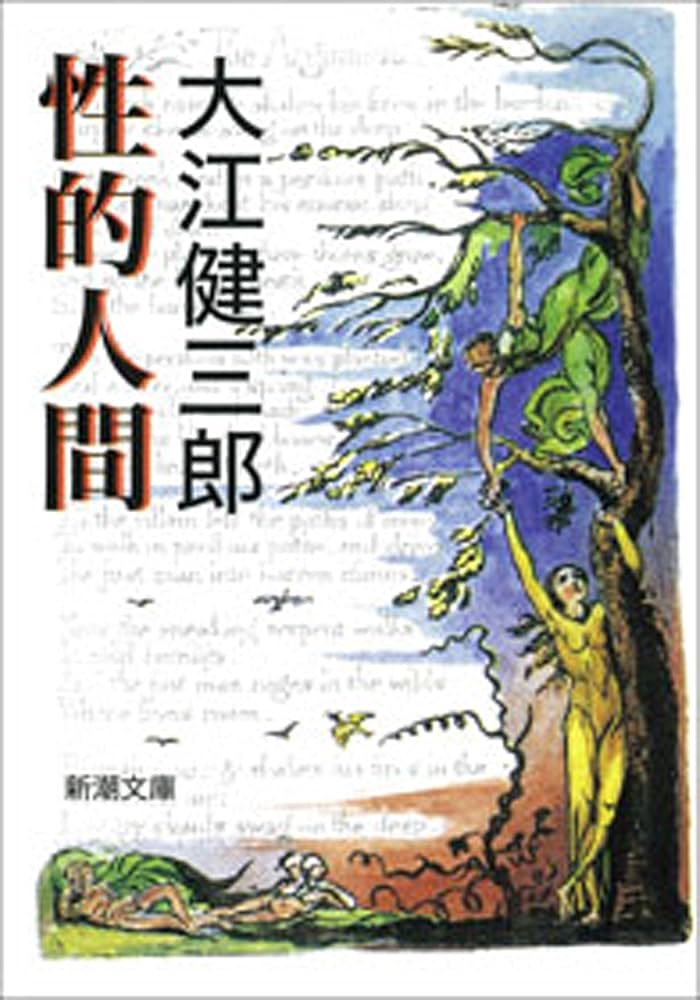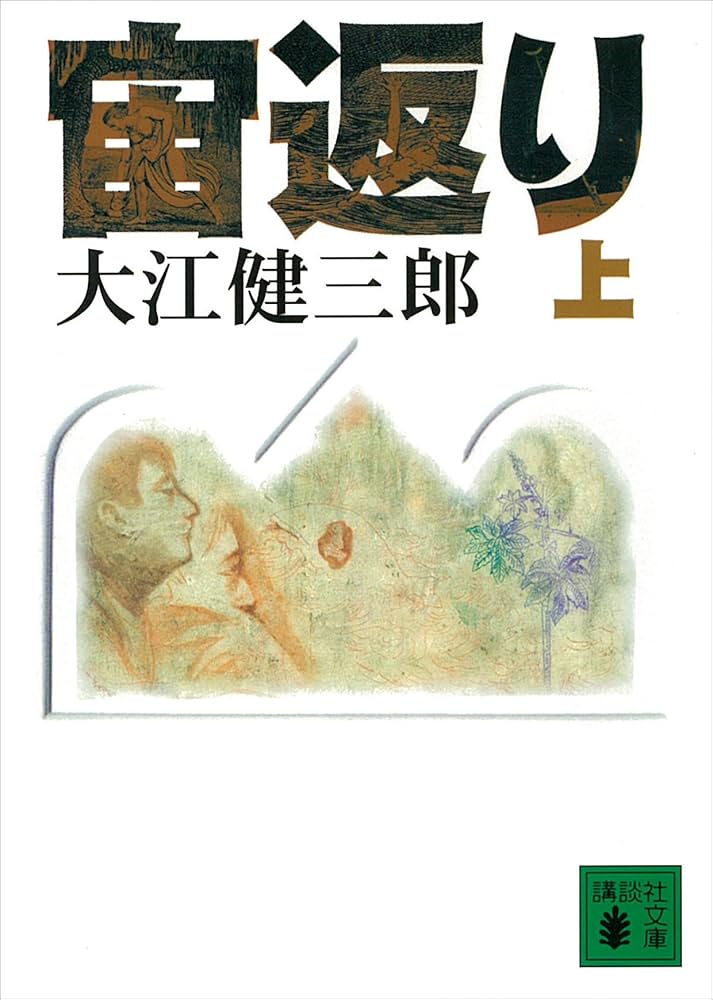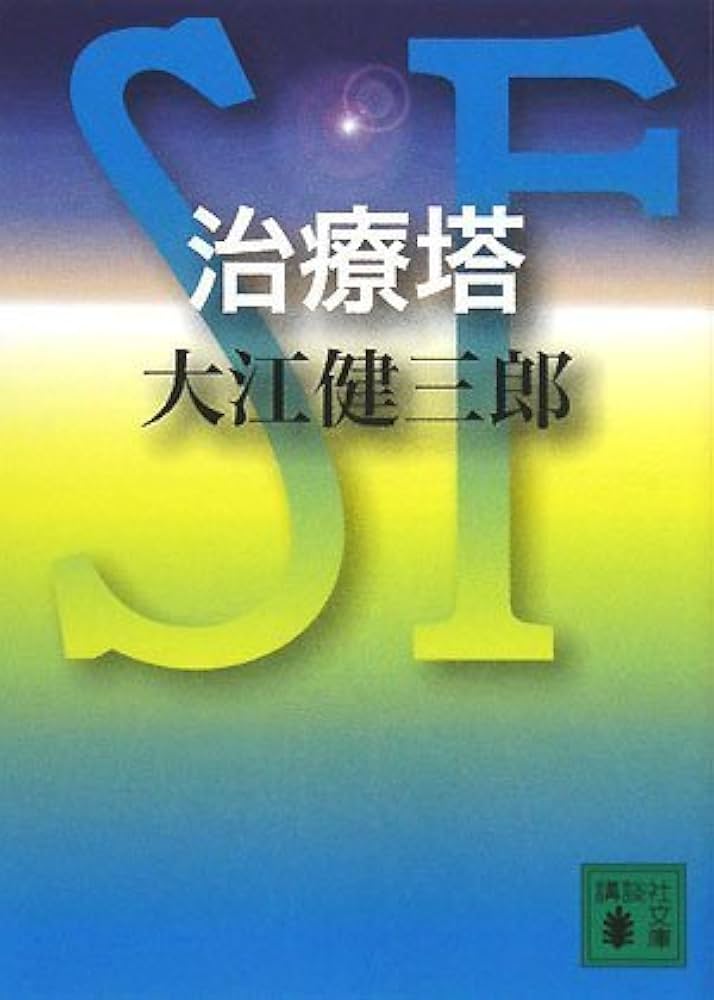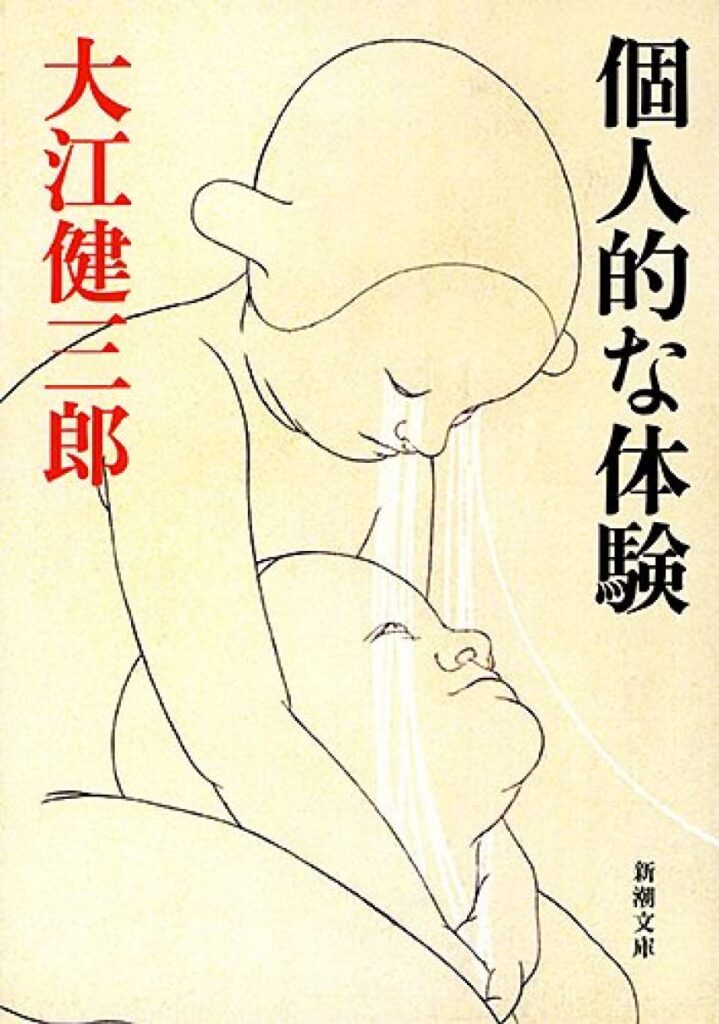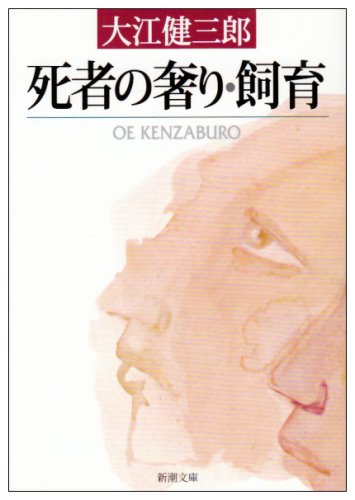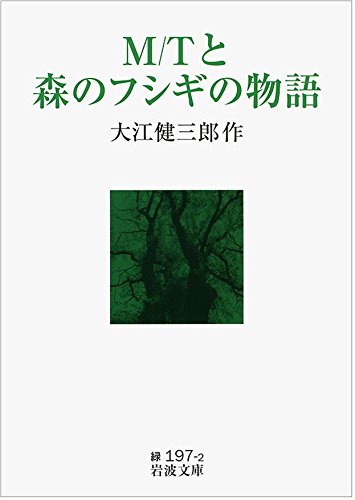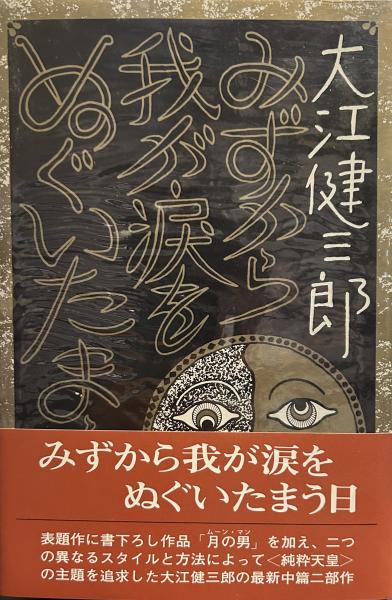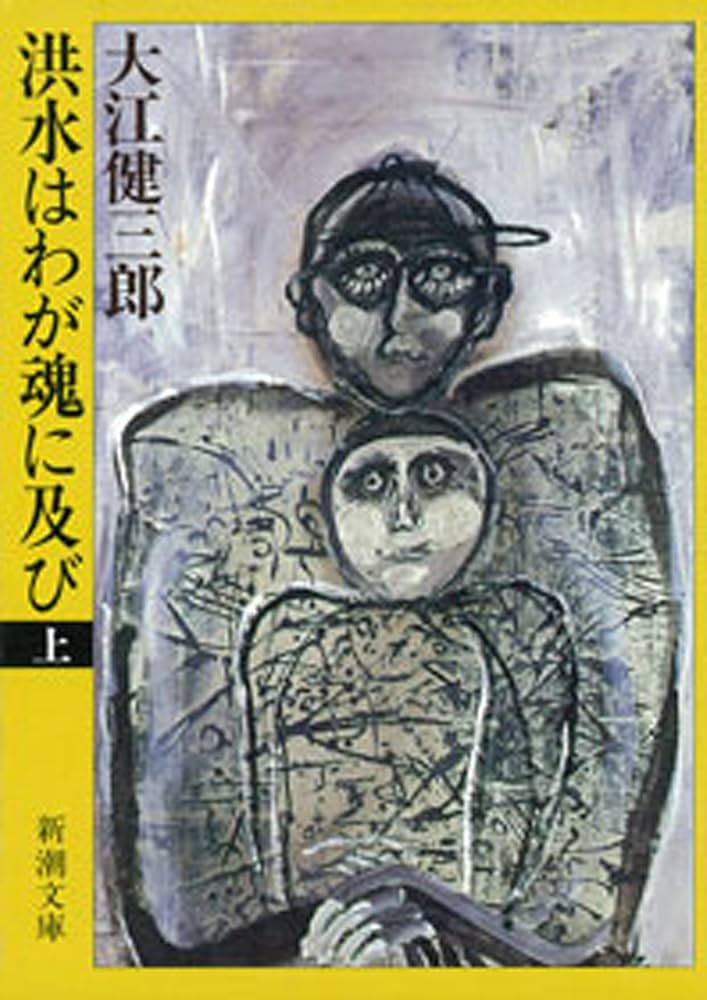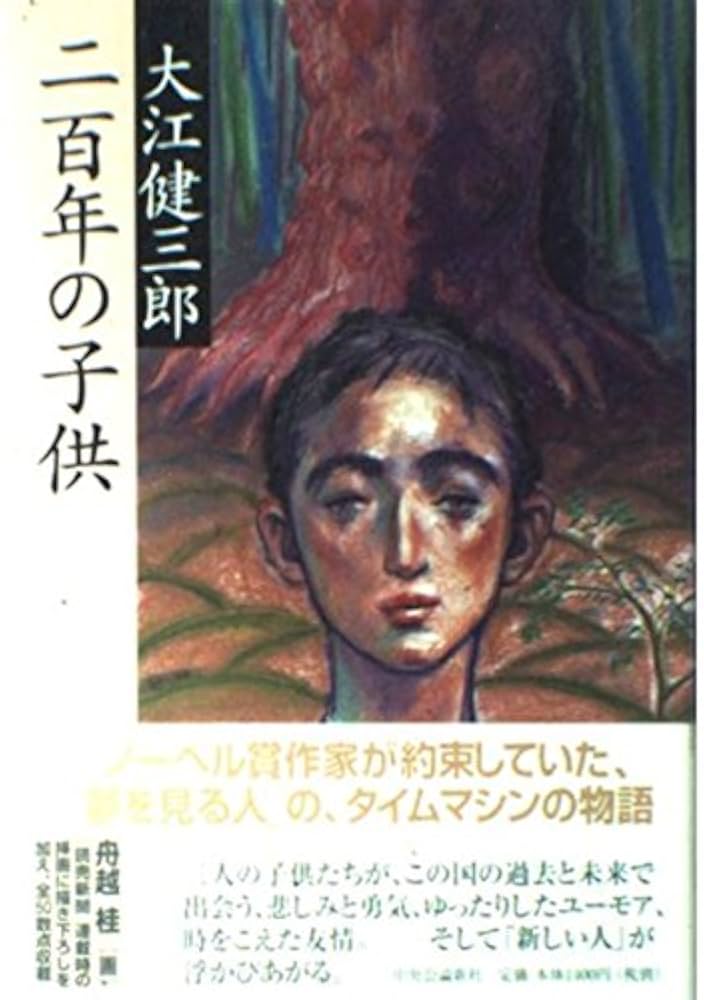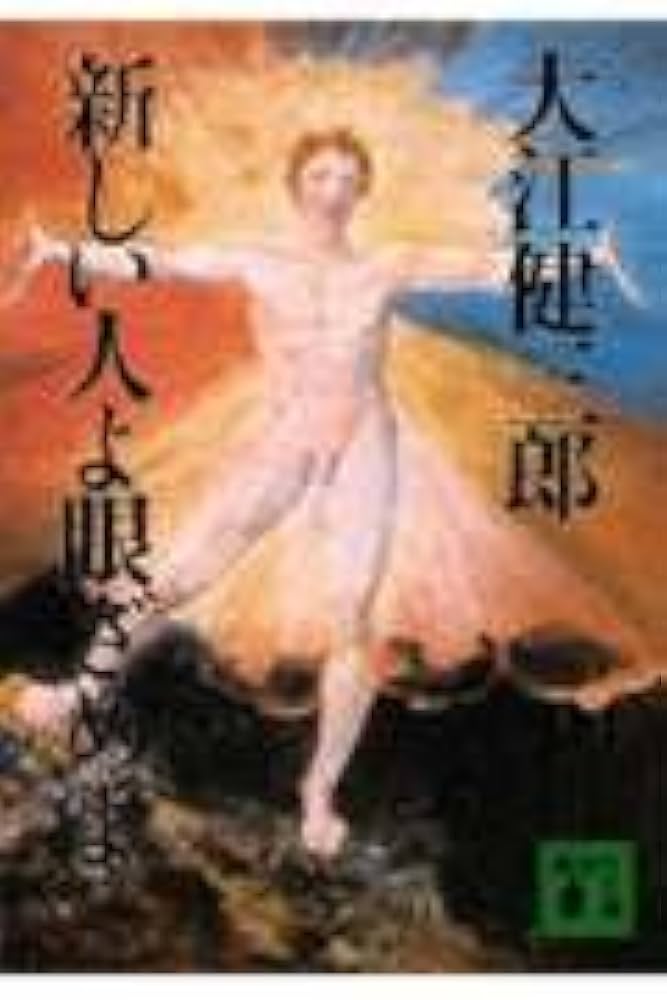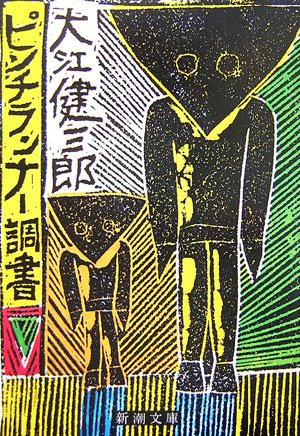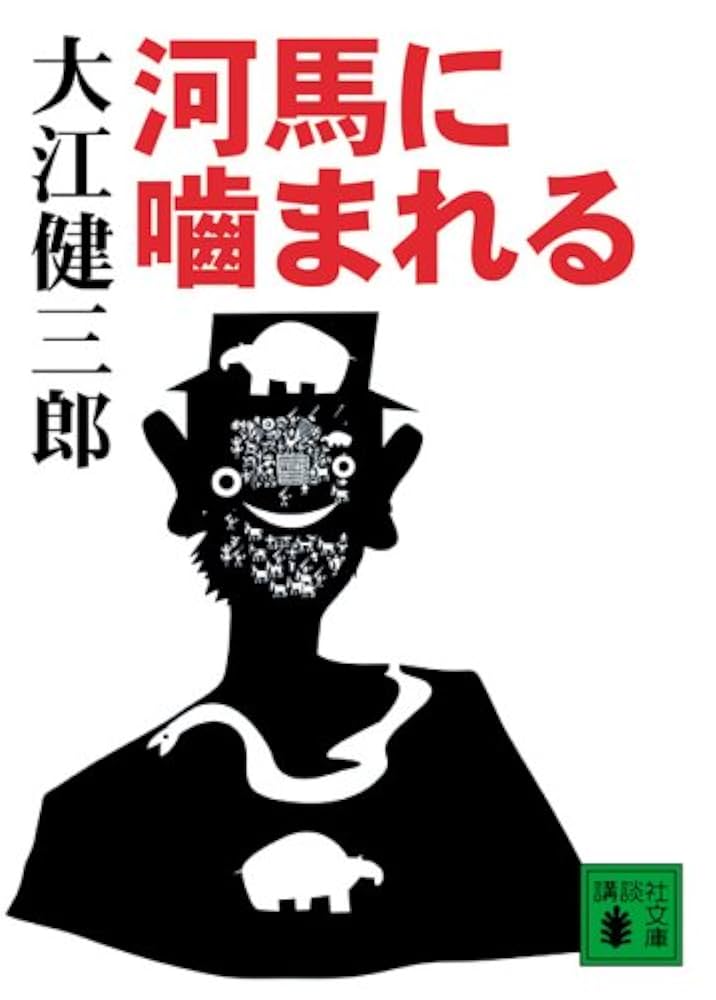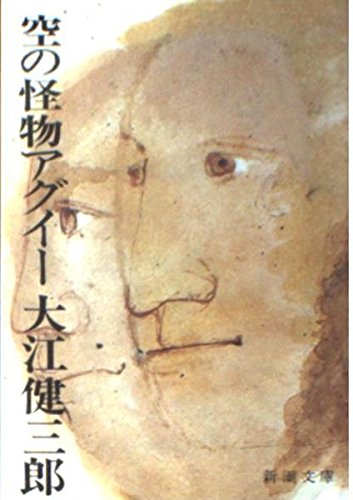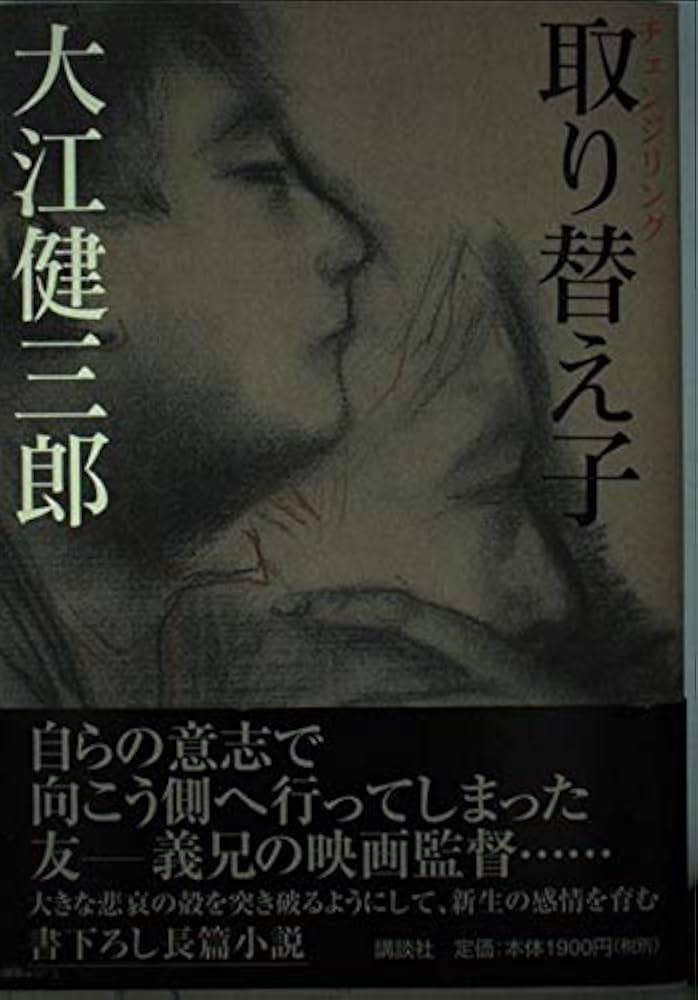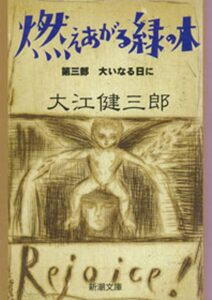 小説「燃えあがる緑の木」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「燃えあがる緑の木」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
この物語は、大江健三郎さんが四国の森深い谷間の村を舞台に、魂の救済という根源的な問いを壮大なスケールで描ききった傑作です。 一人の青年が「救い主」として見出され、人々が集い、やがて共同体が形成されていく。その過程は、希望と同時に危うさをも内包しています。
物語の中心には「ギー兄さん」と呼ばれる青年と、語り手である両性具有のサッチャンがいます。 彼らの眼差しを通して、信じることの純粋さ、組織が抱える矛盾、そして個人の魂がどこへ向かうのかが克明に記録されていきます。この記事では、まず物語の導入部分となるあらすじを追い、その後で物語の核心に触れるネタバレを含んだ深い感想へと分け入っていきます。
特に、なぜ共同体は「燃えあがる緑の木」と名付けられたのか、その名前に込められた意味は、物語を解き明かす上で非常に重要です。 片側は燃え上がり、もう片側は瑞々しく茂る木。 この二律背反のイメージは、作中のあらゆる人物や出来事に通底するテーマとなっています。
これから「燃えあがる緑の木」の世界を深く旅していきたいと思います。ネタバレを避けたい方はご注意いただきたいのですが、この物語が投げかける問いの深さに触れるためには、どうしても核心部分に言及せざるを得ません。この三部作が、なぜ今もなお多くの人々を惹きつけてやまないのか、その魅力に迫っていきましょう。
「燃えあがる緑の木」のあらすじ
四国の森深い谷間の村で、百年近く生きた長老の女性「オーバー」が亡くなる間際、一人の青年を指名します。 彼の名は隆。かつて学生運動に関わった過去を持ち、今は「魂のこと」をしたいと故郷に戻っていました。 オーバーは隆を、村の伝説的な人物の名である「新しいギー兄さん」と呼び、その魂を受け継ぐ者としたのです。
ギー兄さんと呼ばれるようになった隆は、村の伝承を蘇らせ、人々を癒す不思議な力によって、次第に「救い主」として崇められるようになります。 物語の語り手であるサッチャンは、もとは男性でしたが女性へと「転換」した両性具有の若者で、ギー兄さんの最も近しい理解者として、彼の一挙手一投足を記録していきます。
しかし、ギー兄さんの力は一部の村人から反感を買い、偽物だと糾弾されるようになります。 特に、重い病を患う少年との関わりが、対立を決定的なものにしてしまいました。 ギー兄さんへの反感は暴力へと発展し、彼は村人たちから激しい暴行を受けてしまいます。この受難を乗り越えるため、サッチャンはギー兄さんのための「教会」を建てることを決意するのでした。
こうして生まれた共同体は、アイルランドの詩人イェーツの詩から「燃えあがる緑の木」と名付けられます。 新たな信者を迎え、組織は拡大していきますが、そこには特定の神は存在しません。 信者たちは礼拝堂での「集中」と呼ばれる瞑想を通じて、それぞれの魂の救いを模索します。 しかし、共同体が大きくなるにつれて、内部には不穏な空気が漂い始め、ギー兄さん自身も迷いを見せ始めるのです。
「燃えあがる緑の木」の長文感想(ネタバレあり)
「燃えあがる緑の木」は、単なる新興宗教の盛衰を描いた物語ではありません。これは、神不在の時代に「魂の救済」は可能なのか、という大江健三郎さんが突き詰めてきた問いそのものを、小説という形で結晶化させた作品だと感じます。
物語の語り手は、男性から女性へ「転換」したサッチャンという、極めて象徴的な人物です。 彼女の存在そのものが、イェーツの詩に由来する「燃えあがる緑の木」という、二律背反を抱えながら一つであるという共同体の理念を体現しています。 サッチャンの眼差しは、ギー兄さんを絶対的な「救い主」として神格化するのではなく、彼の弱さや迷いをも含めて捉えようとします。
ギー兄さんが示す「救い」は、既存の宗教とは全く異なります。彼は奇跡を起こす超人ではありません。むしろ、小児癌を患うカジ少年に対し、死後の永遠を約束するのではなく、「一瞬よりはいくらか長く続く間の眺めに集中する」ことを優しく説きます。 これは、絶対的な救いではなく、今ここにある生を肯定し、その瞬間瞬間に魂を研ぎ澄ませることの重要性を示唆しています。
しかし、人々が求めるのは、しばしば分かりやすい奇跡や絶対的な教義です。ギー兄さんの教えはあまりに繊細で、彼の共同体「燃えあがる緑の木」は、神という絶対的な中心を持たないがゆえに、常に揺れ動きます。ネタバレになりますが、この共同体の不安定さこそが、物語の悲劇的な結末へと繋がっていきます。
共同体が拡大するにつれて、内部には対立が生まれます。実践的な農場派と、布教を目指す巡礼団。その亀裂は修復不可能なほどに深まり、ギー兄さんの理想は組織の論理に飲み込まれそうになります。彼の言葉が信者たちに届かなくなったと感じた時、サッチャンは深く失望し、一度は共同体を離れます。
ここからのサッチャンの遍歴も、この物語の重要な部分を占めています。彼女はK伯父さん(作者自身を思わせる人物)のもとでアウグスティヌスの『告白』を読み、自らの魂と向き合います。 この思索の期間を経て、彼女は再びギー兄さんのもとへ戻る決意をします。それは、かつてのような盲目的な信仰ではなく、ギー兄さんの苦悩を共有し、支えようとする、より成熟した意志でした。
村に戻ったサッチャンが目にしたのは、反対派の襲撃によって障害を負いながらも、以前より遥かに深い精神性を湛えたギー兄さんの姿でした。彼は、受難を経て真の「救い主」へと変貌を遂げたかのようでした。しかし、皮肉なことに、彼の精神的な深化とは裏腹に、共同体は崩壊の瀬戸際に立たされていました。
この物語のクライマックスと、核心的なネタバレについて触れます。ギー兄さんは、巨大化し分裂した共同体を前に、自らが組織から離れることを選びます。彼はもはや組織の指導者ではなく、ただ「魂のこと」だけを求める一個人に還ろうとしたのです。 しかし、彼を憎む者たちはそれを許しませんでした。
ギー兄さんは、最後の説教を終えた夜、反対派によって殺害されてしまいます。これは、イエス・キリストの受難を彷彿とさせる、衝撃的な結末です。彼の死によって、「燃えあがる緑の木」という共同体は指導者を失い、事実上、瓦解します。
では、この物語は絶望で終わるのでしょうか。私はそうは思いません。ギー兄さんという中心を失った後、残されたサッチャンたちが再び静かに行進を始めるラストシーンに、かすかな、しかし確かな希望が示されているからです。
彼らの歩みには、もはや明確な目的地も、絶対的な教義もありません。ただ、それぞれの魂の救済を求めて歩き続けるのです。それは、一人のカリスマに依存するのではなく、個々人が自らの力で「魂のこと」と向き合っていく、新しい始まりを予感させます。
「燃えあがる緑の木」というタイトルが象徴するように、破壊(燃えあがること)と再生(緑の茂り)は常に一体です。ギー兄さんの肉体は滅びましたが、彼の求めた精神は、残された人々の心の中で生き続けるのではないでしょうか。
この物語は、信じることの危うさと尊さの両面を描ききっています。組織は人を救うこともあれば、その本質を歪めてしまうこともある。ギー兄さんは、その矛盾の中で引き裂かれた悲劇の人物でした。
彼の死は、決して無駄ではなかったはずです。彼が身をもって示したのは、救いは誰かから与えられるものではなく、自らの内側から見出すしかない、ということだったのかもしれません。ネタバレを承知で言えば、彼の死こそが、信者たちを本当の意味で自立させたのです。
サッチャンの視点を通して描かれることで、「燃えあがる緑の木」は、壮大な神話でありながら、同時に非常に個人的な魂の記録ともなっています。彼女の成長と再生もまた、この物語の大きな柱です。
大江健三郎さんは、この作品で安易な答えを提示しません。ただ、神を失った現代において、私たちがどのようにして魂の渇きを癒し、生きていくべきなのかという問いを、読者に鋭く突きつけます。
読み終えた後、重い沈黙とともに、しかし不思議な静けさが心に残ります。「Rejoice!(喜びを抱け)」という、作中でサッチャンに与えられる言葉が、深く響いてくるのです。 悲劇の先にある希望。それこそが、「燃えあがる緑の木」という巨大な物語が私たちに伝えてくれる、最も大切なメッセージなのかもしれません。
まとめ:「燃えあがる緑の木」のあらすじ・ネタバレ・長文感想
この記事では、大江健三郎さんの長編小説「燃えあがる緑の木」について、あらすじから核心に触れるネタバレを含む感想までを綴ってきました。四国の森を舞台に、一人の青年ギー兄さんが「救い主」となり、共同体が生まれ、そして変質していく様が描かれます。
物語は、魂の救済という普遍的なテーマを扱いながら、そこに安易な答えを与えません。むしろ、信じることの難しさ、組織が内包する矛盾、そして個人の魂の行方を、語り手サッチャンの視点を通して深く掘り下げています。ネタバレになりますが、指導者ギー兄さんの悲劇的な死は、物語の終わりではなく、残された人々が自立するための通過儀礼として描かれています。
この壮大な三部作は、読む者に「救いとは何か」「信じるとは何か」を問いかけずにはおきません。ギー兄さんの受難とサッチャンの再生を通して、絶望の先にこそ見出される希望の形が示されています。
「燃えあがる緑の木」は、読み手の価値観を揺さぶる力を持った、まさに文学の到達点の一つと言える作品です。その問いかけは、時代を超えて私たちの心に深く響き続けることでしょう。