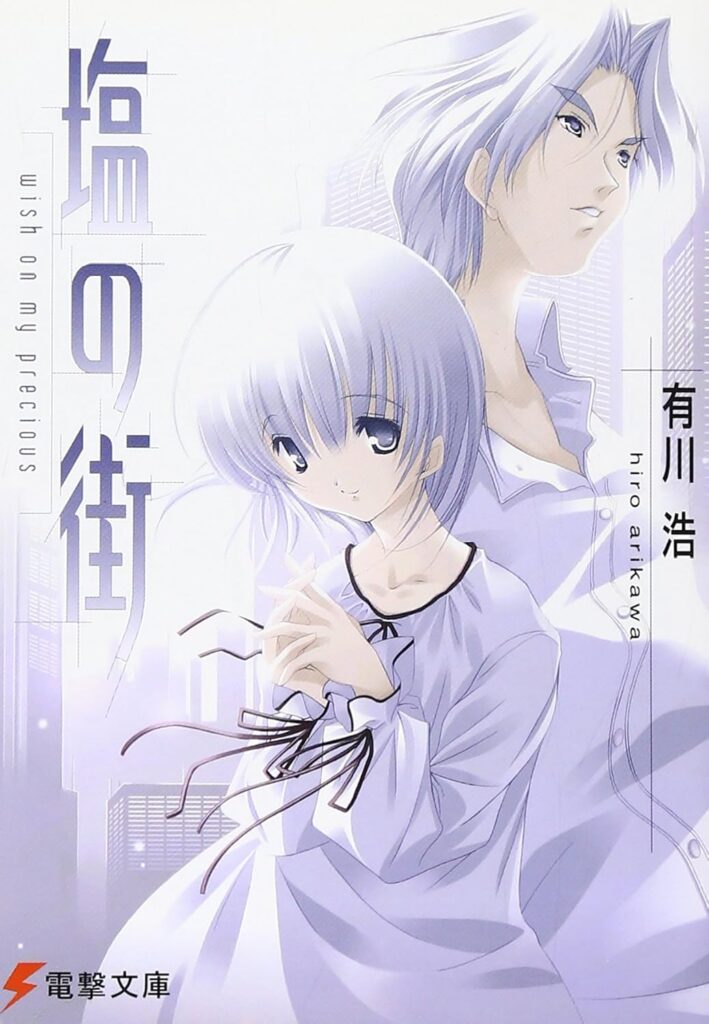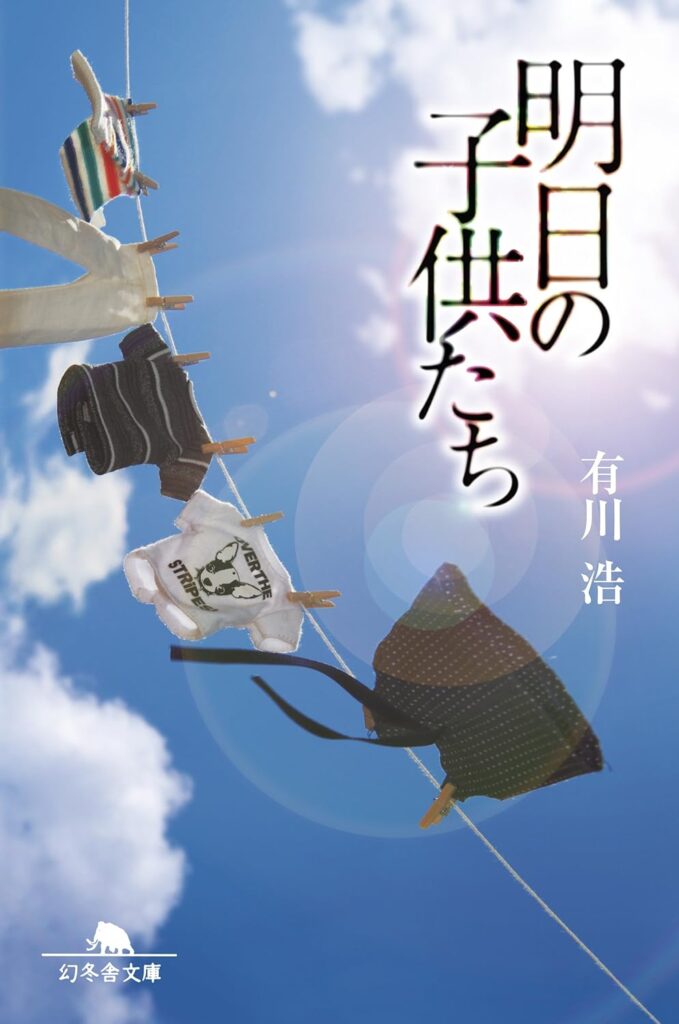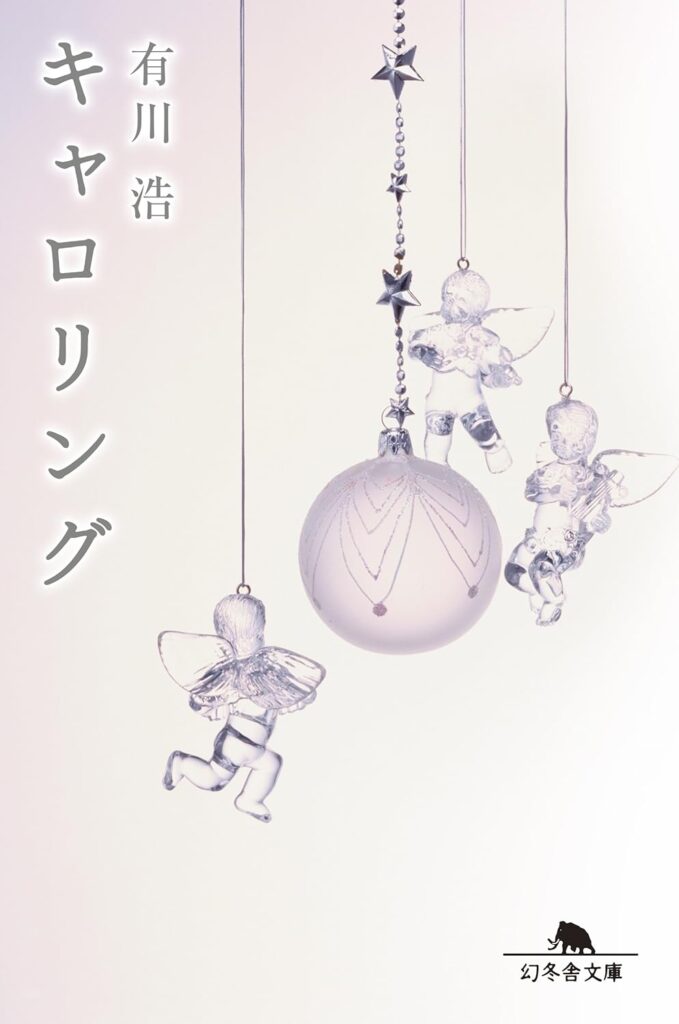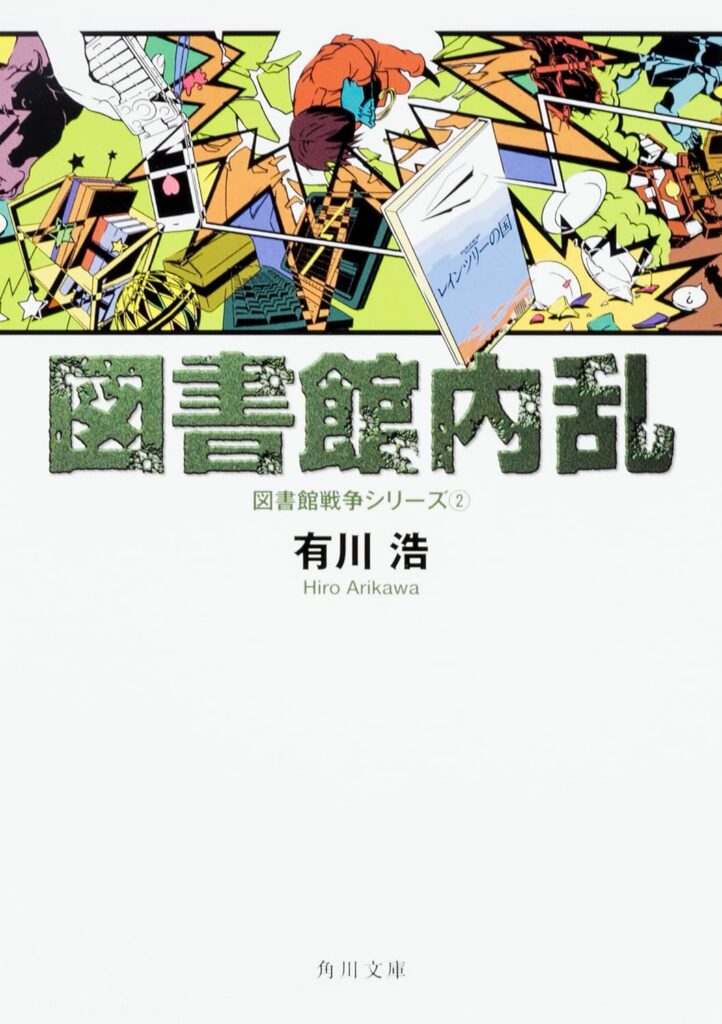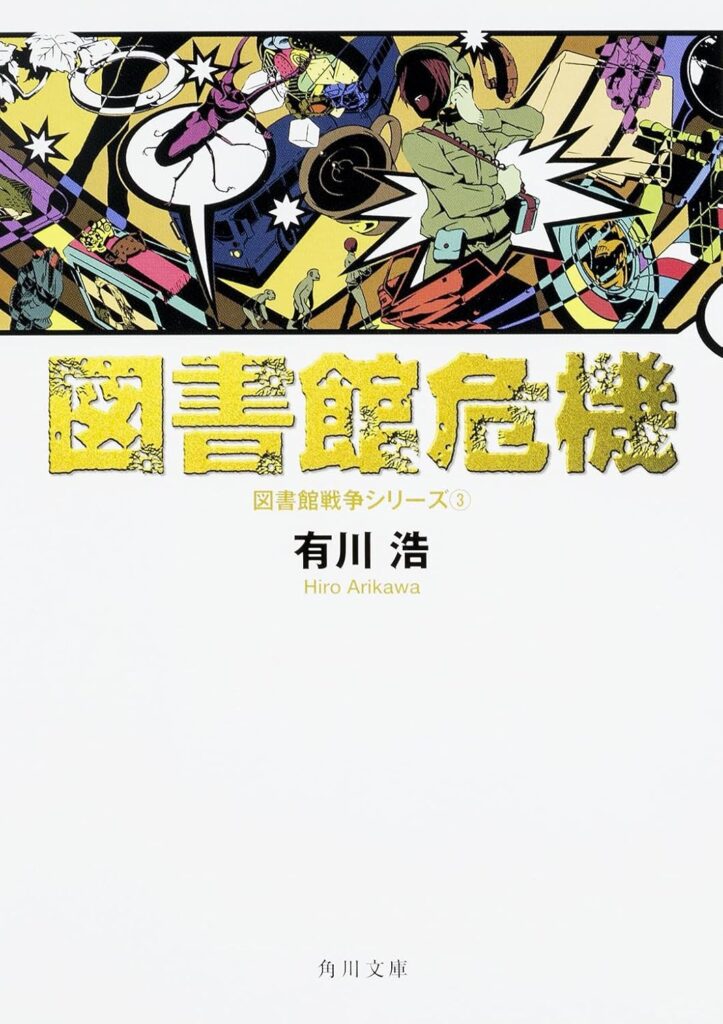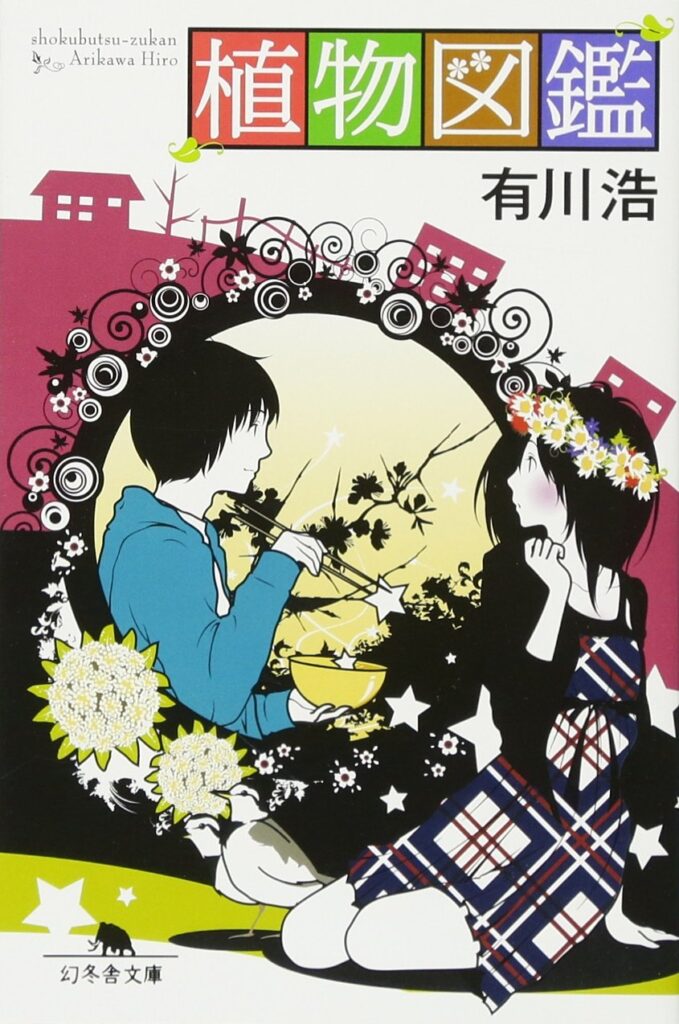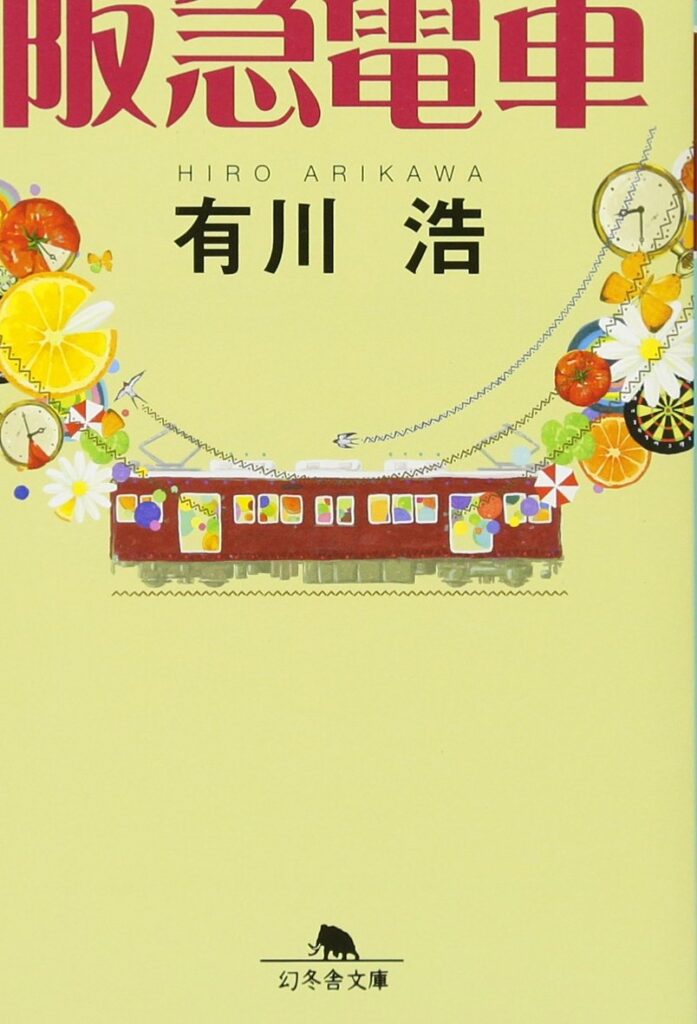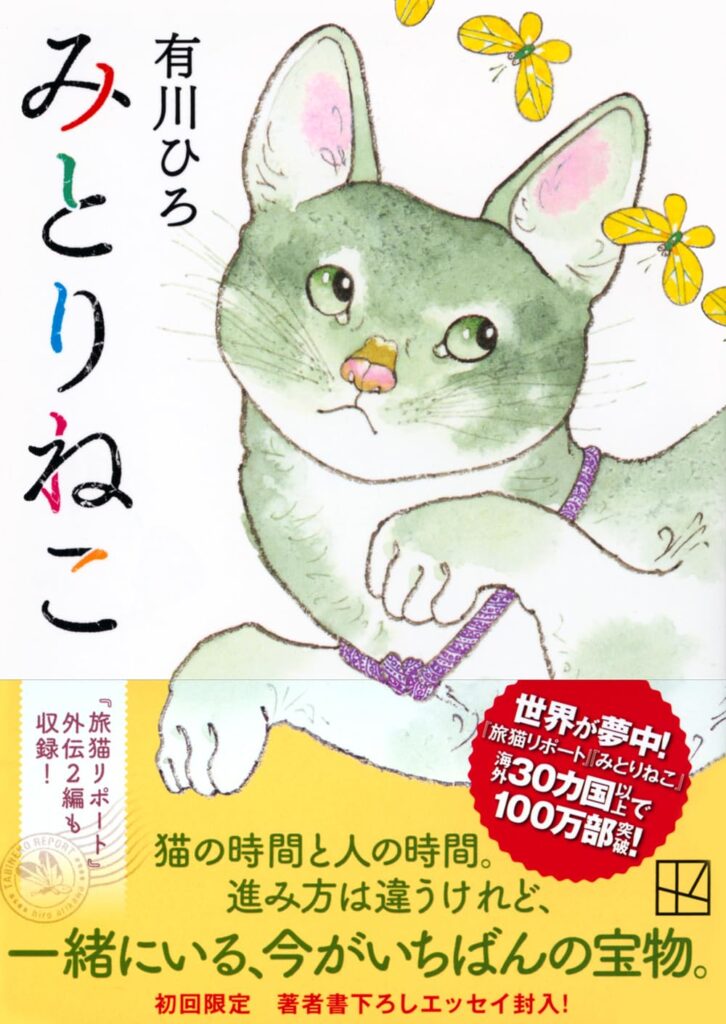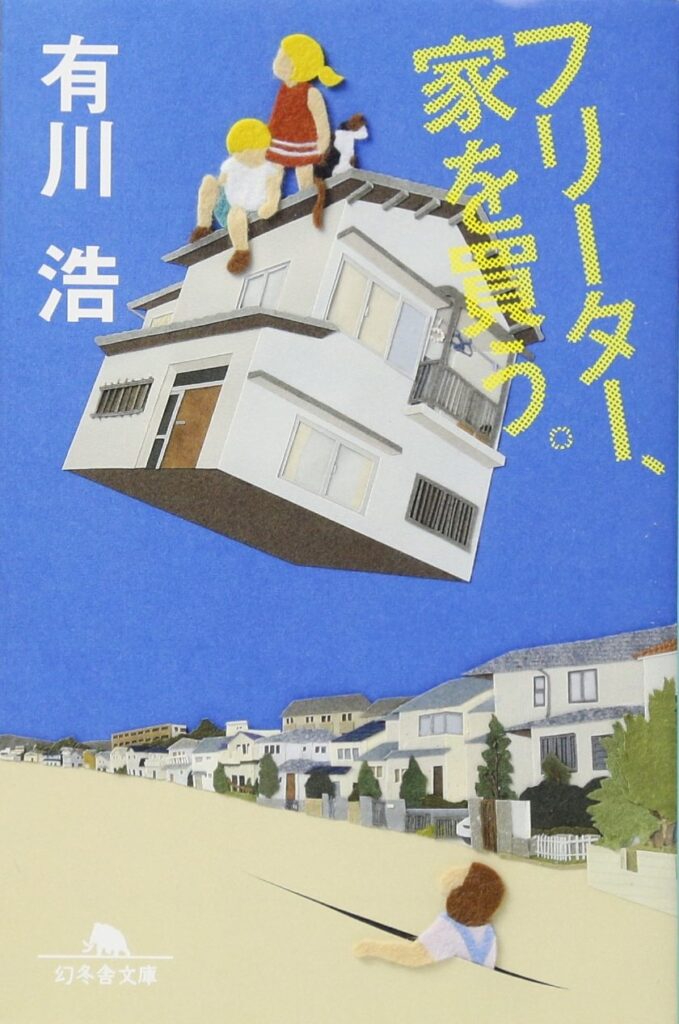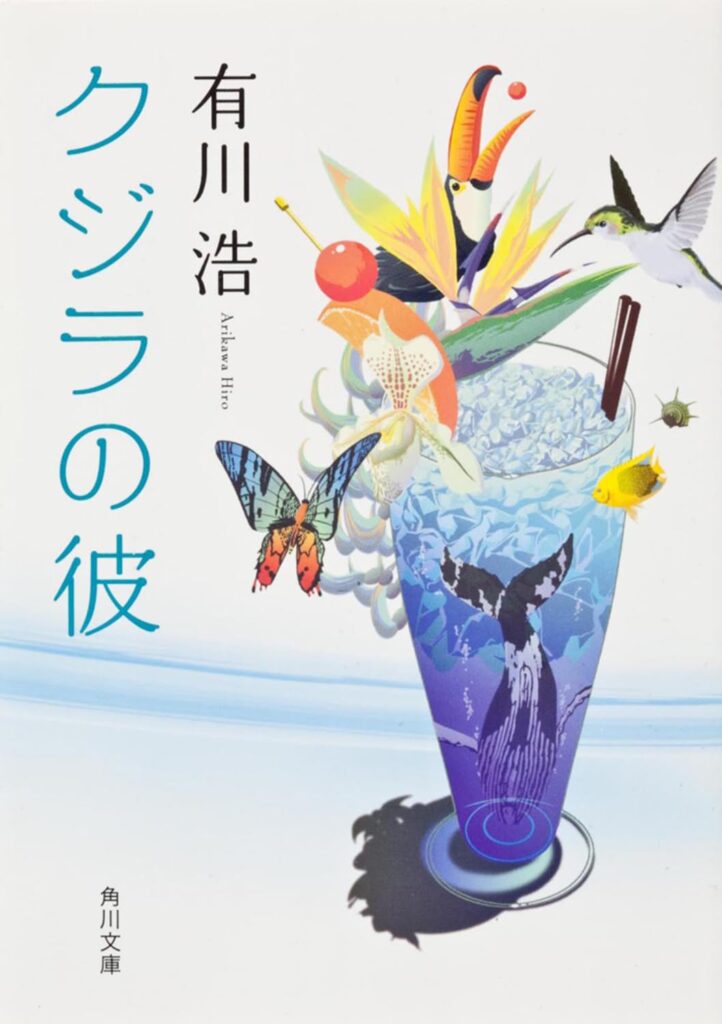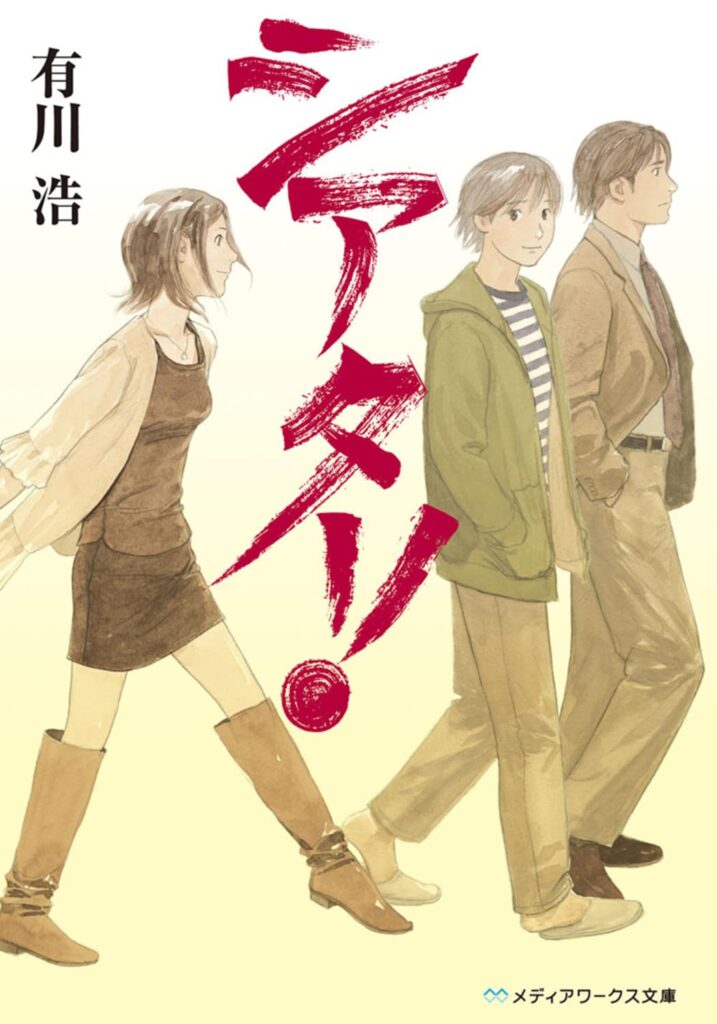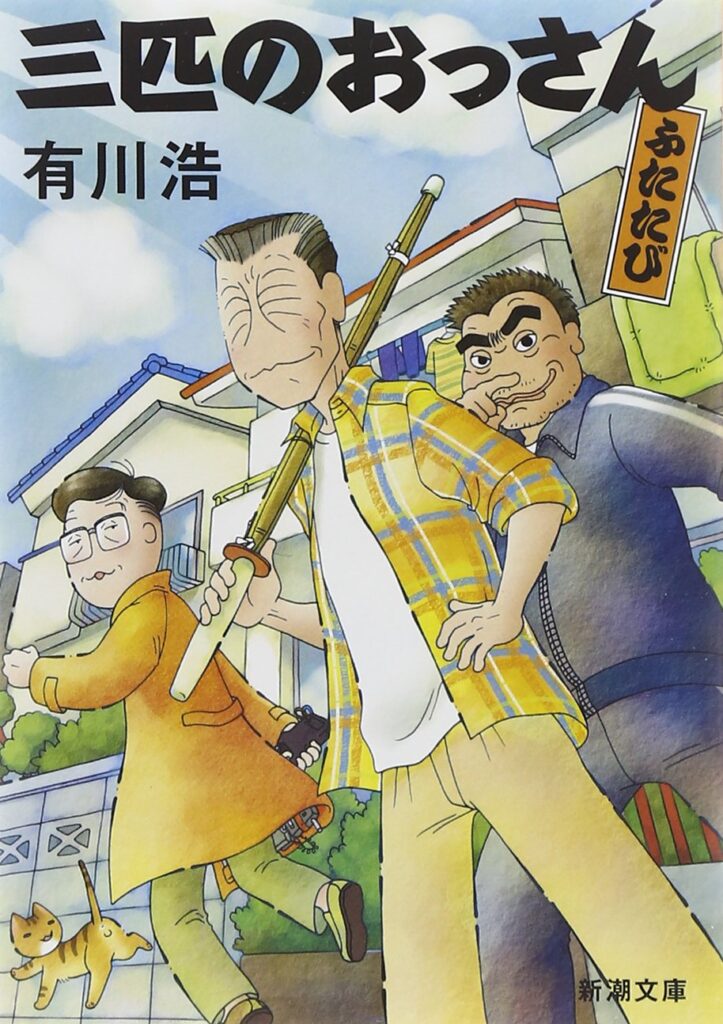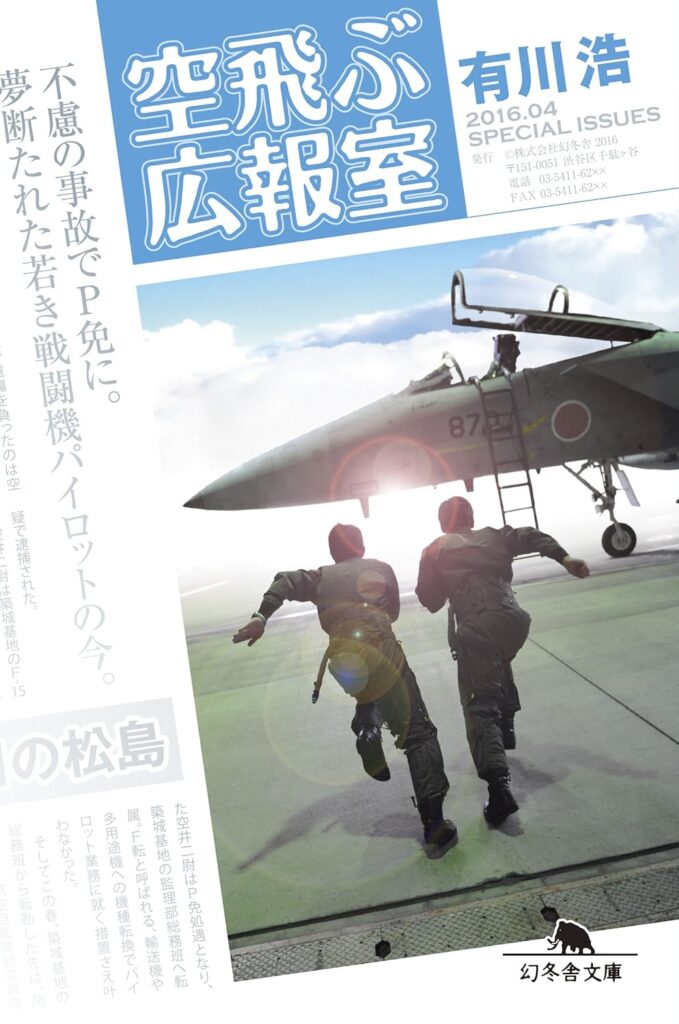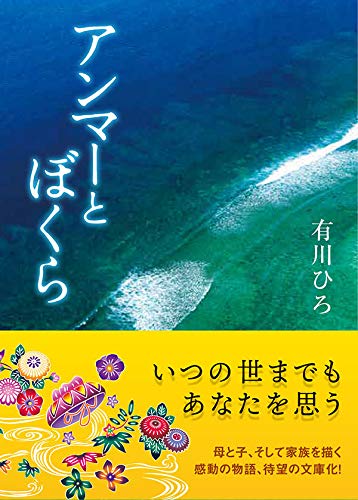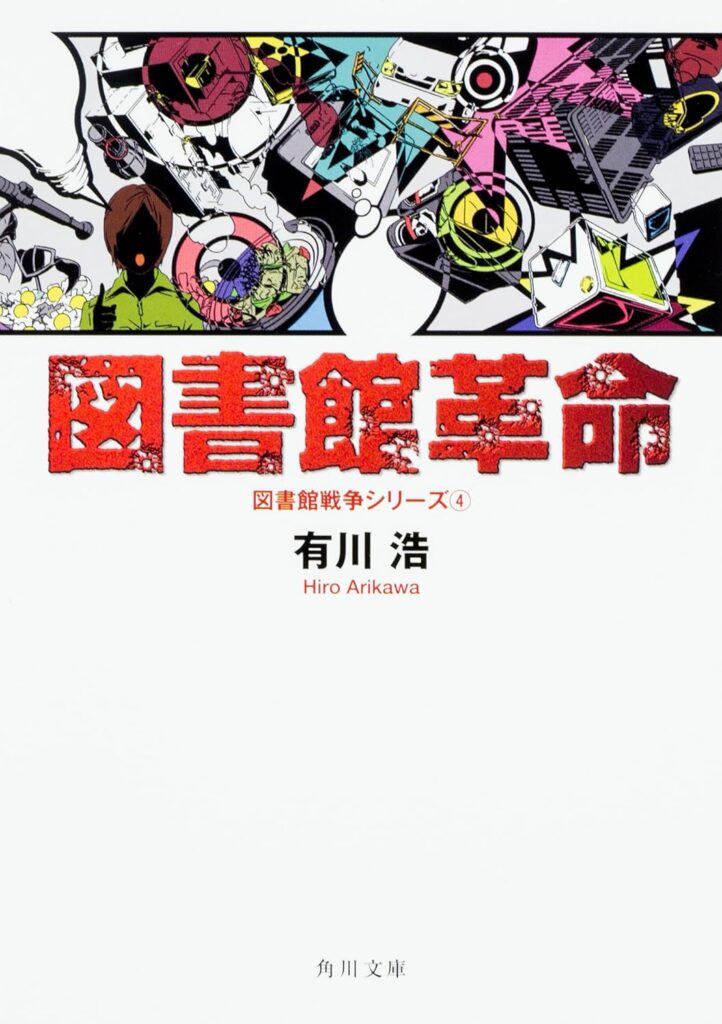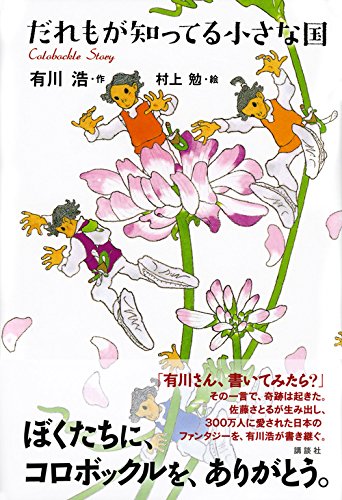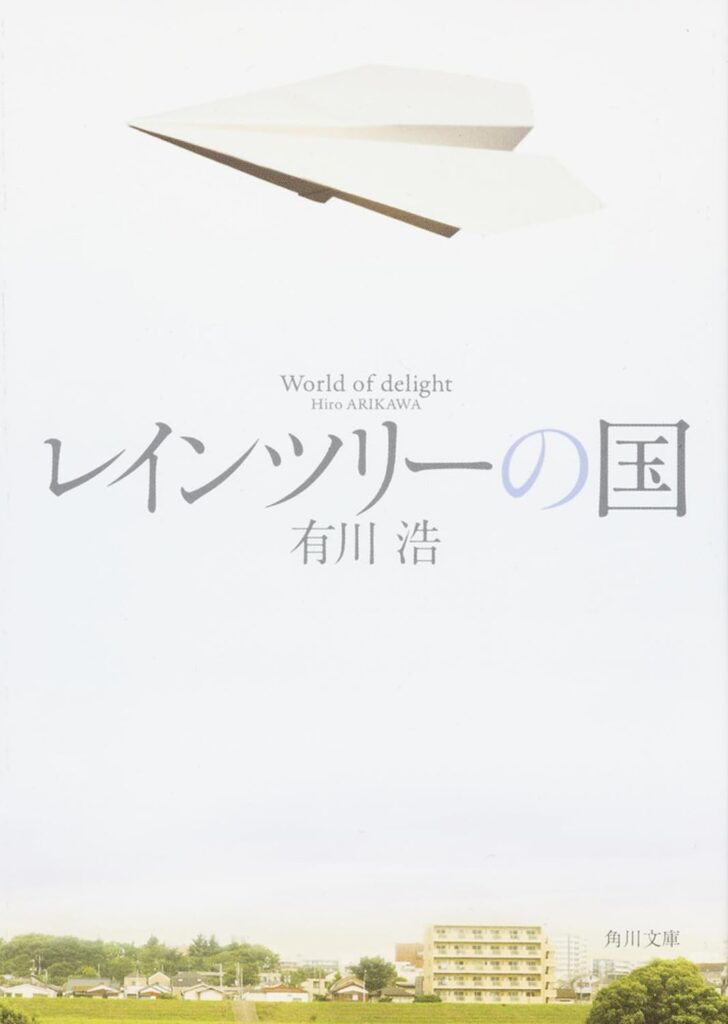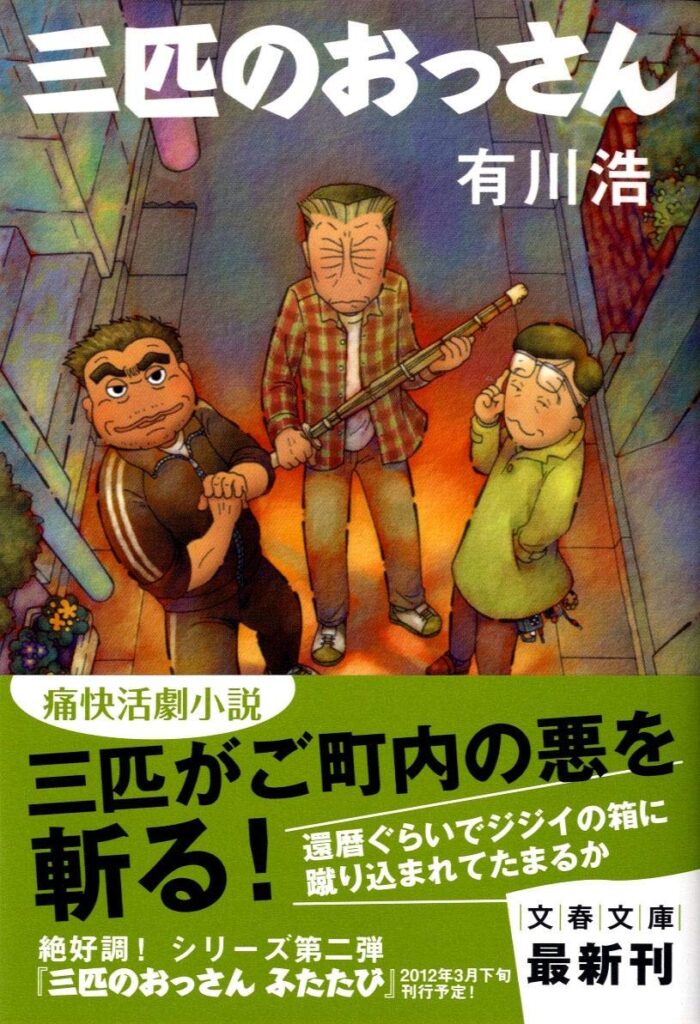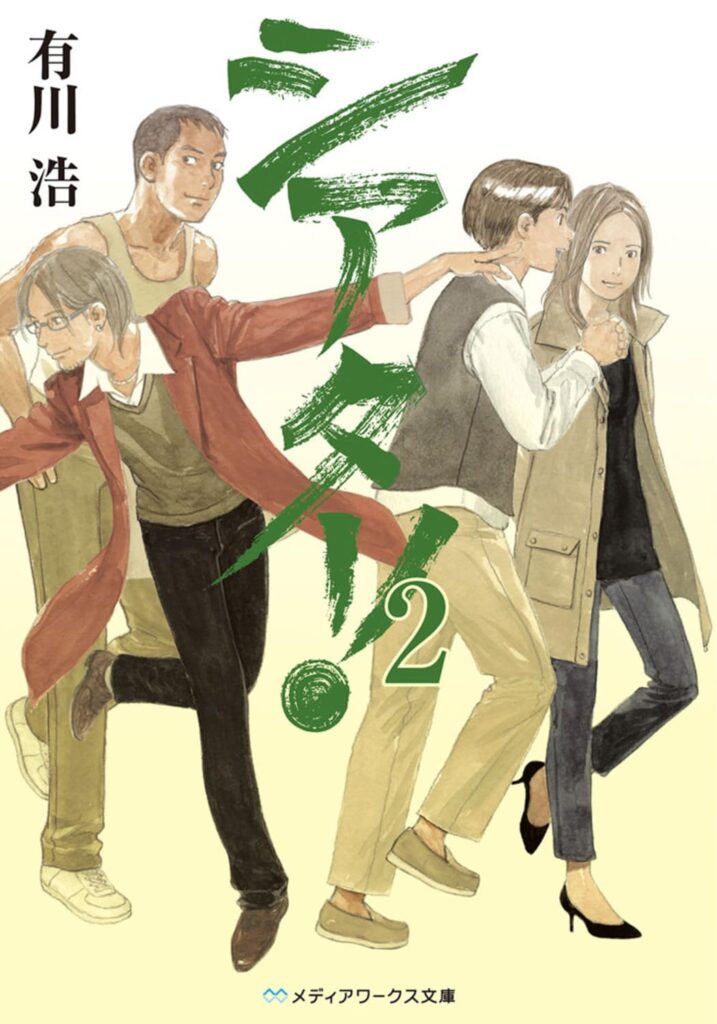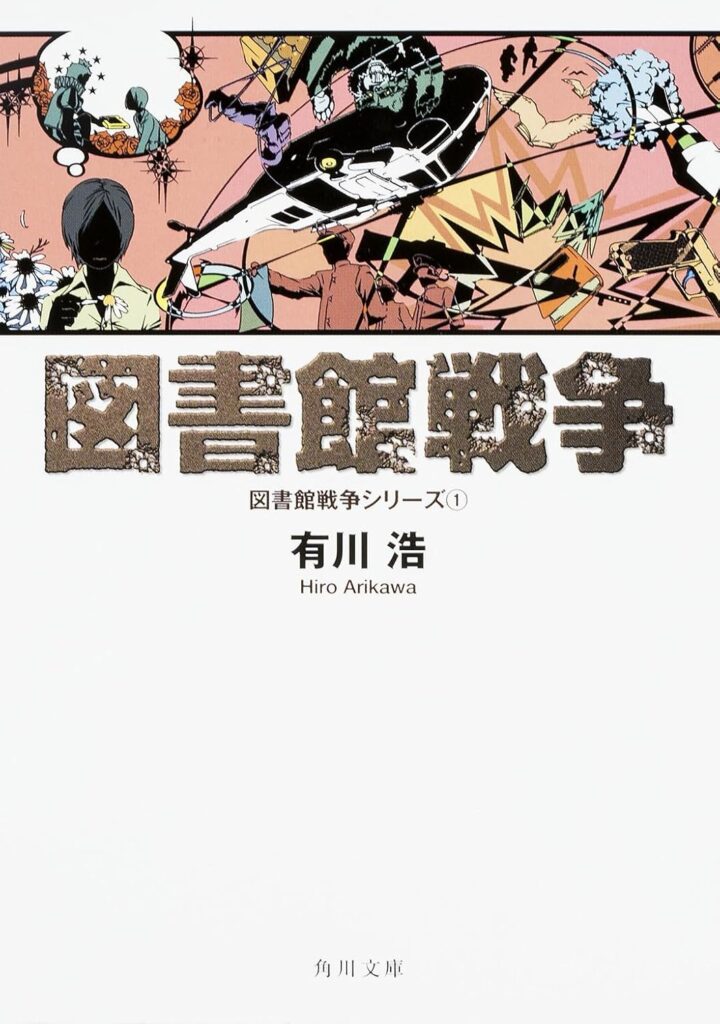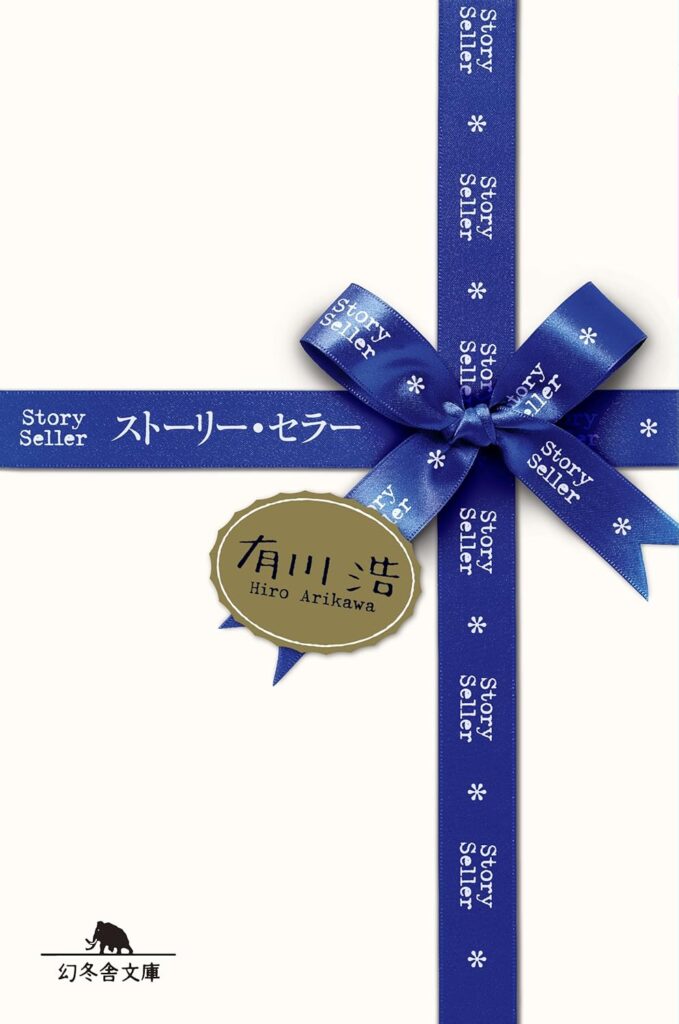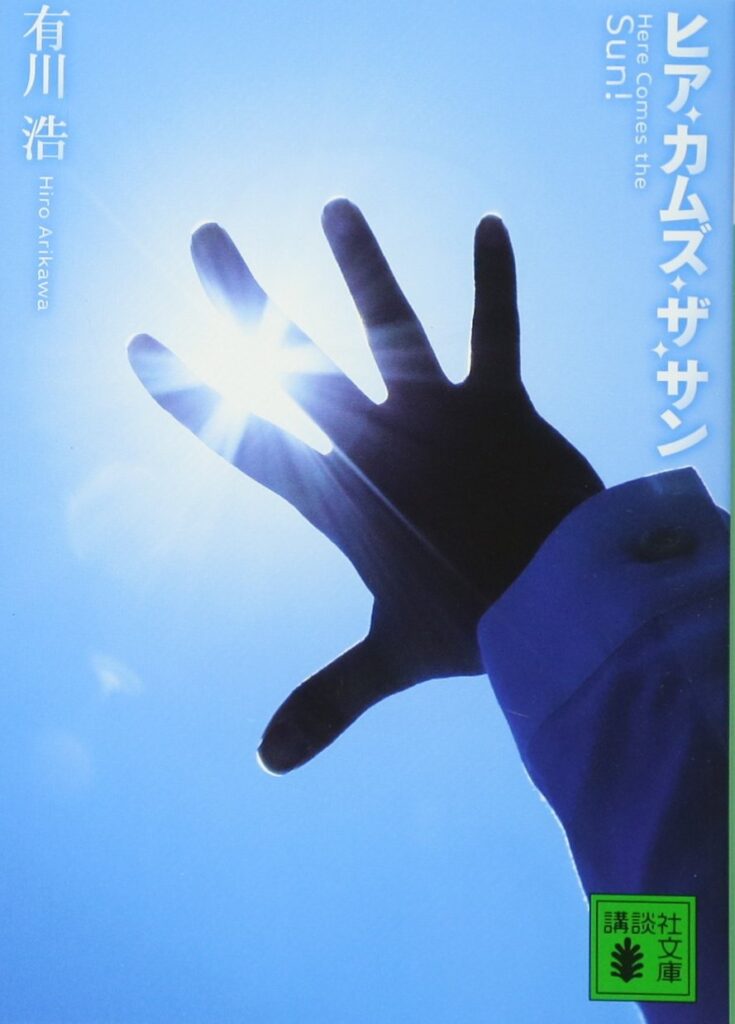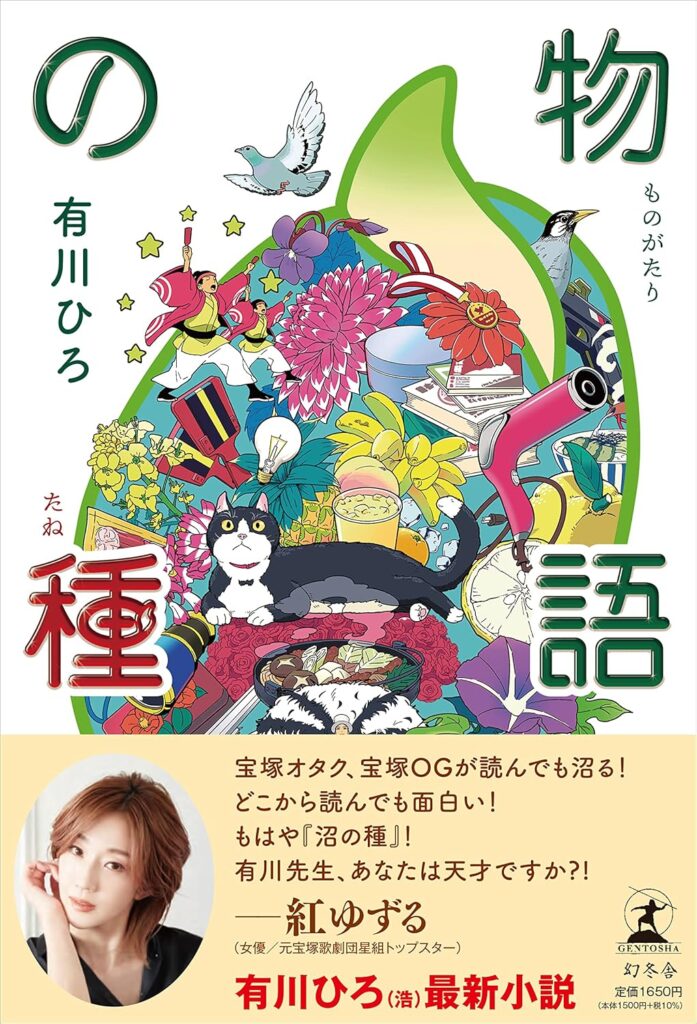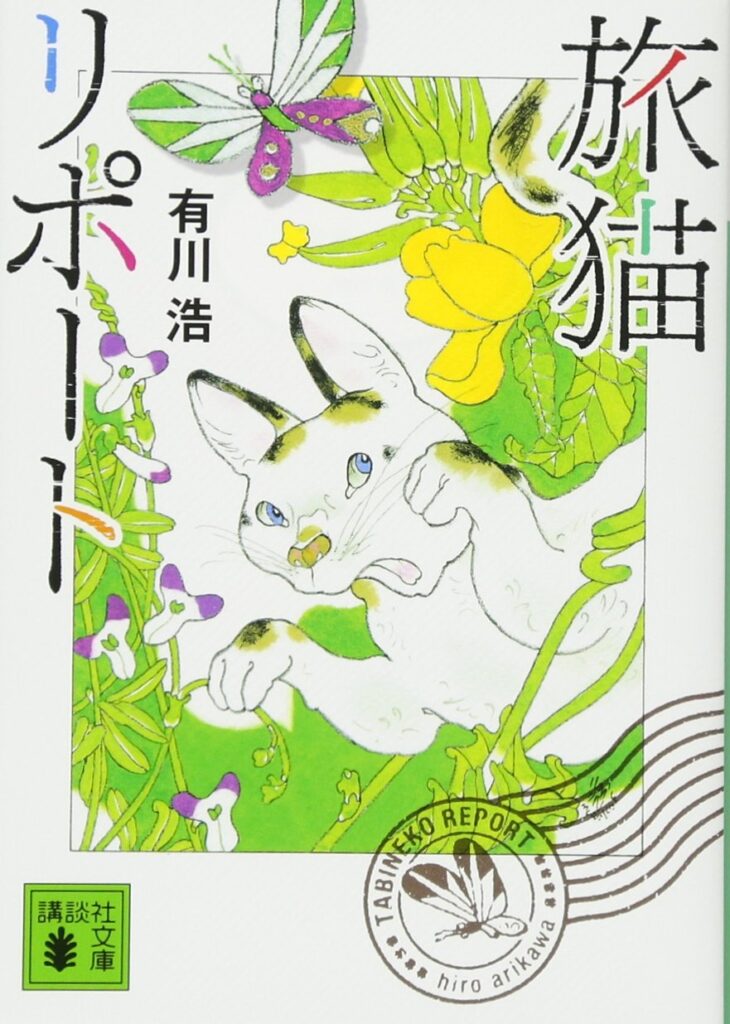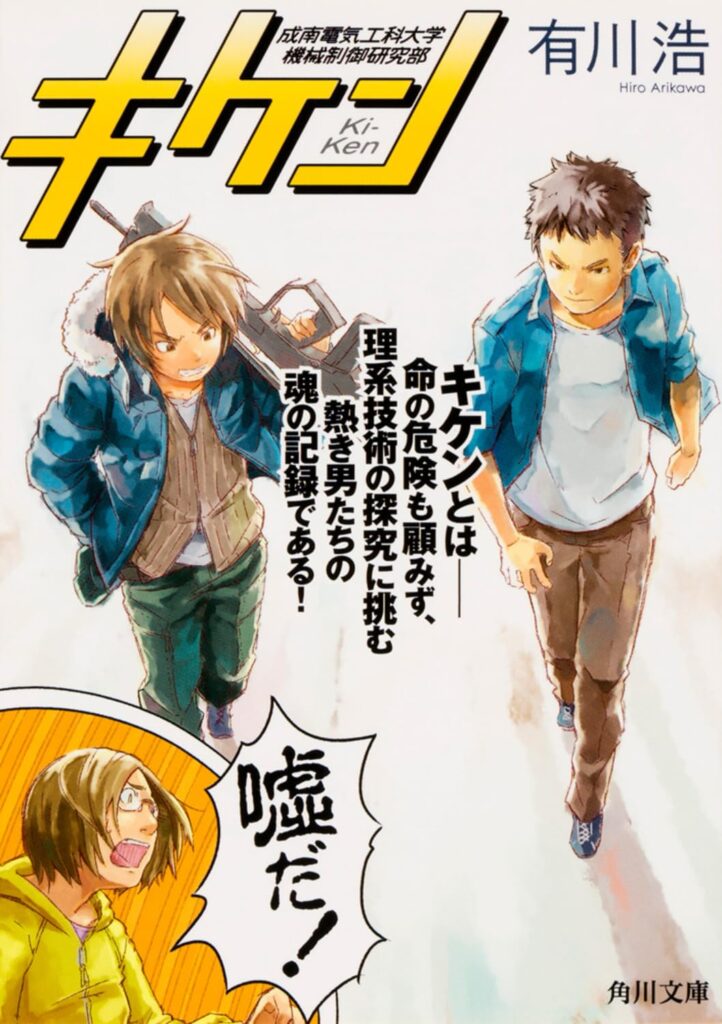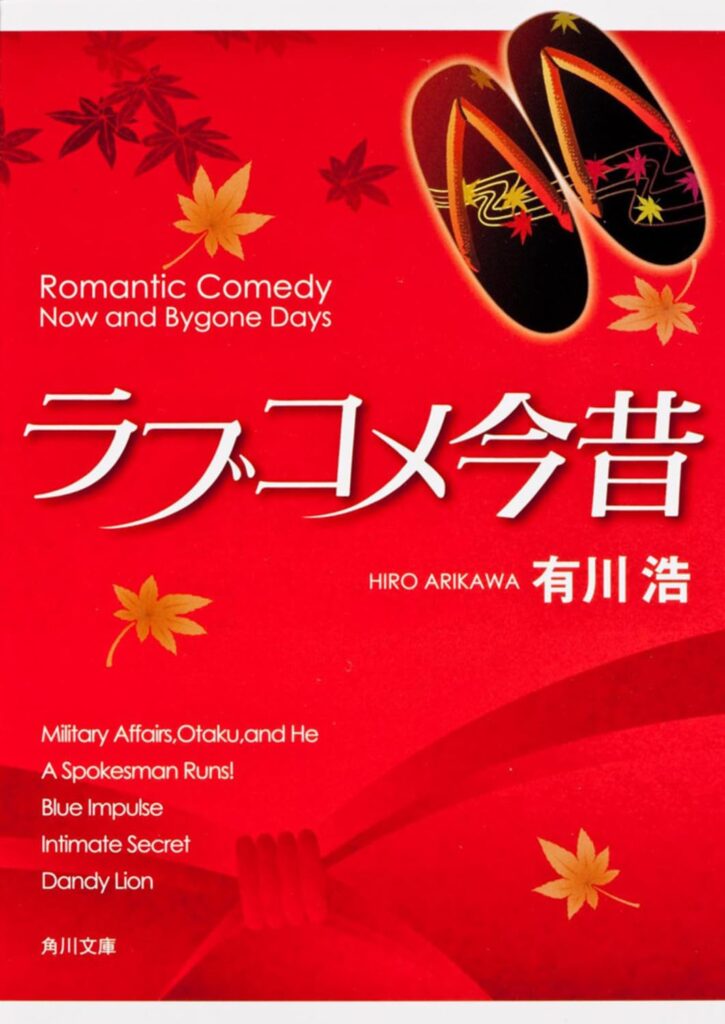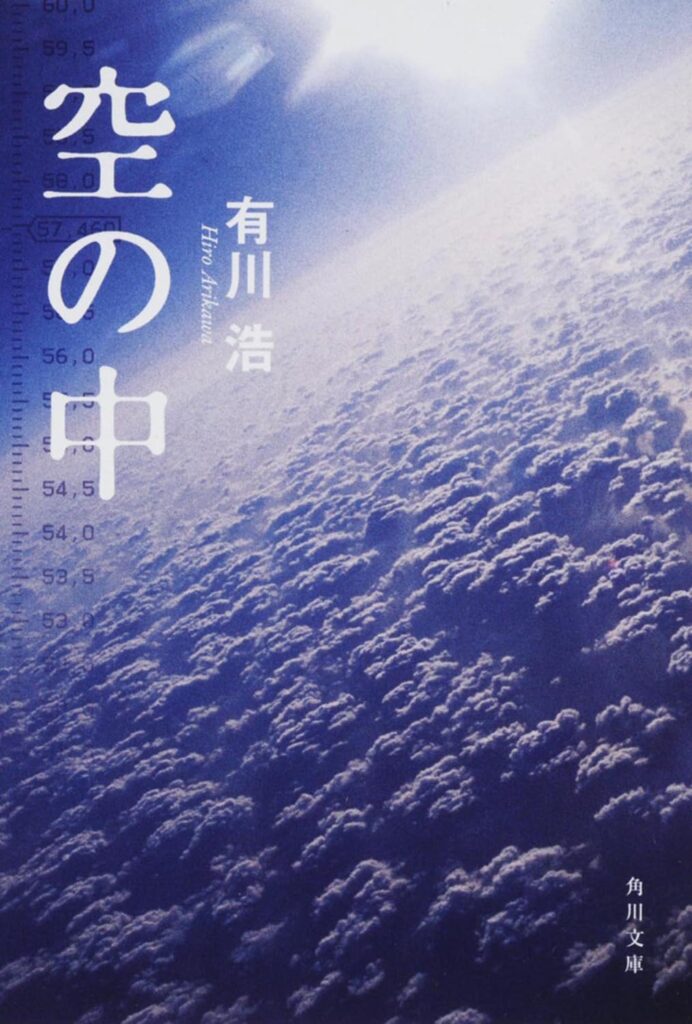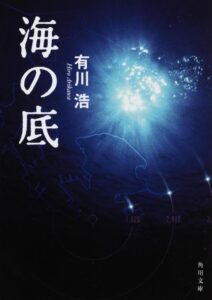 小説「海の底」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。有川浩さんの作品の中でも、特に緊迫感あふれる展開と深い人間ドラマが描かれている本作。巨大な未知の生物に襲われるというパニック要素だけでなく、極限状態に置かれた人々の心理や、自衛隊、警察といった組織の動きがリアルに描かれているのが特徴です。
小説「海の底」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。有川浩さんの作品の中でも、特に緊迫感あふれる展開と深い人間ドラマが描かれている本作。巨大な未知の生物に襲われるというパニック要素だけでなく、極限状態に置かれた人々の心理や、自衛隊、警察といった組織の動きがリアルに描かれているのが特徴です。
この記事では、物語の始まりから衝撃的な結末まで、その詳細な流れを追っていきます。また、登場人物たちの心情や関係性の変化、物語が問いかけるテーマについても、個人の感じたことを交えながら深く掘り下げていきます。特に、物語の核心に触れる部分や結末について詳しく記述していますので、まだ作品を読んでいない方はご注意ください。
有川浩さんの描く、手に汗握るサバイバルと、登場人物たちの心の機微を、この記事を通して少しでも感じていただければ幸いです。読み終えた後、きっとあなたもこの物語の持つ力強さに引き込まれることでしょう。それでは、物語の深部へとご案内します。
小説「海の底」のあらすじ
物語の舞台は、桜祭りで賑わう春の米軍横須賀基地。多くの一般市民が訪れる中、海上自衛隊の最新鋭潜水艦「きりしお」では、乗組員である実習幹部の夏木大和と冬原春臣が、艦内での騒動により上陸禁止となっていました。その平穏な光景は突如として一変します。基地内に、正体不明の巨大な赤い甲殻類、後に「サガミ・レガリス」と呼ばれる生物の大群が出現し、人々を次々と襲い始めたのです。
緊急の退去命令を受け、夏木と冬原は上司と共に基地外への避難を試みますが、その途中で逃げ遅れた子供たちの一団を発見します。子供たちを保護したものの、すでに陸路での脱出は不可能となっており、やむなく停泊中の「きりしお」艦内に立てこもることを決断します。間一髪で艦内に逃げ込みますが、子供たちを庇った上司はレガリスの犠牲となり、千切れた腕だけが残されるという悲劇に見舞われます。
潜水艦という閉鎖された空間で、夏木、冬原、そして保護された子供たちの不安な共同生活が始まります。子供たちは同じ町内会のメンバーで、高校生の森生望とその弟で話すことのできない翔、中学生の遠藤圭介などが含まれていました。しかし、当初から子供たちの間には歪んだ関係性が存在し、特に圭介は望に対して執拗な嫌がらせを繰り返します。食事の準備ひとつをとっても、経験のない夏木たちは苦労し、圭介の反発もあって艦内の空気は重く沈んでいきます。
一方、基地の外では警察が市民の避難誘導にあたっていましたが、レガリスに対抗する術がなく、被害は拡大するばかりでした。事態を収拾するため、警察庁から派遣された烏丸参事官は、現場の明石警部と共に、独自にレガリスの研究を進めていた相模水産研究所の芹澤研究員の報告書に着目。芹澤の協力により、襲来した甲殻類が深海生物サガミ・レガリスであることを特定します。しかし、レガリスは学習能力が高く、毒殺作戦も効果を上げられません。さらに米軍による横須賀爆撃計画も浮上し、事態は刻一刻と悪化していきます。自衛隊による早期の武力介入(防衛出動)が望まれる中、官邸の決断は遅れ、烏丸は状況を動かすため、あえて警察の「壊走」を指示するのでした。
小説「海の底」の長文感想(ネタバレあり)
有川浩さんの「海の底」は、読むたびに心が揺さぶられ、登場人物たちの葛藤や決断に深く考えさせられる作品です。巨大生物によるパニックという非日常的な設定の中に、驚くほど生々しい人間の感情や社会の縮図が描かれており、そのリアリティに圧倒されます。物語は、桜祭りで開放された米軍横須賀基地という、平和な日常の象徴のような場所から始まります。しかし、その日常は突如として、巨大なザリガニのような生物「サガミ・レガリス」の襲来によって破壊されます。この冒頭の描写から、読者は一気に緊迫した物語の世界へと引きずり込まれます。
この作品の大きな魅力の一つは、極限状態における人間ドラマの深さです。主人公である海上自衛隊の実習幹部、夏木大和と冬原春臣は、レガリスから逃れるため、偶然出会った子供たちと共に潜水艦「きりしお」に立てこもります。潜水艦という閉鎖された空間は、登場人物たちの心理状態を映し出す舞台装置としても機能しています。食料や水の制限、外部との途絶、そしてすぐ外には人を捕食する脅威が存在するという状況下で、彼らの関係性は複雑に変化していきます。
特に印象的なのは、子供たちの間に存在する歪んだ力関係です。リーダー格の圭介は、同じ町内会の年上の少女、望に対して、屈折した好意と憎しみが入り混じったような態度をとり続けます。彼の言動は、しばしば艦内の空気を険悪にし、夏木や冬原を悩ませます。圭介の行動原理には、彼の母親からの影響が色濃く反映されており、家庭環境が子供の心に与える影響についても考えさせられます。望を「女のくせに料理もできない」と詰る場面や、望と翔が孤児であることを言いふらす場面など、読んでいて胸が痛くなるシーンも少なくありません。しかし、物語の終盤、自らの浅はかな計画によって本当に危険な目に遭った圭介が、自身の母親の理不尽さを認め、涙を流す場面では、彼の人間的な弱さと変化の可能性を感じさせます。彼は最後まで明確な謝罪こそしませんでしたが、テレビカメラの前で「自分勝手なガキ」を演じることで、夏木たちへの虐待疑惑を晴らすという、彼なりの責任の取り方を見せました。
ヒロインである森生望の存在も、この物語に深みを与えています。彼女は、弟の翔を守りながら、過酷な状況を耐え抜こうとします。当初は圭介の嫌がらせに黙って耐えることが多かった望ですが、夏木との交流を通じて、少しずつ自己主張ができるように成長していきます。特に、潜水艦内で予期せず生理になってしまう場面は、この作品の中でも特に重要なシーンだと感じます。限られた水や物資の中で、望は汚してしまったシーツを隠れて洗おうとし、それを夏木に見咎められます。迷惑をかけたことを謝る望に対し、夏木は「お前に生理が来ることは悪いことか」「謝るな」と強く言います。この夏木の言葉は、望だけでなく、読者である私自身の心にも深く響きました。
このエピソードは、「恥ずかしいこと」と「恥じるべきこと」は違うのだという、大切な気づきを与えてくれます。望にとって、男性隊員しかいない閉鎖空間で生理という個人的な事柄が露見してしまうことは、非常に「恥ずかしい」状況だったでしょう。しかし、それは決して「恥じるべきこと」ではありません。女性の身体の自然な機能であり、誰かに非難されたり、揶揄されたりする謂れはないのです。圭介に「臭いんだよ」と心無い言葉を投げかけられた後、夏木に励まされる場面での「恥ずかしいけれど恥ではない。誰かに謗られる謂れもない。揶揄される自分の恥ではない。揶揄する者の恥だ」というモノローグは、望の精神的な成長と、人間としての尊厳を力強く示しています。この一連の描写は、性別に関わる偏見や無理解に対して、静かに、しかし確かなメッセージを投げかけているように感じます。有川さんの、人間の尊厳に対する真摯な眼差しが伝わってくるようです。
主人公の夏木大和は、口が悪く不愛想ながらも、根は情に厚い人物として描かれています。彼は、守るべき子供たちと、その子供たちを助けたために命を落とした上司への想いの間で葛藤します。参考資料にもあった「そんでも、あの子が死んで艦長が助かったらよかったって思う俺はひどいか」というセリフは、彼の偽らざる本音であり、極限状態における人間の正直な感情を表していて、非常に印象に残っています。自衛官として国民を守る義務があると理解しつつも、個人的な情や喪失感がそれを上回ってしまう瞬間がある。このような人間臭さが、夏木というキャラクターをより魅力的にしています。彼は、望や他の子供たちと関わる中で、ぶっきらぼうながらも彼らを守り、導こうとします。特に望に対しては、父親のような、あるいは兄のような複雑な感情を抱きつつ、一定の距離を保とうとします。最後の別れの場面で、望の告白を遮る彼の態度は、一見冷たくも感じられますが、それは彼女の未来を思っての、彼なりの誠実さだったのかもしれません。
夏木の相棒である冬原春臣は、夏木とは対照的に愛想が良く、冷静に物事を処理するタイプです。彼は夏木の良き理解者であり、時には諌め役にもなります。二人の対照的な性格と、深い信頼関係で結ばれたバディとしてのやり取りは、重苦しくなりがちな物語の中で、読者に少しの安らぎを与えてくれます。彼が、夏木と望の別れの後も、望の進路を知り、5年後の再会のきっかけを作る役割を担っている点も興味深いです。
物語のもう一つの軸は、潜水艦の外で繰り広げられる、サガミ・レガリスとの戦いと、それに関わる大人たちの奮闘です。警察庁の烏丸参事官や現場の明石警部、レガリス研究者の芹澤など、それぞれの立場で事態の収拾に奔走する姿が描かれます。そこには、縦割り行政の弊害や、手柄争い、官僚主義といった組織の問題点もリアルに描き出されています。特に、自衛隊の武器使用(防衛出動)を巡る政府内の駆け引きや、米軍の介入という政治的な要素が絡み合い、事態はより複雑化していきます。烏丸参事官が、膠着した状況を打破するために、あえて機動隊に「壊走」を命じる場面は、常識的な手段だけでは対応できない未曾有の危機に対する、非情ながらも合理的な判断として描かれており、考えさせられます。最終的に、特例として自衛隊の武器使用が認められ、それまで苦戦していたレガリスがあっさりと駆除される展開は、自衛隊という組織の持つ力の大きさと、その力の行使に伴う重い責任を改めて感じさせます。
有川さんの文章は、的確で無駄がなく、それでいて情景や心情が鮮やかに伝わってきます。参考資料にもあった冒頭の「春、寧日。天気晴朗なれど、波の下には不穏があった。」という短い一文は、これから始まる物語の雰囲気を凝縮して示しており、読むたびに鳥肌が立ちます。レガリスの描写も秀逸で、その巨大さや凶暴さが恐ろしいほど伝わってきます。また、時折挿入されるネット掲示板の軍事マニアたちの書き込みが、物語に別の視点とリアリティを与えています。彼らの知識や考察が、時に的を射ていたり、時に的外れだったりする様子は、現代の情報化社会の一側面を切り取っているようです。
物語の結末、騒動から5年後の夏木と望の再会シーンは、ほろ苦くも希望を感じさせるものです。潜水艦から救出される際、夏木は望の告白を受け止めませんでした。「幸せに出会って幸せに始まりたかった」という彼の言葉は、あの過酷な状況下での出会いを、純粋な始まりとは見なせないという彼の葛藤を表していたのでしょう。しかし、5年の時を経て、防衛省の技官となった望が、夏木の勤務する艦に見学に訪れる。そして、冬原の計らいもあり、二人は改めて「初めまして」と挨拶を交わします。これは、過去を乗り越え、新たな関係性を築く可能性を示唆する、静かで美しいエンディングだと感じます。まるで、長い冬を越えてようやく訪れた春の陽だまりのような、穏やかな希望がそこにはありました。この結び方は、読者に深い余韻を残します。
「海の底」は、単なるパニック小説やエンターテイメント作品にとどまらず、人間の尊厳、組織論、危機管理、そして人と人との絆といった普遍的なテーマを問いかける、非常に読み応えのある物語です。読むたびに新たな発見があり、登場人物たちの言葉や行動が心に深く刻まれます。特に、困難な状況の中でも、それぞれの立場で最善を尽くそうとする人々の姿は、私たち自身の生き方をも考えさせてくれる力を持っています。
まとめ
有川浩さんの小説「海の底」は、巨大生物の襲来という未曾有の危機を背景に、潜水艦という閉鎖空間で繰り広げられる濃密な人間ドラマを描いた作品です。この記事では、物語の始まりから結末までの詳細なあらすじを、重要な出来事やネタバレを含めて紹介しました。桜祭りでの突然の惨劇、潜水艦への避難、艦内での子供たちとの共同生活、そして外部での自衛隊や警察の奮闘が、緊迫感あふれる筆致で描かれています。
また、個人的な視点から、物語の魅力や登場人物たちの心情、作品が投げかけるテーマについて深く考察しました。特に、主人公・夏木の葛藤、ヒロイン・望の成長、そして子供たちの間で起こる諍いや和解、さらには「恥ずかしいこと」と「恥じるべきこと」の違いといった、心に残るエピソードに触れています。極限状態だからこそ浮き彫りになる人間の本質や、組織の中で奮闘する人々の姿は、読む者の心を強く打ちます。
「海の底」は、スリリングな展開に引き込まれるだけでなく、読み終えた後に、生と死、守るべきもの、人間の尊厳などについて深く考えさせられる物語です。まだ読んだことのない方にはもちろん、すでに読んだことのある方にも、この記事を通して新たな視点や感動を再発見していただけたら嬉しいです。有川浩さんの描く、力強くも繊細な世界をぜひ体験してみてください。