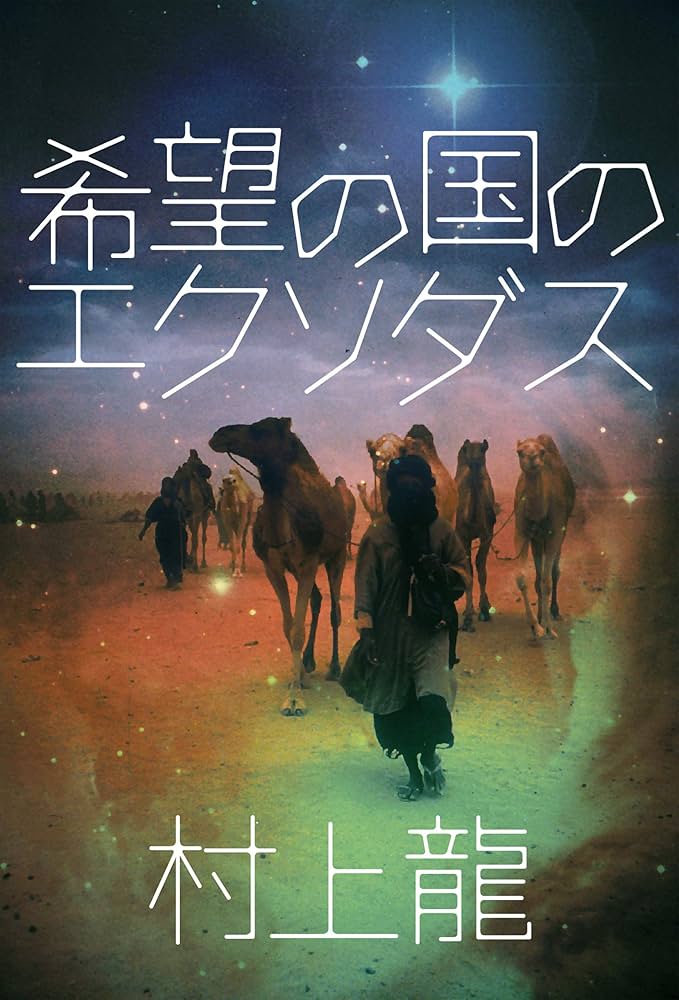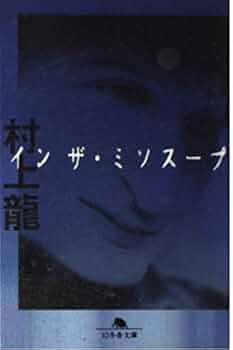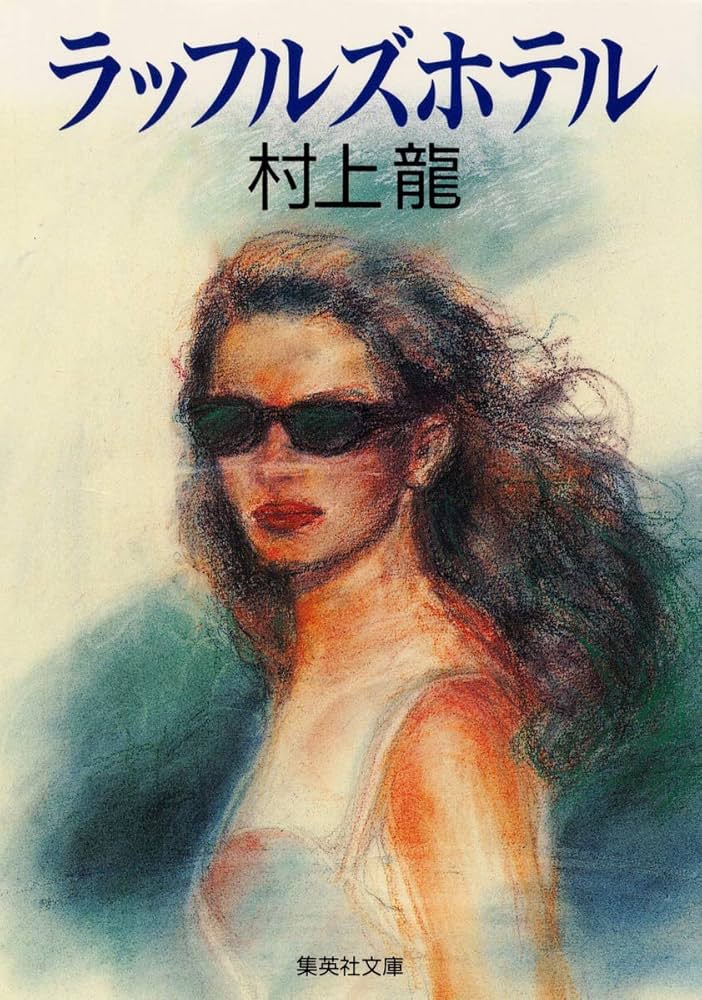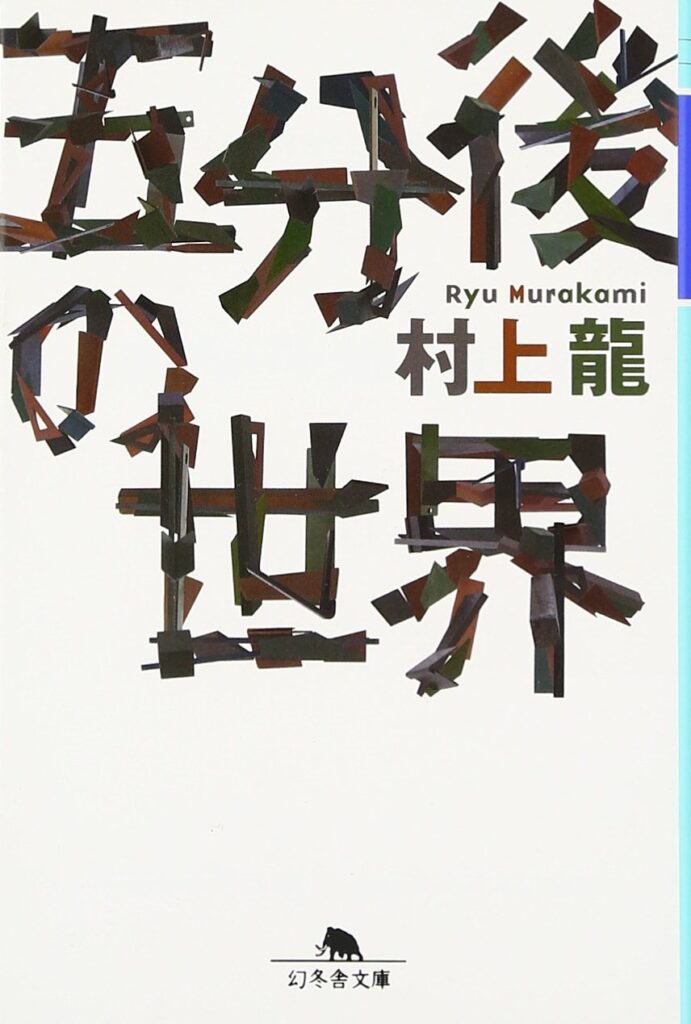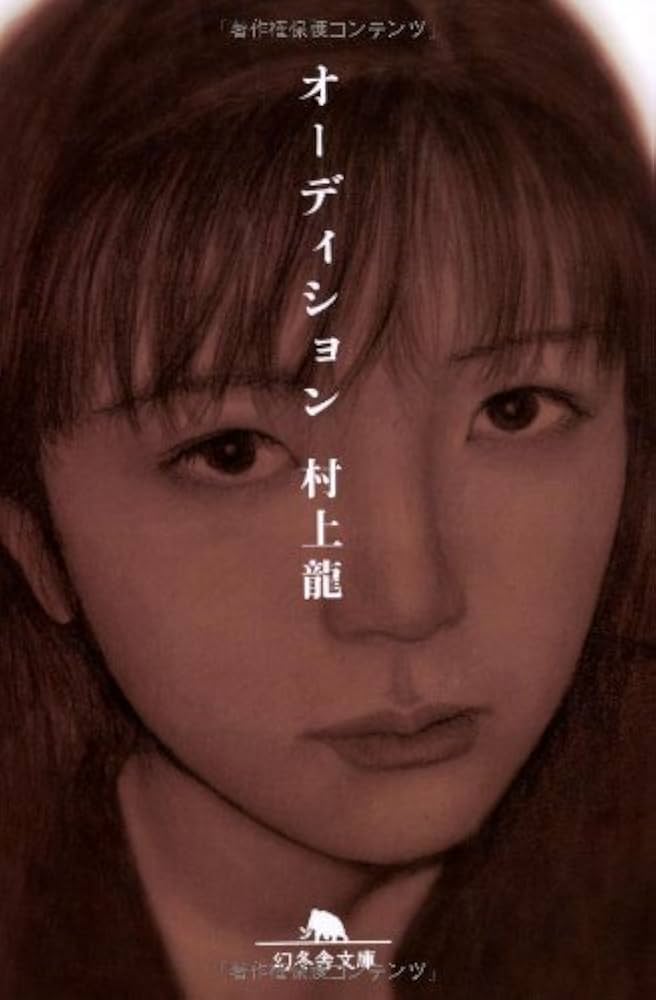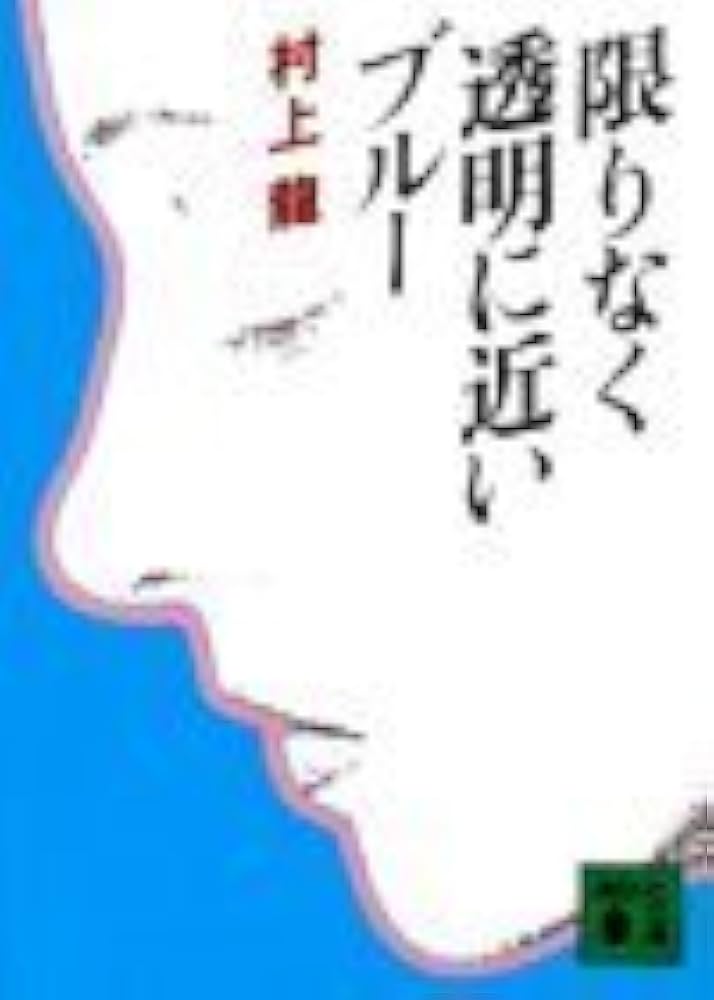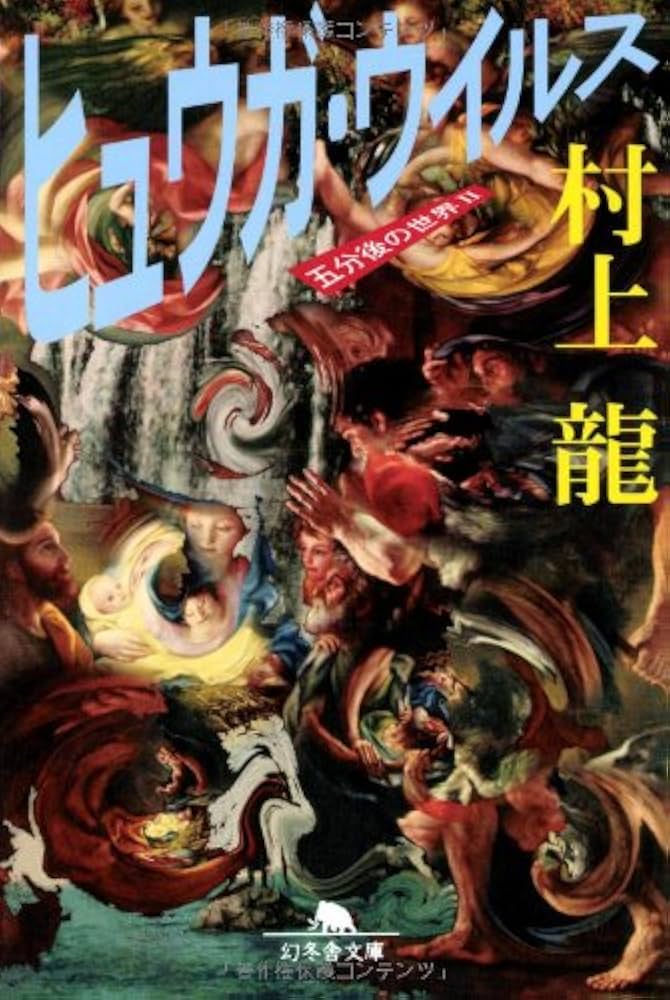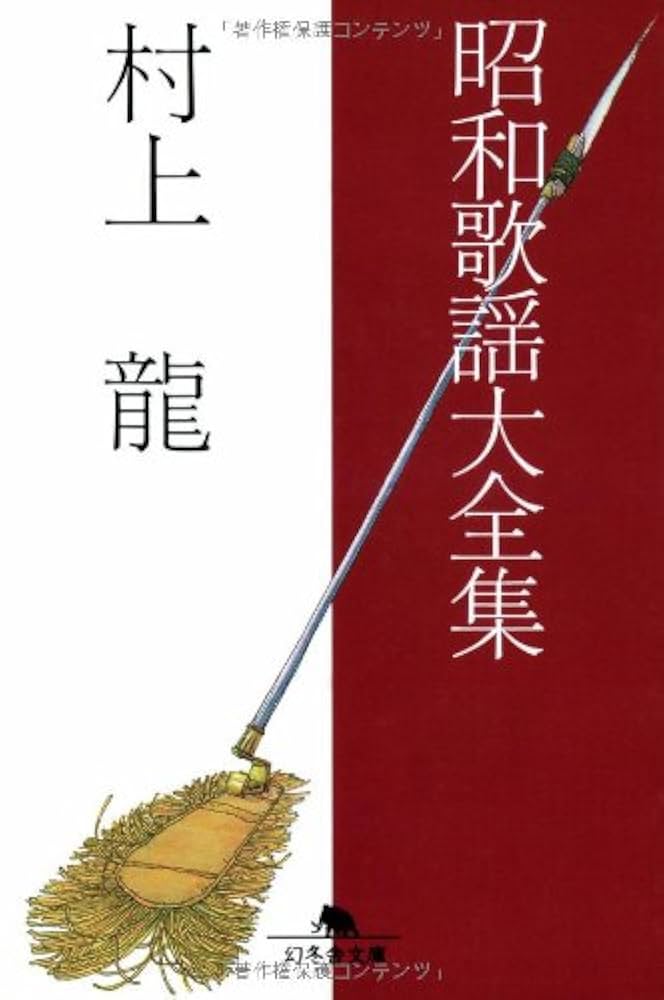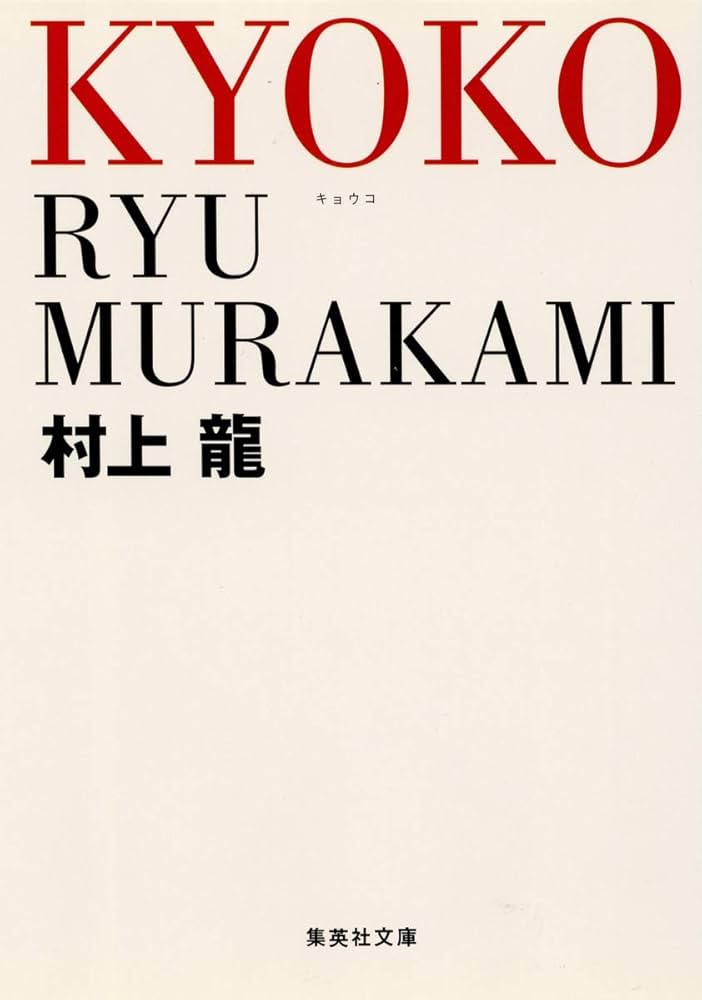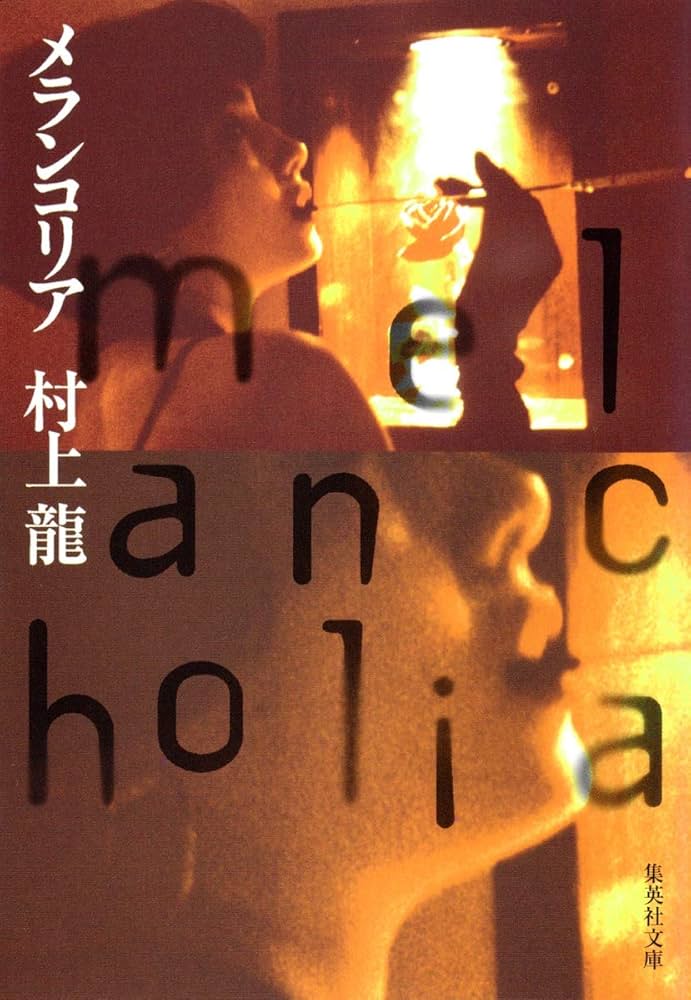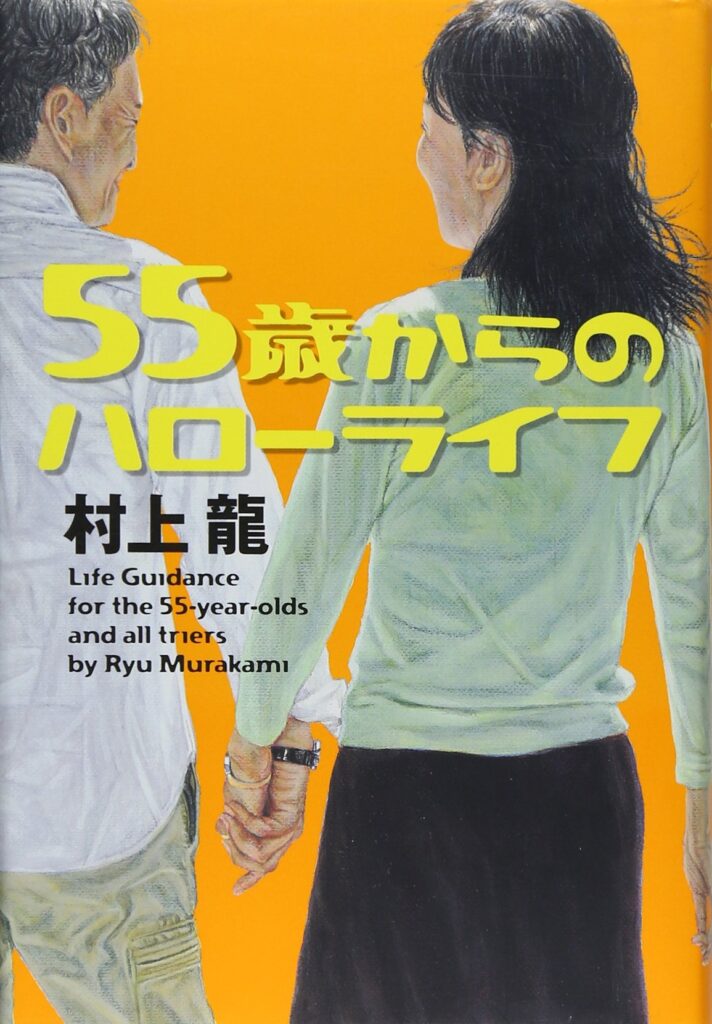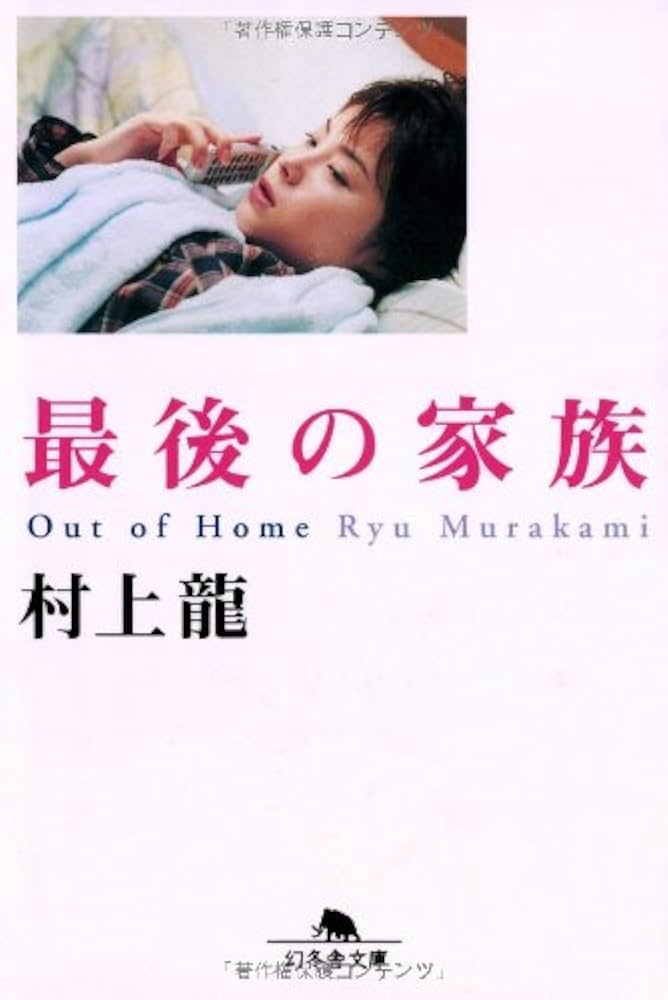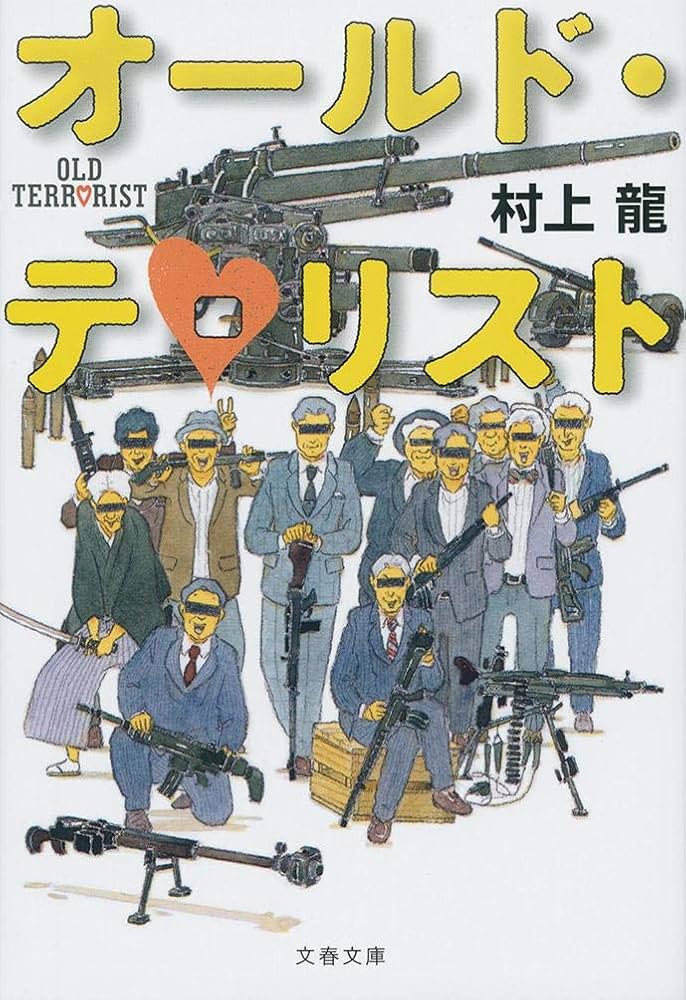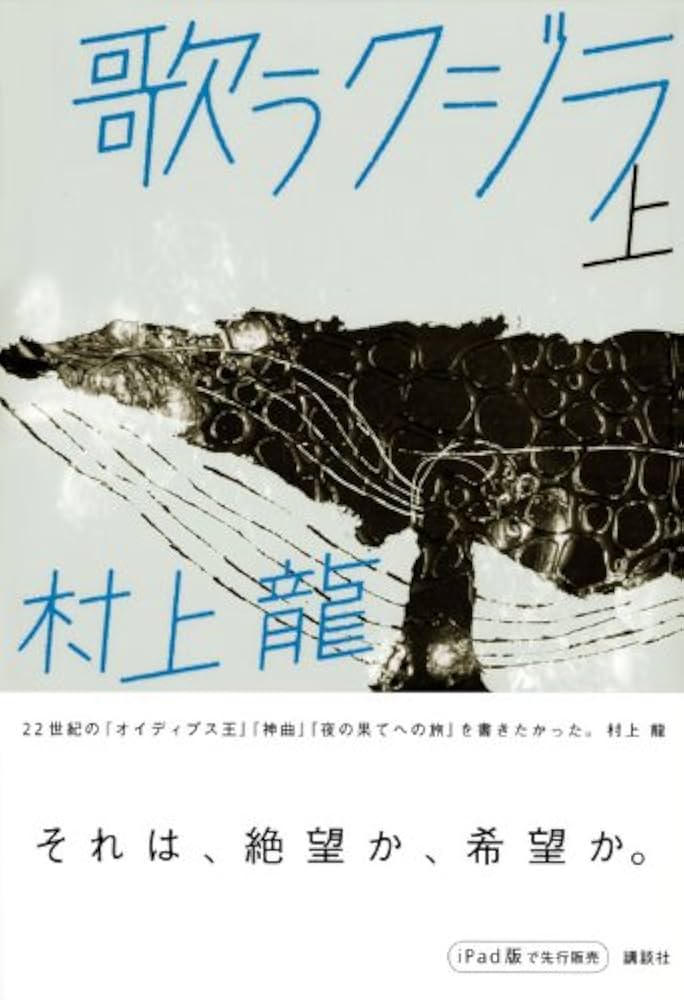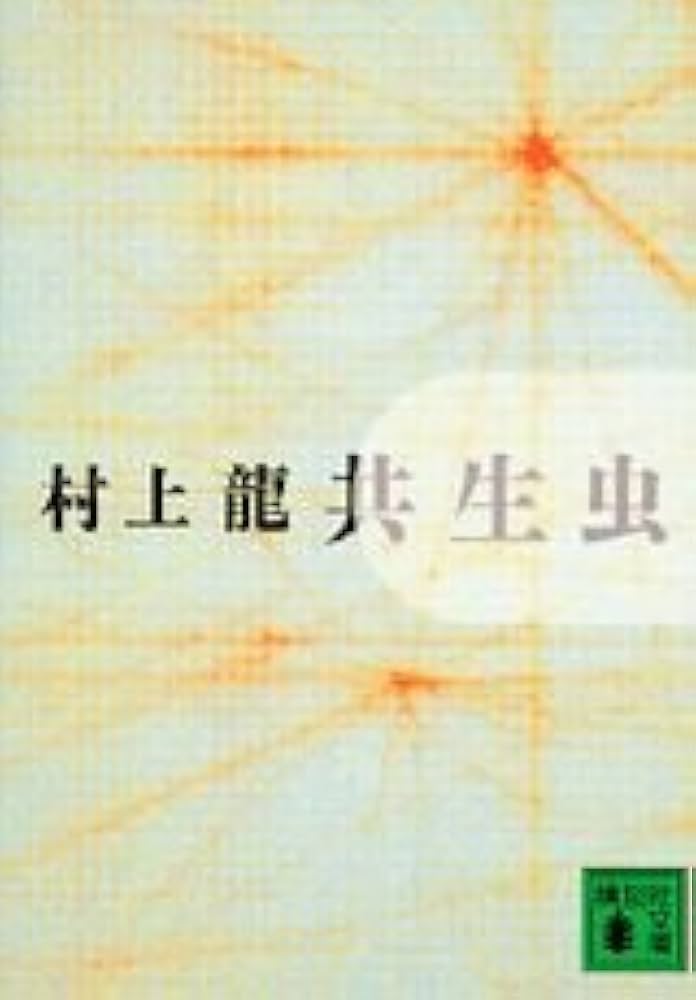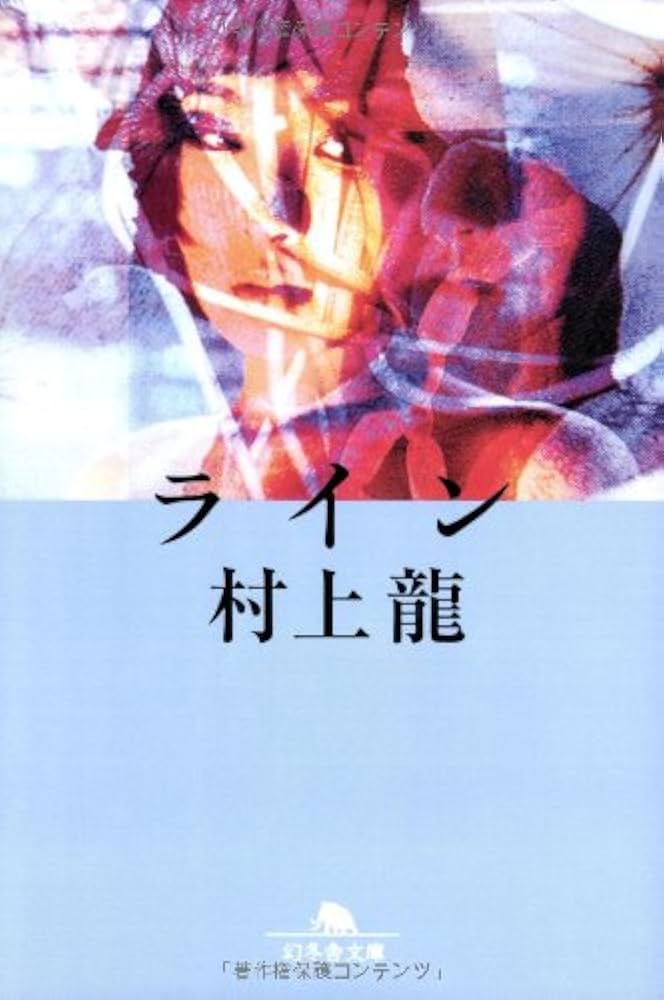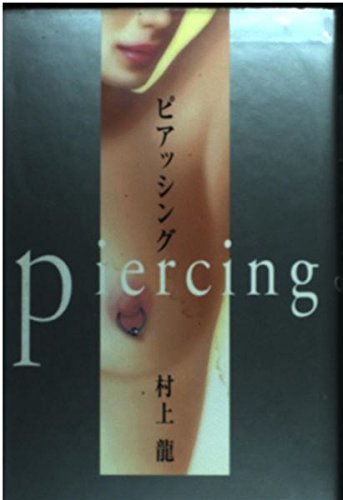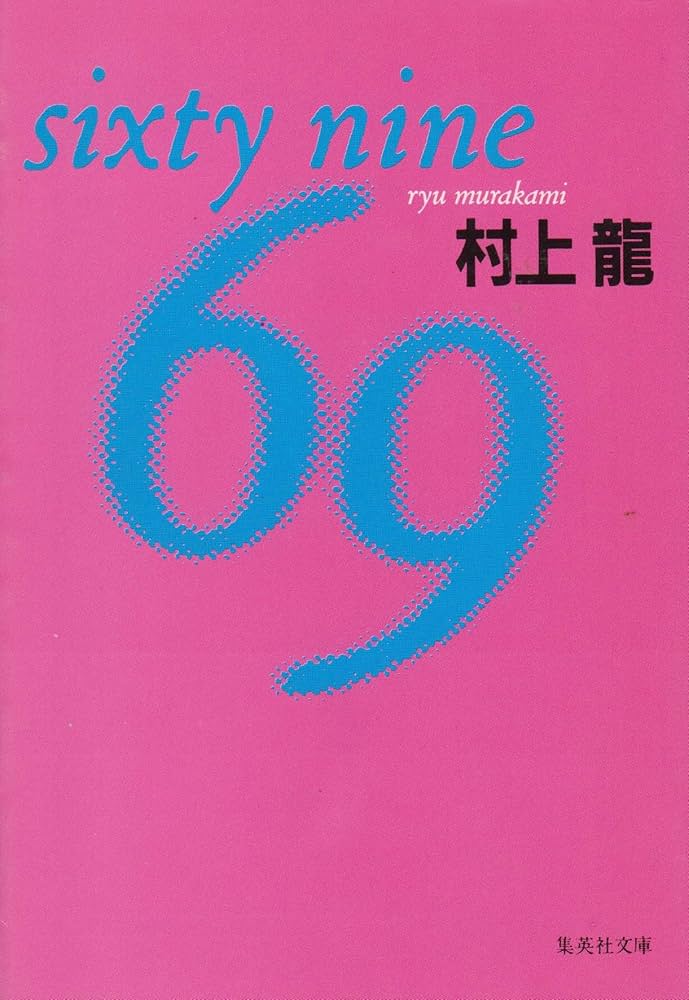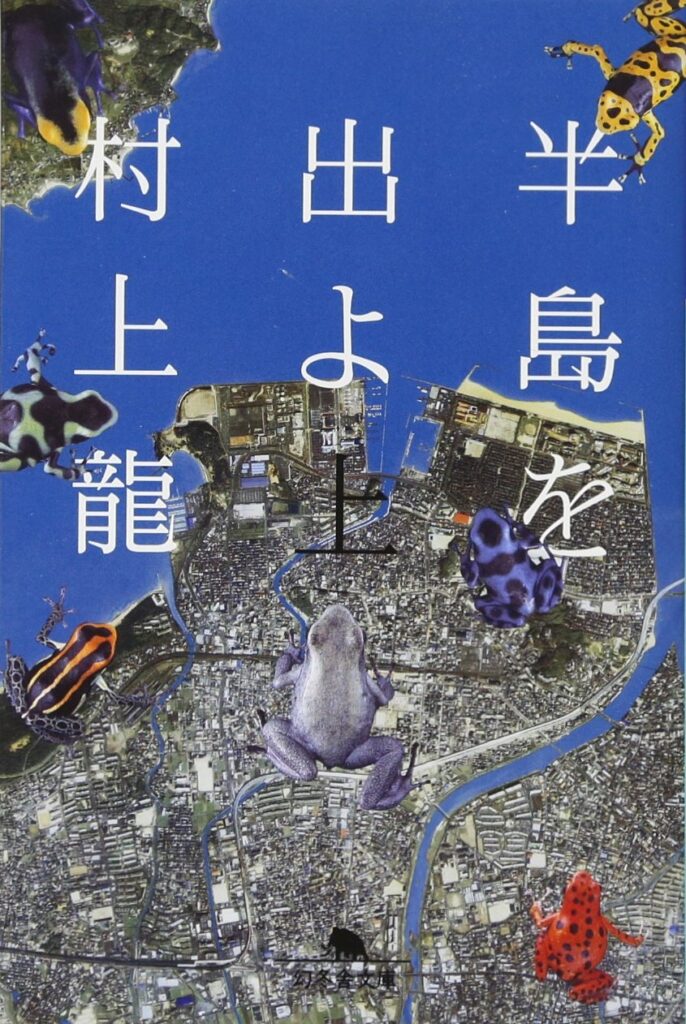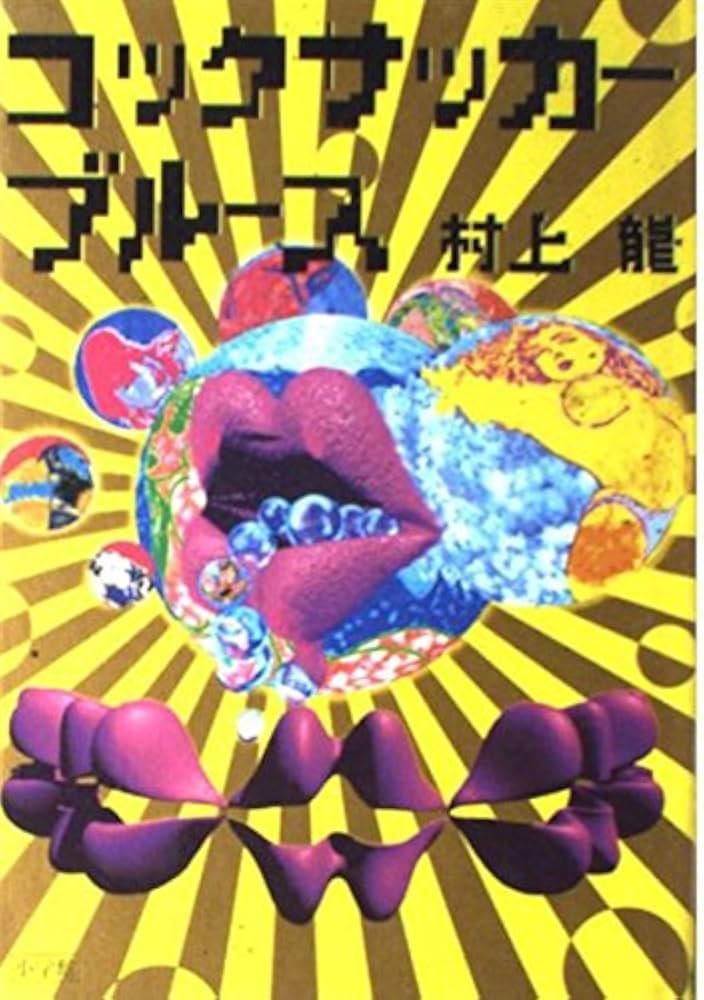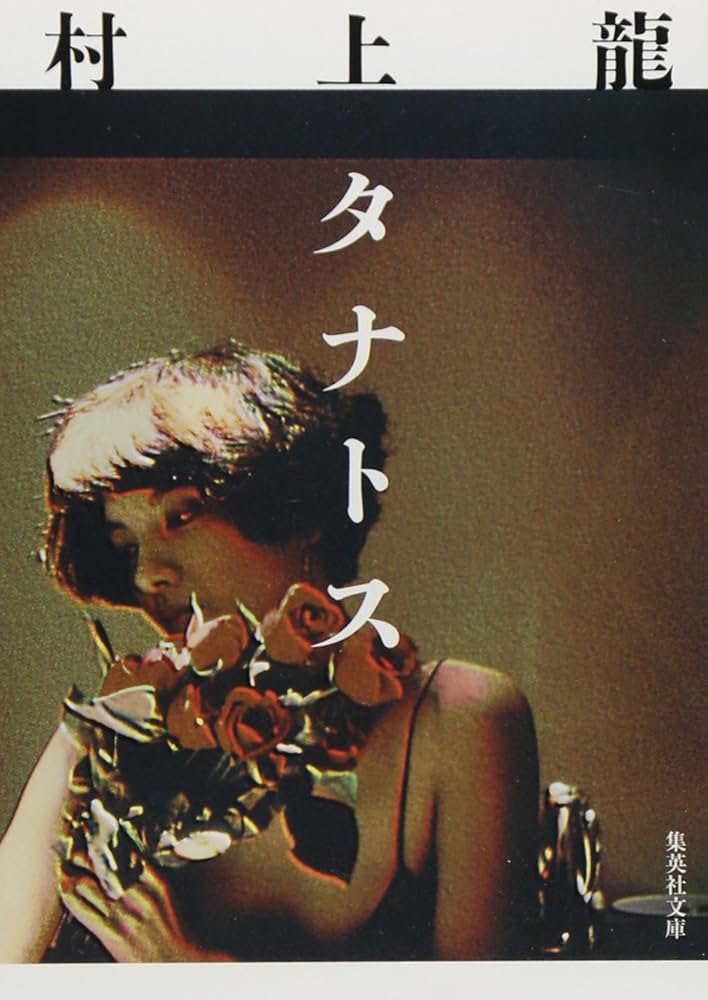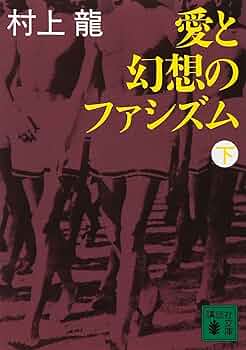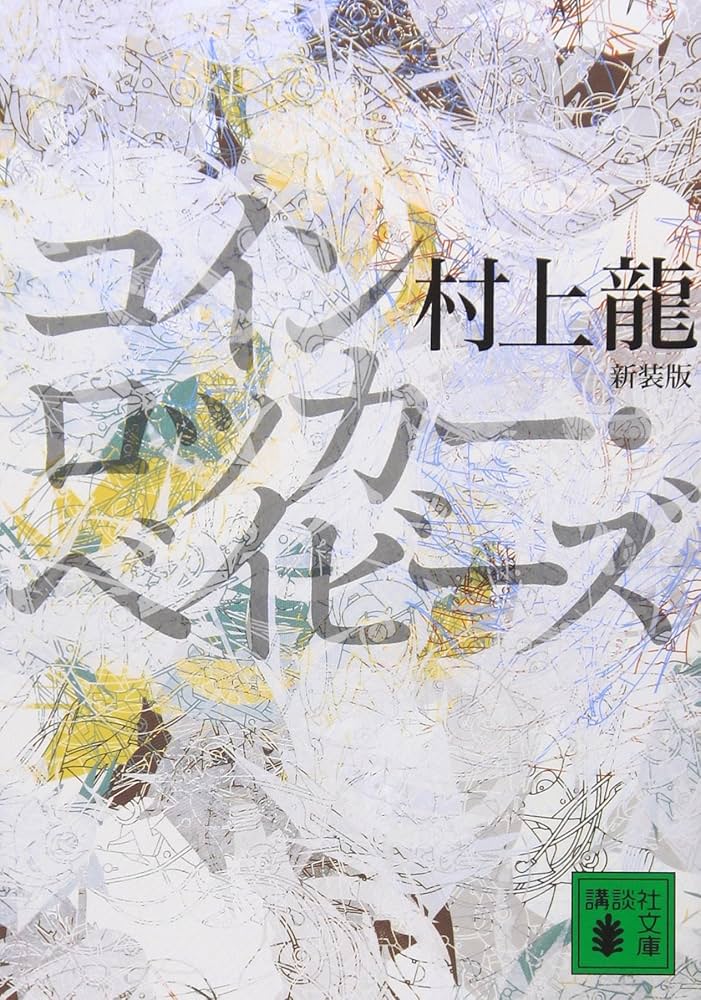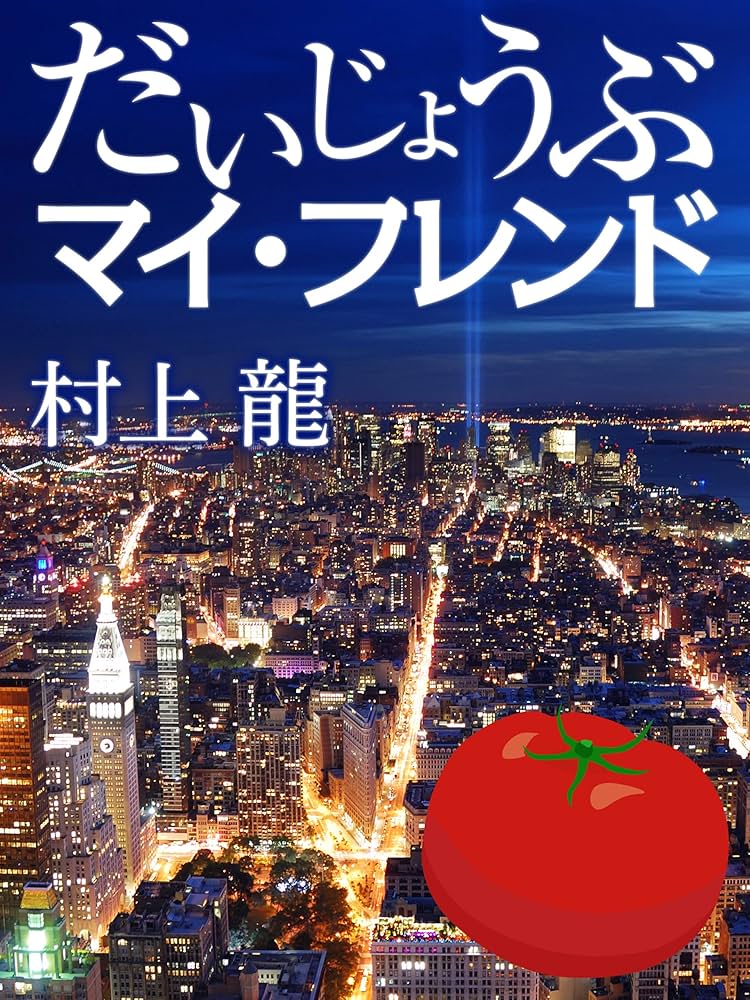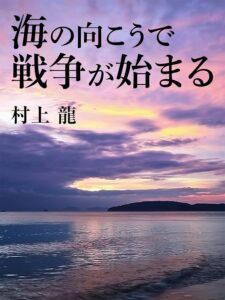 小説「海の向こうで戦争が始まる」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「海の向こうで戦争が始まる」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
この物語は、村上龍さんという作家が持つ独特の世界観が凝縮された一冊と言えるでしょう。発表されたのは1977年。どこか退廃的で、それでいて強烈なエネルギーを内に秘めた文章は、読む者の心を強く揺さぶります。初めて読んだ時の衝撃は、今でも忘れられません。
物語の構造は非常に独特で、現実と幻覚、こちら側と向こう側が、一人の男の「瞳」を介して繋がっていきます。穏やかな浜辺でドラッグに溺れる男女の視点から、突如として架空の都市で繰り広げられる凄惨な戦争の光景へと読者は引きずり込まれるのです。一体何が現実で、何が幻なのでしょうか。
この記事では、まず物語の骨子となるあらすじを追い、その後で物語の核心に迫るネタバレを含む深い感想と考察を述べていきます。この作品が投げかける「無関心」というテーマや、「見ること」に伴う責任について、私なりの解釈を交えながらじっくりと語っていきたいと思います。
「海の向とうで戦争が始まる」のあらすじ
物語は、主人公である「僕」が、恋人と共に穏やかな海辺で過ごしている場面から始まります。彼らはコカインに酔いしれ、現実から少しだけ浮遊した時間を過ごしていました。そこへ、フィニーと名乗る国籍不明の不思議な女性が現れます。彼女は「僕」の瞳を覗き込み、「あなたの目に町が映っているわ」と告げるのです。
フィニーが語るその町は、ゴミと基地があり、子供たちが力強く育っているという、矛盾に満ちた場所でした。そして、その町では今まさに盛大な祭りが始まろうとしている、と。彼女の言葉をきっかけに、物語の舞台は完全に「僕」の瞳の中に映る「向こうの町」へと移っていきます。そこでは、三組の人物たちの日常が描かれます。
一人目は、権威の象徴である大佐。彼は愛人との倦怠に満ちた日々を送り、その生活は退廃の極みにありました。二人目は、体制の末端を担う衛兵。彼は家庭や仕事で鬱屈した不満を抱え、そのはけ口を求めていました。三人目は、支配的な母親と暮らす洋服屋。彼は母親と、そして自分を取り巻く世界そのものに強烈な憎悪を募らせていました。
やがて町では、フィニーが語った通り盛大な祭りが始まります。しかし、その熱狂は次第に狂気へと姿を変え、人々の内に溜まっていた暴力性が一気に噴出します。祭りは殺戮の宴へと変貌し、町は凄惨な戦争の舞台となっていくのでした。この町の行く末は、そして、それをただ「見ている」だけの僕とフィニーは、どのような結末を迎えるのでしょうか。
「海の向こうで戦争が始まる」の長文感想(ネタバレあり)
この物語の感想を語る上で、まず触れなければならないのは、その圧倒的な「距離感」の演出です。物語は、ドラッグによって現実感が希薄になった「こちら側」の浜辺と、これから地獄絵図と化す「向こう側」の町、という二つの舞台で構成されています。この二つを繋ぐのが、主人公「僕」の瞳である、という設定が全てを物語っているように感じます。
「僕」は、自らの瞳の中で繰り広げられる大虐殺を、ただ見ているだけです。しかし、彼の感情は恐怖や憐憫ではありません。作中で明確に「堪らない興奮」を覚えたと描写されています。安全な場所から、遠い場所の悲劇を消費する。この構図は、現代に生きる私たちが、テレビやインターネットの画面越しに、遠い国の戦争や災害の映像を眺める姿そのものではないでしょうか。
私たちは、その映像を見て心を痛めたつもりになり、時には義憤に駆られます。しかし、その感情は一過性のものであり、チャンネルを変えれば、あるいはブラウザを閉じれば、すぐに日常へと戻っていきます。村上龍さんは、その行為に潜む倒錯した快楽と、無自覚な加害性を見事に暴き出しているのです。「僕」は中立な観察者ではありません。彼は、その凄惨な光景をエンターテインメントとして消費する、紛れもない当事者の一人なのです。
そして、この物語で重要な役割を果たすのが、謎の女フィニーです。彼女は、「僕」が瞳の中の惨状に動揺を見せても、どこまでも冷静です。「向こうの町」から流れてくる血で、自分たちの海が汚れるのではないかと心配する「僕」に対し、彼女はこう言い放ちます。「そんなことないわよ、遠すぎる」。この一言に、本作の核心が詰まっていると感じました。
この「遠すぎる」という言葉は、物理的な距離だけを指しているのではありません。地理的、政治的、そして何よりも心理的な距離のことです。その距離があるからこそ、私たちは他者の苦しみを「自分ごと」として捉えずにいられる。フィニーの「でもあたし達は別にいいのよ」という言葉は、この自己中心的な安全保障の論理を、身も蓋もなく突きつけてきます。
彼女の態度は、一見すると冷酷に思えます。しかし、これは私たち自身が日常的に行っている思考停止の正当化そのものではないでしょうか。自分たちの平和や安全が脅かされない限り、海の向こうで何が起ころうと知ったことではない。その無関心は、決して受動的なものではなく、他者の苦しみを積極的に無視し、その存在を消し去るという、極めて能動的な「暴力」なのだと、この物語は教えてくれます。
物語のもう一つの軸は、「向こうの町」でなぜ戦争が始まったのか、という点にあります。それは外部からの侵略ではなく、内部からの必然的な破裂でした。特に印象的なのが、洋服屋の青年です。彼は、支配的な母親と、彼が「汚ならしい嘔吐物」と嫌悪する社会全体に対して、どうしようもない憎しみを抱えています。
彼にとって、やがて始まる戦争は、政治的な出来事などではありません。彼を窒息させる現実そのものを破壊し、切り裂くための、個人的な浄化の儀式なのです。「祭なんか要らない。戦争が始まればいい」という彼の心の叫びは、個人的な鬱屈や憎悪が、いかにして集団的な破壊への渇望へと繋がっていくのかを鮮やかに描き出しています。
大佐の退廃や、衛兵の鬱屈も同様です。彼らは、それぞれの立場で社会に対する不満や虚無感を抱えていました。祭りの熱狂は、そうした個々人の負のエネルギーを一つに束ね、解き放つための触媒として機能します。魚を儀式的に解体する場面は、暴力への禁忌を取り払い、流血を日常化させるためのステップでした。こうして、祭りの狂乱は、ごく自然に戦争という名の集団的な殺戮へと移行していくのです。この移行の恐ろしいほどの論理性に、私は戦慄を覚えました。
物語の終盤、全てが破壊され尽くした廃墟の町を瞳に映しながら、「僕」はフィニーに問いかけます。「フィニー、あの町は夢なんだろうか?」。これは、あまりの惨状を前にした、彼の最後の逃避願望だったのかもしれません。しかし、フィニーはそれを許しません。
「夢じゃないわよ、あなたの目に映っているのよ、あなたは見ているのよ、見ることは本当のことよ」。
このフィニーの返答こそ、村上龍さんが読者に突きつけた、最も重いメッセージだと私は解釈しています。見るという行為は、ただの傍観ではない。それを見たと認識した瞬間、その出来事はあなたにとっての「現実」となり、あなたはそれに対しての責任を負うのだ、と。
私たちは、物語やニュースを「作り物」や「遠い世界の出来事」として簡単に切り捨ててしまうことがあります。しかし、それを見たという事実からは逃れられない。フィニーの言葉は、主観と客観の境界を曖昧にし、観察者に「あなたは無関係ではいられない」と断罪するのです。この一連の対話は、フィニーという存在が単なる幻覚や登場人物ではなく、観察者の責任を問う、普遍的な原理の代弁者であることを示唆しているように思えました。
この物語には、カタルシスがありません。救いも、裁きも、教訓すらも明確には示されないのです。「向こうの町」はただ破壊され尽くし、「こちら側」の僕とフィニーは、興奮が冷めた後の虚無感と共に浜辺に取り残されます。戦争を目撃したという強烈な体験は、彼らを現実に結びつけるどころか、むしろ自分たちが現実からいかに遊離した存在であるかを再確認させるだけでした。
読後に残るのは、ずっしりと重い問いです。私たちは、日々流れてくる情報に対して、どれだけ誠実に向き合えているだろうか。遠い場所の悲劇を、安全な場所から消費してはいないだろうか。その「見ること」自体が、一つの暴力になり得ると自覚しているだろうか。
「海の向こうで戦争が始まる」は、単なる戦争の悲劇を描いた物語ではありません。それは、「見る側」の人間の倫理と責任を、執拗に問い詰める物語です。凄惨な描写も多いですが、それはテーマを描き出す上で不可欠な要素でしょう。読む者の心に、消えない染みを残す。そんな力を持った一冊です。この作品のネタバレを読んでもなお、実際に文章に触れてみる価値は十二分にあると、私は強く感じています。その衝撃的なあらすじと結末は、あなたの価値観を根底から揺さぶるかもしれません。
まとめ
村上龍さんの「海の向こうで戦争が始まる」は、読む者に強烈な問いを投げかける作品です。主人公の瞳に映る架空の町で繰り広げられる戦争と、それを安全な場所から「興奮」しながら眺める男女の姿を通して、物語は「無関心」という名の暴力を鋭く描き出します。
物語のあらすじを追うだけでも、その独創性と衝撃的な展開に引き込まれますが、この作品の真髄は、ネタバレを含む結末とその解釈にこそあるでしょう。なぜ戦争は起きたのか。それは遠い国の他人事ではなく、登場人物たちの内なる憎悪や虚無感が必然的に引き起こしたものでした。
そして何より、「見ることは本当のことよ」というフィニーの言葉が重く響きます。私たちは日々、様々な情報を目にしますが、その「見る」という行為自体に責任が伴うのだと、この物語は教えてくれます。傍観者でいることは、もはや許されないのです。
読後には、決して爽快ではない、むしろずっしりとした感覚が残るかもしれません。しかし、それこそがこの作品が持つ力であり、現代に生きる私たちが向き合うべきテーマを内包している証拠です。忘れがたい読書体験を求める方に、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。