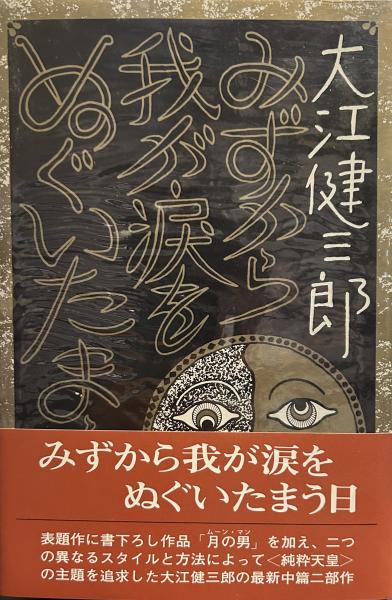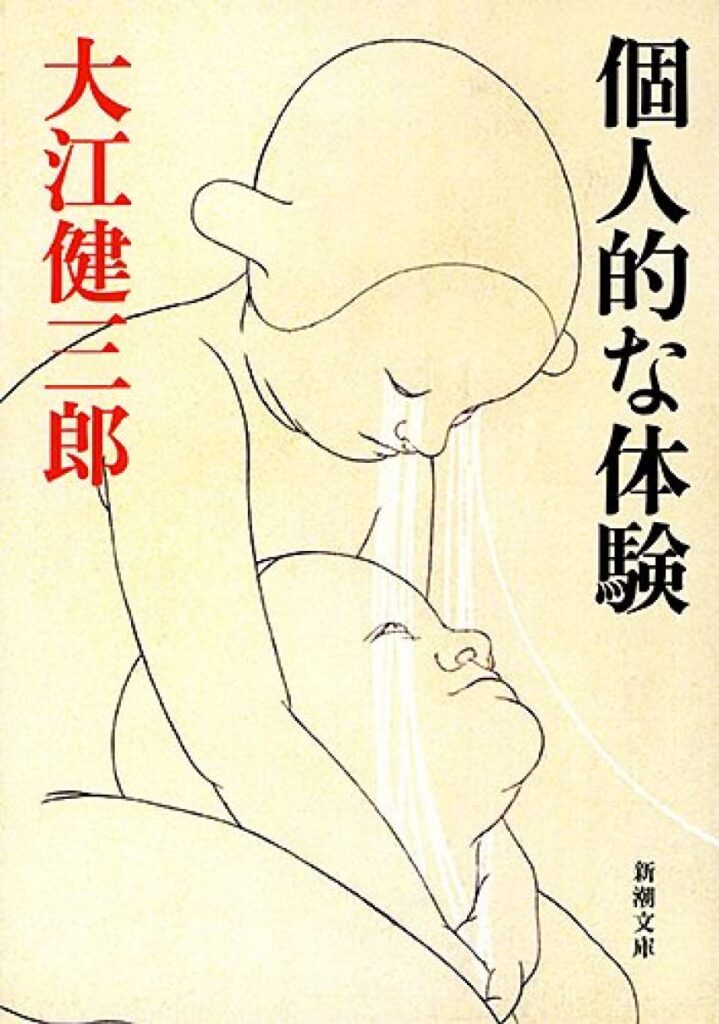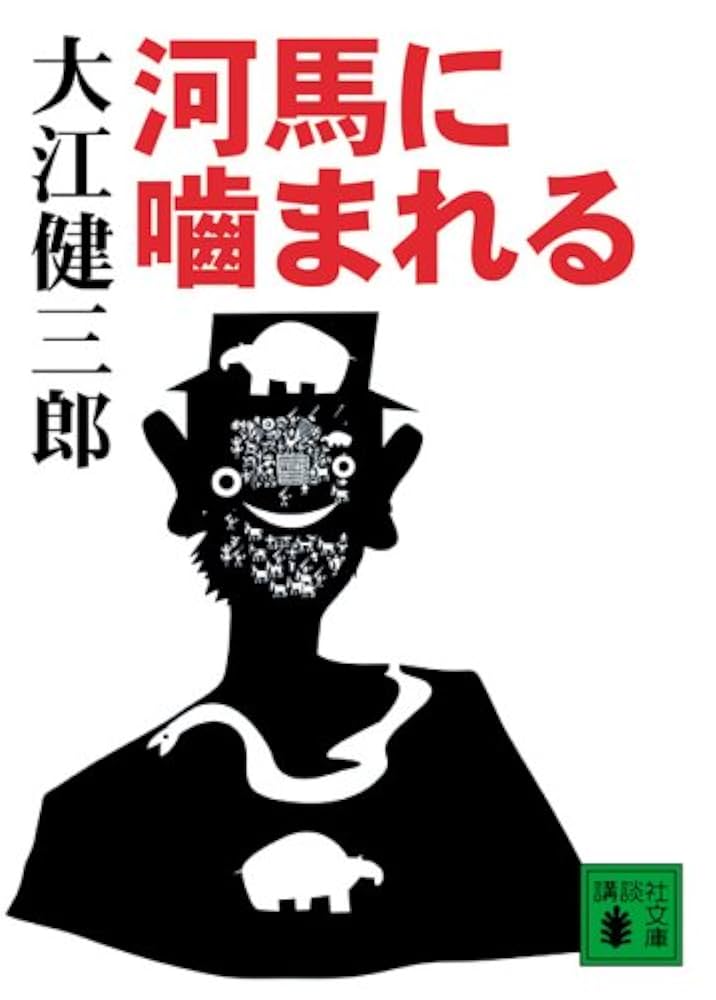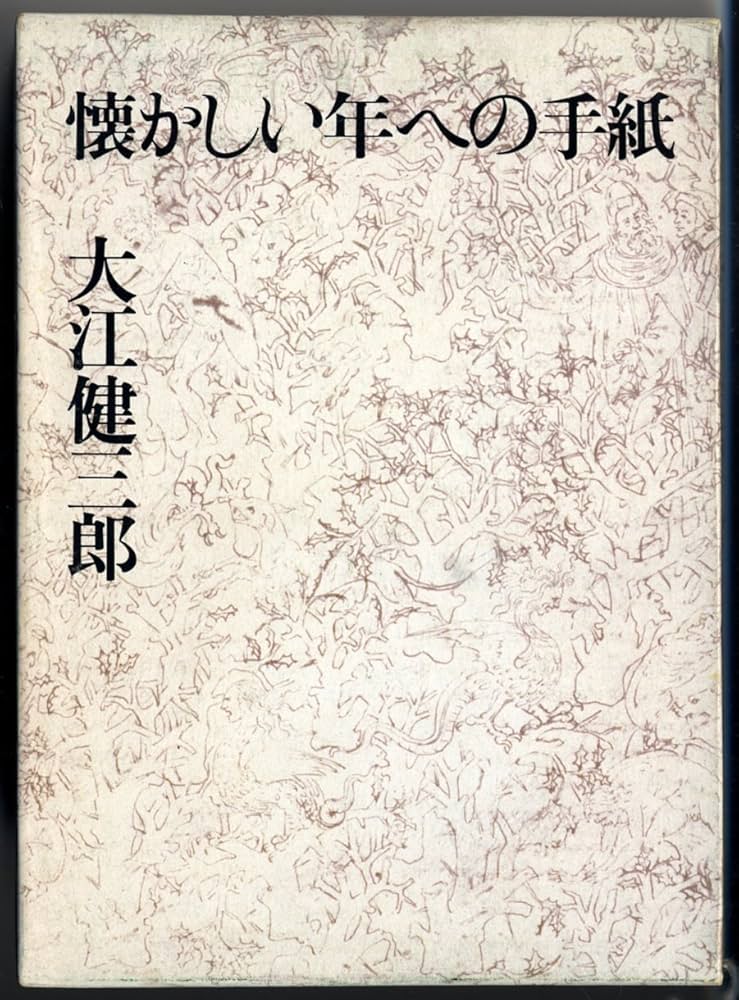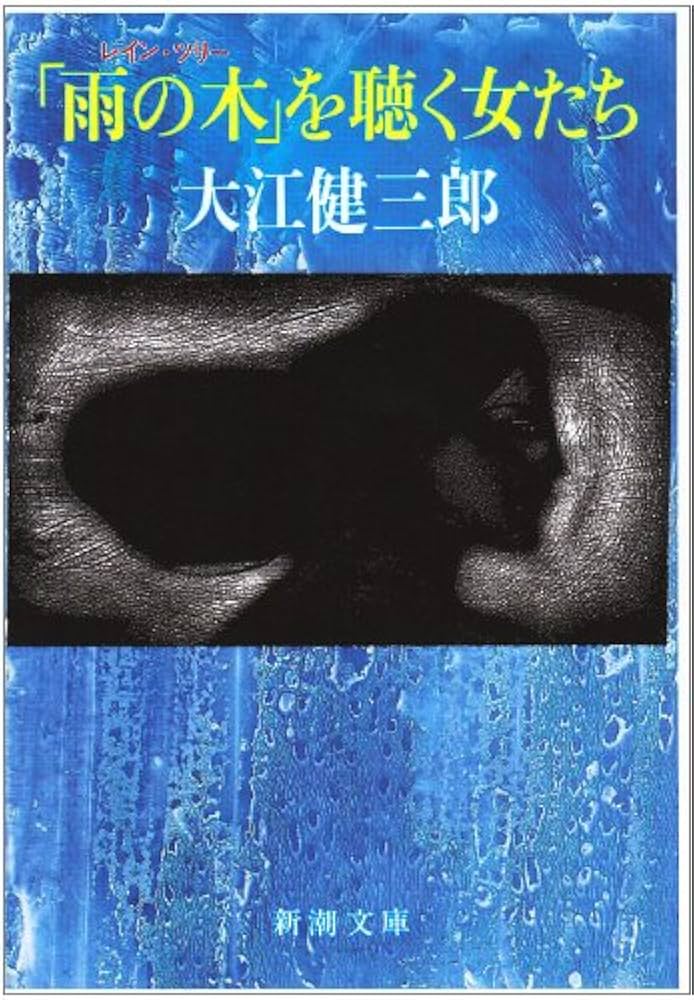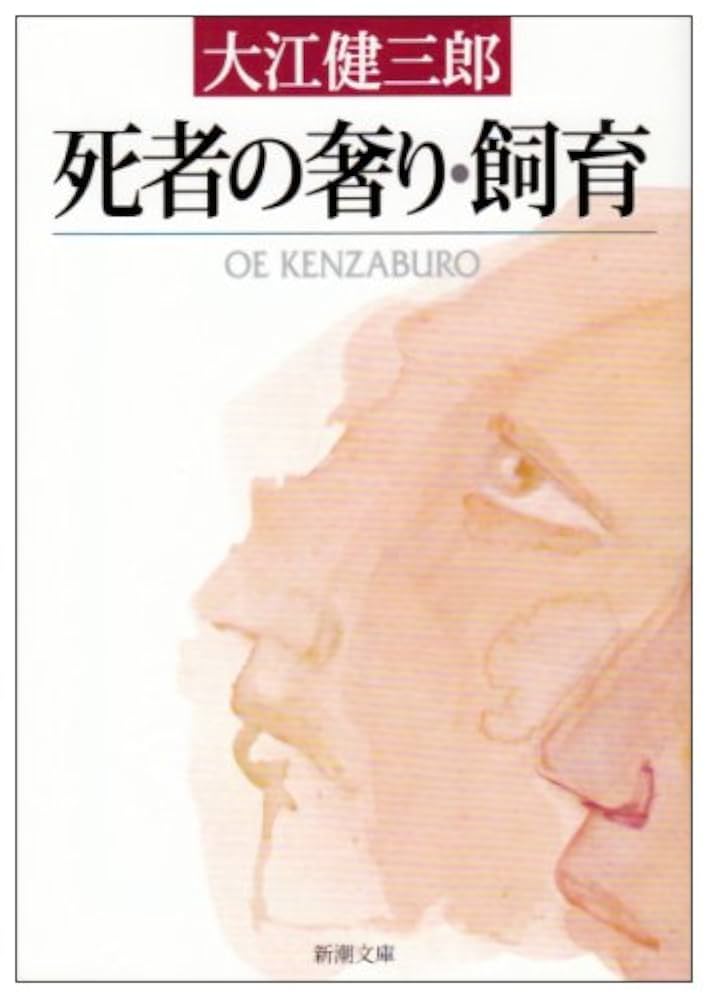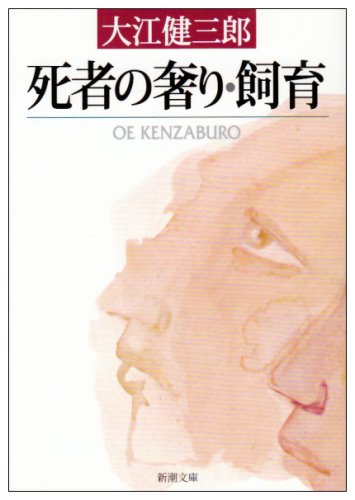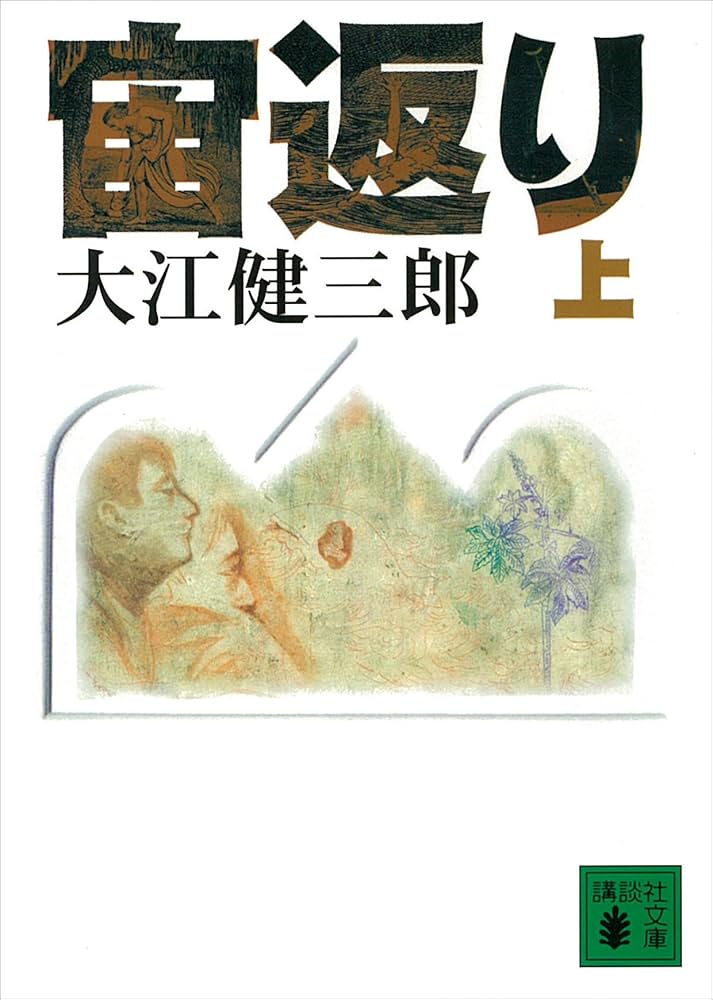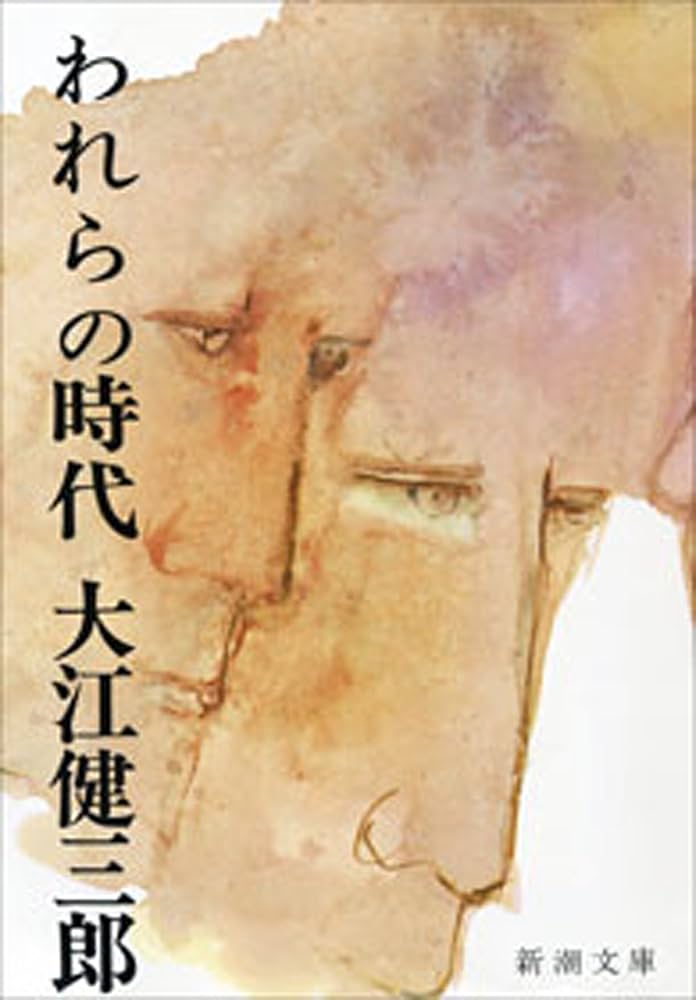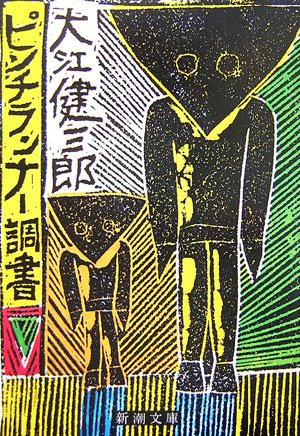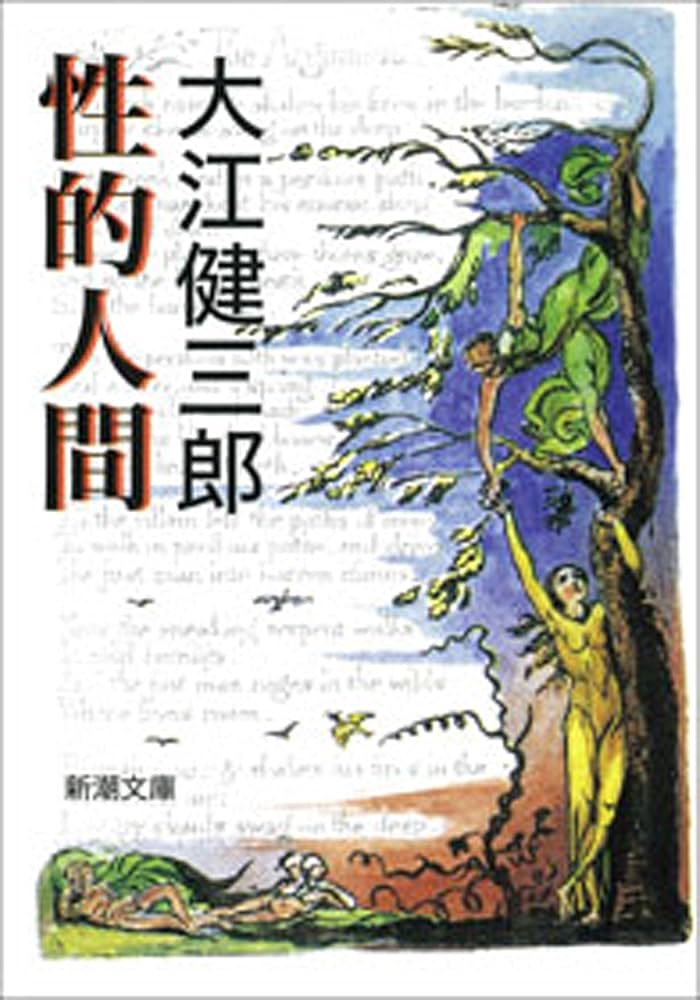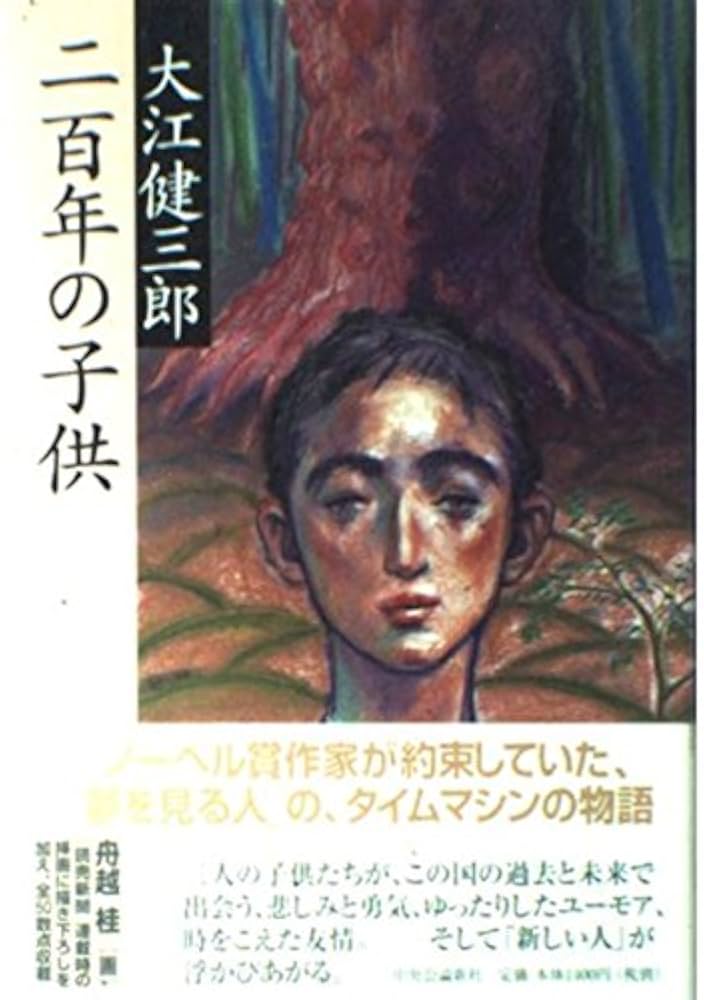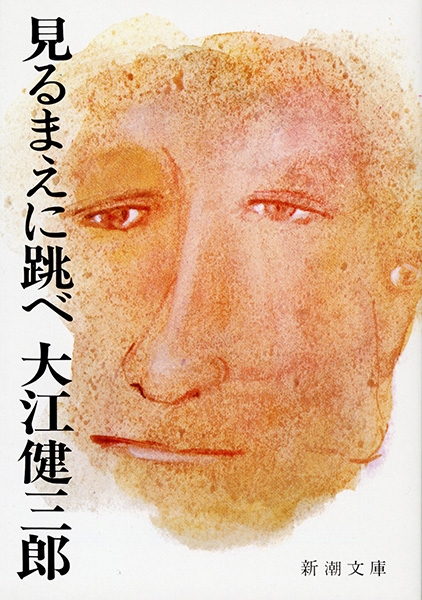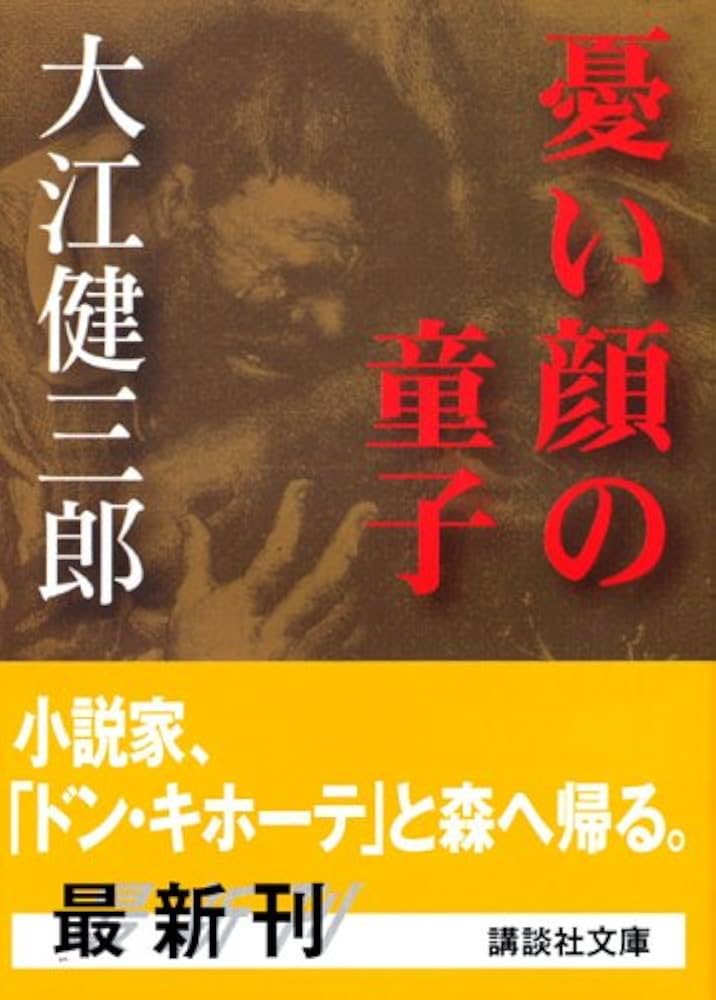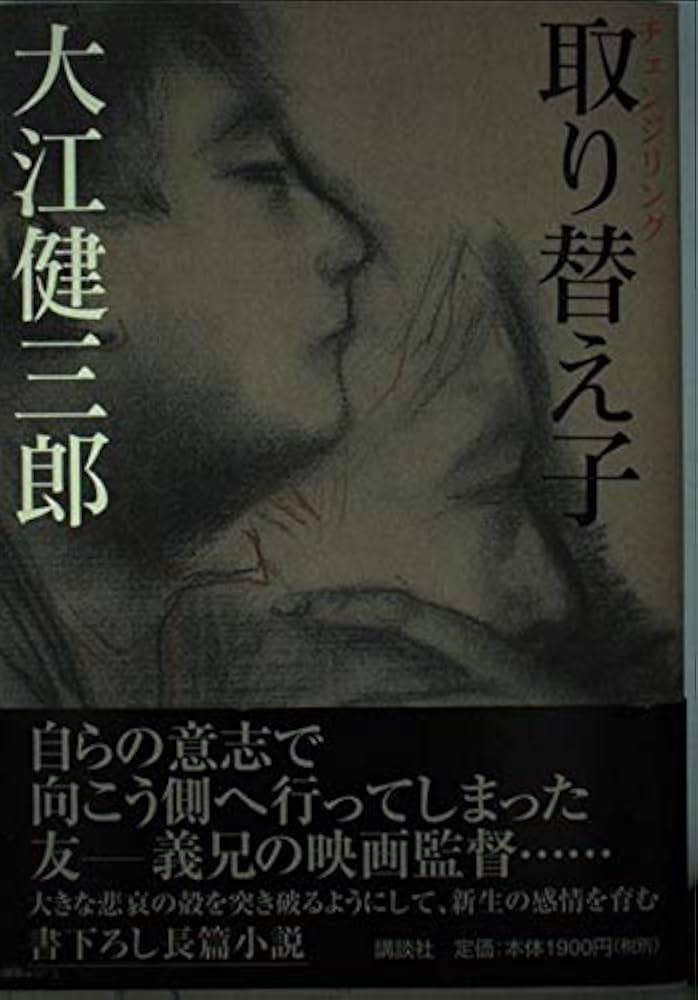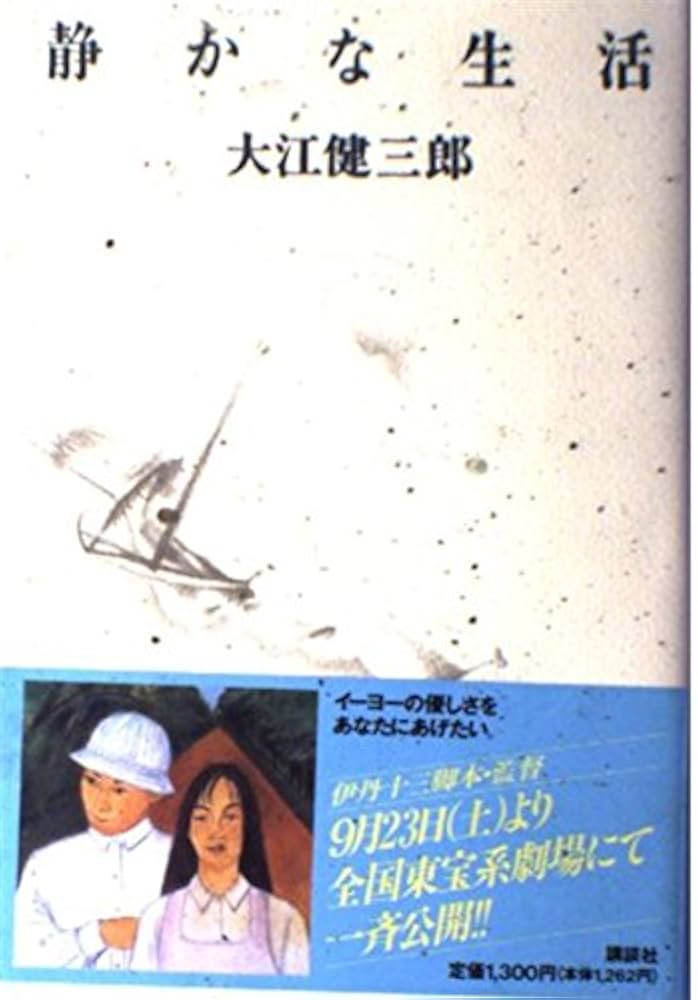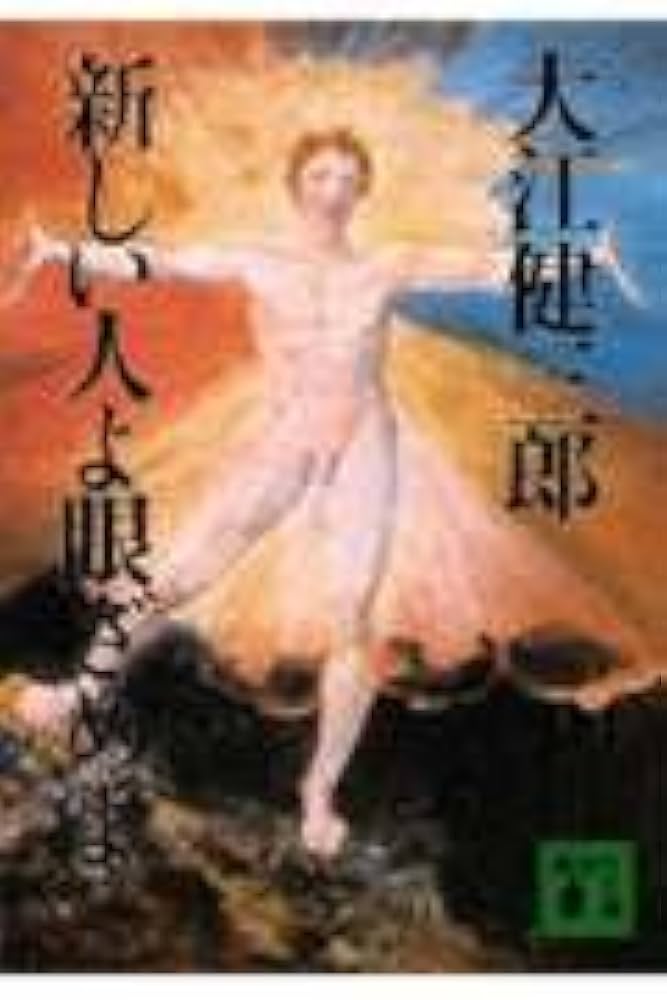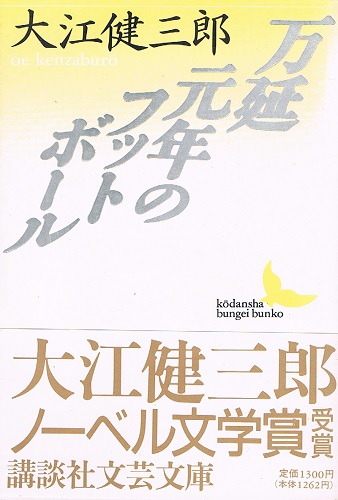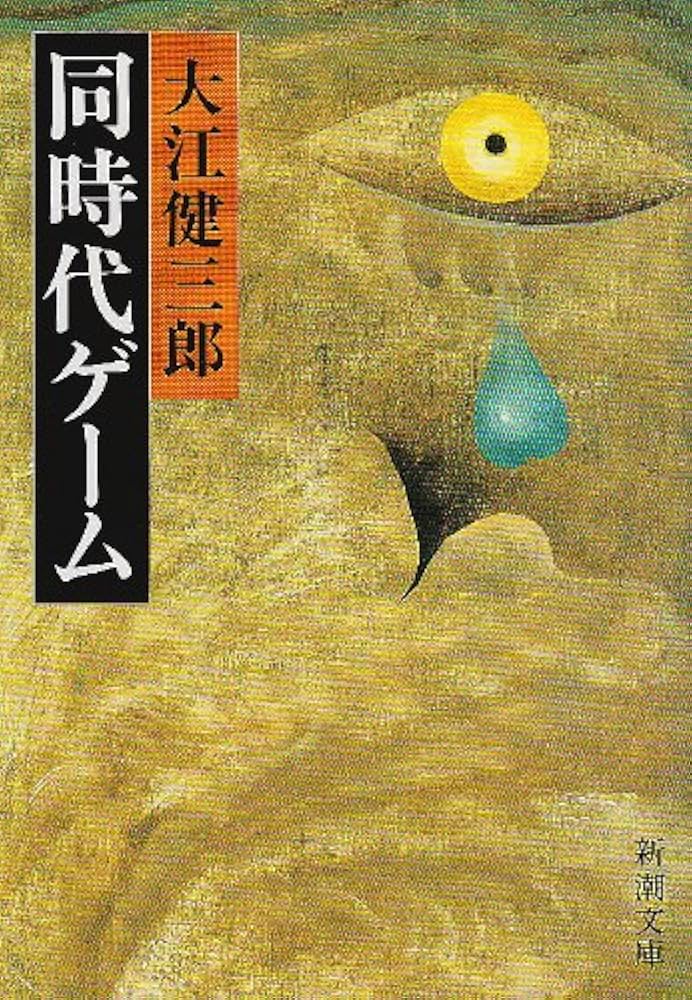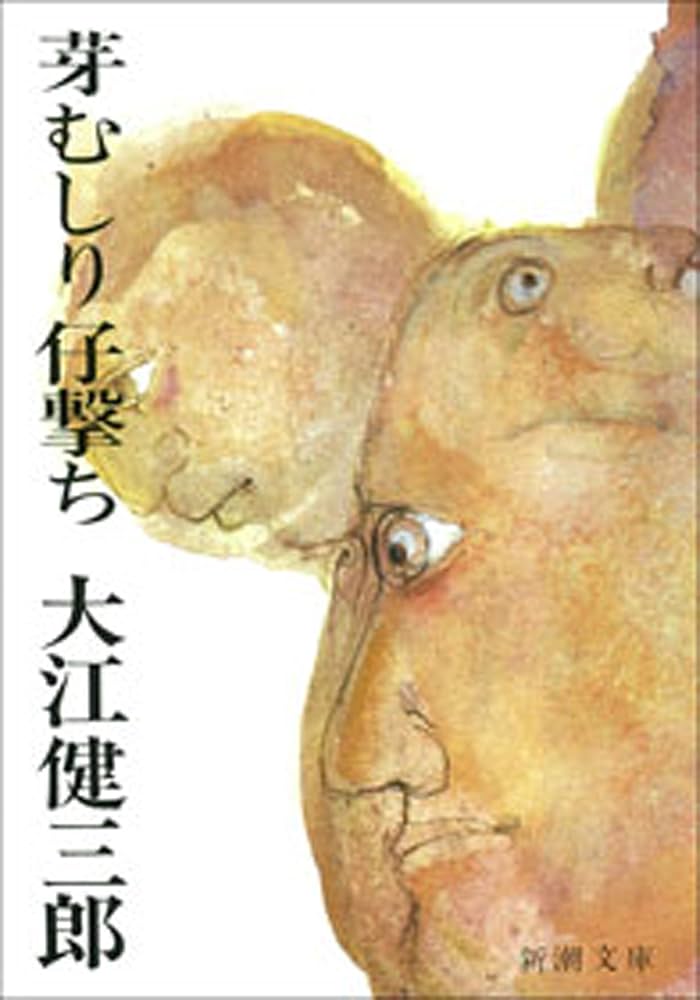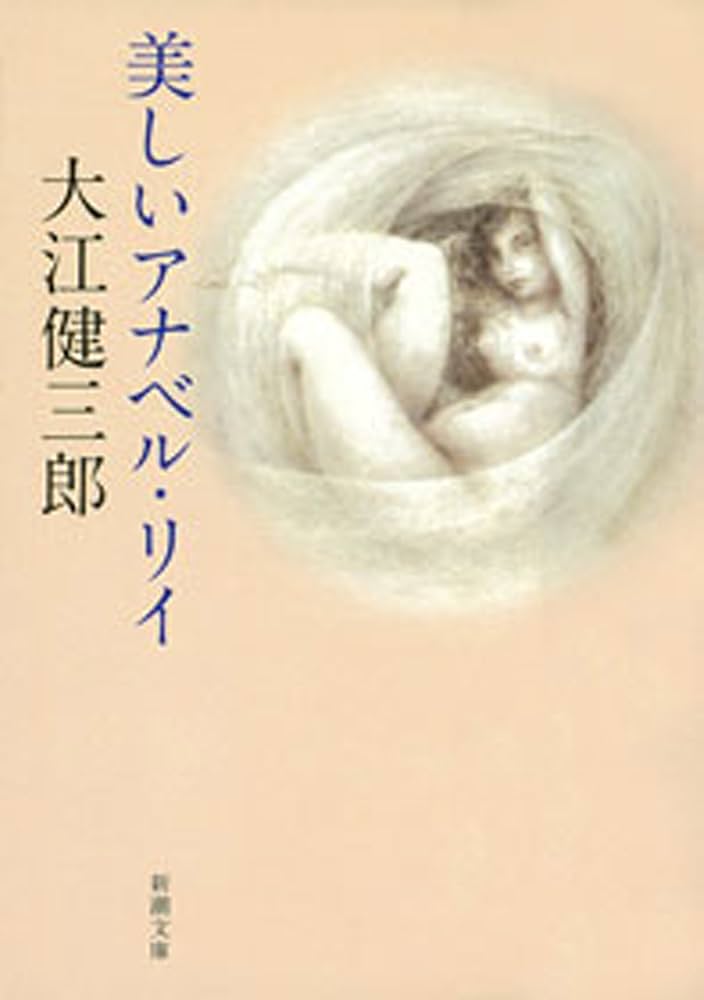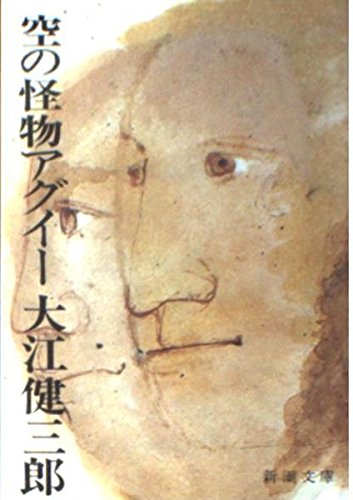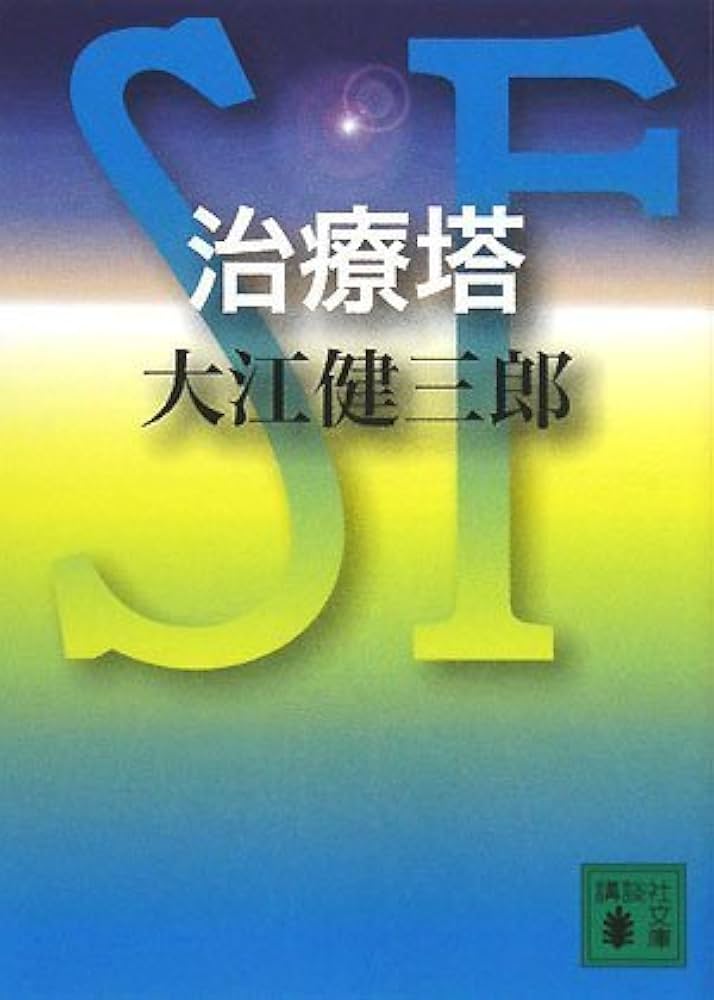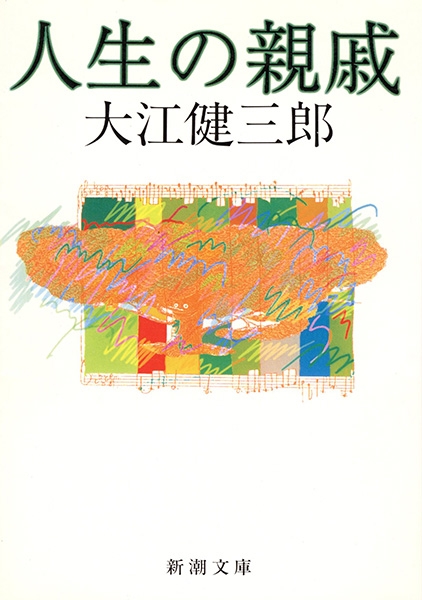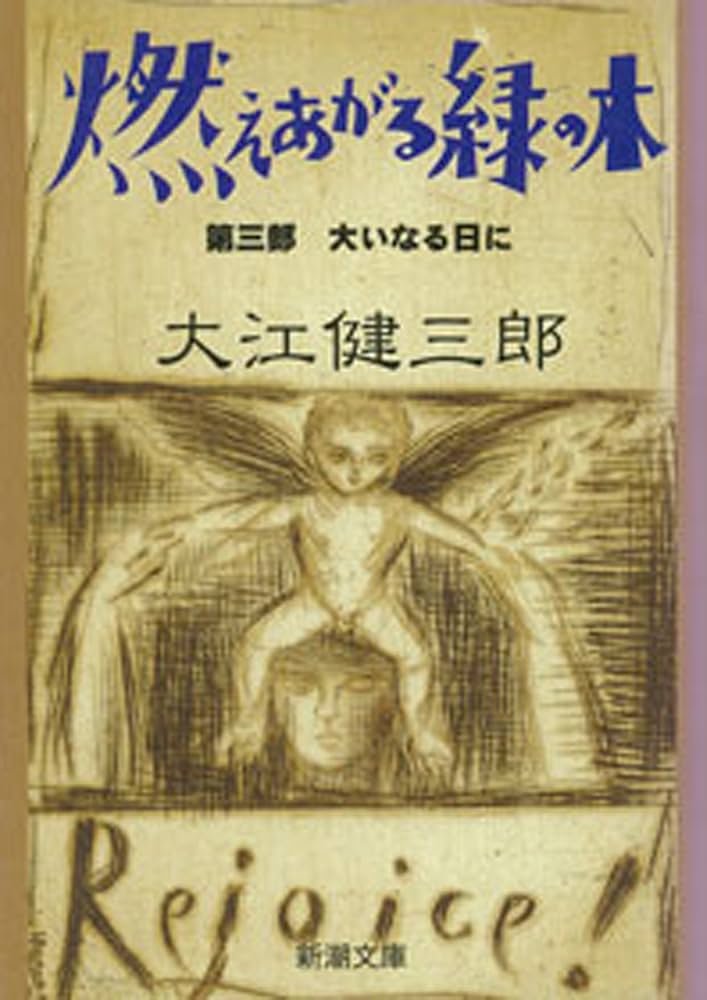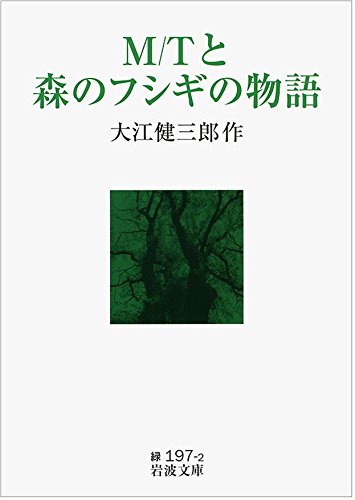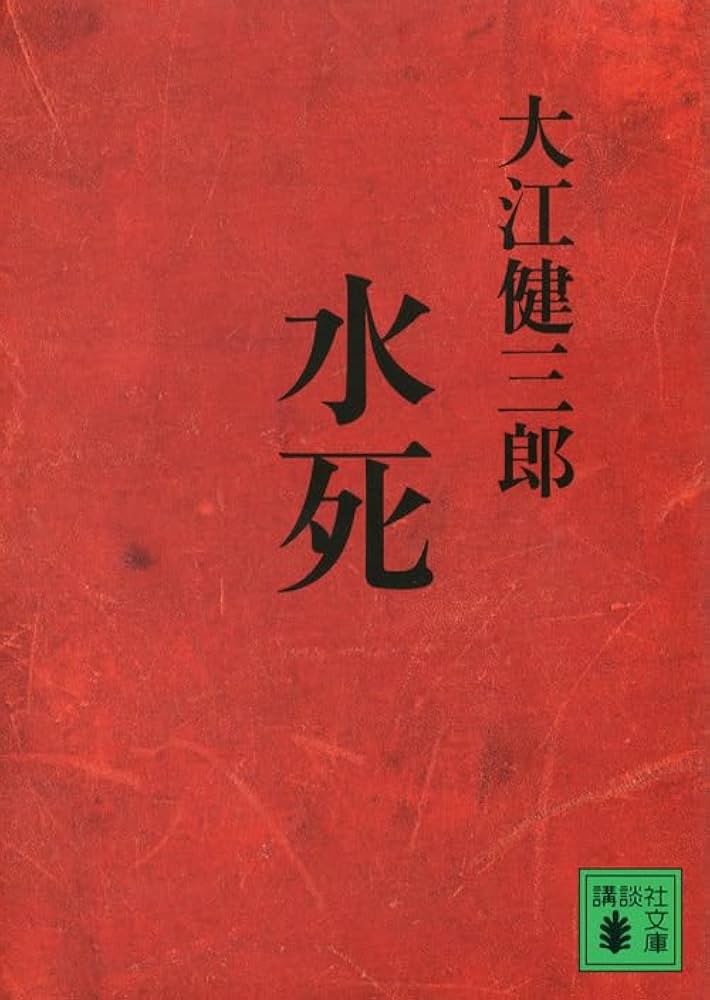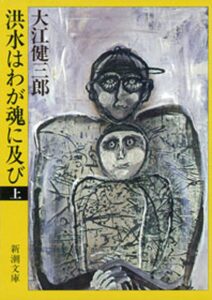 小説「洪水はわが魂に及び」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この作品は1973年に発表され、その年の野間文芸賞を受賞しました。大江健三郎のキャリアの中でも、特に重要な位置を占める長編小説として知られています。
小説「洪水はわが魂に及び」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この作品は1973年に発表され、その年の野間文芸賞を受賞しました。大江健三郎のキャリアの中でも、特に重要な位置を占める長編小説として知られています。
物語は、知的障害を持つ息子ジンと社会から隔絶して暮らす父親、大木勇魚(おおき いさな)の視点で進みます。彼らが暮らすのは、核シェルターを改造した異様な住居。そこで勇魚は「樹木の魂」や「鯨の魂」と交感するという、独自の精神世界に深く沈潜しています。静謐でありながらどこか切迫感のあるこの日常が、ある若者グループとの出会いによって大きく揺らぎ始めます。
この記事では、まず「洪水はわが魂に及び」の物語の骨子を追いかけ、その後、物語の核心に触れるネタバレを含んだ詳しい感想を綴っていきます。本作「洪水はわが魂に及び」が内包する終末論的な世界観や、当時の社会状況との共鳴、そして父と子の関係性という普遍的なテーマがどのように描かれているのか、深く掘り下げていきます。
作品発表から半世紀近くが経過した今、なぜ再び「洪水はわが魂に及び」が読まれるべきなのか。その理由を探る旅に、皆様をお連れできればと思います。現代社会が抱える問題とも通じる、この物語の力強さに触れてみてください。
「洪水はわが魂に及び」のあらすじ
主人公の大木勇魚は、鳥の声を聞き分ける特殊な能力を持つ知的障害の息子ジンと共に、東京郊外の核シェルター跡で隠遁生活を送っています。彼は自らを「樹木の魂」と「鯨の魂」の代理人と任じ、来るべき世界の終わりを静かに待っていました。この生活は、彼がかつて有力な政治家の秘書として犯した罪からの逃避でもありました。
勇魚とジンの閉ざされた日常は、「自由航海団」と名乗る若者たちとの出会いで一変します。彼らは大災害を予期し、船で海へ逃れることを夢見る集団でした。当初は警戒していた勇魚ですが、世界の終末という共通の関心事を通じて、彼らと奇妙な連帯感を育むようになります。しかし、その関係は穏やかなだけではありませんでした。
勇魚は彼らの武器訓練のために場所を提供しますが、合宿中にメンバーの一人が情報を週刊誌に売っていたことが発覚します。この裏切りをきっかけに、自由航海団の内部で凄惨なリンチ殺人事件が発生。この事件は、彼らの理想が孕んでいた危うさを露呈させ、物語を破滅的な方向へと決定的に押し進めます。
警察の追跡を逃れた自由航海団の残党は、勇魚とジンの核シェルターに立てこもります。機動隊に包囲され、激しい銃撃戦が繰り広げられる中、勇魚は絶望的な状況に追い込まれていきます。人質となった息子、迫りくる国家権力、そして自らの内面で増大していく終末のイメージ。物語は、息詰まる籠城戦の果てに、衝撃的な結末へと向かっていきます。
「洪水はわが魂に及び」の長文感想(ネタバレあり)
大江健三郎の『洪水はわが魂に及び』は、1973年という時代が持つ独特の熱気と閉塞感を色濃く映し出した、記念碑的な作品です。発表の前年には連合赤軍によるあさま山荘事件が起きており、本作のプロットにはその影響が色濃く見られます。しかし、この小説が単なる事件の模倣で終わらないのは、大江健三郎の圧倒的な想像力が、社会的な事件を個人の内面世界におけるカタストロフ(破滅)へと昇華させているからです。
物語の中心にいるのは、知的障害を持つ息子ジンと核シェルターに籠る父親・大木勇魚です。勇魚は、世界の終わりを予感し、「樹木の魂」「鯨の魂」といった人間以前の存在と交感することで、現実から距離を置いています。この設定自体が、文明社会への深い不信感と、より根源的なものへの憧憬を示唆していると言えるでしょう。彼の瞑想は、単なる逃避ではなく、来るべき破滅を生き延びるための、彼なりの必死の祈りなのです。
そこへ現れるのが「自由航海団」と名乗る若者たちです。彼らもまた、社会からドロップアウトし、独自の終末論に基づいて行動する集団です。勇魚と彼らは、「世界の終わり」という一点において共鳴し、奇妙な共同体を形成します。世代も立場も違う彼らが結びつく様に、当時のカウンターカルチャーの雰囲気が反映されているように感じられます。しかし、その理想主義的な共同体は、内部の裏切りによって脆くも崩壊します。
この作品の凄みは、リンチ殺人という内部崩壊のプロセスを克明に描いた点にあります。ネタバレになりますが、「縮む男」と呼ばれるメンバーが情報を外部に漏らしたことをきっかけに行われる私的裁判と処刑の場面は、集団心理の恐ろしさを突きつけてきます。正義や理想を掲げた集団が、いかに容易に暴力的になり、内部の論理に絡め取られていくか。この描写は、連合赤軍の山岳ベース事件を想起させると同時に、より普遍的な組織や社会の病理をも暴き出しています。
『洪水はわが魂に及び』は、政治的な物語であると同時に、極めて私的な「父と子」の物語でもあります。勇魚にとって、息子のジンは守るべき存在であると同時に、理解の及ばない他者でもあります。鳥の声を正確に聞き分けるジンの能力は、言葉を介したコミュニケーションが絶対ではないことを示唆しています。この父子の関係は、大江健三郎自身の知的障害を持つ息子・大江光さんとの関係が色濃く反映されており、作品に切実な奥行きを与えています。
クライマックスの籠城戦は、まさに圧巻の一言です。機動隊の鉄球がシェルターを破壊し、水が激しく流れ込む中、勇魚の意識は現実と幻想の境界を越えていきます。ここで小説のタイトル『洪水はわが魂に及び』が、文字通りの意味を持つようになります。物理的な水だけでなく、世界の終わりのイメージという名の「洪水」が、彼の魂の最も深い場所にまで到達するのです。
この結末は、絶望を描きながらも、不思議な静けさと解放感をもたらします。勇魚は、シェルターの地下壕で、自らの内面世界において世界の終わりを幻視し、それを受け入れます。それは敗北であると同時に、彼が追い求めてきた根源的な世界との一体化でもあったのかもしれません。社会的な破滅と個人の魂の救済が、ここで分かちがたく結びついています。
『洪水はわが魂に及び』で描かれる若者たちの姿は、現代から見ると理解しがたい部分もあるかもしれません。彼らの行動はあまりに拙速で、夢想的です。しかし、既存の価値観や社会システムに対する根源的な不信感、そして来るべきカタストロフへの予感は、現代を生きる私たちにも無縁ではありません。
彼らは革命を志向していたわけではなく、来るべき災厄から自分たちの手で生き延びようとする、ある種のサバイバーでした。その純粋さが、結果的に内部での粛清や外部との衝突という最悪の事態を招いてしまう皮肉は、理想主義が陥りがちな罠を描いて鋭いです。
この作品における「洪水」とは、単なる自然災害や核戦争のメタファーにとどまりません。それは、制御不能な暴力性、情報、あるいは社会の圧力といった、個人の内面を侵食するあらゆるものの象徴として読み解くことができます。勇魚がシェルターに籠ったのは、そうした外部からの「洪水」を避けるためでした。
しかし、皮肉にも彼は「自由航海団」という別の「洪水」を自ら招き入れてしまいます。そして最終的には、物理的な放水と、自らの内から湧き上がる終末のイメージという、二重の「洪水」に飲み込まれていくのです。この多層的な構造が、『洪水はわが魂に及び』という作品に、時代を超えた普遍性を与えています。
ネタバレになりますが、最終的に勇魚は最後まで抵抗を続けます。しかしその抵抗は、もはや社会に対するものではなく、自らの運命を引き受け、魂の尊厳を守るための戦いであったように思えます。彼は、世界の終わりという究極の状況において、息子を守り、自らの信じる世界観を貫き通そうとしたのです。
この物語には、明確な救いや希望が描かれているわけではありません。むしろ、登場人物たちは次々と破滅へと向かっていきます。しかし、その破滅の過程で垣間見える人間の意志の強さ、あるいは脆さ、そして父と子の絆といったものに、読む者は心を揺さぶられます。
『洪水はわが魂に及び』は、非常に重厚で、読解には体力を要する作品です。しかし、その文章の密度と、描かれる世界の深さは、他の作品では味わえない圧倒的な読書体験をもたらしてくれます。特に、世界の終わりや社会のあり方に疑問を感じている人にとっては、多くの示唆を与えてくれるはずです。
物語の結末の解釈は、読者一人ひとりに委ねられています。勇魚が見た幻は、単なる狂気だったのか、それとも真実の世界の姿だったのか。明確な答えはありません。しかし、その問い自体が、私たちが生きるこの現実世界を、これまでとは少し違った視点から見つめ直すきっかけを与えてくれます。
この小説が発表された1970年代と現代とでは、社会状況は大きく異なります。しかし、「明日なき人類の嘆きと怒り、恐れと祈り」というテーマは、今なお古びていません。むしろ、環境問題や社会の分断、先行きの見えない不安が広がる現代においてこそ、『洪水はわが魂に及び』は新たな意味を持って私たちの胸に迫ってくるのではないでしょうか。
物語の核心に触れる最後のネタバレとして、勇魚は肉体的には滅びますが、彼の魂は「鯨」や「樹木」といった、より大きな存在と一体化することで、ある種の永遠性を獲得したと解釈することも可能です。それは、大江健三郎が一貫して描いてきた「魂の救済」というテーマの一つの到達点と言えるかもしれません。
『洪水はわが魂に及び』は、読む者を選ぶ作品かもしれませんが、一度その世界に足を踏み入れれば、忘れがたい強烈な印象を残す傑作です。絶望の淵から希望の光を探そうとする人間の姿を描いた、文学の力を感じさせる一冊として、強くお勧めします。
まとめ:「洪水はわが魂に及び」のあらすじ・ネタバレ・長文感想
この記事では、大江健三郎の長編小説『洪水はわが魂に及び』について、物語の概要から核心に触れる部分まで、詳しく見てきました。知的障害を持つ息子と核シェルターで暮らす主人公が、終末を信じる若者グループと関わることで、破滅的な結末へと突き進む物語でした。
あらすじのセクションでは、物語の導入部から、若者グループとの出会い、そして籠城戦へと至るまでの展開を追いかけました。社会から隔絶された父子の日常が、外部からの闖入者によっていかに崩壊していくかが、この物語の大きな駆動力となっています。
さらに、ネタバレを含む長文感想のセクションでは、作品の背景にある連合赤軍事件との関連性や、父と子の関係、そして「洪水」というタイトルが象徴するものについて深く掘り下げました。この作品が単なる社会派小説にとどまらず、個人の内面世界における普遍的なテーマを描いていることをお伝えできたかと思います。
『洪水はわが魂に及び』は、暴力と絶望に満ちた物語でありながら、その先に人間の魂のありようを見据えようとする、非常に射程の長い作品です。この記事が、皆さんがこの難解ながらも魅力的な傑作に触れるきっかけとなれば、これほどうれしいことはありません。