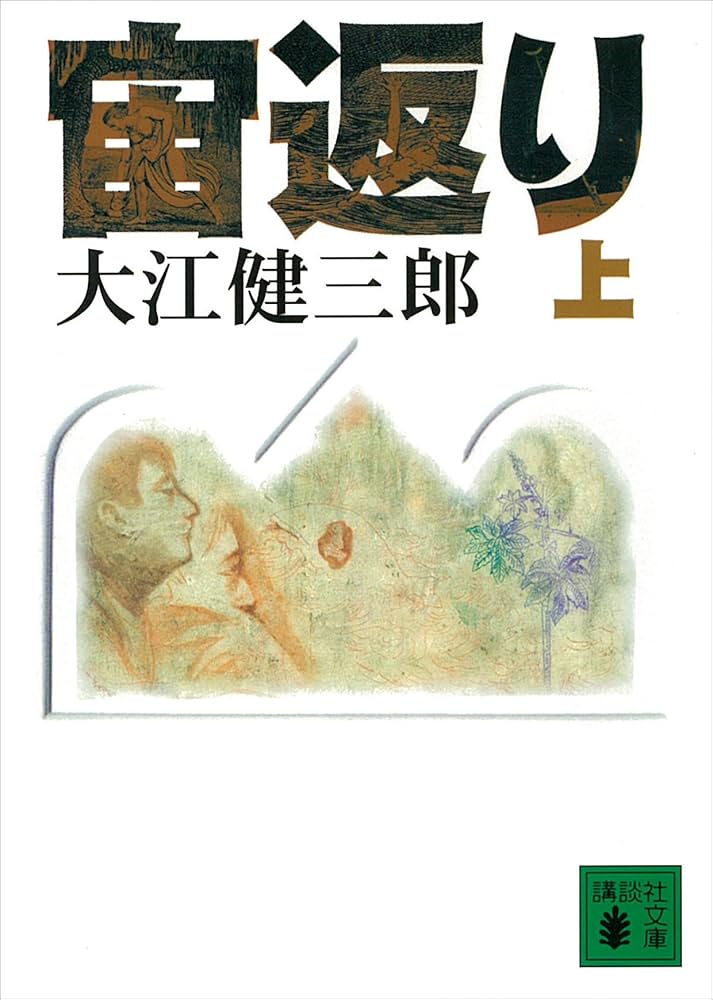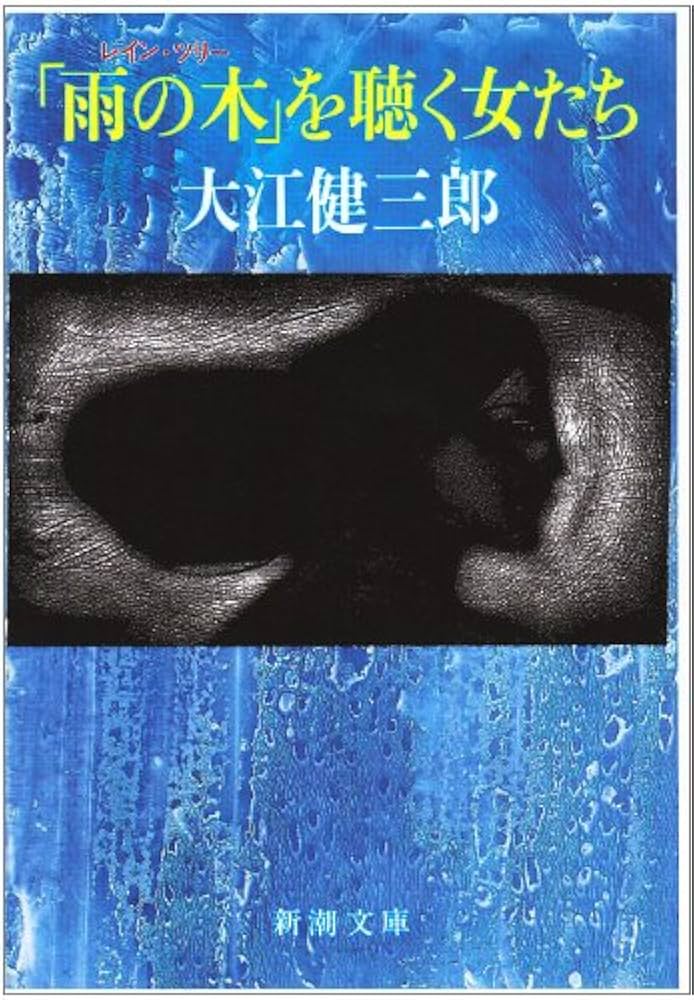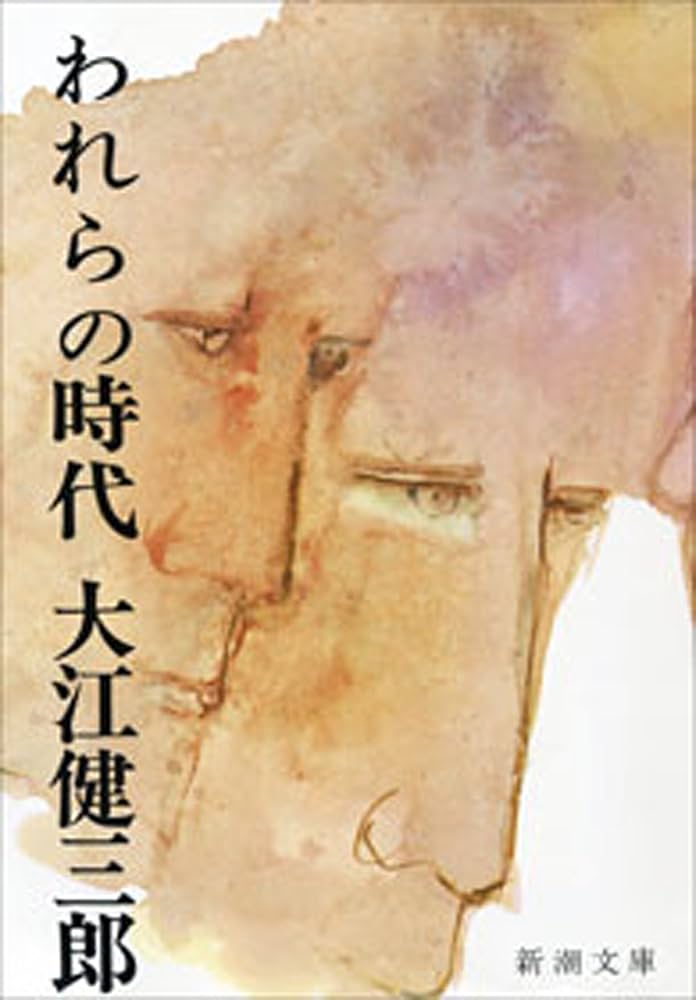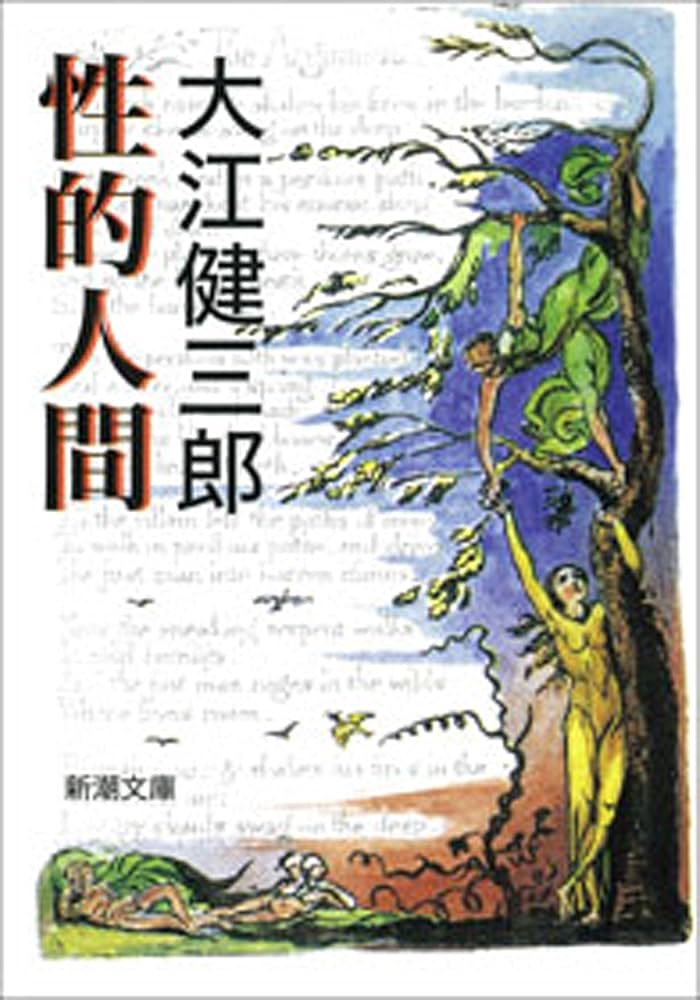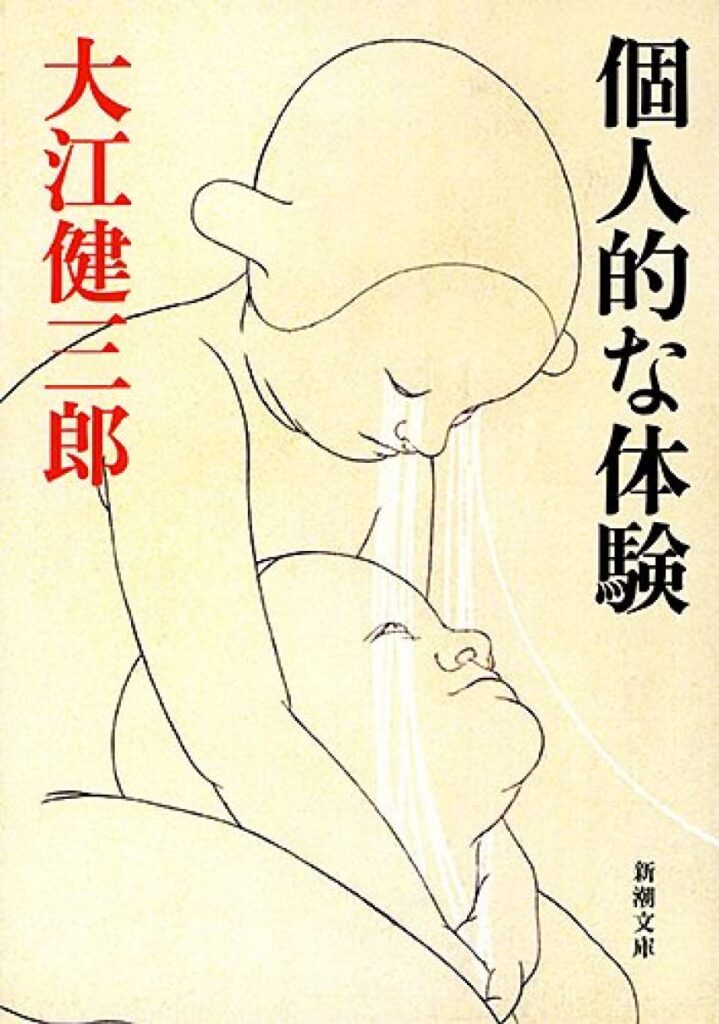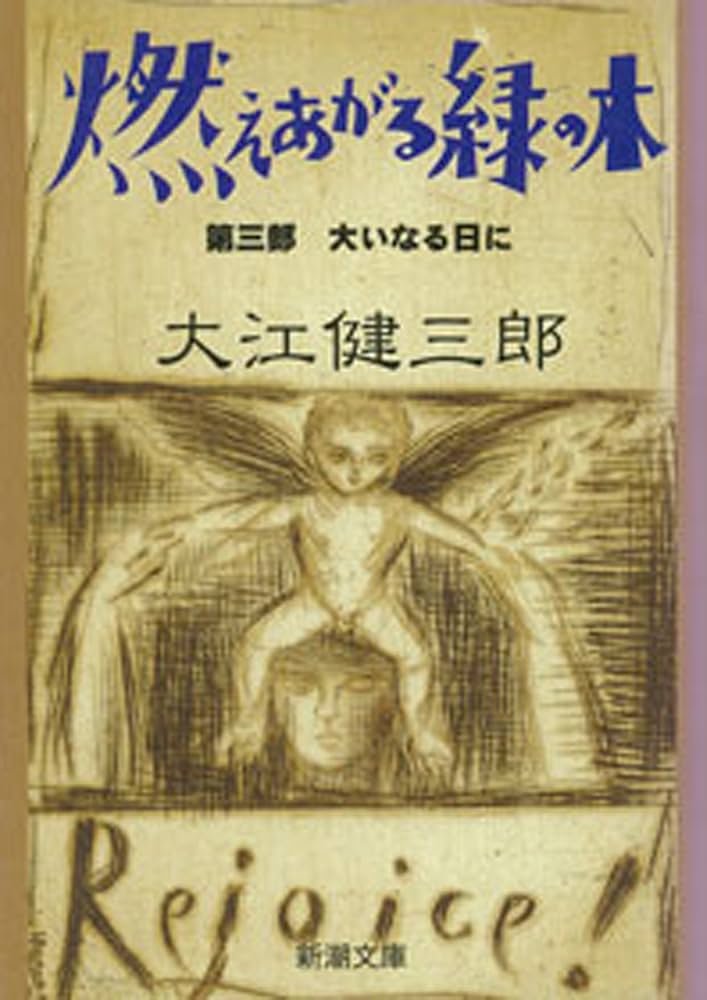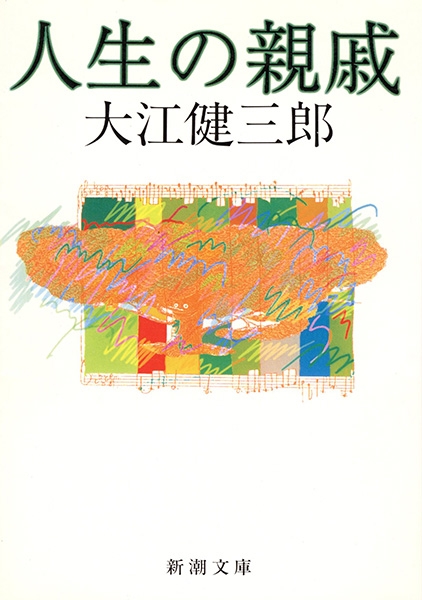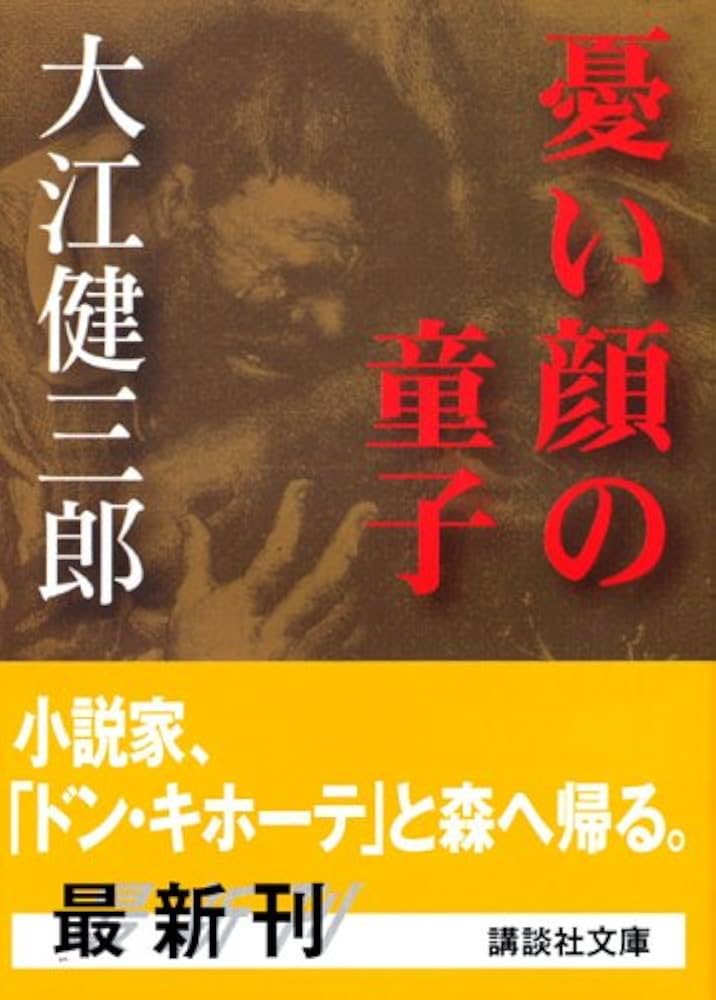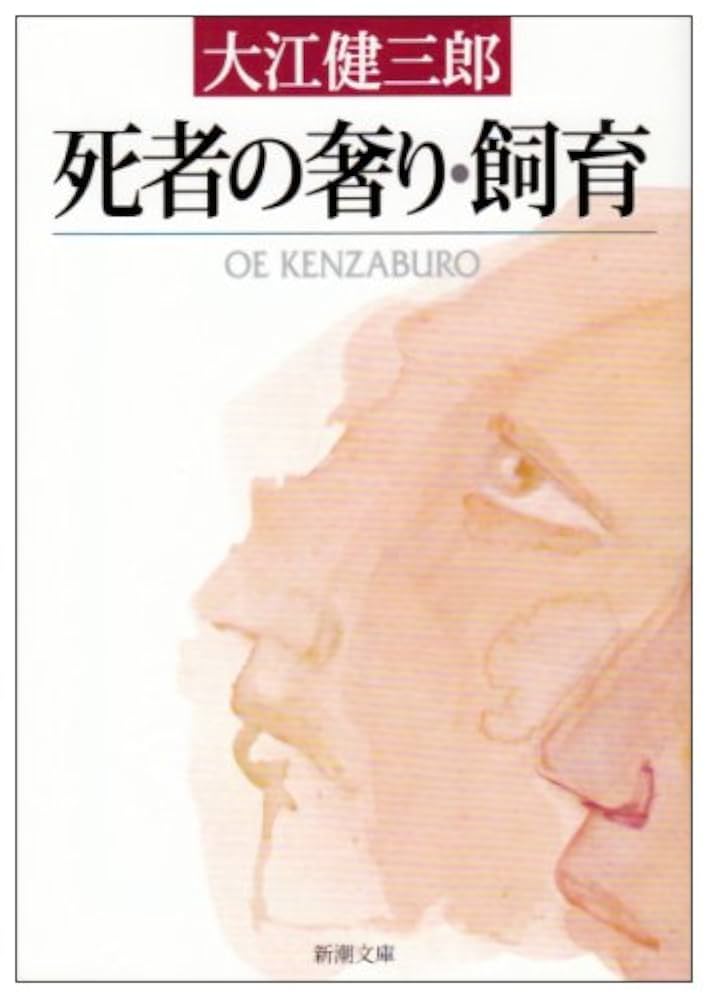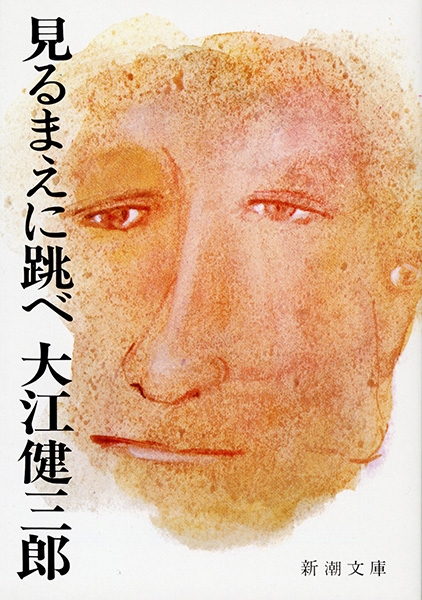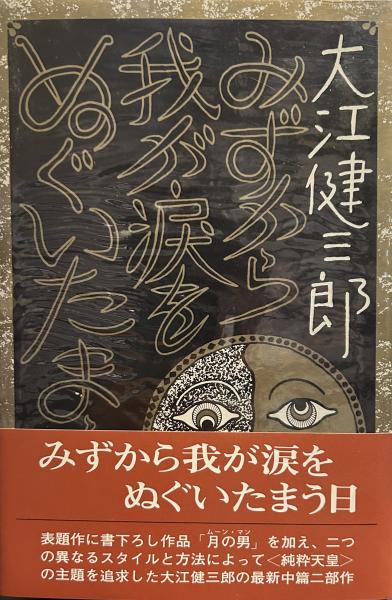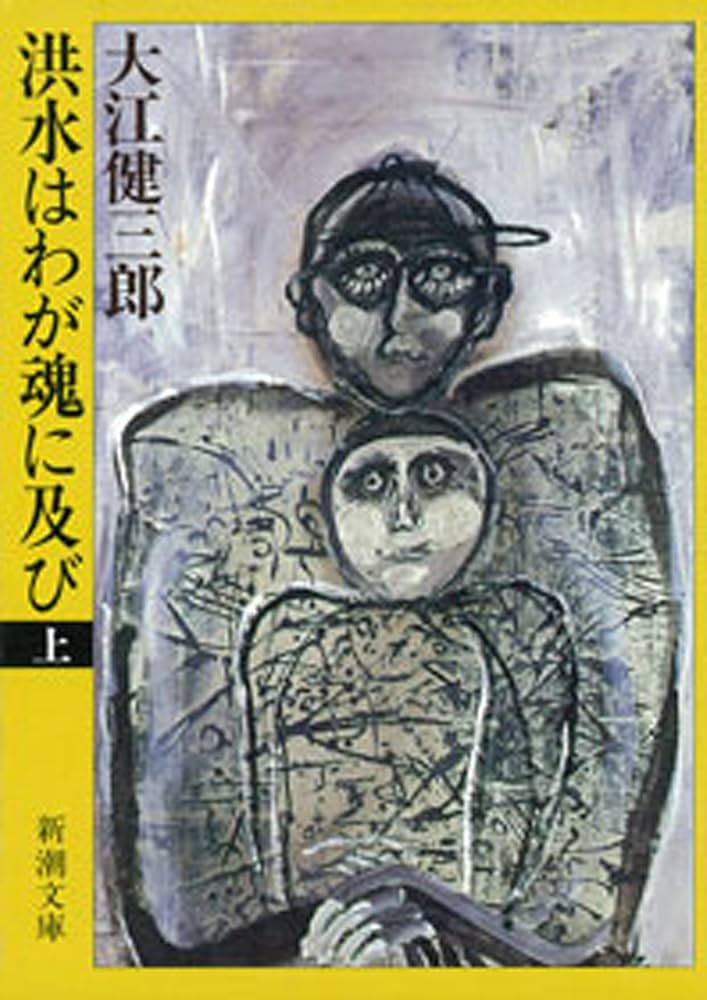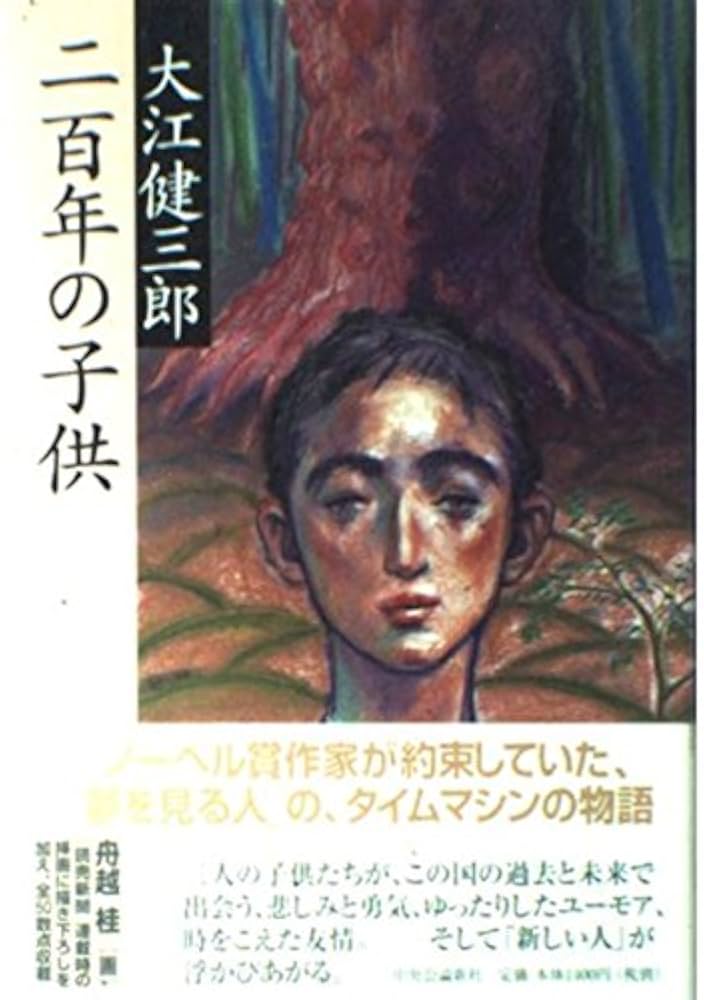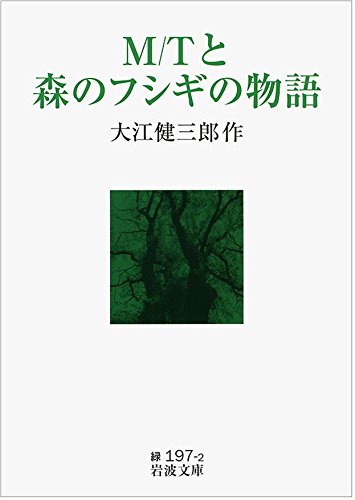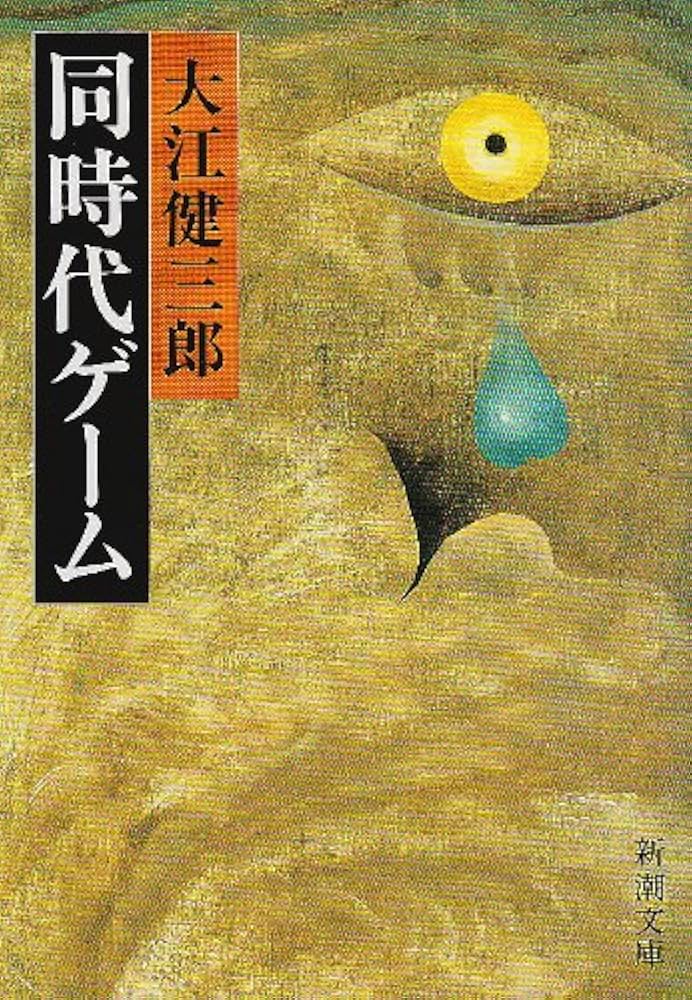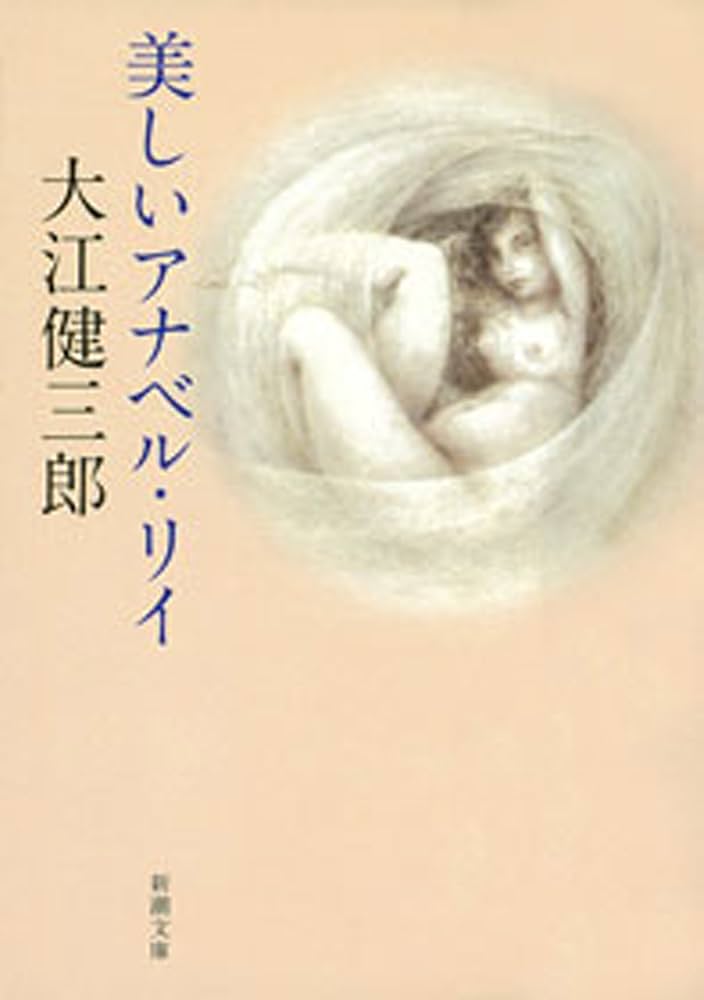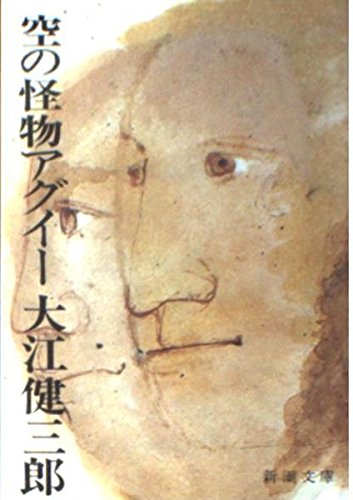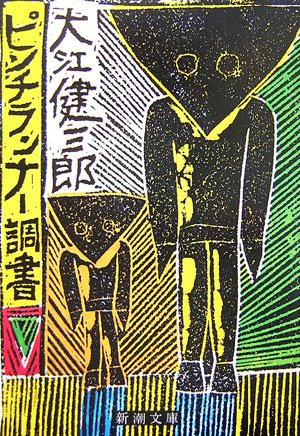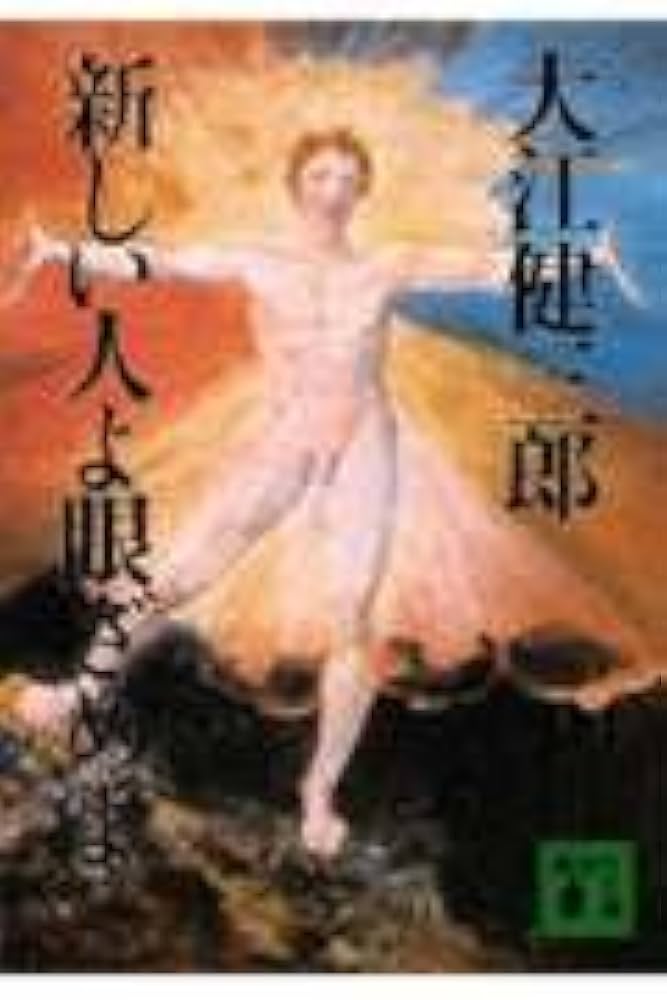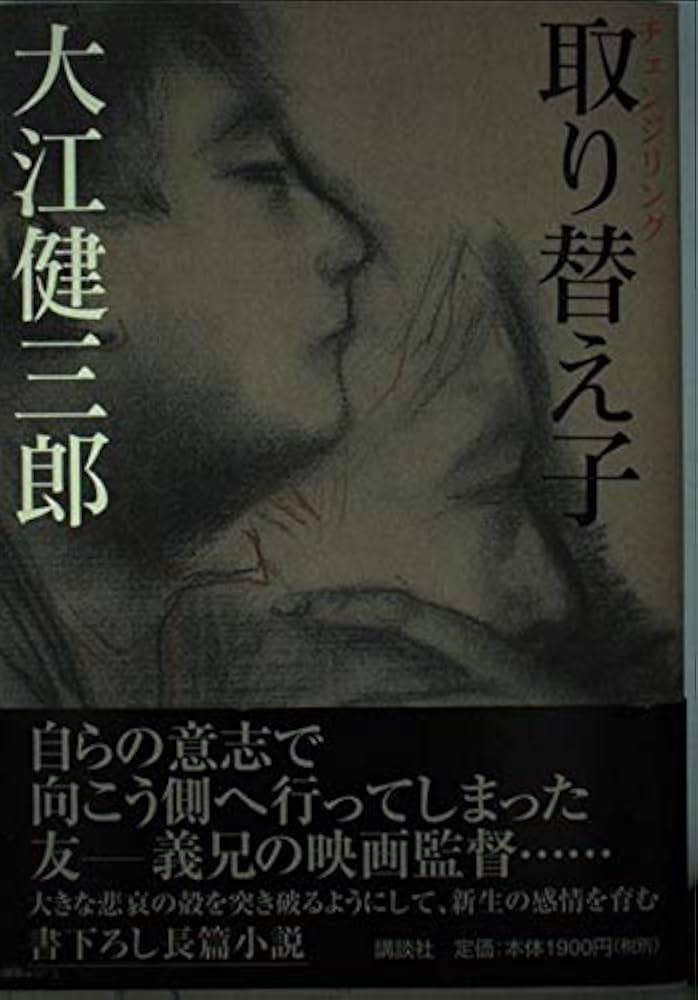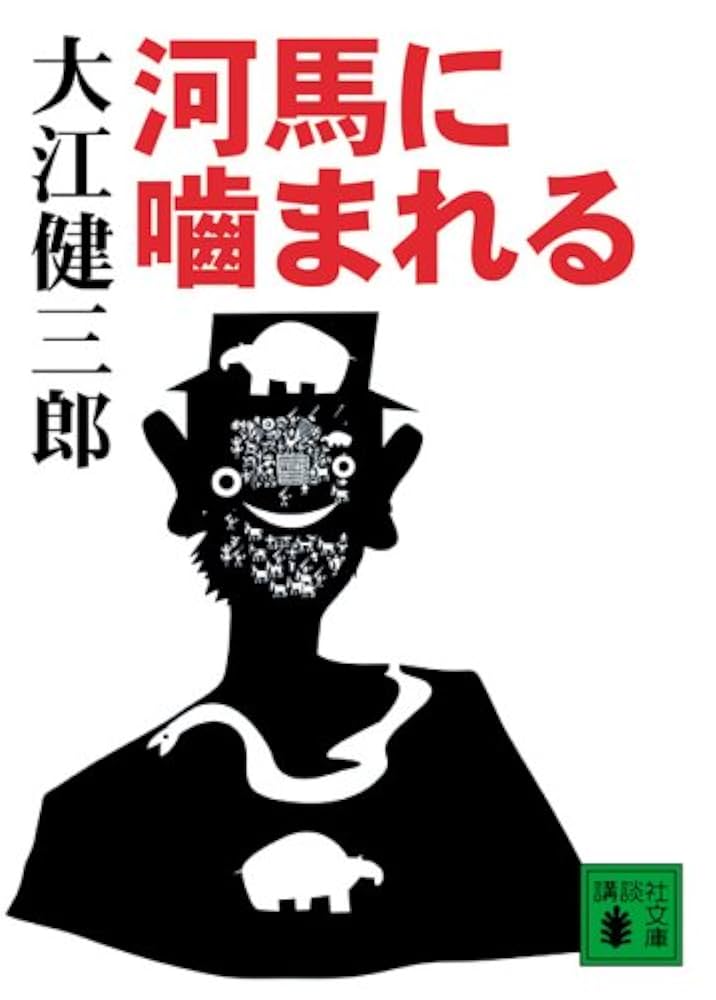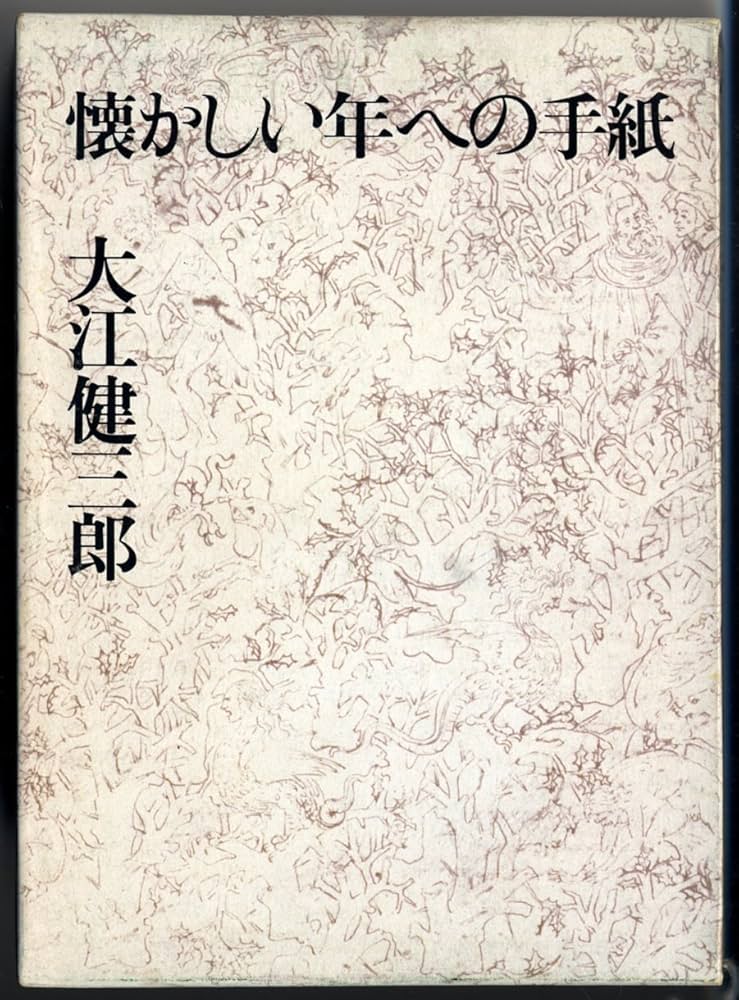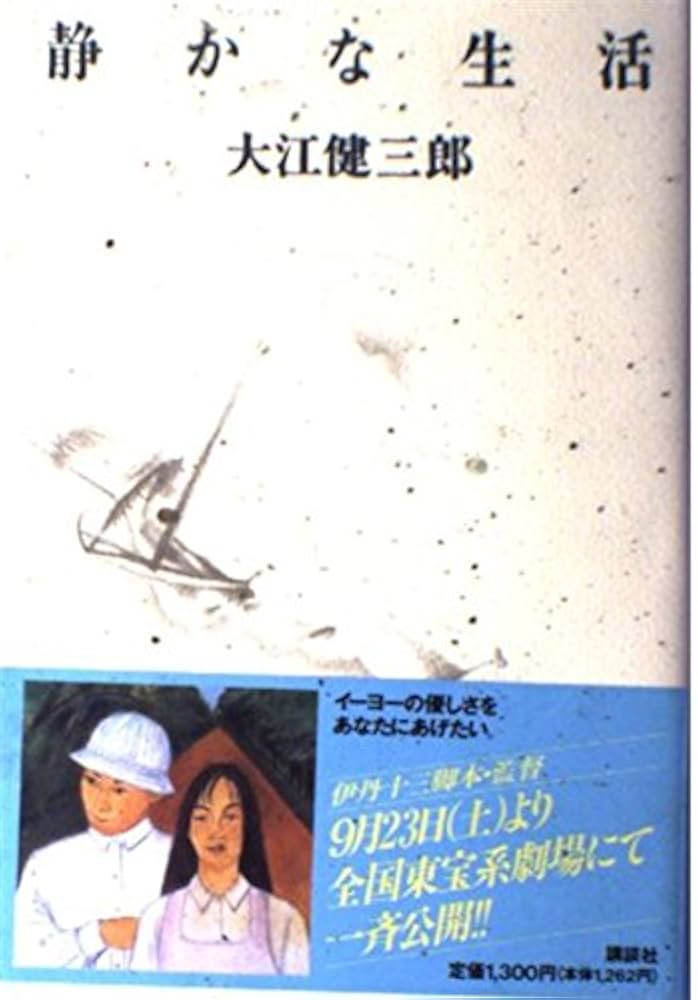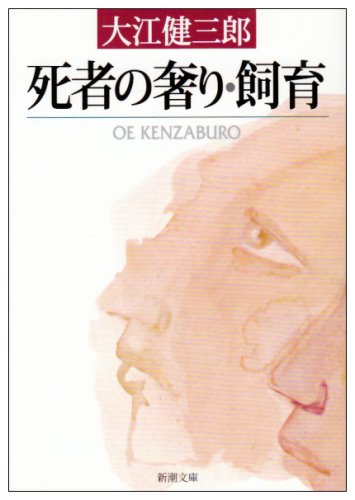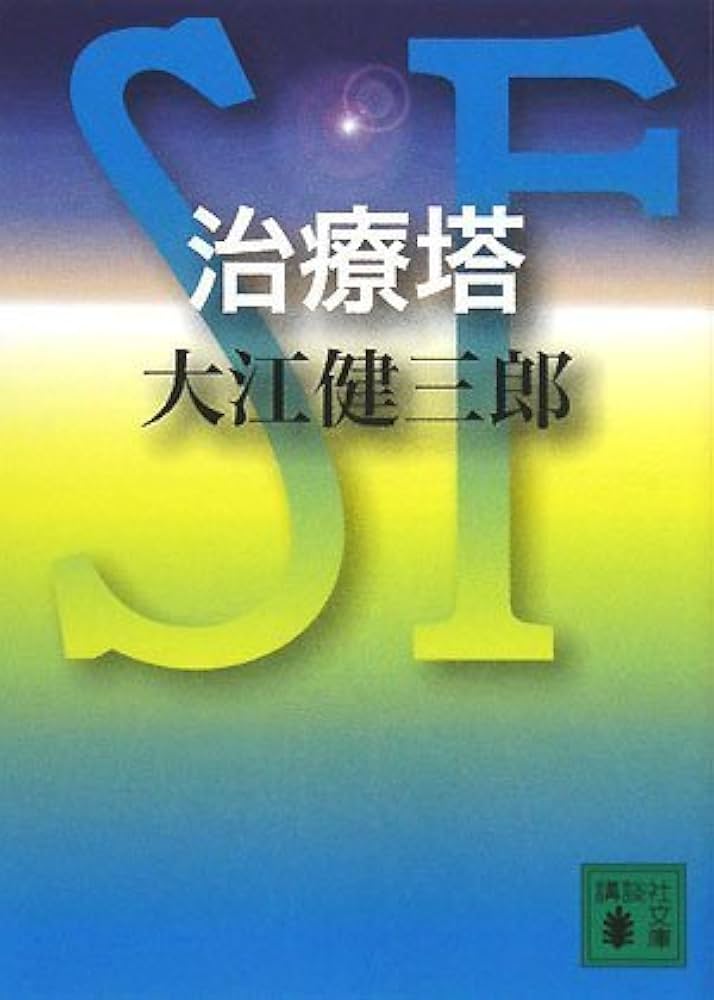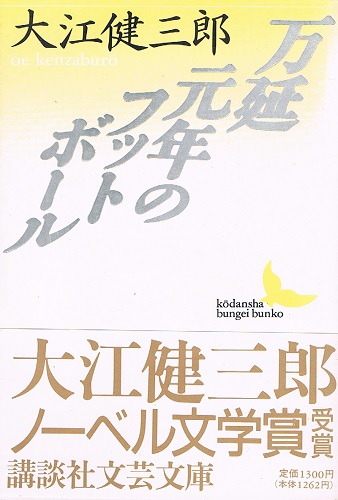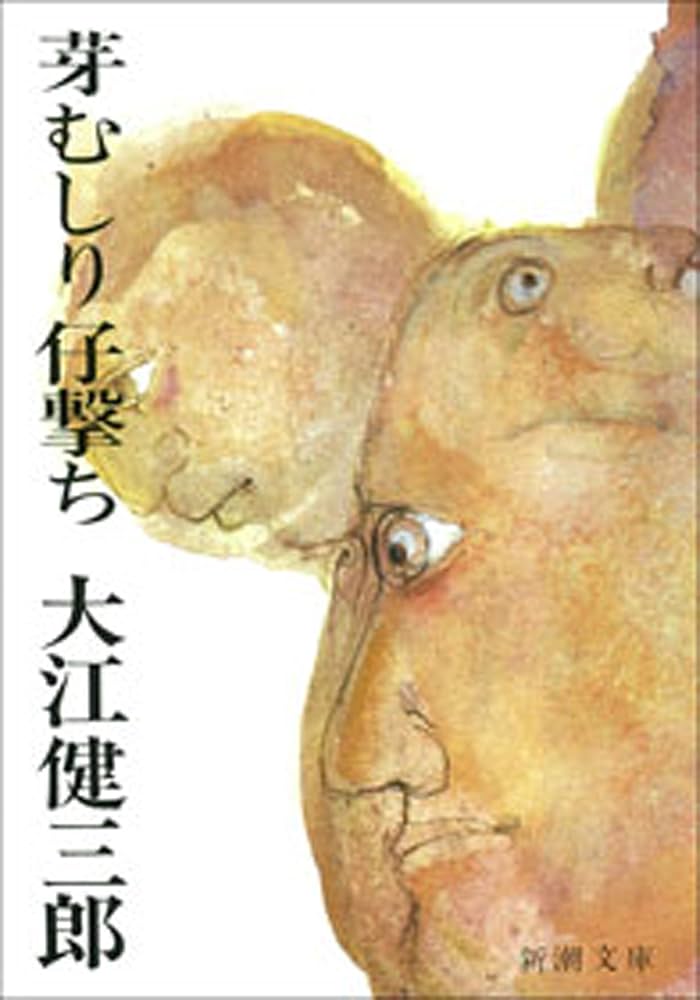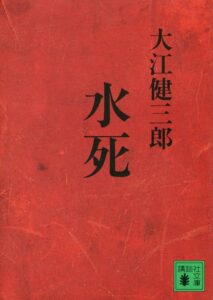 小説「水死」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。本作は、ノーベル賞作家である大江健三郎が、自身の作家人生における根源的なテーマ「父の死」に正面から挑んだ、壮大かつ深遠な物語です。虚実が入り混じる複雑な構成の中に、個人の記憶と国家の歴史が色濃く描き出されています。
小説「水死」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。本作は、ノーベル賞作家である大江健三郎が、自身の作家人生における根源的なテーマ「父の死」に正面から挑んだ、壮大かつ深遠な物語です。虚実が入り混じる複雑な構成の中に、個人の記憶と国家の歴史が色濃く描き出されています。
物語の核心に触れる部分も多いため、これから「水死」を読もうと考えている方はご注意ください。この記事では、物語の魅力やテーマ性を深く掘り下げるために、重要な展開についての具体的な言及、つまりネタバレを含んでいます。特に後半の感想部分では、結末に至るまでの詳細な流れを解説しています。
この重厚な物語をどう読み解けばいいのか、その一つの道標となれば幸いです。大江健三郎の文学の集大成ともいえる「水死」が、私たちに何を問いかけてくるのか。その世界をじっくりと味わっていきましょう。
この記事が、すでに「水死」を読了された方にとっては自身の解釈を深める一助となり、未読の方にとっては作品への興味をかき立てるきっかけになることを願っています。それでは、物語の深淵へと一緒に分け入っていきましょう。
## 「水死」のあらすじ
著名な老作家、長江古義人は、長年心に抱き続けてきたテーマ「水死小説」の執筆についに取り掛かります。それは、終戦の夏、故郷の四国の村で、増水した川へと短艇で漕ぎ出し謎の死を遂げた父の物語でした。父の死の真相を解き明かす鍵は、母が遺した「赤革のトランク」に眠っているはずでした。
期待を胸に故郷へ戻りトランクを開けた古義人でしたが、中身は空っぽで、彼の計画は早々に頓挫してしまいます。大きな衝撃を受けた古死人は、「大眩暈」という病に襲われ、心身ともに衰弱してしまいます。執筆への道を絶たれた彼の前に、一つの演劇集団が現れたことで、物語は思わぬ方向へと転がり始めます。
演劇集団「穴居人(ザ・ケイヴ・マン)」を主宰する穴井マサオと女優のウナイコ。彼らは、古義人の全作品を網羅する演劇を上演したいと申し出ます。古義人の筆が止まったことで、物語の焦点は彼らの演劇創作活動へと移っていきます。特にウナイコは、村に伝わる江戸時代の百姓一揆の伝説に強く惹かれ、これを舞台化しようと提案します。
こうして、古義人が描こうとした父の物語は、村の歴史、そして女性たちの抵抗の物語と交差していくことになります。ウナイコが抱える過去の秘密、村に現れる謎の人物、そして国家の影。古義人は、自身の創作活動とは別の形で、父の死の真相へと否応なく引き寄せられていくのでした。
## 「水死」の長文感想(ネタバレあり)
ここからは、「水死」の核心に触れるネタバレを含む長文の感想となります。物語の結末や重要な仕掛けについて詳しく述べていきますので、未読の方はご注意ください。この物語は、単なる父の謎を探るミステリーではなく、作家自身の魂の遍歴と日本の戦後史が刻み込まれた、巨大な文学的モニュメントといえるでしょう。
まず心を揺さぶられるのは、この「水死」という小説が、作者自身を色濃く反映した主人公・長江古義人の視点で描かれている点です。大江健三郎の故郷である四国の谷間の村を舞台に、知的障害を持つ息子との関係など、作家自身の人生と重なる要素が散りばめられています。虚構と現実が溶け合う中で、物語は圧倒的なリアリティを持って迫ってきます。
古義人が挑む「水死小説」は、単に父の死の真相を追うだけではありません。それは、彼にとって自身の存在の根源を探る旅でもあります。父を理解し、物語として再構築することは、息子である自分自身を理解することに他なりません。しかし、その試みは冒頭であっけなく頓挫します。この「書けない」という苦悩こそが、「水死」全体の通奏低音となっているのです。
物語の構造は非常に巧みです。「水死小説」という中心の物語が書けない代わりに、演劇集団「穴居人」の活動という新たな物語が挿入されます。この入れ子構造によって、古義人の父の物語は、村の伝説や歴史という、より大きな文脈の中に位置付けられていきます。一つの物語の挫折が、より豊かで複雑な別の物語を生み出すという展開は見事というほかありません。
主人公である長江古義人は、栄光ある老作家でありながら、非常に脆く、人間的な弱さを抱えた人物として描かれます。父の死という巨大なテーマに圧倒され、「大眩暈」に襲われる姿。知的障害を持つ息子アカリに対し、思わず心無い言葉を浴びせてしまい、深い断絶に苦しむ姿。彼の葛藤を通じて、私たちは創作の苦しみと家族の再生という普遍的なテーマに触れることになります。
古義人が追い求める父の人物像は、物語が進むにつれて多層的に変化していきます。当初は超国家主義的な思想を持つ、どこか近寄りがたい存在として語られます。しかし、物語が深まるにつれて、彼が村の伝統や共同体を深く愛していた側面が明らかになります。この父の複雑な内面こそが、「水死」という物語の最大の謎といえるでしょう。
この物語の重要な推進力となるのが、女優のウナイコです。彼女は、古義人の創作を外側から揺さぶり、物語を新たな地平へと導きます。彼女が村の百姓一揆の伝説、特に女性が主導したという点に強く惹かれるのには理由がありました。ここから、物語は個人の記憶の問題から、より大きな社会的な問題へと接続されていきます。
ウナイコは、かつて文部科学省の官僚である叔父によって性的暴行を受け、心に深い傷を負っていました。彼女が演劇を通じて一揆の物語を再現しようとするのは、自身の受けた暴力と、それに抵抗しようとする魂の叫びの表れでした。この強烈な告発の意志が、停滞していた古義人の物語を根底から突き動かすのです。これ以降の展開は、強烈なネタバレ要素を含みます。
「水死」において、女性たちの存在は極めて重要です。母が遺した空のトランク、村の伝説を主導した「メイスケ母」、そして魂の叫びを演劇に昇華させようとするウナイコ。彼女たちは、男性たちが作ろうとする大きな物語(国家やイデオロギー)の周縁にありながら、その欺瞞を暴き、物語の本質を指し示す存在として描かれています。
物語のクライマックスに向けて、大黄(だいおう)という決定的な人物が登場します。彼は古義人の父を「先生」と呼び、心酔していた男でした。彼が語り始める父の死の真相は、古義人の、そして読者の想像をはるかに超えるものでした。ここからが、この物語の核心に触れる最大のネタバレとなります。
大黄の口から語られる父の真実は衝撃的です。父は単なる超国家主義者ではなく、村に伝わる「王殺し」の思想に基づき、衰弱した天皇を「殺す」ことで日本を再生させようというクーデター計画に加担していました。しかし、その計画が村の神聖な森を破壊することを知り、国家の論理よりも共同体の伝統を選んで計画に反対したのです。
そして、川での「水死」は、計画失敗の責任を取るための単なる自殺ではありませんでした。それは、自らの魂を息子の古義人に乗り移らせ、意志を継がせようとする荘厳な儀式だったのです。父は、息子のために浮き袋を用意していました。この驚くべきネタバレによって、父の死の意味は完全に反転します。それは絶望の死ではなく、未来への希望を託すための儀式的な死だったのです。
この物語の結末は、暴力の連鎖という形で訪れます。ウナイコの叔父であり、国家権力の体現者である小河は、彼女の告発を阻止しようとします。その卑劣な行為に激怒した大黄は、小河を射殺してしまいます。そして大黄は、雨降る森の中へと消えていきます。父がそうであったように、彼もまた森と一体化することを選んだのかもしれません。
結局、古義人は「水死小説」を書き上げることを断念します。母がその小説化に反対していたことを知り、また、父の真実を物語として完全に捉えることは不可能だと悟ったからです。しかし、皮肉なことに、この「水死」という小説そのものが、父の死を巡る思索のすべてを描き切った、最高の「水死小説」として結実しているのです。
物語にはもう一つの救いがあります。それは、息子アカリとの関係です。父の死を巡る一連の出来事を経て、古義人はアカリと和解を果たします。父から子へ、そしてその息子へ。断絶しかけていた生命の繋がりが、静かに回復していく場面は、この重厚な物語における一条の光となっています。
「水死」は、大江健三郎がこれまで描いてきたテーマが凝縮された、まさに集大成と呼ぶにふさわしい作品です。父と子、神話と歴史、個人と国家、暴力と救済。これらの主題が、複雑なプロットと緻密な文体によって、一つの壮大なタペストリーのように織り上げられています。
読み終えた後に残るのは、ずっしりとした重い手応えと、不思議な静けさです。解き明かされた謎は、さらなる謎を生み、物語は完全には閉じられません。読者は、古義人と共に深い森の中に分け入り、その薄暗がりの中で思考を巡らせることになるでしょう。簡単な答えを与えてくれない、それこそが「水死」の魅力なのです。
この物語は、過去の歴史や個人の記憶と、私たちはどう向き合うべきかを問いかけてきます。物語ることの可能性と不可能性の狭間で格闘する作家の姿は、現代を生きる私たち自身の姿とも重なります。非常に読解には力が必要ですが、それに見合うだけの深い感動と知的興奮を与えてくれる傑作です。
## まとめ:「水死」のあらすじ・ネタバレ・長文感想
この記事では、大江健三郎の長編小説「水死」のあらすじと、核心に触れるネタバレを含む長文の感想を述べてきました。本作は、作家・長江古義人が謎に満ちた父の死を小説にしようと試みる過程で、自身の過去や国家の歴史と対峙していく物語です。
物語のあらすじとして、主人公が「水死小説」の執筆に挫折するところから始まり、演劇集団との出会いを経て、物語が思わぬ方向へ展開していく様を紹介しました。父の物語が、村の伝説やウナイコという女性の過去と交差していくことで、物語はより重層的になっていきます。
感想の部分では、父の死の驚くべき真相や、クライマックスの衝撃的な展開といった重要なネタバレに触れました。「水死」が、単なる家族の物語ではなく、国家による暴力や、魂の継承といった壮大なテーマを内包していることを解説しました。虚実の交錯する巧みな物語構造の魅力にも言及しました。
「水死」は、読者に多くの問いを投げかける、非常に深く重厚な作品です。簡単には読み解くことはできませんが、その分、読了後には計り知れない思索の時間を与えてくれます。大江文学の到達点ともいえるこの傑作に、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。