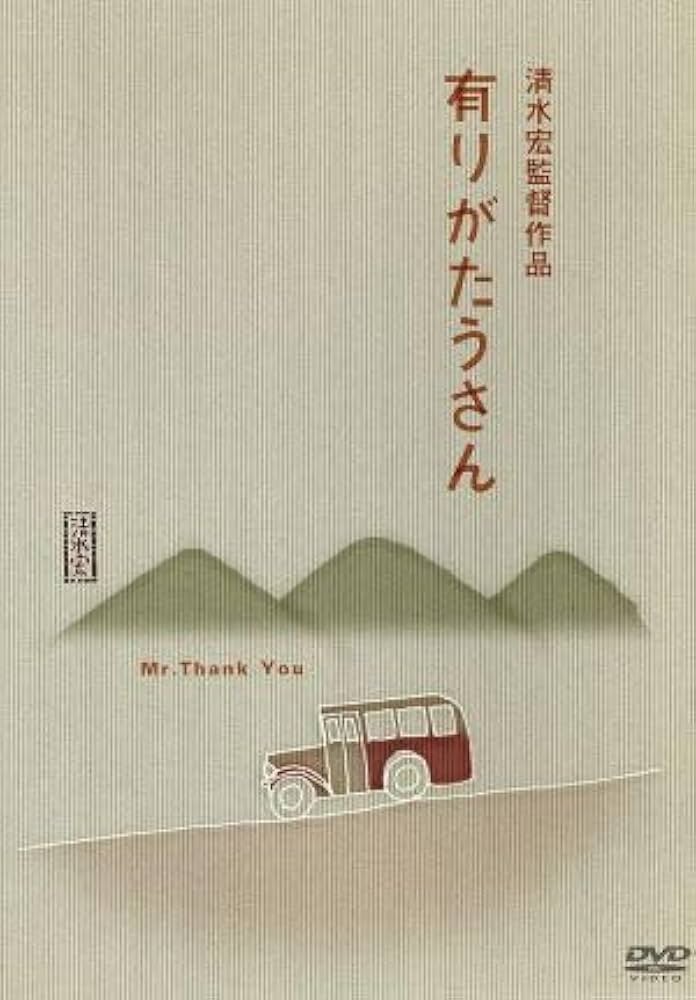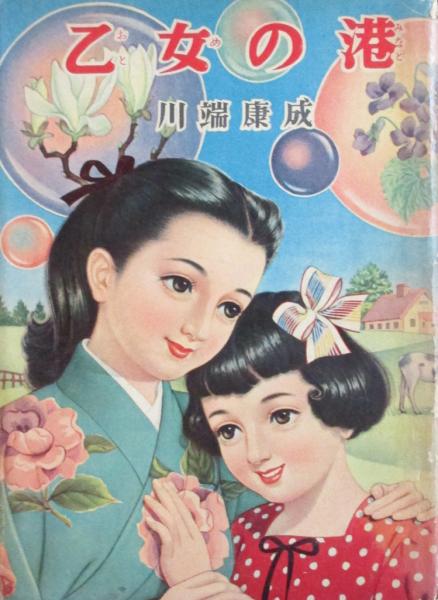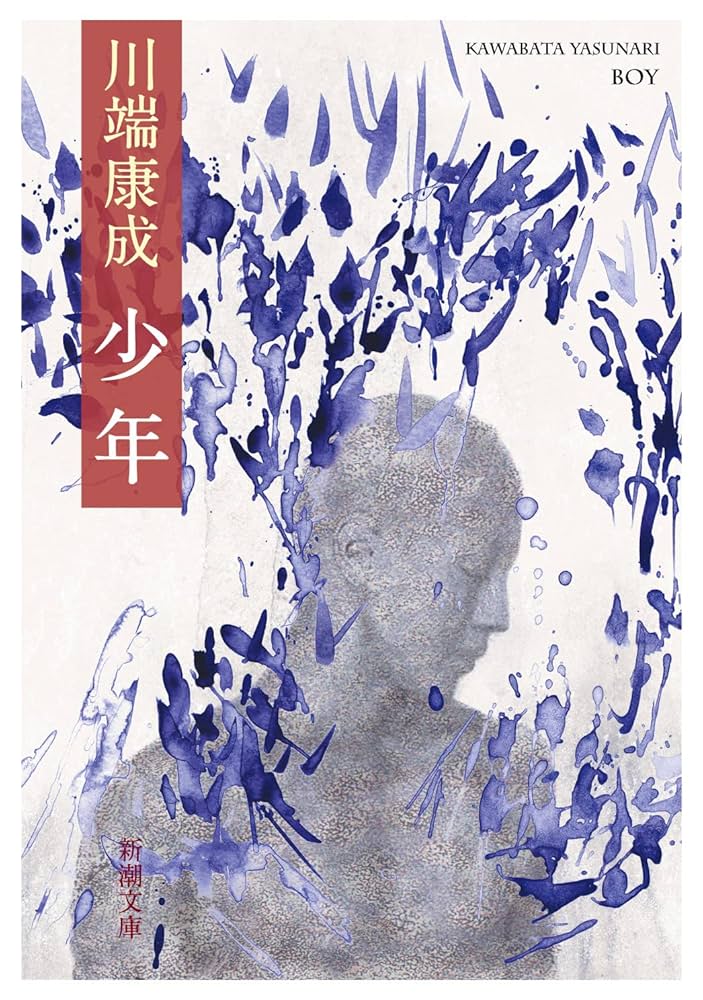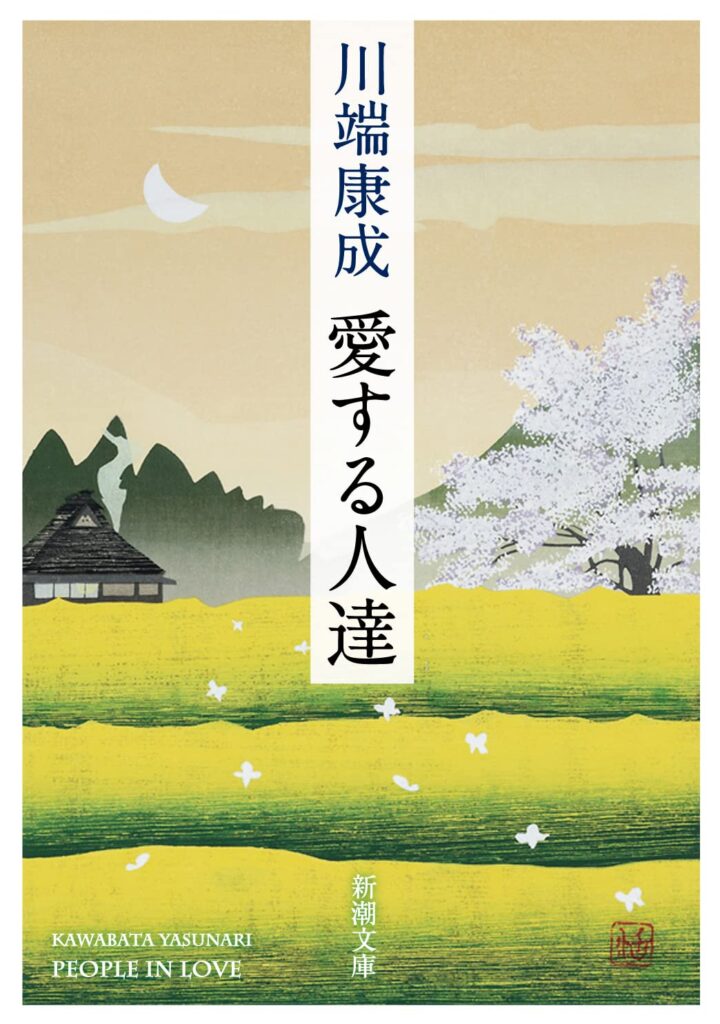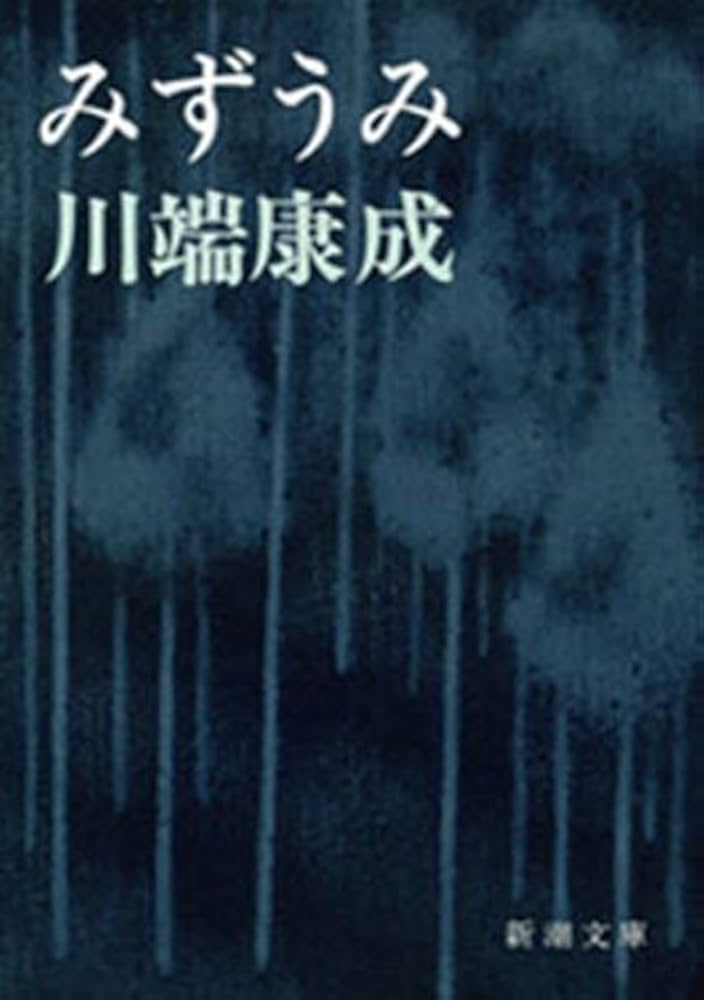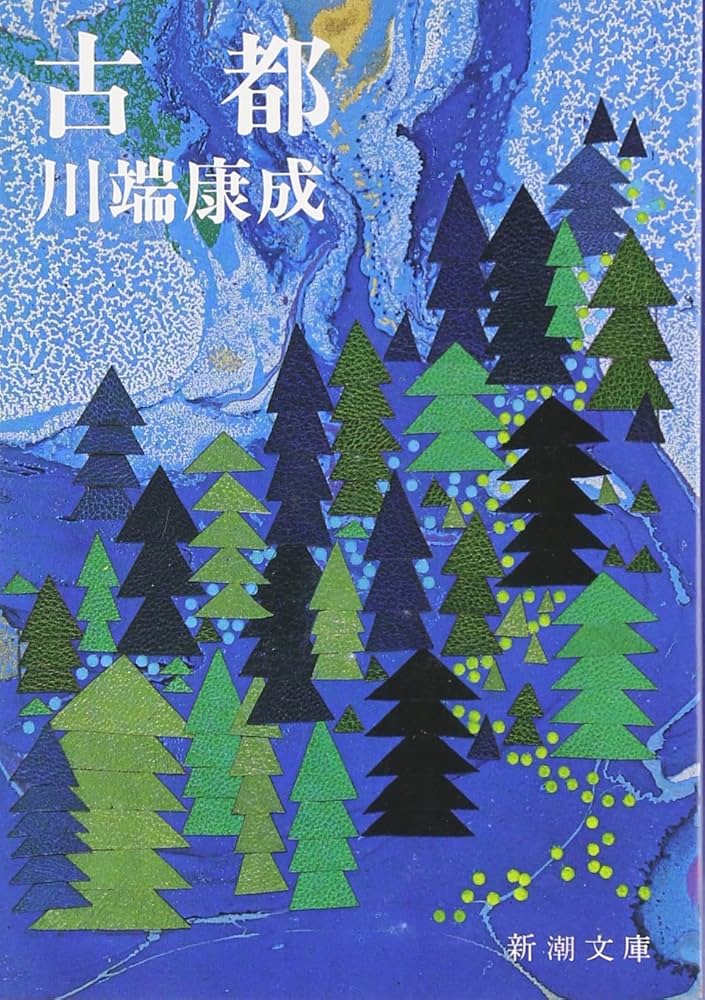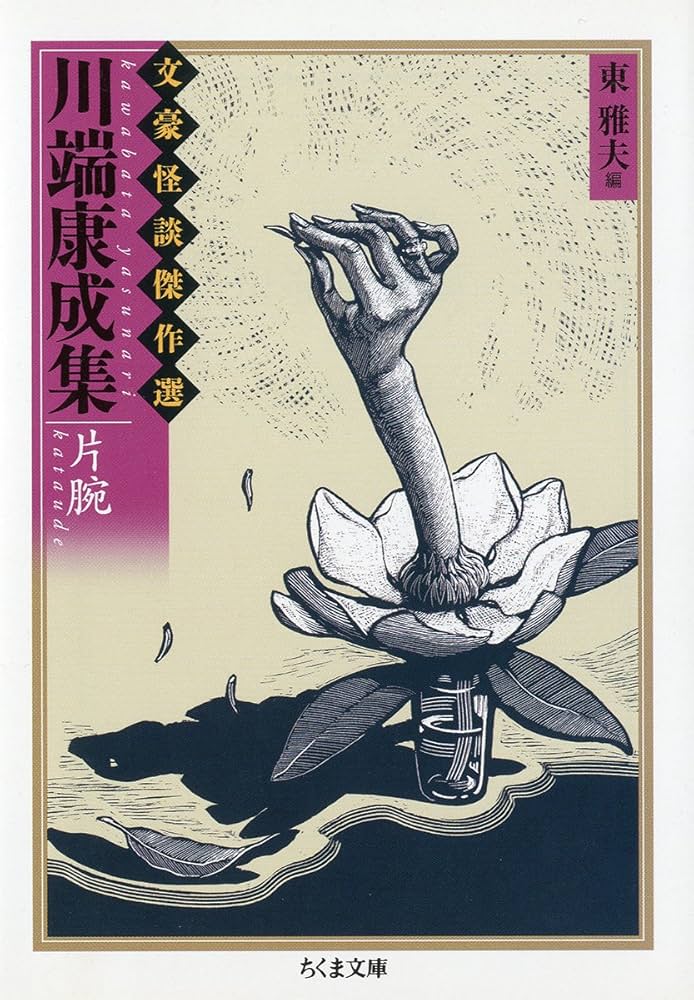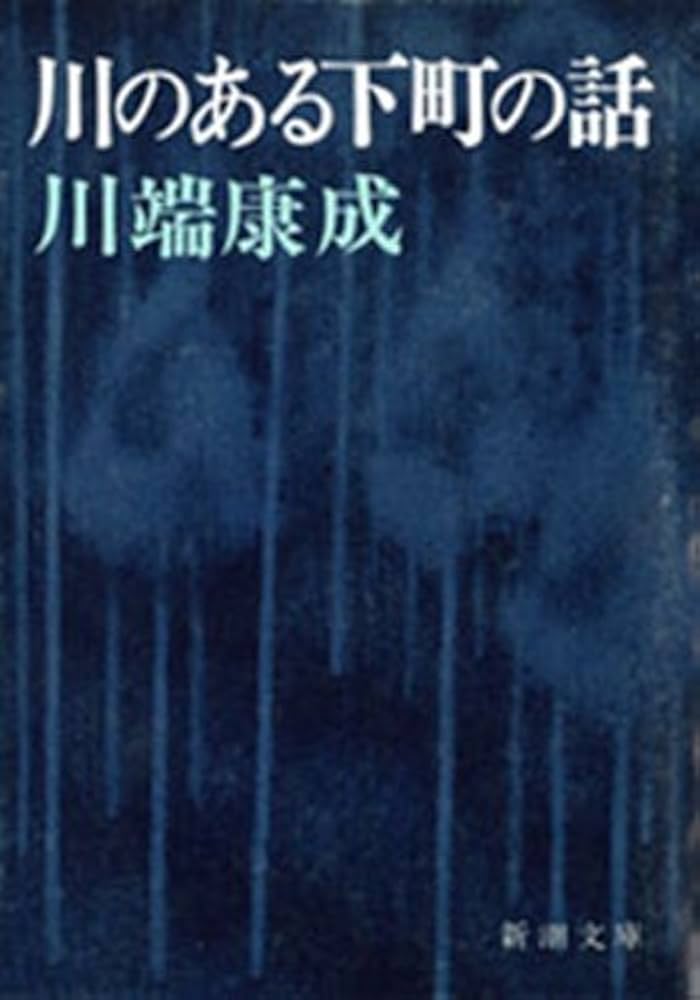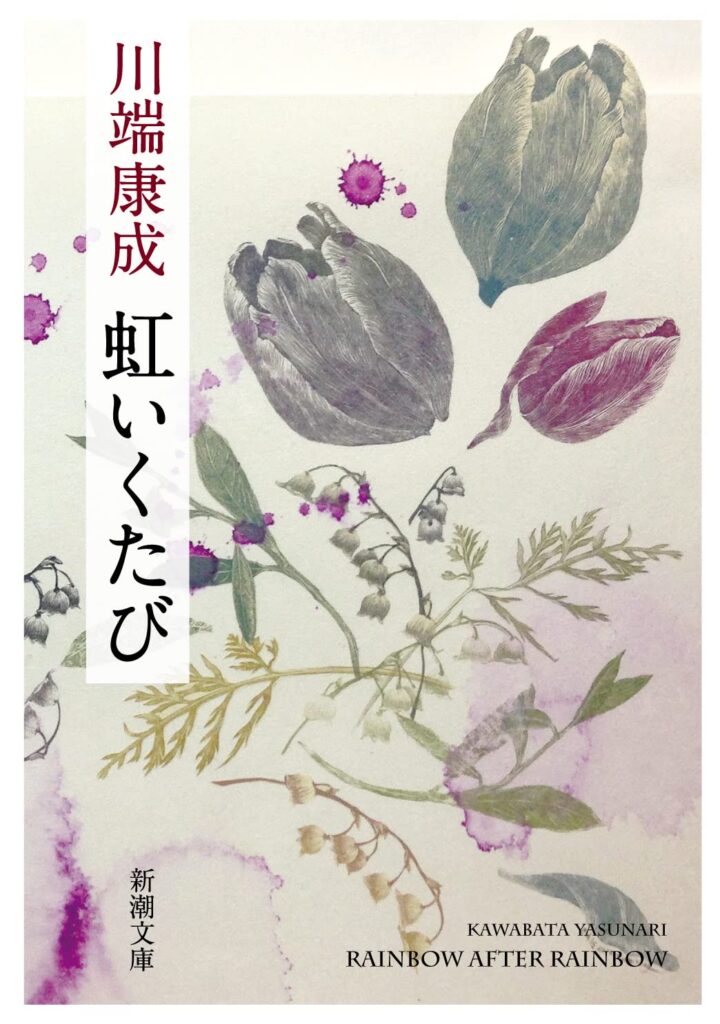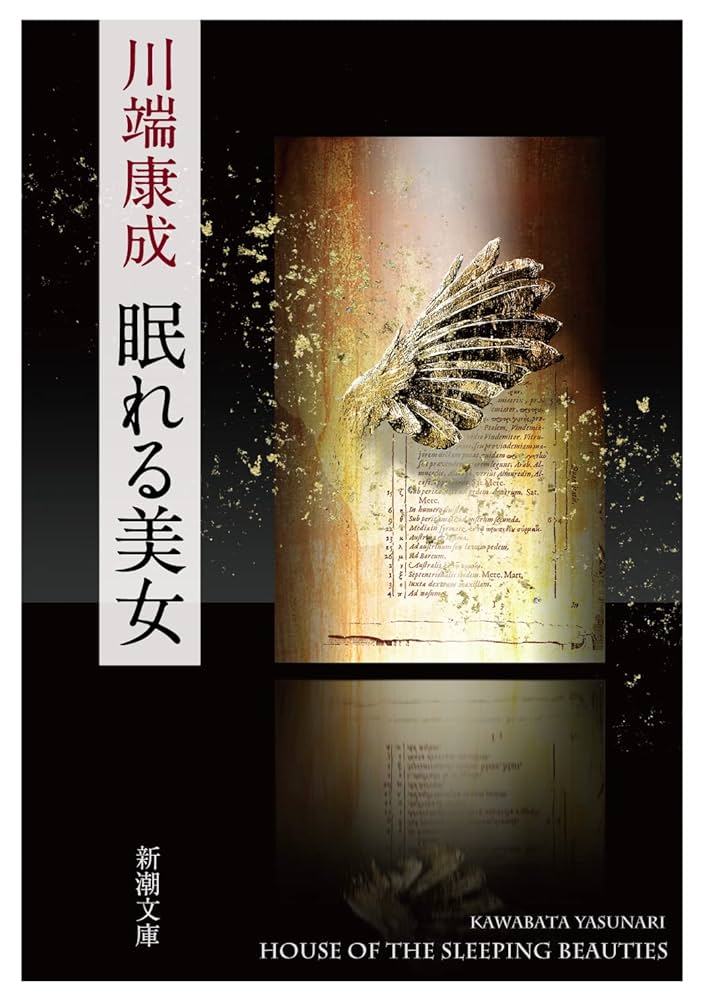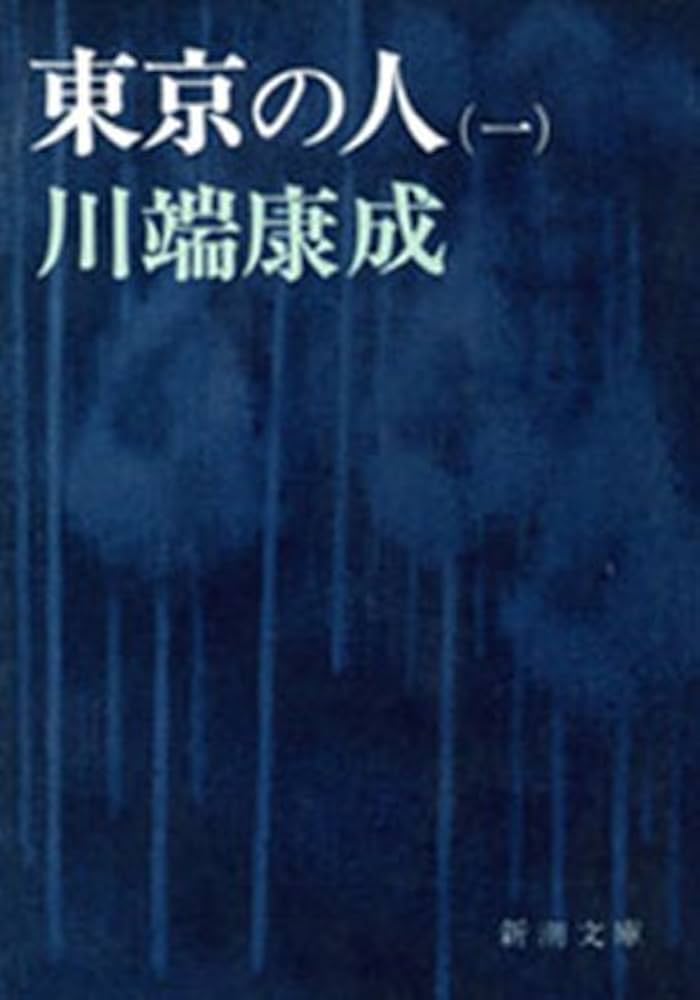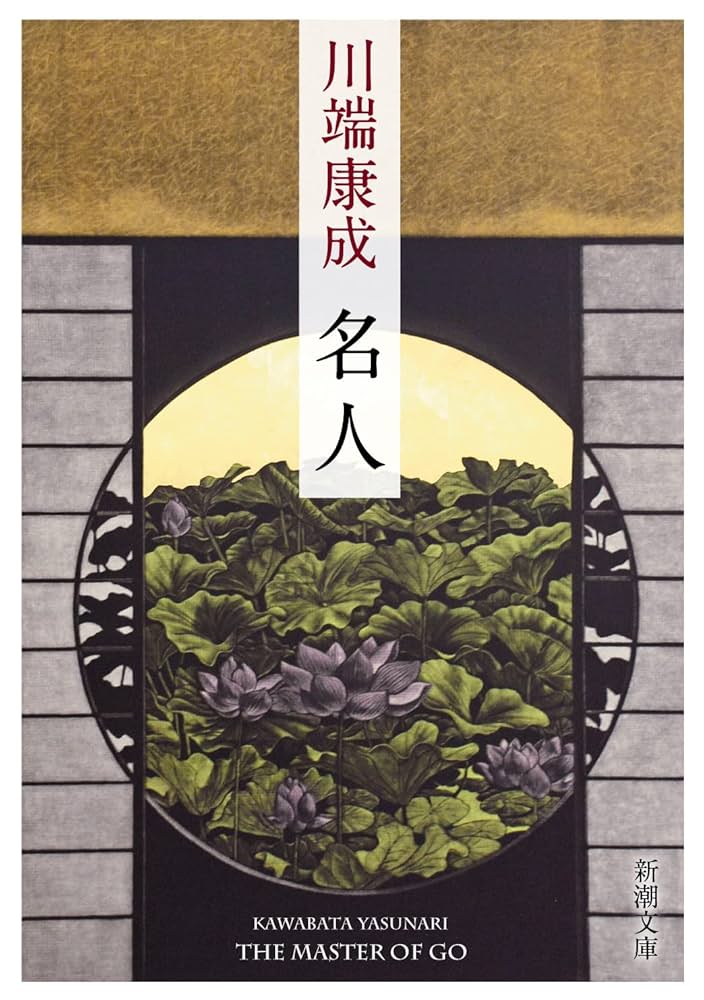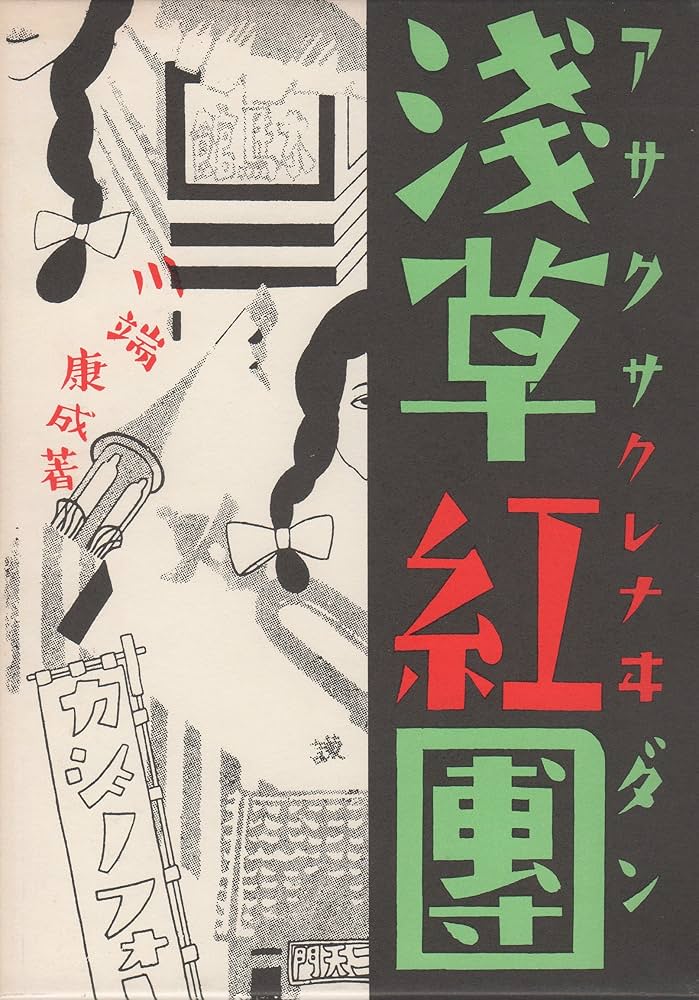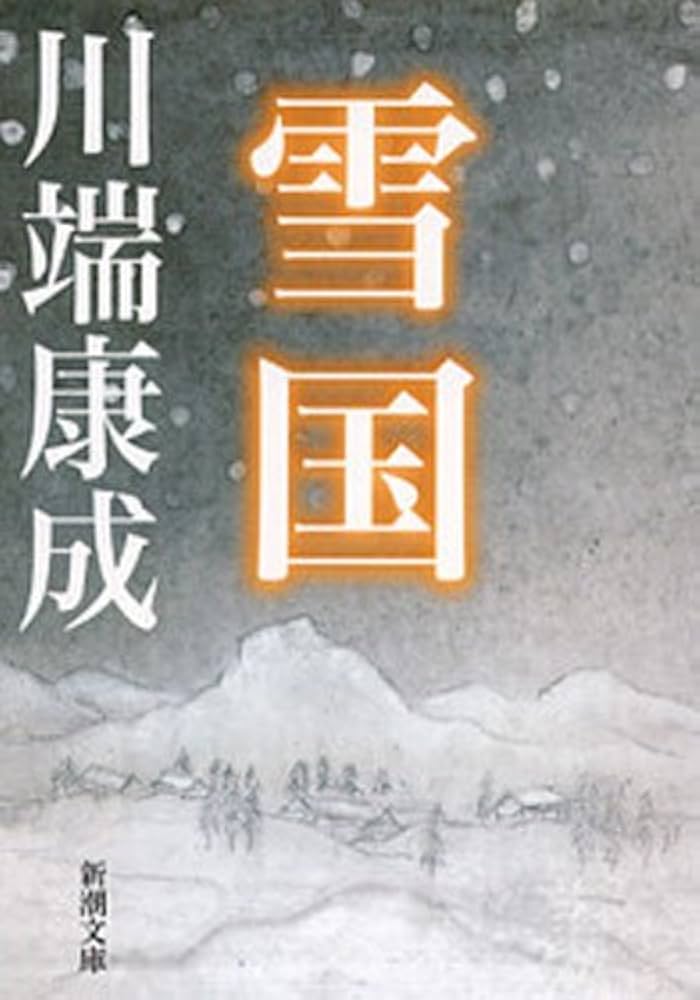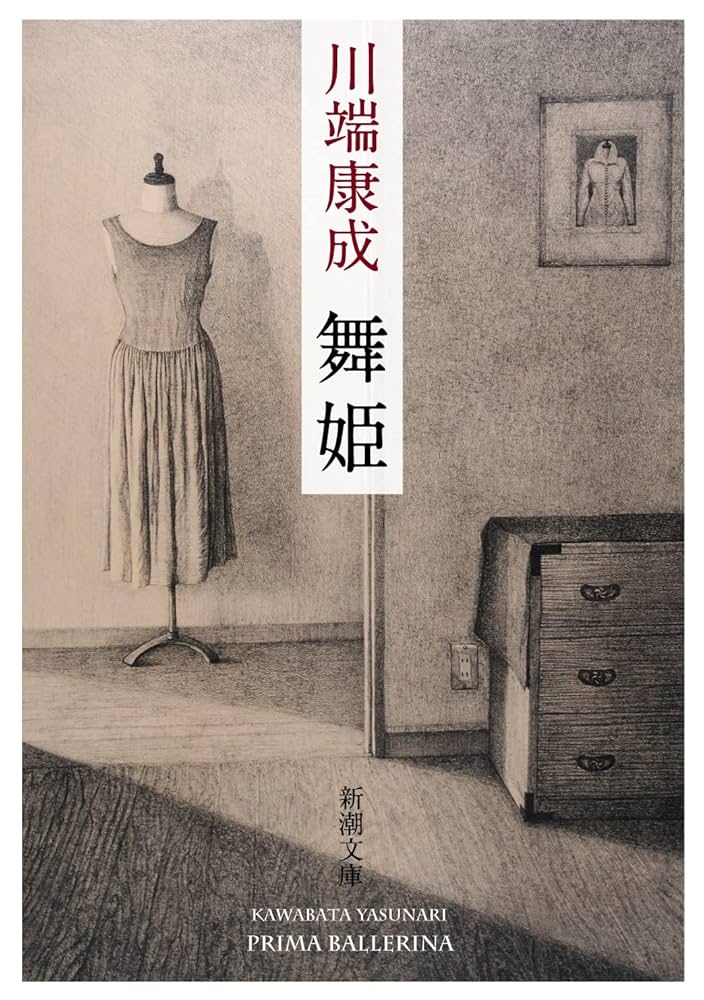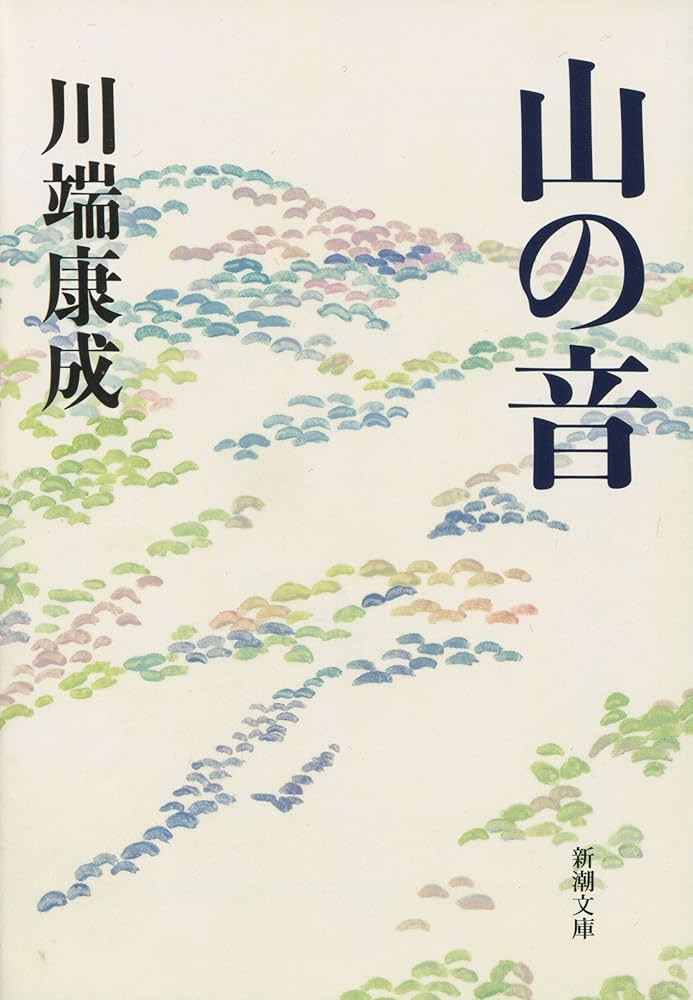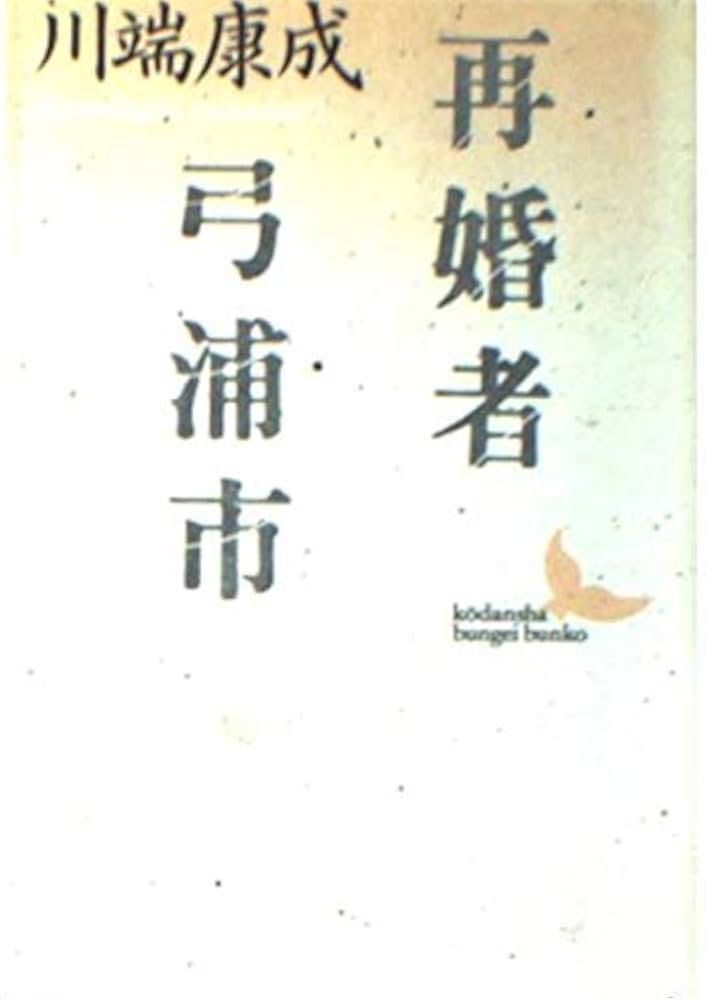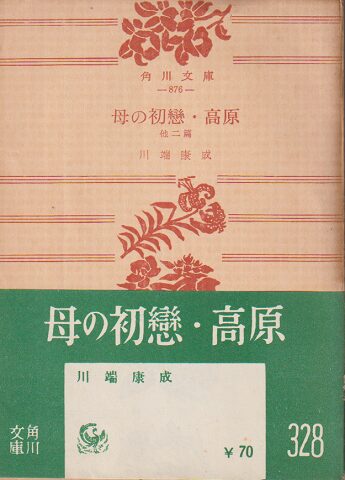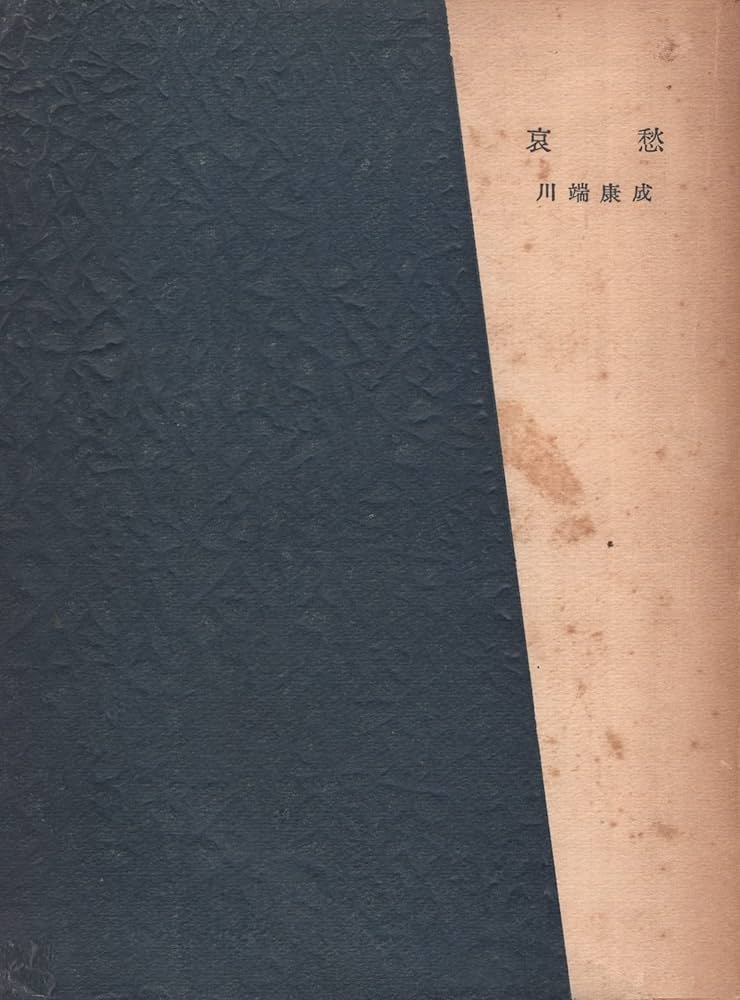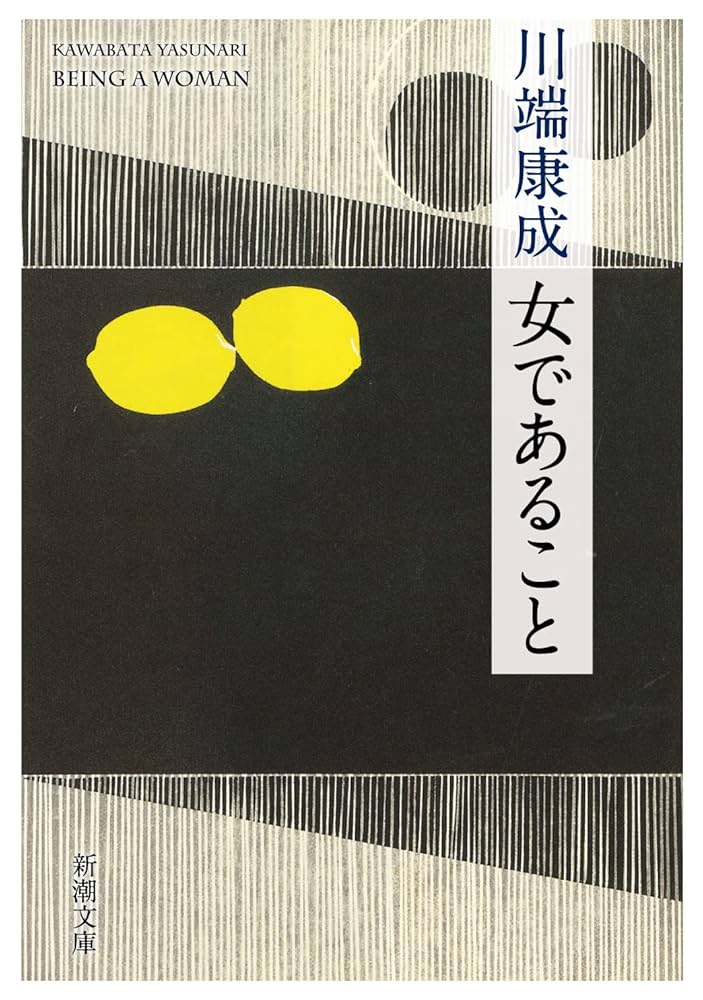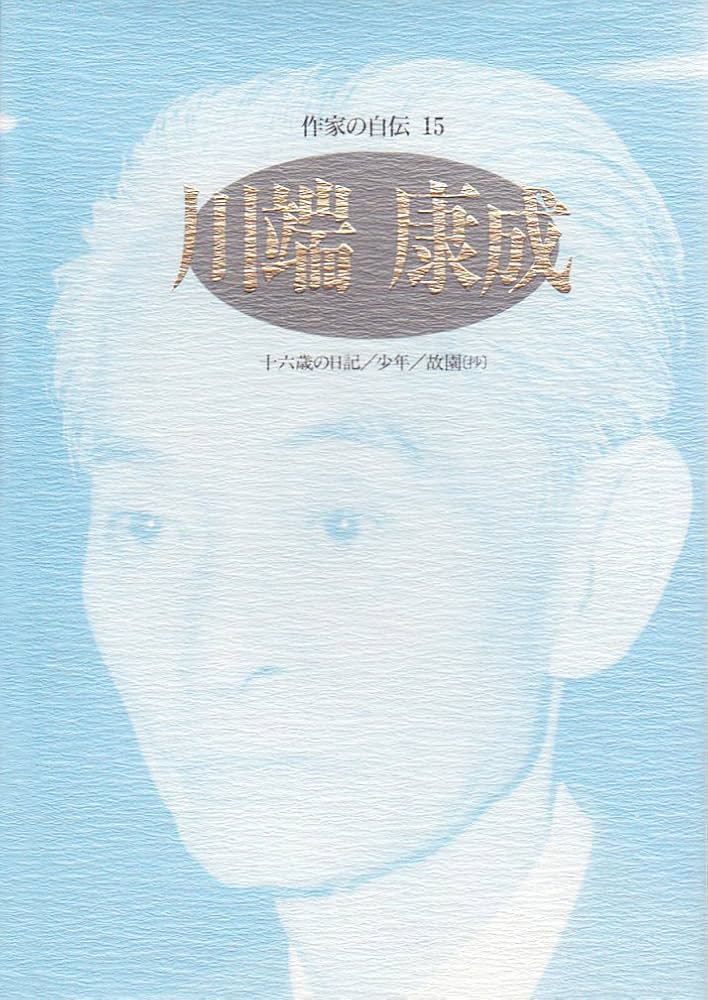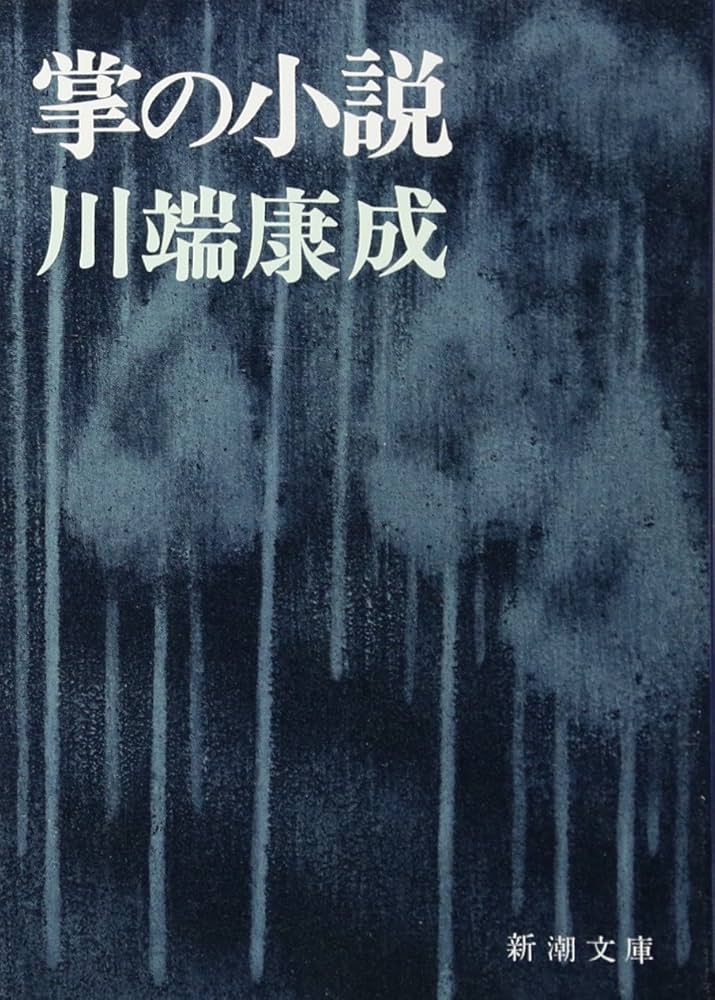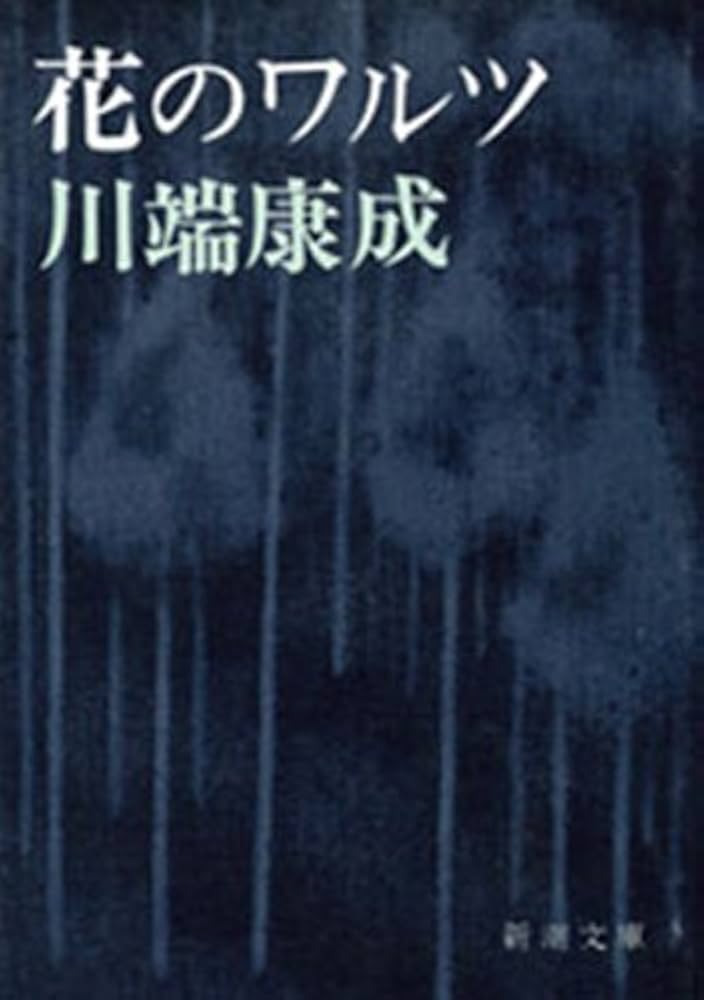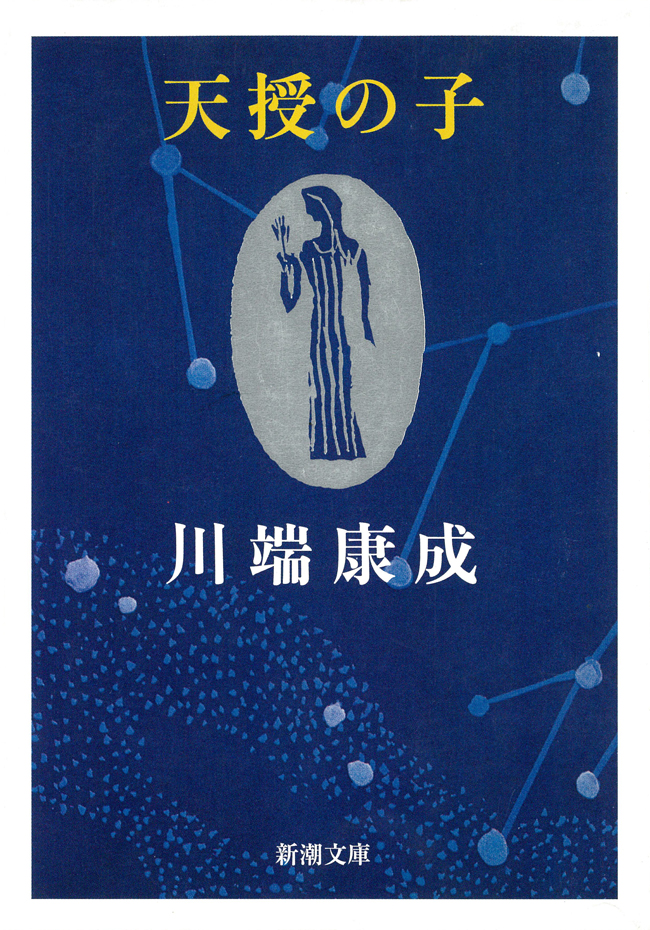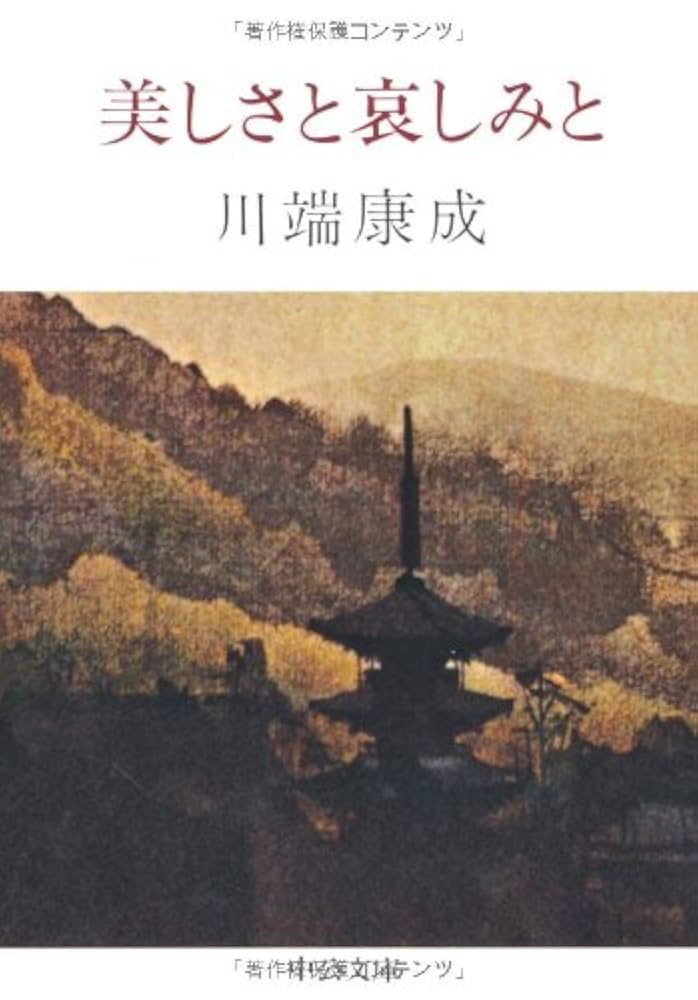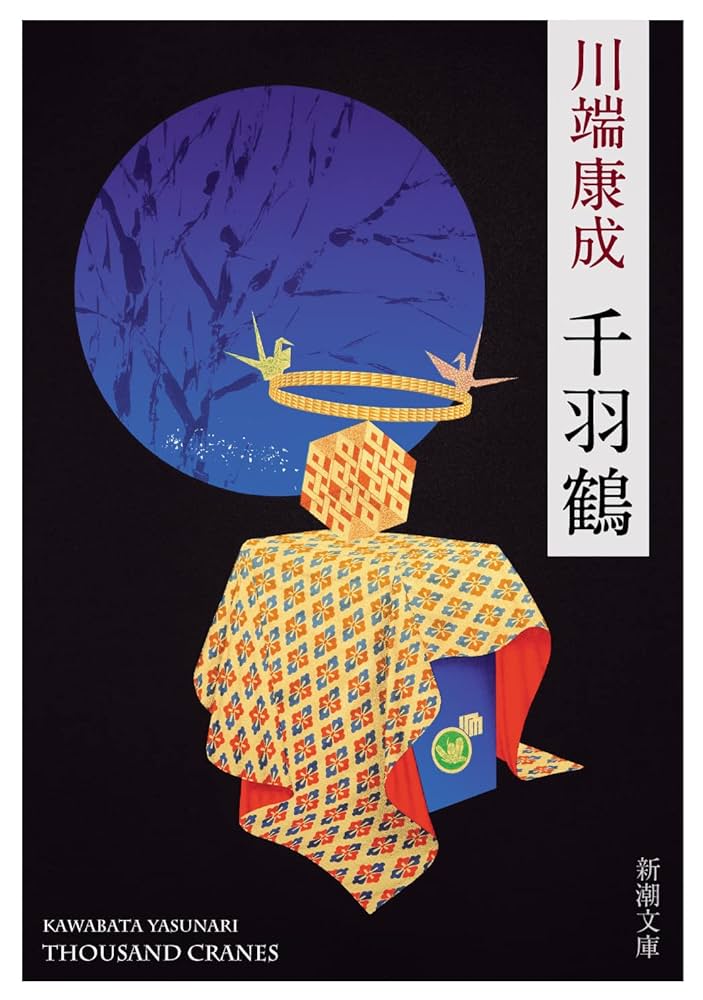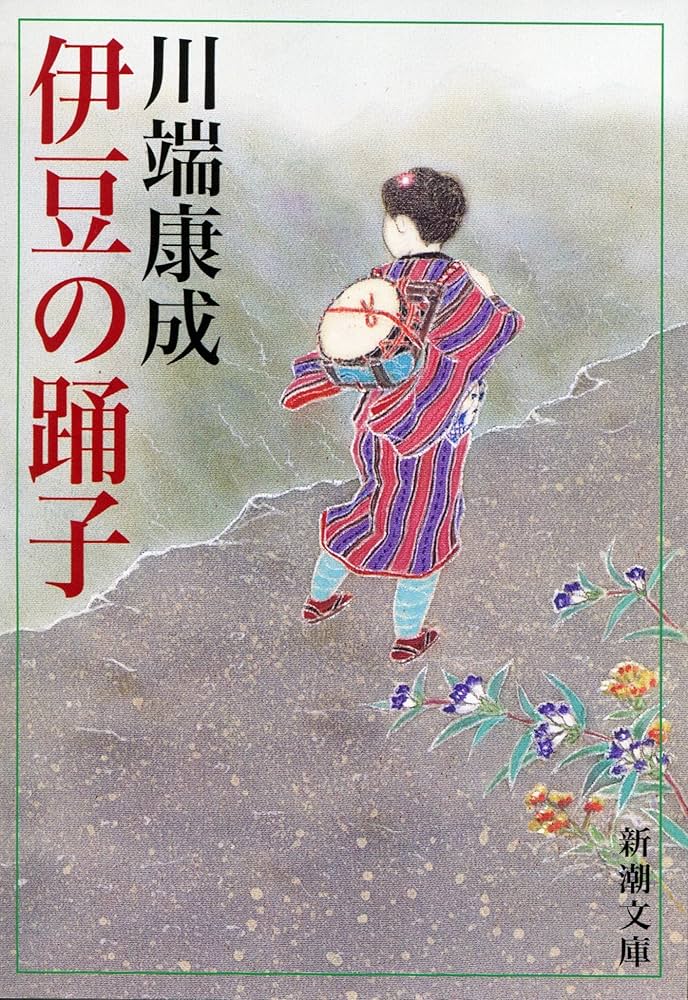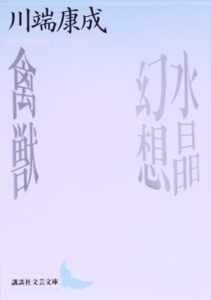 小説「水晶幻想」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「水晶幻想」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
この作品は、川端康成がモダニズム文学の旗手として、その実験精神を最も鮮烈に発揮した一編といえるでしょう。発表された1930年代、海外から流入した「意識の流れ」という新しい手法を駆使し、一人の女性の内面に渦巻く幻想の奔流を言語化しようと試みた、野心的でありながら未完に終わった物語です。
物語の筋書きは、従来の小説のように出来事を追う形では進みません。主人公である「夫人」の心象風景そのものが、この小説のすべてです。彼女の意識は、現実の出来事をきっかけに、記憶や不安、そしてエロティックな連想の洪水を引き起こします。その絶え間ない思考の流れを、読者は追体験することになるのです。まさに、心の中を覗き見るような、めまいを覚えるほどの読書体験が待っています。
この記事では、まず「水晶幻想」がどのような物語なのか、その骨子となるあらすじをご紹介します。ここでは物語の核心的なネタバレは避けつつ、その不穏で美しい世界観の一端に触れていきます。そして後半では、物語の結末にまで踏み込んだ、詳細なネタバレを含む長文の感想を記しました。作品の持つ深いテーマや象徴について、じっくりと考察を深めていきます。
川端康成の作品の中でも、特に挑戦的で、読む者を選ぶかもしれません。しかし、その美しくも恐ろしい幻想の世界に一度足を踏み入れれば、忘れがたい印象を心に残すはずです。この記事が、皆さまを「水晶幻想」の深淵へと誘う、一つのきっかけとなれば幸いです。どうぞ最後までお付き合いください。
「水晶幻想」のあらすじ
物語は、夫人が夫から贈られた真新しい三面鏡の前に座るところから始まります。その鏡は、ただ姿を映すだけではありません。鏡面に映る自らの顔、窓の外の青空、そして動物実験を行う夫の実験室のガラス屋根。それらが夫人の意識の中で結びついた瞬間、彼女の内面への旅が始まります。連想は海の底の生物の死骸から、人間の精子の運動へと、微小な生命の世界へと潜っていきます。
そんな中、一つの出来事が起こります。夫人が飼っている血統書付きの雄犬「プレイ・ボオイ」の交配です。相手の牝犬を連れて、美しい令嬢が家を訪れます。応接間で、二匹の犬は衆人環視の中、けたたましく交尾を始めます。その剥き出しの動物的な生殖の光景は、子供のいない夫人の心に、深く突き刺さるものでした。彼女は、目の前の生々しい現実から逃れるように、過去の美しい記憶へと意識を飛ばします。
やがて発生学の研究者である夫が帰宅します。夫人は、鏡越しに夫と対話を始めます。化粧鏡の中の人生と、顕微鏡の中の人生、どちらが寂しいか。彼女の問いは、二人の間にある深い溝を浮き彫りにします。夫は、感情を見せず、ただ合理的に不妊治療を再び勧めるだけでした。その冷たい言葉に、夫人は青ざめます。
夫人は、かつて医師から不妊の原因は夫にある可能性を示唆されたことを思い出します。そして、彼女の胸には、夫に対するある恐ろしい疑念が渦巻いていました。それは、夫が研究の一環として、自分に動物の精子を注入したのではないかという、グロテスクな幻想でした。物語は、彼女の幻想が頂点に達したとき、ある身の毛もよだつ問いと共に、唐突に終わりを告げます。
「水晶幻想」の長文感想(ネタバレあり)
ここからは、物語の核心に触れるネタバレを含んだ感想になります。未読の方はご注意ください。この「水晶幻想」という物語は、読解が非常に難しい作品です。しかし、その難解さこそが、この作品が描こうとしたものの本質に他なりません。それは、論理や理屈では到底捉えきれない、人間の意識そのものの姿なのです。
物語の冒頭、夫人の前に置かれた三面鏡。これは、この物語を解き明かすための最も重要な象徴的装置です。三面鏡は、一つの視点からは見えない多角的な自己を映し出します。正面には現在の自分、左右の鏡には過去の記憶や、夫のいる科学の世界が映り込み、混ざり合います。これは、夫人の精神が、いかに断片的で、様々なイメージが共存する混沌とした状態にあるかを視覚的に示しています。彼女は、統一された自己を見失い、鏡の中に分裂した自分を見ているのです。
川端は、この三面鏡というポータルを通して、夫人の「意識の流れ」を奔流させます。彼女の連想は、時系列も論理も無視して、自由に飛躍します。鏡に映る自分の顔から、海の底に降り積もるプランクトンの死骸へ。夫の実験室から、新婚初夜に夫の眼鏡を踏み砕いた記憶へ。そして、産婦人科医だった父の冷たい診察室の光景へ。これらのイメージの連鎖は、彼女の根底にある「生」と「死」、そして「性」に対する不安と執着を浮かび上がらせます。
この物語には、フロイトの精神分析学の影響が色濃く見られます。特に、犬の交配シーンは、まさにフロイトの言う「原光景」――つまり、性の場面を目撃してしまったことによる心的外傷的な体験――として機能しています。子供がいないことに深いコンプレックスを抱く夫人にとって、目の前で繰り広げられる動物のむき出しの生殖行為は、耐え難いものでした。この強烈なネタバレ的な場面が、彼女の心の奥底に抑圧されていた不安や欲望を、一気に解き放つ引き金となるのです。
彼女の意識は、この生々しい現実から逃避するように、理想化された過去の美しい少年や、清らかな女学生の記憶へと向かいます。これは、汚されてしまった現在の自分と対極にある、純潔なものへの渇望の表れでしょう。この場面は、跡継ぎを産むことを期待される当時の女性が置かれた、過酷な社会的圧力をも反映しています。その役割を果たせない夫人は、自らを「不自然」な存在だと感じ、だからこそ犬の「自然」な行為が、より一層グロテスクに映るのです。
そして、物語のもう一つの軸が、夫の存在です。彼は発生学の研究者であり、生命の起源を科学的に解明しようとしています。彼の世界は、顕微鏡の中の、冷たく硬質な世界です。彼は、生命を愛でるのではなく、分析し、操作しようとします。この夫の姿は、生命を合理的に支配しようとする近代科学そのもののアレゴリーと言えるでしょう。
この夫婦の対話は、感情的で幻想的な夫人の世界と、理性的で非人間的な夫の世界が、決して交わることのない断絶を明らかにします。夫人は、犬の交配をきっかけに得た令嬢の兄の名刺を見せ、自分が不貞を働いたかのように振る舞うことで、夫の人間的な嫉妬を引き出そうとします。しかし、夫の反応は、彼女の期待を無残に打ち砕きます。彼は、ただ冷ややかに不妊治療を勧めるだけ。このネタバレは、彼女の孤独を決定的にします。
この絶望的な状況で、夫人の幻想は最も恐ろしい領域へと踏み込みます。不妊の原因は夫にあるのではないか。そして、夫は研究のために、自分に動物の精子を使った人工授精を施したのではないか。この疑念は、科学という名の下に行われる非人間的な行為への恐怖の極致です。生命の創造を研究する夫自身が、実は不妊であるかもしれないという皮肉。そして、その彼が提案する解決策が、愛ではなく科学的介入であるという倒錯。
このグロテスクな妄想は、川端自身の個人的な体験とも無関係ではないでしょう。彼自身、子供に恵まれなかったという悲劇は、この不妊というテーマに、切実なリアリティを与えています。夫の冷徹さと夫人の恐怖は、単なるフィクションではなく、近代科学がもたらす光と闇に対する、川端自身の批評的な眼差しが込められているのです。夫は、生命が観察され、分析されるだけで、決して慈しまれることのない、不毛な世界の象”徴なのです。
物語は、夫人が「人間? やっぱり死刑囚だったの?」という謎めいた問いを発して、ぷつりと途絶えます。これは、夫が実験材料として使っているのは、動物だけでなく、ついには死刑囚のような、社会的に抹殺された人間にまで及んでいるのではないか、という彼女の妄想の帰結です。生命を創り出す科学が、生命を収奪する行為と地続きであるという戦慄。この問いは、科学の冷たい視線に晒された生命が、その尊厳を奪われ、単なる「モノ」へと成り下がる恐怖を表現しています。
この物語が未完であること。それ自体が、この作品の最も雄弁な結論なのかもしれません。解決に向かうことのない、堂々巡りの不安。それこそが、夫人の意識のあり方そのものです。もし、この物語に安易な結末が与えられていたとしたら、それは作品のテーマを裏切ることになったでしょう。物語の崩壊は、描かれた精神の崩壊を、そのまま映し出しているのです。
「意識の流れ」という手法は、本質的に、明確な結末を拒否します。思考は、始まりも終わりもなく、ただ流れ続けるものだからです。川端は、この実験的な手法の限界に突き当たり、物語を放棄したのかもしれません。しかし、その結果として残されたこの「未完」のテクストは、いかなる完成形よりも、描こうとしたものの本質を、より強く、より誠実に伝えているように思えてなりません。
最後の問いの後に訪れる沈黙。その沈黙こそが、読者を夫人の「水晶幻想」の世界――どこまでも美しく、どこまでも恐ろしく、そして永遠に解決されることのない袋小路――に、閉じ込めるのです。この作品は、川端文学の実験室で生まれた、奇妙で、いびつで、しかし強烈な輝きを放つ結晶なのです。
この作品を読むことは、他人の夢の中を彷徨うような体験です。論理は通用せず、イメージだけが奔流のように押し寄せる。心地よい読書とは言えないかもしれません。しかし、文学が、人間の意識の最も深い場所にまで降りていく営みであるとするならば、「水晶幻想」は、その最も過激な実践の一つとして、今なお私たちを挑発し続けています。
川端は、この作品で試みた実験を、後の「山の音」や「みづうみ」といった傑作へと昇華させていきました。そうした意味で、「水晶幻想」は、彼の文学的達成を知る上で、避けては通れない重要な作品です。未完であるがゆえの荒削りな魅力と、その核心にある恐怖と美しさは、一度触れたら忘れられないでしょう。
この物語のネタバレを知った上で、改めて本文を読み返すと、一つ一つの言葉やイメージが、いかに周到に配置されているかに気づかされます。夫人の意識の断片は、一見バラバラに見えて、実は「生と死」「性と科学」というテーマの下に、緊密に結びついています。この複雑な構造を解き明かしていくことこそ、「水晶幻想」を読む醍醐味と言えるでしょう。
川端康成という作家の、最も前衛的で危険な側面が、この作品には凝縮されています。それは、安全な場所から物語を眺めることを許さず、読者自身の意識をも揺さぶる、強力な力を持っています。この恐ろしくも美しい幻想の世界に、ぜひ一度、迷い込んでみてはいかがでしょうか。
まとめ
この記事では、川端康成の未完の小説「水晶幻想」について、あらすじからネタバレを含む深い感想までを綴ってきました。この作品は、一人の女性の内面に渦巻く幻想や連想を、「意識の流れ」という手法を用いて描き出した、非常に実験的な物語です。その難解さゆえに、多くの読者を戸惑わせるかもしれませんが、そこには川端文学の神髄が隠されています。
物語の中心にあるのは、三面鏡、犬の交配、そして科学者である夫との対話です。これらの出来事やオブジェをきっかけに、主人公である夫人の意識は、時空を超えて飛躍し、生と死、性と科学といった根源的なテーマを探求していきます。特に、子供がいない夫人が抱く不安と、夫への恐ろしい疑念は、物語全体を不穏な空気で満たしています。
この物語が未完であるという事実は、作品の価値を損なうものではありません。むしろ、解決しようのない人間の不安や意識のあり方を描いたこの物語にとって、唐突な断絶という終わり方は、最もふさわしい結末だったのかもしれません。読者は、答えのない問いと共に、幻想の世界に取り残されることになりますが、その経験こそが、この作品の忘れがたい読後感を生み出しているのです。
「水晶幻想」は、川端康成の他の有名な作品とは一線を画す、挑戦的で特異な一編です。しかし、彼の文学の深淵に触れたいと願う読者にとって、これほど刺激的な作品はないでしょう。この記事が、その難解な迷宮へのささやかな案内図となれば、これに勝る喜びはありません。