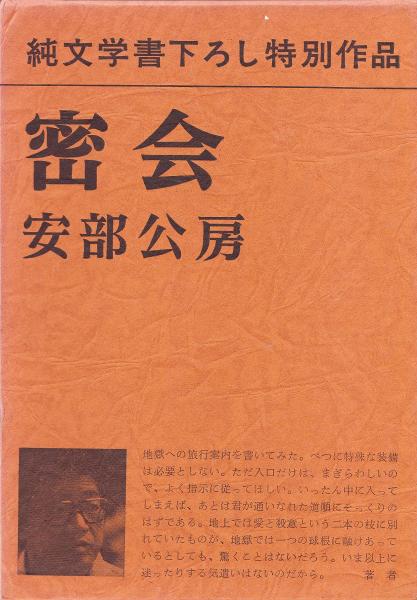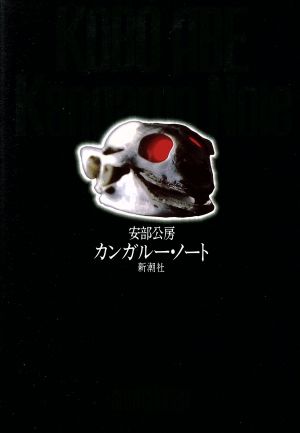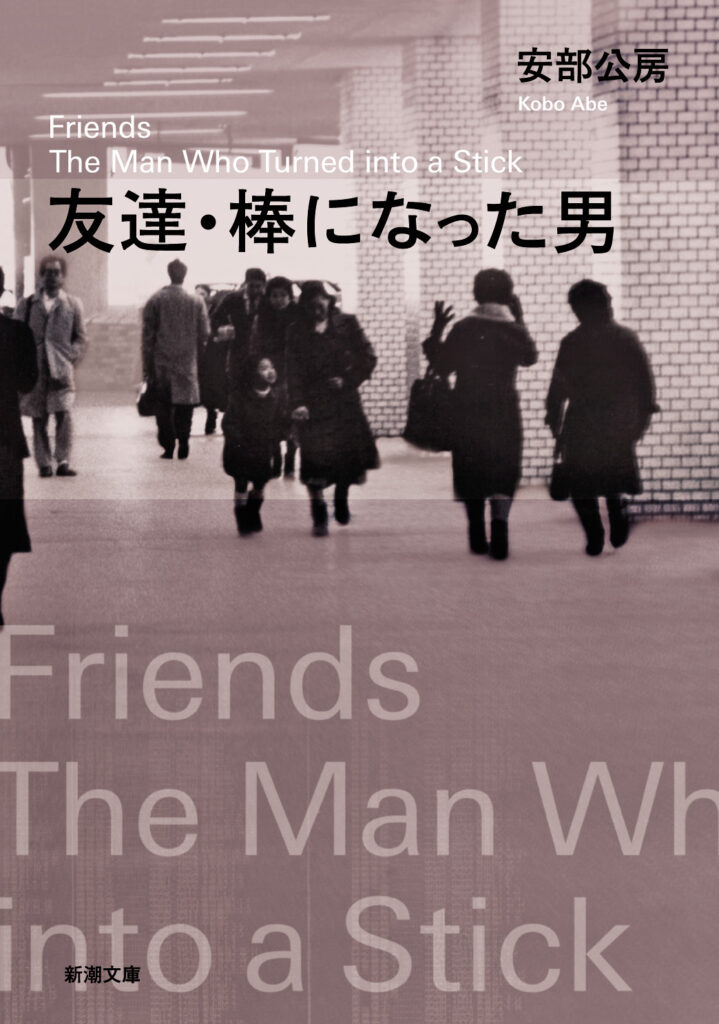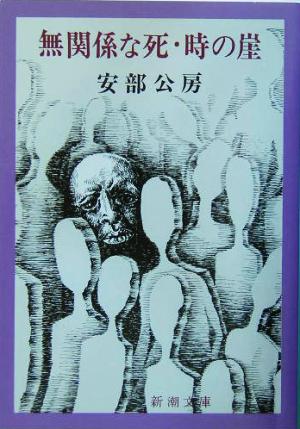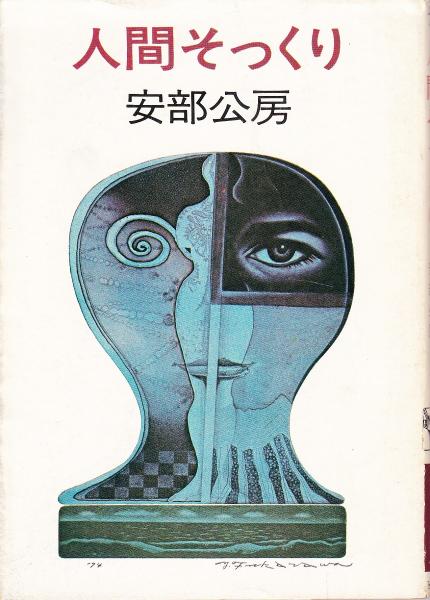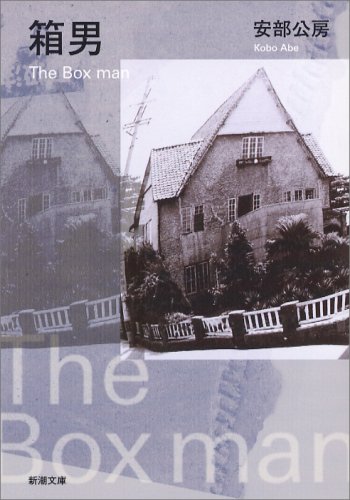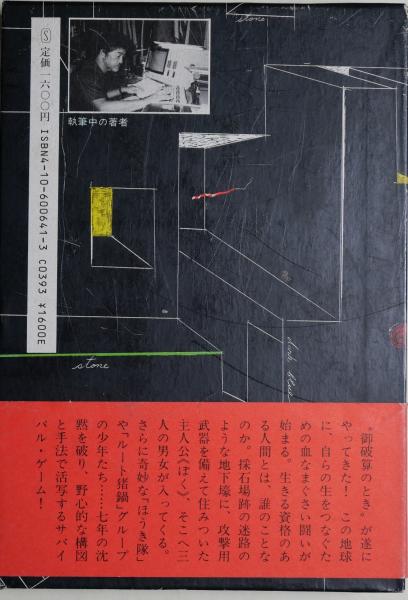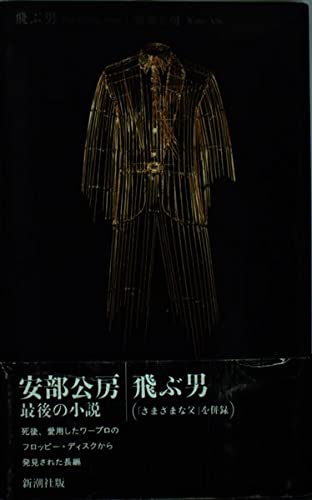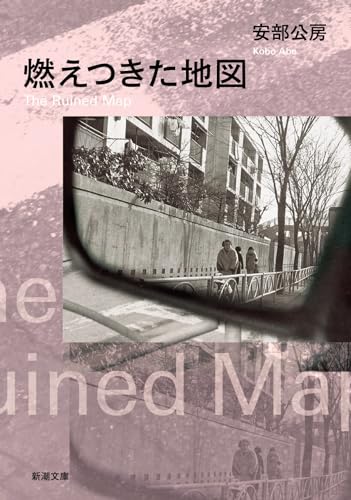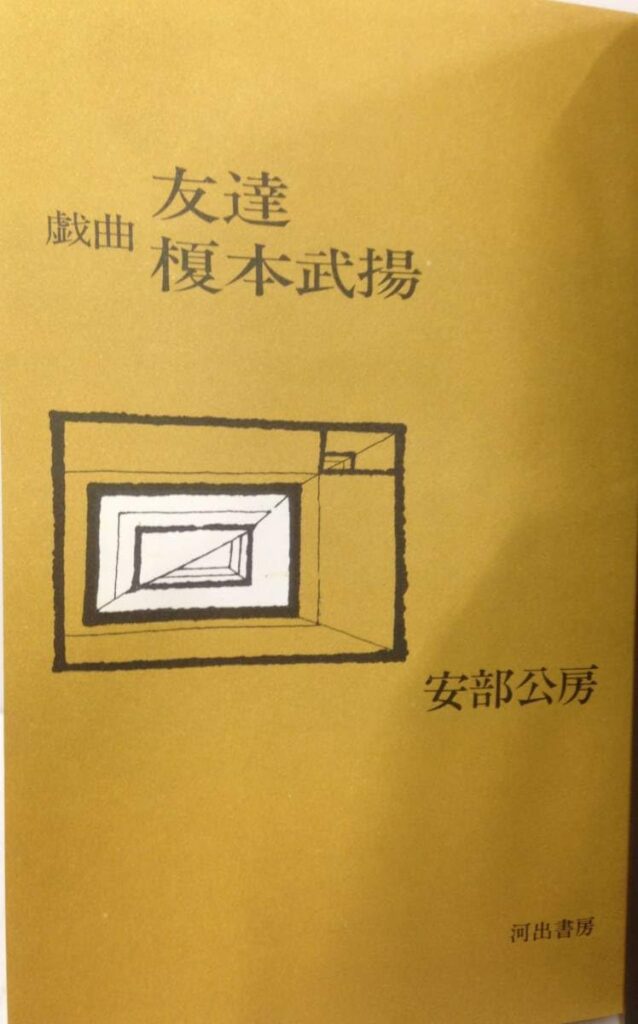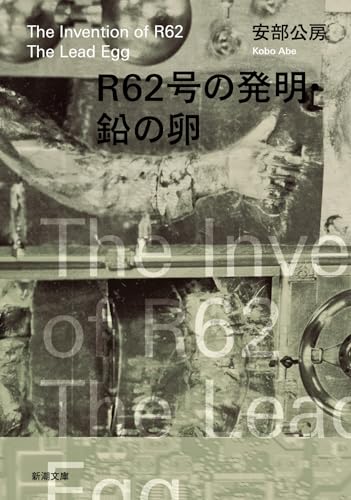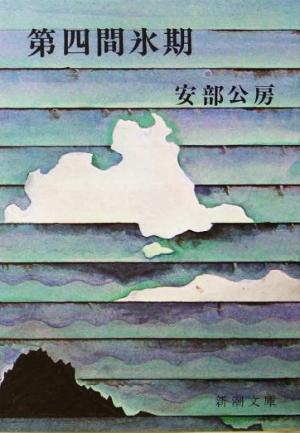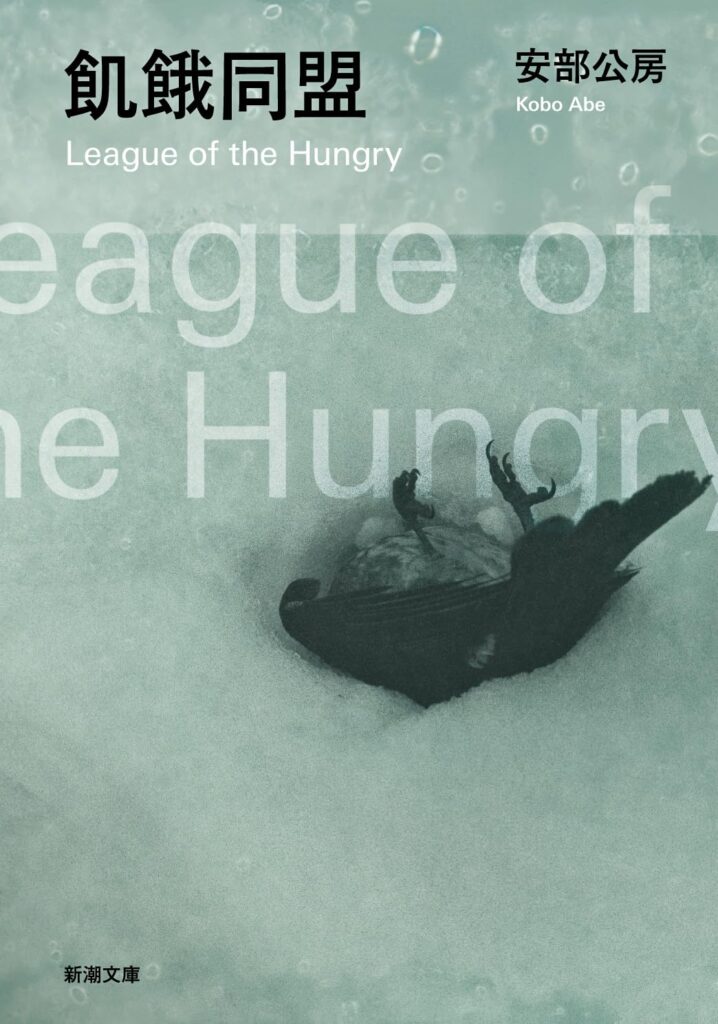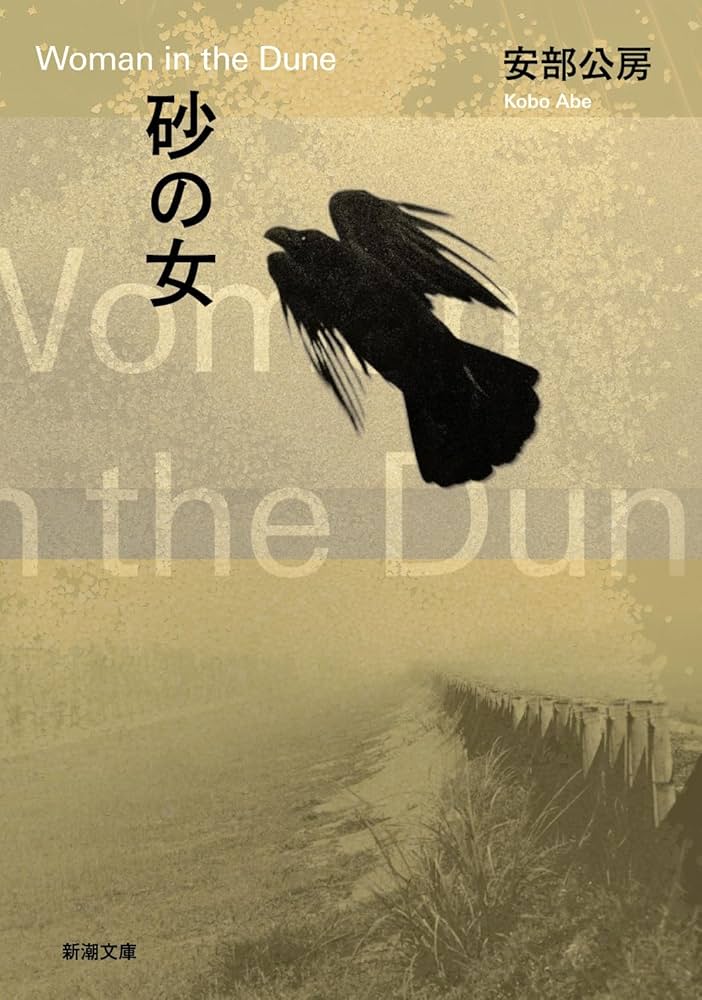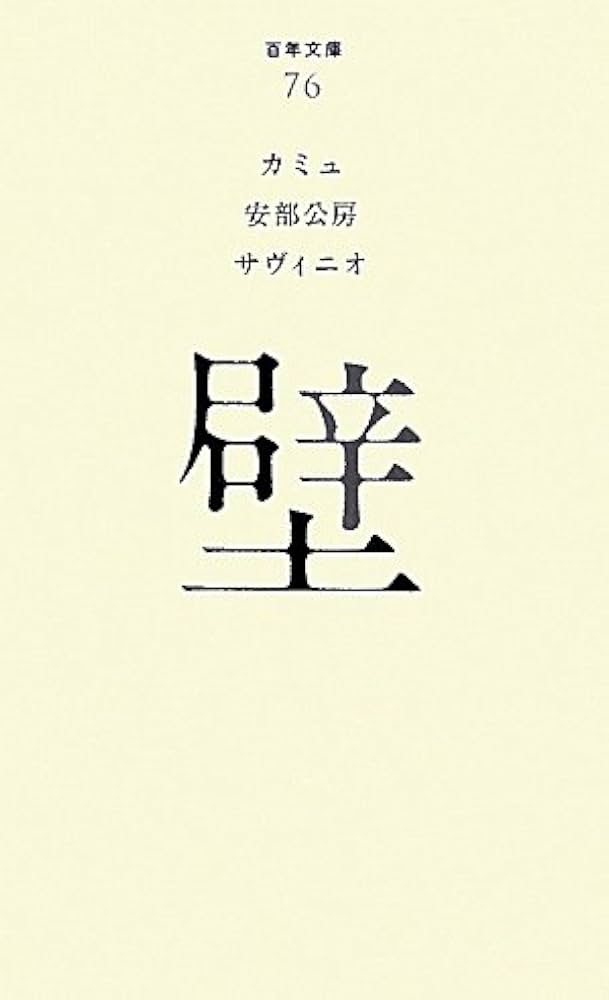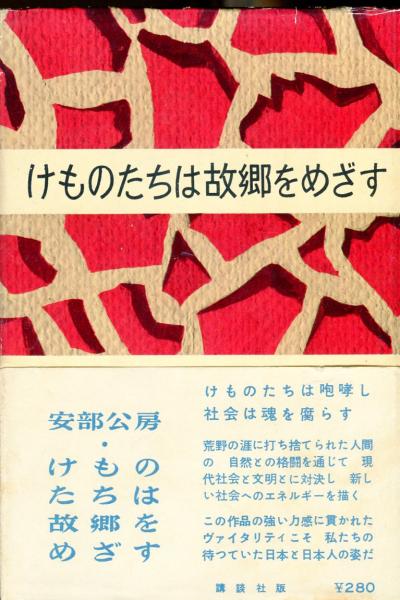小説「水中都市・デンドロカカリヤ」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「水中都市・デンドロカカリヤ」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
安部公房が描く世界は、いつも私たちの足元を揺さぶってきます。当たり前だと思っていた日常が、ある日突然、まったく異なる法則で動き出したら、あなたはどうしますか。この二つの中篇が突きつけるのは、まさにそのような問いなのです。
『水中都市』では、見慣れたはずの街が水に沈み、奇妙な秩序が生まれていく様が描かれます。一方、『デンドロカカリヤ』では、主人公が徐々に植物へと姿を変えていく過程が、内面から克明に綴られます。どちらも「変身」を扱っていますが、その様相はまったく異なります。しかし、根底には共通したテーマが流れているように感じられてなりません。
この記事では、まず二つの物語の導入となるあらすじを紹介します。ここでは物語の結末には触れませんので、未読の方もご安心ください。その上で、物語の核心に触れるネタバレを含む、私なりの深い読み解きと鑑賞の記録を、たっぷりと語らせていただこうと思います。
安部公房の迷宮に足を踏み入れる準備はよろしいでしょうか。彼の言葉が織りなす不条理で、それでいて妙に現実的な世界への旅に、しばしお付き合いいただければ幸いです。きっと、読後にはあなたの見る世界が少しだけ違って見えるはずですから。
「水中都市・デンドロカカリヤ」のあらすじ
『水中都市』の物語は、単調な毎日を送る「おれ」の視点から始まります。ある夜、彼は駅で奇妙な男に付きまとわれ、その男は勝手に「おれ」のアパートに上がり込み、自分は満州にいたお前の父親だと名乗ります。不条理な同居生活が始まる一方で、「おれ」の同僚である間木は、職場のある風景が水の中に沈んだ、予言めいた絵を描いていました。
この絵が現実になるかのように、やがて世界は本当に水中へと変貌を遂げます。しかし、人々は濡れることなく、まるで空気中と同じように水中を移動できるのです。物理法則が書き換えられた世界で、「おれ」は父親が魚へと変身し、街を泳ぎ回る姿を目撃します。首のない人間がさまよい、新たな捕食関係が生まれる混沌とした街。ここには、私たちの知る常識は一切通用しません。
一方、『デンドロカカリヤ』は、「コモン君がデンドロカカリヤになった話」という一文で幕を開けます。主人公のコモン君は、自分が植物になっていくという奇妙な発作に悩まされていました。思考が停止し、太陽の光を渇望する。この不可解な変容の正体を突き止めようと、彼は図書館でダンテの『神曲』などを読み漁り、自分は無意識のうちに自殺したのではないかと苦悩します。
そんな彼の元に、植物園の園長を名乗る「K」という謎の人物が現れます。Kはコモン君を「デンドロカカリヤ」という植物名で呼び、自分の植物園に来るよう誘います。救済者なのか、それとも…。コモン君はKの存在に疑念を抱き、自らの人間性を守るため、ある決意を固めるのですが、物語は予期せぬ方向へと進んでいきます。
「水中都市・デンドロカカリヤ」の長文感想(ネタバレあり)
安部公房という作家に触れることは、安定した地面だと思っていた場所が、実は流砂だったと気づかされるような体験です。彼の作品群、とりわけ『水中都市』と『デンドロカカリヤ』は、その感覚を強く味あわせてくれます。これらは単なる奇妙な物語ではありません。現代に生きる私たちの存在そのものの不確かさを、容赦なく暴き出す文学的な実験なのです。
第二次世界大戦後の価値観が崩壊した日本で、安部公房は「変身」というモチーフを繰り返し用いました。それは、自分が何者であるかという確信(アイデンティティ)が揺らぎ、社会から疎外されていく人々の不安を、目に見える形で描き出すための、いわば必然的な手法だったのでしょう。彼の描く世界は現実離れしているようで、その実、私たちの内面に潜む恐怖を的確に映し出しているのです。
この二つの物語は、存在が崩壊していく二つの異なる道筋を描いた傑作です。これから、物語の核心に触れるネタバレを含めながら、なぜこれらの作品がこれほどまでに心を揺さぶるのか、その理由をじっくりと探っていきたいと思います。
まず、『水中都市』の世界から見ていきましょう。主人公「おれ」の日常は、製薬会社の計算機係という、まさに没個性的なものです。そこに突然現れる「父親」を名乗る男。この侵入者は、過去の亡霊のようでもあり、理不尽な運命の擬人化のようでもあります。「おれ」が彼を無視するという消極的な抵抗しかできない姿は、抗いがたい現実の変化に直面した現代人の無力さを象徴しているように思えてなりません。
この物語で非常に重要な役割を果たすのが、同僚・間木の描く絵です。彼が描いた「水の中に沈んだ工場」の風景は、単なる空想画ではありませんでした。それは、やがて訪れる世界の変容を寸分違わず予言するものだったのです。芸術が現実を写し取るのではなく、芸術が現実を規定してしまう。この倒錯した関係性は、私たちが拠り所とする現実がいかにもろいものであるかを突きつけてきます。
そして、物語はグロテスクな「ネタバレ」の核心へと向かいます。父親を名乗った男は、見るも無残な蛹のような姿に変貌し、やがてその体を突き破って一匹の魚となって消えていきます。この瞬間を合図とするかのように、窓の外の世界は、間木の絵のとおり水中都市へと変貌を遂げるのです。この変身の生々しい描写は、不条理が決して観念的なものではなく、私たちの身体を直接侵犯する暴力性を伴うことを示しています。
水中都市の描写は、まさに悪夢そのものです。人々は水に濡れることなく宙を漂い、魚に頭を食いちぎられた人々が、それでも目的もなく歩き続ける。理性や個性を失った大衆のイメージが、これほど恐ろしく描かれた例を私はあまり知りません。ここでは、かつての物理法則も社会のルールも、すべてが無に帰しています。
この新たな世界で、いち早く商売を始める男が現れます。彼が売るのは「アメリカ製の念珠」。しかし、その彼も「おれ」の父親だった魚に食い殺されてしまう。後にこの男が刑事であったことが判明するに至り、この世界では商業も宗教も国家権力も、すべてが溶け合って区別がつかなくなっていることがわかります。秩序が崩壊した後に生まれるのは、解放されたユートピアなどではなく、より原始的で暴力的な、捕食と被食の関係性だけなのです。
この物語が投げかける本当の恐怖は、その結末にあります。父親の魚は「刑事殺し」の罪で「警察魚」に逮捕されます。そして間木は「おれ」に、お前も「野良魚を養い、刑事殺しに使った」容疑で指名手配されている、と告げるのです。この罪状は、旧世界の常識ではまったく意味をなしません。しかし、この水中都市の法においては、それが絶対の真実となる。理解不能な論理によって罪人へと仕立て上げられた「おれ」が呟く「この悲しみは、おれだけにしか分らない……」という言葉は、圧倒的な孤独と絶望を読者に突きつけ、物語は幕を閉じます。ここには、何の救いもありません。
この物語の背景には、執筆当時、安部公房が日本共産党員であったという事実があります。「水」や「氾濫」が既存の秩序を覆す「革命」の比喩だとすれば、その革命がもたらした水中都市は、まさにディストピアとして描かれています。彼が信じていたはずのイデオロギーが、実は新たな怪物を生み出すのではないか。そんな作者自身の根源的な懐疑や恐怖が、この作品には色濃く反映されているのではないでしょうか。ネタバレになりますが、これはイデオロギーへの痛烈な自己批判の物語でもあるのです。
次に、『デンドロカカリヤ』の静かなる恐怖の世界に分け入っていきましょう。この物語は、「コモン君がデンドロカカリヤになった話」という、すべてが確定した過去形の一文から始まります。この時点で、読者はコモン君の抵抗が無駄に終わることを知らされます。この冒頭文は、抗えない運命を冷徹に宣告しているのです。
コモン君を襲うのは、自分が植物になっていくという奇妙な感覚です。「コモン」という、英語の「common(普通、ありふれた)」を思わせる名前を持つ彼が、なぜ特異な変身を遂げなければならないのか。彼はその理由を必死に探します。図書館へ通い、ダンテの『神曲』にある「自殺者の森」の記述や、ギリシャ神話の変身譚に答えを求めます。この知的な探求は、非合理な運命をなんとか合理的に理解しようとする、彼の人間としての最後の抵抗のようです。
そこへ現れるのが、謎の人物「K」です。植物園長を名乗る彼は、コモン君を「デンドロカカリヤ」という植物名で呼びます。この「名付ける」という行為こそが、この物語の核心的な恐怖の源泉です。フランスの哲学者サルトルは、「他者の眼差し」によって、主体的な自己が客体的なモノへと転落させられる恐怖を語りました。Kは、まさにこの「他者」を体現する存在なのです。
Kに「デンドロカカリヤ」と規定された瞬間、コモン君は、彼自身の意志とは無関係に、「そういうもの」になってしまいます。彼の存在の本質が、他者によって一方的に決定されてしまう。この客体化への恐怖が、植物への変身という形で物理的に現れるのです。彼は、人間としての主体性や移動する自由を失い、ただKの植物園で鑑賞され、分類されるだけの静的なオブジェへと成り果てていきます。
そして、ここにも驚くべき「ネタバレ」があります。安部公房はなぜ、「デンドロカカリヤ」という聞き慣れない植物の名前を選んだのでしょうか。これは架空の植物ではなく、実在する「ワダンノキ」というキク科の樹木を指します。そしてこのワダンノキは、もともとはありふれた草であったものが、小笠原諸島という孤立した環境の中で、独自の進化を遂げて樹木になった、非常に珍しい固有種なのです。
この植物学的な事実を知ったとき、私は鳥肌が立ちました。「ありふれた(コモンな)」草が、地理的な「孤立」によって奇妙な樹木へと進化したように、「ありふれた(コモンな)」人間であるコモン君が、現代都市における社会的・心理的な「孤立」によって、植物という奇妙な存在へと変容していく。これほど完璧なメタファーがあるでしょうか。安部公房の知性と構成力に、ただただ脱帽するほかありません。
コモン君はKを、自分を破滅させる存在(怪鳥アルピイエ)だと誤解し、殺害しようと試みますが、その抵抗はあっけなく失敗に終わります。彼の変身は、もはや誰にも止められません。最終的に「菊のような葉をつけた、あまり見栄えのしない樹」になってしまう彼の姿は、社会というシステムの中で分類され、名付けられ、個人の尊厳を奪われていくことの悲劇を、静かに、しかし力強く物語っています。
『水中都市』の動的で暴力的な崩壊と、『デンドロカカリヤ』の静的で内省的な崩壊。二つの物語は対照的です。しかし、どちらも個人では到底抗うことのできない、巨大で理不尽な「システム」の恐ろしさを描いている点で、深く通底しています。それが政治的なイデオロギーであれ、他者の視線や社会的な分類であれ、私たちのアイデンティティは常に外部からの力によって脅かされている。安部公房の文学は、その脆弱さと不安を見事に描き出しているのです。
まとめ
安部公房の『水中都市・デンドロカカリヤ』は、私たちの日常がいかに脆い基盤の上にあるかを教えてくれる二つの中篇です。どちらの物語も、主人公が理不尽な「変身」を遂げるという、シュールな設定から始まります。しかし、読み進めるうちに、その不条理な世界が、現代社会に潜む歪みや、個人が抱える疎外感の写し鏡であることに気づかされるでしょう。
『水中都市』では、革命のメタファーともとれる洪水が街を飲み込み、新たな暴力的な秩序が生まれます。一方の『デンドロカカリヤ』では、主人公が他者からのまなざしによって、徐々に植物という客体へと変えられていきます。この記事では、それぞれのあらすじを紹介すると共に、物語の核心に触れるネタバレも交えながら、その深いテーマについて考察を試みました。
これらの物語は、明確な答えや救いを与えてはくれません。むしろ、読後にはより深い謎と、ある種の不安が残るかもしれません。しかし、それこそが安部文学の真骨頂なのです。当たり前だと思っていた世界が揺らぐ感覚は、私たちに「人間であるとは何か」という根源的な問いを投げかけます。
もしあなたが、ただ面白いだけの物語に飽き足らなくなっているのなら、ぜひこの二つの傑作を手に取ってみてください。きっと忘れられない読書体験が、あなたを待っているはずです。