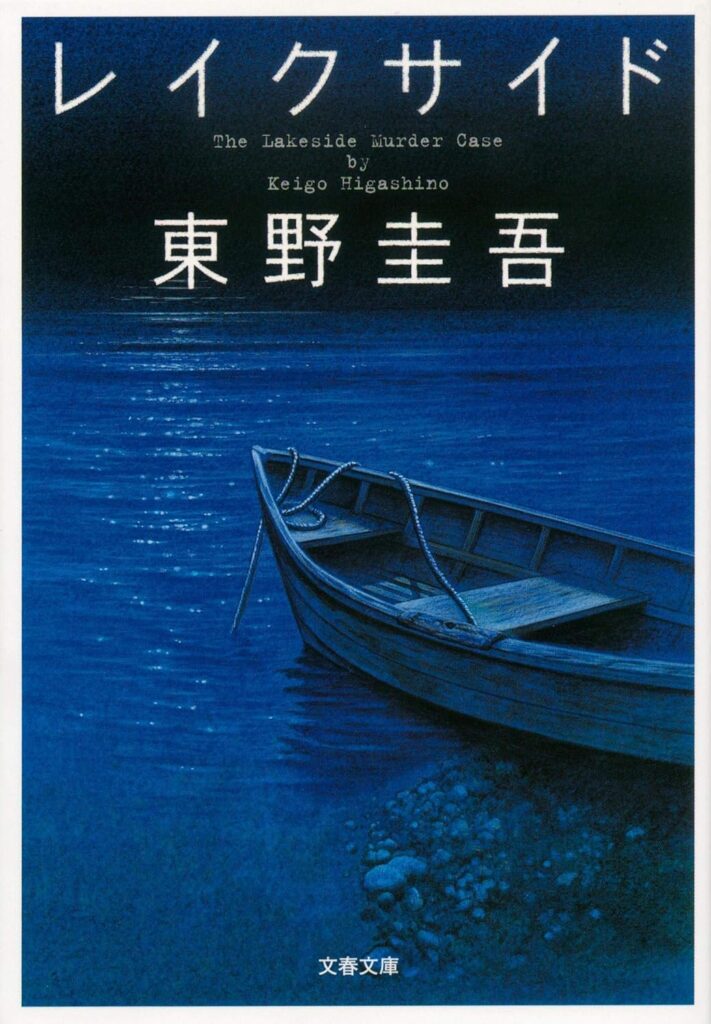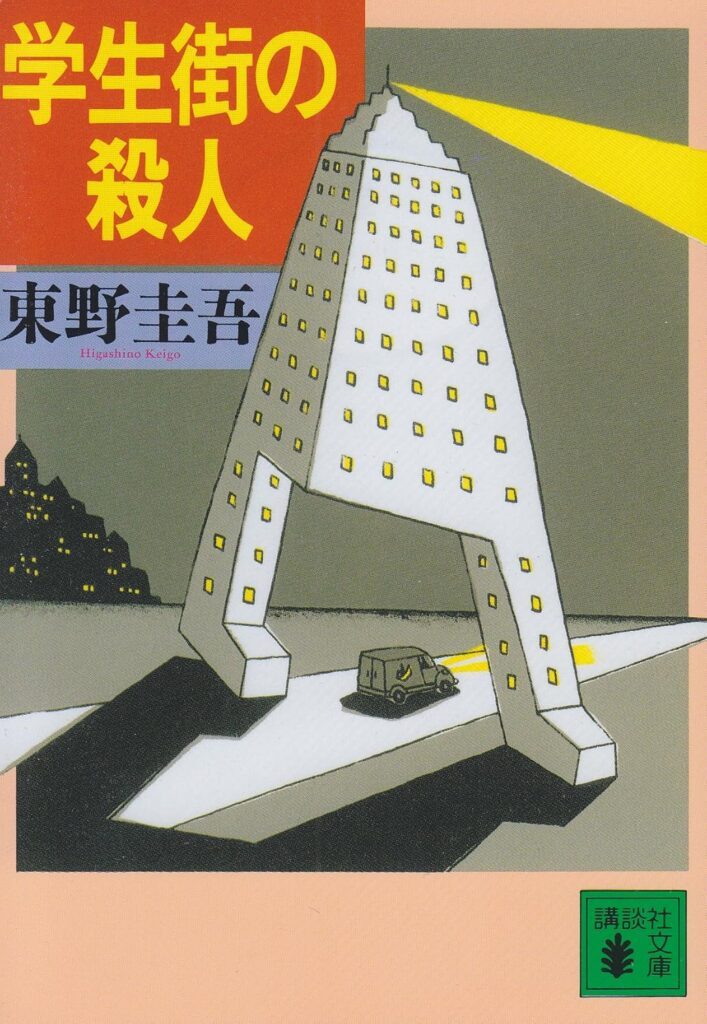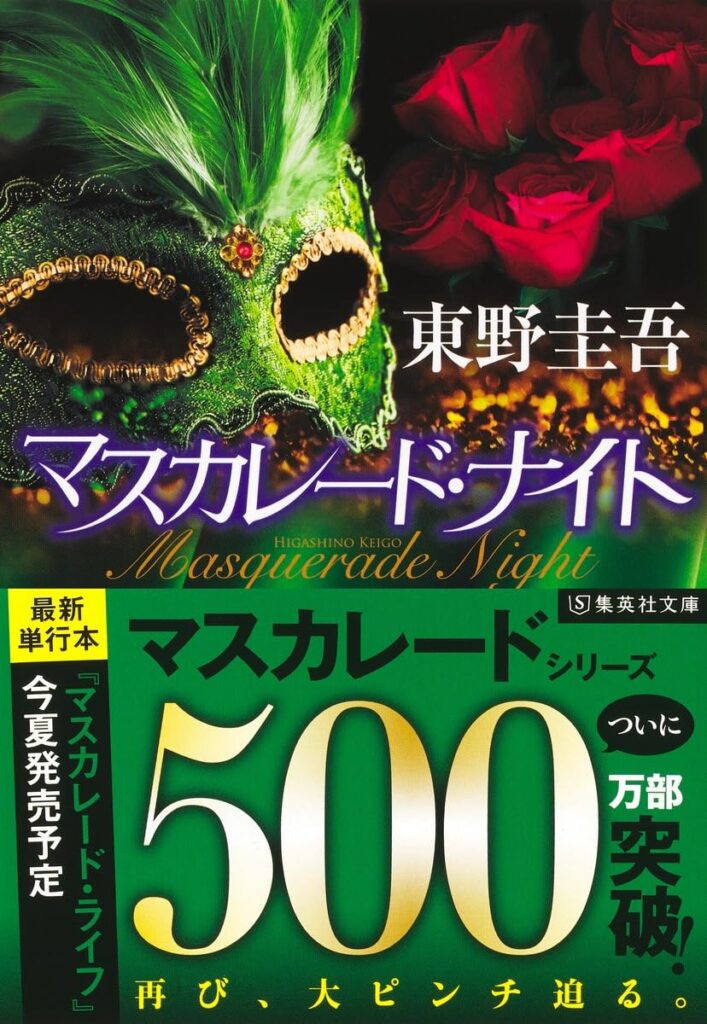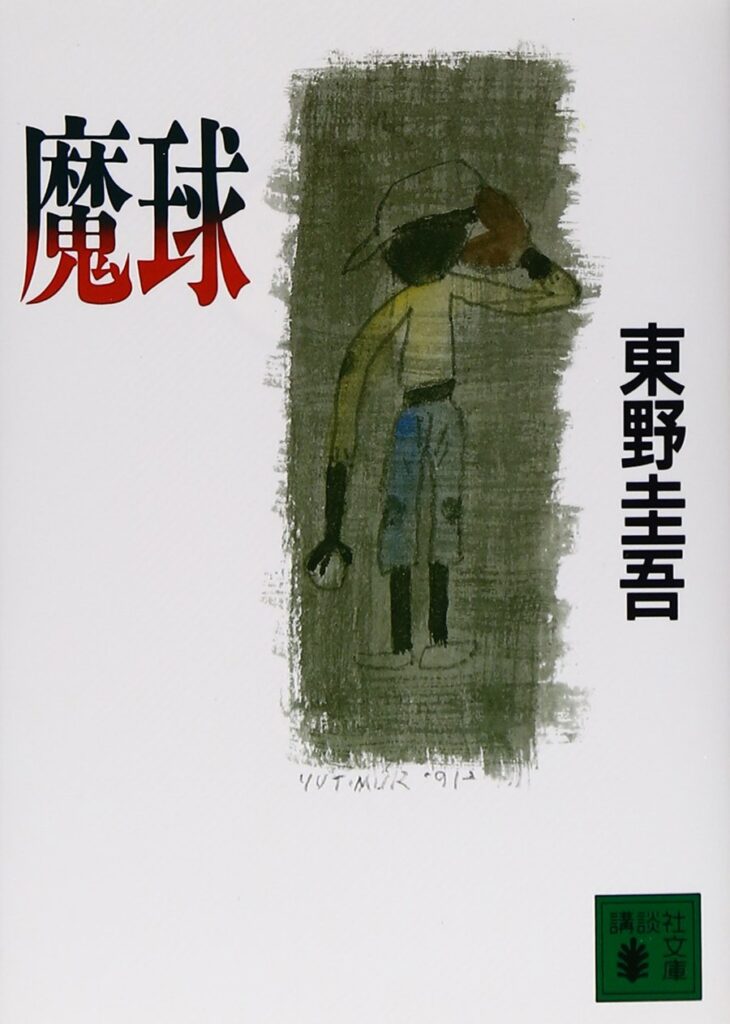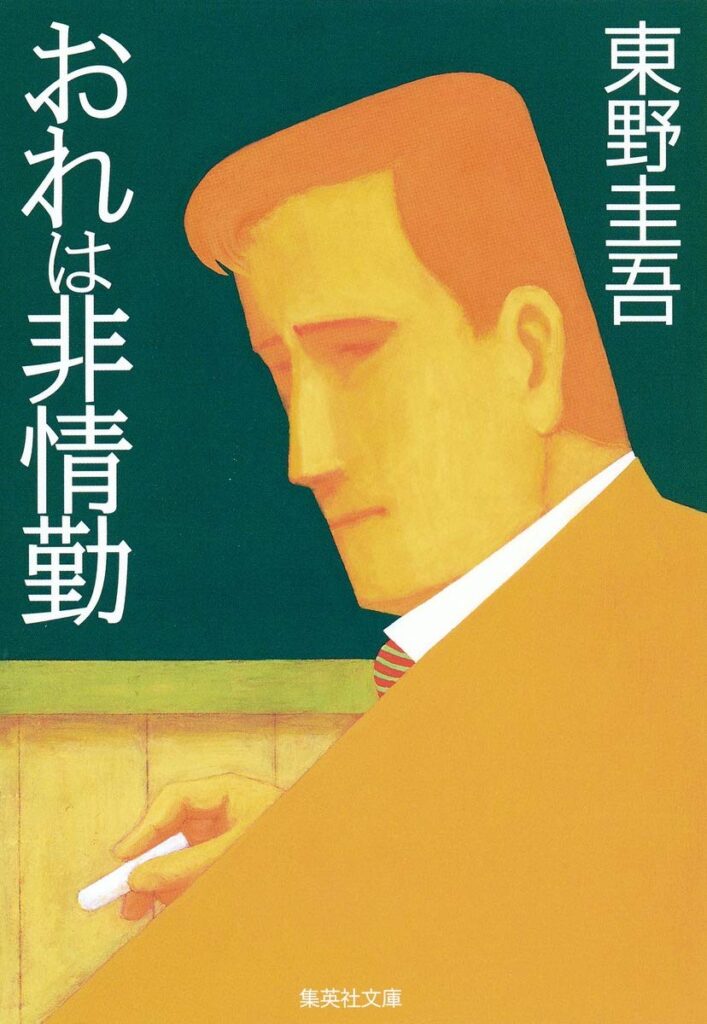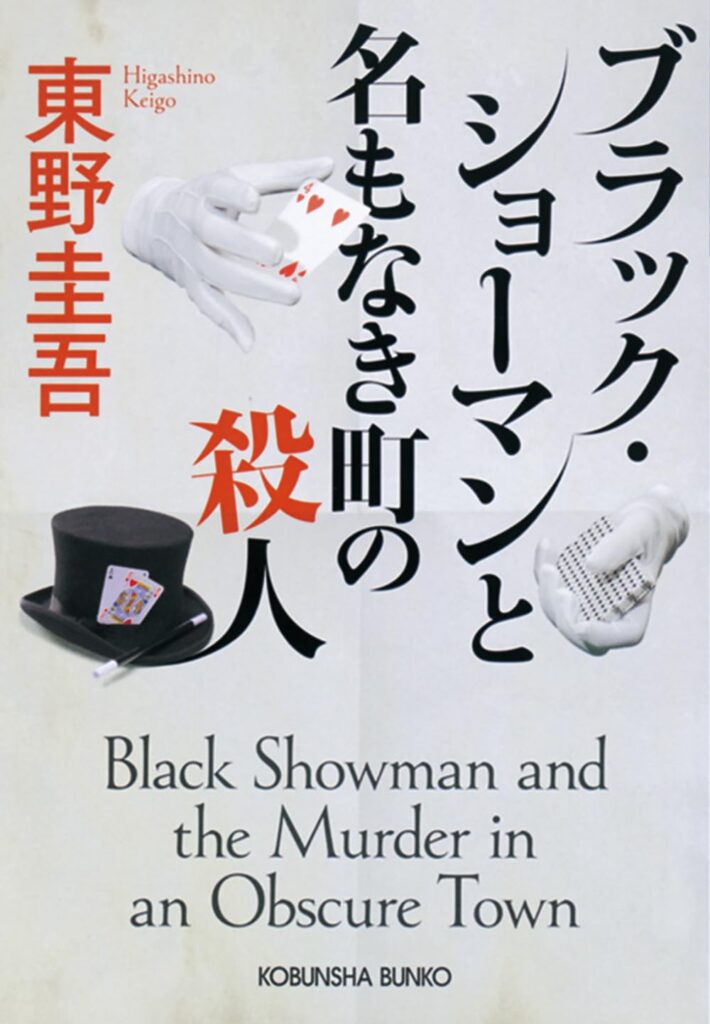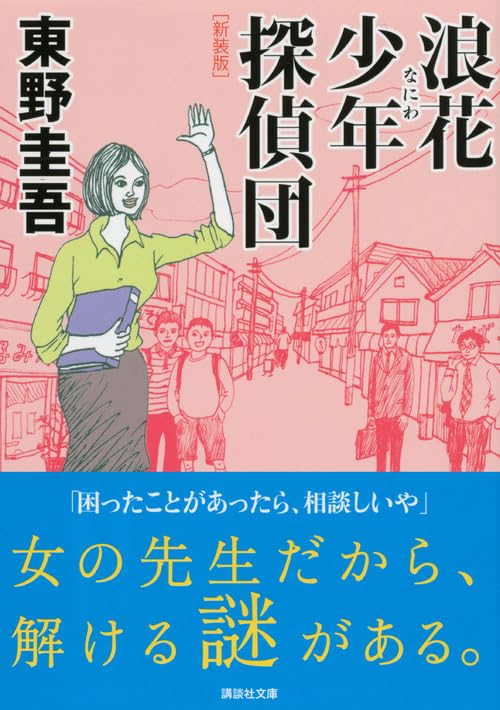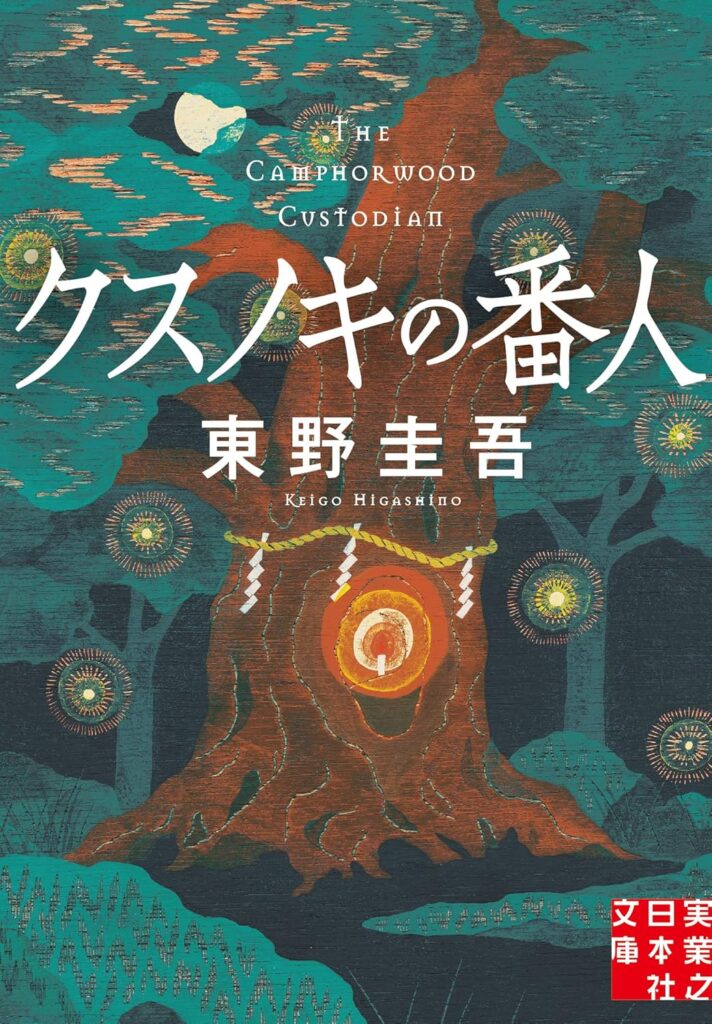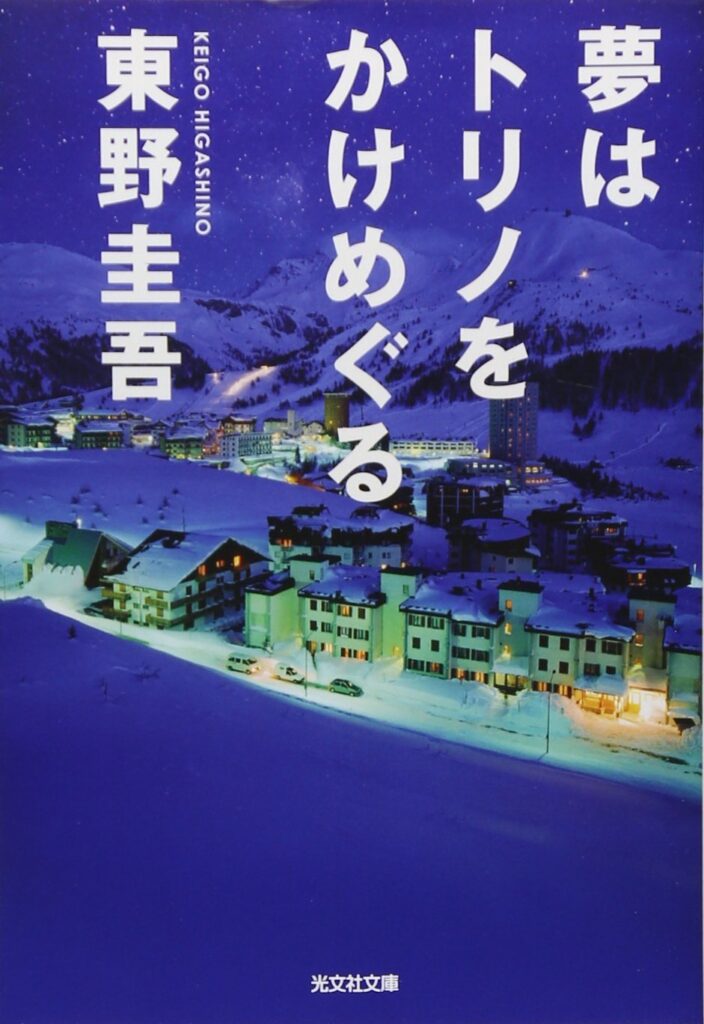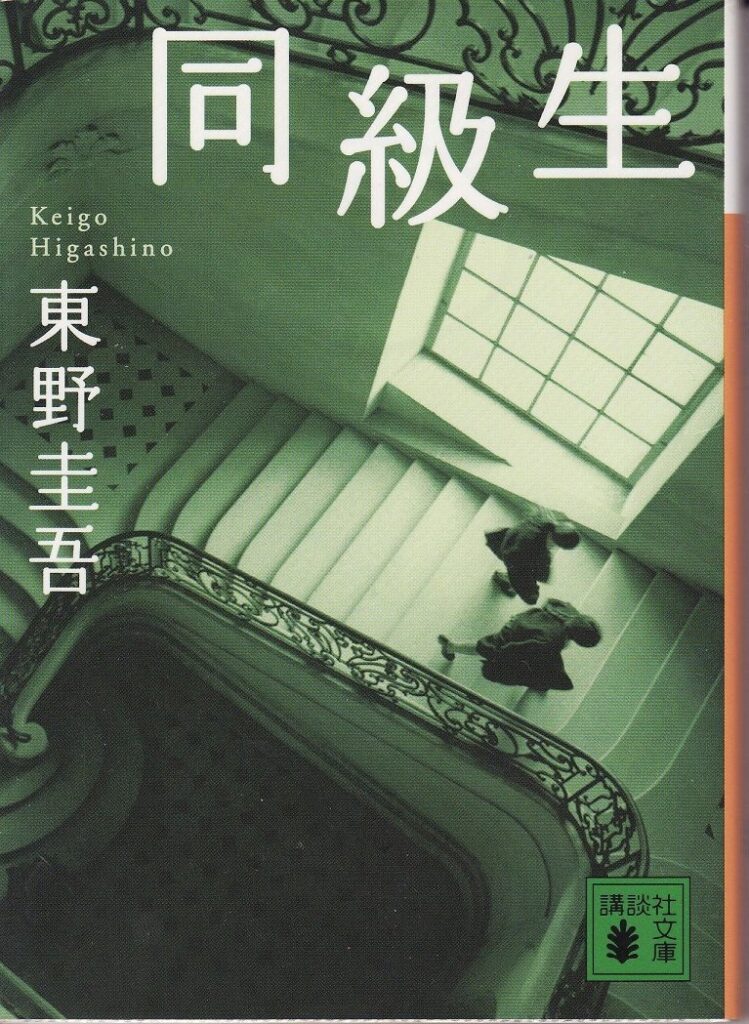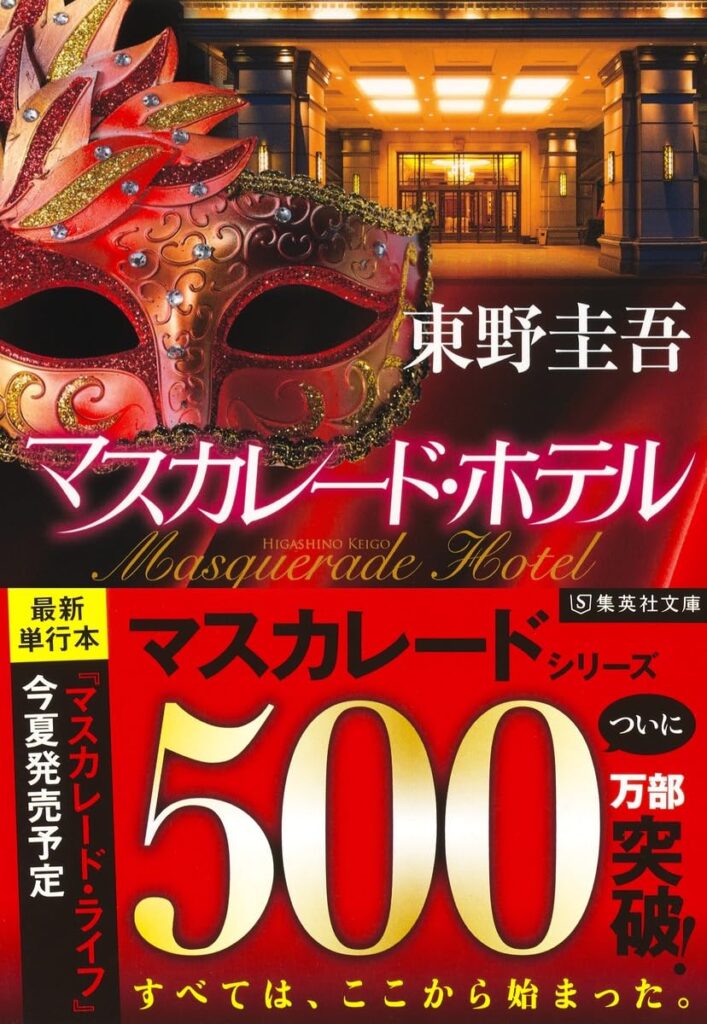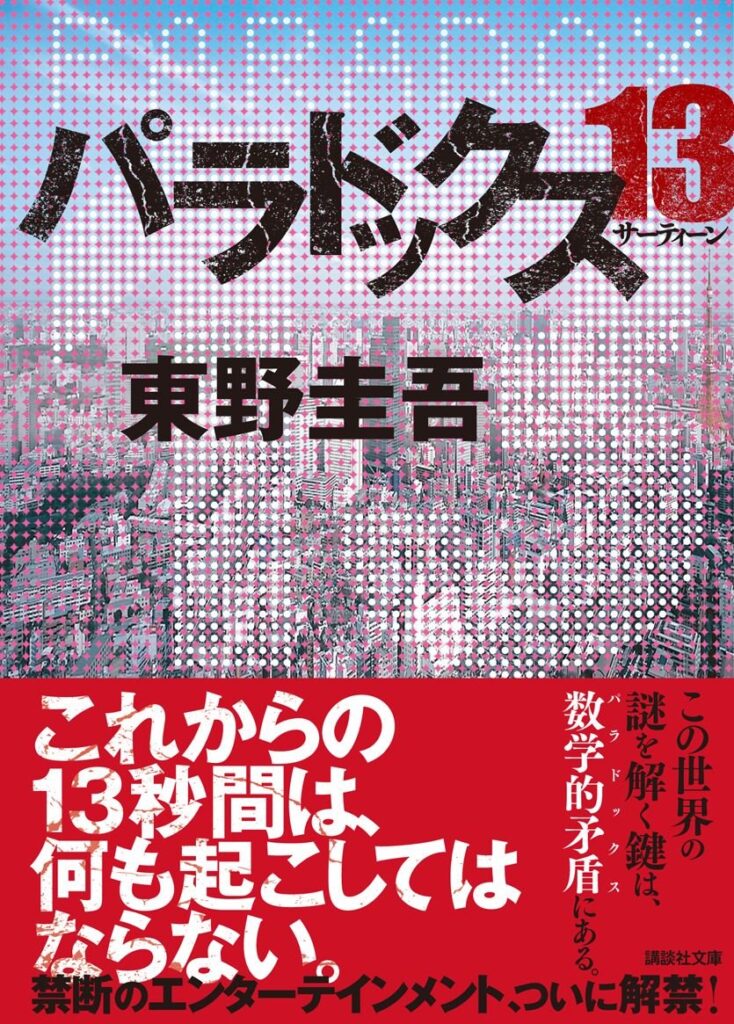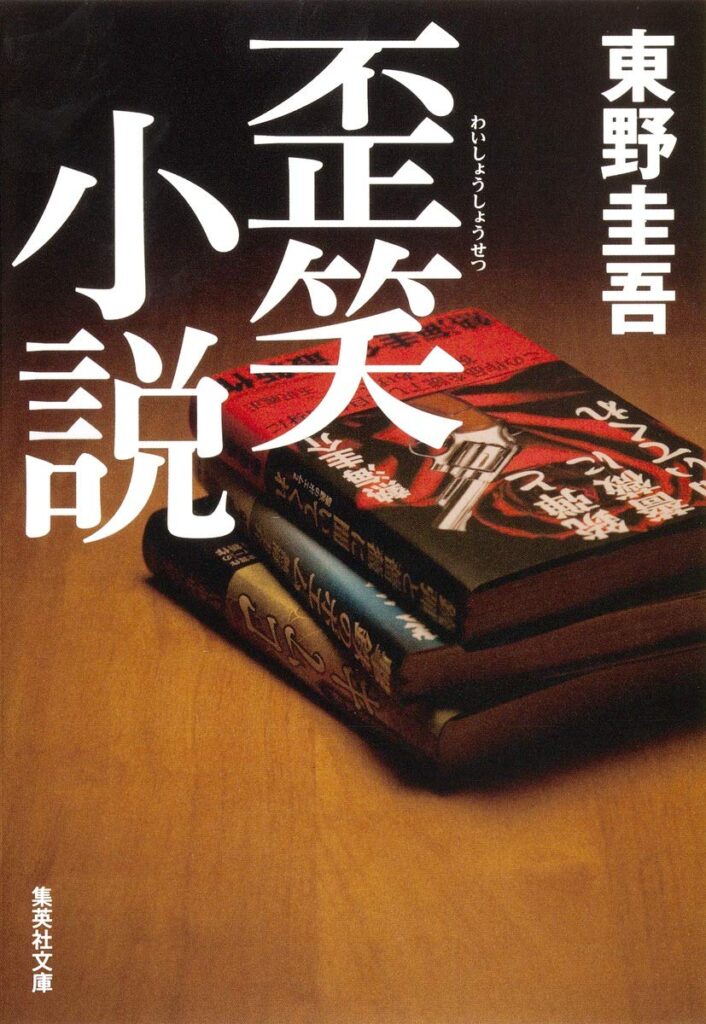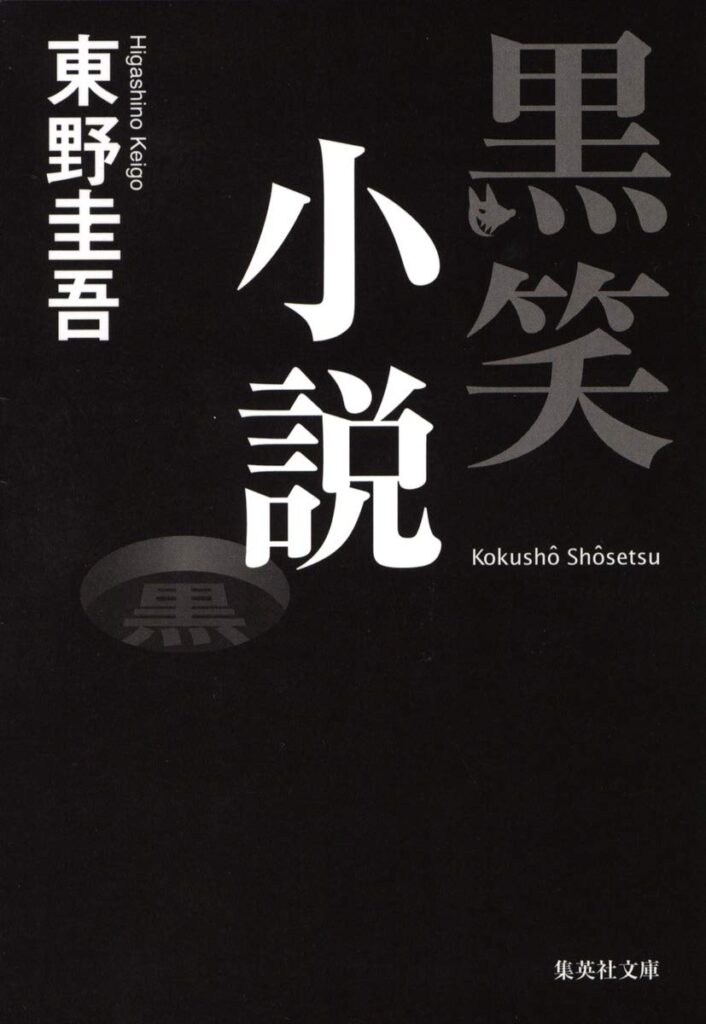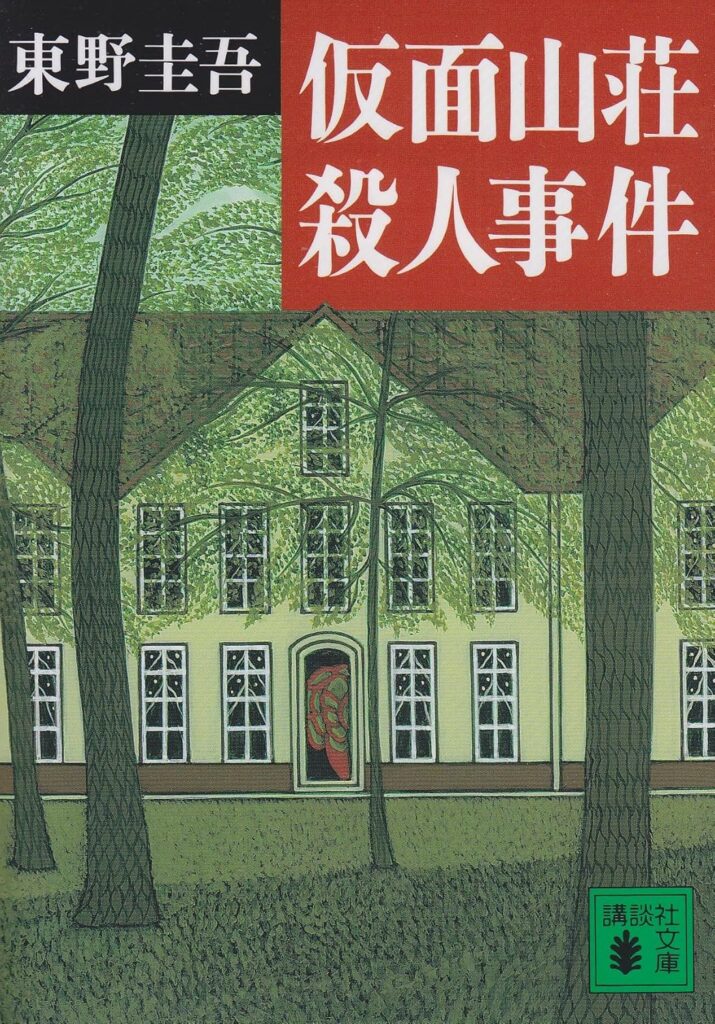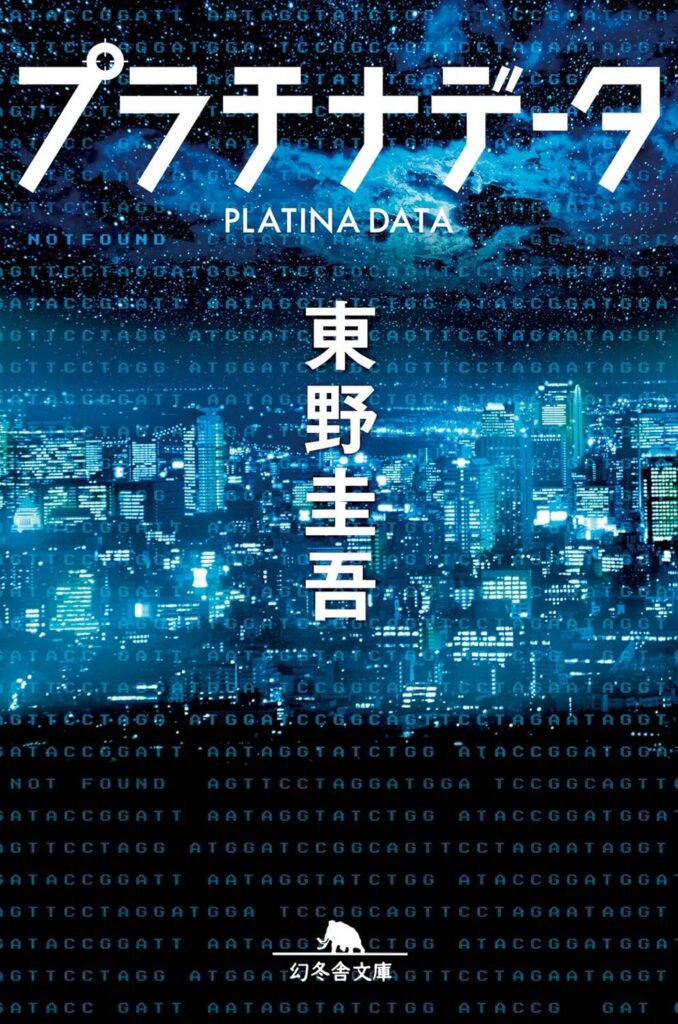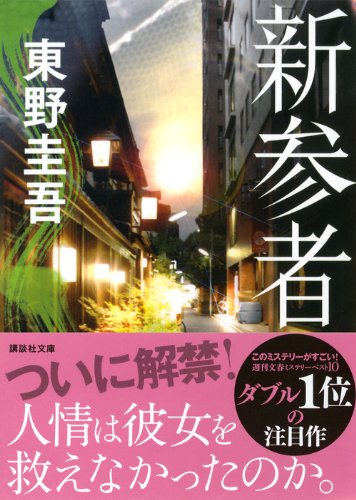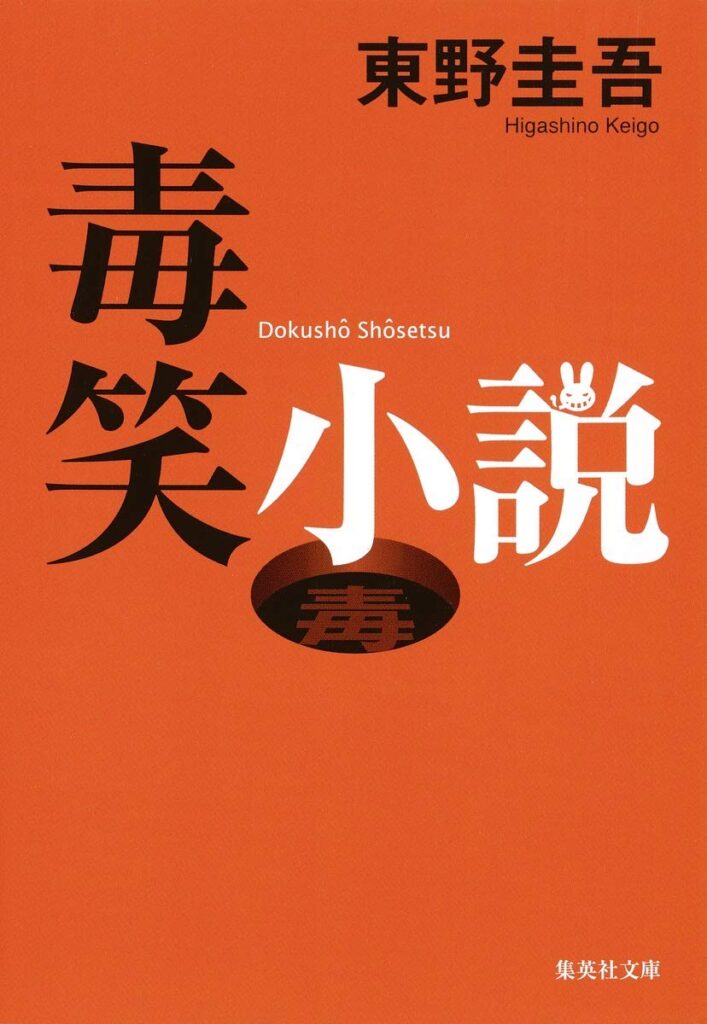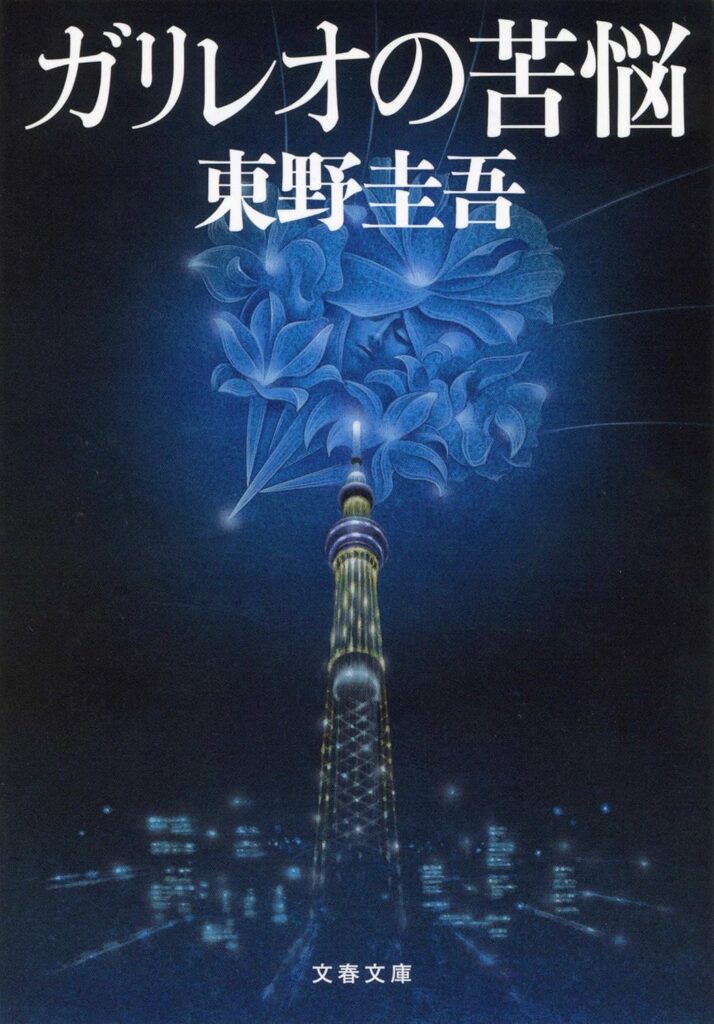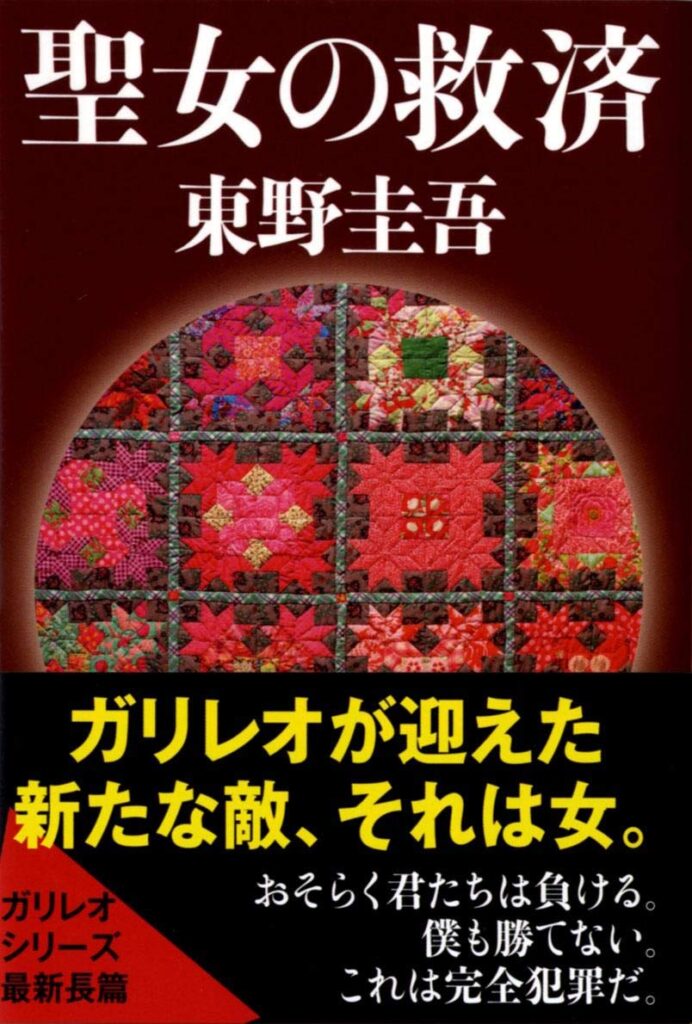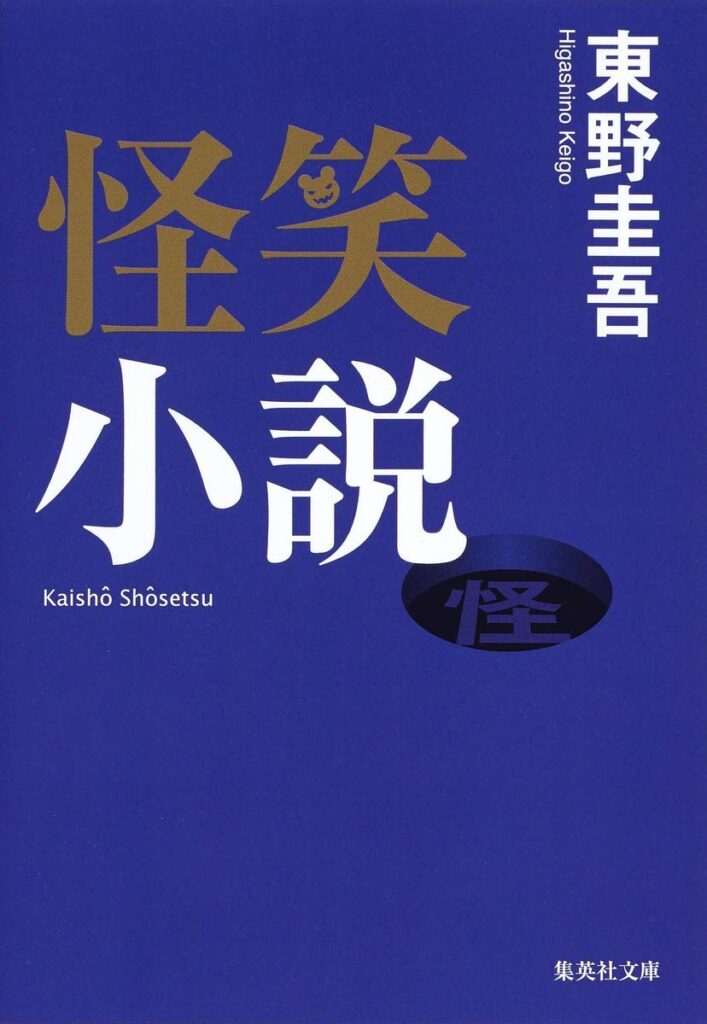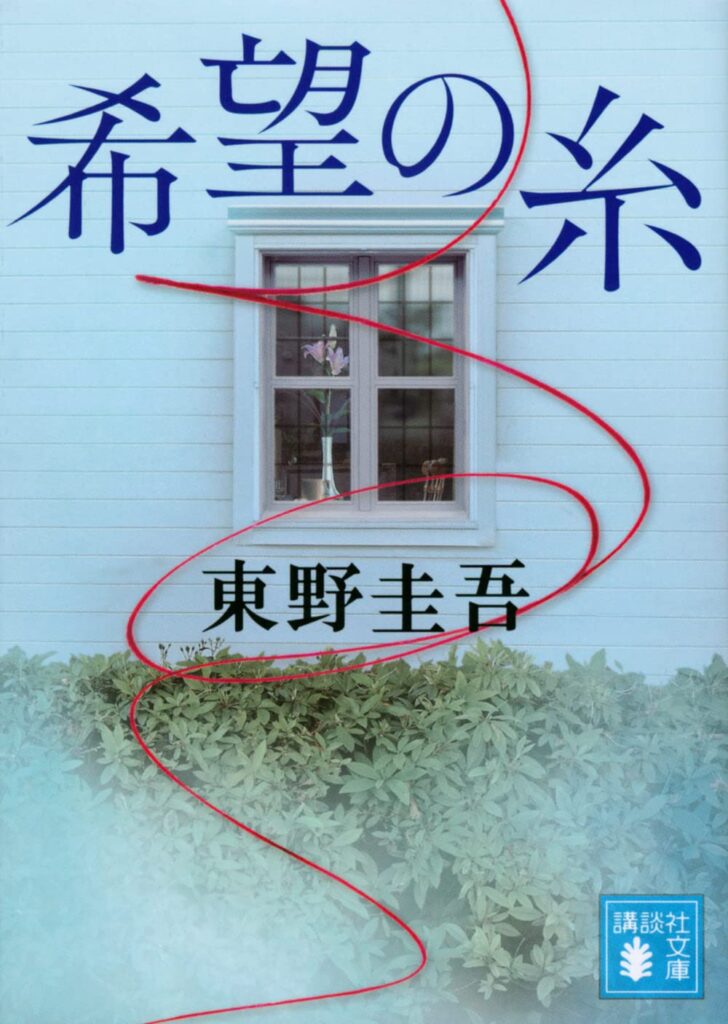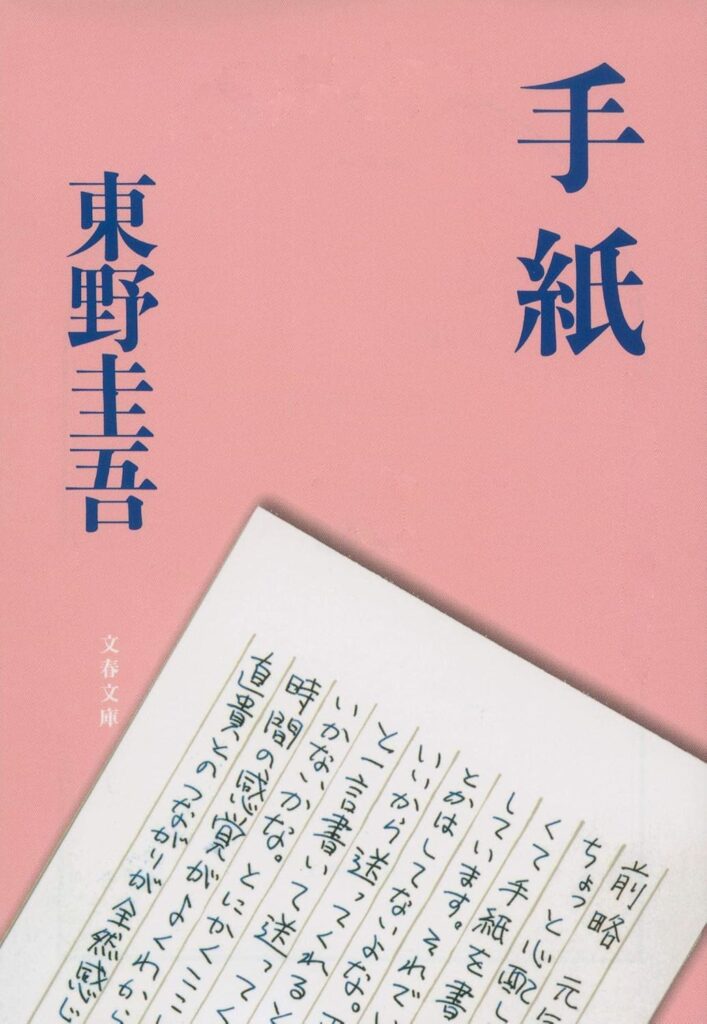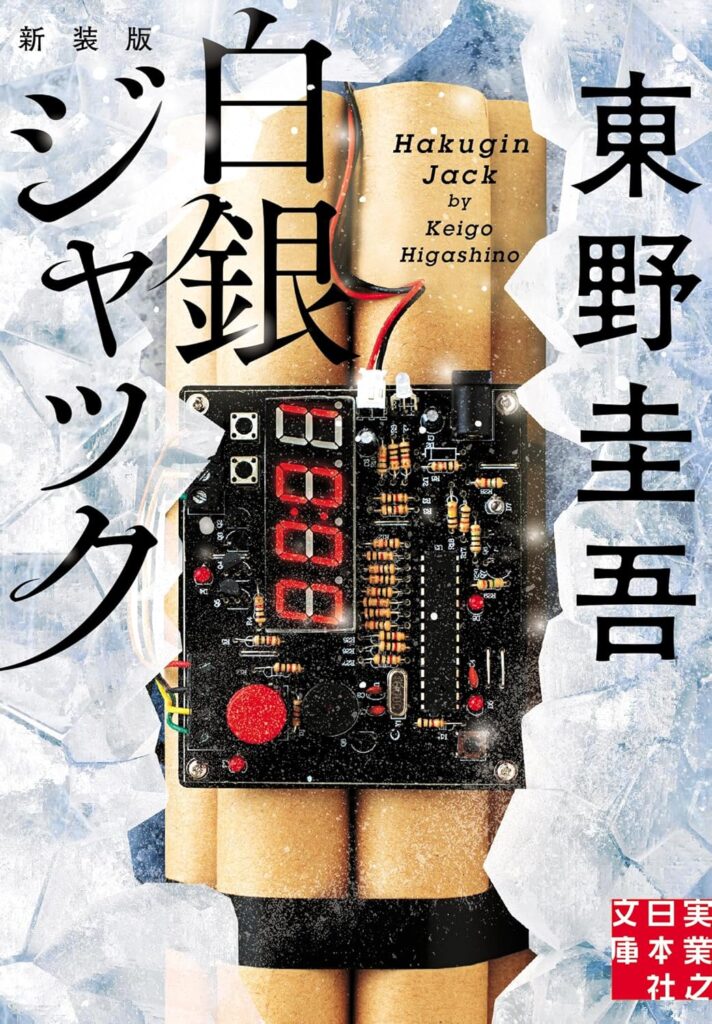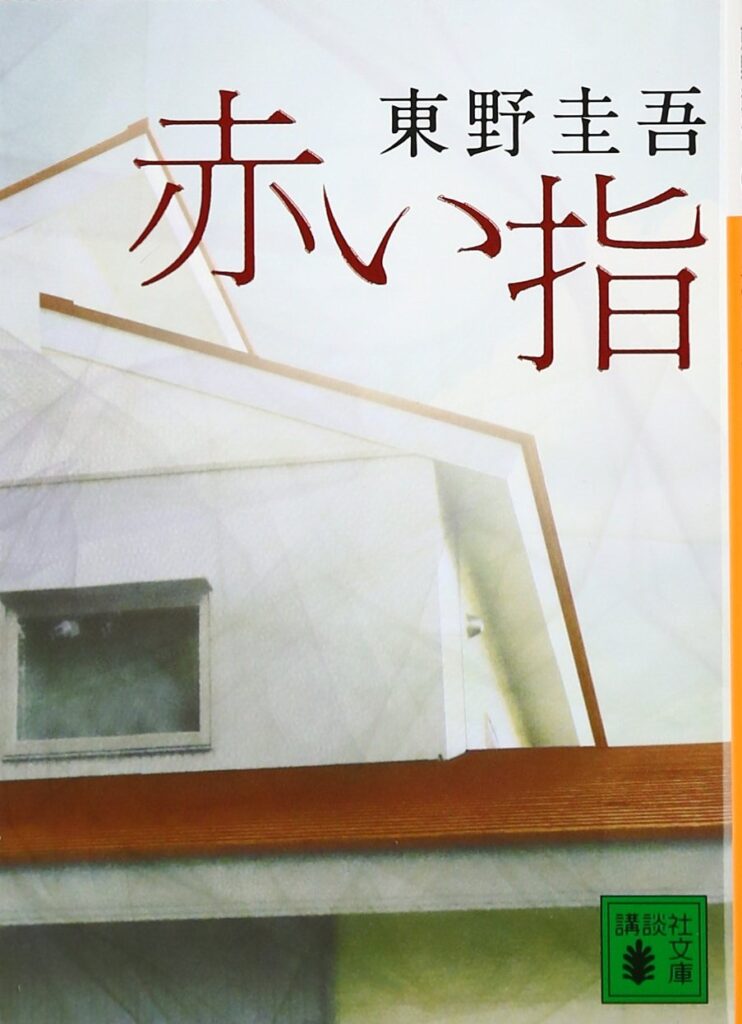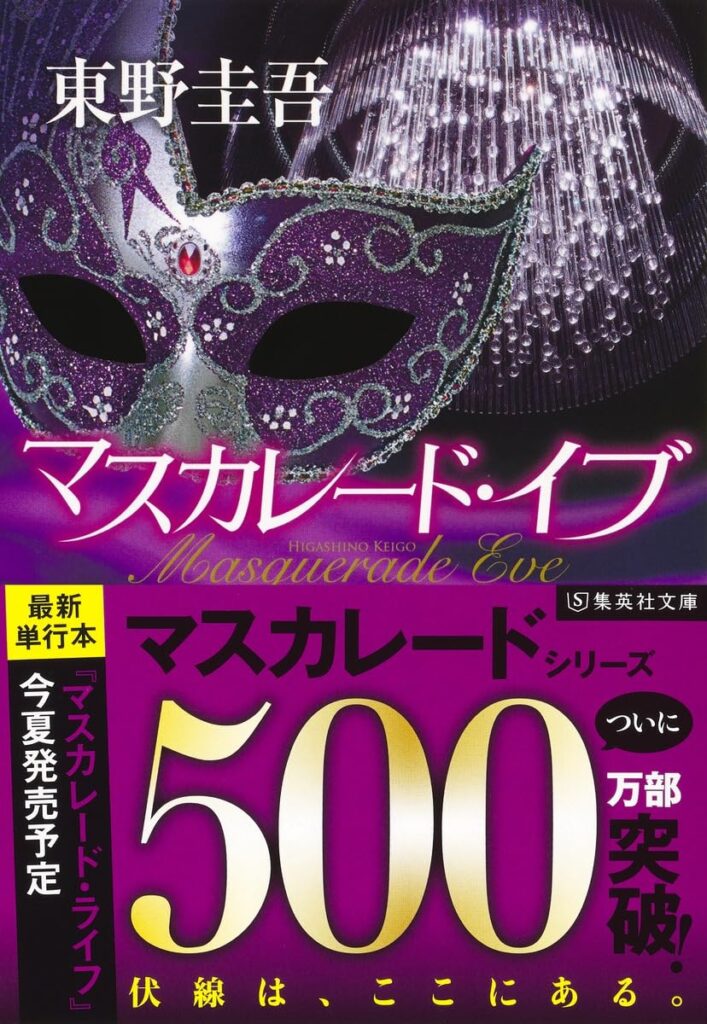小説『殺人現場は雲の上』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。東野圭吾氏がまだ若かりし頃に世に送り出した、少々風変わりなミステリ短編集であります。舞台は華やかな空の上…と見せかけて、実際には地上での滞在先、いわゆる「ステイ先」での出来事が中心となることが多いのは、ご愛嬌といったところでしょうか。
小説『殺人現場は雲の上』のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。東野圭吾氏がまだ若かりし頃に世に送り出した、少々風変わりなミステリ短編集であります。舞台は華やかな空の上…と見せかけて、実際には地上での滞在先、いわゆる「ステイ先」での出来事が中心となることが多いのは、ご愛嬌といったところでしょうか。
主役を務めるのは、新日本航空に籍を置く二人のスチュワーデス、早瀬英子(エー子)と藤真美子(ビー子)。容姿も性格も対照的ながら、なぜかウマが合う同期入社のルームメイトという間柄です。この凸凹コンビが、フライト先や日常で遭遇する奇妙な事件の数々に、持ち前の(あるいは、やや首を突っ込みたがる)性格から挑んでいく、そんな物語が7編収められています。
本稿では、この『殺人現場は雲の上』について、物語の概要、そして核心に触れる部分も含めた詳しい顛末、さらには、この作品に対する私のやや斜に構えた見解をたっぷりと語らせていただきます。しばし、お付き合いいただければ幸いです。
小説「殺人現場は雲の上」の物語概要
『殺人現場は雲の上』は、新日本航空の客室乗務員、早瀬英子(エー子)と藤真美子(ビー子)という、好対照な二人が主人公の連作短編集です。しっかり者で観察眼の鋭いエー子と、少しおっとりしていて時にドジを踏むこともあるビー子。彼女たちは同期入社でルームメイトでもあり、公私ともに良き相棒であります。そんな二人が、乗務するフライトや滞在先のホテルなどで、思いがけず様々な事件に巻き込まれていくのです。
表題作にもなっている「ステイの夜は殺人の夜」では、鹿児島でのフライト後、宿泊先のホテルで、乗客だった大学助教授・本間と再会し、バーで飲み明かします。ところが翌朝、本間の妻がホテルの密室状態の部屋で遺体となって発見されるのです。本間にはエー子たちが証人となる鉄壁のアリバイがありましたが、事件の真相は一体どこにあるのか。二人は素人探偵として、警察とは違う視点から謎に迫ります。
他の収録作も、それぞれに捻りの効いた状況設定がなされています。「忘れ物に御注意ください」では、ベビー・ツアーの機内に赤ちゃんが一人取り残されるという不可解な事態が発生。「お見合いシートのシンデレラ」では、ビー子がフライト中に知り合った大富豪の男性から突然プロポーズされますが、その裏には意外な事情が隠されています。「旅は道連れミステリアス」では、馴染みの和菓子屋の主人が不可解な死を遂げ、保険金殺人の疑いが浮上します。
その他、「とても大事な落し物」では機内で発見された遺書を巡る騒動、「マボロシの乗客」では存在しないはずの乗客が関わる殺人予告電話、そして「狙われたエー子」では、エー子自身の過去と安全が脅かされる事件が描かれます。いずれの物語も、エー子とビー子の掛け合いを交えながら、彼女たちの視点で事件の真相が解き明かされていく構成となっています。空の上という特殊な環境、あるいはステイ先という非日常空間で起こるミステリ、それが本作の持ち味と言えるでしょう。
小説「殺人現場は雲の上」の長文見解(結末への言及あり)
さて、東野圭吾氏の初期作品群に位置づけられる『殺人現場は雲の上』。今や押しも押されもせぬ国民的作家となった氏の、ある種の「習作期」とも言える時代の作品でありまして、その評価はなかなか一筋縄ではいかないものがあります。まあ、結論から申し上げるなら、手放しで絶賛する類のものではない、というのが私の見解です。しかしながら、後の大成を予感させるいくつかの要素や、この時代ならではの粗削りな魅力も確かに存在します。長々となりますが、その辺りを詳しく語らせていただきましょうか。結末に触れる箇所もありますので、未読の方はご留意いただきたい。
まず、この作品集の核となるのは、言うまでもなくエー子とビー子のキャラクター造形でしょう。しっかり者で美人、頭も切れるエー子。対して、ややおっちょこちょいでお人好し、容姿もエー子には一歩譲る(と作中で描写される)ビー子。この典型的な凸凹コンビが、軽妙な会話を繰り広げながら事件に首を突っ込んでいく。これはミステリにおける定番の形式であり、安定した面白さを提供する装置として機能しています。特に、二人の掛け合いは、時にシニカルで、時にコミカル。物語全体を引っ張っていく原動力となっていることは間違いありません。東野氏の姉が実際にスチュワーデスだったという背景も、この職業描写にリアリティ(あるいは、当時のイメージとしてのリアリティ)を与えているのかもしれません。
しかし、このキャラクター造形、現代の視点から見ると、少々ステレオタイプが過ぎる感は否めません。特にビー子の描かれ方は、やや「ドジな女の子」としての役割に固定されすぎているきらいがあります。「お見合いシートのシンデレラ」で見せるような、ビー子の純粋さやロマンチストな一面は微笑ましくもありますが、全体を通して見ると、エー子の引き立て役、あるいはトラブルメーカーとしての側面が強調されがちです。エー子にしても、「才色兼備」という枠組みから大きく逸脱することはありません。この辺りは、刊行された時代の空気感を反映しているとも言えますが、現代の多様な女性像に慣れた目からすると、少々物足りなさを感じる部分ではあります。
ミステリとしての構成に目を向けてみましょう。収録されているのは7つの短編。それぞれが独立した事件を扱っています。表題作「ステイの夜は殺人の夜」は、比較的オーソドックスなフーダニット(Who done it? = 誰がやったか)であり、アリバイ崩しが主眼となっています。ホテルの客室という限定された空間、容疑者である夫の完璧すぎるアリバイ。エー子とビー子が、警察とは異なる視点、すなわち「客室乗務員」としての観察眼や知識(例えば、ホテルの構造や人間の行動パターンに対する細かな気づき)を活かして真相に迫っていく過程は、それなりに読ませます。特に、被害者の甥である田辺秀一が叔母に変装してサンドイッチを受け取ったのではないか、という推理は、意外性もあって面白い。そして、最終的に本間と田辺が共犯であったという真相が明らかになる展開は、一応の決着を見ます。
ただ、このトリック、あるいは真相に至るまでのロジックには、やや甘さが感じられます。例えば、死亡推定時刻の特定方法が胃の内容物のみに頼っている点や、変装トリックの実現可能性など、細かく見ていくと疑問符が付く箇所がないわけではありません。まあ、これは1989年刊行という時代を考慮すべき点かもしれません。科学捜査が現在ほど発達していなかった時代設定として読む必要がありましょう。他の短編にしても、「忘れ物に御注意ください」の赤ん坊取り違えトリックや、「お見合いシートのシンデレラ」のプロポーズの真相、「マボロシの乗客」の存在しない乗客の謎など、アイデア自体は悪くないのですが、解決に至るまでの伏線の張り方や論理展開が、やや強引であったり、ご都合主義的に感じられたりする部分が見受けられます。「旅は道連れミステリアス」における保険金殺人の動機なども、やや類型的な印象を受けます。
特に気になるのは、いくつかの短編において、エー子とビー子が「素人探偵」として真相にたどり着く過程の描写です。彼女たちの推理が、時に直感や思い込みに頼りすぎているように見えることがあります。もちろん、それが素人探偵の魅力でもあるのですが、もう少し説得力のある根拠付けや、地道な調査の描写があれば、ミステリとしての完成度は高まったのではないか、と感じます。警察の捜査が後手に回りがちなのも、物語の都合とはいえ、少々気になるところです。望月刑事などは、最終的には二人の推理を受け入れるものの、当初はかなり懐疑的であり、そのやり取り自体はリアルかもしれませんが、もう少しプロフェッショナルとしての矜持を見せてほしかった、とも思います。
また、タイトルにある「殺人現場は雲の上」という言葉。これは非常にキャッチーで魅力的ですが、実際のところ、事件の多くは地上、それもホテルのようなステイ先で発生しています。もちろん、「忘れ物に御注意ください」や「とても大事な落し物」のように機内が舞台となる話もありますが、タイトルから受ける印象ほど「空の上」がメインステージになっているわけではありません。この点については、少々看板に偽りあり、と言いたくなる読者もいるかもしれません。空の上という閉鎖空間で起こる本格ミステリを期待すると、肩透かしを食らう可能性はあります。
しかし、それでもなお、この作品集には読むべき価値がないわけではありません。まず、東野圭吾氏らしい読みやすい文章と、テンポの良いストーリーテリングは、この初期作品においても健在です。難解な専門用語や衒学的な描写は少なく、エンターテインメントとして素直に楽しめる作りになっています。特に、エー子とビー子の会話は、その後の氏の作品にも通じる軽快さがあり、読者を飽きさせません。
そして、特筆すべきは、後の作品で見られるような社会的なテーマや、人間の心の闇といった要素はまだ希薄ながらも、その萌芽のようなものが感じられる点です。「旅は道連れミステリアス」での保険金を巡る人間の欲や、「狙われたエー子」で描かれる過去の人間関係のもつれなどは、後の深遠な人間ドラマへと繋がっていく片鱗を見せていると言えなくもありません。また、「お見合いシートのシンデレラ」における、一見ロマンティックな出会いの裏に隠された現実的な事情などは、甘いだけではない世の中の側面をさりげなく描いています。まるで色褪せたセピア色の写真を見るような、そんなノスタルジーと、当時の世相を感じさせる描写も、今となっては貴重な記録と言えるかもしれません。
全体を見渡してみますと、『殺人現場は雲の上』は、東野圭吾氏のキャリア初期における、意欲的でありながらも、まだ発展途上の作品であると言えるでしょう。キャラクターの魅力と読みやすさは特筆すべき点ですが、ミステリとしての構成やトリックの完成度には、後の作品に比べると見劣りする部分があるのは事実です。しかし、それは欠点であると同時に、若き日の東野氏の試行錯誤や、当時の時代の空気を伝える魅力ともなっています。完璧ではないからこその愛嬌、とでも言いましょうか。
これを最高傑作と呼ぶつもりは毛頭ありません。しかし、東野圭吾という作家の原点を探る上で、あるいは、肩の力を抜いて楽しめるライトなミステリを求める向きには、一読の価値はあるかもしれません。エー子とビー子のコンビが、その後シリーズ化されなかったのは、ある意味で正解だったのかもしれませんが、彼女たちの溌剌とした(あるいは、ややお騒がせな)活躍は、読者の記憶に確かな印象を残すことでしょう。そう、良くも悪くも、忘れがたい一冊ではあるのです。
まとめ
さて、東野圭吾氏の初期短編集『殺人現場は雲の上』について、物語の筋立てから、少々穿った見方まで語ってまいりました。新日本航空の客室乗務員、エー子とビー子のコンビが、ステイ先や機内で遭遇する事件に挑む、というのが基本的な構成であります。表題作を含む7つの短編が収録されており、それぞれに趣向を凝らしたミステリが展開されます。
この作品集の魅力は、何と言ってもエー子とビー子のキャラクター性と、二人の軽妙な掛け合いにあります。しっかり者のエー子と、おっとり型のビー子という対照的な二人が、時に協力し、時に反発しながら事件の真相に迫っていく様子は、読んでいて飽きさせません。東野氏ならではの読みやすい筆致も手伝って、エンターテインメント性は十分に確保されていると言えましょう。
ただし、ミステリとしての完成度やトリックの独創性という点では、後の円熟期にある作品群と比べると、やや物足りなさを感じる部分があるのも確かです。時代設定を考慮する必要はありますが、論理展開の甘さや、ご都合主義的な解決が見られる箇所も散見されます。それでも、後の大作家の片鱗や、当時の時代の空気を感じさせる点においては、興味深い一冊であります。完璧ではないからこその味わい、と捉えるのが妥当かもしれません。