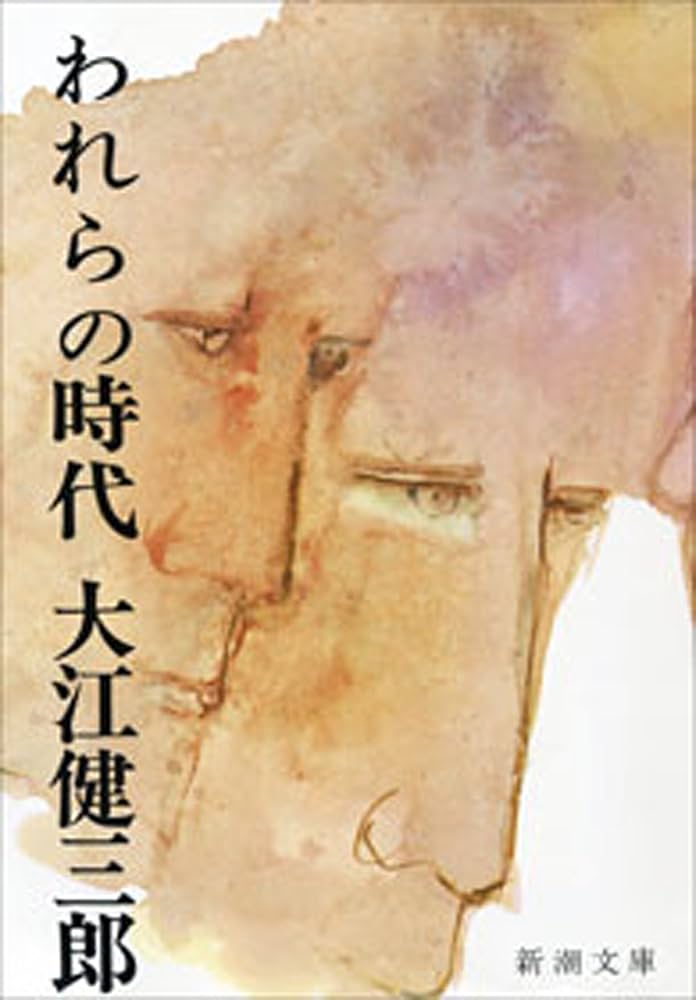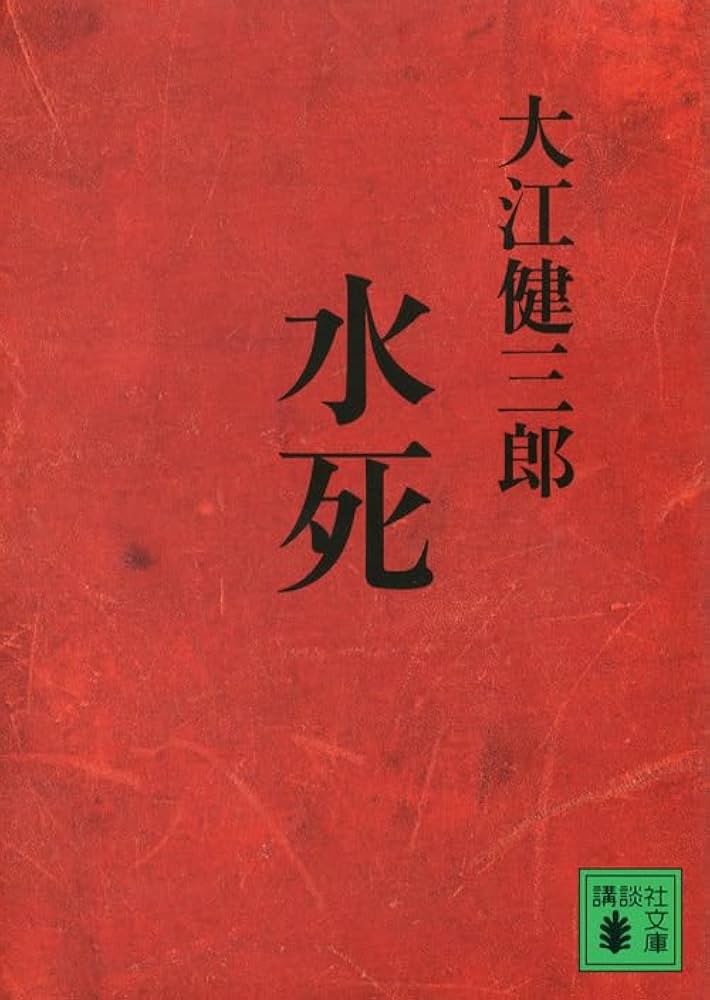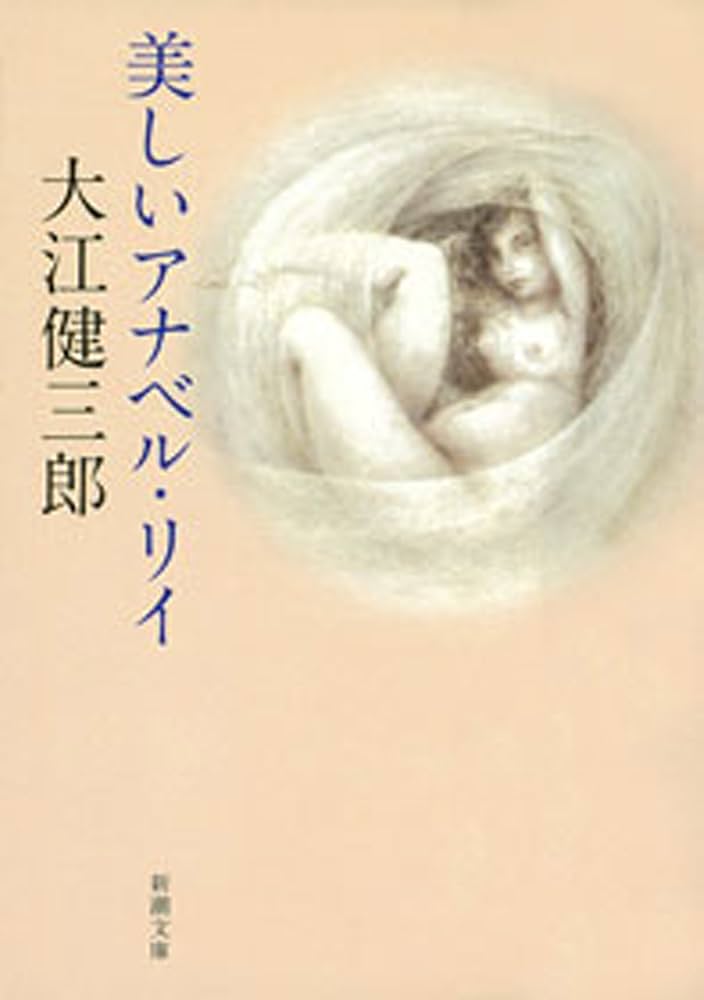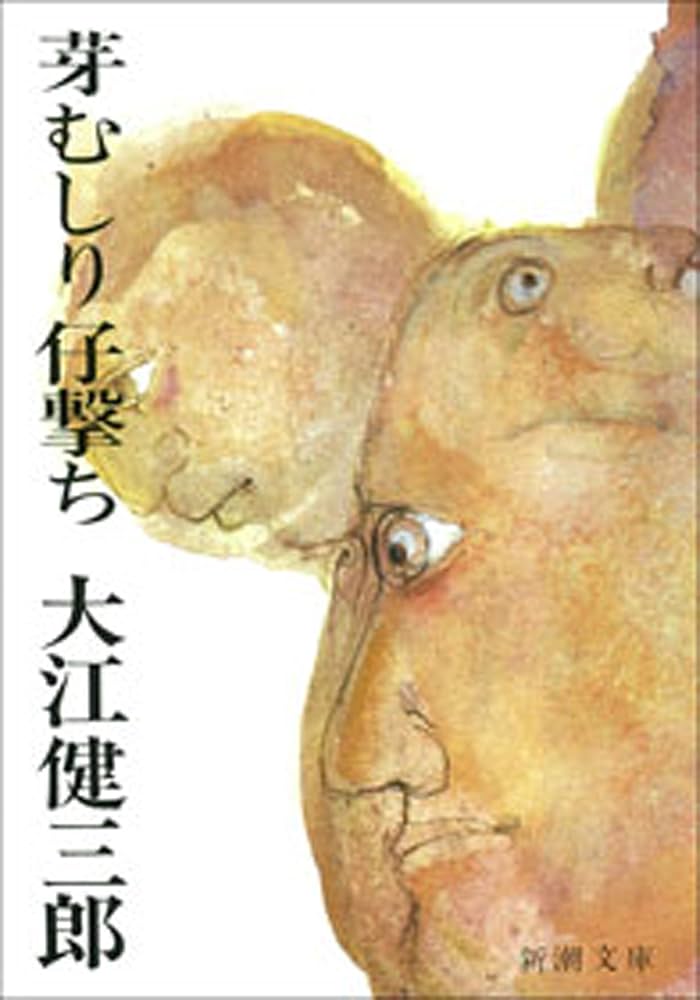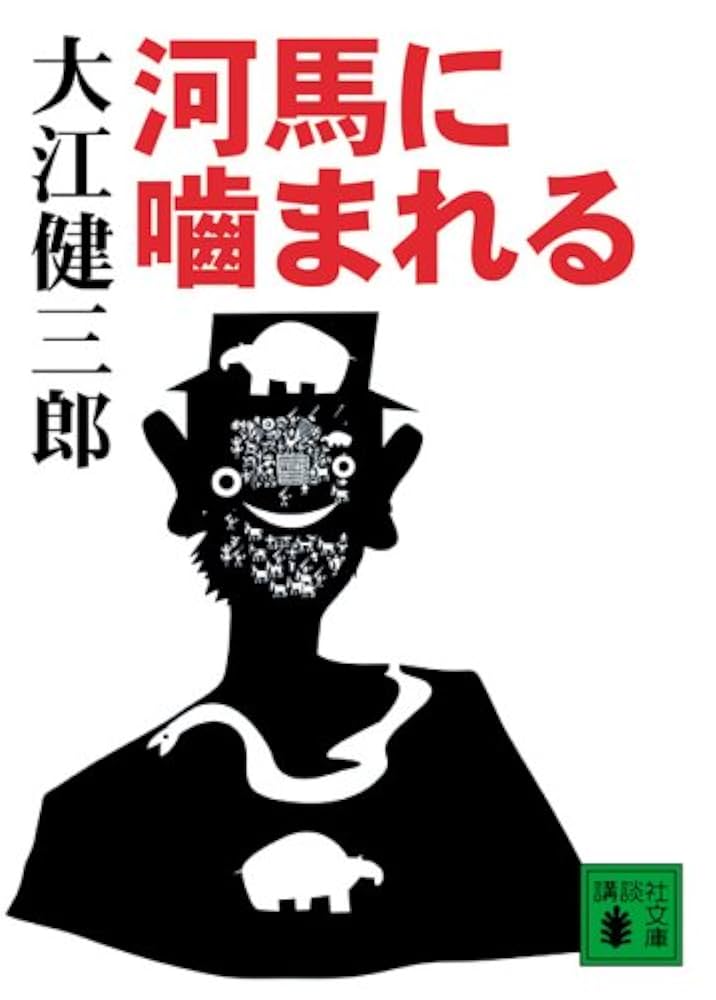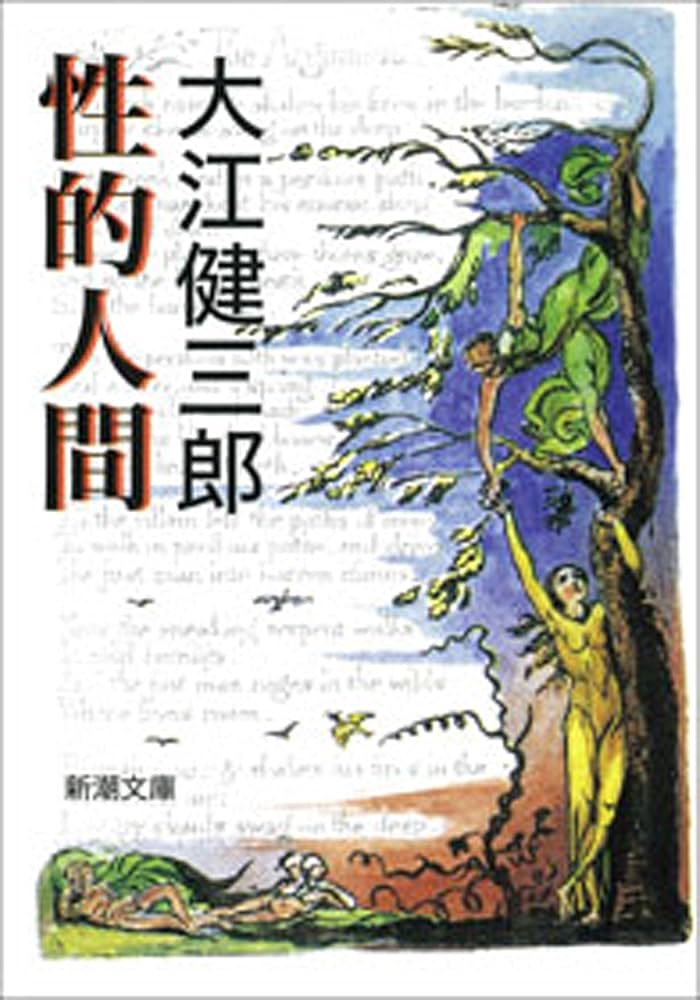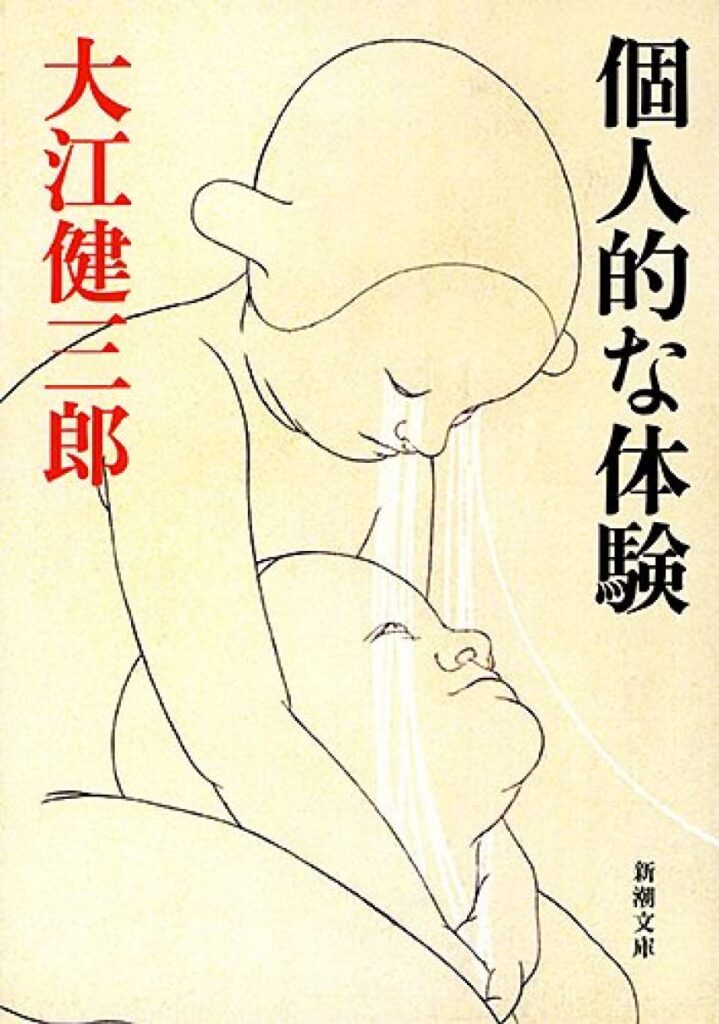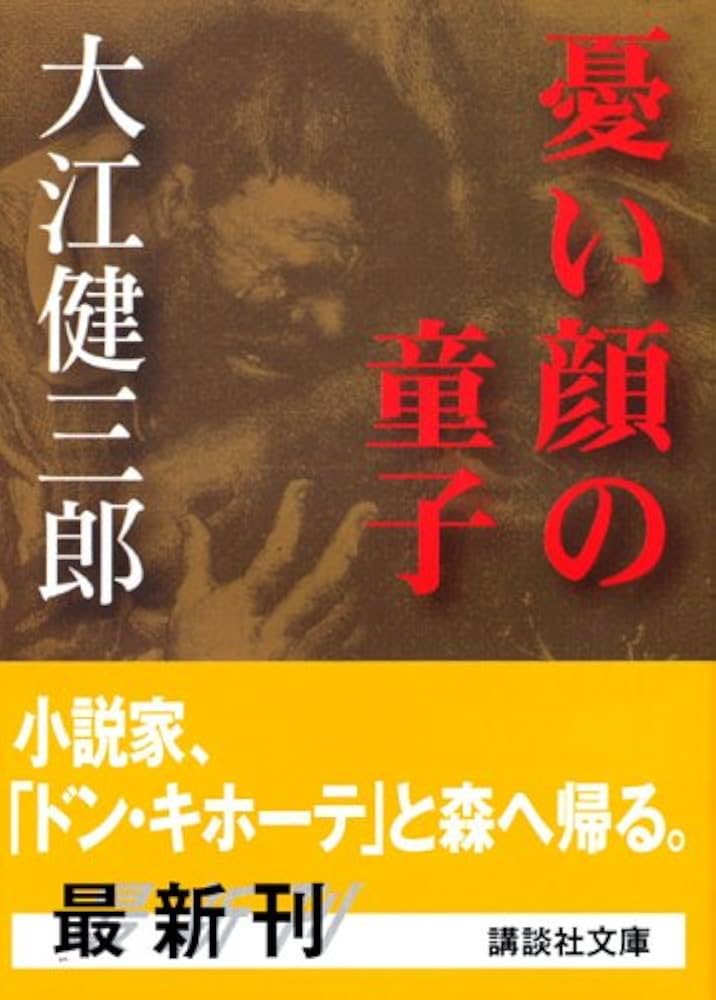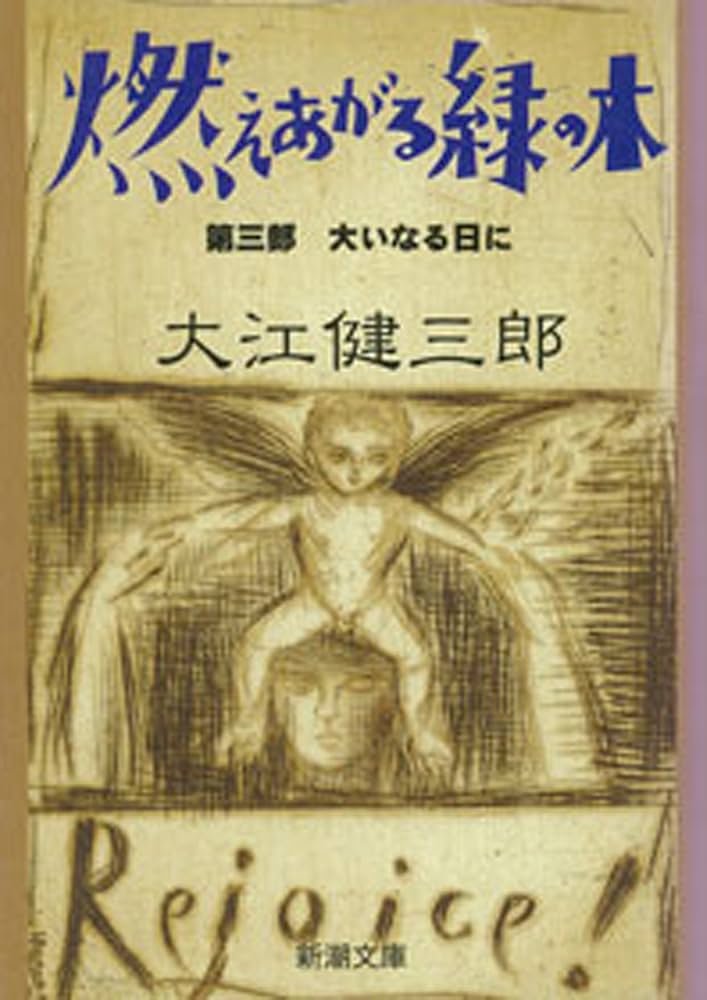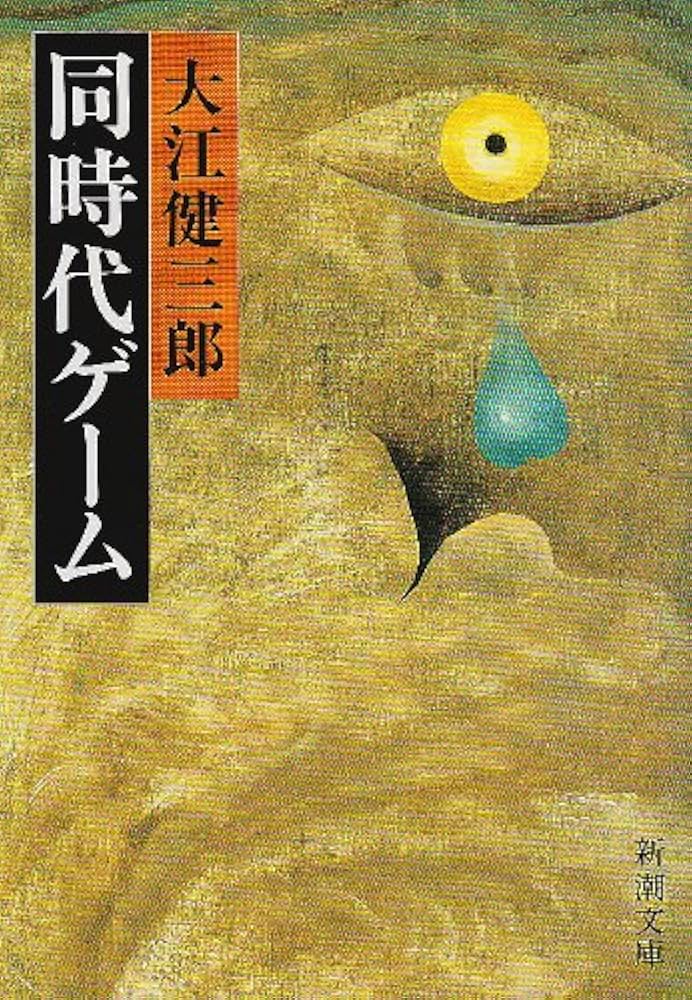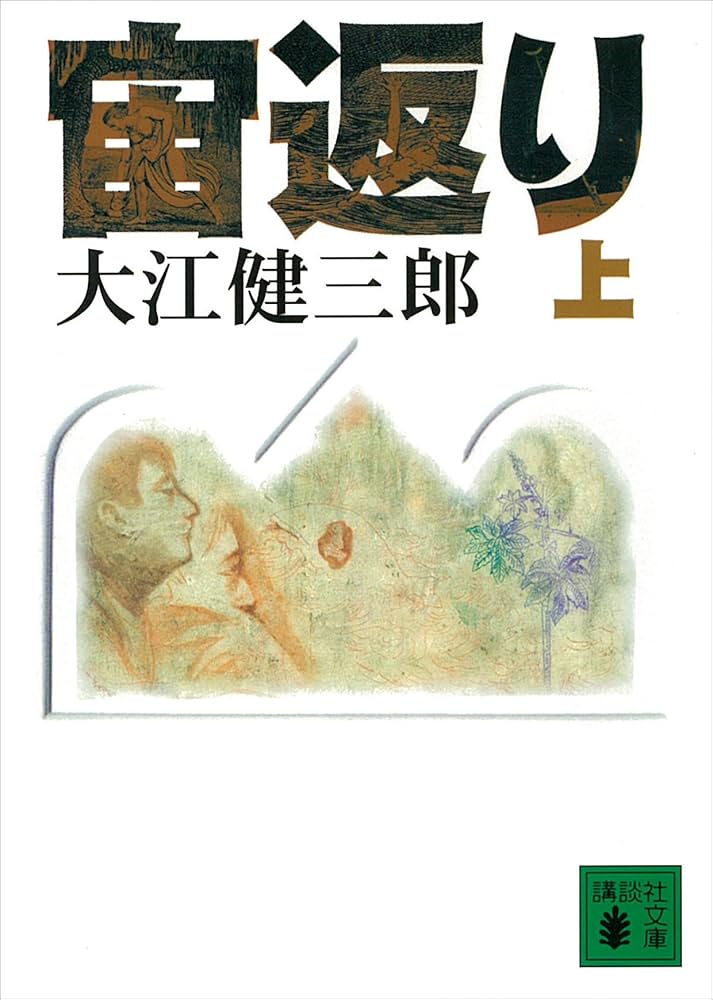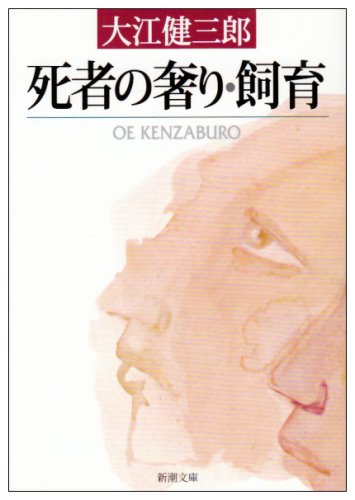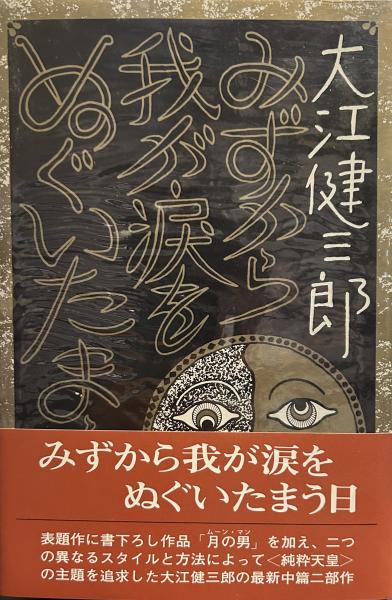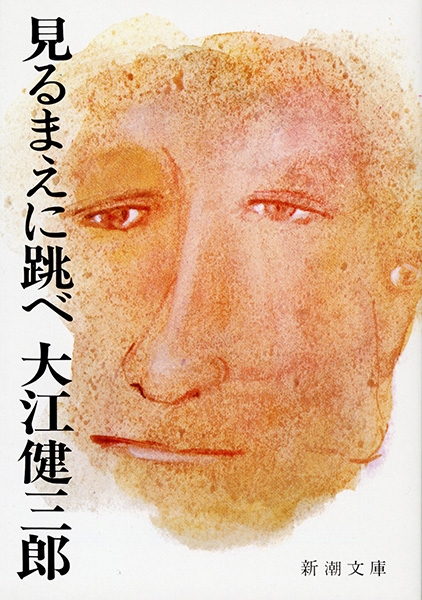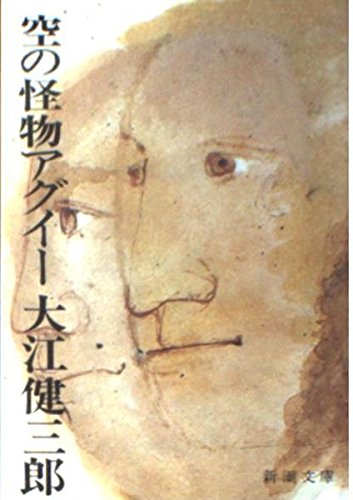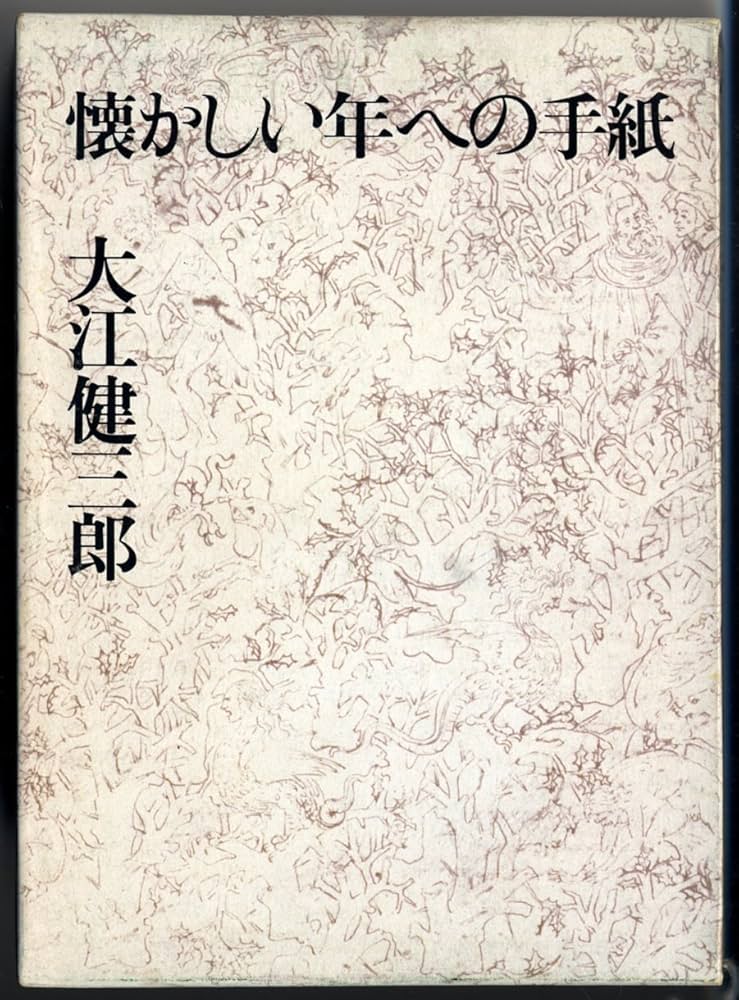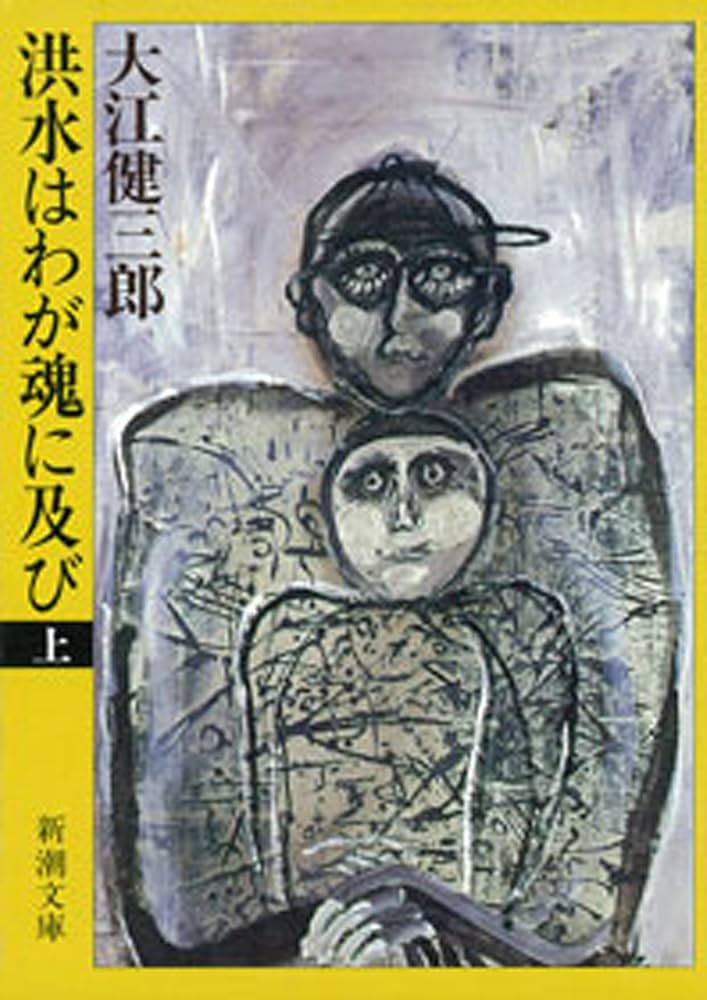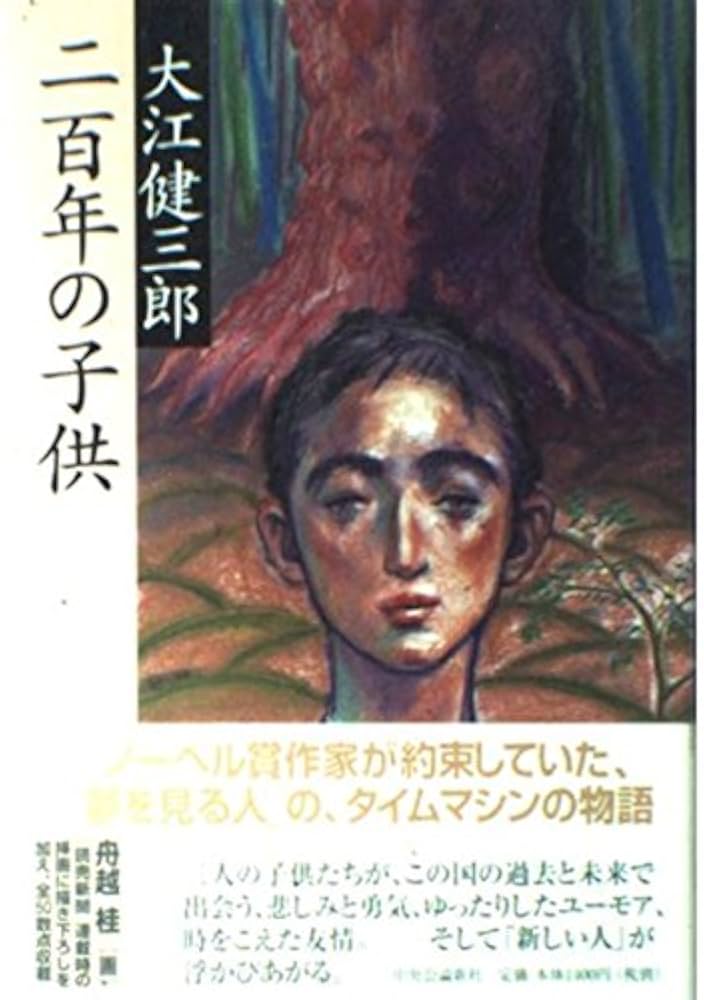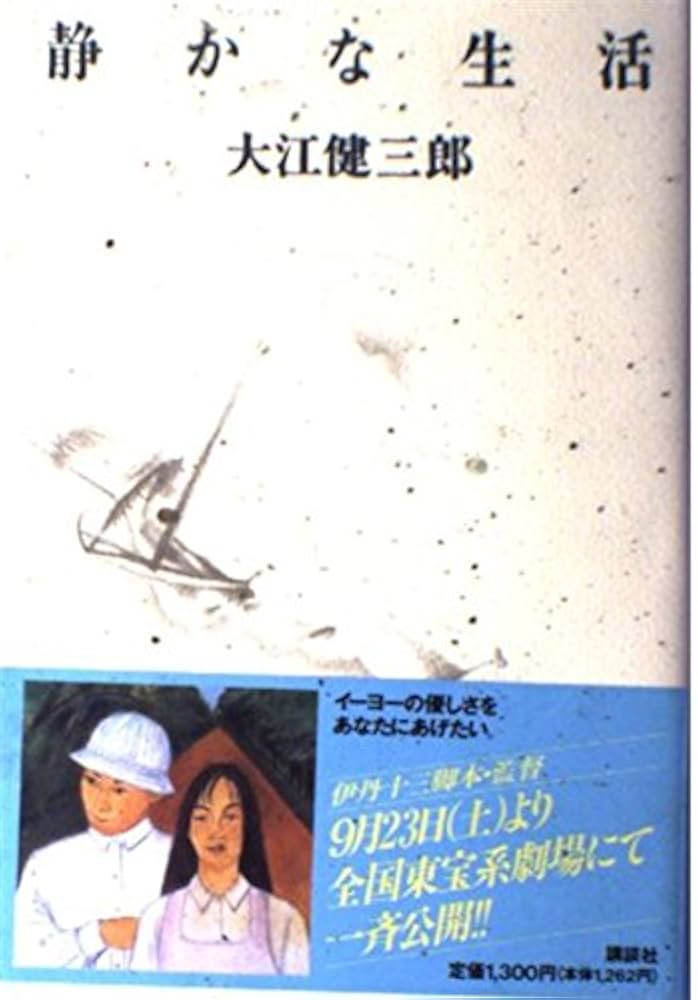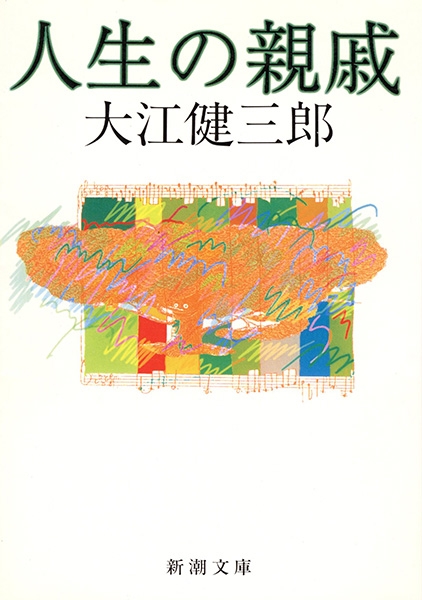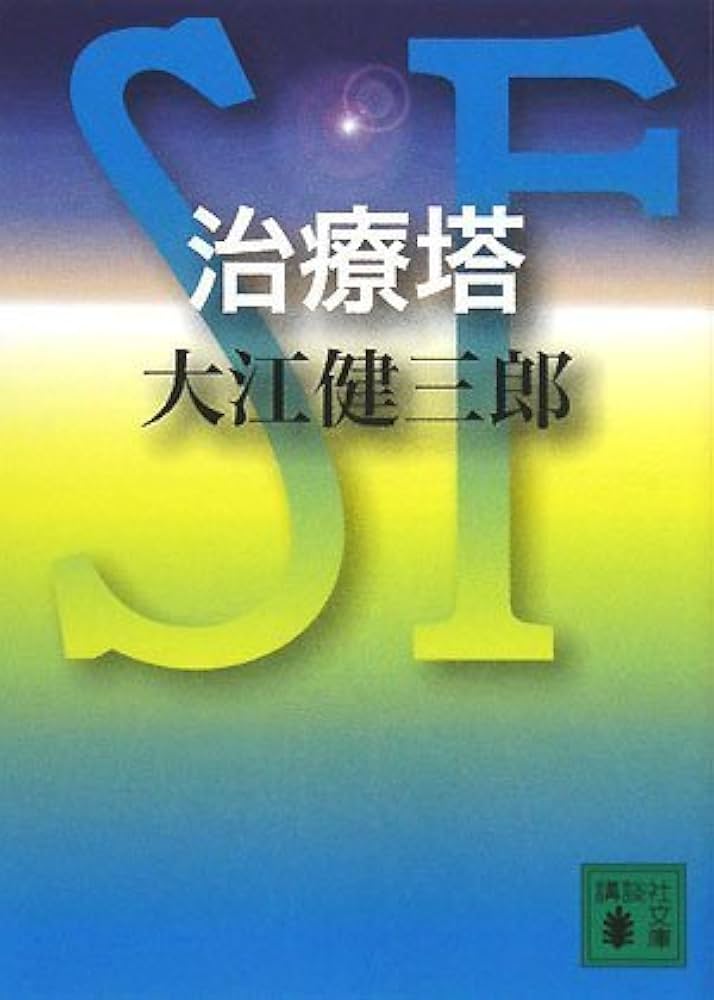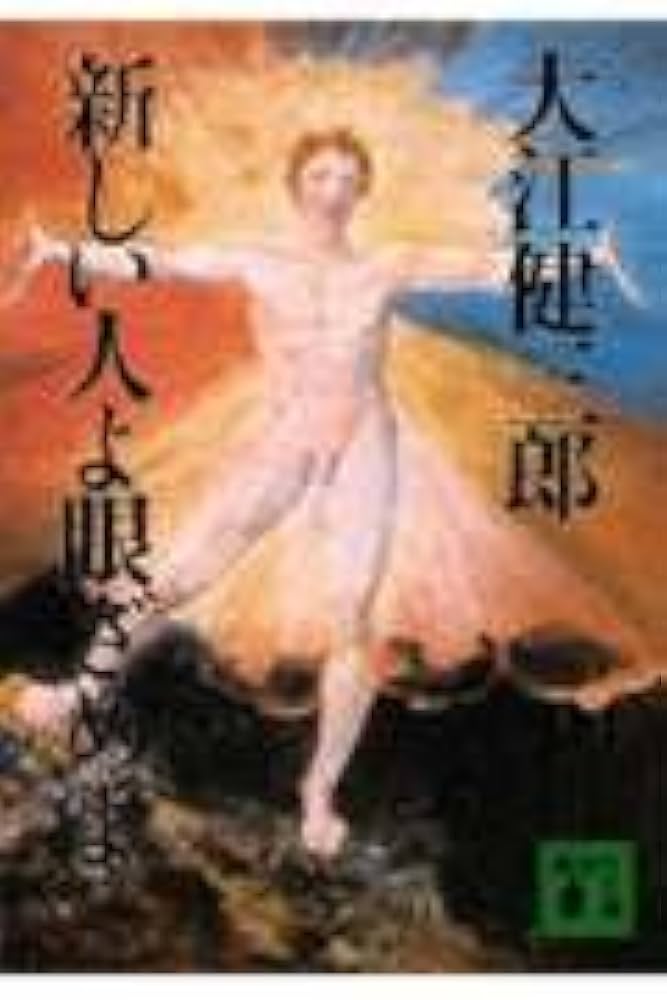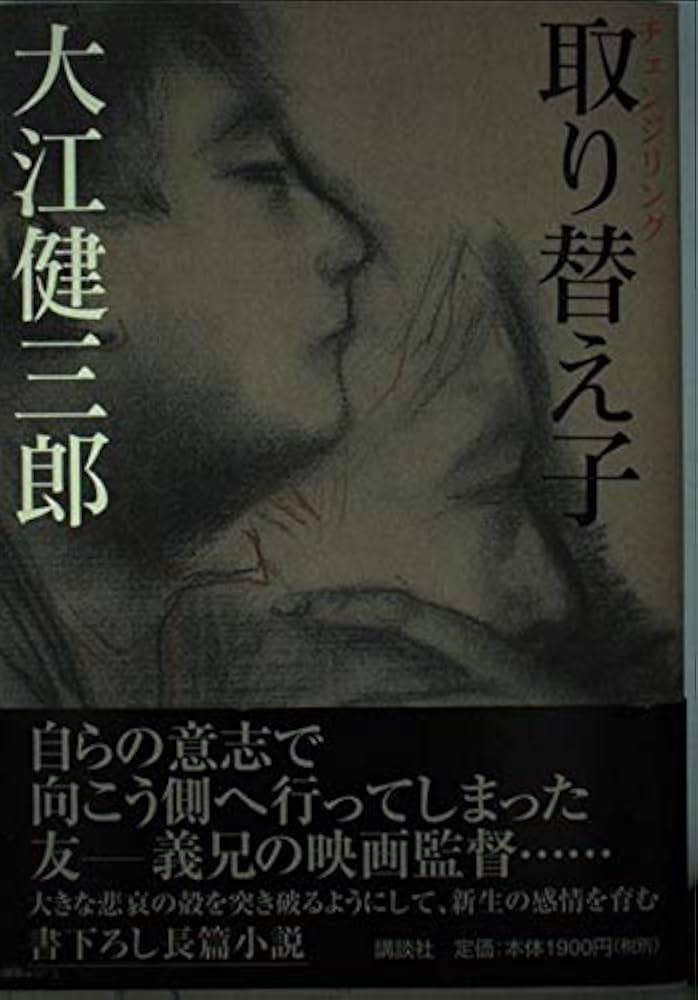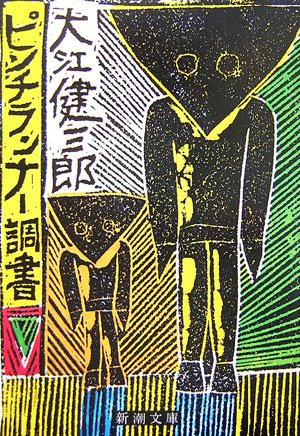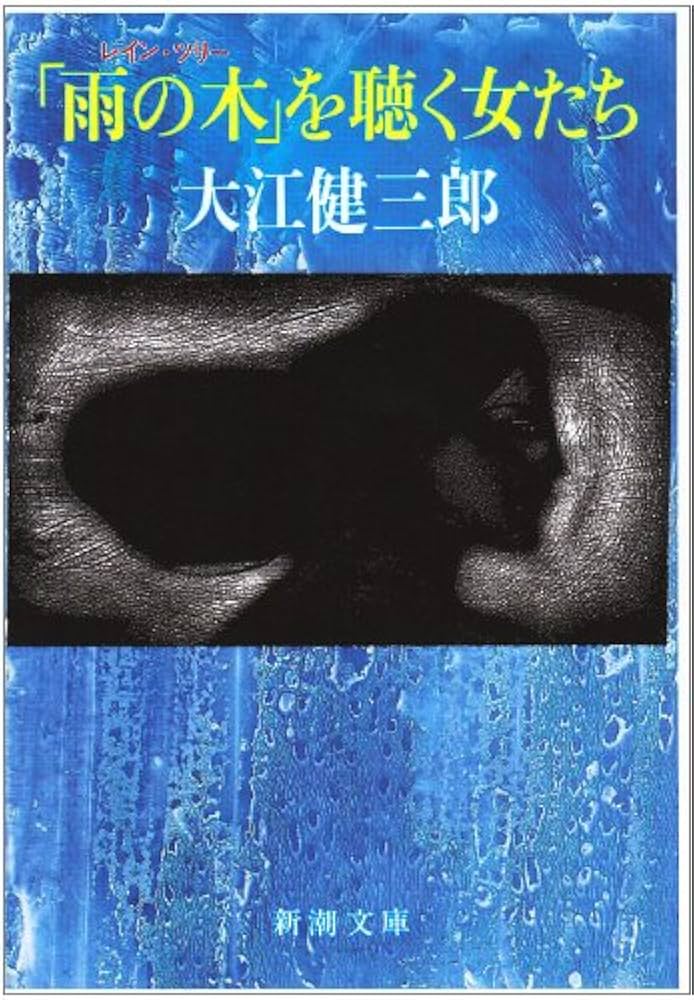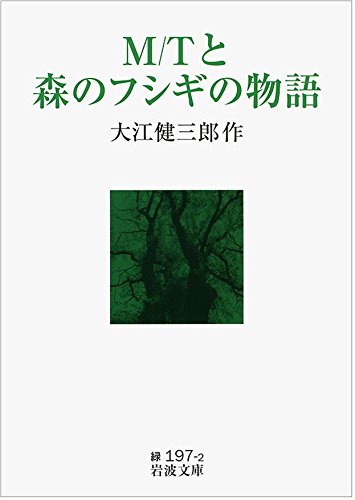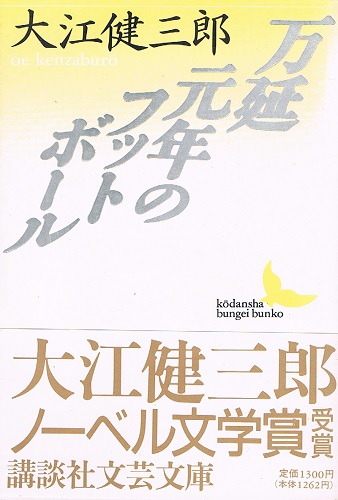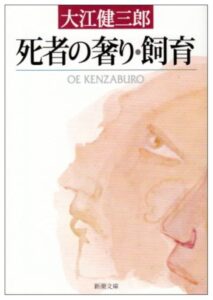 小説「死者の奢り」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この作品は、1957年に発表された大江健三郎の文壇デビュー作ともいえる短編小説です。第38回芥川賞の候補作にもなった本作は、その衝撃的な内容とテーマ性で、今なお多くの読者に読み継がれています。
小説「死者の奢り」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この作品は、1957年に発表された大江健三郎の文壇デビュー作ともいえる短編小説です。第38回芥川賞の候補作にもなった本作は、その衝撃的な内容とテーマ性で、今なお多くの読者に読み継がれています。
物語の舞台は大学医学部の薄暗い地下室。主人公の「僕」が応募したのは、解剖用の死体を処理するという奇妙なアルバイトです。そこで彼は、圧倒的な存在感を放つ死体の群れと、そして「生」の現実に苦しむ一人の女子学生と向き合うことになります。この記事では、「死者の奢り」がえぐる、生と死、そして人間の営みの不条理さについて、深く掘り下げていきます。
この記事を読むことで、「死者の奢り」がどのような物語であるか、その核心にあるテーマは何なのかをご理解いただけるはずです。物語の結末に触れるネタバレも含まれていますので、未読の方はご注意ください。しかし、この結末こそが、本作をただの物語以上のものにしているのです。
それでは、大江健三郎が若き日に描き出した、強烈な閉塞感と虚無感が渦巻く世界へご案内します。この物語が投げかける問いに、あなたは何を感じるでしょうか。
「死者の奢り」のあらすじ
主人公である文学部の学生「僕」は、高給に惹かれて大学医学部の奇妙なアルバイトに応募します。その仕事内容は、地下の死体処理室で、アルコールの水槽に保存されている解剖用の死体を新しい水槽へと移し替えるというものでした。じめじめとした閉鎖的な空間で、「僕」は同じくアルバイトに来ていた女子学生と共に、ベテランの管理人の指示のもと作業を始めます。
水槽の中には、濃褐色の液体に浸された数十体の死体が無秩序に重なり合っています。「僕」は、生きた人間が持つ曖昧さとは対照的な、完全な「物」としての死体に、ある種の確固たる存在感を感じ取ります。作業の休憩中、女子学生は「僕」に、自分が妊娠していること、そして中絶手術の費用を稼ぐためにこの仕事を選んだことを打ち明けます。
彼女は、命を生む責任と、命を奪う責任との間で深く苦悩していました。しかし、「僕」は彼女の深刻な告白に対して、戸惑い、無関心な態度しか取ることができません。生者の世界で渦巻く切実な問題と、物言わぬ死者たちの圧倒的な存在。その二つの間で、「僕」の無気力な心は揺れ動きます。
やがて、夕方になり、すべての死体を運び終えた彼らに、医学部の助教授から衝撃的な事実が告げられます。それは、彼らが懸命に行った作業が、実は全くの無意味であったという信じがたい知らせでした。物語は、解決の糸口が見えないまま、さらなる不条理な労働の始まりを予感させて幕を閉じます。
「死者の奢り」の長文感想(ネタバレあり)
大江健三郎の初期の代表作『死者の奢り』は、読むたびにずしりとした重みを心に残していく作品です。それは単に死体を扱う不気味な物語というだけではなく、生と死、責任、そしてどうしようもない徒労感といった、人間が普遍的に抱えるテーマを鮮烈に描き出しているからでしょう。
主人公の「僕」は、どこか世の中を斜に構えて見ているような、無気力な学生です。彼が死体を移し替えるアルバイトを選ぶのも、そこに何か特別な意味を見出しているわけではなく、ただ時給が良いからです。彼のこの態度は、物語全体を覆う虚無的な空気感の源となっています。
彼と対照的に描かれるのが、同じアルバイトに参加する女子学生です。彼女は妊娠という、まさに「生」の渦中にいます。堕胎費用を稼ぐために死体を運ぶという皮肉な状況の中で、彼女は命に対する責任に苦悩します。彼女の存在は、「僕」の無関心さや傍観者的な態度を際立たせる役割を担っています。
物語の舞台となる大学医学部の地下室は、この小説の閉塞感を象徴する空間です。薄暗く、コンクリートの壁に囲まれた場所で、学生たちは黙々と作業を続けます。そこは、地上の喧騒から切り離された、生と死が奇妙な形で同居する異質な世界です。
水槽に満たされた濃褐色の液体と、その中に沈む数十体の死体。この情景描写は、一度読んだら忘れられないほどの強烈な印象を与えます。「僕」が死体を「完全な《物》」として認識する場面は、『死者の奢り』の重要なポイントです。意識も感情もなく、ただ存在するだけの「物」。その絶対的な静寂が、生きている人間の曖昧さや葛藤をあざ笑うかのようです。
休憩中の女子学生との会話は、物語に生々しい現実感をもたらします。彼女の告白に対して、「僕」は気の利いた言葉をかけることも、真摯に受け止めることもできません。彼の態度は、他者の苦悩に対する現代人の無関心さを映しているようにも思えます。この部分のやり取りは、読んでいて息が詰まるような気まずさに満ちています。
物語の核心に触れるネタバレになりますが、このアルバイトの結末はあまりにも不条理です。事務的な手違いによって、彼らが一日がかりで移し替えた死体は、本来すべて焼却処分される予定だったことが判明します。彼らの労働は、文字通り、全くの無駄骨だったのです。
この徒労感こそが、『死者の奢り』が突きつける最も大きなテーマかもしれません。私たちは日々、何かの目的のために働き、生きていると信じています。しかし、その営みが、実は何の意味も持たないとしたら。この残酷な宣告は、登場人物だけでなく、読者の足元をもぐらつかせます。
この衝撃の事実が発覚した後、女子学生の心境に変化が訪れます。彼女は水槽の死体を眺めているうちに、「一度生まれてからでないと収拾がつかない」と考え、出産を決意したと語ります。不条理な現実を前にして、彼女は「生」を選択するのです。これは、物語における一つの救いと言えるかもしれません。
しかし、主人公の「僕」は最後まで傍観者のままです。女子学生が決意を固める一方で、彼は再び死体を運び出すという、終わりの見えない無益な作業へと引き戻されていきます。彼の無力感と閉塞感は、解消されることなく物語を締めくくります。
では、なぜタイトルは『死者の奢り』なのでしょうか。「奢り」とは、思い上がりやわがままを意味する言葉です。死者は何も語らず、何も求めません。しかし、その圧倒的な存在そのものが、生きている人間の営みを無意味化し、翻弄します。あたかも、死者が生者に対して「お前たちのやっていることなど、この程度のものだ」と奢り高ぶっているかのようです。
この物語は、サルトルなどの実存主義思想の影響が色濃く見られます。人間は主体的に生きることで自らを意味づけていく存在ですが、「僕」はその主体性を放棄しています。彼は現実に関わることを避け、ただ流されるままです。その結果、彼は不条理な状況に飲み込まれてしまいます。
『死者の奢り』が発表された1950年代後半は、戦後の混乱が少しずつ収まり、新たな価値観が模索されていた時代です。若者たちが抱える先行きの見えない不安や虚無感が、「僕」の姿に投影されていると考えることもできるでしょう。
また、この物語は「働くこと」の意味についても問いを投げかけます。労働の対価として賃金を得る、という資本主義の原則が、ここでは無意味な徒労によって根底から覆されます。汗水流して働いた結果が「無」であったと知った時の絶望は、想像に難くありません。
この小説の文体も特徴的です。若き日の大江健三郎ならではの、観念的でありながらも、生々しい肉体感覚を伴う文章が、読者を物語の世界に強く引き込みます。特に、死体の質感や重さ、そして地下室の湿った空気を感じさせる描写は見事です。
物語の結末についてもう少し掘り下げると、ここには明確なカタルシスはありません。問題は何も解決せず、主人公は救われません。この救いのなさこそが、『死者の奢り』が純文学として高く評価される所以かもしれません。安易な結論を提示するのではなく、読後も心に引っかかり続ける問いを残すのです。
これから『死者の奢り』を読もうとする方へ。この物語は、決して楽しい読書体験ではないかもしれません。しかし、人間の存在の根源にある不安や不条理から目をそらさずに描いた、稀有な作品であることは間違いありません。
最後に、この物語が現代に持つ意味を考えたいと思います。情報が溢れ、あらゆる物事が効率化されていく現代社会において、私たちは時として自らの営みの意味を見失いがちです。そんな時代だからこそ、『死者の奢り』が描き出す圧倒的な徒労感と不条理は、私たちに「生きること」の意味を改めて問い直すきっかけを与えてくれるのではないでしょうか。このネタバレを含む感想が、作品をより深く味わう一助となれば幸いです。
まとめ:「死者の奢り」のあらすじ・ネタバレ・長文感想
この記事では、大江健三郎の初期代表作「死者の奢り」について、あらすじから結末のネタバレを含む深い感想までを語ってきました。この物語は、単なる奇妙なアルバイトの話ではなく、私たちの存在そのものを揺さぶるような普遍的な問いを投げかけています。
物語は、無気力な学生「僕」が、大学医学部の地下で死体を移し替える作業を通して、圧倒的な「死」の存在と、妊娠に悩む女子学生という切実な「生」の問題に直面する様子を描いています。彼の無関心と、それを取り巻く不条理な状況が、読者に強烈な印象を残します。
そして、この物語の核心にあるのは、すべての労働が無駄であったと判明する衝撃的な結末です。このどうしようもない徒労感と閉塞感こそが、「死者の奢り」のテーマであり、タイトルに込められた意味を深く考えさせられる部分です。生者の営みをあざ笑うかのような、物言わぬ死者たちの存在が際立ちます。
「死者の奢り」は、読む人を選ぶ作品かもしれませんが、生きることの不条理さや虚しさに一度でも触れたことのある人なら、きっと心に響くものがあるはずです。この記事が、これから作品を手に取る方、あるいは再読する方のための、豊かな読書体験の一助となれば、これほど嬉しいことはありません。