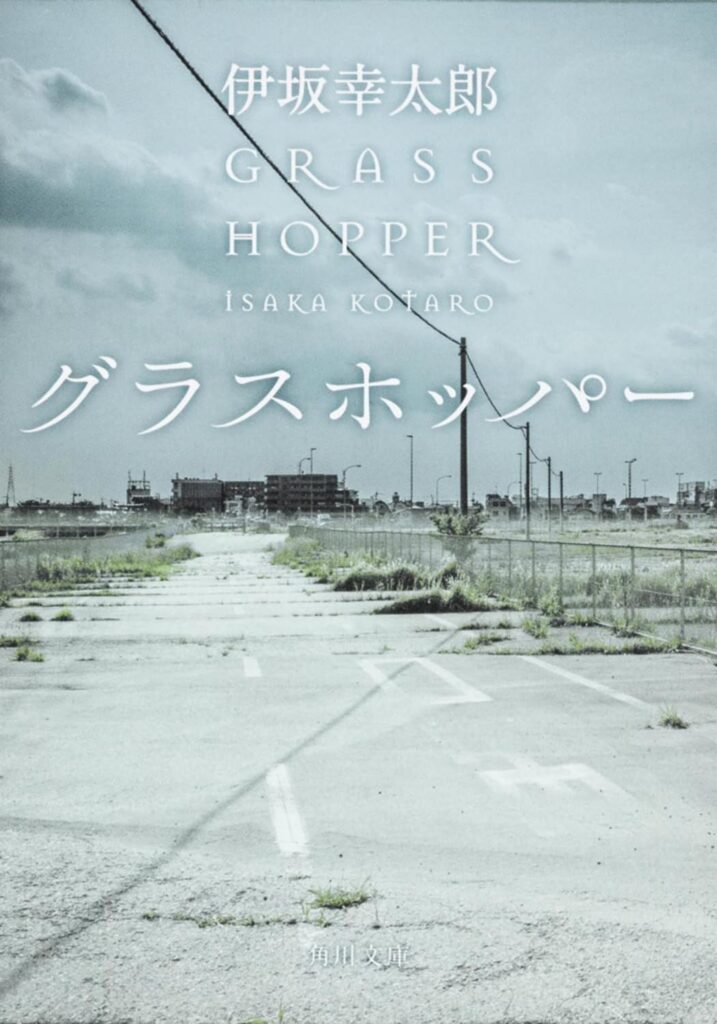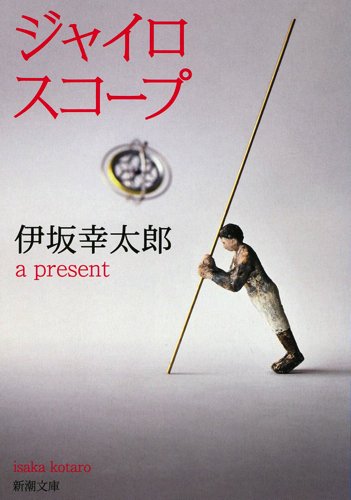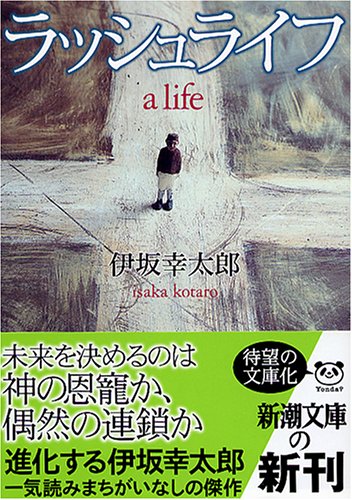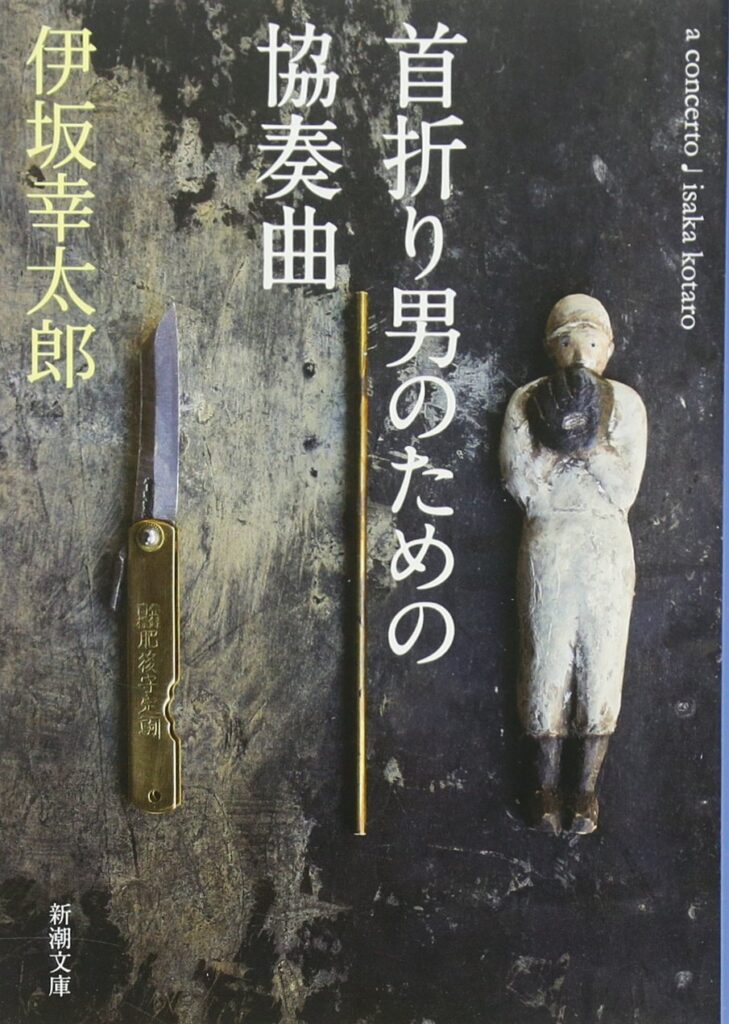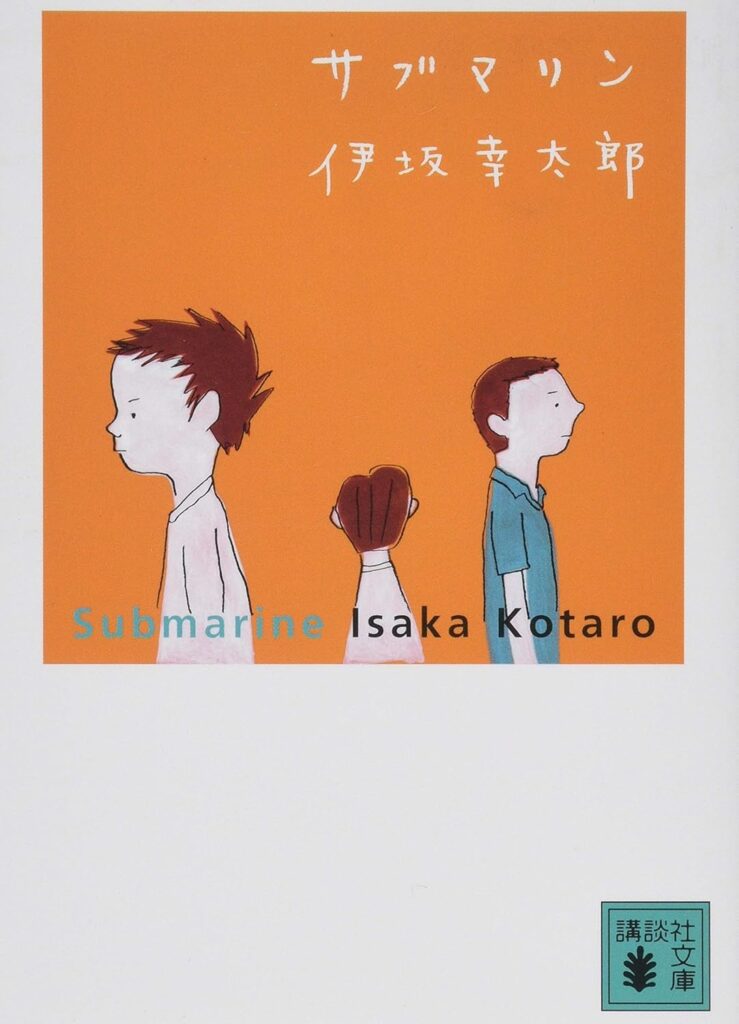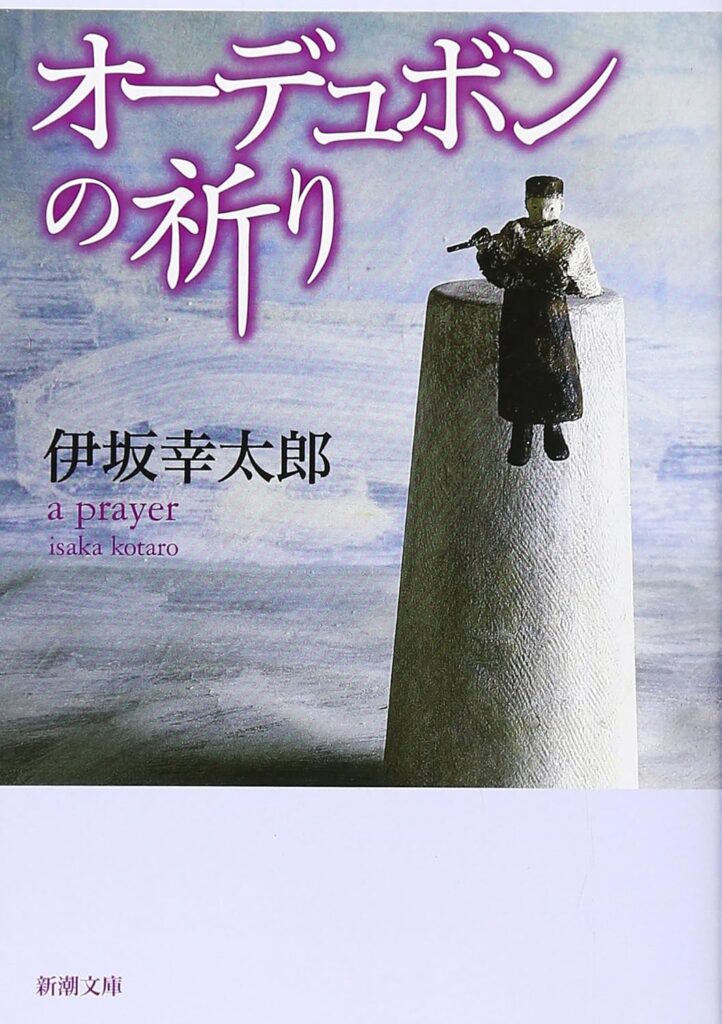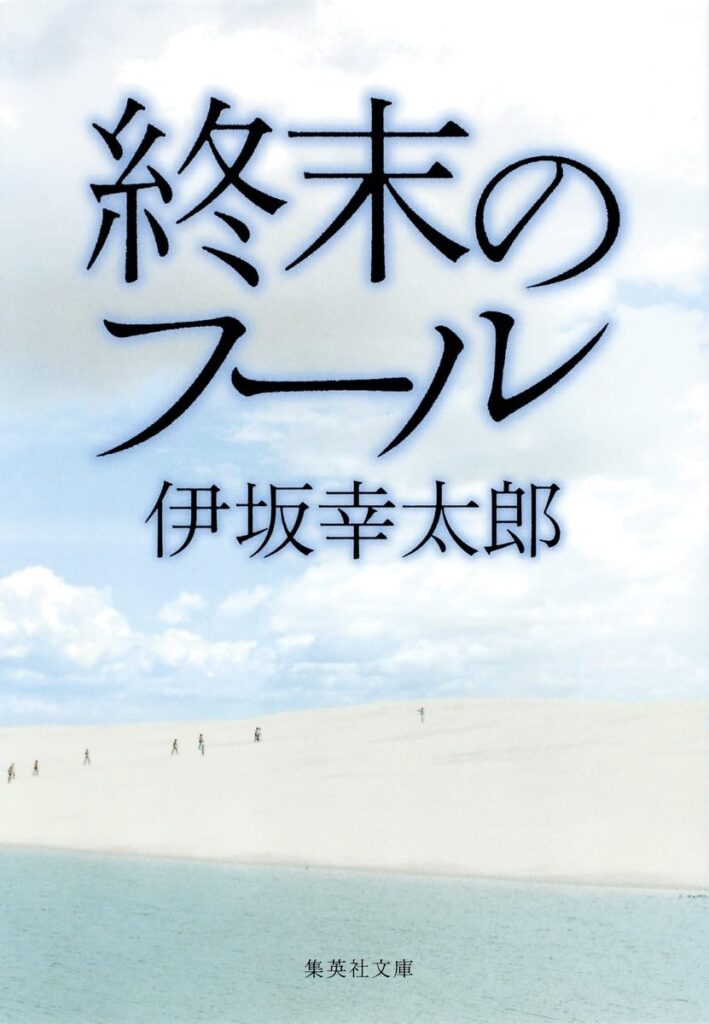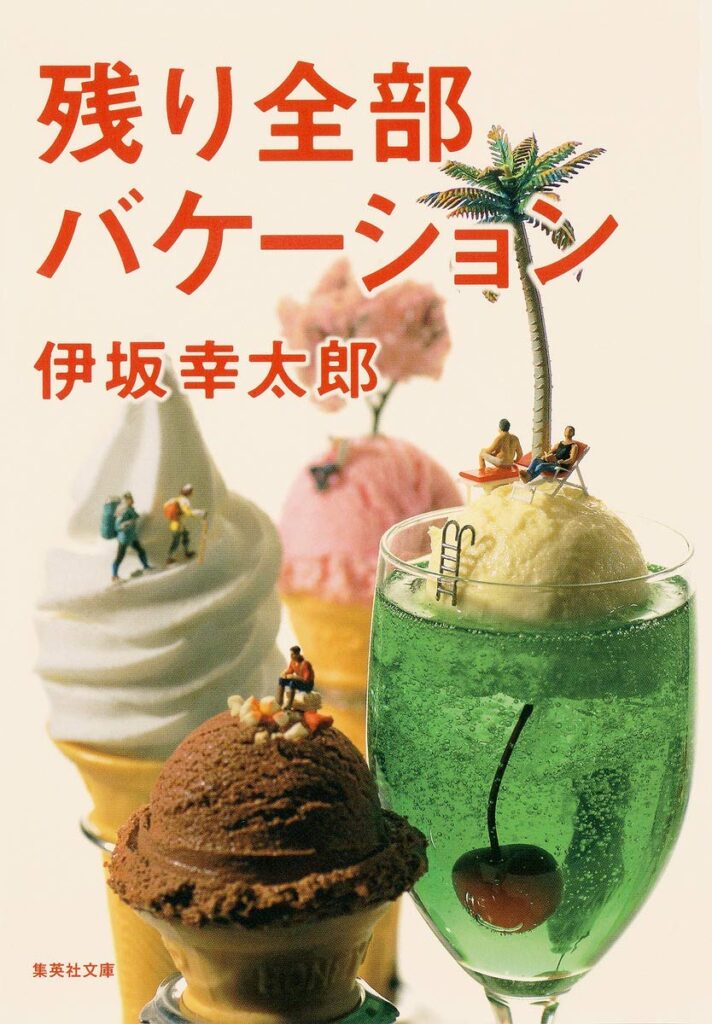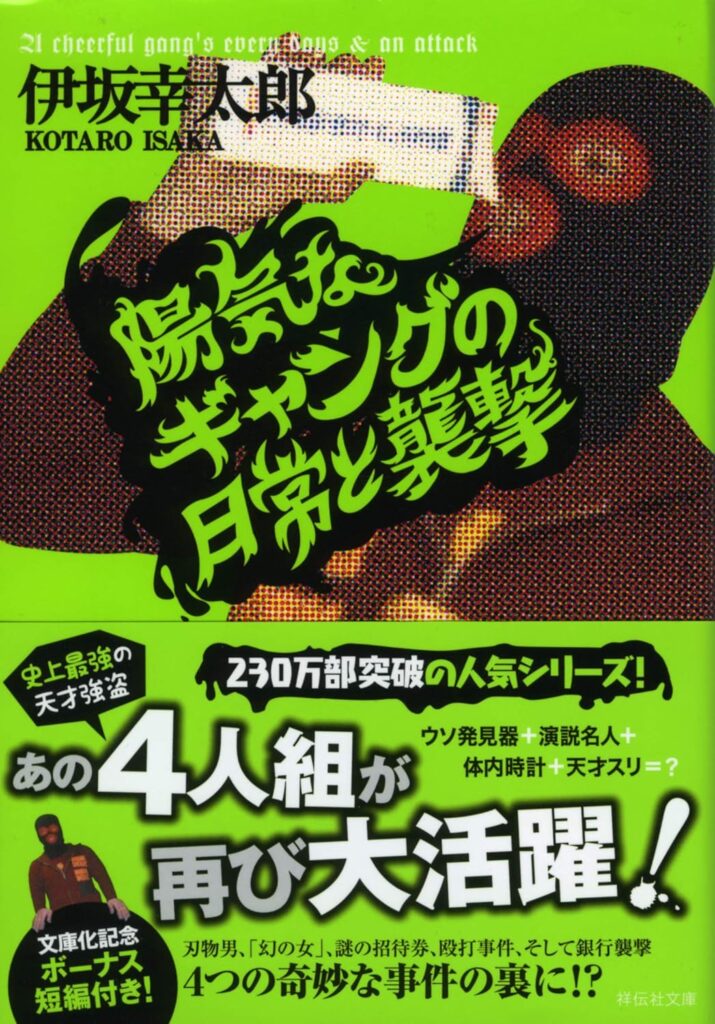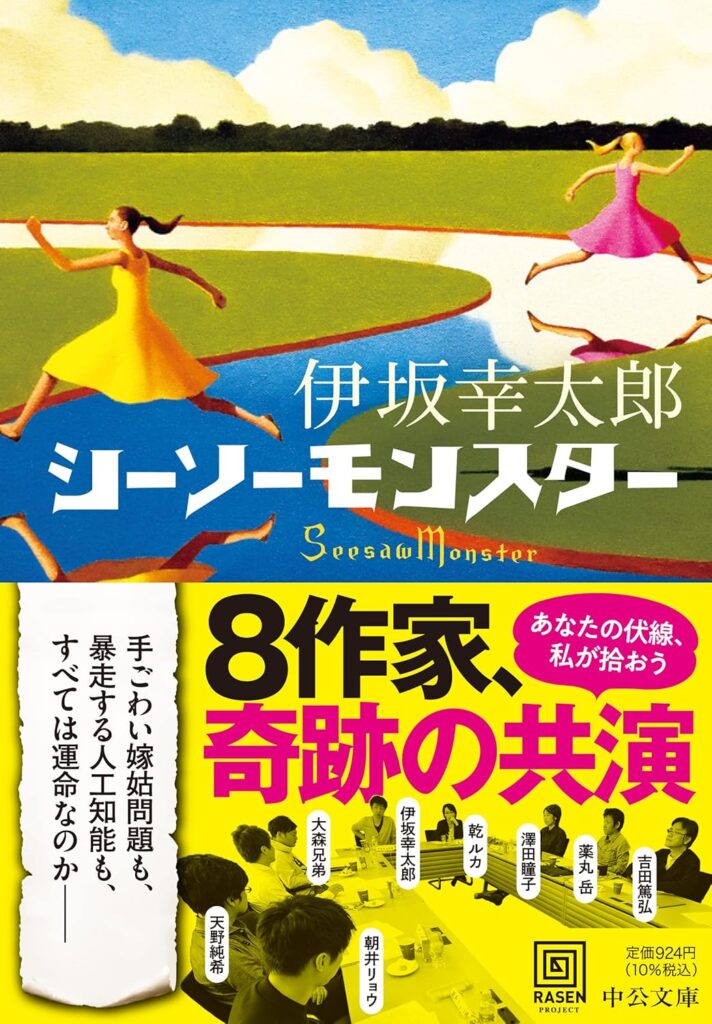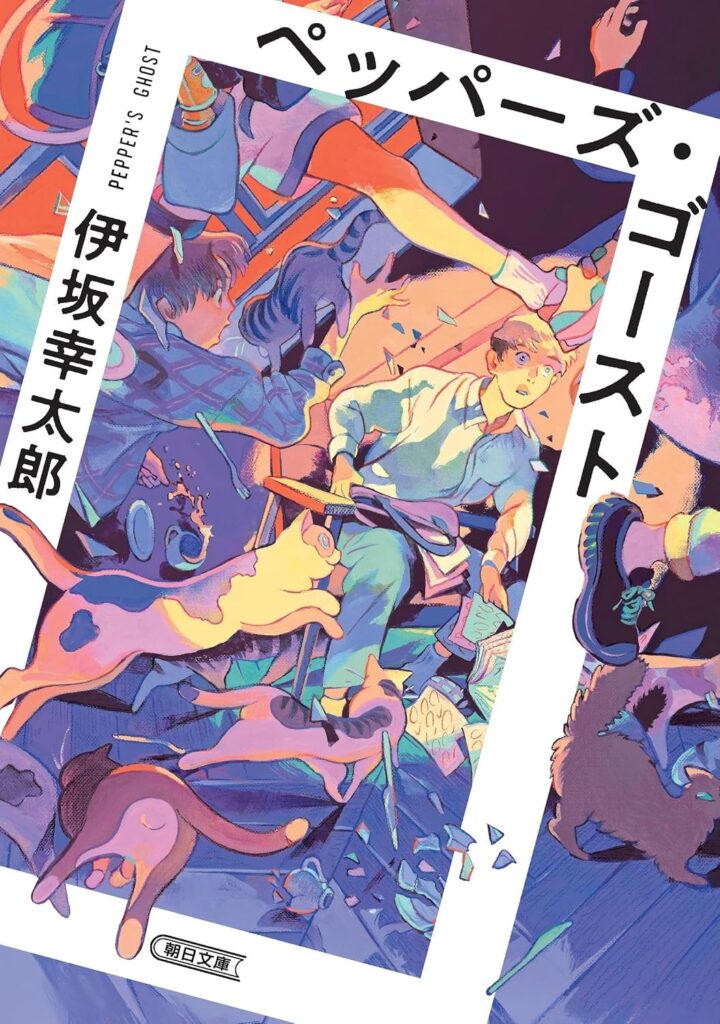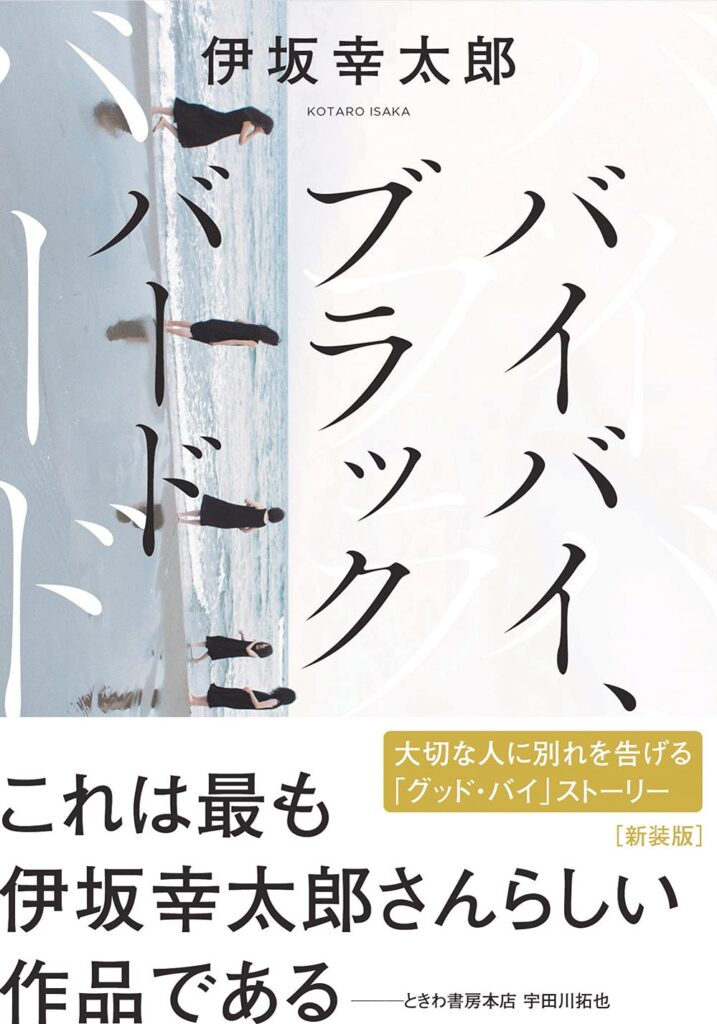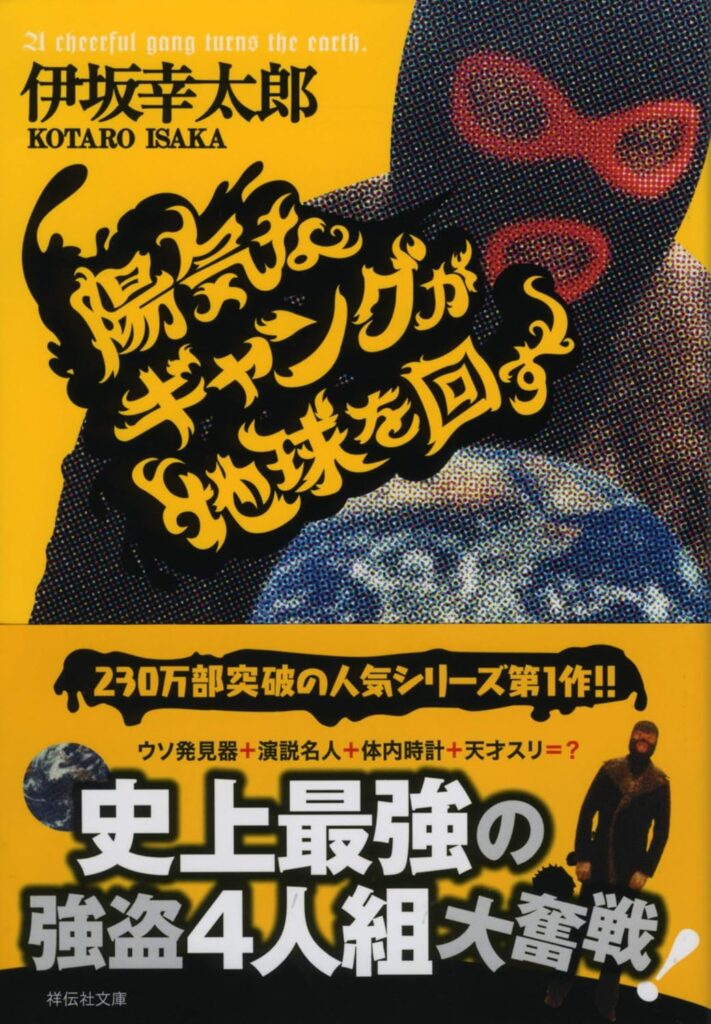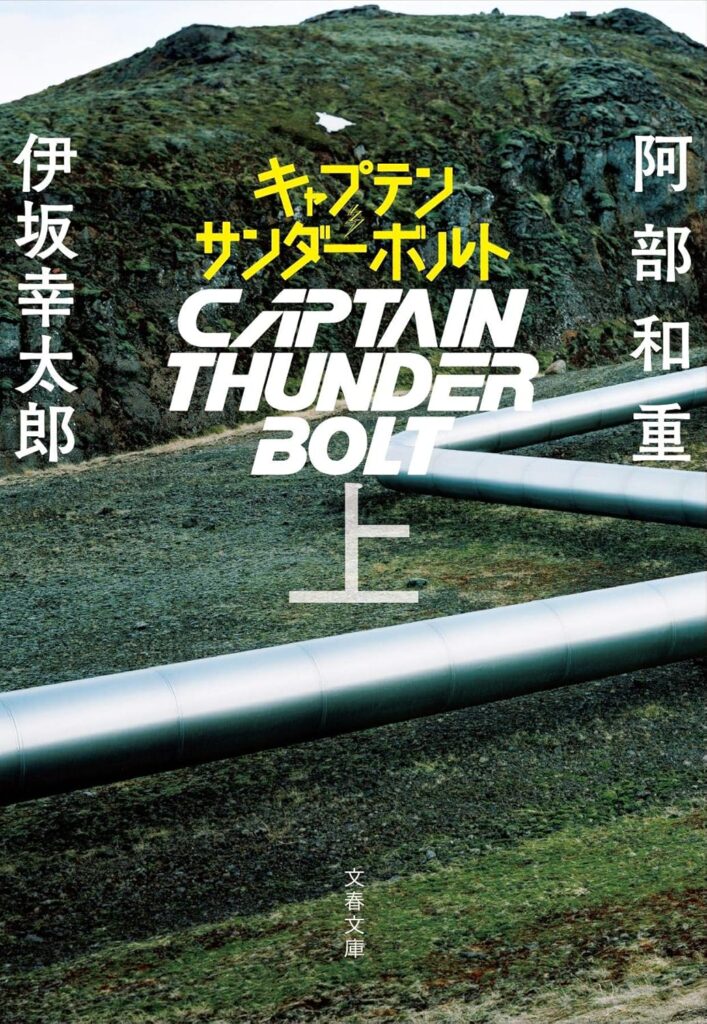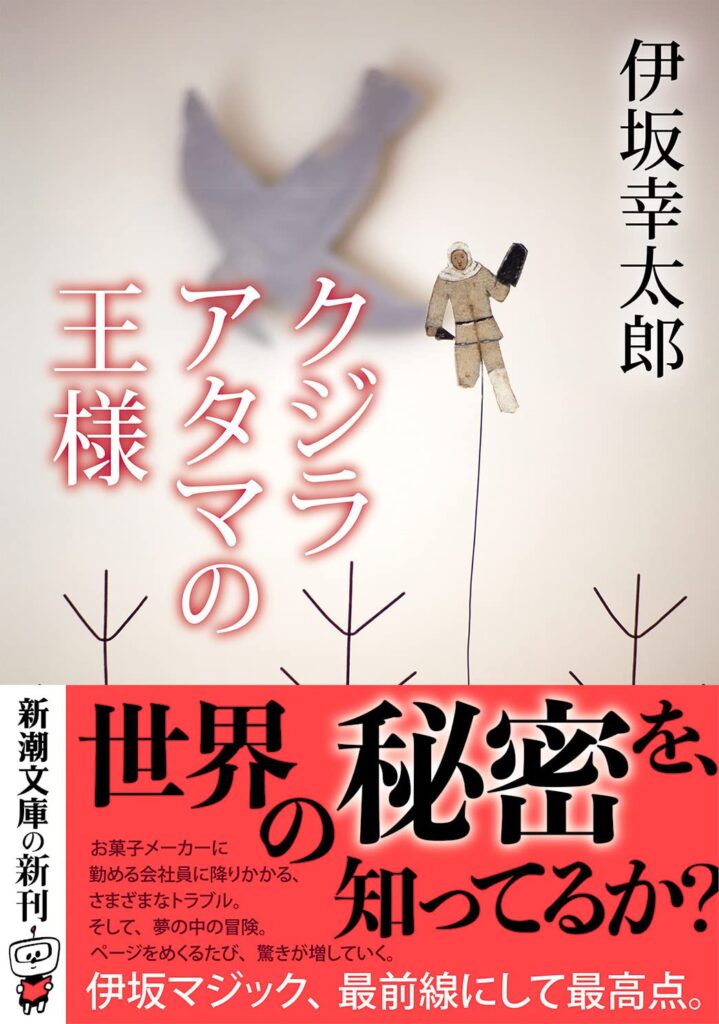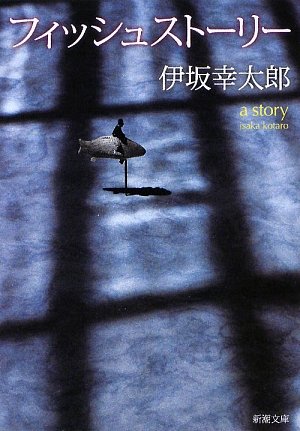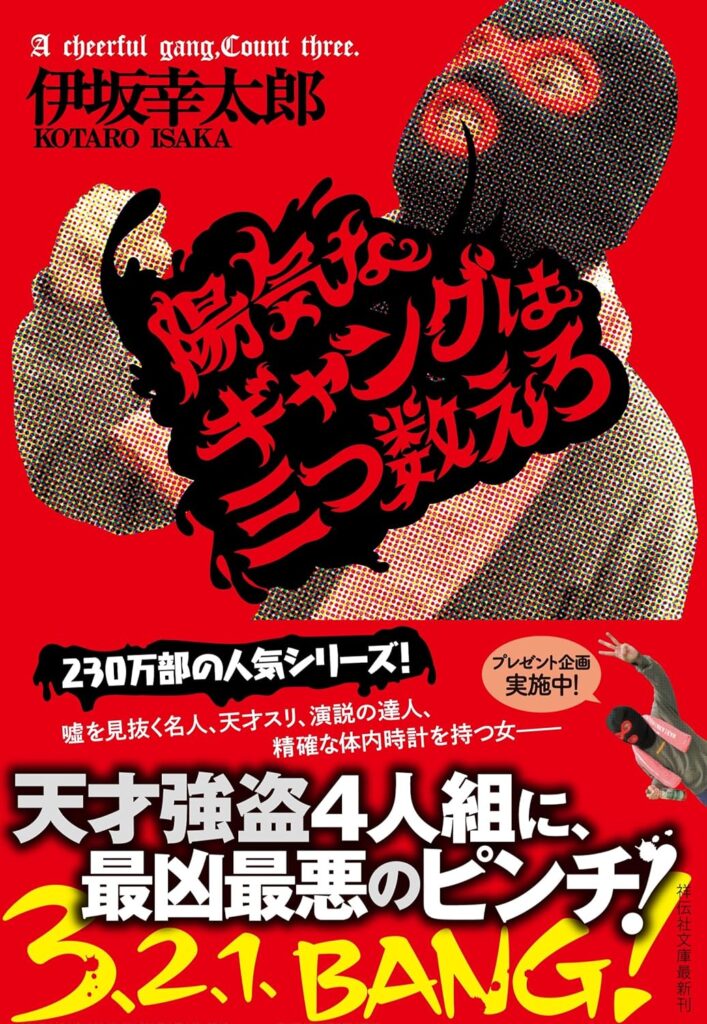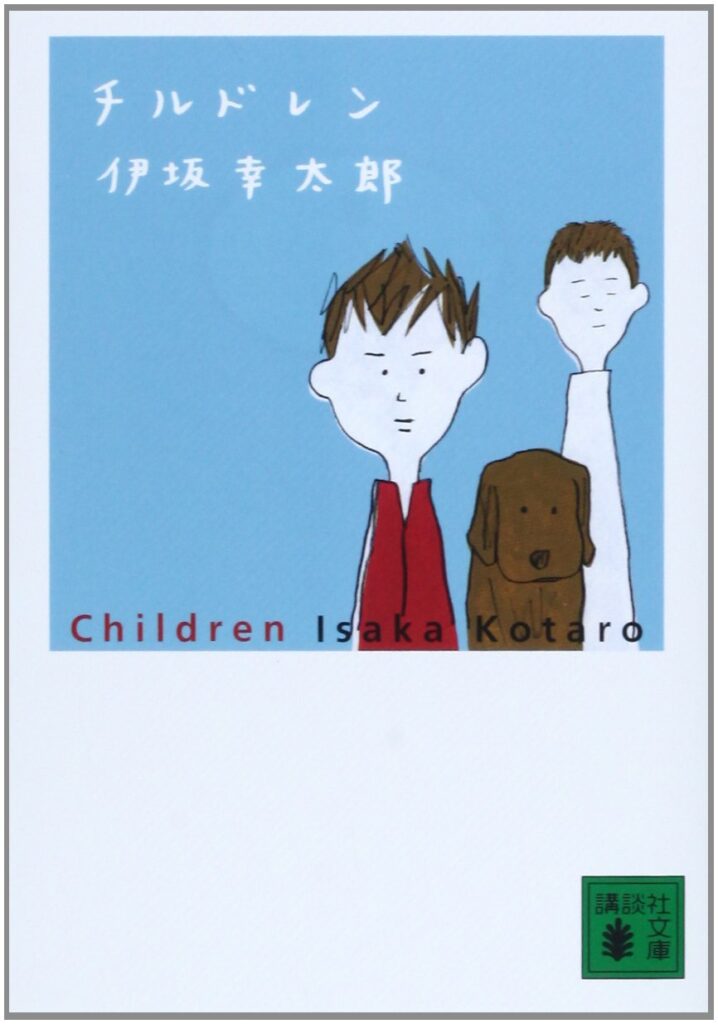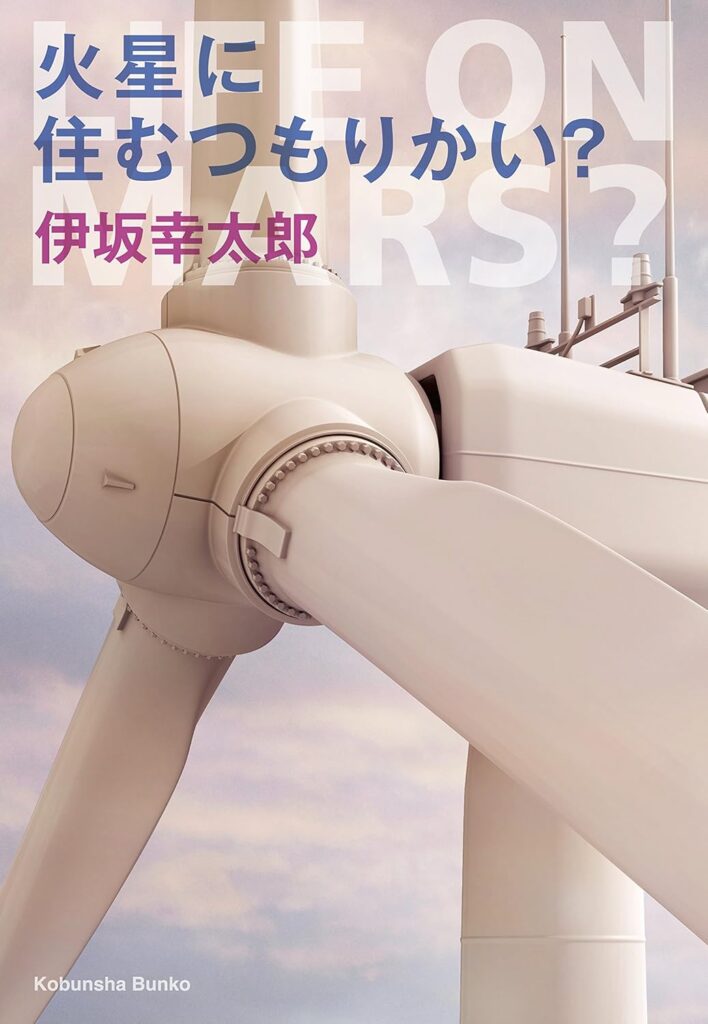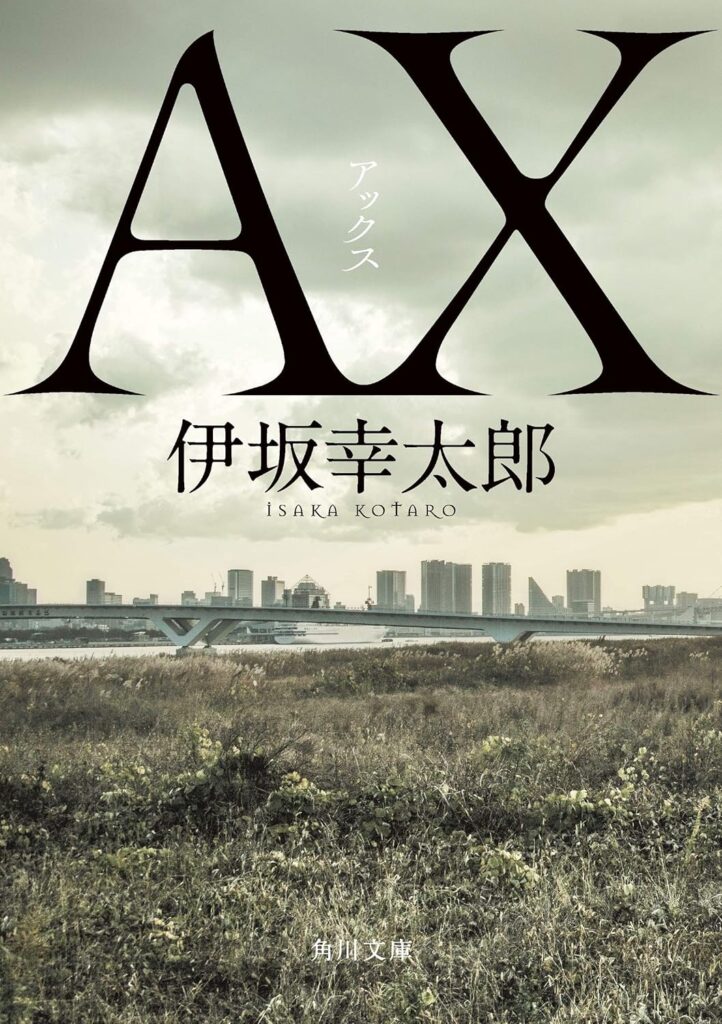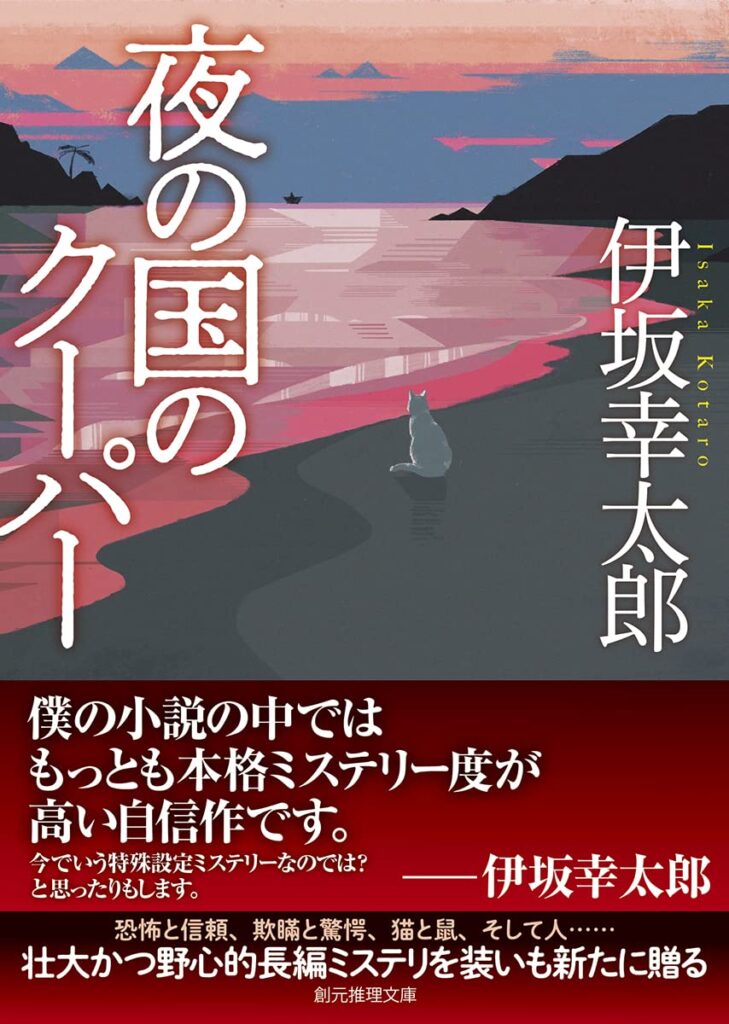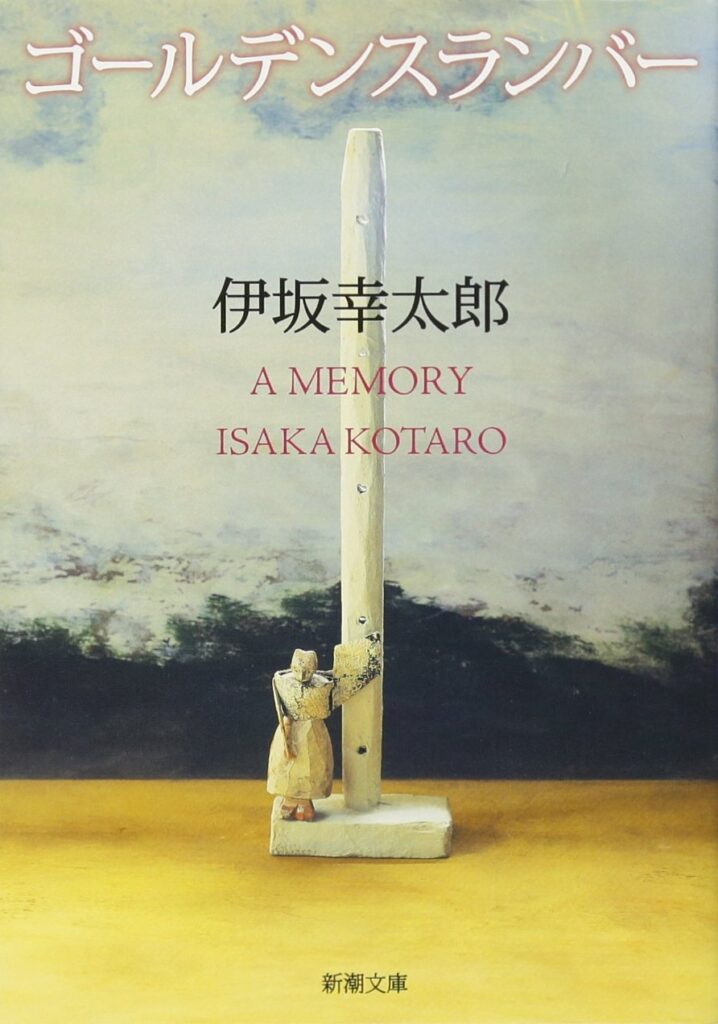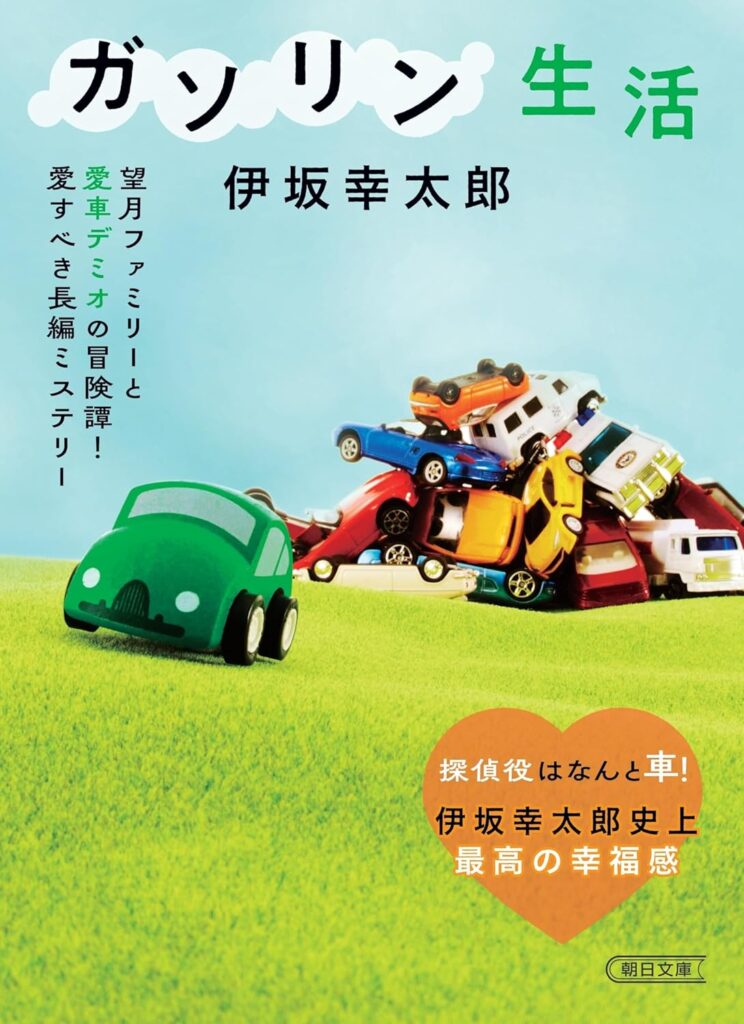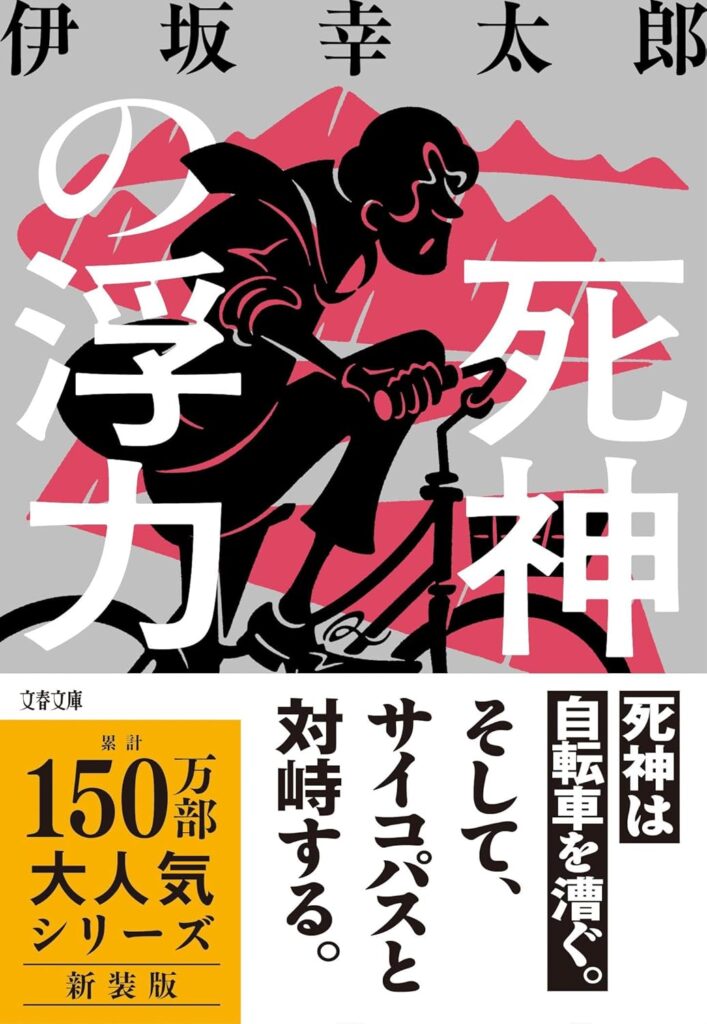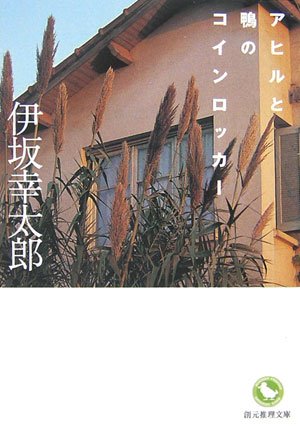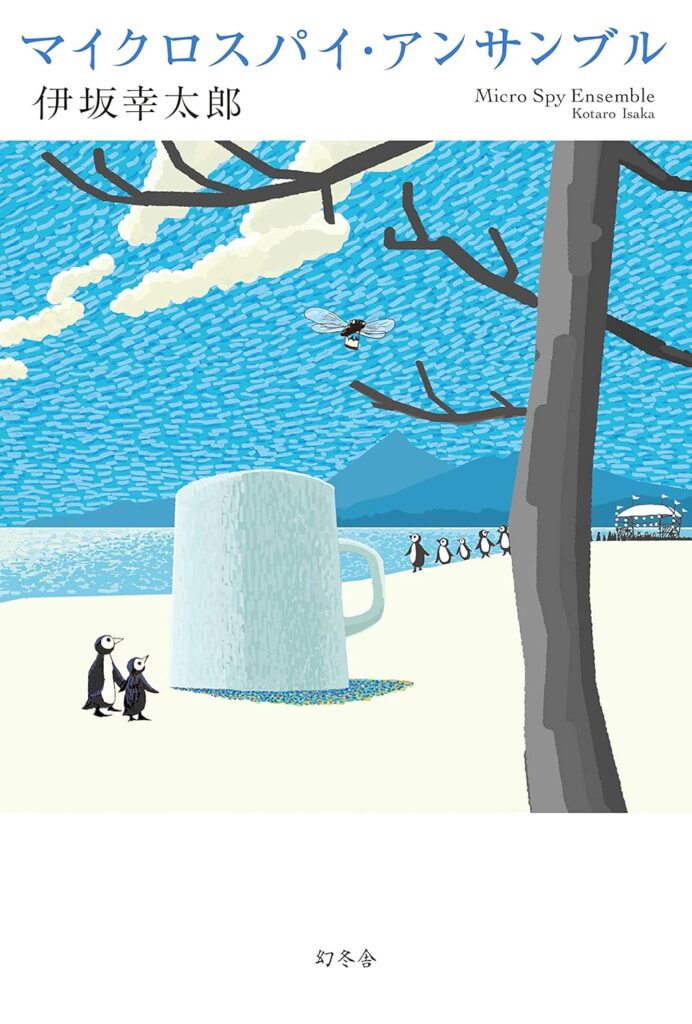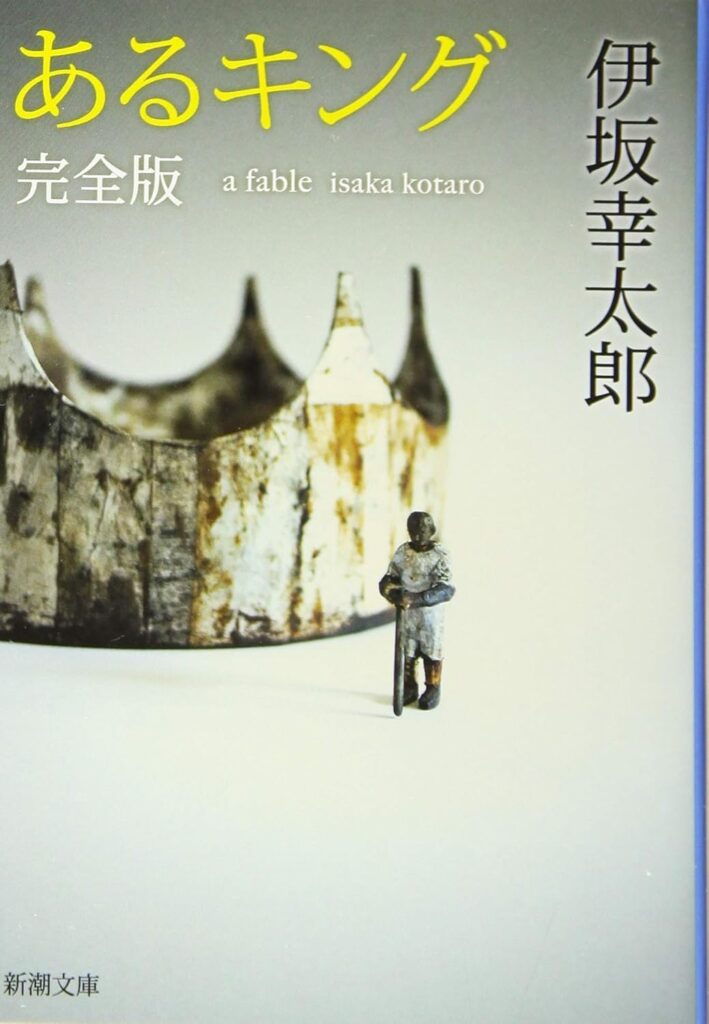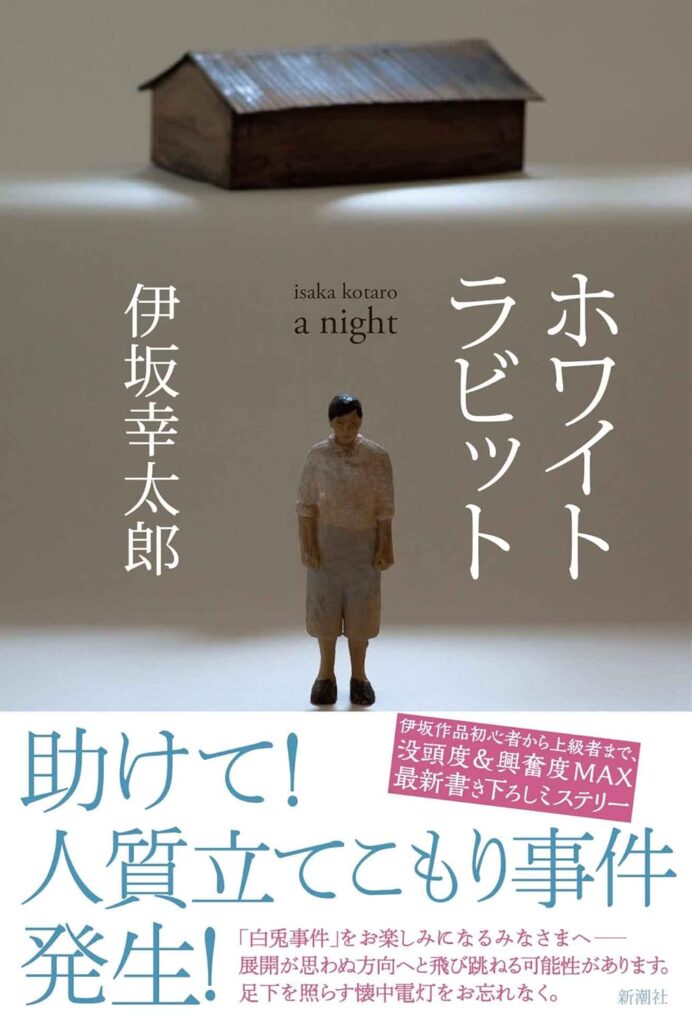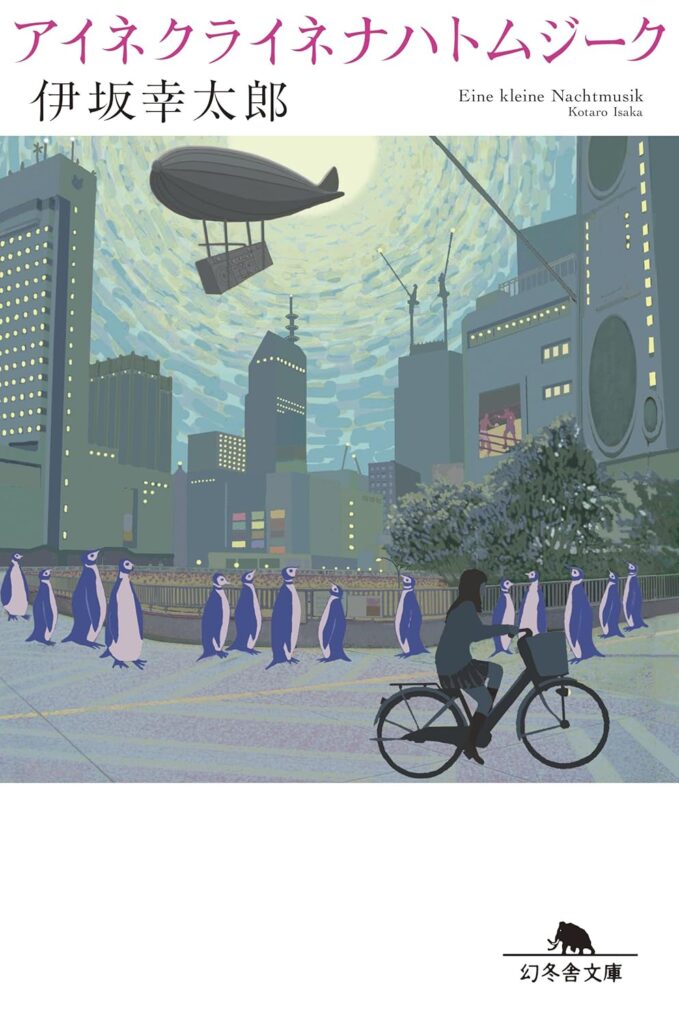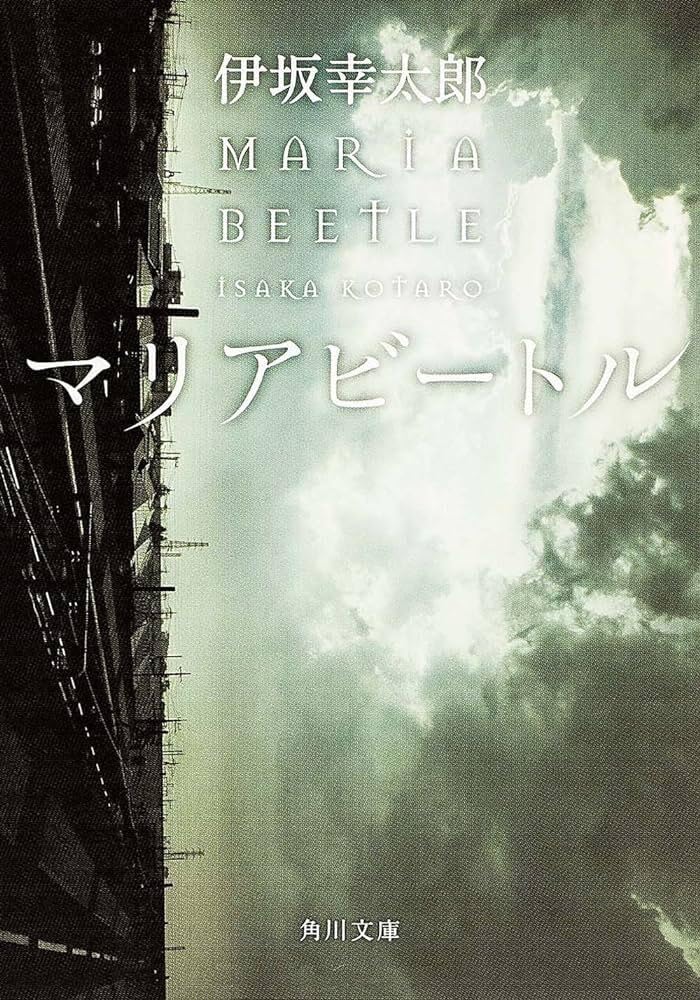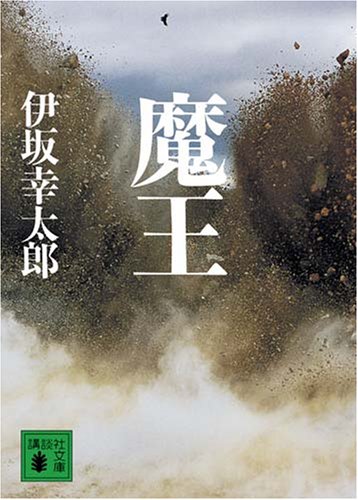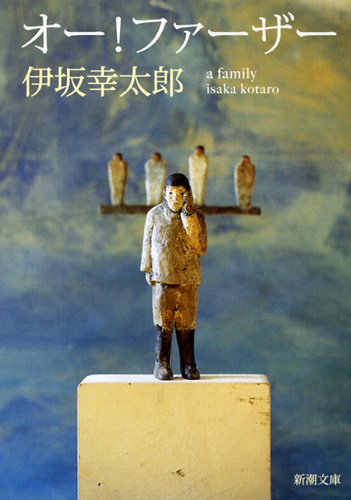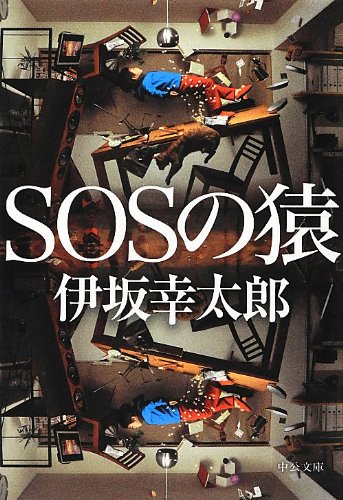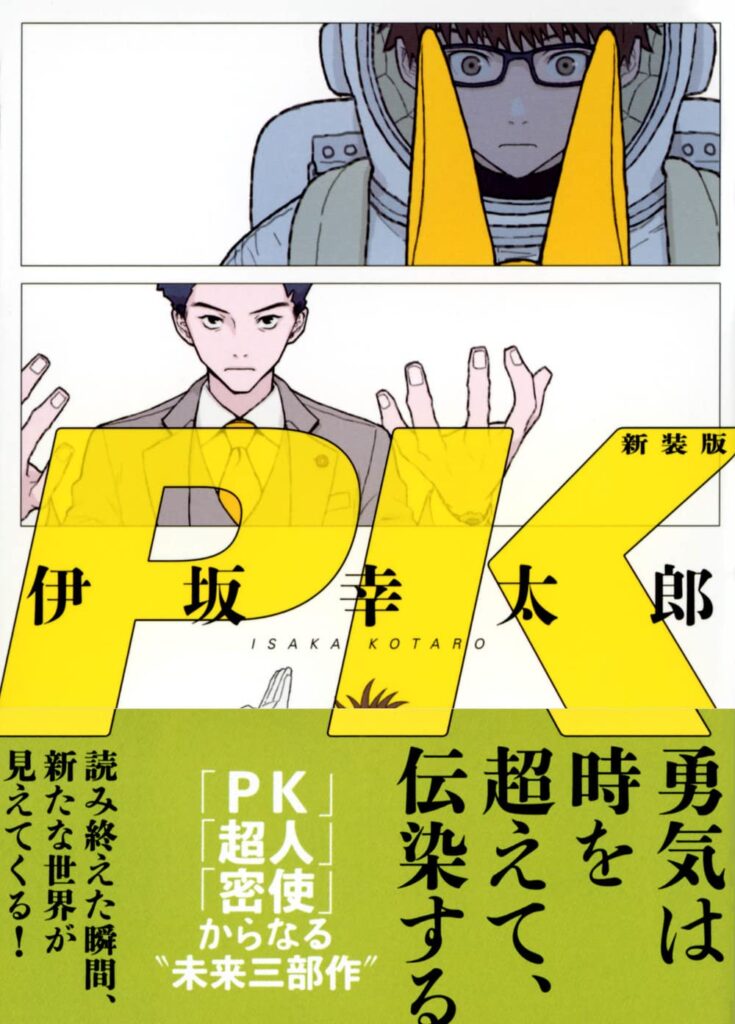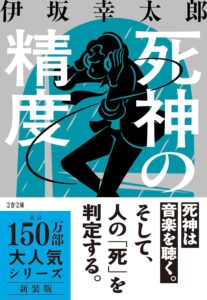 小説「死神の精度」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「死神の精度」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
伊坂幸太郎さんの作品の中でも、特に印象深い一冊として多くの読者に愛されているのが、この『死神の精度』ではないでしょうか。死神である主人公・千葉が、人間の死を「可」か「見送り」か判断するために一週間調査する、というユニークな設定がまず目を引きます。彼が仕事をする日はいつも雨が降る、というのも面白いですよね。
本作は六つの短編からなる連作短編集です。それぞれの物語で、千葉はさまざまな境遇の人間たちと出会い、彼らの人生の断片に触れていきます。電話のクレーム対応に疲弊する若い女性、任侠道を貫くヤクザ、吹雪の山荘に閉じ込められた人々、不器用な恋をする青年、過去に傷を持つ逃亡者、そして人生の終盤を迎えた老女。千葉は彼らの調査を通して、人間という存在の不可思議さや、生と死の意味について、彼なりに考えを巡らせていくのです。
この記事では、そんな『死神の精度』の各物語の概要と結末に触れつつ、作品全体を通して感じたこと、考えたことを詳しく述べていきます。物語の核心に迫る部分も含まれますので、未読の方はご注意ください。既に読まれた方も、新たな発見や共感できる点があるかもしれません。一緒に『死神の精度』の世界を深く味わっていきましょう。
小説「死神の精度」のあらすじ
物語の中心人物は、死神の「千葉」。彼の仕事は、人間の死を決定する調査を行うことです。対象者と一週間接触し、その人物の死を「可(実行)」とするか、「見送り」とするかを判断し、報告します。基本的に「可」と判断されることが多いのですが、千葉は調査対象と関わる中で、時折その判断に迷いを見せることもあります。彼は人間の感情や常識には疎いものの、なぜかミュージック(音楽)をこよなく愛しており、CDショップに立ち寄るのが好きです。そして、彼が地上で仕事をする日は、決まって雨が降るのでした。
最初の物語では、千葉は大手電機メーカーでクレーム対応の仕事をしている藤木一恵という二十二歳の女性を調査します。心無いクレーマーからの電話に疲弊し、「死にたい」と漏らす彼女。千葉は当初、彼女の死を「可」と判断しようとしますが、ある意外な事実を知ることになります。実は彼女を執拗に指名していたクレーマーは音楽プロデューサーで、彼女の声に特別な才能を見出し、スカウトしようとしていたのです。この発見が、千葉の最終判断に影響を与えます。
続く物語では、千葉は任侠を重んじるヤクザ・藤田、吹雪の山荘に集まった人々、恋に悩む青年・荻原、母親を刺して逃亡する若者・森岡、そして海辺の町で静かに暮らす老女と、さまざまな人物を調査対象とします。ヤクザの抗争、山荘での連続死、切ない恋愛模様、逃亡劇、そして長年秘められた過去。千葉はそれぞれの人生模様を間近で見つめ、時には意図せず彼らの運命に関わっていきます。
六つの物語は独立しているようでいて、登場人物や出来事が緩やかにつながっている部分もあります。特に、ある物語で登場した人物が、別の物語で意外な形で再登場したり、その後の人生が垣間見えたりするのは、連作短編ならではの面白さです。千葉は一貫して飄々とした態度を崩しませんが、様々な人間との出会いを通して、彼の内面にもわずかな変化が訪れているのかもしれません。物語の最後、千葉は長年の調査を終えた老女との出会いを経て、初めて「青空」を目撃することになるのでした。
小説「死神の精度」の長文感想(ネタバレあり)
伊坂幸太郎さんの『死神の精度』は、読後、なんとも言えない余韻が心に残る作品でした。死神というファンタジックな存在を主人公に据えながら、描かれるのは非常にリアルな人間の生と死、そしてその間にある様々な感情の機微です。各短編が独立した物語として楽しめるだけでなく、全体を通して読むことで、より深い感慨を得られる構成になっていると感じます。
まず何と言っても、主人公である死神・千葉のキャラクターが魅力的です。彼は人間の生死を判定するという重大な任務を負っていながら、どこか飄々としていて、人間の感情や常識には疎い。そのズレた言動が、物語に独特の雰囲気をもたらしています。「雨男」と「雪男」を同じようなものだと考えていたり、言葉の裏を読めずに文字通り受け取ってしまったり。しかし、そんな彼が唯一情熱を傾けるのが「ミュージック」であるという設定が面白いです。CDショップで視聴に没頭する姿は、死神という存在の非人間性と、どこか人間的な一面とのギャップを感じさせ、彼への興味を掻き立てます。彼が仕事をする日は必ず雨が降る、というのも、物語全体を覆うしっとりとした、時にもの悲しい雰囲気を醸し出すのに一役買っています。
収録されている六つの短編は、それぞれ異なる趣向が凝らされており、読者を飽きさせません。
表題作でもある第一話「死神の精度」。ここで描かれるのは、コールセンターで働く藤木一恵という若い女性です。日々のクレーム対応に疲れ果て、「死にたい」と口にする彼女。千葉は当初、調査対象として「可」の判断を下そうと考えます。しかし、彼女を執拗に指名していたクレーマーが、実は彼女の声に非凡な才能を見出した音楽プロデューサーであり、歌手としてスカウトしようとしていたことが判明します。この展開には驚かされました。一恵自身も気づいていない可能性、未来への希望。ミュージックを愛する千葉が、最終的に彼女の死を「見送り」としたのは、単なる偶然や気まぐれではない、彼なりの価値判断があったように思えてなりません。この物語は、シリーズ全体の導入として、千葉のキャラクター性や死神のルールを提示すると同時に、人の人生には予期せぬ可能性が眠っていることを示唆しており、非常に印象的でした。
第二話「死神と藤田」は、がらりと雰囲気が変わります。調査対象は、古風な任侠道を貫くヤクザの藤田。彼は兄貴分を殺した栗木への復讐を誓っています。千葉は、死神の調査期間中(一週間)は対象者が死なない、というルールを利用して、藤田を助けることになります。藤田の不器用ながらも筋を通そうとする生き様、彼を慕う若い衆・阿久津との関係性が胸を打ちます。千葉が藤田に協力するわけではないけれど、結果的に彼の命を救う形になる展開は、皮肉でありながらもどこか温かい気持ちになりました。死神のルールが物語のギミックとして巧みに使われている点も、伊坂作品らしいと感じます。藤田の「可」の判断は覆りませんでしたが、彼が最期に何を思ったのか、想像を掻き立てられる終わり方でした。
第三話「吹雪に死神」は、吹雪の山荘という閉鎖空間を舞台にしたミステリー仕立ての物語です。複数の男女が集まる洋館で、次々と人が死んでいく。調査対象は田村聡江という女性ですが、実はこの山荘には千葉以外にも死神(蒲田と秋田)が潜んでおり、それぞれ別の対象者の死を「可」としていました。ここでも死神のルール、「死神が盛った毒では死なない」という設定が、事件の謎解きに関わってきます。人間の愛憎が渦巻く中、千葉は相変わらず飄々と状況を観察します。犯人の動機やトリックもさることながら、複数の死神が登場し、彼らが淡々と「仕事」をこなしていく様子が、人間の世界の出来事を相対化しているように感じられました。ミステリーとしての面白さと、死神たちの視点という特異性が融合した一編です。
第四話「恋愛で死神」は、切ないラブストーリーです。調査対象はブティックで働く青年・荻原。彼は向かいのマンションに住む古川朝美に想いを寄せています。千葉は、二人が少しずつ距離を縮めていく様子を見守ります。しかし、物語の冒頭で、千葉が荻原の調査結果を「可」と報告済みであることが示唆されており、読者は切ない結末を予感しながら読み進めることになります。なぜ千葉は「見送り」にしなかったのか? その理由は物語の終盤で明らかになります。荻原は不治の病を患っていたのです。死の間際、荻原が千葉に告げる「最善じゃないけど、最悪でもない」という言葉が深く心に残りました。限られた時間の中で、ささやかな幸せを見つけた荻原の人生を、千葉は肯定的に捉えたのかもしれません。運命の残酷さと、その中で見出す希望の光を描いた、美しい物語だと感じます。
第五話「旅路を死神」は、ロードムービーのような雰囲気を持つ物語です。千葉は、母親を刺し、さらに衝動的に若者を殺害して逃亡中の森岡耕介を調査します。千葉は森岡の運転する車に乗り込み、奇妙な二人旅が始まります。森岡は粗暴で短絡的な面もありますが、千葉との道中で見せる人間らしい弱さや、過去のトラウマ(誘拐事件)が描かれることで、単なる凶悪犯ではない、複雑な人物像が浮かび上がってきます。特に、道中で出会う老夫婦との交流や、森岡が過去に自分を監視していた男・深津と再会し、静かに涙を流す場面は感動的でした。千葉は森岡の逃亡を手助けするわけではありませんが、彼の最期までを見届ける同行者となります。国道沿いのラーメン屋のエピソードが伏線として機能している点や、『重力ピエロ』の春が登場するなど、伊坂作品ファンには嬉しい遊び心も散りばめられています。
そして最終話「死神対老女」。ここで千葉が調査するのは、海辺の町で美容院を営む七十代の老女・新田です。この老女は、千葉が店を訪れるなり、「人間じゃないでしょ」と言い放ちます。長年の人生経験からか、千葉が普通の人間ではないこと、死の気配をまとっていることを見抜いていたのです。そして、物語が進むにつれて、この老女が第四話「恋愛で死神」に登場した古川朝美であることが判明します。荻原との切ない別れの後、彼女がどのような人生を歩んできたのかが語られます。多くの出会いと別れを経験し、人生の達観に至った彼女の言葉は、静かな重みを持って響きます。孫にも無事に会えたことに満足し、穏やかに死を受け入れようとする彼女。千葉は、そんな彼女の調査結果を「見送り」ではなく「可」とします。それは、彼女の人生が満たされたものであったことへの、千葉なりの敬意の表れだったのかもしれません。そして、この物語の最後、老女を見送った千葉は、彼が地上で仕事を始めて以来、初めて「青空」を目にします。まるで、長い雨がようやく上がったかのように。このラストシーンは、死神である千葉の内にも、人間との関わりを通して何らかの変化が訪れたことを示唆しているようで、非常に清々しく、感動的な締めくくりでした。この老女との出会いは、千葉にとって一つの区切りとなったのかもしれません。
『死神の精度』全体を通して感じるのは、人生のままならなさ、そしてその中で見出されるささやかな希望や肯定です。死神・千葉の視点は、人間の営みを冷静に、時にはコミカルに、そして時には温かく見つめます。彼は直接的に誰かを救ったり、運命を変えたりすることは少ないですが、彼の存在が、登場人物たちの人生の最期の一週間に、何らかの影響を与えているのは確かです。そして、調査対象者たちの生き様は、読者である私たち自身の人生や死生観についても、改めて考えるきっかけを与えてくれます。
伊坂幸太郎さんの文章は、軽やかでありながらも、核心を突く鋭さを持っています。会話のテンポが良く、キャラクターたちのやり取りを読んでいるだけでも楽しい。伏線の張り方や回収の仕方も見事で、特に連作短編としての構成の巧みさには唸らされます。それぞれの物語が独立していながら、後の物語で前の物語の登場人物のその後が語られたり、小さな繋がりが見えたりすることで、世界観に深みが増しています。
死という重いテーマを扱いながらも、読後感が決して暗くならないのは、やはり千葉というキャラクターの存在が大きいのでしょう。彼のどこかズレた感覚と、ミュージックへの愛、そして時折見せる人間への(彼自身は自覚していないかもしれない)ある種の共感が、物語全体を独特の優しい空気で包み込んでいるように感じます。人生は思い通りにいかないことばかりかもしれないけれど、それでも生きていくことの価値や、ささやかな瞬間の輝きを、この作品は教えてくれる気がします。まるで、降り続く雨の中に差す、一筋の光のように。それは、読者の心にも静かに染み渡る、忘れがたい読書体験となりました。
まとめ
伊坂幸太郎さんの『死神の精度』は、死神の千葉が人間の死を調査するという、独創的な設定の連作短編集です。千葉が仕事をする日はいつも雨、そして彼はミュージックが大好き。そんな少し変わった死神が、様々な事情を抱える人間たちと出会い、彼らの人生最後の一週間に関わっていきます。
各短編は、クレーム対応に疲れるOL、任侠を貫くヤクザ、吹雪の山荘でのミステリー、切ない恋愛、逃亡犯との旅、そして人生を達観した老女と、バラエティに富んだ物語が展開されます。それぞれの話が独立しつつも、登場人物や出来事が緩やかにリンクしており、読み進めるほどに世界観の深まりを感じられます。千葉の人間離れした視点と、時折見せる人間的な(?)反応が、物語に独特の味わいを加えています。
死というテーマを扱いながらも、決して重苦しくはならず、むしろ人生の肯定やささやかな希望を感じさせてくれる作品です。伊坂さんらしい軽快な筆致と巧みなストーリーテリング、そして魅力的なキャラクター造形が光ります。読後には、まるで雨上がりの空を見たような、不思議な清々しさと深い余韻が残る、素晴らしい一冊でした。