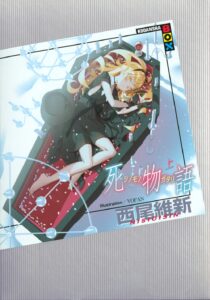 小説「死物語」のあらすじをネタバレありで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この作品は、〈物語〉シリーズのモンスターシーズン最終章として刊行され、多くのファンが待ち望んだ一冊と言えるでしょう。阿良々木暦の大学生活、そして彼を取り巻く少女たちの物語に、また新たな、そして決定的な一区切りが描かれます。
小説「死物語」のあらすじをネタバレありで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この作品は、〈物語〉シリーズのモンスターシーズン最終章として刊行され、多くのファンが待ち望んだ一冊と言えるでしょう。阿良々木暦の大学生活、そして彼を取り巻く少女たちの物語に、また新たな、そして決定的な一区切りが描かれます。
特に今回は「死」というものが、非常に直接的かつ多層的に描かれているのが印象的でした。それは単に生命の終わりを指すだけでなく、関係性の終焉や、ある状態からの不可逆な変化をも内包しているように感じられます。そして、その「死」と対峙することで見えてくる「生」の輝きや、「愛」の形もまた、鮮烈に描き出されています。
この記事では、そんな「死物語」の物語の筋を追いながら、特に心に残った点や考えさせられた部分を、物語の結末にも触れつつ詳しく語っていきたいと思います。読み進めていただくことで、作品の魅力や奥深さを少しでも感じ取っていただけたら嬉しいです。それでは、しばしお付き合いくださいませ。
小説「死物語」のあらすじ
「死物語」は、大きく分けて二つの物語から構成されています。上巻にあたる「しのぶスーサイド」では、主人公の阿良々木暦が二十歳を迎え、国立曲直瀬大学の二年生として過ごす日々が舞台となります。世間では新型コロナウイルスが猛威を振るう中、怪異の世界では「アンチ吸血鬼ウイルス」という新たな脅威が出現します。
このウイルスは吸血鬼のみを死に至らしめるもので、かつて暦を吸血鬼にし、忍野忍の主でもあったデストピア・ヴィルトゥオーゾ・スーサイドマスターがこれに感染し、瀕死の状態に陥ってしまいます。暦と、十三歳の姿へと成長を遂げた忍は、専門家である影縫余弦の要請を受け、デストピア公を救うためヨーロッパへと向かうことになるのです。
調査を進める中で、ウイルスの正体が明らかになります。それは、かつてデストピア公の眷属であったトロピカレスクのデストピア公への歪んだ愛情と、ある姫の呪いが複雑に絡み合って生まれたものでした。忍の決死の行動によりデストピア公はウイルスから解放され、人間に戻ることができましたが、物語はそこで終わりません。人間となった彼女は、二年後、人間界で流行していた新型コロナウイルスに感染し、静かにこの世を去ります。
下巻「なでこアラウンド」では、視点が変わり、元蛇神であり現在は漫画家を目指す中学生、千石撫子が主人公となります。彼女は、怪異の専門家である臥煙伊豆湖の指示で、沖縄県の西表島に潜むという洗人迂路子の調査に向かいます。この洗人迂路子こそ、かつて撫子に蛇の呪いをかけた張本人、臥煙伊豆湖の実の娘、臥煙雨露湖だったのです。
撫子には、かつての恩人である貝木泥舟と、影縫余弦の式神である斧乃木余接が同行しますが、道中で飛行機事故に巻き込まれてしまいます。撫子は無人島らしき場所で、ただ一人、裸の状態で目を覚まし、過酷なサバイバル生活を強いられます。しかし、その中で彼女は自身の能力を駆使し、さらには砂に絵を描くことで斧乃木余接を復活させるなど、目覚ましい精神的成長を遂げるのです。
最終的に西表島で洗人迂路子と対峙した撫子は、力でなく対話によって事態を解決へと導きます。過去のトラウマを乗り越え、コンプレックスを指摘されても動じないほどに成熟した撫子の姿は、まさに「別人」と呼べるほどでした。この一件を通じて、彼女は精神的に大きな飛躍を遂げたと言えるでしょう。
小説「死物語」の長文感想(ネタバレあり)
「死物語」を読了して、まず胸に迫ってきたのは、やはりタイトルにも冠されている「死」というものの重み、そしてそれがもたらす多様な意味合いでした。この作品は、文字通りの生命の終焉だけでなく、ある種の生き方の終わり、関係性の変容、そして過去との決別といった、様々な形の「死」を描いているように感じます。
上巻の「しのぶスーサイド」は、まさにその直球の「死」と向き合う物語でしたね。デストピア・ヴィルトゥオーゾ・スーサイドマスターという、かつては絶対的な力を持っていた吸血鬼が、未知のウイルスによって衰弱していく様は、読んでいて痛ましかったです。彼女の尊厳を守ろうとする暦や忍の姿、そして皮肉にも吸血鬼を殺すウイルスから救われた後に、人間として、当時の現実世界でも猛威を振るっていた新型コロナウイルスで亡くなるという結末は、非常に考えさせられるものでした。
この展開は、怪異の世界の脅威と、我々の現実世界の脅威が地続きであることを示しているかのようです。どんな強大な力を持つ存在であっても、あるいは不死に近いとされた存在であっても、形を変えた「死」からは逃れられないという、ある種の摂理のようなものを突き付けられた気がします。しかし、その死に様が、忍との穏やかな会話の後のものであったという描写には、救いも感じられました。デストピア公にとって、それは決して不幸なだけの最期ではなかったのかもしれません。
そして、このパートで描かれる「愛」の形もまた印象的でした。トロピカレスクの歪んだ、しかし純粋なデストピア公への愛が、結果的に彼女を死の淵へと追いやるウイルスを生み出してしまったという皮肉。愛という感情が持つ、美しさだけではない、時として破壊的にすらなり得る側面を垣間見た気がします。一方で、忍がデストピア公を救おうとする行動の根底にも、かつての主従関係を超えた複雑な情愛のようなものが感じられました。
暦の立ち位置も、これまでのシリーズとは少し異なる印象を受けました。彼自身が吸血鬼の特性を持つがゆえに、このアンチ吸血鬼ウイルスに対して無力ではないものの、決定的な解決者というよりは、事態の推移を見守り、大切な人々のために心を砕く、より人間的な苦悩を抱える存在として描かれていたように思います。二十歳という年齢も、彼の精神的な成熟を促しているのかもしれませんね。
次に、下巻の「なでこアラウンド」ですが、こちらは千石撫子の驚くべき成長譚として、胸が熱くなりました。かつては自分の殻に閉じこもり、極度の自己愛と他者への不信感に苛まれていた彼女が、これほどまでに逞しく、そして魅力的な少女へと変貌を遂げるとは、正直なところ予想を超えていました。
無人島でのサバイバル生活は、彼女にとって極限の試練だったはずです。しかし、その中で彼女は持ち前の描画能力を、生きるための力へと昇華させていきます。特に、斧乃木余接を砂浜に描いて復活させるシーンは、彼女の創造力が持つ可能性の大きさと、仲間を思う心の強さを見せつけられたようで、感動的でした。かつて神様だった頃の独善的な力とは異なる、他者と繋がり、他者を生かすための力の発現だったのではないでしょうか。
そして、最大の山場である洗人迂路子との対峙。かつて自分を呪った相手であり、そしてある意味では自分自身の過去のトラウマの象徴でもある存在との再会です。ここで撫子が選んだのが、暴力ではなく「対話」による解決だったという点が、彼女の成長を何よりも雄弁に物語っていると感じました。自分の弱さやコンプレックスを冷静に受け止め、相手の言葉に耳を傾ける。それは、かつての撫子には到底できなかったことでしょう。
この変化は、貝木泥舟や斧乃木余接といった、彼女を支え、導いてくれる存在がいたことも大きいのかもしれません。しかし、最終的にその導きを生かし、自らの足で立ち上がったのは撫子自身の力です。彼女が過去の自分という「死体」を乗り越え、新たな生へと踏み出した瞬間だったと言えるかもしれません。
臥煙伊豆湖の娘である洗人迂路子(臥煙雨露湖)の存在も、物語に深みを与えています。「何でも知っている」はずの臥煙伊豆湖でさえ、実の娘の問題には十五年間も対処できなかったという事実は、彼女の人間的な側面を垣間見せると同時に、撫子の成し遂げたことの大きさを際立たせているように思えます。
この二つの物語を通して、「死物語」は「死」を見つめることから逃げず、しかし、それによって浮き彫りになる「生」の輝きや、困難を乗り越えていく人間の「成長」の素晴らしさを描いていると感じました。阿良々木暦の物語が一つの区切りを迎える一方で、千石撫子というキャラクターがこれほどまでに力強い再生を遂げたことは、〈物語〉シリーズ全体のテーマ性にも通じる、希望のあるメッセージだったのではないでしょうか。
特に撫子の変容は、自己肯定感の低さやコミュニケーション不全といった、現代社会を生きる多くの人が抱えるかもしれない悩みに対する、一つの答えを示してくれているようにも思えます。過去の失敗やトラウマは消せないけれど、それとどう向き合い、未来へどう繋げていくか。そのヒントが、彼女の姿には詰まっている気がします。
また、作中で描かれる新型コロナウイルスの存在は、ファンタジーである〈物語〉シリーズの世界観と、我々の現実を繋ぐアンカーのような役割も果たしていたように感じます。それによって、登場人物たちが直面する「死」や「困難」が、より身近なものとして、読者の心に響いてくる効果があったのではないでしょうか。
モンスターシーズンの最終章として、この「死物語」は、これまでの物語で積み重ねてきたテーマを集約しつつ、登場人物たちの新たな門出をも予感させる、見事な着地点を示してくれたと思います。読み終えた後には、一抹の寂しさと共に、確かな満足感、そして未来への期待感が残りました。
それぞれのキャラクターが抱える「死」と向き合い、それを乗り越え、あるいは受け入れることで、新たな「生」を獲得していく。そのダイナミズムこそが、この「死物語」の最大の魅力であり、読者の心を揺さぶる力なのだと、改めて感じさせられました。
まとめ
小説「死物語」は、〈物語〉シリーズのモンスターシーズンを締めくくるにふさわしい、深遠なテーマ性と感動的な人間ドラマを内包した作品でした。特に「死」という普遍的なテーマに対して、西尾維新先生らしい独特の切り口で迫り、それが「生」や「愛」、「成長」といった他の重要な要素を鮮やかに照らし出していたのが印象的です。
上巻「しのぶスーサイド」では、デストピア公の文字通りの死を通して、命の儚さと尊厳、そして愛の複雑な側面が描かれました。現実世界のパンデミックが物語に組み込まれている点も、作品にリアリティと今日的な意味合いを与えていたように思います。
下巻「なでこアラウンド」では、千石撫子の目覚ましい成長が描かれ、過去のトラウマを乗り越え、真に自立した一人の人間として立ち上がる姿に胸を打たれました。彼女の変容は、困難な状況下でも人は変われるのだという強い希望を与えてくれるものでした。
この二つの物語は、それぞれ異なる形で「死」と「再生」を描きながら、シリーズ全体の大きな流れの中で、登場人物たちが新たなステージへと進んでいく様を見事に描き切っています。読み応えのある、そして心に残る一冊であったと断言できます。




















十三階段.jpg)







曳かれ者の小唄-721x1024.jpg)




















赤き征裁vs橙なる種-728x1024.jpg)





































兎吊木垓輔の戯言殺し-724x1024.jpg)



青色サヴァンと戯言遣い-722x1024.jpg)


.jpg)

.jpg)


