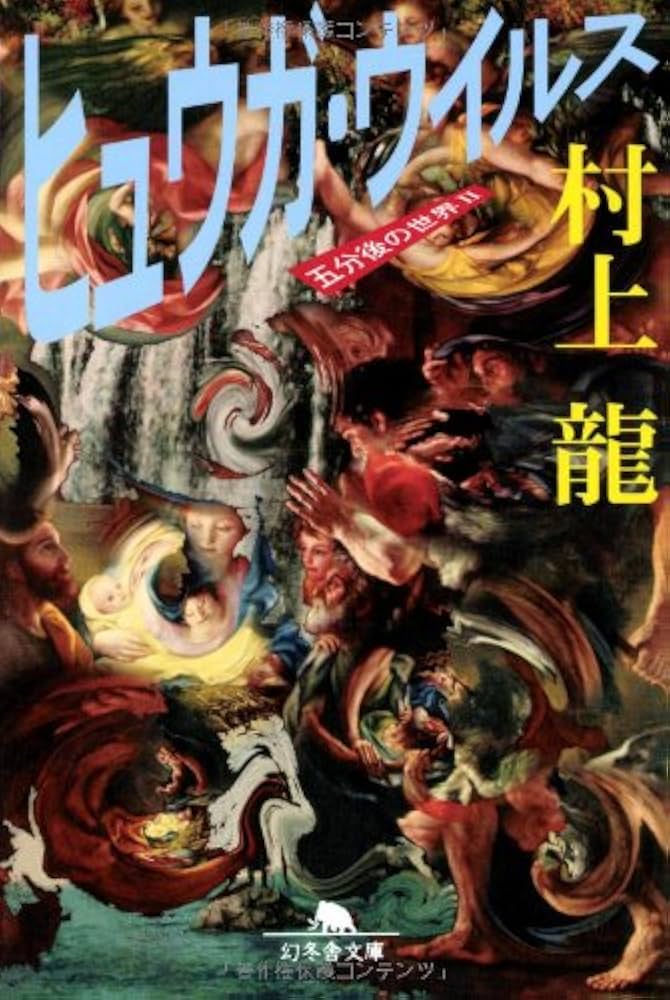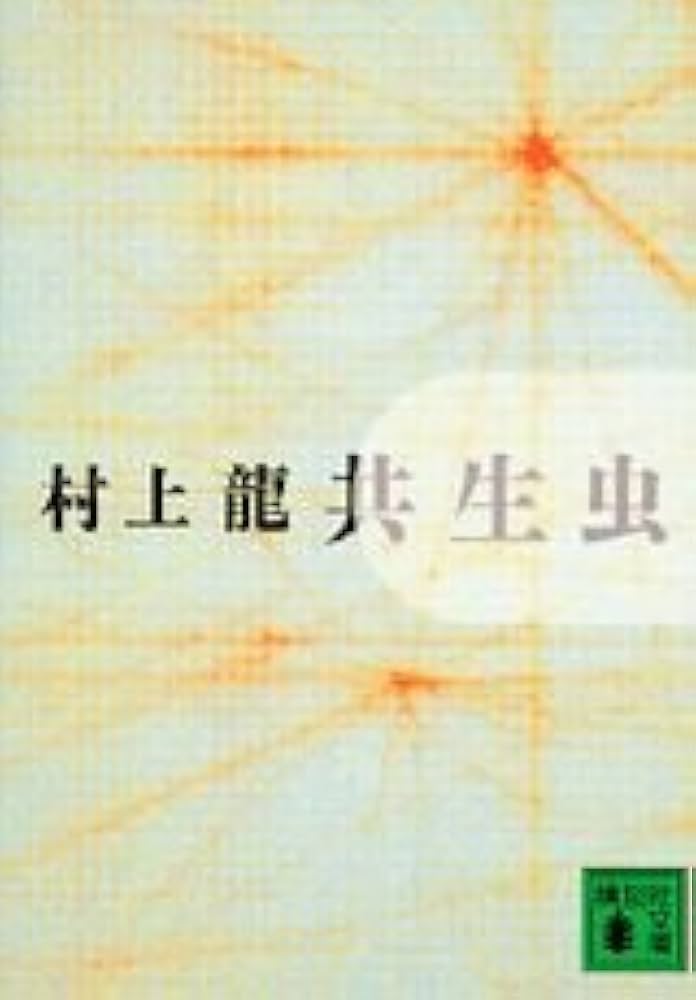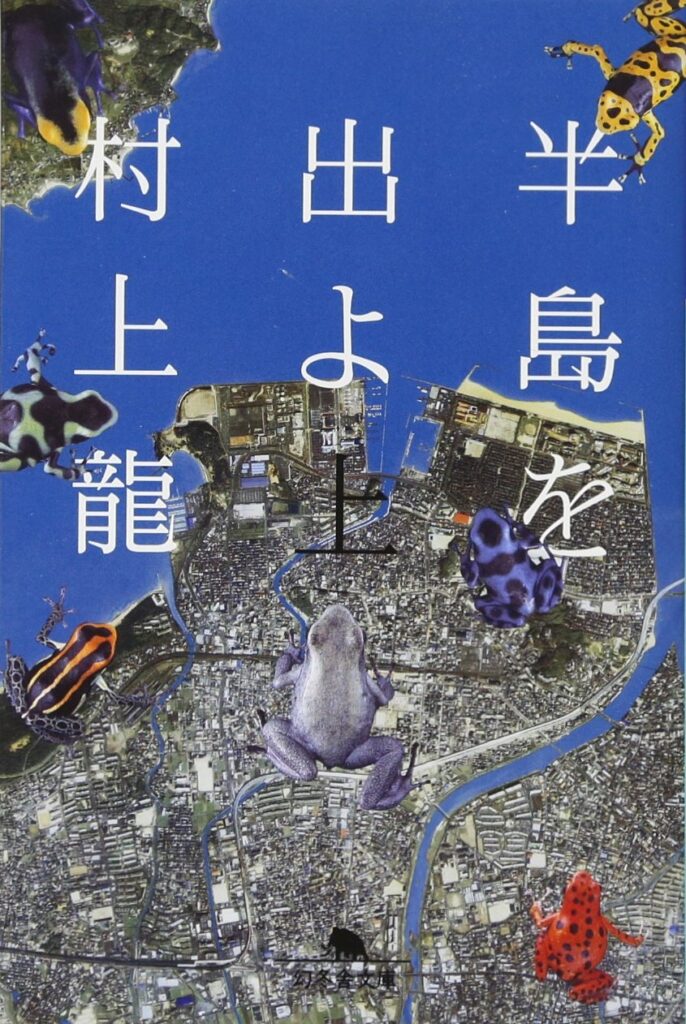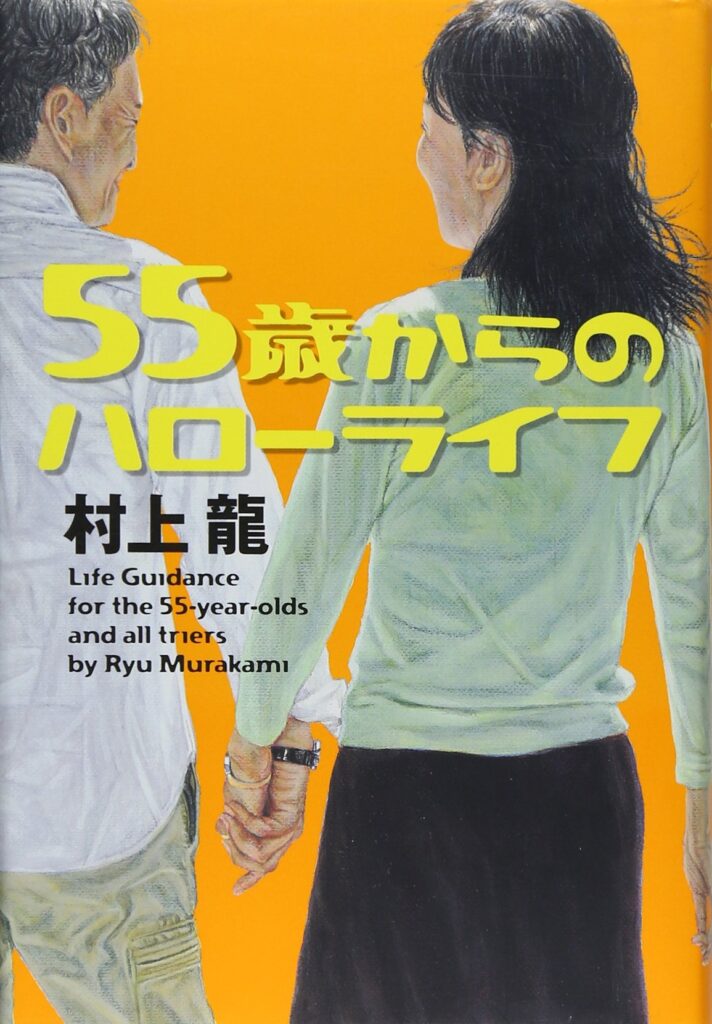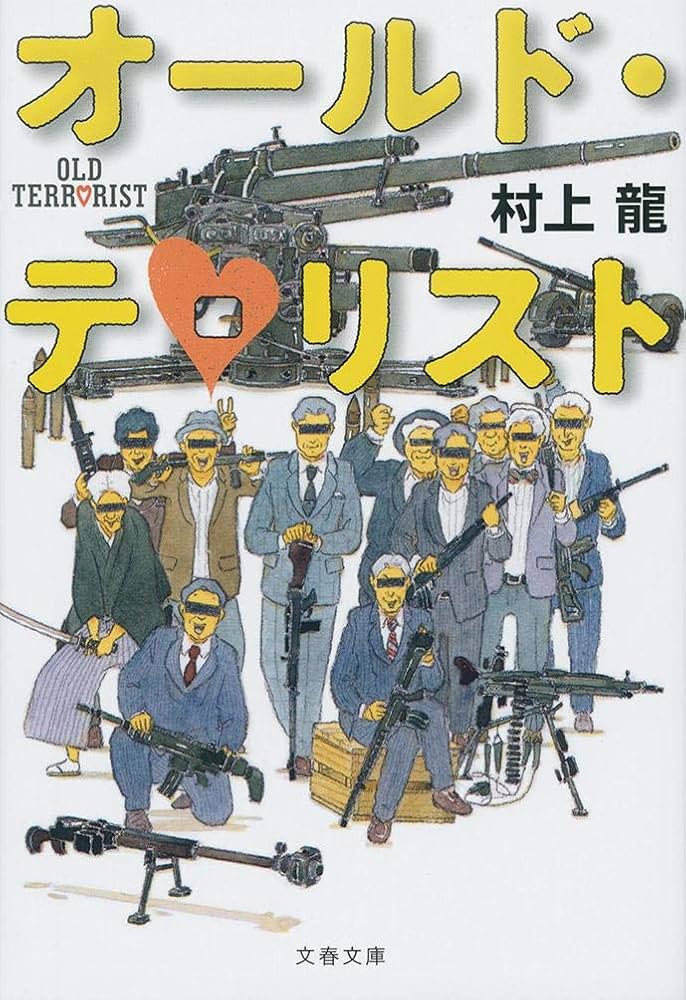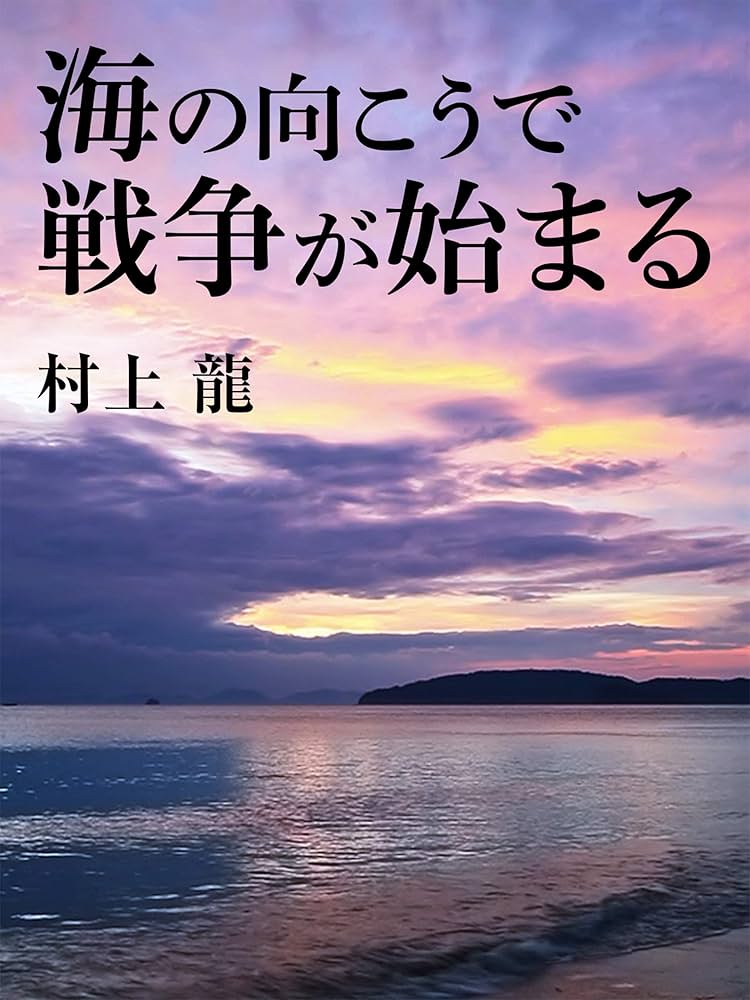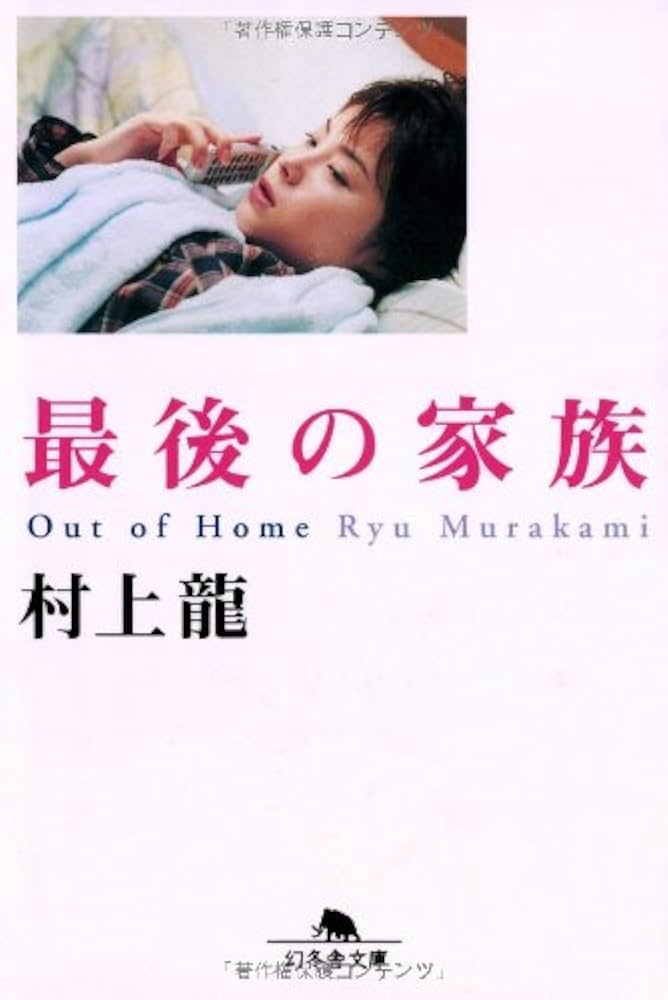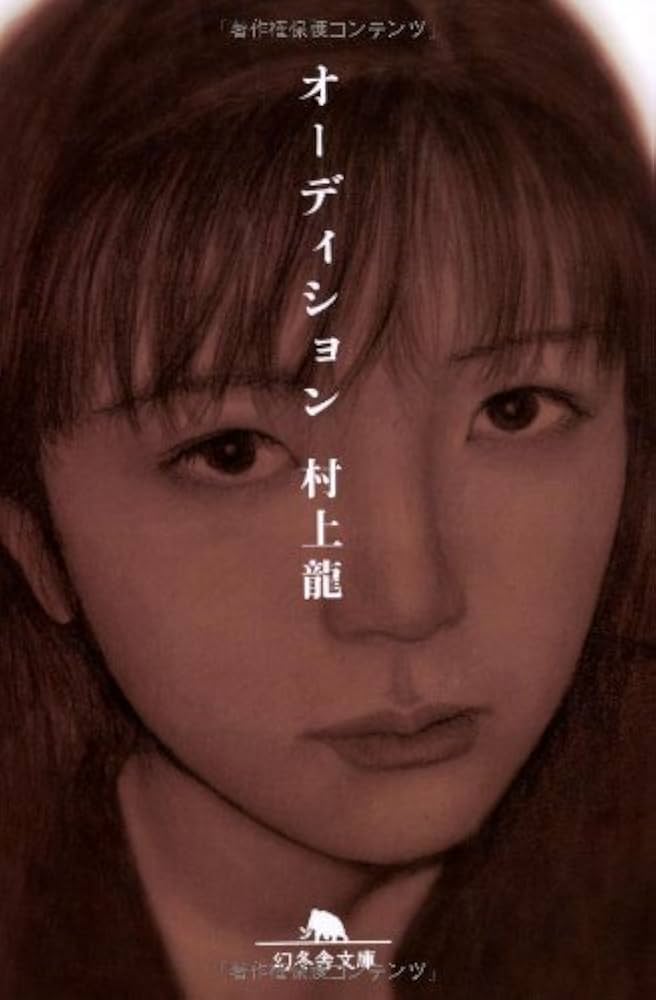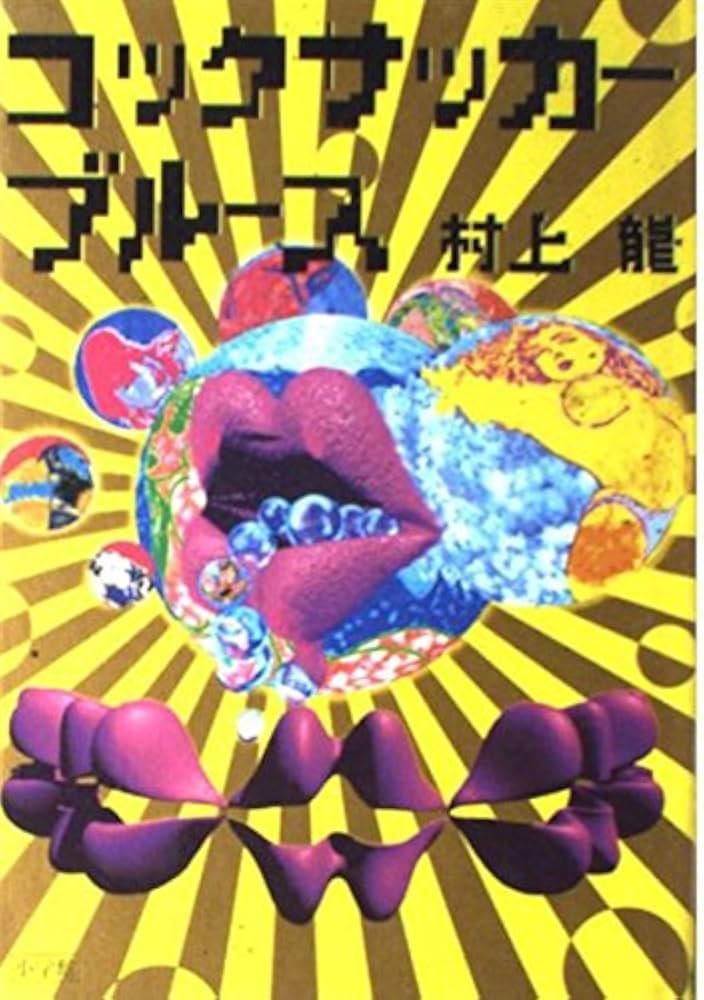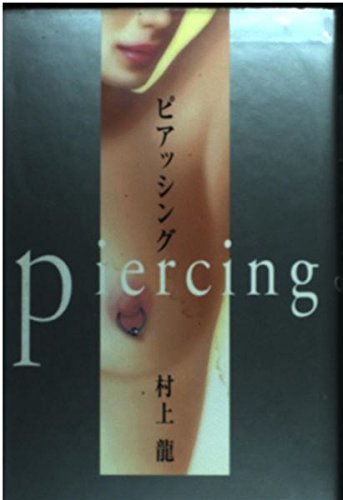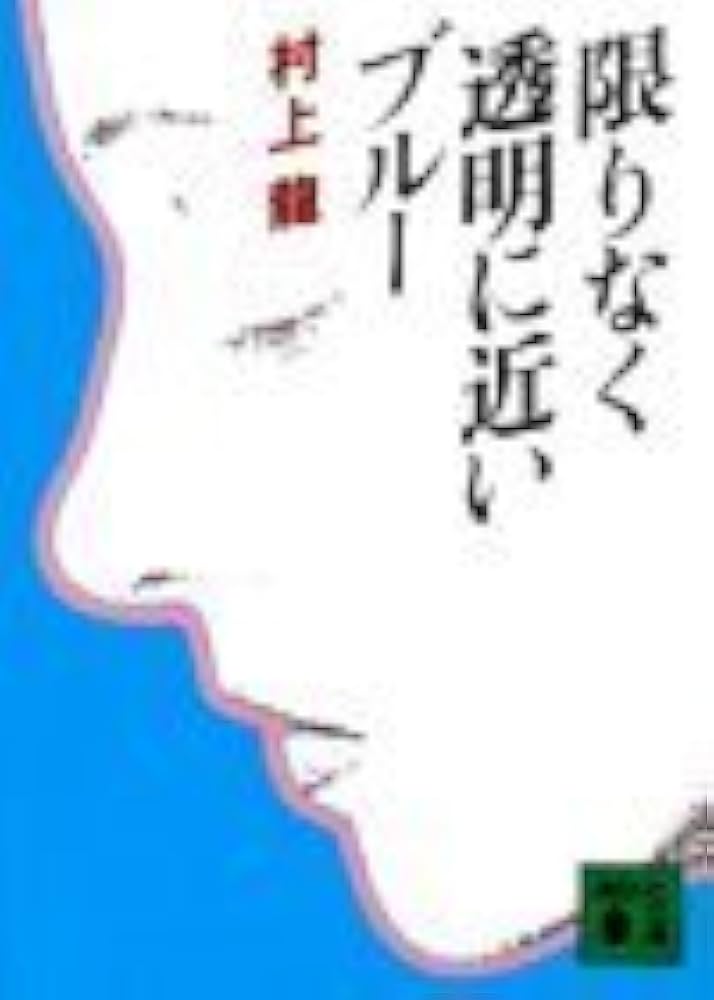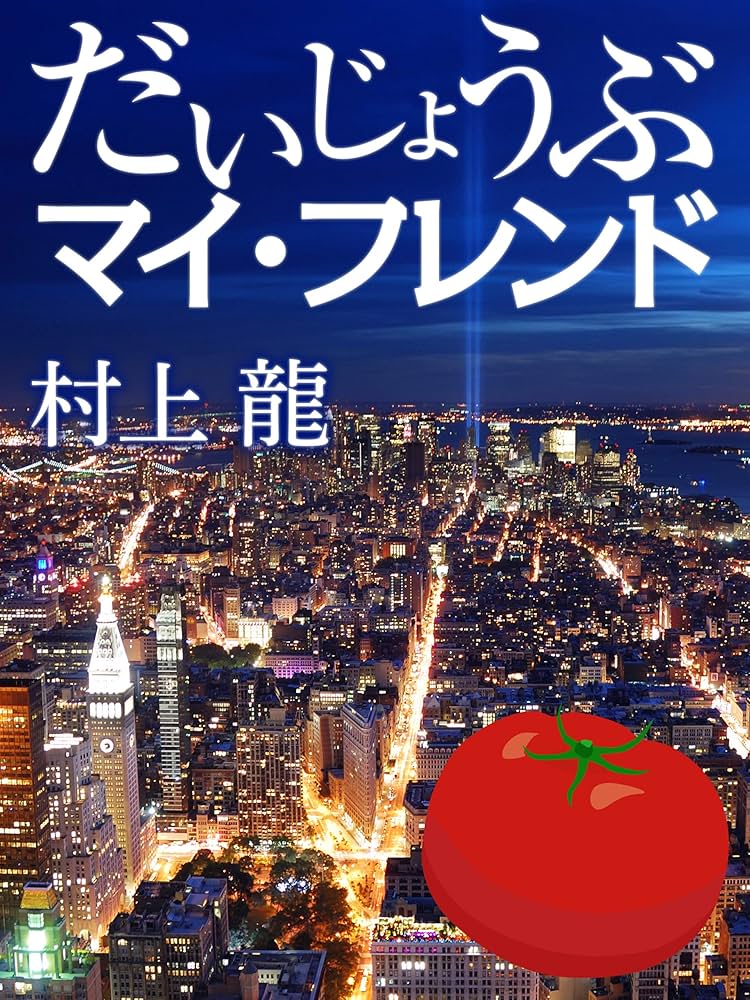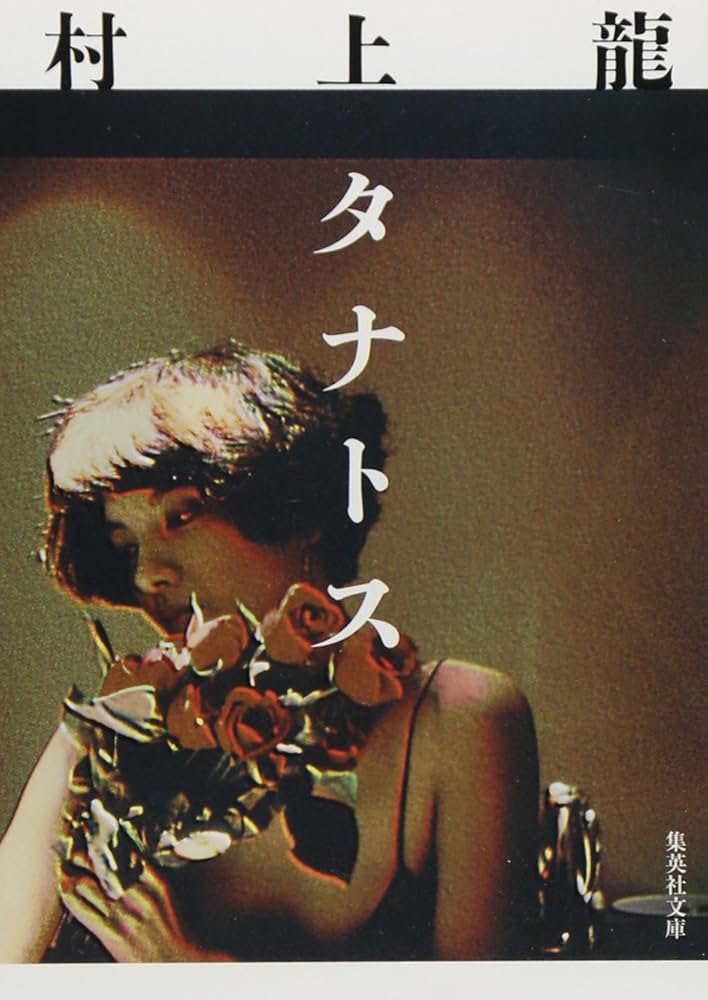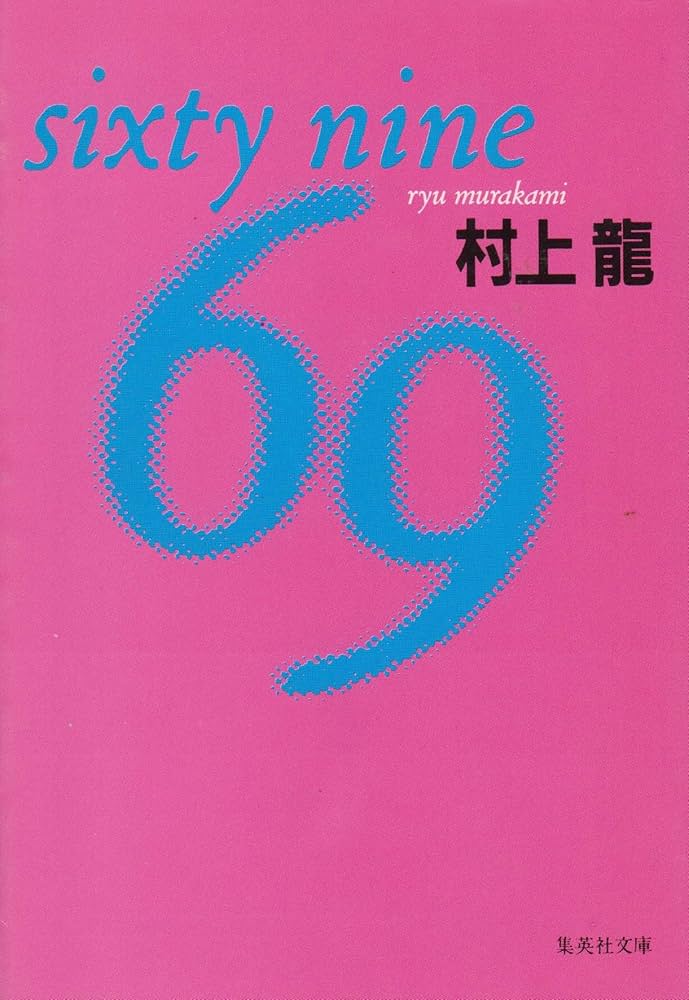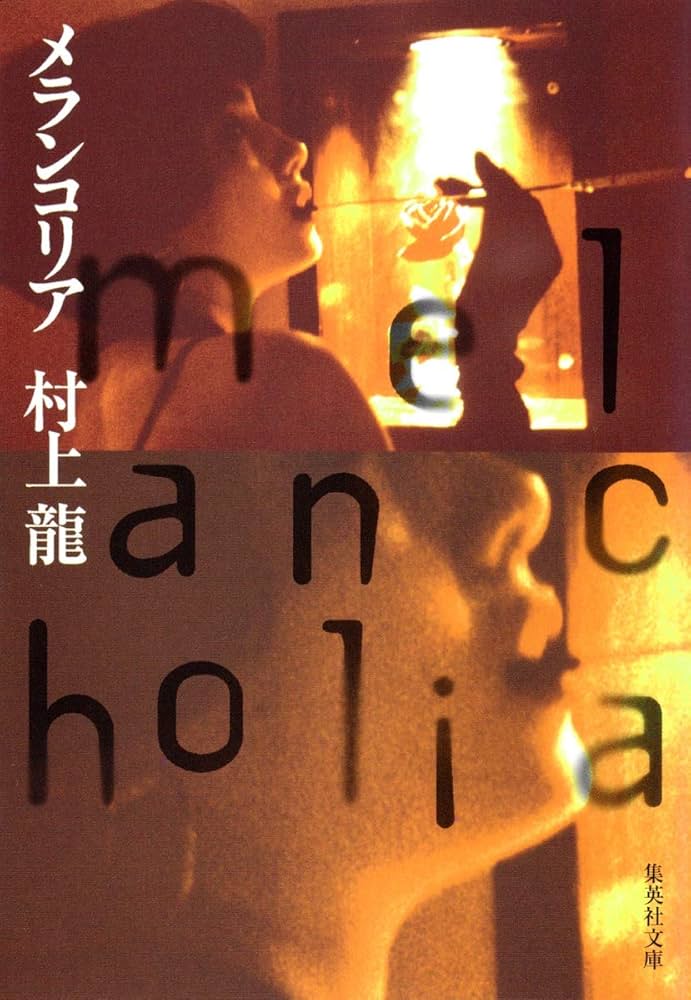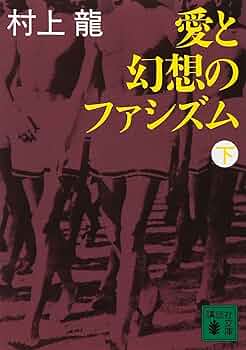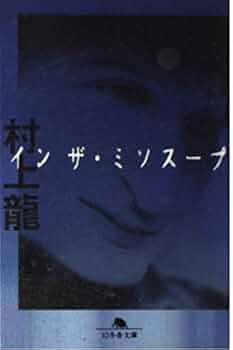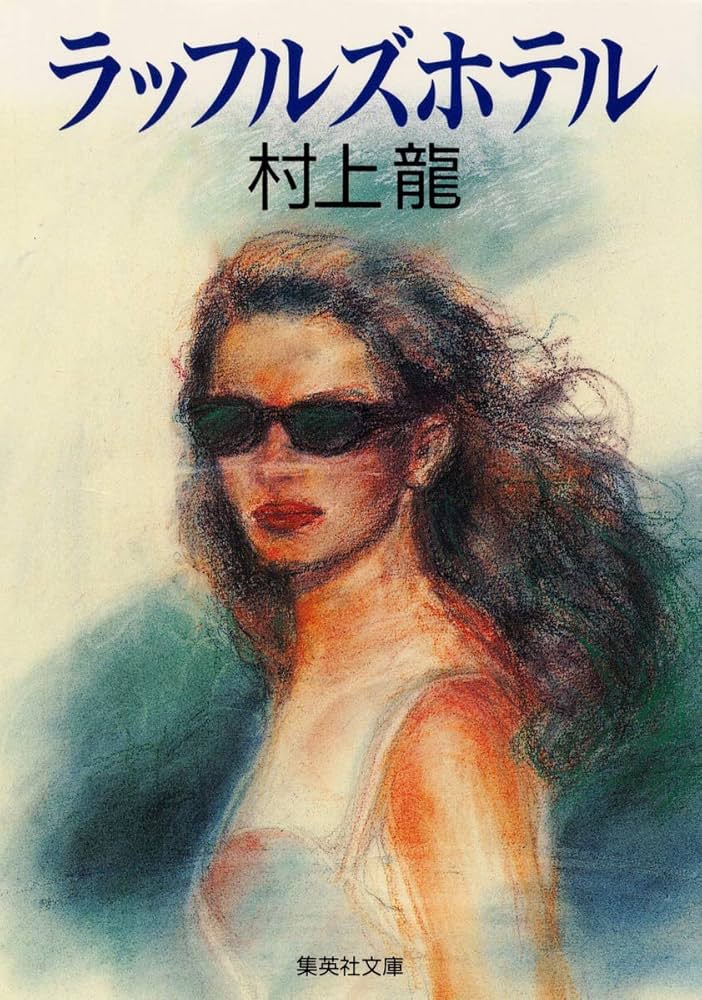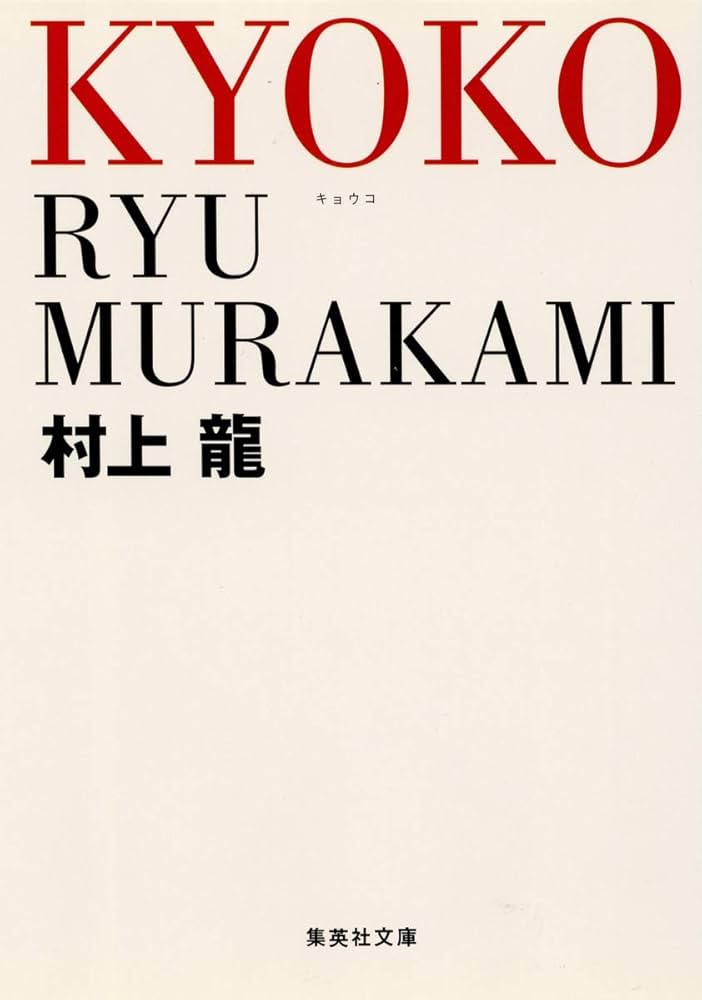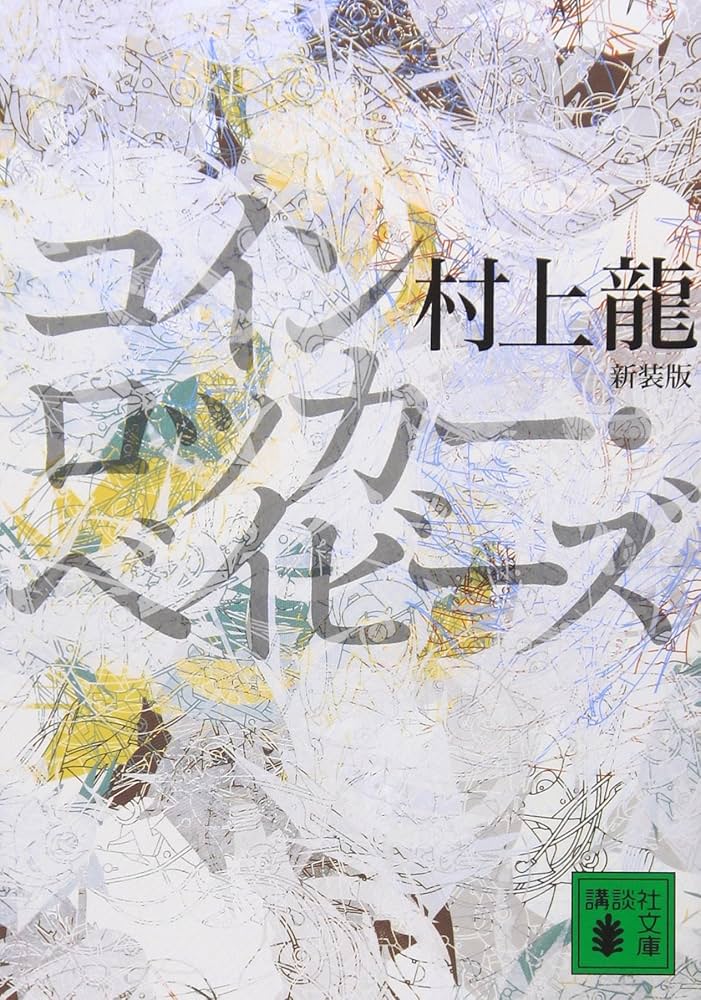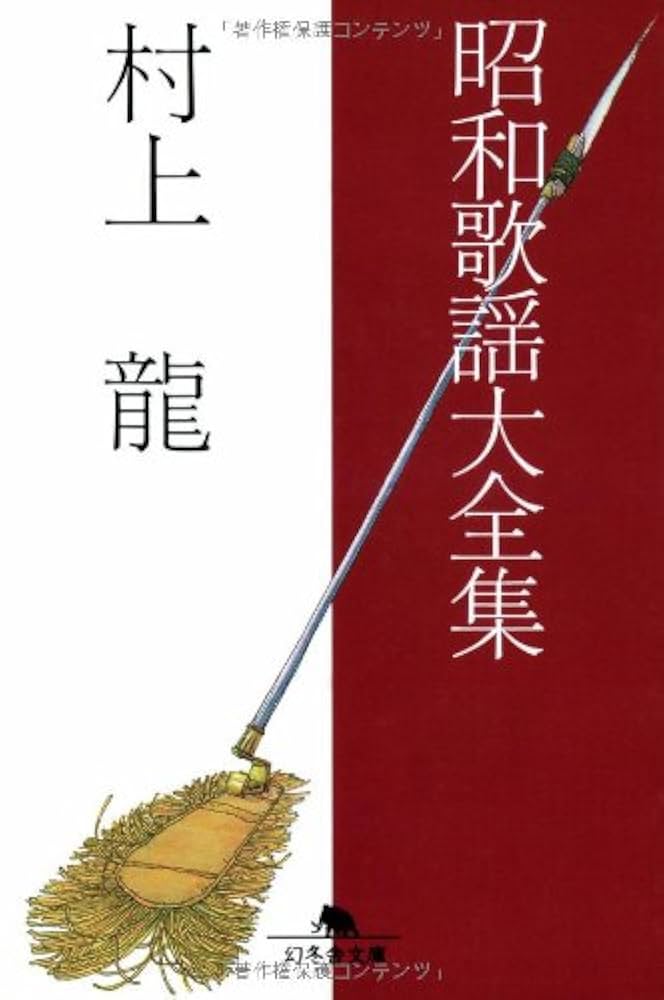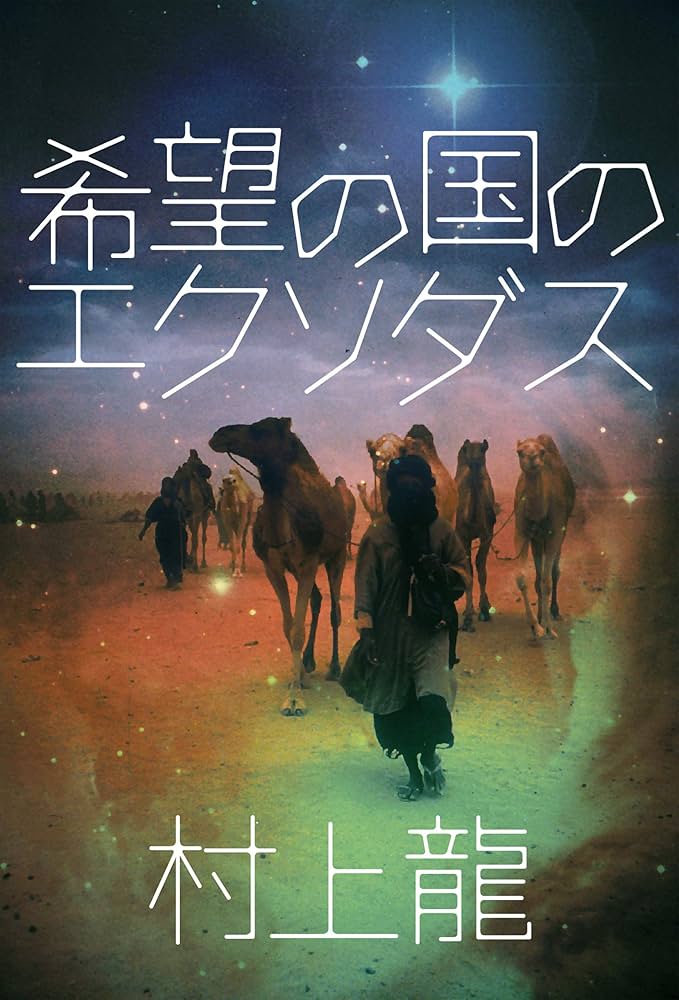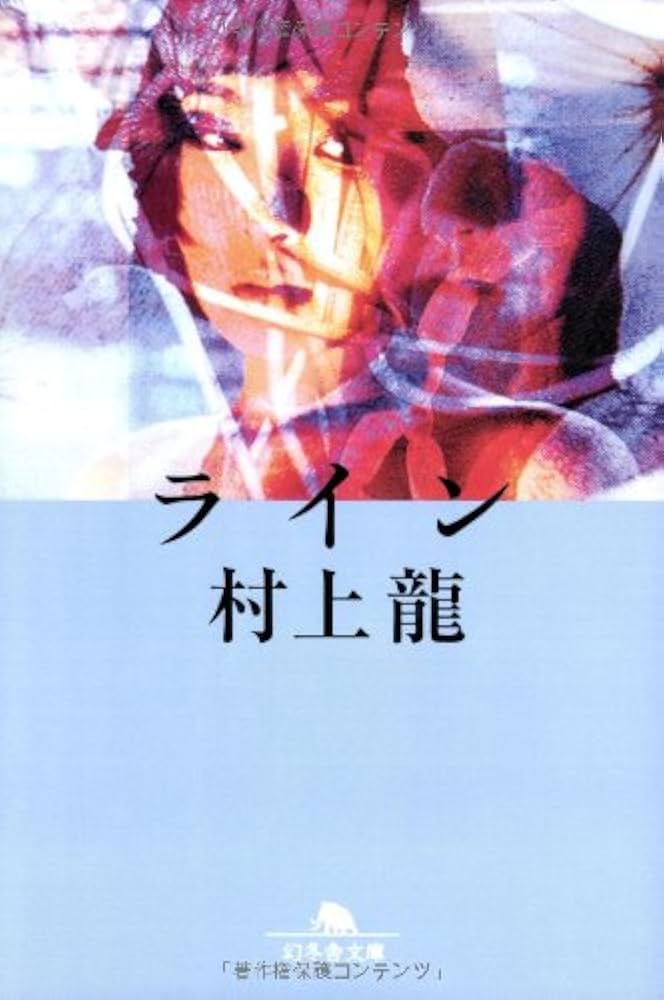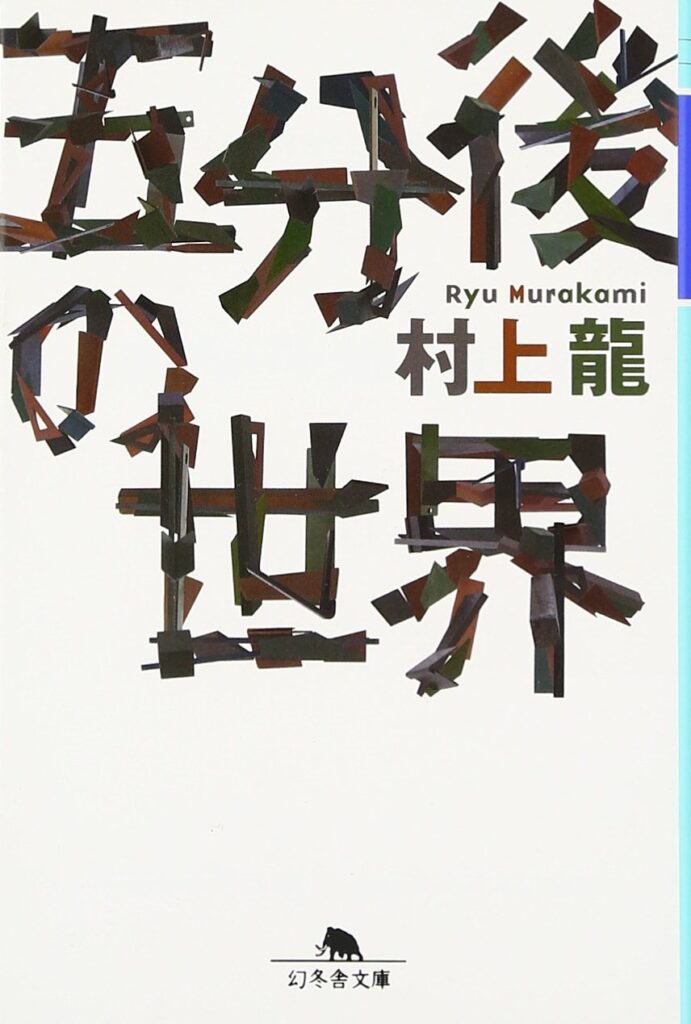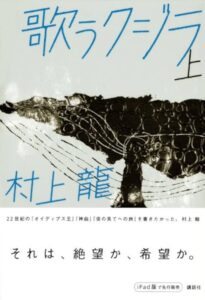 小説「歌うクジラ」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「歌うクジラ」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
村上龍さんが描き出す世界は、いつも私たちの足元にある現実を、少しだけ、あるいは大胆に歪ませて見せてくれます。この「歌うクジラ」という物語は、その中でも特に強烈な光と闇を内包した作品ではないでしょうか。人類が「不老不死」という永遠の夢を手に入れた未来。しかしその先には、輝かしいユートピアではなく、徹底的に管理されたディストピアが待っていました。
この物語は、単なる未来小説や冒険活劇の枠に収まりません。生きることの意味、人間の尊厳、そして「個」であることの痛みと輝きを、読者に鋭く問いかけてきます。主人公の少年アキラの旅路は、そのまま私たちの魂の旅路と重なる部分があるかもしれません。彼の目に映る歪んだ世界は、現代社会が抱える問題を映し出す鏡のようです。
この記事では、まず物語の骨格となるあらすじをご紹介し、その後、結末に至るまでの重大なネタバレを含んだ長文の感想を綴っていきます。この壮大な物語が持つ深いテーマ性や、心を揺さぶるメッセージについて、じっくりと語らせていただこうと思います。どうぞ、最後までお付き合いください。
「歌うクジラ」のあらすじ
物語の舞台は22世紀の日本。人類は「歌うクジラ」から発見された不老不死遺伝子「SW遺伝子」によって、老化を克服しました。しかし、その恩恵は平等ではなく、社会は最上層から最下層まで5つの階層に厳格に分断され、徹底的な管理社会、いわゆる「理想社会」が築かれていました。人々は体内のICチップと自律型ロボットによって監視され、階層間の移動は固く禁じられています。
主人公は、犯罪者や移民が収容される最下層の流刑地「新出島」で暮らす15歳の少年タナカアキラ。彼はある日、性犯罪という濡れ衣を着せられた父が、老化を促進させられ処刑されるという悲劇に見舞われます。父は死の間際、アキラに「ヨシマツ」という最上層の権力者に届けるべき情報が入ったICチップを託し、新出島からの脱出を命じました。
父の遺志を継いだアキラは、過酷な脱出劇の末に本土へ渡ります。ここから、彼の孤独で壮絶な旅が始まります。脳内に直接響く謎の声に導かれながら、彼は階層化された日本の歪んだ現実を目の当たりにすることになります。道中で出会う仲間たちと共に、アキラは世界の支配者が待つという最終目的地を目指します。
父が託したICチップには一体どんな秘密が隠されているのでしょうか。そして、アキラを導く声の主は誰なのか。彼の旅の果てに待ち受ける世界の真実とは、一体どのようなものなのでしょうか。物語は、読者の予想を裏切りながら、衝撃的な結末へと突き進んでいきます。
「歌うクジラ」の長文感想(ネタバレあり)
ここからは、物語の核心に触れる重大なネタバレを含んだ感想になります。未読の方はご注意ください。この「歌うクジラ」という作品は、読み終えた後に、生きることそのものについて深く考えさせられる、重厚な物語でした。
まず、この物語の根幹をなす設定が、あまりにも皮肉に満ちていて心を掴まれました。不老不死の発見という、人類の長年の夢が叶った世界。それは本来、争いや苦しみのない理想郷になるはずでした。しかし、村上龍さんが描いたのは、その真逆の、生ける屍たちが暮らす冷徹なディストピアだったのです。これは、ユートピア的な理想がいかに簡単にその対極へ転じてしまうかという、鋭い指摘だと感じます。
グレゴリオ聖歌を歌うクジラという、神秘的で美しい存在から得られた生命の贈り物が、結果として人間から感情や個性を奪い、社会を断絶させるために使われてしまった。この一点だけでも、科学技術の進歩に対する痛烈な批判が込められているのではないでしょうか。自然の奇跡を、人間がいかに自分たちの都合の良いように歪めてしまうのか。その愚かさが、物語の冒頭から色濃く漂っています。
社会の構造も実に巧みに描かれています。最上層から最下層まで、ICチップとロボットによって完全に分断された階層社会。この徹底した「棲み分け」は、下層の人間が上層の存在を知ることさえできなくさせ、反乱や革命の意志を根源から摘み取ってしまいます。物理的な支配だけでなく、「文化経済効率化運動」という名の下で、敬語や複雑な感情表現といった「非効率」な文化を排除し、人々の精神までをも支配しようとします。
主人公アキラが暮らす最下層「新出島」の描写は、その支配の完成形を示していて圧巻です。精神安定剤入りの栄養ペースト「棒食」によって、住民は意欲や欲望といった人間的な感情を化学的に抑制されている。外側からの監視と、内側からの薬物支配。この二重の支配構造が、このディストピアの恐ろしさを際立たせていました。
物語は、アキラの父が冤罪で処刑され、彼にICチップを託すという、古典的な冒険譚の形で幕を開けます。父の遺志を継ぎ、巨大な悪に立ち向かう少年。この王道の筋書きに、読者である私は「これからアキラの英雄的な旅が始まるのだ」と期待しました。しかし、この物語の本当に恐ろしいところは、この期待すらも巧妙に裏切る点にあります。この導入部こそが、最大のネタバレへの壮大な伏線だったのです。
アキラの孤独な旅を支えるのが、脳内に響く「導きの声」です。当初は亡き父の声のように感じられ、彼に情報や勇気を与えるこの声は、唯一の希望の光のように思えます。しかし、物語が進むにつれて、この声の存在そのものが、アキラの主体性を奪うシステムの一部であったことが明らかになっていきます。父の復讐という目的も、国家を揺るがす秘密が隠されているとされたICチップも、全てが仕組まれたものだった。このネタバレを知った時の衝撃は、物語の構造そのものがひっくり返るような感覚でした。
アキラの旅は、本土に渡ってからさらに過酷さを増します。彼が出会う仲間たちが、この歪んだ世界への抵抗を象徴していて非常に興味深いです。致死性の毒を分泌する能力を持つ「クチチュ」のサブロウ。そして、政府への反乱者の末裔であり、意図的に崩した日本語を話すアン。特にアンの一族が話す言葉は、言語の均質化を進める国家への強烈なアンチテーゼとして機能しています。一方で、アキラが話す古風で美しい敬語がアンを惹きつけるという関係性も、失われた文化への郷愁を感じさせ、印象的でした。
アキラの旅は、このディストピアの悲惨な光景を巡る旅でもあります。死の恐怖から解放された結果、猿のように退化してしまった村。そして、私が最も衝撃を受けたのが、不老不死となったエリートたちが収容された病院の光景です。彼らは四肢を失い、ただの胴体となっても機械に生かされ続けている。永遠の命と引き換えに、生の実感を完全に失ってしまった人々。このグロテスクな描写は、生命を単なる科学的・物質的なものとして捉えることの危険性を、これ以上なく明確に示していると感じました。
物語のクライマックスで、アキラはついに宇宙ステーションにいる世界の支配者「ヨシマツ」と対面します。このヨシマツの正体こそ、この物語最大のネタバレであり、核心部分です。そこにいたのは人間ではなく、培養液に浮かぶ巨大な脳髄でした。彼は機械と接続することで全世界を管理する、ポストヒューマン的な存在と化していたのです。
そして、ヨシマツの口から語られる真実は、読者の想像を絶するものでした。アキラの父の死も、託されたICチップも、導きの声も、彼の旅の全てが、ヨシマツによって仕組まれた壮大な「実験」だったのです。ヨシマツは、自身の脳をリフレッシュするために、過酷な試練を乗り越えさせた強靭な若者の脳髄を定期的に必要としており、アキラはそのための最高のサンプルだった。この事実が明かされた時、アキラの英雄譚は完全に崩壊し、彼の人生そのものが巨大なシステムの掌の上で踊らされていたに過ぎないことが判明します。
ヨシマツがアキラに持ちかける「同化」の提案は、個を捨てて全体の一部となり、苦しみから解放されるという、ある種の甘美な誘惑です。有名なアニメ作品における「人類補完計画」を彷彿とさせるこの構図の中で、アキラは究極の選択を迫られます。神のような超越的存在になるのか、それとも苦しみに満ちた「個」であり続けるのか。
ここでのアキラの決断が、この物語のテーマを凝縮しています。彼は「他人になったら自分を憎むことができない。それは絶対に嫌だ」と言い放ち、同化を拒絶します。幸福な無個性よりも、欠陥だらけで憎しみを抱えてしまうとしても、「自分」であることを選んだのです。たとえそれが苦痛に満ちたものであっても、個として存在する価値を、彼は命を懸けて肯定しました。この場面には、深く胸を打たれました。
ヨシマツを破壊し、宇宙の虚無へと一人で脱出したアキラ。確実な死を前にした、絶対的な孤独と静寂の中で、彼はこの物語の最も重要な真理に到達します。それは、「生きる上で意味を持つのは他人との出会いだけだ。そして移動しなければ出会いはない。移動が、すべてを生み出すのだ」という悟りでした。
この結論は、見事と言うほかありません。意味とは、誰かから与えられるものではない。偽りの父から与えられた目的でも、神のような存在から与えられる幸福でもない。自らの足で「移動」し、他者と偶然に出会うという、予測不可能な行為の中から、自分自身で創造していくものなのだと。この気づきは、アキラが偽りの父の物語を捨て、自らの旅で得た本物の出会いに基づく、新しい生の意義を見出した瞬間でした。
そして、この悟りはすぐに、強烈な「生きたい」という渇望へと繋がります。生の意義を見つけてしまったからこそ、彼は生きたいと願う。その意味を、旅の仲間であったアンやサブロウたちに伝えるために。物語の最後、アキラが宇宙の闇に向かって「生きていたい、ぼくは生きていたい」と祈り続ける場面で、物語は幕を閉じます。
この結末は、最も絶望的な状況の中に、最も純粋な希望を描き出すという、驚くべき両義性を持っています。彼の生存が約束されているわけではありません。しかし、たとえ死の直前であったとしても、生きる価値を見出し、それを肯定する意志を持つこと。それ自体が、何物にも代えがたい勝利なのだと、この物語は教えてくれます。
「歌うクジラ」は、単なるディストピア小説ではありませんでした。それは、管理され、意味を剥奪された世界で、一人の少年が「移動と出会い」を通じて自分だけの意味を発見し、生の絶対的な価値を掴み取るまでの、壮絶で美しい魂の記録です。読み終えた今も、宇宙の闇に響くアキラの祈りが、私の心の中で鳴り響いています。
まとめ
村上龍さんの「歌うクジラ」は、不老不死が実現した未来を舞台に、人間にとっての「生の意味」を根源から問う、非常に深く、そして心を揺さぶる物語でした。あらすじを追うだけでもその壮大さが伝わりますが、物語の核心にあるネタバレを知ることで、作品の持つテーマ性がより一層際立ちます。
主人公アキラの旅は、偽りの父から与えられた目的をなぞる、操られたものでした。しかし、その旅の過程、つまり「移動」と「出会い」こそが、彼に本物の生の価値を教えます。世界の全てが虚構であったとしても、他者と出会ったという事実だけは、揺るぎない真実だったのです。
この物語が最終的にたどり着くのは、どんなに絶望的な状況にあっても、生を肯定し、渇望することの尊さです。宇宙空間という絶対的な虚無の中で、アキラが発する「生きていたい」という祈りは、私たちの心に強く訴えかけてきます。
もしあなたが、日々の生活に意味を見出せずにいたり、大きな物語に飲み込まれそうになっていると感じたりすることがあるなら、この「歌うクジラ」はきっと、何か大切な気づきを与えてくれるはずです。ネタバレを知った上で再読すると、また新たな発見があるかもしれません。