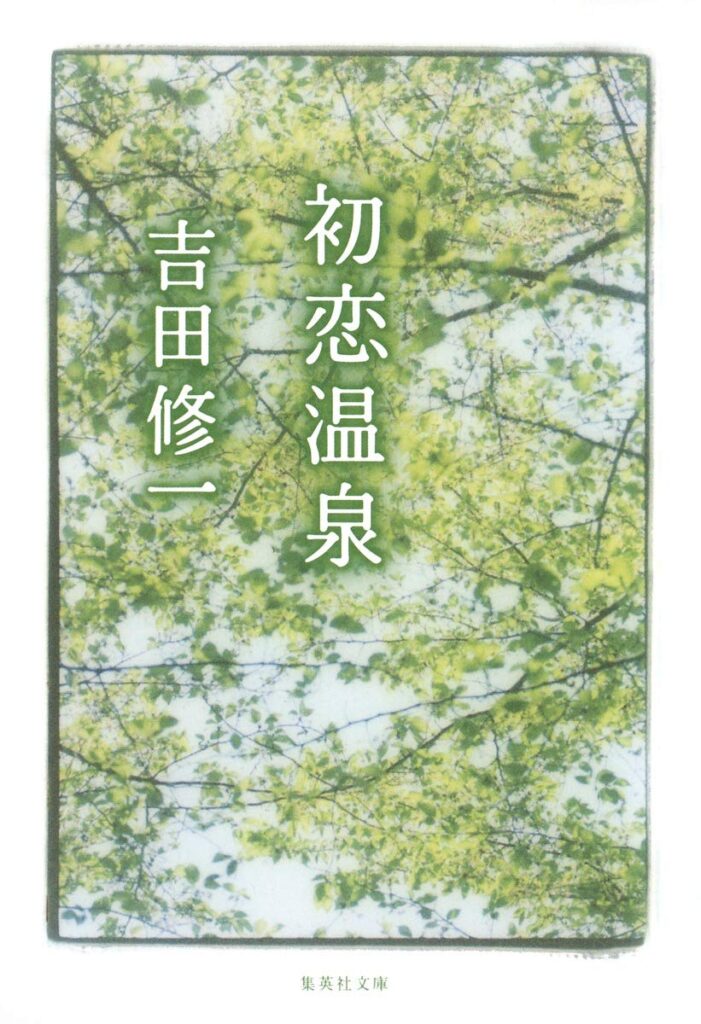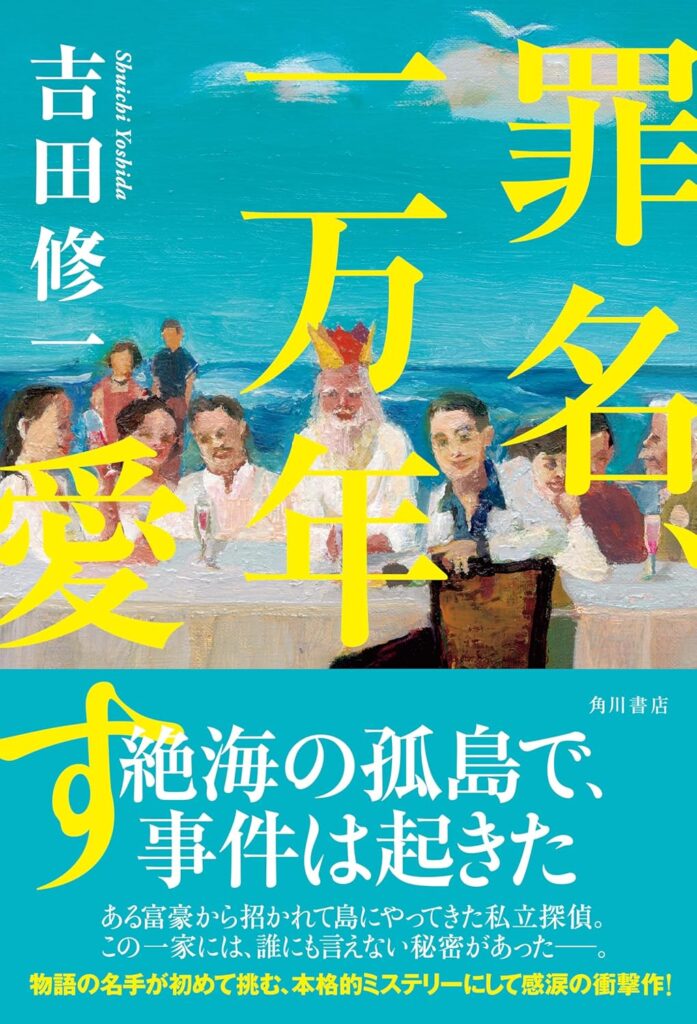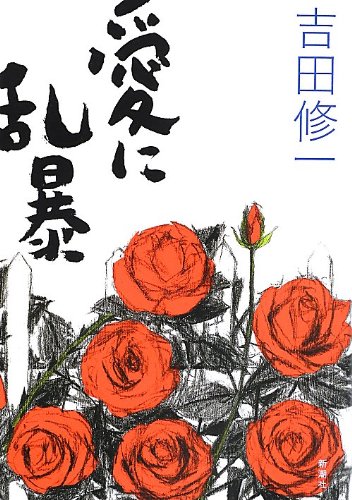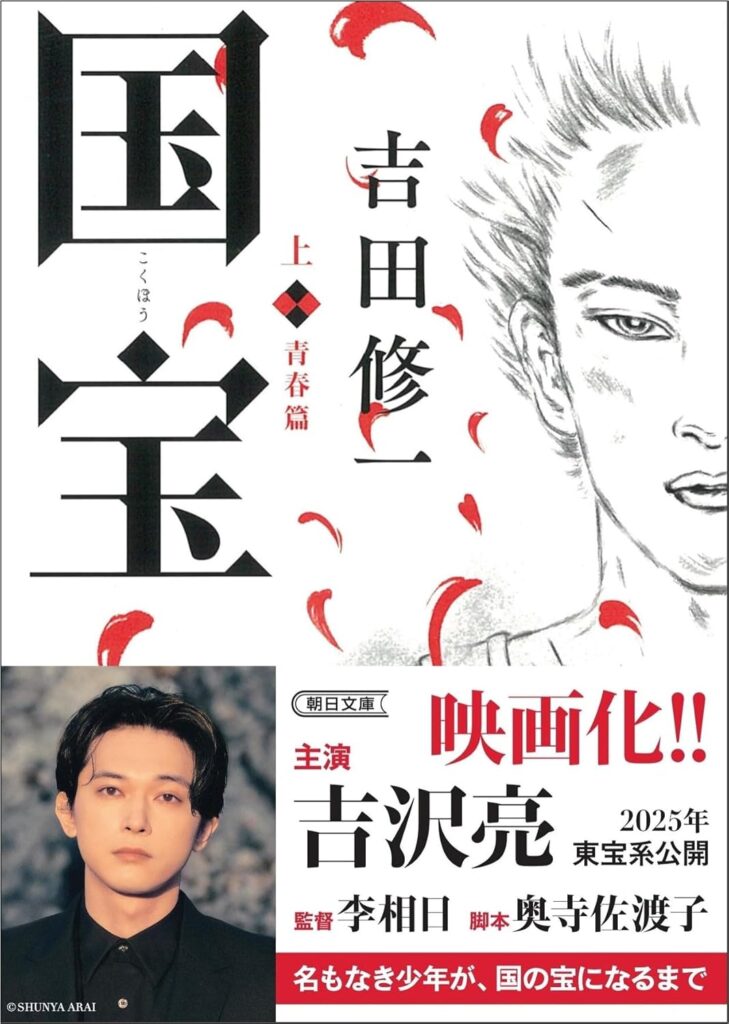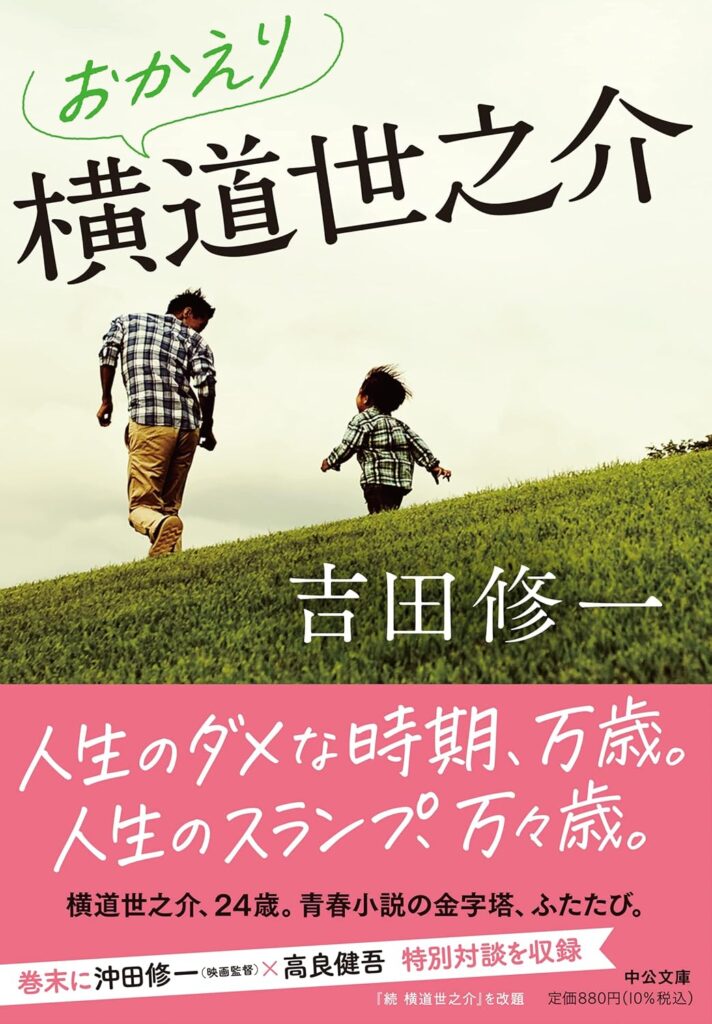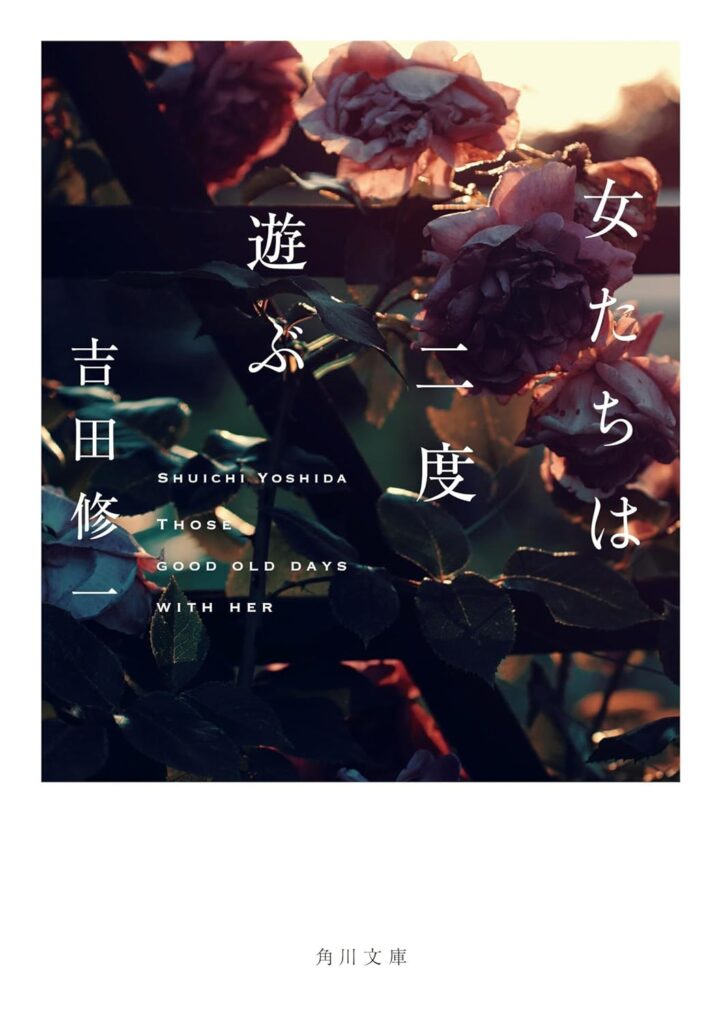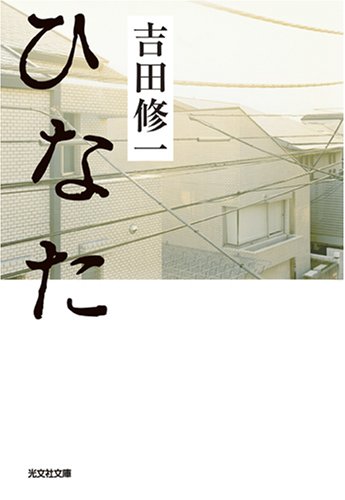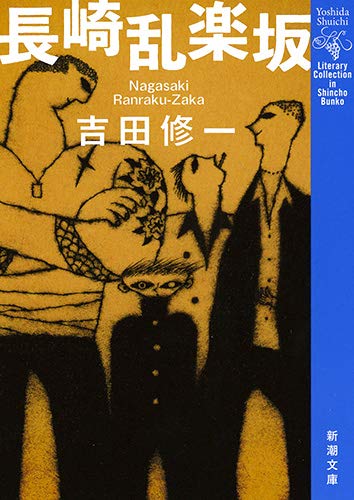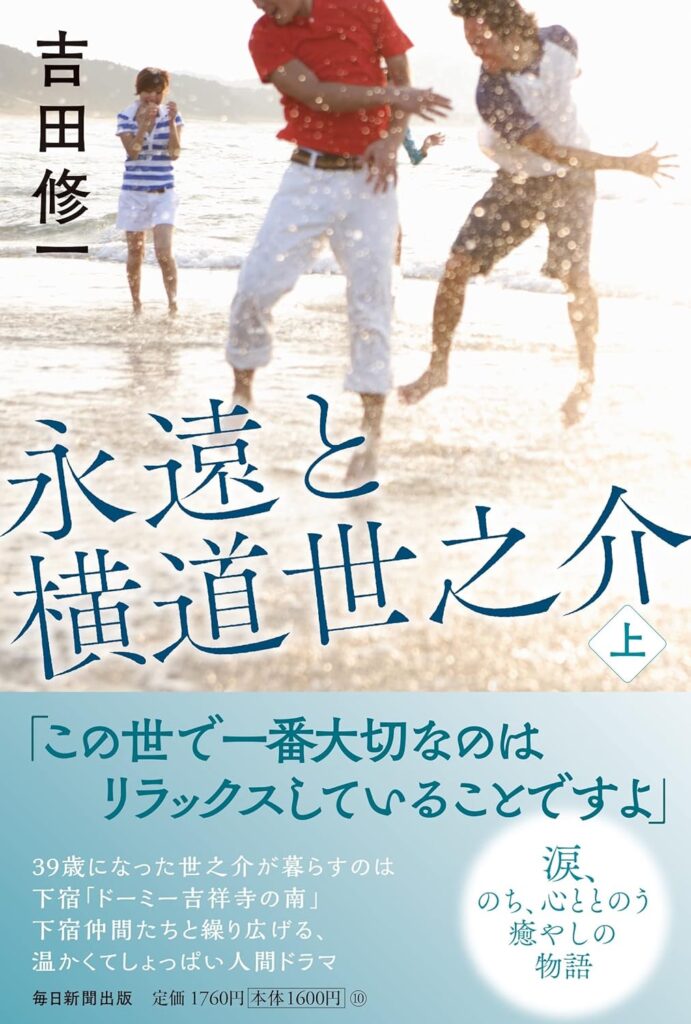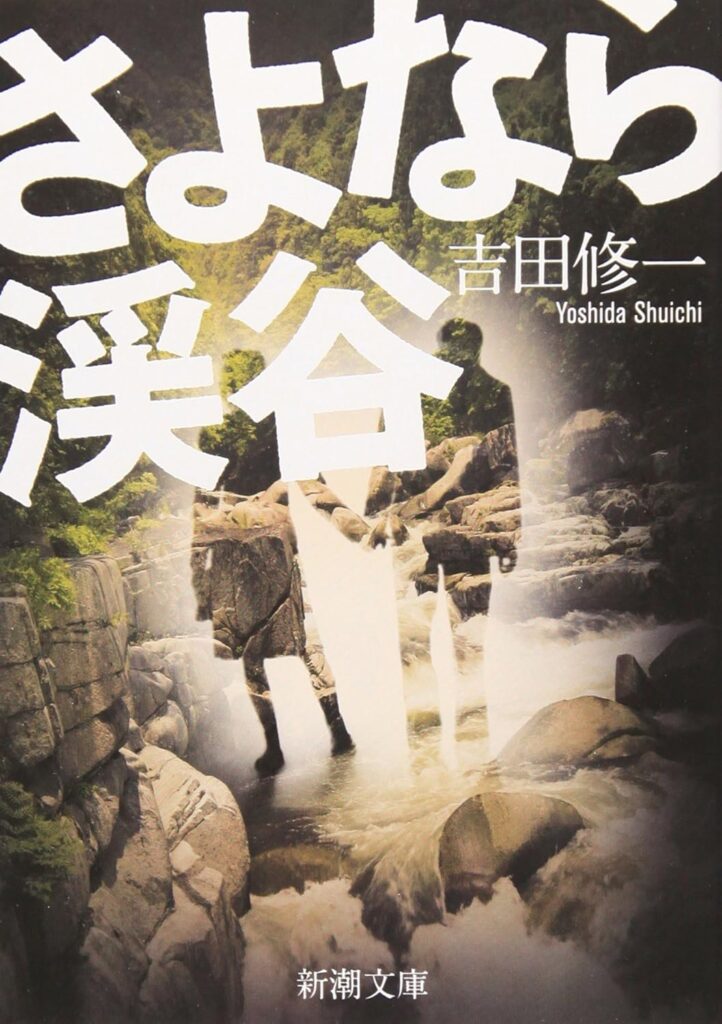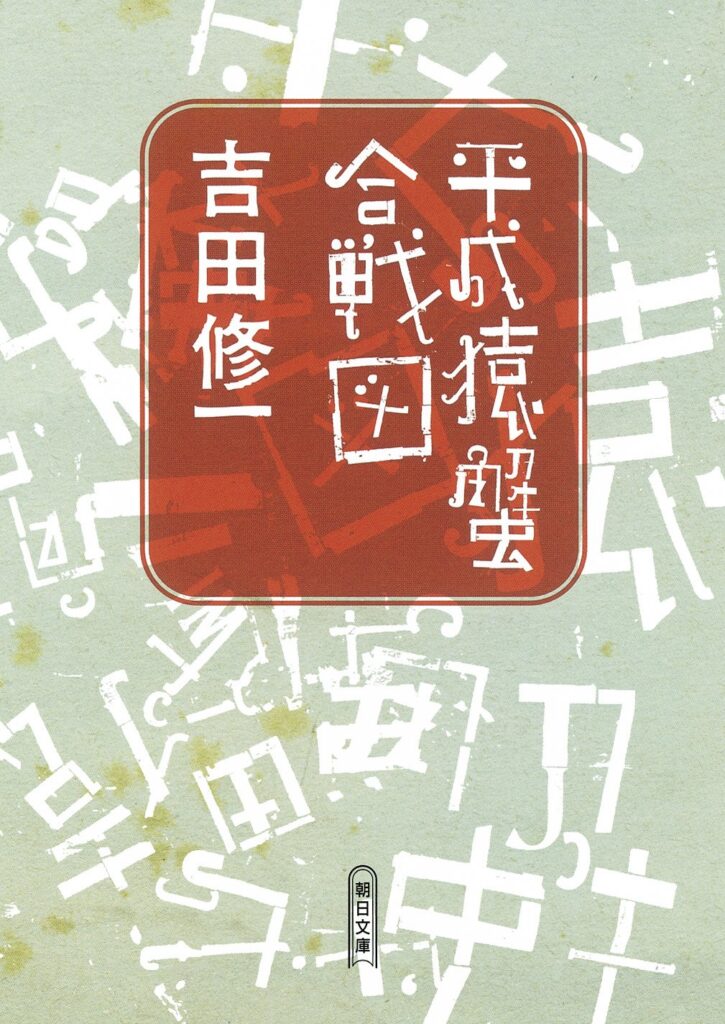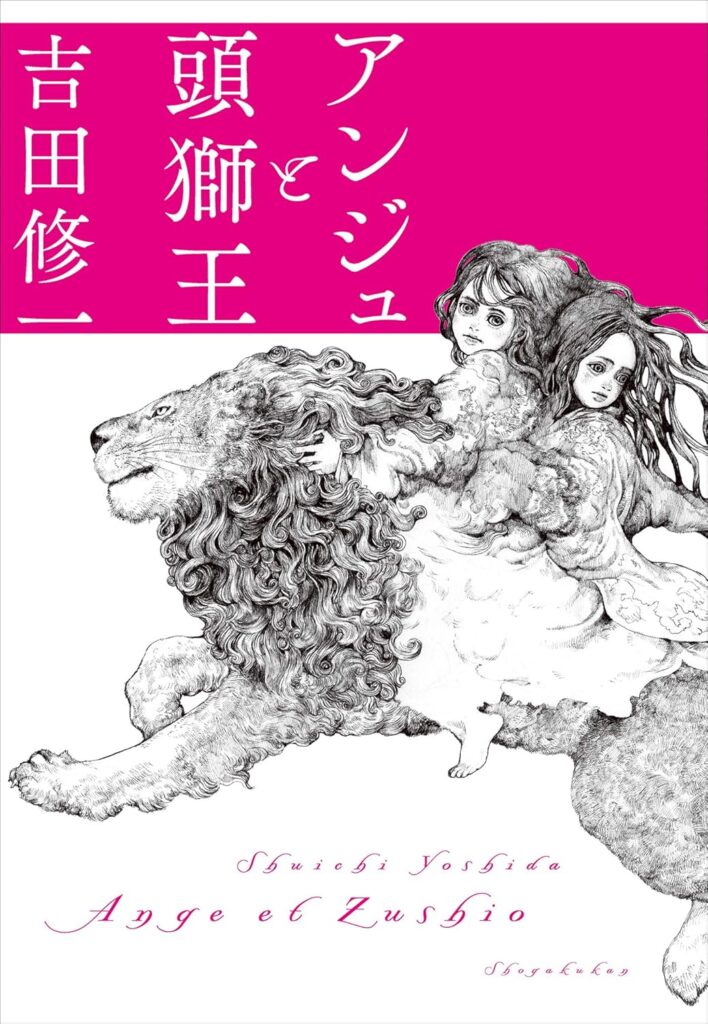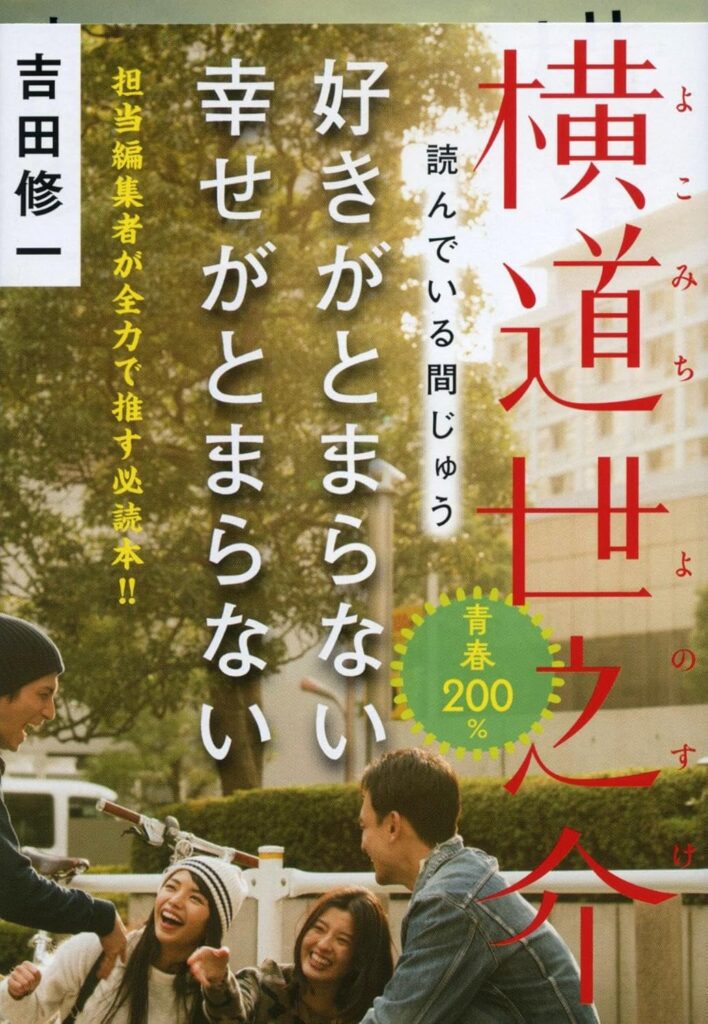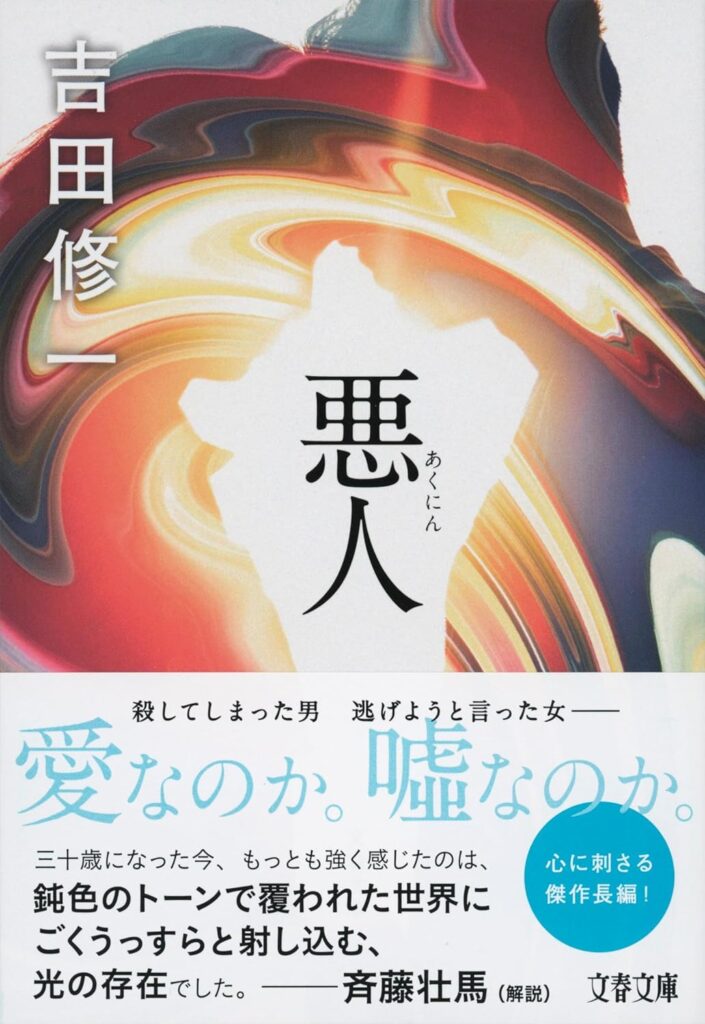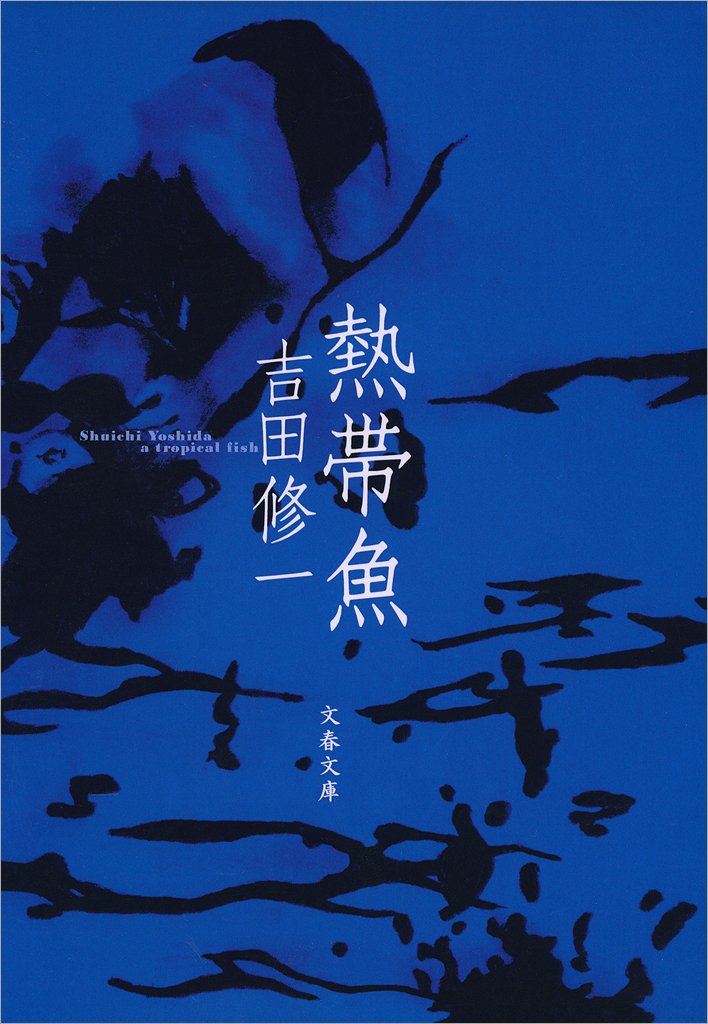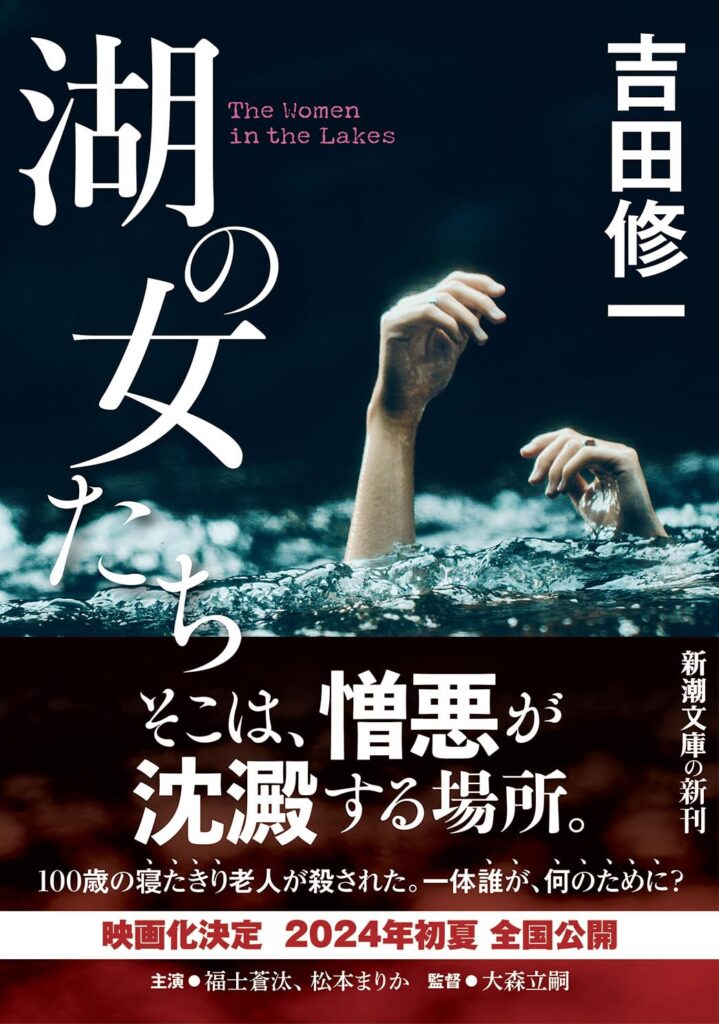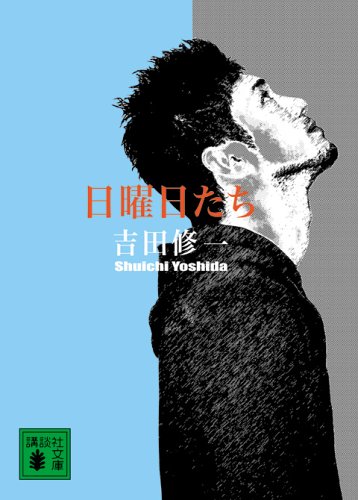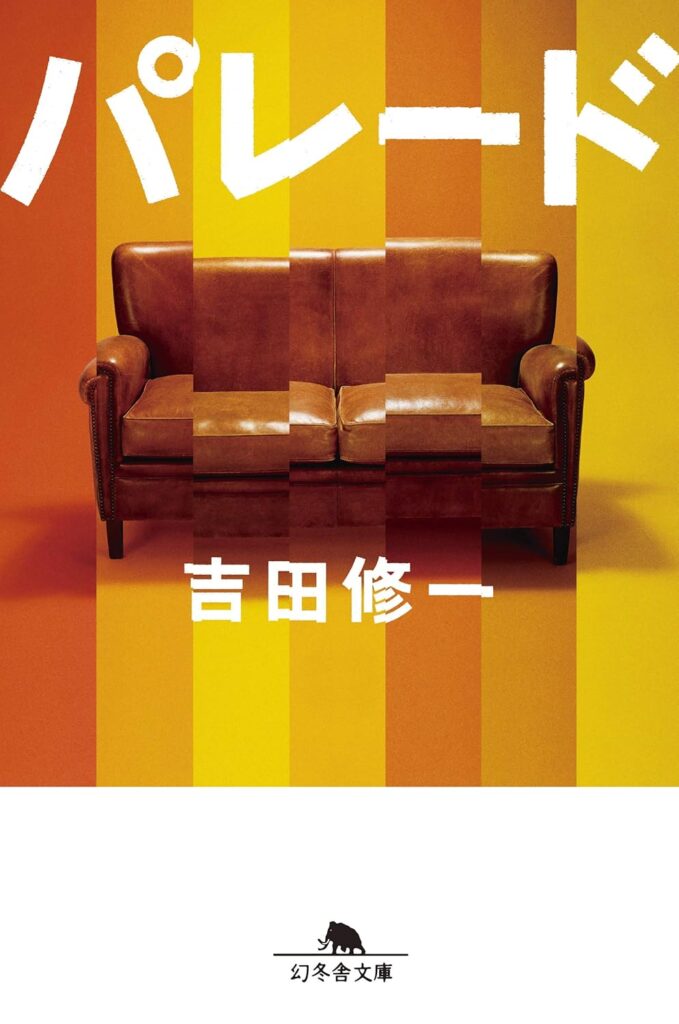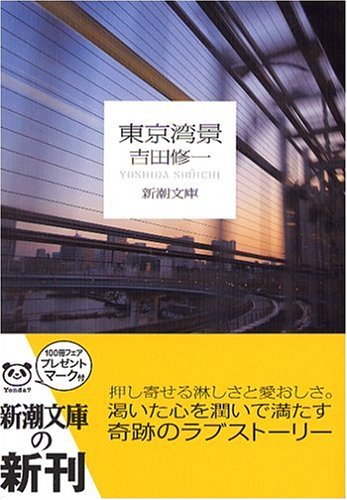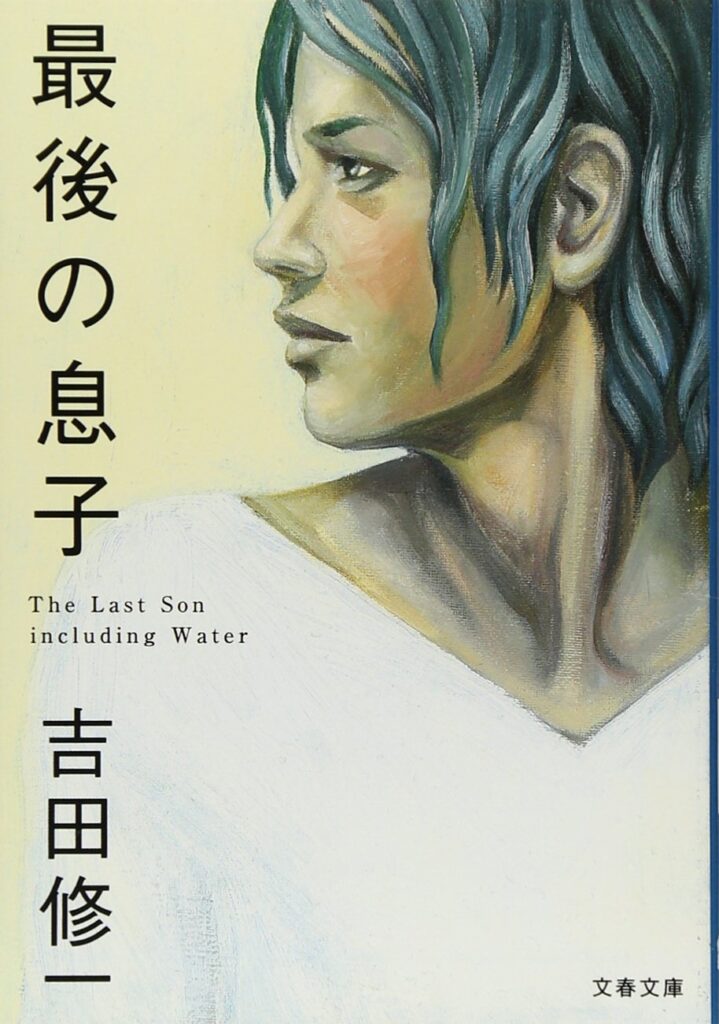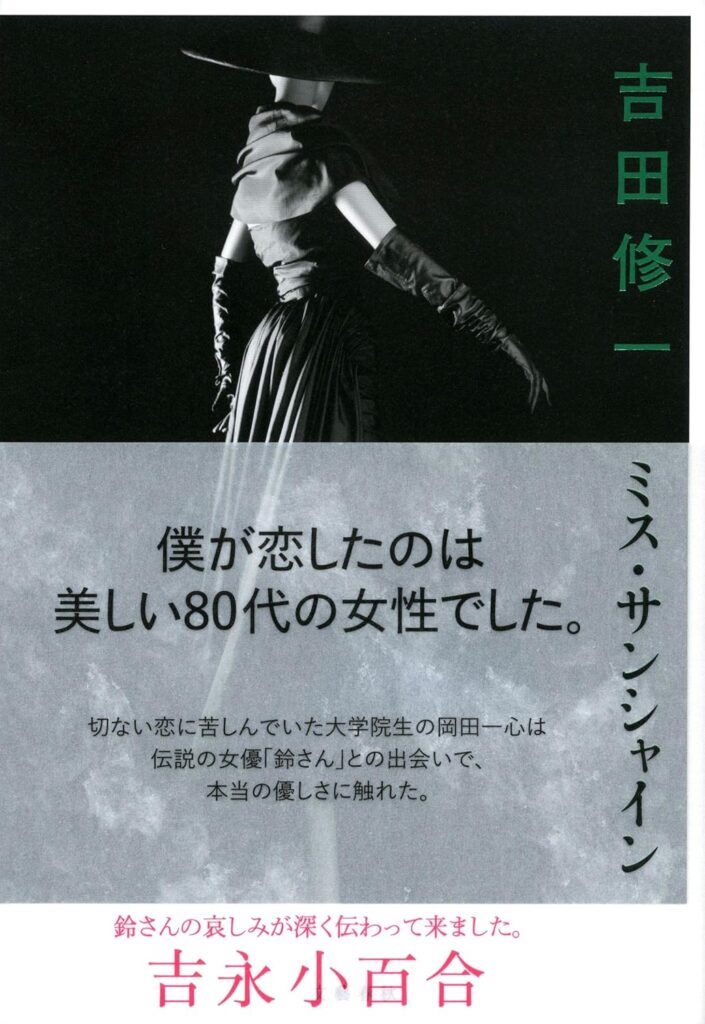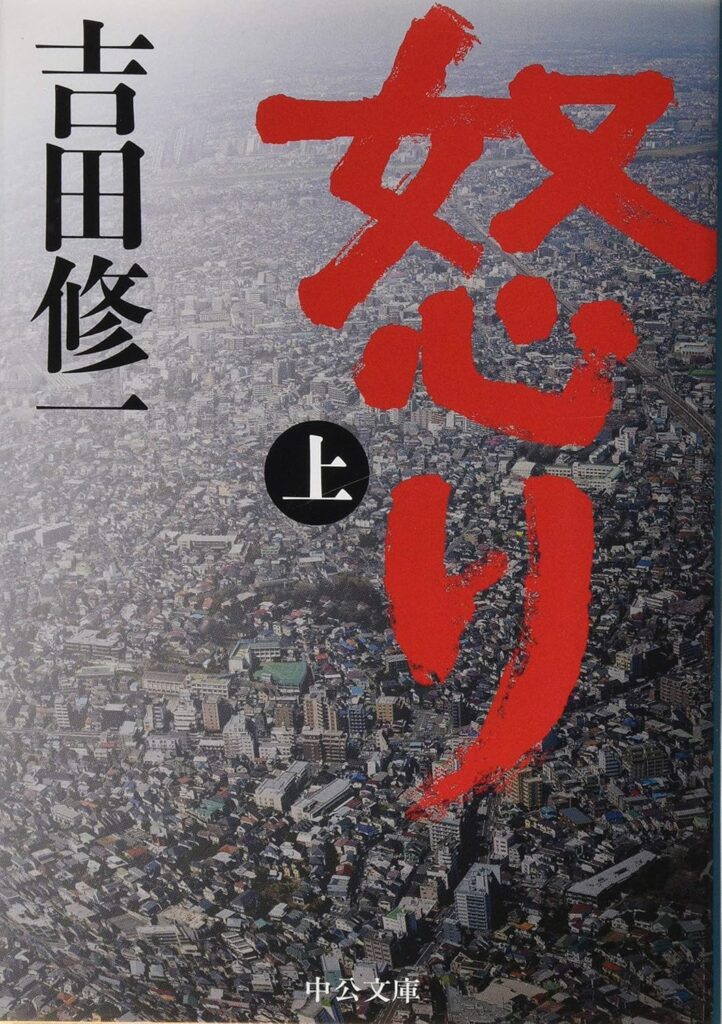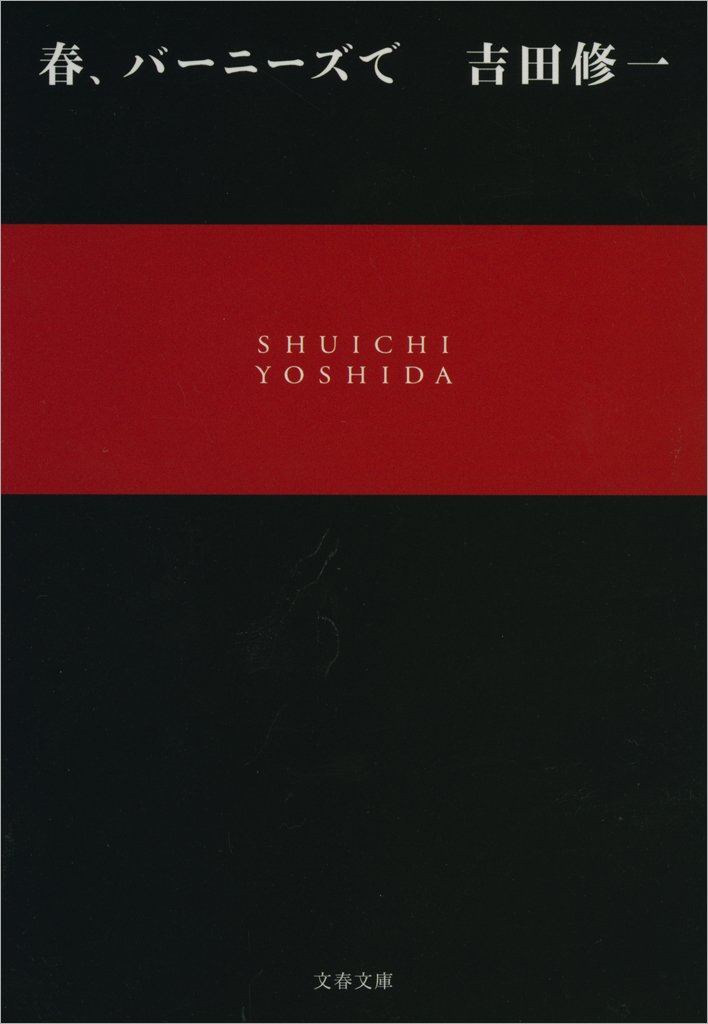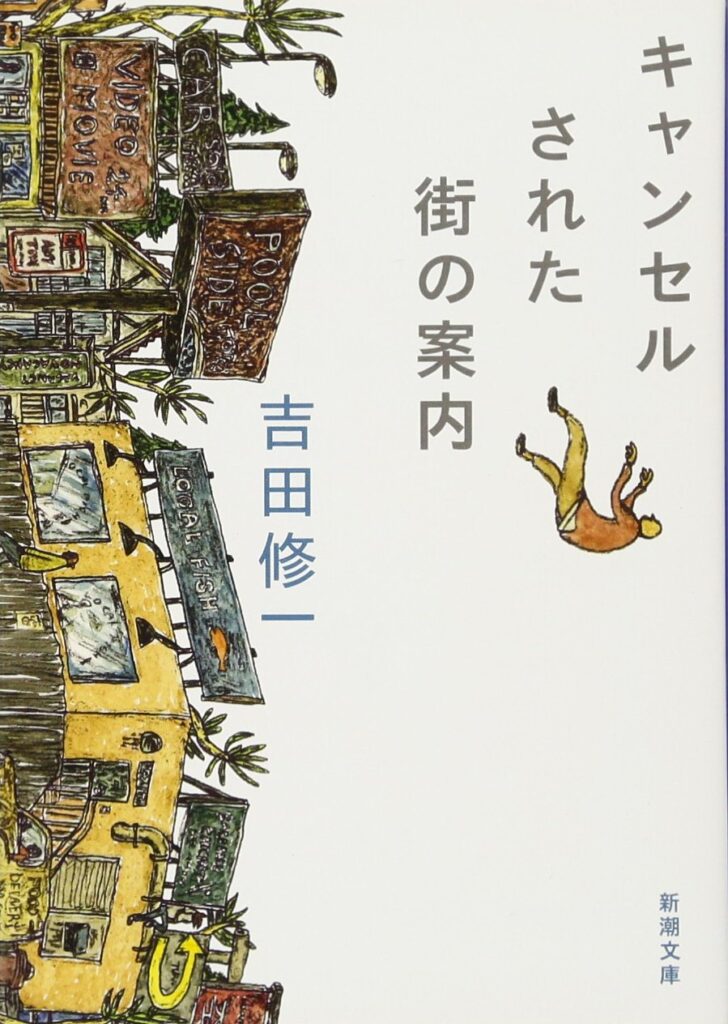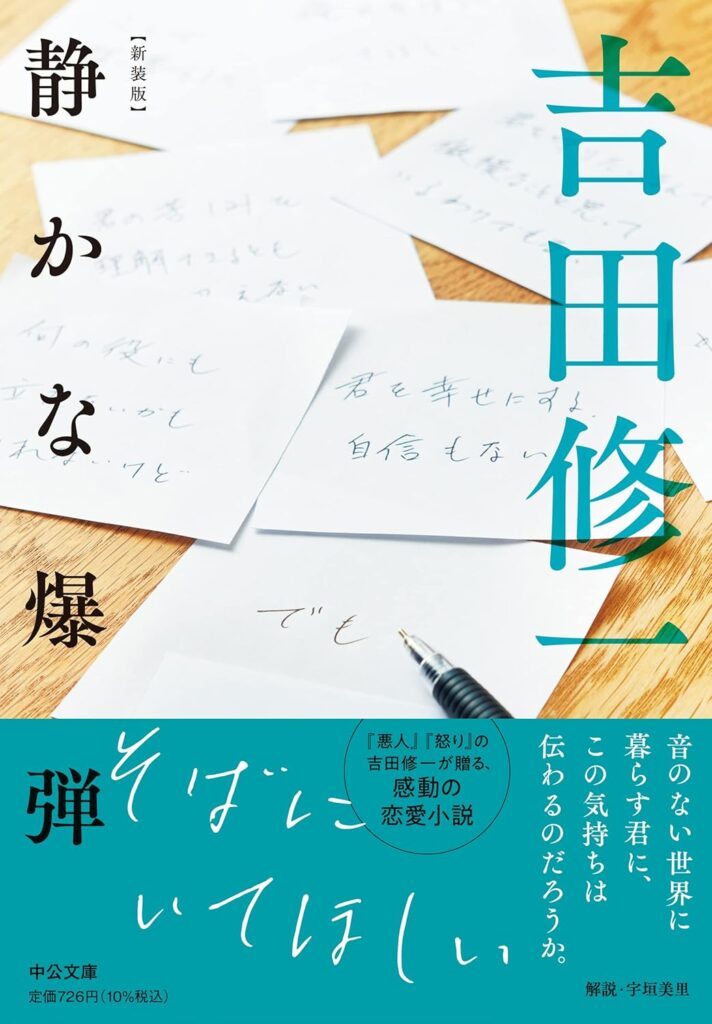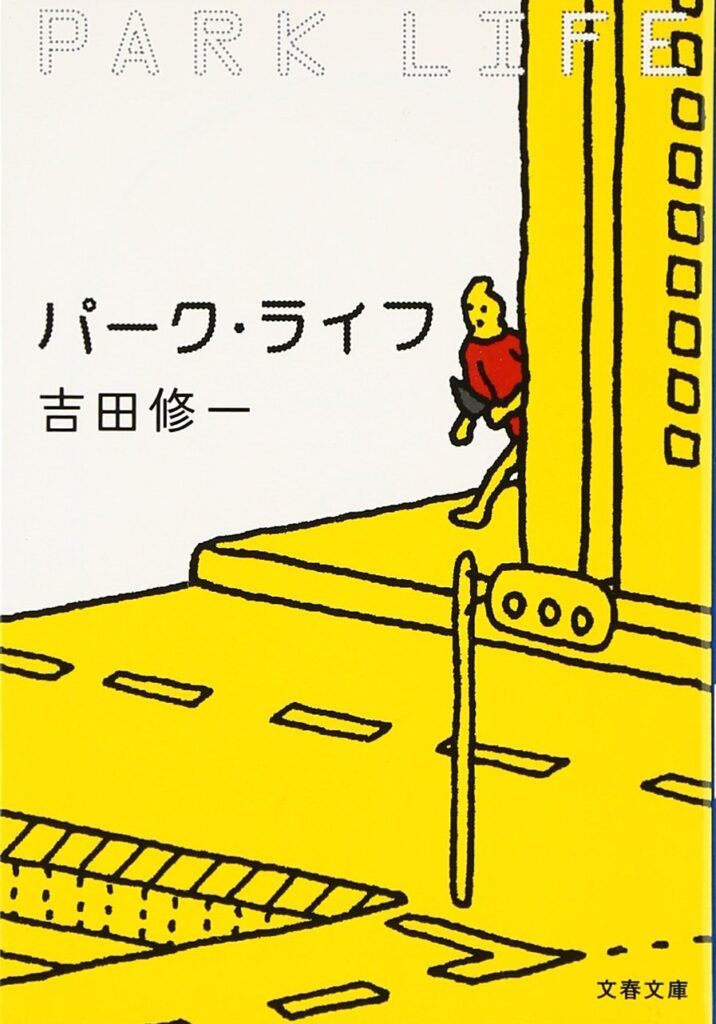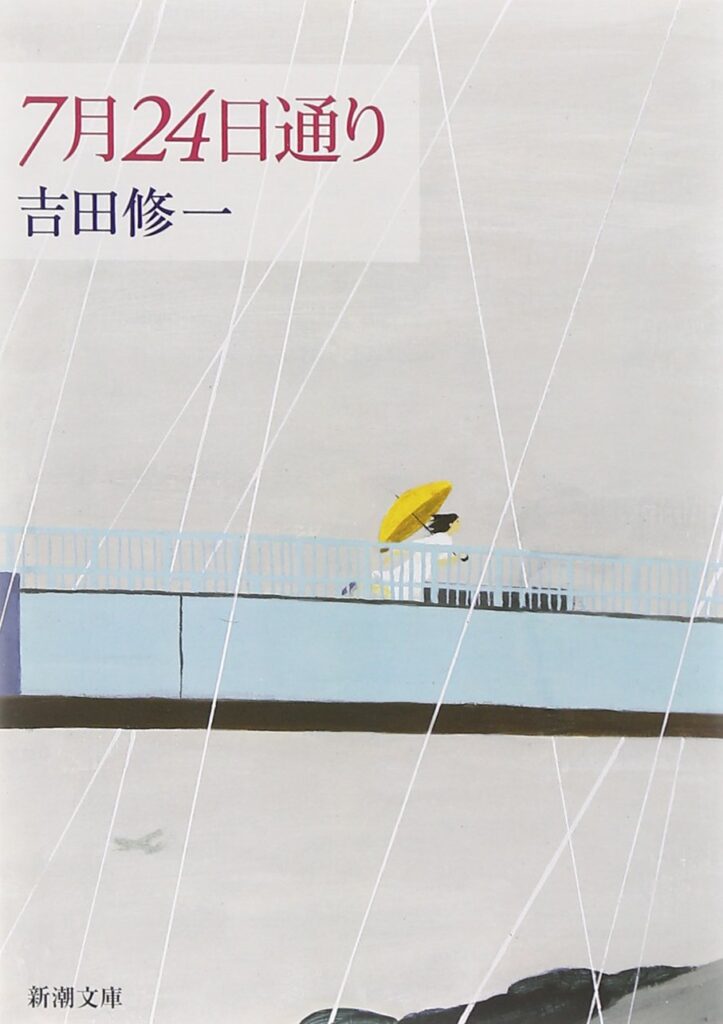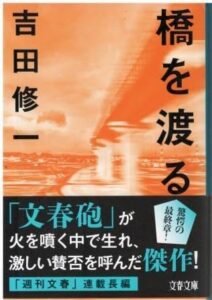 小説「橋を渡る」の物語の核心部分に触れつつ、その詳しいいきさつをご紹介します。後半では、この作品を読んで私が抱いた熱い思いの丈を、たっぷりとしたためましたので、どうぞ最後までお付き合いください。
小説「橋を渡る」の物語の核心部分に触れつつ、その詳しいいきさつをご紹介します。後半では、この作品を読んで私が抱いた熱い思いの丈を、たっぷりとしたためましたので、どうぞ最後までお付き合いください。
この物語は、一見するとバラバラな人生を送る複数の男女の日常と、その日常が思いもよらぬ形で交錯し、やがて時空を超えた壮大なドラマへと変貌していく様を描いています。読み進めるうちに、あなたはきっと、彼らの抱える葛藤や願い、そして未来への問いかけに心を揺さぶられることでしょう。
「橋を渡る」という題名が何を象徴しているのか、物語の登場人物たちは、どのような「橋」を渡ろうとしているのか。そんなことを考えながら読み解いていくのも、この作品の醍醐味の一つかもしれません。この記事が、あなたの作品理解の一助となれば幸いです。
物語の結末や重要な出来事にも触れていますので、まだ作品をお読みでない方や、ご自身で謎を解き明かしたい方は、どうかその点をご留意の上、読み進めていただければと思います。それでは、吉田修一さんが紡ぎ出す、「橋を渡る」の世界へご案内いたしましょう。
小説「橋を渡る」のあらすじ
物語の舞台は2014年の日本。ビール会社に勤める営業課長の新宮明良は、妻の歩美、そして海外出張中の両親に代わって預かっている甥の孝太郎と、穏やかながらもどこか満たされない日々を送っています。歩美が営むギャラリーでのトラブルや、孝太郎の予期せぬ妊娠騒動など、日常の中に小さな波風が立ち続けます。そんな中、明良の家の前に酒や米が置かれるという不可解な出来事が起こり、家族に静かな不安が広がります。
一方、都議会議員の妻である赤岩篤子は、夫の良からぬ噂や、都議会での女性議員への心ないヤジ問題に心を痛めていました。夫が旧友と頻繁に会うようになり、不正な金銭のやり取りをしていることを知った篤子は、苦悩の末、その事実を週刊誌に告発し、自ら命を絶つという悲劇的な選択をします。彼女の行動は、社会の闇と個人の正義感との間で揺れる魂の叫びのようでした。
ジャーナリストの里見謙一郎は、婚約者である薫子との結婚準備を進める中で、彼女の浮気を知ります。相手はかつて謙一郎が所属していた和太鼓サークルの団長で、薫子とは過去に関係があった人物でした。薫子から別れを告げられた謙一郎は、嫉妬と絶望から薫子を殺害してしまいます。逃亡の末に逮捕され、警察に送還される途中、謙一郎は突如として70年後の未来の日本へと時空を超えてしまいます。
未来の日本では、人間だけでなく、ロボットや「サイン」と呼ばれる遺伝子操作された人間が存在し、新たな社会階層が形成されていました。人間はサインを結婚相手とし、さらに人間同士でも恋愛を楽しむという、現代とは異なる価値観が支配する世界。そこで謙一郎は、人間の所有物とされながらも互いに惹かれ合い、逃亡しようとする二人のサインと出会います。
明良や篤子の子孫たちが生きるこの未来社会で、サインたちは人間からの解放と自由な恋愛を求めます。謙一郎は、彼らの逃亡を手助けしながら、自身も元の時代へ戻る方法を模索します。様々な困難を乗り越え、謙一郎は過去の世界への帰還を果たすのですが、彼が犯した罪が消えることはありませんでした。
物語は、現代の人間模様と、SF的な未来世界の出来事を交錯させながら、それぞれの登場人物が抱える孤独や愛情、そして社会の歪みを描き出します。過去と未来、異なる立場の人々が、見えない「橋」で繋がり合い、それぞれの運命を懸命に生きる姿が印象的です。
小説「橋を渡る」の長文感想(ネタバレあり)
吉田修一さんの手による「橋を渡る」という作品は、読み終えた後、まるで長い旅から帰ってきたかのような、不思議な感慨に包まれる物語でした。日常の細やかな描写から始まり、次第に読者の予想を裏切る展開を見せ、最終的には時空を超えた大きなうねりへと私たちを誘います。
まず心惹かれたのは、2014年の日本を生きる人々の、リアリティあふれる姿です。ビール会社の営業課長である新宮明良。彼の日常は、多くの現代人が共感できるような、ささやかな喜びと、漠然とした不安が混在するものでした。妻の歩美との関係、甥の孝太郎の成長を見守る眼差し、そして家の前に置かれる謎の贈り物。これらのエピソードは、家族という単位が抱える温かさと脆さを同時に描き出しているように感じました。特に、孝太郎の彼女の妊娠と、それに伴う若い二人の結婚への流れは、現代的な課題を提示しつつも、そこに一筋の希望のようなものを見出そうとする作者の視線を感じさせます。謎の贈り物が、実は孝太郎たちの未来を祝うものであったかもしれないという孝太郎自身の解釈は、不安の多い世の中だからこそ信じたい、ささやかな善意の表れなのかもしれません。
次に、都議会議員の妻、赤岩篤子の物語は、読んでいて胸が締め付けられる思いがしました。女性議員へのセクハラヤジ問題という、非常に現代的なテーマを背景に、夫の不正という許しがたい行為を知ってしまった篤子の葛藤は、計り知れないものがあったでしょう。彼女が最終的に選んだ道は、あまりにも痛ましく、そして衝撃的です。しかし、その行動の裏には、彼女なりの正義感と、歪んだ社会への抵抗があったのではないでしょうか。篤子の物語は、私たちに社会のあり方、そして個人の倫理とは何かを鋭く問いかけてきます。
そして、物語の大きな転換点となるのが、ジャーナリスト里見謙一郎のパートです。婚約者の薫子への愛と、その裏切りに対する激しい憎しみ。その果てに犯してしまった取り返しのつかない罪。彼が警察に送還される途中でタイムスリップするという展開は、まさに意表を突くものでした。この瞬間から、物語はSF的な色彩を帯び始め、読者は新たな世界へと引き込まれます。謙一郎が迷い込んだ70年後の日本は、ロボットや「サイン」と呼ばれる遺伝子操作された人間が存在する社会。この未来世界の描写は、現代社会が抱える格差や倫理問題を、より先鋭化させた形で映し出しているように思えました。
未来社会における「サイン」の存在は、特に深く考えさせられるものでした。人間によって生み出され、人間のために存在することを運命づけられたサインたち。彼らにも感情があり、愛があり、自由を求める心がある。しかし、その社会ではサイン同士の恋愛はタブーとされています。人間とサイン、そしてロボットという新たなヒエラルキーの中で、サインたちが抱える苦悩や抵抗は、人間とは何か、尊厳とは何かという根源的な問いを私たちに投げかけます。謙一郎が出会う、恋に落ちた二人のサインの逃避行は、まるで禁じられた愛の物語を見るようで、切なくも美しいものでした。
謙一郎がこの未来世界で果たす役割も興味深い点です。過去から来た彼は、ある意味で異物でありながら、サインたちの逃亡を手助けし、彼らの運命に深く関わっていきます。そして、彼自身もまた、元の時代に戻るための「橋」を探し求めます。この時空を超えた旅は、彼にとって罪からの逃避であったのかもしれませんが、同時に新たな出会いや経験を通して、彼自身の内面にも何らかの変化をもたらしたのではないでしょうか。
「橋を渡る」という題名が持つ意味についても、物語を読み進めるうちに様々な解釈が浮かんできます。それは、過去と未来を繋ぐ時間の橋かもしれませんし、人と人との心を繋ぐ感情の橋かもしれません。あるいは、異なる種族や階層の間に横たわる断絶を乗り越えようとする意志の象徴とも取れます。登場人物たちは皆、何かしらの「橋」を渡ろうともがき、時に挫折し、それでも前に進もうとします。
物語の構成についても触れておきたいです。複数の視点から描かれる現代の物語と、謙一郎が体験する未来の物語。これらがどのように結びついていくのか、最初は戸惑う部分もありました。特に、参考情報にもあったように、2014年の日本の描写が詳細で、それが未来のSF展開とどう繋がるのか、伏線として機能しているのか、読み解くのに時間を要する部分があったのは事実です。しかし、それこそが吉田修一さんの巧みさなのかもしれません。一見バラバラに見えるエピソードや登場人物たちが、物語の終盤に向けて収斂していく様は、見事というほかありません。
特に、未来社会に登場する人間たちが、明良や篤子の子孫であるという設定は、過去の出来事が未来に影響を与え、歴史は繋がっているのだというメッセージを感じさせます。篤子の悲劇的な選択が、未来社会のあり方にどのような影響を及ぼしたのか、あるいは明良のささやかな日常が、未来の子孫たちにどのような形で受け継がれているのか。そうしたことを想像するのも、この物語の楽しみ方の一つでしょう。
SF的な要素については、確かに専門的な知識があればより深く楽しめるのかもしれませんが、必ずしもそうでなくても、物語の核心は理解できると感じました。未来社会のテクノロジーや社会システムよりも、そこで生きる人間やサインたちの感情の機微、葛藤に焦点が当てられているからです。ロボットや遺伝子操作といったテーマは、現代でも議論される倫理的な問題を内包しており、それらが70年後の世界でどのように展開しているのかを想像するのは、非常に刺激的な体験でした。
謙一郎が最終的に過去に戻ることができたとしても、彼が犯した罪は消えません。この結末は、ある種の厳しさとともに、現実の重みを感じさせます。タイムスリップという非現実的な出来事を経験したとしても、人間は自らの過去の行いから完全に逃れることはできないのかもしれません。しかし、彼が未来で見たもの、経験したことは、彼の残りの人生に何らかの意味を与えるのではないでしょうか。
この物語は、単なるエンターテイメントとして消費されるだけでなく、読者一人ひとりに、現代社会のあり方、未来への展望、そして人間としてどう生きるべきかという、普遍的で重要な問いを投げかけているように感じます。それぞれの登場人物が抱える問題は、形は違えど、私たちが日常で直面する可能性のある葛藤や選択とどこかで繋がっているのではないでしょうか。
明良のパートで描かれる家族の日常と、その中に潜む小さな亀裂や不穏な空気は、現代の家族が抱える複雑さを象徴しているようです。孝太郎の若さゆえの過ちと、それを受け止めようとする周囲の大人たちの姿は、世代間の繋がりや断絶、そして再生への微かな希望を感じさせます。謎の贈り物が誰からのものだったのか、明確な答えは示されませんが、それもまた、人生における解けない謎や、理屈では説明できない人の善意のようなものを暗示しているのかもしれません。
篤子のパートは、社会の不正義に対する個人の無力さと、それでも声を上げることの重要性を突きつけてきます。彼女の選択は極端であり、決して肯定されるものではありませんが、そこに至るまでの彼女の孤独や絶望を思うと、胸が痛みます。彼女の告発が、その後の社会にどのような影響を与えたのか、物語は多くを語りませんが、読者の想像に委ねられている部分もまた、この作品の深みなのでしょう。
謙一郎のパートは、愛と憎しみの深淵を覗かせるものです。愛するがゆえの執着、裏切られたことへの絶望的な怒り。彼が犯した罪は許されるものではありませんが、その人間的な弱さには、ある種の共感を覚えてしまう部分もありました。彼がタイムスリップという特異な体験を通して、自らの罪と向き合い、何を見出すのか。未来社会でのサインたちとの出会いは、彼にとって一種の贖罪の機会だったのかもしれません。
吉田修一さんの文章は、淡々としていながらも、登場人物たちの内面を鋭く捉え、読者の心に深く染み入ってきます。情景描写も巧みで、2014年の日本の空気感や、70年後の未来社会の情景が目に浮かぶようでした。特に、未来社会のディテールは、単なる空想ではなく、現代社会の延長線上にあるものとして描かれており、リアリティを感じさせます。
この物語を読み終えて、改めて「橋を渡る」という言葉の重みを感じています。それは、困難を乗り越えること、新しい世界へ踏み出すこと、過去と決別すること、あるいは誰かと心を通わせることなど、様々な意味合いを持つのでしょう。登場人物たちは、それぞれの「橋」を必死に渡ろうとしています。その姿は、不器用で、痛々しく、しかしどこか愛おしい。彼らの物語は、私たち自身の人生における様々な「橋」について、深く考えさせてくれるものでした。
まとめ
小説「橋を渡る」は、現代に生きる私たちの日常と、その先に待ち受けるかもしれない未来の姿を、鮮やかに描き出した作品です。複数の登場人物の視点から語られる物語は、やがて一つの大きな流れとなり、読者を時空を超えた思索の旅へと誘います。
それぞれの登場人物が抱える悩みや葛藤、そして彼らが下す決断は、私たち自身の人生や社会のあり方について、深く考えるきっかけを与えてくれます。愛、裏切り、正義、絶望、そして希望。様々な感情が交錯する中で、彼らがどのように「橋を渡る」のか、その行方から目が離せません。
SF的な要素も巧みに取り入れられており、未来社会の描写は刺激的でありながらも、現代社会が抱える問題の延長線上にあるものとして、強いリアリティをもって迫ってきます。遺伝子操作された人間「サイン」の存在は、人間とは何か、尊厳とは何かという根源的な問いを私たちに投げかけます。
吉田修一さんならではの繊細な筆致で描かれる人間ドラマは、読者の心に深く残り、読み終えた後も長く余韻に浸ることができるでしょう。この物語が問いかけるものを受け止め、自分なりに考えてみる。そんな読書体験を、ぜひ多くの方に味わっていただきたいと願っています。

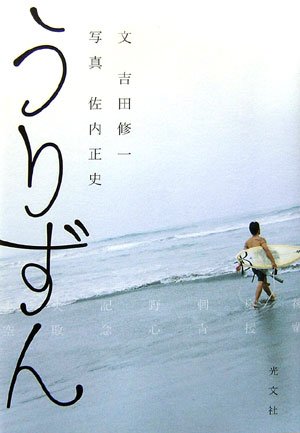
-728x1024.jpg)