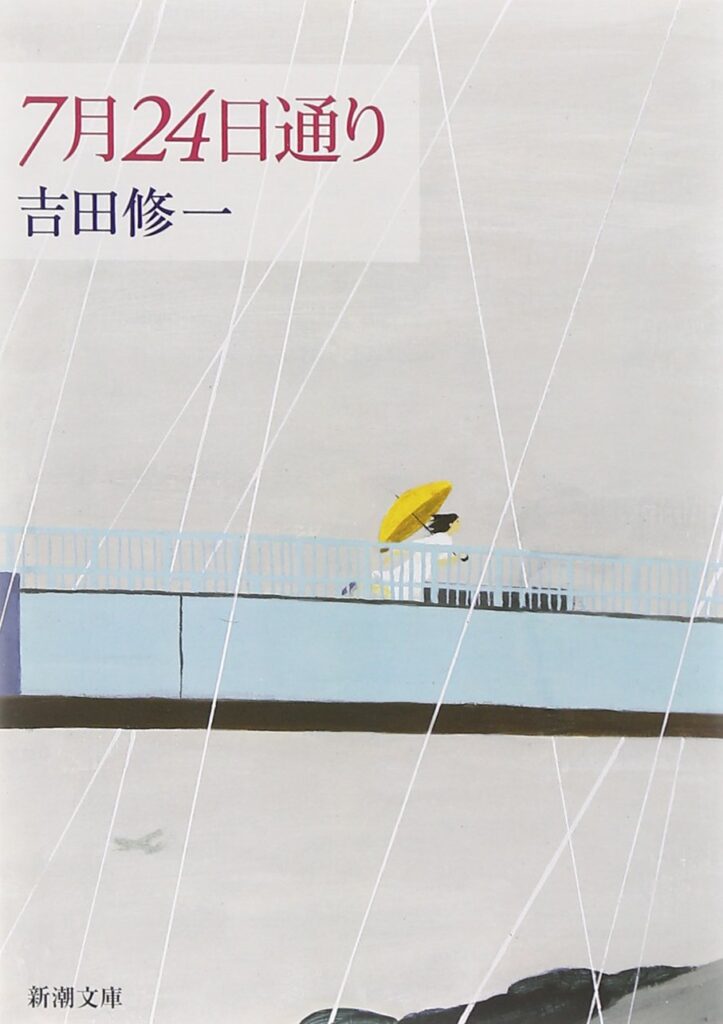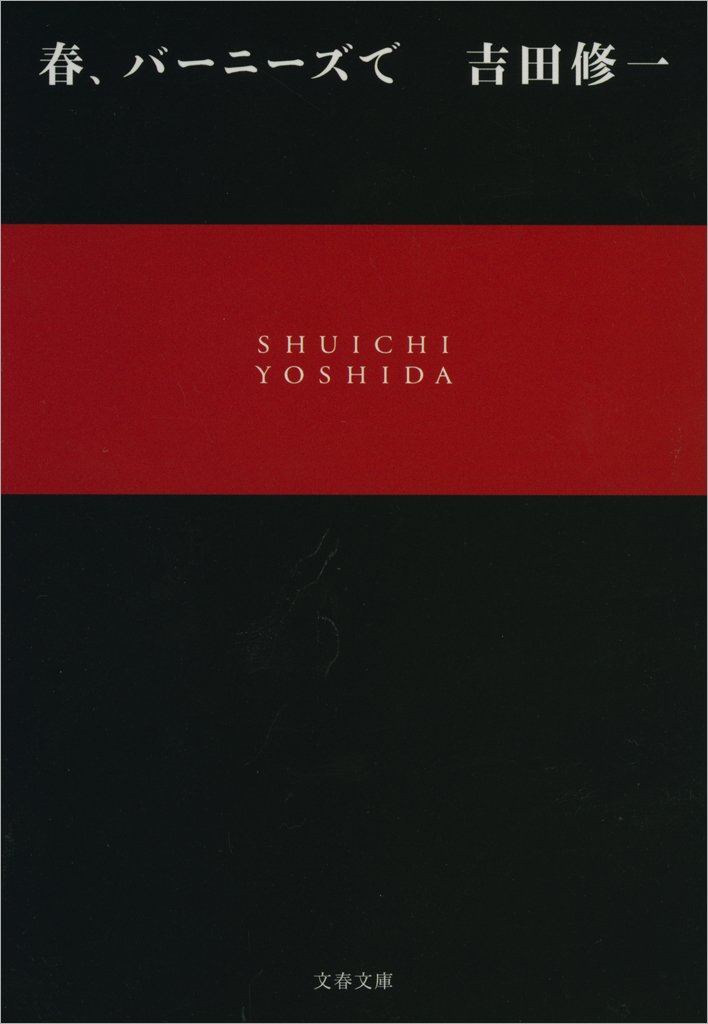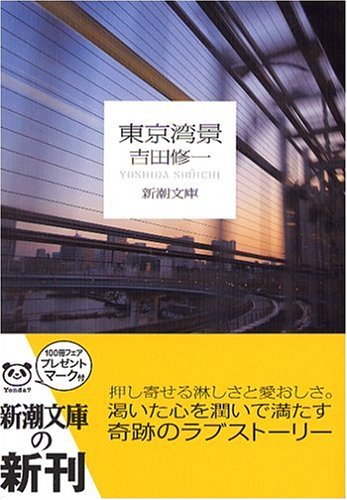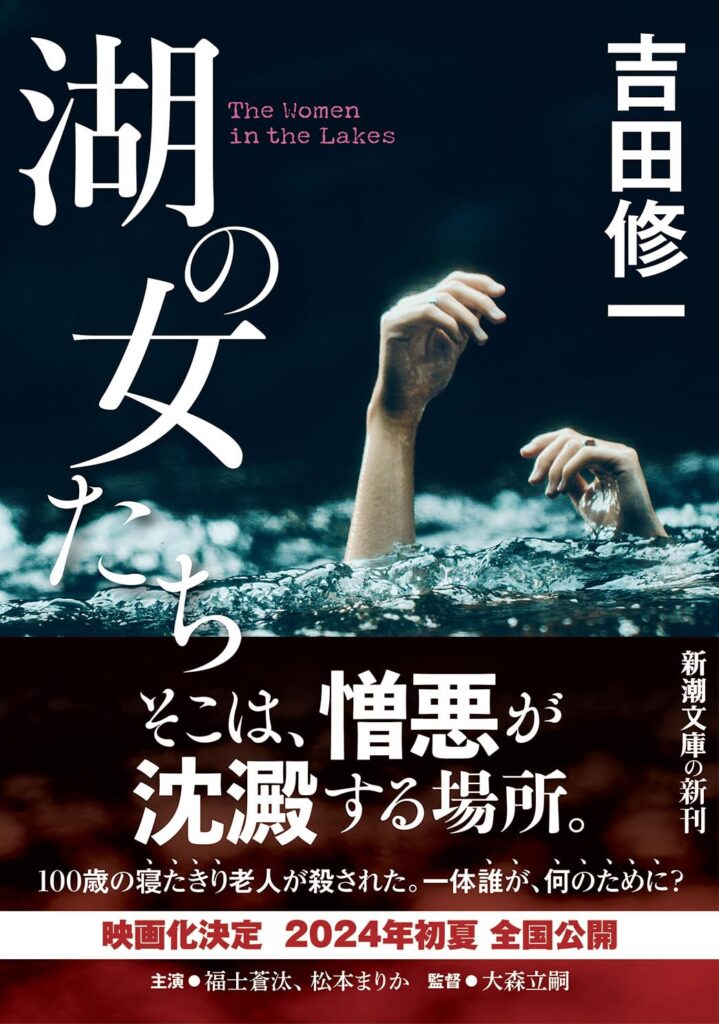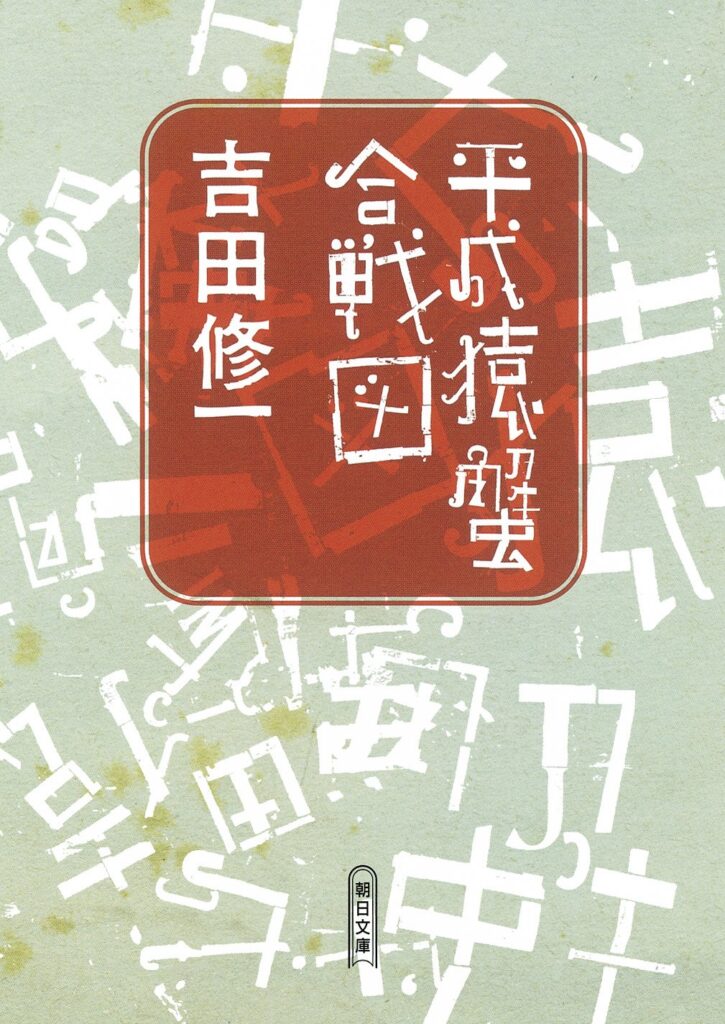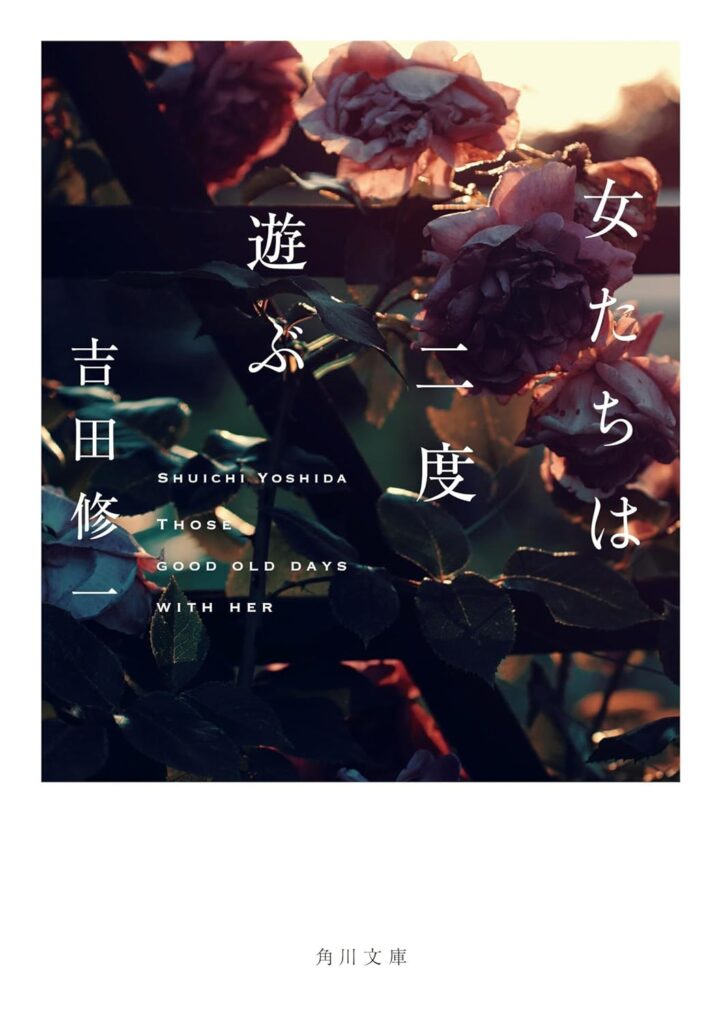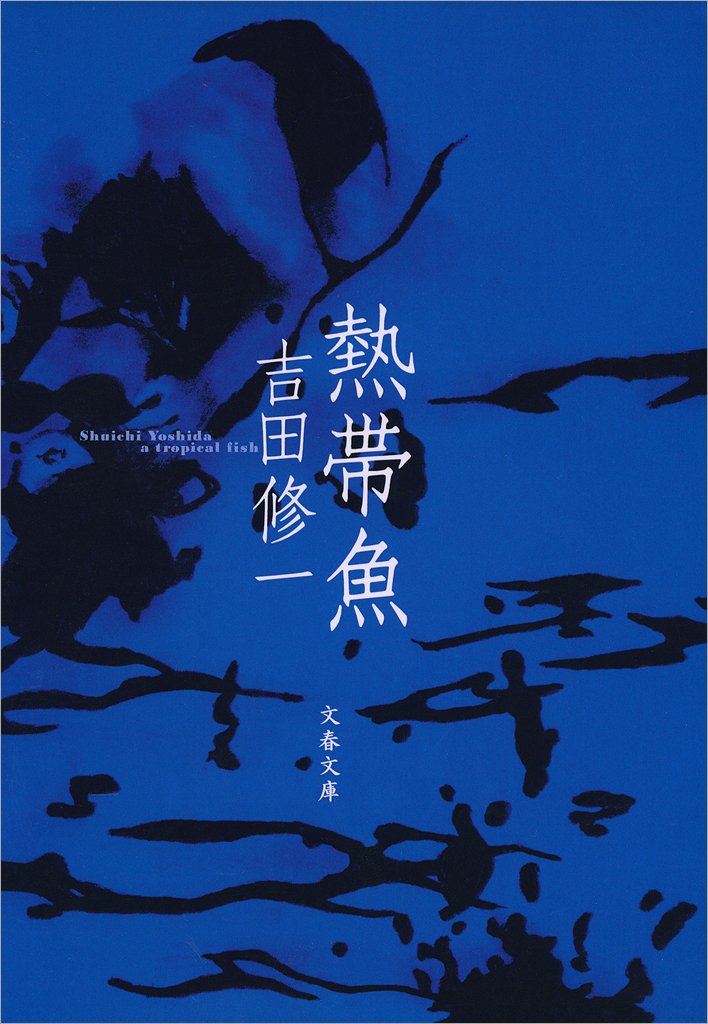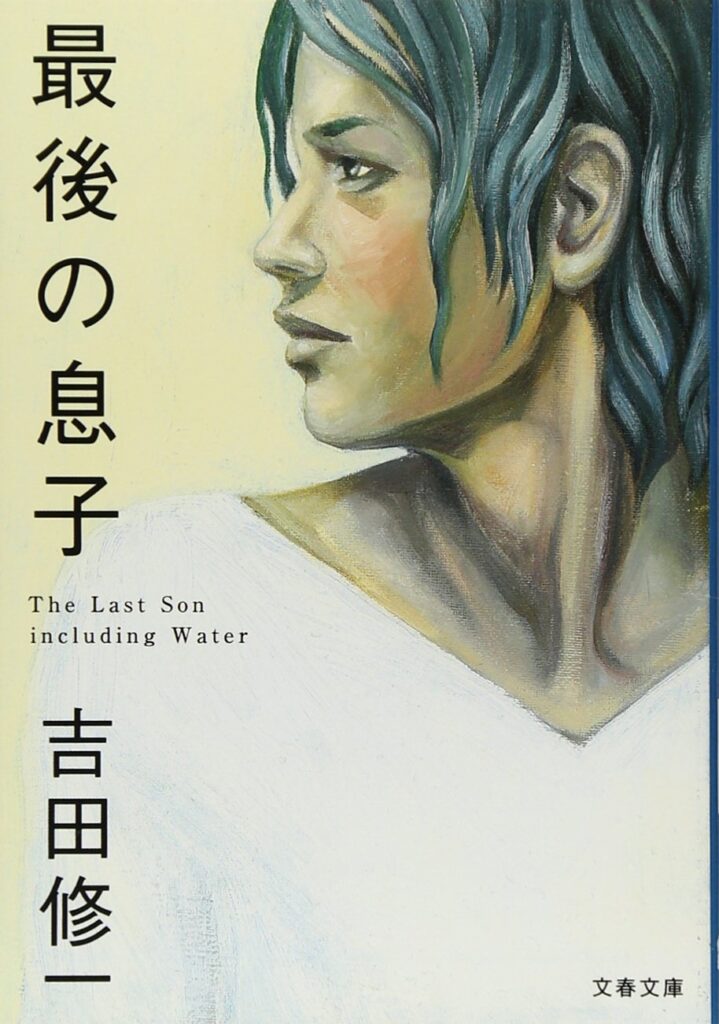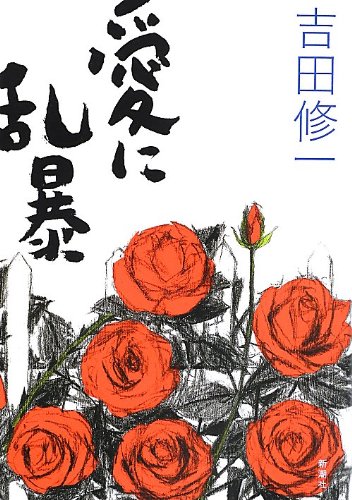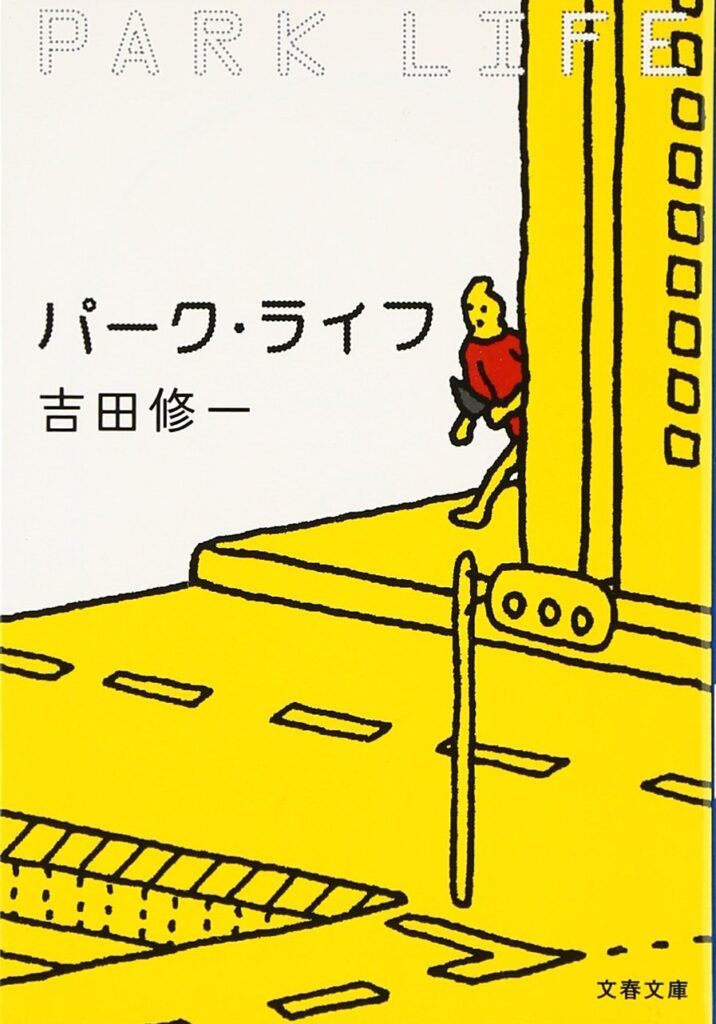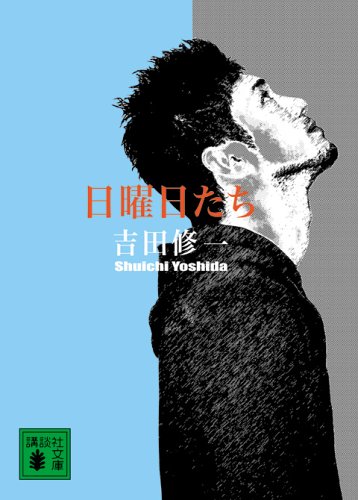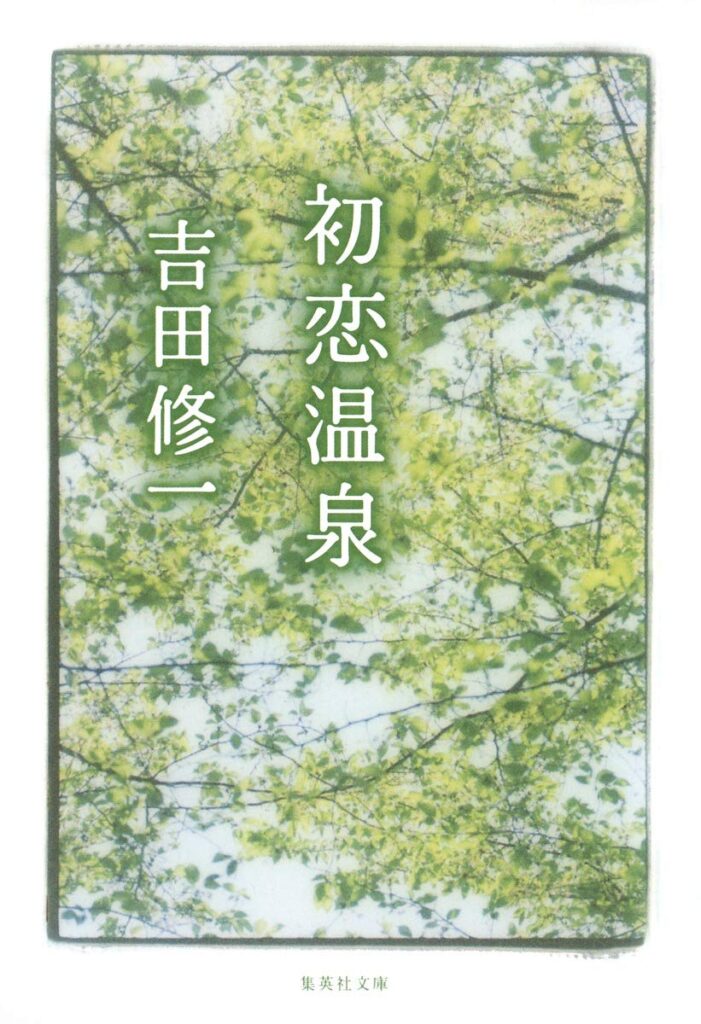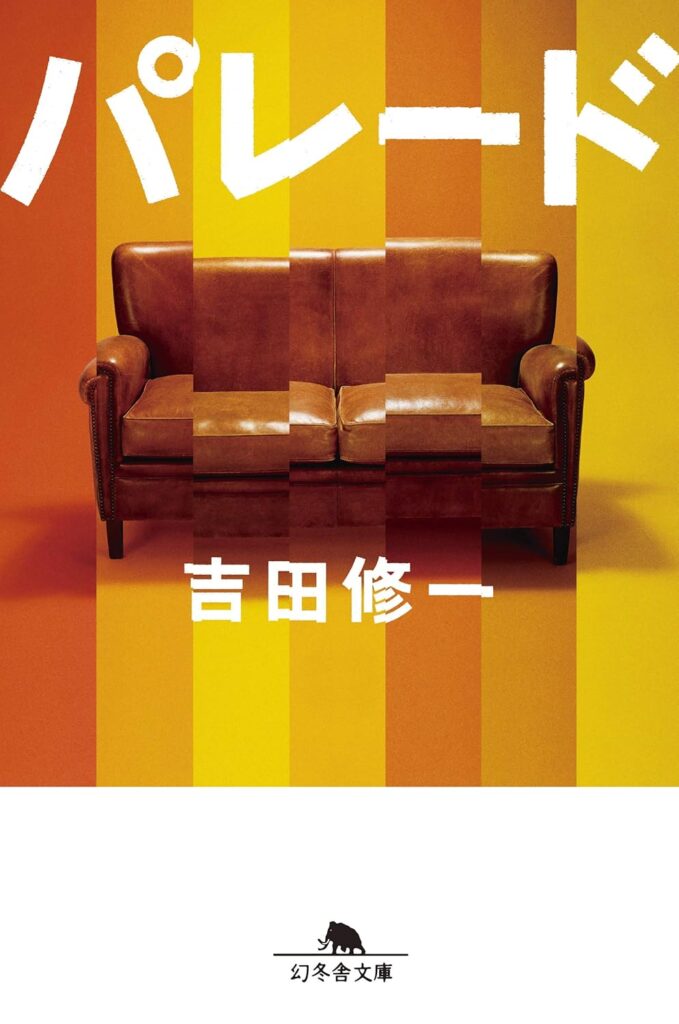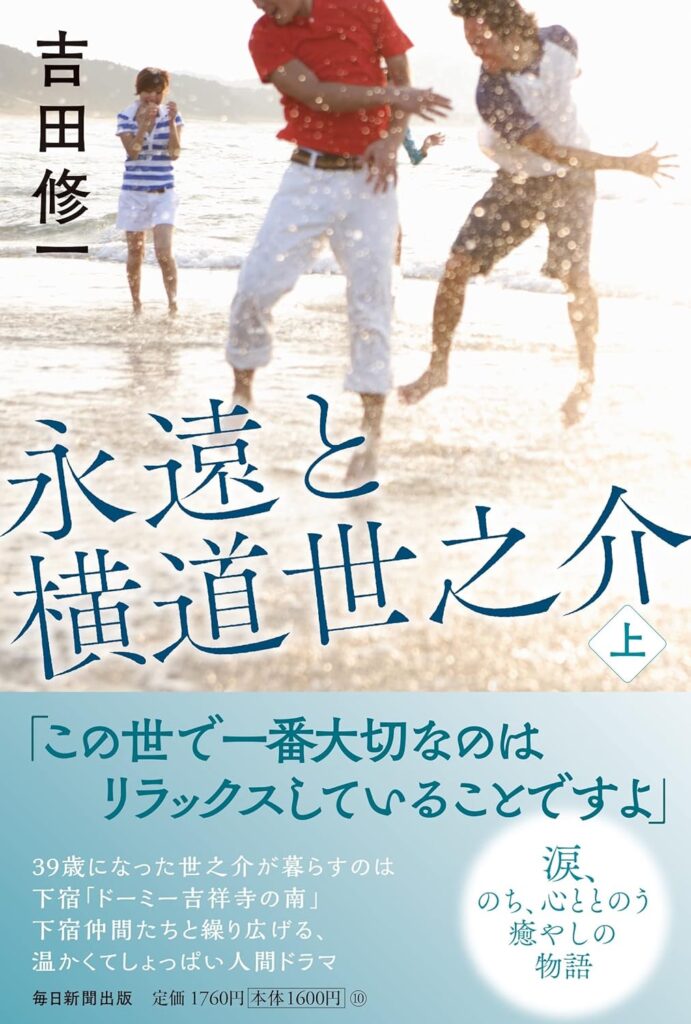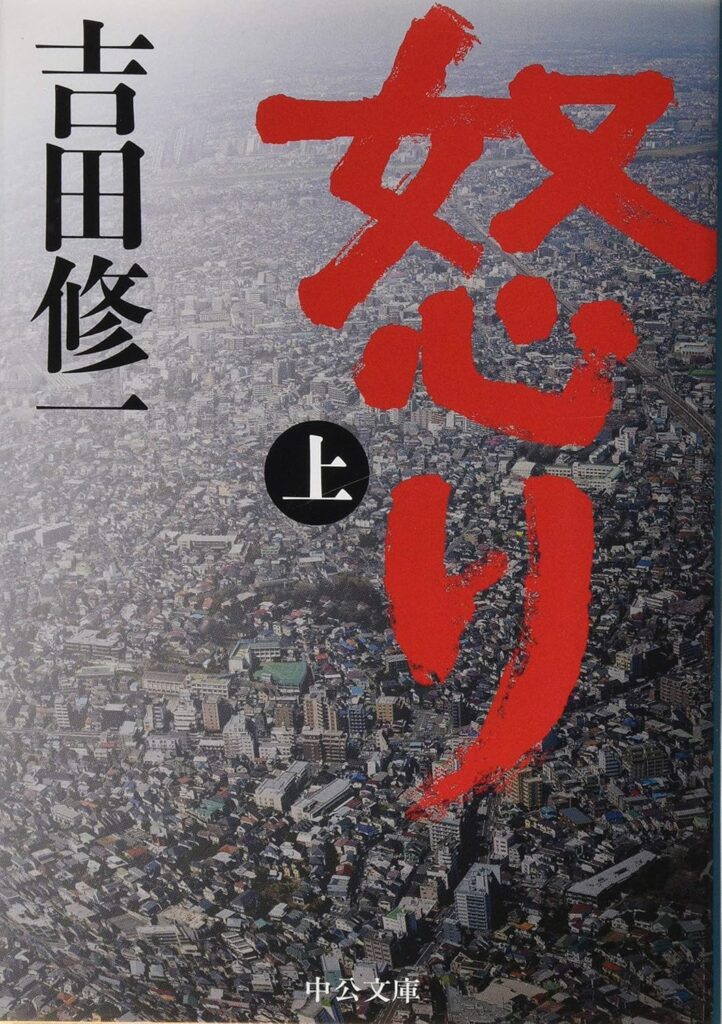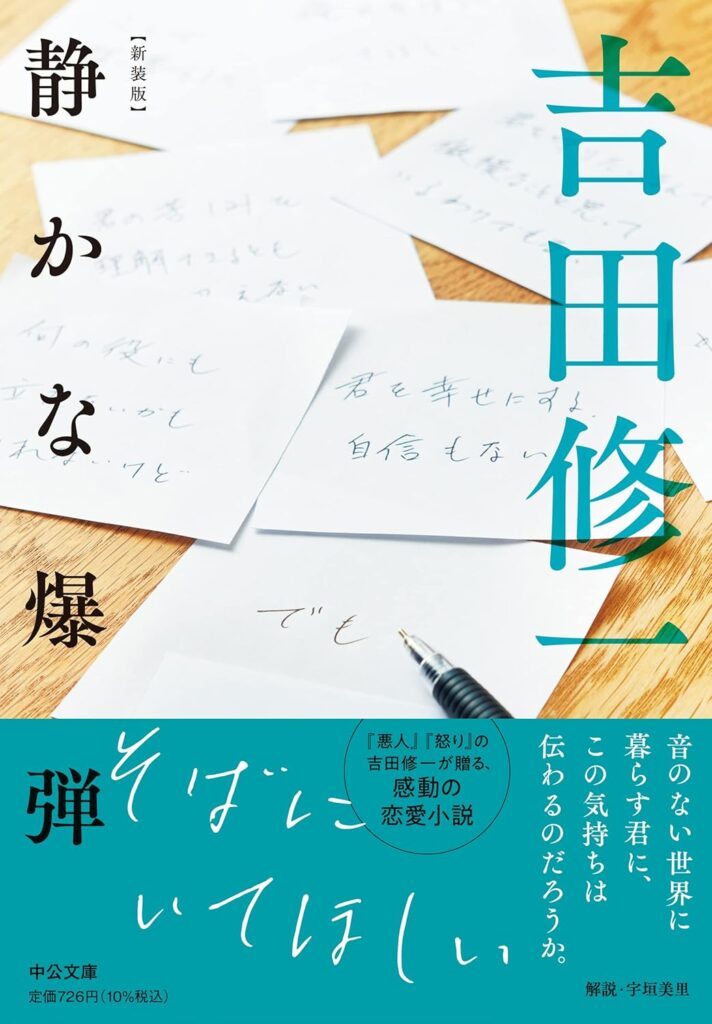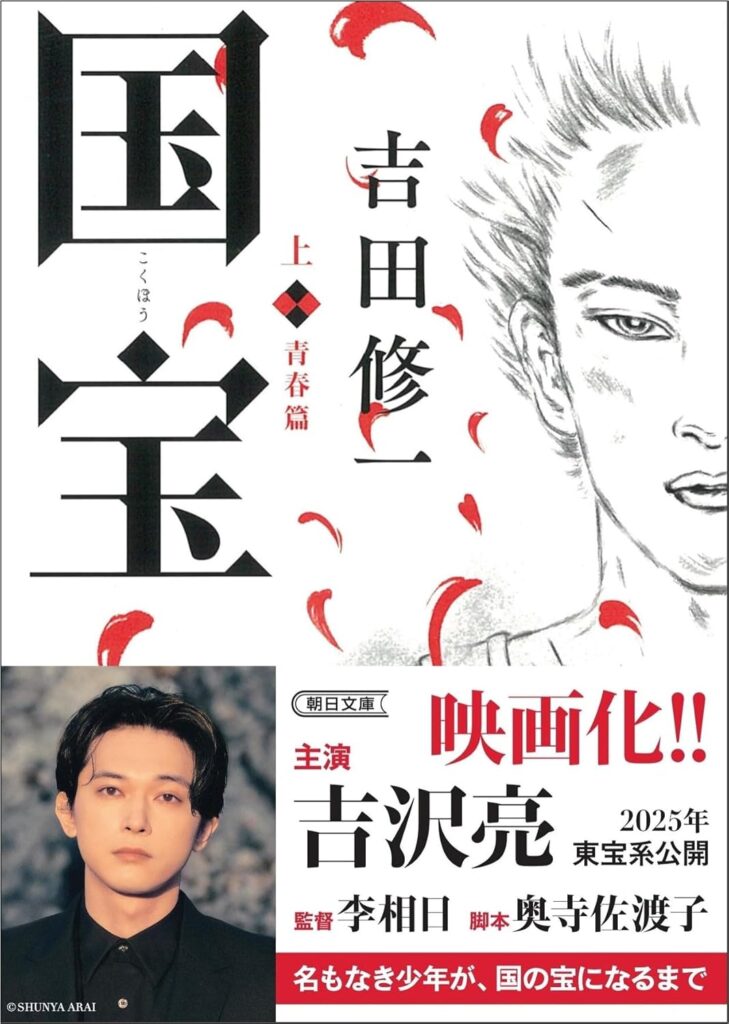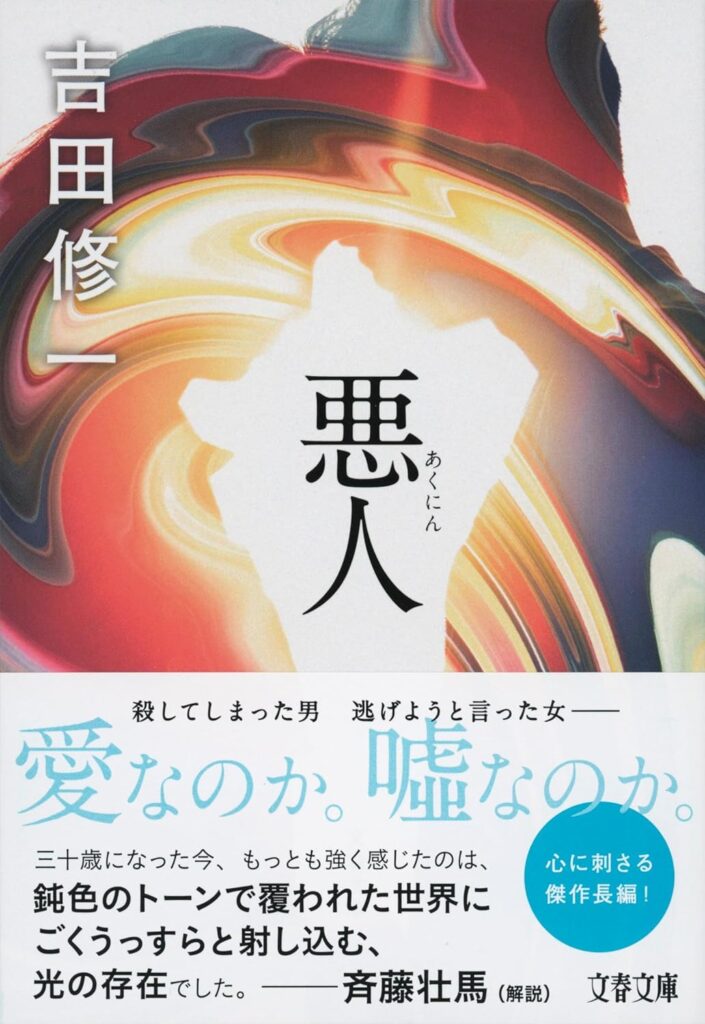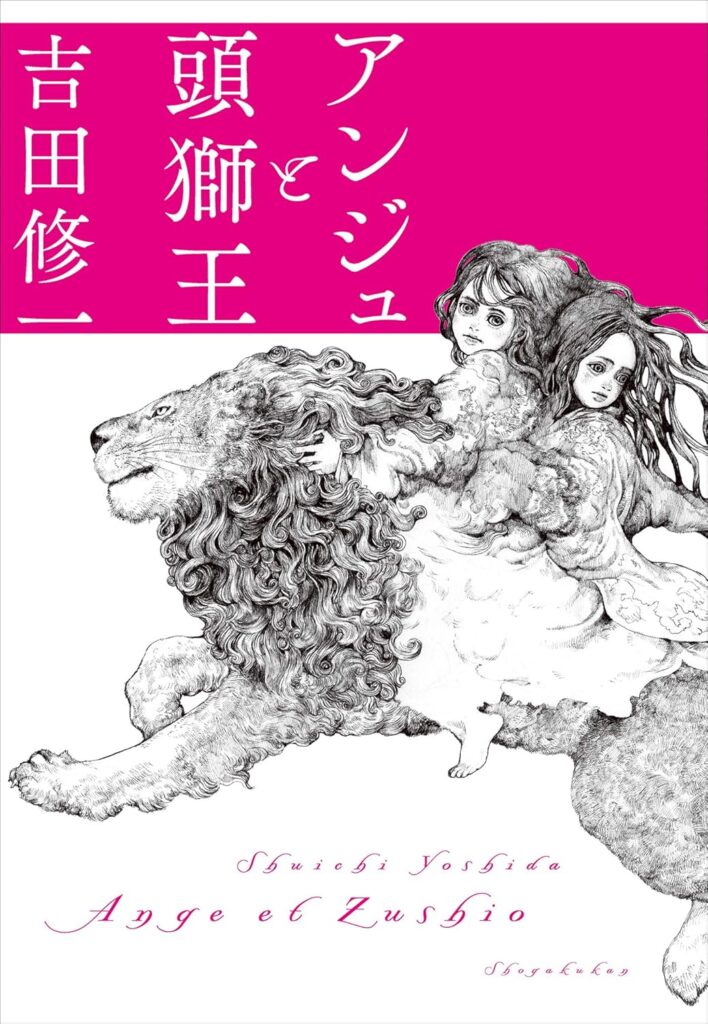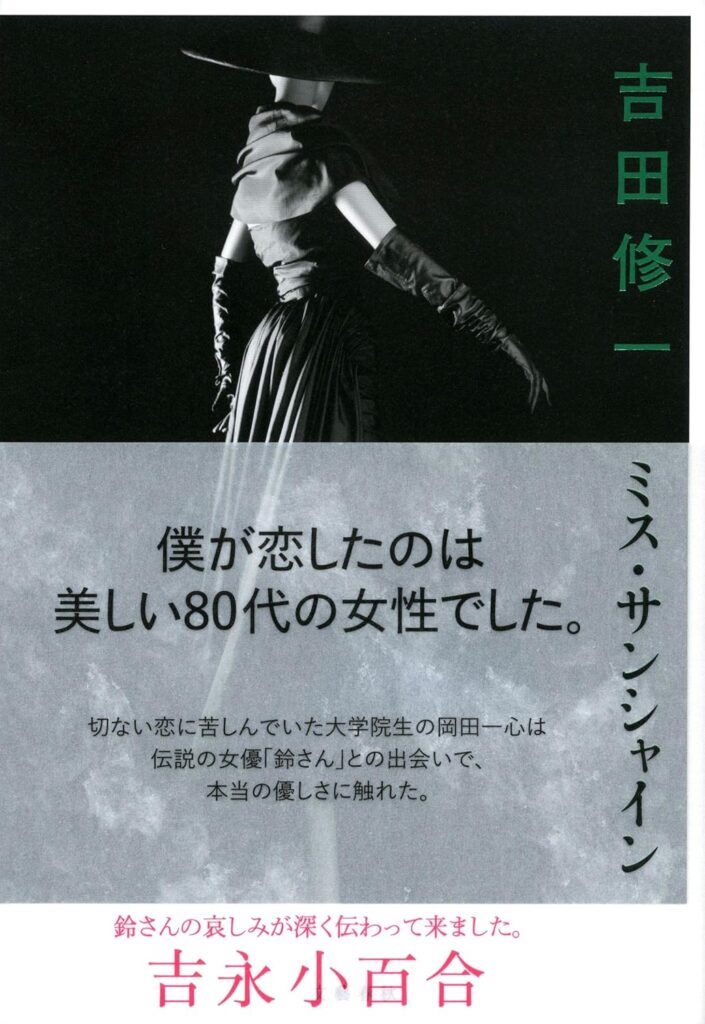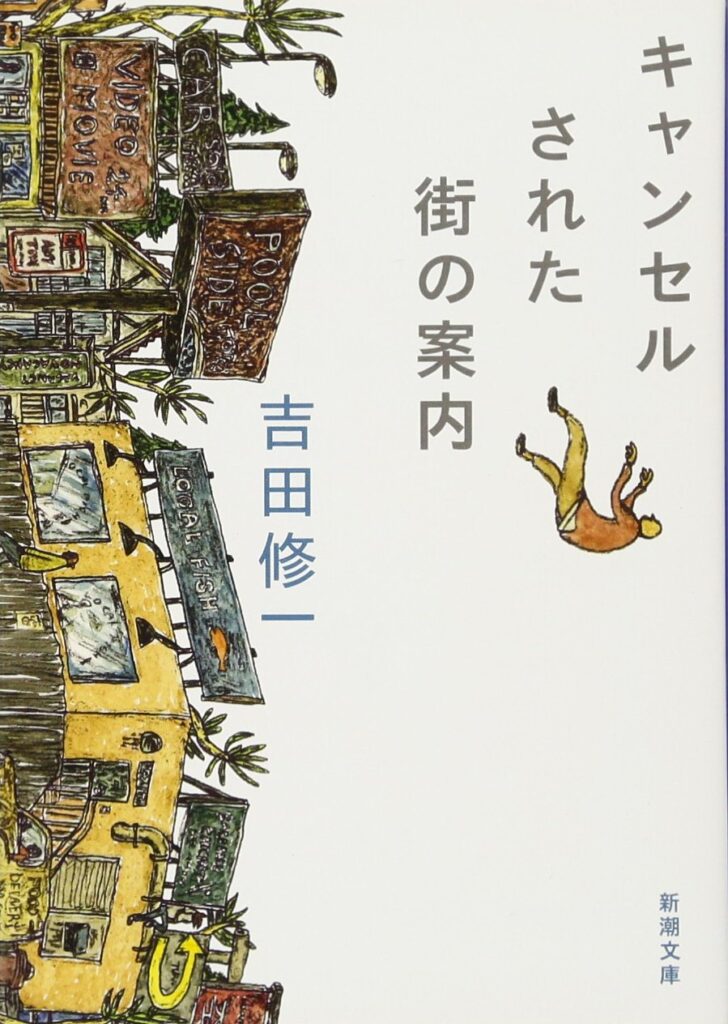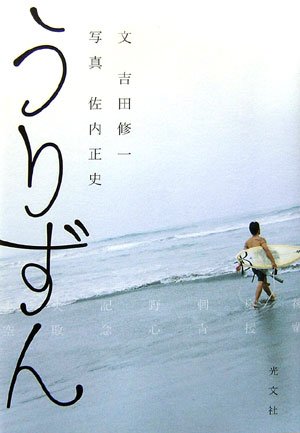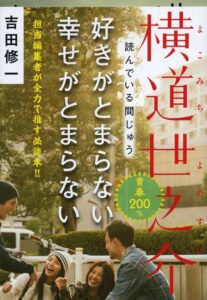 小説「横道世之介」のあらすじを詳細に、物語の核心に触れる部分も含めてご紹介します。また、この作品を読んだ私の心に深く残ったことなどを、たっぷりとしたためた文章も書いていますので、どうぞお付き合いください。
小説「横道世之介」のあらすじを詳細に、物語の核心に触れる部分も含めてご紹介します。また、この作品を読んだ私の心に深く残ったことなどを、たっぷりとしたためた文章も書いていますので、どうぞお付き合いください。
この物語の主人公、横道世之介は、なんだか憎めない、どこにでもいそうな青年です。彼の周りには自然と人が集まり、彼と関わった人々の記憶には、温かな光が灯るように彼の思い出が刻まれていきます。1980年代という、少し昔の日本の空気感の中で繰り広げられる彼の青春時代は、読む私たちにとってもどこか懐かしく、愛おしい気持ちにさせてくれるのではないでしょうか。
物語は、世之介の大学時代と、それから時を経た現代とが交互に描かれ、彼という存在が周囲にどのような影響を与えていったのかを、パズルのピースをはめるように見せてくれます。一見、平凡に見える彼の日常と、その中に散りばめられた出来事が、登場人物たちの未来、そして私たちの心に静かな感動を呼び起こすのです。
この記事では、そんな「横道世之介」の物語の詳しい流れと、私が感じた作品の奥深い魅力、そして世之介という青年が私たちに残してくれたものについて、心を込めてお伝えしたいと思います。読み終えた後、きっとあなたも世之介と出会えて良かった、と感じるはずです。
小説「横道世之介」のあらすじ
1980年代、横道世之介は長崎の港町から大学進学のために東京へやってきます。人の頼みを断れないお人好しで、どこか天然なところもある彼は、法政大学経営学部に入学し、東久留米のアパートで新生活をスタートさせました。入学式で隣り合わせた倉持一平とはすぐに打ち解け、倉持がひょんなことから泣かせてしまった同級生の阿久津唯とも、いつしか大切な友人となっていきます。
世之介と倉持は、流れでサンバサークルに入部することになり、そこで出会った先輩の紹介で、赤坂の一流ホテルでルームサービスのアルバイトを始めます。華やかな世界を垣間見ながらも、世之介はマイペースに日々を過ごします。そんな中、写真家の室田と出会い、カメラに興味を持つようになります。このささやかな趣味が、後の彼の人生を大きく左右することになるとは、この時は誰も知りません。
ある日、友人むつみの計らいで参加したダブルデートで、世之介は与謝野祥子というお嬢様と出会います。裕福な家庭で育ち、少し浮世離れしたところのある祥子でしたが、裏表のない天真爛漫な性格で、世之介の屈託のない言動にも大爆笑するような女性でした。二人はお互いに惹かれ合い、世之介の故郷である長崎へ一緒に旅行に行くなど、忘れられない思い出を重ねていきます。大学一年生の冬、二人は恋人同士になりました。
しかし、順風満帆に見えた二人の関係も、大学二年の夏、些細な喧嘩がきっかけで終わりを迎えます。その後、二人が再会することはありませんでした。世之介は他にも、年上でミステリアスな魅力を持つ片瀬千春に憧れたり、個性的な友人たちとの交流を深めたりしながら、かけがえのない大学時代を過ごしていきます。彼の周りにはいつも、笑いと人の温もりがありました。
物語は、そんな世之介の青春時代と並行して、約20年後の友人たちの姿を映し出します。祥子は国連職員として世界を飛び回り、倉持と唯は結婚して家庭を築き、千春はラジオパーソナリティとして活躍しています。彼らはそれぞれの人生を歩む中で、ふとした瞬間に横道世之介という青年を思い出します。彼の記憶は、彼らの心の中で温かく生き続けているのです。
そして、物語の終盤で衝撃の事実が明かされます。報道カメラマンとなった世之介は、2009年、新大久保駅で線路に落ちた人を助けようとして、自らも命を落としていたのです。40歳という若さでした。彼のあまりにも突然で、しかし彼らしい最期は、彼を知る人々の心に深く刻まれ、読者にも大きな感動と問いを投げかけます。
小説「横道世之介」の長文感想(ネタバレあり)
「横道世之介」を読み終えたとき、私の胸には、温かい陽だまりのような感情が広がっていました。それは、悲しいとか、切ないとか、そういう一言では言い表せない、もっと複雑で、でも確かに心を満たしてくれるような感覚でした。主人公である横道世之介という青年は、決して特別な才能に恵まれているわけでも、何か大きなことを成し遂げようと野心に燃えているわけでもありません。むしろ、どこにでもいるような、少しお人好しで、ちょっと抜けていて、でも憎めない、そんな「普通」の男の子です。でも、彼と出会った人々は、なぜか彼のことを忘れられず、ふとした瞬間に思い出しては、心が温かくなるのを感じるのです。
この物語の魅力は、まさにその「普通」の青年である世之介が、周りの人々に与える静かで深い影響力にあるのだと思います。彼は誰に対しても壁を作らず、自然体で接します。人の頼みを断れなかったり、悪意なく図々しいことをしてしまったりすることもありますが、それすらも彼の愛すべき個性として周囲に受け入れられていくのです。彼の周りにはいつも、なんだか朗らかな空気が流れていて、読んでいる私たちまで、その輪の中にいるような心地よさを感じます。
物語は、1980年代の世之介の大学時代と、それから約20年後の彼を知る人々の現在とが、巧みに織り交ぜられながら進んでいきます。この構成が本当に見事で、過去の出来事が、現在の登場人物たちの心の中でどのように息づいているのかを、鮮やかに描き出しています。大学時代のきらきらとした、でもどこか危うげな青春の日々と、それぞれの人生を歩む大人になった彼らの現実。その対比が、時間の流れというものをリアルに感じさせ、同時に、記憶というものの不思議さ、そして大切さを教えてくれます。
特に印象的なのは、世之介の恋人であった与謝野祥子のエピソードです。天真爛漫で、育ちの良いお嬢様である祥子が、世之介と出会い、恋に落ちていく過程は、本当に微笑ましく、読んでいるこちらも胸がときめきます。祥子の独特な言葉遣いや、世之介の何気ない一言に大爆笑する姿は、彼女の純粋さと世之介への深い愛情を感じさせます。二人が世之介の実家である長崎へ旅行に行く場面は、まるで青春映画のワンシーンのようで、鮮やかな情景が目に浮かびます。彼らの恋は、大学時代のほんの短い期間のものでしたが、祥子のその後の人生において、世之介との思い出はかけがえのない宝物として輝き続けていることが伝わってきて、胸が熱くなりました。
世之介の大学時代の友人である倉持一平と阿久津唯の夫婦もまた、世之介の記憶を大切に抱いて生きています。学生結婚し、若くして親になった二人は、様々な困難に直面しながらも、懸命に日々を乗り越えていきます。娘のことで思い悩む倉持が、ふと世之介のことを思い出し、「あいつがいたら、なんて言うかな」と考える場面は、世之介という存在が、彼らにとって心の支えの一つになっていることを感じさせます。それは、大きなアドバイスをくれるとか、問題を解決してくれるとか、そういうことではないのです。ただ、そこにいて、話を聞いてくれるだけで安心できる、そんな存在。世之介は、そういう温かさを自然と人に与えることができる人間だったのでしょう。
また、世之介が密かに憧れていた年上の女性、片瀬千春。彼女は、世之介のことをどこか利用するような形で関わりますが、それでも世之介は彼女に対して嫌な感情を抱くことなく、むしろ純粋な憧れを持ち続けます。大人になった千春が、ラジオの人生相談で、ふと誰かのことを思い出そうとするけれど、それが誰だったか思い出せない、という場面があります。それはきっと世之介のことなのでしょう。直接的に彼女の人生を大きく変えたわけではないかもしれないけれど、世之介と過ごした時間は、確かに彼女の記憶の片隅に残り、何かしらの影響を与えていたのかもしれない、そう思わせる描写です。
この物語を読んでいて強く感じるのは、吉田修一さんの人間描写の巧みさです。登場人物一人ひとりが、本当にリアルで、血の通った人間として描かれています。彼らのセリフや行動、心の動きが、とても自然で、読んでいると、まるで自分の友人や知人のことのように感じられるのです。だからこそ、彼らが抱える喜びや悲しみ、葛藤に深く共感し、物語の世界に没入してしまうのでしょう。
そして、物語の最後に明かされる世之介の死。報道カメラマンとなった彼が、新大久保駅で人命救助のために命を落としたという事実は、あまりにも衝撃的で、言葉を失いました。しかし、それは同時に、横道世之介という人間の生き方を象徴するような最期だったとも言えるのかもしれません。困っている人を見過ごせない、彼の根っからの優しさが、その行動に繋がったのでしょう。彼の死は、彼を知る人々にとってはもちろん、読者にとっても大きな悲しみをもたらしますが、それと同時に、彼の人生が決して無駄ではなかったこと、彼の存在が多くの人々の心に光を灯し続けていることを教えてくれます。
世之介の死を知った祥子が、彼との思い出を振り返る場面は、涙なしには読めませんでした。彼女が「横道世之介と出会った人生と、出会わなかった人生で、何が変わるだろうか。たぶん、何も変わりはない。でも、青春時代に彼と出会わなかった人が、この世にはたくさんいるのかと思うと、なぜか自分がとても得をしたような気持ちになってくる」と語る言葉は、この物語のテーマそのものを表しているように感じます。
世之介は、大きな成功を収めたわけでも、歴史に名を残したわけでもありません。でも、彼と出会った人々は、彼と過ごした時間を思い出すたびに、心が温かくなったり、少しだけ勇気をもらえたりするのです。それは、お金や名誉では決して手に入れることのできない、人間関係の中で育まれる、かけがえのない財産なのだと思います。
この物語は、1980年代という時代背景も魅力の一つです。まだ携帯電話もインターネットも普及していない時代。人と人との繋がりが、今よりももっと直接的で、温かみがあったのかもしれない、そんなノスタルジックな気分にさせてくれます。世之介たちが経験する大学生活のあれこれ――サークル活動、アルバイト、友人たちとの他愛ないおしゃべり、そして恋――は、普遍的な青春の輝きを放っており、世代を超えて多くの読者の共感を呼ぶのではないでしょうか。
読み終えて改めて思うのは、世之介のような人間が、私たちの周りにもきっといるのではないか、ということです。目立つ存在ではないかもしれないけれど、その人がいるだけで場が和んだり、なんとなく安心したりする。そういう人の存在の大きさに、私たちは普段あまり気づかずに過ごしているのかもしれません。でも、そういう人こそが、実は私たちの日常を豊かにしてくれているのではないか、と「横道世之介」は教えてくれます。
この物語は、私たちに「生きることの素晴らしさ」や「人と人との繋がりの大切さ」を、静かに、でも深く語りかけてくれます。特別な出来事が起こるわけではないけれど、日常の中にこそ、きらめくような瞬間や、心に刻まれるべき出会いが隠されているのだと気づかせてくれるのです。世之介の人生は短かったかもしれませんが、彼が残した温かい記憶は、彼と関わった人々の心の中で、これからもずっと生き続けることでしょう。
この作品は、読んだ後、自分の周りにいる大切な人たちのことを、ふと思い返したくなるような、そんな余韻を残してくれます。そして、自分自身も、誰かにとっての「横道世之介」のような存在になれたら、と淡い願いを抱かせてくれるのです。派手さはないけれど、心にじんわりと染み渡る、そんな優しい物語です。
もしかしたら、世之介自身は、自分が誰かに影響を与えているなんて、微塵も思っていなかったかもしれません。ただ、目の前の人との時間を大切にし、誠実に生きていただけなのかもしれません。でも、その「普通」の積み重ねが、結果として、多くの人の心に忘れられない温かな灯をともしたのです。彼の生き方は、私たちに、本当に大切なものは何かを問いかけているように思えてなりません。
読み進めるうちに、読者はいつの間にか、世之介の友人になったような気持ちで、彼の人生を見守っていることでしょう。そして、彼の死を知ったときには、まるで親しい友人を失ったかのような喪失感と、それでも彼の記憶と共に生きていこうとする登場人物たちへの深い共感を覚えるはずです。吉田修一さんの優しい眼差しが、物語の隅々まで行き届いている、そんな作品だと感じました。
まとめ
吉田修一さんの小説「横道世之介」は、一人の平凡な青年、横道世之介の大学時代と、その後の彼に関わった人々の人生を温かく描いた物語です。彼の何気ない日常、友情、恋愛、そして予期せぬ出来事が、読者の心に深く染み入ります。
世之介は、お人好しで、どこか抜けているけれど、誰からも愛される青年です。彼の周りには自然と人が集まり、彼と過ごした時間は、関わった人々の記憶の中で、いつまでも色褪せることなく輝き続けます。物語は過去と現在を巧みに行き来しながら、世之介という存在が人々に与えた静かで大きな影響を浮き彫りにしていきます。
この作品を読むと、特別なことでなくても、日々の誠実な生き方や人との繋がりがいかに大切かということに気づかされます。世之介の生き方、そして彼の早すぎる死は、私たちに人生の意味を問いかけ、温かい感動と共に、生きる勇気を与えてくれるでしょう。
読後には、自分の周りの人々や、過ぎ去った青春の日々を愛おしく感じるはずです。多くの人の心に残り続けるであろう、素晴らしい一作です。まだ読んだことのない方には、ぜひ手に取っていただきたいと心から思います。

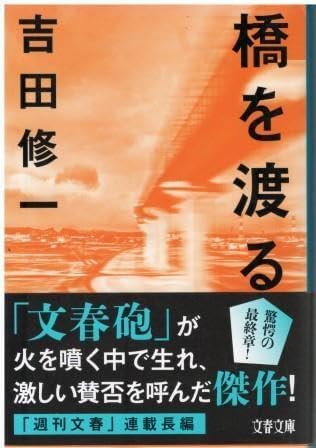
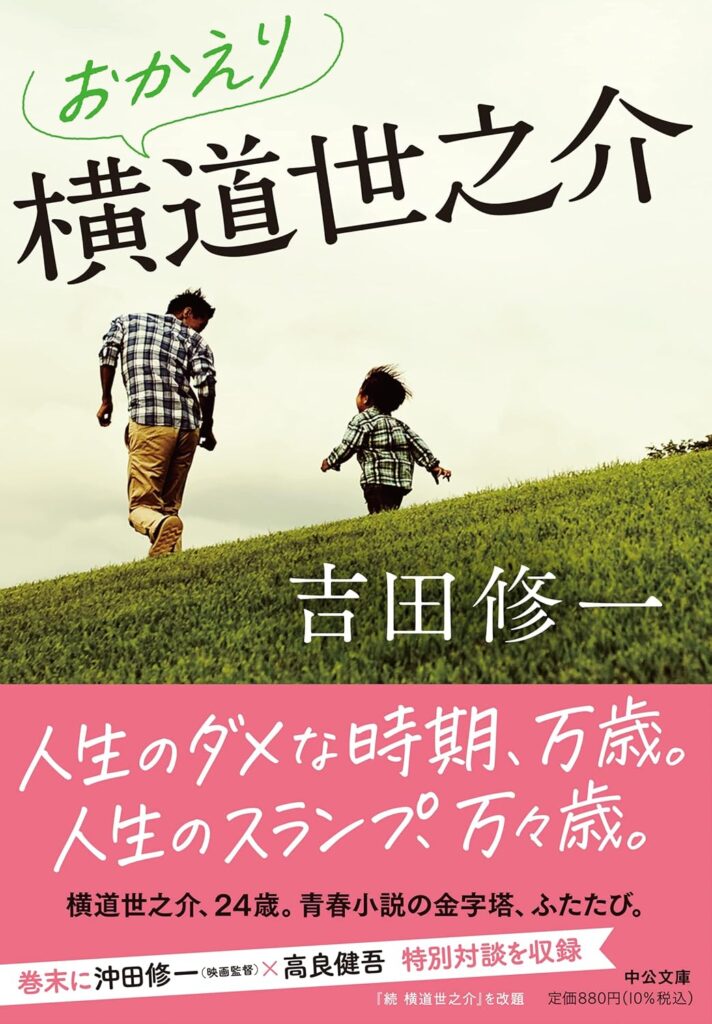
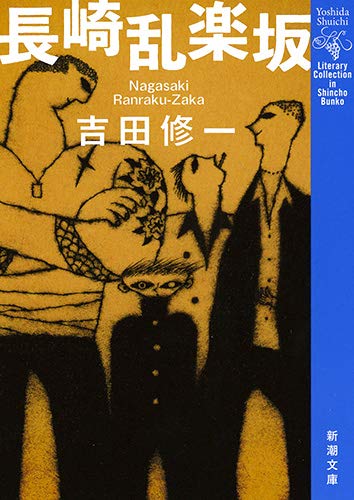
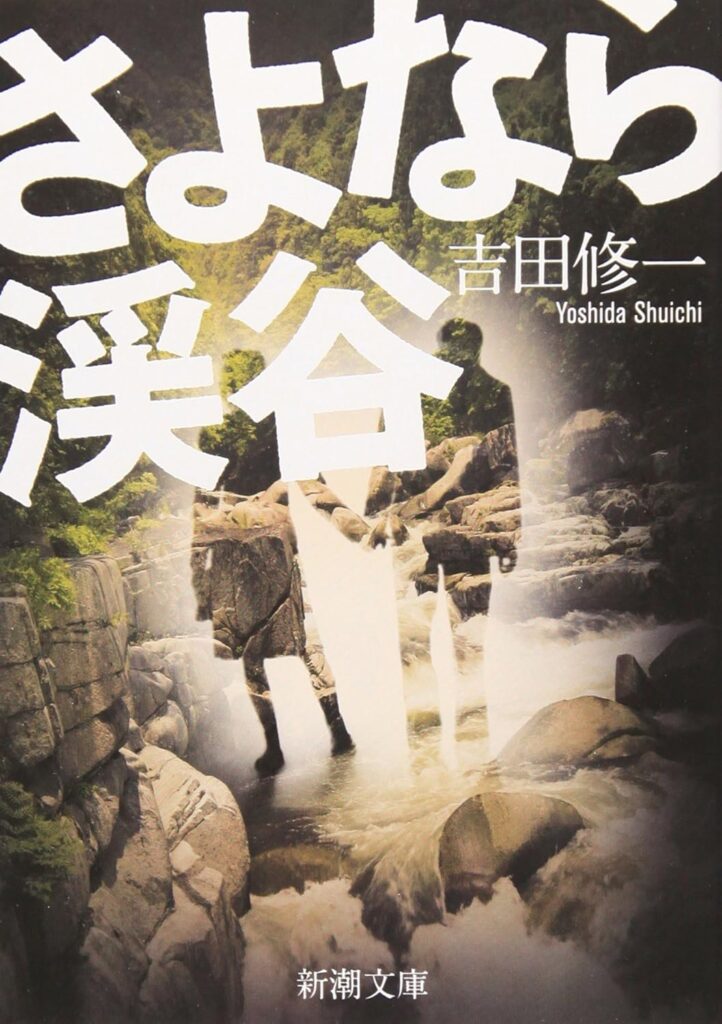
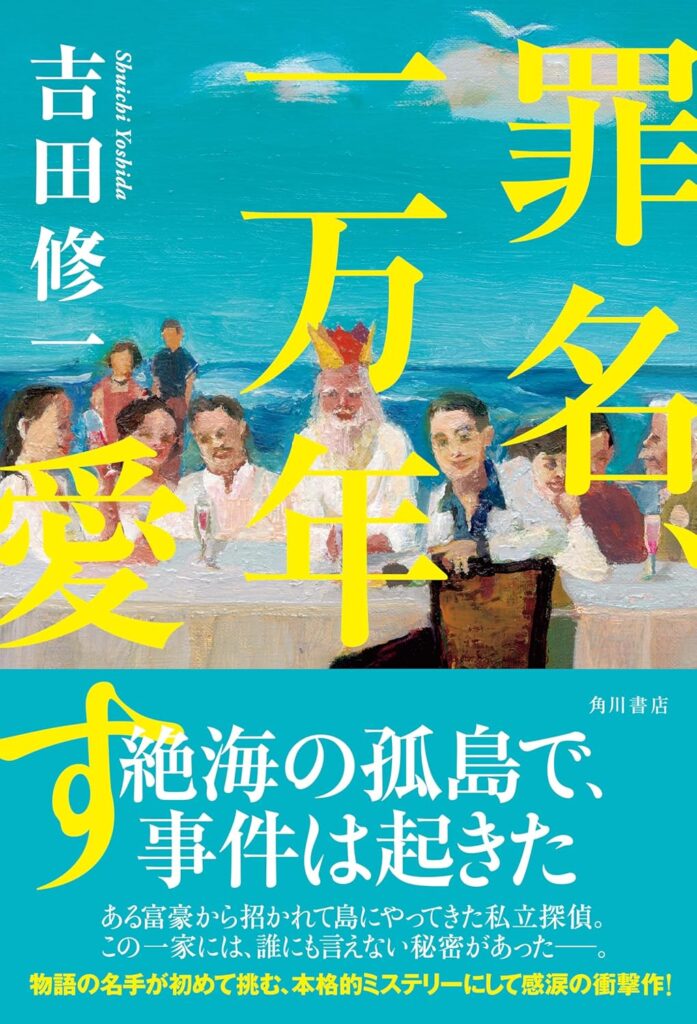
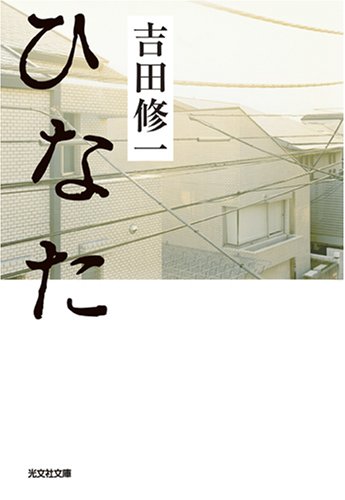
-728x1024.jpg)