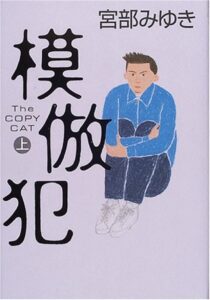 小説「模倣犯」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。宮部みゆきさんが紡ぎ出したこの物語は、単なるミステリーという枠には収まらない、人間の心の闇や社会のありようを深く問いかける大作ですよね。読むのにかなりのエネルギーを要しましたが、それだけの価値がある、忘れられない読書体験となりました。
小説「模倣犯」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。宮部みゆきさんが紡ぎ出したこの物語は、単なるミステリーという枠には収まらない、人間の心の闇や社会のありようを深く問いかける大作ですよね。読むのにかなりのエネルギーを要しましたが、それだけの価値がある、忘れられない読書体験となりました。
物語は、ある公園で発見された女性の右腕から始まります。この衝撃的な事件を発端に、被害者遺族、警察、マスコミ、そして犯人を名乗る人物たちが複雑に絡み合い、物語は予想もしない方向へと展開していきます。特に、犯人が見せる劇場型犯罪ともいえる手口は、読んでいるこちらの心までざわつかせるものがありました。
この記事では、まず物語の骨格となる流れを追い、その後で、物語の核心部分や登場人物たちの心理について、私の感じたことを詳しく述べていきたいと思います。物語の結末にも触れますので、まだ読んでいない方はご注意くださいね。それでも、この作品が持つ重厚なテーマや、読む者の心に残す深い問いかけについて、少しでも共有できたら嬉しいです。
小説「模倣犯」のあらすじ
物語は1996年、東京・墨田区の大川公園で、若い女性の右腕とハンドバッグが発見されるところから幕を開けます。ハンドバッグの持ち主は、3ヶ月前から行方不明になっていた古川鞠子というOLだと判明します。しかし、事件は単純な殺人事件では終わりませんでした。「犯人」を名乗る人物がテレビ局に接触し、「あの右腕は鞠子のものではない」と告げ、さらに鞠子の祖父である有馬義男にも直接電話をかけてくるのです。犯人は義男を挑発し、翻弄します。
ほどなくして、犯人の指示で義男へのメッセージを届けさせられた女子高生が遺体で発見され、鞠子本人も白骨化した遺体となって見つかります。犯人はテレビなどを通じて世間を挑発し続け、その冷酷なやり方は人々の怒りを買います。捜査が進む中で、犯人は2人組である可能性が浮上しますが、捜査は難航します。被害者遺族、特に義男は、悲しみと怒りを抱えながらも、冷静に犯人と対峙しようとします。
そんな中、事態は急転します。群馬県の山中で乗用車が崖から転落し、運転していた栗橋浩美と、助手席の高井和明が死亡。車のトランクからは別の男性の遺体も発見されました。警察は、この事故で死亡した栗橋と高井が連続女性誘拐殺人事件の犯人だと断定し、事件は解決したかのように見えました。世間も、凶悪犯たちの呆気ない結末に安堵します。
しかし、これで終わりではありませんでした。高井和明の妹・由美子は兄の犯行を信じられず、無実を訴え始めます。そして、栗橋と高井の小学校・中学校の同級生だったという網川浩一、通称「ピース」が由美子の後見人として現れ、「真犯人は別にいる」と主張し、マスコミの前に登場します。彼の登場によって、事件は再び大きく動き出し、関係者たちは新たな局面を迎えることになるのです。
小説「模倣犯」の長文感想(ネタバレあり)
宮部みゆきさんの「模倣犯」を全巻読み終えたとき、まず感じたのは、ずっしりとした重みと、一種の疲労感でした。これは決して否定的な意味合いだけではなく、物語が内包する人間の業や社会の歪み、そして登場人物たちが抱える苦悩や葛藤が、深く心に刻まれたからなのだと思います。単に「面白かった」や「つまらなかった」という言葉では到底言い表せない、複雑な感情が渦巻いています。
読み進める上で、特に印象的だったのは、物語が持つリアリティと、時折顔を出すフィクション的な展開との間の揺らぎでした。序盤、事件が発生し、被害者家族である有馬義男の苦悩や、犯人からの不気味な電話、警察の地道な捜査などが描かれる部分は、まるで現実の事件を追っているかのような生々しさがありました。特に、義男が犯人の挑発に対し、冷静さを保ちながらも怒りを内に秘めて対峙する姿には、胸が締め付けられる思いでした。彼の言葉の一つ一つに、被害者遺族の計り知れない悲しみと、人間としての尊厳を守ろうとする強い意志が感じられました。
しかし、物語が進むにつれて、特に終盤に近づくにつれて、そのリアリティが少しずつ薄れ、物語的な都合の良さのようなものを感じてしまう瞬間もありました。例えば、第5巻における建築家の登場シーン。彼は建物の様子を見ただけで、そこにいたであろうピースの性格や心理状態を驚くほど的確に言い当ててしまいます。これはあまりにも鋭すぎる推理で、少し物語から醒めてしまう要因になりました。また、北海道から現れた角田真弓が、ピース逮捕に繋がる決定的なヒントをもたらす展開も、やや唐突で都合が良いように感じられました。もちろん、「現実にはありえないようなことが起こるのが現実だ」という作中の言葉を借りれば、納得できなくもないのですが、それまでのリアリティとのギャップを感じずにはいられませんでした。
警察の捜査の進展についても、少し物足りなさを感じた点です. ピースに疑いの目が向けられるようになったきっかけが、読者に対して明確に示されないまま、物語が進んでいくように感じました。角田真弓の証言が決定打となったのか、あるいは別の捜査線上にピースが浮上したのか。その過程がもう少し丁寧に描かれていれば、より納得感が増したかもしれません。結果的に、ピースを追い詰めていく主軸が、警察ではなくルポライターの前畑滋子というマスコミ側の視点になっていたことも、少しアンバランスな印象を受けました。滋子の奮闘は確かに物語の推進力ではありましたが、組織としての警察の動きがやや影が薄く感じられたのは残念でした。
そして、物語の中心にいるとも言える真犯人、ピースこと網川浩一。彼のキャラクター造形は非常に巧みで、魅力的でありながら底知れない不気味さを湛えています。頭脳明晰で、人を惹きつけるカリスマ性を持ちながら、その内面には他者への共感を欠いた冷酷さと、歪んだ自己顕示欲が渦巻いている。彼が作り上げようとした「劇場型犯罪」は、まさに現代社会の闇を映し出しているようにも思えます。しかし、その一方で、彼が意外なほど挑発に弱く、最終的に自滅していく様は、一部の読者が指摘するように、ややあっけないと感じる部分もありました。あれだけ周到に計画を進めてきた人物が、滋子の言葉や有馬義男の揺さぶりによって、脆くも崩れ去っていく。それは、彼のプライドの高さと表裏一体の脆さを示しているのかもしれませんが、もう少し緻密な攻防が見たかったという気持ちも残ります。ピースを追い詰める決定的なきっかけが、兄の無実を信じ続けた高井由美子の悲劇的な死であったことは、何とも皮肉で、やるせない気持ちにさせられました。まるで、彼の築き上げた虚構の王国が、最も純粋な心によって打ち砕かれたかのようでした。
登場人物たちについても、語りたいことはたくさんあります。有馬義男は、この重苦しい物語の中で、一貫して人間としての矜持を失わない、まさに大黒柱のような存在でした。彼の冷静さ、思慮深さ、そして孫娘を奪われた悲しみと怒り。特に終盤、ピースと対峙し、静かに、しかし鋭く真実を突きつける場面は圧巻でした。そして、最後に彼が漏らした本音には、彼の人間的な弱さも垣間見え、より一層その存在に深みを与えていたと思います。彼がいたからこそ、この物語は単なる猟奇事件の記録ではなく、人間の尊厳を問う物語になり得たのだと感じます。
事件の第一発見者であり、自身も過去に壮絶な事件を経験した塚田真一。彼が自身のトラウマと向き合い、少しずつ前に進もうとする姿も印象的でした。水野久美との交流や、有馬義男との関わりを通して、彼が再生していく過程は、暗い物語の中に射す一条の光のようにも感じられました。彼の結末は、希望を感じさせるものであり、救いの一つであったと思います。
一方で、ルポライターの前畑滋子については、個人的には少し複雑な感情を抱きました。真実を追求しようとするジャーナリストとしての姿勢は理解できるものの、時に被害者の感情よりも記事になる「ネタ」を優先しているように見えてしまう瞬間もあり、共感しきれない部分もありました。もちろん、彼女自身も葛藤し、悩みながら事件に向き合っていたことは理解していますが、物語の結末で彼女がある種の「成功」を収めることには、少し割り切れない気持ちが残りました。(スピンオフ作品『楽園』では、彼女のその後が描かれているとのことなので、そちらを読むとまた印象が変わるのかもしれません。)
そして、この物語で最も悲劇的な存在と言えるのが、高井和明と妹の由美子ではないでしょうか。和明は、幼い頃から栗橋浩美にいじめられ、ピースにも利用され、最期までその関係性から逃れることができませんでした。しかし、彼の中にも確かに友情や良心があり、それが最後の最後で栗橋の心を動かすきっかけになったことは、救いのない展開の中でのわずかな希望だったのかもしれません。妹の由美子は、兄の無実を信じ、たった一人で立ち上がろうとします。その純粋さ、ひたむきさが、かえって彼女を危険な状況へと追い込み、ピースに利用される結果を招いてしまいます。彼女がピースに惹かれていく心理描写は痛々しく、そして彼女の最期は、この物語のやるせなさを象徴しているようでした。高井家が迎えた結末は、あまりにも過酷で、読後も重く心に残ります。
物語の結末について、もう一つ感じたのは、事件後の描写がやや駆け足で、余韻が少ないということです。あれだけの長編で、多くの人物が登場し、それぞれが深い傷を負ったわけですから、もう少しその後の彼らの人生や心情に触れてほしかった、というのが正直な気持ちです。有馬義男や真一、滋子についてはある程度描かれていますが、例えば、最後まで高井和明を信じようとしていた蕎麦屋の常連・足立好子や、事件に関わった刑事たち(特に、栗橋・高井犯人説に疑問を抱いていた武上刑事や、由美子とお見合いするはずだった篠崎刑事)が、事件の真相を知ってどう感じたのか。冤罪だった和明に対して、警察内部でどのような議論があったのか。そうした部分が描かれていれば、物語により深みが増したのではないかと感じます。
「模倣犯」は読むのに体力と精神力を使う作品でした。人間の心の闇、悪意の連鎖、メディアの狂騒、そしてその中で翻弄され、傷つきながらも生きていこうとする人々の姿が、圧倒的な筆致で描かれています。特に終盤の展開や結末の描き方には個人的に不満な点もありましたが、それでも、これほどまでに心を揺さぶられ、様々なことを考えさせられた作品は久しぶりでした。読み終えた後のこの複雑な感覚は、きっと長く忘れることはないでしょう。宮部みゆきさんの作家としての力量を改めて感じさせられる、間違いなく傑作の一つだと思います。ただ、精神的にかなり消耗するので、すぐに再読するのは難しいかもしれませんね。
まとめ
宮部みゆきさんの長編小説「模倣犯」は、公園で見つかった右腕を発端とする連続誘拐殺人事件を描いた作品です。劇場型の犯行を繰り返す犯人と、被害者遺族である有馬義男、警察、マスコミ、そして事件の真相に迫ろうとする人々が織りなす、重厚な物語が展開されます。ネタバレになりますが、犯人と思われた二人が事故死した後、「真犯人X」の存在を主張するピースが登場し、物語は新たな局面を迎えます。
この物語を読んで感じたのは、人間の心の闇の深さと、悪意が伝染していく恐ろしさです。犯人であるピースの冷酷さ、計算高さ、そして歪んだ自己顕示欲は、読む者をぞっとさせます。また、事件をセンセーショナルに報道するマスコミのあり方や、それに影響される世間の反応についても深く考えさせられました。一方で、有馬義男や塚田真一のように、絶望的な状況の中でも人間としての尊厳を失わず、真実に向き合おうとする人々の姿には心を打たれます。
読み終えた後には、面白かったという単純な感想ではなく、ずっしりとした重みと複雑な感情が残ります。特に終盤の展開や結末の描き方については、賛否両論あるかもしれませんが、それも含めて、読後に様々な議論を呼び起こす力を持った作品であることは間違いありません。読むのにエネルギーは必要ですが、現代社会や人間の本質について深く考えさせられる、忘れられない読書体験となるでしょう。































































