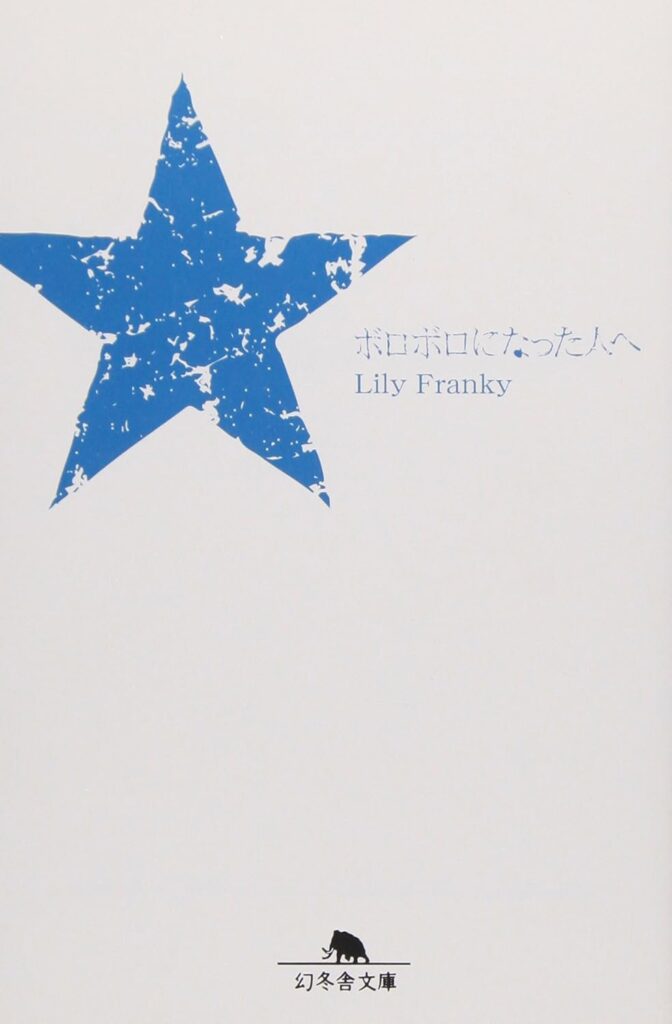小説「東京タワー オカンとボクと、時々、オトン」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この物語は、多くの人が心のどこかに持っている、母親への複雑な、それでいて深い愛情を思い出させてくれる特別な一冊だと感じています。誰もが経験するわけではないけれど、どこか普遍的な親子の関係性が、飾らない言葉で描かれています。
物語の中心にいるのは、著者リリー・フランキーさん自身を投影したであろう「ボク」と、その母親である「オカン」。そして、タイトルにもあるように「時々」現れる「オトン」です。福岡県の筑豊を舞台にした幼少期から、上京、そしてオカンとの東京での暮らし、別れまでが、時に切なく、時に温かく描かれています。
この物語を読むと、自分の母親のことを考えずにはいられません。オカンのように強く、愛情深い母親だったら、と想像したり、あるいは、ボクのように親不孝をしてしまった過去を思い出したりするかもしれません。でも、どんな親子関係であれ、そこには計り知れないほどの歴史と感情が詰まっているのだと、改めて気づかされます。
この記事では、物語の詳しい流れと結末に触れながら、私がこの作品から受け取った感動や考えさせられたことを、できるだけ丁寧にお伝えしたいと思います。少し長い文章になりますが、この素晴らしい物語の世界を一緒に味わっていただけたら嬉しいです。
小説「東京タワー」のあらすじ
物語は、主人公である「ボク」(雅也)が、大人になってから母親「オカン」(栄子)との日々を回想する形で進みます。ボクが幼い頃、オカンは自由奔放で甲斐性のない「オトン」と別れ、ボクを連れて筑豊の実家に戻ります。炭鉱町での貧しいながらも愛情に満ちた生活が始まります。オカンは明るく働き者で、どんな時もボクを一番に考え、深い愛情を注いでくれました。
やがてボクは、絵の才能を認められ、地元の高校ではなく、大分の美術高校へ進学し、一人暮らしを始めます。しかし、自由を手に入れたボクは、勉強もそこそこに遊びに明け暮れ、親の期待を裏切るような日々を送ります。それでもオカンは、文句一つ言わず、黙って仕送りを続けてくれました。
その後、ボクは東京の美術大学に進学。上京してからも自堕落な生活は続き、借金を作ったり、留年したりと、オカンに心配をかけ続けます。イラストレーターとして少しずつ仕事が入るようにはなりますが、生活は不安定なままでした。そんなボクを見かねてか、あるいは自身の体調の変化もあってか、ある日、オカンは福岡のお店をたたみ、ボクの住む東京へやってきます。
こうして、東京タワーが見える街で、ボクとオカンの二人暮らしが再び始まります。オカンは持ち前の明るさと人懐っこさで、ボクの友人たちともすぐに打ち解け、手料理を振る舞い、彼らにとっても「東京のオカン」のような存在になります。ボクも、ようやくオカンに親孝行らしいことができるようになり、穏やかで幸せな時間が流れます。
しかし、そんな日々は長くは続きませんでした。オカンに癌が見つかります。手術は成功したかのように思えましたが、癌は再発し、入退院を繰り返すようになります。ボクは献身的にオカンを支え、なけなしのお金でハワイ旅行に連れて行くなど、できる限りのことをしようとします。壮絶な闘病生活の末、多くの友人たちに見守られながら、オカンは静かに息を引き取ります。
オカンの死後、ボクは深い悲しみと後悔に苛まれます。もっと何かできたのではないか、もっと優しくできたのではないか、と。しかし、オカンが残してくれたたくさんの愛情と思い出、そして彼女を取り巻いていた人々の温かさに支えられ、ボクは少しずつ前を向いて歩き始めます。物語は、かけがえのない存在だったオカンへの尽きない感謝と愛情で締めくくられます。
小説「東京タワー」の長文感想(ネタバレあり)
この「東京タワー オカンとボクと、時々、オトン」という物語が、なぜこれほどまでに多くの人の心を掴んで離さないのか。読み終えた今、その理由が少しわかったような気がします。それはきっと、誰もが持つ「母親」という存在への、言葉にしきれない複雑な感情――感謝、愛情、時には反発や甘え、そして後悔――そういったものを、真正面から、しかも非常に正直に描いているからではないでしょうか。読みながら、何度も自分の母親の顔が浮かんでは消え、胸が締め付けられるような思いがしました。
まず、この物語の太陽のような存在である「オカン」。彼女の生き様には、本当に頭が下がります。夫であるオトンに頼らず、女手一つでボクを育てる。決して裕福とは言えない生活の中でも、卑屈になることなく、常に前向きで、そして何よりもボクへの愛情を惜しみなく注ぎ続ける姿。着るものに困らないように、いつも綺麗な服を用意してくれたこと、ボクの好きな食べ物を優先して作ってくれたこと。一つ一つのエピソードから、オカンの深い愛情がひしひしと伝わってきます。それは、決して押し付けがましいものではなく、ごく自然な、それでいて絶対的なものとして描かれています。
しかし、オカンはただ強いだけの女性ではありません。癌という病に侵され、弱っていく姿、治療の苦しみに耐える姿も、包み隠さず描かれています。特に、東京でボクと暮らし始めてからの、友人たちに囲まれて本当に楽しそうにしていた日々があったからこそ、その後の闘病生活の描写は一層胸に迫るものがありました。それでも、最後まで周囲への気遣いを忘れず、弱音を吐きながらも懸命に生きようとする姿は、痛々しくも、やはり「強い人」なのだと感じさせられました。母親である前に一人の人間としての、その生き様そのものに心を打たれます。
一方で、主人公である「ボク」。彼のダメっぷりには、正直、呆れる場面も多々ありました。高校、大学と、オカンが必死で働いて送り出してくれたにも関わらず、自由を謳歌するあまり、学業を疎かにし、借金まで重ねる。オカンの気持ちを考えろよ、と何度思ったことか。でも、不思議と彼を憎めないのは、そのダメさ加減が、どこか自分自身の若かった頃の未熟さや甘えと重なるからかもしれません。誰もが、親の期待通りに生きられるわけではない。むしろ、親不孝の一つや二つ、心当たりのある人の方が多いのではないでしょうか。
そんなボクが、オカンの病気をきっかけに、少しずつ変わっていく姿には、救われる思いがしました。遅まきながらも、オカンにしてあげられることを必死で考え、行動するようになる。一緒に暮らし、料理を作り、旅行にも連れて行く。ようやく始まった親孝行の日々。しかし、それも束の間、オカンとの別れが訪れてしまう。もっと早く気づいていれば、もっとたくさん親孝行できたのに、というボクの後悔は、読んでいるこちらまで苦しくなるほどでした。親孝行したい時には親はなし、という言葉がありますが、それを痛切に感じさせられます。
そして、「時々、オトン」。彼の存在も、この物語に奥行きを与えています。定職にも就かず、酒癖も悪く、家庭を顧みない。典型的なダメ親父かもしれません。それでも、ボクにとっては唯一の父親であり、オカンにとっても、憎み切れない、どこか特別な存在だったのだろうと感じます。時折見せる父親らしい優しさや、オカンが病に倒れた後に見舞いに来て、不器用ながらも寄り添う姿。離婚してもなお、二人の間には確かな繋がりがあったことがうかがえます。完璧ではないけれど、これもまた一つの家族の形なのだと思わされました。
この物語は、リリー・フランキーさん自身の体験に基づいていると言われています。だからこそ、描かれる感情や出来事が非常に生々しく、リアルに響いてくるのでしょう。そこには、綺麗ごとだけではない、親子の間の葛藤や、どうしようもない現実も描かれています。ボクがオカンに対して抱く、感謝や愛情だけでなく、時には鬱陶しさや苛立ちを感じる瞬間も、正直に書かれているように思います。だからこそ、多くの読者が「これは自分の物語かもしれない」と感じ、共感するのではないでしょうか。
物語の中には、悲しい出来事だけでなく、思わずクスッと笑ってしまうような、温かいエピソードもたくさん散りばめられています。筑豊での子供時代の思い出、個性的な友人たちとの交流、オカンのお茶目な一面。そういった描写があるからこそ、悲劇性が際立つと同時に、救いにもなっているように感じます。特に、東京でオカンがボクの友人たちに囲まれ、第二の青春を楽しむかのように生き生きと過ごす場面は、読んでいて心が温かくなりました。オカンがいかに多くの人に愛されていたかがよくわかります。
印象に残っている場面は数えきれませんが、いくつか挙げるとすれば、まず、ボクがオカンを東京に呼び寄せる決心をする場面です。それまでの自堕落な生活を清算し、ようやく親孝行をしようと決意するボクの姿には、成長を感じずにはいられません。そして、駅のホームでオカンを出迎え、「ずっとこの町でふたりで住むんだ」と語りかけるシーン。ここから始まるはずだった幸せな未来を思うと、切なくなりますが、同時にとても美しい場面だと感じました。
もう一つは、やはりオカンの最期の場面です。壮絶な闘病の末、多くの人に看取られて旅立っていくオカン。そして、葬儀で泣き崩れるボク。どれだけ親孝行をしても、いざ失うとなると、後悔ばかりが募るものなのかもしれません。オカンが残した箱の中に入っていた、ボクのへその緒や手紙。そこには、ただただ深い愛情が詰まっていました。失って初めて気づく、その存在の大きさ。誰もが経験するかもしれない、その普遍的な悲しみが、痛いほど伝わってきました。
オカンの死は、物語の大きな区切りではありますが、終わりではありません。ボクは、オカンがくれた愛情を胸に、これからも生きていかなくてはなりません。悲しみや後悔を抱えながらも、仕事に向き合い、前を向こうとするボクの姿は、静かな決意に満ちています。オカンという存在は、いなくなってもなお、ボクの中で生き続け、彼を支え、導いていくのでしょう。それは、死によって断ち切られることのない、親子の永遠の絆なのだと感じました。
タイトルにもなっている「東京タワー」。ボクにとっては上京の目標であり、オトンにとっては挫折の象徴であり、そしてオカンにとっては、息子と暮らした思い出の街のシンボル。物語の節目節目で登場する東京タワーは、登場人物たちの様々な想いを映し出す鏡のようです。最後にボクがオカンの写真と共に東京タワーに上る場面は、果たせなかった約束を果たすと共に、オカンへの想いを新たにする、感動的なシーンでした。
この物語を書いたリリー・フランキーさんという人は、一体どんな人なのだろう、と改めて思いました。マルチな才能を持ち、どこか掴みどころのない印象がありましたが、この作品を読むと、非常に繊細で、深い愛情を持った人なのだということが伝わってきます。自身の経験を、これほどまでに正直に、そして多くの人の心を打つ物語として昇華させた筆力には、ただただ感服するばかりです。
読み終えて、自分の親のことを改めて考えました。当たり前のようにそばにいてくれる存在ですが、その存在が決して永遠ではないこと。伝えられる感謝は、伝えられるうちに伝えておかなければいけないこと。そして、親が子を想う気持ちは、おそらく子が親を想う気持ちよりも、ずっと深く、大きいのかもしれないということ。この物語は、そんな当たり前のようでいて、忘れがちな大切なことに気づかせてくれました。
「東京タワー オカンとボクと、時々、オトン」は、単なる感動的な親子物語というだけではありません。人生のままならなさ、家族というものの複雑さ、そして、それでもなお人を愛し、生きていくことの尊さを教えてくれる、深く、温かい物語です。涙なくしては読めませんが、読後には、不思議と心が温かくなるような、そんな力を持った一冊だと思います。まだ読んでいない方には、ぜひ手に取っていただきたいですし、読んだことがある方も、きっと再読するたびに新たな発見があるのではないでしょうか。
まとめ
リリー・フランキーさんの小説「東京タワー オカンとボクと、時々、オトン」は、著者自身の体験を基にした、感動的な親子の物語です。主人公「ボク」と、彼を女手一つで育て上げた「オカン」の、貧しくも愛情深い日々、そして避けられない別れまでが、正直な筆致で描かれています。
物語は、時にユーモラスに、時に切なく、読む者の心を強く揺さぶります。特に、どんな状況でも息子への深い愛情を貫くオカンの姿、そして、親不孝を重ねながらも、最後は必死でオカンに寄り添おうとするボクの姿には、多くの人が共感し、涙するのではないでしょうか。また、「時々」現れるオトンの存在も、物語に深みを与えています。
この作品を読むと、誰もが自身の母親や家族との関係について、改めて考えさせられるはずです。親への感謝、後悔、そして愛情。そういった普遍的な感情が、リアルなエピソードを通して伝わってきます。当たり前のように感じている日常や、家族の存在が、どれほどかけがえのないものか、気づかせてくれるでしょう。
単なるお涙頂戴の物語ではなく、人生の喜びや悲しみ、家族の複雑さ、そして生きることの尊厳を描いた、読み応えのある一冊です。まだ読んだことのない方はもちろん、一度読んだことがある方にも、ぜひ改めて手に取っていただきたい、心に残る名作だと感じています。