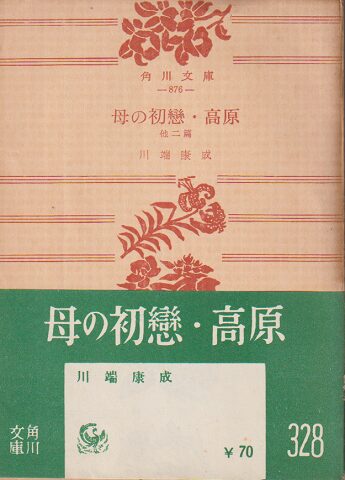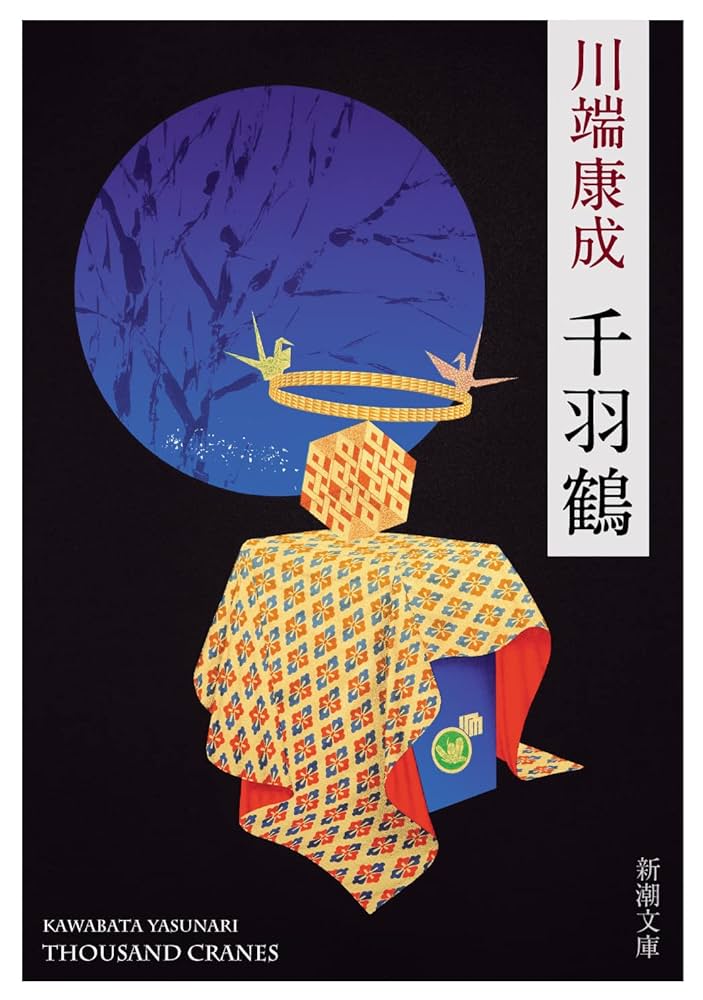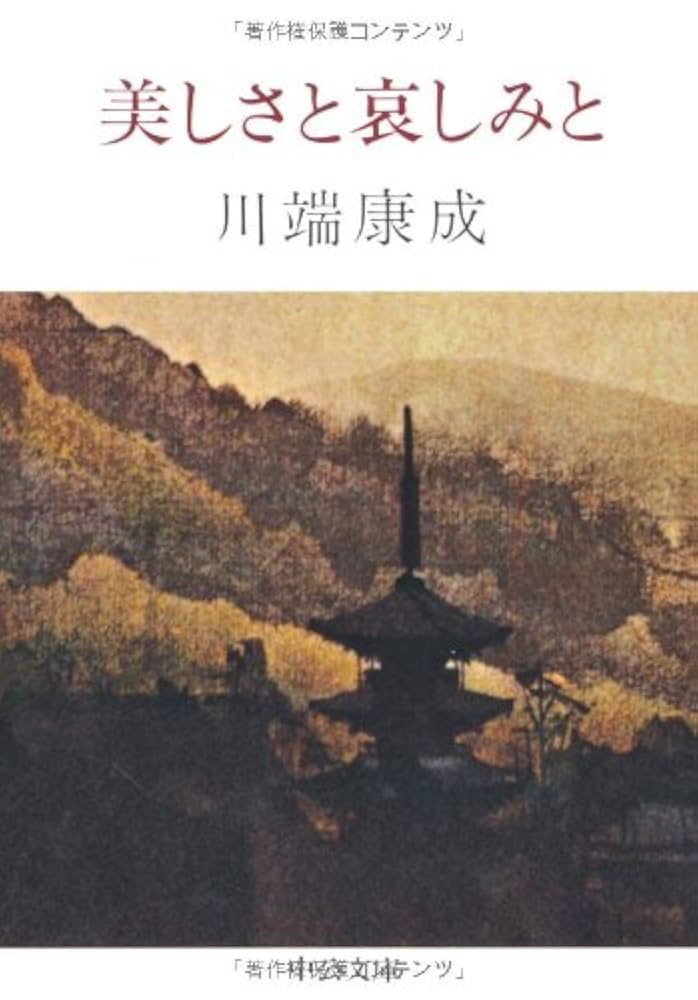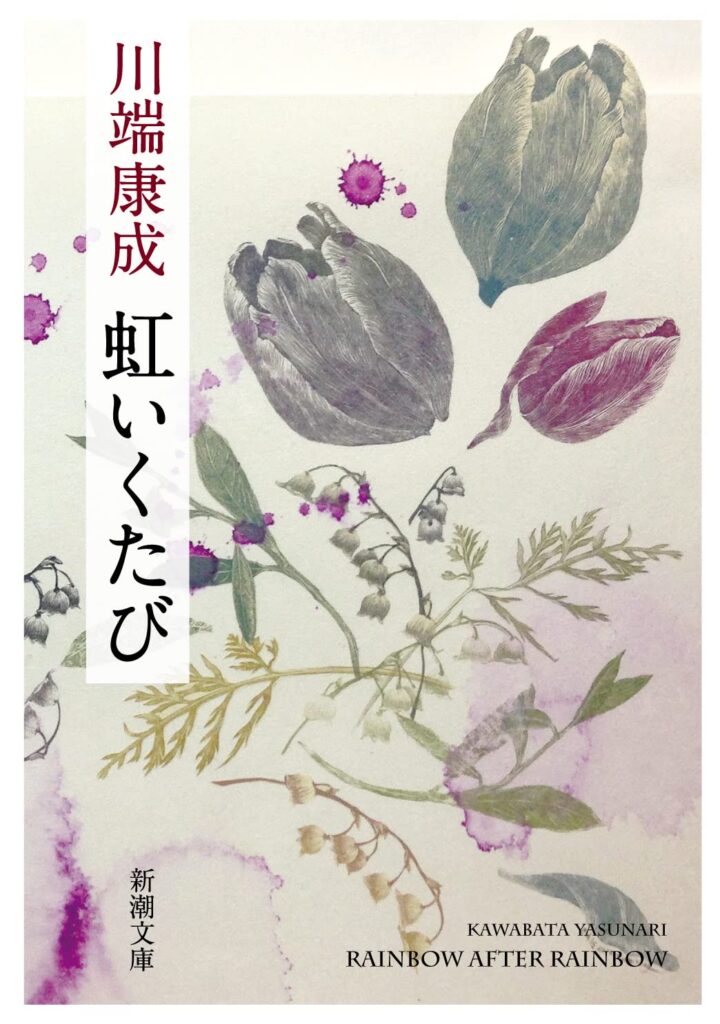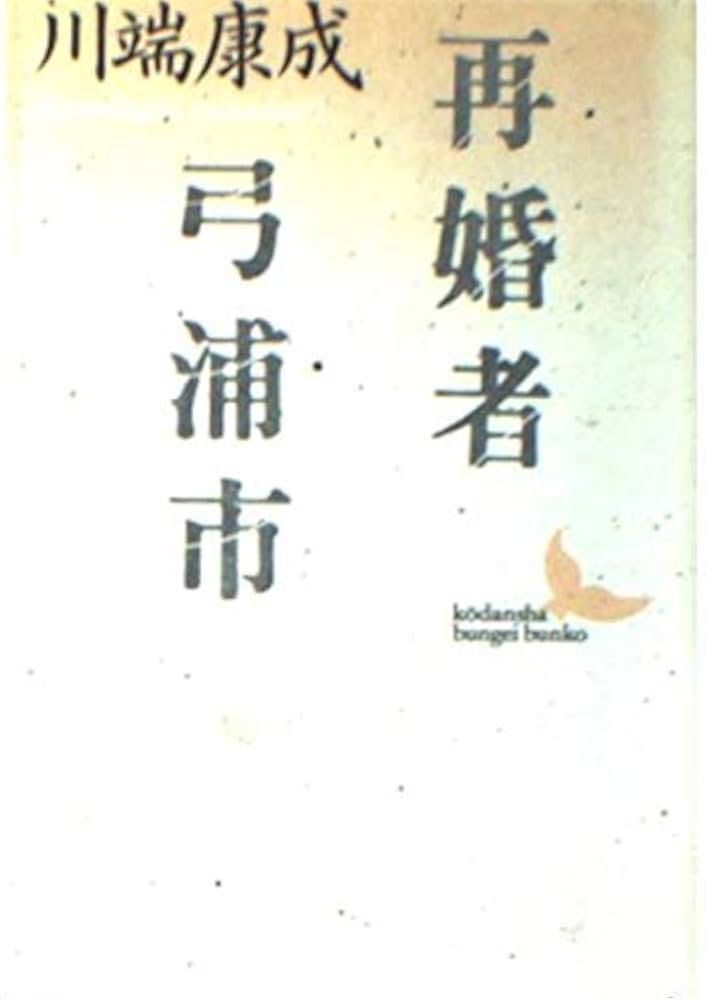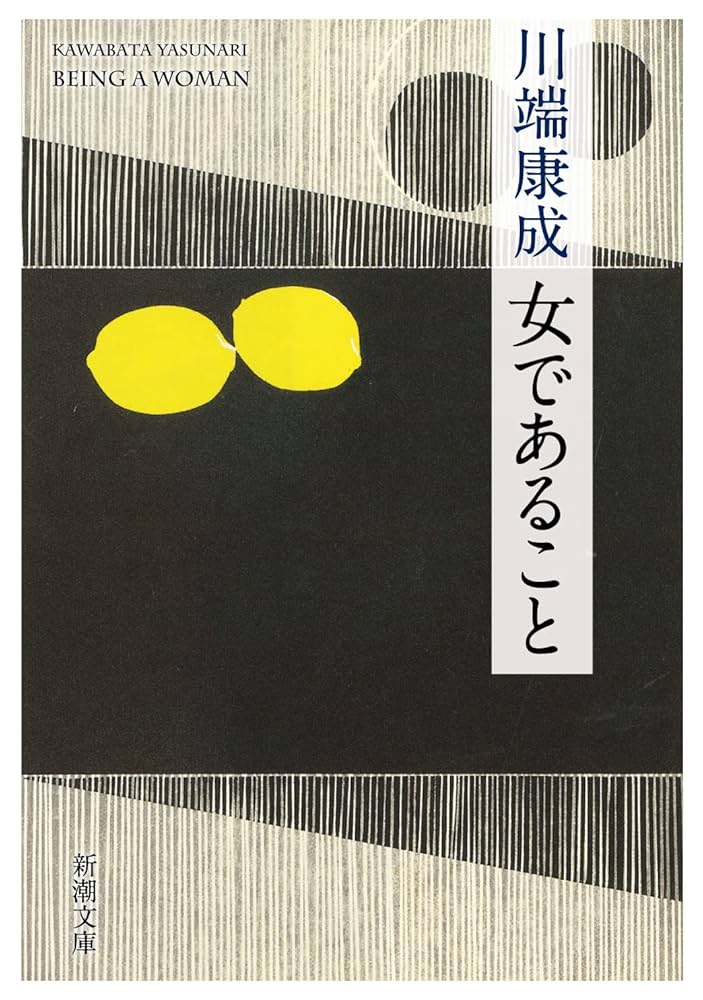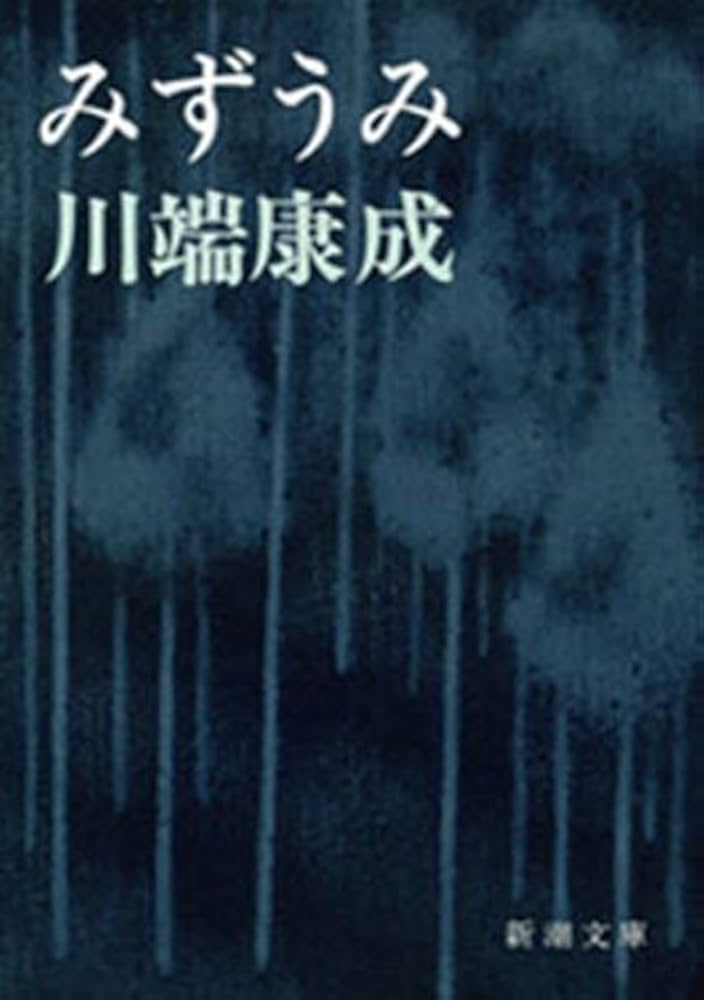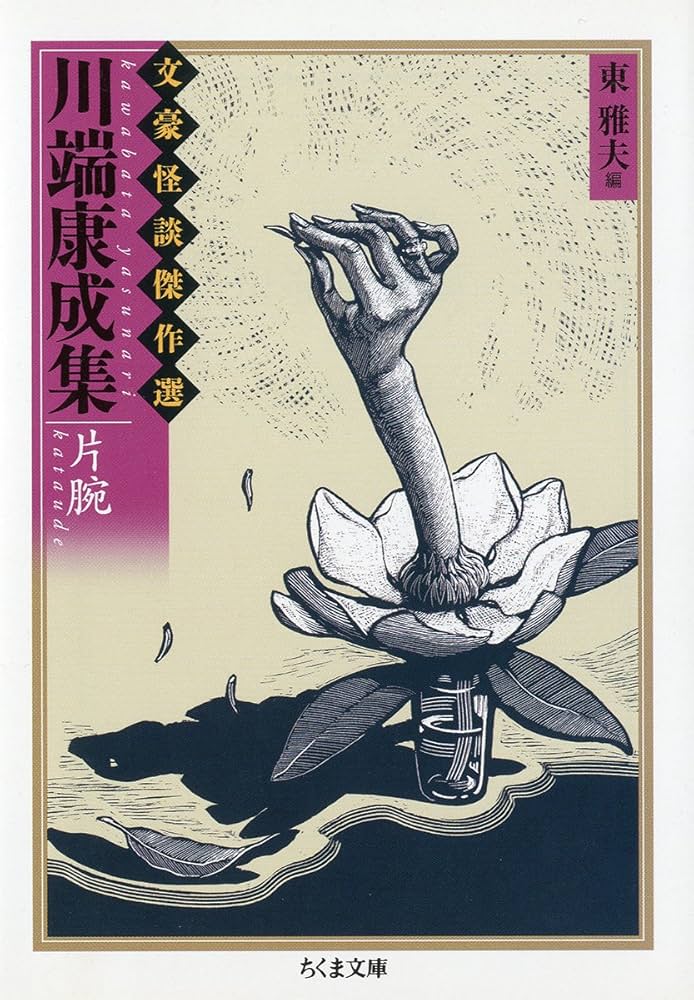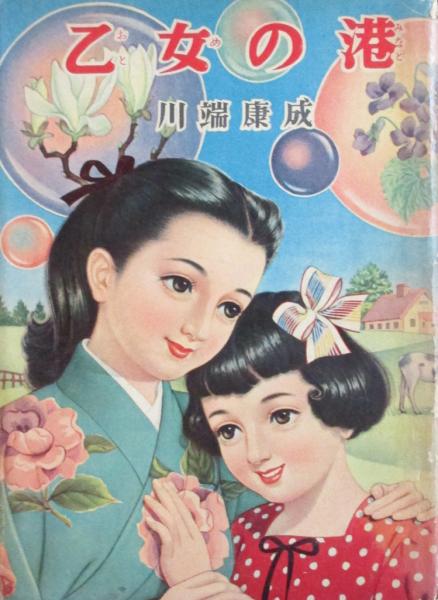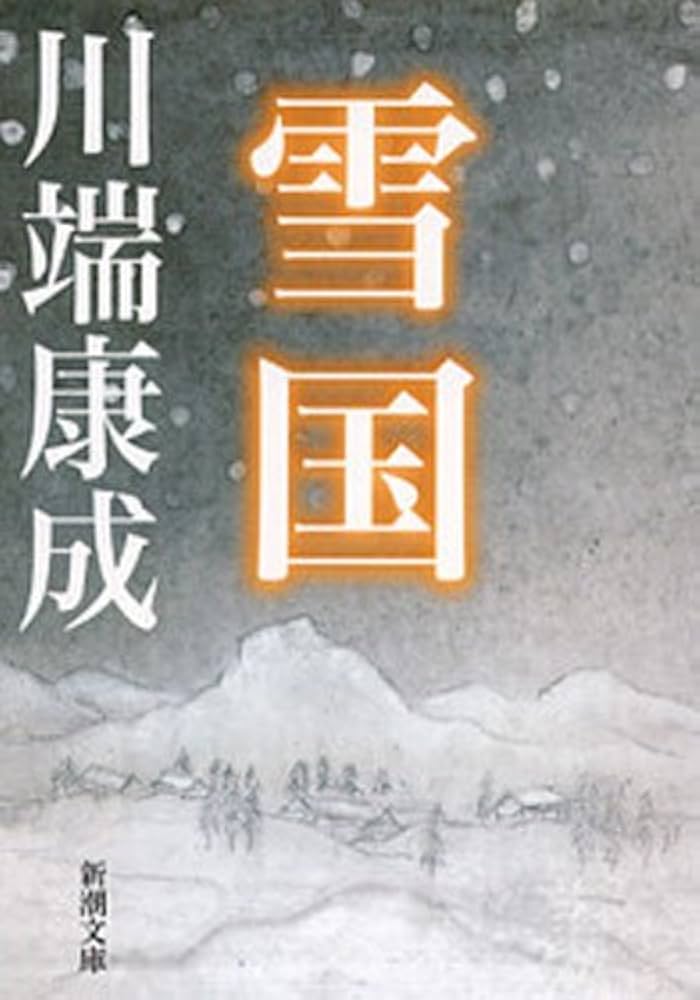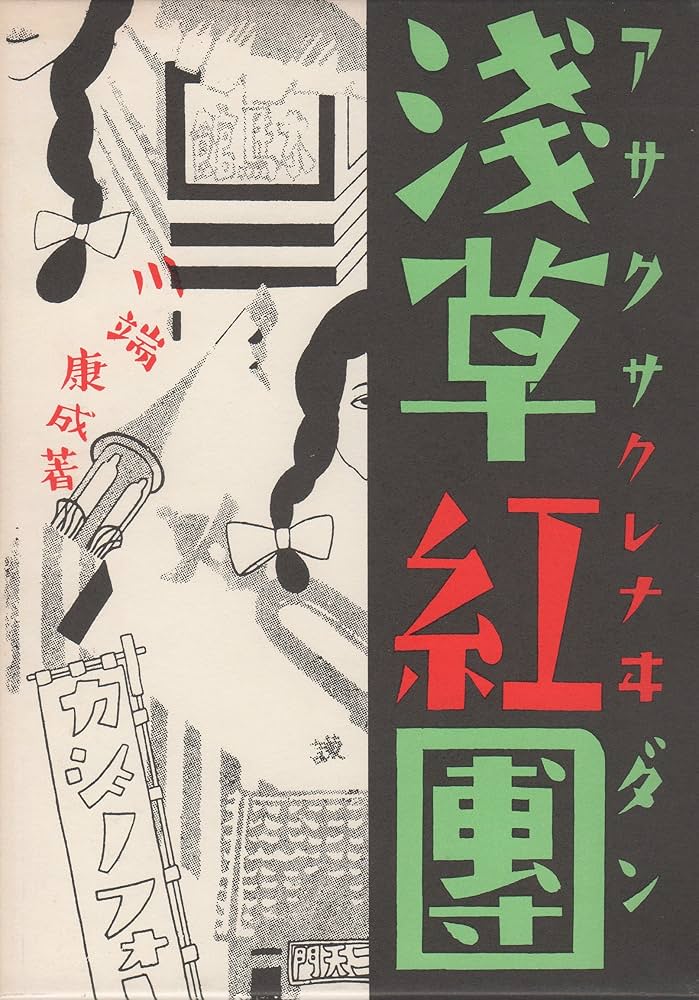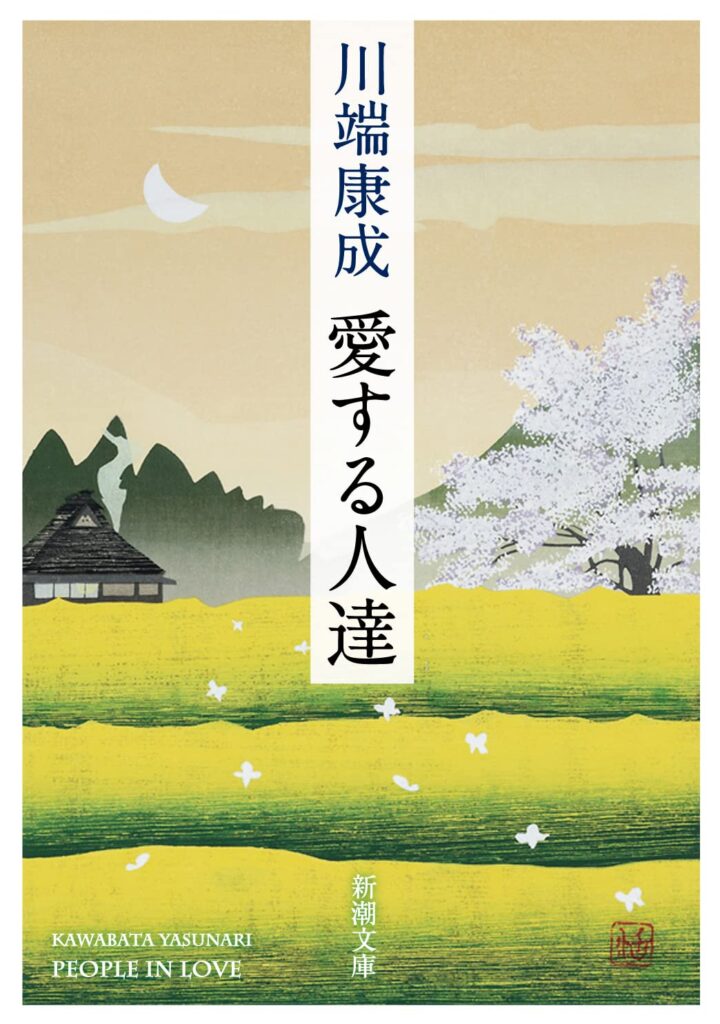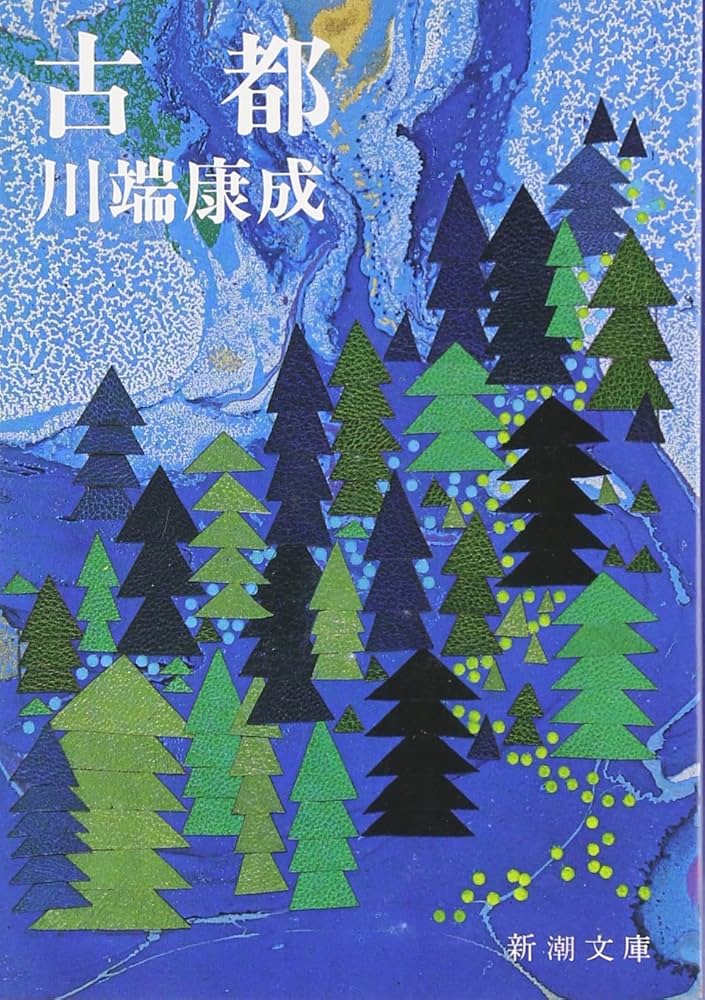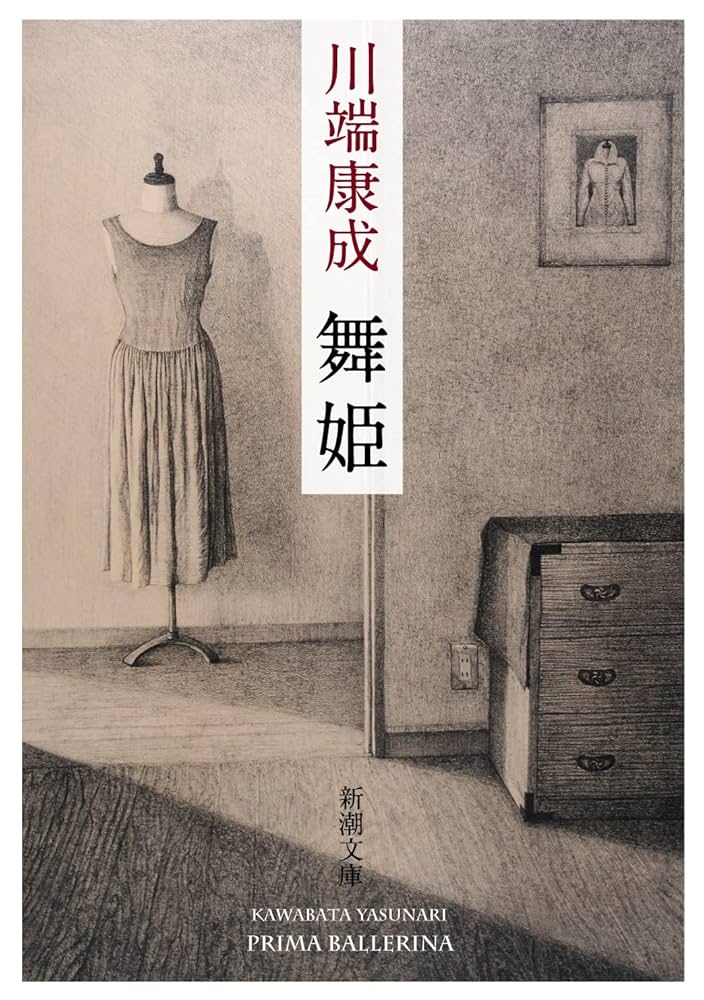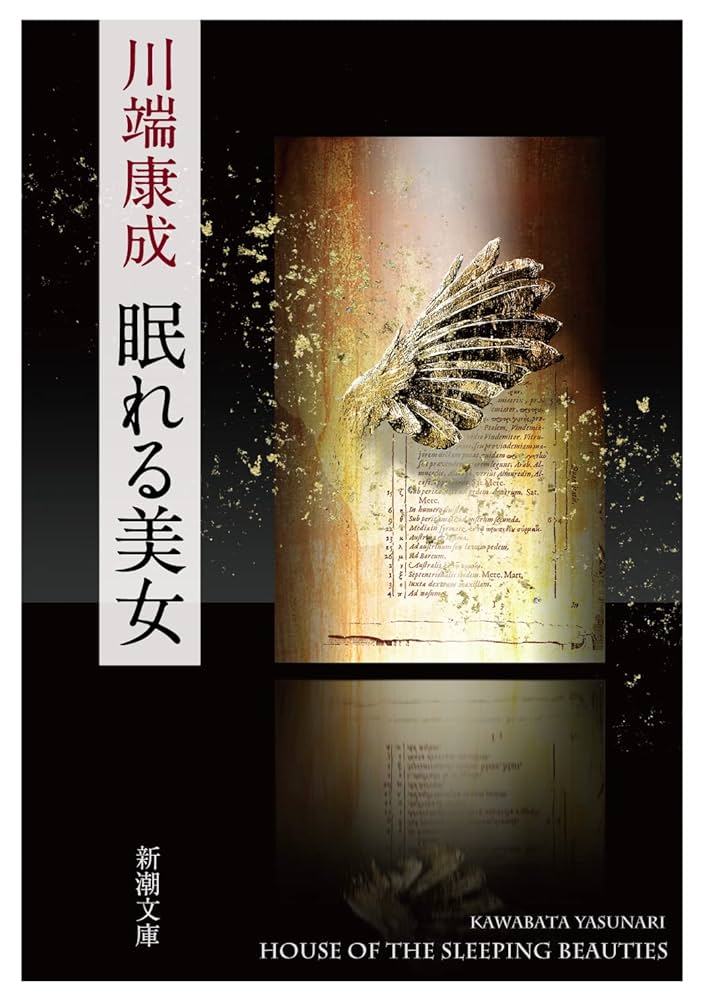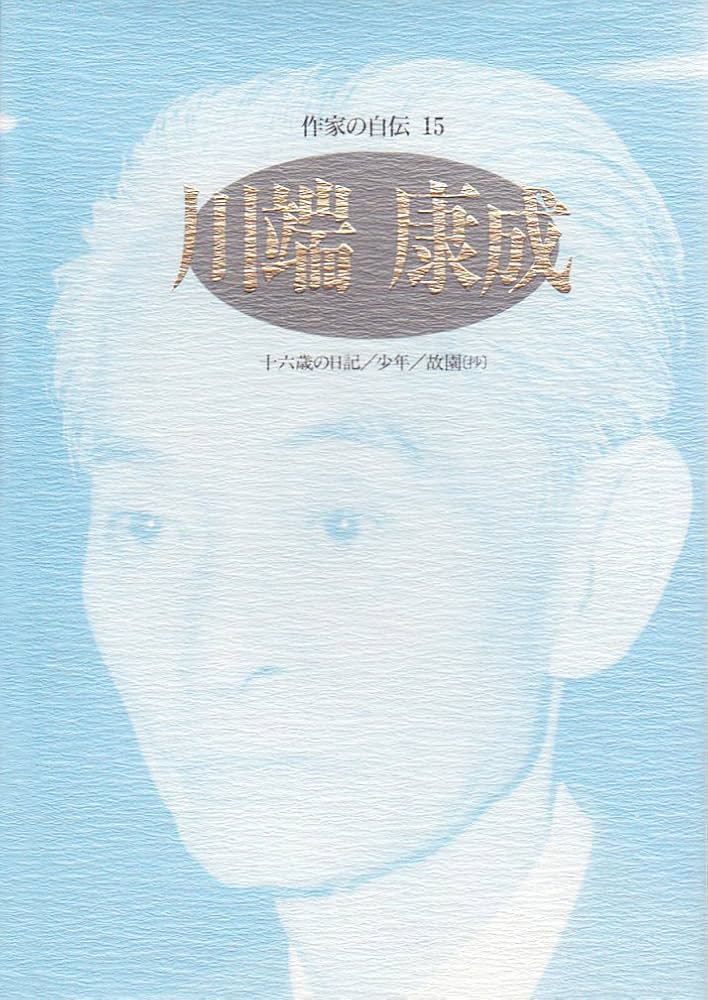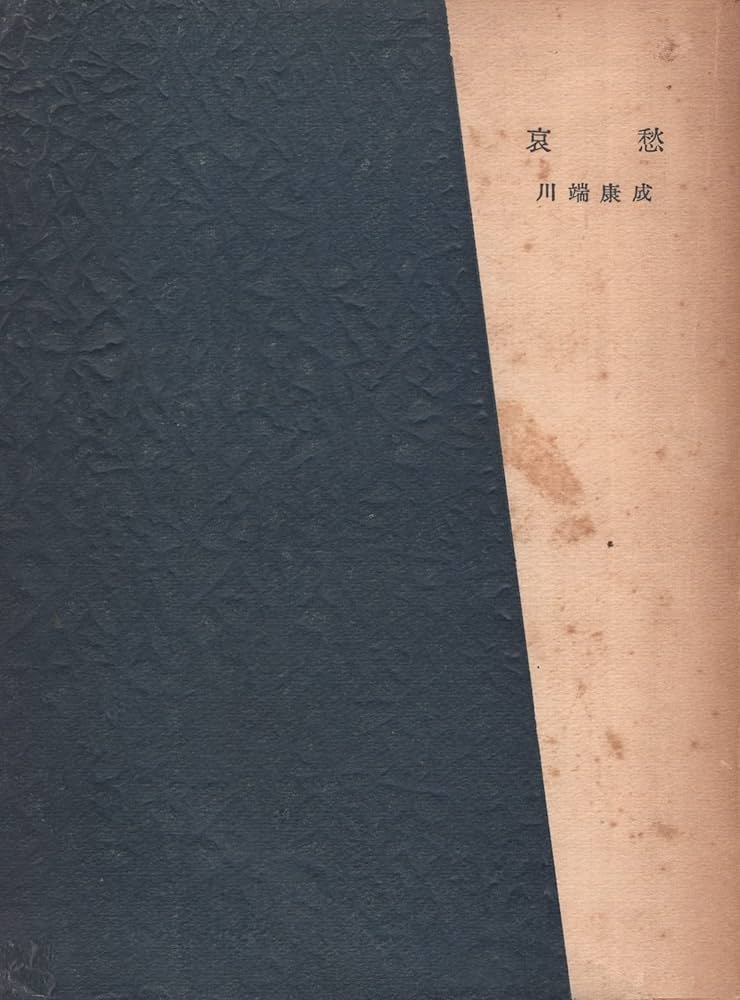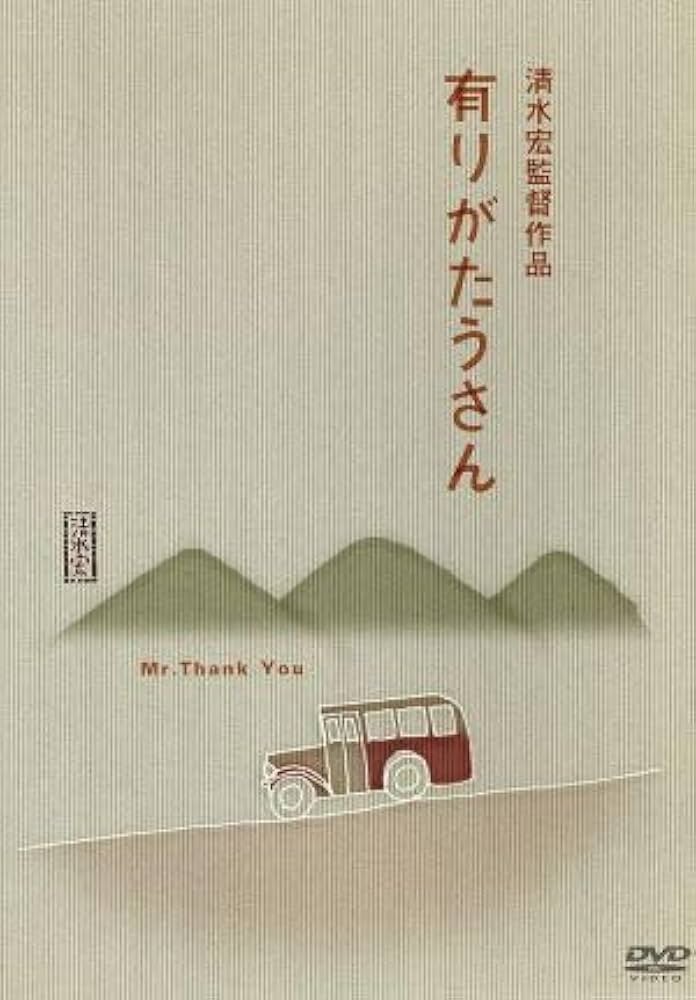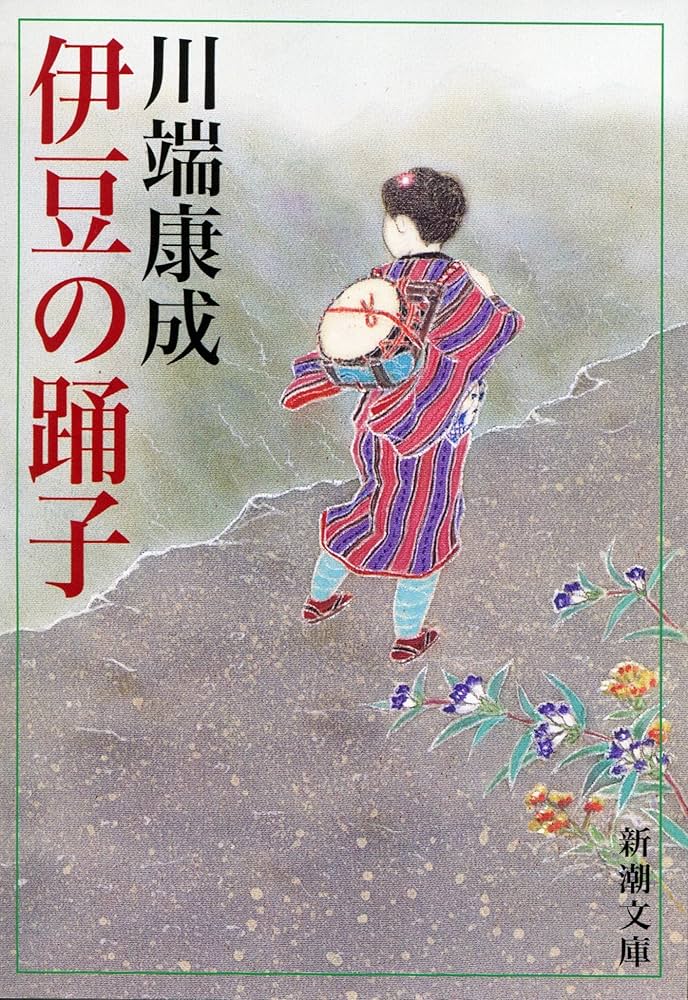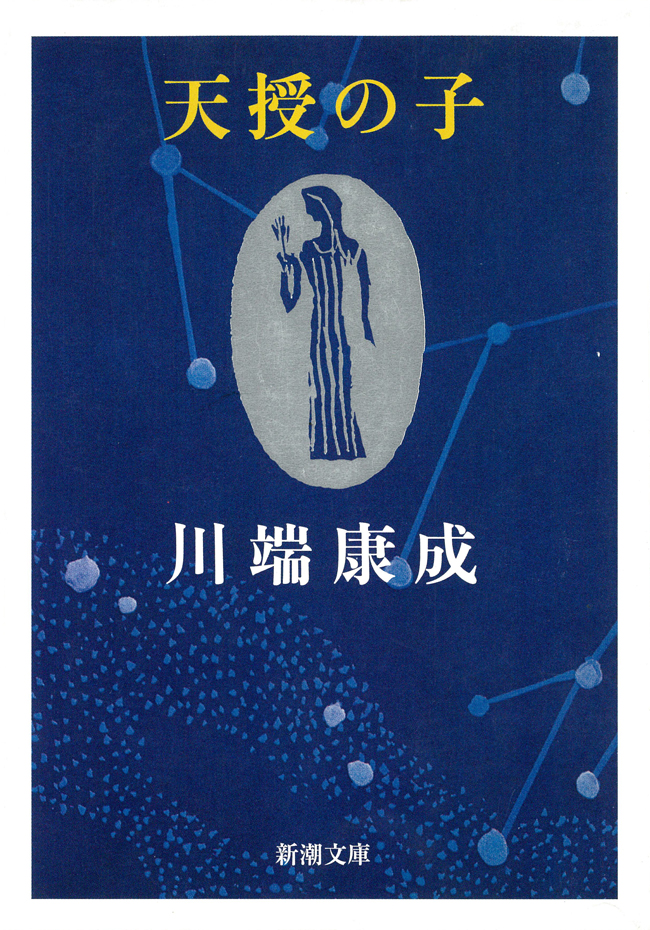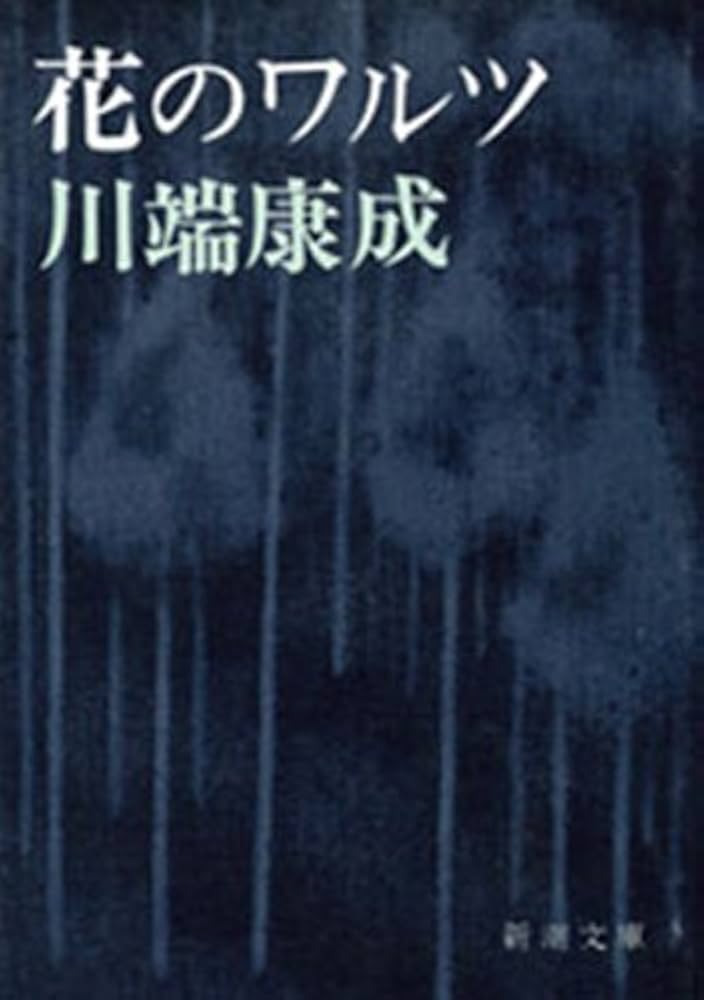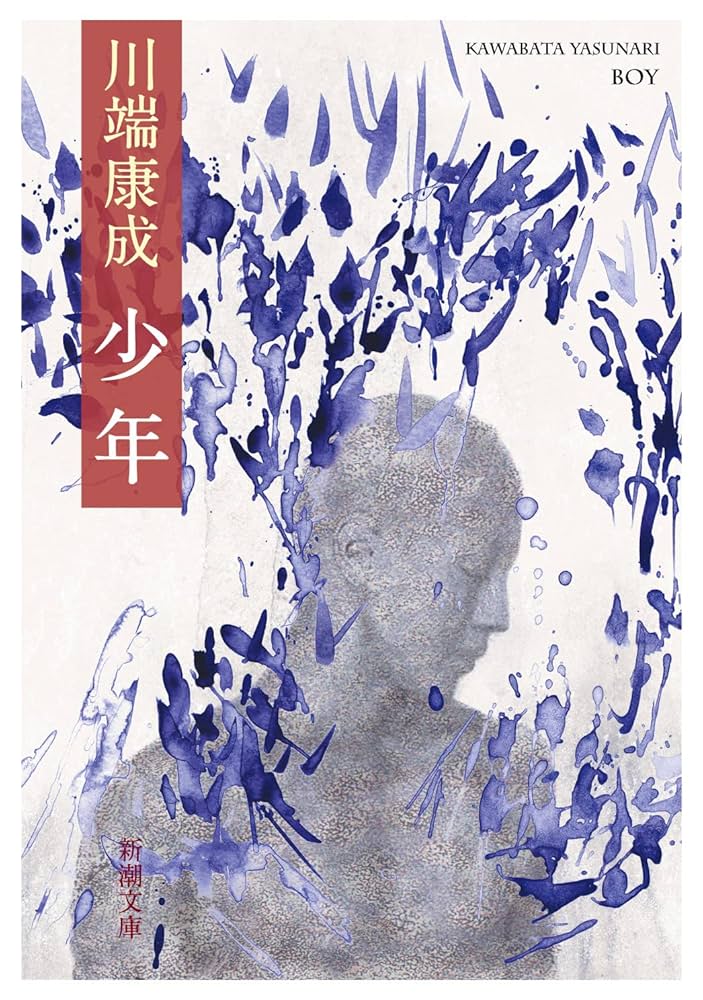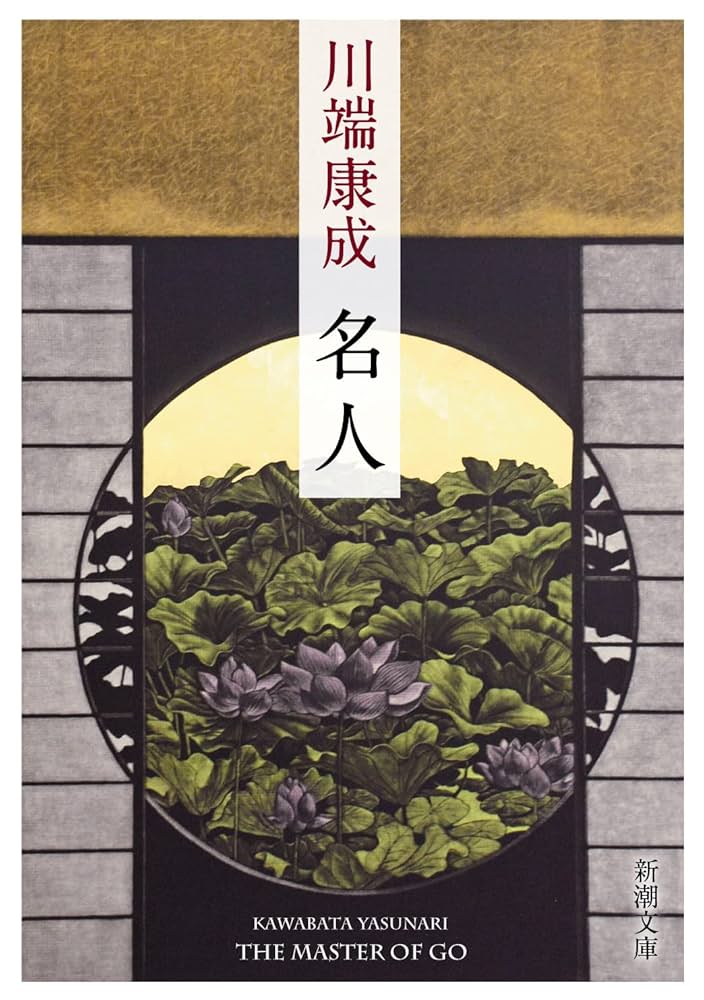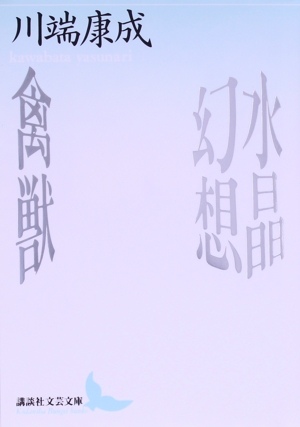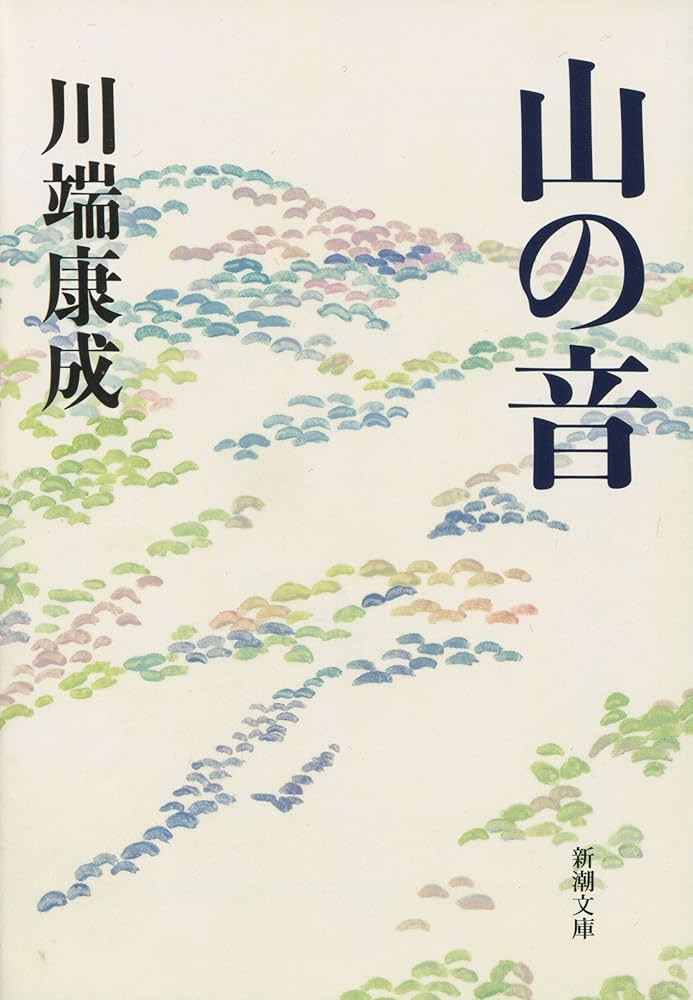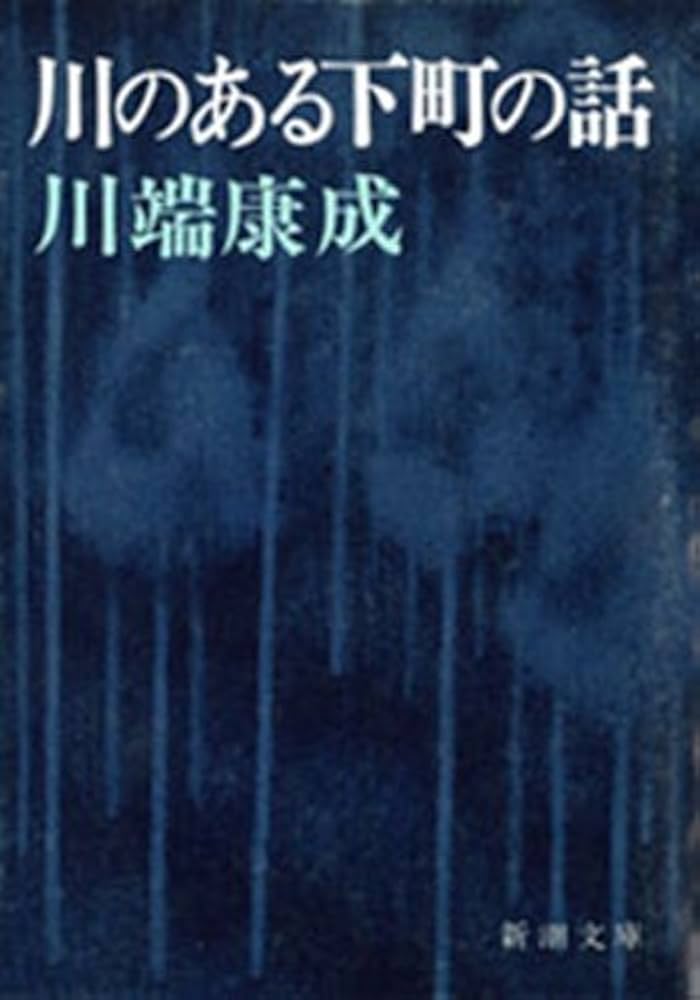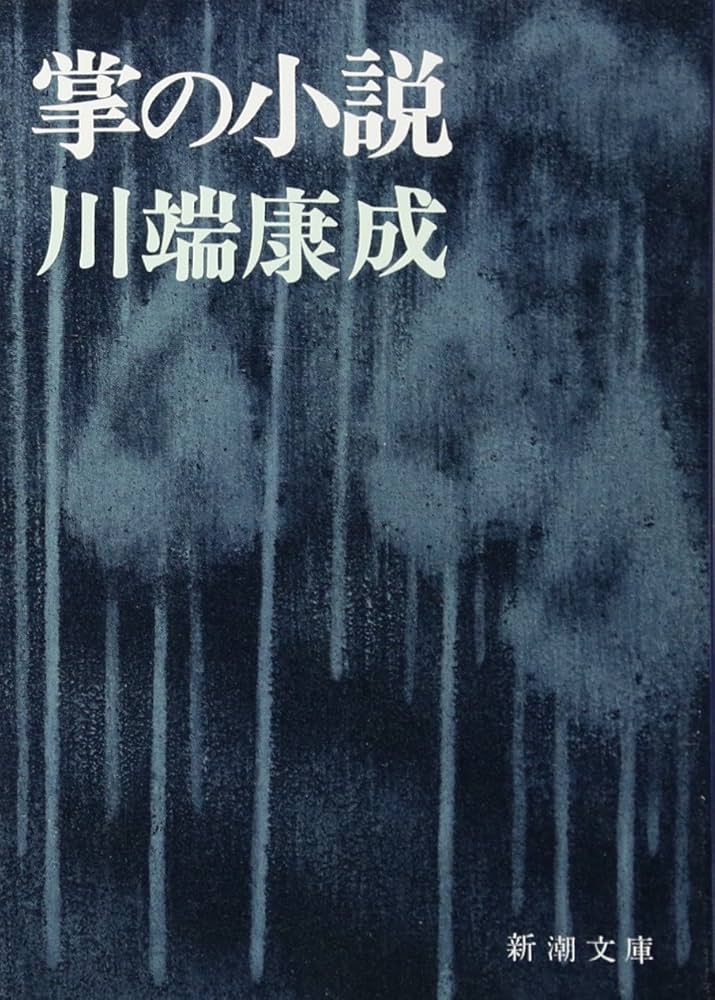小説「東京の人」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「東京の人」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
この物語は、戦後の混沌とした東京を舞台に、一つの屋根の下に暮らすことになった、いびつな家族の姿を描いています。法的に夫婦ではない男女と、それぞれが抱える子供たち。彼らが織りなす複雑な人間関係は、やがて緩やかに、しかし決定的に崩壊へと向かっていきます。
新聞連載小説という形式もあって、物語は次々と起こる事件で読者を惹きつけますが、その通俗的な展開の奥には、川端康成特有の鋭い美意識と、人間の心に潜むどうしようもない虚無が冷徹に描き出されているのです。これは単なる家庭劇ではありません。
この記事では、そんな『東京の人』の物語の核心に触れるネタバレを含みつつ、その魅力を深く掘り下げていきます。登場人物たちの心の動きや、物語に込められた意味を、じっくりと考えてみたいと思います。
「東京の人」のあらすじ
物語の中心にいるのは、出版事業に失敗し、どこか影のある男・島木俊三と、戦争で夫を亡くしながらも宝石販売員としてたくましく生きる女性・白井敬子です。二人は恋人として、敬子の家で一緒に暮らし始めます。俊三には娘の弓子、敬子には娘の朝子と息子の清がおり、彼らは血の繋がらない奇妙な家族としての生活を送ることになります。
しかし、その生活は平穏ではありませんでした。事業の失敗から立ち直れない俊三は、一家の大黒柱としての役割を果たせず、その負い目は彼の心を蝕んでいきます。対照的に、敬子は商才を発揮し、一家の経済を支える存在となっていきます。この力関係の歪みは、二人の間に見えない溝を深くしていきました。
そんな中、俊三は追い詰められた末、会社の金を持ち出して忽然と姿を消してしまいます。残された家族は、彼が自ら命を絶ったのではないかと考え、遺体のないまま葬儀を行います。一家の主を失ったことで、この脆い家族の均衡は、いよいよ大きく崩れ始めるのです。
俊三の不在という大きな空白は、残された人々の心に新たな波紋を広げます。特に、女手一つで家族を支えなければならなくなった敬子の心には、孤独と不安が深く影を落とします。そんな彼女の前に、一人の若く魅力的な青年が現れたことで、物語は誰も予期しなかった方向へと大きく動き出します。
「東京の人」の長文感想(ネタバレあり)
『東京の人』は、戦後の東京を舞台にした、一つの家族の崩壊の物語です。しかし、その内実は、単なる家庭のいざこざを描いたものではありません。ここからは物語の核心に触れるネタバレも交えながら、この作品が持つ深い奥行きについて、じっくりと語っていきたいと思います。
まず、物語の核となる島木俊三と白井敬子の関係を見てみましょう。俊三は事業に失敗した虚無的な男、敬子は夫を亡くし、子供を抱えながらも力強く生きる女性です。二人は恋人として同居しますが、その家には「島木」と「白井」という二つの表札が並んで掲げられています。この二つの表札こそ、彼らが決して一つの「家族」にはなれない、仮初めの関係であることを示しているのです。
このいびつな家庭は、戦後の日本が抱えていた家族という制度の揺らぎを映し出しているように思えます。伝統的な家父長制が崩れ、新しい家族の形が模索される中で、彼らは寄り集まっただけの、継ぎ接ぎの共同体に過ぎませんでした。その中で繰り広げられる激しい感情のぶつかり合いは、当時の社会が抱えていた倫理観の揺らぎそのものだったのかもしれません。
さらに、この家では伝統的な男女の役割が逆転しています。家計を支えるべき俊三は甲斐性を失い、逆に敬子が一家の経済的な柱となっています。この逆転が、物語に絶え間ない緊張感を与えています。俊三の無責任な行動は、単なる彼の性格の問題ではなく、社会の変化の中で男性としての存在価値を見失った者の悲鳴のようにも聞こえるのです。彼の口から出る虚無的な言葉は、彼の心が壊れていく音そのものでした。
そして、この不安定な家庭で生きる子供たちもまた、それぞれに深い葛藤を抱えています。彼らは親たちの愛憎劇の傍観者ではなく、その渦に巻き込まれ、運命を狂わせていく存在として描かれます。
俊三の娘である弓子は、物語の中で「聖処女」と評されるほどの純真な少女です。彼女は血の繋がらない継母の敬子を心から慕っています。この純粋さは、川端作品にたびたび登場する、儚く美しい少女像そのものです。川端康成という作家は、若さや純潔といった汚れのない美しさと、それが無残に破壊される様を、冷たいほどに見つめ続ける作家でした。
弓子という存在は、まさにその美学を体現しています。彼女の敬子への無垢な愛と、青年医師・田部昭男へ抱く淡い恋心。しかし、その清らかな世界は、ある日突然、決定的に破壊されます。ここからがこの物語の重要なネタバレになりますが、彼女が最も信頼していた敬子と、密かに想いを寄せていた昭男が恋人同士であるという事実を、弓子は偶然にも目撃してしまうのです。この瞬間、弓子の世界は崩壊します。彼女の家出は、大人の世界の身勝手さが、いかに子供の魂を打ち砕くかという、この物語の悲劇性を象徴する出来事でした。
一方、敬子の娘である朝子は、弓子とは対照的に奔放で現代的な女性、「山猫タイプ」と評されます。新劇の女優として自立しようとする彼女は、当時の「新しい女性」の象徴とも言えます。しかし、同僚の俳優の子を身ごもった彼女は、相手の無情な言葉によって中絶を余儀なくされます。自由を手に入れたはずの女性が、結局は男性中心の論理に翻弄される。この現実は、彼女の心に深い傷を残します。そしてこの悲劇は、後に母である敬子にも繰り返されるという、不吉な響きを帯びていくのです。
敬子の息子である清は、この家庭の中で静かな観察者の役割を担います。彼は血の繋がらない妹の弓子に密かな恋心を抱き、母と昭男の関係には批判的な目を向けています。彼はこの崩れゆく家における、無力な良心と言えるかもしれません。しかし、彼の正しさは状況を何一つ変えることができません。その姿は、激しい感情が渦巻く世界で、静かな良識がいかに無力であるかを際立たせています。
物語の展開を決定的に動かすのが、小林みね子と田部昭男という二人の外部の存在です。みね子は俊三の会社の事務員で、彼の才能に憧れ、密かに愛し続けていました。彼女の献身的な愛情は、結果的に俊三が社会から完全に逃避し、虚無へと旅立つことを後押ししてしまいます。
そして青年医師の田部昭男。彼の若さと生命力は、夫代わりの俊三を失った敬子の心を強く惹きつけ、二人は年の差を超えた激しい恋に落ちます。敬子にとって、それは生きるためのエネルギーを求める必死のあがきでした。しかし、この恋愛こそが、敬子と弓子の母娘にも似た絆を無残に引き裂き、弓子を絶望の淵へと突き落とすのです。まさに、この二人の存在が、家庭内に潜んでいた崩壊の種子を発芽させてしまったのでした。
ここからは、物語の結末に至るまでの、さらに詳細なネタバレを含みます。弓子が敬子と昭男の関係を知って家出したことで、登場人物たちの運命の歯車は狂ったまま加速していきます。昭男の兄は、何も知らずに昭男と弓子の縁談を持ちかけます。この提案は、秘密の恋人たちを窮地に追い込みました。
罪悪感に苛まれる敬子は、その苦悩のさなか、自分が昭男の子を身ごもっていることに気づきます。そして彼女は、この袋小路を断ち切るために、堕胎するという悲痛な決断を下すのです。これは娘の朝子が経験した悲劇の繰り返しであり、女性が強いられる犠牲の連鎖を強く印象付けます。このネタバレは、物語の最も痛ましい部分の一つと言えるでしょう。
そんな激情のさなか、死んだと思われていた俊三が、浮浪者同然の姿で発見されます。しかし、彼の帰還は希望にはなりませんでした。彼の魂は完全に抜け殻となっており、再会した娘の弓子との間には、埋めようのない「遠いへだたり」ができていました。彼はただ、無へと沈んでいただけだったのです。
そして物語は、あまりにも冷たい結末を迎えます。敬子たちが再び俊三を訪ねると、彼の姿はすでになく、最後まで彼に尽くした元事務員のみね子と共に去った後でした。ベッドには短い手紙が残されているだけ。俊三とみね子を乗せた船が、どこへともなく出航していく場面で、物語は幕を閉じます。彼は「何んに希望をたくすことなく」、ただ虚無の中へと旅立っていったのです。いかなる救済も再生もない、あまりにも空虚な結末です。
『東京の人』は、新聞連載という特性上、次々と事件が起こるメロドラマのような筋書きを持っています。失踪、不倫、中絶、衝撃的な目撃シーン。しかし、これを単なる通俗小説と片付けてはいけません。川端康成は、この大衆的な器を用いて、彼が描き続けた人間の根源的な虚無や孤独を、壮大なスケールで描き切ったのです。
この物語の混沌とした筋書きは、そのまま戦後東京の混沌を映し出しています。そして、その中心にあるのは、やはり「純粋さの破壊」という、川端文学に一貫して流れるテーマです。この長大な物語は、聖処女のような少女・弓子の純粋な世界が、大人たちのエゴによっていかに無残に壊されていくかを、段階的に描くための巨大な装置だったのかもしれません。
弓子の無垢な視線が、彼女自身の世界を破壊してしまう。この悲劇的な構造こそが、本作を紛れもなく川端康成の作品たらしめているのです。『東京の人』は、作家が生涯をかけて見つめ続けた、美しくも残酷なテーマの、最も壮大で、そして最も救いのない探求の記録と言えるでしょう。
まとめ
小説『東京の人』は、戦後の東京を舞台に、一つの疑似家族が崩壊していく様を克明に描いた物語です。そのあらすじは、通俗的なメロドラマのようでありながら、登場人物たちの心理描写は鋭く、人間の心の暗部を深くえぐり出しています。
物語の核心には、常に「救いのなさ」が横たわっています。責任から逃避し虚無へと沈む男、愛に生きようとしながらも裏切りを重ねてしまう女、そして大人たちの身勝手さによって純粋な心を打ち砕かれる子供たち。誰一人として、本当の意味で救われることはありません。結末のネタバレを知ると、そのやるせなさは一層深まります。
しかし、この救いのなさにこそ、本作の価値があるのかもしれません。崩壊していく人間関係の中に、川端康成は、美しさの儚さや、人が生きることの根源的な孤独を映し出しました。読み終えた後に残るのは、ずっしりと重い問いかけと、忘れがたい余韻です。
もしあなたが、人間の感情の複雑さや、ままならない人生の真実に触れるような物語を求めているのなら、この『東京の人』は、きっと心に残る一冊になるはずです。ぜひ一度、このどうしようもない人々の物語に触れてみてください。