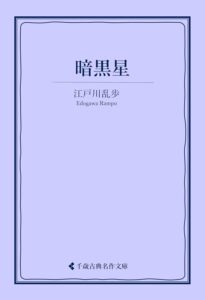 小説「暗黒星」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「暗黒星」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
江戸川乱歩が世に送り出したこの物語は、1939年、雑誌「講談倶楽部」で一年間にわたり読者を引きつけました。戦前の不穏な空気が漂い始める中で書かれた、乱歩にとっては特別な時期の作品の一つと言えるでしょう。創元推理文庫のシリーズでは第15巻に、もう一つの作品「何者」と一緒に収められています。
物語の舞台は、古い西洋館が点在する麻布の一角にある「伊志田屋敷」。そこで起こる不可解な出来事と、名探偵・明智小五郎の推理が描かれます。不吉な夢、姿なき犯人、そして次々と起こる悲劇…。読者を怪奇と謎の世界へと誘う、乱歩ならではの魅力が詰まっています。
この記事では、物語の詳しい筋道と、その結末までを詳しくお伝えします。さらに、読み終えて私が抱いた様々な思いや考察を、たっぷりと語らせていただいています。これから読む方も、すでに読まれた方も、ぜひお付き合いください。
小説「暗黒星」のあらすじ
物語は、東京麻布にある大きな西洋風の「伊志田屋敷」から始まります。この屋敷に住む青年、伊志田一郎が名探偵・明智小五郎のもとを訪れ、「家族が次々と殺される恐ろしい夢を見た」と相談するところから、不穏な空気が漂い始めます。屋敷には父・鉄造、後妻の母・君代、姉・綾子、妹・鞠子、そして祖母が暮らしていました。一郎の相談に、明智はまだ事件が起きていない以上は動けないとしながらも、何か胸騒ぎを感じるのでした。
その予感は的中します。一郎から「屋敷に怪しい人影が…あいつが来た!」という切羽詰まった電話が入った直後、争う物音が。明智が屋敷に駆けつけると、一郎が右目と胸を刺され倒れていました。幸い命に別状はなかったものの、明智はカーテンの影に黒ずくめの不審な人影を目撃。追跡しますが、廊下の角で見失ってしまいます。一郎の部屋では、壁にかけられた自身の写真の右目から、まるで血の涙のように赤い絵の具が流れているのが見つかり、犯人からの不気味なメッセージに一同は戦慄します。
明智は医者に扮して屋敷に泊まり込み、警護にあたります。ある夜、屋敷の円塔の窓に怪しい光を見た明智は、そこで綾子が誰かと光で合図を送っているような場面に遭遇します。しかし、綾子はその事実を頑なに否定するのでした。数日後、明智が屋敷内を見回っていると、浴室から出てきた黒ずくめの人物と遭遇。犯人は拳銃を発砲し、明智は肩を撃たれ負傷、その隙に逃走します。そして浴室では、胸を刺された君代の遺体が発見されるのでした。
明智が入院している間に、さらなる悲劇が伊志田家を襲います。今度は妹の鞠子が、鍵のかかった自室で胸を撃たれて亡くなっているのが見つかります。部屋は密室状態。しかし、一郎は隣の綾子の部屋との壁に隠された穴があり、そこから銃を発射する仕掛けが施されていたのではないかと推理します。この仕掛けを知り、実行できるのは綾子だけのように思われましたが、一郎は姉が犯人だとは信じられないと語ります。
事態はさらに混迷を深めます。屋敷の塔から送られる光信号の相手を探っていた明智の助手・小林少年は、塀を乗り越え屋敷に侵入した男・荒川庄太郎が何者かに射殺される現場を目撃します。その直後、屋敷から綾子と一郎の姿が消えていました。翌日、一郎は物置で麻酔薬で眠らされているところを発見されますが、綾子の行方は依然として不明。警察は、荒川と恋仲だったらしい綾子が、一連の事件の犯人で逃亡したと断定するかに見えました。
しかし、事件はまだ終わりません。鉄造と一郎のもとには脅迫電話が続き、屋敷のあちこちで黒い人影が目撃され、二人は精神的に追い詰められていきます。そしてついに、鉄造と一郎が再び姿を消します。一郎は古井戸の底で発見され、警察が鉄造を探す中、屋敷内に現れた黒い人物を追い詰めると、それは物置の隠し扉から地下道へと消えます。地下道の先で待ち構えていたのは、なんと変装した明智小五郎でした。彼は地下室に監禁されていた鉄造と綾子を無事に救出します。関係者が揃ったところで、明智は事件の真相を語り始めます。真犯人は、綾子に罪を着せようと画策し、荒川を利用して殺害した…伊志田一郎、その人であると。そして、一郎が実は鉄造の実子ではなく、鉄造に恨みを持つ男・瀬下良一の子であり、赤ん坊の頃に入れ替えられ、復讐の道具として育てられたという驚愕の事実が明かされるのでした。
小説「暗黒星」の長文感想(ネタバレあり)
さて、ここからは江戸川乱歩の「暗黒星」を読み終えての、私の個人的な思いや考察を、物語の結末に触れつつ、じっくりと語っていきたいと思います。この作品は、乱歩が戦前に手がけた最後の長編の一つであり、彼のキャリアの中でも少し特殊な位置づけにあるように感じられます。発表された時代の空気も色濃く反映されているのかもしれません。
まず、この物語の導入部、伊志田一郎が明智小五郎のもとを訪れる場面から、すでに不穏な、そしてどこか作為的な雰囲気を感じ取った読者も少なくないのではないでしょうか。一郎の語る「家族が殺される夢」という相談内容自体が、いかにもこれから起こる惨劇を予兆させるものであり、ミステリのお約束とも言えますが、同時に彼の存在そのものが、物語の中心にある種の「歪み」をもたらしているように思えるのです。参考にした文章にもありましたが、一郎の容姿がやけに美しく描写されている点も、読者に「何かある」と感じさせる要因の一つでしょう。美貌の青年が抱える秘密、というのは、乱歩作品に限らず、物語における魅力的なフックとなり得ます。
物語が進むにつれて、一郎は繰り返し黒ずくめの犯人に襲われますが、不思議と致命傷は避け、生き延びます。右目を傷つけられ、胸を刺され、麻酔薬で眠らされ、古井戸に落とされ…これでもかとばかりに被害者としての立場を強調される一方で、そのどれもが決定的な結末には至らない。この展開は、読者に対して「彼が真の被害者なのか?」という疑念を抱かせるには十分すぎるほどです。もちろん、名探偵・明智小五郎が間一髪で救出したり、幸運が重なったり、という説明は可能ですが、あまりにも都合の良い展開が続くと、そこに作者の意図、つまり「一郎を犯人ではないと思わせたい、あるいは逆に怪しいと思わせたい」という狙いが見え隠れするように感じられます。
そして、物語の核となるトリックや謎解きについてですが、本作はいわゆる「本格探偵小説」的な、精緻な論理や物理的なトリックを前面に出した作品とは少し趣が異なります。鞠子の密室殺人の謎は、隣室との壁の穴を利用した仕掛けであり、ある程度は納得できるものの、その仕掛けを準備し、鞠子に穴を覗かせるよう仕向けるタイミングなど、ややご都合主義的な部分も感じられます。また、犯人が屋敷内を神出鬼没に移動できた理由が「地下道」であったというのも、古典的ながら、やや安易な解決策に思えなくもありません。これらの要素は、乱歩自身が後に「あまり調子の出ない執筆だった」「熱のない、長くもないくせに冗長な感じ」と述懐していることとも繋がっているのかもしれません。時節柄、自由な創作が難しかったという背景もあるのでしょう。
しかし、だからといって「暗黒星」が魅力に欠ける作品かと言えば、決してそうではありません。むしろ、乱歩が得意とする怪奇趣味や、ゴシックロマン的な雰囲気が色濃く漂っている点は、特筆すべき魅力だと私は思います。物語の舞台となる塔のある西洋館「伊志田屋敷」の設定は、それ自体が閉鎖的で不気味な空間を演出し、事件の陰惨さを引き立てています。特に、冒頭で一郎が見る夢の描写や、壁にかけられた一郎自身の写真の右目から赤い絵の具が流れる場面などは、視覚的に訴えかける強烈なイメージ喚起力があり、読者の不安感を煽ります。フィルムが焼けただれていくような、じわじわと迫る恐怖。これぞ乱歩、と感じさせる瞬間です。
また、犯人である一郎のキャラクター造形と、その動機にも注目すべき点があります。彼が実は伊志田家の血を引かず、父・鉄造に恨みを持つ瀬下良一という男によって、復讐の道具として赤ん坊の頃に入れ替えられていた、という出生の秘密。これは、単なるミステリの犯人というだけでなく、運命に翻弄された悲劇的な人物としての側面を彼に与えています。瀬下の歪んだ復讐心を受け継ぎ、自らの手で伊志田家を破滅させようとする一郎の姿は、哀れであり、同時に恐ろしくもあります。「魔術師」でも見られた「赤ん坊の入れ替え」というモチーフが再び用いられている点は、乱歩の中でよほど印象的な着想だったのかもしれませんね。育ての親への複雑な感情や、自らの出自を知った時の絶望など、一郎の内面に渦巻くであろう葛藤を想像すると、物語に深みが増します。
そして、名探偵・明智小五郎の存在です。本作における明智は、序盤で負傷し一時的に戦線離脱するという、やや珍しい展開を見せます。しかし、病院のベッドの上からでも事件の真相を見抜こうと推理を巡らせ、助手の小林少年や協力者の越野を動かし、最終的には見事に犯人を追い詰めます。医者に変装して屋敷に潜入したり、最後は自ら黒ずくめの犯人に扮して地下道に現れたりと、その行動は相変わらず大胆不敵。一郎に対して、単なる探偵と容疑者という関係を超えた、どこか心理的な駆け引き、あるいは奇妙な共感のようなものを感じさせる描写も、本作の独特な味わいの一つと言えるでしょう。特に、一郎の美貌や知性に惹かれつつも、その裏に潜む邪悪さを見抜いていく過程は、スリリングです。
タイトルの「暗黒星」について、作中で明智は「まったく光のない星」「つい眼の前にいるようで、正体が掴めない。まったく光を持たない星、いわば邪悪の星だね」と説明しています。これは、まさに犯人である一郎のことを指していると言えるでしょう。彼は伊志田家の一員として、最も身近な存在でありながら、その内には深い闇と復讐心を秘め、誰にもその正体を知られることなく、計画を遂行しようとしていました。光を発しないがゆえに観測されにくい暗黒星のように、彼の邪悪さもまた、巧みに隠されていたのです。このネーミングセンスは、実に乱歩らしいと言えます。黒岩涙香による翻案小説のタイトルから着想を得た可能性も指摘されていますが、作品世界の本質を見事に捉えた、秀逸なタイトルだと思います。
一方で、物語の展開におけるいくつかの粗さや、登場人物の扱いの偏りも指摘せざるを得ません。特に、姉の綾子や妹の鞠子のキャラクター描写はやや薄く、事件の道具立てとして消費されてしまっている印象を受けます。綾子は犯人として疑われ、荒川との関係も匂わされながら、結局は監禁されていた被害者の一人であり、鞠子は密室殺人の被害者となる。彼女たちの内面や、一郎との関係性がもう少し深く描かれていれば、物語はより重層的になったかもしれません。また、祖母や使用人たちの存在感も希薄です。これは、やはり一郎と明智の関係性、そして一郎の復讐劇という中心的なテーマに焦点を絞った結果なのかもしれません。
乱歩自身が「熱がない」と評したように、彼の他の代表作、例えば「孤島の鬼」や「パノラマ島奇譚」のような、強烈なエロティシズムやグロテスクな描写、あるいは奇抜なトリックや壮大な幻想性は、本作では影を潜めています。時代の制約もあったのでしょうが、その分、文章は抑制が効いており、ある種の格調高さすら感じさせます。派手さはないものの、じっくりと読ませる力があり、怪奇的な雰囲気と心理描写によって、読者を物語世界に引き込みます。
犯人の見当が比較的早い段階でついてしまう、という点も、ミステリとしての完成度を問うならば、確かにマイナス要素かもしれません。しかし、「誰が犯人か」という謎解き以上に、「なぜ一郎は犯行に及んだのか」「彼の内なる闇とは何なのか」という動機の部分や、彼と明智との対決にこそ、本作の面白さがあるとも言えます。犯人が分かった上で読むことで、一郎の言動一つ一つに隠された意味を探ったり、彼の苦悩や狂気に思いを馳せたりすることもできるでしょう。
この作品を読むと、乱歩がいかに「雰囲気」を大切にする作家であったかを改めて感じます。論理的な整合性やトリックの斬新さもさることながら、古びた洋館、不気味な夢、姿なき犯人の影、地下道といったガジェットを駆使して、読者の心に直接訴えかけるような、怪しく、おどろおどろしい世界観を構築する手腕は見事です。エログロが控えめであるからこそ、純粋な怪奇小説としての側面が際立っているとも言えるかもしれません。
また、昭和初期という時代背景も、物語に独特の陰影を与えています。震災の傷跡が残る麻布の描写や、西洋文化への憧憬と古い因習が混在するような伊志田家の雰囲気は、どこか退廃的で、これから訪れる暗い時代を予感させるかのようです。一郎の復讐劇も、単なる個人的な恨みというだけでなく、時代の持つ閉塞感や歪みが、一人の青年の運命を狂わせた結果のようにも読み取れます。
「暗黒星」は、江戸川乱歩の作品群の中では、必ずしも最高傑作とは言えないかもしれません。乱歩自身も満足していなかったように、構成の甘さや展開の冗長さ、トリックの弱さといった欠点も散見されます。しかし、それを補って余りある、独特の怪奇的な雰囲気、ゴシックロマン的な魅力、そして犯人である一郎の悲劇的なキャラクター造形は、多くの読者を引きつけてやみません。私にとっては、乱歩長編の中でも、忘れがたい印象を残す作品の一つです。
特に、美貌の青年が抱える闇と、それを追う名探偵という構図は、非常に魅力的です。一郎の犯行が明らかになった後も、彼に対する単純な断罪ではなく、どこか憐憫や、歪んだ共感のようなものを感じてしまうのは、乱歩の人物描写の巧みさゆえでしょう。彼の犯した罪は許されるものではありませんが、その背景にある運命の残酷さを思うと、複雑な気持ちになります。まさに「暗黒星」の名が示す通り、光と闇が混濁した、一筋縄ではいかない物語なのです。
まとめ
江戸川乱歩の「暗黒星」は、1939年に発表された、彼の戦前最後の長編の一つです。物語は、麻布の古い西洋館「伊志田屋敷」で起こる連続殺人事件と、それに挑む名探偵・明智小五郎の活躍を描いています。不吉な夢から始まる一連の事件は、読者を怪奇と謎に満ちた世界へと引き込みます。
物語の筋道としては、伊志田家の長男・一郎が繰り返し襲われ、後妻の君代、妹の鞠子が次々と殺害されていきます。黒ずくめの犯人の影、塔からの怪しい光信号、そして密室の謎。明智小五郎は負傷しながらも推理を進め、屋敷に隠された地下道の存在を突き止め、ついに真犯人・一郎とその驚くべき動機を暴き出します。それは、出生の秘密と長年にわたる復讐計画でした。
この作品は、トリックの斬新さや論理的な整合性という点では、乱歩の他の代表作に及ばない部分もあるかもしれません。犯人の見当がつきやすいという側面もあります。しかし、塔のある洋館というゴシックロマン的な舞台設定、随所に散りばめられた怪奇趣味、そして美貌の犯人・一郎が抱える心の闇と悲劇的な運命は、他の作品にはない独特の魅力を放っています。
派手さはないものの、じっくりと読ませる筆致と、じわじわと忍び寄るような恐怖感は、乱歩ならではのもの。「暗黒星」というタイトルが示すように、光のない邪悪な存在の正体を探る、読み応えのある一作です。乱歩の怪奇世界に浸りたい方、そして複雑な人間ドラマに触れたい方におすすめしたい物語です。






































































