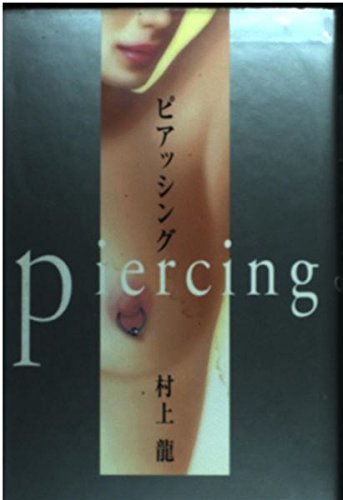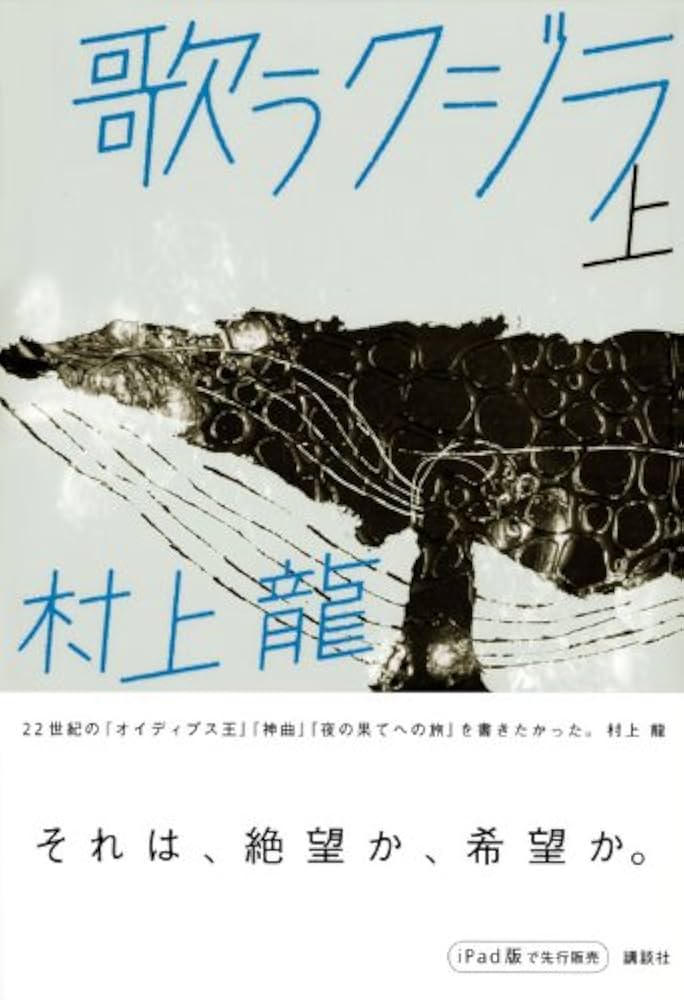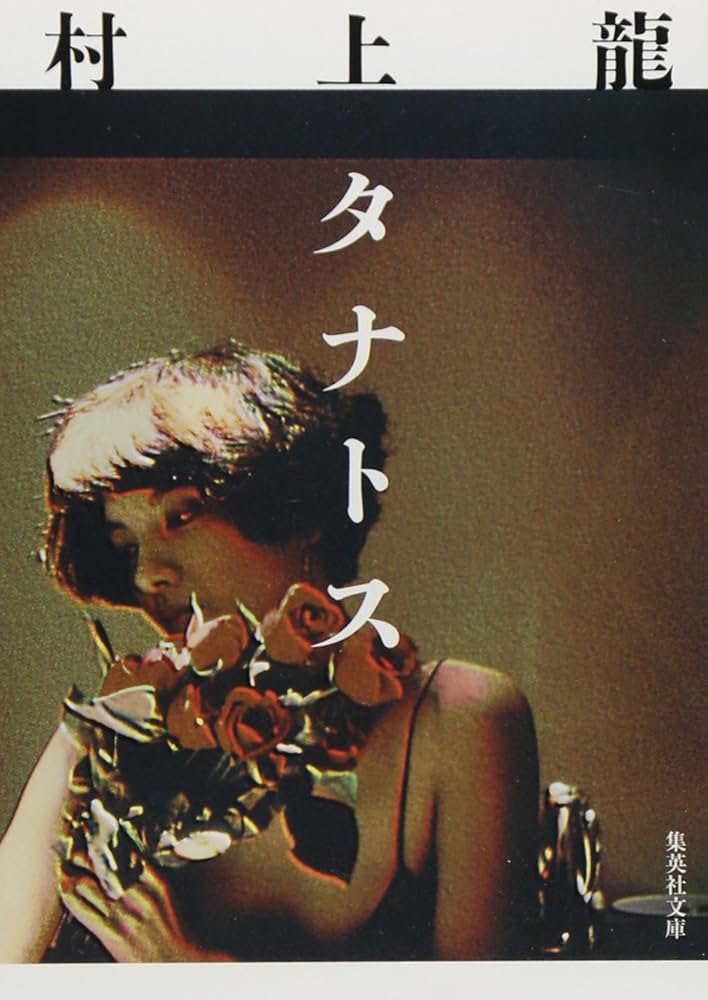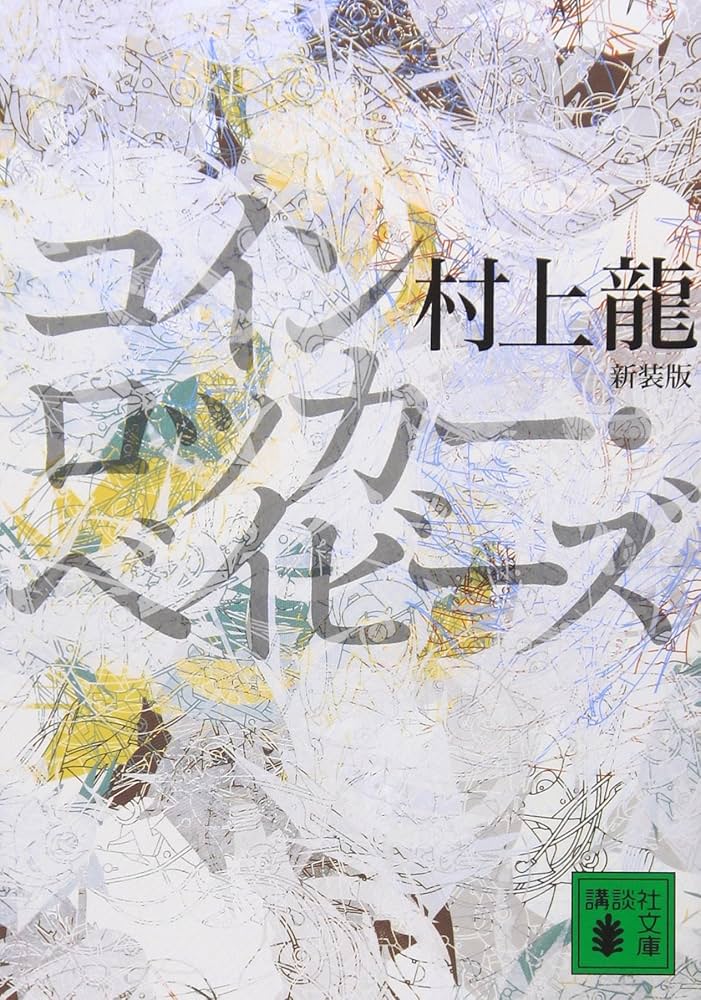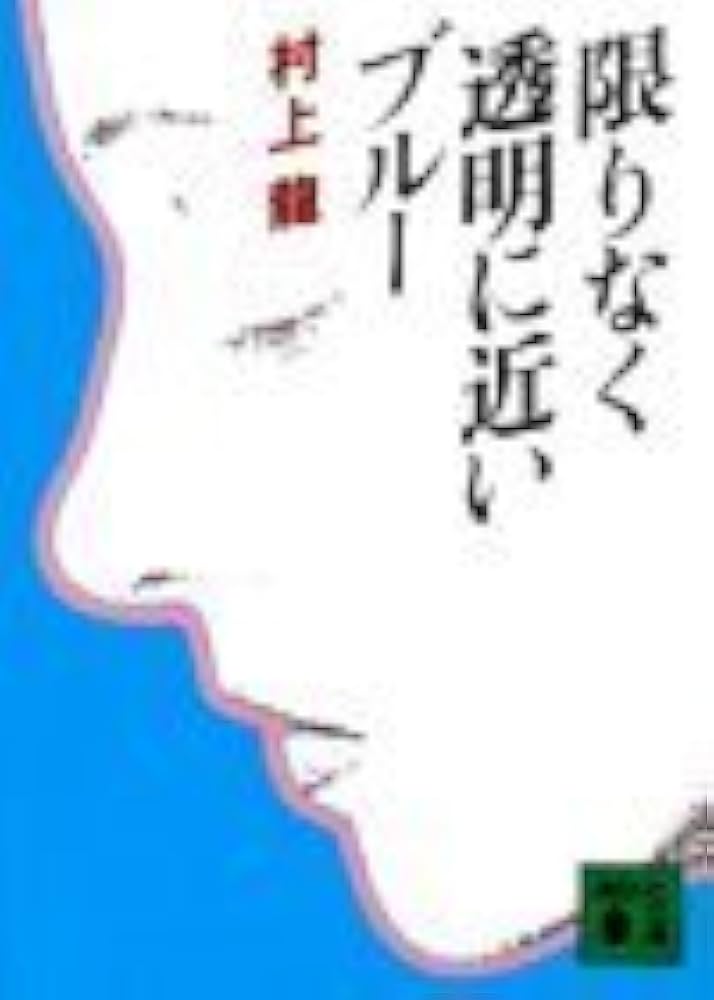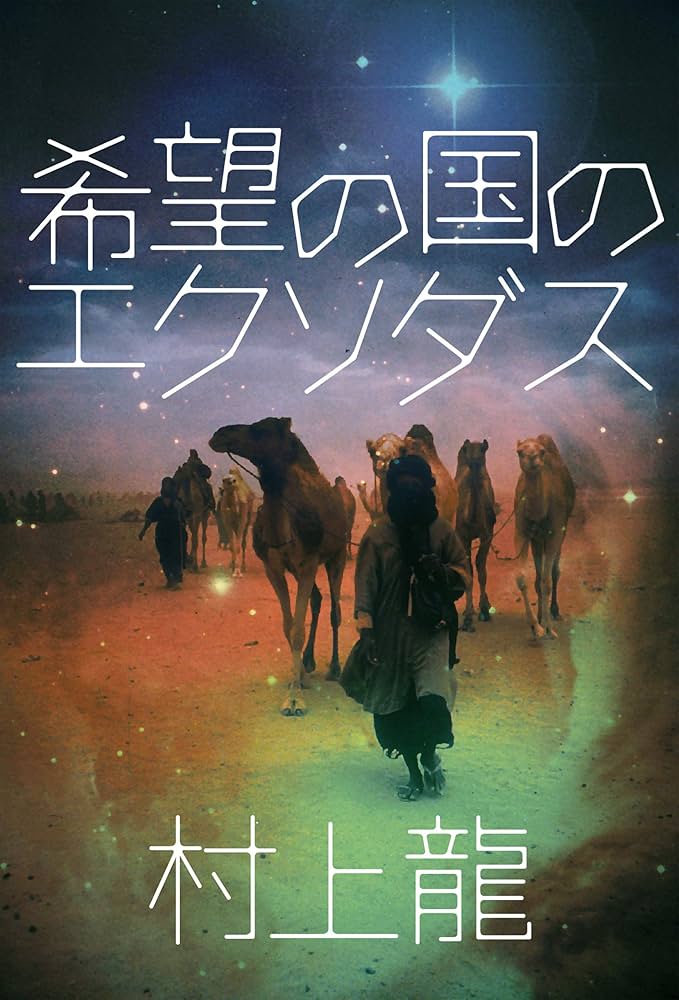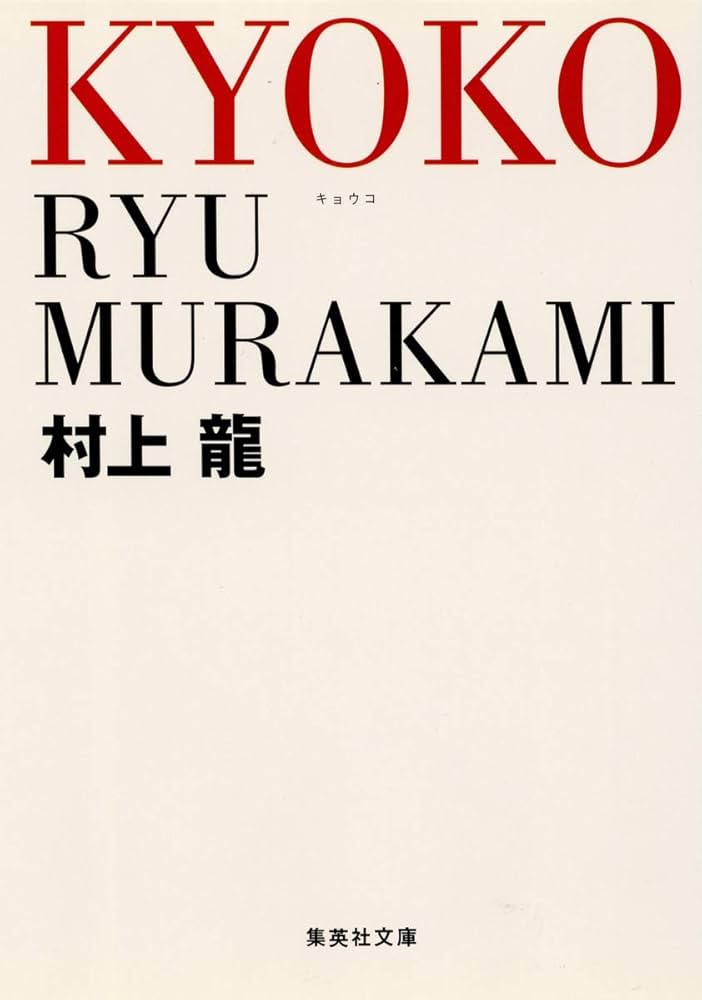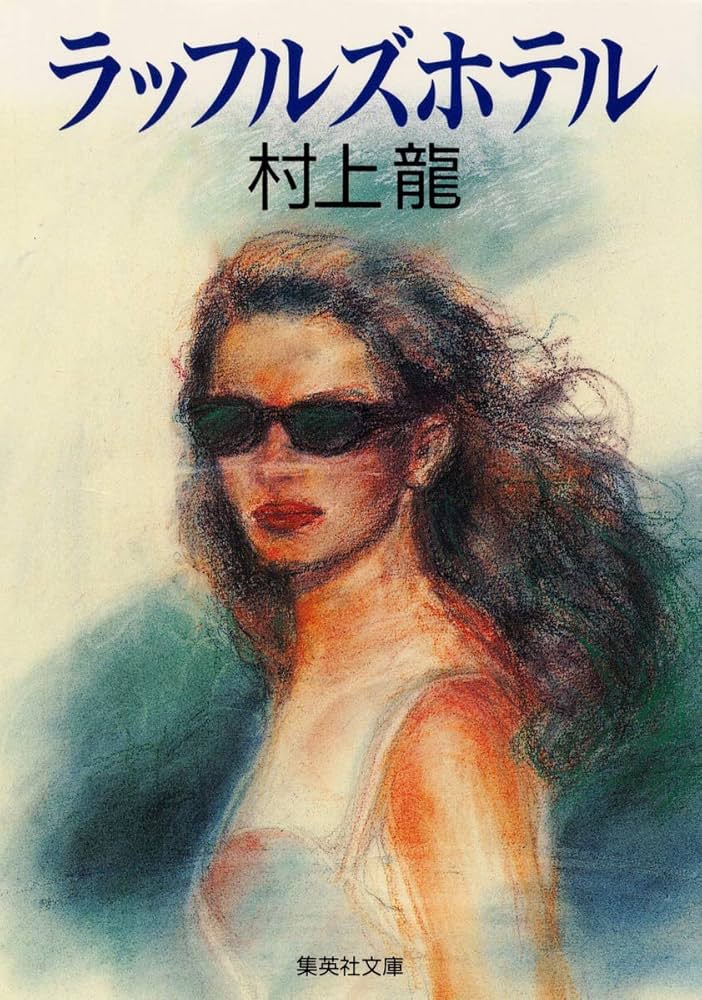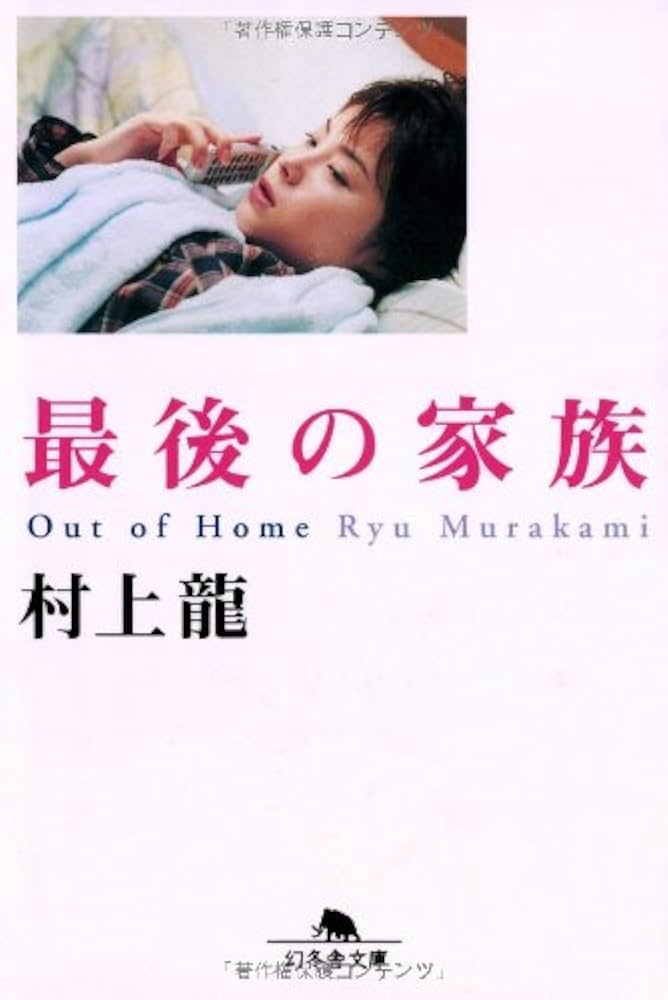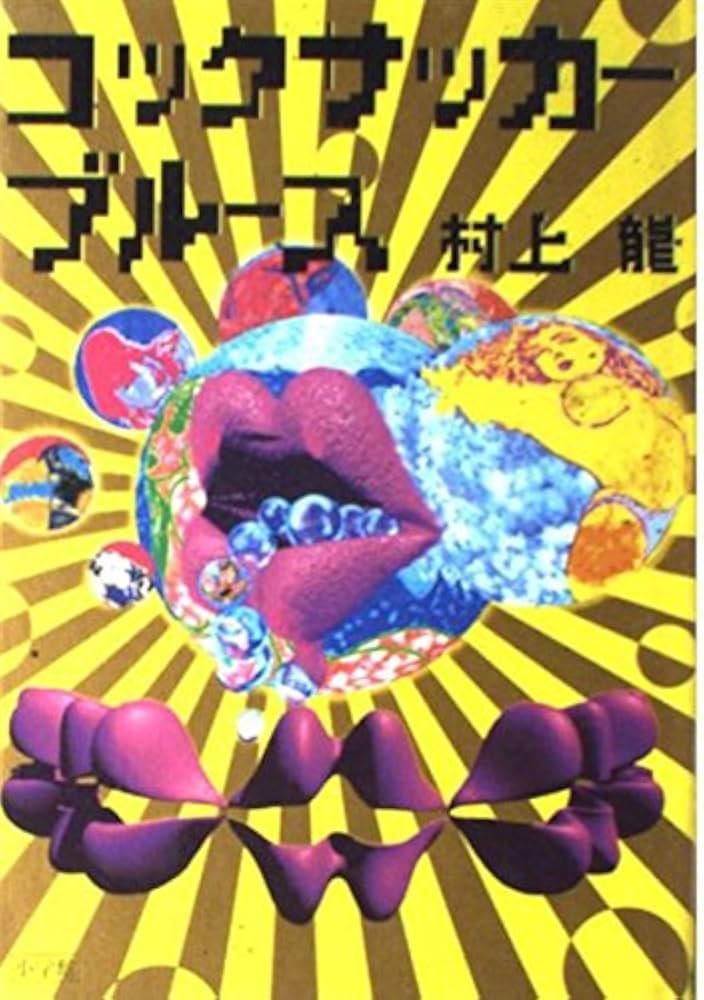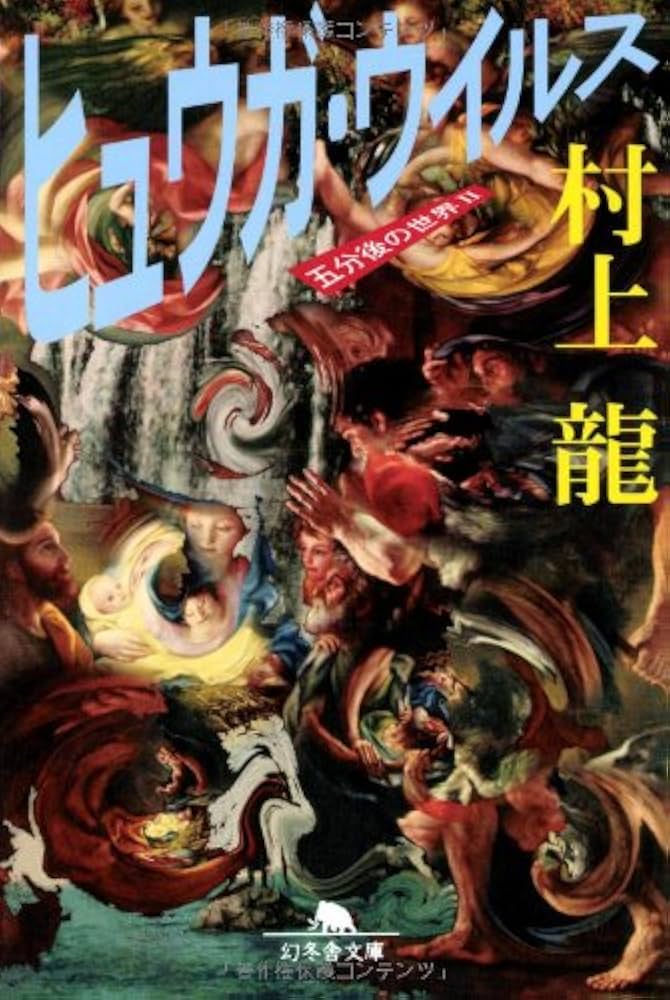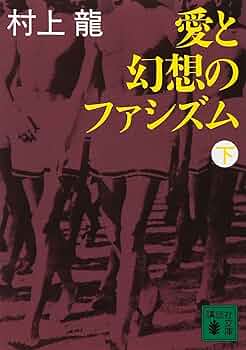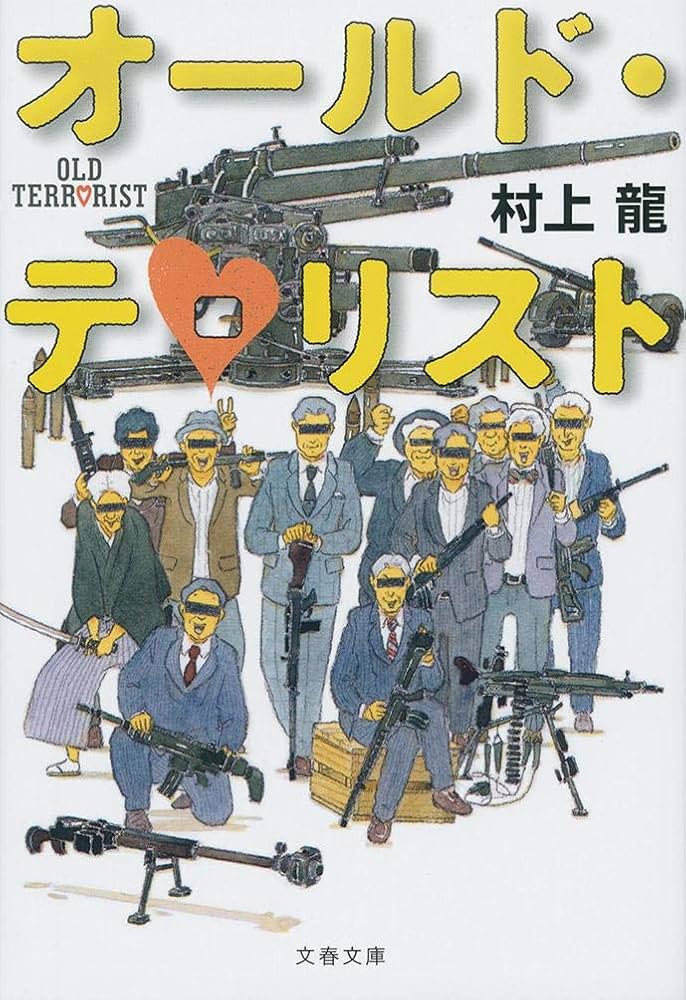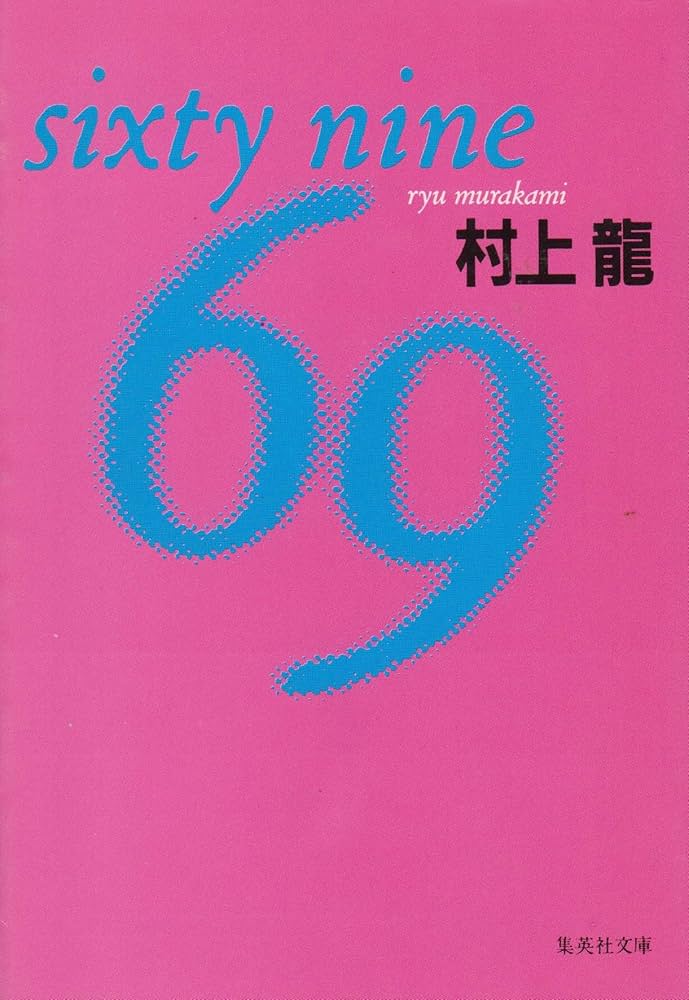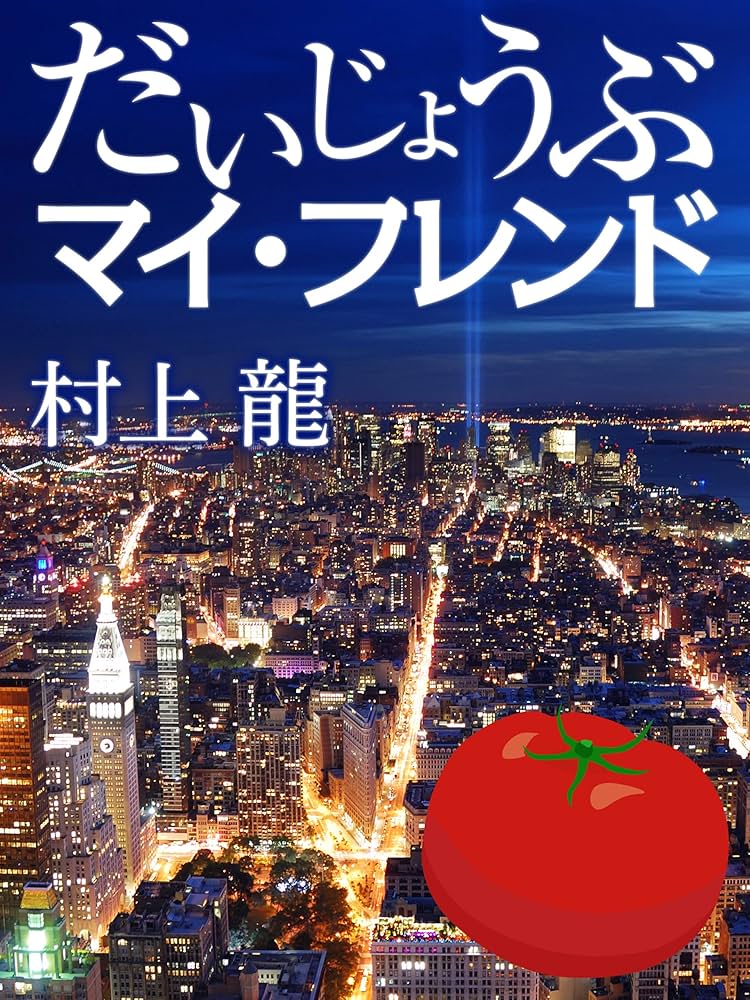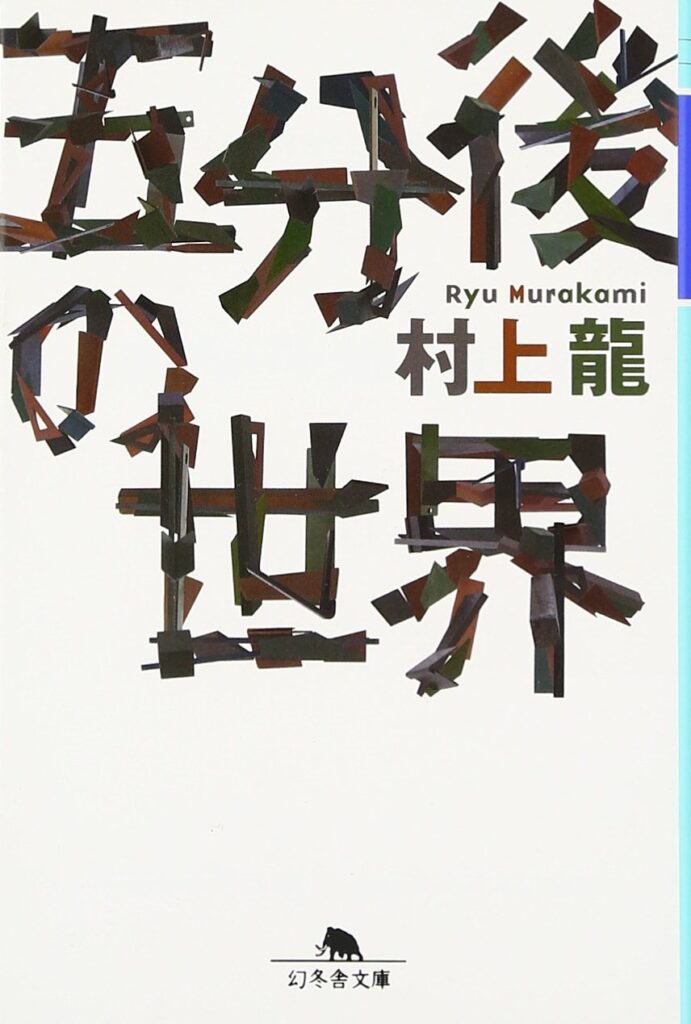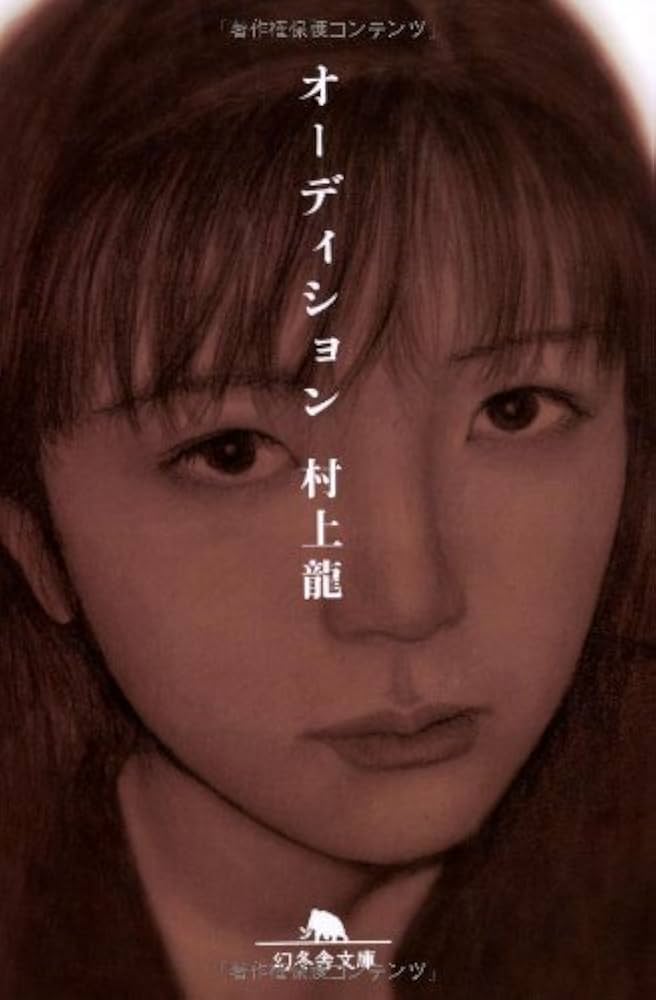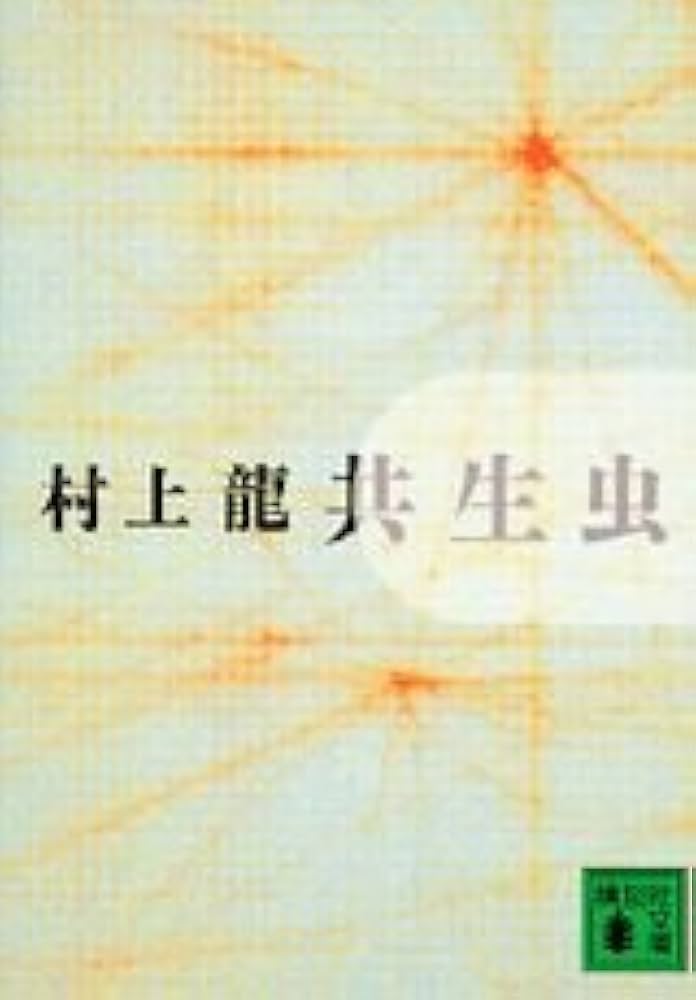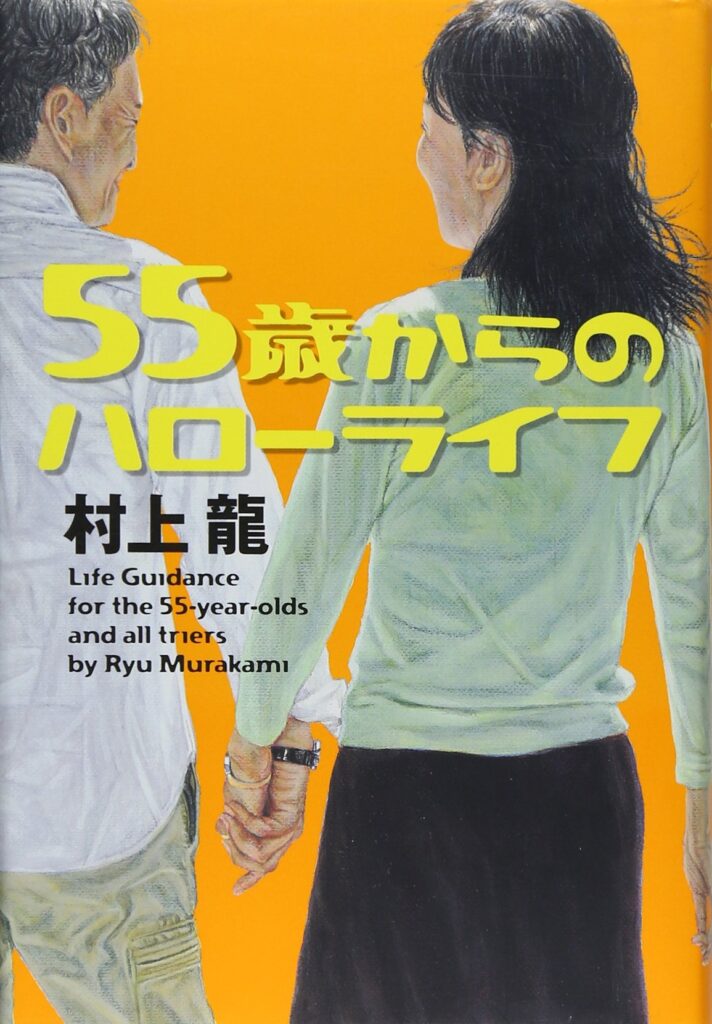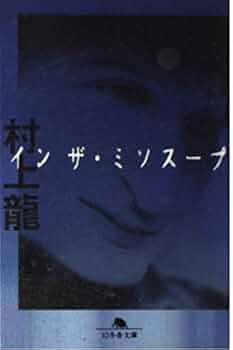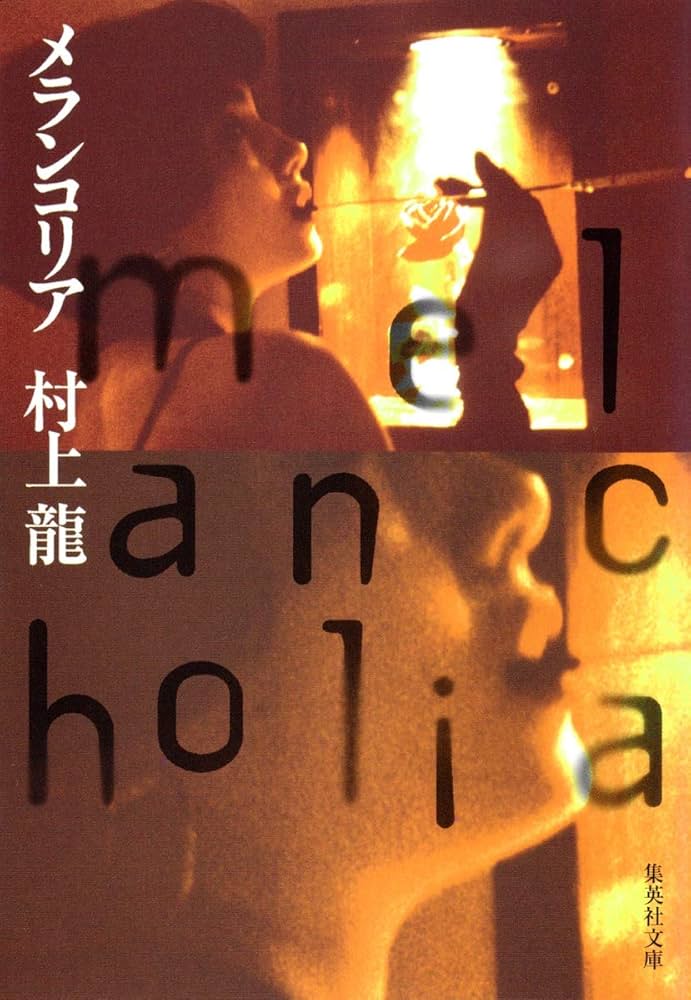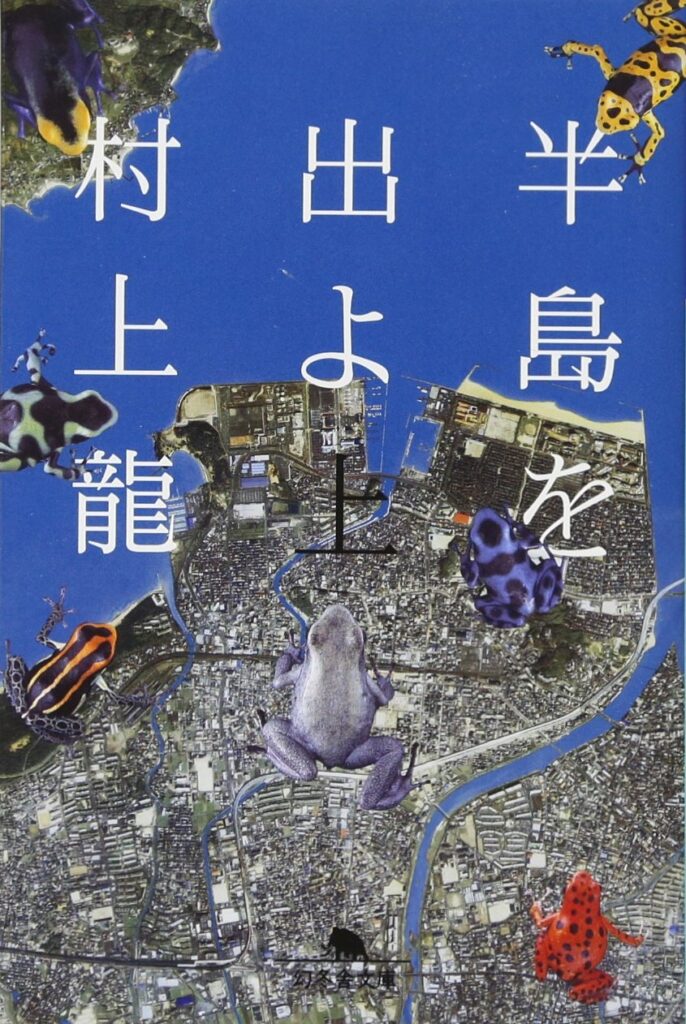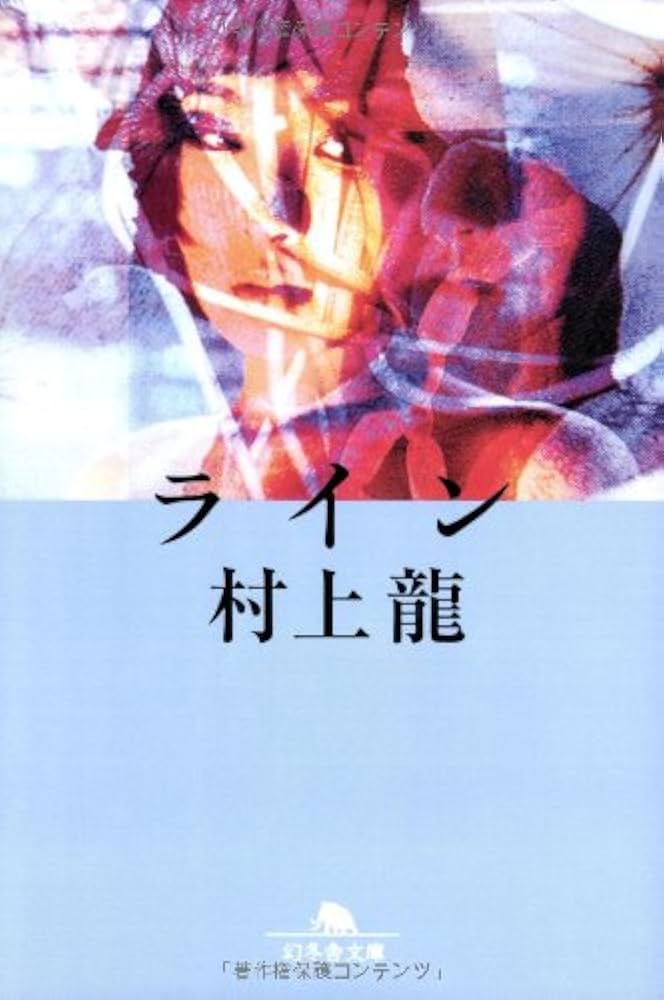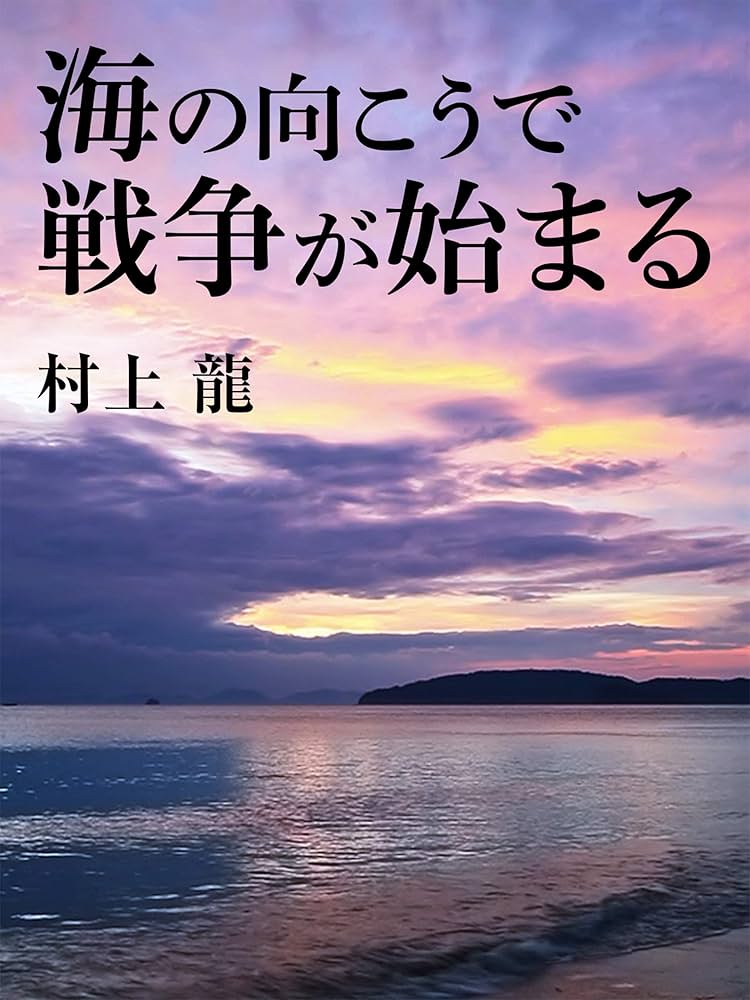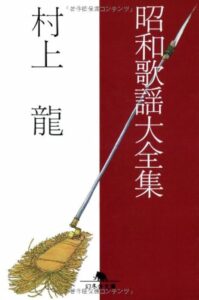 小説「昭和歌謡大全集」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「昭和歌謡大全集」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
この物語は、多くの人が抱くであろう小説の常識を根底から覆すほどの衝撃を持っています。読んでいる間、何度も「これは一体何なんだ?」と自問自答することになるでしょう。しかし、その不条理と暴力の奥には、現代を生きる私たちが目を背けることのできない、ある種の真実が横たわっているように思えてなりません。
物語の舞台は東京のどこにでもあるような郊外の街、調布。そこで暮らすごく普通に見える若者たちと中年女性たちが、些細なきっかけから想像を絶する殺し合いへと突き進んでいきます。それは単なるケンカや抗争というレベルを遥かに超え、まるで戦争そのものです。
この記事では、まず物語の導入部分の概要をお話しし、その後に核心に迫るネタバレを含む深い感想を述べていきたいと思います。この作品が投げかける問いに、一緒に向き合っていただければ幸いです。
「昭和歌謡大全集」のあらすじ
物語の中心となるのは、二つのグループです。ひとつは、イシハラをはじめとする6人の若者グループ。彼らは特に仲が良いわけでもなく、共通の趣味があるわけでもありません。ただ、なんとなく集まっては、それぞれが持ち寄った酒を飲み、昭和の歌謡曲をカラオケで歌うだけの気薄な関係です。
もうひとつは、メンバー全員の名前が「ミドリ」という共通点だけで集まった、6人の中年女性グループ「ミドリ会」。彼女たちは皆、離婚を経験しており、その傷を埋めるかのように奇妙な連帯を築いています。若者たちと同じように、彼女たちの関係もまた、どこか空虚さをまとっています。
ある夜、若者グループの一人、スギオカがカラオケの興奮が冷めやらぬまま街をさまよい、ミドリ会のメンバーであるヤナギモトミドリに声をかけます。しかし、拒絶されたことに逆上した彼は、衝動的に彼女を刺殺してしまいます。これが、後に街全体を巻き込むことになる、血で血を洗う復讐劇の始まりでした。
友人の死を知ったミドリ会は、警察の無力さに絶望し、自らの手で犯人への復讐を誓います。彼女たちは驚くべき計画性と実行力でスギオカを殺害。そこから、若者グループとミドリ会の間には、後戻りのできない暴力の連鎖が生まれてしまうのです。物語の概要はここまでですが、この後、想像を絶する展開が待っています。
「昭和歌謡大全集」の長文感想(ネタバレあり)
ここからは、物語の核心に触れるネタバレを含んだ感想になります。未読の方はご注意ください。この物語の本当の恐ろしさと魅力は、その常軌を逸した展開の中にこそあるのです。
まず、この物語の登場人物たちが抱える「空虚さ」について触れないわけにはいきません。若者たちも、ミドリ会の女性たちも、心にぽっかりと穴が空いている。彼らはその穴を埋めるために、それぞれ「昭和歌謡を歌うこと」「ミドリ会という集団に属すること」に依存しています。しかし、それは本質的な解決にはならず、むしろ彼らの孤独や疎外感を浮き彫りにしているように見えます。
彼らの関係は驚くほど希薄です。若者たちのパーティでは、食べ物や飲み物は各自持参で、会話も弾まない。ミドリ会も、名前が同じという一点だけで繋がっているに過ぎません。この深刻なコミュニケーション不全こそが、物語の根底に流れる不気味さの源泉だと感じます。彼らは平和な日常の中で、すでに見えない壁に囲まれ、孤立していたのです。
そして、その空虚さは、最初の殺人によって暴力という形で噴出します。スギオカがヤナギモトミドリを殺害する場面には、明確な動機らしい動機が見当たりません。ナンパを断られたという些細な出来事が、彼の内に溜まった行き場のないエネルギーの引き金を引いただけ。これは、コミュニケーションの完全な失敗が生んだ悲劇であり、この物語全体を象徴する「理不尽さ」の幕開けでした。ここからネタバレが本格化します。
友人を殺されたミドリ会の変貌ぶりは、この物語の最初のターニングポイントです。彼女たちは悲しみに暮れる被害者から、冷徹な復讐者へと一気に姿を変えます。警察が頼りにならないと知るや、彼女たちは自らの手で正義を執行することを決意します。ウイスキーを茶碗で一気にあおるシーンは、彼女たちが社会のルールと決別し、修羅の道へ進むことを誓った、強烈な儀式として描かれています。
彼女たちの復讐は、スギオカの犯行とは対照的に、極めて計画的かつ効率的です。犯人を特定し、行動を調査し、完璧な計画のもとに実行する。この時点で、暴力はもはや衝動的なものではなく、目的を達成するための「手段」へと変化しています。この変貌こそが、この物語を単なる復讐譚ではない、別の次元へと引き上げるのです。
この復讐の連鎖を加速させる装置として、スガコという謎の女性が登場します。事件の目撃者である彼女は、両方のグループに情報を渡し、まるで運命の使者のように振る舞います。彼女の存在によって、対立は決して収束することなく、さらなるエスカレーションへと向かうことが運命づけられてしまいます。
スギオカの死を知った若者たちは、当然のように報復を誓います。彼らは怪しげな店で拳銃を手に入れ、ミドリ会のメンバーの一人を射殺します。ここからが、この物語の真骨頂ともいえる、常識はずれの武装エスカレーションの始まりです。個人的な殺し合いが、信じられない速度で「戦争」へと変貌していく過程には、もはや笑うしかないほどの異様さが漂います。
拳銃による報復を受けたミドリ会は、なんと自衛隊のコネを使い、対戦車ロケットランチャーを入手します。この飛躍が信じられるでしょうか。しかし、物語の中では、それがごく自然な流れとして描かれます。もはや彼女たちにとって、相手を殲滅するためには、軍事兵器の導入すらためらう理由にはならないのです。
そして、物語は最も衝撃的なシーンの一つである「海岸の虐殺」を迎えます。若者たちがいつものようにカラオケに興じているところを、ミドリ会がロケットランチャーで奇襲するのです。その結果は凄惨の一言。仲間たちが一瞬で肉塊と化す地獄絵図の中で、主人公のイシハラはかろうじて生き延びます。このシーンは、暴力がもたらす圧倒的な現実を、読者に叩きつけます。
この襲撃で生き残ったイシハラは、警察の尋問に対し、狂人を装うことで戦争の秘密を守り抜きます。彼は、この復讐の連鎖を、法や社会の介入なしに、自らの手で終わらせる(あるいは続ける)ことを選択したのです。この時点で、彼はもはや物語冒頭の「冴えない若者」ではありません。
ここで注目すべきは、登場人物たちが「殺人」という行為を通して、ある種の「成長」を遂げているという皮肉な事実です。社会生活では何も成し遂げられなかった彼らが、復讐という目的のもと、計画を立て、武器を調達し、効率的に敵を殺す術を学んでいく。この物語は、人の成長が死者の数と破壊の規模によって測られるという、恐ろしい自己啓発の物語のパロディのようにも読めます。
小説版ではイシハラとノブエの二人が生き残ります。仲間を失った絶望の中で、彼らは一時的に肉体関係を持ちますが、そこに救いはありません。思い出を大切にすることにも、慰め合うことにも何の意味も見出せない彼らがたどり着いた唯一の結論、それこそが「復讐」でした。悲しみや喪失感といった人間的な感情が、純粋で絶対的な破壊への渇望へと変質する瞬間です。
そして、物語は誰もが予想しえない、恐るべきクライマックスを迎えます。イシハラは、かつて銃を手に入れた店を再び訪れ、こう尋ねるのです。「原爆、あります?」。最終的に彼らが手に入れたのは、燃料気化爆弾、あるいはそれに匹敵する大量破壊兵器でした。彼らはそれを使って、ミドリ会が住む調布の街ごと、すべてを消し去ってしまいます。
この結末は、私たちに何を伝えるのでしょうか。「暴力は何も生まない」という安易な教訓を、この物語は木っ端微塵に打ち砕きます。街を破壊し尽くしたイシハラの心にあったのは、後悔や虚しさではありませんでした。彼はこう考えるのです。「仲間がたくさん死んで悲しいけど、またすぐに出来るさ、そうしたら、カラオケパーティだって、また出来るさ」。
この最後のモノローグこそ、本作の最も恐ろしい核心です。イシハラにとって、この大虐殺は失敗ではなく、完全な成功体験でした。彼は、自分を苦しめてきた空虚な日常、意味のない人間関係、そのすべてが詰まった世界を文字通り消し去り、白紙の状態を作り出したのです。それは、疎外された人間が取りうる、究極の自己実現だったのかもしれません。自分に居場所のない世界を破壊し、新たな世界を創造する意志。このニヒリスティックなカタルシスに、私は戦慄を禁じ得ませんでした。
最後に、この物語は村上龍の別の傑作『半島を出よ』へと繋がる、テロリストの誕生譚として読むことができます。調布の灰の中から立ち上がったイシハラは、もはやただの若者ではありません。彼は、目的のためなら大量破壊すら厭わない、完成されたテロリストへと変貌を遂げたのです。この『昭和歌謡大全集』は、政治的な思想などではなく、個人的な空虚さや倦怠感が、いかにして大規模なテロリズムへと繋がりうるかを描いた、戦慄のケーススタディなのです。
まとめ
村上龍の「昭和歌謡大全集」は、単なるバイオレンス小説という枠には到底収まらない、強烈な問題作です。ありふれた日常に潜む空虚さが、いかにして凄惨な暴力へと転化していくのか。その過程を、一切の感傷を排し、冷徹な筆致で描き切っています。
物語のあらすじは、若者と中年女性という二つのグループが、些細なきっかけから殺し合いを始め、その暴力が拳銃、ロケットランチャー、そして最終的には大量破壊兵器へとエスカレートしていくという、にわかには信じがたいものです。しかし、その根底には、コミュニケーションの欠如や社会からの疎外といった、現代が抱える病理が横たわっています。
この物語は、暴力の虚しさを説くのではなく、むしろ暴力によって「意味」を見出してしまう人間の恐ろしい可能性を突きつけてきます。読後、間違いなく心に重たい何かを残す作品ですが、それこそが文学の持つ力なのかもしれません。ネタバレを読んで興味を持たれた方も、ぜひ一度、この衝撃的な世界に触れてみてほしいと思います。
この作品を読むという行為は、安全な場所から地獄を覗き見るような体験かもしれません。しかし、その地獄は、もしかしたら私たちの日常と地続きなのかもしれない。そんなことを考えさせられる、忘れがたい一冊です。