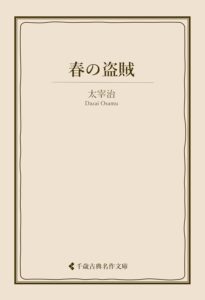 小説「春の盗賊」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。太宰治といえば、その独特の文体と、人間の弱さや葛藤を描く作風で知られていますよね。この「春の盗賊」も、まさに太宰治らしい魅力が詰まった一編なのです。
小説「春の盗賊」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。太宰治といえば、その独特の文体と、人間の弱さや葛藤を描く作風で知られていますよね。この「春の盗賊」も、まさに太宰治らしい魅力が詰まった一編なのです。
物語は、作者自身を思わせる「私」の家に泥棒が入った、という出来事を軸に進みます。しかし、単なる事件の顛末記ではありません。そこに至るまでの「私」の長々とした独白、自己弁護、そして泥棒との奇妙きてれつな一夜の対話が、読者を引き込んでやまないのです。
この記事では、まず「春の盗賊」がどのような物語なのか、結末に触れつつその流れを追います。そして後半では、この作品を読んで私が感じたこと、考えたことを、ネタバレを気にせずに詳しくお話ししたいと思います。太宰作品のファンはもちろん、これから読んでみようかな、と考えている方にも、作品の雰囲気が伝われば嬉しいです。
太宰治が描く、滑稽で、どこか物悲しい「春の盗賊」の世界へ、一緒に足を踏み入れてみませんか。きっと、忘れられない読書体験になるはずですよ。
小説「春の盗賊」のあらすじ
物語は、「私」と名乗る語り手の、非常に長い前置きから始まります。「あまり期待してお読みになると、私は困るのである。」と、いきなり読者の期待をいさめるような言葉で幕を開けるのです。語り手は、これから話すのは名の有る大泥棒の話ではなく、自身が体験した貧しい経験談にすぎないと断ります。そして、かつて自分が悪ぶっていたこと、しかしそれは全て贋物(にせもの)で、本当は小心者であることなどを、延々と、しかしどこか自嘲的に語り続けます。
彼は、過去の失敗から学び、世間の評判を気にするようになり、生活を立て直そうと努力している最中だと述べます。ゲエテの言葉を引用し、自己を制限し、孤立することの重要性を説いたりもします。小説に「私」という一人称を使うことの難しさ、それが作者自身の告白と誤解されやすい風潮への警戒心も吐露します。この物語もフィクションであり、昨夜泥棒に入られたという話も嘘である、とまで断言する始末です。
そんな長い語りの後、いよいよ昨夜の出来事が語られます。語り手は、泥棒が入る前には様々な前兆があったと主張します。不吉な泥靴の夢を見たこと、「やって来たのは、ガスコン兵」という意味不明な言葉が口をついて出たこと、猛烈なしゃっくりに襲われたこと、耳がやけに痒かったことなど、今思えばあれらは全て泥棒襲来の予兆だったのだ、と大真面目に語るのです。
そして四月十七日の夜、寝つけずに布団の中にいた「私」は、雨戸が破られ、そこから白い手が入ってくるのを目撃します。極度の恐怖に襲われながらも、なぜか衝動的にその手を両手で包み込み、握りしめてしまいます。外からはか細い声で「おゆるし下さい」という声が聞こえ、語り手は自分が優位に立ったと錯覚し、逆上してしまいます。
なんと語り手は、泥棒に「さ、はいりたまえ」と声をかけ、家の中に招き入れてしまうのです。入ってきた泥棒は小柄な男で、マスクをし、ハンチングを目深にかぶっています。語り手は、自己保身の計算から、わざと部屋の電灯を消し、暗闇の中で火鉢を挟んで泥棒と対峙します。
ここから、語り手と泥棒との奇妙な対話が始まります。語り手は、泥棒を安心させようとしたり、逆に挑発したり、一方的に自身の空想や持論をまくしたてたりします。しかし、そのやり取りの最中に、泥棒はいつの間にか姿を消していました。隣室で聞き耳を立てていた妻にそのことを指摘され、語り手は自分が誰もいない暗闇に向かって一人で熱弁をふるっていたことに気づき、愕然とするのでした。
小説「春の盗賊」の長文感想(ネタバレあり)
さて、ここからは小説「春の盗賊」を読んだ私の感想を、ネタバレを気にせずお話ししたいと思います。いやはや、この作品、本当に面白かったですね。太宰治という作家の個性が、これでもかというほど前面に出ている一編だと感じました。
まず、冒頭の「あまり期待してお読みになると、私は困るのである」という一文。普通、物語の書き出しといえば、読者の興味を引こうとするものですよね。ところが太宰は、いきなり読者の期待値を下げようとする。このひねくれた感じ、たまりません。でも、そう言われると逆に「おや?」と興味をそそられてしまうから不思議です。最初から太宰の術中にはまっているのかもしれませんね。
そして始まる、延々とも思える自己語り。泥棒の話はいつ始まるのかとやきもきさせられますが、この語り自体がもう、抜群に面白いのです。かつて悪ぶっていたけれど、それは見せかけだけで、本当は小心翼々(しょうしんよくよく)の弱い人間なのだ、という告白。デュマの小説に熱狂して「友を選ばばダルタニアンと、絶叫して酒場に躍り込んだ」なんていう描写は、その情景が目に浮かぶようで、思わず笑ってしまいました。自虐の中にも、どこか誇張された表現が光ります。
失敗から学んで用心深くなったはいいものの、今度は「鎧かぶとに身を固め」「二枚も三枚も、鎧を着た。固め過ぎた。動けなくなった」というのも、いかにも太宰らしい極端さですよね。部屋に引きこもって「癈人(はいじん)」とまで言われてしまう。こういう不器用さ、加減を知らない感じに、人間味を感じてしまうのは私だけでしょうか。共感とは少し違うかもしれませんが、その滑稽さが愛おしくも思えてきます。
世評を気にするようになった、という部分も興味深いですね。ゲエテを師と仰ぎ、生活を立て直そうとしている。かつては世評への反発から猛々しく振る舞っていたけれど、今は違うのだ、と。しかし、その一方で「凡俗へのしんからの、圧倒的の復讐ふくしゅうだ」なんて物騒なことも考えている。この屈折した自意識こそが、太宰文学の核なのかもしれません。芸術家としての矜持と、生活者としての現実との間で揺れ動く苦悩が伝わってきます。
そして、いよいよ泥棒の話に入るかと思いきや、今度は「フィクション」についての考察が始まります。「私のフィクションには念がいりすぎて、いつでも人は、それは余程の人でも、あるいは? などと疑い、私自身でさえ、あるいは? などと不安になって来る」というくだり。この「あるいは?」の繰り返しと、その間に生まれる独特のリズム感、たまりませんね。読んでいるこちらも、「これはどこまで本当なのだろう?」と翻弄されてしまいます。この語りの巧みさ、読者を煙に巻くような手法は、まさに太宰治の真骨頂と言えるでしょう。
泥棒が入る前の「前兆」の話も、実に面白い。泥靴の夢、「やって来たのは、ガスコン兵」という謎の口癖、止まらないしゃっくり。これらを大真面目に「泥棒入来の前兆」だと語る語り手の様子は、滑稽でありながら、どこか不気味な雰囲気も漂わせています。日常の中に潜む非日常、あるいは、語り手の精神的な不安定さを暗示しているようにも受け取れます。特にしゃっくりが止まらなくて死にかけた、なんていう話は、大げさすぎて笑ってしまいますが、本人は至って真剣なのです。
そして、ついに泥棒が登場する場面。雨戸の隙間から現れた白い手を、恐怖のあまり衝動的に握りしめてしまう。この行動には度肝を抜かれました。恐怖と、何か別の感情…作中でも示唆されているように、一種の情慾のようなものが入り混じった、非常に奇妙な瞬間です。普通の神経では考えられない行動ですが、極限状態における人間の心理の不可解さを、鮮やかに描き出していると感じました。
さらに驚くべきは、その泥棒を「さ、はいりたまえ」と家に招き入れてしまうこと。しかも、後々のことを考えて(警察沙汰になるのを避けたい、泥棒に恨まれたくない、自分の顔を見られたくない等々)、わざと電灯を消すという用意周到さ。この自己保身のための計算高さと、泥棒を招き入れるという常軌を逸した行動とのギャップが、語り手の複雑な性格を浮き彫りにしています。小心者でありながら、どこか大胆で、そして非常に利己的でもある。そんな多面性が、この一連の行動によく表れています。
暗闇の中での泥棒との対話は、この小説のクライマックスと言えるでしょう。火鉢を挟んで対峙する二人。語り手は、泥棒を安心させようと下手に出たかと思えば、急に尊大な態度をとったり、自身の貧乏を嘆いたり、かと思えば相手の素性について勝手な推理を披露したりと、目まぐるしく態度を変えます。「金を出せ」とすごむ泥棒に対し、最初は怯えながらも、次第に饒舌になり、一方的にまくしたてる。その内容は、自身の芸術論であったり、人生訓であったり、あるいは全くの創作であったりと、支離滅裂です。
特に、泥棒が女だと決めつけ、「今金酒造株式会社」の印半纏を着ているだの、年下の亭主のために盗みを働いているだのと、滔々と語る場面は圧巻です。これは完全に語り手の妄想、あるいは「小説の筋書」なのですが、本人はさも真実であるかのように語ります。二十円取られたことへの腹いせもあるのでしょうが、この状況でここまで想像力をたくましくし、熱弁をふるえるというのは、やはり尋常ではありません。作家としての性(さが)なのでしょうか。滑稽であると同時に、どこか鬼気迫るものさえ感じさせます。
そして、あの衝撃的な結末。隣室で一部始終を聞いていた妻が、恐る恐る部屋に入ってきて告げる真実。「かえりましたよ」「ちゃんと雨戸まで、しめて行ったのね」。つまり、語り手はとっくに逃げ去った泥棒の幻影に向かって、長々と一人で喋り続けていたわけです。これには、読んでいるこちらも「えっ!?」と声が出そうになりました。あれだけ繰り広げられた緊迫感のある(ように見えた)対話が、全て語り手の空回りだったとは。最高のオチであり、同時に、語り手の孤独と滑稽さが際立つ瞬間でもあります。
妻に「あんな、どろぼうなんかに、文学を説いたりなさること、およしになったら、いかがでしょうか」と、ある意味核心を突くようなことを言われ、語り手は激しく動揺します。「私は、いやになった。それならば、現実というものは、いやだ! 愛し、切れないものがある。」という最後の叫びは、読者の胸に深く突き刺さります。泥棒という現実の侵入者に対して、必死に言葉(=文学、あるいは虚構)で対抗しようとしたものの、現実はあまりにも白々しく、興醒めなものだった。ロマンを求めずにはいられない自身の性質と、どうしようもなく俗な現実との埋めがたい溝に対する絶望が、この言葉に凝縮されているように感じました。
この「春の盗賊」は、単なる「泥棒に入られた話」という枠をはるかに超えて、太宰治自身の内面、創作に対する姿勢、そして生きていくことの苦悩や滑稽さを、濃密に描き出した作品だと思います。自意識過剰で、小心者で、見栄っ張りで、計算高くて、それでいてどこか純粋でロマンチスト。そんな一筋縄ではいかない「私」の姿は、太宰治その人の投影であると同時に、私たち読者の中にも存在する人間の複雑さをも映し出しているのかもしれません。だからこそ、私たちはこのどうしようもない語り手に、呆れながらも惹きつけられ、共感してしまうのではないでしょうか。
まとめ
太宰治の「春の盗賊」は、一読忘れがたい強烈な印象を残す作品でしたね。単に泥棒に入られた体験談というだけでなく、太宰治という作家の精神性が色濃く反映された、非常に「太宰らしい」一編と言えるでしょう。自己弁護と自己嫌悪が入り混じる独特の語り口は健在で、読者をつかんで離しません。
物語は、悪ぶってはいても根は小心な「私」が、世評を気にしつつ生活を立て直そうとしているところに、予期せぬ訪問者、つまり泥棒が現れるところから大きく動き出します。恐怖と奇妙な興奮の中で泥棒を家に招き入れ、暗闇で繰り広げられる一方的な対話、そしてその衝撃的な結末は、滑稽でありながらも深い余韻を残します。
この作品を読むと、現実の味気なさや興醒め感と、それでもロマンや理想を追い求めてしまう人間の性(さが)との間で揺れ動く、太宰自身の葛藤が生々しく伝わってきます。「私」が見せる自己保身や見栄、そして根底にある孤独感は、時代を超えて多くの読者の心に響くのではないでしょうか。
太宰治の作品世界への入り口としても、また、その深淵に触れる一作としても、「春の盗賊」は非常に魅力的な小説だと思います。まだ読んだことのない方は、ぜひ手に取ってみてください。きっと、その独特な世界観の虜になるはずですよ。




























































