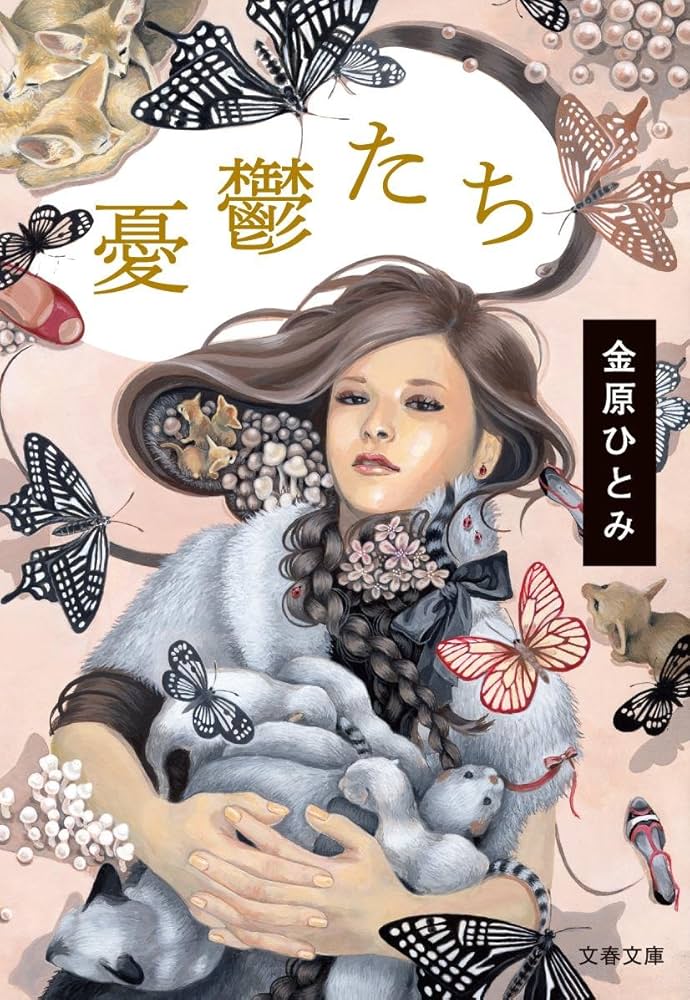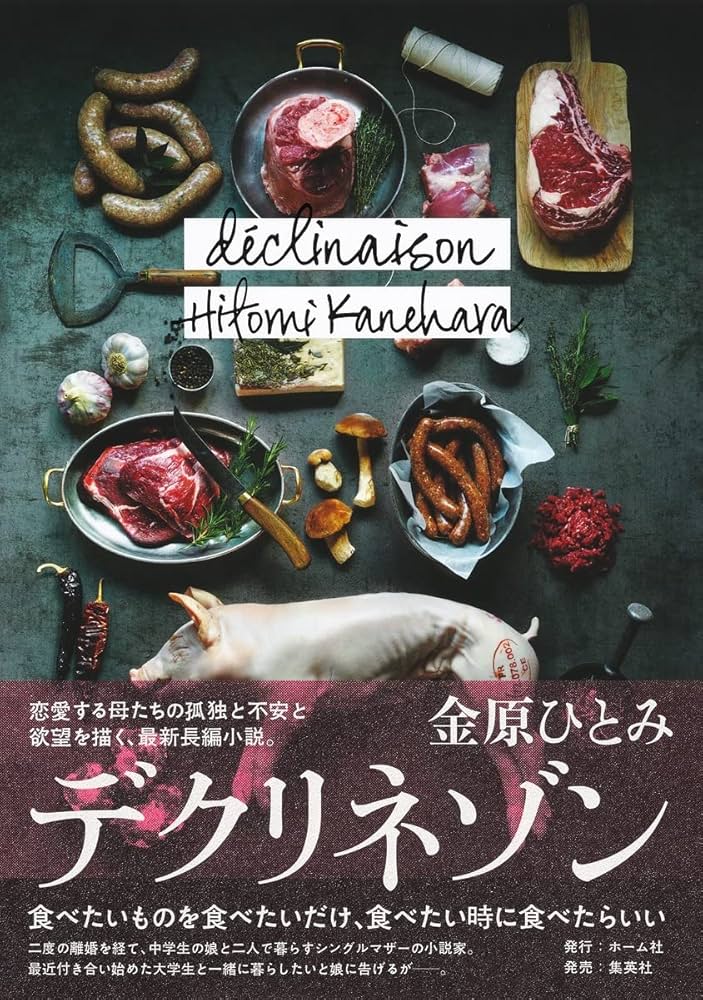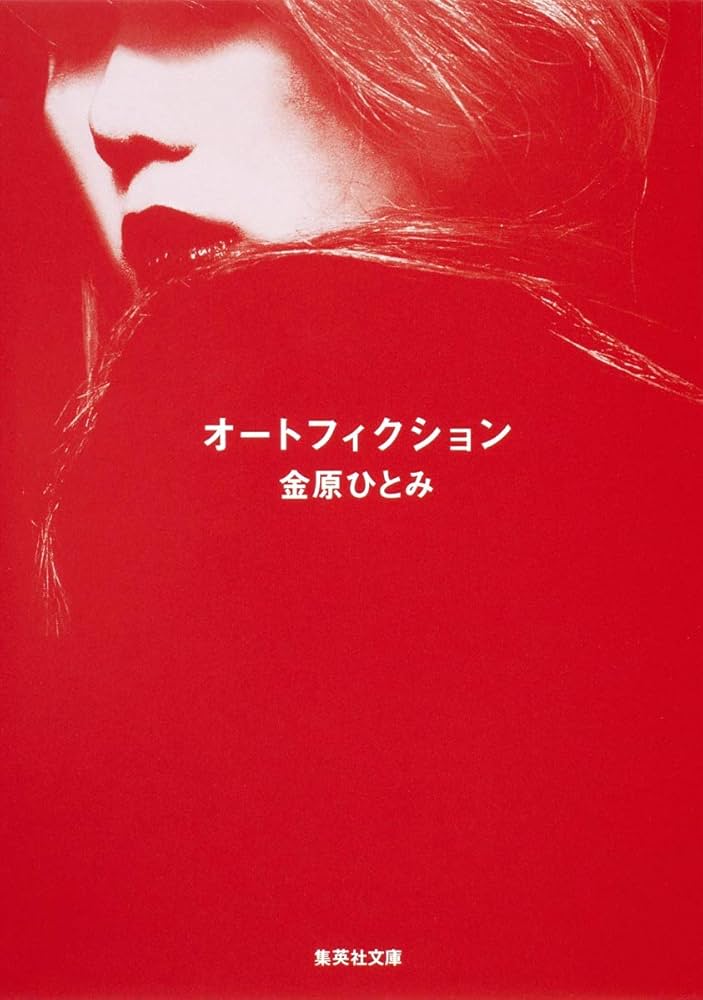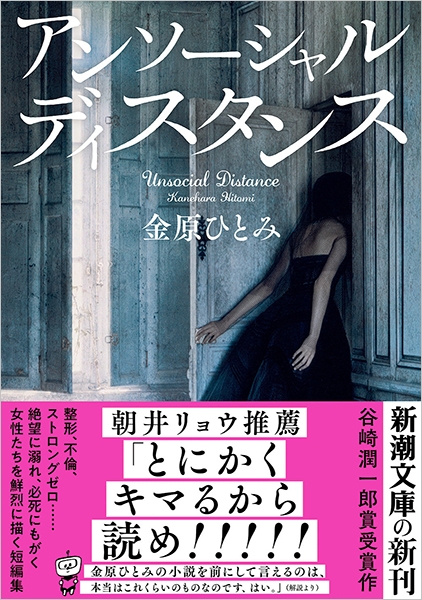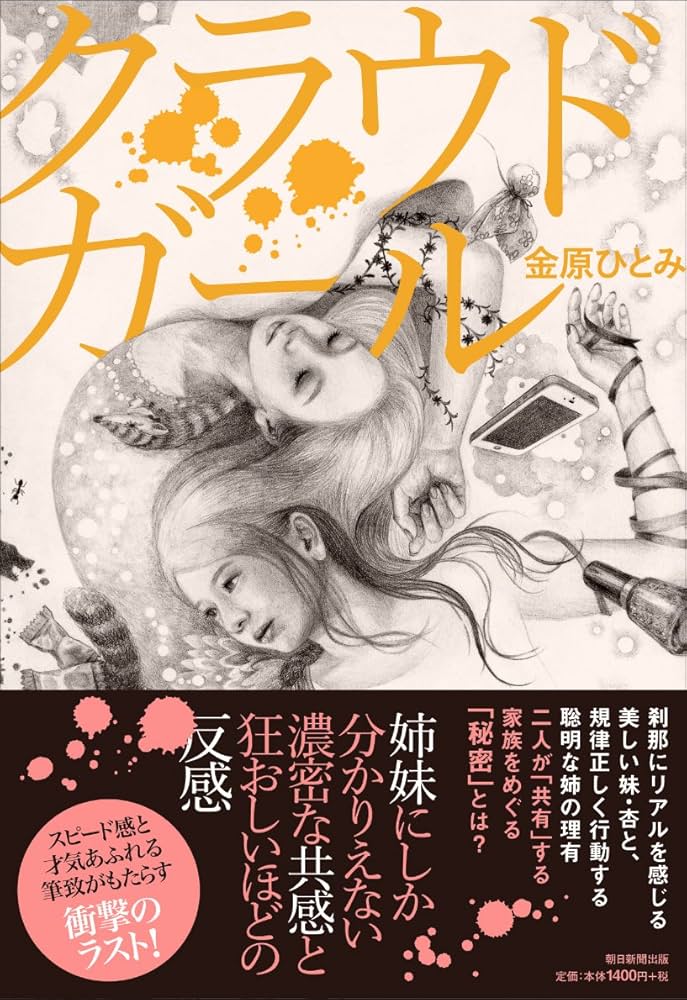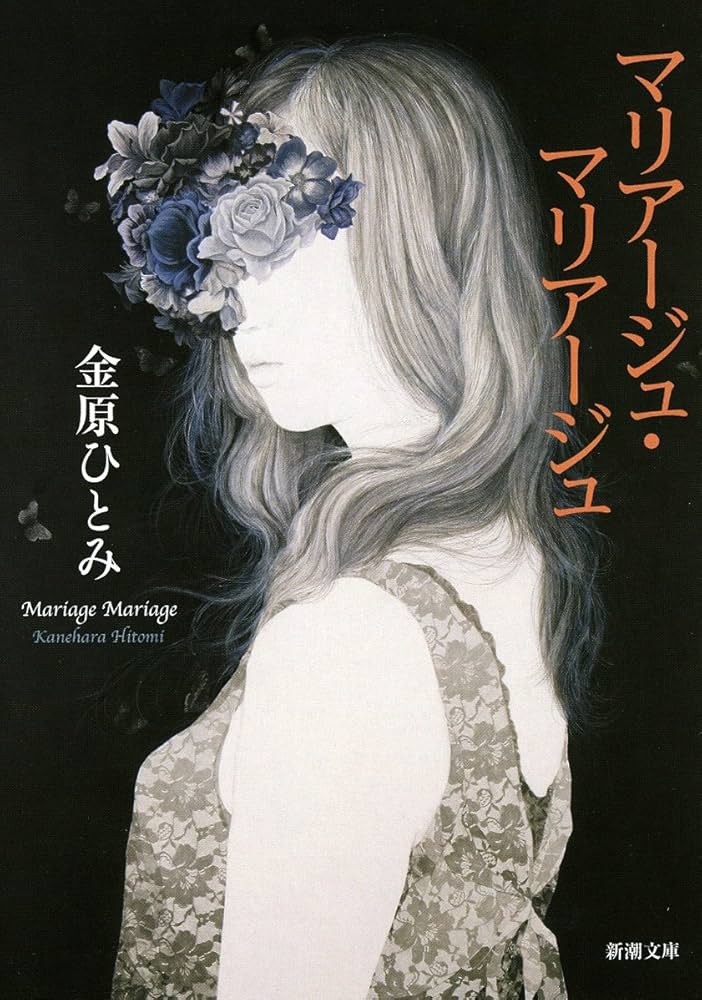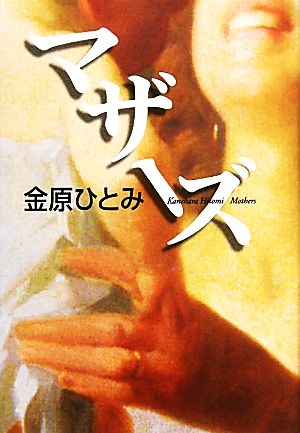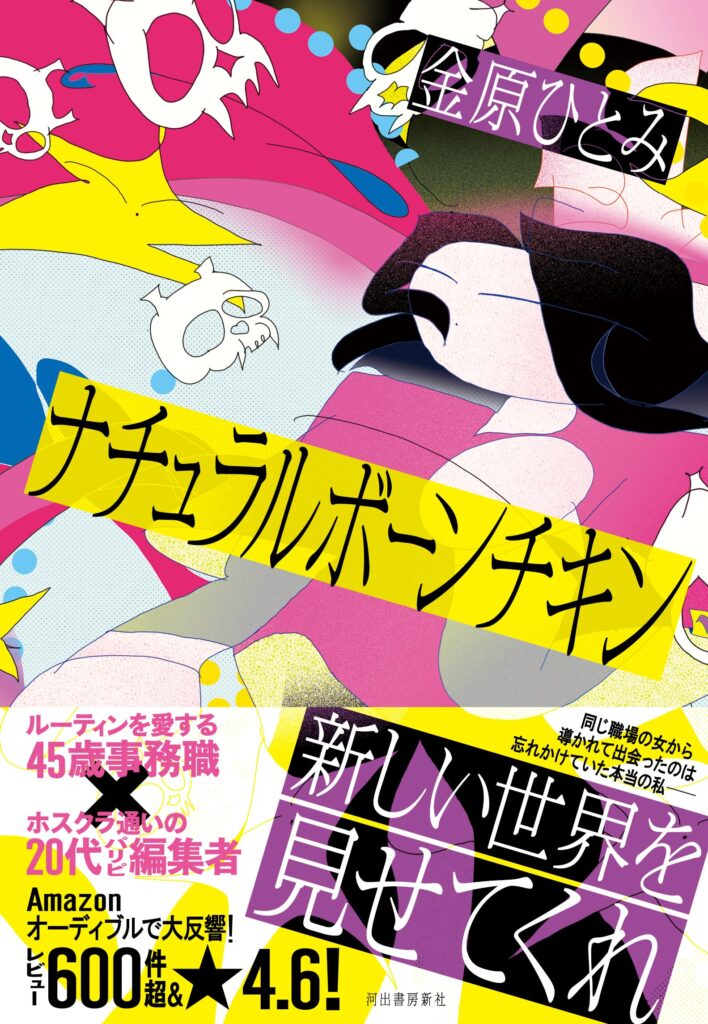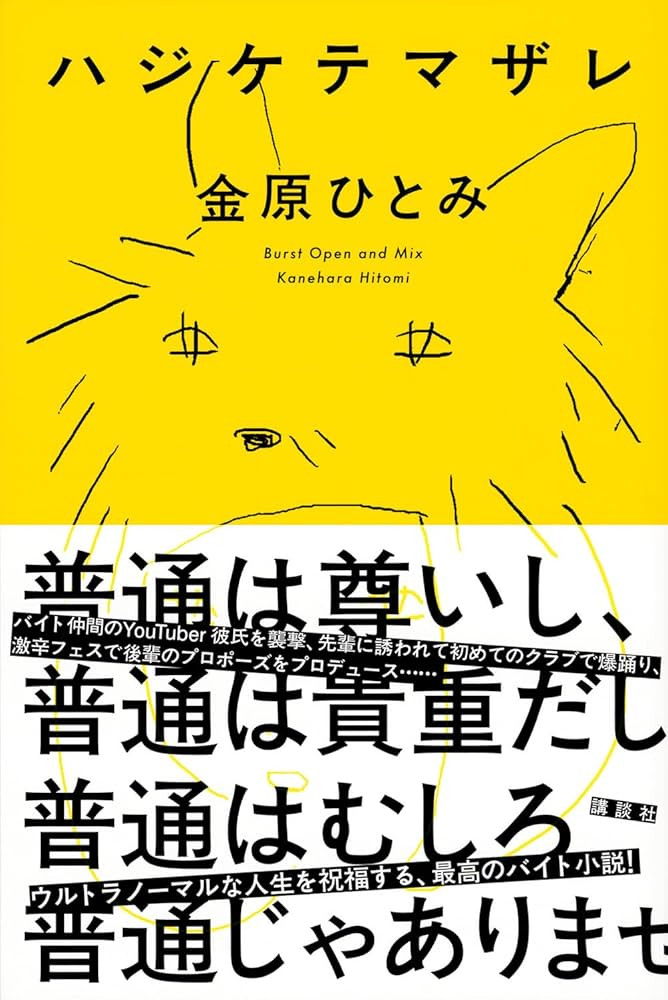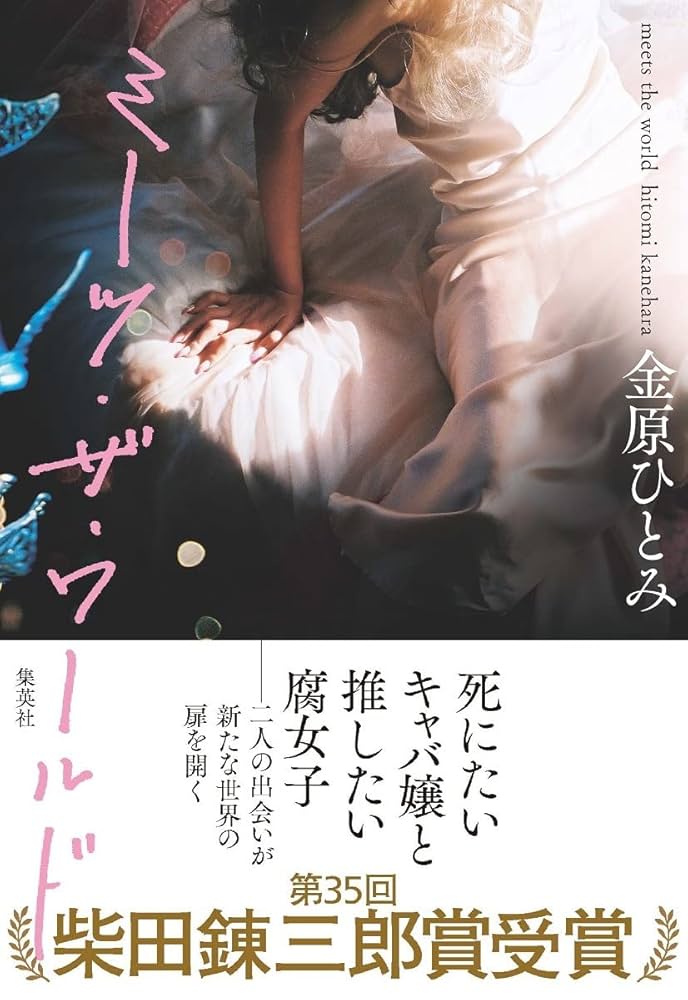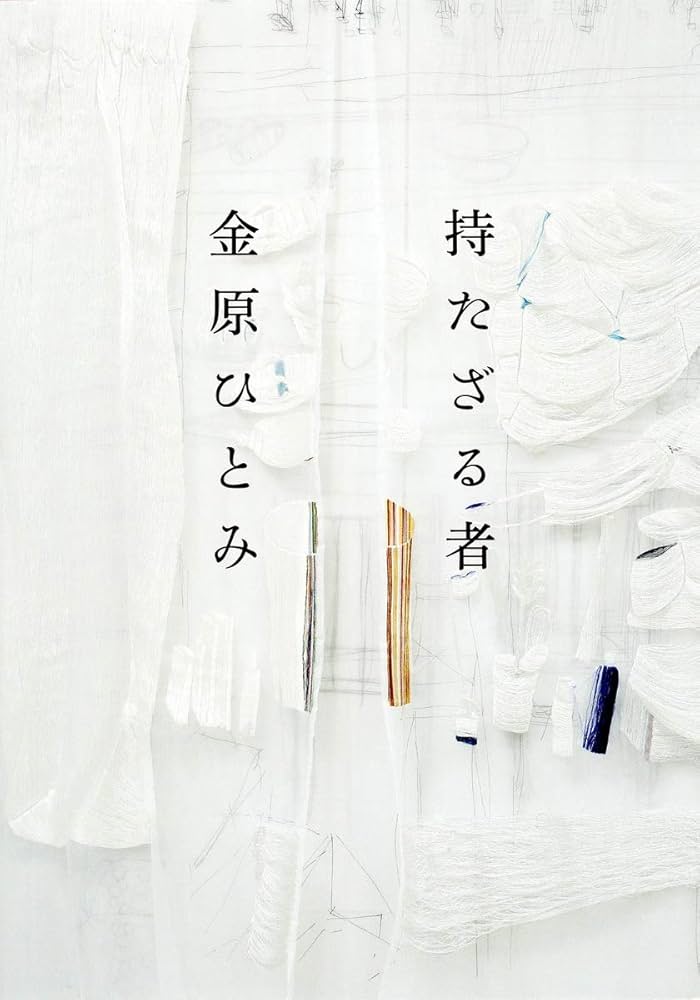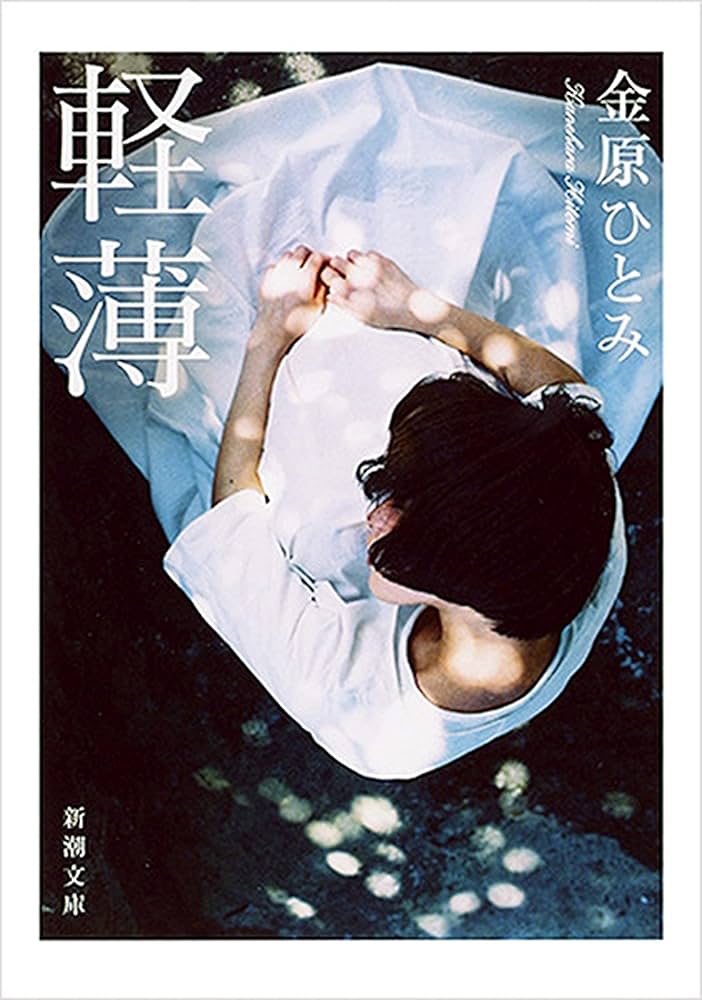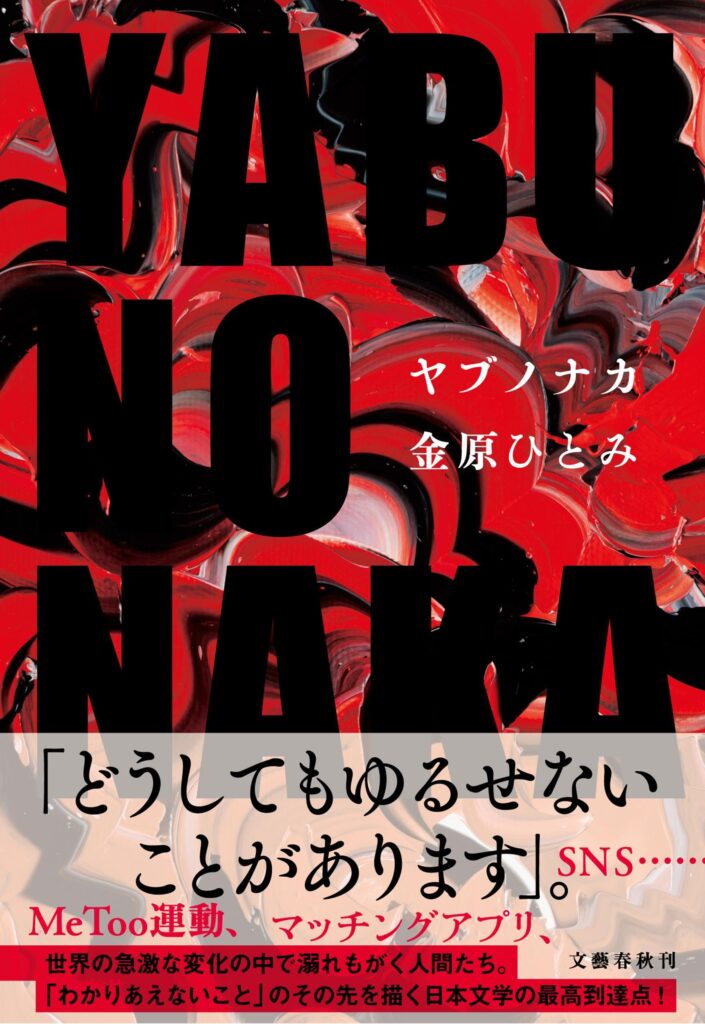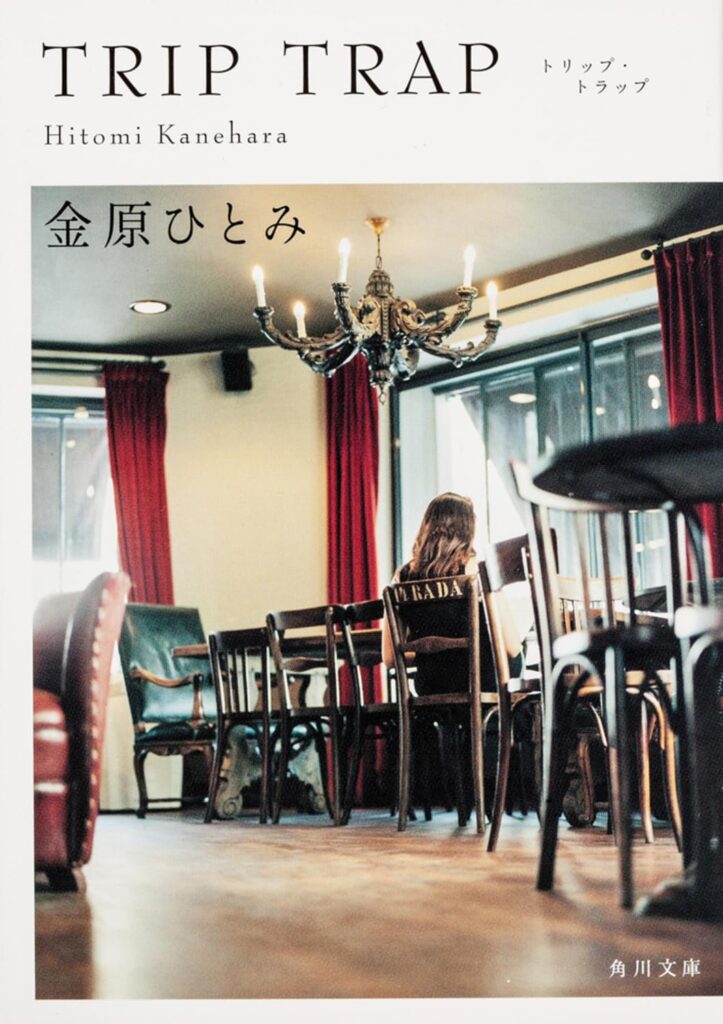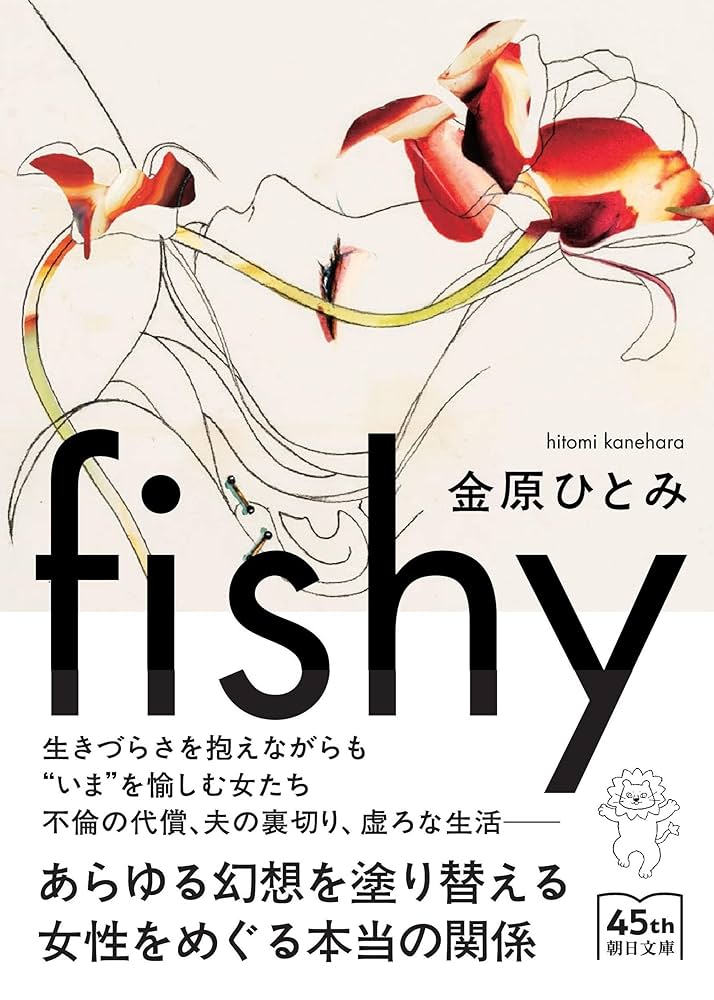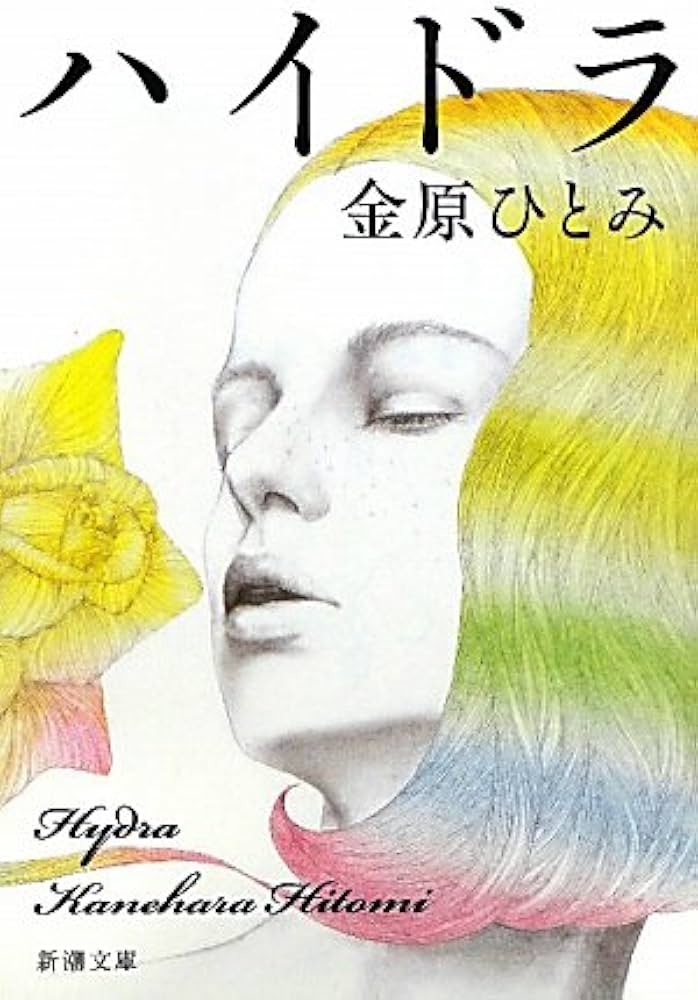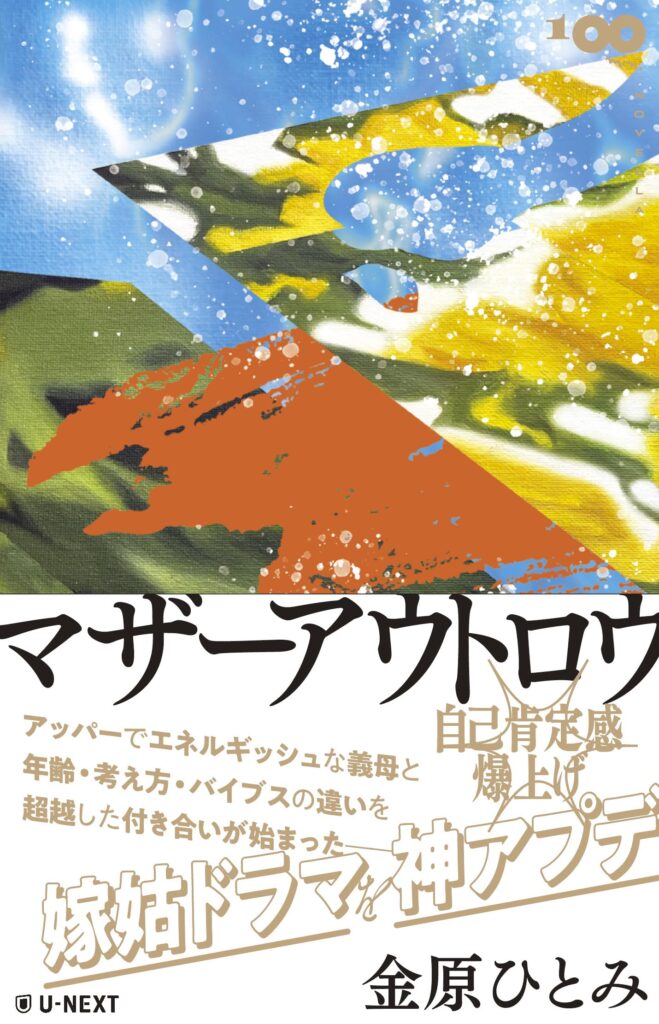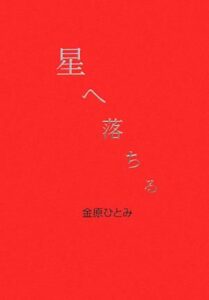 小説「星へ落ちる」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「星へ落ちる」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
恋愛の熱は、人を前へ進めると同時に、足元を空洞化させます。揺らぎは嫉妬へ、嫉妬は執着へ、そして執着は自尊を削ります。
金原ひとみ「星へ落ちる」は、ひとりの“彼”を中心に、「私」「僕」「俺」の三つの視点が交錯する連作短編集です。章ごとに語り手が変わり、関係の矢印がすれ違い続ける構造が、読む手を止めさせません。作品集は「星へ落ちる/僕のスープ/サンドストーム/左の夢/虫」の五編から成り、切実な恋と不安が連鎖していきます。
あらすじをたどりながら、必要な箇所ではネタバレに触れ、最後に読み終えた後の余韻や痛みについて掘り下げていきます。
「星へ落ちる」のあらすじ
「星へ落ちる」は、金原ひとみが描く連作の表題作で、語り手は“私”。“彼”には家で同棲している男性恋人がいて、私は“彼”が来るときだけ扉を開く存在です。望む権利が自分にはないと知りながら、触れられる時間にしがみつく“私”の心は、やがて相手の“彼氏”への嫉妬で軋みます。ここで読者は、愛の形が多様であるほど不安の形もまた多様であることに向き合わされます。
続く「僕のスープ」では、語り手は“僕”。今度は“彼”の側に女の影が見えたのではないかという不安が膨張し、理屈より速く心が煮立ちます。愛情が強いほど想像は先走り、現実を歪めることを、作品は静かに示します。
「サンドストーム」は再び“私”の視点。“彼”と暮らしはじめても、砂嵐のような不安は部屋に吹き込み続けます。満たされたはずの生活で、なぜ渇きは深まるのか――その問いが砂粒のように目に入り、視界を曇らせます。
「左の夢」では“俺”――出ていった彼女を待ち続ける側の視点に切り替わります。そして終盤の「虫」へ。関係がかたちを得るほど、心の奥では別のものがうごめく気配が増していきます。ただし、このあらすじの段階では結末の是非は伏せられ、各話が一方向に閉じない作りが保たれます。
「星へ落ちる」の長文感想(ネタバレあり)
連作を貫く設計
「星へ落ちる」は、直接の語り手が“彼”にならない構造が肝です。語りは常に「私」「僕」「俺」の側にあり、中心人物の内面は空白のまま残されます。この空白が、三人の投影と誤読を呼び込み、読者の想像を無限に回転させます。中心に“穴”がある設計は、引力へ落ちていく運動をタイトルと呼応させる巧さです。
視点の反転とねじれ
視点が入れ替わるたび、同じ出来事が異なる輪郭で立ち上がります。たとえば「星へ落ちる」で“私”が見た優しさは、「僕のスープ」では“裏切りの予兆”に見える。信頼は相対、真実は多面。読者は証拠を積み上げたくなるのに、確証は最後まで差し出されません。
“彼”をめぐる倫理
“彼”には男性の恋人がいる。にもかかわらず“私”の扉を叩き、“僕”の不安も煽る。ここにあるのは正邪のジャッジではなく、人が誰かを必要とする瞬間の身勝手と切実の同居です。金原ひとみは、責める言葉より先に呼吸の乱れを置き、倫理より先に体温を置く作家だと感じます。
「あらすじ」では見えない傷
表題作の“私”は、自分が“二番目”だと知りつつ関係を続けます。ネタバレに踏み込めば、関係を結び直しても、疑いが新しいかたちで蘇る展開が待っています。所有の確約が与えられれば心が安らぐわけではない、という皮肉が的確です。
「僕のスープ」の痛み
“僕”は“彼”の浮気を確信できないまま、疑いを栄養にして自分を痩せ細らせます。タイトルにあるスープは、他者と自分の温度差を埋めようとする儀式のように見え、温める行為そのものが孤独を強調します。食卓の温かさの陰で、心の温度は下がっていく。
「サンドストーム」の風景
同居で得たはずの安堵は、かえって“彼”の不在の時間を際立たせます。鍵がある、部屋がある、生活がある――それでも吹き込む砂を止められない。砂粒は疑念のメタファーであり、取り除いても取り除いても残る微細なざらつきです。
「左の夢」の待機
“俺”の章は、待つことの物理的な苦痛を描きます。部屋の時間が伸び、窓の外だけが進む。未練は時に滑稽で、時に尊い。読了時、“俺”の執着が自壊ではなく自立へわずかに傾いたと感じる読者もいるでしょう。そこに作品全体の呼吸の抜けが生まれます。
「虫」の名が示すもの
最終章の“私”には、安定に似た局面が訪れます。しかし内側からうごめく“虫”が、安心の膜を食い破ってしまう。ここでのネタバレは、幸福のハリボテが崩れるという一点に尽きます。金原ひとみは、約束の言葉よりも、胸の裏でかすかに走る疼きを信じさせるのです。
語り口の切れ味
文は冷静で、情は過剰。断定を避ける余白が多いのに、感情の波形は鋭い。視線の高さや動詞の選び方だけで、登場人物の自己評価が見えるのが巧妙です。
“落下”の物理
「星へ落ちる」という題は、上昇の幻想を裏返します。高みに向かうのではなく、眩しさの中心へ“落ちる”。愛はしばしば、主体的に選ぶ行為であると同時に、どこか不可抗力です。“私”“僕”“俺”は皆、抗えない引力の計算式に組み込まれていく。
不在の中心
“彼”が語り手にならないことで、読者はつねに推測を強いられます。欠けたピースは、作品を弱くするのではなく、三人称の陰影を濃くする。読み手の心の中に“第四の視点”が生まれる設計です。
関係の多様性とリアリティ
同性愛関係の存在は、物語を特殊化するための装置ではありません。むしろ、嫉妬・寂しさ・承認欲求といった普遍の感情を、角度を変えて照らすレンズとして機能しています。立場が入れ替わっても、痛みの構造は同じだと作品は語ります。
初出の散りばめ
各編は異なる媒体で発表されたものが集成されており、単体でも読める強度を備えます。同時に、集められることで一本の長編のような回転力が生まれる。表題作が最初に文芸誌に単発で出て、「サンドストーム」が雑誌『マリ・クレール』に載った経緯は、作品の質感の違いを説明する補助線になります。
タイトル群の呼応
「スープ」「サンド」「夢」「虫」――口に入るもの、風、睡眠、微生物。どれも境界をぼかす性質を持ちます。境界が侵食されるとき、人は自分の輪郭を保とうとして、かえって相手に深く依存していく。題の選び方自体が、侵入と混淆のテーマを下支えしています。
ことばにならない沈黙
会話の合間や、視線の泳ぎ、室内の空気の重さが、台詞以上に多くを語ります。発話の欠落は相手への無関心ではなく、恐れや後ろめたさの表現であり、読者は“言わない”ことの暴力を思い知らされます。
読後の余韻
はっきりした救済は提示されませんが、関係の糸が徐々に細り、ある地点でぷつりと切れる。切断は悲劇であると同時に再生の前提でもあります。星の落下が大地で終わらず、どこかで新しい軌道に乗る可能性を仄めかす終わり方です。
金原ひとみのキャリア上の位置
「星へ落ちる」は、受賞作以後の転調期に位置する仕事として重要です。後年の「マザーズ」「アタラクシア」へと続く、関係と自己像の再編を先取りする実験台でもある。年譜的にも“短編連作の精度”が確立していく局面に置けます。
いま読む理由
読むたびに年齢や経験の変化が反映され、別の痛点が疼きます。十代で読めば衝動の烈しさに、子育て期に読めば不安の持続に、別れを越えた後なら回復の鈍さに共鳴するでしょう。だから「星へ落ちる」は、時をまたいで手元に置きたい一冊です。
まとめ:「星へ落ちる」のあらすじ・ネタバレ・長文感想
「星へ落ちる」は、“彼”をめぐる三つの視点が入れ替わり、恋愛の歪みと渇きを浮かび上がらせる連作です。章ごとに語りの角度を変えることで、同じ出来事が異なる意味を帯びて見えます。
あらすじの段階では結論を曖昧に保ちつつ、ネタバレを踏むと、手に入れたはずの安定が別の不安を呼び込む循環が見えてきます。
「星へ落ちる」「僕のスープ」「サンドストーム」「左の夢」「虫」という配列は、侵入と混淆というテーマを多面的に照らします。読後、誰の心にも残るのは、“彼”という不在の中心と、その周りで揺れる三つの自意識の残響です。
関係は手にした瞬間から失いはじめる――この当たり前の事実を、金原ひとみは痛点に触れ続ける文章で可視化しました。いま“関係の揺らぎ”に向き合う読者に、「星へ落ちる」は鋭い鏡になります。