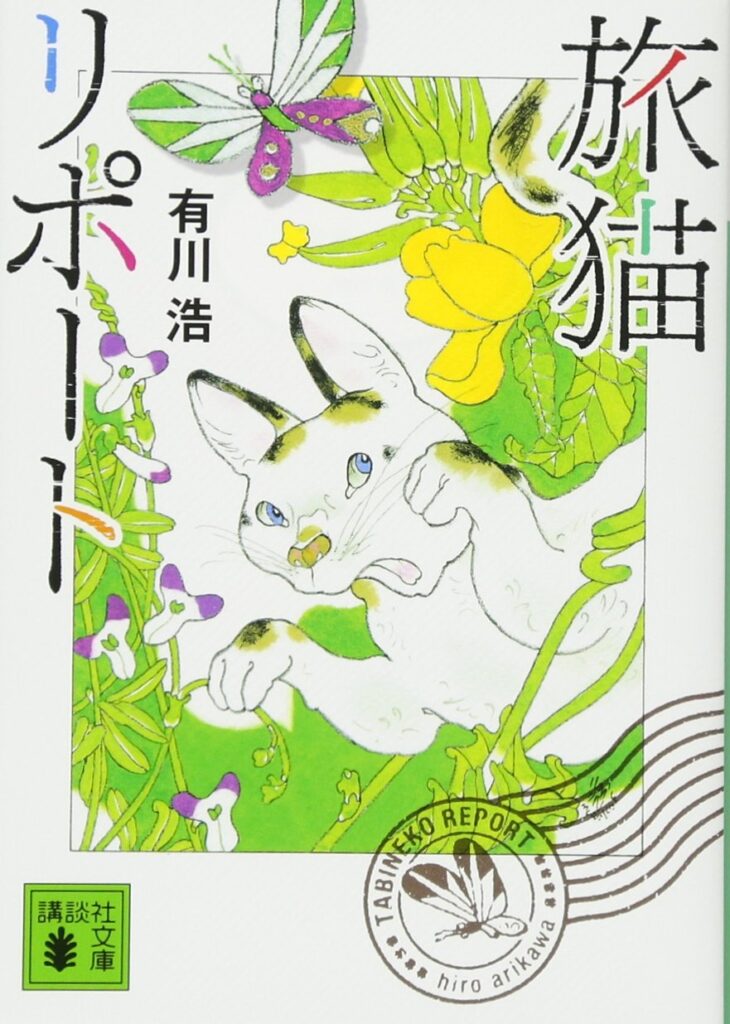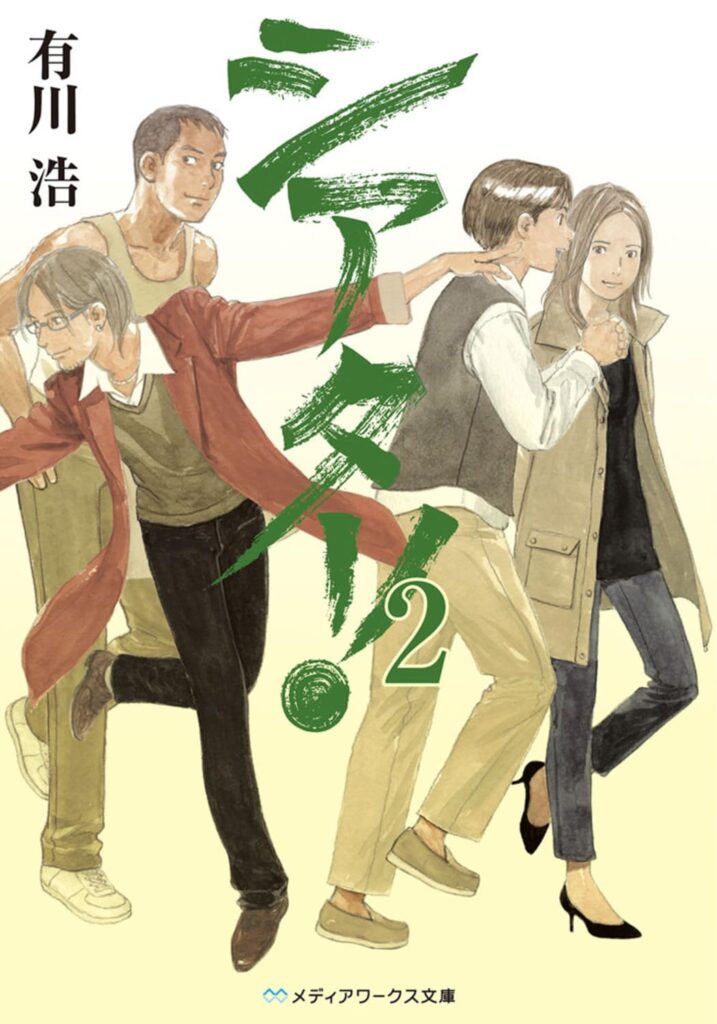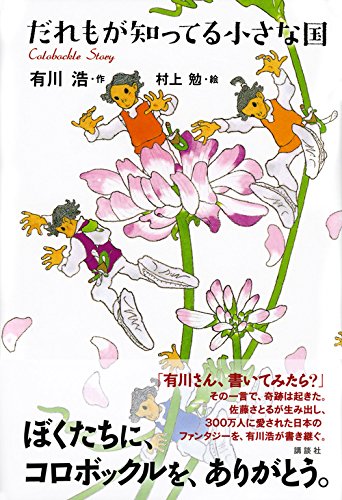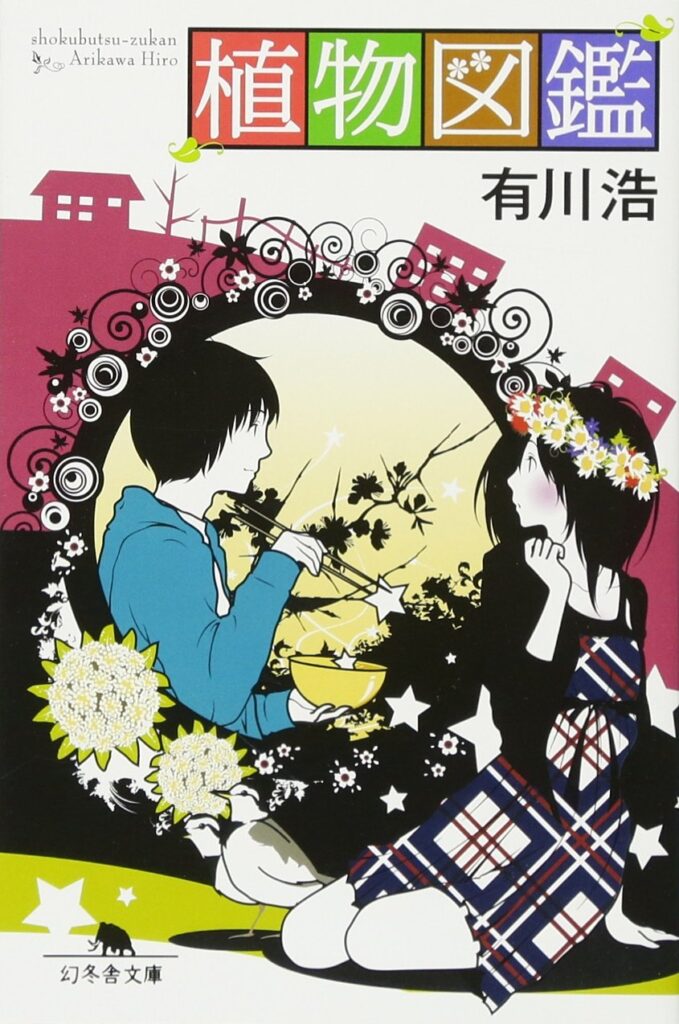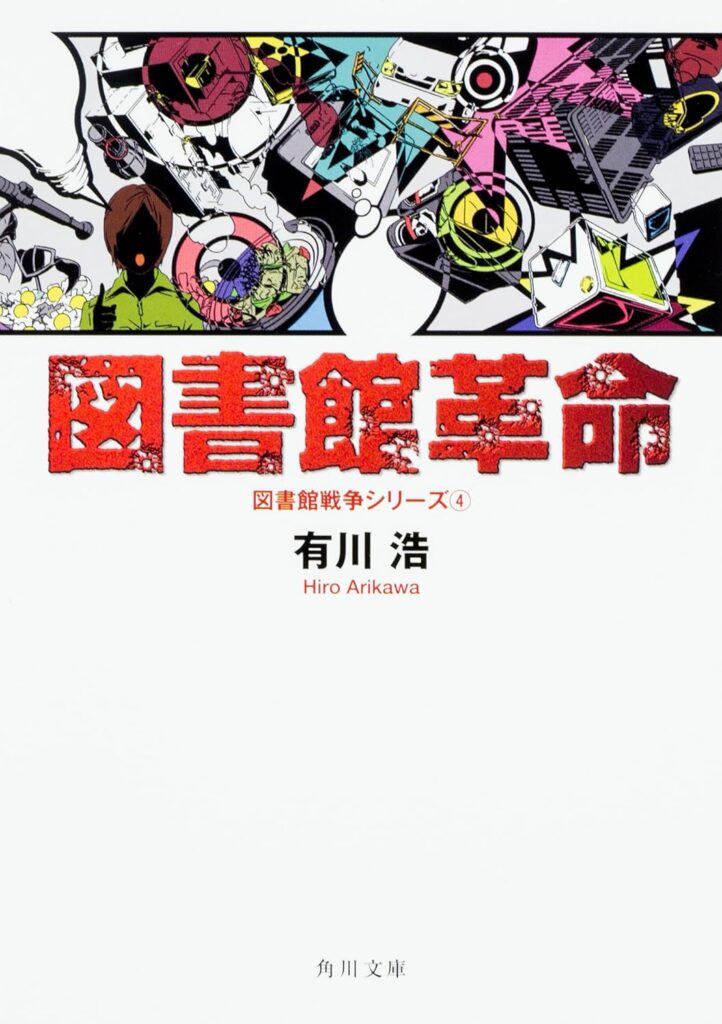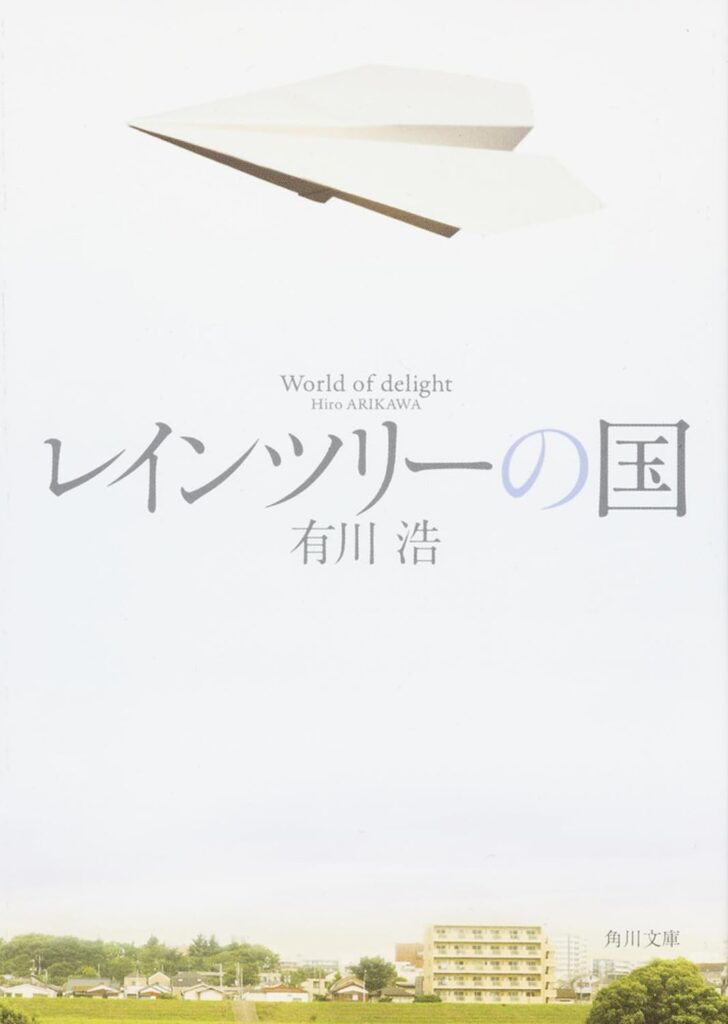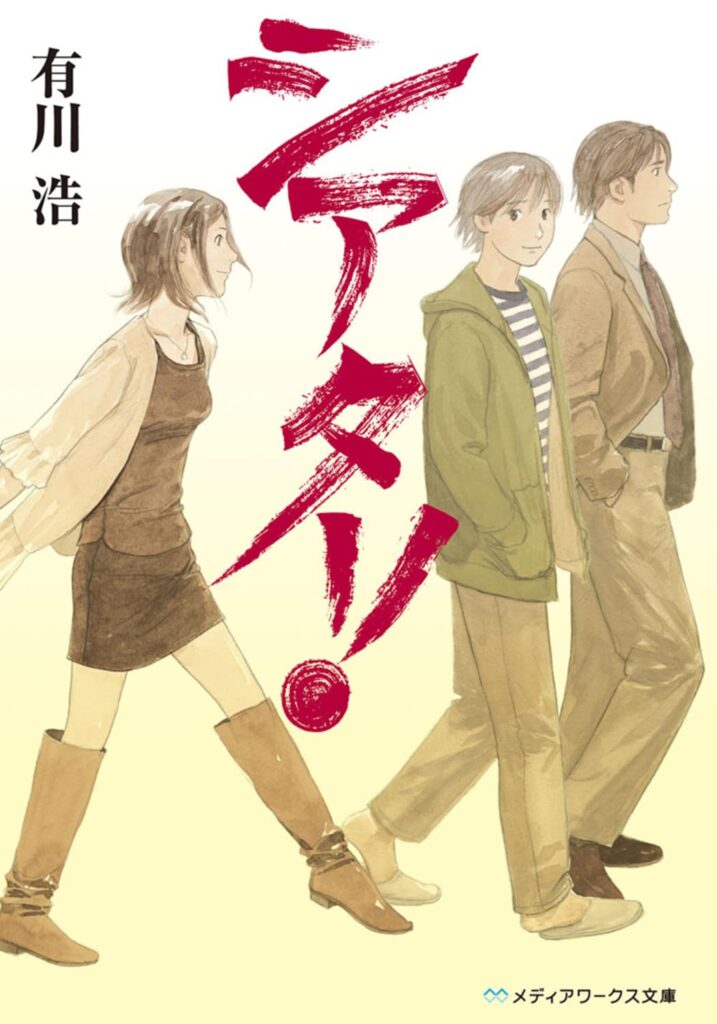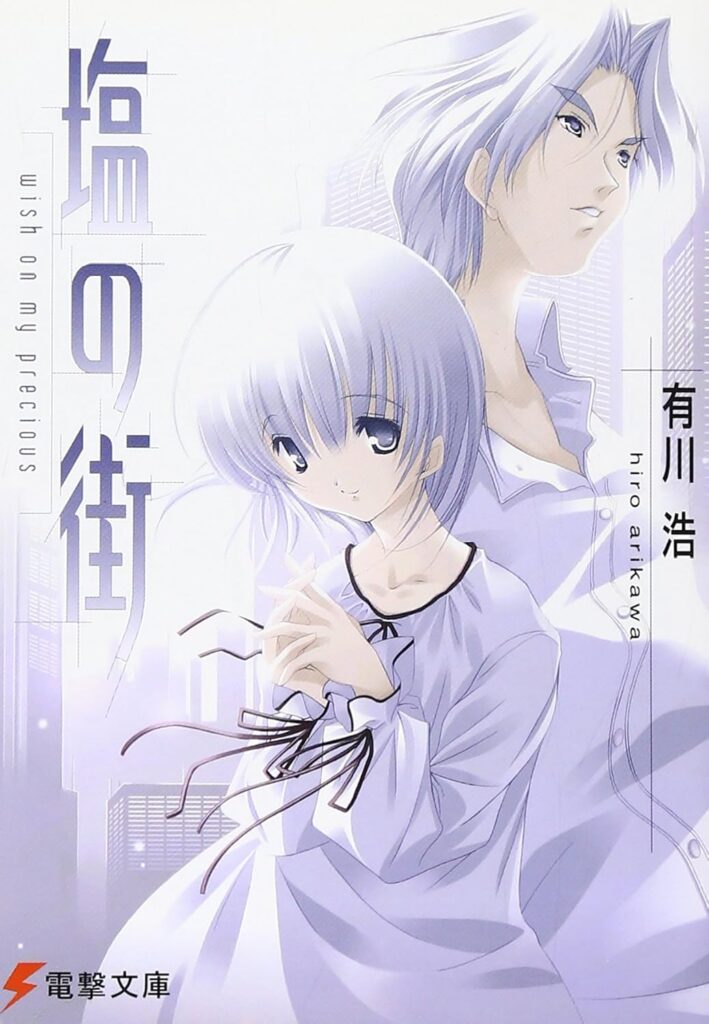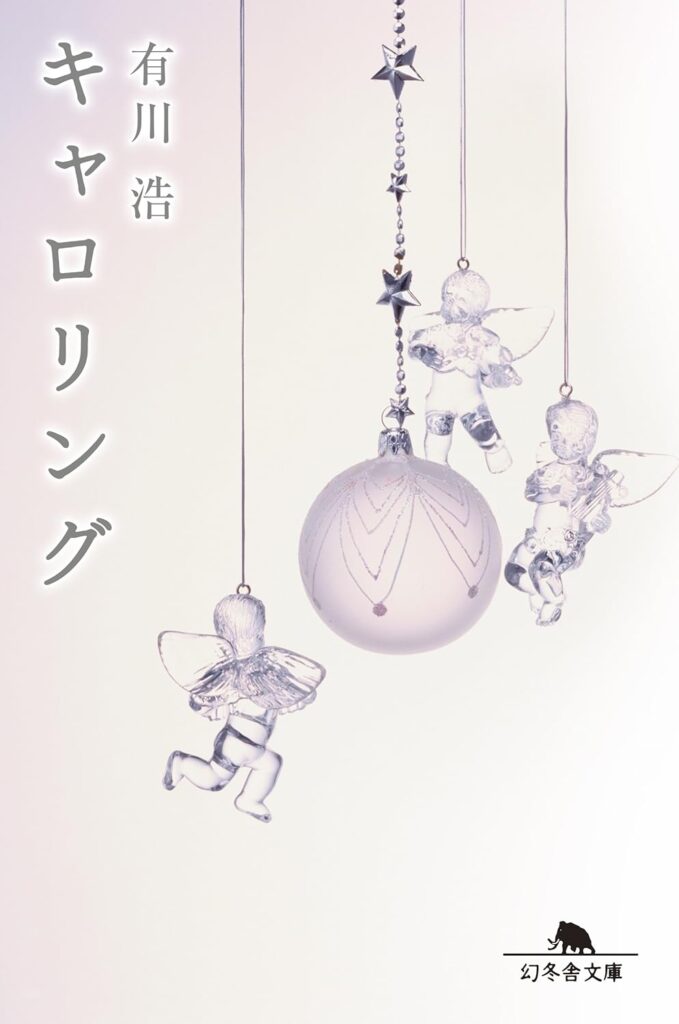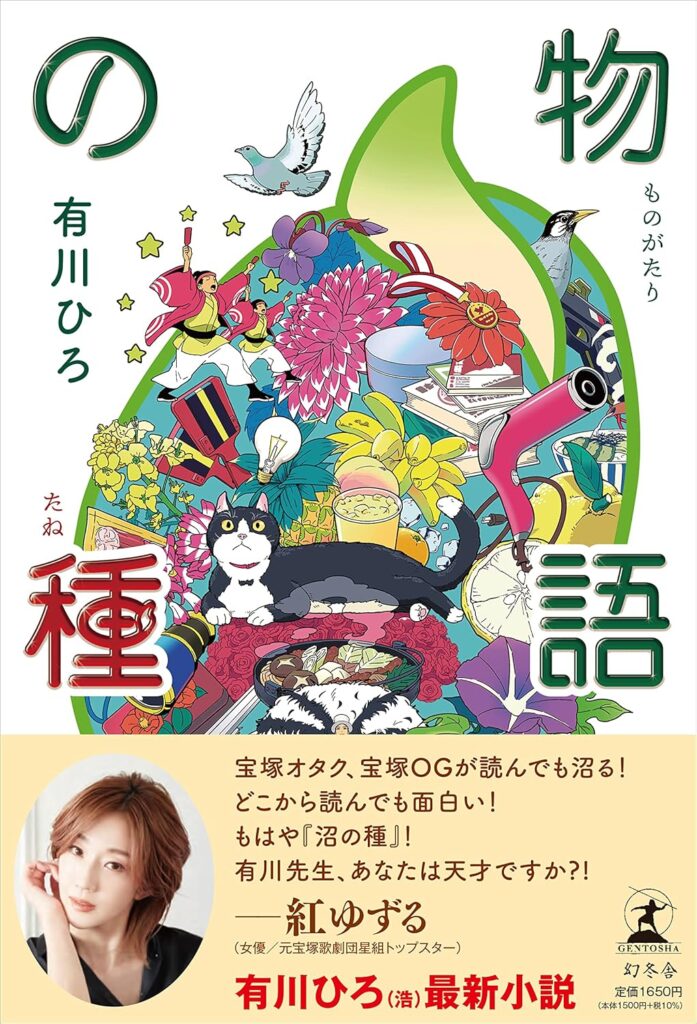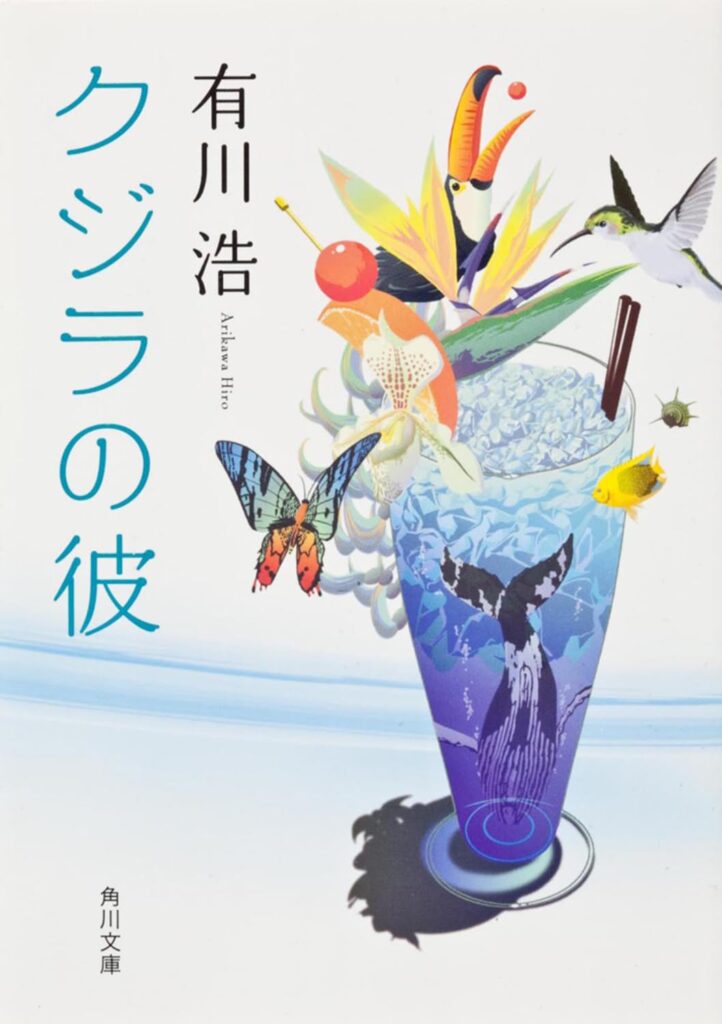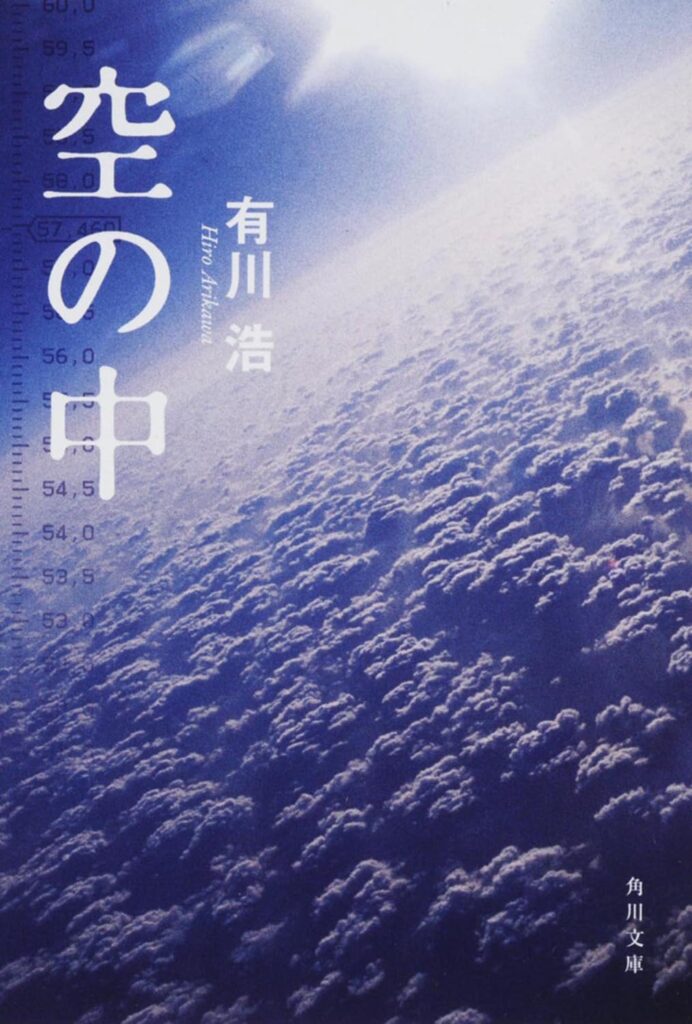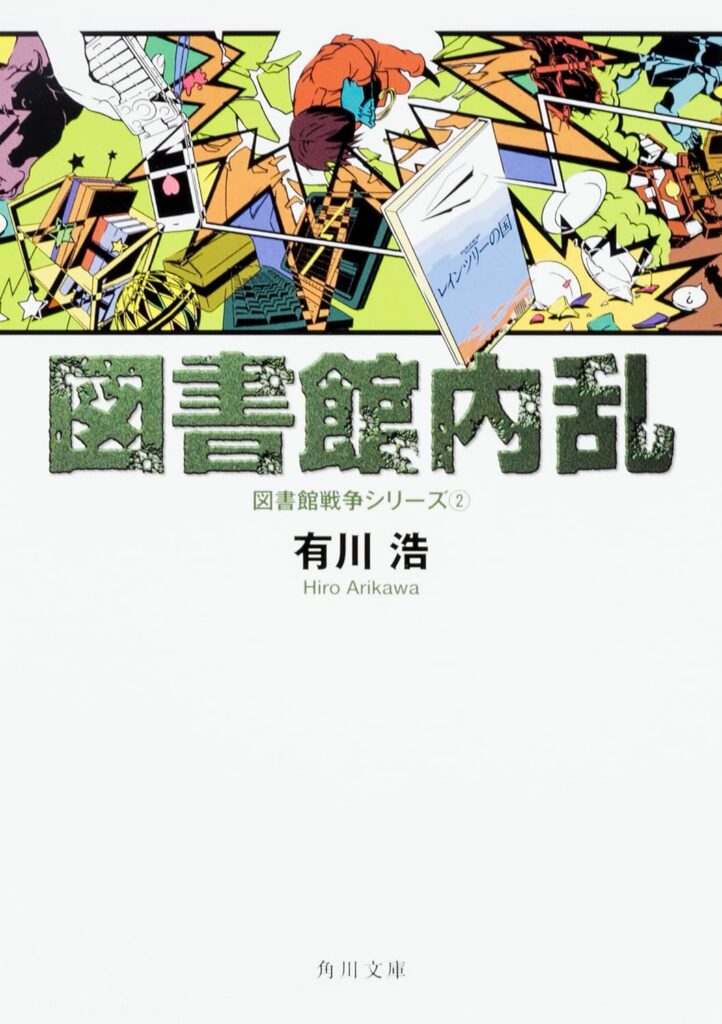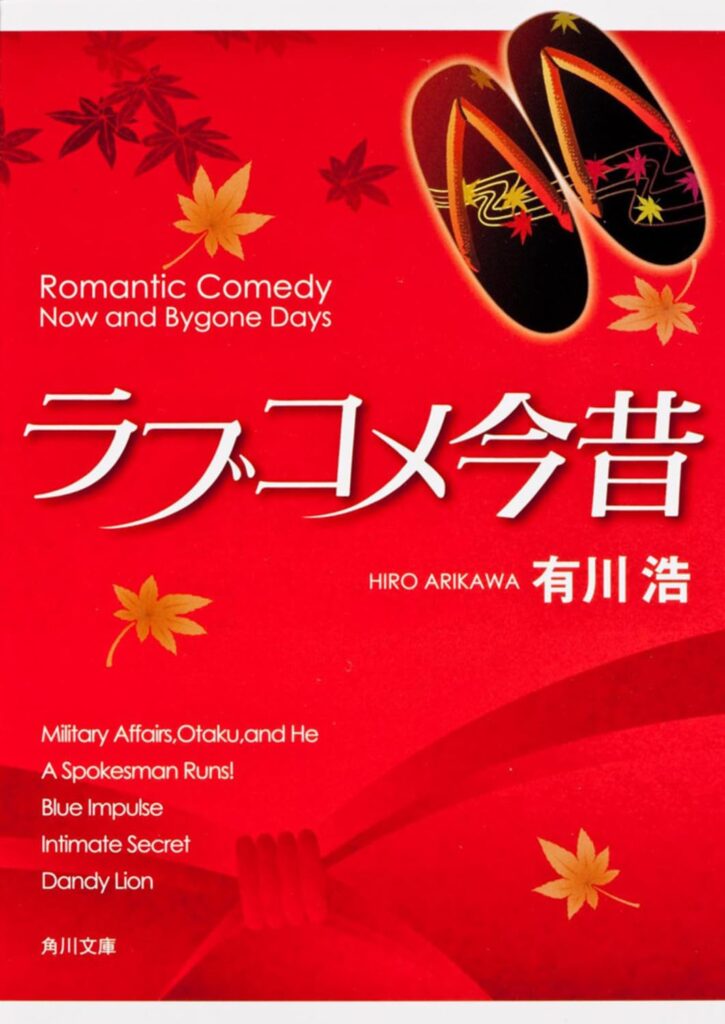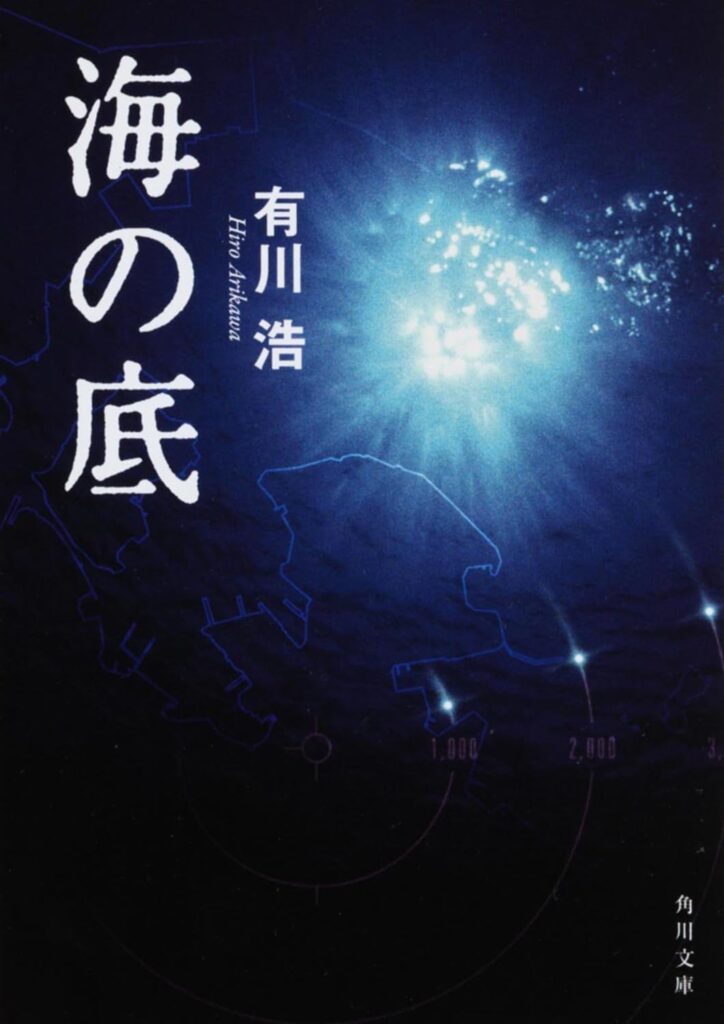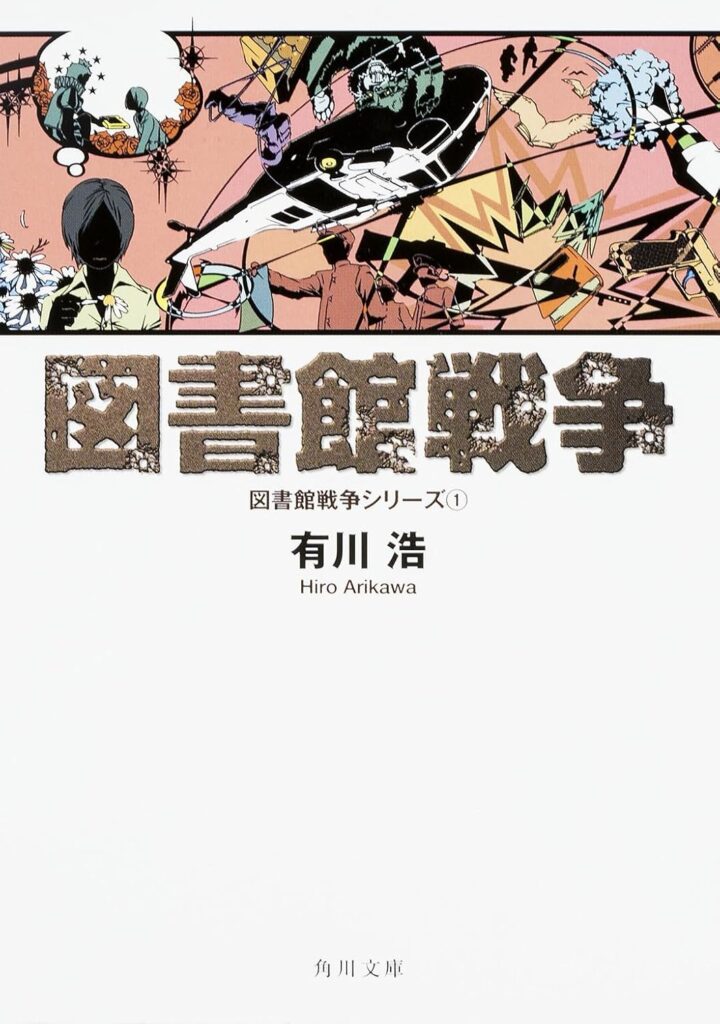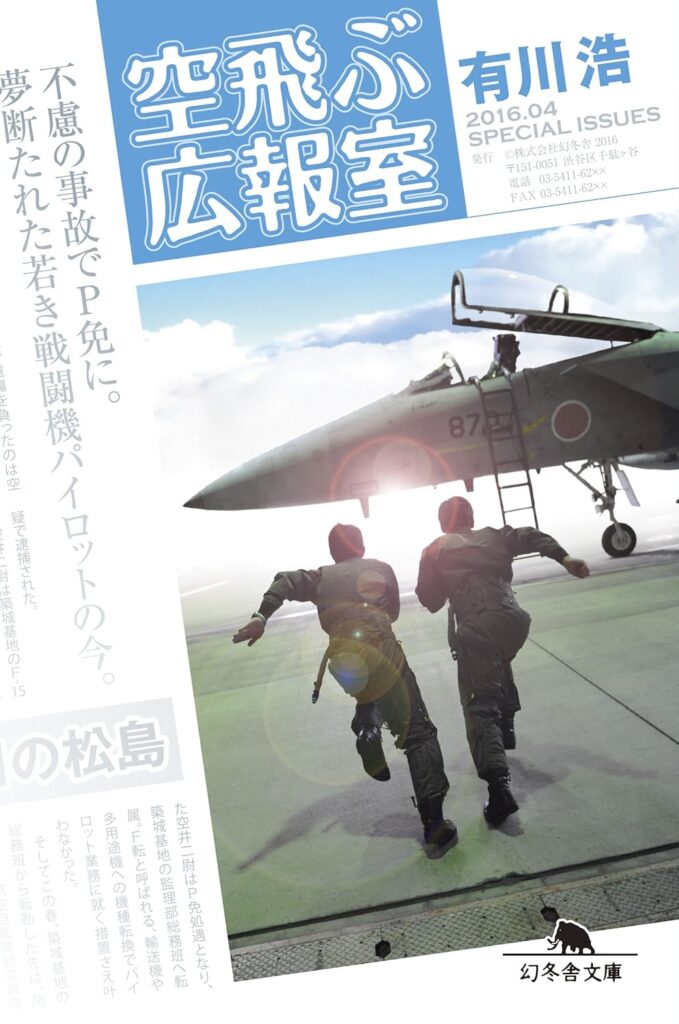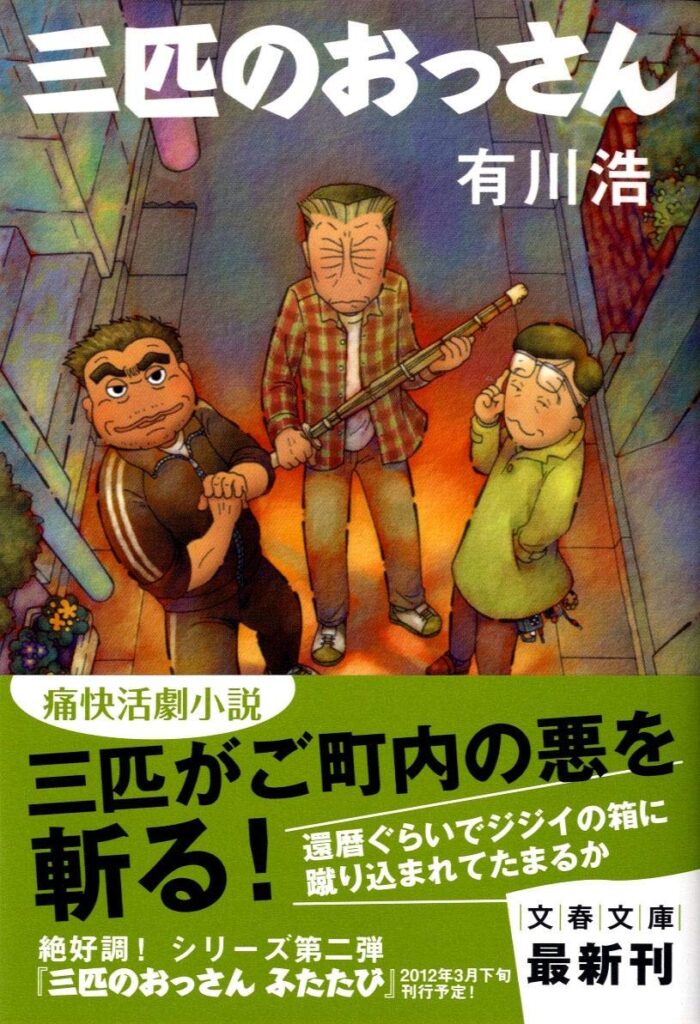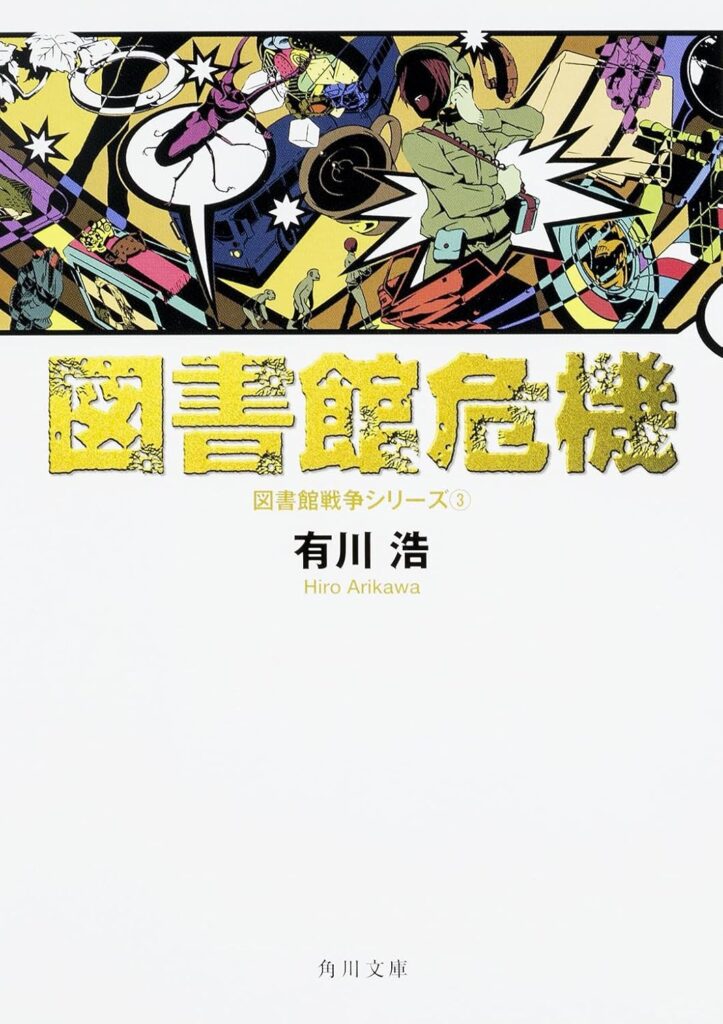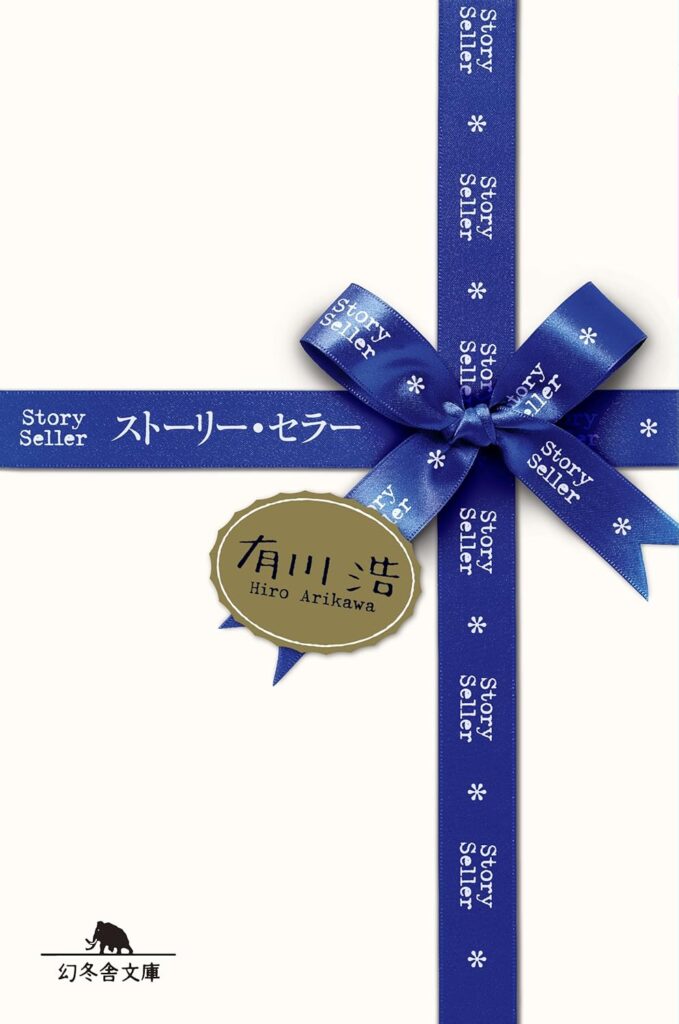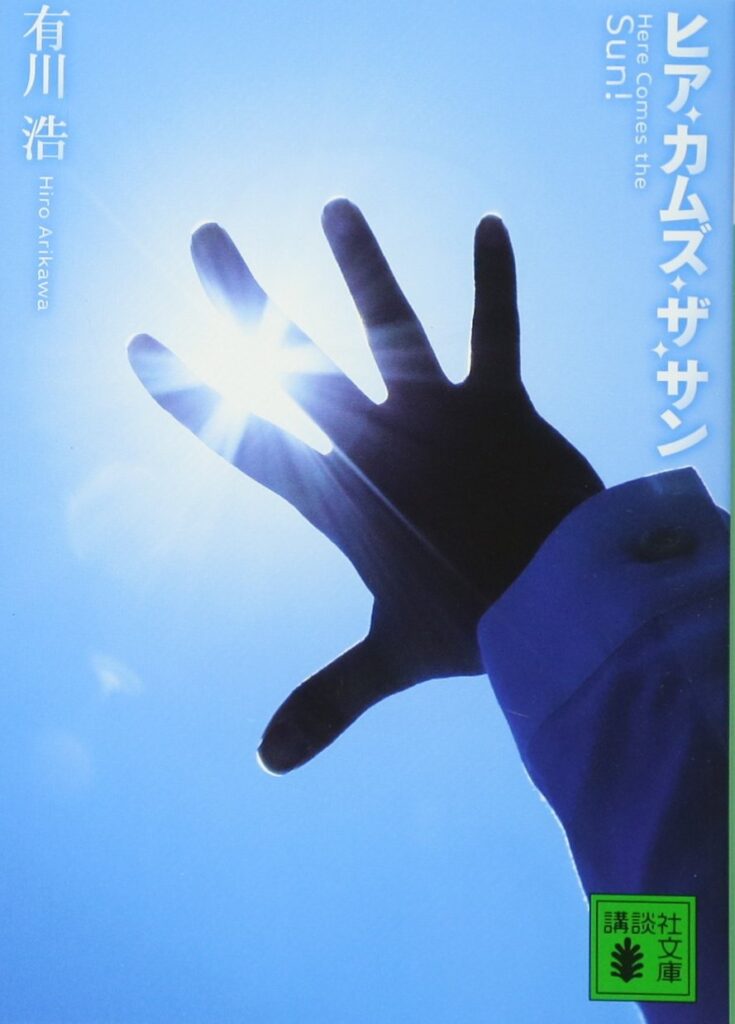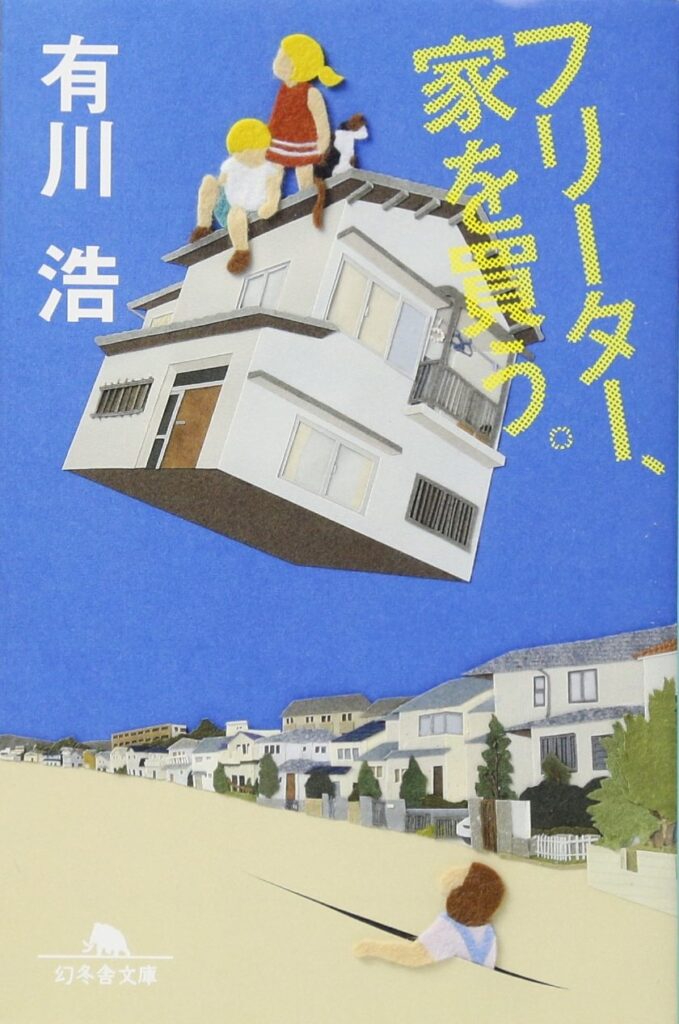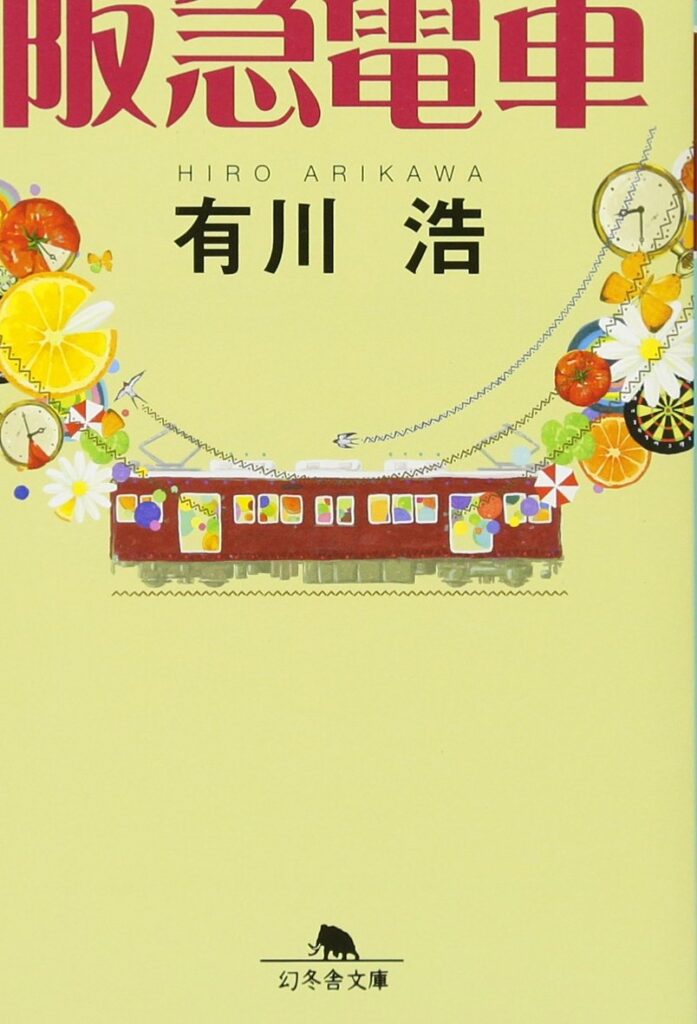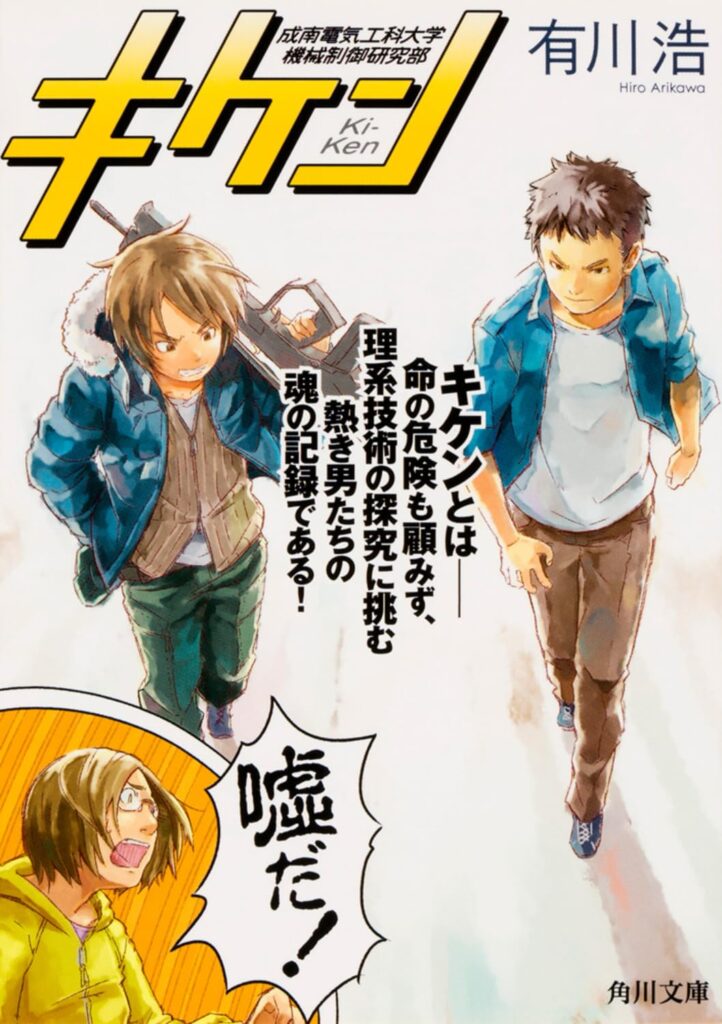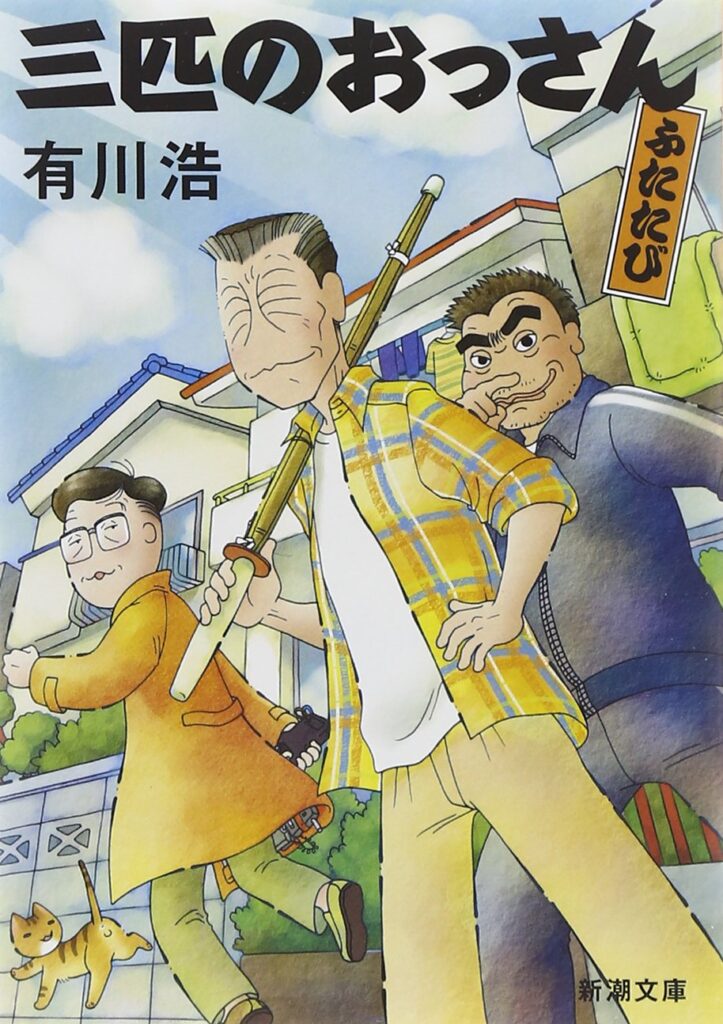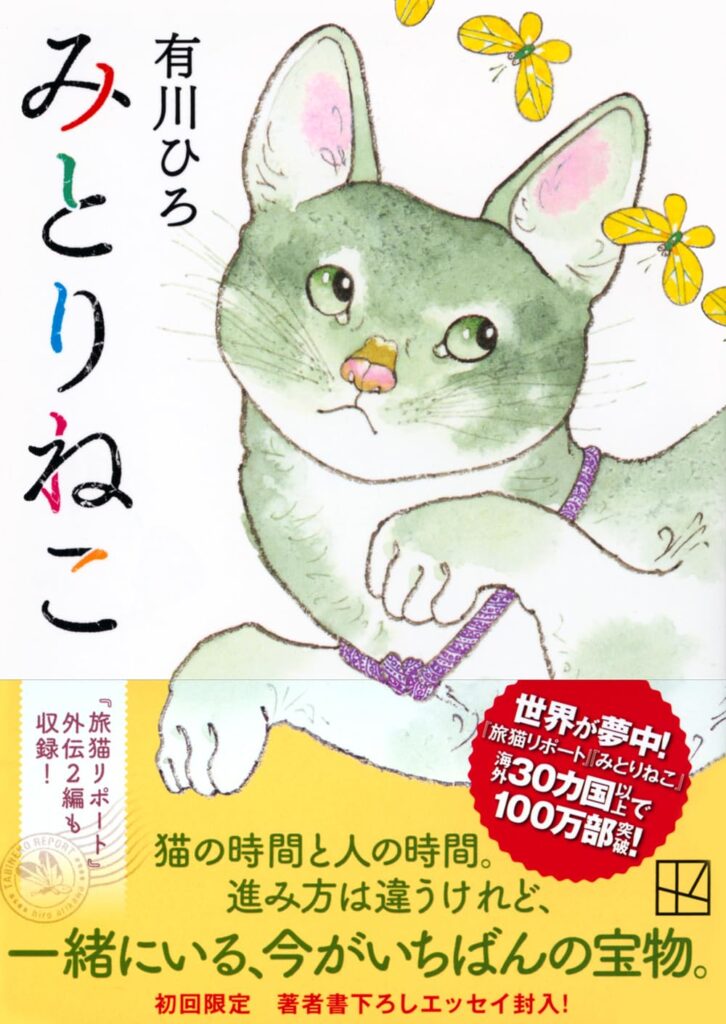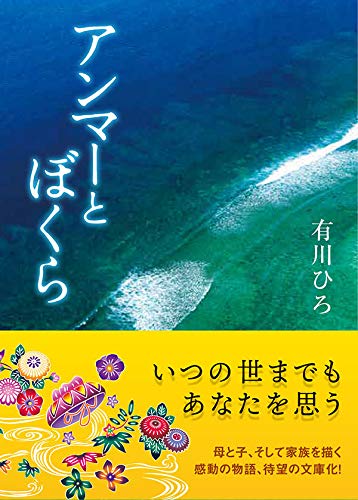小説「明日の子供たち」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。有川浩さんの作品の中でも、特に心に深く響く、社会的なテーマを扱った一冊です。児童養護施設「あしたの家」を舞台に、そこで働く職員と子供たちの日常、そして彼らを取り巻く社会の目を、温かくも鋭い視線で描いています。
小説「明日の子供たち」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。有川浩さんの作品の中でも、特に心に深く響く、社会的なテーマを扱った一冊です。児童養護施設「あしたの家」を舞台に、そこで働く職員と子供たちの日常、そして彼らを取り巻く社会の目を、温かくも鋭い視線で描いています。
この記事では、物語の結末に触れながら、その詳細なあらすじをお伝えします。どのような出来事が起こり、登場人物たちがどう変化していくのか、物語の核心に迫ります。単なるあらすじ紹介に留まらず、物語の背景にある問題点や、登場人物たちの心情の機微にも触れていきたいと思います。
さらに、私がこの物語を読んで感じたこと、考えさせられたことを、ネタバレを気にせずにたっぷりと書き連ねました。特に、作中で描かれる児童養護施設の現実や、子供たちの抱える想い、そして社会が彼らに向ける眼差しについて、深く掘り下げています。読み応えのある内容になっているかと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。
小説「明日の子供たち」のあらすじ
三田村慎平は、テレビで見たドキュメンタリー番組に心を動かされ、それまでの職を辞して児童養護施設「あしたの家」に転職してきた新米職員です。子供たちの力になりたい、そんな理想を持って飛び込んだ世界でしたが、現実は想像以上に複雑でした。「あしたの家」は、様々な事情から親と暮らせない子供たちが生活する場所。慎平は、そこで働く先輩職員や子供たちと関わる中で、多くの壁にぶつかることになります。
出勤初日、慎平は高校2年生の谷村奏子と出会います。人懐っこく話しかけてきた奏子に、慎平は転職の理由として「かわいそうな子どもの支えになりたいと思ったから」と正直に話してしまいます。この一言が、奏子の心を固く閉ざさせるきっかけとなりました。他の子供たちとは打ち解けていく慎平ですが、奏子だけは彼を「先生」と呼び続け、見えない壁を作り続けます。慎平は奏子と向き合おうとし、そこで初めて「かわいそうという自己満足に付き合わされるのは迷惑だ」という彼女の本心を知り、自身の浅はかさを謝罪します。これを機に、二人の関係は少しずつ変化していきます。
慎平の指導役である和泉和恵は、大学進学を希望する奏子のために、奨学金の情報を集めていました。「あしたの家」のような施設では、高校卒業後の進路として就職が推奨されることが多く、進学に関する情報は十分ではありませんでした。和泉のかつての指導役であった猪俣吉行は、進学に消極的な態度を見せます。彼には、かつて担当していた少女を進学させたものの、彼女が学費の問題で中退し、その後連絡が取れなくなったという苦い経験があったのです。猪俣は、自分のせいで少女を不幸にしてしまったという後悔を抱え続けていました。
物語は、施設退所後の子供たちを支援する「ひだまり」という場所との出会いを経て、新たな展開を迎えます。「ひだまり」は、施設を卒業した子供たちがいつでも帰ってこられる、心の拠り所となることを目指して作られた場所でしたが、行政からはその目的の曖昧さを指摘され、存続の危機に瀕していました。奏子は、「ひだまり」のような場所の必要性を訴えるため、「こどもフェスティバル」でプレゼンテーションを行うことを決意します。「あしたの家の子供たちは明日の大人たちです」という彼女の力強い訴えは、会場にいた人々の心を動かし、未来への希望を感じさせる結末へと繋がっていきます。物語を通して、職員たちもまた、過去の経験や子供たちとの関わりの中で成長していく姿が描かれます。
小説「明日の子供たち」の長文感想(ネタバレあり)
有川浩さんの「明日の子供たち」を読み終えた時、胸に温かいものが込み上げると同時に、ずしりとした重みを感じました。児童養護施設という、普段あまり深く知る機会のない世界を舞台に、そこで生きる子供たちと職員たちの姿が、非常に丁寧に、そして真摯に描かれていたからです。
物語は、新米職員の三田村慎平の視点から始まります。彼の「かわいそうな子供たちの支えになりたい」という純粋な、しかし浅はかとも言える動機は、おそらく多くの読者が児童養護施設に対して抱くであろう漠然としたイメージと重なるのではないでしょうか。私も読む前は、どこかで「大変な環境で育った、かわいそうな子たち」というフィルターを通して見ていた部分があったかもしれません。しかし、物語は早々に、その認識がいかに一方的で、当事者を傷つける可能性があるかを突きつけてきます。
奏子が慎平に言い放つ「かわいそうな子供に優しくしてやろうって自己満足にわたしたちが付き合わなきゃいけないの⁉ わたしたちは、ここで普通に暮らしてるだけなのに!」という言葉。これは、頭を強く殴られたような衝撃でした。彼女たちは、決して哀れみの対象として見られたいわけではない。むしろ、親からのネグレクトや虐待といった過酷な経験を経て、ようやくたどり着いた「ちゃんと毎日ごはんが食べられて、お腹すかなくて、ゆっくり眠れて、学校にも行かせてもらえて……先生たちも、ちゃんとわたしの話を聞いてくれる」場所で、ただ懸命に「普通」の日常を送ろうとしているのです。その切実な叫びに、私は胸が締め付けられる思いでした。慎平が自身の過ちに気づき、真摯に謝罪する場面は、読者である私自身の偏見をも省みるきっかけを与えてくれました。
物語の視点は、慎平だけでなく、先輩職員の和泉や猪俣、そして子供たちである奏子や久志へと移り変わっていきます。この多角的な視点によって、児童養護施設が抱える問題や、それぞれの立場での葛藤がより深く理解できるようになっています。
和泉先生の過去のエピソードも印象的です。高校時代に好きだった男の子が施設で暮らしていると知り、「私はそんなこと気にしないよ」と言ってしまったことへの後悔。「気にしない」という言葉が、相手を更に傷つけ、「住む世界が違う」と感じさせてしまった。悪意のない言葉ほど、時に残酷な刃となり得ることを教えられます。「わかった。でも好き」と言えていたら、未来は変わっていたかもしれない…そんな彼女の思いは、コミュニケーションの難しさ、相手の立場を真に理解することの大切さを物語っています。
猪俣先生の抱える後悔も、非常に重いものでした。担当していた少女の進学を後押しした結果、彼女が困難に直面し、行方知れずになってしまったという過去。善意が必ずしも良い結果に繋がるとは限らない、支援の難しさを痛感させられます。だからこそ、彼が再び前を向き、別の形で子供たちの未来を支えようとする姿や、偶然再会したかつての少女が自衛隊員として活躍し、大学の夜間部に通っていると知って涙する場面には、心からの安堵と感動を覚えました。彼の背負ってきた重荷が、少しでも軽くなった瞬間だったのではないでしょうか。
そして、子供たちの視点。特に奏子と久志の、高校生ながらに自身の将来と真剣に向き合う姿には、心を打たれます。親からの経済的な支援を期待できない彼らにとって、進学は非常に高いハードルです。奨学金の問題、卒業後の生活基盤。一般家庭の子供たちよりも遥かに多くのことを考え、覚悟を持って進路を選択しなければならない現実があります。「あしたの家」のような大規模施設では、職員一人ひとりが全ての子供に十分な時間をかけることが難しく、限られた情報の中で将来を決めなければならない厳しさも描かれています。それでも、彼らは自分の力で未来を切り開こうとします。久志が防衛大学校を目指し、奏子が「ひだまり」の存続のために声を上げる姿は、彼らの強さと、未来への意志を感じさせます。
作中で描かれる児童養護施設の日常も、非常にリアルです。職員たちの過酷な労働環境。シフト制勤務、膨大な業務量、決して高いとは言えない給与、そして高い離職率。「三年続いたら古株」という言葉が、その厳しさを物語っています。子供たちへの愛情は当然ありますが、「愛」と「甘やかし」は違うという線引きの難しさも描かれます。慎平が最初にしたように、良かれと思ってしたことが、集団生活の規律を乱したり、他の職員の負担を増やしたりすることに繋がる可能性もある。限られた人員で多くの子供たちの生活を支えるためには、時に非情とも思える判断が必要になる。職員たちの葛藤や疲弊も、丁寧に描かれていました。
物語の後半で登場する「ひだまり」の存在は、一つの希望として描かれます。施設を卒業した後、頼る場所がなく社会的に孤立してしまう子供たちは少なくありません。「ひだまり」は、そんな彼らがいつでも「帰って来れる場所」、心のセーフティネットとして機能しようとしていました。しかし、その「目的の曖昧さ」が行政から問題視され、予算削減の対象とされてしまう。このエピソードは、児童福祉、特に施設退所後の支援に対する社会的な理解や予算配分がいかに不十分であるかという問題を提起しています。奏子が「こどもフェスティバル」で「ひだまり」の必要性を訴える場面は、物語のクライマックスであり、強いメッセージ性を帯びています。選挙権を持たない子供たちの声は、社会に届きにくい。だからこそ、彼らの言葉に耳を傾け、その未来を支える仕組みを作っていく必要性を強く感じさせられました。奏子の言葉が県議会議員の心を動かしたように、社会全体が、まるで固く閉ざされた扉を開けるように、彼らの声に耳を傾ける必要があるのだと思います。
そして、この物語を語る上で絶対に外せないのが、文庫版に収録されている解説です。物語の最後に置かれた、笹谷実咲さんという方の手記。彼女こそが、作中で奏子が書いた手紙のモデルであり、実際に有川浩さんに「児童養護施設のことを書いてほしい」と手紙を送った当事者だったのです。この事実を知った時、物語で描かれてきた出来事や感情が一気に現実味を帯び、フィクションと現実が地続きになったような感覚に襲われました。それまで堪えていた涙が、堰を切ったように溢れ出したのを覚えています。一人の少女の切実な願いが、この素晴らしい物語を生み出した。その事実に、改めて深い感動を覚えました。笹谷さんの勇気と、それに応えた有川浩さんの真摯な姿勢に、心からの敬意を表したいです。
「明日の子供たち」は、単なる感動的な物語ではありません。児童養護施設を取り巻く厳しい現実、社会の無理解や偏見、子供たちの切実な思い、職員たちの葛藤と奮闘。それらを真摯に描き出し、私たち読者に「知ること」「考えること」を促してくれる作品です。読後、施設の子供たちへの見方が変わったという人は少なくないでしょう。私もその一人です。「かわいそう」という言葉で片付けるのではなく、彼らがどのような状況で、何を思い、どのように生きているのか、想像力を働かせ、理解しようと努めること。それが、私たちにできる第一歩なのかもしれません。登場人物たちの成長と、未来への確かな希望を感じさせてくれる、温かくも力強い一冊でした。
まとめ
有川浩さんの小説「明日の子供たち」は、児童養護施設「あしたの家」を舞台に、新米職員の三田村慎平や子供たち、そして彼らを取り巻く人々の姿を描いた、心温まる、そして深く考えさせられる物語です。ネタバレを含むあらすじを紹介しましたが、物語の核心にあるのは、登場人物たちの葛藤や成長、そして社会が抱える課題です。
この記事では、物語の詳細なあらすじと共に、私が感じたことや考えたことを長文で綴らせていただきました。「かわいそう」という一方的な視点の危うさ、施設の子供たちが抱える現実と彼らの強さ、職員たちの奮闘と苦悩、そして施設退所後の支援の重要性など、多くのテーマが織り込まれています。特に、文庫版解説で明かされる、この物語が生まれた背景には、心を揺さぶられました。
「明日の子供たち」を読むことで、児童養護施設という場所や、そこで暮らす子供たちへの理解が深まるはずです。彼らは決して「かわいそう」なだけの存在ではなく、私たちと同じように悩み、笑い、未来に向かって懸命に生きている隣人です。この物語が、社会の偏見を少しでも解き、温かい眼差しを向けるきっかけとなることを願っています。感動と、大切な問いかけを与えてくれる、素晴らしい作品です。