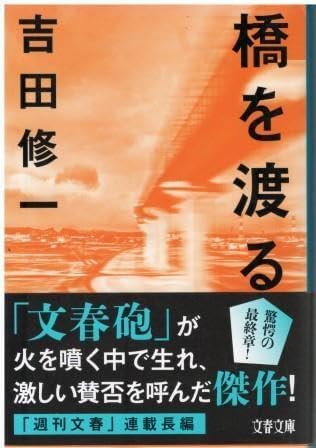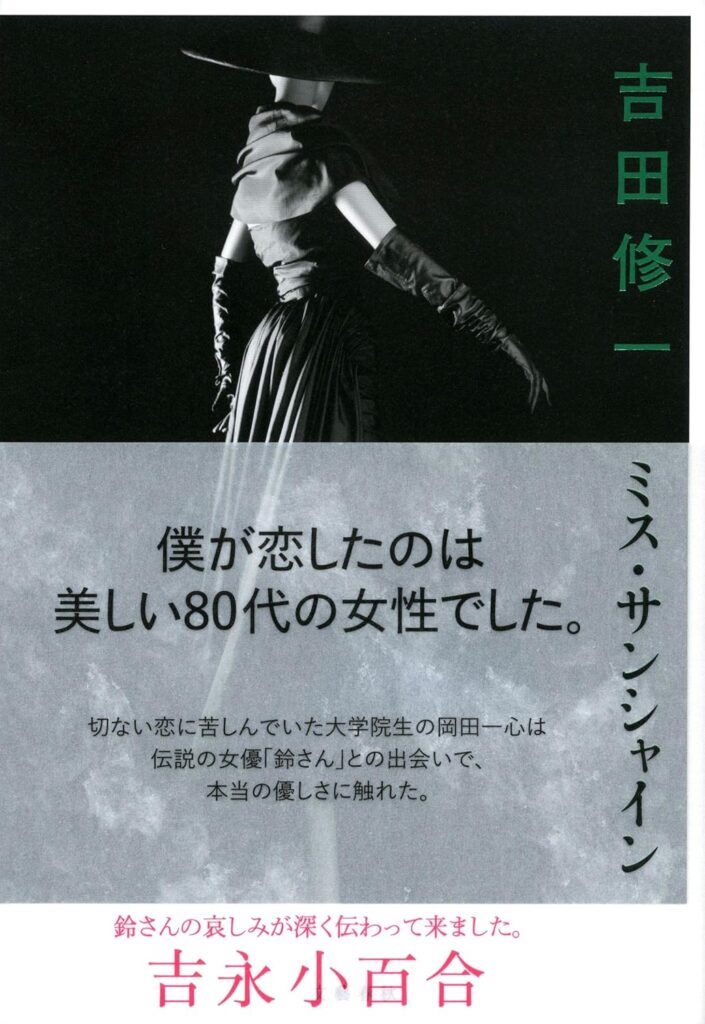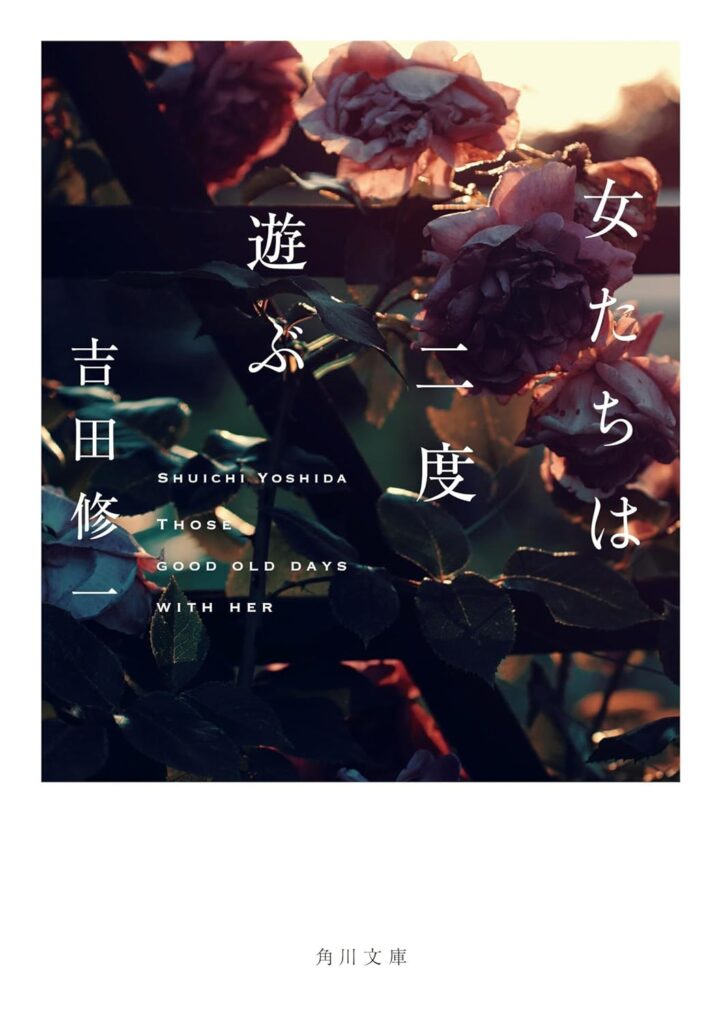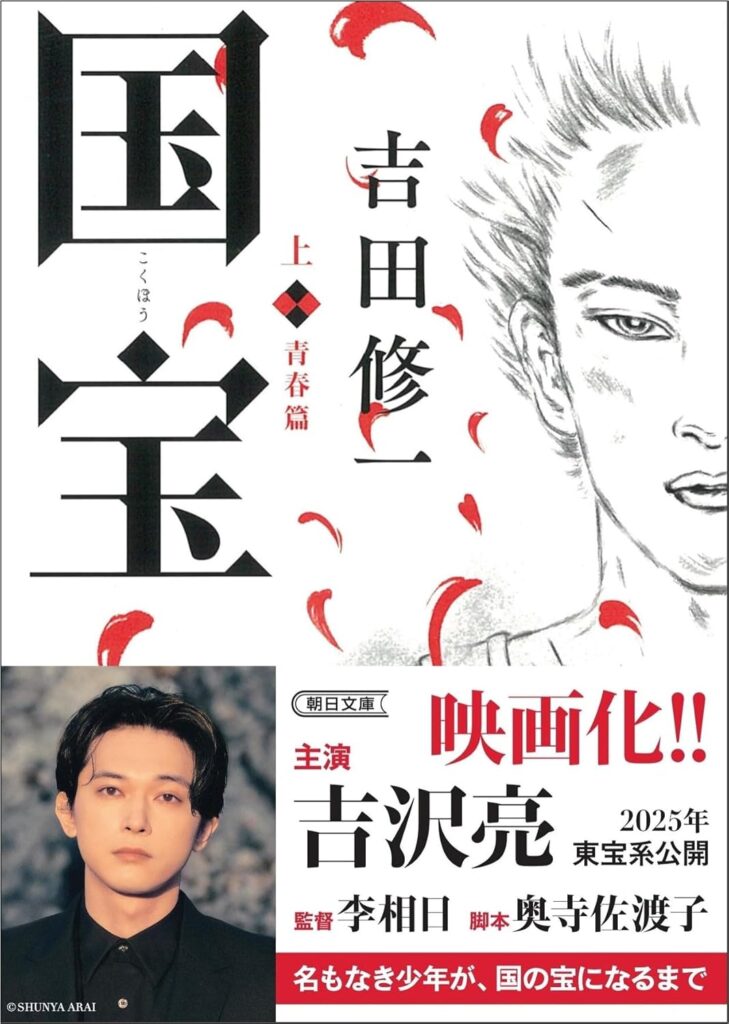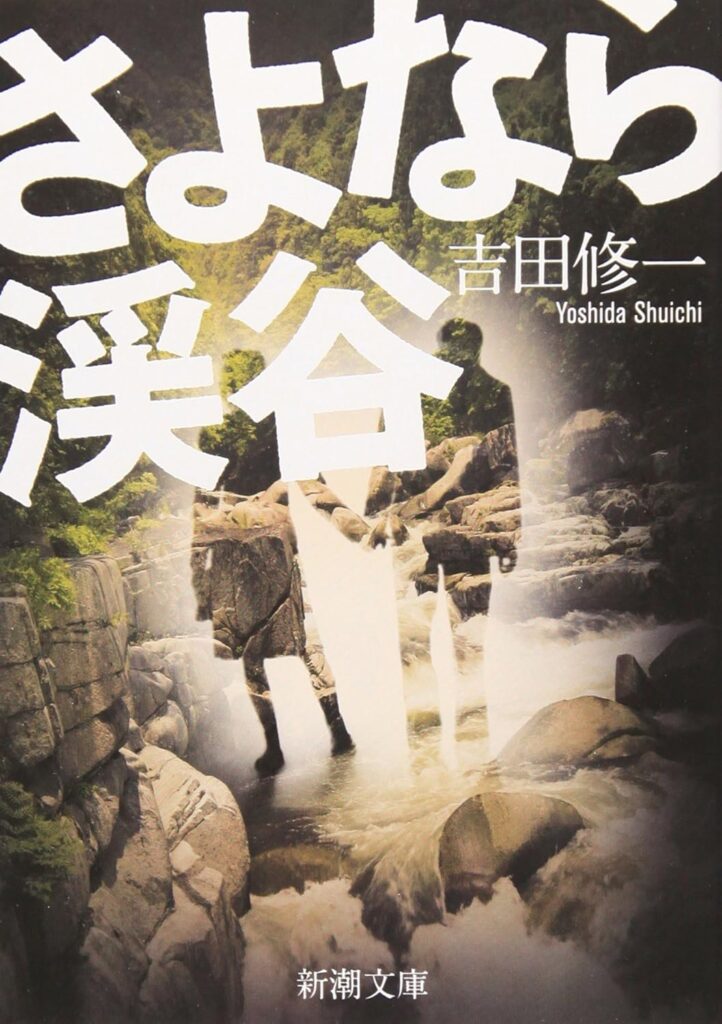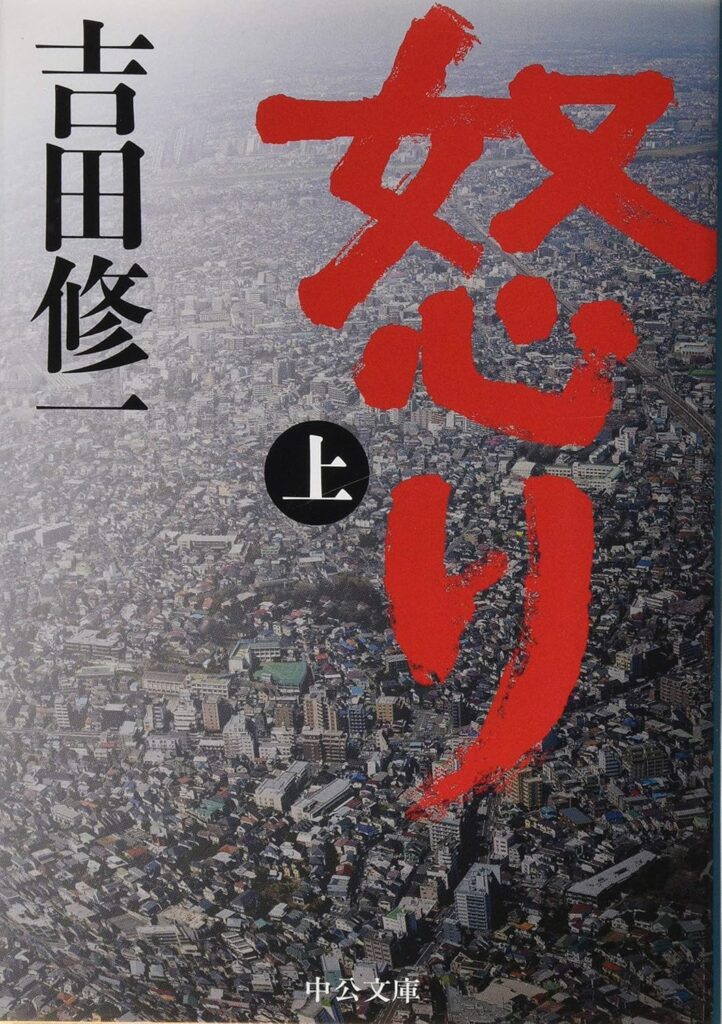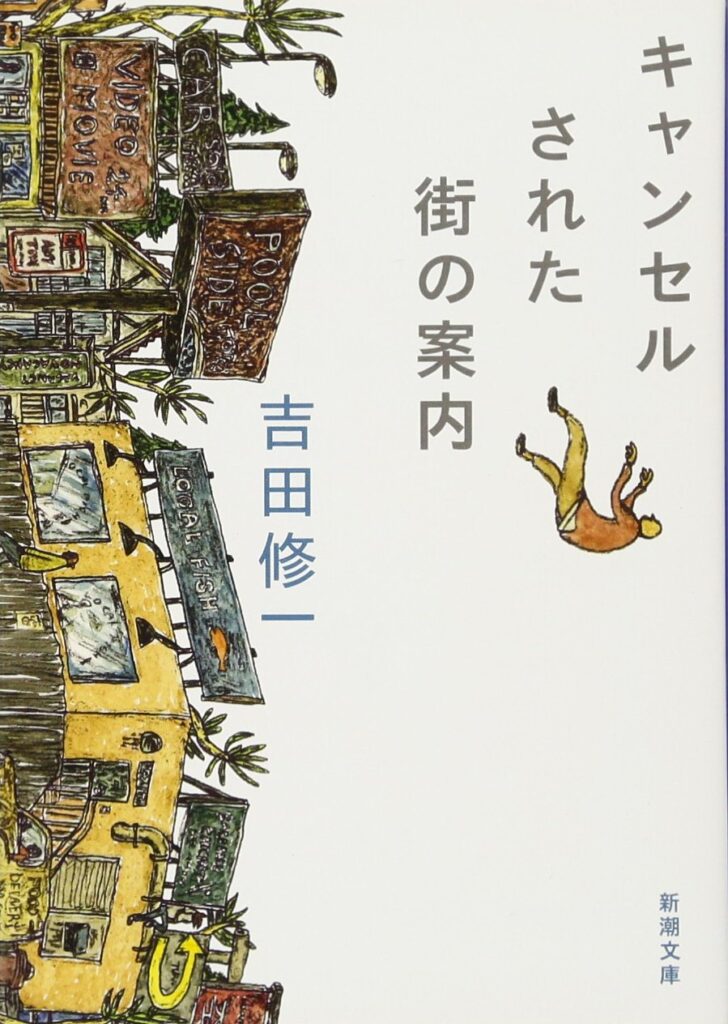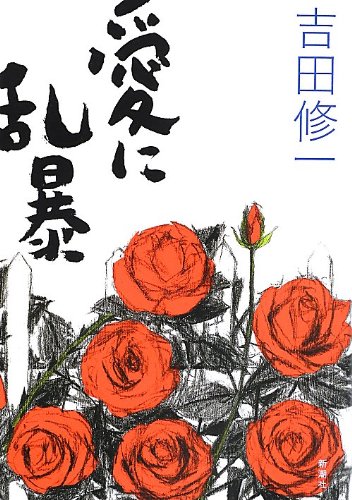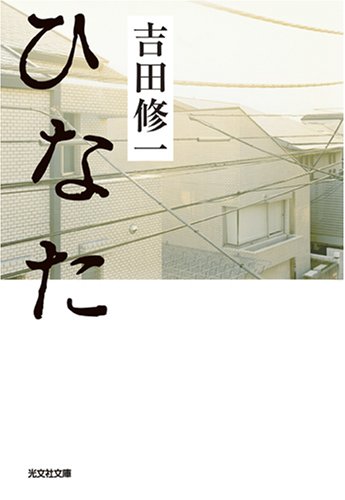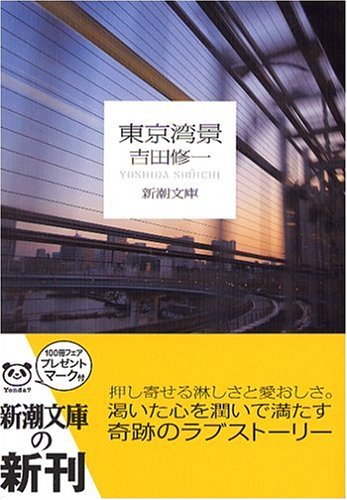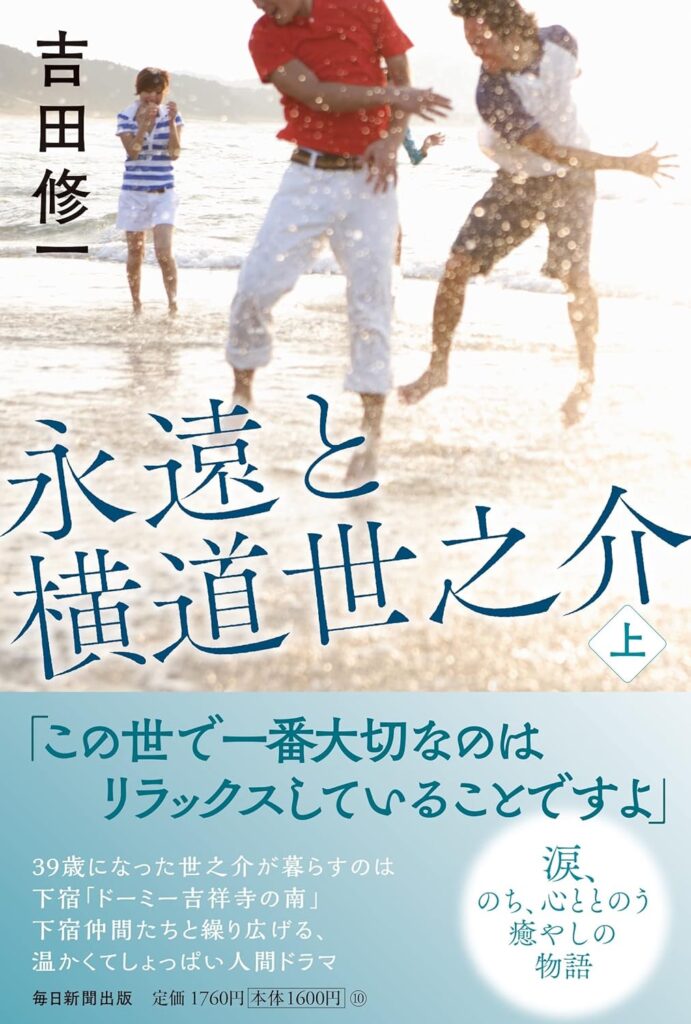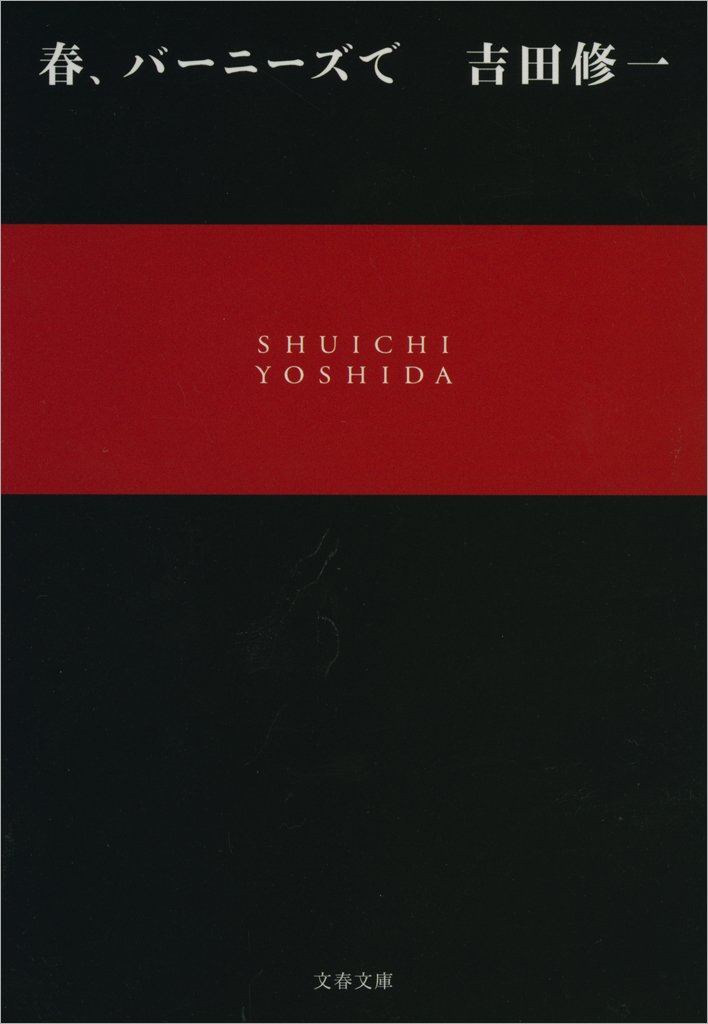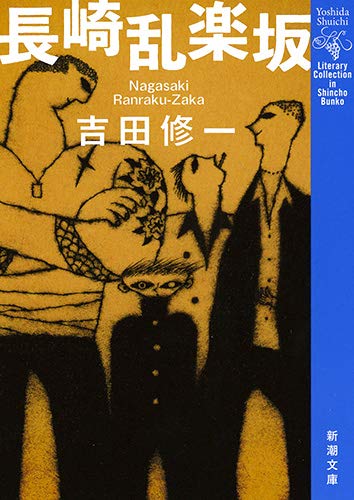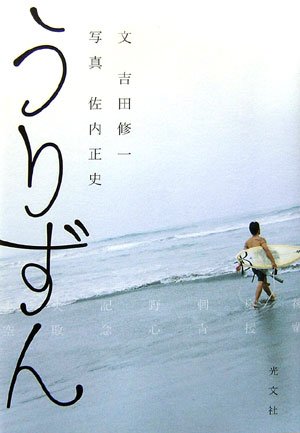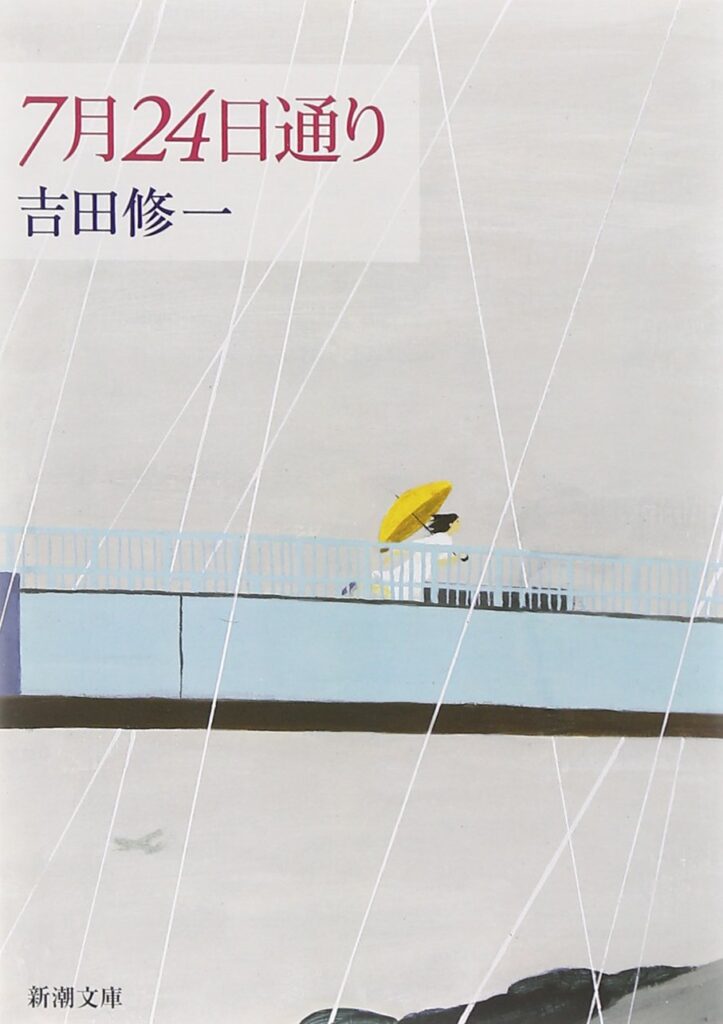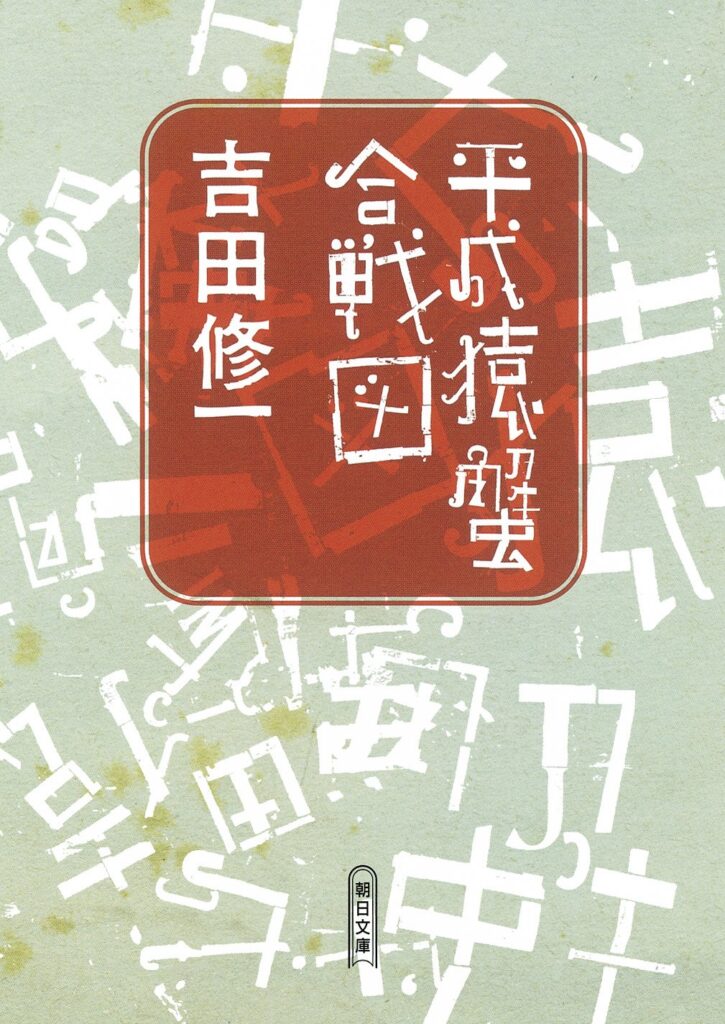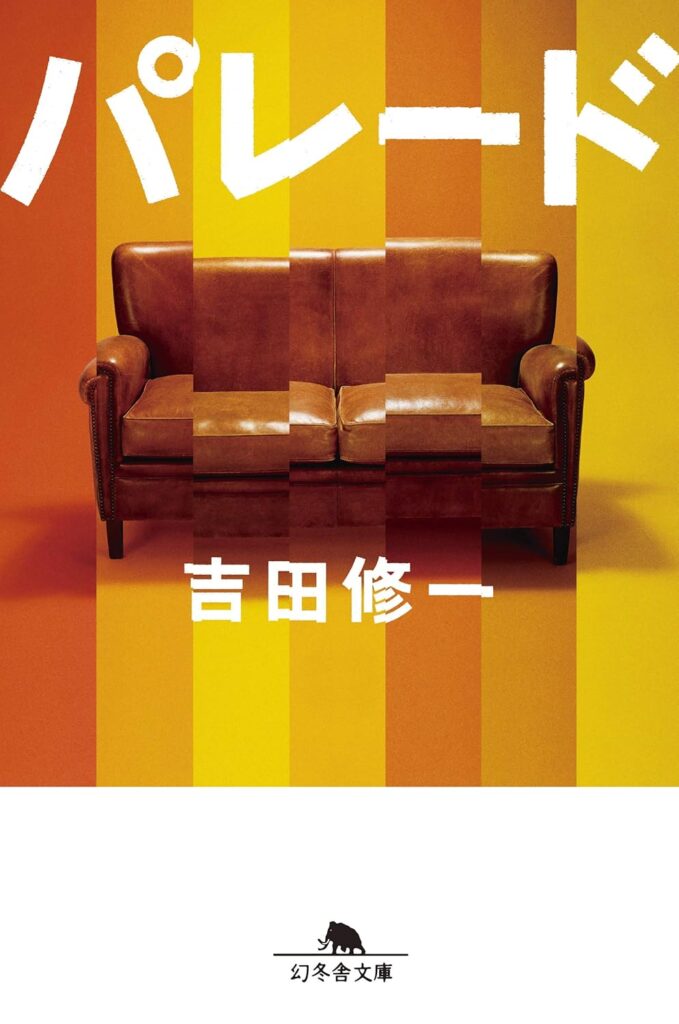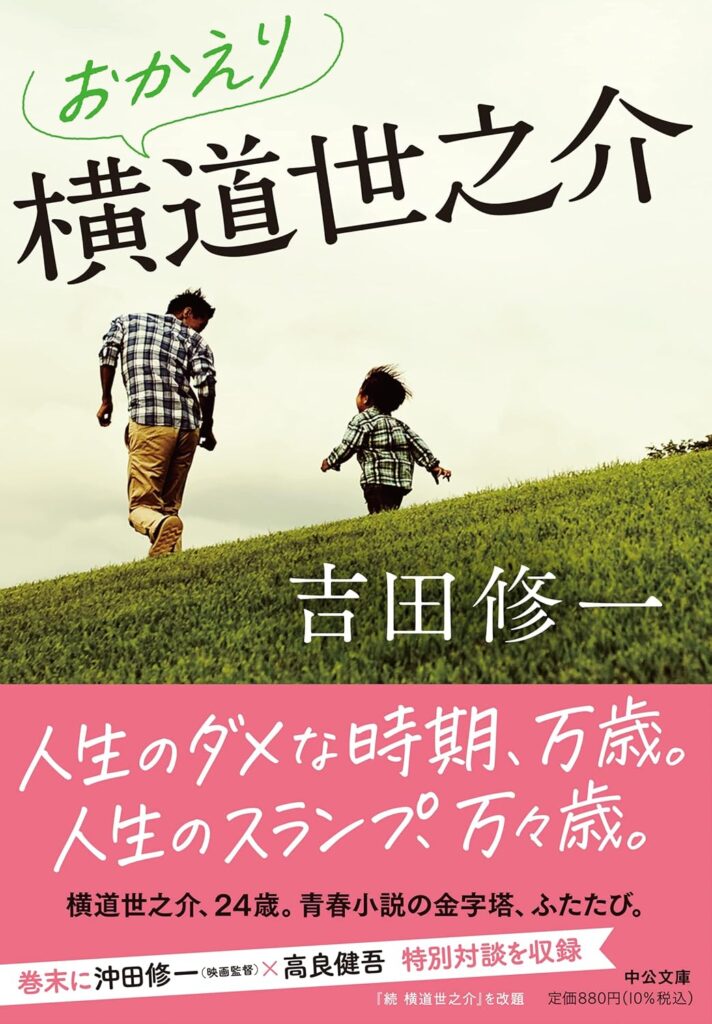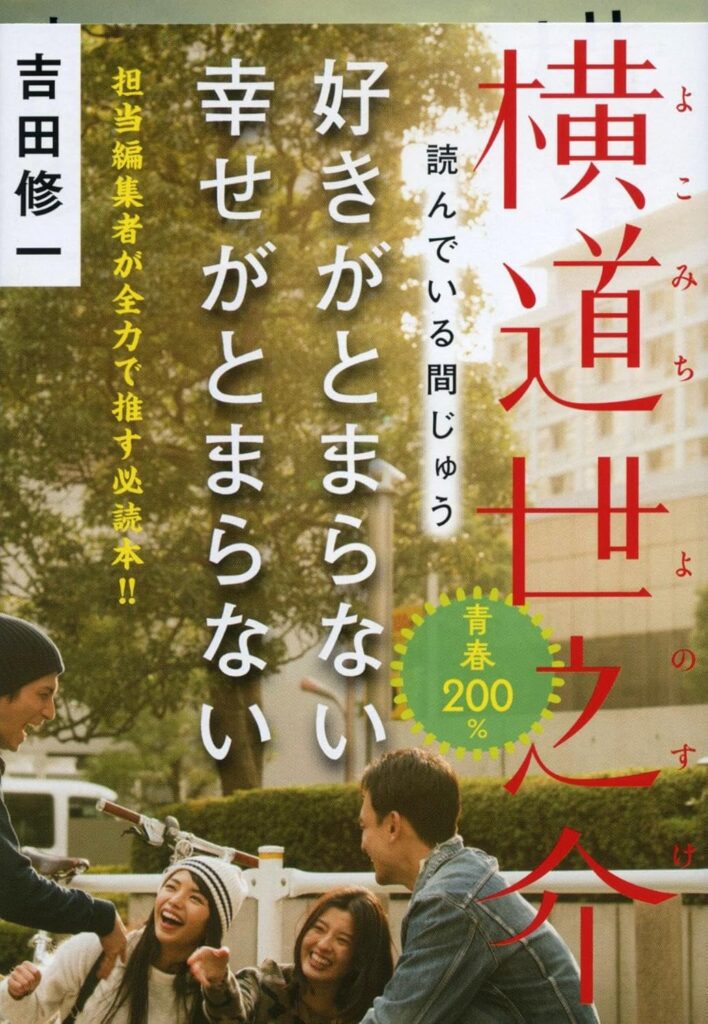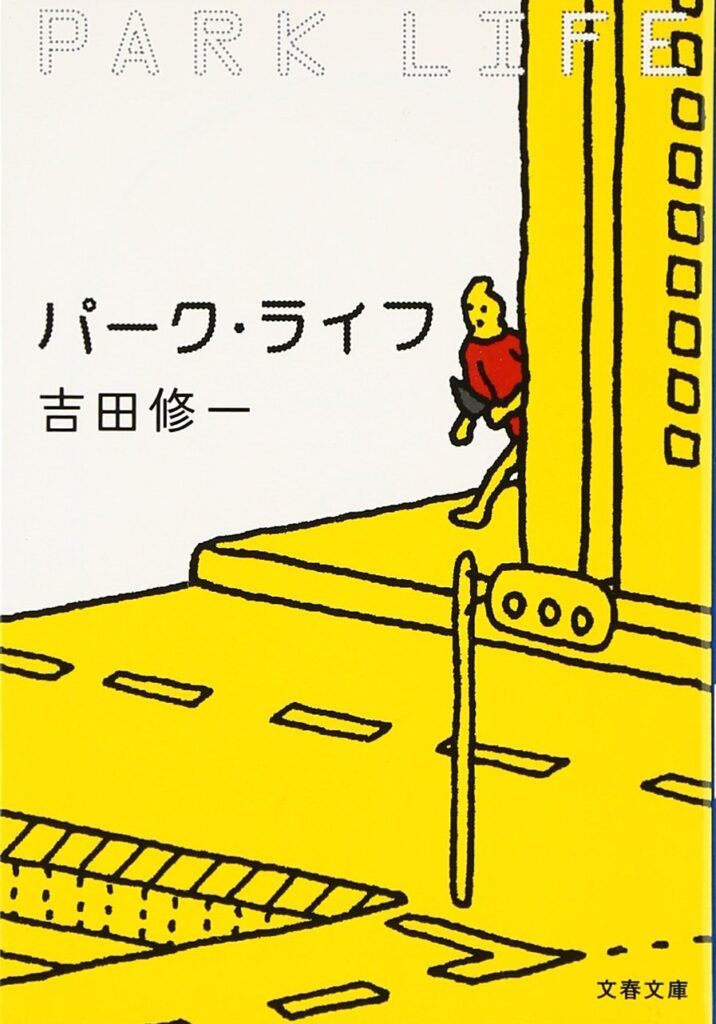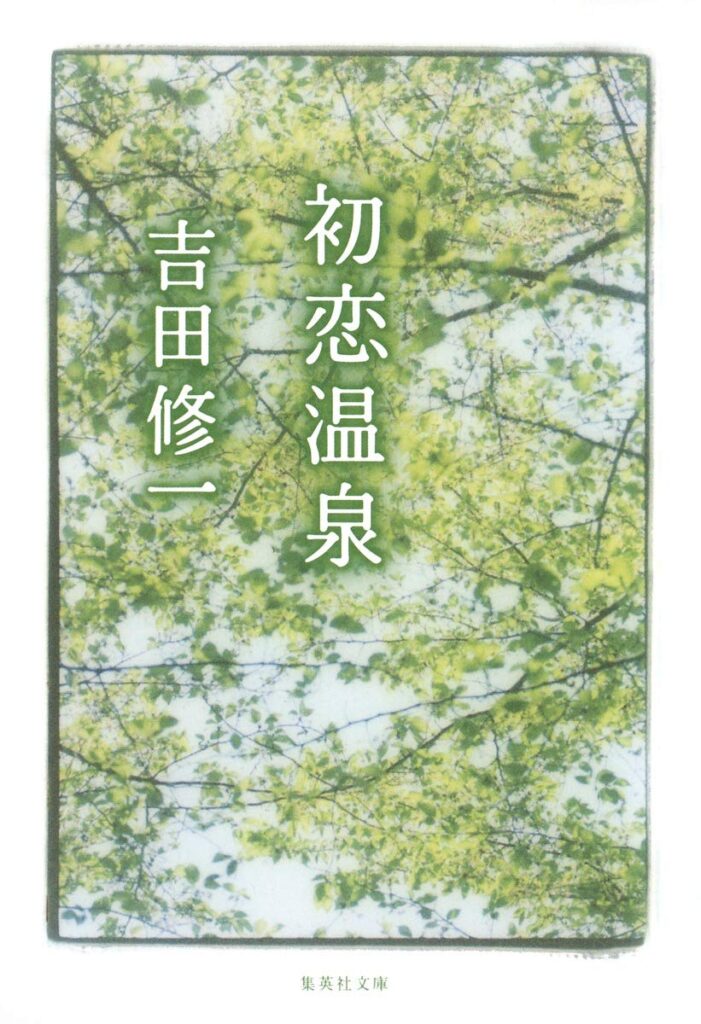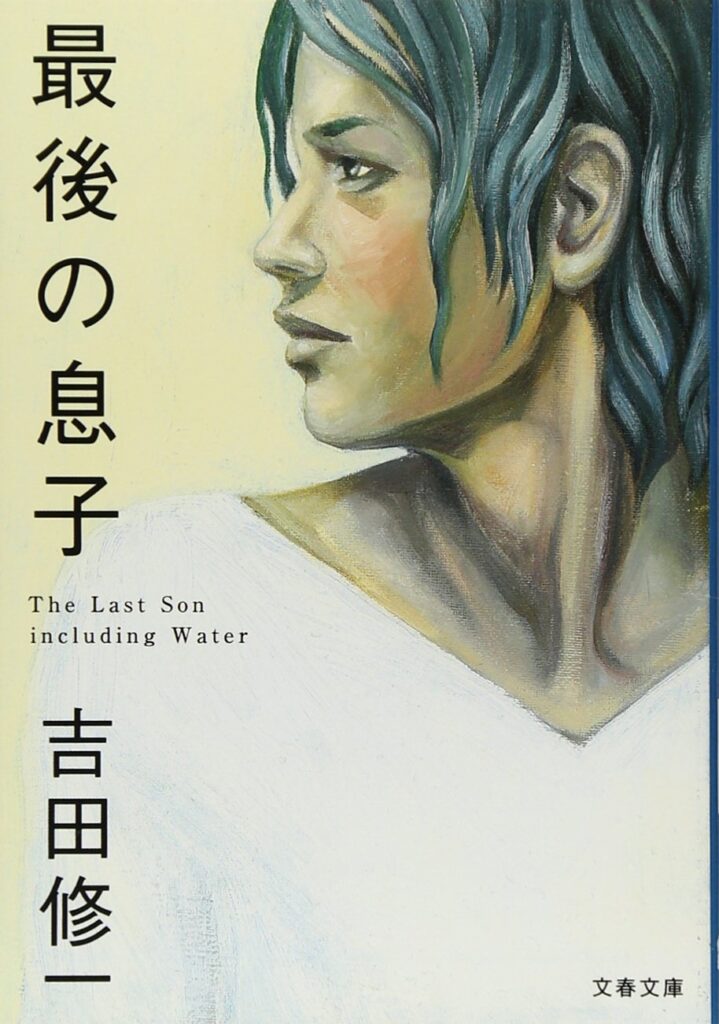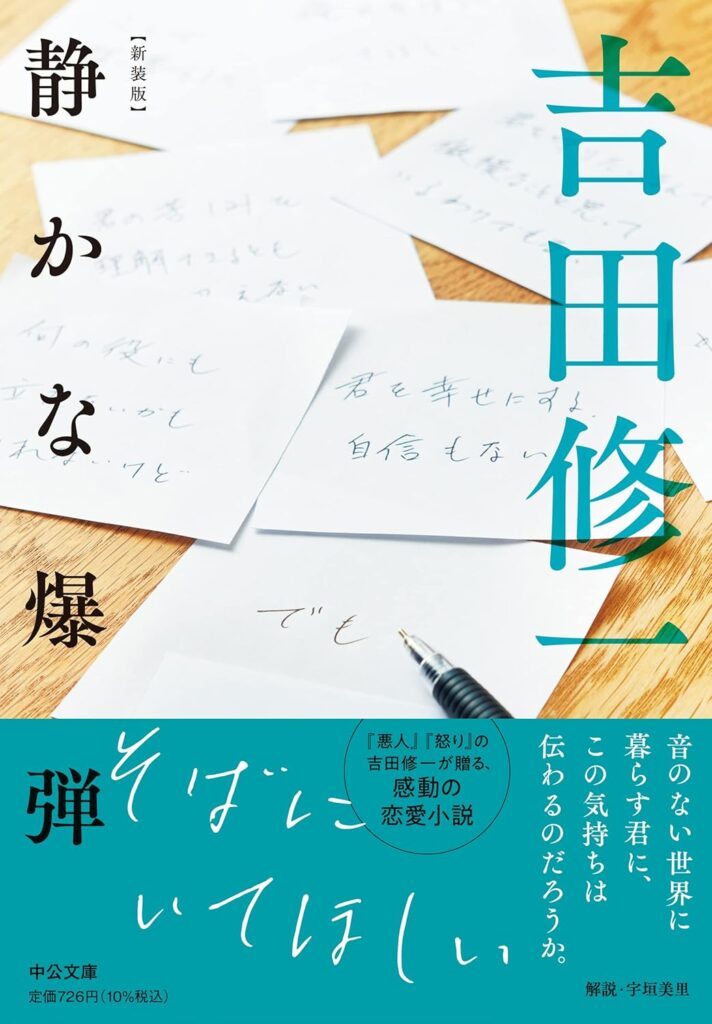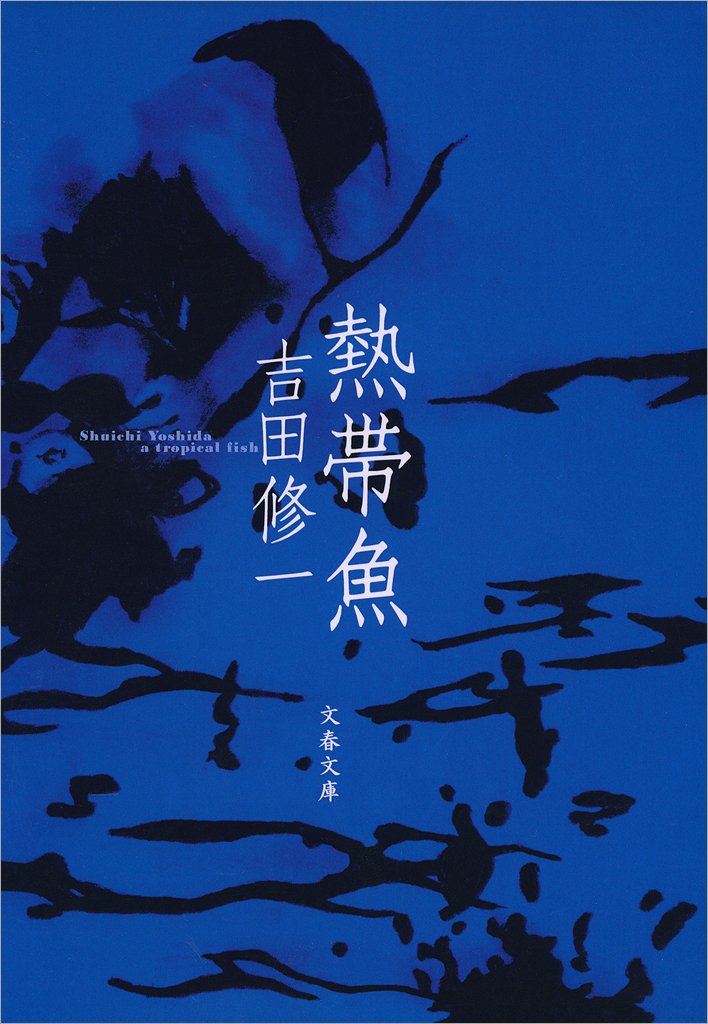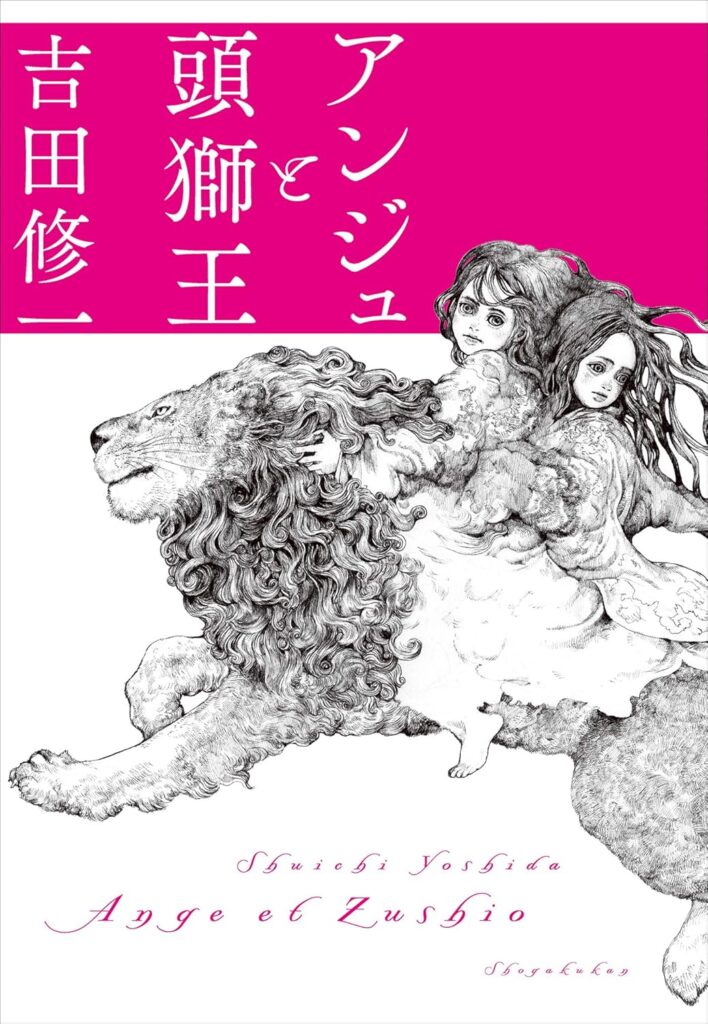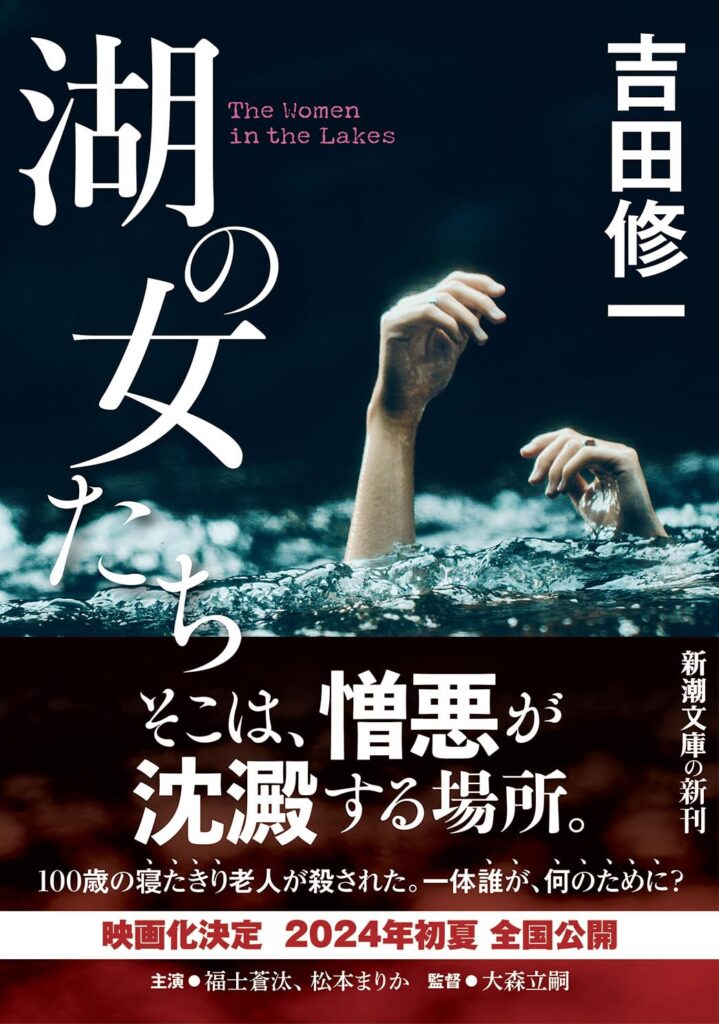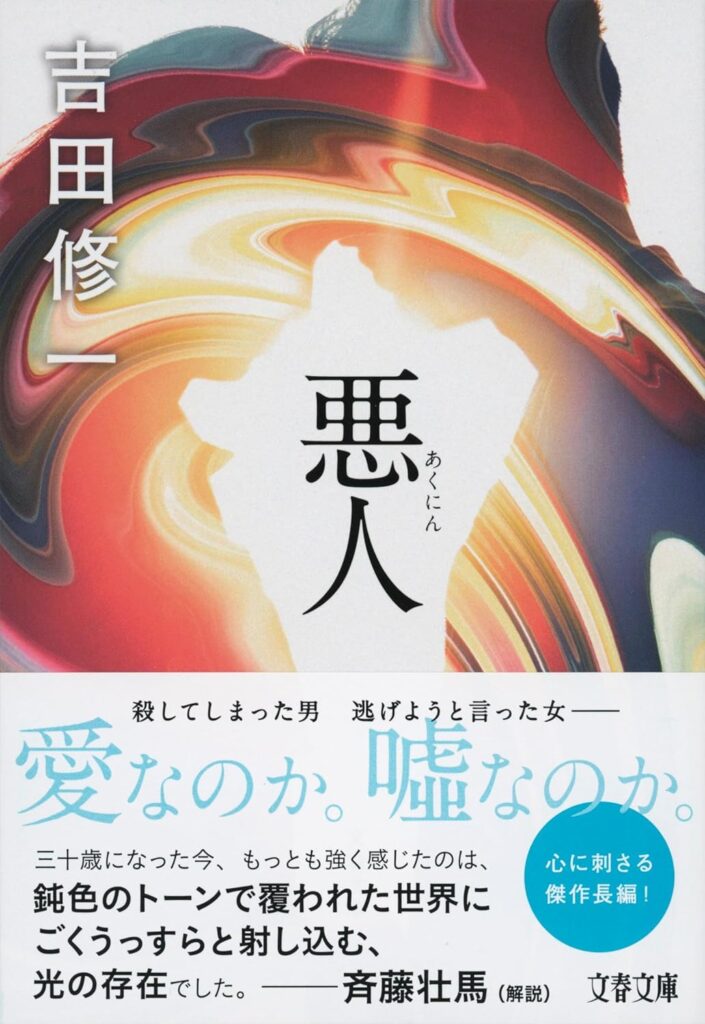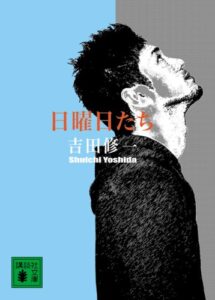 小説「日曜日たち」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。吉田修一さんの手によるこの作品は、東京という大都会の片隅で、それぞれの日常を生きる人々の姿を、五つの独立した短編を通して描き出す連作短編集です。一見バラバラに見える物語は、ある謎めいた幼い兄弟の存在によって、繊細な糸のように結びついていきます。
小説「日曜日たち」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。吉田修一さんの手によるこの作品は、東京という大都会の片隅で、それぞれの日常を生きる人々の姿を、五つの独立した短編を通して描き出す連作短編集です。一見バラバラに見える物語は、ある謎めいた幼い兄弟の存在によって、繊細な糸のように結びついていきます。
彼らの抱える事情や、各編の主人公たちが織りなす人間模様は、時に切なく、時に温かく、私たちの心の琴線にそっと触れてくるでしょう。この記事では、それぞれの物語がどのように展開し、兄弟がどのように関わってくるのか、その核心に触れながらお伝えしていきます。
この物語を読み解くことで、現代社会に潜む孤独や、それでも失われない人の温もり、そしてささやかな希望の光を感じ取っていただけるはずです。物語の結末部分にも言及していきますので、まだ作品をお読みでない方、内容を深く知りたい方は、その点をご留意の上、読み進めていただければ幸いです。
吉田修一さんが描き出す、ありふれた日常の中の特別な「日曜日」たち。その世界を、これからじっくりとご案内いたします。それぞれの登場人物が迎える日曜日の出来事、そして彼らの心の内側を、一緒に追いかけていきましょう。
小説「日曜日たち」のあらすじ
物語の通奏低音となるのは、九州から母親を捜して東京へやって来たとされる、幼い兄弟の存在です。彼らは時に空腹を抱え、薄汚れた身なりで、都会の喧騒の中で途方に暮れた様子で登場します。この兄弟の旅路が、各編の主人公たちの人生と交錯し、物語全体を繋ぐ一本の太い線となっていきます。
最初の物語では、失業し目的もなく街をさまよう青年が、パチンコ店の駐車場で空腹の兄弟に出会い、たこ焼きをご馳走します。これは、兄弟が受ける最初の具体的な助けとなり、彼らの長い旅の始まりを予感させます。続く物語では、旅行帰りの新幹線の中で、兄弟が何らかのトラブルに巻き込まれている様子が目撃されます。彼らが依然として不安定な状況に置かれていることが示唆されるのです。
さらに物語は進み、親戚の結婚式のために九州から上京してきた青年が、父親とのぎこちない時間を過ごす中で兄弟と出会い、寿司を振る舞います。また別の日曜日には、迷子になった兄弟を助けようとする女性と、その様子をどこか他人事のように、しかし気になる様子で見守る男の姿が描かれます。兄弟は自ら母親の居場所を尋ねるなど、少しずつ積極性を見せ始めます。
そして、物語は終盤へ。過去の辛い経験から立ち直り、新たな人生を踏み出そうとする女性が、かつて自立支援センターで出会った兄弟のことを回想します。彼女は彼らに銀のピアスを渡していました。そして数年後、東京を離れようとする彼女の前に、成長した弟の姿が現れるのです。この再会は、兄弟の旅路に一つの大きな光をもたらし、読者に深い安堵感を与えます。
兄弟の背景にある親のネグレクトといった問題や、彼らを取り巻く謎は、物語が進むにつれて少しずつ明らかになります。それぞれの物語の主人公たちもまた、孤独や不安、過去の傷を抱えながら生きています。そんな彼らが兄弟と関わることで、ほんの少し心が動かされたり、無意識の優しさを示したりするのです。
最終的に兄弟がどうなったのか、その全てが明確に語られるわけではありません。しかし、最後に示される彼らの姿は、多くの困難を乗り越え、ささやかながらも確かな希望を見出したことを感じさせます。それは、彼ら自身の力だけでなく、出会った人々からの小さな善意の積み重ねがあったからなのかもしれません。
小説「日曜日たち」の長文感想(ネタバレあり)
吉田修一さんの「日曜日たち」を読み終えたとき、心の中にじんわりと温かいものが広がるのを感じました。都会の日常に潜む孤独ややるせなさを描きながらも、決してそれだけで終わらせない。むしろ、そうした状況の中でふと示される人の優しさや、ささやかな繋がりの尊さを、この作品は教えてくれるように思います。物語の核心に触れながら、私が感じたことをお話しさせてください。
この作品は、五つの「日曜日」の物語から成り立っています。それぞれの物語の主人公たちは、私たちと同じように、日々の生活の中で様々な思いを抱え、時には立ち止まりそうになりながら生きています。そして、彼らの日常に、ある幼い兄弟が影のように、あるいは一筋の光のように現れるのです。この兄弟の存在こそが、本作を貫く最も重要な要素と言えるでしょう。彼らは、親の愛情を受けられず、母親を捜して九州から東京へやってきたとされています。その姿は痛々しく、読者の胸を締め付けます。
第一話「日曜日のエレベーター」の主人公である渡辺は、仕事を失い、無為な日曜日を過ごしています。元恋人との過去をぼんやりと思い返す彼の前に現れたのが、お腹を空かせた兄弟でした。渡辺は、彼らにたこ焼きをご馳走します。自分自身も決して満たされているとは言えない状況の中で見せたこのささやかな行為は、物語全体を覆う優しい眼差しを象徴しているように感じました。誰かの優しさが、必ずしもその人の境遇や心の余裕に比例するわけではない。むしろ、自分自身が苦しさや寂しさを知っているからこそ、他者の痛みに寄り添えるのかもしれない、そんなことを考えさせられました。
続く「日曜日の被害者」では、友人たちとの旅行帰り、混雑する新幹線の中で兄弟の姿を目撃する夏生が描かれます。この物語のタイトルは非常に示唆的です。直接的な被害を受けるわけではない夏生が、兄弟の置かれた困難な状況を目の当たりにすることで、ある種の感情的な影響を受ける。それは、見過ごすことのできない他者の苦境に触れたときの、心のざわつきや無力感に近いものかもしれません。兄弟自身が状況の「被害者」であることは明らかですが、それを見つめる者もまた、何かしらの痛みを共有させられるのです。
「日曜日の新郎たち」は、親戚の結婚式のために九州から上京してきた健吾と、その父親・正勝の物語です。独特の価値観を持つ父親との、どこか不器用な関係性が描かれる中で、健吾は空腹の兄弟に出会い、寿司をご馳走します。この行為もまた、打算のない純粋な優しさから生まれたものだと感じます。結婚式という華やかな場を背景にしながらも、物語は父子の間の微妙な空気や、健吾の心の動きを丁寧に捉えています。「新郎たち」というタイトルは、結婚式に出席する人々だけでなく、人生の新たな門出や、他者への思いやりによって未来へと「整えられていく」兄弟たちの姿をも暗示しているのかもしれません。
そして、「日曜日の運勢」。この物語では、母親の家を訪ねてきた兄弟を荻窪まで連れて行こうとする女性と、その様子をなぜか尾行する男・田端の姿が描かれます。田端のキャラクターには、どこか憎めない飄々とした雰囲気があり、物語に軽やかなリズムを与えています。兄弟が助けてくれる人を見つけたのは、まさに「運勢」と呼ぶべき幸運だったのかもしれません。しかし、それは大げさなものではなく、日常の中に転がっている、ささやかな偶然の連鎖なのでしょう。誰かが誰かを助ける。その善意のバトンが、見えないところで繋がっていく。田端の視点は、そうした都市の中の温かい繋がりを、私たち読者にそっと教えてくれているようです。
最後に置かれた表題作「日曜日たち」。この物語の主人公・乃里子は、過去にDV被害を受け、心に深い傷を負いながらも、自立支援センターの副所長として新たな一歩を踏み出そうとしています。彼女はかつて、シェルターで幼い兄弟に出会い、彼らに銀のピアスを渡した過去がありました。物語の終盤、東京を離れる乃里子の前に、成長した弟が作業服姿で現れます。彼は乃里子のことを覚えていました。この再会シーンは、言葉少ないながらも非常に感動的で、涙なしには読めませんでした。乃里子が兄弟を助けたように、兄弟の存在もまた、乃里子にとって何かしらの救いになっていたのかもしれません。
この最終話のタイトルが、それまでの「日曜日の〇〇」という単数形から「日曜日たち」と複数形になっている点も見逃せません。これは、個々の主人公の日曜日だけでなく、彼らと関わってきた兄弟自身の積み重ねられた時間、彼らの人生そのものに焦点が当たっていることを示唆しているように思います。兄弟はもはや単に保護されるべき存在ではなく、自らの足で立ち、生きていく主体として描かれているのです。乃里子が渡したピアスは、困難な時期を共に乗り越えた記憶と、人と人との繋がりの証として、彼らの胸に残り続けるのでしょう。
作品全体を通して感じるのは、吉田修一さんの人間に対する温かい眼差しです。登場人物たちは皆、どこか不器用で、弱さを抱えています。しかし、だからこそ愛おしい。彼らが示すほんの小さな優しさが、誰かの心を温め、そしてまた別の誰かへと繋がっていく。兄弟の旅は、そうした善意の連鎖によって支えられていたのだと、読み終えて強く感じました。
また、吉田さんの描く「細部」の描写は本当に見事です。登場人物の何気ない仕草や言葉、街の風景、空気感。それらが積み重なることで、物語に圧倒的なリアリティと深みが生まれています。大きな事件が起こるわけではないのに、ページをめくる手が止まらないのは、そうした細やかな描写によって、登場人物たちの息遣いや心の揺れ動きが、まるで自分のことのように伝わってくるからでしょう。
この物語は、都市の匿名性や孤独を描き出しながらも、決して絶望だけを描いているわけではありません。むしろ、そうした現代社会の側面を静かに見つめながら、それでもなお失われない人間の温かさや、ささやかな希望を描き出そうとしているように感じます。兄弟が最終的にどのような道を歩むのか、その全てが語られるわけではありませんが、読後には不思議と爽やかな気持ちと、前を向く勇気をもらえます。「嫌なことばっかりだったわけではない」という乃里子の言葉は、人生の困難さを認めつつも、その中に必ず光を見出そうとする、この作品全体のメッセージを凝縮しているのかもしれません。
「日曜日たち」は、私たち一人ひとりの心の中にある「善なるもの」を静かに揺り動かし、人と人との繋がりの大切さを改めて教えてくれる作品です。読み終えた後、きっとあなたの心にも、温かい何かが灯るはずです。
まとめ
吉田修一さんの小説「日曜日たち」は、東京という大都市で生きる人々の日常と、そこに迷い込んだ幼い兄弟の姿を通して、現代社会における孤独と、それでも失われない人間の温もりを描き出した珠玉の連作短編集です。一つ一つの物語は独立しながらも、兄弟の存在がそれらを繋ぎ合わせ、読後には大きな感動と希望を与えてくれます。
各編の主人公たちは、それぞれに悩みや葛藤を抱えながら生きています。そんな彼らが、困難な状況にある兄弟と出会い、ほんのささやかな善意を示す場面は、私たちの心に深く響きます。それは、大げさなヒロイズムではなく、ごく自然な人間的な反応であり、だからこそ胸を打つのです。
物語の核心には、親の愛情を受けられずにいる兄弟の痛ましい姿がありますが、彼らが様々な人々と出会い、助けられながら成長していく様子は、私たちに勇気と安堵感を与えてくれます。特に最終話での再会は、この物語が持つ救いと希望を象徴する場面と言えるでしょう。
「日曜日たち」は、派手な出来事が起こるわけではありませんが、登場人物たちの心の機微を丁寧に描き出すことで、読者を物語の世界へと深く引き込みます。吉田修一さんならではの繊細な筆致と、細部にまでこだわった描写が、作品にリアリティと温かみを与えています。日々の生活に少し疲れたとき、人との繋がりの大切さを見失いそうになったとき、この物語はきっとあなたの心に寄り添い、そっと背中を押してくれるはずです。

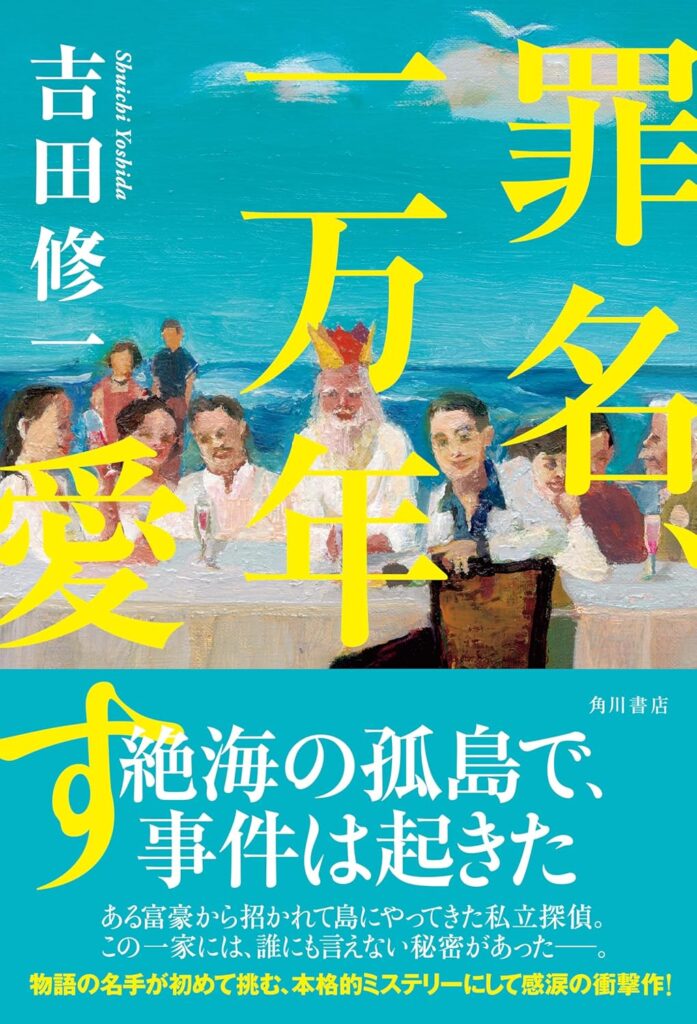
-728x1024.jpg)